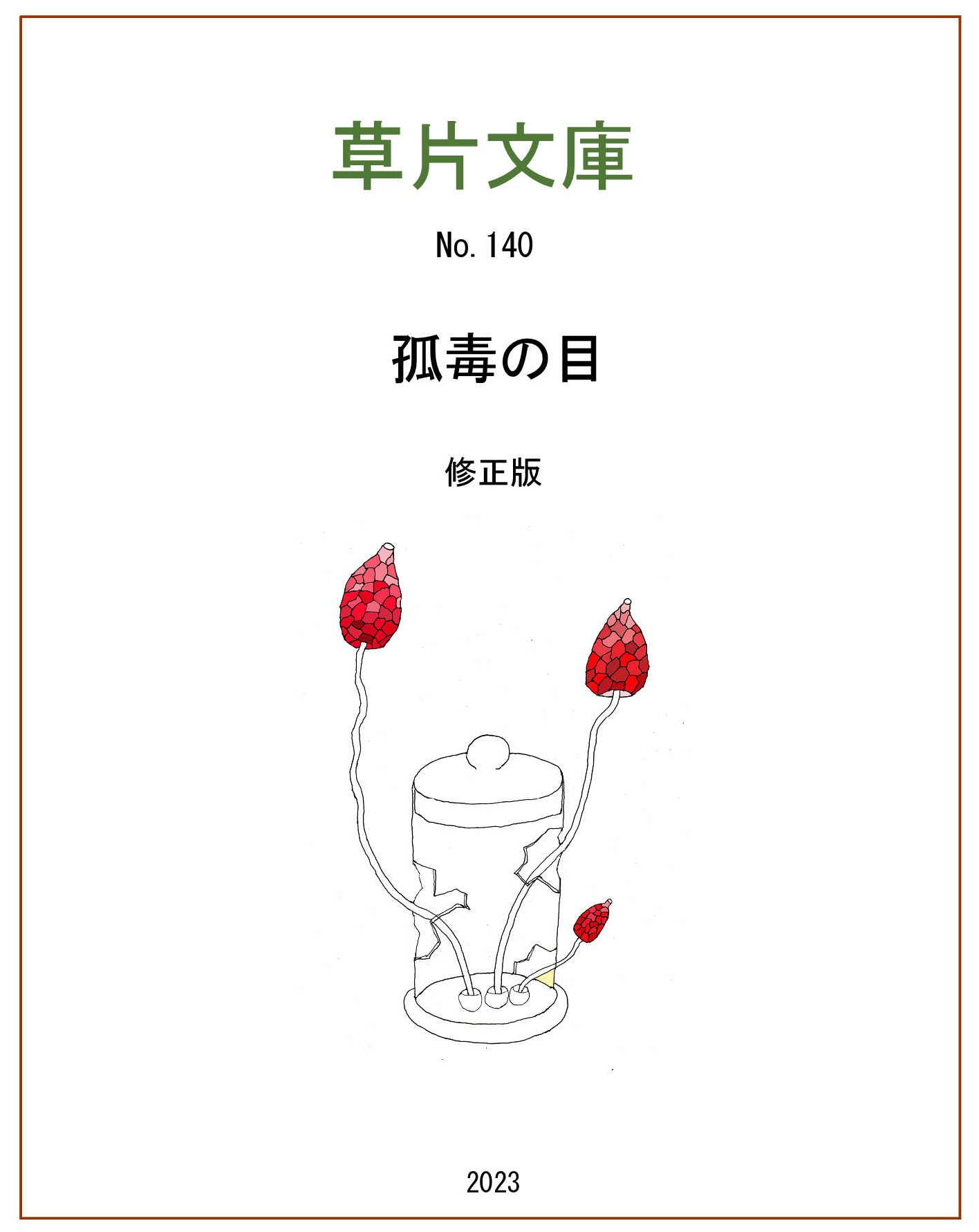
孤毒の目
探偵小説です
私の目をつぶしてほしい、私が見つめる人はみんな毒で死ぬの、だから、目はいらない、こう言う女がいた。
年は四十一。独り身で、今は自宅のマンションで内職をしている。内職は昔ながらのもので、そのときによって違う。
女がテーブルの前に座り、真っ白の封筒にシールを貼っている。テーブルには一万枚の封筒と、封筒の裏に張り付けるためのシールがやはり一万枚ある。
シールには赤い水玉模様の茸の傘の下で、ハリネズミが茸の匂いを嗅いでいるイラストが描かれている。絵の下には緑色で出版社名がある。封筒の封をしたところに張り付けるものである。封筒の中には有名な茸のイラストレーターの絵がはいっている。
子どもの本のおまけづくりをしているわけだ。
本人も絵を描く。それなりに知られた美大をでて、児童文学の出版社にはいった。そのころは、作る本のレイアウトやら、装丁などを担当し、三十半ばまで、かなりの数の本を世に送り出していた。
ところが、突然退職願を出した。職場では、仲のいい同僚もいて、中堅どころとして頼られる存在になっていたこともあり、トラブルなど一度もなかったこともあり、誰もが不思議に思った。当然のこと、会社としても強く慰留した。しかし、一身上の都合だといって、やめてしまった。
同僚たちもどうしたのか全くわからず、どこかの出版社に引き抜かれたのじゃないかという噂が立った。かなり有能な女性だったからだ。しかし違った。内職や校正の仕事で生計を立てていた。
会社をやめてから一月たって、特に仲のよかった同僚の女性が彼女のマンションにいった。その女性がやめて一番驚いたのは二人で何冊もの本をつくったその彼女だったのである。やめる前、その同僚にも相談など全くなく、理由を知りたかったからだ。
彼女がマンションを訪ねると、やめた彼女は以外と明るく、訪問を喜んでくれた。
マンションの部屋に案内されると、彼女はコンピューターで得意なグラフィック絵を描いていた。
「勤めてないの」
同僚が尋ねると、彼女はコーヒーの準備をしながら、うなずいた。
退職金はそれなりにでているにしても、そんなに裕福ではないことを知っていた同僚は、
「どうするの」と聞いた。
「私、外にでないことにしたの」としか言わなかった。
「どうやって食べていくの、まさか株なんていわないでしょうね、あなた、ああいうのきらってたものね」
「うん、今でも株なんてきらいよ、家でできる仕事をさがしてるの」
「あてはあるの」
「ないわ、だけど、校正やコンピューターグラフィックの補助的なアルバイトは結構あるし、一応、職業紹介会社には登録してあって、たまに内職的な仕事があるから、引き受けたりしている」
彼女の様子は、勤めていたときと比べると、がらっとかわってはいたが、体の調子は悪くなさそうだし、話す調子もひどいメンタルの病になっているようにも見えなかった。同僚は少しばかり安心したが、心の中には解決できないもやもやが残った。
会社の上司が問題なのかしら。とも思ってみたが、どの上司にしろ、家庭的な人だったり、山歩きの好きな人だったりして、みな女性に対してはさっぱりしており、そのような人はいない、といいきる自信があった。
その日はお茶をいただいて、会社のしごとで、家でできるバイトがあったら、紹介するわといって、帰った。おまけ作りは彼女が持ってきてくれた内職だった。
女の名前は朝霞美澄、同僚の名は今井遙花、会社の同期で、朝霞は絵の領域、今井は文の領域で、自然にお互い協力しあいながら本を作り、編集部の幹部として育ってきた仲である。
今井は朝霞を訪ねた次の日、編集部のスタッフに、
「美澄は元気だったわよ、理由はわからないけど、外で仕事はしたくないようなの、バイトとしていろいろ手伝ってもらおうと思うのよ」
「他の会社にいったのかと思った」
「俺は美澄さん結婚するのかと思ってた」
若い男の社員はそう言った。美澄は落ち着いた雰囲気の美人でもあった。
「そういう話聞いたことないな」
「今井さんいつも一緒だったけど、朝霞さんはボーイフレンドいなかったの」
「うん、私飲めないでしょう、だからたまに美澄とは食事したくらい、私は結婚してすぐに子供も産まれ、家庭に帰る毎日だったせいもあるけど、彼女にボーイフレンドのいる気配なかったな、男性の話をしなかったわね」
「大学は違うんでしたね」
「私関西の文学部だもの、彼女は東京の美大で、大学時代のことは知らないなあ、彼女も話してくれなかったしね」
「あの能力と美貌で一人ということでなにもないということはないでしょう」
男の見方はいつもこうだ。
今井遙花はそう思った。確かに美澄はきれいな女性で、女性からも好かれるタイプでうらやましいと思ったこともあった。そういわれたら、なぜ彼女は男の話をしなかったのか。会社に入りたての時に、自分は彼女に自分の彼のことをよく話した気がする。六年つきあって結婚したわけだが、彼女は自分のことは話さなかった。男がいる雰囲気もまったくといっていいほど感じなかった。たしかにそんなことはないはずなのに、なぜ私は気がつかなかったのだろう。自分のことで精一杯だったのかもしれない。美澄はとても信頼できる同僚としてつきあってきたことが改めてわかった。うん、確かにおかしい、遙花は今度あったら、そのことを話そうとも思った。
その後、遙花は中途採用した絵の担当の女の子と、一冊の絵本にかかりっきりになった。指導もかねて、彼女にその本の絵を描く画家を選ばせて、編集をすすめていた。
その絵本が校了になり、後は出版を待つだけとなったある日、遙花は美澄から電話をもらった。美澄がやめてまだ一年たっていない。
「わたしだめ、眼いらない」
そういって、美澄は電話の向こうで泣いていた。
そんな美澄を見たこともなかった遙花はあわてた。一緒に仕事をしていたときに、ミスったからといって、嘆いたりせずに、果敢に次にとりかかるような気丈な美澄しか知らなかった。
すぐにマンションに行くといって、会社をとびだした。時間の余裕のあるときでよかった。
マンションでは、美澄が目を赤く腫らして、「ごめん」と一言いって、遙花を中に招きいれた。
「今日は話すわ、お願い、きいてくれる」
美澄らしくない。ずいぶん弱気だ。
美澄は今日の朝刊をもってきた。遙花が何だろうと美澄が広げた新聞を見た。
大した事件はおきていない。今の首相が作ろうとしている子ども庁のことが大きく載っている。出生率や子育ては国にとって根幹的なことだ。もちろん教育もそうだが、本来子どもを育てるのは国のためではない。動物としての人間が行う自然の営みで、子どもの自由な生き方を保証し、本人が納得する人生を全うすることができるようにするのが国の役割だ。ところが、今の政府がいっているのは、人口が減ると働き手が少なくなり、国が衰弱するのを心配してのことだ。江戸時代のように伸び伸びと庶民が暮らせると子供は増える。と、遙花が自分の子育てを振り返りながら思いを深めていると、美澄が数行の小さな記事を指さした。
美澄を見ると涙をためている。
改めて新聞のその記事のタイトルを見た。
「謎の鉄道自殺」とあった。自殺の話はほとんど新聞に載らない昨今である。何か特殊なことがあって、このタイトルが付けられたのだろう。ほかに記事がなかったのかもしれない、珍しく自殺に数十行をさいている。
遙花は文をおった。昨夜十一時、30半ばの男性がホームの階段をかけおり、はいってきた電車に飛び込んだというものである。そこまではよくある話だと遙花は思った。その後の文章に謎があった。
本人はとても健康で、小さいながらも堅実な出版社を経営している社長だった。ようするに自殺の原因がみあたらないということである。男の出版社の社員は社長の自殺に全く思い当たることは全くないといっており、出生地である鹿児島には両親兄弟が堅実な暮らしをしていて、両親もその男が自殺する理由に思い当たらないということだ。
電車に飛び込む前に階段を駆け下りてくる男を目撃していたホームの乗客の数人が警察にこう言った。男の眼がなんだか光っているようで、電車を見て一目散で飛んで行ったとい。怖い眼だったという。精神疾患を疑った警察は男の病歴を調べたが、そのような兆候は全くなかった。そういったことが書かれていた。
遙花はこの男と美澄の共通点は出版社だ。仕事の上で知り合いだったのかと思った。それにしても、美澄は眼がいらない、などという言葉をどうして電話で叫んだのか。男の目が光ったというのとどうつながるのか。
「お知り合いなの」
そうたずねた。
美澄はうなずいた。
「だけど、まだ一度しか話をしていないの」
「それなのに、この人の飛び込み自殺があなた関係しているの」
「おそらくね、あなたにも話したことがないことをこれから話すわ」
美澄も落ち着いてきたようで、やっと遥花の目を見た。
美澄は中学生のとき、生徒会長だったちょっとかっこいい男の子に、当たり前の女子中学生として、初恋をした。だれものあこがれだった男の子で、彼女も普通の女子中学生だったわけである。
美澄は生徒会長がマイクの前で話をするのをふわふわする気持ちできいていた。眼はその男の子を見つめていた。頭がぼーっとなると言うより、眼がとても熱く感じられることがたびたびだった。その男の子を見ていると、眼が火照るように熱くなり、指で瞼の上から眼を触ると明らかにに熱くなっていた。そのうち眼が小刻みに揺れているのがわかるようになった。といって、見ているものは揺れることがなかった。
夏休の直前の生徒会で、一番前の椅子に腰掛けた美澄はいつものように話をする男子生徒を見つめていた。話し終えた生徒会長がお辞儀をして、ふっと美澄を見た。眼があった。そのとき、異様に美澄の眼が揺れた。男の子の眼が青っぽく見えた。
そのときはそれだけだった。夏休みも半ばになって、生徒会長だったその男の子が電車に飛び込んだのを新聞で読んだ。生徒会の委員をやっていた女の子に電話をして話を聞いたところ、東大をめざしていた彼は、成績が落ちたことを苦に自殺したのだろうと言った。そのときは、残念としか思わなかった。もちろん初恋の男が死んで寂しくは思った。
美術大学にすすみ、絵本の歴史を研究している男の先生の講義を聞いて、今まで特に興味を持っていなかった絵本に目がいくようになった。その先生は研究をするかたわら、自分でも絵本を出版していた。美澄はイラストを中心とした現代絵画の実践コースを選んだ。その先生とは個人的に指導も受けた。
「今絵本がたくさん出版されているが、本当に子どものためになっているのは少ないね、昔のイギリスやドイツの絵本は画家が身の回りの好きなものを丁寧に描写して、自分にとって好きな本として作り出されている、今日本でも画家が独自の視点で描いたものが絵本になっていて、いい本がたくさんあるのは確かだが、一方で、教えよう、が強くて、子どもの感性を育てるようなものではないようなものがよく売れている。そういうものも否定はしないが、子どもの感性の原点になるような絵本がいいよね」
「どんな絵本でしょうか、先生はそういう記憶がおありですか」
「それがないんだよね、我が家は絵本をふんだんに買えるような裕福な家じゃなかったこともある。親は生活のためにいつものら仕事をしていて、小さかった僕をそんなにかまってはくれなかった、あぜ道で蛙を見たり、トンボを見たり、猫をかまったり、よくある農家の生活だったからね、だから、田圃が一枚の絵本の一ページで、そこにいる生き物や植物が動画として流れていた、そういった子どもには、田圃とは違った画面の絵本があったら、感性が幅広くなっただろうと思うよ」
「どういうことですか」
「ピーターラビットなどの外国の絵本を見たら、違う田園風景のあることを知ることになるだろうね、君はどうなんだい」
美澄は中学校の絵の先生だった父親と、国語の先生だった母親の与えてくれた膨大な絵本を思い出していた。今思うと、先生だった二人は、思春期の始まる中学生を相手に忙しい思いをしていて、自分をかまいたくても時間がとれず、あんなに絵本を買い与えてくれたのだろうという思いに至っていた。その絵本の中で、なにが好きだったか、思い出せない。今も兄の家にあるだろう。頭に浮かんだのはどうしても漫画家の本だけだった。
自分が美術の大学を選んだのは、少しばかり絵がうまいとほめられていたからだ。小学校の時から展覧会では入賞していた。父親は風景画を好きで描いていたので、娘の自分も一緒に写生をしたことを覚えている。そういった自然の流れの中で、自然と美大を選んだ。油絵などの本格的な美術ではなく、デザインを選んだのは、父親と同じ方向には行きたくないという思いが頭の隅にあったからかもしれない。父親が嫌いなわけでもないし、写生も楽しかったのだが、すでに父親の領域だ、自分は違うところにいこうという意識があったのだろう。
「私は、絵本はたくさん買ってもらいましたが、どれって言う絵本が浮かびません、むしろ少し大きくなってからのマンガの方が印象に残っています、章太郎のジュンなんか好きでした」
「それでデザインなんだね、何でもいいけど、誰でも、大きくなる課程で、そういった自分の生きる方向に影響を持つものがあるんだ、絵本の影響力はすごいものだと思うよ」
先生が美澄を見た。眼があった。その先生の目の中に黄色く実った稲の植わっている田圃が見えた。柔らかいその眼は充実した満足感がただよっている。
ふっと、美澄は高校の時の生徒会長だった初恋の男の目を思い出していた。
改めて見た先生に顔が火照ってきた。すてきな先生だ、そう思って、研究室をでた。
その翌日である。その先生は鉄道自殺をした。
学内でいろいろな噂が飛び交ったが、結局理由はわからなかった。その先生は大学での評価、学生からの評価はとても高く、穏やかないい家庭ももっていた。
そのとき、先生の死を残念に思ったが、それで終わった。
高校の時の初恋の男子、大学でのあこがれを持った先生、その二人の死に自分が関わっていることを知ることになったのは、児童書の出版社にはいってからだ。遙花を始めいい仲間と、優しい上司に恵まれ、仕事は順調だった。
誰も知らないことだったが、入社して数年後、一人の絵本作家と個人的につきあうようになった。美澄の出版社から本を出した人で、美澄が担当した。東京の下町の工場を主題として絵本を作っている男だった。自分自身も江戸切り子を作る職人で、下町の生活の清楚さ、人間のひたむきさを絵本にしている珍しい立ち位置の男だった。それこそ話し下手で、ただひたすら手を動かすことに幸福を感じていた男である。そのような男が美澄をみそめた。美澄も惹かれてつきあうようになった。彼の本の売れ行きはそこそこで、美澄の出版社からはその一冊しか出さなかったが交際はつづいた。
なかなか眼をあわさない恥ずかしがり屋のその男と、初めてまともに目を合わせたのは、始めて肌を合わせたときだった。
「あんたの目は死にたくなる眼だな、強い眼だな」
そういいながら美澄をもとめた。
その男は数日後、電車に飛び込んだ。江戸切り子の名人と言われていた父親に、もっと気持ちを入れて作れと言われた次の日のことでもあり、それが原因だろうと言われた。
だが、死にたくなる眼だといわれた美澄は自分が見つめたためではないかと疑いをもった。そういえば、高校の初恋の男も、大学の先生も眼をあわせた後に死を選んでいる。
そして、美澄を自分の会社に引き抜こうとした出版社の若い社長。
用事でその出版社に行ったとき、その社長から、うちに来ないかと誘われた。今の会社に十分に満足していた美澄は当然断った。だが、その若い社長の眼を美澄は素敵だと思った。まだ憧れにもいってなかったが、自分の眼が揺れるのを感じた。このような人が伴侶ならとは思った。その男が地下鉄に飛び込んだのだ。
それが退職を決意した出来事である。好きになった男と目を合わせると、その男は死を選ぶ。どうしてか、そんなことわかるわけはない。本人は自責の念にかられ、おそらく一時の鬱におちいっていたのであろう。外にでるのが怖くなった。
こう言った話だった。
遙花は美澄が心の病の入口に立っていると思った。
遙花の高校の同級生が看護師になって東京の病院にいる。共に仕事先が東京だったことから、就職したてのころはよく一緒に食事をよくした。お互い家庭を持ち、それぞれ仕事に責任が増してきて、最近はあう機会もほとんどなくなっていた。丁度いい機会と思い、遙花はその友達にあった。
「好きな男性と目を合わせると、その男性が自殺するなんて、思いこみだなあ、もしかするとかなり心的傷害がある人なのじゃないのかしら、心理カウンセラーもいいけど、精神科の先生にみてもらったらいいわよ」
「だけど、本人は病気だと思ってないようだし、私も彼女が病気とは思えないな、どうしたらいいだろう」
「そうね、だけど、病院にいったほうがいい、そういう人を精神科にみせるって大変なのよね、私の看護大学の先輩に、警察病院にいる人がいるわ、何度か同窓会で会ったことがある、人の心理状態をよく知ってる人、看護学校の私のよく知っている先輩と同級生だから、紹介してもらえると思うよ、遥花の気にしている人の様子をメイルで私にしらせてくれれば、その人に伝えるようにする、患者さんの名は仮名でいいわよ」
「それはありがたいなあ、やっかいなことお願いして悪いけど、警察病院の人はなんて言うの」
「高胎(たかはら)さんて言ったと思う、ちょっと時間かかるけど、やってみるわね、遙花のメイルアドレス教えちゃうかもしれないけど、いい」
「いいわよ、ありがとう」
その後しばらくしたら、相談した彼女からメイルが入り、そのあと警察病院の高胎さんからメイルがはいった。高胎蓉子とある。高胎からのメイルでは出版社の男性の自殺のことは知っていて、奇妙なできごととして、高胎の所属する、警視庁捜査支援分析センター分室にも情報がきているとのことだった。
美澄の前に揺花と話がしたいということだった。
揺花は高胎蓉子と喫茶店で会って話をした。高胎は背の高い、どちらかというとモデルか秘書といった感じだ。
「美澄さんは物事を客観的に見ることのできる方ですか」
高胎蓉子は言葉遣いや物腰は柔らかいが、眼の奥が光っている。揺花はこういう眼を画家や作家の人でみたことがある。穏和な画家がちらっと見せる眼だ。自分の見たいもの、知りたいものを見たときだ。
「はい、彼女とは就職したときから一緒に絵本づくりをしていましたが、読者、これは赤ちゃんから幼児たち、そのおかあさんたちですが、彼女たちがどのようにその絵を見るのか見抜く人でした。だからいい絵本をたくさん世に送り出しています、私は文字の方です」
「そうですか、今もですか」
「現在は退職をして、内職などをしています、今でも客観的に自分を見ています、だけど、私の眼が相手を殺してしまうと思いこんでいるのは病だと思います」
「彼女は客観的に自分を長い間みてきて、その結論にたっしたのではないかしら」
「真実だとおっしゃるわけでしょうか」
「そうですね、まだ断定はできませんけど、我々の仕事は、そんなことはあるはずはない、という常識を捨てて事件に向かわなければなりません、それで、かなり、それが事実であるということがあるのです、世の中の理にあわないような、非科学的な事実が、特に人間にはあることがあるわけです」
揺花はこの女性の言っていることがすぐにはわからなかった。絵本づくりは常識の枠内で物語を作る。
「絵本をつくるとき、登場した猫がしゃべりますね」
なにをいいたいのだろうと、揺花は高胎を見た。笑顔で見返している。
「絵本の中では猫がしゃべるのは常識でも、もし、子どもが、猫が遊びたいと言っていたよ、と言ったら、お母さんは、猫がしゃべるわけないでしょ、と思うでしょう」
それはわかる。
「だけど、子どもは猫の動きをみて、自分の今までの経験から、頭の中で、猫が遊びたいと言っているのを聞いているのです、大人の常識でははずれていても、本人にとって、まちがいではないわけです、頭の中で聞いているのです、実際の音のように、美澄さんは、自分の眼でみたものに、自分の眼が何らかの影響をあたえている、と言う考えが経験の積み重ねから芽生えたのでしょう、だから、彼女にとって、それは正しいことで、客観的なことです。私たちが信じてあげるとすると、それを立証するには、どうしましょう」
難しい質問だ。考えたこともない。
考え込んでいると、彼女は、
「美澄さんの眼を科学的に調べるのです、科学が勝つか、人間の頭がかつか、もしなにもでてこないとすると、美澄さんの、言うなれば思いこみと言う結論になってしまいますが、もしかすると、他人に何らかの影響を持つ目かもしれません、そこをはっきりさせると、客観的な美澄さんも納得するのではないでしょうか」
「どうしたらいいのでしょう」
なんだか、言葉のあやにからめ取られているようだ。
「我々の関係の医療機関で検査をするように、話していただけますか」
「いやがるのではないかと思います」
「精神科だとか、心理分析とは違います、眼そのもののチェックです、眼科領域の検査です、精神科の医者じゃなくても、その医療施設の医師はどの領域の先生でも、心理分析のできる人です、眼科の先生も眼の検査をする傍ら、その患者さんの心理も分析しています。医者はそうあるべきですけど」
そういわれるとその通りだと思う。
「眼科の検査を勧めるわけですか」
「そうですね、眼の疲労はいろいろな現象を引き起こすとでもおっしゃって、美澄さんに知り合いの知り合いの眼科医に見てもらうと、連れてきていただきたいのです」
「はい、やってみます」
彼女が教えてくれた病院は警察病院の分室のようなもので、通常では考えられないような病状を呈している患者をみるところだそうである。パンフレットをくれたが、外からは個人病院にしか見えないもので、薩摩総合病院と書かれていた。
揺花は自分もマジックにかかったような気分で高胎と分かれた。
「ねえ、美澄、とてもいい眼の病院を知り合いの看護師からおそわったわよ、眼のどんな状態の人も相談になってくれるということなの、いってみない」
揺花は内職の仕事を依頼のために、美澄のマンションに行き、仕事の手順を話した後に切り出した。
「それって、私の話したことが眼の疲労からでたと思っているの」
「それはそれとして、眼の疲労って強いストレスを引きおこすそうだから、それだけでもとれれば、美澄も楽になると思ったから」
「うん、そうね、ずーっとコンピューターを見ているし、細かな手作業だから疲れていることは確かね、ストレスはますます眼の疲労を助長するものね」
遥花の持って行ったエクリアを食べながら、彼女は以外と素直にうなずいた。自分なりに懸命に自分の眼のことを解決しようと悩んでいるのだろう。
「そこにいく」
「うん」
「いつならいける」
「バイトしかないのだから、いつでも大丈夫よ」
「中野にある警察病院の分室なの、予約を入れておくわ、土曜日なら私もいけるからどうかな」
「警察病院って、犯罪者の病気をなおすところじゃないの」
「そうじゃないんだって、一般の人もいけるのよ」
揺花は美澄の家から帰る途中に、警察病院の高胎に電話を入れた。揺花もついて行くことに関しては、送ってくるだけにしてほしいと言われた。
当日、美澄とは中野駅で待ち合わせをして、指定された病院に向かった。その病院は警察病院の近くにあった。
「揺花の知り合いの看護婦さんも警察病院にいるの」
「いいえ、私の同級生は品川の病院、警察病院のひとは高胎さんといって、同級生の先輩なの、なんでも早稲田の文学部を卒業してから、看護学校にはいった人で、とてもしっかりした人らしい」
警察病院分室は三階建てのこじんまりしたものだった。
「以外と小さいものね」
玄関をはいると、一般の病院とは違って、ただの受付しかない。しかも人がいなかった。呼び出しのぼたんがおいてある。
揺花がボタンを押すと、すぐに看護師がでてきた。
「はい、ご予約の朝霞さんですか」
出迎えたのは高胎蓉子そのものだった。
「はい、朝霞です」
「まず、問診票を書いていただきます、その後ドクターの問診があります、この病院は研究病院ですので、場合によっては、検査結果などを研究に使わせていただくことがあります。医療費は免除になります。手術や入院が必要な症状と診断された場合には、警察病院の方でおこないます」
美澄はうなずいた。揺花は美澄の肩に手をおいた。
「いいかな、私これで帰るね、戻ったら電話ちょうだい」
「ありがとう、だいじょうぶよ」
揺花が病院から出て行くと、高胎が話しかけながら、相談室と書かれた部屋に美澄を案内した。
「朝霞さんはお医者さんにはかからないほうですか」
「ええ、ほとんどありません、まだ婦人科にも行ったことがありません、風邪気味の時、内科にいくぐらいです」
「健康でいいですね、婦人科に行ったことがないと言うことは生理痛もなく、生理も正常なんですね」
「はい、アレルギーもなくて、花粉の時期も大丈夫です」
「この部屋で、この問診票を書いていただけますか」
応接室のようにソファーの並んだ相談部屋に案内され、紙を渡された。
「ここは様々なからだの異常を調べる病院ですので、どのようなことでもかまいませんから、ご自分の感じていることをすべてお書きください、できれば時間をおっておねがいします。」
そういって、問診票を渡された。それには体重、身長、病歴、それに従事してきた仕事内容、など一般的な質問事項のほかに、自覚症状を叙述する白紙の紙が数枚ついていた。
「些細なことでもかまいませんので思うことすべてお願いします、それに、箇条書きのようなものでもかまいません、文になっていなくてもいいですので、ゆっくり書いてください、終わったらこのボタンを押してください、とりにきます」
そういうと、看護師は部屋をでていった。
美澄は揺花に話たように、かなり時間をかけて正直に書いた。
書き終わった美澄がコールボタンを押すと、すぐ高原看護師がきて、
「ご苦労様でした、これから一般的な眼の検査をおこなって、それからドクターの診察になります」
と検査室に案内された。
そこには幾つかの機械類が並んでいて、やっと病院に来たといった感じを持った。「ちょっとまっていてください」
美澄をデスクの前の椅子にすわらせると、高胎は書いた問診票をもってでていき、すぐにもどってきた。
「問診表を医師に渡しておきました」
そう言われて、美澄は一つの機械の前に案内された。美澄は言われたとおり、顎とおでこを機械にのせた。眼科ももちろん始めての経験である。高胎が前に座ると機械に眼を当て、美澄も光の点を見るように言った。一連の指示に従い、それがおわると、今度は十字の光が現れ、眼に風がふっと吹きかけられた。なにをしているのだろう。
次も同じように顎を乗せる機械で中をのぞいた。美澄は次々と機械を移動して検査をうけた。
さらに看護師は機械をのぞいて、ペンライトを上、右上、右、右下、下、左下、左、左上、上、と動かし、片目ずつチェックし、「眼の動きは正常ですね」と言った。
片目をつむって、カタカナを読んだり、輪の欠けたところを指摘する視力検査は、離れた掛け軸のような紙を見るのではなく、机の前のディスプレーに現れるカタカナや輪をみるものだった。高校や大学でやった眼の検査とはずいぶん違う。大学の体力検査以来である。眼には自信があったし、いつも1.5で眼の優等生だった。
今回も一番下の段はなかなか読めなかったが、高胎看護師は「いい眼ですね、裸眼でどちらも1.2あります。眼を使うお仕事をなさる方は、どうしても視力が下がっていくのですけど、全く問題ないですね」と言った。
さらに一角にあった暗幕の張られた中の機械で、視野の中に光のスポットが見えたら、手に持ったボタンを押す作業をした。緑内障のチェックだと看護師さんがいった。
「眼の瞳孔を開く目薬をさします、薬が効くと、周りが少しまぶしく見えるとおもいます、一、二時間でもとにもどります」
そういわれ目薬をさされ、しばらくまって、その機械の一つで眼底写真もとられた。
「それでは、また相談部屋でしばらくお待ちください、」
美澄はソファーにうずまってまっていた。瞳孔を開く薬で確かに周りが少し白っぽく光ってみえている。
十分ほどすると、背の高い医師がはいっていきた。高胎看護師もいっしょだ。
「ちょっとお話を聞かせてください」
医師はソファーに座り、美澄をみた。自分の眼を観察している。と美澄は感じた。
医師は神経眼科の専門だと言った。
「朝霞さんの眼そのものは、右も左も正常そのものです。形状もとてもいい。視力は右も左も1.2、白内障も緑内障も全くその気がありません。眼圧も正常、眼を動かす動眼筋が一つの眼に六種類ありますが、どれも正常、眼科医としてはなにも言うことはありません、
ただ、これからが肝心なことですが、朝霞さんが問診票に書かれた、あなたが好きになられた人と目を合わせたら、その人が自死を選んだというお話、ご自分ではどうおもっていらっしゃいますか」
医師は美澄の眼をのぞき込むようにみつめた。
美澄は自分が考えに至った事柄が、あり得ないことであることは十分承知していた。 「私はそう思います、どうしてもそうなのです、精神的なものではないと考えています」
「何度かそういう経験からそう思われるようになったのですね、それは事実なわけで、精神的な病ではないわけです、だけどどうでしょう、朝霞さんは健康体です、ですけど、ちょっと胃が重いなと感じたことはありませんか」
「あります」
「腕がしびれたなどということはありませんか」
「あります」
「それは病気ではないのですが、からだの異常には違いありません、精神も同じで、病気ではないけれども、調子が狂うことは、毎日起きていることです、それを気にするようになると、ますますひどくなる、今朝霞さんはそういった状態なんでしょう、それに眼が関係している」
この先生の言っていることは確かだ。美澄はそう思った。
「眼に何か起きているのかどうか、一つ一つ詳しく調べていきたいと思いま、この診療所は、研究施設でもあり、医学領域ではない専門家との連携をはかって、患者さんの納得がいくまで、解析をおこないますが、おつきあいいただけますか」
美澄はうなずいた。
「それじゃ呼んできて」
医師は高胎に声をかけた。彼女は診察室から出ると、二人の男性と一人の女性をつれてもどってきた。白衣を着ていない。
医師が三人を紹介した。一人の背の高い男性をさして、「こちらは古書さん、医学の古文書の解析が専門です」といい、もう一人の若い小柄な男性を「物理専門の宙夜博士、丸顔のキュートな女性を化学の吉都博士です、すでにみなさんにも朝霞さんの問診票を読んでもらっています、それぞれの領域から問題点をさがしてもらっています」
医学書、物理、化学の専門家が、なぜここにきたのだろう。美澄には全く理解ができなかった。
彼らは丁寧にお辞儀をすると、美澄の周りにこしかけた。三人とも物腰が柔らかい。
この人たちの正体を明かしておこう。警視庁の刑事科の捜査支援分析センター分室である第八研究室での分析官だ。刑事でもある。実は高胎もその一人である。
朝霞美澄の奇妙な振る舞いの話は、それをきいた高胎が第八研究室にもちかえって検討した結果、室長の薩摩冬児が、美澄を解析するチームを編成した。薩摩は警察病院の眼科医師、凡手(すべて)公平に協力を頼んだ。凡手は眼科医であるが、神経眼科という精神科、神経科にまで踏み込んだ解析ができる医師である。
古本が話し始めた。
「じつは、とても昔のことですが、美澄さんと同じような人がいたことが文献に載っていまして、それは、その女性が男を見つめると、男が狂うと言う話です。狂うというのは、自分でも知らない内になにかをしでかしてしまうということで、死ぬわけではありません、朝霞さんと違うのは、その女性が好きになった男とはかぎらないようで、ふとすれちがいざまに、眼と眼があった男の気がどこぞえか、いってしまう、と書かれています。
それが書かれたのは鎌倉時代なのですが、それよりももっと昔の、平安ですね、紫式部も男をおかしくさせる眼を持つ女子であることが書かれたものがみつかっています」
それを聞いて、美澄はおどろいていた。そんな人がいたとは信じられない、実は心の中で、ただの偶然だろうと思う部分もあったのである。むしろ、本当にそのような眼があるとしたら、どうしたらいいのだろう。
古本は「古いものには、そのような眼の女がいると言うことがかかれているだけで、特殊な眼とは書いてありません、ということは、目力というのでしょうか、その女性全体からでるなにかしらに、男がすいつけられ、そのような表現になったのだと思います。ですから、まだわかりませんが、朝霞さんも眼だけの問題ではなく、朝霞さん本人からにじみ出るある意味では魅力のようなものが、自殺した男性の精神に影響を与えたのかもしれません」
美澄は医学古書の解析専門家がここにきたことがわかると同時に、自分とはだいぶ違うにしろ、そういう女がいたという書き物があることで少しばかり肩がゆるんだ。
「しかし、私が好きになった人だけです、そうなったのは」
「そういいきれますか、すれ違っただけの人は名前もわからない、そういう人が自殺していても、あなたは知ることができないのです」
美澄ははっとなった。もっとたくさんの男の人が私の生で死んでいるかもしれない。
「なにが原因だか、わかれば、朝霞さんはかわることができます、そうすれば解決します」
古本がそう結んだ。そんな見方があったのだ。美澄は驚いた。
宙夜が口を開いた。
「朝霞さんに関しては、今、私は特になにも特別なことは感じられません、もちろん個性はおありです、と言うことは、特定の、朝霞さんに感受性の高い人が、朝霞さんの目の動きになにかを感じて影響を受けると言うことかもしれません、それについては、精神科、心理学領域ですが、そちらにいく前に、朝霞さんの眼の動きなど、見ることとは違う領域の解析をしてからにしたらどうでしょうか。視野や眼の動きに他の人と違いがあるかどうか、物理的な検査も含めて、もしその気がおありなら、私と、吉都さんで検査の方をマネージしますが」
美澄は自分の眼の動きがどういうものかなど考えたことはなかった。
「はい、調べていただき対と思います」
「一月ほど、検査のために警察病院と必要な場所に行っていただきますがよろしいですか」
美澄はうなずいた。
医師の凡手が、
「今日おつかれでしょう、次はいつが大丈夫ですか」と聞いた。
美澄はバイトの入ってない日を知らせ家に戻った。
まさか古文書に私と同じような眼がのっているとは、私の眼の動きになにかあるとは、今まで考えてもみなかったことを言われ、何かわかりそうな気持ちになってきた。この病院に来て良かったとも思った。
美澄が帰ると、警察病院分室では彼らが話をつづけていた。
「彼女はとても遠慮深い人ですね、積極的に好きになった男性を自分のものにしようとする行動をしていません、それにかなり客観的すぎるほどに物事をみていることは付き添っていてわかりました、絵本をつくる仕事は、子どものこと、親のこと、いろいろ配慮することができる人でなければできません、ということは、本当に彼女の眼は他の人と違う、他人に影響を及ぼす何かを持っているかもしれません」
美澄の担当となった高胎が言った。この場は高胎がしきっている。
「そうですね、どうでしょう、そういう人って、逆に脳波が強いということはないですか」
宙夜がそう言って医師の凡手を見た。凡手は精神神経眼科医という誰もやっていない領域の研究者だ。
「そういう考えはおもしろいと思うが、そういったデータは今のところないな、一般の脳神経科医は、積極的によくしゃべれば、神経活動が高くなり、脳波が強くなると考えるけど、宙夜さんのは逆で、しゃべらずに思いこむ人ほど、脳の中で考え込むので、神経活動が高くなって、脳波が高くなると言うものだな、それは発想ですね。そういう法則が証明されたら、世界の注目を浴びるよ」
「眼は神経系に属すけど、眼の神経の活動は脳波としてとらえることはできるのですか」
質問したのは、目の大きな、化学の学位をもつ吉都希紅子だ。
「見るための神経の電気活動とそれにより派生する脳波をとるということは誰もしていないな、微量で難しいな、だいたいが、見ることで活性化された脳の中の活動を表面にでた脳波でとらえるというのが普通だからな」
「美澄さんの眼にかかわる脳波を一般の人と比較するのは無意味でしょうか」
「いや、そんなことはないでしょう、一応、やる必要あますね、その前に、MRIによる脳の視覚にかかわる部位に構造的になにかあるかどうか、つぎに、見つめるときの脳の働き具合を一般人と比較することかな」
「もし本当に、眼が会ったことで、相手の行動が変るとすると、彼女の目から何かでているか、眼の色が変わったり、相手が気づく変化があるのだと思いますが」
珍しく科学的なことには口を出さない古本が言った。
「古本さん、その通りだとおもいますよ」
宙夜もうなずくと、みんなもうなずいた。
「そうね、相手の眼に働きかけるとは、なにをしているのだろうね、しかも精神的なものにまで影響を及ぼすんだから、相当な仕掛けがないとね、眼科医として彼女の目を見たとき白目の部分が少し青みがかかって見えたんだ、他の人とはちょっと違うなと思ったけど、それがどのようなことにつながるかわからないな」
凡手医師が思いだすようにいった。
宙夜がすかさず反応する。
「白目の部分は白膜のつづきですね」
眼球は一番外側に白膜があり、脈絡膜、網膜と重なっている。一番内側は網膜である。ただ、眼球前面、真ん中には丸く白膜がなく虹彩になっている。そこが黒目で、動くことで瞳孔が広がったり縮まったりする。日本人の虹彩表面はメラニン色素が多いので、黒だったり、茶色だったりするが、量が少ない白人では青だったり緑色になる。白膜の部分が白目である。
「そうだけど」
「白いと言うことはすべての色を反射していることだけど、青っぽいと、その部分だけ青だけが強く反射され、ほかの色は少し透過していると言うことですか」
「宙夜さんはさすが物理、ロジカルだ、そういうことですね」
「青以外の光が白目から眼球内に入って何かをしている」
「ほんの少し、白膜に色素があって青を反射している可能性があるね、たしかにそこは他の光を透過させているかもしれない」
「それは調べてみないとわからないのですね」
「うん、調べればすぐわかることだよ、それに眼を動かす筋肉の状態と、脳波の関係も調べた方がいいね」
凡手公平医師の言ったことを受けて、高胎蓉子が場をまとめた。
「調べることがだいぶにつまったようですね。
ファンクショナルMRIをつかって、注視したときの脳の状態、眼を動かしたときの筋電図と脳の状態、もちろんその前に眼そのもの構造、色素細胞の状態などを中心に最初の検査を行うことにしたいと思います、それと、朝霞さんのとても好きなものをきいておきます、それを見たときの反応をそうじゃないものと比較したいと思います」
「それがだいじだった、忘れていた、注視するだけじゃだめだからね、精神的な問題もある、高胎さん、ありがとう」
凡手医師が頭をかいた。
美澄が家に戻り、部屋に入ると同時にスマホがなった。高胎からのメイルである。次の検査をする日時場所が書かれていた。警察病院の眼科にくるようにと言うことだった。日時は変更できるともあった。それと、特別に好きなものは何か聞いてきた。食べるものでも、なんでもいいのだが、手に持てる大きさのものがいいということだった。それを向こうで用意するとある。プライベートのものであれば、例えば写真などでもいいのでもってきてほしいとのことだった。
病院にいく日時に関しては了承のメイル返信をおこない、好きなものに関しては、あとでメイルすることを書いた。
そのことで、揺花にメイルをうった。
すぐに返事がきて、その日、働いていた絵本会社の近くの、よくいくレストランで一緒に夕食をすることになった。
「どうだった」
揺花がいつもたのむカルボナーラを口に運びながらきいた。
「眼の検査もしたけど、おかしなというか、今まであったこともないような人たちと話をしたのよ、古い書に私と同じように、男性を狂わせる女性がいたことがのっていたようなの」
「狂わせるって、夢中にさせるって言うことでしょ、女性はみなそうじゃないのかしら」
「そうか、だけど、私は気が狂うと言う意味に聞いていたんだけど、それにそれを話してくれた人は、私の場合とは違うけど、と言っていた、だって私の場合は好きになった人だけ、しかも目を合わせたときだけのことだから」
「それでこれからどうするのですって」
「眼は全く正常だけれど、精密な検査をする気があるかどうか聞かれたので、すると言ったわ」
「どんな検査」
「物理的な調査や化学的な検査だそうよ」
「どこでやるの」
「警察病院よ、警察病院って一般の人もつかえるんですってね」
「そう、いいじゃない、なにかわかれば、美澄もすっきりするでしょう」
「ええ、揺花には心配かけてごめんなさい、やってみるきになったわよ、眼科の先生と、看護師さんのほかに、科学捜査の捜査官が三人いて、皆独特の雰囲気なの、揺花が紹介してくれた看護師さんが担当してくれるそうよ、もう、次の予定の連絡が着たわ」
「私の同級生が、高胎さんは相当しっかりした人だと言っていたわ、普通の大学出の看護師さんだから、我々よりかなり年上ね」
「ずいぶん落ち着いた人で、とても切れそう」
「それからね、特別に好きなものを教えてくれって、手でもてるものだって、写真なんかでもいいみたい」
「なににするの」
美澄はちょっと眼を伏せた。
「思い出したくないけど、そうしないといけないのかな、高校の時の彼の載っている卒業アルバム」
美澄は顔を上げて、遙花を見た。思ったよりさっぱりしている。いつもの美澄の顔だ。これなら大丈夫だ、もとにもどる。
「あ、そうだ、社長が、美澄さんさえよければ、体の調子がよくなったら、会社に戻ってもらえないか言ってたわ」
美澄の顔がちょとほころんだ。
「ありがとう、しばらく治療を受けてみてから考えるわね」
揺花は美澄が変わり始めているとはれやかな気分になった。
予定された日時に、美澄は警察病院の受付にいった。すぐに高胎がむかえにきて、研究棟に連れていかれた。
「これもってきました」
美澄が手にしたものを見て高胎はおどろいた。まさか高校の時の初恋の相手の写真を持ってくるとはおもわなかった。写真を持っていくと返事を受けたとき、母親か友達の写真だろうと思ったからだ。
「ありがとうございます、初恋の人はどの人でしょう」
美澄はアルバムをみただけで、初恋の男性の写真を持ってきたことに気づいた高胎におどろいた。そうは伝えていない。彼女の想像力がすごい。
個人の顔が写っているページをひらいて、彼を指した。
すると、高胎は「この男性はどういう人ですか」と彼の隣に写っている人を指差した。美澄はその同級生の名前を忘れていた。写真の下に印刷されている名前をみても、あまり話をしたこともなく、どんな子だったか思い出さない。そんな話を高胎に言った。
「はい、それでは、まず凡手医師の眼の検査から始めますので、こちらにどうぞ」
警察病院の検査室に案内され。凡手医師が笑顔で待っていた。
眼の表面を詳しく検査された。次に眼の動きの筋電図をとられた。それが終わると、高胎につれられてMRI室1と書かれた部屋に連れて行かれ、服が汚れるといけないからと、白衣のようなものを着た。女性の技師がまっていた。
はじめてMRIをみる。寝台の頭のところにトンネルがあるような機械だ。頭に何かを当てることは想像できる。
MRIというものを受けたことがない美澄は、頭を動かせない状態が数十分続くのはつらいと思った。
説明は高胎がしてくれた。
「これはファンクショナルMRIではなくて、ふつうのMRIです、脳の画像をとるものです。画像でどこか異常がないか調べることができます。まず朝霞さんの脳の画像をとります、寝たままトンネルの中に上半身がはいって20分ほど脳の画像をとる間、いろいろな大きな音が聞こえるので、気にしないで下さい、頭はできるだけ動かさないで下さいね」
美澄が台の上で横になると、途中でやめたいときは押すようにと、ボタン装置を手に握らされた。
大丈夫ですね、それでは始めますと技師が美澄をみた。美澄がはいと言うと、台が動き美澄の頭がトンネルの中にすいこまれていった。
どかたかたかた、どっどっど、ぐーいーん、いろいろな音が聞こえ、どうなるかと心配になるうちに二十分過ぎた。意外と短く感じた。
「だいじょうぶでしたか」
「はい、すごい音でした、誰かがわざわざ違う音を出しているみたい」
高胎はそれを聞いて笑った。
「ほんとよね」
機械からおりると、すぐに、コンピューターで脳の画をみせてもらった。画面に脳の切断面が映しだされる。自分の脳を見るのは初めてだ。おもしろい。こんな絵本をつくったらいいかもしれない。
「よく撮れています、眼もほらきれいにうつっている、脳の血管もきれいですね、いい脳をしています」
そう言ってくれた。
自分の目玉が脳の前に二つずいぶん丸く大きくうつっている。眼から脳につながる眼の神経が脳の中に入っていく形もみせてもらった。
「細かな説明は先生がしてくれます、次はファンクショナルMRIです、これはからだの動きは固定されますが、何かを考えたり、何かをみたりした状態の脳をしらべることができます」
そう教わって、どのようなことをするか説明を受けた。
別の部屋に入ると。そこには頭の部分がもっと大きくて全面にいろいろなものがついているМRIがあった。
「基本的には前のものとそんなに変わりません、ただこの中にはいって、ものをしっかり見ていただきます。それを何回か繰り返します、ちょっと大変だけど、耐えられないようなら言ってください」
そこに凡手医師がはいってきて、落ち着いたら始めることを告げた。
「はじめましょうか」
左の人差し指に血中酸素量をはかるオキシメーターと言うものをつけられ、MRIのなかにはいった。
目の前にある小さなモニターに写る写真を注視してくださいと、機械の中に備え付けのスピーカから、高胎看護師の声がきこえた。でてきたのは、夏目漱石の写真だった。それを見つめて漱石の吾輩は猫であるを思い出しながらMRIにかかった。
いったんトンネルの中からひきだされた。
「5分ほどしたらまたお願いします」
次はもってきた高校の同級生の写真が目の前に映し出された。彼の隣に写っていた男の子一人だけ引き延ばしたものだ。名前も覚えていない子だった。MRIにはいってみつめていると、教室の真ん中ほどに座っていた。何度か話したことがあったけど、そうだ、薬学系の大学に進んだのではなかったかなどを思い出した。そんなことで、おわった。
同様にいったん外にでて、五分後にまたはいった。
次の写真は、初恋の子だった。自殺してしまった。大人になった今見ても、すてきな男子だった。彼が生徒会長として、皆の前で堂々と話をする姿を思い出していた。そうあのと眼があったのだ。彼の目は熱く燃えていた。だが、自分にたいしてではなく、おそらく生徒会長として燃えていたのだろう。そんなことを考えていたら、終わっていた。
「ごくろうさまでした」
高胎さんが手を貸してくれ、下におりた。
「お疲れさまです、今日はこれまでにしておきましょう、この結果ですべてが分かるわけではありません、何回かきていただかなければならないのですが、だいじょうぶでしょうか」
凡手医師がそういった。
「この結果は、次にお話しします、専門家を交えて検討を加えます」
検査服を脱いで上着をきると、高胎看護師が出口まで送ってくれて、アルバムを返してくれた。
「よく写真をもってきてくれました、次は眼球運動について調べることになります。眼を動かす筋肉の様子を調べることになります」
美澄はこのように脳の中まで調べてもらうことなど考えてこともなかったので、どのような結果になるのか、楽しみにさえなってきた。
夕方、第八研究室の人たちはセミナー室に集まった。美澄の脳の結果を、脳神経内科の専門家ととともに解析することになった。
「脳のそれぞれの部位のことは、専門的知識のある人にみてもらいました。まず朝霞さんの脳は構造的には他の人と顕著に異なるような部位はみつからなかったということです。次に写真に対する反応は、まず視覚の情報が入る後頭葉、それに二次、三次視覚野とされる側頭葉などはそれなりに反応がみられ、三つの写真に対する違いは特にないようです。視覚情報を言語に置き換える部位などにも同じ反応が起きています。ただ初恋の男性の写真に対しては脈拍がすこしはやくなりましたね。それと、前頭葉と扁桃体、海馬も少し色が濃くでましたね、やはり恋の経験はいつまでも残っているということがわかりましたが、それだけです」
「恋に落ちるという人の脳のメカニズムはわかっているのですか」
吉都が質問した。
「いや、不思議なメカニズムですね、なかなか好きになると元に戻れない、どこが関与しているのかわからないのですよ、ただ、朝霞さんの結果をみてもわかるように、もう恋のような強いものはのこっていなくても、特別な記憶として濃く刻まれていることはわかります。そういうものは恋ばかりではなく、強い刺激が長く残るというということです、まあ一般的に知られていることです」
「恋がトラウマになるメカニズムですね」
古書が言った。
「何でも強い刺激はトラウマになる、それはファンクショナルMRIではっきりしたわけだけど、彼女の眼についてはなにもでてきませんでしたね」
宙夜が凡手のほうを見た。
「そうでしたね、心理学者はファンクショナルMRI依存で脳と心理を解析しようとしているけど、MRIだけで脳の中の数え切れないほどの神経の働きを見ることは無理だよね、MRIを繰り返してもしょうがない、別のアプローチが必要だな」
凡手もうなずいた。
次に警察病院に行った美澄は、凡手から、自分の脳の写真を見ながら、細かな報告をうけた。凡手は結果が得られなかったと言ったが、美澄は初恋の男の写真を見たときに、ほかの写真と違い、脳の前の部分や、いくつかの部位で色が赤く濃くでていたことに、驚いた。恋をするとそこが働くのだと言うことを目で見ることができたのである。すごい、と思った。それにファンクショナルMRIによる脳の写真は赤黄色緑、青のグラディエーションになっていて、話すときの脳の色、食べるときの脳の色、お母さんと一緒のときの脳の色、お父さんと一緒のときの脳の色、こうした絵本になると思った。
その日は頭や、目の回りに電極というものをはりつけられて、眼を左右上下斜め、いろいろ動かし、さらにまた、写真を見せられ、半日にわたって脳波をとられた。脳の働きを調べるのは大変なことだということもわかってきた。
「朝霞さんの眼を動かす筋は丈夫にできています、言い換えると、しっかりとしているということです、ご存じでしょう、芸術家で、細かな作業をする人は腕の筋肉が発達しています、しっかりした筋肉があるからこそ、脳はそれにむかって、細かな指示をすることで、細かな動きをさせることができるのです。朝霞さんの眼の筋が発達しているということは、細かな眼の動きができるということにも繋がります。ただ、それが霞さんの懸念していることに関わっているのかどうかはわかりません」
凡手医師はモニターに映し出されているグラフをみながら説明してくれた。
何回警察病院にかよっただろう、いつ終わるのかというちょっと疲れた気持ちになってきたとき、遥花からメイルがはいった。
「同級生からメイルがきたわ、とてもむずかしいと、警察病院の人たちもいっているそうよ」
「ありがとう、いろいろな検査をしたわ。初めての経験で、だけど、脳がとてもおもしろいものだとわかってきたわ、脳の絵本をつくったらいいわね」
「それはいい考えね、でも、テレビによくでている脳科学者ってなんだかいかさま臭くて」
「心理学での人だからでしょ、わたしいい経験しているわ、脳神経のことを基礎から知っているお医者さんに相談しなければだめだなと思うようになったわ」
そんなやりとりをした。
揺花は美澄が絵本のことを言うようになったことを喜んだ。
次の週に美澄が警察病院に行くと、高胎看護師が今日は検査がない、と言った。応接室に通されると、捜査支援分析センター第八研究室の人たちが集まっていた。
「朝霞さん、ご苦労様でした、私どもできる限りの検査をした結果を今日お話しします」
凡手医師がそう言って、さらに
「朝霞さんの眼には毒がありました」
と結んだ。
それを聞いて、高胎看護師が笑い顔になった。
「先生、そんなことを言うと、朝霞さんがびっくりするじゃないですか」
「あ、そうか、失礼しました、毒というのは、影響を強く及ぼす薬で、人の体をあぶなくすることもあれば、使い方によって病を治してくれるものです、影響を及ぼすものと言うことで言ったので、どうもすみません」
「先生、その説明はとても説得力がありますよ、毒をもっている動物は魅力的だ」
古書がそういうと、吉都希紅子が、
「古書さん、なにいってるの、朝霞さんが魅力的と言ってるわけ」
「あ、そういうわけでは、いや、魅力的ですが」
古書があわてて頭を書いた。
美澄はこの人たちをおもしろいと思わずにいられず、つい笑ってしまった。
「ほら笑われた、おまえたち、もっとまじめにやんなさい」
いきなり野太い声が聞こえて、いや響いて、美澄はおどろいた。見ると、一番端にがっしりとした、と言うより少し太り気味の大きな男がすわっている。
美澄が誰だろうとそちらを見ると、
「いや、内の若いもんが、失礼しましたな、責任者の薩摩冬児です」
凡手が笑いながら、
「第八分室の室長で、警視正の薩摩さん、不思議な事件をたくさん解決してきた方なんですよ」
説明を加える。それに薩摩警視は、
「いや、この連中がみんなで解決してくれましてね、ワシなんてただいるだけですわ」
とつぶやいた。
これが警察の人なのと、美澄は暖かくなった。
「それで、我々の結論を言いますね、これが正しいかどうかわかりませんが、おそらくそうだろうというくらいのものです、この宙夜さんが、気がついたことなので、宙夜さんから説明をしてもらいます」
「宙夜です」
ちょっと小柄だが、きびきび動いている男性だ、物理学と言っていたっけ、いったいどういう人だろう。どの人もひと癖もふた癖もある。
「私は鉱物の結晶、とくに水晶について研究を進めてきました。特定の鉱物結晶は電波を増幅することをごぞんじですか。昔鉱石ラジオというものがありました。王鉄鉱や方鉛鉱などの鉱物はアンテナでとらえた電波から音声信号を取り出す作用があります。それを利用したのが、鉱石ラジオです。それらの鉱物が持つそのメカニズムはまだ明らかにされていません、現象だけわかっていて、人間は利用したわけです。
水晶は残念ながら鉱石ラジオには使われていません、そういう現象を持たないからです。ところがご存じだと思いますが、水晶発振時計というのが当たり前に使われています。クオーツと言う時計です。電波時計がつくられる前まではもっとも正確な時計でした。水晶は電圧を加えると発振、一定の電気信号をだします。原子レベルの振動です。それで時刻を示す針を調整して動かすわけです。このように原子レベルの振動発振が身の回りで起こっています。
そこで、人間の体のどこかにそのような現象が起きないかと考えたわけです。脳波ではありません。
脳からの神経指令により眼球を動かす筋肉が収縮して、見たいものの方に目を向けます。もし、眼球が人の眼にはわからないほど早く振動したら、もしかすると、微弱だが音のような空気の振動を作らないかと考えたわけです。
皮膚には体毛が生えています。寒いと鳥肌が立ちます。それは、寒さにより交感神経が働いて、体毛をたたせ、寒さを防いでいるわけです。怖い目に遭うと同じ症状がでます、感情が筋に影響を及ぼすわけです。
寒いときには鳥肌ばかりではなくふるえます。それは身体でも、部分を収縮させる筋と、伸ばす筋が同時に働くので生じる現象です。震えることで熱を作るわけです。やっぱり怖いことがあると身体ががたがた震えます。熱を作ってからだを温め、すぐ行動に移せるようにする役割を持つとも解釈されています。
ともかく感情が筋に影響を与え、ふるえを作り出すわけです。
身体を思い切りかたくすると、こきざみなふるえがでてきます。
左右上下斜に目を動かす筋肉が眼球にはたくさんついています。一つの眼に六種類もあります。外眼筋とよばれています。それは何種類もの神経によりコントロールされています。外眼筋に来ている神経繊維をだしている細胞は中脳というところにある、神経細胞の集まりである神経核にあります。そういった神経核がたくさんあります」
朝霞さんの外眼筋の働きをモニターしました」
美澄は電線が機械につながっている吸盤のようなものを眼の脇に張り付けられて、なんどもテストをやったことを思い出した。
「まず、朝霞さんの眼の筋肉はどれも太くて丈夫にできています、そこにきている神経については、他の人と違いはありませんでしたが、感情によりその神経の働きが強まりました。しかも、眼球を右に向ける神経と、左に向ける神経が同時に収縮していました」
美澄はあっと、思った。彼の写真をみせられたときだ。
「きづかれたようですね、眼球が震えていました。とらえることはできなかったのですが、おそらく、なんらかの信号、音波、がでていたのではないかと思います
感情が高ぶると、涙を流すことはだれも知っていいます。感激しても悲しくても涙がでる。涙腺にいっている交感神経という自律神経によって分泌が嵩まることで涙がでます。感情を司る脳の部位が交感神経とつながっていることでそうなるわけですが、これも推測ですが、朝霞さんの眼球を動かす筋肉にいっている神経の中に、涙腺にいっている交感神経がまじっているのではないでしょうか。
恋愛感情が芽生えると、動眼筋にいっている交感神経が興奮し、眼球がふるえる結果をもたらす。音波に相当するものが放出される現象がおきたのかもしれません。その電磁波が相手の脳に感じ取られると、自殺を誘起したのかもしれません。
鬱状態というのは脳の中のセロトニンという神経伝達物質が低下します。朝霞さんの眼からでた音波は相手方の脳のセロトニンを低下させ、鬱状態を急激に作った可能性があります」
驚いた。そんなことがあるのだろうか。
「あくまでも仮説ですが、宙夜さんが言ったように、朝霞さんの眼を動かす筋については事実です、他の人とちょっと違います、それが原因の可能性はあります」
美澄は思い切って質問をした。
「私の眼が毒だったとして、防ぐ方法はあるのでしょうか」
「もちろん大丈夫です、仮説のとおりだとすると、簡単に防げます、眼からでる音波をメガネなどで防げばいいわけです。ただ、音波は強いものではないでしょうから、ふつうのメガネで十分でしょう」
そう聞いて美澄ちょっと安心した。
「検査を続けてもいいのですが、少し時間をおきましょう、終わりにしてもかまいません、音波が眼からでるとしても、まだ微細な音波を測定する方法も機械もありません、いろいろデータをとらせていただきました。ありがとうございました、それにたとえそんな音波がでていたにしても、それを感じるほうの仕組みは全くわからないので、すべて仮説です、誰かが一生かけて朝霞さんを調べてもわからないことかもしれません」
凡手医師の言葉に美澄はうなずいた。周りの人たちが立ち上がったので、美澄も立ち上がった。
「お聞きになりたいことがあったら、いつでも私に連絡してください、とりあえずおわりにしましょう」
高胎がそう言った。
美澄はなぜかわからないが、なみだがでそうになった。半分涙声でみなに向かって頭を下げた。
高胎看護師が出口まで送ってきてくれた。
「高胎さんは警察病院の眼科にいらっしゃるのですか」
彼女はほほえんで、「いえ、私も刑事課捜査支援センター第八研究室の分析官です、もちろん看護師の資格は持っています」とおじぎをした。
美澄はだいぶ驚いた。すごい人。
丁寧にお礼を言って、警察病院をでた。
そのあと、第八研究室のメンバーと、凡手医師があつまった。
「宙夜さんの話はすごかったね、水晶からはいるとは思わなかった」
「いや、僕の専門ですから、でも本当に何かあるかもしれない。猫や犬はまともに主人の目を見て、なにを言っているのか理解するでしょう、もしかすると、愛情の眼というのは音波のようなものを発しているのかもしれない」
「宙夜さんはSF作家にもなれそう」
古文書を解析するまじめな古書がうらやましそうに言う。
「野夢さんにこの話を聞かせたら、小説を書くかもしれない」
野夢とは巣鴨にある庚申塚探偵事務所所長の奥さんで、いくつも小説をだしている。所長の詐貸美漬は第八研究室長、薩摩冬児と大学のサークル仲間で、難事件を一緒に解決してきた。捜査官の吉都希紅子はその事務所の探偵、吉都可也と結婚している。
「朝霞さんの件はどうしようか」
室長の薩摩が精神神経眼科医、凡手公平に尋ねた。
「もう少し整理して、眼のふるえという現象としてとらえて、科学的な検討を加えれば、新たな体のメカニズムとして教科書に載るくらいの発見になります。本当に音波がでている、でていないはその先の話で、眼も寒いところでは熱が必要だから、そういう機能があってもいい。これに気づいた宙夜さんはノーベル賞ものだ」
「それは朝霞さんで調べる必要はないよね、凡手先生におまかせしよう」
「そうですね」
「朝霞さんからは何か連絡があったら先生に相談します」
「おねがいします
「みんな高胎君のおかげだよ、朝霞さんもこれがきっかけで、眼の孤毒が消えたようだから、よくなりそうだね」
薩摩警視は孤独と毒をくっつけてしまった。
「それじゃ、われわれの毒消しに、今夜は巣鴨の神無月にいきますか、庚申塚探偵事務所の連中も呼んで、凡手先生はじめてでしょう」
宙夜がそういうと、凡手医師はうれしそうにうなずいた。酒はすきそうだ。神無月は巣鴨にある、第八研究室スタッフと庚申塚探偵事務所のスタッフが集まる居酒屋だ。
それから一月後、高胎に朝霞からメイルが入った。直接あって話したいと言うことだった。
高胎は警察病院に来てもらうより、もっと明るいところの方がよいだろうと思い、神田の古本屋街にある古い喫茶店で待ち合わせをした。
高胎が約束の時間より少し早く行ってまっていると、グレーのツーピースをきた朝霞がさっそうとはいってきた。
彼女が笑顔で高胎をみた。
高胎はどきっとした。柔らかいがすごい眼だ。目力がある。孤独の眼ではない。孤でなくなり、毒だけ残っている。
「おひさしぶりです、おかげさまで、私、出版社に出戻りです、また絵本を作ることになりました」
眼はそのままだが、心は全く治っている。ふっと、この女性がまた誰かを愛して、その男が自殺するようになるのではないかとすら思った。
彼女は細い銀縁のメガネをだすとかけた。
人が考えていることも読める。
高胎がおどろいていると、「どうでしょうメガネをつくりました、これなら好きな人ができても大丈夫でしょうか」
彼女が高胎をみた。
確かに柔らかくなる。
「元気になられましたね、よかった、メガネよく似合います、それなら大丈夫ですよ」
「高胎さんがいなければ私、立ち直れなかったと思います、ありがとうございます、みなさんにもお礼言いたい、宙夜さんてすごいですね、科学と文学の垣根なしで話すことができる」
「彼だけではないんですよ、うちの連中みなああなんです、それで、今日おききになりたいことはなんでしょう」
「眼はもういいんです、ご相談は、絵本のことです」
「絵本というと」
「脳の絵本を作りたいと思っています、ただ科学的ではなく、ええーっと子供たちが驚くような、生きていて、見ていて、しゃべる脳のお話を」
「おもしろそうですね」
「第八研究室のみなさんからアドバイスいただきたいと思って、いや、第八研究室著作の本でもいいと思い、高胎さんにメイルしました」
ぎょっとした。警視庁刑事科、科学捜査分析センター、第八研究室が絵本を出す。そんなことができるのだろうか。みんなは面白がるかもしれない。薩摩さんは困ったなというだろう、それにしても野霧さんに相談しなければならないだろう。
「みんなに伝えてみます」
「楽しい本にしたいんです」
「あの、野霧という作家をご存知でしょうか」
美澄はうなずいて、
「八人のヒミコや夢久家(むくけ)の人々ですよね、変った探偵小説で面白かった」
と言った。彼女は野霧を知っている。
「野霧さんは巣鴨の庚申塚探偵事務所所長の奥さんで、ヒミコの事件では私たちも手伝ったのですよ、捜査員の吉都喜久子のご主人はその探偵事務所の探偵さんです」
美澄は驚いた。
「あれは本当にあったことなんですか」
「ええ、そうなんです」
「野霧さんにもお話うかがいたいです」
「紹介してあげますね」
結局、美澄が第八研究室にきて、室長の薩摩にその話をすることになり、喫茶店をでようと、立ち上がった。そのとき、
「眼は脳の一部とありました、脳は寒いと振動して暖かくなろうとするのでしょうか」
と朝霞美澄が言った。
高胎はびっくりした顔を隠せなかった。
宙夜が言ったことと同じことを言っている。
孤毒の目


