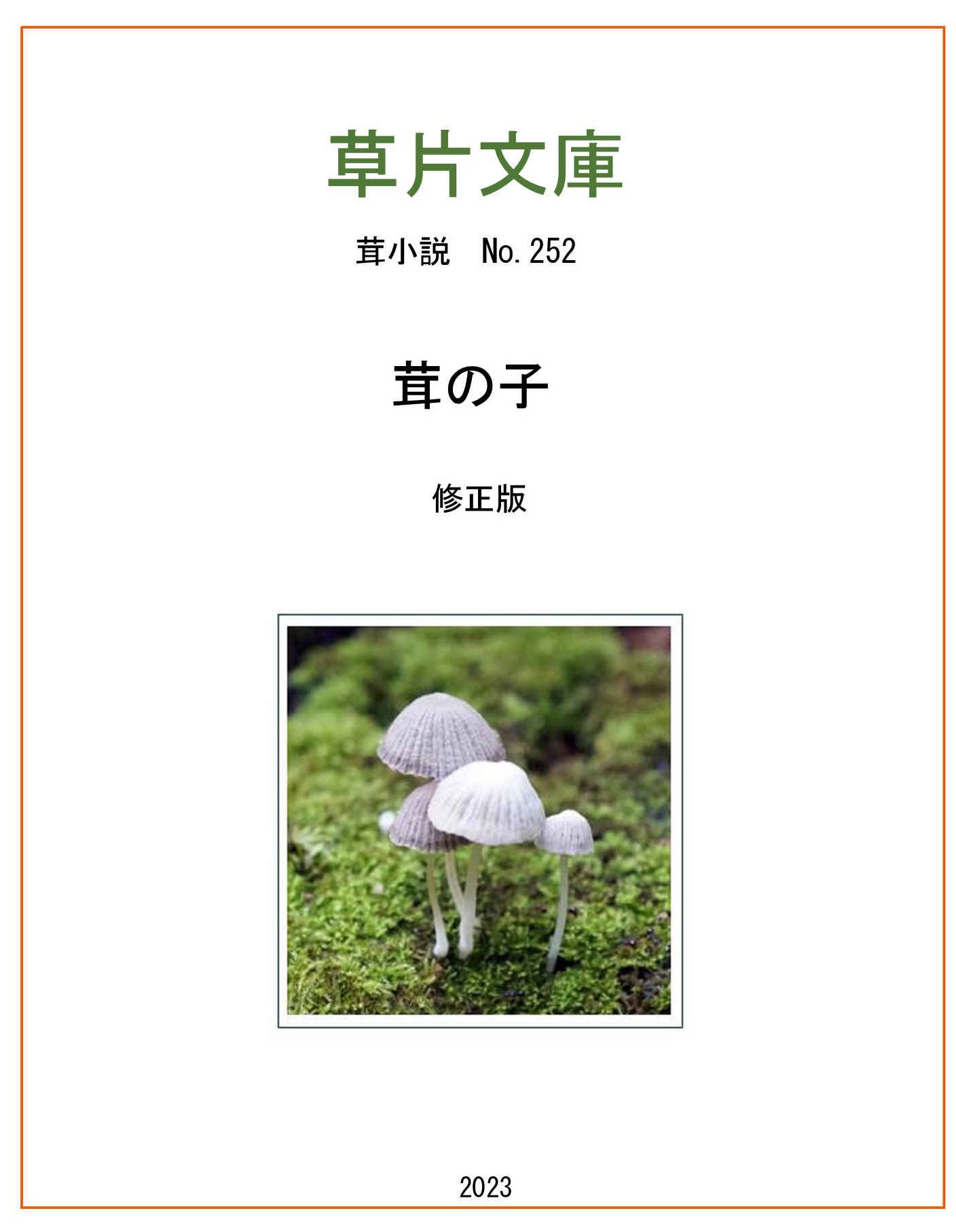
茸の子
彼の仕事は自費出版会社のマネージャーである。最近はネットでの自費出版注文が多いが、直接会社に来て細かに注文をするひともいる。そういった人はかなり装丁に興味のある人で、天金を希望したり、マーブル紙や手漉きの和紙を使いたいという人もいる。彼は自費出版のアドバイザーの資格をもっており、そういう人たちの相談に乗ったりする仕事である。
秋のある日、朝早く目覚めた彼は、日帰りで山にでもいくかと、気軽なハイキングという本を開いた。彼としては珍しく外にでる気になった。天気もいいし、ちょっとした山道を歩くと、茸も顔を出している。
休みの日は必ずと言っていいほど古本屋巡りで、神田を中心に、めぼしい古本屋に足を運ぶ。彼の家には早世した父親が残した本が入った棚が居間に並んでいる。父親は本が好きで、若い頃から何人かの作家の著書を買い込んでいた。小説本を好み、だが、直木賞だとか芥川賞には興味がなく、自分にとっては面白いと思う作家の本が集まっている。彼が子供の頃、父親がとても残念がっていたのが、久世光彦という作家のことだった。売れていたテレビドラマの脚本家でもあったようだが、ある時から小説を書き、戦後の風景、映画や絵画についてエッセーを書きはじめたそうだ。その作家は70にして急になくなり、その後でた本をすべて買い込んでいた父親をおぼえている。親父は彼が大学に入る前に脳溢血でなくなってしまった。
彼が大学生になった頃、その本を開けてみて、書かれていることもおもしろく、文体も気取らないわかりやすいものでありながら、個性が光っているものだと言うことを知った。それだけではなかった。A5判の本が多く、中島かほる、立石修司によるきれいな装丁のものが多い。カバーをとった本体は、どれも銀色にきらきらしていて、あたかも浮世絵の綺羅刷りのような雰囲気を持った本であった。
そんなことで、彼も本の世界に引き込まれたのだが、集めたのは全く違う、世界の茸の本である。その中でも写真のものではなく、きれいな絵図のものを集めていた。茸がなぜか好きだったからだが、といって茸を研究しようとか、美味しい茸の料理をたべにいこうかということではない。本になっているものがいいのだ。
茸に惹かれたのは庭に生えてきたアミガサタケにであったからだ。家の者はみな気味悪がったが、まだ小学生だった彼だけ、茸って奇妙で面白いと思い、山などに行って茸をさがすようになった
自分で茸の写真をとるようになったが、大きくなるにしたがって、綺麗な茸の絵に興味が移り、そういった本を買うようになった。文学部に入った彼は北欧文学にふれ、茸の挿絵の入った本に出会うことになった。今でもヨーロッパの茸の本をあさっているわけである。自分の部屋にはそういった本がずらりと並んでいる。
彼は山歩きの本を開いていて、滝のあるところに行くことに決めた。滝つぼの周りには色々な茸がはえるものである。
都内に住んでいる彼は、丹沢や秩父、近くは高尾山などあるが、名の知れたところは、休日はとても人が多い。千葉、房総もいい。本をめくると、滝と名のつくものがぞろぞろでてくる。黒滝、白糸滝、南玉不動滝、内梨滝、雨降り滝、どれもすごい、養老渓谷には六つの滝巡りなどと書いてある。
やめた。今度は湖をさがしてみた。高滝湖、亀山湖、雄蛇ヶ池、八鶴湖、やっぱりたくさんある。鶴だ蛇だ亀だと動物の名前が多い。亀山湖はとても古いダム湖で、久留里線で上総亀山駅からいく。雄蛇ヶ池(おじゃがいけ)は江戸時代の用水地で周りを歩ける。今はブラックバスなどがいて、釣り人に人気があるらしい。おまけに心霊スポットまであるという。八鶴湖ははっかくこと読む。家康の御殿づくりの時に広げた人造の湖のようだ。それにしても自然の湖は少ない。それでもいいかと思い、東金市の雄蛇ヶ池にいくことにきめた。東金線福俵駅から30分ほど歩くことになるが、東京駅から特急わかしおにのり、大綱で、東金線に乗り換え一駅だ。1時間でいく。ちょうどいいところだ。
ザック一つの身軽ないでたちで出かけた。
電車もそんなに混んでおらず、ゆったりと座れた。福俵駅から池までも茸を探しながらの散歩で楽しい。山間の道をいくと、かさかさと風によって林の中の落ち葉がすれる音も心地よく、来てよかったと深呼吸した。ところどころで茸が見られたが、写真機を向けるほどものにはであわなかった。
池までだいぶ近くなったのではないかと時計を見ると針が止まっている。昭和の自動巻きが出始めた頃の時計だ。古道具屋で購入したのだがしばらく使っていなかったが、引き出しからとりだし、軽くふって時間合わせをしただけだったのがいけない。腕につけていれば自然に巻けるだとうとおもっていたのが間違いのようだ。機能が低下しる。いや、自分の手の振り方が十分ではなかったのかもしれない。
スマホを取り出そうとしたとき、斜面の下の方から、水の落ちる音が聞こえた。滝のようである。駅においてあった蛇ヶ池の案内マップには描かれていない。
少し先まで歩くと、木々の間に下に降りる道が見えた。ちょっと降りてみるかと、その道にはいった。道の脇のまだ青青としている羊歯の下には茸がいくつも顔を出している。天狗茸の仲間やイグチの仲間がある。千葉は茸がいいところで、茸愛好会の出す会報が茸仲間でではよく知られている。
緑色の茸が数本固まって生えている。かなり珍しい茸ではないか、カメラをリュックから出した。昔はどんな茸でも写真機を向けたが、今はこれはと思う茸だけ写真を撮る。
緑色の茸は数種類あるが、名前はわからない。家に戻ってから調べてみよう。
さらに降りていくと、水の音が高くなってきた。滝があるに違いがない。
木々の間から大きな石が転がっている谷川が見えてきた。思った通り池につながる川のようだ。
小さな谷川だ。河原に降りると上流に小さ滝が見えた。石ごつの中をあるいていくと、三メートルほどの滝が、これまた四畳半ほどの滝壺に水を落としている。かわいいし形がいい。滝のミニュチュアだ。庭先にこんな滝があったらとてもいい景色になる。近づくと、滝の脇の羊歯の葉に緑色の布のようなものが数枚かかっている。
ぬるぬるしていそうで、ちょっとさわる気がしない。何かの分泌物か、排出物か、卵だったりするかもしれない。何だろうと思って顔を近づけて見ていると、滝の音にまじって、人の声が聞こえた。
「ほら、人が来てしまった、どうするの」
「いやね、いっちゃうまでまってましょ」
「昼間からきたいって言うからいけないのよ、やっぱり夜じゃなきゃ危ないわよ」
「しー、こっち見てる」
気のせいかと思ったが、あまりにも内容がはっきりわかった。
林の中を見たが、人が動くような気配はない。
「きゃーやだ、ナメクジ来たわよ」
「ほんとだ、やなにおい」
「しょうがないでよう」
そんな声が聞こえたと思ったら、滝の中から四人の小人が飛び出してきた。
「はやくはやく」
裸の女の子だ。ミルク色のからだをしている。こどものようなからだをしているが、大きな乳房を揺らしている。
彼女たちはあわてて羊歯の上にかけてあった緑色の布をとると頭からかぶった。
そのまま、林の中にかけていく。
あの緑色の茸だ。
なにが起きたのか。
滝の中から、赤茶色の大きなナメクジが顔を出した。こいつに追われてあの娘たちはでてきたのか。
最後の茸が林の中に飛び込んだ。
おいかけよう。
林の中にはいると、斜面を走っていく緑色の茸が見えた。
おいかけていくと、さっき、写真をとった緑色の茸のところにでた。
四つの緑の茸はクジャク羊歯の下に集まるとゆらゆらゆれている。
大きな茸だ。
夢なのかもしれないと思いながら、カメラを四つの茸に向けた。何枚も写真を撮ると、さわってみようかなやんだ。
手を伸ばして人差し指を茸の傘にふれようとしたら、「やめたほうがよくてよ」
と声が聞こえた。
手を引っ込めると、緑色の茸の一つの傘が揺れた。
「賢明なこと、見たことは忘れなさいな」
また声がした。
ふっと、「写真をとらせてほしい」と思いついたことをいった。
「それで、どうするの」
「本を作る」
「どんな」
「緑色の茸の妖精の本」
「やめてよ、妖精なんて、あんなうそつきやなこった」
「どうしてうそつきなんだい」
「あの肉食、妖精なんて子供たちの夢を食い荒らし、しまいには子供の脳に住み込んで、ばい菌になっちまうんだ」
「そんなことはないだろう」
「妖精で育った子供たちが、純真のままでないでしょ、大人になればみんな金儲け」
「それはそうだが、それで写真をとらせてくれるのかい」
「それほどいうのならいいわよ、ほらカメラを構えていなさい」
四つの大きな緑色の茸にカメラを向けていると、ぶるっと緑色の茸の柄がふたつに裂け、中からミルク色の女の子が四人でてきた。
「ほら、撮っていいよ」
それぞれの女の子がポーズを作ってにこっと笑った。
あわててシャッターを切ると、女の子たちは緑色の茸の中に飛び込んでしまった。
一眼デジカメのディスプレーに撮った写真をだしてみた。ちょっぴり、いや、かなり四人の女の子の裸体が出てくるのを期待した。だが、画面に出てきたのは四体のミルク色の骸骨だった。
「残念ながら肉体は写らないのよ」
緑色の茸から声が聞こえた。しょうがないか。
「周りの小さな緑色の茸たちも中に女の子がいるのかい」
そう聞いてみた。
「いるわよ、三年たてば、私たちと同じ大きさになるのよ」
「女の子だけなの」
「ねえ、人間さん、女の子ってなあに」
「だって、茸から出てきたミルク色の君たちにお乳があったじゃないか」
「ああ、あれがあると女の子って言うの」
「男の子にはないんだ」
「でも、男の子と女の子ってなあに」
「動物はその二つで子供を作るんだ」
「そうなの、私たちは男も女もないわよ、みんなでてきていいわよ」
そんな声が聞こえると、周りの小さな緑色の茸の中から、ミルク色の人間の形をした生き物がでてきて、うろうろしはじめた。胸には乳房があり、股間はつるんとしていて、なにもない。人間の女性の形だが、どこか違う。
「その乳房はなにのためにあるの」
「この膨らみはね、胞子の製造装置よ、胞子をつくって傘の下の襞のあいだにつるすのよ」
小さなミルク色の女の子が彼の前に集まってきた。
「あんた、ここへなにしにきたの、赤黒ナメクジの手下じゃないでしょうね」
「散歩にきただけだよ」
「あたいたちを食べようって言うんじゃないわよね」
「もちろん食べないさ、きれいだから写真をとったんだ、家に帰ったら、名前を調べようと思う」
「なによ、名前なら聞けばおしえてあげるじゃない」
「なんていうんだい」
「緑の乳の風の茸よ、乳緑茸」
「きいたことがないな」
「大昔からいるのにね」
彼は彼女たちの写真をとった。ミルク色の小さな女の子たちが思い思いのポーズをとるものだから、我を忘れてシャッターをおした。
小さな女の子から、風の匂いがしてきた。とてもさわやかで、言われ古した言葉かもしれないが、牧場の香り、草の香りだ。
おや、甘い匂いになってきた。搾りたてのミルクの香り、蜂蜜がそれにくわわった。
次第におなかが空いてきた。彼は目に入ったヘビイチゴの赤い実を口に入れた。彼女たちの香りが口いっぱいに広がった。そうか、ヘビイチゴはミルク色の女の子たちの味なのか。
おいしい。そういえば今日家をでてからなにも食べていない。もっていたペットボトルのお茶をのんだだけだ。
ミルク色の女の子たちが、ひそひそ話をしている。
「あの人間、ほら、赤茶になってきてるよ」
「そうね、まさか赤茶なめくじの化身じゃないかしら」
「そうだと、わたしたち食べられるのよ」
「乳緑茸はとても甘くておいしいから」
彼の耳にそんな会話が入ってくる。
「あ、やっぱり赤茶なめくじだわ、みんな家にはいるのよ」
一人の女の子が声を上げた。
茸の中にみな飛び込んだ。周りの小さな乳緑茸にも、小さな小さな女の子たちがとびこんでいった。
彼は甘い蜜の滴る乳緑茸をみつめていた。
すぐ目の前に、甘い香りを強く発する乳緑茸、食べたい、と思った。
ヘビイチゴの花粉で作られたミツバチの密。
ふと乳緑茸を見ていた彼がカメラを落とした。
緑色の茸の傘から、ヘビイチゴの蜂蜜がながれだしていた。
手を伸ばして一つの緑の茸をもぎとった。
「きゃー、赤茶なめくじだー、助けてー雄蛇さん」
そんな声が彼の耳にきこえてきた。雄蛇ってなんだろう。そうか、雄蛇ヶ池にきたんだっけ。
緑色の茸を口にいれた。あまいあまい、すっぱい、汁が口に広がり、やがてミルクのかかったイチゴの味に変わり、彼の喉にながれていった。
もう一本もぎとると、口にいれた。
こんなにおいしい茸が世の中にあったのか。
もう一本大きな緑の茸に手を伸ばした。。
もっと食べたい。
彼は手に持った茸を口に入れようとすると、パンと割れて、中から乳白色の蛇が顔を出した。
蛇が彼の舌をかんだ。
「痛て」
彼の頭が土の上に落ちた。
彼はクジャク羊歯の下ではいずった格好で、乳緑茸の香りに包まれ、固まった。
木の上から動物が見ている。リスのようだ。日本リスじゃないな、おおきいじゃないか。そうか台湾リスか。
蚊が飛んできた。彼の鼻の頭にとまって口吻をのばした。赤茶色の血が蚊のからだに吸い取られていく。蚊がころりと鼻の頭から落ちた。
苔の上に落ちて足をぴくぴくさせている。
蚊は死んだ。
目は瞑っているがみな見えていた。
木々の間にそよぐ風で、枝のすれる音が聞こえる。
土の上の手の甲に座頭虫がのぼってきた。こそばったい。
皮膚の感覚もあった。
だが、彼は体を動かすことができなかった。
夜になり、かなり冷たい風がほほにあたった。目の前をムカデが走っていく。夜が更けてくると、かさかさと、ネズミが枯れ葉をかきわけてくる。
ネズミが彼の着ている服の上にのぼってきた。
手で払いたいと思ってもては動かない。
ネズミがズボンに穴をあけた。だが、彼の足にかみつこうとはしなかった。
夜のあいだじゅう、虫が彼の上にのぼってきたが、けっしてかみついたりしようとしなかった。
やっと、薄明るくなってきた。朝がきたのだ。もうすぐ日が昇り、林の中も明るくなるだろう。
ミルクの匂いがただよってきた。
彼の指の皮膚がぷちっと割れると、小さな白い腕がでてきた。ミルク色の小さな女の子が彼の手の甲の上でのびをした。
他のところからも出てきた。
ネズミがかじりとったズボンの穴のところでも、皮膚を破ってミルク色の女の子が出てきた。
林の中に日が射してきた。
彼の手の甲と足から緑色の茸が頭を出すと、朝日を浴びてのびてきた。
「できたわよ」
ミルク色の女の子たちは緑色の茸のなかにはいった。
茸がぐーんとのびていった。
そのとき、彼は体中が火照り、気持ちがよくなった。射精の際のオーガズムスと似ていなくはないが、股間とは結びつかない、脳の中に新たな快楽の仕組みがあることを彼は認識した。
本を読むことはこの快楽の仕組みを刺激しているのではないか。まだ人類が気づいていない、知ることの快楽の仕組みが、緑茸が生えるときにだされ物質によって強く刺激されたのに違いない。
そのあと、眠気がおそってきた。それまで、林の中ではいつくばったまま硬直していた彼は、眠ることなく外からの刺激に翻弄されていたのである。
しばらくすると、人間の声が聞こえて、目を覚ました。
「こんなところに来ているとは思いませんでした、確かに彼です」
自費出版会社の上司、いや社長の声だ。
「こんな遠くまで来ていただきまして、お手数おかけしました、彼には妹がいますが、いまニューヨークで、すぐにはこれません」
この人は誰だろう。
「なくなって何日目ですか」
「あの、実は亡くなっていないのです、硬直はしていますが、医者の話では、感覚の反応があり、神経系は生きているということです、弱いのですが、脳波もでているということです」
「刑事さん、それならどうして、病院に運ばないのですか」
「医師の話では、動かすと、どのようなことが起こるかわからかないということです、動かしたとたんに脳波が消えるかもしれないそうです」
「どうしてこうなったのです」
「ハイキングにきたようですが、ここで、茸を食べたようです、茸の小さなかけらが、歯の間にはさまっていたということです、毒茸のようです」
「彼は茸が好きで、茸の本を集めていました、茸の知識はそれなりにあったはずで、始めて見た茸を口に入れたりはしないと思うのですが」
「彼以外に誰かがいた形跡はありません、誰かに無理矢理食べさせられたということはないようです、ということは自分で食べたくて食べたとしか言いようのない状況です」
「どれでしょうか」
「ほら、彼の顔の脇にはえているでしょう、緑色の茸、どうもその茸をたべたようですな、名前はまだ付けられていないと、科研の茸の専門家が言っていました」
「それにしても、このままじゃかわいそうです」
目を覚ました彼は、またからだじゅうが熱くなってきた。脳の中に快楽がうずまきはじめた。
「あ、またはじまった」
自費出版社の社長が彼を見ると、洋服の破れのところから、緑色の茸がにょきにょき生えてきた。
「なんですかこれは」
社長の驚いた声が聞こえたが、彼の脳の中では快楽が渦巻いて、声はかき消されていった。
「我々が、彼をみつけて一週間になりますが、二日おきに緑色の茸が生えてきて、枯れて、また生えてきてを繰り返しています、茸の近くにはよらないでください」
「冬虫夏草という虫につく茸のことは知っていますが、その種類ですか」
「いえ、そうではないと、科捜研の担当者は言っていました、幻覚を引き起こす物質を放出して、それを吸うとおかしくなるようです」
「幻覚茸でね」
「私は茸のことはよく知らんのですが、まあ、そのたぐいのものだと思います、だけど、食べると、からだが硬直し、動かなくなり、茸の胞子が皮膚からはいって、茸になるのじゃないかという話です」
「彼は雨に濡れたままですか」
「そうですね、もう少しデーターが集まれば、病院なり、研究所に運ぶことも可能だと思います」
彼の身体からでた緑色の茸が傘を開いた。胞子がただよいでた。胞子は林の中を静かに風に流され、奥へとはいっていった。
その瞬間、彼はぶるっとからだを震わせ、近くに人がいるのも忘れて、
「あっつ、ああーー」と声を上げた。
警察官と上司は驚いて彼を見た。
「苦しいのでしょうか」
上司が刑事に言っている。
「いや、顔は苦しそうじゃないな」
彼は何もかも忘れて、ズボンの中に射精をしていた。胞子の放出は股間に繋がった。
「医者は大丈夫と言っていることだし、あとはまかせましょう、我々はもどりましょう、雄蛇ヶ池の周りには毒蛇もいるかもしれませんしね」
刑事と社長はパトカーに乗り込んだ。
彼は人間が離れると晴れやかな気持ちになり、また緑の茸が生えるのを楽しみに、林の中の出来事を肌で感じていたのである。
茸の子


