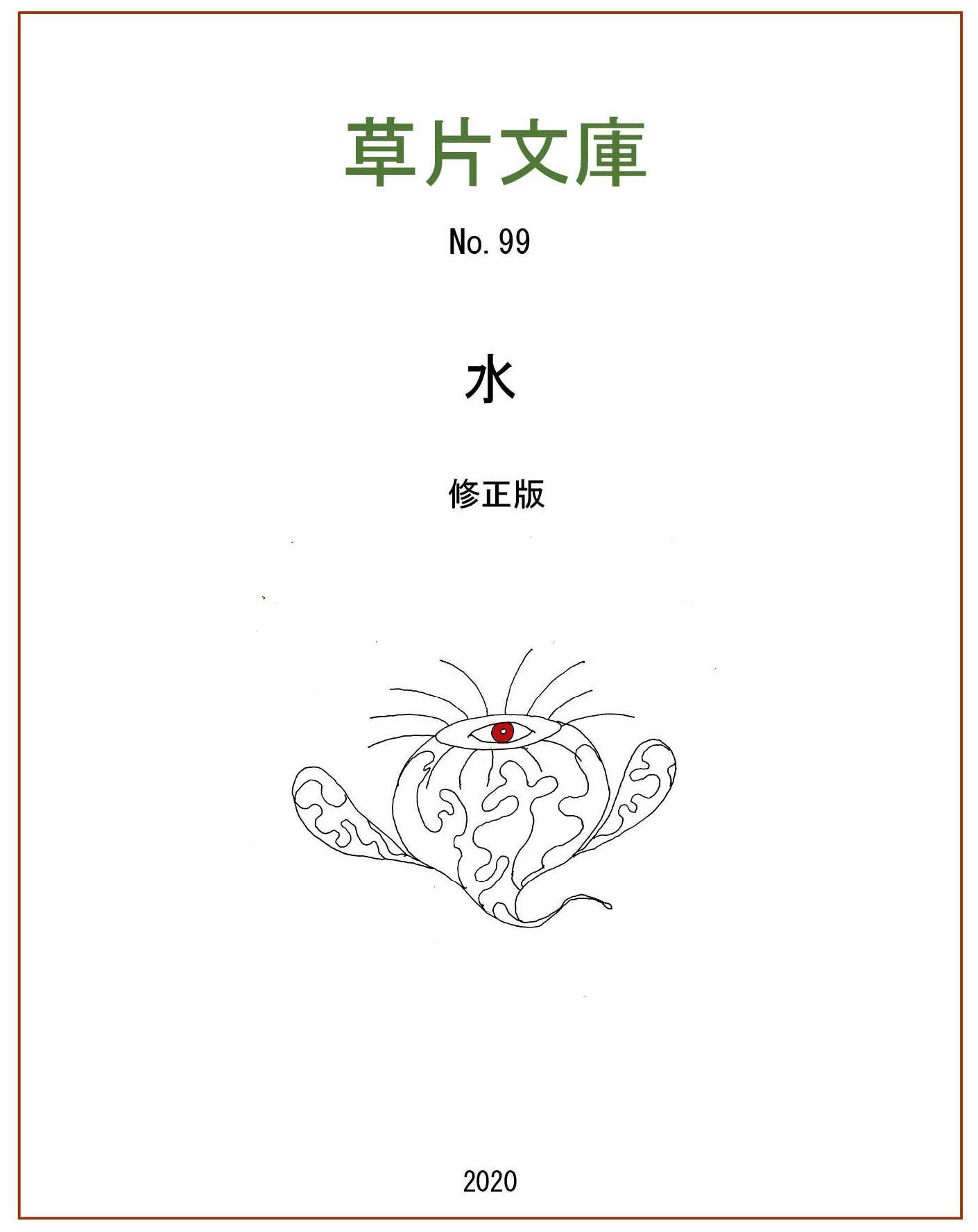
水
SFです。
八月の終わり、全世界に衝撃が走った。月の周りを得体の知れない物が回っている。
最初にそれを発見したのは、軍でも科学者でもなかった。信州で暮らしている宇宙が好きな一人の男である。二十三歳になって、ぜひ彗星の一つも見つけたいと、仕事が終わると一晩中天体望遠鏡をのぞいている。彼は町を通る国道わきの唯一のガソリンスタンドに勤めている。
明日新月という日だった。彼が自分のアパートの窓から夜空を眺めていると、薄い刃のような三日月の暗い部分で小さな点がぴかっと光ったのである。ふつうの光ではない、といって隕石の光ではない。彼はあわてて望遠鏡を担いで、山の上の公園にむかった。彼のアパートは山の中腹にあり、近くに一軒の農家があるだけで夜は明かりが乏しく、窓からでも夜空の星を見ることができる。だが、山の上まで登れば、別世界が開ける。丘に毛がはえた程度の山で、彼は自分の庭のようにらくらくと階段を登っていく。
山の上で望遠鏡を構えると月にレンズを向けた。月の暗い部分になにか物体があるようだ。それがたまにぴかっと光る。望遠鏡の焦点を合わすと黒っぽいものが現れてぴかっと光るとすぐ消え、また光る。それを1秒ごとにくり返す。見ていた限りでは自分で光を出しているようだ。そいつはそこにいるのではなく、いったんいなくなり、また現れるを繰り返しているようだ。一分ほど現れないときがあった。光が現れたとき、位置が少しずれていた。ふたたび一秒に一度ほど光った。しばらくすると、また一分ほど消えたままで、ずれたところに光があらわれる。
光りながら月の周りを回っているものがあると考えるのが順当のようだ。なんだろう。どこかの国が月の人工衛星を打ち上げたとは最近聞かない。月の周りに宇宙ステーションを組み立て、火星へ行くベースを作るという話は聞いたことがあるが、まだまだ遠い先の話しだと思っている。
もし月の人工衛星であるならば、月の円周は約1100キロ、だから、時速306万キロになる。人工衛星は一箇所にとどめておいて、観察を続けるのが普通だろう。それとも、自在に操れる人工衛星をどこかの国が作ったのだろうか。それにしても早すぎる。彼はこのくらいの計算は頭の中ですぐできた。
しばらく眺めていたが、同じ繰り返しなので、家に帰ることにした。
明くる朝、仕事にでて、給油の車がいないときに国立天文台に電話をかけた。
小淵沢から小海線にのり、野辺山でおりて40分ほど歩くと国立天文台がある。子供の頃は山梨市にすんでいたので、親につれられて遊びに行き、中学生、高校生の頃は一人で、観察会や展示会に参加したものである。中高と天文部一筋で、星を毎日見ていた。そういうこともあって、天文台には何人か知っている研究者がいる。その一人に電話をしたのだ。安宅昇主任研究員である。専門は宇宙の起源だ。ブラックホールだとか超新星が専門である。
「昨夜、不思議な光を月の上に見つけたんです」
「え、そのような報告はないけど、なんだろう、宇宙のちりじゃないのかな」
そこで、彼は見た通りのことを話した。
「そりゃあ確かに宇宙の塵じゃないね、規則正しく動いているものだね、どこかの国で月になにか黙って打ち上げたのかね、最近月をねらう国が多くなってるからね」
インドも月の反対側に着陸させようとして成功させている。
「ちょっと調べてみるよ、なにかわかったら電話するよ」
安宅主任は約束を守る人である。彼は期待して電話を切った。
その日のうちに、彼からショートメールがはいった。
「忙しくなった、とりあえず、連絡しとく。どの国のものかわからない宇宙船が月を回っている、地球外かもしれない」
こりゃ大変だ。今まで生きていて最も衝撃的なできごとだ、彼は仕事が終わるのが待ち遠しく、そわそわと落ち着かなくなってしまった。
仕事の時間がやっと終わった。挨拶もそこそこに、アパートに戻り、望遠鏡を持ち出して、山の上に行った。幸い明日は木曜日で、自分の休みの日である。
周りはまだ明るいが焦点を薄く空に浮かんでいる月に合わせると、光る物体は確認できた。
そのとき携帯がなった。
「やー、大変なことになった、世界中の天文台が騒いでいる。もちろん政府も知っている」
「やっぱり宇宙船ですか」
「そうだ、大きさはジャンボジェットほどであまり大きくはない、形は要するに球型だ、自分で光っているので、相当強い光を出している」
「なぜでしょう」
「きっと、船内のエネルギーを光にかえて外に出している」
「ということは船内にいる宇宙人は冷たいところじゃないと住めないわけですか」
「その通りだね、その可能性もあるが、防衛のためかもしれない、防衛のバリヤーとして光を出している。あの光の強さは尋常ではない、もし地球に来たら、皆目を開けていられないだろう」
「地球に来るのでしょうか」
「そうだと思う、世界の天文台で意見が一致しているのは、月の周りを回りながら、地球の方を観察しているということだ。地球の様子を逐一見ている」
「でも、それなら、一点に止まって地球を見た方がいいのではないですか」
「月も一緒に探っているのだと思うよ、ともかく日本では君が第一発見者のようだ、また連絡するよ」
彼はまた月を観察した。すると、一瞬だが、月がまん丸の黒い玉になり、太陽のコロナのような光の放散が黒い月の周りから起こった。
なにが起きたのだろう。
また電話がなった。
「どうも月の裏側に宇宙船の大集団が現れて、おそらく着陸したらしい。太陽の当たっている方だから、宇宙人は太陽の光が必要のようだ」
「どこから現れたとか、そういうことはわかっているのですか」
「いや、全くわからない、アメリカも、ロシアも中国も宇宙軍が動き出しているが、国連からくれぐれ動きに注意するように言われているようだ。なにせ、地球の科学で太刀打ちできるわけはない、怒らせたら地球人などあっという間に抹殺される可能性がある」
「日本はなにをしているのです」
「日本はデーターを解析しているところで、おそらく地球人の動きの重要な判断材料になると思う、最初君が発見した一つの宇宙船が偵察船でそれが今は地球側にはいない。それが出てくるのをまっている」
彼は望遠鏡をのぞいて確認した。
「もう月の周りの光は消えましたね」
「ああ、宇宙船団が着陸したのだろう」
彼は月の暗い部分に光が現れたのを見た。天文台の安宅が「でた、切るよ」
と電話を切った。
それから、電話はこなかった。なにが起きているのだろう。だいぶ目がつかれてきた。もう夜中の1時である。夕食もとらずに空を見ていたわけである。
アパートに戻った。カーテンをあけたまま月を見ながらカップ麺をすすった。テレビでは何も言っていなかった。管制がしかれているのだろう。
明日の新聞には記事がでるのだろうか。彼は床に入った。
朝、アパート入口の郵便受けに新聞を取りに行った。広げながら階段を上ったが、一行も宇宙船のことはのっていなかった。
安宅が言っていたように、地球外のものだったら、大変なことである。HGウエルズの宇宙戦争のような事態にはならないまでも、もしそんな宇宙船団が地球にあらわれたら、地球ではどのようなことが行われるのだろう。映画未知との遭遇のように、冷静に出迎えができるのだろうか。
昨夜月の周りがコロナのように一瞬輝いていていた。なにかが起こっていることは確かである。新聞社の科学記者が見ていないということはないだろう。きっと宇宙機構はてんやわんやの大騒ぎに違いない。
今日仕事は休みである。天文台に直接行ってみよう。久しくたずねていない。彼は給料のすべてを天体観測に使っていて、車を持っていない。通勤に使っているバイクでいくのだが、自宅から一時間ほどかかる。いつも持ち歩く小型の宇宙望遠鏡をザックに入れて出かけた。
天文台に着くと、安宅に電話をかけた。
「あ、連絡をしようと思っていたんだ、あの件はまだ公表してはいけないということで、できなかったんだ。もうすぐ新聞に載ると思う、全世界同時だよ、こんなことは今までになかったことだ、共産圏の国もまだ国民に通知していない。知っているのは宇宙に関わる人だけだよ、それに政府だね」
「実は今天文台の入り口に来ているんです」
「そう、日本での第一発見者だといって、所長に許可をもらうから守衛室の前でちょっとまってて」
すぐに、守衛さんから声がかかった。研究室にいってほしいということだった。
安宅研究主任の研究室には何度か行ったことがある。
研究室にはいると、安宅さんを囲んでいた学生が一斉に彼を見た。以前からいろいろな大学の宇宙物理学科の大学院生や学生が研究に来ている。
彼は物理が得意ではなかったので文学部で美学を学んだのだが、大学では星をみる会に入っていた。大学生のときにも、アマチュアの一人として、天文台にはよく来ていて、安宅主任研究員とも付き合いが長い。卒業してから星を見るために条件のいい場所として今の住むところを選び、その後、就職口を探して、ガソリンスタンドに勤めたのである。
「安宅先生、お久しぶりです」
「あ、いらっしゃい、みなに紹介しておこう、胆沢さんだ、星の好きな方で、君たちより何百倍も星を見ていて、とても詳しい人だ、今回出来事は、彼が最初に見つけて、僕に連絡してきたんだよ」
彼を周りの学生に紹介した。
「今の学生は星を見ないで、数字ばかりだから、星の発見の楽しみをしらなくてね、それはともかく、今度のことは、本当に大変なことでね、明らかに地球外生命の乗り物が月に来ている、日本では胆沢さんが最初にみつけたけど、同じ頃、宇宙ステーションでも大騒ぎしていたらしい、あの物体は光をだしているが、電波望遠鏡などではとらえることができないんだ、電波が素通りしているようだ、だから宇宙ステーションでも窓から外を見ていた飛行士がおかしいものがあると気が着いたようだ、今は大きな光学望遠鏡で観察が行われているらしい」
安宅の研究室の壁に掛かっている8Kモニターに、専門家に送られてくるデーターや画像が映し出されている。
胆沢は学生の後ろの椅子に腰掛けて画面を見た。
「地球を観察しているのではないかと、安宅さんが言ってましたけど、やはりそうなのですか」
「うん、おそらく宇宙船の大集団が月の裏に着陸していて、偵察船が月の周りを回りながら、こちらを観察しているのだと、NASA、世界の宇宙開発の関係機関すべてが考えていることだよ」
「どこから来たとか、そう言うことはわかっていないのでしょうね」
「全くわかっていない。ただ、想像できるのは、いきなりやってこないのは、地球の環境を気にしているのかもしれないからなんだ」
「どういうところでも、宇宙服があれば大丈夫なのではないでしょうか」
「そこなんだ、住むところを探しているのではないかと上は考えている。そのための詳しい観察をしているのではないかという想像なんだ、とすると、条件があえば地球に住むためになにをするのかわからない。地球の生命にとって一番怖いことだよ、たとえ穏和な宇宙人でも、一緒に住むとなるとそう簡単なことではないからな」
「そこまで考えているのですか」
そのとき、画面に「緊急集合」の文字が現れた。
「胆沢さん、君はここで待っててください、大会議室にいかなければならない、学生諸君は、データー収集室に行っててくれないか、なにか指図があるかもしれない」
そう言って、彼らは安宅の研究室を出ていった。
画面が月に変わった。大きく映し出されている。
胆沢は画面を食い入るように見た。なにも変わったところはなかった。
すると、突然、画面に光が現れた。胆沢が最初に見たものである。月の画面の下に「緊急事態」の文字がながれた。すると安宅たちが研究室に戻ってきた。
「所長の説明があって、政府はテレビニュースにこのことをながした。もう我々の手ではなく、防衛庁の所管の事柄になった。画面を見ているほかはないな、手伝いの要求がきたらいくだけだよ」
「なにが起きたのですか」
「宇宙船の一つが地球に向かっている」
「え、それは大変だ、すぐにきてしまう」
「そう、胆沢さんのいうとおり、月の周りを時速300万キロほどで回っていたから、そのままのスピードで地球に来るとすると、月まで38万キロだから10分で来ることになる」
「このモニターには、宇宙船を追っている映像が集められ、必要なものが映し出される、天文台や研究機関、それに大学などにもデーターや映像がながれているはずだ。テレビ局にも流していると思う、一般の人にもテレビ局が選んだ映像が映し出されることになるだろうね、しばらく見ているしかない」
地球に向かう宇宙船に焦点が当てられ拡大されているが光しか見えない。おそらく強い光で船を守っているのだろう。画面の下にカウントダウンがはじまった。あと3分で地球に来るようだ。
「あの光が直接地上にあたったら、どうなるのか心配だな」
安宅がつぶやいた。
「熱を出しているのでしょうか」
「わからない、あの熱じゃ地上がどうなるか」
そんな心配をよそに、2分にせまった。
画面から光が消えたと思ったら、丸い黒い玉が向かってくる。
「光を消した、地球をだめにしたくないからだ、あの熱だと地球の土は溶ける」
安宅が言った。
画面が変わった。日本のどこかの海岸が写った。空には黒い球体がせまっている。
球体の大きさが表示された。直径十メートル。
ジャンボジェットの全長は二十メーターだから、半分の大きさしかない。人間だったら数人しか乗れないだろう。それでいてあれだけの光を出していたとは恐ろしい技術をもっている。
場所は鳥取砂丘とでた。大気に変化はないとでている。放射能などの心配もないようだ。
空にヘリコプターが飛んでいる。
真っ黒な宇宙船は球形をしていることしかわからない。
1分、カウントダウンがはじまった。
すると、いきなり黒い球体の宇宙船は動きをとめて、空中をゆっくりとまるで落下傘を着けているように静かに着地しようとしている。
テロップに、国連の人たちが日本に向かっているとでた。他の国の人たちはきていないのだろうか。アメリカやロシア、中国は何もいわないのだろうか。
テロップに、国連が日本にたいし、国連以外の人を入れないように要請したとでた。
安宅が言った。
「日本に任したような形だが、日本に犠牲になってもらおうという気があるんだろう、もし侵略なら日本がやられるわけだ。きっとアメリカなどは軍隊派遣の準備をしている」
胆沢にはそう言う発想がなかったので、なるほどと安宅の言うことを真にうけた。
「だけど、アメリカの軍隊をもっても、かなわないのではないでしょうか」
学生の一人が安宅に言った。
「その通りだよ、いずれにせよ、なにが起きるか全く予測が立たないわけだ」
そう言っている間に、スクリーンには砂埃一つたてないで砂丘の上に黒い球体がおりたった。
この映像はどこから撮っているのであろう。
黒い宇宙船がおちついたところで、画像が周りを映し出した。砂丘の周りに報道車や警察の車、自衛隊の車が集まっている。まるで昔のSF映画だ。胆沢は小さいときにみたゴジラやモスラを思い出した。
「宇宙船は入口も窓も見えませんね、それに見てください、砂の上の宙に浮いている」
彼はなにが出てくるのかよりも、宇宙船の構造が不思議でならなかった。よく見ると、球の宇宙船は着陸していない。砂丘砂の中にめり込んでおらず、むしろ浮いている。
「着陸していないね」
安宅も気がついている。
「まだ、地球を信用していない。だから本当の形を現していない、光を吸収しているから宇宙船の外壁がみえない」
10分ほど同じ状態だった。日本の出迎えている連中も動いていない。
すると、黒かった球がだんだんと姿をあらわしてきた。円い窓が連なっている。大きな丸い窓がハッチのようだ。
宇宙船が砂の中にめり込むように入っていく。
円い窓のところまで埋まると、窓が上にあがった。
映画未知との遭遇では音で歓迎を表現していたが、ここではなにもしていない。
それなのに、相手は安全だと判断したのだろうか。
世界の人々がテレビを見ていることだろう。
出口が大写しになった。
砂の上に直接出てきたのは、二本足の二本手のある、頭と胴をもった生き物だった。一人だけである。歩いている。ただ、感覚器がない。目も耳も鼻も、それに口もない。のっぺらぼーだ。我々と同じような洋服を着ている。
宇宙人が大写しになった。手を見ると片手に八本の指がある。
カメラが少し引いた。
だが、歩いて車の集まっている方に、たんたんとやってくる。つるんとした顔だけでは表情が読めない。
自衛隊の連中が拳銃を片手に宇宙人の方にかけよっていく。それを見た宇宙人は驚いたように、逃げ始めた。身を翻してかけて宇宙船に戻るかと思ったら、宇宙船を通り越し、砂丘を駆け下りていく。報道陣も追いかけていく。
カメラマンが、宇宙人が砂丘の先の海の中に身を投げる様子をとらえた。
画面がかわった。宇宙人が海の中に飲み込まれていく。
「なにやってるんだ」
安宅が叫んだ。胆沢をはじめ、学生たちも、まるで映画の撮影を見ているような錯覚に陥った。
なんなんだ。テレビ局の虚像じゃないのか。
胆沢は疑った。
自衛隊や警察、それに報道、そんな人たちが砂丘をかけていく映像が映った。
カメラマンのハンドカメラに映像が変わった。
海の中が写っている。岩にぶつかる波が白いしぶきをあげているだけである。
また映像が変わった。
自衛隊が宇宙船の周りにバリケードを作っている。報道関係者も入れないようである。あれから宇宙人は降りてこない。こんな大きな船にたった一人しか乗っていなかったのだろうか。とすると、この球体の中は、色々な計器が詰まっているに違いない。それにしてもなぜ宇宙人は探査船に戻らずに、海に飛び込んだのだろうか。たくさんの疑問が胆沢の頭をめぐった。
胆沢は立ち上がった。
「安宅さん忙しいところおじゃましてすみません、僕は家に帰ります」
「その方がいいでしょう、テレビで見ているのとかわりがありません、これからおそらく月の裏にいる仲間がやってくるでしょう、地球がどうなるか、食料なども確保しておいた方がいいですよ」
「はい、僕もそう思いました、また連絡させてください、望遠鏡で月を見ていたいと思います」
彼はそう言って安宅の研究室からでた。
バイクでアパートに戻り、すぐさまテレビをつけた。宇宙船の内部をやっているかと思ったら、解説者がハッチは開いているのだが中に入ろうとすると押し返されてしまうと言っていた。
しばらくテレビを見ていたのだが、進展もないままだし、海に入った宇宙人のこともまったくわからないらしいので、望遠鏡を担いで山の上の公園に登った。まだ明るいが、月がうすいウエハースのように見えている。
陽が落ちるまで時間は大分ある。
月に望遠鏡をあわせた。
スマホでテレビを見た。鳥取砂丘の海でたくさんの船が海中に入った宇宙人の捜索を行っている。ダイバーが潜っている様子が映し出された。宇宙船はまだ中に入れないようだ。何人かの捜査員が円い窓から覗こうとしている。手持ちのカメラがそれを映し出しているが、真っ暗というより、真っ黒でなにも見えない。
ニュースの時間になった。
アナウンサーが、鳥取砂丘に着陸した宇宙船は、地球のものではないことは明らかだが、どこから来たか、目的はなにか、なにもわからないといっている。海に入った宇宙人はどこにいったのでしょうと、アナウンサーが叫んでいる。
宇宙人の顔写真が引き伸ばされて画面にでた。のっぺらぼうで毛は金髪、手は八本の指があり、指に爪がない。着ていた服は、上が白い長袖のTシャツ、ズボンは日本の左官屋さんがはくニッカボッカのようなもの、靴は履いておらず、どうも地下足袋のようであった。ちょっと古い日本人のような格好だ。
スマホのテレビをのぞいていた彼ははっとして空を見上げた。空が急に明るくなったからだ。薄い雲がたなびいている空に、大きく輝くものが現れて近づいてくる。少しまぶしいくらいだ。
あの月の裏側にいた船団が地球めがけておそってくるのではないだろうか。
胆沢は安宅に電話をかけた。
「あ、連絡しようと思ったところなんだ、宇宙船団がくる、どうなるのか、手の施しようがないな、政府はどうしようというのか聞こえてこない」
安宅も情報がなく、心配しているようだ。
「いま、丘の上で、肉眼で見ています。花火どころじゃない、あのまま地球に来たら、皆目がつぶれてしまいそうです、どんどん近づいてます」
「目をやられないようにね、ぼくたちもそとにでてみるよ」
「はい、サングラスをかけていますが、それでもまぶしい」
「地球がどうなるか、身の回りを整理しておいたほうがいい、僕たちは政府からの要請があればいつでも手伝えるようにしているんだけどね、十分以内には地球に到達するよ」
「ずいぶん光が強くなっています、僕はここでしばらく見ているつもりです」
「気をつけてくれたまえ」
そこで電話を切った。
あと7ー8分もすると地球に来る。望遠鏡などは役に立たない。
あと、5分と言うときである。いきなり光が消えた。
空をみていると、黒い点が無数に浮かんで空一杯に広がっている。船団だ。
浮遊しているようだ。それがいきなり散らばると、地上に向かって、落下してくる。いや降りてくる。光っていないところを見ると、ゆっくりと降りているようだ。
やがて、いろいろな方向に降りて消えていった。一つ目に見えるほど近いところに降りてきて消えたが、どのあたりだろう。諏訪湖あたりのようだ。
スマホのテレビを見ていると、江ノ島がうつった。そのあたりにも降りたようだ。
ニュースが流れた。すべての宇宙船は世界の海に降りていったと言っている。江ノ島のカメラが海の上に浮いている宇宙船をとらえた。
これからどうなるのだろう。
彼は家に戻ることにした。
アパートでテレビをつけた。アナウンサーはこんなことを言っている。
世界中の海に黒い球体の宇宙船がおりて浮いている。
集団で来た宇宙船は全て同じ大きさであった。降りた宇宙船の数は正式には発表されていないが、およそ百万にもなるだろうということだ。日本に最初に降りたものから、一人の異星人がでてきた。とすると、百万人の異星人が地球に降りてきたことになる。彼らが宇宙艇から外に出たところを見たものはいない。まだ宇宙艇のなかにいるのかどうかもわかっていない。
鳥取に下りた宇宙船からでてきた宇宙人が海の中に飛び込んでしまったのはどういうことなのか。どの国でも海の中の捜索に当たっているようだが、何もわかっていないようだ。ただ、どこの国の科学者も、宇宙人は海が目的だったと話していた。
アメリカ、ソビエト、EU、中国、日本も何一つ明らかにできないでいる。
テレビニュースではいつものように科学者が呼ばれ、なにか言っているが、ただの憶測だけである。地球の科学の小さなことが露呈した形だ。
彼はテレビを切って、夕刊をとりに行った。いつもとちがって夕刊が厚い。
開くと、一面に宇宙船が海の上に浮かんでいる写真である。日本の近くに降りたものの場所が一覧になっている。千いくつもあるという。テレビよりは詳しく宇宙船について解説してあったが、結局何もわかっていない。海に浮かんだままの宇宙船に近寄れても触ることは全くできないという。鳥取砂丘の宇宙船と同じ状態だ。
テレビでも新聞でも、今後何が起こるかわからない、備えを十分にして家から出ないほうがいいといっていた。都会ではパニックになることを恐れている。食料はいずれ配給制になることが説明されていた。これに乗じた犯罪を警察は恐れ、街中のパトロールを強化していた。政府は人々への沈静を訴えていた。
これからさらにたくさんの宇宙船が来るかもしれない。そう思いながら、彼は部屋の窓から外を見た。映画みたいだ彼はまたそう思った。望遠鏡はいらない。目で見ているだけでいい。ベッドの上に転がっても窓の外が見える。
夜の十時頃だっただろう。窓の外を見て「あ」と声を出してしまった。
月が二つだ。
月の大きさのものが月の隣にいきなり現れた。どんどん大きくなっていく。
彼は外に出た。テレビでもやっていたのだろう。外に出て空を見上げる人たちがたくさんいる。
大きな玉の光で、周りが照らし出されて、昼間のようだ。
公園の山に登り始めたがやめた。もしあれが宇宙船の本当の母船であったなら、あっという間に地球の真上に来るだろう。
思ったとおりだった。まぶしいくらいに輝いている光がとまった。
月夜の空に、大きな真っ黒な玉が陰のように空に浮かんでいる。
地球の未来はないと誰しも思ったことだろう。
大きな玉がはじけた。中からくずれるように小さな玉が放り出された。すでに降りてきた宇宙船である。再び大集団がやってきた。
再び階段を登りながら、スマホのテレビをみていると、それは全世界の海に降りて、前と同様の状態になった。やはり百万を越す数の宇宙船が下りたようだ。
丘の上には何人かの人がすでに空を見ていた。またこないかと心配している。
ここでも昔読んだSFを思い出した。急に現れたのは時空を越えてやってきたのか。超光速にしてもあんなに急に現れることはできない。
部屋に戻った。百万もの小さな宇宙船で旅行すると葉どういうことなのかというkとを、テレビの中で科学者が疑問を呈していた。大きな母船がくるのならわかるが、母船だと思っていたものが、ばらばらになり、小さな宇宙艇になった。少人数で旅行するなど無駄が多すぎるだろう。空になったのかどうかわからないが、小型の宇宙船は海の上に浮かんでいる。そういえば、波が当たってもゆれていないのはどうしてだろう。北海道の荒海の上の宇宙船の映像が映し出されている。
その宇宙船からは数え切れない宇宙人が海の中におちていったという、目撃情報が寄せられていたが、眉唾のようだ。それにもかかわらず、集団自殺ではないかと説明している生物学者がいる。彼はバカな学者だと思って聞いていた。学者の発想は今まで見たものからしか作られない貧弱なものだ。
宇宙人が魚と同じなら、いきるために飛び込んだことになる。空気中では生きていれない。もしそうなら、宇宙人は海や湖の底で喜んで歩いているかもしれない。
海の捜索はまだはじまったばかりだ。海の上では、いつもアメリカや中国、色々な国の艦隊がうようよしている。ところが船のそばには落ちてこなかったと言っている。日本でも同じで、船のいるところには落ちていない。意識的に避けている。
一番最初の超小型の偵察船だけが日本の砂丘に降りた。彼らにとって、失敗だったのではないだろうか。日本人の対応にも問題があったのかもしれない。あの時点で、宇宙人とコミュニケーションを取れていたら、もっと情報も多いし、彼らの目的も分かったはずだ。
次の時間のニュースではアメリカや中国、ロシアでの海中の探索結果が話されていた。海中には宇宙人は全く見つからないということである。日本においても同様のようだ。
浮いている黒い宇宙船もおかしい。巡視艇などが近づくと逃げていって、また元のところに戻る。決して捕まらないということである。乱暴なアメリカの海軍が銃を撃ったり、小型のロケット弾まで打ち込んだりしたようだ。すると、すべて跳ね返って、自分の方に打った玉やロケット弾が戻ってきて、自分の船が傷ついたということである。地球は非力だ。
大騒ぎは一月続いた。現実に宇宙船が海に浮いていても、全く手がかりがつかめず。一般人の心配も少し薄れてきた。政府は気を緩めないように訴えてはいるが、人間はストレス状態に長くいることができない。とりあえず何もしてこない宇宙からの来訪者のことは頭の隅に追いやられ始めていた。慣れてきたということである。少しばかり、前の生活に戻っている。
「安宅さん、宇宙人はどうなっているんでしょうね」
彼はふたたび、天文台を訪ねた。
「海の中で何をしているのだろうね。深海艇で捜索しているようだが、なにもつかめていない」
「地球人はどうしたらいいんですか」
「いつもの暮らしをするしかないね」
胆沢は安宅と話をするとなんとなくおちつく。彼は冷静に物事を見ている。
安宅が言ったとおり、科学者は半ば解析をあきら、心配していた海の中もなにも起こらないことから、漁業関係者もいつものような漁をおこなうようになった。海の水の検査では、水質や温度など何も変化していなかった。
ちょっと変わったことは、大国の軍事が宇宙に向けられ、国々の間のいがみ合い、競争が下火になったのである。いいことである。宇宙に我々の知らない世界の生き物がいる。実際に地球に来た。それは、科学のうぬぼれをなくし、ともに黒い球体宇宙艇の解析に力をそそいでいた。
国際宇宙人研究所が立ち上げられ、日本支部が重要な役割を担うことになった。最初の宇宙探査艇が地上に着陸していて、調査がしやすいということからだろう。
時は黙っていても過ぎていく。それから二十年の歳月が流れてしまった。
胆沢はとうの昔にガソリンスタンドをやめ、天文台の資料室に勤めるようになって十年以上になる。安宅が副所長になっている。文学部を卒業し、図書の司書の資格も持っている胆沢に中途採用の枠に応募するように勧めてくれたのだ。日本で最初に宇宙船に気がついた人間だからでもあったが、胆沢は天体観測も開始していて、念願かなって新しい彗星を見つけた。そういったこともあって、天文台に向かいいれてもらえたのである。しかも、星の研究者の卵と結婚をした。大学院をでた彼女は天文台で博士後期研究員として働いていた。
ちょうど宇宙船がきて二十年目の日、8月の30日のことである。テレビニュースで、漁業者がおかしなことを言っていた。深い海の魚が全くとれなくなったということである。深海魚がいないという。深海を探る研究者も、その日に研究のために潜らした深海挺のカメラになにも映らないといって、なにか異常が起きていることを示唆した。深海とは海面から200メートル以上深いところを言う。我々が好んで食べる魚がたくさん棲んでいる。キンメダイなどはその代表だ。
魚だけではなく、クラゲも蟹もなにもいない。海底火山は今でも熱湯を吹きだしていて、以前ユノハナガニが群れていたのに、その蟹もいなくなった。だが深海の水質検査では全く異常はないことが報告された。
それは深海だけの話で、その上で生活をしている海の生き物たちはいつものように、平和に暮らしており、漁民たちも働いてそいつらを捕まえて生きている。むしろ海の魚たちや生き物は増えているようだった。
天文学者たちは頭の上の宇宙のはてに思いをはせていたのだが、海に消えた異星人たちのことを気にしない人たちは誰一人としていない。宇宙の果てのことを、海に消えた異星人たちに聞きたくて仕方がない。胆沢も天体望遠鏡で、宇宙を見ながらいつもそう考えていた。異星人の調査に当たっているのは、海のことをよく知っている海洋学者たちだが、いざというときにそなえて、一部の天文学者、安宅もその一人だが、調査に加わっていた。
どの国の軍人たちは、深海に宇宙人の国が作られているのではないかと心配していた。深海探査挺や調査方法が急激に進化し、新たな機械が開発されていた。そういった物を使って国際的な調査が展開されていた。しかし、海に消えた異星人たちをみつけることすらできなかった。
宇宙人は海に身を投げるために地球を選んだんだ。などという、小説も流行った。ともかく宇宙人は姿を現さなかった。
宇宙人が海に身を投げてから35年がたった。
一人の水質学者が海の中の宇宙人が放射能を使っていると気がついた。
海の水に放射能が全く含まれていない。宇宙から放射線もとんでくる。原子力発電所からもわずかながらも放射能を含む水がすてられている。ところが、どこを調べても、海の水には放射能が含まれていない。
水質学者の発表に、原子力発電を行っている電力会社は少しばかり管理がずさんになった。流す水の処理の工程を減らし、今までより高い放射能レベルの水がうみにながれた。それでも海の水の放射能は消えていた。そんなことがあり、一時、原発を廃炉にするという取り決めは反故にされ、新たな原発が作られ始めた。クリーンエネルギーとして登場してきた風力発電や、地熱発電、太陽光発電の新たな開発が中断された。
少数の研究者は海水中のなにが放射能を消滅させるのか調べてはいたが、深海の宇宙人の仕業だとしても、やらせておいたほうがいいと、政府は考えていたのだろう。
明らかに原発が出す放射能水が増加するようになって、恐ろしいことが起きた。
深海だけではなく、海や湖の魚や生き物がすべて消えてしまった。鯨もアザラシなど水性哺乳類も、海草も、ともかく海や湖に生き物がいなくなったのである。釣りができなくなったなどという嘆きにとどまらない重大事件だ。
海の幸という言葉が使えなくい。寿司の国日本は大打撃であった。魚を食べることができなくなったのである。かろうじて養殖の海の魚を食べることができた。
宇宙人が何かやっている。
一般の人もそう思うようになった。だが、どこにいるのか、なにを考えているのか何も分からない。どの国でも政府の怠慢が槍玉に上がった。
科学者はしりをたたかれ、人工食料の開発はそれなりにすすみ、陸のものから、すなわち家畜や植物から、魚の味のある、魚と同じ栄養価のある食物をつくりだした。
一つの例として、蟹そっくりの蒲鉾を日本が発明していたが、魚のすりみが作れなくなったことから、人工の魚の肉が大豆などの穀物と少々の動物の肉から作られるようになったのである。
胆沢にも中学生の子供がいた。食べ盛りの子供に魚が食べさせられなくなったのは人の体にどのような影響を与えるのか。子供が大きくならないとわからないことでもあった。人間や動物の生活は海抜きのものになった。海は船の通り道、泳ぐところ、遊ぶところになった。魚類学者が川の魚を海に住めるように改良して、海に放したが、すぐに消滅した。
国際的な機関は、海に浮かぶ地球外生命体の宇宙船がなにかしているのではないかと、宇宙船の周りに測定機器を積んだ船を待機させ、観測を続けたが、その真っ黒な球体物質は、なにもおしえてくれなかった。そのころになっても海や湖に浮かぶ宇宙船の中に入ることができなかったのである。
一番解析しやすいのは、最初に地球に着陸した、小型の探査挺である。日本の鳥取の砂丘にいまでもあった。球体の宇宙船に乗っていたのは一人である。機械が一杯に詰まっているのではないだろう。とすると中にまだ誰かがいるのではないかという疑念は解消されていなかった。海に浮かんでいる宇宙船が地球の生き物をとらえ、どこかに運ぶ準備をしているのではないだろうかと宗教家は考えた。ノアの箱舟思想である。
風雨にさらされても探査艇は何ら変化を見せず、調査隊が触ろうとすると、手が押し返され、触ることもできなかった。乱暴な自衛隊が火炎放射器でバリアーを破ろうとした。ただ炎が押し返され、自分たちの服が燃えただけだった。
探査艇の周りの空気や砂に全く変化はない。風雨に曝されても動かない。
中学の理科先生の提案で探査艇の下の砂を掘って、探査艇の底を調べた。砂をどけても探査艇はそのまま浮いていた。ということは、そこに固定されていて、時だけは地球の生き物と同じに過ぎているということになる。降りたところから動こうとしないわけである。
それに気がついた学者が、海に浮かぶ大型の宇宙艇について調べた結果、宇宙艇は海に少し沈んでいた。しかし、諏訪湖などにおりた宇宙艇は変らない。温暖化によって海の水が増えたことから、宇宙艇の位置はかわらないが、海の中に深く入ったように見えたわけである。
真っ黒の球体宇宙艇は地球の科学では解明できない錨を空間におろしているのである。その錨はどこに固定されているのか。地球の物理では解明できない次元のものであろう。
もし、この宇宙人が人類に敵対したら、とてもかなう相手ではない。海底のどこかにいるのだとしたら、共存の道を探らなければ人間は生きていけない。
彼らはなぜ海の中の生命をみな消滅させたのだろうか。
そう言ったことを討論する番組がテレビで流された。
一人の学者は海や湖が乗っ取られた、取り返すのにはどうしたらいいかと発言した。別の学者は海や湖を明け渡して我々は彼らから役に立つ知識をもらって陸を守った方がいいと言った。ほかの学者から、地球人が早く月に住めるようにしたほうがいい意見を言った。その意見に、取り返せと言った学者が、地球を明け渡して逃げるのかと怒った。
人間は全く変わっていない。進歩していない。
胆沢は異星人との共生の道を探るべきだと思った。それには、異星人がどこにいるのか、コミュニケーションはとれるのか考えなければいけないのではないかと思った。
水の中の異星人は人間の動きをすべて見ているのではないか。人間が馬鹿な結論を出すと滅ぼされる。
胆沢は天文台所長になった安宅にそのような思いを話した。
「たしかにな、全くコミュニケーションがとれないのはどうしてなのかな」
「あれだけの科学の発達した異星人なら、コミュニケーションをとるくらい簡単なのではないでしょうか。彼らは黙って、我々人間の性格を見極めようとしているのではないでしょうか」
「胆沢さんそうだよね、誰かそう言わないといけないね」
「安宅さんは、そう言う場にでる機会があるのではないですか、ぜひお願いします」
「そうだね、言わせてもらう、文を書くときには一緒にだそう」
この考えは、天文台の出している会報にまず載せた。安宅所長は宇宙人に関わる会議に出たときにはそう言ったことを発言し続けた。新聞にも賛同する趣旨の社説などがのったりしたが、日本人、地球人はあまり深刻にはとらえていないようだった。生活は変わらない。
もし、宇宙人がいて、共同生活をするとなると、お互い困ることはしないのが大原則である。地球人は黒い宇宙船に乗ってきた宇宙人が海にいることを忘れていた、と言うか、もういないと思っていた。
「安宅先生、海だけではなく水がどうなっているのでしょうか」
「わからない、我々の科学ではわからない変化が起きているに違いない、おそらく海水に放射能の入った水を流したからではないだろうか。宇宙人はどこかで生きている、放射能の水は彼らに攻撃を仕掛けたことになったのではないだろうか」
「先生、それを発表してください。やめさせないと」
「そう書いた投稿原稿を新聞社に送ったよ、文科省にもそういったことは伝えてある。環境省にもね、大分前に出したけど返事はない」
「これは人間への警告ですね、人間は水を飲んでも大丈夫なようです」
安宅の書いた投稿原稿は二つの新聞社で採択され掲載された。しかし、文科省も環境省も全く動かなかった。ただ、原発の汚染水をできるだけほかの方法で処理するように電力会社には通達を出したようだ。しかし、いったん楽な方法を知った世界の原発会社はなかなかやめようとしなかった。
安宅が胆沢に言った。
「国は本気なのだろうか」
安宅も胆沢は個人的なメッセージを出し続けた。
そんなある日、原子力関係の研究者が、研究道具をもって鳥取の砂丘の上に浮いている探査艇に近づいた。
今でも、世界中にある宇宙船は人が近づかないように柵も作られ、セキュリティー会社が保護している。
その研究者は、世界的に知られている人で、前もって防衛省に許可をもらっていた。探査艇を作る物質を解析するために何度も訪れているので、セキュリティー会社の人も問題なく彼女を柵の中に入れた。彼女は片手をのばし、探査艇にそうっと触ろうとした。指先が探査艇の一センチほど手前で跳ね返されている。バリアーが張ってあるのだ。それは昔からわかっていたことである。
彼女は霧吹きで水をかけた。水は直接探査艇の壁には掛からず、水滴となって下に落ちた。これもすでにわかったことであった。
いつもその作業をやっているのを見ているガードマンは、何事も起きないと思いながら、柵の中の見回りに歩きだした。
研究者はジュラルミンの箱の中から鉛の容器を取り出した。中から鉱物を取り出して、それを探査艇に近づけた。キュリー夫人になったつもりなのだろうか。
その後、その鉱物になにやら計器をあてると、「やっぱり」
と声を上げた。
そのとき、突然、黒の球体の探査艇が転がり始め、砂丘の先から海の上に落ちた。探査艇は波が来ても揺れることなく、海に浮いていた。
驚いたのはガードマンである。あわてて、本部に連絡をすると、すぐに防衛庁関係の車やヘリコプターが到着し、その研究者は連れて行かれた。
鳥取県庁の一室で、研究者の女が話を聞かれていた。
「それで、ウラン鉱を探査艇に近づけたのですね」
「ええ、すると、ウラン鉱の放射能が消えてしまいました」
「その後に、あの探査艇は海に落ちたのですね」
「はい、触れてはおりません」
「なぜウラン鉱を近づけたのです」
「海の水が放射能を消すのは、宇宙人がしていることかもしれないと思ったので、やってみました」
「ちゃんと許可を得てからそう言うことはやってもらわないとね」
「すみません、しかし、探査艇は放射能を吸収するか消す働きがあります。海の水が放射能を消すのは海の中の宇宙船がやっているのではないでしょうか」
それに対して、質問をしていた係官は答えずにいた。
「もういいでしょう」
そう言ったのは、その様子を遠隔テレビカメラで聞いていた、宇宙人の解析に携わっている国際宇宙人研究所の日本支部長だった。
「もう帰ってもらっていいのでしょうか、それに新聞記者がたくさん来ております、どうしましょうか」
「結構です。新聞社にはこちらから記者会見をしますので、そう言ってください」
科学者も質問をしていた防衛庁関係者もなぜもっと彼女を追求しないのか不思議に思った。なにしろ、良かれ悪かれ、宇宙艇に反応を起こさせた初めての出来事だったからだ。海に浮かんで止まっている宇宙艇もどのようなことをしても動かせないし、反応しなかったにも関わらず、この女性科学者がウランを近づけたら、放射能は消えて、探査艇が動いたのである。
科学者は家に帰された。
そのころ、国際宇宙人研究所の日本支部はあわただしく動いていた。
日本支部の支部長が天文台の安宅に連絡を入れていた。
「安宅天文台長ですね、書かれていることを読ませていただいています。私は安宅さんのおっしゃることが正しいと思っております。我々もコミュニケーションをとろうと努力しておりました。放射能水を海に流すのは失敗だったと思います。宇宙人は海のどこかにいて、自分たちの宇宙艇も監視しています。
最初は深海に住むつもりだったのでしょう。放射能水が流れこみ、きっと攻撃ととらえられたのかもしれない。そして、実は今日、一人の科学者がウランを近づけたら、鳥取砂丘の探査艇が海に逃げました。
これは、大変なことがおこります。宇宙人は世界中の海にある宇宙艇も攻撃されると見なすでしょう。なにがおこるかわかりません」
「国際研究所ではどうするつもりでしょうか」
「現実に起きていることだけを伝えます、しかたがありません、宇宙人たちがやっているだろうということは言いません、わかる人はわかるだろうと思います」
日本の陸地ではこんなことがおき始めていた。
雨が降って小さな水たまりができて、ちょっと経つと、原生動物やプランクトンがあらわれたものである。ミジンコや緑虫である。
小学生が学校の課題で水たまりの水をとって、顕微鏡を覗いたら、原生動物どころか珪藻類など植物性のものもいなかった。
子供たちの報告に、最初先生は水の採取の仕方がいけなかったのだろうと思った。ところが、原生動物を研究している科学者もそれに気がついた。
それだけではなかった。野生の動物たちがいなくなっていった。
動物園の飼育員が、井戸の水をくんで動物たちにあたえた。水道のカルキの入った水より体にいいだろうと、いつも与えている水である。
すると、動物が溶けた。水を飲んだ動物が屋内で、屋外でとろとろに溶けて、水になり、そこに水たまりができた。
鳥が飛ばなくなり、鼠がいなくなり、モグラがいなくなった頃である。
国際宇宙人研究所日本支部では、国際会議が行われていた。安宅と胆沢も招かれて、オブザーバーとして参加していた。
世界の各地から、陸上の生き物たちが消滅していることが報告された。アフリカでも同じである。象やライオンが水になって乾いた土の中に浸み込んでいった。
日本支部の支部長が安宅の意見を述べ、安宅を紹介し、オブザーバーだが、特別に発言してもらうことを説明した。安宅は原発の放射能を含んだ水を海に流したことと、鳥取の探査艇にウランを使って放射能にたいする影響を調べたことが、宇宙人にとって大変な攻撃になった可能性を述べた。
その意見に賛同する人たちもかなりいたが、宇宙人が海の中で生存している可能性を否定する国もあった。
安宅は地球に来た宇宙人がコミュニケーションをとろうとしていないのではなく、人間とは全く異なる生命体で、とることができない可能性を説いた。
深海の生物が消滅したのは最初の警告で、そのあと、放射能がながされたことで、さらなる警告として水の中のすべての生き物を消滅させた。
その上、探査艇にウランを近づけたことから、陸上の生き物も水になって消滅しはじめた。生き物を水にしてしまっているが、人間はまだ大丈夫だ。ここで、放射能を吐き出すものをすべて廃棄しなければ、我々人間も消滅させられる可能性がある。
宇宙人は人間の形になって現れた。彼らは自分の星が何らかの形で住めなくなったので、住めるところを探して宇宙をさまよっていたのではないだろうか。やっと水のある星を見つけ、その住人である人間の形になって、まず交渉しに鳥取に下りた。水にすむことを認めてもらいたかったのではないかと思う。人間が知らないうちに水の中にすむこともできたのではないかと思うが、こういう形でしか、メッセージを送る方法がなかったのかもしれない。
水の中は宇宙人がすむ、人間は陸に住む、平和にやろうということではないだろうか、と安宅は結んだ。
それに対し、もしそうだったら、どのように彼らに交渉したらいいかという問いがあった。
安宅は「原発、原爆をすべて、破棄すればいい」と言った。
うなずいている者も何人かいた。
ノールウェーの代表が質問した。
「北の海に宇宙船は降りたが、南極に降りたのは少しだけで、しかも海の上だ、どうしてでしょう」
ハンガリー人の所長が「安宅が言ったように、水をもとめていたのじゃないだろうか」と答えた
「なぜ、宇宙人は宇宙船を人間に見えるところにとめてあるのだろう」
オランダの代表が質問した。
「宇宙船が我々に見えるところにおいておくのは、我々が水の中にいるぞと言うことを示しているのだろう」
所長が答えた。
「これからの、問題は、安宅の言った、放射能の撤去をすべての国で行うことだろう、それが人間の生き残る道だろう」
大国と言われる国の代表たちは、宇宙人はもういないという立場をとっていた。
それでも、その会議の結論は世界に発表された。といっても、その結論が原発、原爆を破棄することにすぐつながるわけではなかった。
大国の一つが地下で新型原爆の実験をおこなった。その地の地下に、とてつもなく強い放射能が充満した。
その国の人間が水を飲んだとたん水になって溶けていった。人が水になって土に染み込んでいく。大きな大陸をしめるその国の人間はすべていなくなった。
一つの大国が自分の国で打ち上げた宇宙ステーションから、太陽に向かって水素爆弾をつんだロケットを打ち出し、途中で爆発させて威力を調べた。地上でなければいいだろうと思ったのだろう。
そのとたん、その国の住人どころか、地球の陸上の生き物、人間も次から次へと水になっていった。水道水を飲むと人は水になった。
日本でも例外ではなかった。
その日、胆沢は朝、いつものように妻と紅茶を入れて飲んだ。そのとたん、自分のからだが放散していくのを感じた。目の前の妻も溶けていく。
胆沢はキッチンの床の上の水溜まりとなった。水になった胆沢は水蒸気になって、空の上に昇り、雲になった。それでも胆沢の意識だけはあった。なにも周りは見えないが意識だけである。
ところが、雨になって海にふりそそいだときである。海の中を魚が泳いでいるのが見えた。その周りを真っ黒なアメーバーが浮かんでいる。
ほかを見ると、水母とともに真っ黒なアメーバーがからだをくねらせている。大きさは人の大きさだ。
胆沢は海の底を見渡した。黒いアメーバーが海底の蟹の間に浮かんでいる。
胆沢はすぐそばに黒いアメーバーがよってきて、自分を見ていることに気がついた。
「やっとお互いが見えるようになったね、はじめからそうしても良かったんだが、元の形のまま共存できればと思ったんだけどね、だけど我々と同じになってもらわないと、共存できないことがわかったんだ」
「宇宙から来た人たちですか」
久々に彼は他者に向かって声を出した。今の自分がどのような格好をしているのか、周りの魚などは見えるが、自分は見えない。
「そう、自分の星が住めないような状態になって、住む星を探していた」
「どこにあった星ですか」
「地球では光を単位にしているが、我々は意識を単位にしている。意識はどこにでもあっという間に飛んでいける」
「それでは速さはないと言うことでしょうか」
「瞬時といっていいけど、受け手がないと宇宙で彷徨うことになる」
「あなたの星では意識だけが存在しているわけですか、形がないわけですか」
「いえ、水の中でこのように、意識が水のある素粒子をまとめて、黒い不定形の固まりになっていますよ、あなたが、アメーバーと言ったような形です、水に溶け込んだ意識という生き物です、こういう形になっているときが我々は安定した気持ちになれるのです」
「それでは、分裂して増えるのですか」
「いえ、地球人と同じで、好きあうと合体します、それで、子供を産む、今あなたが話している私は、親同士が合体して一つの意識になったものです」
「意識は乗り物がなくても飛ぶことができるのに、なぜ、宇宙船に乗ってきたのですか」
「さきほどいったように、受け手のあるところにしかいけません、意識だけは想像したところにいけますが、現実にそこがなければ元に押しもどされます。現実に水のあるところを偵察する宇宙船を四方にとばしています。水のある星をみつけると、宇宙に飛ばしている宇宙艇がそこにあつまります。鳥取に下りた偵察船は下見におりたのです。意識の一人がその宇宙船に飛びうつり、外に出たわけです。地球の生命体がここまで進化していることは知りませんでした。偵察に行った一人は歓迎におどろいて、水に飛び込みました。そして、彼は黒いアメーバーの形になったわけです。水があることを知った我々は、すぐに地球の海の中に移動しました。そのあとで、宇宙艇を全て海の上に着水させたのです。地球が我々にとって住みよくなければ次の星を見つけに行かなければなりません」
「あなたの星では水がないのですか」
「はい、熱くなって燃えて水分はなくなりました」
「海の中に魚が泳いでいるのが見えます」
「そうでしょう、地球の生き物は皆海の中で生きています。意識だけになっても水の中では元の形になります、ただ、人間だけは違います、そのうち海の中で会いますよ、またお会いしましょう」
黒いアメーバーは海の中をくねっていってしまった。
胆沢はどうしたらいいかわからないが、動きたいと思った。すると、海の中を移動できた。白いアメーバーが近づいてきた。
「あなたのようね」
妻の声だった。人間は白いアメーバーになって、海の中で生きていた。
下を見ると、海底を猫とライオンが歩いている。
妻の白いアメーバーが近寄ってきた。
黒いアメーバーが気に入った相手と見つけるといっしょになって、新たに意識を持つといっていた。胆沢はその話を妻のアメーバーに言った。
「人間の場合どうなるかわからないから、もう少し様子をみたほうがいいわよ」
妻の意識は人間の時と同じで慎重である。
黒いアメーバーも近寄ってきた。
胆沢は聞いた。
「意識を一緒にさせるとどうなるのです」
「全く新しい意識になって、昔のことは忘れます」
人間にとって昔を忘れることは、個人をすてることになる。死んで新しく生まれ変わるのと同じである。この宇宙人たちは自分をなくすことが、相手を好きになることなるわけである。
それを聞いていた妻のアメーバーも「やめときましょう、自分のままでいた方がいいわ」
と言った。胆沢もそう思った。それが人間で、寿命のある一生が、自分、個人なわけである。死ぬと自分はいなくなる。宇宙人たちは新たな意識を産むために自分の意識を死なせることになる。
いろいろな生き物がいるものである。
「宇宙船はどのように作ったのです」
「我々は集団になると、意思で物質を変えることができます、放射能は物質を変える我々の力を押さえます、生きているだけならいいが、我々が活動できなくなります。放射能さえなければ、陸にすむ地球の生き物と水の中に住むわれわれと共存できたのですが、難しいと判断しました」
「コミュニケーションができれば、我々も考えたと思います」
「そうでしょうね、話をすることができない宇宙の生き物はたくさんいます、そう言う生き物と遭遇したときには、そのときそのときで、工夫をします。今回、我々に同化してもらうほかにコミュニケーションはとれないことがわかりました。
我々は侵入者で申し訳ないと思いますが、我々も種族を残さねばなりません、地球の生き物に我々と同じ世界の生き物になってもらうしかなかったのです」
「我々地球人はあなた方と同じ意識だけになったわけですね、これからどうしたらいいのでしょう」
「これから何千、何万年も経てばその結論が出るでしょう、今、まだかなりの数の宇宙船を飛ばしてあります。まだ水の豊かな星を探しているのです。もし、住める水の星があれば、我々は地球から出て行きます。地球の生命はそのままでよければ、水の中で暮らしているでしょうし、元に戻りたければ、そうなれるようになるでしょう、時間はかかりますが」
「意識だけで学ぶことはできるのでしょうか」
「物質をも変えることができるようになります」
「どうしたらいいのでしょう」
「我々も、何億年も生きてきてそうなりました、元は形があったのです。素粒子の宇宙でした。今は意識というものになっています、地球人もそうなるでしょう」
黒いアメーバーはそう言うと、うねうね海の中を動いていった。
「あなた、人間同士集まって、解決しなければいけないわね」
「リーダーが必要だな、安宅さんがどこかにいると思うよ」
「意識を変えた方がいいわよ、あなたがリーダーになりなさいよ」
人間は合体しなくても意識を変えられる。そこが宇宙人と違うところかもしれない。
そう言えば、寿命を聞くことを忘れた。
通りかかった黒いアメーバーに尋ねた。
黒いアメーバーは答えた。
水


