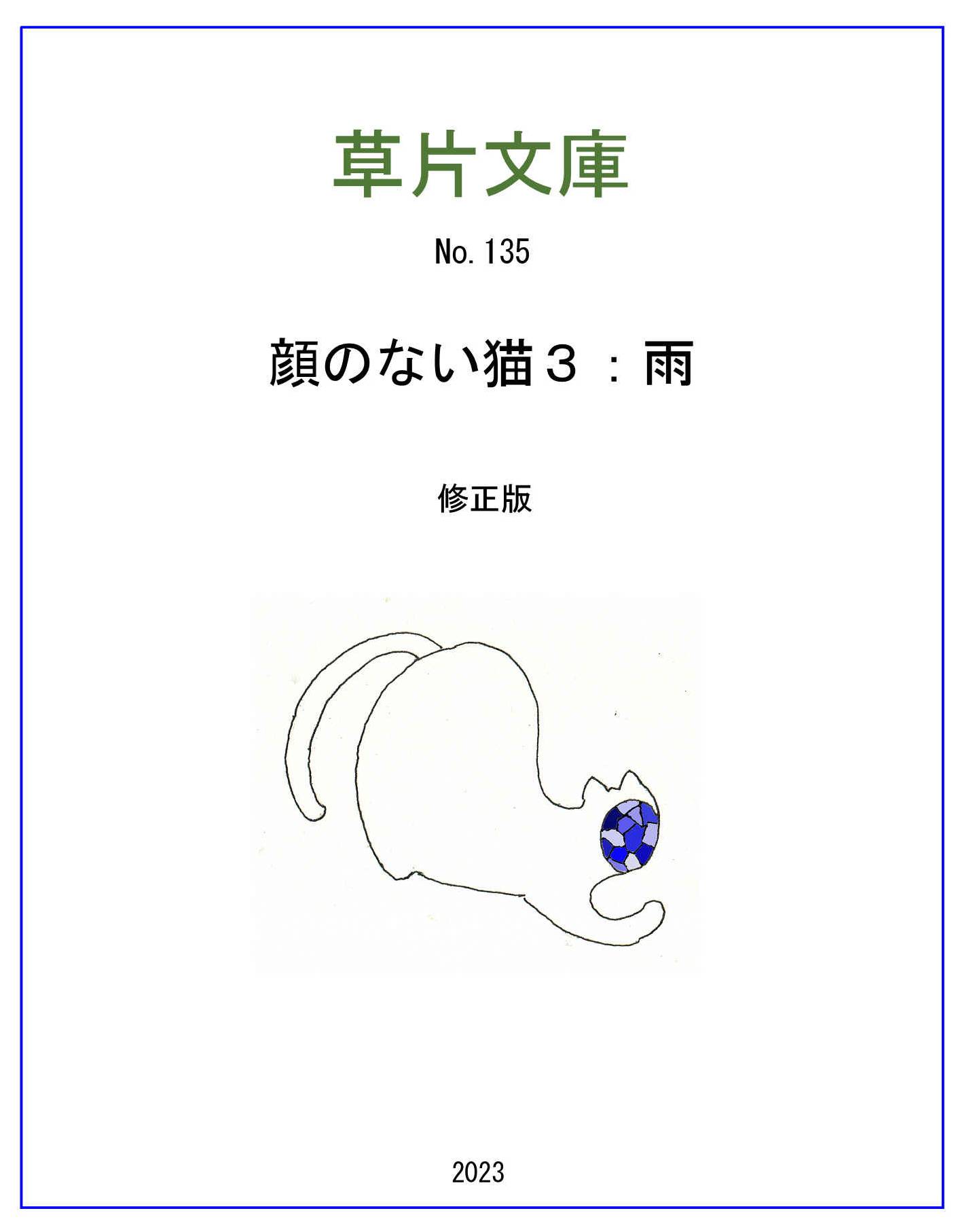
顔のない猫3ー雨
猫幻想譚
顔のない猫3-雨
今日の雨はしとしとと、あたかも時代がむかしにもどったような、おしとやかな降りだ。最近ひどい降りが多いのは、地球の大気の温度が上がったからだといわれている。一方で、乾燥で山火事が猛威をふるっているところもある。ともかく、昔のように季節の変化に沿って、詩が詠めるような降り方が少なくなった。
校正の仕事を途中で切り上げ、今日も新宿駅で私鉄の最終電車にやっと間に合う時間になっていた。それでも、最終に間に合えばいいほうで、もっと遅くなると、自分の駅にまで行ず、途中が終点の電車になり、その終着駅からタクシーということになる。
やっと駅に着き、まばらな客に混じって駅からでると傘を差した。
この駅のある市はベッドタウンとして開発された地域の一つで、住宅地が広がっている。
私の家も駅から東の方に十分ほど歩いた低い丘の一角にある。
コンビニ、小型の量販店、ラーメン屋など、小さな店にはさまれた二車線の道を五分ほど歩いていくと上り坂になり、また五分ほど上ると小さな公園がある。それを過ぎると横道があり、曲がると一戸建てが群がる住宅街になる。その一角に我家がある。
公園が見えると、あ、家に帰ってきたという気になる。小さな公園の入口を通ると、園内の暗がりに猫の目が光っていた。このあたりに野良猫はほとんどいない。もちろん飼っている家はたくさんあるが、ほとんど猫を外にだすことをしない。
祖父の家は地方のためもあるだろうが、猫は自由に家を出入りして、昨日の夜にはどこどこの家の猫とどこどこの猫がけんかをしていたとか、仲良くしていたとか、まるで、自分の子供のように噂話をしていた。
この地で猫が雨の中の散歩とは珍しい、野良猫の可能性もあるが、住宅地で見かけたことはない。駅の近くの食べ物屋のまわりにいたことがあるが今は見ない。
公園を通りすぎ、道を曲がるとき、ふと公園の入り口に目がいくと、白い猫の顔が宙に浮いている。
どきっとして立ち止まってしまった。まだ浮いてゆれている。顔が白くて体が黒い猫だと思いついてなぜか安心したとき、猫の白い顔が自分の方に歩いてきた。
胴体がない。顔だけ雨の中に浮いている。
またぞくっとして、あわてて早足になって、道を曲がってすぐのところにある自宅に戻った。
なにを見間違えたのだろうか。こんをつめて校正をしたすぐあとは、眼の焦点がなかなか合わないことがある。今日もそうだった。目が疲れているようだ。やはり顔だけが白っぽい猫だったのに違いない。公園の角にある街灯はあまり明るくない。電球が古く汚れている。そのせいもあるのだろう。
玄関を開け、明かりのスイッチを入れると、ほっとため息がでた。疲れている。
両親が亡くなり、一人暮らしになって三年、やっとなれたところである。
風呂を沸かし、暖まると、さっきの白い猫の顔が目に浮かんだ。あの猫は自分のほうに向かって歩いてきた。野良猫の目ではない、飼い猫が主人を見るような嬉しそうな目をしていた。と今になって思った。両親が相次いで死んで、長くかわいがっていた茶虎の猫もその一年後に死んだ。子供の頃から猫が何匹かうちにいた。両親も猫好きだったが、一人っ子の自分はどうしても猫と遊ぶ時間が長かった。
一人暮らしだが、今の仕事なら、猫ならば飼うことはできる。出張もはいることがあるが、預けるところを見つけておけば大丈夫だ。もう少し落ち着いたら誰かから猫をもらおう。
そんなことを考えながら、風呂から上がり、ミックスナッツの封を切り、ビールを飲んだ。もう夜遅い、食事は校正の合間をみて、弁当屋から買った唐揚げ定食を食べた。
ビールを飲み終え、ノンカフェインのビタミン剤をのむと、パジャマに着替えた。明日も、校正の続きをしなければならない。最近の作家の書くものは枚数が多い。作家が万年筆を使わず、コンピュータで書くようになってからの現象だ。
朝、昨夜しとしとと振っていた雨が止んでいた。しかし雲がどんよりと空を覆い、いつ雨粒を落ちて来るかわからない様子を見ると、気持ちが圧迫され、落ち込んでしまう。
さー仕事だと自分にむちをうち、駅にむかった。家をでてすぐに角の公園の椿の木が眼に入り、昨日の猫の頭が思い出された。元気なときだと、幻想風景を楽しむ余裕があったのだと思うが、疲れていたのだろう。角を曲がると公園を囲む小さく刈り込まれた木々の葉が元気いっぱいにとがっている。梅雨は植物にはうれしい季節だ。
入り口のところで、足に何かが押しつけられ、驚いて足元をみた。なにがあるわけでもない。なんだまだ続いているのか。どうも昨日から気持ちが落ち着かない。今担当している小説はSF冒険物で、気が滅入るような話でもなく、どちらかというと荒唐無稽なおもしろい内容だ。
気持ちを切り替えなければと、駅に急いだ。
その日は一日雨が降りそうで降らず、日も照らないので、かえって町は陰気な雰囲気がただよっていた。
やはり終電になってしまった。
街灯の明かりがぼんやり続き、公園にさしかかったとき、動機の高まりを感じた。
なにもいない。ところが、にゃーという猫の声が聞こえた。動機の高まりがおさまらない。捨て猫がいるのだろうか。それなら飼ってやってもいい。そんな気持ちになって、公園の入り口に立ち止まった。
公園の中に目を走らせた。いない。茂みの間をにらんだ。やはり何もいない。あ、っとおもって足元に目をやった。自分の足に猫がこすりついた。だが足下にはなにもいない。動機がさらに強くなった。
また、にゃーと声が聞こえた。
最初の日に感じた恐怖感のようなものが首筋をはい、心臓のなかにはいりこんできた。怒りは胃と腸から生じ腕から手に伝わり伝わり拳を作るが、恐怖感は首筋からはいり、手の形になって心臓をつかむ。つかまれた心臓は手をほどこうとどくどくと暴れ始める。
動機が早くなるのを感じて、公園からとびだした。猫の声は空耳だったのかもしれず、足にこすりついたのはただの風のいたずらかもしれない。
家の玄関の前にきて、やっと胸の中がおちついた。鍵を出して、戸を開けると、玄関に飛び込んだ。後ろでニャアという声が聞こえたような気がしたが、もういい、かなり頭が疲れているようだ。そういえば、有給休暇をほとんどつかっていない。今度の仕事がおわったらしばらく旅にでもでよう。
いつものように、風呂を沸かし、湯船につかった。
こんなに気持ちが混乱したことはない。会社の産業医にも、あなたは鬱などからはほど遠い人ね、うらやましい、と言われている。からだに問題はないこともあり、デスクワークでもかなり無理ができる。
鬱や妄想などは医者が病名をつけるからいけないのだくらいにしか思っていなかった。
体を動かして頭を休めなさい。とはいわれていたが、作家の書いた文を校正し、よりよい形にしあげることは自分にとって楽しい仕事でもあり、一冊の本として世に出たとき、その本の著者とは別の嬉しさがあった。自宅の本棚には自分が関わった本がならんでいる。中には後書きで自分に謝意を書いてくれている本もかなりある。たとえそのように名前がのらなくても、本を作り上げるという課程では装丁家とともに主役である。
風呂から出ると、いつものようにビールを飲んだ。冷蔵庫にはいろいろな会社の缶ビールと、機会があるごとに買っておいた地ビールのたぐいがいつでも飲んでくださいと冷えている。今日は北海道の流氷ビールにした。新宿のデパートで地方の物産展をよくやる。そういうときに購入したものだ。
飲み終わると無性に眠くなった。心臓が疲れて眠りを要求しているようだ。すぐにベッドにはいった。
あくる朝、目覚めは昨日のくすぶった頭の中とはうってかわって、高原のさわやかな風が吹いていた。きっといい質の眠りだったのだろう。
だが、寝室の窓のカーテンから外を見ると、梅雨の雨がおちている。だけどなぜか気持ちが明るい。
トーストと紅茶といった簡素な朝食がやけに旨い。
食事を終えて、あとかたづけをすると、玄関の戸を開け、外の様子を見た。雨の様子を見たかったからだが、開けたとき玄関先から白い物が自分の脇をすり抜け飛び込んできた。
そいつはにゃーと鳴いた。
猫だ。白い猫が雨に濡れて、玄関脇で自分を見ている。これでもっと自分の気持ちが晴れやかになった。昨日一昨日の夜の出来事は頭のせいじゃない。猫はちゃんといたんだ。
猫は僕のほうを向いて、またニャアと鳴いた。
昨日の夜、公園から自分のあとをついて来たに違いがない。大人になったばかりのまだ若い猫だ。腹が減っているはずだ。もう飼うつもりになって、白猫を抱き上げた。猫はいやがらず、なされるがままになっている。金と銀のオッドアイの整った顔をしている。
風呂場につれていくと、タオルでからだをふいてやり、キッチンにつれてきた。床の上に下ろすと、猫はおとなしくおちゃんこをして、僕の動きを見ていた。
器に牛乳を入れ猫の前においた。
猫はすぐに顔を突っ込むと、髭をふるわせながら、ぴちゃぴちゃと音をたて、小さな赤い舌を上下させた。ミルクがどんどん減っていく。すぐなくなった。
その間にツナの缶詰を開けて、身を皿に入れた。
帰りに猫えさかってくるからな、まってろよ、声をかけて、皿をおくと、あぐあぐあぐと、あっというまに食べてしまった。
白猫はどうやら満足したようで、顔をしきりと洗い、濡れたからだをなめている。
時計を見た。もうすぐ家を出る時間だ。
廊下に古くなった毛布を敷き、空いている段ボール箱を脇においた。どちらかが寝床かトイレになるだろう。
用意をすると、白猫の頭をなでた。猫はしきりに身体を舐めている。
ツナ缶をもう一つ開け、皿にあけると家をでた。
その日、やはり夜遅くなり、コンビニで何種類かの猫の餌を買い家に戻った。
玄関を開けるときっと白猫がでてくる。そう期待して、鍵を開け、家の中をのぞいたのだが、猫はでてこなかった。
廊下の毛布の上にも段ボール箱にもいなかった。与えたツナは全部食べてある。きっとどこかで寝ているに違いない。キッチンか居間だ。寝室や自分の部屋の戸は閉めてある。
キッチンに行ったのだがいない、居間にもいなかった。
猫の鳴き声が近くで聞こえた。どこにいるのだろう。
キッチンの隅においてあるごみばこまでさがしたがいない。この家には猫の出入りできるような穴はない。
二階の寝室や自分の部屋も調べた。
おかしなこともあるものだ。
しょうがない、いつものように、風呂を沸かした。
風呂に入っていると、脱衣場からニャーと猫の鳴き声が聞こえた。
湯殿の戸を開けたが、脱衣場にはなにもいない。風呂場の湯気がわーっと脱衣場にながれていくのがわかる。
脱衣場に湯気がみたされていくと、床に白い物がぼんやりと現れた。やがてそれは白い猫になった。こちらを見て、ニャーと鳴いている。
目が疲れているのだろうか。
急いで体を拭いて、脱衣場にいくと、白い猫は足にこすりついてきた。バスタオルで自分の体をふき、パジャマをきると、白い猫を抱き上げた。猫は腕のなかで、ぐにゃっとなって、トロンとした目になった。
眠そうだ。猫は自由だ。人間は幸せそうな何かを見るのが好きだ。猫は気ままというが、確かに一番したいことしかしない。だから、いつも気持ちの良さそうな表情がある。それが人間をひきつける。あたかも自分がその猫を幸せにしてやっているような錯覚におちいる。猫は自由気ままに好きなことをして、幸せそうな態度でわれわれと接する。
白い猫があくびをした。目を閉じた。湿っていた毛が乾いてきた。
あ、っと、猫をとり落としそうになった。胴体が消えていく。だが、手には猫の毛の感触があるし、ずっしりと重みも感じている。手足が消えた。顔が消えていく。消えながら目を開けて僕を見てニャーと鳴いた。
私は透明になった猫をかかえて途方にくれていた。
ベッドに連れていった。
そうっと、布団の上の足下の方に置くと、布団がくぼんだ。
首筋から尾の付け根まで触ってみる。ごろごろいいはじめた。透明の尾っぽに触ってみる。先がほんの少し曲がっているが、ほぼまっすぐだ。頭をなで、のどをさすると、ごろごろの音が強くなってきた。
家にいないと思った猫が風呂場で湯気にあたりいきなり姿を現した。抱き上げると手の中で消えていった。いや透明になっていった。夜公園で見かけたのは雨のしとしと降っているときだ。我が家に入れたときも雨に濡れていた。
まさか、と思いながら、湿したタオルをもってきた。猫のあたまからせなかをふいた。うっすらと白い猫の毛が浮き上がった。顔を拭いた。猫が顔をぶるっとふるわせて現れてきた。
眠くなったのも忘れてみていると、現れた白い顔と背中はだんだん消えて見えなくなった。
水に濡れると見えるようになる。
自分の頭も朦朧としてきた。電気を消して、猫の脇で布団の中に潜り込んだ。あっという間に寝てしまった。
朝の目覚めは気持ちがよかった。目を開けて交感神経の働きが目覚めると、ほほに猫の毛がふれた。枕元に手を伸ばすと、猫がいた。昨日の夜を思い出した。この白猫は毛が濡れると現れる。
透明の猫に、おきるぞと声をかけた。とんと猫が床に飛び降りる音が聞こえた。
洗面所にいくま柄に、キッチンで猫餌を器にいれてやった。カリカリと食べる音が聞こえ、餌が消えていく。
自分は洗面所で顔を洗いひげをそった。
湿したタオルをもってキッチンに行き、自分の食事の用意をした。カリカリと音が続いている。音が途切れた。触ってみると猫がおちゃんこしている。顔を洗っていたようだ。抱き上げて、湿したタオルで猫をふいた。白い猫があらわれてきた。床に戻すと、また餌を食べ始めた。
湿したタオルだけではすぐ消えてしまう。だが濡らしてしまうのは猫にとって本意ではないだろう。
このくらいはいいかと、観葉植物のためにおいてある霧吹きにお湯を入れて、軽く猫に吹きかけた。
白い顔がこちらを向いた。よってきて、足元にこすりついた。だきあげると、毛が湿っていてあまり気持ちがよくない。猫にとってもいやだろう。そう思って床におろした。
猫はキッチンからでると居間にはいっていった。居間をのぞいてみると、ソファーの上で身体をなめていた。やがて猫は透き通っていき、見えなくなった。
こうして、透明な猫と一緒の生活がはじまった。
見えなくても膝の上に上がってきて、ごろごろと喉を鳴らす。寝ていると、枕元によってきて前足でほっぺたをたたく。餌がほしい時のようで、半分寝たままベッドから出て、寝室に用意しておいた餌を、器にいれてやる。一階のキッチンまで下りるのはいやだから、猫餌を寝室に用意するようになった。寝る前にはキッチンの器に、必ずかりかりをもりあげておくのだが、それもたべてしまって、もっと欲しいときに寝ている僕の顔をたたいて起こす。
雨がやんでいるとき、一緒に家を出ることがある。白猫は透明のまま一日遊んでいる。腹が減らないかと思うのだが、透明になっていると、ネズミは取り放題のようだ。どうも駅の近くの方まで遠征して、食べ物屋のあたりに出没するネズミをたいらげているようだ。
一日遊んでいるときは、夜中に僕が家に帰り、鍵を開けようとすると、足にこすりついてくる。あけると飛び込んでキッチンに行く。透明な猫でもうごきがわかるようになってきた。
そんな猫との暮らしが半年続いた。
冬になり、雪が降った日曜日、見えない猫は庭にとびでて、白い雪の上を歩いた。猫の足跡がずぼずぼとついて行く、やがて、真っ白な雪の上に、真っ白な猫があらわれた。雪が毛について溶け、濡れたからだ。
家にはいると、餌を食べ、また外にでた。白い猫は一日中庭の雪で遊んでいた。
夜になり、部屋の中で毛が乾いた猫は透明で見えない。だが、今日は尾だけが白いままだった。
あくる日も透明な猫の尾っぽは白いままだった。
ベッドの布団の上で、白い尾っぽだけが、ぴこぴこと動いていた。もう尾っぽは消えなくなった。
尾だけが白く見えるようになった猫は、庭には遊びにでたが、公園にいくことはなかった。自分の尾が人の目にもネズミの目にも見えるようになったことを理解しているようなのである。
暮れも押し詰まり、仕事が休みになった日に、雪がまた降った。この暮れの二度目の雪である。その朝、尾っぽだけ見える猫はめずらしく外に出たがった。
寒いぞ、と言って、玄関を開けると、尾っぽが外に消えていった。庭に行った猫は雪の中で飛び跳ねていた。からだも濡れてきてだんだん見えるようになり、顔も現れた。金と銀の目が私を見て、こっちにこいといっているようだ。そばに行ってだきあげた。かなり重い。立派な成人の雄猫だ。
ごろごろと喉の鳴る音が雪に反射する。
下におろすと、積もった雪の中にずぼずぼはいっていく。雪と同じ真っ白な猫だ。
遊び疲れて家の中に入ってきた白猫は、餌をたくさん食べ、寝室のベッドの上でまるくなった。ふとんが濡れてしまう。丸くなったままのからだの上をタオルで拭いてやる。寝たままだ。寝息もたてている。いい夢をみているのか。
丸くなった猫は頭からだんだん透明になった。だが下半身はまっ白のままだった。
下半身は消えなくなったのだ。
明くる朝ベッドの上で伸びをした白猫は、まだ布団の中の私の枕元にくると、見えない前足でほっぺたをぱたぱたたたいた。餌をくれということだ。ついでに起きようと、二回におり、キッチンで餌をやり、洗面所にいった。
キッチンに戻ると、下半身だけ見える猫がカリカリと音をたてて餌を食べている。
年も明け、仕事が始まった。猫は一日中家の中ですごしている。猫の餌とトイレに流すことのできる猫トイレ用の紙でできた砂を買うことが日課の一つに加わっている。休みの日にそれらのものの買い出しに出かける。
二月に入り、また寒気団が南下してきた。大雪の注意報がだされ、予報通りに丸一日雪が降り続いた。その朝は電車も止まり、自宅で仕事をすることになった。
昼前には雲間から日が出でた。猫は喜んでふかふかの雪の中に身を沈めた。だんだんと上半身と顔も現れ、久しぶりに白の顔をみることができた。金と銀の目がきょろんと、居間のガラス戸越しに見ている僕を見た。玄関に走っていく。昼になると中に入りたくなったようだ。玄関の戸を開けてやると、びしょびしょになって中に飛び込んだ。タオルで拭いてやると、餌をたらふく食べ、また外に出たがった。
校正の仕事をしているときには、ずーと庭で遊んでいた。夕方になると、さすがに疲れたのだろう。気がついたときには玄関の前でぼーっとしていた。開けてやるとあわてて飛び込んでキッチンで餌を食べた。タオルでからだをぬぐったが上半身はなかなか透明にならない。ずいぶん濡れてしまったようだ。居間のガスヒータの前で暖まっている。からだは乾いたようだが頭だけ見えている。ソファーに腰掛けテレビを見ていた私の脇にくると、身づくろいをはじめた。タオルであたまをふいてやった。だんだんと顔がきえていく。
テレビの天気予報では、寒気団はまた大陸の方にもどり、二月は全般に例年より暖かい日がつづくだろうといっていた。
隣に座っていた猫は、丸くなって寝てしまった。身体は白いままで、顔だけみえなかった。胴体から首まで、消えることなく、ふつうの白い毛の猫になった。
顔だけ透明である。顔のない猫だ。
わたしはようやく、雪に埋もれると猫が透明にならないことに気付いた。だから顔はそのままなのだ。
次の雪の日には、顔も永久にみえるようになってくれるように願った。顔に雪をぬっちまおう。そう思うと雪の日がまちどおしくなった。
だが、天気予報ははずれなかった。四月になるまで、何度かちらちらと粉雪がまったが、つもることはなかった。
桜の花が咲いた。
家の中では顔のない白い猫がうろうろしていた。天気の良い日は庭で遊んでいる。
ソファーに腰掛けていると、胴体だけが近寄ってくる。明らかに顔は私の方を向いているのだが。となりに座りたいといっているようだ。ほら、ソファーの上をたたくと、すぐに飛び上がり、隣にきて顔をこすりつけてくる。髭がごぞっとする。頭をなでてやる。喉の下をさすってやる。すぐごろごろといいはじめる。
編集の仕事は今年に入って三冊目だ。自分の担当はどちらかというとシュールかかった作家の物がおおい。だが、今担当しているのはどちらかというと素朴な、ノスタルジックな、だけど幻想味たっぷりの話しだ。猫も登場してくるが、夜は好きなところをさまよう昔の家猫だ。
その文章を読んで着ると、早く家に帰って、顔のない猫を膝の上に乗せたいと思う。冬になって雪が降れば、顔が現れるに違いない。
連休は少しばかり休みが取れた。だがこの期間は旅行にでかける気がしない、山も海も、もちろん寺社仏閣も人に埋もれる。人間は誰もが新しい刺激を必要としている。自分はどうだと考える。もちろん普通の人間だ。新しい刺激はほしい。しかし、顔のない猫との生活ほど刺激的なことがあるだろうか。顔のない猫が家の中をうろうろしているのだ。
いつぞや猫の頭の付け根を見てみた。首の切り口になる。首の中の骨や気管や食道、それに血管の切り口が見えるかと思ったのだが、ミルク色の霧がかかったようにぼんやりとしている。下半身が現れたときも、同じように切り口はぼんやりと霧だった。もしはっきりと臓器が見えていたら、さすがに気味悪く近づけなかったかもしれない。
六月になった。半ばになると梅雨の宣言がくだった。雨がひどくないときには、猫は庭にでる。顔が現れ、金と銀の目をまるくして、髭をぴんとたてて、遊びまわった。
そのときはよく一緒に庭にでた。遊び疲れて家にもどると、顔がだんだんと消えていく。かりかりと顔のない猫が餌を食べる音が聞こえてくる。
この白猫は雌である。このあたりに野良猫もいないし、外飼いの猫もいない。子供を作る心配はないだろうが、顔が消えなくなったら、獣医に連れて行って、避妊手術をして、登録をしなければならないだろう。
今年の梅雨も雨の量は多かった。
七月に入っても雨はよく降った。ニュースでは梅雨明けは半ばになると予報している。
梅雨明けの頃は雷が鳴る。
日曜日日、目が覚め、ベッドの上から窓のカーテンをめくってみると、どんよりと曇っており、薄黒い雲が垂れ下がり、今にも雨が降りそうな様相をしていた。いよいよ雷が鳴る、
顔のない猫はベッドの上でまだ寝ている。珍しい
時計を見ると7時を過ぎている。
起きて朝の儀式を終え、着替えると朝食の用意をした。トーストにヨーグルト、トマト、紅茶、いつもおなじだ。
食べていると、猫が起きてきて餌をねだった。器にカリカリを入れてやると、あっという間に食べて、もっとと要求した。さらに入れてやると、それも食べてしまった。
顔のない猫は、おそらくこっちを向いて、ニャーと鳴いた。外にでたいようだ。庭でおしっこでもするのだろう。玄関を開けてやると、蒸した空気が流れこんできた。すぐにでも雨が降りそうだ。でたいのかと思ったが、なかなか外にでようとしない。
どうした、と声をかけると、足下にきて、ズボンの裾が引っ張られるのが感じられた。
猫がズボンの裾をくわえて引っ張っている。
僕にもでろっていってるのだろうか、そうなのかいと言いながら、玄関から外にでた。
猫は門のほうに歩いていく、途中でたちどまった。首の形から自分を見ているのがわかる。外に出る気なのだろうか。うちに着てから一度も門の外には出ようとしなかった。
一緒にきてくれというのだろうか。
門のところにいった。猫は鉄格子のとびらの間から外にでた。立ち止まった。やはりこちらを向いているようだ。
今日はいつもとは様子が違う。
日曜日の朝、あまり人は通らない。誰かが顔のない猫を見たら、仰天するに違いない。そういえば自分はどうして平気なのか、すんなりといつの間にか透明なこの存在を受け入れ一年以上たっている。
顔のない猫は道を歩き始めた。僕もついていった。猫と最初に会った公園にきた。猫が中に入っていく。小さな公園だが、一つだけベンチがおいてある。
顔のない猫はベンチの前の濡れた草地におちゃんこをした。私はベンチに座り、猫に話しかけた。
「きょうはどうした、何で公園にきたんだ」
猫は私の方に首をあげたようだ。
そのとき、バリバリバリという音とともに閃光が目の前にはしった。
一瞬、猫の白い顔が浮かんだ。私を見てニャーと鳴いた。
びりびりと電気が自分の顔の周りをうずまいた。
白い猫からするどい炎があがった。
猫が燃えている。
大粒の雨がおちてきた。ざーっという音とともに激しい雨になった。
赤い炎が静まり、黒く焦げた猫が草原によこたわっていた。
声がでなかった。
雨が猫に降りかかり、黒くなった死体は土の中にしみこんでいった。
私はのろのろと立ち上がって、猫のいたところに手をやった。猫はもういない。
涙なのか雨なのかわからない、顔がびしょびしょになった。
そうだ、なぜ猫に名前をつけてやらなかたんだ。
ざんざんぶりの雨の中、家まで歩いた。やっと歩けた。
門を開け、玄関を見た。
真っ黒な猫が玄関の上でたたずみ、黒い尾を揺らしていた。
黒い猫には顔があった。金と銀の目で、私の帰りを待っていた。
「黒」
思わず呼んだ。
黒猫はニャーと鳴いた。声は白だった。
顔のない猫3ー雨


