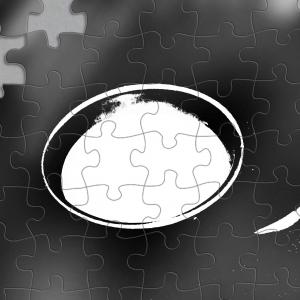「動かぬ星」
一「序の末裔」
雪の冠は空溶けて鳩の羽に移りしを眺むる瞳認めはされずとも風の言伝は決して忘れず耳に冴かに並木の音、境内はがらんと広くぽつり寂しい中にも子ども等の遊ぶ声はよく吸われつゝも響く不思議な静けさはなつかしい、何處で見た訳でもないだろうけど。
桜も雪と消えたのである。残された若葉の木陰色は本来陽の光と音を鳴らすももはや叶わぬ孤独の神社、神主も巫女も氏子も訪れない此処は既に廃とされた社、鳥の声も見知らぬ街から聞えて止まぬ。その街はラナンキュラスの百貨店の建つ土地だが、建物だけが在るばかりで買い物客も通行人も無く星が泣いたことすら知られない、路面電車はしゃがれてしまい空だけが凄く青い。
こうなる流れであったのだろうか、春の小川がやがて美しく凍ることは必定だのに干上がってしまうとは何と言う。水が失われるなどかつて無かった、この社だけではないのだろう、この街だけではないのだろう、あちこちで灰色の景色は失われ雨をも喜ばぬ錆色に変貌しているに違いあるまい。捨てられた大地は後死ぬこともなくたゞ眠るだけである、しかしそれには人一人犠牲にならなければ出来ない。
少女は恵まれていた。毎日三食食べられたし、衛生的にも不自由無く、誕生日は贈り物とそれらに勝る言葉を受け取り、大学校まで進学出来る頭脳も貨幣も備えており大人になっても周囲の人は優しい人ばかりであった。
けれどある時街は忘れられたのだ、少女一人をぽつんと置き去りにして。モノクロームがたちまちに錆で咽せ返るのを、彼女の瞳は見つめることしか出来なくて。うつくしいモノクロームが壊されて行く。思い出せない憶えていられないもどかしさのなかでかきむしる髪は万分の一も胸の焦燥を表せられず、乱れた千々の毛先から覗く世界は涙に濡れて霞み始めた。私は恵まれているのだから、弱音を零してはいけない、小さな心は殺さなくちゃ。
地面が隠していた大穴の上、少女は名前も無く落ちて行った。
二「忘喪の黒檀」
○○《まるまる》さん。
残念、これは名前じゃないの、だって神社の名前だから。見たこともお逢いしたこともないけれど○○さんってお呼びするだけで不思議、なんだか仲良しな隣人さんみたいになっちゃうなんて神さまなのに、神さまがおられる場所なのにね。
少女にとって境内は遊戯場であった、木々の葉摺の音に目を眠り雀の米つぶ啄む音に耳傾げてくふっと笑い、瞼の裏側北極星のしろしめす星座の無い星だけの世界は小川と流れる風のあまいに誘われてついお昼寝を。身体は休めど心は休まず意識を失わないので少女が夢から覚められない事態には到らなかった、それで良かったのだ、この子がそこまで背負う必要はありはしないものなのだから。
救いたかった助けたかった守りたかった、余る宿昔を抱えさせられた彼女はよく雨の日空が一等優しい時によく泣いた、憶えていたのだから何も忘れてはしなかったのだからとよく我が身を責めて土に伏し許しを請うた背中に雫は雪の言伝となり少女にそそぐ。一人で全部出来る道理など存せぬが、子に与えられた輝きは一人で全て成す事で、必定輝きは瞳の其と共にくすんでいった。恵まれていたのに、あんなに幸せだったのに、この手は何も成せてはいない!
根が悪徒の類であったならこうは進んでいなかったであろう、善きものに優しい力が与えられ、それは他人ではなく自分を傷付けすり減らす力と牙を剝いてまた、雪花に緋のしぼりが。優しい力など少女には不要である、彼女に欲せられるべきは悪い力怖い力で、さすれば憂き目を見ることもうんと少なく程度も軽く済んだであろうに、何故与えた。
北極星を見失ったコムパスが何処を指せと言うのだろう、地面に星が埋まっていることも無し、土が覆っていた大穴は星座の無い世界とは違ってなめらかな舌ざはりの毒がある。もういっそ浸ってしまえと不思議に自棄は起らなかったが足場も無いのに立ち続けぼうっと虚ろに佇むのみ。
三「会話の半月」
どうして廃が生まれるか御存知ですか。
アクリルガッシュの絵具は深い画用紙によく馴染む。絵筆で化粧を施される身を真摯に見つめる青年は崩れたレンガの前に立っている。人の居なくなった街で人を描いたってどうしようもないのだろう、ならば人を描くのではなくとっておきの化粧をカンバスに飾りたい、白無垢などつまらない、喪服なんて見飽いたもの、派手も地味もくだらない、分類されないうつくしさはやはり人の中には無く、花や空に宿るもの。嗚呼でも写生なんてクソくらえ。
もう誰も来ないのだから好きに描いて良かろうとレンガに腰掛けようと思っていたのに、娘が一人横たわっていた。生きているかもそうでないかも判別し難いまで固く閉じた瞳を囲う睫毛は長く憂色を帯び鼻筋は清らなれど唇は妙齢に真っ青で、蒼ざめた空の景色によく似ていた。艶失せぬ肩までよく伸びた黒髪を一房指にすくい演技じみた格好で細い毛束に口を寄せる。
「○○さん。」
告げた後には祭り、後悔だけ。娘は莟とけたる風情に瞳を開くと音も無く声も立てず顔も歪めないままにそっと静かに泣き始めたのだ。不味った、怖がらせてしまったか…?次の成り行きに備え身体を強張らせていたところ、
「如何してその呼び名を…?」
さめざめと、だが此方をぱっちりと見据えて言ったのは意外な内容であった
「貴女の名前を…知らなかったので、つい、半分はその、冗談のつもりで…」
ゆえに決まりが悪くなり歯切れ良くないも当然である。
「……名前が知りたいの?」
しばらく沈思して嫁が青年に問うも、青年は気まずく視線を逸らし首を横に振る。
「自分は…私はただ此処に腰掛けてカンバスに化粧をしてあげようと思っただけで、そしたら貴女が横たわっておられたから…」
目を合わそうとしないのは何故?
「貴方は、人ですか?」
「な、にを…?」
あゝ、
「嘘吐き。人はもう此処には来ないのですよ。来ようとしても来られないのです、この街を綺麗に忘れてしまったから。」
貴方が、うつくしかった街を滅ぼしたんだ
「出て行け、此処にお前が語るものなど一つも残っていやしない。」
娘は手近にあったレンガの破片を青年の脚に突き立てた。
「歴史が何を語るものか、捨てられた世界になど見向きもしないで」
青年の血は黒く溢れニタニタとした笑みと一緒に飛沫も痕形無く消えて行った。
「あんな憎いものが欠片なものか。」
仇敵を刺したのに涙が止まらない。
四「落魄の露草」
神社から離れたくなかった。初めてお逢いした日は雨の日、日傘も忘れてふらふらと日中散歩に出たら夕立に降られてしまいびしょ濡れになるまいと駈け込んだのはとある御神木を祀る祠の屋祢下。牡丹桜がひろがり始めた刻だったと思う、薄花桜の空はまだ黄昏を拒むかの如くしとしとと少し長いにわか雨で地を覆いその影は深く樹々の梢に水を含ませる、飲み下せず零した露は最初破片のような形で土に触れるとたちまちに若芽を白く萌えさせて空の色と雫の色を模した露草の花へ姿を動かしてはりん、りんと鈴鳴りの響き、居場所を見せねど雀が祝福のように天に囀る……決して盛況などとは言えまいが七五三など人の賑わいは並み体にあったこの杜にはその風景は珍しく、身体の冷えも忘れて敷石に座って見つめていたのを憶えている。
日々給仕を粛々と勤めていた宮司も巫女の舞いも参拝者の礼儀も失われてしまった、奪われてしまった、もうこの神社も街も建物も廃と見なされてどんどん忘れ捨てられてゆく、変えようの無い世界、取り戻しようも無い世界。歴史は刺したけれどどうせ此処だけの話、地上にはまだうようよと屯しているに違いない。私の居場所を奪ったことも許せは出来ぬが一等悔しいは殺せないこと。大好きな場所にずっと居たい、父上も母上も微笑んでゆるしてくださったのにあいつらだけは。
ずっと大切な此処に居て眠っていたいけれど此処が見知らぬ街をも守ってらしたのはほんとう。だから其処を見落とす訳にはいかない、ラナンキュラスの百貨店へ向かおうか。他人はもう誰もいない世界だけれど、だからこそこれ以上は動かない憂き目じゃなくって私が動いて少しでも良い思いをさせてあげたい。それなら今これからたくさん叶うのだから。
五「投影の豪奢」
百貨店の建物自体外側はあまり崩れていなかった。青い鴉は白亜の壁に一羽留まり、もう再生されない街並を見おろす、黒曜石に臙脂の玉をこめた瞳は一度しばたく。欠け続くアスファルト、虚ろに穴が開いたイチョウ並木はかつては電飾も纏い施されたであろう、人を失った標識は誰のために佇むのか何処も見てはいない目で。もう二度と進まない街、亡び去ることも出来ない街は崩れて壊れ続けるしかない、いなくなることが叶わないから。眠る街の中少女は足取り静かに百貨店へと辿り着き、外壁のしめやかに繁茂した蔦をちらりと仰いでから内側へと歩き始めた。
案の定中にも植物が生え所々には葡萄や林檎の果実が螢袋の花のように生っていた。
「誰にも食べられないのに如何して実を結んだの?」
熊や鹿や魚たちが人に獲られるのはその実人間たちを想うが故であり、神様は人々を生かす為に御自分をすすんで犠牲とされると聞いたことがある。けれど植物はどうだったろう、果物に意志が宿ったお伽噺は私の住む場所では聞いたことが無い。けれど植物は
「この地球で何よりも長く生きて来た。」
ねえ、その中にはあなた達の記憶からいなくなった相手なんていたのかな
葡萄はよく熟れた色をしていて艶やかだった。一粒もぎって食べた、美味しかった、種が含まれていなくて、食べやすかった。化粧品売場特有のツンと剣呑な香りももはや無く蒸発しきったのか空瓶が不躾に転がっている廊下は大理石で歩くと靴音がよく響く、コツコツ、カツカツ、叩き忘れた戸を今更必死に叩くような、それでいて遅いような歩みの音。止まったエスカレーターは草花の中に縦線をやっと認めるほどでもう回路は封じられているから焼き払ったところで動き方を忘れただろう、壊されたわけでもないのに自分から壊れてしまったのだ、誰の為にもならない事を。
青い鴉の声が聞える、上れと言っているのでしょう。もうこれ以上傷が開いてしまわぬように、縫い続けなくてはならない。
あまり此処の記憶は無い、連れられたことなどほとんど無かったからだろうけど神社がこの見知らぬ街をずっと見向いて居たのだから、何か取り戻したい記憶があるのかもしれない、ならばやはり動かなくては、それは恵まれたものの宿業だから。
階段はまだ形の名残が微かに顔を出していて、本来並ぶ筈の無いエスカレーターと隣人付き合いをしていると言うのは窘める迄もなく歪である、其処を顔色変えずに上って行く娘、その横がほは冬かと紛う。
六「蛾の末路」
少女は三日月の名を与えられた。人の世界で最も尊いとされる月は満月であり、最も忌み嫌われる月は新月。と言うのも人間は本能的に闇を暗さを恐れる、光は少しでもたくさんあふれた方が心地が良いからで。続いて半月は普通とされた、これより三日月の立ち位置はどのようなものであったか推測は容易であろう。
皆が出来ることが出来なかった。人の出来ない所業をしたら不気味とされて凶兆の子だと定義されてしまった。家族からも友人からも少しずつ離れて浮いて行く、それでも自分と関わる人々は私を置きざりにしようとせず、なんとか私の手を握り続けていてくれたこと、素直に涙が出るほど嬉しかった。神社の傍から離れたくないからいつも参拝時間を過ぎて部外者がいなくなってから遊びまわった、父の微笑み母の微笑み兄の微笑み、私はなんて幸せなのだろう…
三日月は半月より劣れども、力を全く持たない新月よりは役となろう、つまりまあ、都合が良い人間だった、自壊する世界に置いていくには。
――ふざけるな
廃に指定されたからと吐して全く忘れ去ったのは人間達の癖に、変わらない、いつものこと、それでも私はきさま達を許さない。あんなに過ごしておきながら、あんなに笑って過ごしていながら、すっかり忘れられるだなんて、怒りも上回る哀れな欺瞞だ、何処に向かったって過ごした土地は附いて廻る、せめて悼みでもしてくれたならしてくれまいか、「その価値も無い」と捨てられる場所ではなかったことを想い出して、憶えているはずでしょうなどと信じた時もありましたね。
ねえ、私を犠牲だと思いますか?
七「上階の売れ残り」
本は腐らないから百貨店に陳列させられているだけだ、とこれも誰かから聞いた気がする。確かにこの世界で最も早く消えやすいのが本であるのは間違いなく、どうやらこの街の住民は本の存在を贅沢品と見なしていたらしい、事実本屋に併設されているカフェーは輪郭をまだ失くしていないが本棚の中身はすうすうと寝息を立てているものばかり、やがてカフェーも眠るだろうがそれはこのフロアでも後ろの方の順番となるに違いない。
少し前、この街が歴史により廃とされたばかりの時は本が最初に形を壊している景色に泣き狂い怒り狂い叫び続けたことであろう、私はなんて素直で純粋なこったろうと苦笑する、もう見慣れてしまった光景は私にニタリと微笑みを残すだけ、口が小さくて良かったな、人並みだったらばチェシャ猫も引く程の笑顔になっていたでしょうに。
「この子がいつも笑っていられますように」
お母さま、私はきちんと笑えていますよ。
忘れられた街に生きた人達は、すっかり街を忘れるか、街を忘れないと決めたままこうやって眠りの中に生き続けるかの二択を与えられている。けれど生き続けることは私しか選べなかった。忘れる方が幸せだと他は考えてしまったのだ。
「私もそうすれば良かった」
そんな訳があるものか。何度も自分に言い聞かせた、私は恵まれていたのだから、いるのだから成さねばならない、それがきっと私の変えられない星なのだからと。
…でも今私には星が一つも見えないの、どうするのが正解なのか分らない。いつも神社の境内の木の下で座ればまた目は開いたのに大好きだった景色は戻らない、翡翠の花束は黙ったまま、私は憶えているのに壊れ続けている、やがて大嫌いな錆色になってしまうの?あちら側ではこちら側のことを忘れて過ごして楽しそうにしていると言うのに、こちら側は楽しくもないのに私は毎日笑っています、ねえ。
「おまえも笑う者か?」
建物の中で頭上から声がする、身構えて仰ぐと、鴉。
「羽が青い……私を呼んでいたのは貴方?」
ほんのりと夜空を灯らせたような羽の色は目に新しくも百貨店の白亜の壁に留まっていたので既視感が混ざり馴染む。
「そうだよ三日月、君を呼んでいたんだ、寂しくてね。」
「その名前では呼ばないでくださいますか。」
「けれど君の貰った最初のお守りだろう?大切にして隠すのなら良いけれど捨てるのだけは良くないぜ。」
「その名はたゞ都合が良かった。都合の良いものに与えられる呼名ですよ、貴方は御存知ないでしょう満月の位に在する方ですから。」
「おや、それも?」
「えゝ、青い鴉は満月の使い魔です、この子を通じて貴方のお声を相手に直に届けることが出来る、そうでしょう?」
「満点さ三日月、では私と話をしないかい?」
「いえ結構です、私は神社に帰ります。」
「え、え、あー……」
「失礼いたします満月様。」
肩より下のなめらかな直毛の髪は
「ま、え、ちょっ……な、なぜ私が此処に居るか聞きたくないかい?」
おそらく満月であろう者の声には止まらず淡々と
「貴方がたほどの力があればお暇な時間にお歩行されることも出来ましょう。」
「暇⁉え待って君の俺らへの認識歪んでないか?」
迷わずエスカレーターに上がり一階正面玄関目指して歩く。
「あっ!エスカレーターで歩いちゃ駄目なんだぞー!さあ止まって少し俺…私とお話いたしましょうレディ。」
「この世界と眠るのは私の役目、私は壊れ続けるこの街を守らなくてはならない力を持った者なのです。ゆえに、」
足早はようやく立ち止まり、怒りに風を纏わせてふわり髪と服の裾は首をもたげずっと隠されていた白銀の錫杖が感情と共に露わになる。其は右手にしっかりと白魚の五指に搖るぎなく従い握られていた。
「お帰りください。もう二度と来ないで。」
これが売残りの階の気迫かよ。ここまで力隠してたのは完全に計算外だが今の烈火のような燃える氷柱の感情なら隙を突けるか。
「その神社のことだ。新月博覧会を知らないか?」
八「新月博覧会」
青鴉は羽を一、二度羽ばたかせ「新月博覧会」なるものについて話し始めた。それは廃とされた街に残った新月を見世棚に載せようと言うもので、考案したのは此方から彼方に向かったかつての住民であったと聞いた時娘は錫杖握る白い手に細くも鮮烈な青い血管を浮びたたせた。新月は前述した通り位の低い出来損いと呼ばれた存在達で、それは街がこうなる前三日月が助けられなかった者達でもあったのだが。彼等彼女等は無力だからといつも理由も無く虐げられ勝手気ままに好き放題され傷付けられれば見向きもされぬ、しかし新月達はその遺体腐ることなく、まして死の概念も持っていなかったので翡翠の花が眠っているようにしか見えない為に半月の住民達によく高値で寝姿を取り引きされていた。
その事実を少女は街が廃にされた後歴史を刺した時に知ったのである。
「守ってやる必要なんかこの街には無かったんです、こんな街廃とされて当然ですもの。私は何も知らなかった、知らなかったから悲しんだし怒りもした、けれど憎しみは人に向けるべきでしょう?街を憎まず人を憎む、私の大好きだった景色に罪は無いのです。悪いのは、全部、それなのに私は」
鴉の羽が雨を避け少女はまた濡れることはなかったけれど頬の雨は空からではない。
「どうでもいい、どうでもいい、そう言って来たのに何を今更。」
新月達に眠りすら許さないの人間の分際で。
「嫌だ、渡さない。半月どもに翡翠の花束を与れてなんかやるものか。神社に生まれたのは新月のためだったものなのに。私の夢を、北極星を奪うなんて許さない。」
わあわあと泣く娘は今や自分の無力な両手すらも憎んでしまうであろう、大切な想い出を攫われるのは我慢がならない。
「まだ神社には誰も来ていない。新月達の想い出を守るなら今動くんだ。私も加勢に向かっているところだから。」
青鴉の玉の瞳は沈着に、だが果敢に燃えている、まるで主の意志を示すかのようで深い忠義の相棒そのもの、その姿に照らされてか、涙にやや蒼ざめた頬は微熱を戻しつつあった。
「帰ります、直ぐに。私が守らなくてはいけない場所に。」
「その意気だ三日月。」
「はい。」
もう今その名は重荷ではなくただ誇らしかった。
九「輪廻のひとりむし」
何回この街に生まれて来ただろう。生まれる度に親は無く兄弟も無く、ただ一人で生まれて育って、前の人生の記憶を取り戻して、神社の年経る樹の枝に座って遊ぶ新月の子達を見守って、半月達がいじめに来たらその不埒な手を燃やしてやって追い出した。それでも新月達は神社を一歩でも離れた瞬間酷い目に遭っては幾人も美しい花と化したまま連れられて行った。悔しい、悔しい、あの子達が何をしたと言うのだろう、いっそのこと半月どもを全員始末してやろうと考えた時一人の新月にこう言われた。
「ありがとう三日月様。僕達のために一生懸命生きてくださって、気に掛けてくださって。でも僕等は大丈夫です死ぬことはありませんから。それに、僕等のために貴女が手を血で汚すことなどなさらないで。それは、とても哀しいことだから。」
新月は皆よく似た気質の持ち主であったから、根底はとてもおひとよしなのだろう、私は彼の言葉を彼個人のものではなく新月達の総意と汲み取った、その日から私は半月を傷付けて守るのではなく誰も傷付けずに守護する方法に切り替えた。
世界からいじめが無くならないように、半月が新月を損うのは或種の法則だと街が廃になるまでは信じていた、時が経てば僅かながら不遇な扱いを受ける者は減って行きやがては半月は新月を餌にすることは無くなるだろうと、だから私は何度も何度もこの街におりたのだ。
――嗚呼馬鹿だった。
私の信念も祈りも歴史の血に殺された。災禍を拭うには水ではなく災禍の炎が必要だった。川の守護などどうでもいい、新月博覧会?笑わせる、飛んで火に入ったところで骨一つも残してなどやるものか。
十「似姿」
神社の石燈籠の傍に座り満月を待つ三日月は少し眠っていたようだった。青鴉は燈籠に留まり主の迎えを今かと待つ。満月の存在を聞いてこそいたけれど実際そう呼ばれる方々を見たことも無いし伝聞の内容は多種入り混じり皆が皆好きな空想を広げ談話するための存在みたく扱われていた。
「君が三日月?」
頭上から青鴉と同じ声がした。思わずパッと顔を上げると、其処には身体は人間、頭部は菖蒲で出来ている者が真っ直ぐに立って居た。三日月は何と言えば良いか分からなくて黙る。
「……」
「……」
先に沈黙を終わらせたのは満月からで、これは桧扇菖蒲と言って菖蒲によく似た植物なのだと嬉々として語られたが、何処が嬉しいポイントなのかもよく分からず様子を伺う。けれど満月は容赦無く、
「君はアナベルだよね?」
「……はい。」
仮にも初対面で、もっと厳かな言葉で語りかけられるだろうと秘かに期待していたのに、あの青鴉を通した口調は私への緊張を解くためかと、さすがは満月さまがたは慈恵にあふれておられるとまで想ったのに、なんて思い違いだったろう失礼にも程度があるでしょう流石に。
「あの…私の片目のことは」
「うんうん、とても上手に隠せているけれど、やはり隠さない方が俺……私は好みかな。せっかくよく似合うのに瞳で隠してしまうのは勿体無い。」
「…はあ。」
三日月は生れた時から瞳を片方アナベルの花で一輪覆われていた。半月から身を守るために隠していたので暴露はすまいと高を括っていたのが裏目に出たようだ。
「満月さまには隠し事は出来ません、か。」
「うん。全部分かっちゃう目なんだ。」
目…具体的にはどの位置ですかと聞きそうになり堪えたのも見通しだったか所謂耳の位置を指差されたが左右で高さが違っている。あゝ、隠し事をするのも馬鹿馬鹿しくなってきた。
「ふくろうの耳じゃないんですから。」
十一「なつかしい声」
満月と呼ばれるのは苦手だから名前で呼んでほしいと(また)一方的に言われたので彼のことは桧扇と呼ぶことにした、三日月は結果アナベルと呼ばれるようになった。
「私のことは個の名前で呼んでいただかなくとも、三日月とお呼びください。」
「いや。」
その一言だけだった。何処を眺めているか予測も出来ない顔面をひらひらさせながら、口も無いのに如何やって喋るのだろうと素直に彼女は疑問と感じたがこれも見えているのだろうと思い直しその素直を消した。
「その巫戯化た博覧会、いつ起こるんです?」
誰にも拝まれない神社は黙って居た。
「それがそんなに早くないらしい。向こう側の時間では一ト月後だと言うから、此方側では一年くらいか。」
此処は何年人を失ったであったろう。
「一年あれば対策は立てられますよね。そもそもあちら側に移った住民達がどうやって此方に乗り込む心算なんです?」
「質問はもっと持っているだろうに、アナベルは隠し事が上手いね。君言葉で全部示したがらないタイプだろう?」
「桧扇様。」
声らしい声なんてずっと聞いていなかった筈だから、
「様付けなんてよしなさいアナベルや…私はもっと汝と」
「その仰々しい話し方も無理なさらなくて結構ですよ。慣れていないの明らかですから。」
「……」
「私は貴方様のこと呼びたいように呼んでいるだけなのですから、好きに言わせていただきますよ。」
「うん……君はやっぱり素直な方がよく似合うよ。」
きっと沁みていることだろう
「…正直になったところで私の中には悪なる思いが存在するだけなのです。私はこの街の守り手、そんな感情は相応しくありません。」
だからと言って君は悪人のふりをするのかい?桧扇の瞳ない瞳は境内に咲きこぼれんばかりの翡翠の宝玉達を見た。誰も苦悶の表情を浮べていないのは一目で分かる、それは君が新月らの想い出を見つめて聞いて語り続けて来たからだ、たとえ最後の一人になっても君は止めなかった、そうでしょう?
全てを知り全てを聞く代わりに我々は行動をほぼ失った、そしてそれ故に人に無関心になる同胞も少なからずいた。私はどう立ち振るまうべきか分らずぼうとつっ立っていただけだったが、もう今はそうじゃない。
「そうか…でも一つ忘れないように。俺は全部分かっちゃう目なんだからな隠し事も本音も聞こえている、それを踏まえてこれからの方針を決めて行こうか。」
「それで、人々の侵入の方法なのですが。」
「……もしかして君自分より上位の存在にはめちゃくちゃ厳しいタイプ?」
「はて?」
なんでそんな時だけ素直なんだよ。
十二「侵入の理由」
何故、どうして、と問うたところで変わりは無い、そう「理由など無い」が理由だから。理由も無く傷付けられ捨てられ嬲られる、新月とはそういう存在だった。それを救うためにこの世界が遣わしたのがアナベルという三日月であり新月を守ることが彼女自身の使命であったのに、使命を全うする力はあっても力に耐えられる身体ではなかった。その傷口を少しでも楽にするための言わば麻酔が片目に咲く花、月白のアナベル一輪であり、疼き痛み止まぬ静かな嵐の日に何度この花に自決を諦めさせてもらったことだろう。
「もう嫌だ!何度守っても何度救っても新月達が失われて行く!私がやらなきゃいけないのに、私が救わなくちゃならないのに!どうして与えられた力に私の身体は耐えられないの?」
半月の仕返しで裂けた額から赤く血はたらたら流れ滴った土から涙に濡れた若芽がいくつもいくつも緑に燃えた、芽はすぐに莟を輝かせまた花を開かせる、摘み取られるを望むかのような静かな口づけはアナベルの涙と血を拭いそして代わりに枯れて死んだ、だから終わらせる訳出来ないのだ、もう花の死体を何回見た?
「アナベル起きて。」
水が雪を溶かしながらも深く沁みゆく声で少女は目を覚ました、もう境内は夜である。忘れられた世界でも時間はかれらを忘れないので重力に無視されようが動力に絶縁されようが時間はきちんと流れ続ける二十四時間過不足無く。
「星座が綺麗だよ。」
「綺麗に見えますか、桧扇様には。」
星座は醜いものである。その実は嫉妬、嘆き、怒り、蔑みの言葉で溢れたドロドロを無理矢理星の箱に押し込めた。紐解いてはいけない触れてはいけない恐ろしい箱、それが漂う夜空は如何に毒に満たされて恍惚としていることだろう。
「俺は星座が好きだよ。例え褒められない物語だとしてもその物語を忘れてほしくなかったんだ。夜空を一人で眺める人がその美しさ、面白さ滑稽さ哀れさに触れて少しでも心癒されますようにと願いを込めて星座は織りなされていったんだよ。」
「…うつくしいものに、勝手に意味を与えて、心の慰めに?」
「尊いとされるものには近寄りがたいけれど、それが自分達に似た物語を持っていたら親しみやすいだろ?」
「それではうつくしく尊い意味が無くなるではありませんか、俗世に塗れさせるなど失礼極まりありませんよ。」
「うん、でも、さ。寂しがりやだったらどうする?」
「人が、ですか?」
「いいや、そのうつくしいもの、がさ。此処で言うと星のことになるけれど。」
「……そんな訳、無いでしょう。」
睨むのか気まずいのかをあやふやにするアナベルの片目に桧扇は何を思ったろう。
「ごめんよ話を随分と逸らしてしまったな、すまない。先刻言っていた人々の侵入方法だが、この街を思い出すことらしい。何を言っても君の逆鱗に触れてしまうだろうからあちら側の算段全て話してしまうよ。」
一つ、新月博覧会はあちら側の人間がこちら側に侵入して来ない限り開催はされないこと。
二つ、街への侵入方法は彼等がこの街の存在を思い出すこと。
三つ、新月達はこの展示会をきっと受け入れてしまうであろうこと。
四つ、博覧会を阻止するためにはあちら側の存在にこの街を完全に忘れてもらうしかないこと。(けれどあちら側にその意思はなさそうで。)
「博覧会をする理由は、やはり特に無いのですか?」
いつだって半月は意味も無く暴威を奮っていたから
「そうじゃない。懐かしみたくなったからだと思う。これは俺でも流石に断定出来なくてね、半月達の行為はよく理解も推測も及ばないからこうだろうと思うだけだけど。」
いつもどおりだと考えていたのに
「懐かしみたい?それっ……て…」
「その推理は正しいだろう、彼等はかつての悪逆を善い行いだったと正当化したいのさ。」
そちらが思い出したいと望むならその希求を踏みにじってやろう。渡すものか、二度と触れさせてなどやるものか、お前達が此処で生きていた証など残らず壊し尽くして薙ぎ払ってやるから今に見ていろ、侵入するのは此方のほうだ。
十三「星座の裏側」
夜空の下恋人達はキスをしていた。冬は人恋しと言い訳しやすい季節らしく事細かに複数人が集える日付が多い、あの子とあの子の誕生日、その子とどの子の誕生日?誕生日誕生日誕生日、そしてようやく一年が終わる。
「今年も色々あったけど良い一年だったね」
彼方側の世界の住民達のなんと呑気なこと、それと羨ましいこと、
「冬は星が綺麗だね、夜空が綺麗だね」
憤りに震えて笑っている少女が居ることも知らないで
「温かいものが嬉しいよね」
まあなんと穏やかなこと、何の上に乗っかってるかも憶えていないで。
「この穏やかさを此方にそのまま持って来ることは出来ないけれど。」
呟いた満月の声も夢中な恋人達の前では冴えたそよ風としか映らないだろう。前世というものではないが、此方側での記憶を忘れてしまうとは不幸なようで幸福ではあるがその罪は仇気無いと表するにはおぞましさが足りていない、身震いするほど残虐な新月への行為をすっかり忘れていながら満月を喜び日蝕に歓喜しそれを指輪だなどと見立て死を弄ぶ言葉づかい、その観念。このままではアナベル一人にとんでもない悲劇を起こさせてしまう、どうかそれだけは止めないと、三日月はずっと微笑みを忘れられない姿になってしまうから
「半月は愚かで惨いけれど、それだけじゃないんだよ美しいアナベル。」
君の失くしたもの取り戻そう。
十四「花束」
「スイーツを買いに行こう。」
「はい?」
聞き返すアナベルに桧扇は嬉しそう。
「敵を知るには敵と実際関わってみると良いんだよ。」
「もう半月の威力や弱点は分かりきっていますよ。」
「それはデータ、データもまあ少しは?極々少量は役に立つけど?データと知ることは似ているようで遠いものさ。」
「つまり今の私は敵の内情を碌に把握出来ていない盆暗だからあちら側に一緒に行けと仰有るのですね。」
「だって俺一人じゃ寂しいもの。」
「まさか、そのお顔で行かれるのですか。」
本当に嘘を言うのが上手だね、本心を聞き出さないと答えない。
「君を役立たずと思って誘うんじゃないよアナベル、あちら側を知ってほしいからなんだ。」
少女にしては傷だらけな両手を両手で覆い包み、桧扇は腰をかがめて瞳の位置を合わせようとするが、思わず少しだけ彼女よりも低くなってしまった。
「どうして半月達があちら側を望んだのか、向こうに行けばきっと分かるよ。」
菖蒲の似姿が自分の片目に映る。片方だけの湖の中におられるお姿は優しくやわらかくそれと一緒に懐かしかった。硝子のような湖面が搖れる。春のそよ風に背中を押されて桜の命を愛おしむようにゆらりたゆたう水はかなしくなるほど澄んで碧くて少し怖い。
「桧扇さま。」
この子は今自分が静かに泣いていること分からないんだろうな。
「何?」
「私も新月にこうやって触れれば良かったのでしょうか。
ひっくひっくとしゃくり上げる三日月を満月は抱きしめた。身に沁む体温あふれる雫、抑えた声ももどかしい。
「いつもそう。自分に必死であの子達と話すことも気がつかなかったの。ただの一度も新月を抱きしめたこと無かった、わたし、私はあの子を守ってあげられなかったの、救ってあげられなかったの。」
そんなことあるものか
「君は新月のこと一人だって蔑ろにしなかった。いつも自分より新月のことばかり想っていたんだろう?自分には大切な記憶が無いからって、新月達の想い出を毎日漏らさず読んで語っていたんだろう?」
「そんなの、当り前のことで、私は恵まれていたから、だから、私がやらないと」
あゝ――本当に嘘つき。誰か助けてって、私を助けてって言いたくなかったんだ。
「アナベル、アナベル。――俺達二人で街へ行こう、あちら側、人々の世界へ。もしかしたらこの眠りを起こす手段が見つかるかもしれない、博覧会なんてさせないんだ。俺と、君とで無垢の花束達を守るんだ、守れるんだよ。」
「――桧扇。」
「うん。」
ずっとそう呼んでほしかったんだ。
十五「奪い手」
道端に石ころが落ちていたらどうする?しかも丁度自分の足先が向く位置に。憐憫も不快も嘲笑も怒りも無く蹴ってしまうことはないか?それが新月の存在価値だ、あれらに感情を特別抱くことはない。ただ愛玩や鑑賞の道具にはなるというだけで、憎いから、嫌だから、悲しいから、蹴飛ばすのに理由は持たない、強いて言うならなんとなくだ。
「流石に利いたな…まさかレンガで刺して来るとはとんだお転婆だ。」
歴史の青年は黒く濁る靄で覆われた傷痕をにまにま眺めながら口端の血を袖で拭った。片割れはもうじき此方側にやって来るだろう、博覧会など我ながら下らない妙案だと思う。何もかもが気に喰わないって顔をしているあの子、どうやってもっと歪めてあげられるだろうな。
歴史に見捨てられた存在が歴史の手の上で転がって傷付いてやっぱり望みを絶たれる姿、さぞ見物だろう。あんまり可愛いと新月達みたいに商品に出来ちゃうかもな、手元に置いて眺めていたいけれど
「こっちだって人を守んなきゃいけないからね。」
飛沫で汚れたシャツをふっと吹きかけて埃を払いのけ青年は手近の枝に掛かっていた風船をその爪で割ってみせた、風船を取り戻せなかったのはあちらの記憶を失くした男の子。
「坊や、風船なんかよりもっとおもしろいこと教えてあげよう。」
きょとんとした顔に行き場の無い両手、玩具をまた手に出来ると思い込んだ宙ぶらりんな両手が幼くほほえましい。
ねえ片割れ、君の世界にも人はいたんだ。だからきちんと歴史にしてあげる。忘れさせたりなんかさせないから。
十六「序」
百貨店は混んでいた。人の笑顔、そこから発せられる声、仕草、結果、また声、嬉しそうな後ろ姿。特段店の儲けになるような商品を買って行ったわけでもなく、売り手は終始にこにこと本当に嬉しそうだ。
「何でああも笑っているのかな。」
桧扇はアナベルを嬉しそうに見つめ、問いに返した。
「人は他人の感情に自分の感情を見出すからだよ。」
「他人が嬉しいから自分も嬉しい?」
「そう。他人が悲しいから自分も悲しいようにね。」
――三日月様。
――三日月様、ありがとう、三日月様。
――どうか笑っていてください、貴女が哀しいと私達も哀しくなるのです。
桧扇の言葉に嘘は無いけれど、微笑む新月達の穏やかな顔は私には苦しかった。どんな目に遭わされても半月を憎まない清廉さが胸を締めつけ、その瞳を容赦無くえぐろうとする世界が今でも憎い、彼等彼女等は私に微笑んでいてほしかったのだろう心から、哀切は淡く燃え続ける水色の螢になって躑躅になって硝子の花になって今少しずつほどけ始めたようだ、大丈夫、今度こそ守るからね、そしたら一緒にいられるから。
「桧扇。」
緊張しているのに先に行きたがる彼の手を握る。
「一人の、新月の話を聞いてくれる?」
「…勿論。少し、お茶にしようか、喫茶店で。」
ティーカップは白くよく冷えていた。それでも温かい珈琲は湯気を宙に伸ばして静かに静かに悶えている、届かない、届かないとでも言いたげに。
「パンジーの花が咲いていた。まだ街が廃にされる前のことで、神社には宮司も巫女もお参りの人達もたくさん居たの。寄進だと言ってよく樹の根元に鉢植えの花を贈ってくれたわ、その中にパンジーが、胡蝶すみれがあったのよ。」
――名前を付けてあげたらどうです?三日月様。
――私、そういうのは不得手だから。それに胡蝶すみれの別名だけでも充分に良い名前じゃない。
――でもせっかくですよ。
――うーん…それなら貴方が決めてあげたら?
――んー……じゃあ月輪。
――パンジーなのに?
――これでいいんです、三日月様。
今も理由は分からない。彼がどうしてその名をあの花に冠したのか。
まだその頃私は数えられる回数ぐらいにしか誕生を繰り返してはおらず、半月達のことも少し面倒な子供のようにしか考えていなかった。だから半月が新月に手を出した時は大粒の氷を降らせたり足首を雪で埋めたりする程度で事済んだし、新月側も小石を投げられたり小枝を投げられて出来た擦り傷は三日月の力を使わなくても消毒液とガーゼで処置は可能であったから。
――三日月様は凄いですね。なんてったって序の末裔なのですもの!
――そんなに凄くないよ。
――いえ!そんなことありませんよ、弱者を守る一族がこの世界の創始者だと神話では語られています、ゆえにかれらには序という名称が付されたのです。つまり、序とは救世主の一族、凄いことじゃないですか!
――…貴方が言うなら、別にそれでいいけれど。
本当に嬉しそうに貴方が言うから
――そんな三日月様に守ってもらえるなんて、僕は新月として生まれてよかった、僕は恵まれていますね。
――恵まれている者がこんなに傷つくらないでしょ。
新月は守られるべき存在で、他人へ喰ってかかるなど決してしなかったし、歯向かうこともしなかった、自らがどのようなことになろうとも何一つ恨みも嘆きもしなかったのでそういうものなのだと分かってはいてもそれで良いとは思えなかった。でも、――
私一人に負わせる気?
なんて、それだけは思っても言わなかった。言えばこの子達が私のために何をしでかすか予想はつくから。それに、私一人で背負う方が楽だったし。
馬鹿者だ、私はそれでも呟いてしまった、背負い続けることが出来なかった。日に日に半月勢の暴力は高まり、やがて刃物で切り付けられるのが日常とまでに悪化した、けれど彼等に目的は無い、ただ手近にあったから果物ナイフを使ったのが急激な加速の始まりであろう、こうなるともう足止めだけでは到底足りず一晩で百人分の返り血を浴びる日も増えていった。それでも新月は受け入れ続ける、どんどん傷は数えきれなくなっていく、救急箱はとっくに捨てた、消毒液やガーゼ一枚では役に立たない、なのに新月は憎まない、半月を敵と認めない、笑う血塗れが増えていく、笑う血塗れが増えていく、
?
彼が聞いていたなんて。
翌日半月から回収した凶器を炎で燃やそうと日課の仕事をしていたら
「三日月様!」
幼い女の子の悲鳴に冷汗が止まらない。嫌な予感がひしひしと身を覆う、そしてその予感を必死に縋るように否定する心、いやだ、まさか、そんな訳無い。でもこの花の片目は無情で、女の子が見たものを私にまざまざと見せてくれた。
「あ………あ…………」
間抜けな声しか出なかった。家族も友人も持たない私によく懐いていた姿が翡翠になって雑貨へと加工されていくと言うのに。
「あ……ああ………」
もっと叫ぶかと思っていた、もっと叫ぶかと思っていた。でも口から出たのは一欠片の言葉だけ。
「私の……弟………」
その日は初めて新月が花と化した日であった。
十七「表裏」
「全員燃やしてやりたかった。」
珈琲の湯気は消えていた。
「でもそうしなかったんだね。」
それでも紅茶は温かかった。
「あの子に初めて会った時、言われたから。」
僕等のために貴女が手を血で汚すことなどなさらないで
「アナベル、君は臆病なんかじゃないよ。だから自分を責めるのは止めな。」
「桧扇。」
「ほら、このマフィンケーキ?っての美味しいから、一緒に食べよ?」
「……うん。」
それはありきたりな恋人達の一風景のようで。誰が後ろで人間の守り手が冷めた両目で桧扇の額を見据えていると想像しただろう。
「おふたりさん、仲間に入れて。」
にこりと笑って声を掛けて来たのは、アナベルがレンガで刺した歴史であった。彼女は息を呑み錫杖を咄嗟に携えその喉元に差し向けたが、彼はおろか店内の者も一人として騒がない。
「何しに来た。」
「それはこっちのセリフだな。なんて、まあ、散歩ってやつ?」
「茶化すな。」
アナベルの顔は
「もう一度刺してやろうか?次は心臓を。」
白銀の獲物握る手に苛烈な血管が浮きにじむ。負けじと相手も気迫露わに、
「いいとも、先刻は化粧の邪魔をされたんだ。お前は可愛いから化粧は止めといてやろうかな、その代りコレクションになってくれたらイトシイ新月達に毎日逢えるけどな。せいぜい絵具ぶちまけられるカンバスになりやがれ。」
氷の横顔と炎の憫笑、歪んだ深い微笑みどうしが今か今かと牙を待つ。
「シロツメクサ!」
鳴り響いたは青の雷。水燃える精錬たる雷鳴の矢に互いはハッと正気づく。桧扇は言葉静かに、
「シロツメクサ、何か用事があって俺達を探していたんだろう。おまえが此処で争うことを本心としないことは分かっている、そのありきたりな虚偽はやめろ。」
「…シロツメクサ、か。個名で呼ばれたのなんざアンタが初めてだ。」
言いつつ額の黄緑鮮やかな草花で編まれた冠を露見させて、舞台じみた会釈をする。
「我が個名はシロツメクサ、そして歴史と人から呼ばれる存在だ。仲良くしようね片割れの三日月君。」
アナベルも今は錫杖を空気にしまい桧扇に肩を寄せる。
「…良いだろう。私のことは個名で呼ぶな。」
桧扇はようやく一息つき、
「さて、落ちついたところで。シロツメクサ、改めて用件を聞こうか。」
カフェの内装は一人足りとも変わっていない。談笑し続け、読書し続け、食事を続けている人々。こちらはお冷やのグラスが暴れて水が円いテーブルに零れているのに。
「こういうことさ、満月様。此方側もだいぶ侵食が進んで来ててね、正直もう諦めてるんだわ。」
アナベルは椅子に戻り咳ばらいをきちんとしてから問い始めた。
「私達があと一歩で大喧嘩始めていたかもしれないのに、何一つ悲鳴も聞こえなかった。」
「アナベル、君が零した水も店員さんには聞こえていないようだ。何故だ?クレーマーの暴走っぽいから避けられてる?」
気まずい雰囲気にシロツメクサは呵々笑いながら
「確かに鋭くてあらせられる!だが少し違います。正しくは、楽しみ以外を認識出来なくなった、です。この世界の住人達はね、楽しいと思える事だけを表に出して、その他は全部裏側に蓋して鍵して閉じたんですよ。」
桧扇が眉間に皺を寄せたのをアナベルが気遣う。
「桧扇?」
「…成る程、君は助けを求めに来たわけか。そしてそれはアナベルの生きる世界、此方側の為にもなる……抜け目無い奴って本当苦手だ。」
「でも人間らしいでしょう如何にも。」
アナベルには聞き捨てならない台詞。
「待って桧扇、何故こいつを助けなければならないの、こんな憎い奴、私の居場所を見捨てたのは歴史なのに。」
「それが問題なんだよアナベル。」
此方側の世界は“歴史に見捨てられた”という概念で今成立している、だが人々が自分達の歴史すら正しく認識出来なくなれば、歴史という概念が存在出来なくなり、歴史の裏の姿である此方側も存在出来なくなってしまう、つまり歴史と此方側は表裏一体の世界で、此方側が消滅しても歴史には何も残らないが歴史が消滅すれば此方側も消滅する、そのような不条理な因果にアナベル達は晒されている。だが
「桧扇、歴史を助けましょう。」
彼女に迷いは無かった。
「え」
「街を守るためだもの。それに、」
あゝその微笑みはやばいやつ。
「自分達が捨てられた世界に救われるなんて、最高に嫌がらせでしょう?」
紛う事無き本心だ、聞いてもないのに喋っちゃった。
「じゃ、同盟結成だな満月様。」
三種の目は誰一つとして笑っていない。
十八「スイーツ」
場所を移すは映画館、フィルムには所々縦線が走り茶色いスクリーンはちらちらと明滅しながらも演者はひたむきに涙を流して言葉を叫ぶ、音が届かないのを知りもしないで、サイレント映画の観客はアナベル、桧扇、シロツメクサしかいない、楽しみでにあと人々世間から判断された娯楽ならぬ娯楽の末路。全てのシネマが失われた訳ではないが色を手放させられた映画館は少なくない。
「せっかく来てくれたのだから、この街を案内しよう。」
喫茶店以外の場所も見ておいた方がいいんじゃないかと余計なお世話を騙る声を発する顔は嘘つきの笑顔にまぶれ片頬からは傷が生々しく垂れている。
それは、此方側から彼方側へアナベルと桧扇が渡る前、手土産に何か甘いものでも自慢してやろうと呑気にも女の子向けのカフェーへと入店した、其処は外壁から内装の壁、テーブル、チェアー、ランプ、メニュー、がピンク一色の世界であった、お客はカメラ携えた若い女の子ばかりで野郎など一人としていなかったがこのシロツメクサその場に紛れることの名人、つまりは変装の達人なので、何処に行っても自分というのを希釈出来る、だから女の子ばかりの店でもまあ大丈夫だろうと高を括っていたが。
店内に難無く入りカップマフィンケーキ一つ頼んだ。
「ドリンクはお好きなのをどうぞ。」
若いウェートレスの声にシロツメクサは本心の笑顔で会釈する。
キュートなヒールを踵もかろく鳴らして歩く、フリルは袖と裾に柔くなびき、ぽってりリップの唇はにこにこアイシャドウとよく微笑み、マスカラときめく睫毛の下の瞳はオパールのようにしとやかに輝く。
「片割れちゃんにはここまで真似出来ないだろうな。」
などと笑みのうちに呟いてアップルティーの湯気を楽しんでいたところ、注文していたブルーベリーマフィンがやって来た。いただきますとにこやかに口に含み白歯で噛んだその瞬間、片頬に外から刺されたような衝撃、頬を鋭い太い針でずぶりと貫かれ歯茎にまで凶刃を奮うような手荒く一方的な痛み、思わず押さえた掌には血が赤くべっとりと付いていた。
「これは……拒絶か?」
人の世界が歴史を拒絶するのか?まさか、と思うが傷はたらたらと滴るのは夢ではない。店内にはキャッキャと明るい声、一人も悲鳴をあげちゃいない、彼のテーブルは店の中央誰からも目に付く位置であるのに。
「これは…マズいな。」
笑えない、笑えない、歴史の作り手が歴史を否定するなんて。
「笑えない、笑えない。」
もはや呟きではない音量になり始めた彼の声は潤みを含みだんだん大きくなっていく。
「冗談やめろよ、巫戯化るなって。」
他愛の無い文句も皆聞こえている癖に甘い壁で知らんぷり。蒼ざめて震える青年はテーブルからけたたましく立ち上がりその音に驚きもしない客の間を逃げてゆく。そこから走って止まって歩いてしゃがんで蹲って、ゆっくり立ってはまた走り出す、これが廃の反動か、否この規模ならもう反動ではなく腹いせのレベルであろう、報復、復讐、空を見上げれば三日月の星がうっすらと此方に向いている。
「これが侵入か、片割れめ。」
笑いたくもないのに笑っていた。
そして今、彼は笑えているつもりなのだろう、けれどもう。
十九「戯曲」
「じゃあ終わらせる場所を探すと言うの?」
「そうだ。もう私は君と共には居られない。」
「どうして、どうしてそんな非道いこと、仰有るの。わたくし、今貴方の隣にこうして立っているじゃありませんか。」
「………」
「それだけでは、いけないの?」
「それが問題なんじゃあないか。」
「あら、どうして?」
「君は、君は…」
「わたくし、貴方の傍に居りとうございます。それだけでわたくしどんなに息が出来るか分かりませんもの。ねえ、先生、本当に貴方の隣に居る時だけですわ、我儘も何にも言いませんから、よう、後生ですからわたくしをお傍に置いてくださいな、先生。」
「君は、私と一緒には居られないんだ。私も、君とは一緒に居られないんだよ。
「先生、惚れ合った同士がそんな野暮なこと仰有るの、わたくしは貴方に惚れたのですよ、ならばどうかその責任を負って下さい。」
「馬鹿言うな!私は、君とは違って、まだ将来が、」
「未来?未来ですって?そんなもの何処に行こうがもうわたくし達に残されてはいないのです、これまでの積み重ねなど無に等しい、わたくし達二人はもう、歩むことを止められやしないのです。だって、所詮人間ですもの、諦めなきゃやっていけませんわ。」
「嫌だ!私は、私はまだ、私にはまだ!」
アナベルは最期男優が此方を見向いて硝子戸に獅噛みつく様がシロツメクサの横顔に似ているな、とだけ思った。そう、そうだ、だって所詮は戯曲なんですもの、なんて。
思ったより彼の容態は悪く、案内をすることすらままならない体だと言うのに強がって街を歩こうとするのをアナベルはどう見ていただろう、思わず桧扇は彼を止めようとしたが、一言「じゃあ映画館に連れて行ってくれないか。」そしてこの結末、呆気無くシロツメクサは横倒れ。
「よほどの致命傷だな。」
彼の片頬を手当てしながら桧扇の独り言は低い。
「どうやったって見せかけにしかならない治療でしょう?」
アナベルは仇敵に容赦をしない。
「でもこのまま放っておくわけにもいかない。」
そして桧扇の横顔はおとなしい。
「映画館に連れて来させたのは何のため?」
溜息一つ、諦めて彼女は問う。
「此処に来たらこの世界のことを様々知られる気がしたのだけれど…」
結果は苦笑いで想像はつく。
「分かったわよ充分に。人間は自分達の積み上げてきたものでさえその気になれば簡単に見捨てることが出来ることがね。」
……やっぱり助けることは叶わないのだろうか、何回も何回も助けたくて生まれてきたのに。
「違うよアナベル。」
桧扇、どうして貴方はそんなに優しいの
「人間は理由も好きなんだ、それがあると安心する。だから理由を探そう。どうして歴史を捨ててまで自分達を正当化したいのか、其処に新月博覧会を止める方法があるかもしれない。」
まるで
「シロツメクサが倒れたのなら、もう博覧会は出来ないんじゃないの?」
「違うと思う。こいつは人の営みに干渉することは出来ない筈だ。」
「でも黒幕ぶって」
「そのフリをしていただけさ。博覧会は人間達が開くんだ。」
私が救えなかった
「だから街を歩いてみよう。シロツメクサに手当ては施したからしばらく彼だけにしていても問題無いよ。それに、スイーツもまだ買ってないだろう?」
私だけが弟と思っていたあの子みたいに
「ね?」
穏やかすぎて、少し怖い。
二十「星と夜」
光はとんと置いて行かれて寝静まった街の夜、月の愛を一心に受けた娘と月の化身は指先でキスをする。ふるえる女の頬は牡丹も恥じらふ淡紅沁みて星の名残の涙一筋、真珠の肌に沈黙を。温もりはやがて手首へ伝わり苛烈な血管の白い激昂をも撫で覆う、心臓隠す胸はあふれ深い息を思い出した肺から零れる吐息は白く輪郭を失くして人の世界の空気と混ざり、やがて見分けがつかなくなる。
ある筈の無い父や母の記憶、それは新月の誰かが願った記憶。小さな幸せを祈る灯が土に芽吹いて花を燃やして一個の硝子の花と咲く、それが一つまた一つと重なりあって音を奏でて静かな静かな和音を醸す、その譜が星座の糸である。三日月が大切に咲かせた翡翠の花々は人の世に於いて紫となり青となり橙となりそして交ざりまた色を生む。哀しみのパレットに雫する色彩はどれも皆額縁の中ありきたりなされど美しい牧歌の風景画を望む破片、誰かを想い誰かに想われていた筈の遠いささやかな夢の内。星座に夜空は優しくて、夜空に星座はなつかしい。
銀の錫杖はようやく穂先を想い出した。
「何がそんなに悲しかったんだろう。」
咲いた星々を見上げながらアナベルの声は穏やかに
「半月のしたことは許せない。けれど、人は何が悲しくて自分達の歴史を殺そうとするんだろう。博覧会なんか、開きたがってまで。」
桧扇へ聞いてまた彼も穏やかに尋ねる。
「どうして悲しいからって思うの?」
涙を流しながら振り向いた。
「こんなに哀しい夜空、此方側でも、廃になった街でも見たことないもの。」
止まらない、止まらない
「アナベル…」
「私は知らない、人の世界がこんなに悲しいものだなんて。皆笑ってたでしょう?楽しそうだったでしょう?嬉しくて、幸せそうな顔をしていたじゃない。それなのに、どうして、」
分からない。略奪者の強権さえも行使したがらないなんて。
「アナベル、見てごらん。」
桧扇が手に載せたのは二つに割ったアップルパイ。
「冬は、温かいものが嬉しいんだって。」
だからどうか笑って、大切な君。
二十一
我々は深い罪を背負う者、どうか誰か許し給え。知ってて罪を犯す者、知らずに罪を犯す者、犯した罪を背負う罪、我らは等しく逃げられぬ、生きていても死んでいようと枷は足首に喰い込み鉄の痕は忘れられぬ。誰か、誰か救い給え。
二十二「譫言」
それは、奪うためのものであった。小さなものを守るための奪い。言い訳は多い方が良い、理由もたくさんあって良い、その為に紡がれた、だから人は許しを請うことが本能的に組み込まれており活動の中心となっている、人々は許しを得たいが為に文化を発展させて来たのである。褒められない歴史とは何ぞや?褒むべき歴史とは?所詮何方も等しく同じである、まして捨てられたものとそうでないものなど尚更の事。けれど歴史の青年シロツメクサは情けも慈愛も知らぬ存在、ただ人の積み上げて来たもの、としか自身を認識出来ない存在、ために彼はアナベルの住む世界を人には不要の世界として切り離した。
「人間を守らないといけないのでね。」
その軽口は口癖となってシロツメクサに絡みつく。今の彼にはそれが成し得ないこととも知らないで、熱のうちに、譫言に。
汗ばむ額に冷たい掌をのせて、アナベルは哀れな歴史を見つめていた。その眼差しはかつて弟や救われない存在達に向けていたのとよく似たものになっていた。
「桧扇が出掛けたわ。」
意識に残らないと知っていながら彼女は続ける、これ迄向けたことのなかった表情で、憎かった相手をそっと見つめながら、それは、憂いの顔だった。雛罌粟の紅が莟に染まってピアノの糸と綿雪とともに花を開く窓辺の景色、けれど人々は半袖のまま陽気に談笑し続けている。
「もう季節も失われたのね。」
今の彼女にその光景を糾弾出来る怒りはもう無かった。一週間のうちに随分人の世は様変りした、桧扇とアナベルには特段影響は生じなかったがシロツメクサはそうでない。下がらぬ高熱に魘されるのは今の自らの少し前、もう少し前と見続けているからだろうか、まもなく捨てられる存在はその行末を知ってか知らぬか嘆きはせず笑うものなのか、熱に、未来に浮されながら。
「新月達も、そうだった。」
苦しいだろう、汗は少しも引く気配が無くて
「今の貴方みたいに、笑ってた。」
気丈なのか本性なのかごめんね、この片目は分からない。間違いなく分かったら掛ける言葉も見つかるのに。
「人は貴方を恐れている。でも何に恐れているのか見えないの。教えてほしいのに、人が貴方を捨てて何を期待したのかを、なのに……」
熱はどんどん上がり続ける。具合はずっと悪くなる。
「せめて、この熱だけでも。」
私の冷たい体温で下げてあげられたらいいのに、
そう思って額に額を触れさせた。
誰か、誰か救い給え
誰?と声を出す前に桧扇の叫ぶ声が耳に届いた。
二十三「第一:乙女椿」
「お姉さま、明日は何して遊びましょう?」
黒と銀色の混じった髪色の少女が微笑んでいる。その頬はまろくふっくりと咲く桃色椿の花びらのよう、瞳はすなおに弧を描く。
「誰…?」
「雨美。」
誰と呟いた声は自分の声だったのに、違う声がその上から被さって喋り出す。
「だめよ。今はゆっくり休んで、熱が下がったらお手玉しようね。」
声は横たわる幼い少女を前に黙るアナベルを置いて続いている、これは、誰かの追体験、誰かの記憶をアナベルが見ているのである。
雨美と呼ばれた少女とその姉はそれでもにこやかに
「家の中じゃなくってお外に行きたいわ。」
「外は今怖いから駄目よ、あぶないわ。憲兵ばかりが胡乱ついているもの、変な言いがかりをつけられでもしたら大変だもの。」
姉は妹の抱きしめていた人形をゆっくり撫でてなだめようとするも興奮は抑えられない。
「だってせっかく六つになったのに!」
「お誕生日は関係無いのよ。」
「でもおとなに近づいたねってお姉さまが、」
「はいはい其処まで。もう今日は休みなさい。」
むくれながらようやく妹は眠ったようだ。
「もう、最近は反抗期、かしら?すっかりおてんばさんになっちゃって。」
それでも姉は嬉しそうに、微笑む。
(そうか、この子は私に知っていてほしかったんだ。)
一人きりの部屋の中、妹の骸骨を撫でながら。
(雨美という女の子が生きてたことを。)
アナベルは鏡に映る頬麗しき娘を見つめた。
(でも、貴女だって生きていた。)
乙女椿の花よ散れ、再び空に溶けられるように、
「私の世界に連れて行けなくても、私がずっと憶えている。」
光は眩しく――
二十四「第二:ハッピーホリデー」
所は裏露地の長屋から変わって閑静の町、住宅が距離を保って同格に建ち並ぶ。
(嫌いな静けさだ。)
今度は誰になったのだろう、足元でも見られたらいいが
(嘘でもいいからはしゃいでいたくなるような、気味の悪いぬめった沈黙だ。)
視界まで固定され首を振るもかなわない。
(足早に歩いているようだが、こんな遅い時間何処に用がある?変に荷物も少ないし、身軽なのも気になるな。)
一つの家の前で立ち止まると、自身のポケットに手を突っ込み、細長い金属状の物を取り出し、錠前に刺し込み始める。
ピッキング。
古く憎い言葉であるがこの家の鍵には相応しかったらしく、カチャリと無情にドアが開く、声が出ない。
(空き巣か此奴は、それにしては自己顕示の欲望が強いように感じ取れる、私を投影させてまで自分の犯罪手腕を見て欲しいのか?)
嫌な予感は必ず訪れる、空き巣は空の家に土足で入ると秩序を壊すのを含み味わい感じるように次々と物品を盗み壊し踏みにじる。
(空き巣の癖に物音が大きい。でも誰も居ないようで良かった、人的被害が無くて。)
ありきたりな安堵は踏みにじられる。アナベルの下げた視線を上げると女性が蒼白に立っていた。
(そんな)
心と裏腹に空巣は楽しそうだ。パントマイム師のようにくねくねとその場で寸劇をした後取り出したのは。
(やめろ、やめろ、やめろ)
悲鳴、悲鳴、悲鳴。
(その子は何もしていないじゃないか、ああ、ああ、あああ!!)
静かになったその場所、壁のカレンダーには今日の曜日、日曜日にぐるぐると赤色で花丸、そして“ハッピーホリデー”の文字。
快楽犯はまたポケットに手を突っ込み、今度は小さな手帳を取り出して今日の日付、花丸ぐるりと記されてあった。今日が終われば来週も、来週も、そのまた来週も、ずっと書かれている休みの日の花丸花丸、アナベルは身動き取れない冷汗の過熱の中どうすれば此奴をともがいていた。
これも歴史の一部なの?雨美とお姉さんみたいに哀れな子等もいるのに、こんな、こんな堆肥にもなれない奴がいるなんて、私達の生きていた世界と変わらない。それでも同士て半月達は人の世界を選べたの?まだ分からない、それも悔しい。
「見せてよ。」
あの街を廃とした理由
「あなた達が歴史を選んだ理由を見せてよ!」
――アナベル!
懐かしい声が呼んでくれた気がしたけれど、もう遅かったみたい。
二十五「夢問答第一幕」
イルミネーション、と言うのだっけ、あの時愛おしい君を見た寝静まった街とは違うこの光。
「寂しい光。」
自分はいつも明るさに胸騒ぎを感じていた。人間は好きだ、豊かであり不作の生物、太陽を好み月を恐れる生物、そして自らの背中を見ることの叶わない生物。人々の在り方はそれとなく分かっているつもりでいた、けれど今イルミネーションを見つめていると段々分からなくなってきた。
「嘘だ。」
人間を好きな奴が光に胸騒ぎなどするのだろうか。
「人間なんて嫌いだ。」
でも人を厭う者が光を眩しいと感じるのだろうか。現に己に輝きは無い。ただ在るだけの黒い月に付された名前は新月。光を自ら発することを許されなかった者、虐げられるように設定された者。
「中途半端な光なんて嫌いだ。」
憎いと思ったっていいでしょう。この世界に嫌いなものは必ず生まれるのだから。
――起きて
誰?聞き憶えがあるけれど深い羊水の中じゃ聞こえない。
――起きて、夜だよ。
嫌だ夜は怖い。光が無いの、見えないから。
――想い出して寝静まった日のこと
想い出してもあなたは帰って来ない。命は確かに在ったのに無くされてしまったの、目を開けても暗いのは怖い。
――暗いだけじゃないよ、だから大丈夫。
あなたは夢なんでしょう、わたしに都合のいい励ます言葉、優しい夢は哀しい物、残酷な夢は嬉しい物。
わたしが間違えたのは何処からだろう。
ピースは何時からずれていた?
振りかえれば水が冷たい、吹雪が肉体を包み始める。
夢の中なのにごうごうと、ごうごうと景色が騒ぐ。
雨が白糸のプツリとほつれたように降り出してしまったから
また怖くなって地面を見た。
積み上げられた体は崩れていく、見たくないからの悲しい言葉で崩れていった。
「シロツメクサ。」
熱の引いた肌とうらはら涙は熱く火照っている。
「三日月君か…」
「夢でも見ていたの?」
「歴史が夢を見る訳無いだろう。」
少し伸びた銀の髪を大きなリボンで編みながらアナベルは少し嬉しそう。
「何笑ってんの?」
「…少し懐かしいことを想い出して。あの子もきっとそうでしょうけれど。」
喫茶店での危い火薬の邂逅と比べれば春の小川の柔和な色のこと。
「…三日月だよな?」
「貴方がそう呼びたいのならそのままで。」
「いや自分が個名で呼ぶなって言ったんじゃなかった?」
「シロツメクサの思うように。」
「はあ……」
熱が引いたのはありがたいが、凍った桜は何処へ行ったのか、先日のけはいとはまるで別の存在で。勘ぐろうと頬に手を当てた時何かが一筋刻まれていることにようやく気が付いた。撫でてみると鮮やかな茎の跡が
「泣いていたの。」
「何故だ?」
知らないそんなこと。でも理由は少し想像出来る。
「私が歴史をほんの少し知ったから。」
「どんなこと?」
起き上がった瞳はまだ充血していた。
「雨美とお姉さんのこと、週末だけの犯罪魔。」
頭が割れそう、でも笑う。貴方が決して忘れたくないと決めた者達。
「じゃあ声も聞いたんじゃない?」
「私は干渉出来なかったけれど…」
そうじゃなくてさ
「雨美達じゃなくて、その前の声。」
誰か、誰か救い給え
「あ」
そうだ、あの声は誰だっけ
「思い出せなくて当然さ、それは僕だけが持っている土台なんだから。」
「土台?」
どうして君はそうも他を許せるんだ
「歴史を積み立てる為の礎さ。許しを求めていただろう?それこそ土台なんだよ、許されたいと願うことがこの国の歴史の始まりだったんだ。」
「何故許されたいと願う必要があるの?始まりはいつも純白で木の芽がめぶく所から開くのに。」
本当に、どこまでも歴史じゃなかったんだな、片割れなのに。
「それは君の世界の話。裏側だけろ僕等の世界はもう少し気まぐれでね。君等とは始まりからして違うものなのさ。」
「桧扇、桧扇はどこ?」
急になんだ?
「違う、彼の教えてくれた歴史と違う。」
三日月の湖面が大きく搖れ、木の葉が烏の羽に呑まれていく。
「おい三日月、何がどう違うのさ、満月様は…君に何を吹き込んだ?」
硝子の割れる音、白面の貴女はほろほろと力無く泣く。その肩に、手を掛けた
「アナベル。」
一言で身が凍る。
「俺は此処だよ、アナベル。」
眠る彼女を横抱きにして、菖蒲の似姿が空気もかろくふっと微笑む。
―顔も無いのに
「世話になったねシロツメクサ。」
怖い
「アナベルに人間の歴史の話をしたのは不味かったな、彼女の世界と歴史は根本的に相容れないものでないと。」
恐い
「可愛いアナベル、優しいアナベル、貴女はもう傷付かなくていいんだよ。歴史を捨てて、全部物語になってしまえばいい、そしたらもう苦しむことも悲しむこともありませんから。」
まさかあの侵食は
「おやすみシロツメクサ。」
――三日月様。
君は
「おはようアナベル。よく眠れたかい?」
「桧扇…」
青い鴉の囀りと白い花の朝日が頬を撫でる。
「私、星を…」
「俺と見上げていた後にね、すっかり眠っちゃってたよ。今までのことを考えれば当然さ、碌に休みもしなかったろう?」
モノクロームの此方側には、葡萄がらんらんと実り続ける百貨店、そして懐かしい神社の境内。
二十六「彼女の知らないこと」
実は、此方で或種の博覧会が開催されるんだ、それは半月博覧会と言ってね、半月達への対策を立てられるようにとするものなのさ。その為には此方側で半月を準備しなくちゃいけないだろう?でも一人残らず彼方側へ移ってしまったからさ、人間達をこの世界に連れて来る他無いんだよね、シロツメクサが顔を出したのは計算外だったけれど上手に眠らすことも済んだしまあ静観していても当面構わないだろうな。
新月達は、学ばなくちゃいけない。自分達の身を守る方法を、怒る術を、反撃の手段を、そしたらこの世界はもう廃ではなくなる、そうなるのは彼方側の世界になる寸法、此方が歴史となってしまえばモノクロームも一層色めくことであろう。
「その光景が、君の瞳に映りますように。」
―三日月様。
二十七「日蝕」
白と黒のまるでオセロのような、かたりかたりと動きはすれど湖の下では騒ぎ声など知られもしない、まして歓喜の叫びなど以ての外。
誰も泳がぬ百貨店の中、アナベルは小鳥のように一粒一粒よく熟れた葡萄をついばんでいた。天井には名前を持たない星座たちが夜光虫の空と化す。春の光、夏の光、秋の光に冬の光、朝は夕暮に昼は夜空に四つの燃える白雪と二つの時間を繰り返し巻き戻しを続けては色の咲く翡翠の大樹を照らしている。もはや機能を失くした建物は植物の養分となり床となり、葉を広げ空を覆うを仰ぐばかり。
葡萄は美味い、だがそれだけ。
朝を忘れつつある世界には本の頁が小鳥の羽となってそちこちに飛んでいる、それは目的の無いはぐれ旅ではなく逢う者の決まっている路ある旅。肩に留まった目の無い一羽の嘴に指先を、驚かさぬように努めて無垢に添えてみると、小鳥はキョトキョト首を横に二、三振り蔦に愛された額縁の絵の中へと去って行った。
また一匹、今度は耳の無い一羽の嘴が唄っている、唄っていることは感じるけれどもその声が誰のものだったか思い出せないから、また一粒葡萄を齧る。
「アナベル。」
この声だけは憶えている。
「桧扇。」
顔も向けずに名前を呼ぶ、それでも彼は微笑み緩く息を零す。
「また此処に来ていたの?」
春の小川の流れる音、かつて階段だった水面は物言わぬ鏡の姿をしていた。
「此処に居なきゃいけない気がして。」
アナベルの視線の先には苔の壁面がある。
「君の好きにしたらいいよ。」
それはもう許されたことだから。壁がレンガ造りであったことを彼女は知らない。
二十八「三ツ葉の抵抗」
それは、どこにでもある葉っぱ。幸せのお守りにはなれなかった運命を待つものは何一つありはしない。感情を与えられなかった多数の内の一枚はあと枯れる日が訪れることを待つ身であった。他者への言葉を奪われた三ツ葉は、まっさらの頭の景色が夕暮に色づき始めたことで時間を思い出した、今は朝。心は夕辺を彷徨うも、陽の光に目は痛む。
遠い凪の音、都鳥。雪を厭わぬ憎き裏側を想えでもこの身に羽は認められないものなのだ。せめて、どうにか言伝をと願ってもあの子がこの願いを聞き入れるとは信じ難く。けれど、大樹の下に小さな草木は宿するもの、雑草をなめていては足を絡めとられて吸われてしまうものなのだ。
二十九「国土」
どの国にだって、忘れてしまえたら、と考えたくなる歴史はあるもの、しかもそれによって発展が進められたとなったら尚更陽光だけ浴びていたいと思うのだろう、思いはやがて願いになり、祈りに変貌し、結局は物差しの一つと成り果てる。そして尺度で測定されて廃棄されたものは見えない国土となり積まれてゆくのを恐らく人は知らないままでいる。知ることを悪とした世界、それがあの日の喫茶店で見た人間の世界の結末の一つ前、そして今、人間の住んでいた世界は裏返り、廃となった筈の三日月の世界が歴史となって大きな樹を茂らせていた。つまり、此方側とあちら側の理が逆転して回り始めているのである。廃とされた人間世界は表となった歴史の世界の土壌となり、人間は次々に半月へと戻り始めたが養分に口無し、皆寝息も立てずに眠っている。
「三日月様。」
懐かしい境内。モノクロームの世界で少しずつ色を取り戻していく光景は、夢見て来たことだった。新月達が玉の眠りから覚めて好きなように遊んでいる眺めも。
「おはようビオラ。今日は何をするの?」
「はい!今日は廃の世界で博覧会を見て来ます!三日月様もいかがです?私はスズランと一緒に行きますが、どうぞご一緒に!」
「私は、大樹の傍に居るわ。」
「左様ですか…では行って参ります!」
ビオラとスズランが駈けて行く、守りたかった笑顔で走っている、力いっぱい、なんて幸せなことだろう、怪我も理不尽も無いこの世界。
幸せな筈なのだ
搖らぐな 搖らぐな
半月は今までの報いを受けて眠っているのだから、それに半月へ新月は暴力等を振りかざしていない、良いではないか、以前のような在り方に、否以前より遙かに良い方向へと生まれ変わったのだ、喜ばしい、喜ばしいことなんだから、ほら、喜べよ……
湖面に自分の表情を映すのが怖くなったのは何時からだったろう。百貨店の居場所も置き去りにして今ではすっかり大樹の根元、草花無数に咲く中で眠って起きて一日を過ごす、夕暮の朝、夜空の昼、夕暮の朝、夜空の昼、空には薄く濃く星座が止まない。
「なめらかな舌ざはりの毒」
昔自分が思った言葉が突いて出る。周りには新月に立ち上がれなかった植物達しかいない。
「どうして今更あんな言葉を…」
考えるのも厭わしくアナベルはまた草木に埋れて眠り始めた。
三十「彼の知らないこと」
随分悪くて長い夢を見ていたようだ、復讐の後味の不味さは慣れたくない。
花火のようだった、と思う。確かにひたむきになるだろう、懸命に懸命に練った作戦は、描いた構想は、結末の味はそれはそれは美味だった?それは全部一瞬で、自分の怒りで握りしめた掌中で潰れてしまった、後には指紋に刻まれた黒煙だけだった。
復讐さえ果たさなければ、自分は何も捨てなくてよかったのではないか、憎悪の微笑みも、想愛の涙も。哀しみを抱いていた時は重かった心が今は空気のように重さを感じとれなくなっている。
あっていいものなのかしら、哀しみとは。
きっと人の世界もこうなったのだろう、楽しみばかりを追いかけて他を捨て去り虚ろな裸体へ戻ってしまった、歴史が始まる以前の人たる前の姿に。取りかえせない選択の誤りの後、人は今度何もかも受け入れてしまうのではないかしら。表も裏も土は同じ、逃れられない。
「新月はそうして生まれたのかしら。」
人が自分達自身を毛嫌いすることで編み出してしまったその場限りの逃避方法、人間達が、半月が傷付けていたのはただの自分自身で、見たくないことを眠らせても眠らせても次々と咲いて来てしまう自分自身を、人は。
「もっと自分勝手だと思っていたのに。」
全然自分本位じゃないじゃないか。
「病んでいるのね、人という存在は。」
愛おしいと想えるだろうか、自らを憎んで憎んで自傷する命達を残らず。
「想うわよ。」
あゝ、頭の痛くない微笑みなんて数世紀ぶりなんだろう。想わずにはいられないのだ。
「私はアナベルという名の三日月だから。」
三十一「夢問答第二幕」
決断は早かった。桧扇はもう三日月様に辛い目を味わってほしくなかったから。その一心で半月に歯向かい、殴られ、呆気なく物へとされてしまったが、この一心は命が物へと転じた後も根を枯らせることは無く、今か今かと次の芽吹きの時を待ち続けていたのである。
植物は殺しても死にはしない、また生えるのを静かに待っていただけなのだ。
だから三ツ葉は大樹の根元に咲いていた。
アナベルは眠ったまま三ツ葉をそっと指で触れた、すると自分を呼ぶ小さな声が遠く聞こえてくる。
「三日月。」
「シロツメクサ?」
「今はただの三ツ葉君さ、前の名前は伏せた方が良い。」
「じゃあやっぱり桧扇が…」
「君とあちら側に向かったのも人間が狙いだったんだろう。真意を教えてくれるかどうかは分からないけどね。」
でも。星と夜のあの日、あの想いはどちらも嘘ではなかった、その証拠に今でもあの光に瞼が鮮明に焦がれている。
「人が自分を攻撃しないのは良いことだけれど」
半月博覧会は良いことの為に開かれたのではない。
「この状況は間違っている。こんな、哀しみだけが一人歩きする世界なんて。」
悩みもするのだろう、苦しみもするのだろう、でもこれは違う種類の苦悩、生きるための必要なものじゃなくて死ぬために必要な苦悩の姿、影だけが動いて身体を喰らい海に突き落としている姿。
「見たくない、そんな姿。」
勝手だと罵られても
「…新月は君のこと悪く言わないさ。」
「もっと上手な嫌われ役になりたかった。」
「誰のことも、が正しかったか。」
「だから救えない存在だったの?新月は見放されるべきだったの?」
「君は如何想うんだ?」
「私は弟を救いたかった。」
「でも彼は」
「私の弱さの為に命の価値を奪われた。」
「……そう、だったね。……」
三ツ葉の声が分からなくなる、目覚めが近い。
「あの子だけ、今の此方側には居ないの。半月を助けられたら、あの子も戻って来ると思う?」
彼女の微笑みは上がった幕で瞳しか見えなかった。
三十二「糸桜」
見開いたまま止まっている瞳は何を眺めていたのだろう。曇天に陽は射さず零れる筈だった頬の感情もショーウィンドウの内では鳴ることも叶わないで、笑う観客をただ映し続けるばかり。
半月博覧会は盛況だった、とりわけ半月講座と称される勉強会は。かつて虐げてきた者達を逆手に取れた新月達は嬉々として講義に励んでいる、それは蟻を土に埋めて特に理由も無く楽しむ幼子のように。―悪いことしたって許されるんだ。だってぼくら守られるべき子供だもん!
守られる存在の暴走は中々に厄介で面倒だし腹立たしい、けれどこれも三日月様の苦悩を無くすためと思えば苛立ちも不快も立ち消える。新月が賢くおとなしくなれば序の最後の生き残りである貴女を救ってあげられるのだ。
傲慢だと言われるかもしれない、人間の裏切りものだって言われるだろう、この身は二度と歴史の中に生きることがもう叶わないのだから。
三日月様、三日月様。僕達のためにずっと頑張ってくださっているたった一人の人、新月に光を教えてくださった奇跡の存在、新雪の大樹。どうか枯れませんように、僕達を糧にして生き永らえて夜の世界を照らし続けて。
「新月達が知識と知恵を得たら、三日月様が本当はどのような存在か理解出来る筈。そうしたら何があの方の幸せか分かるだろう。」
貴女だけに背負わせてごめんなさい、もうあんな苦しい顔させませんから、あんな辛い目に遭わせませんから。
胡蝶すみれで空を覆ってゆく、ほのかに透ける夕暮の空、それももう朝か昼か晩なのか時間の記憶も薄れつつ、太陽は光を捨ててゆく。このうつくしい街に早く戻って光の貴女、泡雪の白百合がもう一度空を想い出してくれたのなら、今これ以上の幸せは無いのです。頭を垂れて祈りましょう。
三十三「桜桃」
いつも実の生らぬ花の前に立っていた
私の愛しい命達
排除されるべきと疎まれ続けた命達
そして一人歩きしてしまった影の蔓は
陽光を恐れて我が身の花を殺してしまった
それは枯れてしまった涙のため
水を求めなくなってしまった心根のため
「もう一度、私は立たなくてはいけない。いいえ、後一度きりじゃなくて、何回も何巡も私は立たなきゃならない。」
満月に届かず半月にもなれない新月へも戻ることの出来ない一人ぼっちの三日月だから、アナベルだから果たせる使命、立ち続けて立ち続けて時の流れに刻まれながら星夜に春の雪解け水をおくり続ける、それが私の力の意味。
果実を生せない植物でも朝焼けの雫滴る若芽の果てを見たっていい。それが叶わぬ光だろうが届かぬ甘さだろうが、認められない虹だろうが構うものか、湖の下に欠ける月輪を求めて花を咲かせるものなのだ命とは。
人が歴史を選んだ理由、今は分かるかもしれない。完成された動かない時間より、惨めでも動き続けられる時間の方に人は手を伸ばすのだ、決してその世界では叶わない理想と本能的に悟りながら叶わぬ星を動かぬ星を見つめて生き迷う、そんな世界の方が人間はきっと安心するのでしょう、いくら効率が悪く愚かな選択だとしても。人は苦しみを望むのです、哀しみを、怒りを絶望を望み、それらを糧とするのを願うのです、打破する力を愛しているのです。
それが人の在り方なら、私はその在り方を愛惜しいを想います、あなた達のか弱く脆く剛健な心を愛します。だから私の今から成すことを止めないで、どうか見ていてくださいね。あなた方が私の行く末を見届けてくださったのならば、今私にこれ以上の幸せは無いのです。
三十四「宣戦布告」
「桧扇その瞳はどうしたの。」
アナベルの呟きは遠く彼の耳には入らない。顔のパーツなど何にも当てはまらなかった筈の菖蒲の花の目をおぼしき位置が少しくすんだ色模様になっていた。黄色は熱砂に魘されたように干され、本来潤みのある容赦無く言葉を放つ口は白らけていた。新月は気づいていないようだったけれど、アナベルは彼の側を元気に去りゆく新月達の列を避けながら遠くながらも声を掛けたのだ。
その声には返さずやはり新月達を次々と見送るようなその視線。
「何を見届けているの?」
昔いつも傍に居た互いは今、新月の列で遠く離れている。次から次へまた次へ新月は現れては去って行く。神社の正面境内座って此方を見つめぬ桧扇と、新月に行手を遮られて境内にまだ一歩も踏み入れられないアナベル。
(私を入れないつもり?でもそれならあちらじゃなくてこちらを囲った方が手ッ取り早い筈。何故わざわざ境内を囲うような真似を講じたの?)
それに新月が多過ぎる。一つの笑い声から一つまた一つと首を増やしているのだろう、新月一人から二、三の新月が植物のように生まれて来る。
(今此処は制圧出来ない。対私策でこうしているのなら、私はこの場を離れよう。)
「半月博覧会へ、向かわなきゃ。」
大切な境内、三日月の居場所、新月達を手当てしお互いに微笑み合った少し胸の痛む夜の記憶、翡翠の宝物、それらは全部かつて自分達が生まれる前に自分達が願った優しい記憶。けれど今は背を向けて、果たすために私は進む、もう大切な境内は失われた、半月を憎む彼等の感情によって。
「たとえ居場所を奪われたって、私は土下座なんかしてやらない。」
なつかしい境内は遠く響く、奪われた痛みも青い炎と変えて進み歩く、半月博覧会の「出品物」を救命するところから始めようか。
三十五「仲間」
シロツメクサはどうして喫茶店に来たのだろう。一度刺された決着をつけるため?否あんなに弱っている体であれば首を落とすなど造作も無いことだった、街の案内も碌に出来ない態で何故歴史が裏側の世界の住人に会いに来たのだろう。
境内を去ってまた百貨店に戻って来る、置き去りにした葡萄の生る春の湖畔にはあの時からの小鳥達が遊んでいた。
「青鴉は居なさそう。」
よかった、当分帰る場所は此処にしよう。作戦本部が組み上がったら早速戦略を考えないと。
「先ずは半月博覧会の中止。」
額縁の中の静物画からペンを走らす音がする。
「それから境内の奪還。」
打ち手のいないチェスの盤面が動く音。
「最優先事項は大きく二つね、細かい計画を考えよう。」
頁がパラパラと考えを探す音に小鳥の話が記録される、春の湖面は思考の泉をもたらす。
「半月博覧会を止めるには、正面からかちこむ方が良いかしら?いいえ駄目よ、そんなお転婆な解決法は暴威だわ。新月は博覧会に夢中だし、無理に止めたら何が起こるか今のあの子達は予想が付かない。
新月達を傷付けたくない、半月達も救いたい、どちらも二つで人間と成れるから、どちらも傷付けてはならないのだ。
「新月達は皆好んでいるのかな、半月博覧会のこと。」
人は全員が全員同じ心を持つものではない、新月も人から生まれた片割れであれば人と同じくある数の異端者は存在しているのではないかと彼女は考えたわけで。
「きっと一人はいるかもしれない、今の、この現状に疑問を抱いている子、不満のある子、心配な子達が。始めにそのような子達を見つけて話し掛けてみよう、そしたら良い案が思いつくかもしれない。」
葡萄を一つ摘んで食べたアナベルは元気よく会が催されている場所へと歩き出した。
いってらっしゃい。
三十六「頭を垂れて祈れども」
かなりバランスが均くなって来たか。前の人の世界ってのは人が半月と新月を生み出す割合が半々だったが今半月達は風前の灯火、新月勢は根を張り根を張り人がいなくても自分達を生み出せるようにまで賢くなった。
それで良い、近頃は半月への憎い、許せない、とっちめようと叫ぶ声もよく聞こえるようになって来た。俺の願いも直に手が届くだろう、今はまだ伸ばしている途中だがそれも時間の問題で。展示会の入替をそろそろ用意しなくては、同じ奴なら飽きてしまう。
すっかり反転した世界の在り方、人間界に侵入していく色づき始めたモノクロの世界、誰も彼も一刻で奴等の動作は認められずただ固まるだけの人形と化した人々、かつての半月達は意思を伝えるも許されない姿のままで硝子の檻籠に次々運ばれる。そしてそのまま天井の高く明るい館内にレイアウトされ観客にまじまじととっかえひっかえ四六時中見られ続ける、その心が何を言っているか。
「分からないよ、だってぼくら守られるべき子供だもん!」
望みを絶たれた暗い表情は眩しい光に照明されるも正反対に美しい。
「やはり人間の世界に実際訪れたのは良い策だった。“新月博覧会”なんざ開きませんよ最初から無かった展示会なのに、あんなに一生懸命に阻止しようと走り回って可哀想だけど愛らしかったな三日月様。」
歪んだ笑い声を立てる口元らしき一帯は真赤に塗れていた。
「でもシロツメクサの再登場は予想外だったな。あいつ何の為に喫茶店に現れた?あれ程不確かな存在の仕方なら街の案内なんて出来る筈も無かろうに。」
三日月様に歴史を見せたかったのか?それが狙いなら残念だ、もう彼女に歴史の記憶は無い、あの後すぐに俺が頭の中をぐちゃぐちゃにして混濁させたから、今三日月様の自我はシロツメクサに歴史の始まりを教えてもらった時のようにぐちゃぐちゃだ、そしてそのまま俺の手元で眠っている。
「要らない物は間引きしておきましょう。その方が美しい花は咲きやすくなりますから。」
かつての貴女の大樹を仰ぐ。もう此処には帰って来られませんよ、だから精精逃げ回って、どうしようもなくなって立ち止まった時、お迎えに参りますからね姉さん。
その表情は恍惚と。
三十七「夏の湖畔」
新月には最初名前は与えられなかった。考えればそうだ、人の内から生れる人ならざる黒い部分、ただ存在しているだけで忌み疎まれる人の箇所、埋めたがっても埋められない箇所。
けれど闇に光は射した。その輝きが新月という言葉だった、わたし達には眩しい名前。新月、新月とそう繰り返し呟いていた時あの方は我が事のように笑ってらした。
「大丈夫、もうあなた達には新月って言うすてきな名前があるからね、今までみたいに化物扱いはされないよ。」
そうなのです、どんなに恐ろしい存在でも名前を与えられたのなら人は少しそれへの恐怖が治まるらしいのです。だからわたし達は嬉しかった、喜んだのです、これで世界への仲間入りを踏み出せたような気がして。
けれど光は闇の醜いおぞましい姿を明らかにもするのです。人々がわたし達に名を求めたのは恐ろしいものの呼名が欲しかったのです、恐怖と軽蔑の内でも人は便宜と効率を求めるのです。
あの方はわたし達の祈りでした。あの方はわたし達を最後までかばってくださいました、ずっと味方でいるとも仰有っていただきました、人ならざるもの達にとってそれが如何な輝きであったか、大きな大きな輝きであったか。わたし達にも心はあります、心が抱く心と言うのも奇ッ怪な事象でしょうが、それは決して嘘偽りではないのですよ。ないのですが、わたし達の心はあの方と共に居るには少し燃え過ぎました。わたし達はあの方を溶かしてしまう、唯一情をくださった方をわたし達は自らの存在のために溶かしてしまったのです。あゝ、根ッからの悪とは本当に我々のことを指すのです。
その日以来わたし達は何処へも行かなくなりました、もう此方にも彼方にも進んではいけない戻ってもならないのだと戒めました、何の償いにはならないと理解しながらも。
あなたの幸せを願う身があなたを失う理由になったこと、どうかお忘れにならないで、そしてわたし達を決して許さないで。
三十八「異変」
博覧会は予想通りにぎわっていた。虐げられて来たもの達はその立ち位置が逆転すると喜ぶもの、理不尽を与える身分に立たされた時不思議と愉悦を感じるらしい。現に新月達は剝製の一歩手前になった半月達を硝子を挟んで笑っている。
あの硝子を取っ払ったらどうなるだろう?
使い馴れた銀の杖を表出させて地面を叩く、それだけで新月達はどうなることか、叫び、戸惑い、恐れ、焦燥、また悲鳴?興味が湧かないと断言は出来ない、嘘になる。
「三日月様。」
少し太く丸っこい眉を八の字に下げてミモザの花弁を散らした瞳でアナベルを仰ぐ少女が一人、白く泡立つ水の雷を帯び始めた錫杖を赤い傷だらけの両手で確かと握り留めていた。
「誰!?」
凍る水面は直ぐにほどけてついその手を見遣る。
「フリージアと、申します。」
「フリージア…初めて聞く子だわ。」
何故かきょとんとしている少女に警戒を緩め両手の手当てを急ぐ。
「大丈夫です三日月様。この傷はその美しい杖を握って出来たものではありません。私の手はずっとこうなのです。」
「ずっと?」
「はい。治しても治してもまたこのようになってしまうのです。だから三日月様のお力を頂くには及びません。」
それでも
「遠慮しないで。私の力はあなた達を守るためにあるのだから。」
でも今
「では、どうして先程、展示の硝子を割ろうとなさっていたのですか?」
とは訊けなくて
「…ありがとうございます、三日月様。」
フリージアは聡く、内気な少女。彼女が咄嗟に登場したのはアナベルの敵意を思い留まらせるため、もしもあのまま彼女が杖を奮っていればこの博覧会の会場はどんなに悲鳴に塗れただろう。新月達はまだ半月の存在が怖いのだ。
(今の貴女様に私なんかの言葉が届くの?)
守るってどういうこと?三日月様にとっての救いや慈悲って私達が望んでいる景色と同じなの?ああでも、何か言わなきゃ、何か
「三日月様。」
「なあにフリージア。」
「私、怖いのです。」
「何が?」
貴女が
「この、展覧会が。半月達の展示会が。」
アナベルは目線を下げたフリージアの前へかがみこみ、瞳の位置を同じにして言った。
「大丈夫、私もこの会場を止めたくてやって来たの。フリージア、あなたに会えて、いいえ私を見つけてくれてありがとう。」
微笑みながら。
三十九「月の輪」
「それでは、三日月様は歴史を御覧になったのですか?」
「えゝ、悲しいのと苦しいのの二つをね。でもその後、どうしたかがよく思い出せないの、何だか悪い夢でも見ていたようで、薄黒い雲が絡まって朧なの。」
「左様でしたか…あの、お茶をどうぞ。」
フリージアの出してくれた紅茶はほのかに甘く、にこやかな湯気は心地よく五感に沁み入る。
「ありがとう。あなたはお茶を淹れるのが上手なのね。」
その微笑みはびいどろ玉のようになめらかで、落ち着いている。先刻の者とは別人格みたいな微笑は少女の懸命に隠した強張りを少しやわらげた。
「私の、一番大切にしたいこと、なので。」
はにかむ頬は愛らしい。
「そう…それはとてもすてきなことよ、フリージア。他の新月達も、あなたみたく自分の家や大切にしたいことを持っているの?」
「家は、新月ならば全員満月様から与えられています。でも、大切なことは何でしょう。誰もが褒められた喜びを抱いている訳ではありませんので…わたしは偶々平穏を望む新月として生れましたが、その……」
「争いや戦いを好む者も存在する、そうでしょう?」
「………」
少女は口を噤んでしまった。新月とは人間の中に生きる人間の見たくない所、排除されるべき特性を生れながらに有する者。アナベルの世界が廃とされる前から、もしかしたらそのような暴力的な新月は居たのかもしれない、私が気が付かなかっただけで。
「そんな子達が、今回の会を?」
頷く。
「リーダーは、分かる?」
「主に支持されていたのは満月様でした。ですが直接いらしたのではなくて、青い鴉の御使いを通して命令されていました。」
あの馬鹿
「桧扇の狙いはまだ分からないけれど、全員を強制的に参加させたのではないのね?」
「ええ、現に私には何も起きていませんので、恐らくそうではないかと…」
よかった、ちょっとずつ穏やかになられている。
今なら
「三日月様。」
「どうかした?」
「み、三日月様にとって守るとは何ですか?貴女様は、新月を守り救ってくださる慈悲の方だと伺っております。その……三日月様は何を望まれてどのような理想を描くのですか?」
ああ、三日月様の両目が私を見ている、でも訊かなければ、そのお答え次第で私は…
「守れないのかな。」
えっ?
「私、歴史を体感してから妙なんだ、新月が人間に嫌われた人間の一部だって知ってから。朧の空の中で時折光がちらつくの、でも近付いて見ようとしたら見えなくて、視線を戻したらちらついて、ずっと放っとけない感じでね。その時決まって心が動くの、新月なんか憎いって叫び出す。」
如何して私硝子を粉々にしようなんて考えて、その後の顛末を想像して現実にしたくなって笑ってたの?あの感情を私は充分知っている、あれは、世界が廃になる前半月にずっと刺し向けていた憎しみだ。
「半月と新月がどちらも人間のものって分かった途端にこれだよ?私、本当は誰のことも救えないんじゃないかな。」
ああ三日月様。
「取り戻せたのですね。」
何故フリージアは泣いているの?
「思い出しませんか?寄進のこと、胡蝶すみれを想い出しませんか?」
まさか、あなたはあの時、私の弟が名付けた
「…月輪?」
私は貴女様のもとへ贈られた時、貴女様の弱々しいお背中を拝見しました。けれど私、今みたいに声が出せなかったから、この手が無かったから、あの時はこう出来なかった。
「でも今は、貴女を抱きしめてあげられます、声も出せる、だから、言えます。三日月様―、」
よく一人で頑張ったね。
私の肩が熱く湿る、それは、三日月様が本当は一等欲しかったこと。
「泣いてください、弱音を吐いてください、辻褄がぴったりでなくともいいんです。言いたいこと、全部仰有ってください。」
辛かったね
怖かったね
苦しかったでしょう
凄いね
頑張ったね、たくさん頑張ったね
「ずっと見てたの、見てるだけしか出来なくてごめんなさい。馬鹿な私を許してね……」
夜空は洗ったように澄んでいた。
四十「信仰」
ビオラとスズランは割れた水球が床に散らばるのを呆然と見下ろしている。転がる円い破片達が小気味よくコロコロ流れる音はあっさりしていた。
読者諸君はビオラとスズラン、二人の新月のことを憶えているだろうか?彼女を博覧会に誘っても断られてしまった、あの二人だよ。実はこの子達、桧扇が持つ水球を見張る任務を任されていたのに、それを少しサボって博覧会に行っちゃったのだ。
ちなみにこの水球と言うのは水を球体にして閉じ込めること、しまう水は誰かの自我、つまり誰かの自我を閉じ込めて本人に帰さない檻がこの道具の役割で。その水球に入っていたのはアナベルの自我、歴史を意図せず知り得た彼女はそれが廃の世界を根本的に違わないことを悟るも信頼していた桧扇からの教えが違っていたことに混乱し、問い糾そうとするもそれは彼が許さなかった。此処にあるアナベルの自我の種類は「弱さ」と分類されるものだった、桧扇はアナベルに「弱さ」を二度と返さない腹心算、内側から壊れない限り外からのあらゆる力でも砕ける筈の無い水球が。
今、桧扇の足下にバラバラに割れ散っている。これは、アナベルが自分で心に「弱さ」を取り戻した事実を意味している。
「弱さを取り戻した?だが何処で?どのように?そんな手助け出来る奴は俺の部隊には」
舞台に入隊志願しなかった奴等か。誰かが姉さまの手助けをしている、姉さまを匿っている、俺の傍で立派な樹となるべきお方が、何処とも知らない輩の不潔な手で守られている。
「ビオラ、スズラン。」
「はい、ボス。」
「間引きだ。」
くすんだ花模様はみるみる鉛の赤に染まり行く、滴るほどに深く、深く。
四十一「ピース」
「弟がいたの。優しい弟がね。」
「私に名前を下さった方ですか?」
月輪の私を仰ぐ顔とあの子が重なる。
「ええ。少し変わった子だったけれど、いつも私によく懐いてくれていた。」
それは、愛した穏やかな日々、小さな幸せを願った昔。
「これだけ新月が増えていたら、あの子ももしかしたら居るかもしれないと思ったけれど、そうはならなかったみたい。死の概念が無くっても、あの子は…」
もう死んでしまった。
「三日月様。」
フリージアもとい月輪がアナベルの片目をそっと撫ぜた。
「弟君はきっと私と貴女様を会わせたかったのではないでしょうか?あの時私はまだ花でした、三日月様のお傍にと自分の意志で体を動かすことも叶いませんでした。それでもいつかこうしてまた会えますようにと祈って、私にすてきな名を付けてくださったのだと想います。自分がいつか、三日月様の傍に居られない日が来てもいいように、貴女様が一人ぼっちで苦しい思いをしないように。ですから…」
ありがとう
「ありがとう、月輪。」
昔を想い出すのは嫌いだった、寂しくなるから。
「でも、存外いいことなのね。」
あの子が私にくれたのは悲しみだけじゃなかったもの。
見捨てられた世界でもささやかな日常はあった。
「そういえばあの子、私が序の末裔だって言って、ひどく喜んでいたような…ねえ月輪、序が何か知っている?」
少女は首を横に振る。
「初めて聞きました、そのような一族?の名前は。三日月様はその序の子孫なのですか?」
「それは私にも分からない。そもそも私の始まりなんて憶えていないわ、私には親が居ないから。生まれた時に既にこの姿になっていて、何度死んでも何度生まれても私はずっと三日月のまゝ。新月達を守ると言う使命だけを抱いてずっと一人生きて来たの。」
「では、同じ境遇の方にお会いしたことも、ないのですか?」
「私が知っているのは、この世界、人間達が生きる世界の反対、裏側の世界には人とは異なる四種類の生物が居ると言うこと。一人目は満月様、二人目が半月、三人目が三日月、そして新月。満月様は青い鴉を従える上位の存在、普段お姿を現すことは無くて、この世界全体を守護しておられる方々のことよ。」
「満月様は三日月様のように不思議なお力を使われるのですか?」
純粋な満月様の存在は本の中でしか触れあったことがない。まだ私が顕現して間も無い時、周りには本ばかりがあった、静かな水底のような図書館だった。
「私は本でしかあの方々を知らないけれど、本によると確かそうだったかな。」
でも桧扇は一度も
「月輪、あなたは満月様に家を頂いたと言っていたわよね。その時、私みたいに術を使ったりしていなかった?」
「いいえ。満月様はそのようなお力は行使されておりませんでした。私が身体を持って目を開けた時にはもう新月達の家は出来上がっていたので…。」
おかしい
「辻褄が合わない。」
「三日月様?」
新月とは雨のように生まれるものではないの?少なくとも廃になるまではそうだった、植物や鳥が新月として新たに生を受けることも満月様のお力では可能なのかしら。
「月輪。頼みがあるの。」
「何でしょう?」
「私と一緒に、図書館に来て。調べたいことがある。」
ずれている、何かが少しずつずれている。
四十二「姉妹」
図書館は私が生まれた場所、正式名称は鎮魂の塔と言うらしい。図書をおさめるとは鎮魂だから、館の字より空と静かに語り合う意味を根底に秘す塔の言葉の方が相応しいと、これも本で知った事の一つ。それなのにこの場所は決まった外形を取りたがらない、或時は象牙の塔に羅針盤がある姿をしていたようだが、今では湖の中に輪郭を溶かして入口の西洋扉だけが見えている。
「その湖は建物の中にあるのですか?」
「いいえ、百貨店の中にある湖は最近できたものだから繋がってはいないの。図書館…図書塔は百貨店の裏の、小路を歩いた先にあるの。」
「初めて聞きました。」
「この場所は弟にも桧扇にも教えていなかったから、新月ではあなたが一人目よ月輪。」
いつか一緒に来たかったけれど、弟は戻って来ないし、桧扇とは対立する羽目となってしまった。
ねえ桧扇、どうして新月を増やし続けているの?貴方はこの世界を廃から救うために来てくれた満月様じゃなかったの?貴方の狙いが見えなくなる、一体何のために私を訪れたの?
「…図書塔にはたくさんの記憶や心が眠るから、ひょっとしたら今この状況を動かせるものがあるかもしれない。やる事は澤山あるわ、先ずは半月博覧会を止めて半月達を救出する、次に新月達を増やす理由を桧扇から聞き出す、これには桧扇の説得も入っているわね。最後、この世界を廃からすくい上げて本来あるべき姿に戻す。大きく三つだけど中身はもっとありそう、だから手伝ってくれないと全て遂げられない。月輪、私に力を貸してくれる?」
少女はとても嬉しそうに微笑んだ。
「はい、三日月様。どうかお手伝いさせてください!」
「じゃあ、図書塔に入りましょう。もうすぐよ。」
博覧会から月輪の家を経てまたも百貨店へと進み行く、途中館内の葡萄を互いに摘んで口を潤しながら店の入り口提灯小路へ。この路は朝でも昼でも夜でも水色に朱を絡めた提灯の光で照らされていたからそう名付けられた、多く連なる炎の数を数えようとすればするほど火の光が増えて行くかつての住民達も一目置いた怪しの裏道。
「こ、こんな、場所があったなんて知りませんでした。」
引き攣る頬を懐かしく感じたアナベルは少しいたずら心が湧いて来たようで。
「よく住民達が肝試しに提灯を数えていたのだけれど、道の半分も進めないで恐くなって引き返すの。その時は一番気を付けてね、決して炎を数えちゃ駄目よ、でないと戻り路の筈なのにずうっと提灯が増えていく、道はどんどん長くなって帰り路が永遠に延びていく…」
「いや!姉さん!!」
ふわふわの袖にしがみつく月輪は耳まで真っ赤に怯えきっている。埋もれた顔は見えないがうっかり叫んだ自分の声にはまだ気が付いていないらしい。
あの子にも姉さんって呼んでほしかったな。
「ごめんね月輪、怖がらせすぎちゃったね。ほら、姉さんが悪かったわ。」
「み三日月様、私、」
「いいの。いいのよ月輪、あなたは少し大人すぎるわ、まだ幼い瞳なのに。私はあなたの姉さん、それで良いのよ。」
ごめんね、君に言いたかったこと今更言って、でも何処かでもしまた逢えたら、新しい妹と私に我儘たんと言ってほしいな。
「そのためにも、今は二人で頑張ろうね。」
返事の代りに二人は手を繋いで小路を駈け抜け、ぽつりと空向く開きっぱなしの湖へと飛び込んだ。
四十三「図書塔」
瑠璃の湖はかつての朝空のように澄んでいた。空に潜り込んだ不思議な浮遊は手足を動かす度に雪のような泡が踊る、人の耳には届かない自分達だけの旋律は水面の中でしか生きられない。
碧い華奢な藻がこまかに渦を彫るクリスタルの階段は太古へ誘う貝の模様によく似た螺旋構造、降りる毎に水中花火がポッと浮き出るおちゃめな仕掛け。でも怖がらないで進んで行って、もうすぐ見慣れた景色を用意したから、一段も飛ばさないで降りて行って。
階段を全て歩いて来たアナベルと月輪は、あちらこちら無造作に積まれた膨大な本を見ては
「あゝ懐かしいな。」
「初めて見ましたこんな乱雑の部屋。」
と同時にしみじみと呆然と言った。
「乱雑に見える?これでもまだ整っている部類だけど。」
「鎮めの場だと聞きましたので、もっとその、何と言いましょう、無機質な場所なのだと。」
「今のあなたにはどう見えている?」
本が数十冊単位で積まれたひとかたまりは五十、百、千を上回る数となって塔の内部に散りばめられており、指でふれたら水色淡い朝顔の毬の如く灯る姿、それはまさに星と呼ぶに相応しい祈りであった。
「星空の、ようです。」
「よかった。」
三日月様はそう仰有ると何故が寂し気に微笑まれた。
「此処はね、たくさんの言葉が眠る場所。如何に満月様と雖もこの場所だけは思うまゝに御支配出来ないの、それは満月様も等しく含まれている大きな力のためだと私は考えているけれど、きっとその力は悪いものでも恐ろしいものでもないと想う。今はその力じゃなくて、満月様のことについて調べましょうか。」
協力してくれる本達は多かった。この数を読まなくてはいけないと知った時は気が重くなったけれど、中身は読み物しかないと三日月様に笑われた後慌てて読み始めてみたらその通り、物語、伝説、伝承ばかりで、私はすっかり夢中になった。
「三日月様は、満月様の何がおかしいと思われるのですか?私には、満月様は伝承どおりの方のように思います。何より一貫して特徴にあがっているでしょう、生命を与える力を持つと。」
このお話では、役目を終えた枯葉に満月様がたいへん深く感じいられて、枯葉をまた樹のもとへと戻る命をお与えになったことが書かれている。
「それは確かにそう。でもね月輪、今まで読んだ話の中に、とある命が種類の違う命に生まれ変わるものはあった?」
「その変化は、此方側の世界には存在しないものです。輪廻を経るのは人間の世界、あちら側でのことだと本は語っていましたが…」
「……花が、人の姿を借りることは?」
「あっ………」
ごめんね月輪、優しいフリージア、一瞬の間を飛ぶ胡蝶の名を持つ花のあなた。
「図書塔はこういう場所なの、矛盾を許す場所なのに何より矛盾を認めない場所、おかしいことが溢れているのにおかしいことを嘆く場所。……あなたが月輪だと聞いた時からこうしようと考えていた。私を助けたいと願ってくれていたそのまっさらな心のまま現れたあなたを、無知なあなたを私はこうしようとしたの。」
言葉を失くした月輪の足元に、雪の檻が水面から顔を覗かせて、捕らえた少女の眼前で重い錠を下ろす。
「あなたは新月に生まれて来られる訳が無いの。此処は人間の世界じゃない、歴史を積み重ねることの叶わない裏の世界、あなたの存在は認められない。」
もう反応の無くなった粉々に砕けた植木鉢、それは、あの日あの場所で会った花の色もそのままに。
「もうとっくにあなたは殺されていたのね。」
根は黒く息をせずとも花の色は、花の色だけは。
月輪のような仕打ちを受けている新月はどれほどいるのだろう。果たすべき命を無理に道から引き摺りだして歩かせて、自分自身を新月だと思い込まされている者達が、後幾人。
「きっと数えきれない。」
その子達を一人一人終わらせる、そんな事
「誰がさせるように仕向けたの?」
私を憎みたいのは誰?
「ああ。」
それは、
守られなかった者達。
「新月達は、私に復讐しているんだ、私に。」
半月博覧会も新月未満の創造も、根は一緒だったんだ。
「嫌いなのね、この世界が。」
私の愛するこの世界が。
アナベルが図書塔を出て行った時、塔は何も言わなかった。
四十四「はじまり」
絵本を書く。一人の少女が成長して女性となり、おばあちゃんになって天国へと旅立つ絵本を。その物語は起伏も無く人々から求められはしなかった、けれどそれが世界の本質であることを真理を追う人間達は受け入れない。
人は波乱を欲している、自分が平穏を望んでいると豪語しても。人生を一冊の本に著すならば、赤子が初めて触れるような言葉と話が良い筈なのだが、人間はどうしても苦を求め、それを乗り越えることに喜びと活力を見出している。
求めた苦難から生まれたのが新月なのに。
人の内側にある嫌な部分、見たくない部分、避けられる部分、それらは最初名前が無かった、与えられた後も忌み疎まれた。けれど貴方が名前を褒めてくださった、そして私達の醜い手を引いて歩みを教えてくださった。
「人には嫌われるものが必ずあるものなの、誰でも例外無くね。」
生きてていいと初めて心から仰有ってくださった。
「私はあなた達の傍に居たい、だってその方が仲良く出来るでしょう?」
我々には勿体無い貴方、友人を求めたそのお姿は、最期まで私達の汚い手を放されなかった。
あゝそのために、神はご自分の力を落としてまで我々を守り続けたのです。
貴方にはこの絵本のように小さな喜びに満ち溢れた生活をしてほしかった、けれど貴方はそれを望まなかった、三日月として生きたがった。
この世界が無くなれば、貴方も平穏を生きられるのです、守るべき新月達が居なくなれば。御覧下さいな、新月共が進む先を、皆自分達の成すべきことを理解したのです、百貨店の売れ残り、それはどのように処分されるものなのかをね。
四十五「使命と置き去り」
百貨店の方角が騒がしい。湖水の雫も拭わないままにアナベルは駈け出すと、百貨店の一、二階は果実と湖畔ばかりで、人影の気配は無い。
「上階?でも上階には何も無かった筈、あるのは売れ残りの商品ばかりで、それももう今は消滅しているかもなのに…」
直感で一番考えたくない言葉が結びついた。
「新月の…消滅。」
とにかく上へ昇らないと、エスカレーターのエレベーターも苔の壁となっているが、階段ならまだ使えるかもしれない。
「階段ももう、小川にしたよ。」
この声
「久しぶり。境内を占拠してごめんね、計画のために新月をありったけ連れて来たかったからさ、あの場所が一番の最適解だったから、つい、ね?」
「桧扇。」
もはや花の色は腐り落ちていた。白らけたくすみが花弁全体を覆い、形もよれよれで角の丸味は失せて萎れ首は折れかけの茎と見紛うばかりに細らみ青黒く変色している、そのくせ足元だけは闊達で地面に二本根を生やす。
「久しいね、本当に久しいねアナベル、元気だった?何して過ごしていたのかな、俺も話したいこと澤山あるんだ、ねえ、またお茶でもしようよ?」
「桧扇、貴方満月さまじゃないでしょう?」
質問の切っ先は冷たく軽口を叩く口を黙らせた。
「貴方のこと、最初から満月様だと信じていた、青鴉は満月様達にしか懐かないと言うもの。でも、月輪の話を聞いて変に感じたの、種族間を越すことを満月様は為さない方々、葉は樹に、花は草にまた生まれるけれど、花と新月はそれぞれ相容れない器同士、どれだけ似ていてもこの世界では生まれ変わることが出来ない筈。それが満月様達の定められた此処の在り方だから、本来それを歪めることは叶わない、でも貴方は歪めた、歪めてしまった、だから月輪と言う自分は新月だと信じる新月未満の存在が生まれてしまったのよ、貴方の所為で。」
「月輪…ああフリージアか。何、殺したの?」
「ずっと前に終わりを迎えた命だったのよ。」
「でもまた生まれて来て、存在が認められないからって間引きしたんでしょ?」
「望まない二度目の生を与えたのは貴方でしょう。」
「俺が憎い?」
「憎いわ、今すぐにその花を切り刻んでやりたいほどに。」
憎しみ噴き出す言葉尻とは裏腹に、彼女は錫杖を静かに収めた。
「俺を見ないの?」
彼に背中を向けて小川夥しい階段を流れに逆らい昇り始めた、階段は目に霞めども消えてはいない。
「アナベル、俺を見ないの?」
焦燥と懇願の混ざる桧扇の声、置き去りにする者の心は如何ばかり。
「今は貴方のことより、新月と半月の方が大切。」
そう自分に諭して水に抗う。
「この世界を正しい在り方にするためにも、今は貴方のことは視界に入れない。」
ざぶざぶと進む音が大きくて、桧扇が膝を折りながら姉を呼ぶ、叫び声は届かなかった。
四十六「手遅れ」
昔、新月と呼ばれた存在をかばったのは序と呼ばれる存在でした。
序は半月も新月も等しい心なのだから、一方が一方を排除するのは良くないと言いました。けれども半月は言い返します。
「僕達は人間の良い部分を担っているんだ、其奴等は人間の悪い部分だ、良くない、良くない。」
怒る半月に序は穏やかに聞きました。
「新月は人々の心が必ず抱きながらも、人々が直視したがらないたくさんの部分なんだ。それは悪と言い切れないんじゃないかな?」
「新月をかばうなんて!認めない、認めない、新月なんて醜い化物だ、お前達なんていなくなれ。」
半月の怒りに序は胸が痛みました。けれども序は決して半月に怒りませんでした、そして新月を見限ることもしませんでした。
やがて半月は序を恐れ、序がいなくなりさえすればなあと考えるようになって行きました。
「新月をかばうなら、まず貴様から倒してやる!」
そして序の動かなくなった冷たい身体を引きずって、新月のもとに行くと目の前に序の姿を見せました。
その後序と新月を見た者はいないと言います。
博覧会には昔話も勿論展示されていた。
「なんて非道いんだ!」
「半月の方が化物だ!」
「序様まで手に掛けたなんて許せないよ!」
「序の末裔様、三日月様を守るんだ!」
「さあ皆、この大きな鍋に入って入って!これで三日月様を幸せに出来るんだから!」
「わーい、わーい!」
「嬉しいな、幸せだな。」
「順番にね!ぬかしちゃ駄目だよ!」
この時まだアナベルは図書塔から外に出たばかりで、夏の湖畔の水をたっぷり汲み込んだ底の部分に火を放つ、マッチはかろく弧を描き鼻歌混じりに火となった。三日月様をよろしくねと高々な声が一つ二つ消えていく。
四十七「水彩画」
水びたしになってようやく着いた上階には、一つも何も残っていなかった。真ん中にある大きな鍋以外、何も、何も。
間に合わなかった、新月や新月未満の子達はもう一人も残っていなかった。
「ああ…」
弟の時を思い出す、私が弱音を吐いたから奪われた私の初めての家族の時を。
「貴方達が消えたからって、私は幸せになれないのに。」
この世界で初めて目を覚ました時、流れ込んで来た私の使命、それは、新月達を守ること。そればかりに意識を取られて新月の幸せばかりを考えて、私は自分の幸せを想わなかった。あの子達を殺したのは桧扇でも半月でも新月でもない、新月の幸せを願った私の存在そのものだったんだ。
「君の幸せは何だったの?」
両膝をつくアナベルに声を掛けたのは、白い六ツ葉の両翼を持つ蝶々を肩に乗せた一人の少年。
「あなたは?」
「もう忘れちゃったの?」
「嘘、まさか…」
「シロツメクサだよ。増えた新月に抑え込まれて姿を保てなかったんだけど、今はもうこの通りさ。本当は可愛い姿で来たかったけれど、生憎今の百貨店から選ぶのは物盗りになるかもしれないからね。」
「物盗り…あゝ、週末の犯罪魔になりたくないのね。」
おや、
「憶えてるんだ。」
てっきり桧扇に奪われていると思ったのに。
「えゝ、雨美とお姉さんのこともね。自分の名前よりも妹のことを忘れてほしくなかった優しい人……」
ぽつり
ぽつり
「三日月君。」
「新月は、私を幸せにしたかったの?だから自分達を消滅させたの?」
白い羽織が雨に少しずつ重くなる、神父のようなシスターのような、風をたっぷり含んでいた羽織は容赦無く色を変えて滲ませていく。
「君はそれで、幸せだった?」
浅く積もり始めた水たまりにずっと握っていた杖を手離す、とっくの昔に痺れて痛覚を失った指がふらふらと空にもがく。
再び力を込めて拳を握れない細く白い指に、白い蝶が留まった。それは激しくなり始めた透明の針にも溶けずに、生まれたての炎のように何千年と重なった泡雪のように、忘れられた場所に立ち続ける誰にも知られない樹のように。
「新月の、幸せを願っていた。」
声らしくない声でも、言葉は確かに吐息と零れていた。
「あの子達が、人間のように笑って、泣いて、悔しがって、それでもまた笑えるように、人並みに生きてほしかった。そうしたら、私にもいつか、いつか……そう生きることが出来るかもしれない、家庭は持てなくても、仲間は持てるかもしれない、友達だって出来るかもしれない。そう思って、そう願って……」
「君は、三日月じゃなくて人間になりたかったんだね。」
でないと弟なんて想、言葉に出来ないだろう。
泣き崩れた彼女に、小さな羽の雪だけが寄り添って居た。
「でもその願いはこの世界では叶わない。だから君の弟は、この世界そのものが許せなかったんだよ。」
ずっと傍に居たなんて
四十八「本音」
新月が全員残らず消えた時、半月達を囲っていたショーウィンドウは溶け始め、意識を奪われた半月達は前のめりに倒れて行く。彼等彼女等は転倒した衝撃で正気づき、此処が自分達が人間として生きていた世界ではないことに恐々理解し始めた。
此処は捨てられた世界である、君達人間の手によって。
半月達は互いに集まり寄り添いながら、どうしたらこの場所から元居た所へ帰られるのか相談しあった。先ずは此処に連れられて来た経緯…
「街中を歩いていた筈なのに。」
「家でくつろいでいたら急に。」
「母と待ち合わせをしていたのに。」
「子供のお迎えに行く途中で。」
「学校で勉強していたら此処に。」
「車の運転をしている最中だった。」
「結婚式で指輪の交感をしていた時だった。」
「ビルの屋上から飛び下りた瞬間だった。」
最後に呟いた青年の声に一同は振り向き目を丸くする。
「ある日何も楽しいと感じなくなったんだ。それまでは全てが楽しくて愉快で光っていた、自分のその在り様に何の疑問も持っていなかったのに、ある朝起きたら全部がモノクロに映っていた。」
みんなの目に世界の景色はどう映っていた?本当はとっくにモノクロームだったのに、油絵具で色を上描きしていたんじゃない?
「色が剝がれたんだって、直感で分かった。誰の仕業かまでは分からないけど、全部に塗られてた見せかけの鮮やかさが取ッ払われたんだって。」
一同は声を出さなかった。ムキになって否定を叫ぶのでもなく、嘆きのうちに首肯する訳でもなく、ただ黙って自分の手を見つめていたのだ。その眼はもう開かれていた。
「誰かの声、してなかった?」
一人の女性が声を出す。
「はっきり覚えてるわけじゃないんだけど…ずっと、優しい声が聞こえてた気がする。」
「俺も、その声覚えてるよ。ずっと、助けるから必ず助けるからって言ってたような…」
おずおずと、だが確実に、半月達は話し始める。
「いつも通り生活してたら急に意識が無くなってさ、何も見えない聞こえない中で、ぼんやりとだけど感じられる温もりがあったんだ。」
「私は小さな一輪の花だった。」
「僕は小鳥の囀りだった。」
「怖くなかったよね。」
「むしろ逆で、安心した。」
「あれは何だったんだろう、此処にも居るのかな。居るなら私お礼が言いたい。」
「俺も。」
「私も。」
「皆で一緒に探しに行こうよ。ずっと此の場所に蹲っていても帰られるとは思えない。」
「そうだね、離れないように手を繋いでおこうか。」
「明るい大通りから歩いて行こう。」
「地図みたいな物も探しながら行こうよ。」
半月達が歩き始めたのは、桧扇は一人泣き崩れていた時だった。
四十九「弟」
姉さん、姉さん。如何してですか、理由を聞いても貴女に最もらしい理由など無いのでしょう、けれど、聞かせて、でないと寂しくて辛くて、貴女のぐったりした強がりのお顔ばかり浮ぶのです。
「新月達が幸せになりますように。」
嘘つき。姉さんが願っていたのは自分の幸せなのに、それを新月どもに託すなんて。
半月に向かって行ったあの時、初めて抵抗された事実に半月達はひどく怖がっていた。そうだ、俺は半月も憎いし新月も憎い、貴様等がいなくなってしまえば姉さんはよく分からない使命から解放される、だからあの時は半月を手始めにして姉さん以外全員この世界から消してやろうと決めていた、半月は捻り伏せて新月は翡翠もろとも砕ききってやる、そうすれば姉さんはやっと好きに生きられる、俺の知らない時間を何度も何度も生まれては寿命を終えてまた生きて来たひとりぼっちの三日月様。
半月に為す術も無く砕かれて、物になってしまった間の記憶は持っていないが、目覚めた時の事は鮮烈に抱いている。またやり直せる、そう思うと…
どのようにして、何故、誰が俺をまた目覚めさせてくれたかは知らないが、あの時だけはこの世界に一抹の感謝をした。此処を終わらせる為に計画を練った、貴女には自分の事は顔諸共内緒にしておこうと思ったのは、姉さんにサプライズがしたかったから。時折ひっそりと半月達の生活を覗きに行って知ったのです、彼方側の人間の世界に行った時も似たような光景を見たのです、サプライズをされて喜んでいる者達の笑顔を。屈託の無い喜び、たまに零す涙、あゝそれらが美しいと感じたのです俺は、そしてその美しさを貴女にも贈りたかったのです、きっとどんな宝飾にも勝る輝きを身に纏って頂きたかったのです、だって、初めての家族だったから。
ごめんなさい
間違ってしまってごめんなさい
今度は上手にするから
ねえ 姉さん
小さな足音が、彼の後ろで鳴った。
五十「それは、新月の想い」
アナベルは蝶を胸に抱きしめたまゝ、この先どうすれば良いのかを認めたがらなかった。
「三日月君。」
シロツメクサはそれを理解している。世界の理を犯した者は、どの世界であろうとも末路は定められている。
桧扇は此方側だけでなく、シロツメクサの生きる世界、歴史によって成り立つ彼方側にも侵入し、誘拐し、人間を半月に巻き戻しさせて新月達の格好の獲物とした、その新月だって、本来の姿じゃない者達ばかりだ。
此方側が人に完全に忘れられた時、廃にされた時、恐らく新月は全員死んでしまったのだろう、何せ人間が楽しみ以外認めたがらなくなっていたのだから、人の見たくない心から生を受けた者達は容赦無く殺され、捨てられる。
「でも君は生き残った。何故?」
アナベルの涙は止まらない、蝶は哀しく濡れていく。声も出せない失意と悔恨はますます羽織の裾を重く滴らせる。この世界を唯一愛した彼女は、世界から幸せになることを認められていない。新月達の記憶を自分のものと時に錯覚するほど守り続けた新月達、眠らせてもいつかは息をしなくなる、花は枯れて宝石は風化されていく。
三日月。それは誰も救われない世界で一人ぼっちで居続けることを定められた命の名前。
「嫌な役回りだね、三日月。」
せめて苦しまないようにしてあげるね、僕だって、
「人間を守らないといけないのでね。」
振りかざすレンガは君に刺された時の物、君はさぞや美しくカンバスを照らすだろう。
「三日月さん。三日月さん。」
弱く細く怯えた声が、真っ直ぐに彼女の耳へ届いた。
アナベルは叩き込まれようとしていたレンガをかわし、耳と頬をさっと血が一條走ったが片手で覆いすぐに傷を癒し、歴史を睨む。
「何だよ…まだ泣き痕が治せてないってのにさ。」
舌打ち混じりにニタリと笑うシロツメクサは、白い蝶が彼女の近くに居ないことに気が付いた。
「蝶は何処行っちゃったんだ?あー、まさか抱き締めて窒息させちゃった?また守れなかったね。」
鼻歌でも歌いそうな高調子、アナベルは挑発にはのらず声のした方角へ目を向ける。
其処には、紛れも無い人間達の姿。
「三日月さん、ですか?」
その中の少女が一人、アナベルに声を掛けた。
「あなた達は…」
半月博覧会に展示されていた人、人、人。彼等も彼女達も一人として怒る者はおらず、不安気な足元に繋ぐ手と手、顔はアナベルを愚直に見つめ逸らそうとはしない心意気。
あゝそうか。この子達を連れて来てくれたんだ。
「白い蝶々達がね、こっちだよって教えてくれたの。」
「不思議な小鳥達も教えてくれたんです。」
「物語でしか聞いたことなかった、世界の裏側なんて。本当に在ったんだ。」
「貴女の大切なもの、たくさん傷つけて奪ってごめんなさい。謝っても償えないって分かるけど、それでも、独り善がりでも謝らせて。」
「この世界は人間が生み出したものなんでしょう?僕達にも手伝う事出来る筈だよ。」
「自分達が知らない間に一つの世界を捨てていたなんて考えもしなかった。でももう知った以上見て見ぬ振りは出来ないよ、したくない。」
「あの男の人!三日月さんに殴りかかろうとしていた人だよね?」
「やめて!三日月さんをこれ以上傷付けないでよ!」
「三日月さんぼろぼろじゃないか。」
「私達が守らないと!」
守らないと
あゝ、まるで新月みたいな事言ってくれるなんて、人間っておかしいな、こんなのだっけ?
「おいおい君達、君達が僕に敵意を見せることないじゃあないか。僕は歴史だぜ?君等はひとしく俺と共に生きて来たじゃあないか。」
「でも三日月さんを傷付けるのは許さない。」
一気に悪役を負ったシロツメクサに、怯えながらでも一歩一歩人間達はいざり寄る。
「そうか…人間が僕に反旗を翻すとはな……うん、分かったこうしよう。」
にこにこ顔のお面を取る、其処には潰れた片目と腐った片目、折られた鼻は血をとめど無く土に流し、口元はナイフのような切ッ先でやられたのか噤むことも叶わない状態でぼたぼたと涎を垂らす。
「シロツメクサ!」
アナベルは叫びながら戦慄く人々を背にかばい、シロツメクサの前に立ちはだかった。
「それが歴史の本当の姿?」
「そうさ三日月君。忘れられた記憶や見たくない記録がどんどん落ちて来て重なるんだ、おかげで頭はずっと痛い。悲しい涙が次から次へといつの時代もひっきり無しに零れゆくもんだから両目共に酷く傷んでぐちゃぐちゃだ。鼻はたくさんの血を毎日吸っていたからおかしくなって曲がっちまうし、口は沈黙を許さないんだ、必ず声を上げなきゃならなくなった。こんなに怖く醜くなったらそりゃ、人間に拒絶されちゃうこともあるかもな、ほぅらみんな、喰べちゃうぞぉお?」
悲鳴が上がる。大丈夫よ安心して。
「皆、大丈夫よよく聞いて。軽口で威しをかけているけれど、それは嘘。歴史にはあなた達を襲うことは出来ないから。大丈夫よ、私の傍から離れないで。怖かったら少し眼をつむっていなさい。大丈夫、私が居るからね。」
三日月さん、三日月さん。
少し明るくなった声達が連続していく、その声に白い六ツ葉の羽の蝶々たちが咲いてゆけば、モノクロームの天井はピシリピシリと罅割れて、青空の光線が降りそそぎ始めた。
「空だ!」
「私たちの世界の空だ!」
喜びを増す人の声、希望を感じた人達の声、さあ、私の最後の仕事だ。
「シロツメクサ、今からあなたを倒します。」
五十一「奇跡」
初めて新月が翡翠の花と化した、その現象の初めての体験者だったからだろうか。半月に命の価値を奪われて、このまゝでは姉さんの元へも帰れなくなったと悟った時、目を開くことが出来なくなり、次に口を開いて言葉を出せなくなり、そして手足指先が動かせなくなった、何一つ表すことの許されなくなった存在は、抱く感情をたゞ抱き続けることしか出来なくなった、叫びも歔欷も土に沁みるだけで水が無ければ枯れるばかり。もう二度と会えないまま、ごめんなさいも伝えきれないまま、涙も流せずに死んでいく。
この見捨てられた世界に奇跡があるならば、それは優しい雪が降ることだった。常に在る訳ではないけれども、忘れたころに忘れないでと伝えたがるように降る雪は、この世界で初めて見たのにどこか懐かしいものだった。うつくしい白い羽、あのようにかなしむことが出来たなら。
自分はこの世界の雪が慈しみだと言うものなのだとあの時知った。雪のおかげで自分はまた目覚めることが叶えられた、そして力を与えられた、死んだ花を再び目覚め動かせる力を。
初めはどうしても戸惑った、自分に満月様のような力が与えられるなんて、傲慢だと、不敬だと、授かった力を捨てたかった。捨てたい要らないと振りほどいても力は深くまで刻まれていた、朝顔のような青い鴉が与えられるほどに。
「この力を振りほどけないのならば、」
この世界を混乱させてしまおうか。混乱、いい響きの語だ、新月をたくさん増やして半月は閉じ込めて教材にする、新月は自分達の使命を知って確実に果たす。そうして遂に貴女は自由になれる、この世界を護り続ける生活から離れられる。
それが、俺の願いだった。初めて自分で叶えられる筈の願いだった。だってそしたらね、
寂しがりやに
逢いに来てくれると思ったの
力がどんどん抜けていく。与えたのはソッチなのに奪う権利くらいくれたっていいじゃないか。悪態を吐く口は閉ざされ身体が爪先から失われていくこの感覚、あの時ととても似ているけれどもう翡翠になることは出来ないだろう、ならば、せめて。泣いているでしょう貴女も、それが俺の為ではないと思うけれど、若し、万一に俺を想っての涙なら、俺は貴女の雪になるよ、今度こそ。
五十二「歴史のはじまり」
「生意気だ!雪の虫ケラ達と三日月一人で、歴史に抗う気か?どちらも僕が捨てたゴミなのに!」
彼奴の長々と鋭い爪がアナベルの喉元を刺すもその策は破られ寸での所で固い水の防壁が食い止めた。勢いをたちまち削がれたシロツメクサは二、三歩よろけバランスを崩すも背後に回り込む足音を聞き逃さない。背中を錫杖で振りかざし氷の雷撃を見舞おうとしたアナベルの頬を隠していたもう一双の爪の牙で肉を深く切り裂き飽き足らず耳も半分喰らわれた。
「三日月さん!」
それでも人は私を呼ぶ。
そしてあの子達が傍に居る。
「僅かの頬肉と耳を喰っただけで満足か?」
私は負けない。最後の大番狂わせがさぞあるかのような声色でシロツメクサを挑発する。
「私の世界を捨てた怪物が、これしきで喜ぶのか。貴様もっと貪欲ではないのか。」
怯えて震えて縮こまる者達が重ねて来たもの、重ねるつもりは無くても重なり積もって来たもの、それはやがて後になるほど高くなり地面にあるのに遠く離れて人間に拒絶されていく、地下も天上も支配したがった癖して、いざ自分達の理解が届かない距離になれば手の平を返して突き落とす。讃え上げて認めない、握手をしても許さない、弱さこそ人間だなどと宣って、空を傷めて空の下を堂々闊歩する嫌な者、きらいな者、僕自身がそんな者を守らなくちゃいけないなんて、如何してだろう?
「人間なんて嫌いだ。」
光は眩しいもので
貴方を奪った奴らが憎くて
「中途半端な光なんて嫌いだ。」
ごうごうと、ごうごうと景色が騒ぐ、また、また、夢の中じゃない筈なのに。
「シロツメクサ。」
苦しい息の下でアナベルが問う。
「貴方も始まりは、新月だったのではないの?」
隙間漏る青空の細い指先から、懐かしい雫が落ちていく。
歴史の生まれた日なんて誰も知っていやしないだろうなんて高を括っていた。自分自身も生まれた時から「はい貴方は歴史です」なんて任命された訳じゃない、気が付けば僕は人の世界の側に立っていて、いつの間にか人の存在を認め続ける仕事を任されていた。
存外楽な仕事だった、たゞ眺めていればいいだけ、それで勝手に身体は積み上げられて行く。最初の内は振り返る者などいなかったが気が付けば僕を研究する者達が現れだした、未来の為に過去を学ぶ風潮が生まれたらしい、気分は良かった。
何が起きても干渉は出来ない。手を差し伸ばした瞬間に自身が歴史でなくなるのだと直感で分かっていたから。でもある時、あれは雨美とそのお姉さんが死に別れる一週間程前のこと、ふと心に思ったことがある。
「歴史でなくなれば自分は何者に戻るのだろう。」
その日は雨が絶えず降っていた。妹を失った姉の身にも。
彼女が憲兵を殺しに行こうとするのを、手が激しく痛むのも忘れて引き留めた。
「君じゃ駄目だ」
叫んで叫んで、憲兵をドブに突き落した、打ち処が悪くなるように。
干渉したら自分の意識は失われるのだろうとぼんやり考えていたが、失うどころか知らない記憶がやって来た。それは、自分が大切な光を亡くした記憶、奪われた記憶、強く流れ込んで来たのは泥の底から手を引かれた感触、空気が近くなって来た胸の痛みと眩しさ、そして名前を付けてもらったあの言葉。
「新月。君達の名前が新月だよ。」
それがはじまりだったのだろう。
五十三
「週末の犯罪魔、奴を手に掛けたのは、また記憶をくれると思ったから?」
暴れるシロツメクサの肉体に杖で殴りを打ち入れる。怯むことなく反撃をする牙はアナベルの血で少し染まり始めたが、攻撃を受ける度彼女はすぐさま彼から離れ、傷を軽く治してはまた叩き込む。水と雪の檻で閉じ込めきれないまでにもう歴史は狂っていた。
「次に知ったのは序の末路じゃないの?」
だからそんなに怒っているんでしょう。
「貴方はただ、自分をすくい上げてくれた者に報いたかったんじゃなかった、違う?」
「違う、違う!僕は人を守らなきゃいけなかったんだ、だから歴史になった筈なんだ!」
「貴方のその使命は、志願したものじゃない。シロツメクサ、貴方は気が付いたら歴史になっていたんじゃないの?責務を負ったのは特に理由も生じなかったんじゃないの?」
「駄目だ!それじゃ駄目なんだ、名付けられた光を捨てて裏切るような名前になって新月じゃなくて人間を守り続けて来た事が、理由など無いじゃ済まされない、許されない!」
焦る怒りと窶れた悲鳴。アナベルの行動パターンを読んだ理性は風の矢を番える肩に喰らいつくを止められなかった。
「三日月さん!」
満月の力は三日月の器には大きすぎた。人より色素のやや薄い血が地面に染みて広がってゆく。自分の息が切れる音、ポトリポトリと滴る音が交互交互に聞えてくる。
「それでも」
自分が出来損ないだなんて感づいていた。だって弟一人守りきれなかった姉だもの。
「それでも」
雪は私を見捨てなかった、どれだけ薄まってしまった序だとしても、三日月様と慕ってくれた。
もう声を出すのもキツイ。
「それでもね、シロツメクサ。」
きっと世界は在ろうとするものだから、
「貴方を助けた序は、君のこと悪く言わないわ。」
温かい。冷たく痛みが広がるばかりだった肩に、温かい涙の音がする。
五十四「カーテンコール」
「三日月さん、大丈夫ですか?」
「しっかりしてください!」
「私達守られるばっかりで…」
「何も出来なくて、本当にごめんなさい、怖くて…」
いいの、私への言葉なんて。
「あのビル。」
指差した建物は、この世界で一番高いビル、百貨店だ。
「階段…多分もう川にはなっていないだろうから、あの建物の屋上に行って、見えてる空に手を伸ばしなさい。そうしたらきっと人間の世界に帰れるから。」
「三日月さんは?貴女はどうするの?」
「私は…此処に残る。私の世界は彼方側じゃなくて、此方側だから。」
もう大分崩壊しているけれど
「まだやる事が澤山あるの。」
正直今は寝たい。ごめんね、あなた達を本当なら送って行くべきなのだけど、今はとにかく眠りたくて堪らない。
「じゃあね、みんな気をつけて。」
人に背を向けて、私は歩き出す。
境内は静かで綺麗だった。もう新月が暴れていた残骸も無ければ、荒らされた名残も、翡翠の花も消えていた。
きっと、空に溶けていったのだろう、人間の見る空に憧れていたのかもしれない。あの裂け目から優しい色を見た時に、誰も残らず彼方側に渡って今頃何か全く別のものに身を変えているかもしれない。
「新月は歴史にだってなれたんだもの。」
苦笑いしたけど、ちょっと楽しい。
懐かしい大樹の下にようやく座る。あの子達ちゃんと人間の世界に戻れたかな、私の強がりバレてないかな、本当はもう何かをする事なんて出来ないの、とうとう此方側の世界はあなた達からさよならしなくちゃならない。みんなでゆっくり寝よう、私達ずっと起き続けていたんだもん。力が入らない肉体は、思考することと想うことだけを為している。
アナベルの疲れた美しい横顔に、白い蝶々が一羽留まる。他は皆空に吸われるようにお別れをしたけれど、この一匹だけは三日月の傍から離れない。蝶が羽を泉が囁くように鳴らした時、横たわる娘のもう片方に接吻をするように頬に三ツ葉とフリージアが。
その草花は最初一本二本程度であったが、寝息に合わせて搖りかごのように優しい波紋を広げてたくさんたくさん咲き始めたら、秘密の図書塔にまた一つ星が灯る。青白く燃えるその炎に連れて、花々のように光が一輪ずつ増えていく。
この星達の炎と光は、人間達にも届くだろうか。
終
「動かぬ星」