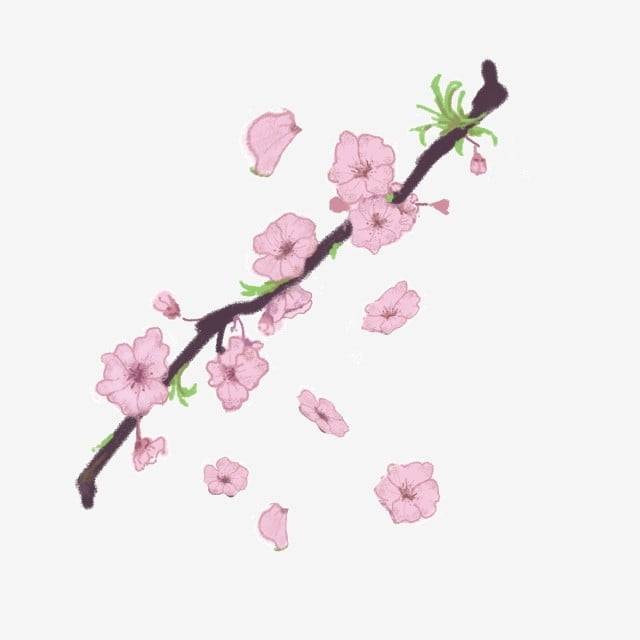
すもも
A4小説 #4
いつも桃のふわっとした、甘い香りのする人だった。シャンプーなのか、大好きな桃の水からなのか。それはとても優しくて、華やかな匂いだった。
僕と君が出逢ったのは中学生の時。まだ恋の何かも知らない馬鹿で、女の子に変に興味を持つ年頃で、ご多分に漏れず僕は君に恋をした。席替えで隣の席になって、授業中にたまに目が合うだけで僕は勝手に勘違いして、君を好きになった。今思うと何て単純なんだろう。ただ、今よりもずっと純な気持ちで、僕は恋をしていた。
「変わらないね」
そう君に言われた時、僕は不服だった。あの時のままではなく、君よりももっと、もっともっと大人で居たかったから。二十歳になった人間が謎に集まる成人式、その場に君は居た。周りの同級生から「京都の私大に行ってるらしいよ。あんだけ綺麗じゃ、男いるだろうな」と聞いた時、僕は奇妙な気分に駆られた。もう、というか元々自分のものでも無いのに、他の男に取られたようで居心地の悪さを覚えた。付き合っていたのはもう五年以上前のことで、というかそれも『付き合う』の風上にもおけないような儚い関わりだったのに、僕は傲慢だ。示し合わせて二人で登下校して、たまに手を繋いで、好きな歌を二人で口ずさんだ。変な区切りで記念日を祝って、ありもしない永遠をいつまでも祈って、そしてこれが愛なんだと知った気になった。でもそれがあの頃は幸せの全てだった。
「変わったよ。ほら背、高くなっただろ?」
「確かに。あの頃はほとんど一緒くらいだったもんね」
「そうだったか」
「ま、そういう風に張り合うところ、やっぱ変わってないけどね。」
「うるさいな」
同級生たちの喧騒から離れて、僕たちは二人で話した。いつかと違って、こそこそもせず堂々としていると不思議な気分になった。昔の知り合いというだけじゃない、いけない人に会っているようなそんな感じで。
「京都、いるんだって?」
「うん。誰かに聞いた?」
「まあね」
「一人暮らしだよ、大変だけどね」
女子の一人暮らし。そう聞いて、その家に彼氏を連れ込んでいるのかもなと不埒な想像をしてしまった自分を僕は戒めた。周りの女子と違ってドレス姿の君はその首元に細いネックレスを留めて、穏やかな性格には似合わないピンヒールを履いている。その姿を一瞥して「時間が、経ったんだな…」と僕は時の流れを思い知った。
「でも、その匂い、変わってないな」
「匂い?」
「そう。その、優しい匂い。」
何かを言い返したくなって溢した言葉は、恥ずかしいものだった。でも君は少し頬を赤らめたかと思うと「覚えて、たんだ」とうつむいて呟いた。僕たちがなぜお別れをしたのかは覚えていない。けれど、甘酸っぱい記憶は、二人の中に今も息づいていて、それは昔の小さな恋だった。
「そういうところ、嫌いじゃないよ」
「え?」
「好き、とは言ってないけどね」
「知ってるよ」と憎まれ口を叩いても、君は罪なくらい可憐に笑っていた。今の彼氏はどんな人なのだろう。この子を幸せにしてくれるんだろうか、なんてのは僕の考えるべきことじゃなかった。
すもも

