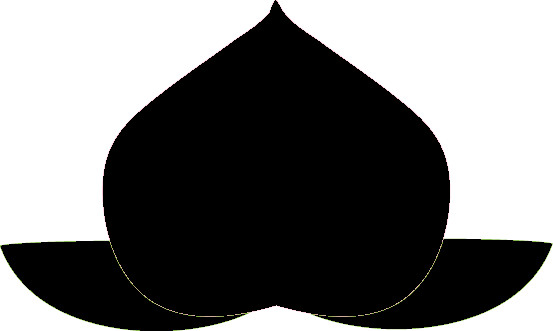
嘘に満ちた<桃太郎>
序章
むかしむかしあるところに、おじいさんとおばあさんがいました。
おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。
おばあさんが洗濯をしていると、ドンブラコドンブラコと、大きな桃が流れてきました。
おばあさんは、その桃をたいそうひどく気味悪がりました。その桃は、人間一人入っていると言われても信じてしまうくらい大きかったのですから、それも当然でしょう。
けれどおばあさんは、その桃を拾いました。確かに気味悪く思いはしましたけれど、おばあさんの家はたいそう貧しく、日々の食事にも困る有様なのです。だから、そんな大きな食料を見つけたら、それを持ち帰らずにはいられないのでした。
家に帰ると、すでにおじいさんは帰ってきていました。
「おじいさんや、大きな桃を見つけたぞよ」
「おお、よくやったばあさんや。では、早速切ろうかのう」
おじいさんは台所から包丁を持ってきて、桃に刃を入れました。
しかし、桃には傷ひとつ付きません。
不審に思ったおじいさんは、桃を持ち上げました。
すると、なんということでしょう。今までビクともしなかったあの頑丈な桃に、亀裂が走り、そして、割れました―――
「なっ、これは、なんということじゃ……」
「そ、そんなっ……」
二人の表情は、途端に曇りました。
それもそのはず。桃は、桃ではなかったのです。とても堅い木箱のようなものを、桃の形にしただけのものだったのです。彼らは食べ物を望んでいました。けれど、見つけたものは食べ物ではなかったのです。
その中に、何か食べ物が入っていればまだ救いはあったでしょう。けれど、そう上手くはいきませんでした。
その中には、赤ん坊が入っていたのです――――
男の子は、再び桃箱の中に入れられて、川に流されました。
第一章「二人の桃」
1
「なあ、親父」
「どうした、太郎?」
「次は、いつ村を襲うんだ?」
「ガハハハ!んなの決まってるだろ!金かメシがなくなったらだ!ガハハハハ!」
「そっか。そりゃそうだよな……」
「あぁん?なんでぇ、それがどうしたってんだ?」
「俺も、そろそろ街を襲ってみたいんだよ!俺は、俺のことを捨てたり、親父たちがいない島を攻めてくるような人間が許せない。だから、俺の手でアイツらに復讐してやるんだ!」
「ああ、はいはい。お前それ何度目だぁ?いい加減聞き飽きたわ」
俺の名は桃太郎。桃の形をした箱に入っていたから桃太郎。なんて安直な名前なんだろう。でも俺はそれでもぜんぜん構わない。俺のことを拾って、育ててくれた親父たちに文句なんてあるはずがない。
まあ、いきなりだってのは理解しているけど、親父は人間じゃない。鬼だ。人間共の村を襲って、金品や食料を巻き上げることで生計を立てている。
俺は人間だから、そんな親父のことを恨むべきなのかもしれない。けれど、俺は人間のことが大嫌いだ。できることなら俺だって鬼になりたい。
俺は、実は親父の本音が分かっている。
親父は、俺が村を襲うのを邪魔している。
俺はもう十八歳だ。本来なら――本当の鬼の子なら――とっくに村を襲う仲間に入っていてもおかしくない。
けれど、俺はいつまでたっても仲間に入れてもらえない。
親父は俺に行かせたくないのだ。
その理由は…………いや、やめだ。それを考えるのはやめよう。それは何もいい結果を生むことはない。悪い結果を生む可能性は、とんでもなく高いっていうのに。
けれど、頭ではそう分かっているのに、考えずにはいられない―――
人間と鬼とでは、当然だが基礎体力が段違いだ。
成人男性と五歳程度の鬼とでちょうど同じくらい。
そして、鬼の子が村を襲い始めるのは十歳。そして俺はもう十八歳。
つまり、俺は、足手まとい、なのだ―――
でも俺は、そんなことで諦めたくない。
親父は俺が人間に捨てられていたのを救ってくれた。
それはどうやっても返すことのできないくらい大きな恩だ。
だけど、だからといって恩を仇で返していいはずがない。
俺は少しでも親父に恩返しがしたい。
だから――――
鬼たちは、幾つかのグループに分かれて略奪をする。現在の鬼の総人口は約二千。その内、略奪をするのは十歳以上の男のみ。つまり、約千名だ。それを一班から五十班までに分けている。その間、女鬼は子供の世話をしたり、武器や船を造っている。人間ならばその仕事も男がやるものだが、鬼は人間とはスペックが桁違いだ。だから女でもその程度は造作も無い。
本日は一週間振りとなる略奪の日だった。
鬼たちが船へ乗ってゆく。
できることならば俺も一緒に船に乗って行きたいところだが、親父を始めとした鬼連合――鬼たちの自治組織。ここ鬼ヶ島では、彼らに逆らうと生きてはいけないというくらい強大な権力を持つ――に、俺を略奪に行かせてはならないと全鬼に伝えられてしまっている。俺は人間だから、鬼たちが皆持っている二本の角を持っていない。だから船に忍び乗る前にバレてしまうだろうし、それに俺が船に乗ったことが鬼連合の連中にバレたらその班の鬼たちに迷惑がかかってしまう。
これは俺のわがままでしかない。他の誰かに迷惑をかける訳にはいかない。怒られるのは俺だけじゃないといけない。だから結局のところ、俺が取れる手段はひとつしかなかったということだ。
船を造る、それしかない。女鬼たちは随分と容易くやっているように見えるが、あれでけっこう重労働だとか。そうやって近所のおばさんが漏らしていた。まあ、当たり前といえば当たり前ではあるが。鬼たちはみんな見えっ張りなのだ。
今日から略奪に同伴したいところではあるが、まだ船はできていない。というか、まだ造る技術すら身に付けていない。とりあえずは女鬼たちの作業を盗み見るとか、マニュアル本を読み漁るとか、そういった手段に頼るしかない。そんな付け焼刃の知識で海を渡る船を造るなんてのは、単なる夢物語なのかもしれない。いや、きっとそうなのだろう。けれど、それ以外に方法がないのだから仕方がない。
それから俺は、見て読んで、少しずつではあるが確かに知識を身に付けていった。
けれどそれはあくまで「知識」でしかなく、「技術」には程遠いものでしかなかった。
2
私は鬼が嫌いだ。
鬼とは、それすなわち悪である。
奴らは自分たちが楽をして生きるために村を襲い、人々の生活を無茶苦茶にしていく。私の大切な人達は、そんな奴らのせいで命を落とした。
私はとても幼い時に両親を亡くした。鬼に襲われたのだ。だけど両親は死の間際に私を逃してくれた。その私を拾って、育ててくれたおじいさんとおばあさんには感謝してもしきれない。
私達はとても幸せに暮らしてきた。村には頻繁に鬼がやってきてはいたけれど、私達の家は村の奥の方にあるから今まで無事だった。けれど一週間前、ついに鬼が私達の家を発見した。
鬼どもは私を犯そうとした。それをおじいさんが必死になって助けてくれた。だけど、そのせいでおじいさんは死んでしまった。私はおじいさんのお陰で犯されずにはすんだけれど、けれどおじいさんが死んでしまうくらいならまだ犯されていたほうが良かった。私は泣きながら、おばあさんにそう言った。するとおばあさんは、「そんなことはない。わたしは、桃子が無事で嬉しいよ。おじいさんもきっとそう思って死んでいったはずじゃ」と言ってくれた。
その日の夜、私が寝てからおばあさんが泣いているのを見た。それを見て、私は決心した。鬼を、必ず討ち滅ぼすと。
行動は早い方がいい。私はすぐさまおばあさんに鬼退治に行くと告げた。もちろんおばあさんは反対した。けれど、私の意志は強く、どれだけ反対されたところで気持ちは変わらなかった。おばあさんの考えも、変わらなかった。
だから私はおばあさんに断りなく鬼ヶ島に行く事にした。行ったからって勝算なんてないし、きっと何もなすこともできずに私は犯されて死ぬことだろう。でも、そうせずにはいられなかった。こんな衝動的な感情に動かされて死ぬなんて、傍から見たら馬鹿もいいとこなんだろうけれど、私の死ぬ方としてはそれも悪くはないんじゃないかと思う。
夜に準備をし、朝早くに家を出た。おばあさんは朝が早いほうなので、かなりの早起きになった。まだ空は真っ暗で、けれどまったく道が見えないという程でもない。私は歩き出す。死への一歩を。
歩く、歩く、ただひたすらに、歩き続ける。
鬼ヶ島の場所は、村の誰もが知っている。何年か前、とある村の青年が決起し、鬼ヶ島を攻めたことがあったのだ。そのとき、その青年が村の集会場にみんなを集めて鬼ヶ島へのルートを説明していたのだ。でも結局、誰も彼に賛同するものはなかった。誰の目から見ても、それは明らかに分の悪い闘いだったからだ。村に来た鬼を打ち倒すことならば、事前に周到な準備をしていればできないことはないだろう(もっとも、その後に大群で来られた場合は勝率0パーセントだけれど)。だが、鬼たちの本拠地に乗り込んで勝利することなど、不可能である。奴らがいったいどれだけいるのかは誰も知らない。しかし恐らく百人はいることだと思われる。我々の本拠地、すなわち村で用意周到にしても十体の鬼を倒すのが精一杯なのに、その十倍以上の鬼を倒すことなど、できるはずがない。
その青年は、「きびだんご」という筋力増強剤、さらに鬼でさえ死に至らしめる猛毒の二つを開発し、鬼退治に向かった。途中で彼を見かけた人の話によると、彼は犬、猿、雉と一緒だったそうだ。それには村の誰もが笑った。鬼を舐めているにも程がある、と。
だが、青年は勝利した。勝利して、しまった。ちょうどその時は子鬼と女鬼しかおらず、男鬼に比べればひ弱な鬼たちを、彼は倒したのだそうだ。これには村の誰もが驚いた。だが、村人たちの態度は彼のある発言によって逆転した。どうやら彼は、鬼の命を奪ってはいなかったのだそうだが、宝を奪い帰ってきてしまったのだそうだ。そんなことをされれば、鬼たちが人間たちに報復し、宝を取り返そうとするのは当たり前で、だから、誰もが想像した。鬼の軍団により、恐ろしい、悪夢のような状態になってしまう村の姿を。
案の定、鬼たちは攻めてきた。どれだけの鬼がいたのか、それを数える余裕のあるものは誰一人としていなかった。だが、今までの数倍にもなる鬼たちの猛攻による村の被害は収まることを知らなかった。家は焼かれ、田畑は踏み荒らされ、女は犯され、男は殺され、全ての村人がたちまち絶望に叩き落された。
鬼ヶ島を攻めた青年は、すぐに鬼に捕まった。彼は相当酷い殺され方をしたそうだ。
でも、そんなことは私にとってはどうでもいい。言っちゃ悪いが、その男は自業自得だからだ。でも!私達はそうじゃなかったはずだ!私のお父さんが、お母さんが、何をしたっていうんだ!?一人の身勝手な男のせいで二人は殺された!!私は、どうあってもあの男が許せない。
だけど、なら、私が今していることはなんなのだろう。私はあの男とまったく同じ事をしている。このままでは村はまた襲われるかもしれない。そんなことは絶対にあってはならない。だから私は、鬼を皆殺しにする。そうすれば村への報復なんてできるわけがない。
やっぱりそれは建前でしかなく、本当はただ私がそうしたいだけなんだけれど。
鬼を退治すると言ったって、私一人ではどう考えても不可能だ。だけど、村の誰かに頼むわけにもいかない。それに、きっと頼んだところで誰も手伝ってはくれない。いや、それどころか必死になって止めさせようとするだろう。だから、私もあの男のように動物を集めるしかないのだろうか……。
「なあ、お嬢さん」
物思いに耽っていた私に、突然声がかけられた。
「はい、なんでしょうか――っ!?」
声の正体に愕然とする。だが、もう遅い――
それは山賊。それも一人や二人ではない。私は既に囲まれていた。完全に、アウト。
もう、私の未来は、確定した――
あれから何日が経過したのだろうか。
はじめはそんなことを考えるような余裕はなかった。
けれど、時が経つに連れ、何も感じなくなり、ふとそんなことを考える余裕が生じた。
今日は五人。昨日は四人。その前は八人。さらにその前は―――
ああ、そんなことはどうでもいいや。
また新しい男がやってきた。
今日は何もさせられるんだろう?
咥えさせられるんだろうか?それとも挿れられるのだろうか?
まあ、そんなことはどうでもいいや。なるようになるよ、きっと。
同じようなことばかりをする日が続く。
時折すごい要求をしてくる男もいたけれど、それも何度か続けば新鮮さは失われ、マンネリ化する。
だから、今日は何をされるのだろうか、なんて考える気にもならない。
もう、どうにでもな~れ。あはは。
そんなある日、私の日常は脆く崩れ去った。
妙な格好をした少年が私のいる小屋にやって来た。
少年は、私の姿を見て、とても戸惑って、そして何かに対して怒っていた。
そんなときに、いつものように男たちがやって来た。
すると少年は、その男たちの首を、なんの抵抗もなく、はね落とした。
「なんだよ、なんなんだよこれは!やっぱり人間は許せない……。こんな、なんの罪もない女の子に、こんな酷いことを……!!いったい奴らはどれだけ罪を犯せば気が済むんだ?どれだけ、俺を、苦しめるんだ……!?」
少年が何かを叫んでいる。でも私は何も理解できない。
だって私はとうの昔に壊れてしまっていたから。
男たちの手によって、壊されてしまっていたから。
何もかもが、遅すぎたんだ―――
少年が泣きながら私の近くによってきて、そしてそのまま私の意識は途絶えた。
第二章「初任務」
1
あれから、五年もの歳月が流れた。でも、未だに俺は船を造れていない。もしかしたら、俺には親父たちへの恩返しと俺自身のための復讐、そのどちらも叶えることができないのだろうか―――
鬼連合に呼び出されたのは、ちょうどそんなときだった。
「お前に初任務を命じる」と、鬼連合会長。
「え……!?」
「今から案内する小屋に囚われている者を救出してくるのだ」
「え、あ、うん。でも、その程度のことをどうして俺に?」
「逆だ。その程度だからこそお前にやらせるのだ」
「なっ……!!」
「重要な任務を貴様のような人間ごときにやらせるはずがなかろう」会長は、何が間違っているのかとでも言わんばかりに俺を見下ろす。
「この野郎っ!!」我を忘れて席を立つ。そして、会長に殴りかかる。
だが、
「ぐはッ……」
「人間風情が鬼に逆らうなど、身の程をわきまえんか。下郎が」
鬼最強である会長に俺ごときの力で歯向かうことなど不可能で。
「お前が仕事を欲しがったのだろう?だからやらせてやるのではないか。感謝こそすれ、そのように怒り出す意味が分からぬ」会長は蹲る俺の頭に足を載せる。
「会長、それくらいで……」鬼連合副会長、すなわち親父が、会長を宥める。
「ふむ、まあいい。おい人間!さっさと俺の前から消えぬか!!」
親父が俺を担いで外に連れて行った。
鬼連合は会長と副会長の中があまり良くない。その原因は、俺だ。親父は人間である俺を育ててくれている。でもそれは、他の鬼からしたら考えられないことなのだ。鬼たちにとって人間は敵だ。数十年前ですらそういう考えは鬼たちの中で蔓延していた。そこであの人間による鬼ヶ島攻撃だ。鬼たちの間では俺を処刑しろという考えがどんどんと広まっていった。そして、そのときの処刑派代表が鬼連合会長だった。
それから親父が必死でみんなを説得してくれた、幸運なことに、俺の処刑を反対する鬼は親父だけではなく、多くの鬼が親父と一緒になって会長を説得してくれた。みんなの熱意と誠意のおかげで俺は今もこうして生きていられる。だから俺は親父に恩返しをしたい。俺が略奪参加を願い出ているのはそれが理由なのだ。だが、親父はそれに反対する。もちろん俺のことを心配してくれているからだってことは分かっている。分かってはいるけれど、それが悔しくて悔しくてたまらない。きっと今回の件は親父が会長に頼んでくれたことなのだろう。本当に、俺は親父に迷惑をかけてばかりだ。
2
「なんだよ、なんなんだよこれは!やっぱり人間は許せない……。こんな、なんの罪もない女の子に、こんな酷いことを……!!いったい奴らはどれだけ罪を犯せば気が済むんだ?どれだけ、俺を、苦しめるんだ……!?」
案内された小屋に行くと、そこにはボロボロになった女の子がいた。どうやら山賊どもが彼女を辱めていたようだ。許せない。人間共は、どこまで腐っているのだ。
俺を女の子を背負って小屋から出た。そうしてお供の鬼に彼女を託す。
そして、俺は歩いて行く――
「どこに行くんだ?」お供の鬼が俺に尋ねる。
「ちょっと、トイレ」
「それくらい我慢しろ」
「もう限界なんだ。我慢出来ない。今行かないと、きっと俺はどうかしてしまう」
「ハァ、好きにしろ。副会長には黙っててやるよ」
「ありがと」
「だから、絶対に無事で帰って来い。ここでお前が死んだら副会長の努力が水の泡だろ。副会長だけじゃない。俺を始めとしたお前の味方みんなの努力が水の泡だ。もう一度言う、無事で帰って来い」
「うん……!!」
必死になって駆ける。目的地ははっきりしている。山賊のアジトだ。奴らを壊滅させてやる。俺一人では無謀だってのはわかってる。でもお供の鬼を巻き込むわけにもいかない。鬼たちは連合に無断で人間と争ってはならないのだ。その掟を破ると会長によって厳罰がくだされる。だから俺一人で行く。たとえ無謀だとしても、そうしないと俺の気は収まらないから。
周りは木に囲まれ、見晴らしは最悪。けれど誰かが近くにやってきたら木の揺れる音で瞬時にわかるであろう、敵から身を守ることをよく考えられているのかどうのなのか微妙な場所に、アジトはあった。
そここそが、今から乗り込む場所で、そしてもしかしたら俺の墓場になるかもしれない場所。
今ならまだ引き返せる。まだ、決定的な間違いを犯してはいない。でも俺には、ここで引き返すなんて選択肢は元より存在などしていなくて、だから迷うことなく小屋へ乗り込んだ。入りながら怒鳴ることもせず、走って入ることもせず、ただただ余裕な様子を装って、平然と歩いて進んで行く。
「誰だ?お前は」
「……」問いかけられるが、そんなことに答えるつもりはない。ただただ無言で前へ進む。
「誰だって、訊いてんだがな~?」
「……」何も、答えない。
「チッ、シカトかよ……」男の堪忍袋の緒が切れたようだ。つまり、ちょうど頃合いだ。
「ふんっ!!」
「ぐはっ……!?」
男が動くよりも早くナイフを突き刺す。
男―山賊―の周りにいた連中がどよめく。
だが俺は連中が動くよりも早く連中にもナイフを突き刺す。
刺す、刺す、刺す、刺す――
その場にいる者を、誰一人無事では済まさない位のつもりで、猛進する。
けれど、その場にいた山賊は十人以上。俺はたちまち押さえつけられる。
これで立場は逆転した。
殴られる、蹴られる、踏みつけられる。
俺の持っていたナイフで刺すようなこともなく、ひたすらに山賊は殴る、蹴る、踏む……でも、まだ終わらない――
なんとか立ち上がろうと努力する。しかしすぐさま山賊が踏みつける。
踏みつけてきた脚に噛み付いた。それにより、一瞬だけ身体が解放される。
だが、それはやはり一瞬でしかなく、立ち上がって逃げるにはあまりにも短い時でしかなかった。
再び押さえつけられる。
連中の怒りは頂点に達した。
攻撃がエスカレートする。
先程までは連中には明確な殺意はなく、ただ俺を弄ぼうとしていた。けれど今はもう違う。持ち主に反抗する玩具に価値はない。連中は明確な殺意を持って攻撃を続ける。
俺は所詮こいつらと同じ人間だ。鬼ではない。鬼ならばこの程度の攻撃は屁でもない。どれだけやられ続けたところで死ぬことはない。でも俺は、人間なんだ。だからいつかは死ぬ。そして、そのいつかは、もうそう遠くないことも分かっている。
俺は悔しい。俺には、結局何も出来なかった。一時の感情に任せて山賊を倒しに来たはいいが、それがこのざまだ。まったく、情けないったらない。英雄にでもなったつもりだったのだろうか。長いこと鬼だらけの環境にいたせいで、人間の強さを忘れてしまっていたのだろうか。たとえそうだったとしても、俺だって人間なんだから、複数の大人に敵うはずがないって、気付いても良かったのにな…………
どれくらいの時が経過しただろうか。いや、きっとそう長い時は過ぎていないだろう。俺がまだ生きているのがその証拠だ。だが、山賊たちにも疲れが見え始めてきた。だから、連中にはもう余裕がなくなっていた。余裕がなくなると人は何をするかわからない。子供一人を殺すことなんて、大人が複数いるんだから武器なんて必要ない。でも連中はそんな当たり前の思考ができなくなっていた。
山賊はナイフを持ってきた。桃太郎の持っていたナイフではない。それはただのナイフではない。鬼ですら死に至らしめるほどの猛毒を瓶から垂らして掛けている。そんなものを、人間の子供である俺に対して使おうとしている。なんて、愚かなことだろう。もう俺には抵抗する気力も体力も残ってはいない。だから殺そうと思えばすぐ殺せるのに、わざわざそんな物を持ってくるなんて、まったく馬鹿だなぁ。
眉間にナイフを突きつけられる。
もう片方の手には毒瓶を持っている。
どうやら、毒を掛けてじわじわと殺すか、それとも毒付きナイフですぐに殺すかを検討しているようだ。
これにてゲームオーバー。英雄気取りの坊やの冒険は、ここらで終了のようだ残念だなあ。リセットとかできないのかな?
そんな感じに、俺の精神はもう普通ではなかった。
だから、これから起きる出来事も、あたかも何もおかしくはないかのように受け入れてしまった。どれだけの後悔をすることになるかなんて、微塵も考えることもなく。
「うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!!」
案内役として一緒に来ていた鬼が、叫び声を上げながら突進してくる。
山賊連中は俺の時とは比べほどにないくらい慌てふためき、毒瓶を落とす。
でも、そんな状況でも、連中はどうすればいいのかを理解していた。
ナイフを、投げた。
血が飛ぶ。
何かが倒れる、大きな音がした。
その、血の持ち主は、その、音を出したものは、ついさっきまでとっても元気で、とても頑丈で、動かなくなる姿なんて想像することすら困難で――
「あっ…………」
でも、もう動くことはない。すでに、終わって(、、、、)しまって(、、、)いる(、、)。
山賊たちが歓声を上げる。唯一の脅威を除き、あとは瀕死のガキ一匹にとどめを刺すだけの簡単なお仕事。山賊の一人が今夜の宴会について話し始める。連中にとって、すでに今のこの時は終わったに等しい。
「ヒッヒッヒッ……」
下卑た笑いを漏らしながら山賊が俺の元へ歩み寄る。
俺は、そんな状況がとても辛くて、だから、逃げた。転がっていた毒瓶を拾いながら、走りだした。
「なっ!?」
最低限走るだけの力はまだ残っていた。だから、走る。できることならあの鬼を連れていきたい。けれど、そんな余裕はない。死ぬのが怖い。もう、気が収まらなくたって構わない。ただただ、怖い。人間が、怖い。
必死に必死に走り続けて、ようやく船の元へたどり着く。
どうやら山賊はすでに振り切っていたようだった。
船には助けた女の子が横になって眠っていた。助けたとはいっても長時間酷い目に会っていた事実は変わらない。だからやっぱり嫌な夢を見ているのかもしれない。表情からは何も読み取ることができない。もしかしたら夢を見る事もなく熟睡しているのかもしれない。もしかしたら夢のなかではとても幸せに過ごせているのかもしれない。俺は彼女に夢を見ていてほしくないと思った。これから彼女が行くのは鬼ヶ島だ。人間で鬼に好意的な感情を抱いているものは、俺を除き皆無といっていいだろう。だからきっと彼女もそのはずだ。ならば、いま俺がやろうとしていることは、本当に彼女のためになるのだろうか?彼女にとってはここでこのまま殺してやったほうが幸せなのかもしれない。でも、俺にはそんなことはできない。たとえかすかな可能性だとしても、彼女が鬼のことを嫌っていなくて、これからの人生を幸せに送れますように、と祈るしかない。
山賊のアジトで拾った瓶を胸に抱え、しばらく祈り続けていた。
そして、『桃太郎』は舞台から降りて、進行はナレーターが引き継いでいく。『桃太郎』はこの時点で主役の座を降りることになった。その主役の席を誰かが引き継ぐこともなく物語は進行していく。その席はきっと、彼だけのもの。その彼が席を放棄してしまったのなら、そこは空白のままであるべきなのかもしれない。
3
鬼は、人間と比べると確かに恐ろしく強大な存在だ。
だが、完全な存在とは程遠い。
人間と同じく、栄養摂取を怠れば死ぬ。だから鬼は当然食事を摂らなければならないのだが、鬼たちには自らの手で食物を作り出す術がない。人間たちを脅して稲作の方法を教えさせはしたが、どれだけ人間が丁寧に教えたところで鬼たちは稲作を出来るようにはならなかった。
鬼は、その超絶的な身体能力の代わりに、根気というものを持っていない。だからどれだけ教わったとしても、永遠に稲作をマスターすることはない。
そうなるとなぜ造船はできるのかという話になるが、鬼たちの造る船は基本的にイカダだ。それもかなり質の低いイカダだ。大陸と鬼ヶ島の間には、人間が泳ぐにはあまりに長すぎる距離を海が広がっている。だが、それはあくまで人間にとっての話でしかない。鬼にとってはそれくらいの距離を泳ぐらいは実にたやすいことで、つまり船が必要になるのは人間たちから盗んできた食料や財宝を運ぶ時だけなのだ。だからそこまで強靭なイカダを造る必要はなく、ゆえに鬼たちでも造船だけはできるのだ。
すると、なぜ桃太郎にはいつまでたっても船を造ることができなかったのかという疑問が浮かび上がってくることだろう。その答えは簡単だ。鬼たちはイカダを造るときに、力づくで木を切り落とすのだ。それには当然、かなりの腕力が必要で、だから人間である桃太郎には何時まで経ってもできるようになるはずがないのだ。人里で暮らせばすぐに木を手に入れる方法がそれだけではないと知ることになるのだろうが、桃太郎が大陸に渡ったのは初任務の時が初めてなのだ。そしてその時もすぐに島に戻っているので、結局知ることはない。ここから先、知ることになるのかもしれないが、それはまた別の話。
「桃太郎が帰ってきたぞ!!」
「おい、どういうことだ?案内役として一人付いていったはずなのに、そいつがいないぞ?」
「なんだなんだ、どういうことだ」
桃太郎が鬼ヶ島に帰ってきた。そこには桃太郎の養父であり、鬼連合副会長でもあるジャックを始めとした、『鬼人共生派』の鬼たちが待っていた。
彼らは桃太郎が無事帰ってきたことに安堵し、歓声を上げるが、すぐに異変に気づいた。
「太郎、一緒にいた鬼はどうしたんだ」ジャックが尋ねる。
だが、桃太郎は何も答えない。いや、答えられるはずがないのだ。
「う、うう…………」
「太郎……?」
「うわああああああああああああああああああああああ……!」
突然泣き崩れる桃太郎。周囲の鬼たちは当然のことながら困惑する。
なぜ、桃太郎は突然泣き始めるのだ?
なぜ、一緒にいた鬼がいないのだ?
そして、この女は誰だ?
桃太郎が島に帰ってきてから、はや一週間が経過した。
桃太郎の精神状態はまだ良好とは決して言えない。だが、そろそろ鬼連合会長の我慢は限界だった。早く同胞がどうなったのかが知りたくて、彼は桃太郎が帰ってきた日から一睡もしていないのだ。そんな様子は周りの鬼たちも心配せずにはいられなかった。だから、我慢の限界に来ていたのは彼だけではなく、多くの鬼たちも、なのであった。
彼は桃太郎を連合本部に呼び出した。もちろんジャックは反対した。桃太郎の精神状態が安定してからにして欲しいと、そう何度も懇願した。だがそれも最早限界なのであった。一週間待っただけでも、根気のない鬼にとっては奇跡の所業といえるかもしれない。
「…………」会長の前に桃太郎が跪く。だが目は虚ろで、とても報告などが可能な状態ではないことは誰の眼からも明らかだった。
「人間よ、なぜ共として用意したものが帰ってきていない?」しかしそんなことは会長にとっては瑣末なことでしかない。答えないのならば、殺す。彼は桃太郎がこの場に現れる前からそう決めていた。
「…………」もちろん桃太郎はその問いに答えることが出来ない。
「ふむ、よくわかった」会長が口元に不気味な笑みを浮かべながら言う。
「お待ちください!!」ジャックがすかさず口を挟む。彼は息子や部下の前では放埒な様を見せているが、会長の前だけではこのような態度となる。会長はかなり保守的で、上下関係にとても執着している。ゆえに、普段と同じ態度で彼に接した場合、たとえ副会長であるジャックであったとしても厳罰を与えられることは間違いがない。
そして、会長にとって人間とは階級の最下層に位置する存在である。そんな者が会長の問いに答えなかった。それはすなわち、その人間――桃太郎――の生命の危機を意味している。このまま放っておけば桃太郎の処刑はほぼ確実であった。だからジャックは口を挟む。
「なんのつもりだ、ジャック?貴様に発言権を与えた覚えはないが?」
「はい、申し訳ございません。その者に対する尋問ですが、私に任命していただけないでしょうか」
「今までの一週間がまさに貴様に任せていた期間ではないか?だが貴様はなんの成果を残すことも出来なかった。そればかりか、この人間は俺の問にすら答えない。こいつは確か、貴様が養っているのであったな。まともな教育はしっかり施したのか?この島で俺に逆らったら処刑ということは、全島民にとっての常識のはずだが?」会長は、ジャックの弱点を容赦なく突く。
「……申し訳ございません」それにはさすがのジャックも何も言い返すことはできない。
「俺は謝罪を求めているのではない。責任をとれと言っているのだ。恐らくアシックは死んだのだろうな、こいつの様子を見る限り」桃太郎のお供として大陸に渡った鬼はアシックという名であった。
「大切な同胞を失った責任をとれ、俺はそう言っているのだ」
「……切腹でもなんでもご命令ください……」ジャックには、そう答えるしかない。彼だってもちろん死にたくはない。だが、それ以上に己の愛息子のことを守りたかった。
「ああ、命じさせてもらおう。切腹しろ」
「…………はい」会長の取り巻きの鬼がジャックに金棒を渡す。鬼にとっての切腹とは、自らの力で腹に金棒を突き刺すことである。
「ああ、違う違う。切腹するのは貴様ではない。そこの、人間だ――」
「ふっ――――!!」
「なっ――――!?」
事態は、一瞬の出来事だった。会長が桃太郎に切腹を命じる言葉を口にした瞬間にジャックは金棒を会長の腹部に思い切り叩きつけた。
「な、何をする、貴様あああああ!?」
「うおおおおおおおおおおおお!!」
会長は突然のジャックの乱心に動揺し、反撃に移ることができない。
その隙を逃すことなく、ジャックはひたすらに会長を金棒で殴打する。
取り巻きの鬼がジャックを羽交い絞めにする。
だが、鬼連合副会長をたった一人の鬼の力で押さえつけることなど出来るはずもなく、ジャックはすぐに取り巻きを振り払い殴打を再開する。
その姿、邪神の如し。ジャックは一心不乱に殴り続ける。はじめは激しかった抵抗もしだいに衰えていき、今ではもう無抵抗のまま会長は殴られ続けている。命が途絶えるのもすでに時間の問題だった。
だが、そんな光景を目の当たりにしても、まだ桃太郎は自我を喪失したままであった。
ジャックはそんな彼の様子を横目で盗み見て、やはり落胆の年を隠さずにはいられなかった。だから殴り続ける。その攻撃には、現実逃避の意味も込められていた。
鬼連合会長は死んだ。副会長であるジャックによって、殺された。その事件はすぐさま島中を駆け抜けた。その知らせを受けて動揺しない者はいなかった。会長は、その傲岸で横柄な様から確かに鬼たちは不平不満を抱いていた。反対に、ジャックは皆からの信頼に厚かった。だからこのニュースは、鬼たちにはとても奇異に見えた。普段のジャックならば、このような気の狂った行いをするはずがなかったのだから。
そんな中、『人類家畜化派』である鬼の一人がこう言った。
「副会長殿はとても立派な方だった。そんな方がご乱心なさった理由、それはあの人間なのではなかろうか!あの人間を殺せ!」
その考えは、火のように島中を伝染した。今までは『鬼人共生派』であった鬼たちまでもが、桃太郎の処刑を要求した。
そうして、『鬼人共生派』の鬼は、次々と減っていった。
『人類家畜化派』は、その名の通り人類を家畜とし、今現在人類が持っている自由と領土を全て剥奪し、鬼が人類を統括することを目的とする派閥である。その頭目は、鬼連合会長であった。
対して『鬼人共生派』は、これまたその名の如く、鬼と人が共に暮らしていくことを目的とする派閥である。だが、これは断じて人類に対する略奪行為を廃止しようという意味を含んでいるわけではない。鬼たちが生きるためには人類から略奪をしなければならないのだから、それは当然のことといえる。そして、その頭目は鬼連合副会長ことジャックである。
『鬼人共生派』の思想を逸脱し始めているジャックのことを不審に思い、彼に尋ねた者がいた。
ジャックの一番の友、カイムである。
「ジャックさん、あんたはどうしてあの人間を育てると決めたんだ?あんたが未だに新しい嫁さんを貰えないのだって、やっぱりアイツのせいだと思うんだが……」
「……さあな。気づいたら俺が育てるってそう決めてたんだ。ガハハハ!」
「そんな、その程度のことで……。それなら、今すぐにでも考えを撤回するべきだ!」
「おお、そういえばカイム。前回の略奪品の中に今までに見たことない酒を見つけたんだ。一緒に飲むか?」
「なっ!?行く行く!俺んとこの班は前回ちょっと微妙でなあ。食料ならまあまあ見つけたんだが、酒は全くないときたもんだ!!ほんとありがてえよ、ジャックさん!」
「ガハハハ!おーし、今夜は飲むぞー!!」ジャックは笑いながら彼の家に向かって歩いて行く。そこにはもちろん、桃太郎もいる。
「……ジャックさん。あんた、酒ぜんぜん飲めないじゃねーかよ」ジャックの背中を眺めながら、カイムはジャックに聞こえないくらい小さな声でそう呟いた。
時は残酷なまでに進んでいった。
ジャックは桃太郎を救うため、鬼たちを説得して回った。
「会長を殺したのは俺だ!なのに、なのにどうして処刑されるのが俺じゃなくて桃太郎なんだ!?頼む、俺と一緒にみんなを説得してくれ!!」
だが、誰もジャックの言うことに耳を傾けてはくれない。
鬼たちは皆、基本的に人間が嫌いなのだ。
だからジャックが桃太郎を育てると決めた時も、皆が反対した。
それを、ジャックは一人で皆を説得して回り、ようやく鬼ヶ島の人口の過半数以上の賛同者を得ることができた。
その鬼たちは、信頼の厚いジャックの頼みだからといって賛同したのだ。だが、もちろんそれだけではない。人間ごときが何をしようと、自分たちには何も害を与えることなどできやしまいと思っていたことこそが、最大の要因であった。
しかし、今になって鬼たちは考えを改めるようになってきた。
まず、あの人間による鬼ヶ島攻撃だ。あの時、多くの鬼が人間の力を思い知った。それ以降の略奪行為が今まで以上に容赦がなくなったのも、再びそのような被害を受けたくないと心から思い、各々が独断でやっていることである。
そして、今回のジャックによる鬼連合会長殺害事件。この事件に人間は関わっていない。だが、人間である桃太郎の側にいるからジャックがおかしくなったのだという考えが広まってしまった。もちろん、誰もが桃太郎のせいだと思っているわけではないだろう。
しかし、
『人類家畜化派』の者は目障りな桃太郎を排除するために。
『鬼人共生派』の者は、ジャックの皆からの信頼を少しでも回復させるために。
目的は違えど、その両派閥は同じことをした。
もう、誰が何をしたところで、この鬼ヶ島にいる限り、桃太郎の処刑は免れない。
だから、ジャックは桃太郎と桃子を連れて、鬼ヶ島から大陸へと逃げ出した。
第三章「鬼ヶ島大攻撃」
1
これは、桃太郎の初任務から数年前の出来事。
人間、鬼、そのすべてを驚愕させた事件。
数年経った今でさえ、この事件の話をすれば鬼は苦虫を噛み潰したような顔をし、人間は恐怖に震え出す。
鬼には精神的に、
人間には精神的にも物理的にも、
計り知れないほど甚大な被害を出したこの事件。
その首謀者の名は、桃彦という。
2
村にはどんよりとした空気が漂っている。それも、かなり昔からずっと。
数百年ほど前までは村には活気が溢れていて、誰もが皆笑顔で暮らしていた。だが、鬼と名乗る者たちが現れてから、その様子は一変した。
はじめは鬼に抵抗する者も多かった。しかし、そのすべてが鬼の前には為す術もなく、無残に殺されていった。そして人間は、抵抗することをやめた。同時に、人々の間から笑顔が消えた。
なぜ鬼などというものが突然現れたのか。村人たちの間では『別の大陸からやってきた』という現実的な考えや、『神が我らに罰を与えるために鬼を創ったのだ』という幻想的な考えの二つが有力である。そのどちらが正しいのか、もしくはそれ以外が真実なのか、それはわかっていない。誰も鬼にそんなことを尋ねることなどできないのだから当然ではあるが。
そんな、人々がとっくに全てを諦めきって日々を過ごしていたある日。
「みんな、鬼ヶ島への道を発見した!奴らを倒しに行こう!そうすれば、これからは皆笑顔に満ち溢れた幸せな生活が待っているんだ!」
一人の青年が、立ち上がった。
「突然村人全員を集めるから何かと思えば……」
「若者の戯言なぞ、聞く価値もないわい」
「はあ……時間の無駄だった。まだ稲の収穫が終わってないってのに……」
「馬鹿な人」
「帰ろ帰ろ」
けれど、誰もまじめに耳を傾けようとしない。
鬼に勝つことなど不可能であると、身をもって知っているからだ。
「確かに今までの俺達じゃどうあがいても鬼に勝つことなんて不可能だった。でも俺は、『きびだんご』という団子を作った。山に大量に生えていた謎の草を使って団子を作って食べてみたら、突然力が湧いてきたんだ。なんでもできるって、そう信じられるくらい強い力が!これがあれば、鬼だって俺達の力で倒せる!」青年は、必死になって村人たちを説得する。
「なあ、桃彦。もういい加減止めないか?」桃彦の父、太郎が息子を宥める。
「これだけじゃない!たとえ鬼でさえ倒すことができるくらい強い猛毒もつくった!この二つがあれば、鬼なんて余裕で――」
「桃彦ッー!!」太郎が叫ぶ。
「っ……!!親父……。なんだよ、なんなんだよ!?お前ら鬼が憎くないのか!?ぶっ殺してやりたいって思わないのか!?そうかよ、そうかよ……。もうお前らの力なんて借りない。俺の力で、俺の力で鬼をぶっ殺してきてやる!!」そう言って、桃彦は駆けていく。
「待て、桃彦!」太郎が呼び止める。が、桃彦はそんな声を聞くこともなく、ひたすらに駆けていった。
周りは木に囲まれ、見晴らしは最悪。けれど誰かが近くにやってきたら木の揺れる音で瞬時にわかるであろう、敵から身を守ることをよく考えられているのかどうのなのか微妙な場所に、桃彦はいた。
「ごめん、村の人達は協力してくれなかった……」
「まあ、だろうなぁ……」
「過ぎたことは仕方ねえよ。ここから先のことを考えようぜ。俺たち山賊団だけでなんとかしないといけないしな」
ここは山賊のアジト。つまりここにいる連中はみな、山賊だ。もちろん、桃彦も。彼らは桃彦の村以外のところで多くの略奪行為をしてきていた。
だが、それらは決して楽な生活を営む為などではない。
鬼ヶ島へと攻めこむために必要な物を集めていたのだ。そして、その必要物資は全て揃い、ついに鬼が島を攻める時がきた。その計画には桃彦の村人の協力も計算に入れていたのだが、協力は得ることはできなかった。
「今まで通りひと月ごとに鬼が略奪に来るとしたら、それは明後日だ。もうこれ以上待ってはいられない。いいか、親分?」
「……ああ。確かにもう限界だ。俺の村の人達なら協力してくれると思ったんだけどな……だから今まで一度も攻めなかったわけだし。でも、もう仕方ないよな……。
よし!お前ら、出発するぞ!!」
「「「うおおおおおおおおおおおおお!!」」」
桃彦率いる山賊団が鬼ヶ島へと進み始めてから数時間後。
「アニキ!」突然大きな声が響いた。
「俺のことか?って、お、お前は――」と、桃彦。
「アニキ、どこ行くんですか?」
「万吉!?」
「ええ、そうですよそうですよ!アニキの子分の万吉ですよ!そんなオイラに何も言わずにどこ行くんですか!?」
「何も言わずに……?俺は村人全員を集めて鬼退治に行くと告げたはずだが?俺と一緒にいたければ、その時に名乗り出るべきだった。違うか?」
「そ、それは……」万吉は何も言うことができない。桃彦の言うとおり、彼もまた桃彦の宣言を聞いていたからだ。
「万吉」
「な、なんですか……?」
「村の人達にはさ、俺は犬、猿、雉をお供に連れて鬼退治に向かっていったとでも伝えておいてくれ」
「へ?それはどういうことで?」
「後ろにいるこいつらのあだ名みたいなもんさ。だから嘘じゃない」
「そういえば、そちらの人たちは……?」
「だから、犬、猿、雉だって」
「そうじゃなくて――ッ!?」万吉の腹部に強い衝撃が奔る。
「……」桃彦が殴ったのである。
「どう、して……」
「悪いな」
桃彦は万吉を抱き上げ、道の端に寝かせてから、
「待たせたな。行くぞ!」
そう山賊たちに告げて、再び歩みを進めた。
「ついに、来たな……」大陸と鬼が島を隔てる海を眼前にし、桃彦が呟く。
「おお!早く行こうぜ、親分!」犬が、いますぐにでも行こうと叫ぶ。
「待て、犬。攻めるのは鬼たちの略奪部隊が出発してからだ。だから、まずは情報を集めるんだ」と、猿。
「なら、いつも通り雉に探ってきてもらうしかないな」
「わかったよ親分。……そういやさ、前から気になってたんだけど、どうして俺が雉なんだ?俺は空なんて飛べないぞ?」雉が桃彦に尋ねる。
「理由なんてないさ。それでもあえて言うなら、そうだな……。お前が雉じゃないと都合がわるいのさ」
「親分にとってか?」
「世界にとってさ」
「意味がわからねーよ!」雉が桃彦に馬鹿にされていたと気付いて怒る。
「おい雉、無駄話はそれくらいにして……」
「うるせーよ猿!」
「うがああああ!めんどくせぇ!俺が一気に鬼どもをぶっ潰してくるぜ!」
「おい、お前ら……」
各々が自分のやりたいようにし始めてしまう。山賊は、こういうときに不便である。
「誰を、ぶっ潰すだと?」
突然低い声が響く。
それは、桃彦たちの誰の声でもない。つまり――鬼の声である。
咄嗟に構える桃彦たち。
だが、それは間違った選択であった。
声の主が動く。その動きはあまりにも速すぎて、動体視力にかなりの自信がある桃彦ですら何が起きたのかを理解するのに数瞬を要した。
「え……?」
「がっ、がはっ……!?」
犬が血を吐きながら吹き飛ぶ。犬がいた場所には、正拳を付き出した鬼が立っている。
桃彦たちは、鬼に見つかったと気づいた時に、すぐさま逃げるべきであったのである。
鬼は、たった四人でどうにかなる相手ではない。
しかも、桃彦は知らなかったが、この鬼は鬼連合副会長なのである。敵うはずが、ない。
「で、お前ら、何のようだ?物騒なことを言いやがった馬鹿はぶっ潰しまったけどな!ガハハハ!!」ジャックが笑う。
「ぁ……」
だが、桃彦に笑うだけの余裕があるはずもない。
彼は、これまでは本気で鬼にだってその気になれば勝つことができると思っていた。しかし、こうやって鬼の真の力を目の当たりにしてしまった今、そんな希望はガラリと音を立てて崩れ、後に残ったのはただ鬼に対する恐怖心のみ。
でも、と桃彦は思う。彼には責任がある。山賊たちを、自分が世間知らずであるばかりに、死地へと連れてきてしまったのだから。
桃彦は山賊の親分だ。だからせめて、猿と雉だけでも逃がしてやらなければならない。たとえ、そのために自分が死ぬことになったとしても、だ。
覚悟を決めた桃彦は、きびだんごを十個まとめて口に放り込んだ。
「親分!?きびだんごは身体にかなりの負担をかける。それを一気に十個も食べるなんて、馬鹿げてる……!!」
きびだんごの力は永続する。つまり、きびだんご十個分もの力が、人間という小さな器の中に在り続けることになるのである。そんなもの、普通は耐えられない。
「でもさ、猿……。確かに負担はかかるけど、ここでまとめて死ぬよりは幾分かマシじゃないか?逃げてくれ、お前たち!!親分として、お前らだけは逃がしてやるから!!」
桃彦がジャックに飛びかかる。
「うおおおおおおおおおおおおお!!」
「ガハハハハ!随分と威勢のいいガキだ!面白い、その勝負受けてやろう!!」
ジャックもまた、桃彦の元へ走り寄る。
両者が互いに右拳を突き出し、衝突する。
そのあまりの力の衝突に周りの岩が割れる。
もちろんこれだけで終わるはずがない。両者は再び攻撃を開始した。
猿と雉は逃げながら桃彦の闘いを見ていたが、そのあまりの疾さに彼らの目が追いつかない。
「す、すげぇ……」雉が彼らの親分の勇姿に対し、これ以上ないくらい素直な感想を漏らす。
「…………」
しかし猿は、雉のようにただ喜んでばかりいることはできなかった。桃彦は、自分たちを逃がすために、あのような無茶をしているのだ。それに対し、「すまない」と思いはしても、「すごい」だなどと喜んでばかりいることなど、彼には到底できなかったのだ。鬼退治は桃彦が言い出したことなのだから、言い出しっぺが責任を取るのは当然であるという考え方もあるだろう。だが、それはあくまで一般的にはというだけの話。彼は桃彦に己の命も含め、何もかもを預けている。だから桃彦のミスは彼のミスでもあり、ゆえにこの場で桃彦一人が責任をとって残ることが猿には我慢ならない。
猿は突然方向を変え、桃彦の方に走りだそうとする。
「っ……!!」
「やめろ!」
だが、それは雉の手によって防がれる。
「放してくれ、雉。俺は、親分を助けに行くんだ」
「俺だって親分を助けたいさ!だけどここで俺たちが戻ったら、親分の覚悟はなんだって言うんだ!?きびだんごの力はたしかにすげぇよ。でもだからといって、それだけで鬼に勝てるわけがない。そんなところに俺たちが戻ってみろよ?すぐに殺されるに決まってるだろ!!鬼ってのは俺達とは次元が違うんだよ、完膚なきまでにな!!だからせめて、せめて俺達だけでも生き残って、親分は最後に俺たちを鬼から救うっていう大仕事を果たしたことにしてやろうじゃねーかよ……。なぁ、猿?」
「…………お前に説得されるなんて、俺も落ちたもんだなぁ」まだ納得いってはいない様子ではあるが、少なくともこの場から逃げることを、猿は決心した。
「どういう意味だよ、馬鹿」
「さあな」
そして二人は走りはじめた。
「はあ!はあ!はあ!」
「……ガハハハ、なかなかやるじゃねーか、人間」
桃彦はまだ生きていた。鬼連合副会長であるジャックと闘って、まだ生きていた。
だが、このままいけばジリ貧だ。きびだんごは確実に桃彦の肉体を蝕んでいる。
「うわああああああああ!!」もうやけくそだ。桃彦は最後の一撃だとでも言わんばかりに猛進する。
「ふん」
しかし、そんな猪の如き直線的な攻撃は難なく回避されてしまう。
勢い余って桃彦は地面に倒れ込む。もう、彼に立ち上がる力は残ってはいない。
「ちくしょう、ちくしょうちくしょう!!なんでだ、なんで、ここまでやっても勝てないんだ?鬼ってのはいったい何なんだよ……。こんな強さ、反則だ……!」桃彦が嘆く。
「その通りだ」桃彦の嘆きに、ジャックが答える。
「その通りって、どういう意味だ……?」
「俺たち鬼の強さは、お前の言うとおり反則なんだよ」
「だから!それはどういう……」
「お前がさっき食った団子、あれ山に生えてた、なんか虹色というかとにかくそんな感じの神々しい色をした草から作ったんだろう?」
「なっ!?どうして知って……」
「俺達の強さの原因も、あれにあんだよ」
昔、ある男がいた。彼は木を切りに山へ入ったところで熊に襲われ、しかし命からがら逃げることに成功した。でもそこは、彼の本来のルートとはまったく違う場所で、彼にはそこがどこなのか分からなかった。つまり、遭難したのだ。
木を切ったらすぐに帰るつもりであったから、当然食料は持ってきていない。とはいってもどうしても空腹にはなってしまうもので。だから彼はなんでもいいから食べられそうなものを探した。
そして見つけたのが、なんだか神々しい色をした草だった。彼はそれを、微塵もためらうことなく口にした。すると、突然力が湧いてきた。
「ああ、これならなんでもできる!!」彼は叫びながら走り続けた。
途中で先の熊に出会った。だけど何も問題はない。今の彼には、なんでもできるのだから。
流石に余裕とまではいかないが、けれども普段ならば倒すことなど不可能であるはずの熊を、彼は見事に倒してみせた。もう笑いが止まらない。
再び走り回って、ようやく知っている道にたどり着き、下山することができた。
それから数年後、彼は結婚し、子供が生まれた。
その子供は他の子供達よりも力が強かった。男のきびだんごによって増幅された力が、子供に遺伝したのである。
男は、「これはいい、これなら畑仕事が楽になる」と思い、息子をあの山へ連れていき、あの草を食べさせた。そしてその草に名前を付けた。『虹神草』という名を。
その子供も、更にその子供も、自分の子供に虹神草を食べさせた。
しかし、あまりにも強い力を持ちすぎたせいで、彼ら一族は村人から気味悪がれてしまった。この島にはもう暮らせないと思ったその時の戸主が、離れ島への移住を決定した。その島こそが後の『鬼ヶ島』で、そして彼ら一族こそが、『鬼』の始まりなのである。
「そんな、話が…………」
「この話は鬼連合――ああ、鬼の自治体みたいなもんだ。それの会長に代々受け継がれる文献に書いてあった」
「っ、ということは、お前鬼の親分なのか……!?」
「いんや、俺は副会長だよ。ちょっと色々あって、会長が目障りになってきたんだ。だから会長の家に忍び込んで何か弱点でもねえかと思ってたら、その資料を見つけてしまい、真実を知ってしまった。そういうことだ」ジャックは彼の息子――桃太郎――の顔を思い浮かべながら桃彦の問いに答えた。
「まあ、そんなことはどうでもいい。あー、そういやお前、名前は?」
「桃彦だ」
「俺はジャックだ。で、お前。ちょいと頼みごとを受け入れてくれないか?」
「……内容による」
「なーに。ちょいと鬼が島を攻めてくれればいいんだ」
「はあッ!?」ジャックの唐突な依頼に桃彦は驚きを隠せない。いや、隠す気にすらならない。
「なんだよ、お前ら元々そのつもりだったんだろ?なら問題ねーじゃねーか」
「いや、まあそうなんだけど……」
「明日、略奪部隊が島から出ていく。その隙に攻めろ。ただし一人も殺すな。少し傷めつけるくらいなら構わないが、絶対に殺すな。もし殺したら、人間共は俺が何としてでも滅ぼしてやる――」ジャックが桃彦を威嚇するように睨む。
「っ……」効果は絶大。桃彦はすっかりジャックに逆らう気を失ってしまった。
「お前のその力なら問題はないさ。女なんてのは雑魚ばっかだ。まともに闘える奴なんて、人間にも鬼にもいやしない。というわけで、明日は頼んだぞ。ガハハハ!!」ジャックは言いたいことだけ言ってさっさと去っていった。
「あ……」桃彦は呆気にとられてしばらくその場から動くことができなかった。
「これで会長が責任を問われて辞職してくれればいいんだがな……」
ジャックのその呟きは、誰にも聞こえはしなかった。
「うおおおおおおおおおおおおッ――!!」
桃彦は怒涛の勢いで鬼が島を攻めた。ジャックとほぼ互角の戦いが可能な彼に敵う鬼は、略奪部隊を欠いた鬼ヶ島には唯一人として存在していなかった。
しかし、いくら桃彦と言えどもその力が永遠に続くわけではない。既に力は失われつつある。恐らく、次の日になれば彼は強大なる力を失い、そしてまた翌日には一般的な成人男性の身体能力を大きく下回り、いずれは死に至るであろう。だから彼は焦る。この怒涛の鬼ヶ島攻略は、そうした彼の焦りに寄るものである。そしてそれは、結果的には良い方向に働く。略奪部隊が島に帰投するまでにかかる時間はひどく短い。人間たちは既に鬼に抵抗することを諦めてしまっているので、鬼の要求にはなんでも素直に答える。よって、自然と略奪にかかる時間は短くなるのだ。最早これは、『略奪』ではなく『徴収』と言えよう。
桃彦はすぐさま鬼ヶ島制圧に成功した。彼としては、ここで鬼どもを滅ぼしてやりたかった。女鬼と子鬼が絶えれば、鬼は絶滅するはずだ。しかし、もしそうすればジャックによって人類は滅ぼされてしまう。それでは意味が無い。だから桃彦は唇を強く噛み、なんとか殺意を押しとどめた。それでも完全に我慢することはできなかったので、桃彦は鬼たちが今まで村人から強奪していった食料や宝物を取り返して、村に帰ることに決めた。
鬼ヶ島を瞬く間に制圧し、しかし誰一人として殺すことはなく、ただ食料と宝のみを奪い去っていく。桃彦のその行動は、鬼たちの自尊心を酷く傷つけた。彼女ら鬼にとって、人間とは劣等種族なのだ。そんな連中が、奇跡的に(と、彼女らは思っている)自分たちを倒し、なおかつ命を奪わなかったという行動は、彼女ら鬼を舐めきっていることを意味している、と彼女らは思ったのである。
彼女らは略奪部隊が帰投するとすぐに、休む間を与えることもなく再度村を襲うことを求めた。女鬼全員の請願には、さすがの鬼連合とはいえ逆らうことはできず、結局彼らは再び人村へと赴くことになった。
何もかも、ジャックの思い通りにはならなかったのである。
3
鬼たちの人村制圧は、桃彦の鬼ヶ島制圧など比べ物にならないくらい迅速に、冷酷に行われた。桃彦はすぐさま鬼に見つかり、虐殺された。それでも女鬼の怒りは収まるところを知らず、鬼たちはまだ暴れ続ける。
鬼は、長いこと人村を荒らし尽くしていった。田畑は荒れ、人々が出歩く機会は激減し、そんな人々を探して鬼たちは家を壊し、山を燃やした。
そこまで行って、ようやく女鬼たちの怒りは収まった。しかし、人々への被害は最早取り返しがつかないほど甚大なものとなっていた。それによって収穫量も減ってしまい、鬼たちもまた被害を受ける結果となった。
こうして、人間と鬼とを巻き込んだ前代未聞の事件は幕を下ろした。双方に多大な――多大過ぎる被害を与えて。
第四章「親と子」
1
ジャックが桃太郎と桃子を連れて大陸に渡ってから、一ヶ月もの時が過ぎた。その一ヶ月は彼らにはとても長い時のように思えていた。なにせ、様々なことが起きたのだから。
いくら鬼から追われてきたとはいえ、それでもジャックが鬼であるという事実は変わらない。だから当然人間たちには恐れられ、また鬼がジャック一人であるということから攻撃を仕掛けることを考えたものも大勢いた。桃太郎、もしくは桃子がそんな者たちを説得すればそれで一段落ではあったが、それは不可能であった。桃太郎も桃子も、依然放心状態が続いている。ジャックがどれだけ話しかけても、彼らは何も反応を示さないのだ。
今、ジャックは人間に見つかるたびに移動を繰り返している。既に島から持ちだした物資は尽きようとしており、そろそろこの旅も限界であった。
「はぁ、はぁ、はぁ……」
二人を抱えたジャックはついに限界を感じ、人村に降りてきていた。彼としては、略奪を行うつもりなど皆無であったが、この状況となってはそれも致し方ない。
しかし、この場に鬼はジャック一人しかいない。いくら鬼が強大であるとはいえ、たった一人では村を襲うことなどできやしない。その為に、桃太郎と桃子を連れてきているのだ。
「おいっ、人間ども!!このガキを殺されたくなかったらありったけのメシを持って来い!!」
人間には人質作戦が効果的である。大陸に渡ってから発見した書物にそう書かれていたのである。その人質として適任であったのが桃太郎と桃子というわけだ。
だが、そんな彼の目論見は、鬼という恐怖に震える現代の人間たちにとっては、脆く儚く、そして愚かなものだった。
「なぁ、鬼だぞ……?」
「ああ、鬼だな。それもたった一人でお出ましだ!」
「へへっ、これはよう、やっちまうしかないよな?」
「ギャッハッハッハ!!いくぜ!」
鬼は彼ら人間にとっては決して許すことのできなに、最凶の敵である。そんな奴が、たった一人で村にやってきて、さらにその鬼はかなり疲労しているのだ。ここで日頃の鬱憤を晴らさずにいられるわけがない。
「チッ、こんなとろこで暴れるつもりはなかったが……こうなったらやってやるさ!」
この村人たちの考えは、決して間違ってはいない。たとえ鬼とはいえ、こうも疲労していれば、人間の男四人もいれば楽勝だ。だがそれは、普通(、、)の(、)鬼(、)ならば(、、、)、という話でしかない。この鬼は、鬼ヶ島最強である鬼連合会長を不意打ちであるとはいえ破った、最強にして最凶の鬼――ジャックである。ゆえにこの人間たちの結末は既に決まっているも同然であった。
「うおおおおらあああああ――!!」
桃太郎と桃子を地に下ろし、ジャックは猛攻をかけた。村人たちはジャックのその動きに反応することができない。もともと彼らはジャックが疲弊して、まともに動くことは不可能だということを前提にしてジャックに挑んだのだ。だからここまで俊敏に動くことなど予想できるはずもなく、故に瞬殺されるのだ――
「嘘、だろ……」倒れ伏した内の一人がそう漏らす。彼以外の者は、既に息絶えている。
「残念ながら、コレが現実だ。貴様ら人間ごときが俺たち鬼に敵うはずがないんだよ。それを理解しろ。たとえ鬼がどれだけ疲弊していたとしても、それでも貴様らは勝てないんだよ。これが生まれながらにして絶望的なまでの差だ」
ジャックは完全に、完璧すぎるほど圧倒的に、そして完膚なきまでに村人を捻じ伏せた。全身から漂う圧倒的強者の風格。敗北など微塵も想像すらしていないであろう自信に満ちたほほ笑み。そう、人間はジャックの言うとおり、疲弊しきった鬼にすら敵いはしないのだ。
だがしかし、そんな鬼とはいえ、肉体的限界は必ずやって来る。満身創痍な身体に鞭打って圧倒的勝利を見せたのはいいが、それで彼の身体は限界を超えてしまった。
「げふっ……!!」
吐血する。今この場にまた村人が現れれば、その時こそ彼の命運はそこで尽きてしまうことはあまりにも明らかな事実であった。
そしてその場に、村人は現れた――
「もも、こ……?」現れた老婆が呟く。
「く、そっ――!」ジャックはさらに身体に鞭を打って立ち上がり、威圧する。
「桃子なのかいっ!?」だが、そんなジャックの精一杯な頑張りは、老婆の前には何も効果がない。決してジャックの威圧に凄みが足りなかったわけではない。普段ならば、きっとそれだけでこの老婆は息絶えていたことだろう。しかし今は、普段通りではなかった。
「桃子っ!!」そう、彼女こそが、桃子の育ての親なのである――
ジャックたちは老婆の家にやって来ていた。
「そう、そんなことが……」
「ああ……」
老婆はジャックを自らの家に連れてきていた。その目的は、当然桃子について尋ねることである。
ジャックは知っている限りのことを老婆に話した。ジャックも親だ。だから娘のことを心配する老婆の気持ちが、彼にはよく分かった。
「今日は、泊まっていってくださいな」ジャックが語り終えると、唐突に老婆がそう告げた。
「なっ、だが俺は鬼――」当然ジャックは困惑する。だから反論する・
「はい、そうですね。ですが、あなたは私の娘の恩人ですから。いえ、恩鬼とでも言うのですかね?ふふふ」しかし老婆がジャックの言葉を遮る
「もし俺を匿うなんてことが他の村人たちに知られたら……!!」
「私はたぶん、もうこの村にはいられなくなるでしょうね」
「だったら……!」
「でも、それでもあなたは娘の恩人なんですよ……。私の、いいえ私達の大事な桃子を救って下さった方に失礼なことはできません」
「失礼だなんて俺は思わない。だって俺らが人間に嫌われるのは当然だ……。俺らは、それだけのことをあんたらにやってるんだから……」
「そうですね」
「それが分かってるんなら……」
「私は鬼が嫌いです。おじいさんも、それに桃子の両親も鬼に殺されました」
「っ……」
「だから!私にはもうこの子しかいないんです……。この子を失ったら、私は……ううううう……」老婆が泣き出す。
ジャックは何も言い出せず、ただ、老婆を苦渋の表情で見つめることしかできなかった。
ジャックも妻を亡くしている。だから、家族を失うことの苦しみは、人一倍知っていて、それが故に何も言い出せない。こういう時に何を言ったって無駄だということを、実体験で知ってしまっているから。
だから、どうにかしてあげたくても何もできなくて、唇を噛み、老婆の苦しみを少しでも共有しようと励む。それだって老婆には何の意味もないことは分かっている。でも、彼の心はこうでもしなければ落ち着いてはくれない。いや、実のところはこの程度で落ち着くはずもないのだ。でも気休め程度にはなる。たとえ気休め程度だったとしても、今の彼にはそれだけでも十分すぎるほどにありがたかった。
そうやって自己満足を第一に考えてる自分に気付き、ジャックの心は再び沈んでいった。
そして、翌日。
既にジャックの疲労は癒えていた。鬼は人間よりもかなり優れた回復力を持っているが、彼はその中でもかなり優れている。彼は何事においてもほとんどの鬼を超越する能力を兼ね備えているのだ。そんな彼が島を抜け出して疲弊しきっているなどとは、きっと誰にも思いもよらなかったことであろう。
最も優れた鬼が、最も惨めな目に遭う。
人間よりも圧倒的に優れているはずの鬼が、人間以上に苦しんでいる。
ああ、なんて皮肉――
「じゃあ、そう言うわけでよろしく頼む」
「はい……ですが、本当によろしいので?」どうしても釈然といかず、老婆が尋ねた。
「ああ、桃子はもちろん、太郎だって人間なんだ。いつまでも俺のような疫病神と一緒にいるわけにもいかないさ」苦笑しながらジャックは言う。
そう、ジャックは、二人を老婆に託すことに決めたのだ。自分といたら幸せになれないことが、わかってしまっているから。
「だけど、婆さんも本当にいいのか?負担じゃないのか?」不安げに尋ねるジャック。
「ええ、大丈夫ですよ。爺さんがいなくなって、そして桃子までいなくなって、私は生きがいをなくしてしまっていました。ですが、あなたが再びこの子に会わせてくれた。この御恩を返さないわけにはいきませんよ。それに、最初にこの子を助けてくれたのは桃太郎くんなのでしょう?それならこの子だって私の恩人ですよ」老婆はとてもいい笑顔を浮かべていた。それは、今までにジャックが見たことのあるどんな笑顔とも違った。これが人間と鬼の違いなのか。それともこの老婆だからこそなのか。何の根拠もないが、ジャックは後者だと思った。
そうして、ジャックは桃太郎と別れ、再び山へと向かっていった。もう桃太郎も桃子もいないのだから鬼ヶ島へ帰ったとしても自分が罰を受けるだけなので問題はない。しかし、どうにも帰る気にはならなかった。別に罰を受けるのが嫌なわけではない。むしろ、罰は受けるべきだと思っている。それなのに、どうしてか帰る気にはならない。そんな自分に嫌気が差して、でもやはり帰る気にはならなかった。
山に向かったのはとりあえずの処置だ。老婆の家にいたままでは迷惑をかけてしまうことは明らかで、そもそもそれでは桃太郎と別れた事にはならない。山ならば人間に見つかる可能性も低いだろうし、食料だって探せばなんとかなるだろう。
なんとも楽観的な考えだが、それでいいと思った。今はもう、何も考えたくないと思った。
何も考えず、ひたすら無心で山を登り続けた。
ジャックは、もう二度と息子に会うことはないのだと悟っていた。
2
そして、数ヶ月が過ぎ、彼と彼女は――
「桃子や、久しぶりに一緒に釣りにでも行こうや。爺さんが大変上手で、私らはいつも悔しい思いばかりしてたのう……」
「そう、だね。……ごめんね、おばあちゃん。私のせいでおじいちゃんは……」
「桃子……」
桃子は確かにあの頃よりは断然良くなっている。が、それでも彼女は未だにこんなことを続けている。それでも諦めないで、老婆は何とかしようと日々努力している。
「えーっと、太郎さんも一緒に行きますか?」
「いえ、俺は遠慮しておきますよ。お二人で楽しんできてください」
桃太郎はすっかり回復していた。もともと彼に必要なのは時間だけだった。ここに居れば辛いことに直面する機会は滅多にない。そう、少なくとも鬼に関しては。
桃太郎たちがやってきて以来、少なくともこの村には一度も鬼が現れてはいない。鬼連合会長と副会長を同時に失ったことで指揮系統が混乱し、組織的な行動が出来ずにいるのだと桃太郎は考えている。
だから、今は平和だった。この平和がいつまで続くのかは分からないけれど、一日一日を大切に噛み締めていきたいと、桃太郎は思っていた。
そうたとえ、老婆との間がギクシャクしていても、それでも彼は日々を楽しんで生きていくと決めた。それが、自分を助けてくれたジャックに対する唯一の恩返しの手段なのだから。
最初のうちは、そう考えていた。
けれど今は違う。
この平和を――この素晴らしき日々を、永遠に続けていきたいと、そう考えるようになっていた。
そして彼は動き始めた。
だからここからは、再び彼の舞台と化す。ここからは彼自身が主役で、彼自身の視点が全てで、そして彼自身が物語を紡いでいくのだ。
長い長い休憩は終わり、再び彼が主役に返り咲く。
それは遥か昔から決められていたことで、もはや『運命』と呼称しても良いものかもしれない。
物語の主人公は『桃太郎』。それは、誰もが知っている至極当たり前のことだ。
物語は、正しい主人公の手で、正しい結末へ導かれていくものなのである。
第五章「桃太郎の鬼退治」
1
俺にできることを考えた。
俺には鬼に勝てるような力はない。
残念なことに、頭だって良くない。
だから俺一人では何もできない。
けれど、そんな俺でも、数さえいれば何とか出来るのではないだろうか。
俺がやること――やらなければいけないことは、とても難しいことだ。
過去にも同じようなことをやろうとして大惨事を引き起こした人がいる。
そんなことに協力してくれる人がいるかは、分からない。
でも、だからといって諦めるわけにもいかない。
これは、何が何でも俺がやらなければいけないことだから――
2
親父が、俺を置いて出ていった。
理由はわからない。でも、俺のことを疎ましく思ったから、と考えるのが自然だろう。それが悲しくないといえば嘘になる。いや、大嘘だ。悲しくて悲しくて、もう涙も出てこないくらいだ。
でも、泣かない。それじゃあ何も変わらない。俺は、親父に見捨てられたくない。だから、親父に見捨てられた今の俺のままじゃ駄目だ。変わらなきゃならない。昔のように戻るのでも駄目だ。昔の自分に戻ったところでまた同じ事を繰り返すかもしれないから、根本的な解決にはならない。だから俺は、新たな自分に、生まれ変わらなければならない。
同じ家にいるからといって、いつも一緒に行動するわけではない。老婆だけでどこかへ行く事もあるし、俺だけがどこかに行く事もある。それぞれ、どこへ言っているのかは話さいが、恐らくおばあさんは畑仕事だろう。俺も、本当はそれを手伝うべきなのだと思う。けれど、おばあさんはそれを反対する。男の力があったほうが仕事が捗るのなんて、考えればすぐ分かるはずなのに。でも俺は、尋ねない。きっと訪ねちゃいけないのだと思うから。
俺は毎日村を散歩している。他にやることがないというのもあるが、前々から一度人村を見てみたいと思っていたのだ。とはいっても、以前そう思っていたのは、いずれ俺も村を攻めることがあると思っていたからなのだけれど。今はもうそんなことを考える必要はないなんてのは分かってるし、そもそも略奪行為をする気は今の俺にはない。ただ、なんとなく見て回ってみたかった。
だからだろうか。気がついたら俺は、囲まれていた――
「……」十数名ほどの男達が俺を取り囲んでいた。
「何、あんたら?」
「……」反応はない。
「だから、誰だって聞いてんの」
二度目の質問。しかし、まだ反応はない。
「俺、帰りたいんだけど。通っていいかな?」わずかに苛立ちが募ってくる。が、そんな気配は微塵も漂わせないように気をつけて告げる。
「……お前、鬼と一緒に俺達の小屋に来た奴だよな?」
「ッ――!?」まさか、コイツらはあの時の山賊なのか……!?
「その反応……やはりお前か。ひとつ尋ねたい。桃彦という男を知っているか?」
「桃彦……?確か数年前の鬼ヶ島大攻撃の主犯……」
「それだけか?」
「あ、ああ……」答えると、山賊たちはどこか失望した様子を見せていた。
「……じゃあ、こういう鬼を知っているか?」そう言って、連中はとある鬼の似顔絵を見せてきた。
「えっ……」その鬼は――
「知っているのか!?」
「お、親父……?」ジャックだった。
俺は、山賊たちから全てを聞いた。
鬼ヶ島大攻撃の真相の、全てを。
それは、俺の知っている事実とは大きく異なっていた。でも、なぜ。なぜ親父は島の鬼たちを売ったのだろうか。今となっては分からないが、少なくともその頃は、親父は島の皆のことを大切に思っていた。その親父が皆を売っただなんて、正直信じがたい話しだった。けれど、連中の言葉に嘘がないのは明らかで、だから俺は山賊を信じることにした。親父ではなく、山賊を。ああ、やはり俺は親父のことを恨んでいるんだな。そりゃそうか、突然こんな村に置いていかれたのはやっぱり納得いかねえよ。まさか自分の本心にいまさらになって気づくとはな……。
「で、どうしてあんたらは俺にそれを教えてくれたんだ?」今はとりあえず親父のことは忘れよう。いつまでも文句ばかり考えていても仕方がない。現実を見なきゃ。
「あんたに頼みがある」
「頼み……?」おい、この連中は何を言っているんだ?俺は忘れていない。桃子をひどい目に遭わせたことも、俺に同伴していた鬼を殺したことも、そして俺を殺そうとしたことも、全部覚えているんだぞ?それをこの連中は理解していないのか?そんなにも山賊ってのは愚かな生き物なのか?
気持ちが顔に出ていたのだろう。
「あんたの気持ちはわかる。あんたは俺らを憎んでるんだろうな。そんなことは分かってるさ。だが――」
「ふざけるな!!気持ちがわかるだって……?簡単に言ってくれるなよ!お前らに何が分かるってんだ……。あれから俺に――俺達に何があったかを知ってるっていうのか!?分かってるだなんて軽々しく言うんじゃねえよ……」
どうしても我慢ならなかった。これは明らかに失敗だって分かってる。ガキがこんな調子に乗ったことを言えば、コイツらは俺を殺そうとすることなんて分かってる。でも、我慢ならなかった。俺の苦労を、親父の苦労を、桃子の苦労を、何も知らない赤の他人が――いや、それならまだいい。俺たちにその苦労を与えた元凶が、俺の気持ちを分かってるだって……?冗談にも程がある……。
「一応、言い訳をさせてくれ。あの時のことは、全部命令されたことだったんだ……」
は?
命令……?
誰、に……?
「鬼連合会長に――」
「ッ――!?」鬼連合の、会長、だって……?
「あんたが俺達の小屋に来る十日ほど前、俺達のもとに鬼が数人でやってきた。俺たちは当然死を覚悟したさ。でも奴らは言うんだ。『ここに数日後、人間がやって来る。そいつに地獄を見せるために、女を輪姦せ。あのガキにはそういう現実を叩きこむくらいがちょうどいい。さっき周りを部下に確認させところ、ちょうどいい事に女が一人でこの近くを歩いている。そいつを輪姦せ』ってな。この山賊団は絶対に必要最小限の悪事しか犯さない。それが、桃彦――俺達の親分が掲げた鉄の掟だ。それを俺たちは奴が死んだ後もずっと守ってきた。だから、断りたかったさ……。でも、断れなかった。結局俺たちも死ぬのが怖かったんだ。奴らに逆らえば殺されるのは明らかだった。死を恐れる俺達には、それ以外どうしようもなかったんだ……」
山賊が説明を続ける。だが、俺の耳にはもう何も入ってこない。あまりの衝撃に、既に俺の脳の限界を超えてしまっているようだった。
今の俺の頭の中にあるのは、鬼への憎しみ、ただそれだけだった――
「……あんたらの頼みってのは聞いてやるよ。でもその代わり、俺の頼みも聞いてくれ」
「なんだ?」
「鬼ヶ島をぶっ潰すのを手伝ってくれ――」
揺らぐことのない決意を込めて、そう告げた。
「元よりそのつもりだ――」
そして山賊が、彼らの運命を決定的に変えてしまう提案を、承認した。
山賊たちに連れられて、山賊の小屋に来ていた。
「へぇ、思ったよりもたくさんいるんだな」
百人はいるだろうか。当然小屋には入りきら無いのでほとんどは外に出ている。
「これだけの人数がいるのにこんな小さな小屋だけで大丈夫なのか?」
疑問に思い、先程自らの説得に来た頭領らしき男に尋ねる。
「ああ、それについては問題ない。俺たちは皆ここに住んでるわけじゃないんだ。ここに住んでるのは俺とコイツだけだ」そう言って、男は隣に立っている男の肩に手を置いた。
「おっと、紹介が遅れたな。俺は猿。で、コイツは雉だ」
「猿に、雉……?」
「渾名みたいなもんだよ」
「はあ……」
「さて、話が逸れたな。俺たち以外の連中はそれぞれの村で暮らしてる」
「なっ――!?」山賊団の一員が村に暮らすだって……?
「俺たちは猿隊、雉隊の二つに人員を分けている。地域ごとに人員を分けてるんだ。猿隊所属の連中が暮らす村には雉隊が行く、ってな感じでよ。だから村人に正体がバレる心配はない」
猿はこう言うが、本当に心配はないのか?村に自分の仲間が略奪に来るんだぞ?抵抗はないのか?
「お前が何を心配しているのかは分かる。だが、その心配はない。コイツラは皆仲間だ」
「でも!」
「それに、もしもの為に五人組制ってのを採用してる。誰かが規則を破ったら同じ組の四人も同様に罰する。だから誰も裏切らない」
「なるほど」それなら心配は無用、か。
「さっそくだが、あんたには俺達の親分になってもらいたい」
「はあ?」な、何を言ってるんだこの男は……。
「現在、ここには親分がいない」
「あんたじゃないのか?」
「ああ。何年も前、ここには四人しかいなかったときがあってな。でもその後いろいろあって、親分ともう一人は死んじまったんだ……」
猿が苦々しげに語る。隣を見ると、雉も似たような様子であった。
「まあ、俺は別になっても構わないが……外の連中はそれに納得するのか?俺みたいな突然現れた奴がいきなり親分になるなんて」
「納得できなきゃ出て行ってもらうだけだ」
「おいおい……」
「それくらい本気だってことだよ」猿が真剣な眼差しを向ける。こいつの言うことに嘘はない、そう思った。だから――
「いいぜ、俺が親分をやってやるよ――」
俺は、山賊の親分になった。
3
鬼が島を攻めるのには当然それなりの準備が必要だ。今のまま向かった所で瞬殺されているのは目に見えている。むしろ見えすぎている。だからどうしてもなんとかする必要があった。
「『虹神草』?」
「ああ。それが鬼に対向する唯一の手段といっていい。もっとも、その呼び方は鬼たちがしているものであって、俺達はその草で団子を作り、『きびだんご』と呼んでるけどな」サルが自慢げに語る。
「それがあれば鬼に勝てるのか!?」
「勝てる……かもしれない」だが、途端にその表情は曇った。
「どういうことだ?」
「『きびだんご』を大量に食った桃彦は、鬼連合副会長のほぼ互角の戦いを繰り広げた」
「親父と!?そいつはすげぇな……」
「ただし、身体に半端無く負担がかかる。桃彦は鬼連中に虐殺されたとなっているが、実際はそれより早く衰弱死してたんだよ……」悲しみを堪えながら猿が語る。
「す、衰弱死……?何だよそれ、危険過ぎるじゃねーかよ……」
「だが、俺達にはそれ以外に鬼に対抗する術はない」猿が断言する。
「……」
「『きびだんご』は俺と雉が食う。お前は他の連中を指揮してくれればいい」
「――いや、それは俺がやる」
「…………いいのか?」
「ああ、それはきっと俺がやらなきゃいけないことだと思うから――」
「そうか、了解した。なら『きびだんご』は俺達三人で食おう。全体の指揮は他のやつにやってもらうことにするよ」
「どこまで死にたがりなんだよ、お前らは」笑いながら猿に言った。
「なーに、これでも随分我慢したほうだぜ?本当なら桃彦と犬と一緒に死ぬつもりだったからさ――」
「犬?」
「ああ、もう一人の仲間だよ」
「そっか」
そうして俺達は、準備を進めた。全てはそう、鬼に勝つために。
どんな汚いことだってした。勝つために必要なことならば、俺達は一切ためらわなかった。だからきっと、村人たちには俺達と鬼に違いなんてないのだろう。でも俺は――俺達は、それでもただひたすらに準備を進めた。心を鬼にして。鬼を倒すために自らが鬼にならねばならないなんて、なんて皮肉な話なのだろう。もう俺達は鬼だ。
だから、俺達の鬼退治の最後の敵は――――俺達自身だ。
そして幾年かの時が流れ、遂に準備を終えた。
「じゃあ、明日。手筈通りに」
「「了解」」猿と雉が答える。
「じゃあ今日はもう解散しよう。明日に備えて少しでも休んだほうがいいからな」
「それもそうだな」と、猿。
「よっしゃー!!明日は鬼どもを皆殺しだぜー!!」と、雉。
「なんかお前、どんどん犬の奴に似ていくな」
「うっそマジかよ……。あんな脳筋野郎と一緒なのかよ……」
「何気に酷いな、お前」
「知らなかったのか?」
「いーや、知ってたさ」
「だろうな!」
楽しそうに談笑する二人を横目に、俺は小屋を出た。
俺の足は、自然と老婆と桃子の暮らす家に向かっていた。
山賊になると決めた日から、俺はあの家には戻っていない。俺のせいで迷惑をかけることだけは何が あっても避けたかったから。
だけど俺は今そこに向かっている。これはきっと未練なのだろう。俺は、もしかしたら桃子に惚れてしまっているのかもしれない。特に話した覚えもないのに、変な話だ。でも俺だって年頃の男なんだから、 変な恋のひとつやふたつ、別にどうってこともないさ。
そう思いながら歩き続けた。
「なあ、どうしてそんなところに立ってるんだ?もう夜も遅いし、寝たほうがいいんじゃないか?――桃子」桃子は家の前に立っていた。まるで、俺が来るのを知っていたかのように。
「行く気なの?」俺の言うことになど一切耳を傾けず、尋ねてきた。
「行くってどこに」同様を決して顔に出さないよう努める。
「決まってるでしょ?鬼ヶ島よ――」
「ッ――!?」だが、限界は早かった。
「本気で鬼に勝てると思ってるの?『きびだんご』がどれほどのものなのかは知らないけど、ちょっと楽観視し過ぎなのではなくて?」
「だから、なんだよ――」
「別に。ただあなたが本気で行こうとしているのか確かめただけよ」
「本気だったらどうだって言うんだよ――」
「そうね、何て愚かな奴なんだろう、って思うかしら」桃子は、恐ろしく冷酷な視線を向けてくる。
「喧嘩売ってるのか、お前?」ああ、だんだん腹立たしくなってきた……。
「いいえ、そんなつもりはないわ。ただ、それで私がどんな目にあったかしらないわけじゃないでしょ?」
「お前は一人だった。でも俺は――」
「仲間がいるって?でもその人達はどれだけ信用できるの?だって、私を輪姦した張本人たちじゃない」
「何なんだよお前は!?お前には関係ないだろ?これは俺の闘いなんだよ!!無漢検な奴が余計な口出しをするな!!」もう、限界だった。苛立ちがどんどんと言葉となって漏れだしていく。
「関係大有りよ。鬼ヶ島大攻撃のせいで何が起きたかくらい知っているでしょ?」
「……俺は成功させる」
「その根拠は?」
「世の中に絶対なんて無い。だから、絶対失敗するなんてこともないし、絶対成功するなんてこともない」
「詭弁ね」
「どうとでも言え」
俺は笑って告げた。正直なところ、俺は失敗した時のことをまるで考えていなかった。いや、考えないようにしていたというのが正しい。俺は絶対に成功しなければならないという義務感にとらわれて、失敗を極度に恐れていたらしい。あの聡明な猿のことだ、きっとこのことについても考えているのだろう。まったく、これじゃあ俺は完全に親分失格じゃないか……。
「もう俺は行くよ。じゃあな、もう会うこともないだろうけれど」
「何それ、やっぱり成功させるつもりはないんじゃない」
「違うよ、俺はもうここには帰ってこないって言ってんだよ」
「なぜ?」
「そんなの、言うまでもないだろ……」
「……まあ、いいわ。それではさようなら。もしあなたと話していることが誰かに見つかったらおばあさんにも迷惑をかけてしまうわ」
「そいつは悪かったな」
会話を無理やり終えて、俺は小屋へと戻った。もうこれ以上、話したくはなかった。
ああ、なんだよ、もう俺の初恋は終わりかよ。たしかに、たった一度たりとも話したことのない相手のことを勝手に好きになってたのは俺だ。でも、それでもこれは、けっこう来るものがあるな……。ああ、ちくしょう……。
小屋へと戻ると、既に猿と雉は眠っていた。
俺は、よく眠っている二人の隣でモヤモヤとした気持ちを抱えながら眠れない夜を過ごした。大事な日を迎えてるってのに、俺は何をやってるんだろうな……。
気づいたら朝だった。眠れないだの何だのといっておいて、ちゃっかり寝ていたらしい。いやまあ、良かったといえば良かったのだけれど……。
「さて、じゃあ鬼退治を始めるか――」
「「「「「「「「おおおおおおおおおおおおおおおッ!!」」」」」」」」」」」」
山賊たちの雄叫びが、山に響いた。
ここからは俺に余裕なんてものは一切ない。だから、俺は主役の座は譲らないけれど、語り手の役は手放すことにする。忸怩たる思いがないわけではないが、仕方ない。俺は、何があってもこの作戦を失敗させる訳にはいかないから。
4
攻撃は、迅速かつ冷酷に進められた。
鬼たちは、前回の鬼ヶ島大攻撃を反省して、略奪時にも五班――すなわち戦闘可能な鬼百名を鬼ヶ島に配置していた。しかし、桃太郎率いる山賊団の勢いは凄まじく、戦闘員は全滅、女子供は一人残らず囚われの身となっていた。
「貴様らに告ぐ」捕虜とした鬼たちを眼前にし、桃太郎が心底見下した表情で告げる。
「これからは人間が世界を支配する。貴様ら鬼などという下等生物に出る幕などない。故に、貴様らのような汚れた血はここで途絶えさせねばならない。よって、貴様らを誰ひとり逃すこともなく、ほんの少しの悦楽を得させることもなく、殲滅する――」
「「「「なッ――!?」」」」
桃太郎の言葉に鬼たちは驚愕する。
だが、この言葉に驚愕したのは鬼だけではなかった。
「どういうつもりだ、桃太郎?」
「おい親分!!どういうことだよ!?」
猿と、雉である。
「何って、当たり前のことだろう?前回の鬼ヶ島大攻撃が結果的に失敗に終わったのは、鬼を殺さなかったからだ。女鬼を絶滅させれば新たな鬼が生まれることもないし、子鬼を絶滅させてしまえば報復を受ける恐れもない。だからそうするのはむしろ当たり前のことなんだ。逆に聞きたい。なぜお前らは反対するんだ?」桃太郎が全く理解できないとばかりに尋ねる。
「だからって、そこまでしたら俺達も鬼と一緒じゃないか!!」すかさず猿が反論する。
「そうだよ。今更何を言っているんだ?俺達はいったい今まで何をやってきた?村人から略奪してきただろう?あんなことをしておいて自分は鬼じゃないだなんて、いくらなんでも都合が良すぎるとは思わないのか?」
「それ、は……」これには流石の猿とはいえ、反論できなかった。彼自身も、心の何処かで自らの行いの矛盾に気付いていたのである。
「そして、これは鬼退治だ。だから俺達が最後に討つべき相手が誰か、もう言わなくても分かるよな?」
「おい、正気かッ!?」
「どういう意味なんだ、猿?」すぐさま桃太郎の言わんとする所を理解した猿に、まっったく理解できなかった雉が尋ねる。
「こいつは、鬼を全滅させた後に俺たちも殺すって言ってるんだよ……!!」
「ッ――!?」
これには雉だけでなく、仲間の山賊たちも、そして鬼さえもが驚愕した。
「俺達は、もうお前には従えない……」山賊団総員を代表して、猿が桃太郎に告げた。
「だろうな――」
ガスッ!
「え……?」
桃太郎の拳が、猿の腹部を貫いていた。
「猿ッ!!」叫ぶ雉。
「うおおおおおッ!」
しかし、雉が動き出すよりも早く桃太郎は雉の首をへし折った。
山賊団の古株で、団員に親しまれていた二幹部が、地面に崩れ落ちた。
「さて、これで『きびだんご』を食ったのは俺だけになったな。お前らも見たろ?鬼百人を相手に無双した『きびだんご』の力を。もうお前らでは俺には勝てない。だからお前らの生きる道はひとつだ。俺に、従え――」
圧倒的な力を背景に、桃太郎は山賊団を脅迫し、そして従わせることに成功した。
最早この場に彼に適うものは誰ひとりいなかった。
「おい太郎、なんだよそのやり方は――」
そう、唯一人を除いて。
「おや、じ……?」
「がっかりだぞ。がっかりだ。本当にがっかりだ。俺が求めていたお前は、そんなお前じゃない。お前は誰だ?本当に俺の知っている桃太郎なのか?俺は知らない。お前なんて、俺は知らない」
「――ああ、そういえば、あんたも鬼だったな」ジャックの発言は敢えて無視する。ここで乗るわけには断じていかなかったから。
「だったら?」
「決まってるだろ。鬼は、殲滅する――」
そう言って、桃太郎は懐から瓢箪を取り出して蓋を開け、同時に仮面を取り出して被った。
「一体何のつもりだ……?」ジャックが不審に思い、尋ねる。
「いや別に。ただそうだな、敢えて仮面を被った理由を答えるなら、鬼如きを直接目にしたくなかったから、かな」微笑しながら桃太郎が答える。
「――ッ!!」ジャックは怒り、跳び出した――
否、跳び出そうとした。
「な……ん、だ。身体が、重いし、それに……」ジャックが突然倒れる。その身体は、緑色を帯びた暗紫赤色や緑色を帯びた暗赤褐色の斑点ができている。
桃太郎の後ろでは、山賊たちも続々と倒れていっていた。こちらもまた、ジャックと同じような斑点ができている。
その場に立っているのは、桃太郎ただ一人。
「これは鬼を殺すために開発した武器の一つでね、まあ君等に言ってもわからないだろうから、とりあえず結果だけ教えてやるよ。お前らは、全滅だ――」
そう告げて、桃太郎は瓢箪の蓋を閉じ、その場を離れた。
そこには人間と鬼といった種族を問わず、数多の死体以外、何一つ残ることはなかった。
毒ガス。かつて桃太郎は桃子を救出した際に、山賊の所有していた毒瓶を盗み出していた。その毒によって、桃太郎は山賊団には内密に毒ガスを制作していたのだった。
『きびだんご』
『毒ガス』
このふたつこそが、桃太郎が鬼を倒すために手に入れた、最悪の武器である
「……」
桃太郎は、鬼ヶ島にある、昔ジャックと二人で住んでいた家に帰ってきていた。
そして、誰もいないその空間で、孤独に静かに泣いていた。
これは、本来彼が望んでいた結果ではない。
ただ、そう――天からのお告げというか、運命として既に定められているかのような、そんな気がして、彼は行動を起こした。いや、これは『そんな気がした』なんてものではなく、ある種の強迫観念を彼は抱いている。
己が鬼を滅ぼさねばらないと。
己以外、誰もそれを成し遂げることはできないと。
だから、なんとしても鬼を滅ぼすのだと。
そのためなら、たとえ修羅の道を歩むことになったとしても構わないと。
「……」
しかし、それほどの使命感を抱いてはいても、やはり悲しいものは悲しく、つらいものは辛かった。
今まで何年も共に鬼打倒を目指してきた仲間を裏切り、そして敬愛する父を不意打ちじみた方法で破り、そして己自身を含めた鬼を、殲滅することになる。
当然彼だって人間だから、死は怖い。もっと生きたいと、そう願っている心がないはずがない。だけど、それでも彼はもう後には退けない。もう、ここまでやってしまった。もしここで逃げ出してしまったら、今までのことはいったい何だったというのか。何も、何一つ意味がなくなってしまう。それだけはどうしても許すことができない。だから彼は使命を全うする。それが独り善がりな考えであるなどとは、微塵も考えることもなく。
しばらくして、略奪に出ていた鬼たちが島に戻り、その惨状を目の当たりにした。
「なんだよこれ……」呆然と立ち尽くす者。
「誰だ、誰がやったんだ!?」動揺し、怒り、周りに喚き散らす者。
「うわああああああああああ!!」あまりのショックに精神が崩壊してしまった者。
それぞれ反応に多少の差異はあれども、あまりに予想外の出来事に、対処しきれていないという点は共通していた。
「……」
だからそれは、桃太郎にとっては格好の餌食でしかなかった。
仮面を被ったまま、持っていた瓢箪を全て開けた――
「はは、ははは……」
遂に、鬼という呪われた種は絶滅した。
ようやく、彼の悲願は果たされたのである。
「はは、は……」
だが、桃太郎の胸には何かぽっかりとした穴のようなものが開いてしまっていた。
悲願を達成したのだから、嬉しくて、嬉しくて堪らないはずなのに。
なのに、ちっとも嬉しくない。
「俺は、鬼になりきれていなかったのかな……」
今まで散々心を鬼にして、やりたい放題やってきた。もう、全ては過ぎ去ってしまったことなのに、今更後悔している。
「他に道はあったのかな」
あった――そう、桃太郎は思った。やりようは、あった。きっとあったはずだ。でも、彼はこれ以外の方法を選ぶ気にはならなかった。己はこの物語の主人公なのだから、より劇的な行動を起こさなければならい。そう信じて疑わず、だからこうなった。
「俺は、主人公だから……だから、ここで本当に俺が死んでいいのか……?」
そして遂に彼は死からの逃避を始める。
「こうやって後悔しているから、俺はきっともう鬼じゃないんだ……。だから、別に俺が死ぬ必要なんて、どこにも――」
ふいに、桃太郎は胸に何か違和感を感じた。
「あ、れ……?」
胸からはナイフが突き出ていて、血が止めどなく溢れている。
桃太郎が後ろを見ると、そこには――
「お前が父ちゃんたちを……!!」
鬼の、子供。
「そん、な……まだ鬼が生きていたなんて……」
「鬼はお前だ――!!こんな、こんな酷いことをするなんて、俺達よりもお前のほうがよっぽど鬼じゃないかッ!!」子供は叫ぶ。喉が張り裂けんばかりに、仲間の仇に向かって叫ぶ。
「俺が、鬼……?違う、俺は主人公、だ――」
そうして桃太郎の息は途絶えた。
終章
桃太郎率いる山賊団の起こした事件は、『桃太郎の鬼退治』と呼ばれた。
その結果を聞いた時、村人たちは嘘だと最初は一蹴して、けれどそれからしばらくの時がたっても一向に鬼たちが略奪に現れないことから、村人たちはその話を信じるようになった。
その話は、ある村のある少女が最初に言い出したことだった。その少女は桃太郎と何年もの間共に暮らしていたという。桃太郎の最後の目撃者もまた、彼女である。彼女は桃太郎について、とにかく語って回った。それは所々真実とは変わっていたところがあったけれど、彼女は桃太郎とともに出向いたわけではないので本当のことは知らず、だからそれは彼女の作り話でしかない。けれど、その話は誰しもに愛された。もし、『桃太郎の鬼退治』のありさまを、ありのままに伝えていたらこうはならなかったことだろう。村人は、鬼を滅ぼしてくれたことには感謝するだろうが、それでもここまで彼を尊敬することはなかったはずだ。それは全て、彼女――桃子――の功績である。
桃子はおばあさんと一緒に畑を耕し、稲を植え、そして時間が空いた時には村の子供達に桃太郎のことを語って聴かせた。あるときから、おばあさんも桃子とともに桃太郎の話を子どもたちに聴かせるようになった。しかし、おばあさんの語るお話は、少しだけ桃子のものとは違っていた。桃子の語ったお話では、最初に桃太郎は老夫婦に拾われはするも、すぐに捨てられてしまっている。だが、おばあさんの話では桃太郎はその老夫婦に拾わて、そのまま捨てられることなく育っている。桃子がそのことをおばあさんに尋ねると、
「だって、可哀想じゃないか。結局彼は捨てられたことを憎みながら死んでいってしまったのじゃ。だからせめて、せめてお話の中でだけでも、彼に救いをあげたいんじゃ。これで少しでも罪滅ぼしになれば……とも思うよ」と語った。桃子はおばあさんに罪とは何のことかと尋ねたが、おばあさんは答えなかった。
後にその物語は絵本となるのだが、それはまた別の話。
村人たちは皆、鬼が滅んだと思っている。だがしかし、真相は違った。
桃太郎を殺した鬼の子供、彼だけは生きていた。
彼は、鬼の証である二本の角を折り、そして人村に降りて行った。角さえなければ人間の子供と見た目的にはそう違いがないのだ。もちろん、身体能力には圧倒的な差があるので、それについてはかなりの努力を必要としたのだが。
そうやって彼は村で人間として暮らし、人間の女性と結婚し、子供を産んだ。
彼はその子供に角が生えてこないかヒヤヒヤしていたが、心配は杞憂に終わり、角は生えて来なかった。また、彼と比べればであるが、多少身体能力も人間に近づいていた。
それから、彼は森に向かった。誰もがいなくなってしまった鬼ヶ島にあった資料を読むことで、彼は鬼の由来について知った。だから、もう二度と同じ過ちが起きないように、『虹神草』を燃やしに行ったのだった。これで、もう二度と鬼が生まれることはないだろう。
皆、鬼がいない世界に少しずつ、少しずつ慣れていった。
もう今の日常が当たり前で、少し前まで鬼に怯えていたことが嘘みたいに平和な日々を過ごしている。その平和がいつまで続くのかは誰もわからないけれど、少なくとも今この瞬間だけは確かに平和だった。
では、そろそろここで桃太郎のことに触れなければなるまい。
彼は、統合失調症だった。
この世界は誰かに作られたもので、そして己はその物語の主人公であると信じて疑わなくなっていた。
彼がこうなってしまったのは、初任務の際の強烈なストレスが最も大きな要因であろう。幼い桃太郎には、あの事件はあまりにも刺激的過ぎたのである。
誰もが憧れる英雄の正体は、統合失調症患者だった。
誰がこんなことを信じるだろうか。
信じるはずがない。
誰も信じてはいないのだから、これはもしかしたら真実ではないのかもしれない。
『そうである』ということは、『そうである』ということを誰かが認識しなければ、『そうである』ことにはならないのである。
だから、この物語は全てが嘘だ。
嘘に満ちた<桃太郎>
別に<桃太郎>という作品をけなしているわけではありません!妄想100%の作者の戯言です……。気分を害されたならすみません。でも、楽しんでいただけたなら本望です。作品のタイプは一貫していないので、他の作品も楽しんでいただけるかどうかはわかりませんが、ぜひ読んでいただけたらと思います。
執筆期間が長かったので途中から初期構想からどんどん外れて行ったりしていて、回収していない伏線や、意味の分からない場所があるかもしれません。自分で気づいた場合には出来る限り直していくつもりですが、何分気移りの激しい性分でして。既に別の作品に取り掛かっています。なので、この作品を直していくことはないと思われます。というわけで、もし説明不足な部分などがあったりしたらご自身で補完していただけるとありがたいです(責任放棄)。
ではでは~。

