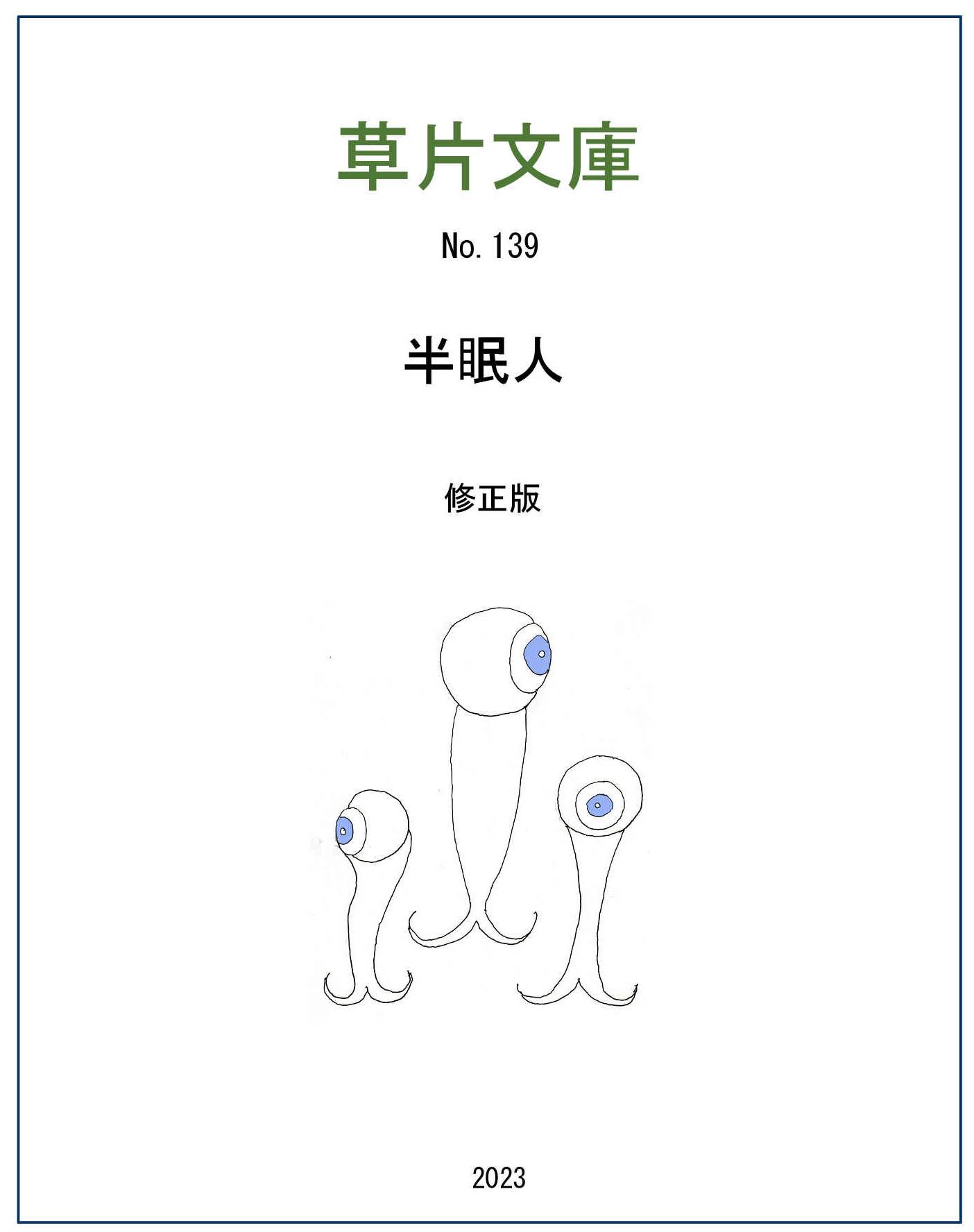
半眠人
人間イルカの物語。
静岡に住んでいる友人に自分の祖先は猿じゃない、イルカだと言っている男がいた。石垣紀夫である。大学時代同じ文学部の研究室にいたのだが、彼は優秀な卒業論文を書いて、学部の最優秀論文賞を受賞した。当然大学院に行くものと周りは見ていたのだが、静岡の小さな町にある水族館に就職してしまった。
彼の書いた卒業論文は「人魚の生態」と言うタイトルで、人魚の果たした日本人に対する役割を解析したものである。第一章には実際に生息する、ジュゴンやマナテイーなど、人魚の原型とされている実在の生物についての記載が、生物学者より詳しいほどにかかれている。二章には人魚伝説のかずかず、三章には日本における人魚にたいする人々の思い、第四章には小説に見られる人魚など、よくこれだけ調べたという卒業論文だった。
大学時代、彼はつきあいがよく、四年になっても仲間と飲み歩いたり、アルバイトに行ったりしていたが、いつの間にかその卒業論文を書き上げていた。
卒業式で、僕は彼によくあれだけのものを書き上げる時間があったな、あれだけ遊んでいて、ときいたのだが、そのときに、彼がいったのは、自分の祖先はイルカと言う言葉だったのだ。
僕には生物の知識が乏しかったので、意味が分からなかった。それが卒業十年近くたった今、テレビで睡眠をあつかったバラエティー番組を見ていてわかったのである。
イルカの脳は半分寝ることができる。渡り鳥も半分寝ることができる。イルカはほ乳類で水の中で寝てしまえば、水面にでて息継ぎができないからおぼれて死んでしまう。渡り鳥も寝てしまえば長い渡りの最中に羽が止まって落ちて死んでしまう。半分ずつ脳を眠らせておけば、そういうことはおきない。
その番組を見て、彼がイルカと言った意味が理解できたのである。昼間はわれわれと同じようにつきあってくれて、夜半分寝ている脳で、あの立派な卒業論文を書き上げたのである。と理解した。
彼は寝なくても大丈夫なのだ。本当だろうか。
今頃になって彼を理解した気になった僕は、推測が事実かどうか静岡の私設遊園地の水族館に勤めた彼に数年ぶりに電話で連絡をした。
彼は電話を喜んでくれて、「そうなんだ、僕の脳は半分ずつ寝ることができるので、体としては、寝なくていいんだ、だけど、体はそれにあった形にはなっていないから、もう若いときのようにはいかない、やっぱり夜は横になるようにしているよ」と電話先で笑っていた。
私はとある大学の図書館に勤務している。休みが取れたら水族館をたずねると約束して電話をきった。
祝祭日は水族館のかき入れ時である。人が多いから休館日の月曜にくるといいと言っていた。たまたま勤めていた大学の創立記念日が今年は月曜で、図書館も閉館になる。そこで、その日の午後に静岡につくように出かけると彼に連絡した。
水族館のある子供向けの遊園地は静岡の駅からバスで15分ほどのところだった。彼の住まいも園の近くだという。
「やあ、久しぶりだ」
園の入り口で待っていてくれた彼は全くといっていいほどかわってしまっていて、がっしりとした体つきはスポーツの選手だ。運動選手がするように手を高々と挙げて合図をしてくれている。
「ずいぶん筋肉粒々になったね」
「眼の前の海で泳ぐからね」
そう言って日に焼けた顔にえくぼを寄せた。その顔は大学時代の面影が残っている。
われわれは裏口から園内にはいった。子どもたちが喜びそうな乗り物や、おいしそうな絵が並んでいるアイスクリーム売店、それに大きな食堂がある。休日にはわーわーきゃあきゃあ満員になるのだろう。そういった建物に混じり、小さいながら、チョウチョの舞う昆虫館、は虫類館、子ども動物園、それに水族館があった。どれも有名なところと比べるとかなり小振りだ。
水族館に向かって歩いていくと、どの施設にも作業着を着た人たちが働いていた。
「休園日にメンテナンスしているんだ、水族館でもスタッフやアルバイトが水槽を掃除したり、動物のために一週間の食事の下準備をしたりしている」
「今日は大丈夫だったの」
「朝早く自分のやることをすませたから大丈夫」
「わるいね」
「いや、僕も君に飼っているイルカを見せたくてね」
水族館の裏口から中にはいると、二人の女性が帰り支度してでるところだった。
「終わったの」
「はーい、まだ施設の人が点検してます」
「そう、ごくろうさん」
「それじゃ、館長失礼します」
若い女性たちは彼に挨拶をしてでていった。
「館長なんだ」
「いや、園の組織としては主任なんだよ、水族館では館長だけど、一番年とっていると言うだけ」
水族館の中は小さな水槽がならんでいて、中には色のきれいな魚や蟹、それにクラゲがあそんでいた。いかにも子供たちが喜びそうだ。その施設のとっつきに大きなイルカの水槽があった。外にあるイルカのプールの後ろ側になる。
石垣が部屋にはいったとたん、三頭のイルカがガラスの面に、片方の目をくっつけた。明らかに石垣を見ている。
「石垣が部屋に入ったのがわかるんだね、すぐにガラスによってきたじゃないか」
「うん、右から一雄、次男、三男だよ」
「ああやって、ガラスに目をくっつけて君をみてるのか」
「ああ、彼らはおまえは誰だといってるんだ、だから俺の友達だと知らせたよ、ほら」
彼がそう言うと、イルカたちの目が私のほうに動いた。
確かなようだ。
「イルカの表情を読むとこができるんだな、イルカも君の表情を読める」
「まあ、それもあるけど、まだ誰にも言っていないけど、彼らの超音波発声が聞こえるんだ」
「でもイルカ語がわからなければ意味がわからんだろう」
「おお、いいとこついたね、そうだよ、実はわかるんだというよりも、俺の脳にはイルカ語を理解する神経回路というより、イルカの言語野が遺伝的に備わっていたようで、イルカが話したことが、日本語になって聞こえるんだ、そう、君の声を聞いているのと同じようにね」
「そんなことあるのか、ほら、コウモリなんて超音波を利用して虫を捕まえているし、話もしているっていうことだけど、コウモリの声などもわかるのかい」
「いや、君は猫や犬の声が聞こえるだろ、ニャアニャアとかわんわんとか、でも言葉としてはわからないよね、コウモリの声もそんな聞こえ方をするよ、コウモリの言語を勉強すればわかるだろうな」
「超音波が聞こえてうるさくないかい」
「ああ、うるさいけど、生まれてからずーっとだからなれているからね」
「じゃあ、大学時代もそうだったのか」
「そのころは、雑音としかきいていなかったけど、イルカとつきあうようになって、わかるようになってきた」
三匹のイルカがガラスの面からはなれると、尾鰭で立ち上がるような格好で、鰭をひらひらさせ、私の方を見た。
「よくきましたね、楽しんでください、っていってるよ、水族館にきた子供たちにそうやっていつも話しかけているんだ、もちろん子供たちも親もなにを言っているのかわからないけどね」
「そうか、イルカと一緒に働くようになって、自分の能力がわかったわけか」
「そうなんだ、さて、ここをでて、ビールでも飲もうか」
まだ三時半である。われわれは遊園地をでると、彼の行きつけだという、ウナギ屋に行った。まだ暖簾が畳まれている。
「やってないんじゃないか」
「五時からだけどね、だけど大丈夫」
戸を開けて中にはいると、老人が開店の準備をしていた。
「らっしゃい、いつもの席でいいね」
「うん、適当にみつくろって、ビールちょうだい」
「あいよ」
われわれが席に着くと、ウナギ屋の主人は、料理の仕込みをしながら、串を炭火の上に載せた。
「よくくるんだね」
「うん、週に3度はね」
「そんなにウナギ食ってるんだ」
「まさか、裏メニューがたくさんあって、夕飯をくいにきているだけだよ、親子丼だって、お茶漬けだって、何でも作ってくれる、常連にだけだけどね、ウナギはお客さんが一緒のときだけたのむ、この店は食べ歩きの本などには載っていないが、一番うまい店だと思っているよ」
「あの食べ歩きの本は、店の宣伝用で、本当に舌の肥えたやつが書いていない」
大学の図書館には、学生の要望もあり、グルメの本もおいてあるが、どれも同じで、個性がない。
「見栄えばかりでね」
「そうだね、しかも高いとこばかり」
「ここは2000円の鰻重がいちばん高いものだけど、本当にうまい、だから常連は他に言いふらさない、みんなが、よほど親しい人じゃなきゃ連れてこないようにしているんだ」
「そりゃあ、光栄だな」
主人が、ビールと串焼きをもってきた。ウナギの肝だ。
「お、今日の肝、ふっくらしてるね」
「石垣さんがはじめてお客さん連れてきたからねえ」
「お世話になります」
私も主人に挨拶をすると、「石垣さんは動物に好かれる人でね、うちの気の荒いはちゃめちゃな猫が、この人にはこすりついていくんだよ」
「いまどこにいるの、鰻重は」
「遊びにいっちまってる、去勢したってえのに、もてるんだよあいつ」
「うらやましいねえ」
石垣と主人の会話がおもしろい。そうだ、石垣はなんで結婚しないのだろう。
「まだ、ひとりだって」
「うん、だけど、君だって一人じゃないか」
「給料が少なくてね」
「おなじく」
と言った結論に達したようだが、僕は本当のことでもあるが、石垣は他に何かありそうだ。
「今でも、脳を半分眠らしているのかい、イルカのように」
「うん、だけど、電話でも言ったけど、夜には寝るようにしているんだが、週に半分は起きているかな」
「その日の夜はなにをしているんだい」
「夜中の海で泳いでいるんだ、誰もいないのでゆったり泳げるんでね」
「それで、そんなにいい体格になったのか」
「ああ、ずいぶん筋肉がついたし、皮も厚くなった」
刺身が出てきた。鰯、鯛、貝類、さまざまである。
「この魚は石垣さんが釣ってきたんだ」
主人が説明した。
「釣りもやるのかい」
「夜釣りだよ」
「夜中を活用しているんだな、うらやましい」
うまい刺身である。
僕は大学の仕事が引けると、図書館に残って、西洋の降霊術の歴史をしらべている。夜は家で、その整理をしているが、すぐ眠くなってしまう。
「脳を半分ずつ寝かすのはどうやったらいいんだ」
「うーん、こればっかりは普通の人にはむりだね、生まれたときからなんだよ、気がついたのは受験勉強を始めころからだから、高校生のときだな、夜中に眠くならなかったんだ、ただ、不思議だったのだが、夜中になると、右利きなのに、左手でふつうに字が書けたんだ。練習なんかしないでだよ、そのときはどうしてかわからなかった、大学に入って、図書館に行ったら、ほら、医学部用の専門書がおいてあるコーナーがあるだろ」
卒業した大学は総合大学で、医学部があった。医学部の図書館もあったが、中央図書館にも医学の本がそろえてあった。
「脳の本がたくさんあって、右手は左の脳でコントロールして、左手は右の脳と言うことがかいてあった。それで、受験勉強の時、よく使った右手を休ませるので左の脳が寝ていて、右の脳の働きがつよくなって、左の手がよく効くようになったのじゃないかと思っているというわけだ。寝ることについても調べてみたよ、生物学の棚にあったな、イルカや渡り鳥が半分脳を眠らせることを知ったんだ。きっと俺もそうだ、と思ったわけだ」
「医者に調べてもらったのかい」
「いや、幸い、風邪さえ引かないくらい丈夫でね、医者に縁がない」
「そうだったな、うらやましいね、僕はアレルギーがるから、花粉の時期は大変だ」
「医者なんかに調べてもらうと、モルモットにされて、見せ物にされちゃうよ、やだから医者には近づかない」
彼の前に、ぶつ切りのうなぎがでてきた。しかも生のままである。
「お、きた、君もやってみるかい」
「生のウナギ食べるの」
「石垣さんのお気に入りなんですよ、こんなにウナギ好きの人いないね」
主人が笑い顔で説明した。
「ウナギの刺身だよ」
そういいながら、彼はぶつ切りのウナギを口にいれた。うまそうだ。そのあとビールをぐっと飲む彼の顔は笑みでいっぱいだ。
「学生時代はそんなことしなかったろ」
「そりゃあ、ウナギなんて食えなかったしな、実はこの喰い方はイルカの食事を見ていてやってみたんだ。イルカに魚をやると、うまそうに喰うんだ、そのとき、イルカの頭から喜びがわき出てきて、俺もそれを感じてね、最初は俺たちが刺身をうまいと言って食べる感覚かと思ったが、ちょっと違う、それで、生きのいい鰯をかってきて、頭だけとって、喰ってみたらうまくてね、俺の食べ方だど思ったよ、と言うことはイルカの食べ方なんだよ、太い骨の魚、鯛なんかは無理だけど、細いものは丸かじりがうまいことを知ったんだ。それで、ここの親父さんに鰻のぶつ切りをたのんだんだよ、うまかったな」
それを聞いていた主人が、「商売あがったりだよ、それじゃあ」と笑いながら団扇で炭をあおいだ。
「いや、焼いたのも好きだよ」
最後はお茶づけでしめた。
彼とはまた来ると約束をして帰宅した。
それから、彼とはメイルのやりとりを始めたが、僕の趣味としての、降霊術の調査も本格化してきたこともあり、なかなかあう機会はなかった。メイルにはイルカの写真も貼付けされていることがあったが、いつも彼はにこにこしてプールの脇でイルカによりそっていた。
そんなある日の朝、キッチンで新聞を広げると、イルカが盗まれると言う見出しが目に入った。石垣の写真ものっている。
静岡のあの水族館から三頭のイルカが盗まれたとある。犯人は水族館館長で、いるかの飼育係の石垣紀夫が重要参考人として指名手配されていた。
そういえば1週間前、彼のメイルに、旅行をするので、しばらくメイルができないむねが書かれていた。珍しいことだと思ったが、調度忙しいときでもあってそのままにしてしまっていた。
新聞には静岡の水族館の脇の海岸に穴を掘ろうとしたあとがあったと書かれていた。しかし、さほど深いものではなく、今回の犯罪には関係ないと結んであった。海に放して連れて行った可能性があるが、全く方法はわからないとある。ただ、とても一人でできるしごとではなく、世界的な犯罪組織がやったのではないかという。石垣紀夫はイルカを連れ出す役割で、そうするように強要された可能性が指摘されていた。
連れ出したイルカを売ることはむずかしく、盗み出す費用のことを考えると、金儲けのためではないだろうと言う識者の意見がそえられていた。それは、過激な愛護団体によるものの可能性を示唆していた。さらに、周りの人たちの意見として、石垣は無類の生き物好きで、イルカたちが最もなついていたということで、もしイルカがまとめて連れ出されているのなら彼が面倒を見ているのに違いないと言うことを言っていた。
あわてて、彼にメイルを送ったのだが、宛先がみつからないという、メイルが帰ってきた。メイルが消されているということは、いきなりこの事件が起こったのではなく、彼はそれを知っていたことになるのではないだろうか。少し心配になった。
刑事が会いたいといってきた。石垣のことだった。彼と最近会ったのが僕で、どんな話をしたのか聞きたいということだった。大学の図書館ではまずいので、家に着てもらうことにした。
マンションにきた刑事に卒業以来はじめて彼にあったことで、鰻屋でのでことなど、半分づつ寝るということができるということ以外は詳しく話した。刑事は石垣を疑ってはいなかった。やはり過激な愛護団体がやったことで、調教師だった石垣はイルカの面倒を見させられているのだろうと推測していた。刑事はおそらくもう日本にはいないと思いますが、きっと探し出しますと言って帰った。
彼は完全に消えてしまった。事件は解決の糸口すら見つかっていない。人々の頭からは忘れ去られており、マスコミから完全に消えていた。
これはあれから二年後のことである。
僕は亡くなった祖父と彼の写真をもって津軽に出かけた。西洋の降霊術の歴史に興味を持って調べていた僕は、日本の降霊術には知識が多くはなかった。しかもまだ降霊述そのものを経験したことがない。そこで、日本の降霊術で有名な東北地方のイタコに彼のことを聞いて見ることにした。彼はどこかでイルカとともにいると信じていたので、イタコがどのような反応をするか知りたいと思ったわけである。
イタコは死者の霊を自分に乗り移らせ、依頼者に死者の様子を知らせ、安心させるという心の安らぎをもたらす働きをもつ霊媒師である。東北地方には、名前こそ違うが、同様の信仰があるいろいろある。宮城にかけては「オガミサマ」、山形では「オナカマ」、福島では「ミコサマ」などとよばれている。昔のイタコは弟子入りをして、厳しい修行をしたといわれる。津軽のイタコなどは昔から伝わる形をしっかり身につけているという。
イタコというと、下北半島の恐山があまりにも有名であるが、イタコは恐山に住んでいるのではない。恐山の大祭のときに、イタコが集まり、霊をよびだす口寄せをおこなう。今ではそのツアーもくまれていて、イタコと話をする時間などとれるわけがない。もう伝統的なイタコは多くない。
僕がいこうと思った津軽の五所川原市の霊媒師も正式なイタコではない。八十をすぎた人で、子供のころ麻疹を患い、弱視になったという。密光寺という十三湖の脇の寺の住職の嫁である。
イタコを専門に研究している人が、学会であったときに、その人のことを教えてくれた。イタコは基本的には人間の死者をよびこむところ、その霊媒師は人間ばかりではなく、動物たちの霊を呼ぶことができるという。荒木詩玉さんという。電話で連絡すると、前の住職はなくなり、息子さんが住職を継いでいて、詩玉さんは畑などやりながら、頼まれると口寄せをやるということであった。
新幹線で青森にでて、バスで五所川原駅から。さらにバスの十三線にのり十三でおりた。東京から9時間もかかってしまった。
海とは反対側の十三湖の近くである。教えられた道をいくと、小高い石垣のうえに寺が見えてきた。石段をあがると、小さいがこぎれいな寺があった。十三湖がよく見える。隣にある墓地も手入れが行き届き、何しろ明るい。寺の陰鬱な雰囲気がまるでない。寺の敷地の一部に野菜畑があって、トマトやキュウリが勢いよくくっついていた。
向かいに出てきた今の住職、詩玉さんの息子がでむかえてくれた。
「きれいなお寺ですね」
「ええ、建物はもう百年はたちます、墓地も墓場も母がよく働くので、どこもきれいになっています」
イタコとして働いていることを言っているのかと思ったのだが、あとでそうでないことがわかった。
住職に案内されて部屋にはいると、詩玉さんが猫に囲まれていた。
「お世話になります」
「いんえ、おやくにたちませば、よろしいのですが」
丸いひしゃげた顔で僕をみた。大きな目の脇には深いしわが刻まれ、すいこまれそうな透き通ったひとみがあった。とても目がみえないようにはみえない。
そこに年に数回透き通るという十三湖があるような透明感のある目だった。
「イタコになられたことをお聞きしたいのですが、それに行方不明になっている友人のことも知りたいと思います」
僕は詩玉さんの前に座った。猫が二匹よってきて、値踏みするように僕の匂いを嗅いで、にゃあとないた。
「おまえたちはむこうにいっとき」
詩玉さんの声で、猫たちがそろって廊下にでた。
「イタコになったのは、五つほどの時ですか、麻疹になって、目が弱くなりましてな、ふつうの小学校にはいけません、目の不自由な子たちがいく学校いきました、そこでこのような目の者が一人で生きていく方法を学びました、少し大きくなると、まわりはぼんやり見えることから、そんなんでもできることなら何でもやりましたは。あんまも考えましたけどな、人にふれるのがいやでして、掃除婦になったのです」
「イタコをそこで教わったのではないのですか」
「いえ、私が正式なイタコではないことをお知りでしょう、ほんとのはイタコの弟子になって学ばねばならんです、そのようなことはしておりません、この寺の掃除婦になって、飯炊きやったり、本堂や廊下の拭き掃除、墓石の拭き掃除、ようやりました、それで、若かった住職が私を嫁にしてくれましてな、住職の妻になってからは葬式の準備なども手伝っておったんです、あるとき棺桶の中から声が聞こえましてな、死んだ人が私に話しかけよるんです、あんたを通して外がよく見えるというんです、驚きましたな。
私が見ている遺族の顔を、棺桶の中の死人(しびと)が見ることができるというんですわ、遺族や知り合いが涙を流しているのを見るのは死人にとって、とても癒されることのようでした、死人が家族の顔を食い入るように見入っているのがわかりました、そのことを、遺族にいいましたら、遺族のかたもおどろいて、およろこびになりましてなあ、なんかいもそのようなことがあり、私が死人の霊と話ができるという噂がたちまして、争議のときには私が必ず棺の脇に座るようになったのです。あの世で、病気だったのは治ったのか、なにをしているのかとか、亡くなった人の家族や知り合いが聞きに来るようになったんです。
私はな、そういうことで、イタコにされちまったわけです」
詩玉さんは自分からイタコになりたくてなったのではないようだ。ある意味では本当のイタコだろう。
ふっと、詩玉さんを見ると右目をつむっている。目が悪いといっても、両目を見開いて話していたのだが、突然である。
「死人から話しかけられるようになったのはおいくつのころでしょうか」
「そうよな、結婚してまだ子供ができていないころだから、40を少しまえのころでしょうな、息子は四十をすぎてからの子でしてな」
「死んだ動物たちの声も呼び寄せるとお聞きしたのですが」
「それも、やはりここでの葬式のときでしたか、散歩をしているとき、連れていた犬と一緒に車にはねられた若い女性の葬式でしたな。遺族は犬も一緒に棺桶に入れたいと希望したのを主人はうけいれまして、そうしたら棺桶から、その女性と犬の声が聞こえたんですわ、それから、死んだ動物たちの声も聞くことができるようになりました」
「どの動物の声が聞こえるのでしょうか、虫だったら、死骸がたくさんあってたいへんですね」
「一緒に住んだり、家畜としていたりする生き物たちで、みんなじゃありませんね、実は死んでいる動物ばかりじゃないんです、生きている動物とも話ができます。猫とは目で話すんですわ、コウモリはそのまま頭の中に聞こえます」
石垣と同じようなことを言っている。思い出したことがある。これもテレビで見たことだ。イルカの脳は半分ずつ寝ることができるが、右が寝ているときに左の目を閉じている、左だと右目だ。目の前の詩玉さんは今半分寝ている。右目をつむっているから左の脳が寝ている。
「それじゃ、イルカやクジラの声も聞こえるのでしょうか」
「聞いたことがないですけどな、きこえるかもしれんです」
「そろそろ、口寄せをお願いしようと思うのですが、いいでしょうか」
「はあ、どうぞ、なにも用意するものもありませんで、お名前を聞かせてもらえりゃ、よびよせますだ」
詩玉さんは両目をあけた。
「私の友人で、イルカの調教をしていました、そのイルカが盗まれて、彼もいなくなりました、名前を石垣紀夫といいます」
「生まれはいつでしょうな」
「あいつは僕と同じ1980年で、8月26日うまれです」
「しばらくおまちくださいな」
詩玉さんは顔をまっすぐにして、両目をつむった。両手はだらりと座布団のうえにのせ、力を抜いている。
やがて、その姿勢のまま寝息をたてはじめた。
5分10分とすぎていく。廊下にでていた猫たちがあつまってきた。
だいぶたったなと、時計を見たときに詩玉さんが目をあけた。
「石垣紀夫さんはなあ、聞こえませんな」
「だめでしたか」
ちょっとがっかりした。
「いえ、死んだ人しか私に話しかけてこんですから、生きとるということです」
「あ、そうですか」
「イルカも一緒かもしれませんが」
「それもわからんです、近くの海にきたクジラたちの声は聞こえるんで、イルカはいませんな」
「でも、あいつが生きているのならよかった」
「すいませんな、私は、本当のイタコではないんです、イタコの人たちは感じたことに、教わった方法で、話を作って、頼まれた人に安心を届ける、カウンセラーですが、私は声が聞こえたときその通りにつたえるだけです、もっとも、依頼者が驚くようなことを使者たちはいいますので、そこは加減しますがの」
「今回はその加減がありますか」
「いんや、まことに、聞こえません、生きていらっしゃる、そこははっきりもうします」
「ありがとうございます」
ここで、もってきた祖父の写真を見てもらおうと思ったのだがやめた。密光寺の詩玉さんは、ただのイタコではない。本物の霊媒師だ。きっと石垣と同じように、脳を半分ずつ寝かせることで、一日中考えている。死人と動物たちの声で満ち満ちているこの世の中で、いつも耳を澄ませているのである。
ここには何度か通わねばならない。詩玉さんの一生を一冊の本にすることは、日本どころか西洋の降霊術者の本質を世に知らしむことになる。
脳を半分ずつ眠らせることのできる人はこれで二人目だ。日本中にはもっといるのではないだろうか。世界ではどうだろう。文献研究だけではなく、今を生きるそういった体質の人を見出して、そういった人の能力を人間の未来を開拓するために使ってもらう。地球の大きな進歩となるに違いない。
「また、お話をきかせていただきにきてよろしいでしょうか」
「どうぞ、こんなことしかなあ、話すことができませんか、お役に立つことがあれば、なんなりと」
彼女はそう言ってくれた。
それから数ヶ月がたった八月のはじめ、詩玉さんの息子さんから電話があった。
僕にできれば来てほしいと、詩玉さんがいっているという。遠いところで申し訳ないけれど、大事な話しがあるということだった。
石垣のことだ。そう思った僕は喜んでいくことを約束した。
大学の夏休みは長い、休暇も取りやすい。
八月十五日、終戦記念日に十三湖にでかけた。
密光寺は蝉の声で埋もれていた。確かに暑いが、東京のそれと比べると、のどかで、むしろさわやかさがからだを包む。
玄関で声をかけると、詩玉さんが自らでてきた。
「よういらっしゃった、どうぞおあがりになって」
僕は東京から人形焼きをみやげにもってきた。こういうとき、とんと気がきかない自分にいやけがさす。考えても詩玉さんになにがいいのか出かけるまで思いつかず、自宅のある駅中の出店で買い求めたたにすぎない。
わたすと、「あれ、呼び立てたりしたうえ、このようなもんまで、申し訳ないす」
詩玉さんは左目をつむったまま顔を僕の方に向けた。半分寝ている。
部屋にはいって、座布団に座った詩玉さんにたずねた。
「今、半分寝てらっしゃるのですね」
「そうでもあるし、そうでもありません、半分寝ている頭に、コウモリの声などが聞こえます。それを起きている片方で意味をかいし、返事をしております。夜中に墓地の掃除をするときには死人の声が聞こえることもあります。それを理解するのは起きている方の頭です」
「そうなんですか、石垣も脳を半分眠らせることができました。イルカと話をすることもできましたけど、コウモリの声は聞こえるが理解できないと言ってました。」
「知っております、石垣さんと話ができました。今ではコウモリや他の動物とも話ができると言っておいでです、それで息子に電話をかけてもらいました」
「やはりそうでしたか、それで彼はどこにいるのでしょうか」
「日本海に来ています、十三湖の沖にいるのです、呼びかければ、浜にくるでしょう」
「海の中でくらしているのですか」
「そうです、イルカと一緒に暮らしています」
「今もはなせますか」
「できます、もうあなた様が来ていることを伝えました、石垣さんはすぐにでも会いたいが、人目があるので、夜中にしたいと言っています」
「今日の夜中にあえるでしょうか」
「はい大丈夫です、夜中の十二時に浜辺にくるそうです、寺にお泊まりになってください、浜までは歩くと1時間ほどかかります、浜にいけば石垣さんがみつけてくれますで」
「ありがとうございます、それだけしていただければ十分です」
「石垣さんは元気にイルカになっている、と伝えてほしいそうです、あとは直接おはなしするということでした」
「そうですか」
「息子には何日かかかると言ってあります、ゆっくり泊まっていってください」
「ありがとうございます」
そのあと、法事に出かけていた息子さん夫婦が帰ってきた。控えめな奥さんの目が半分つむっている。
「お世話になります」
「母から聞いております、寺には空いている部屋がたくさんありますので、どうぞお使いください、お食事は家内の作る者しかありませんが、ご一緒にと思っています」
とてもありがたい申し出である。
「部屋に案内して、私は失礼して服を着替えてきます」
住職は奥にはいっていき、僕は奥さんに案内されて部屋にいった。
「この部屋です、必要なものがあったらなんでもいってください」
やはり片目をつむっている。
「つかぬことをお聞きしますが、もしかしたら、詩玉さんと同じように、イタコをなさっているのですか」
「いえ、母のように死人の声は聞こえません、私はしておりません、目はふつうに見えますから」
奥さんはほほえんで両目をあけた。この人もイルカの声がきこえるのではないだろうか。
「コウモリの声は聞こえるのではありませんか、詩玉さんとおなじように」
そういうと、びっくりして、困ったように首を横に振った。
「どうしてですか」
逆に聞き返された。
「なんとなく、詩玉さんの振る舞い似ていたからです、失礼しました」
「義母に似ているといわれることはよくあります」と彼女は笑った。
そこに着替えた住職がきた。
「あの、海辺まで歩いてみたいのですが」
「ちょっとかかりますから、車で送りましょうか」
「いえ、周りの景色をみながら歩いてみたいと思っています」
「そうですか、海への道は難しくありません、間違えやすいところはありませんからご心配いりません、1時間くらいかかります」
「ええ、かまいません」
僕は道を教わって、十三湖の海側にむかった。1時間ほど歩くと、海岸沿いの道にでた。黒っぽい海面が続いている。今日の波は穏やかだが、冬には荒れるという。
海の浜辺は長い。どこに現れるのか、詩玉さんが教えてくれるだろう。
寺に戻ると、食事の用意がしてあった。
詩玉さんが、息子の嫁がとても料理上手なことを、嬉しそうに僕に話した。奥さんはなんだか恥ずかしそうにうつむいている。
「さあ、どうぞ」
息子さんがビールをついてくれた。
テーブルには昆布の煮物や新鮮な魚の刺身、煮魚、畑でとれた野菜、糠味噌漬け、それに味噌汁がならんでいた。
おいしい。広々とした畳の部屋の真ん中で、四人が普段着でテーブルを囲んで、素朴な手料理をつつく、おそらく自分にとって初めての経験かもしれない。都会の高い金額を払って食べる料理とはおいしさがまるで違う。味というのは、同じものでも一緒に食べる人、場所、空気によって全く違ったものになる。
食べ終わってしまうのがもったいない、そういう食事だった。
詩玉さんが、息子夫婦に「夜中も浜まで散歩されたいそうだでよ」と言ったら、二人ともうなずいていた。
「懐中電灯、玄関に用意しときます」
奥さんが言った。
眠れなかった。こんなとき、脳が半分眠れると身体が疲れないのだが。昨日長時間の電車の旅で疲れているはずなのに眠れない。
とうとう12時になってしまった。
着替えをして、寺から出た。あいつに会ったとき、みやげとしてなにがいいのか考えて考えて、結局おもいつかず、寺にもってきたのと同じ人形焼きの入った袋をつるした。
月明かりで懐中電灯は必要がない。会ったときになにを聞こう、そんなことばかり考えていて、浜へはあっという間についてしまった。
日本海だが昨日と同じで、波は少なくおだやかだった。砂浜にさらさらと月の光に金色に輝く波が静かに寄せている。
「おーい」
離れたところから黒い影が波の中から現れた。かけてくる。はやい。
あっという間に僕の前に石垣がたっている。黒く焼けた身体に月の光が鋭く反射している。つるんとして、それでいて、筋肉のかたまりのようでもある。
「すごいね」
僕が最初に発した言葉はそれだった。確かに石垣のにこやかな顔がそこにあった。だがそこには茶色のイルカがいるような錯覚におちいる人間がいた。
ぱっと見たら、真っ裸である。あ、頭の毛もない。下の毛もない。逸物がそそり立っている。
「かわらないね」
彼は大きなビニール袋をつるしていた。
「みやげなんだ」
「僕ももってきたけど、人形焼き」
彼は大きく口を開けて「わははは、人形焼き、なつかしいよ、うれしいよ」
おかしすぎで涙まで流している。
「向こうで食べよう」
浜から道にあがるところに吹き寄せられていた砂の山にこしかけた。
彼は渡した人形焼きをほうばった。
「うまい」
「どこに住んでいるんだ」
「海の中だ、イルカと一緒だ、場所はいえないが、海底の山の裾に海底洞窟をみつけてね、中には空気もあるし、真水もわいているしね、イルカも嬉しくてね」
「イルカを連れ出したのは石垣なのか」
「ああ、水族館じゃかわいそうでな、イルカたちがでたいといったんだ」
イルカと話ができるようになったのだ。
「どうやって水族館からイルカをつれだしたんだ」
彼は指笛をならした。
すると、波打ち際に三匹のイルカが顔を出した。立ち上がって、尾鰭を使って歩いた。
砂浜をゆっくりと、僕たちの前にきた。
一匹のイルカが僕の頭を口先でこちんとたたいた。
「こんにちはといってる」
もう一匹も、もう一匹も同じことをした。
「一度水族館であったといっている」
僕もたって、三匹のイルカの前びれをにぎった。
イルカがキュウーとないた。
「よろこんでいるよ」
イルカが前鰭をふって、海にもどっていく。ちょっとペンギンが歩いている雰囲気だ。
「あいつら、尾鰭で歩く練習をさせたんだ、よく歩くよ、それで、夜中に水族館から俺がつれてでたんだ。あそこ海が近いだろう、そのままあいつらはうみにはいった。俺も洋服をきたまま海の中に入ったんだ。まだあいつ等のように早く泳げないから、一匹の背鰭につかまって、日本から離れた。あいつ等と一緒に魚を捕まえて食べてね、小さな島にいたこともあったが、海底の洞窟を見つけて住処にしたんだよ」
「楽しいんだな」
「ああ、もう人間の生活には戻らない、だがこうやって会えないことはない、あの詩玉さんの声が頭の中に聞こえたときは驚いた。俺と同じような人がいたんだね、おかげで君と会えたよ」
「そうだね、降霊術の研究をしていてよかったよ」
「霊媒師というのは、イルカに近い能力をもっているのにちがいないね」
「詩玉さんは死んだ人ばかりじゃなく、ほ乳類の声も聞こえるそうだ。もちろんイルカ、コウモリなどの超音波発声もわかるそうだ。やっぱり頭を半分眠らすことができる」
「そうだろうな、詩玉さんがいれば、また会える、これはね、みやげだよ」
石垣が大きなビニール袋を開いた。中には立派なサザエなどの貝がはいっていた。
「食べてくれよ、詩玉さんたちにあげてくれ」
「息子さん夫婦もいい人たちだ」
「それとこれだ、俺がもっていてもなにも役に立たない」
ビニール袋の中から、小さなビニール袋をとりだした。中のものは小判だった。
「すごい数だな」
「大昔に沈んだ船から見つけたものなんだ。役に立ててくれよ」
「どのような船だったんだ」
「木でできた船のだ、日本のだよ、もうばらばらだったが、砂の中から、小判がでてきた」
「どうしたらいいのかな」
「浜に打ち上げられていたのを拾ったことにしなよ、自由にしていいから」
「詩玉さんにあげてもいいか」
「もちろんだ」
イルカたちが波打ち際に来て、尾鰭で立ち上がった。月の光の中で体を動かしている。三匹同じ動きだ。
「あいつ等、海の中でもああやって踊るんだ、歌を歌いながらな」
「いつも違う歌だ、創作能力は人間以上だよ、俺も退屈しないんだ」
「元気でよかった」
「いや、詩玉さんに声をかけられたときは、やっぱり嬉しかったよ、おまえさんのおかげだ。人間と連絡ができたんだから」
イルカたちが胸びれを動かしている。
「帰ろうよ、っていってる、それじゃまたどこかで会おう」
「うん、僕もいつか、海のそばに住むようにするよ」
石垣が立ち上がった。波打ち際まで一緒に歩いた。大学時代の友人が、こんなことになろうとは全く想像もできなかった。
石垣が握手をもとめてきた。焼けた顔に目が輝いていた。
「海の底は珍しいものばかりだ、きれいだぞ」
「元気でな」
「おまえもな」
石垣はイルカと一緒に海の中に消えていった。
胸の中が熱くなった。感動のためだ。別れのためではない。いつでも会えるんだ。
大きなビニール袋を持って、海沿いの道路まであがった。
ふっと道路脇を見ると、小型の車が止まっている。その前に二人の人間が立っていた。
「お待ちしてました、すべて聞いておりました、イルカたちの声も」
住職と奥さんがそこにいた。奥さんがそう言った。
「わたし、主人の母のいとこの子供になります。この人とはふたいとこになります。ひいおばあさんとおじいさんが同じと言うことです。今日、コウモリの声が聞こえないと言いましたが、私にも聞こえます。主人も知っています。でも、義理の母をみていると、大変そうで、私は霊媒師にはなりたくありません、それに私には死人の声はきこえません。動物の声だけがわかります。だけど、今回のことを聞いてしまって、私も協力してもいいと思いました。イルカたちの為にもなりそうです」
やっぱりそうだった。
「車に乗ってください」
息子さんが車の戸をあけてくれた。後ろの座席に腰掛けると、二人は前の席にはいった。
「ありがとうございます」
私は頭を下げた。息子さんが車を出した。
寺に入ると、玄関で詩玉さんがまっていた。
「おかえり」
「お義母さん」
息子さんの奥さんが驚いたように詩玉さんを見た。
「知っとったよ、お茶入れてある」
私たちは座敷のテーブルにすわった。
「詩玉さん、石垣とイルカにあえました。あいつはイルカになっていました。元気です、詩玉さんに声をかけられたこととても喜んでいました」
「よかったなあ、海の中で暮らせる人間なんて、不思議なことで、それに、紅実さんがのう、私と同じだということを明かしてくれましたから、私が死んだあとも、石垣さんやイルカたちとは連絡できますからなあ」
「お義母知っていなさったんですね」
「ああ、法明(のりあき)の嫁になるまえからの」
住職は荒木法明、奥さんは紅実(あけみ)である。
「でも、私には死人の声は聞こえません」
「それのほうがいい、決して楽しいものじゃないからの」
「石垣が、これをみなさんにと言うことでした」
大きなビニール袋を住職に渡した。
「こりゃすごい、大きなアワビやサザエだ、このビニール袋のものはなんですか」
息子さんが小判の入っているビニール袋をとりだした。
「小判です、石垣が大昔に沈んだ船からみつけたものです、おそらくご用船でしょう、自分には無意味のものだから使ってほしいと言うことでした」
「それじゃ、石田さんのものですね」
彼は僕に小判をわたそうとした。
「いや、僕では処理できません、どうぞ、荒木さんのほうで、利用してください、浜に打ち上げられていたと言えばいいと、石垣も言っていました」
「この近くの海でみつけたのでしょうか」
「詳しいことは話してくれませんでした」
「わたしがきこうかね」
詩玉さんが片目をつむった。すぐに
「石垣さんがそういっているよ、浜からそう行かないところに沈んでいるそうだ」
小判に関しては荒木さんが考えてくれることになった。
「石垣さんも海の中では奥さんはみつからんなあ」
詩玉さんがいきなりつぶやいた。
「どうしたんですか」
僕がきくと、
「石垣さんは奥さんをほしがっている」
そういった。きっと石垣の脳がそう思っていることを詩玉さんには感じられたのだろう。
私は言った。
「あいつは、きっと、人魚がいると信じているんです、卒業研究で人魚のことを調べているうちに、人魚を捜す気になったんだ、人魚もイルカの仲間だとおもったんだろう、自分と同じように半分づつねることができる生き物だと思ったんですよ、人魚に恋をして、イルカのように生きればあえると思っている。竜宮城を探しているのだと思います」
僕は熱く彼の学生時代のことを話して聞かせた。
あれから十年、詩玉さんは百を越えたが、まだ元気に霊媒師の役目も果たしていた。あの小判は市の博物館に寄贈され、沖合にしずんでいたという船の調査も行われている。
今では紅美さんが石垣との間をとりもってくれている。イルカとも話をして、イルカの本を書こうとしている。僕が代筆をすることになるだろう。
僕のほうは世界の降霊術の本をまとめ上げた。もうすぐ出版される。
石垣からはまだ人魚に会ったという報告はない。
必ず会える。僕はそう信じている。
半眠人


