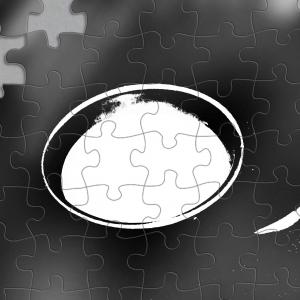「星の祈り」
白い靄のなかを
ぼろ切れにくるまって歩くのが居る
酷い身なりだ
その両脚にはナイフの切り傷が迸り
ふくらはぎには鞭の痕
太ももには鎖の圧
背中と腕はぼろに巻いてあるから
目には見えずとも
鼻には夥しく滴る生血のにおい
足元に流れて
淀ませて
自ら血池の地獄にひたひたと
足を温めるためであろうか
持つのは涙でぐしょ濡れたぼろ一枚
涙がせめて消毒液ででもあったれば
背中も腕も激痛と共に治癒のなされようものを
涙は飲み水でしかなく
命を繋ぎ留めても
傷は癒せない
せめて周りのこの靄が
むらむらと湧き立つ白靄が
やわらかな綿布団となればいい
そんならいつでも倒れられる
一生目覚めずに済む…
白い靄は歩けと言う
火薬を呑んだ酔っぱらいどもの命令でなく
浮世の空に水を湛える赤りんごの白花の祈りであろう
ぼろと共に歩く者には
薫りたかい乳の川が、天の川がひき添って居る
夜に愛されしは幸ひ
星に慰められしは幸ひ
その瞬きは
瞳の此方を見つむるあかしであるから
「星の祈り」