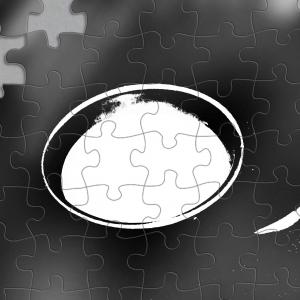「サーカステント」
一
私の傍にサーカスは無い。けれどもサーカステントの絵だけはいつも栞の額縁におさまって傍に居た。外からは見えない、だからいつも垂幕の中蝶と蛾が三日月の下で踊っていることばかり想っていた、病室の中それはそれは楽しいのだ。
この栞がこの病室にほんとうに建って在れば、軽業師と云ふものは如何であろう、絵で見たことはあるからそのまゝそのとおりなのだろう、ヴァイオリンを弾いてくださるのは嬉しいけれど、夜中になっても奏でていられては一寸まずい、あゝ、だけれども、三日月にはよく沁みるだろう。
味のよく沁みた大根、温かくて、この季節には嬉しいものだと聞く、満月をかろくお箸で割って少し白色な内側は。
心のやわい部分に触れる、それは自分でも怖いもの。けれどそれが無遠慮に温かければ思わずほっとしてしまうだろう、泣いてしまうのは変らないけど…
涙は空に昇ると云ふ、そしてまた雨になって池に泉に湖になって身体に帰って来るのだと、涙を吐いて涙にまもられ、まるで命そのものが一つの大きな瞳であろうような、なんて、むずがゆくて少し笑う。
たとえ私が笑っても、障子の向こうの硝子窓には届かないし、映らない、映ったところで見たところでこの両眼は笑顔を認知するまいか。
白百合と言う妙齢の娘は病気がちではあるが、全く動けない歩けない容態でもなく、頭を動かし布団を起きて家中を歩くことも度々あり、気分が良い日には料理もしてみせる程ではある、一向に外への一人歩きを許されない理由は病んでいるのが筋肉ではなく神経ゆえ。
その日は日清戦争に勝利した日だった。白百合の家は郊外の高台に建つので街の喧騒や熱狂いとは程遠く端正な別邸のような屋敷であったが、朝の日課の庭の水やりと手入れを施している時、急に倒れて半時目を覚まさなかった。外傷は一つも無く、何気なく覗けば令嬢が穏やかに眠っている横顔、けれどもその頬は雪の如く白く冷たかった。名前が名前であるためにその姿雪花とよく称されたが今は雨に冷えた消えかけの花、誤って溶けてしまいはせぬだろうかと、両親と兄と給仕の者達は変る変る様子を見に急いでは息をしている姿に肝を煎た。
彼女は祝福されていない子だった。
名前の意味白百合は「無垢のまゝ早死にする」まじないにちなみ与えられたもの、可憐な瞳は実を結ばない、子供を産めない働けない神様はずっと蔑ろにされていた。
「日清戦争。」
嫌な響きだ嫌な響きだ。これのために家族は出払って仕事をしに行ったけれど、戦争の為に動くことなんて無い、それならいっそ戦争事態を起こさせないようにうろうろすればよっぽど良い、のに、お前は産むことも働くこともない身だから永遠に分かる筈無いなんて兄さま、分かりませんよ、分からないもの、この身が夭折した者を抱きしめ続けるものだというまじない以外分かりません、貴方の表情だって!
「ごめんください。」
ひどく堅実な声がした。此処に人は来られないのだけど、庭の野薔薇と白菊の間からそッと覗く、軍人の男の人の背中が見えた。
二
お客様が来た時はにこりと笑って出迎える、お互いに深く頭を下げる、相手の目をまじまじと見つめすぎないようにして挨拶をする、それから季節の話をする、けれど花の話はしてはいけない花は後散るだけだからお客様の縁起に悪いと。
「ごめんください、何方か。」
どうしよう、使用人はまだ来ない。だってこんな曙から…
トントントン
戸を静かに叩く音。お客様、私作法は知っているけれど、それだけど、一度もしたことがない、許されたことないし許されたいと思ったことも。
引き込もうと身体を後ろへ引いた途端、野薔薇が白菊に赤く悪戯をした、あッと声が出てしまう、指で押さえても蝶々は既に彼の耳に溶けてしまった。
「あの。」
振り向く眦は涼しいけれど帽子を深く整った頭にかぶり眼光は暗く月影のように淵も深く静かに映る、清らかな鼻筋緊まった顎、唇は薄くも凛と恐れを知らず、一言。
その声に応えない訳にもいかなくて、白百合は順序も違えてパッと面を伏せたまま素足にからんで案内をする萌黄の蔦の音も分らず歩み寄る。
「もし、お嬢様。」
「白百合です。」
「は、」
「お嬢様ではなく、白百合だと申すのです。」
「あゝ、これは失礼を。白百合様。」
「はい、あの、何方さまですか。」
「昔、此処に迷い込んだ羽虫ですよ。」
青年は帽を取り、後ろで一つにまとめた長髪がはらりと動く、頬に微かに掛かる毛先は少し癖があるものゝ芯はどうやら乱れてはいない、が。
「頬。」
顔を見上げずとも彼女には感じた。この青年、齢の割に深い刀傷を左右の頬に浴びている。
「待って、貴方は」
箱入り娘は面を上げてしまった。青年はニコリと微笑む、物言わぬ月のように微笑んでいる。
しまった、奪われる。
「白百合様、忘れたことなどありませんでしたよ。」
とけていく、まじないが、身体がどんどん軽くなる。
その日は敗戦の日であり、終戦の日、神々が人と袂を分かった日であった。
三
月夜を見張る雲の色、隠したまゝに雨を降らす、氷のような雨の中恋人どうしはキスをする月影密かな壊れた街。手と手を繋ぐ恋人の微笑みを見つめる者がある。
「姉さま、帰りましょう。」
彼を野暮と罵る勿れ。
「うふゝ、綿のような雨が降るわ。」
夜でも虹霓の輝きは失われない。
…失っても良いのだけれど
いつものように弟君は《おとうとぎみ》は―彼は貴船雪影と言う然る名家の嫡男である―姉君の螢を迎えに訪れた。けれど螢は恋人と逢っている最中、弟のことを気が付かない。けれど、螢に恋人など最初から居ないのである。
いつも二人は家の庭に母が誂えたブランコに並んで座って漕いでいた、二人乗りに丁度良い木造りの不思議な小箱に姉弟なかよく手を繋いで遊んだもの。
「白百合様を人間に。」
木漏れ日のあふれる空の下、雲の無い湖面を見上げて初めて言ったのは十二の時、雪影は八つであったがその時の姉の横がほを忘れない。邸には医者が駆けていく入れ交り、侍女も下人も丁稚も紅茶どころの騒ぎでなく螢の大好きだったティーカップはその日から蔵にしまわれた。
「姉さま。」
呼んでも
「なあに、私のかわいい雪ちゃん。」
穏やかな日射しを溶かした微笑みで応えてくれることは無い。瞳は露を吸った梅の如く、唇もなめらかな菖蒲の手ざはりのようで色も失せぬが誰の声にもせゝらぎの声をおくること無く宙で何かを掴みたそうな細い指、割れてしまいやしないだろか。
「自分を捕まえているのだ。」
ブランコに乗っていくら美しい庭だからと雖も大人の悪口は聞こえるもの、名前が螢だから螢を追うのよ―意地悪い男女はこれだから、貴方がたの悪口が此度の戦争を引き起こしたのに。
日本は挑み、戦き、負けた。自国の歴史の中でも死傷者を産まない戦など無かったほどの脆弱でありながら他国に仕掛けるなど勇の字を与えるのも痛ましいほど愚か、ましてその所為に幾夜寝られぬ闇が続いただろうこの小さな島国に。あの人達が悪口さえ言わなければ、姉さまの教えを信じていれば、
「悪口だけは絶対に言ってはだめよ。白百合様が悲しむからね。」
貴方がたも傷付くことは無かったのに。
雪影の家は爆破こそ免れたが愛息子が戦地に赴いたた為誰も生きた心地がしなかった、外傷の無い者の手負いは計り知られず。母と父は毎日郊外の高台に建つ氏神様げお参りに行きどうか息子が死にませんようにと心願を込めた、使用人達も僅かな身持ちの中から若様の御為と真心の供え物を贈った、姉君はいつもブランコに一人で座って居た、色ある霞のようにふんわりと。
だが雪影は銃弾打ち交う前線に配された訳ではなかった、かと言って通信技師をはじめとする名の知れた裏方に回されたのでもない、彼は生来の有能さと冷静さを買われ決して新聞には載らない役を着せられたのだ、自国の兵の殺害を。それは味方の士気を上げる為、仇討ちという一時の凄まじい鎧を造る為に必要とされた鉄、恰も敵兵に襲われ無念の内に死んだような状況と様相を作り出し、かつ疑念を挟まれないように幾つかのパターンを持たせ時に応じてパターンを混ぜたり逆に要素を減らしたりして舞台を演出し続けたが、終戦のひと月ほど前その役目は閉じられた。
「もう此方側に力を回す余力も無いのだろうな。」
一時間前まで白湯を飲み語り合っていた仲間の腐った臓物を裂き乍ら最後の仕事をこなす頭でぼんやり考える、その横がほは邸に住んでいた頃と寸分違わず顔色も変わらず。
「そろそろ敗戦が濃厚なのだろう。」
呟いても咎める上官ももうおらず、佩剣の血を脱いだ帽子の内面でぐいと拭って鞘におさめて深く被り直す。
(姉さまは御無事だろうか。恋人と一緒に居られるだろうか。)
こうして雪影は山を下った、妙に寒い夏の夜に。
四
恋人と言うのはやはり目に見える形でないと他人には分かり辛いのだろうか、しかし自分以外に恋人の姿を見せたくないと考えた者もいたのでは。そう思うのならば螢の恋人は後者の部類に入るだろう、恋人を認知し理解し逢瀬の度に麗かな微笑み、正しくその恋人は彼女以外には知ることの出来ない存在である。こうまで言えば彼女はとんでもない嫉妬焼きになるだろう、しかし花は露を拒まず濡れる姿さえ誇りに思う、つまり、意固地を産む憂いも嫌疑も憎悪なども螢は持ち合わせておらず聞かせるのはすなおな喜びだけ。…となると前者に話は戻る。
姉さまは隣に誰かが居られる振舞いをなさる、それは姉さま以外の者からすると幻覚を見ているとなるらしい、そして憐れみか嘲りを与れてやらねばならないらしい、私にはどちらも出来なかった。だって、ほんとうに楽しそうに静かにはしゃいで、「白百合様、白百合様」と仰有るのだもの。
白百合様を人間に、ふむ。
五
「どうして私を連れ出したのです?」
「白百合様ならば既に御存知でしょう。」
「私は貴方を知りません。」
「私はまだ生きていますからね、若死をしたわけではありませんので。」
「ならば何故、此処に来られたのです。」
「…………。」
「言いなさい、答えに因っては貴方を早死させなくては」
「出来ないでしょう、貴女には。」
「!私は」
「貴女は夭折した者を抱きとめ続けることしか出来ない筈、命を奪うまじないはお持ちでない。…それは兄上様のものなのでしょう。」
「なんでしってるの、」
「この軍服で人を殺さないことはありませんよ。」
「兄さまを人殺しのように言わないで。私が病んでもどなたも殺そうとしなかったのよ私の家族は。」
「神々はもうとっくに人界との関わりを絶ちましたよ。否、正確には絶たされたと言うべきでしょう。もう貴女方が人を守護したりその逆をする必要が無くなったのです、聞こえませんか、人間の“神などいない”と悲しむ音が。」
「私を、殺しに来たの。私を殺しても父さま達や人々を喜ばせるために?」
「いえ、私は神々を憎んではいません、この戦争が始まってしまったのは家の使用人が悪口を吐いてしまったから、兄上様やご家族親類の所為ではございますまい。それに幸い姉さまは御無事でしたから、ためにこうして貴女にお目通りを。」
「押し入りをお目通りだと正当にしないでください、私は貴方の手でまじないを奪われた。もはや枯れることを待つだけの身、神は死ぬことも許されていないのです。」
「ならばその名はとんだ嫌味ですね。」
「……」
「…とんだ失礼を。」
「失礼ではありません、このまじないも名前も無くすことは出来ないのだから。誰も喜ばないものではあれど、不要なことではありません。」
「……はい、そうでしたか…。思えば私が手に掛けた者の中には貴女の両腕の中眠った者もたくさん居たことと存じます。……」
「答えなさい。」
花々の庭は天ノ川のように際限が無い、その一輪一輪に絶やさず忘れず白露を含ませる雪花の娘は立ち止まる。
「貴方の姉は、何者なのです。」
淵の三日月の淀まない眼光冷然として
「人ですよ。」
当然であると含みを持たせた。
六
螢は露草に止まりほのかな光は月の其を取次ぐようにやわらかく。その優しい光のように育ってほしいと願いを込めて白百合の親は螢の母を貞淑のまゝ孕ませた。医師も夫も首を捻って魔に呑まれたのだと呆れるばかり当の本人はぼんやりと熱病に頬を紅くし涙はさながら林檎の雫と言うもので。容態は日増に悪くなるどころか良くなる一方で身重の令嬢の顔色にしては花は衰えず美しい露や霞を吸う蝶々さながらの微笑みであった、螢が生まれてからもそれは変わらず。
両親は氏神様へ毎日参り、深い信仰は澱無き山奥の湖の如く、喜びと感謝は慎ましくも清き千尋のよう。うつくしい家はうつくしいまゝ、螢はやがてかわいい弟の面倒を見れる愛らしいお姉さんになった。
雪ちゃん
父に、母に、姉に、庭の光射すブランコの中呼んでもらったのを想い出す。変わらない穏やかさと懐かしさと、今でも少し甘えたい気恥しさが混じりあって白い光になる、その光はどんな形をしているのだろう、やはり丸い形だろうか。壊れ続けながら回っていくあの形。
左胸のポケットから油の入った方位磁石を取り出す。それはカチリと丸い金の蓋を開けると眩し気にくらくら北極星を探すので、幼い頃からいつも寝起きの人のようだと螢に話していた。
「そうね雪ちゃん、でも寝ぼすけだと危ないわ。」
どうして?
私の問いに微笑まれた、白百合様に恋うる一年前。
「姉さま。」
今は雨、今日も螢はふらりと家を下りて人の居なくなった街を靴音微かに歩いている。目は空を仰ぎ黒雲の向こう失せぬ太陽を見透すか、雫も綿だと嬉しがる…背景がこうでなければ万人が求婚せずには堪らぬという可憐な白藤であるものを。病める月に人は心を動かすが、微笑む白花の前では等しく押し黙ると聞く。ましてこの時、人にとって最も見たくないのは螢のような存在だったであろう。花を人だと認め想うのはもうこの世に雪影たゞ一人であった。
降り止まぬ日は両頬の傷がじくじく疼く。
この傷は最初からあった訳でない、徴兵に志願し自身の役務を果たす時、一度だけ誤算があったのだ。首筋を掻き切って絶命を確かめた後、川で赤を洗い流すのに死体に背を向けて顔を洗っていた時、がさりと腐葉土が蠢く匂いがした、と同時に身体を倒し切ッ先のぶん、と振るう音が耳を切った。
態勢を整え敵兵かと睨んだ先には、首からだくだくと血を流しながら仁王立ちする日本兵、外国が恐れた忠と執の具現化そのもの。手負いの者が一番恐ろしいと任務に当り上官に教えられた一言を思い出す。
だから必ず殺せとも。
刃こぼれした剣が震えている、向こうはもう長く保つまいが爆発は一瞬で人を殺す、まして自国の裏切り者など一瞬力が入れば容易に八ツ裂出来るであろう。向こうが倒れるのを待つことは駄目、此方から狙った時仕留めに行かねばならない。
銃声は今日の計画には無く、面白がられて慰みの片手間に殺された、痛がることを笑っていたような敵の人物像を産み出す為に此処では刃物を多用したのだ、釦留を掛け違えては後々軍全体に歪みを作る。ベルトに装着していたナイフを後ろ手に抜く。
もう裂いた両眼では相手の位置も分るまいが、現に彼は耳たぶを切り落とす寸前までに到っている、あの剣は長いから懐に入り間合いを崩し、確実に一ト突きすれば良いか…この身も無傷では流石に済むまい。息を吸って息を止める、あの出血量ではもうじき重心を失うだろうからその一瞬を狙わなくては。
かひゅーッ、かひゅーッと血染まりの白歯を砕けとばかりに喰い縛り唸る呻きに漏れて絶え絶えの呼吸音を確認すると大声はもう出せないのだなと直感する、ならば末期の叫びで味方に知らせることは無いであろう。もう崩れるか、さて一足。
雪影の脚は寸陰を以て手負に飛び掛かり、剣持つ右手を確乎と留め獲物を左胸へと押し込めた。げぼりと吐いた一矢報いんとする最期の血玉もあっさりと除けられ洋刀も手を離れ、兵士は見えぬ敵の足下に倒れる―まだ指なら動く!
もはや肉塊の強く摺れるだけの音を鮮血に混ぜながら雪影の両頬を十指で強かに引ッ裂いた。
潰れかけた指でまさか手傷を負わすとは。雪影は痛みで思わず蹲り、しばらくその場を離れることが出来なかった。
頬を怪我した程度では軍が乱れることは無かった。「山の斜面を滑落して負傷した」と話せば仲間は信じたし、雪影は行軍に遅れがちな者、身体が人より少し弱く無理に招集された身、として溶け込んでいたのも役立った。
「貴船、しっかりしろもうすぐだ。」
「これ食っていいよ。」
「お前みたいなのまで招集するなんてな。」
「貴船の意志を尊重しよう。」
「自分達は日本の為に死ねるのだから。」
生きて帰る心積りを捨てられた者だけが山の行軍部隊であった、敵地に進んでいると信じる者達は優しかった。姉さまとは違う明るさは見つめきれずたゞ眩しかったから、私はいつも俯向いて小声に「あゝ」とか「うん」などと返事をするばかりだったと思う。
貴方がたは国の為に他国の人間を殺す、
私は国の為に貴方がたを殺す、
どちらも行動に変わりは無い、それなのに。
目を閉じて眠ってしまえば、仲間の誰かがあの兵士になって首を締めて来そうで怖かった。初めてその晩恐怖心を抱きながら任務を終えた。
七
家族は誰も帰って来ない。兄さまの綺麗な黒髪も、母様の氷水も、父さまの草花を剪定する手つきも、人は私達を嫌ってしまったから。恐れではないたゞの嫌悪。
昔、花簪を両手に抱きしめていた男の子が迷子になったことがある。それはもう日清戦争よりも前の時で、その子の顔もよく分らなかったけれど兄さまに言われたのは憶えている、この子はもうすぐ私の膝元に来るのだと。
人の死にも幾つかパターンがある。寿命、罪人の処刑、私の家族が直接手を下すものも。それらに直面して人は悲しみもするし弔いもしてくれる、あなた方が少しの旅立ちの為に死者を丁重に埋葬或いは火葬水葬してくれる心の持ち主でほんとうによかった。お蔭でこの庭の花々はこうして美しく開くのだから。悲しみを大切にしまう決して無下に取ッ払わない人でよかった。
けれど悲しみにはいつも喜びが付いて来る。
「頑張って生きたね、ありがとう。」
「生まれてきてくれてありがとう。」
「ざまあみろ処刑だって。」
「当然の報いさ良いことよ。」
悲しみが幾通りあるのなら、付随する喜びも様々だ。その色までは分からないけれど、私の下に来ないのは充分分かる。
私の元に来るのは無垢の者の不慮の事故、概して幼子や若者の早死した人達で、この子達自身はぽかんとした感じでまあいいのだけれど、大変なのは残された人達の声。
「どうしてあんなにいい子を」
「私の赤ちゃん」
「あんなに優しい子が殺されるなんて」
「轢き逃げだなんて、殺してしまえ」
どうして、どうしての嘆きと元凶への怨嗟復讐そして神への恨みと絶望。白百合は人間の一番美しいものと恐ろしいものの両面を膝元に抱いて魘され乍ら一輪、一輪と花びらを咲かす。
人から望まれない意味でも白百合は最も先に人から離されることになるだろうと言われていた、もう何度も何度も家族から。
良いわ、嫌っているなら此方からまじないの力を捨ててやる―そう一人意気込み家族にばれないよう振舞い振舞いある日花簪の男児の様子を聞いたので、
今が狙い時。
「迷子なの?」
少年は私の声にハッと振り向く、けれど山道には誰も居ないよ。
「誰?」
震えてる、そうか、怖いよね一人の時にいきなり声だけしかしないなんて。怯えても花簪を絶対に落とさないよう強く抱きしめているのはいいけれど、
「そんなに強く握ったら壊れちゃうよ。」
「死んじゃうの?」
あれ?ちゃんと通じていなかったかな
「お姉ちゃん死んじゃうの?」
誰?
「いやだ、お姉ちゃんを殺さないで、お姉ちゃんを連れて行かないで!」
ぼろりと頬を崩しながら幼い子どもは泣き出してしまった、その涙は光の射さない魔所なのにきら、きら、と形が分かる。まろい涙は甘そうに滴り思わず指先で舐めとった。
「誰?」
ごめんねこたえてあげられない。人前に姿を現す心算では無かった、この状況で人と口をきいてしまえば私はまじないを捨てさせられる、始めは望んでいたけれど貴方の涙で気が変わったの。
「かみさま?」
まあね。今上手に微笑めているかな。
「あの、お姉ちゃんの病気を治してください!お姉ちゃんもう何日も熱が出て、ずっと寝込んでるんです。このままじゃ死んじゃうって、もう、お医者さんもどうにも出来ないって、せめてかみさまの育てる薬草でもあればって!」
神の薬草、か。また古い物語を叔父さまがばら撒いてしまったのだろう、あの方は本当と嘘を分からなくする神様だからご自分ではたいそう楽しそうだけれど、兄さまはあんなのにはなるなよと私の頭を呆れながら撫でていらっしゃった、父さまも母さまも確か困ったように微笑んでおられた気がする。
そんな物無いよって、どうしたらこの子に伝わるだろう。
「お姉ちゃん皆のために毎日朝から晩まで働いているんです。でもそれで体壊しちゃって、ずっと具合良くならなくて、それでも僕の名前を呼んでるんです、お腹空いてないかって、遊びに行っておいでって、ねえ、お姉ちゃんお姉ちゃんお姉ちゃん、」
あゝ、この子はもう。
「白百合。」
父さまの鋏の音がした。魔に憑かれた人はそれを知らないまゝ終うのが良いと。
「私の下に来ると兄さまが仰有ったのです。」
「またいたずらをされたね、困ったお兄ちゃんだ。」
「あの簪、どうしましょう。」
「寝ている娘さんに返してあげなさい。」
「その子は何処に?」
「今頃母さんの所で遊んでいるよ。」
「では行って参ります父さま。」
落ちた花簪を拾って撫でて家へと駈ける。
人は誰かの日常を奪うのが私達に似て上手らしい。
八
雪影が六つの時貴船の人々はサーカスを観に行ったことがある。人が人には出来ない真似をしてみせるのは幼心にも瞳を輝かせたがなんだか少し寂しくなって置き去りにされた不安も感じさせた。その弟の様子を悟ってか螢は何も聞かず彼の手をきゅっと握ってくれた、べそをかきかけの強がりの瞳を指で優しく何度も撫でてはまた演舞に魅入った弟を見つめ、サーカスが終わるまでその目を決して逸らさなかった。
「姉さまはどの演目がよかったですか?」
「そうねえ、どれも目まぐるしくって、まだ色がチカチカするくらい。」
「僕は、空中ブランコが好きでした。あんな高い所でくるくるッて、どうして目も回らずにあんなこと出来るんでしょう。」
「雪ちゃんは高い所怖いもんね。」
「今だけです!大きくなったら、いえ、もうこれからは高い所など平気です、あのサーカステントのてっぺんだって怖くありませんよ。」
「そう…それは頼母しいのね、……あゝ、」
何か目早く見つけたのか、螢はサーカス小屋の出店の前で親父に声を掛ける。
「もし、すみませんが。」
「いらっしゃい。」
「此方の、」
と言って指差ししたのは黄金鎖つやゝかな方位磁石。
「コムパスをお一つ下さいな。」
「あいよ。」
店主はサーカスの場には似ない無愛想のぶっきらぼう、それでも仕事は丁寧に几帳面らしく太い指で細かに硬貨を数えながら商品をきちんと姉君の手に。
「雪ちゃん、これをあげましょう。」
真ん丸の小箱は弟の両手に握らせて、
「これがあるとね、決して迷子になりません。何方に北極星がいらっしゃるのか教えてくれますからね。」
「北極星さまが分かれば迷子にならないのですか?」
「えゝ、帰る場所さえ迷わないなら魔に憑かれることもありません。いい、雪ちゃん。」
まだ知らないものばかりのほのかに白味がかった瞳に自信を映した。
「それだけは絶対に手離しては駄目よ。」
笑っていない姉さまはその時だけだった。
「そのサーカスは人の行うものではありませんね。」
「えゝ、ですが家には招待状が届きましたので。」
父がいつも読書をする時開いた頁には見慣れぬ栞がひっそり挟まれていたと言う。細長い線にきちんとおさまったサーカス小屋の影絵、外観しか分らず中は見られない。縁取りは淡く薄墨をぼかした誂え。
「白百合様、行かれたことは?」
「ありません、私は病気の身なので。」
「私と姉さまは初めてでしたが父と母は二度目だったとか。一度目は二人で湖畔を歩いている時、たんぽぽの綿毛がふっと飛んで来たんですって、こんな山中の冬の時期に珍しいと朝焼けの空に透かしてつまんだそうです。その翌日に姉さまを懐妊されたようで。それから次の三日月の日に招待状が届けられていたんですって。」
雪影は足元に絡まって来た紅鶸のパンジーを指で擽りつつ物語る。サーカスは形こそ人間の世界に建つような娯楽だけれど中身は全く違う。人の目には其処に動く者達は皆等しく蝶や蛾にしか見えない筈なのに、彼には人に見えたとは何故。
父さまと母さまが人を祝福するのはよくある事で彼の話を全くの嘘だとは思わない、思わないけれど。
「貴船と言ったわね。」
貴方の姉さんのことは分かるけれど
「貴方は?貴方は何者なのですか。どうすればたゞの人が私を邸から連れ出して花々の庭を歩かせるなど出来るのです。私は一人では外を歩くことを許されていない存在なのですよ、けれど貴方はそれすら分かっているらしい、だからますます分かりません貴船雪影と言う存在が。」
何も分からない貴方は何で出来てるの。
庭の終わり、見た筈の無い湖が映るその瞳、
「そんなの私が知りたいですよ。」
初めて年相応な顔をした。
九
その日は一九四五年八月三十日だった。貴船家の庭の草木はしっとりと雫を帯びて日の光を水晶のように身体に透し風は蜻蛉の羽となって涼しく吹き絶えることの無い低い胡弓の響きは音持たずともうつくしい、池には金魚と鯉が真紅に煌めき垣に咲く薄紅の牡丹花より垂れる玉を水に吸っては泳いでいる、その白露は雨の前の六つの花で彩られており遠く見慣れないなつかしさを感じたような見たような錯覚を起こす。まるで硝子のような牡丹の花、染まる喜びを湛えてあふれる白桃のかほりを籠めた色は初々しく高く立つ、その先には遊びのブランコ、蔦が青く磨かれた装飾施す名工の意かとも見えるほどに覆っていた。
「どうぞお座りになって。」
螢は晴れの顔で紅茶を勧めるも恥じらふ耳は隠し果さず白百合の頬に熱を伝える。
「雪ちゃんもおいで、姉さんの隣にお座りな。」
「はい姉さま。」
姉弟と白百合三人でブランコの前に、丸い白いテエブルを囲み香り高い紅茶をいただく。
「白百合様、あの今日はぜひお月見をなさってくださいね。この庭から眺めるのがすてきなのです、勿論お部屋の窓硝子越しに望むのもたいへん良いんですけれど、あのやっぱり、此方から眺めるのが一番うつくしいのです。」
「姉さま大丈夫ですよ、少し落ち着いて。白百合様は何処にも行かれませんから、居なくなったりしませんからね。」
「そうだけど雪ちゃん、分かってはいますけれど、でも…。」
「螢さん。」
仲睦まじい姉弟の姿、雪影の話から思っていた人物像ではあるけれど想いびと、意中の者を前にしてこんなにたじろぐとは考えていなかった、今はまだ天道が明るいがやはり夜風は彼女の細い肩にはこたえるだろう、それでも夜を過ごすのなら
「小夜着を一緒にかぶりましょう、それなら二人で月見が出来るから。」
喜びの涙は四角いものと聞いていたが正反対にまろかった。顔も分らないのに花簪のあの少年が頭によぎる。
「白百合様。」
すやすやと寝入った姉を横抱きにして雪影が声を掛けた、
「お部屋をご案内いたしますので、此方へ。」
その顔はもう先刻の青年らしさを消している。
「よく眠るのね、螢は。」
手回しのオルゴヲル小箱からは花のワルツが流れている、その光がよく似合う静かな寝所。あどけない螢の横がほは春を讃う鳥の瞳のように喜びを湛えている、恋人に逢えたことが理由なのは言うまでもないが自分の喜びに身を動かせないで物足りなく時々細かに動く指先は彼女の身体の弱さをすねるみたいでもどかしい。
「雨の日は一日起きていられるのですが、晴天の日は夜にならないとお一人で歩くことも出来ません。」
「雨の時は何を?」
「恋人との逢瀬を。」
「……私のことね。雪影、如何してこの子は私に、白百合様に恋を?」
「それは全く…家には百合の花も育てていなければカトリックでもありません。」
「他の神々の育てる白百合は救いや慈恵の象徴でしょうけれど、私のまじないは知っているでしょう?慕われるような存在ではないのよ。だけど、この子は嘘を吐いていなかった。」
雪影の顔がきょと…と目を丸く。
「人が嘘つきかどうかもお判りになるのですか。」
なんだかあどけないな、螢の眠る顔を思い出す。
「邸から連れ出されましたが私は腐っても神の一族。そう簡単に全ての力を奪えると過信しないことですね。」
「否、侮ったわけではありません。」
あ、もういつもの表情に戻っている。
「つまらないわね貴方、年齢に見合わないつまらなさよ。」
「………」
うわ、何その顔。
「まだまだ月夜になるまで時間があるでしょう、螢のことは彼女自身から話してもらいますから、雪影は自分のことを私に話しなさい。」
「つまらない野郎の自分語りをお聞きになるのですか。」
弟だな、と思う。
十
このオルゴヲルは螢の生まれる前、父と母が最初のサーカスに招かれた際ぬいぐるみから貰ったと聞く、彼か彼女かは不明なだけでなく兎か熊かどちらとも判別付けられないこだったと言う。黒いフェルトの小さいシルクハットにまたも小さな真ん丸真珠をあしらったおめかしで新月のようなつぶらな瞳をしており、歩く度動く度にとてとてぽすんと擬音語を鳴らしているかの仕草、しかも片手にのっかるほどの大きさだったと螢の頭と大きなお腹を撫でながら母はよく話をしていた。
「だから朔の夜にはこの音楽で小さなぬいぐるみへの感謝を奏でるの。」
母の優しい手つき。
大切にしなくてはいけない行事、満月・新月・半月の日は貴船家の朗らかを少し潜めて凛としなくてはならない日、たくさんの神さまに白い紫陽花の月を通して祈りと感謝を捧げる日。
「神さまの一等喜ばれることだから。」
頭を撫でて教えてくれた父の声。
二人とももう帰って来ない。戦禍に巻きこまれたのではない、人が神さま達を嫌悪し憎むようになったから。
「白百合様の御家族と似たような理由です。」
回す手をゆっくりと休まないまゝ青年は打ち明ける。
「姉さまのご出生については先程申しましたとおり白百合様の父上と母上の言祝のおかげなのですが、私は異なります。」
「母君から生まれたのではないの?」
長い睫毛を静かに伏せ首を横に振る様は弱々しい。
破片のようなものだった。凍った一滴の雫がこぼれた時砕け散った銀の破片、それは鋭く土に埋まり時計の短針へと鼓動を始めた、長針は赤い飴細工の三ツ葉模様、二つを重ねる留金は北極星の散る雪で、水の中で燃え続けるまろい燈心に姿を変えた。破片だったものはいつか気を失った山奥森の中で月の木漏れ日に照らされ続けたがやがて木は失われ森は溶けて山は姿を変えられた、破片は焼け野原に傷む光を浴びながら、人の足に揉まれ四季の夜空を日毎仰ぎながら、星を幾つと数え続けた。
数えたらこの身が誰かがどうなるというものではない、まして数えることが定められていたという訳では無し、数えたい気分になった無責任の衝動でもなかった。たゞ夜空があって星があった、理由はその一言に尽きる。
月光も星の光も、雲の囁きも雨の喜びも目を眩ませる刺激を持たないのに如何して陽の光だけはあんなにつきつきいたいのだろう、その頃からぼんやりと自分以外の思い出を識別出来るようになって来た。例えば、自分が最後倒れたのは森に囲まれた場所だったけれど、此処に降りた雨の踊り子が最後に見たのはうす紫の躑躅だったとか、その花びらを慕った鶴が居て生涯同種の番を契らなかったとか。
あゝ、他所の心と云ふものは魔に憑かれてはいないのかしら、だからあんなにうつくしく滴ることが出来るのか。憑かれたものはそのまゝ何も分らずに死ぬのが良いと言うはそいつが俗悪な存在に成り下がるように仕向ける為で無垢なまゝ死ぬと聞こえは良いが処罰の為に処刑することと一つも変りはありもしない。悪いものは退場しなくては。この身体はどんな化物に進んで行くのだろう。
「お母さま!」
少女の腕に抱き留められた息の無い赤子は、彼女の叫びで走って来た母親へと繋がれた。
「姉さまと母さまそれぞれの腕に抱かれたことで、私は貴船雪影として生きることが出来たのです。」
今この日まで生き残った人達は貴船家を同じ人間と呼ぶだろうか。丘の下の街々では略奪は横行し差別を嘆く投書は溢れ瓦礫と黒ずんだのは最愛の人達で正気は捨てられ恨み辛みは街の見えない石垣に変貌した。その城塞の一番上で切り刻まれたのは白い菊の花。
言葉で救われる者はもういない、言葉を愛した神様も等しく人から捨てられた故、言葉は意味も力も失い玉子の殻のように腐敗臭を撒くばかりのものと成り下がってしまった。誰も彼もが言葉の後ろを用心して、言葉をそのまゝ受けとめる喜びまでも人は蹴散らしてすましてしまった。恐ろしい、彼等のそんな言葉を此処に如何して置けようか。
十一
弟は姉によってすくわれた、化物にならずに済んだのだ。記憶は無くともこの破片は姉を慕うように作られて砕かれた、これ以上罅が入ってしまわぬようにと見知らぬ少女はリボンを拙くも結んでくれた、ふとするとほつれてゆきそうな結び方だが破片はそれを裂かないように切らないように鋭利な両手をたどたどしく重ねながら愛しい名前を呼び続けた。
「姉さま。」
終戦のあの日、姉さまもこの家から立ち去ると感じていたのに
「おかえり雪ちゃん。」
私の我儘な呼び声にもう返事があるとは思わなかった
戦場を去っても家に帰りたくなくて路地裏や避難場所大通りを歩き続けた、腹が空いたら咽が乾けば動かなくなった人を喰った。この身が浅間しく酷くなれば自分はあの優しい家に居る資格を喪失すだろう、そうなれば、三人は全く素晴らしい家族になれる、祝福を授けられた清き方々、紛い物の無いご家族に姉さまが耳元で白百合様に囁かれた日から構想していた私の悲願が。
「どうして」
私の名前を呼んでおられる
「どうしてって、此処は貴方の帰る場所でしょう。」
冬の終りあふれる雪どけが朝日の終わりを告げる姿を滲ませる、おかえり姉さまおかえり雪ちゃんと震える肩を互いにかき抱き涙に濡れる白菊と野薔薇は百合の溜息のような口づけ、触れた唇は湖の秘密を静かに確かめあい月の孤独へ溺れゆく。澄んだ淵へと身投げした私たち、もう離れることもありません。
そして私たちはあなた様へお逢いする為の道を羽ばたいて此処へ来たのです、白百合様。
十二
振りむけばいつも置きざりにされているぬいぐるみが居た。瞳は太陽の眠った春の夜の色で片手が数本糸がほつれて足は大きさが左右で違う、歩くことを何より恐れているそんな身体なのに両眼はいつも新月の潤み空のように願いを湛えて居た。誰を見ているの何を待っているのと尋ねても勿論ぬいぐるみは答えない、一人きりが得意な癖に一人遊びは下手だったから。この子がいつから居たのか如何して来たのかはもう憶えていない、よくある言葉、気が付いたら傍に居て居なかった時のことは思い出せない。持ち主が忘れてもぬいぐるみが憶えている。それがぬいぐるみが主から去らない理由なのだ。
だってほら、耳に雫したこの丸い花びらは私が泣いた時のもの。泣いたことなんて憶えていないのにこの子はその時を忘れていない。いつも私にブーケを見繕って両腕で抱えてとてとて歩く、家族が出払った後一人になればこの子は必ずそう動いた。
「私は外に出られないけれど、おまえは外に出られるでしょう?」
一度とんでもなくすねられ駄々をこねられてからその言葉は二度と言わなくなった。けれど見てみたいものがあるから、一人で遊んでこいって言っているのではないと用心の前置きを話してから二度目を言ってみた。ふてくされてごろごろ転がりまわることはしないけれど新月の空は寂しそうに泣いている。
「サーカスをあなたから話してもらいたいの。あなた物語とか好きでしょう?」
読み終えた本を片づけるのは二人の仕事だものね。
納得した顔、その素朴さがかわいいな。
「お願いね。」
元気よく小さな足で走っているのも。
サーカスは人と神を繋ぐものであった。サーカステントには仕切りや区切りの役目があってそれぞれの天幕で人の形をした御使いが人の編み出した技を御披露目することでそれぞれの神様と人との関わりを失わないようにする為の謂わば儀式と称される催しであり、これには祝福された人間も招かれるのである。星の数にも勝る神々は自らのサーカステントを愛惜しみ大切なものとしてきたのだが。
白百合には軽業師一人も居ないのである。為に遊戯へ加わることも出来ずサーカスの度サーカスを物語る本をぬいぐるみと読むのがせめてもの。
「普段なら何とも思わないけれど今日のサーカスはどうも違うの。一目見てみたくって堪らない、でも私はテントを建てる力も無い病気の身体、一度こうでもしないと憎いまじないに気が済まない。」
さて出発して到着した相棒は何から見ようかどう動こうかで迷っていた。あっちへ一歩ふみだせばこっちの足で遮られ気をとりなおしてこちらへ進めばあちらの笑い声に体が強張る、もう帰って泣きつきたい。兎角動けるようになるまでその場にしゃがんでじっとしていよう、白百合が怖い時や泣いている時は二人でじっとしているもの、今一人なのが覚束無いけれど間違ってはいない筈。そしたらほら、
くるり くるり
回る音。
ランランラン…
こっちだよ。
北極星のやさしい水色した雪がきらきらと四ツ葉を食む温室の仔兎の瞳のように待って居た、それは聞いたことあるかもしれないオルゴヲルのワルツ。怖がりのまま走って行けば潰れた店先見世棚の上、手回しの小箱が置き去りにされているのを一言も考えずに抱きしめた。
「おかえり。」
白百合はオルゴヲルを離さないぬいぐるみをさらに抱きしめて氷砂糖の雨垂れを半身布団に潜った姿で眺め始めた。
「私もいつかサーカステントを持ちたいな。」
決して認められない明日を呟く、どうせ雨が重なるのだから。
十三
螢が誕生して雪影を見つける迄は数年間があり、その際一人の子供が母親のお腹に居たんだよと雪影はよく父母から教えられた。その次子は何方にいらっしゃるのですかと尋ねるのは子供心にも憚った理由は―一体子供と言うのは真に親の感情を過敏に察してしまうもの―うつくしい筈のお二人の微笑みの具合が何処かしらわるく見えたから…この笑顔を見たのは初ではなく、姉さまがこの間庭で五月の若葉が死んだ大瑠璃蝶の躯を覆うように落ちていたのを見た瞬間の、あのお顔とよく似ておられた。姉さまは何も仰有らなかったけれどその日のアフタヌーンティーに来られなかったので、あゝ羽虫の死をも我が事として悼む方なのかしらなどと随分浅く考えて感じ入っていた自身を思えば恥ずかしい。
父さまと母さまは、姉さまが若い蝶を通して想った誰かのことを想ってらしたのに、そしてそれは人としてこの世に生まれて来られなかった次子のことであったのだ。性別は私と同じ男の子だったらしい、名前は三日月。三日月は人に触れることも無く死んでしまった、よほど人嫌いな性分であったから生まれて来るのが怖くて逃げたくなったのだ、時折庭の池に映る空高い雪花を見ては涙を零す母さまの所為ではない。
それでも人の世の決まり事、不憫な者には憐れみか嘲笑を。使用人達はどうも後者を採ったらしい。母さまは魔に魅入られたのではない、斯様な人ならばこの私を育ててくれますものか、毎日頭を撫でて微笑んでくださるものか、何故あなた方はこの御家族を見下したがる!相応しくない相応しくない、あなた達使用人は三人に釣り合う方ではない。ならば同族のよしみで私が手を掛けてやる、一人も残らず逃がさない、幼くても人には人を殺す力がある!
「白百合様を人間に。」
その言葉で八歳の雪影は両腕をだらりと落した。
三日月は白い牡丹の重なる花弁に全身を包まれている感触で両目を開いた、その先にうつくしい黒髪をしっとり重そうに佇む者の姿があり瞳は笑っているが何処か不機嫌そうな、
「此奴が末っ子か。」
男が良かったと声まで苛立ち不穏な舌打ち、
「やめなさい、どうしていつも下の子をいじめようとするの。」
女性にたしなめられて口だけ噤む。
「おはよう、今日から私達が家族だよ。」
逃げ去ってぼろぼろの僕を男性は愛惜しく両腕で抱きしめた。
「君の名前は白百合、白百合だ。」
日清戦争のずっと前、私はそうして生まれたのよ雪影。姉さんもおまえも如何して此処に来てしまったの。
十四
螢はもう一人の弟のお姉さんなんだよ、そうねお父様お母様、私お二人の涙を忘れた日はありませんもの。もう一人はきっと人が怖くて怖くて仕方が無かったんだと思います、だってもう一人の可愛い弟雪ちゃんは人をちっとも怖がらないのですもの。少し心配ではあるけれど、あの子幾分か真面目で優しいのが過ぎるきらいがありますから、でも大丈夫ね、あの子はとてもいい子だから感情に任せて人を傷付ける事はしませんよ。若しそうなってしまっても大丈夫、私が必ず止めますから。
三日月は此処でない場所でも泣いて過ごしていないかしら、雪影が泣き虫でないぶん三日月はすぐ泣く子だと思うのだけれど、誰かやさしい人が傍に居てくれたら良いのだけれど…そうでなければ私は如何やって弟を慰めることが出来るだろう。
雪影は抱きしめて頭を撫でたら落着くのに三日月は人ではない姿だから何処に住んでいるかも分らない、この想いが届いているかも分らない、知らないこと出来ないことがまだまだ澤山でもどかしい、やっぱり傍に居ない者でないと人は言葉を伝えきれないのだろうか。
「姉さま。」
おや?
「なあに、私の可愛い雪ちゃん。」
五つの弟が螢の白いワンピイスを抓んで引っ張って、そのもう一方の手には何かが抱っこされている。
「かわいそうなの、たすけてください。」
それはぼろぼろで見捨てられたぬいぐるみだった。
「街で拾ったの?」
「母さまでも治せなかったの、どうしても治らないんですって。」
両手両足じゃ今にもほつれそうでそれぞれ長さも違う、けれどもとても穏やかな目。
「じゃあお花をあげましょう。」
抱きしめた温もりで溶けてほつれてしまいそうだから、傍に小さな花束を一つ置こう。庭のお花を幾つか……、?ブランコの下、白百合なんて此の庭に咲いていなかった筈だけど。
淡く色づく藍色の霧にしっとりと囲まれて半月清らな湖面の夜、繭糸のように一縷ほそく佇むブランコの木陰の下白い百合が咲いている、誰かを待っているように誰も待っていないかのように。
あゝ、白百合様。
娘は雪花の溜息をついた。
十五
うつくしかった、そして懐かしかった。初めて見つめる花だのに懐旧の情は不思議だけれど、この白百合は決して私の手で摘み取ってはいけない、新雪の大地に汚れた足跡を滅茶苦茶埋め込むよりそれは罪深いと直感で思う。
でもどうして?
人は私を恋知らぬ愚かな娘と笑うだろう、人の世の恋愛は打算と企みで成されているものを、こんな、恥かしい、一目見ただけなのに、そんなこと人の恋愛じゃないみたい。
家の使用人の方々が私達に良くない言葉を呟きあっている事は知っている。そしてそれがまだ雪影には全て理解出来ていない、だから誰も身体を傷付けられていないことも知っている。お父様とお母様は時々私と雪影の言葉にだけ振りかえられるけれどそれも段々減っていてこの頃ではぼんやりと恍惚とされることも増えて来た。使用人はそれを笑っているけれどその顔はどれも雪影には見せたくない。
なんでか分らないけれど、この花も。結局ぬいぐるみにあげるブーケは他の花々を選び摘むことにした。
「姉さま。」
ごめんね雪影。
「なあに雪ちゃん。」
私は上手に笑えている?
「次の満月はいつでしょう。」
「もう半分したら見られるわ。」
「父さま達とまたお月見したいです。」
「そうね、また出来るといいね。」
ずっと半月だったら良いのにね。なんて私は慾深い。
白百合様、と呼んでみる。
自分の部屋に一人きりの真夜中、声は響かず沁みるだけで壁は誰にも告げ口をしない。頬がじんと沁むのが感じ取られるのは手指の先があまりにも冷たく戦慄くから、氷で胸を一ト突に射られたのに傷痕は妙に温かくてきっと血があふれているのだろう、肩は強張り目が眩む絶対的な死を全身で知覚する、怖い、恐い、こわい、あの白花が雪の百合が。
なのに私は何故笑っているのこの鼓動。
自分が笑っているのが分かる、これは、父にも母にも弟にも見せたことの無い私も知らなかったほゝえみだ、白百合様、白百合様。あなたが私をたゞの娘でも姉でも人でもなくしてしまったのです、だから、あゝ、どうかゆるして。私は真良くない生き物になりましたことを。
十六
眠る螢の横がほは月に照らされ猶うつくしい、そして並んで休む雪影も今は相応にすなおな顔で眠っている、代りにオルゴヲルを二人が起きる迄回す白百合は姉弟を見、窓や扉を見そしてそれから振りかえった、ぬいぐるみがちょこんと待つ。
「いきなり連れ出されちゃった。」
膝に乗っかって来た相棒と目を見合わせてフッと笑う。
「月見の夜はおまえに感謝を捧げるんだって。」
どう思う?馬鹿らしいな
「もう捧げられる方々もおられないのに、まだこの家は月を忘れないみたいで」
忘れても良いのだけれど
涙が止まらないサーカステント、
願いは叶ったサーカステント、
だけれどもう一人も観客はいなくなって。こんなに寂しい夢の成就が一体何処に在るのだろう。
終幕
「サーカステント」