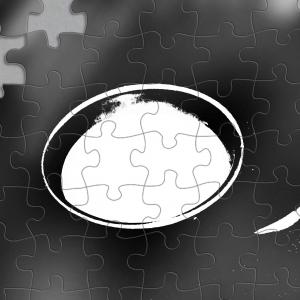「蛤の声」
一冊の厚い本を胸に押しあてて
走る人影 ひとり
白々しい街灯の大通りを忌み
露地のさみしい行燈の
ほつほつと仄暗い光をゆく
その乾燥した頬が紅くなるのは
寒さのためか
喜びか
それとも…
噛みしめた唇の白歯の傷は
あらわになる事を厭う
救いの無い砂漠で
水の蜃気楼を泣いて悦ぶは愚者か
それがために力を得たものは間抜けか
どうせ何人も
自然の花を生むことは成せない
干涸びた地面に
杜若のいとしい濃紫の羽を想っては
焦がれて慕って恍惚する…
それがために懊悩するは馬鹿か
水は生命の根幹なるぞ
たとえ涙であろうとも
「蛤の声」