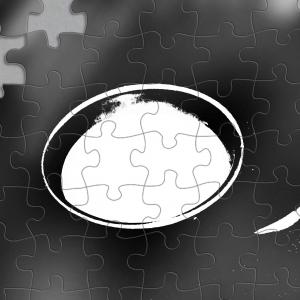「眠る者達」
一
糸垂桜がのぼっていく、きっと、空を仰ぐのであろう。
紫陽花の夢を起こさないように、そっと日が昇るに連れて、桜の後ろ姿は物語を想い出す。図書塔から彼岸花の口伝で聞いた物語は、さみしい花簪の其であった。
簪には別れた持ち主がいて、彼は彼女のことを“こいびと”と秘かに呼んでいた、すなおだが少し癖のある黒髪を風鈴のように飾ること、それが彼の慎ましい喜びだった互いは何と言って離れてしまったのか、それは、彼女が娘から女性になったかららしい。
娘は大人になると髪を短く切り揃え、長く伸びようとする毎に手入れと称する散髪をする仕来りとか言う、為に花簪はこいびとを亡くしてしまった、月がのぼる度に孤独な主人公はスポットライトにほろほろ泣く、その涙は小川に流れて湖面となって、さみしい月光を声も立てず反射し続けて居ると言う、そのようなお話だった。
全部嘘かもしれない。
けれどあの日、彼岸花の震え赤子を看取る眼差しのようで、これが嘘だとは思えない。
では本当なのか。それなら、それなら……
私はもう、こいびとには逢えないのでしょうか。
二
桔梗が白く溶けていく、それは、よろこびだったのだろう。
人身御供の舞台にもなったらしい湖では、図書塔の物語が行方も分らずよく沈んでいた、誰にも語られず、誰にも望まれず、誰に喜びもされない歌は声を失くして唄となり、湖にふれて詩となった。人は此処を言葉の墓場と罵り、とうとう距離を置いてしまったが、それこそもしや桔梗の花たちの目論みであったかもしれない。
また、図書塔の彼岸花に聞いてみた。どうして花は散るものなのに、人は繋がり永遠を望むのだろう、さよならの仕方も礼儀も知っているのに、別れを終わりを悲しむ心があると言うの?彼岸花はふるえていた、どうして君はいつもそうしてふるえているんだろう。こんなに優しい瞳なのに、毎日毎日眼を閉じてきれいな唇も薄く噛んで、この身と話をしてくれない。
私は君の物語が好きなのに、君の話を知りたいの。
「わたしに物語は無いの、それでもいいなら傍に居て。」
いつも困った微笑みで図書塔の根元で風と搖れる、なんて哀しい嘘つきだろう、彼岸花に物語が無い訳も無く。
それなら私が話しましょう。
だからその頬に一度だけ触らせて。
雪どけは、それは何處にでもある話。
「眠る者達」