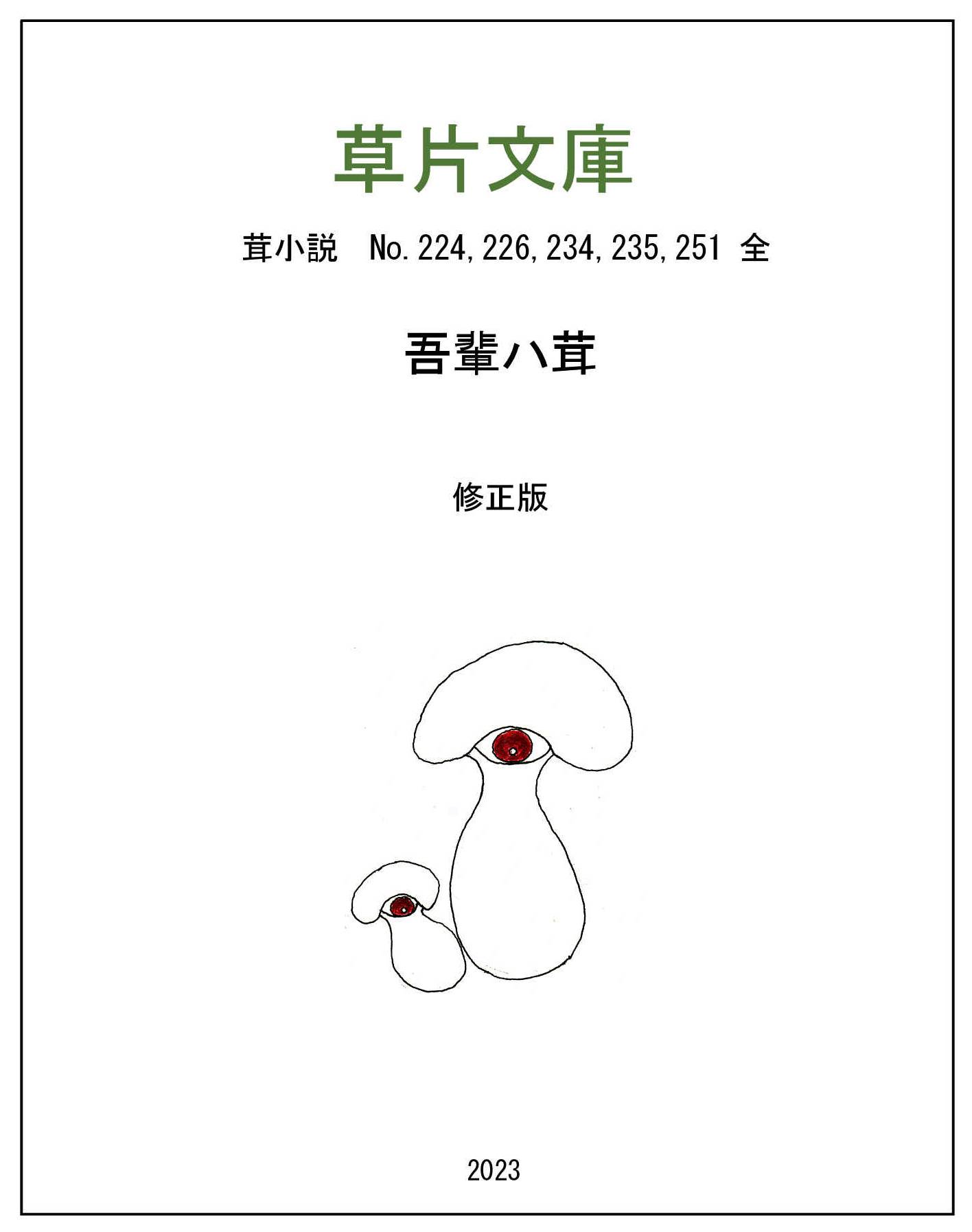
吾輩ハ茸
200枚ほどの長い,ちょっとばかばかしい茸滑稽譚です。茸小説の掲載はこれからしばらくお休みです。この年になって、初めて漱石の「吾輩ハ猫デアル」を岩波版初版で、読み通しました。面白い。やはりすごい。
吾輩ハ茸 目次
序章―吾輩ハ猫デハナイ P5
一章―玉玉玉 P33
二章―妾横丁の祝玉 P67
三章―玉だらけ P103
四章―妾横丁の大玉 P141
終章―女中、玉の運命 P175
(P)は600字一ページとしたときのページ数です。量的な目安にしてください。
主たる登場人物
野良茸 主人公
冬目草咳 ぼっちゃん、虫下し 探偵小説作家
実野 虫下しの細君 音学学校卒業
実野の父親 大日本女頼神教司祭
女中の玉、秋田出身、15歳で奉公
猫 玉 虎茶 家に入り込む 三匹子供を産む
後玉 白猫 玉の一年後拾う 二匹子供を産む
又玉 三毛猫 もらってくれと頼まれる 一匹子供を産む。
大玉 八間がそだてる。玉、後玉、又玉の亭主
横溝精子 八間入道 書道家、画家 句会仲間
桑子絹鳥(けんちょう) 別名 桑っこ 詩人 句会仲間
酒本立一(たちいち) 別名 木琴 音楽学校教師 句会仲間
町街早合士(さがし) 双子社探偵小説雑誌「犯人と探偵」編集長、元小倉出版社員
町街有瑠世(あるよ) 双子社詩の雑誌「あいうえお」編集長 早合士と双子
序章 吾輩ハ猫ではない
縁側を開け放して、ぼっちゃんが原稿を書いていると、「ニョ、ニョ」と猫の鳴き声がする、変な猫の声だ。
どこかの猫が庭に入ってきたようだ。
ふっと、庭を見ると、縁側の上に猫の首が乗っかっている。いや、猫が靴脱ぎの石の上にのって、こちらを見ている。顔だけ見えるのだ。薄茶色のぶっくりした大きな顔だ。
「どこの猫だ」
声をかけると、「ウェ」と鳴いた。
なんだこの猫は変な声を出す。
ほっとこうと思っていると、勝手にあがってきて、そばにきた。にーっと笑い、そのように見えたのだが、大きな体をムリムリと、あぐらをかいている足の上にのっかってきた。
あまり猫臭くないところをみると、どこかの飼い猫だろう。尾っぽを持ち上げるとついている。雄だ。大きな雄猫である。
連載推理小説の締め切りが明日だ。しかも第1回目だ。書き上げなければならない。猫がのっかったまま原稿を書いた。尾っぽだけがパタンパタンと目の前でゆれていると、おやおや不思議だ。アイデアに行き詰まっていたのに、するすると書ける。ふっと気がつくと、原稿用紙50枚がうまってしまった。初めての連載小説である。
坊ちゃんが大学のゼミにでているとき、ゼミの卒業生が教授を訪ねてきた。町街早合士(まちがいさがし)という、小倉出版の編集者で、新しい小説の書き手をさがしているという。いつもの癖で、大風呂敷を広げて、探偵小説を書く話をしたら、そりゃおもしろい、連載で書いてくれと言うことになった。ぼっちゃんとしてはとてもありがたくうれしいことではあったがちょっと自信がない。それまでまともに小説を書いたことはなかった。
引き受けて一月もの間考えていたのだが、いいストーリーがでてこない。毎日、縁側で庭を見ながら考えていたのだが、どうしてもだめだ。
あせっていまになり、猫が膝の上に乗ったとたんに書きあがるとは、嬉しいことだ。
ふーっと安堵の息をはき、股の間を見ると、大きな薄茶色の猫が丸くなって寝ている。よだれをたらしてやがる。だが頭をなでてやった。おっぽの先がぴくぴく動いている。これが良かったのかもしれない。
「どこの猫だ」
つい話しかけた。
猫は髭をひくひくさせ、太い尾っぽをぱたぱたして、片目だけをちょっと開けた。
「座布団うるさい」
人の声を聞いたような気がした。誰の声だろう、豆腐屋の三吉ではないし、角の雑貨屋のおやじでもない。出版社の編集者の声でもない。
まあいいと思い、猫をどけて立ち上がった。
「せっかく気持ちよく寝てたのに」
やっぱり猫だ。振り向いた猫が文句言っている。猫に膀胱を押されていたのですっきりしたくなって立ち上がった。
「おまえどこからきた」
そう言って猫の顔をのぞき込んだら、右の前足でぽんぽんとほっぺたをたたかれた。右ききか。
「どこいくんだ」と猫が聞くから、「厠だ」というと「それじゃしょうがねえか、いっといで」と生意気な口を利いた。
ともかく廁に行き、放尿をして、手水場で、手を洗い部屋に戻った。
すると、猫がいない。と思ったら床の間にでんと座っている。後ろには虎の掛け軸がかけてある。同じ仲間なのになんと迫力が違うことか。
「おい、猫、家出してきたのか」ときくと、猫が「吾輩は猫ではない」と答えた。
全く何様だと思っているのだろう。ともかくできあがった原稿をもう一度読み直した。なかなかのできだ。
明日の朝に雑誌の編集者がとりにくる。ともかくできあがってよかった。
そこへばあやの清世(きよよ)が「ぼっちゃんきょうはなにをめしあがります」と聞いてきた。
「なんでもいいよ」
「それじゃあ、魚屋に行ってきませう、おいしそうな魚があったら買ってまいります」
清世は魚好きだから任せておけば生きのいい魚を選ぶだろう。
床の間にいた猫が、お腹をだぶだぶさせて庭にでた。ゆっくるゆっくら歩いて、椿の根本の柔らい土をほじくった。そこに座り込むとこちらを向いた。
「見るな、くそがでない」
と言ったように聞こえたので、テーブルの上の書いた原稿をもって、自分の書斎に引っ込んだ。気持ちのいい日は庭に面した座敷で原稿書きをする。寒くなってくれば自分の書斎で書く。今日は座敷に秋の日が当たり気持ちが良かったので、座敷で書いていた。
書斎の家具屋に作らせた机の上にできあがった原稿をおいた。さて、次の号の案を練らなければならない。こんなに行き当たりばったりに書いていて大丈夫なのだろうか。
彼の書いているのは「茸のしっぽ」という探偵小説だ。
茸に関しては彼の頭の中に根を張るものがある。四国の松山の実家の座敷の床の間に大きな万年茸が飾ってあった。茸の好きな親父は、いい形をした万年茸をどこからか購入してきて、それぞれの部屋にかざっているほどだった。客によく自慢をしていた。
建築設計技師だった父親は、建築会社の人たちを家に招くことがよくあった。おやじと客がワイワイ言いながら酒を飲んでいるとき、子供たった彼は、大人の話に入れるわけもなく周りでうろうろしていた。誰も相手にしてくれないし、立っているのも飽きた彼は、床の間の万年茸の脇に腰掛けた。そのとき、大人たちが、二つくっつけたテーブルのまわりで笑ったり、怒ったりしているのを見て、万年茸のやつはこうやっていつも座敷の中を見て笑っている。そう思った。
東京の大学の文学部に入って、教養課程で生物学を学んだ。植物の講義のとき、先生が、茸は動物や植物よりあとにでてきてたと話していた。しかも茸の本体は土の中に広がっている菌糸で、茸が枯れても生きているという。そこで彼は考えた。茸はいたるところに顔を出す。人間の生活をつぶさに見ている。動物は命が亡くなれば記憶がなくなる。植物だって、古い杉は千年、二千年と生きるかもしれないが、枯れてしまえば記憶はそこまでだ。ところが、土の中の菌糸は茸が地球に現れたときからの記憶を蓄えている。と彼は想像した。だから、茸は大昔の情報をもっている。それだけではない、顔を出した茸はそのときのことを菌糸に蓄えるのである。茸の中には人間担当のやつがいて、人間の歴史を菌糸の中にしまっている。要するに茸は物知りである。その授業では茸とはそいう言う生き物だということが頭に植え付けられた。
そんな経験によることもあるのだろう。ペンネームを漱茸とした。もちろん同じ大学の大先輩が石でうがいをするという大文豪がいるが、漱石とは中国に伝わる話から頑固な人のことをさすそうで、自分はもっと軟いから、茸にしようと思っただけである。
書き始めた探偵小説「茸のしっぽ」では茸好きの大富豪が誘拐されてしまう。秋田の茸のよく生える山を買い取り、そこに別荘をたて、秋になると茸狩りを楽しみ、茸学者を呼んで、自分の山に生えている茸の図鑑を作らせたりする。茸の本のコレクターでもあるのだがいなくなってしまった。懇意にしていた茸レストランの経営者が素人探偵になり、富豪行方を探す探偵小説である。
それでどうして茸のしっぽなのか。猫のおっぽというのは、意識しているのかしていないのかわからないが、いつも動いている。猫が自分のおっぽにじゃれるのは、おっぽを自分のものじゃないと思っているのではないか。とすれば、おっぽは勝手に動いている。動く必要はないじゃないか。寝ている顔のわきに猫がやってきて、けつを向けると、尾っぽが勝手に顔に当たる。迷惑だ。子供のころおっぽを捕まえてやれと思ってもひょこっとよけて逃げられてしまうことが多かった。おっぽをつかむというのはあっちだかこっちだかわからない方向を知るということだ。家にいた猫の名前は「きのこ」である。そこで「きのこのしっぽ」という題にしたわけである。彼の家の猫の茸は十八歳とその頃としては長寿の猫で、老衰で死んでしまった。今庭から入ってきた猫とは全く違う美形の三毛猫だった。母親が知り合いからもらってきた猫で、猫が来た日に風呂場に黄色い茸が生えたので、母親がきのこと名前をつけたのだ。母親も茸が好きだったのかもしれない。
座敷の方から、ニョ、ニョと猫の鳴く声がした。また座敷に上がってきたようだ。廊下を伝って、書斎の方に鳴きながらやってくる。もうこの家の猫になったつもりなのだろうか。これだけなれているのだから、どこかの飼い猫だろう。
まあ、いつか帰るだろう。好きなようにさせておこう。
と思っていたら、ドアをがりがりと爪で掻いた。こりゃまずい、綺麗な木の戸が傷だらけになる。書斎は庭につきだした洋風の建物になっていて、持ち主の父親の書斎だった。入り口は一枚板を使ったドアになっている。持ち主の父親は昔からの家に洋風の部屋をつけたかったようだ。
かさかさ音がすると、ドアが廊下側に引かれ猫の手の先が見えた。と思ったら、頭で押して開けて入ってきた。
器用な猫である。尾っぽをたてて、きょろっと彼をみた。
「おい、猫、おまえどこの猫だ」
「吾輩は猫ではない」
また言っている。
「書斎にはいってきてどうしようてんだ」
「寝床だ」
「寝室は二階だ」
「おまえのあぐらだ」
こいつは吾輩の足の上が寝床だと思っているようだ。困ったもんだ。
「坊ちゃま、お食事の用意ができました」
清世の声だ。助かった。
薄茶の猫を放っておくことにして居間に行った。用意された膳の前に座る戸、目に入ったのはヒラメの煮ものと、茸と野菜の煮物、香こに、豆腐のおみおつけだ。
ばあやがお茶をもってきた。
「源さんにおいしそうないきのいいヒラメがありました」。二丁目の魚屋源兵である。
「うまそうだ」
「坊ちゃまはヒラメが子供の頃からお好きでございましたね、目を寄り目にして、このおととがおいしい、と申されて、おかわりまで召し上がりましたのですよ」
話し始めると長くなるからこのあたりで切らなければいけない。
「おなかが空きました、すぐいただきます」
箸をとると、煮汁に浸されて、湯気が立っているヒラメの肉をつついた。
「お、おいしいな、ばあやの料理は」
甘くなく辛くなく、薄口の醤油の東京の味だ。白い飯がうまくなる。坊ちゃんは四国より東京の味のほうが口に合うようだ。ばあやもそれを知っていて、美味しい味付けにしてくれる。
「お茶をここにおいてきます、何かいりようでしたら、およびくださいまし」
ばあやは台所に引き下がった。そこで自分の食事をする。一緒に食べようと言っても、私にはここが食べるところでございます、と言って一人で食べる。一人で食べるのはつまらんと言うと、早くお嫁さんをお迎えくださいましと言われてしまう。
ばあやが引き下がると、薄茶の猫がのっそりとはいってきて、自分のお膳の前におちゃんこをした。
ヒラメの匂いがするのだろう。
一人で口に入れているのが悪いような気になる。味噌汁の椀の蓋にヒラメの身をすこしのせて、猫の前においてやった。
猫は「ぶす」っと言って横を向いた。普通の猫ならばとびつくはずである。
猫は「こいつをくれ」と言うと、いきなり、豆腐のおみおつけをなめ始めた。
「おお、いい味だ、味噌も豆腐も俺の親戚がつくっているんだ」
この猫はどうやら味噌屋か豆腐屋で飼われていたらしい。豆腐まで食っちまった。自分の飲む分がない。
「ばあや、おみおつけくれるかな」
大きな声で清世を呼んだ。
「おや、めずらしいですね、もう飲んでしまわれたので」
「うん、うまかった」
「今お持ちしますよ」
ばあやがもう一椀、おみおつけをもってきた。
「おや、きれいに飲まれたこと」
ばあやはうれしそうだ。猫はと見るといない。いつの間にか部屋を出たようだ。
「おいしかったよ」
「よございました」
ばあやは空いた椀を台所に持って行った。
おつけをのんだ。いつものばあやのおみおつけだ。慣れというものはいいものである。それを一番おいしく感じられる。
ばあやが漬けたキュウリとナスの糠味噌漬けは、これまたうまい。しっかりと糠の味のしみこんだすっぱみの強い、いいつけものだ。白い飯がすすむ。
あの猫がまた部屋に入ってきた。
キュウリの糠味噌漬けにかじりついた。
「うまい味噌汁だった、全部飲んで悪かった」
「なんだ、おまえは東京の猫じゃないのか、おつけというのだ」
「味噌を溶かしたのだから、味噌汁だ」
「東北のでか」
「寒い方が好きだからそうかもしれん」
「猫が寒いのを好むとは希有な奴だな」
「だから、吾が輩は猫ではない」
「キュウリまで食いやがった」
「ぬかみそもうまい」
「本書きのじゃまをするんじゃないよ」
「手伝ってやろうと思ってきたんじゃないか」
「猫の手は借りなくていい」
「猫ではない」
「何の手だというのだ」
「草片の手という」
「なんだそれは」
「俺の手だ」
猫の奴大きな前足の手のひら、いや梅の花をみせおった。どこが草片なんだ。
「このヒラメの煮た汁は飲まんのか」
「腐った魚なら食ってやる」
「なんだどそれは」
「消化にいい」
「それで、なにの手伝いをするって言うのだ」
「あんたの小説のネタをやろうと思ってな」
そこにばあやの清世が膳を下げにきた。
「坊ちゃん、誰としゃべっていなさったのです」
猫とはいえず、ちょっと独り言をとごまかすと、「坊ちゃんもいい小説家におなりになった」と、膳をもって台所にいった。
まだ一つも本をだしていないのに、雑誌の原稿を書いている様子を見るだけで、清世は彼のことを小説家と言っている。
清世は彼が2つの時からばあやとして雇われ、一人っ子の彼が帝大の文学部にはいったことから、四国から東京までついてきて、借りたこの家で坊ちゃんの面倒を見ているのである。彼がいま24だから、22年坊ちゃんの面倒を見ているわけである。3年前彼の両親が新コロナで肺炎を起こし、相次いで他界した時も、元気に実家の家の始末をしてくれた。もう50を過ぎているはずである。ぼっちゃんと呼ばれている彼が大学をでて、いっぱしの小説家になって、身を固めたら、故郷の松山に帰りたいといっている。松山には人に貸している自分の家もあるという。近くには自分の妹夫婦がやっている寿司屋があり、そこを手伝いたいと思っているようだ。
「いいばあやだな」
猫の奴がぼそっと言った。そこだけはうなずいた。
これから、次の号の案をねらなければならない。猫の奴はほっといて、書斎にいった。
朝日が射してきた。昨日は、次の号のプロットを考えていたらやけに眠くなったので、早く寝てしまったのだ。
台所に行くとばあやがもう食事の支度をしていた。
「天気がよございますので、洗濯をしてしまいました。庭に薄茶色の茸が二本も生えておりますよ、食べられないでしょうけれどきれいな茸ですよ」
座敷の障子を開けて、庭をみると、確かに大きめの茸が二本、椿の木の下に生えている。昨日、あの猫が糞をしていたところだ。色が猫と似ている。肥料になったのか、そう言えばあの猫はどこに行ったのか。もう家に帰ったのかもしれない。
床の間を見ると、でんと座ってこっちを見ている。
「おい、猫、まだいたのか」
声をかけると、ニーイと笑って、ニョっと鳴いた。まるで不思議の國のアリスのチシャ猫のようだ。
「家に帰らないのか」と声をかけると、首を横に振った。おや今日はしゃべらない。いやあたりまえだ。昨日こいつが話をしたのは、俺の頭の中だけの出来事だったに違いない。小説のことばかり考えていたので、猫がしゃべっても当たり前と思うようになってしまったんだ。いや、首を横に振るだけでもおかしい。
彼は猫をみた。前足をそろえて、おちゃんこをして、こっくりこっくり居眠りをはじめた。こんな格好をして寝ている猫なんぞ見たことがない。
お食事の用意ができましたよとばあやの声が聞こえた。
「今いく」
と答えたら、猫が目を開けてのそのそと縁側から庭にでていった。
「どこ行くんだ」ときくと、「しょんべん、動物はめんどうだな」と言って、アオキの脇に行くと、足をあげて放尿をした。
しょうのない奴だ。
居間にいくとお膳が運んであった。
食事をすませ書斎にいった。今日は雑誌社の編集者が原稿を取りにくる。
ラジオのニュースでは台風がくるようなことを言っている。
猫が書斎に入ってきた。
「茸のしっぽたあ、面白いタイトルだ、茸が好きか」ときいてきたからうなずいた。
「まあ、好きだ、親父もお袋も好きだった」
「好きにならんと茸は動いてくれないぜ、好きなものは自由に動かせるが、嫌いなものは動かせない」
「饅頭が好きだが饅頭をうごかせない」
「あんた、作家だろう、動かすと言うのは、話の中でいろいろな形で動くと言うことだよ、饅頭が嫌いな奴は摘まんでもみないだろう、好きな奴は親指と一差し指で摘まんで、こりゃ、柔らかい皮でげすな、などと言って、口に入れる、お、小豆は北海道でしょう、などと、書くことがたくさんできる。要するに動かすことができるんだ、好きじゃない奴にとって、ただのまあるい石ころだ」
言いたいことはよくわかる。以外とわかっている猫のようだ。
「茸は世の中をしっかりみておるからな、風呂場に生えた茸などは、風呂に入っている奥さんや旦那の素っ裸をみていて、菌糸に蓄えているから、十年後に生えてきて、どこにしわが増えたとか、ほくろが増えたとか、尻がたるんだ、おっぱいがしぼんだなどとわかっちまうんだ、また菌糸の中にそれを記憶すると、つぎに生えたとき、あ、あの夫婦死んじまった、なんていってるんだぜ、小さかったぼけっとした子どもは物書きの卵になっているなんてこともな」
茸の本体は土に中の菌糸で永遠の記憶を持っていると、植物学の講義で茸好きな先生が話していたことを思い出した。
うなずいて聞いていると、「まあ、おもしろい話をかいてくれ」
猫は尾っぽを立てて書斎を出ていった。
しばらくすると、小倉出版の編集長が見えましたと、ばあやの清世がいいにきた。編集長じゃなくて編集員だが、そう思わせておこう。「編集長が直接くるなんで、ぼっちゃまもたいしたものです」そう思わせておいた方がしあわせだ。くるのはまだぺいぺいの編集者、町街早合士(まちがいさがし)だが、十ほど年上だが、十返舎一九の卒業研究をした男で、作家をあきらめて、編集者になった。
「座敷に通してね」
ぼっちゃんは原稿を持って座敷に行った。
町街は庭を不思議そうに眺めていた。
「原稿はでました」
「あ、どうも、冬目君、それにしても庭にたくさんの薄茶色の茸がはえてるね」
庭を見ると、アオキの下のところにも茸が三つも生えている。あの猫が糞をしたり、しょんべんをしたところに茸が生えるようだ。
「そうなんです、猫のせいです」
そういいながら、テーブルの上に原稿を乗せた。
「どんな話しか楽しみですな」
町街は原稿を広げた。
そこへ、清世がお茶を持ってきた。羊羹までつけている。
「編集長様、どうぞ、赤門前の羊羹でございます」
「こりゃあ懐かしい、学生の頃は高くて食えませんでね」
ばあやがたちどまって、そう言った町街をみている。
「ばあや、原稿読むのに集中しなければならないのだよ」
「はい、おぼっちゃま」
ばあやはあわてて奥に引っ込んだ。
「ばあやさん、冬目さんをおぼっちゃんと呼んでるんだな」
町街が笑いかけたのだが、ばあやが廊下にまだいることに気付き、あわてて「茸のしっぽですか、面白いタイトルですね」とおべんちゃらをいった。
「連載がうまくいったら、本をだしましょう」とも言ったので、ちょっとはつんときた。
「よろしく頼むみます」
「でだしがいいね、吾輩は茸である、しっぽはまだない、か」
「探偵茸はまだ犯人のしっぽをつかんでいないいのでそうしました」
「ははは、そりゃいい、あの床の間にある万年茸が主人公かと思ったよ」
床の間には大きな黒光りのする万年茸が信楽焼の壷にさしてある。家を借りたときから、その万年茸はそこにあった。
「家主さんの話では、この家の梅の木の下に生えたものらしい
「きっとこの茸が、冬目君に茸の物語を書くようにしむけたのだな」
「うーん、そうですかね、全く意識はしていなかっのですが」
「次の号もおねがいしますよ」
「はい、考えています」
「楽しみだ、私はこれで失礼ししよう、お茶と羊羹うまかった、婆やさんによろしく」
「言っときます、よろこびます」
こうして彼は無事に原稿を渡した。玄関の音がしたのでばあやがあわてて出てきた。
「編集長様はお帰りになったのですか」
「うん、お茶と羊羹お気に召したようで、ばあやによろしくといって帰ったよ」
「それはよございました、編集長さまに気にいられれば、すぐに本になります、ばあやは楽しみです」
「今日はこれから神田にいってくる」
「はいはい、お昼はお外でございますね、ランチョンあたりがよございますよ、オムライスなど」
「ばあやが食べたいのだろう」
「おや、そうでございますね、近頃は外にでないので、そのうち銀座の三色アイスクリームでも食べてまいります」
「ああ、それがいいよ、たまには清世も遊びに行ってらっしゃい」
「そうですか、今度の日曜日よございますか、一日、あそんでまいります」
やけに嬉しそうだ。なにかあったのだろうか。まあいい、神田に茸の図鑑を買いに行こう。「茸のしっぽ」には茸が登場するから、茸のことを少しは知らなければならない。理科は苦手だが植物や昆虫の図鑑を見るのは好きである。
ぼっちゃんはいつも行く文学書の古書店ではなく、明臨館という理学書を扱う本屋に行った。何とも厳かな本がそろっている。
農業と書かれたところに茸の本があった。川村と言う人の本があるが、そろったものは高い。一冊ものがいいと見てみると、それなりの本があった。食菌と毒菌、これがいい。
それを買い求めて、ランチョンでオムライスを食べ、家に帰った。清世は自分の部屋にいるようだ。
本を持って座敷に行くと、あの茶猫が床の間で丸くなっている。いついちまうつもりだろうか。
障子を開け、庭を見ると、またまた、薄茶色の茸が増えている。
そうだ、まず、この茸の名前を調べねばならぬ。
傘は最初饅頭型で少したつと開く、柄は太く松茸のような形だ。似たような絵をさがす。黄金茸の形に似ているが黄色だ。薄茶色で似ているのは何だ、原茸か、柄が細すぎる。わからん。
そのとき脇を、猫が音もなく通り過ぎ、縁側から庭に降りると、鼠もちの根本で片足をあげた。じゃあっと音まで聞こえる。
終わるとおっぽをたててふるわせ、こっちを見て笑った。ようにみえた。ばか、なんてことだ。
猫のやつとことこ歩いて帰ってくる。
あ、しょんべんしたところに茸が生えてきた。庭中茸だらけだ。やけにはやい。
部屋に上がってきた猫が「俺のしょんべんに胞子がはいっているからだ」と言った。
猫がなんで胞子のしょんべんをするんだ。
「吾輩は猫ではない」
とまた言った。
「おまえ家に帰えらんのか」
「ここが俺の家だ」
「勝手に決めるな」
「それより、次の話を考えたのか」
「まだだが」
「前の話は何の茸だったのだ」
「赤い茸をつかった。ただそれだけで、名前はわからん、と言うより俺は茸を知らんのだ、だから茸の本を買ってきた」
「ほとんどの茸にゃ名前が付いていない、だから、名前を付ける必要はない、黄色い茸でも黒い茸でも、網編みの茸でも何でもいいではないか」
猫の言うことはもっともである。それで、茸の本を読むのをやめた。
「それじゃ、庭の茸は猫の糞の茸とでもするか」
それを聞いた猫の奴おこった。
「俺の子供に何という名を付けるんだ、くそったれ」
汚い言葉遣いだこと。
「じゃあ、なんという茸だ」
「うんちたけ」
「もっと臭ったらしいじゃないか」
「運知茸といってな、将来を知る茸たちだ」
「それで何で、猫のこどもが茸なんだ」
「吾輩は猫ではない」
「それじゃないんだ」
そう言ったら、猫の奴、床の間に行っておちゃんこをした。しっぽを高く持ち上げると、うーんーち、というや、煙を上げて、薄茶色の大きな茸になって、どでんとすわった。脇にいけてあった万年茸がおどろいて、
「これはこれは、運知茸大王さま、わが家にようこそ」
「吾輩ハ茸」
運知茸は吾をみてにーっと笑った。
そういえば「茸のしっぽ」に出てくる茸に名前がない。探偵小説だから、運知茸はいい名前かもしれない。
きったねえ名前付けるな。
吾輩ハ茸。
吾輩は茸であるといえないのにはわけがある。植物なら私は草ですとか、木ですとかいう。動物は吾が輩は猫であるなどと主人のようにふるまう。茸の吾は、草のようになよなよにはいえず、といって、動物のようにえばったようには言えない。そもそも、動物は動き回って、植物は土の中に根をはって、好き勝手に地球を荒らす。我々茸はそんな植物と動物のよごした後かたづけをする生き物だ。古風なとこもある。それで、あっしは茸です、とか、あちきは茸です、とかいうのだが、ちょっと夏目漱石のように言わせてもらって、主張しても、吾が輩は茸である、とはいえなくて、せいぜい「吾輩は茸」どまりなのである。
ただ、地球の上や中、空気の中で動物ども植物どもの、なんともこっけいな生活ぶりを、どこからでも眺めて楽しむことのできる唯一の生き物なのである。
実は、吾輩はビールを飲んで猫じゃ猫ジャと踊りながら、井戸に落ちて這い上がれず、あの世にも行かず、井戸の中で茸と合間見え、ここにいるわけである。
吾輩ハ茸。
第一章 玉玉玉
さて、時は移り、大学在学中に書いて本になった探偵小説「茸のしっぽ」が大当たりをしたぼっちゃんは、卒業してから、今まで借家だった家をかいとり結婚をした。ばあやの清代はそれを機に松山の田舎に帰った。坊ちゃんは奥さんの実野さんと女中の玉さんと暮らしている。さらに身の回りには三匹の猫がうろうろしている。
清代にぼっちゃんと呼ばれていた探偵小説作家、冬目漱茸は、今、虫下しと呼ばれている。
結婚して三年たった。探偵小説作家として独立した坊ちゃんは、座敷のテーブルで連載小説案を練っている。天気の良い日はそこで書き物をする。
家の庭に生えた茸が家を見上げた。
吾輩は茸である。名はまだない。いやずーっとないだろう。まてよ、誰かがつけてくれるかもしれない。茸はボーっと庭を見ている探偵小説作家を見てそう思った。こいつも大学を卒業して、本をだし、細君までこさえるたあ、なんとラッキーな男だ。まあ、偶然にもうまくいく人間もいるものだ。だが、こいつが俺に名前をつけてくれるのだろうか。どうせろくな何ならないだろう。いちぞやは運知茸とかいっておったが、それじゃたまらん。名がないほうがいい。
この家のご不浄は縁側の突き当たりにあるが、吾輩はその庭先の鹿威しの脇に生えたのだが、けっして、ウンチ茸と呼ばれたからではない。
作家が女中の玉に何か言っている。
玉が吾輩のところにやってきた。
「この赤い茸でいいですか」
「ああいいよ」
主人の一声で、玉は吾輩の足元にシャベルをグサッと突き刺した。園芸用のシャベルなのだが、吾輩から見ると凶器のように見える。
吾輩は庭の土の中に広く張っている菌糸から切り離され、シャベルの上に乗っかった。玉の手が吾輩の足元の土を丸め、あらかじめ用意してあった鉢につっこんだ。周りに土を入れ、吾輩は下のほうを土の中に埋められてちっと気持ちが悪い。
「こんでええじゃろね」
女中の玉は鉢に立たせられた吾輩を見てうなずいた。
茸って言うのは菌糸から切り離されれば萎れるしかないんだぞ。そうじゃなくても一週間で萎びるから、若いのにバトンタッチするんだ。
玉はそんなことおかまいなしに、吾輩が植わった鉢を大事そうにもって縁側に上がった。
「玉、座敷の床の間に置いておくれ」
女中の玉が素焼きの鉢についていた土を雑巾で拭うと、床の間に和紙を敷いて、その上に吾輩の植わっている鉢をのせた。
「うんいい、掛け軸はなににするか」
虫下し先生が、吾輩にあいそうな掛け軸を思い出そうとしていると、いきなり「玉、なにをする」と怒鳴った。
部屋を出ようとしていた秋田から来た女中の玉が。顔を赤くして、「旦那様すみません」と振り返って謝ったのだが、頭をパチンとひっぱたかれたのは、鉢に植わった吾輩に鼻先をくっつけようとしていた、猫の玉だった。猫の玉は虫下し先生を見て「なにをしやがる」という顔をしている。
女中の声で逆にびっくりしたのは虫下し先生の方だ。女中の玉が真っ赤になって謝っているのを、こりゃ悪かった、「こいつでね」とまた猫の玉の頭をひっぱたいた。
猫の玉は虫下し先生の手をひっかいた。
「いて」
女中の玉はあっと思ったようだが、「すみません」とまた謝って、猫の玉を抱き抱えて、部屋を出ていった。
虫下し先生の細君は、評判の猫好きで、三匹も飼っているのだが、猫の名前は「玉」しか思い浮かべることができず、最初に家に上がり込んできた虎猫に玉と名づけ、一年後に拾った白い猫にも玉としたのだが、その玉はまぎらわしいので「後玉」と呼ばれている。もう一匹もらってくれと頼まれた三毛猫にまた玉となづけた。それでそいつは「又玉」という。女中を選ぶのにも、猫でもないのに、今ここにいた十五歳の秋田の娘の名が玉だったので雇うことにしたのだ。
細君は虫下し先生の大学の時に偶然であった娘で。おっとりとしていて、なかなかの器量よし、虫下しにはもったいないとの評判だったが、似たり寄ったりの二人で、ある意味おしどり夫婦である。
「あなた、後玉こなかったかしら」
細君が座敷に入ってきた。
「いま、玉が連れて行ったよ」
「あれは、玉ですよ、私がさがしているのは、後玉」
ふと虫下し先生が細君の抱えているもの見たら白い猫である。
「そいつが後玉でしょう」
細君腕の中の猫を見る。
「あらいやだ、探していたのは又玉でしたわ」
「どうして探しているのかね」
細君は白猫の後玉を下におろすと首を傾げた。
「あら、何で探していたのかしら、ご主人様は探偵小説家、おわかりになりませんの」
そういわれて、虫下し先生も確かにそうだと思って話しを変えた。
「今日は初めての月見の句会ですから、お酒を用意してくださいよ」
といって、床の間の吾輩を指さし「今日のお題ですよ」と言った。
「茸ですか」
「なんという名前の茸かしらんが、庭に生えておった、勝手に庭に入り込んで、野良茸だな、ははは」
虫下しが笑った。
「では、又玉がきたら、私が探していたと言ってくださいな」
「この茸を知っていますか」
「いいえ、真っ赤できれいですけど毒でございます、赤玉毒茸でございます」
そう断定した。というわけで、吾輩は細君に赤玉毒茸と言う名前が付けられた。
虫下し先生は細君がいなくなると掛け軸を天袋から引っ張り出した。寺の住職が描いた富士の山の掛け軸である。
掛け軸を床の間にかけていると、玄関の方から大きな声がした。
「虫下し、入るぞ」
八間入道だ。書家と言われているが、筆で字を書くのより、筆でエッセイや絵を書いているほうが多い。内田百閒のような随筆家になりたいと思って八年、それで八間だ。百年経たなければ百間先生に追いつかぬと言っている。鼠が大好きで、家をかじり放題にさせているため、八間の家の柱はでこぼこ穴だらけ、天井の板は鼠のおしっこで世界地図が書かれている。いつぞや訪ねた虫下しが臭くないのか問うた。すると、バラの香のようじゃと答えたという。
大きな体でずかずかと座敷に入ってきた。
「なんだい、八間さん」
「月見の句会だろう」
「そうだが、まだ昼前ですぞ」
「句などは早く考えて、月見酒にする」
「それにしても早すぎる」
「ほら持ってきた」
八間は浜納豆持参である。昼はこれで茶づけである。浜納豆は鼠の糞だ、うまい、といったぐあいだ。
「今日の題はなんだ」
言われた虫下しが床の間を指さした。
「茸か、赤い毒茸だな」
「毒かどうかわからんが、うちのもそう言っていた、赤毒茸だと」
「そうか、実野殿が言うのならそうだろう」
八間は小学生の時、虫下しの細君と同級生で、虫下しと年は同じだが違う小学校に通っていた。
細君と虫下しの出会いはこんなものだった。
虫下しが帝大の文学部三年のときに、東京音楽校に通っていた実野と神田の古本屋ですれ違った。次は上野の駅ですれ違い、早稲田の古本屋で江戸川乱歩の初版を購入して帰る途中、家の近くの曲がり角で正面衝突をした。気絶したのは虫下しの方で、あら大変と、実野は自宅に手伝いを呼びに行った。虫下しの家と実野の家は意外と近かったのだ。
実野の父親は大日本女頼神教の教祖で、信者がたくさんいたので、虫下しを自宅にかつぎ込み医者を呼んだ。医者が正露丸をかがせたら気がついた。実野の父親は虫下しが帝大生で文士ときくと、その場で「ふつつかな娘が、大変なことをした、お詫びに娘を差し上げる」と相成り、なぜかめでたく虫下しが帝大を卒業した年に婚姻の運びとなったのである。
虫下しはそれでも、在学中に書いた一冊の探偵小説がかなりの売れ行きで、学生のときに住んでいた借家を持ち家にして、その上、しばらくは楽に暮らせる印税が入ったのである。
八間もそのころ前衛毛筆家として売れており、その奔放な字が一部の愛好家たちにもてはやされていた。虫下しが探偵小説「茸のしっぽ」を出すとき、出版社が箱の題字を八間にたんだことから、知己をえることになった。そのときは、八間が細君になる実野と同級生だったとは想像だにもしていなかったわけである。
虫下しが結婚をしてまもなく、「茸のしっぽ」の縮刷版がでることになった。その本の題字も八間に頼むことになり、八間は虫下しの家に呼ばれもてなしを受けた。
そのとき、挨拶に顔を出した実野を見た八間が大声を上げた。
「あ、実野さん」「あ、入道」と小学校以来の再会を果たしたわけだ八間入道の本名は横溝精子というのだが、小学校の時から体が大きく入道と呼ばれていたそうだ。
「うちの虫下しの本をきれいにしてくださってありがとう」
と、実野は八間に礼を言った。
そのあと、しこたま酒を飲んだ、八間は虫下しに聞いた。
「何で、虫下しなのですかな」
それを聞いた実野が、
「あら、私がそう言ったら、みなもそう言うのよ、きっとぴったりなんですわ」
としれっとしている。
結婚してまもなく、腹がおかしくなった虫下しが医者にいったら、回虫でしょうと虫くだしを処方され、しばらく飲んでいたら回虫がでた。
「あら、お出しになったの、もったいない」
細君はそう言っていたのだが、他人に虫下しを飲んでいると言いふらした、それがあだ名になってしまったということだ。
八間が帰ると、実野は
「おほほ、八間はそのころ、あたしのあとを追いかけていた糞」
と言った。
驚いた虫下しが細君の顔を見た。糞なんて言葉を結婚してからこのかたまで発したことがない。だがそう言ったあとの細君の顔はまったく変わりがなく、おほほという顔をしている。虫下しは目を丸くしたままだった。
今日の句会にはあと二人、仲間が来る。一人は音楽大学の教師で作曲を教えている木琴と、詩人の桑子だ。木琴は実野の音大での同級生で、優秀ゆえ学校に引き留められ音楽学校の教師になった。ぬぼーとしていて、木琴の玉のついたたたき棒で頭をたたきたくなるの、と細君はそう言って、木琴そのものよといい加えた。それで、虫下しが、あの木琴と言っていたら、ほかの奴も木琴と呼ぶようになってしまった。本名はみな忘れてしまっているが、酒本立一という。
桑子は早稲田大学の文学部を中退して、劇団の一員になりながら詩を書いている。虫下しは細君とその芝居を見に行って、彼が芋虫の格好をして、せりふ、恋の悩みも知らぬ間に、命ほどかれ糸となり、光の布に輝くも、お蚕哀れ、と言うのをきいた細君が、お蚕さん、くわこというのよね、と虫下しに大きな声で言うものだから、観客からくすくすと笑いが漏れた。本名は桑子絹鳥(けんちょう)である。
演劇を見に行ってからしばらくして、姉妹社に用事で行った虫下しが、編集部からしょげて出てきた男と鉢合わせしそうになり、虫下しが彼に気がついた。あの劇はおもしろかったですなと言うと、ありがとうございますとうつむいたまま答えた。それで気になった虫下しが、どうしましたと聞くと、詩がだめでした、というので、彼が原稿をこの出版社に持ち込んだことがわかった。そのときはまだ名前を知らなかったわけだ。
双子社は探偵小説の雑誌「犯人の探偵」と詩の雑誌「あいうえお」を出している不思議な本屋である。編集部はそれぞれに分かれているが、デスクは北と南に分かれ、双子の妹の町街有瑠代が詩の雑誌の編集長、兄の町街早合士が探偵小説の編集長をや
町街は坊ちゃんの大学の先輩で、「茸のしっぽ」を出してくれた小倉出版社の編集員をしていた。虫下しの担当だったのだが、それが独立して妹と双子社をつくった。
それには虫下しの書いた二冊目の探偵小説「猫のしっぽ」が関係している。「茸のしっぽ」の最初の原稿を町街が編集部にもって帰ると、編集長から「茸のしっぽ」は面白かったが、これでは売れないと言われてしまった。町街はそれを機に大手のその出版社をやめて雑誌出版社をつくったのである。「猫のしっぽ」は姉妹社の「犯人は探偵」に掲載され、姉妹社から本になったがそこそこしか売れなかった。
今、虫下しは雑誌「犯人の探偵」に毒茸による幻想小説を書いている。読みきり短編シリーズ「茸十夜」である。自分に幻想小説は無理だと思っていたのだが、町街にやってみたら面白いよといわれ、その気になって引き受けたのだが、なかなか第一回が書きあがらない。次号も無理だと言いに来たところである。
虫下しはよせばいいのに、彼に原稿を見せてといって、接客用のソファーにひきもどして、原稿を手に取った。詩の三つ目に、恋の時効と題されたのがあった、「殺されたのは誰ですか、赤い血は出ましたか、殺したのは誰ですか、あなたですか、彼ですか、殺されたのはいつですか、大学の時ですか、そんなことは、そんなことは、きれいさっぱり忘れましょうね、ときがながれ、気も変わり、みんなさっぱりわすれてますか」
と言うものだ。これなにと聞くと、流行歌を聴いていたらできた詩だという。
それで何を血迷ったか虫下しがその詩を探偵小説のデスクに持っていって編集長に見せた。またそこで何を血迷ったか、編集長は正月号の巻頭にのせるといいかもしれないと言った。しかし、タイトルは「恋の」を削ってただの「時効」となった。ついでに時効をテーマの探偵小説を虫下しが頼まれた。ということで、意味がかわるにせよ、その男は自分の詩が初めて活字になるということで大喜びをして、虫下しに頭を下げ、桑子絹鳥土名乗った。それ以来虫下しのことを先生と呼んで、恩人と慕うようになった。
虫下しが家に帰り、そんなことがあったと話したら、「あーら、あのくわっこが」と細君は大笑いした。そのとき、「くわこ」ではなく「くわっこ」と言ったものだから、桑子は、くわっこ、くわっこと呼ばれるようになった。
よく考えると、虫下し先生の周りの人間はすべて細君に命名されていることになる。
吾輩も赤毒茸となづけられたじゃないか。
ところで、句会に浜納豆を持ってきた八間入道は、細君がお茶と白い飯をもってきたので、浜納豆のお茶漬けを食べている。
「あなたもめしあがります」
細君に聞かれた虫下しは、鼠の糞はいやだ、うめぼしでいいとそっぽをむいた。
「それじゃ、小梅をもってきますわ」
細君は白い飯に小梅をころころのっけて持ってきた。
「どうぞ、小梅茶づけ」
そう言って、細君は部屋から出ていった。
八間入道は腹一杯になったと見え、吾輩に目を向けた。
「赤は毒、茸をつかう、アメリカ軍、どうだ虫下し」
「なんだそりゃ、茸は秋だが、なにをいいたいのですかね」
「アメリカに行くのに、入国の時に、共産党かと言う設問がある」
「それはそうだ、アメリカは共産主義を嫌っている、だがアメリカ軍がどうやって、茸を使うのですかね」
「広島、長崎で使ったじゃないか」
「ああ、原爆ね」
「茸雲を作る奴だ、ソビエトと茸雲の大きさで競っている」
吾輩は聞いていて不愉快になった、茸は菌糸からはえるが、茸雲は人間のおろかさから生える。
「入道は茸雲より、入道雲のほうが似合う、夕方までここで昼寝してるといいさ」
「虫下しはどこへ行く」
「ちょいと、アメリカ屋に」
「なにしにだ」
「帽子でも見繕いに」
「お内儀をおいていっていいのか」
「ご随意に、猫に引っかかれるなよ」
虫下しはそういって本当に出かけてしまった。
しばらくすると、入道はもそっと立ち上がった。
吾輩は床の間で、入道がなにをたくらんでいるのか、聞き耳を立てていたのだが、ただ、へいこらする「はいはい」という入道の声が聞こえるばかりである。
夕方、アメリカ屋で帽子を買った虫下しが家に戻ると、台所でぬかみそを入道がかき回していた。
「けけ、なにしておる」
虫下しが入道に聞くと、入道顔を上げて、「実野どのが、きゅうりを出して新しくつけてくれと申された」
「キュウリが今日の酒のつまみか、それで、実野はどこに」
「向こうだ、三匹の猫とお遊びだ」
「それで、入道君は何でぬかみそだ」
「実野殿に遊ばぬか、ともうしたら、喜んで、はいと、お返事なさった」
「それで、ハッケンさん喜びましたな」
「そりゃもう」
「それで」
「実野どのは、猫と遊びたかったのじゃ、それじゃ入道、ぬかみそをよろしゅうに、と、玉、あと玉、また玉をつれて、奥にいらっしゃる」
「女中の玉はどうしましたかな」
「入道がぬかみそつけるそうじゃ、玉も向こうで、遊びましょうと、つれていった」
「そりゃあそりゃあ、よろしく」
と虫下しは買った帽子を細君に見せに行った。
「いいお帽子、貸してくださいな」
細君は虫下しから帽子をとると「ほら」と畳の上に頬り投げた。おりゃきた、と猫たちは目をきょろつかせ飛び上がった。三匹はひっくり返った帽子の中に入りたくて取り合いをした。
「貸しておいてくださいな」
そう言われた虫下しは、すごすごと座敷に戻った。こうして吾輩はこの家の支配者が誰であるのか知ったのである。もちろん彼らの名付けの親である。
夕方になると木琴と桑っこがやってきた。
細君が玄関に迎えにでる。猫たちも顔をだした。
「いらっしゃいませ八間さんがもうお見えでございますよ」
「お久しぶりです、今日はお世話になります」
木琴と桑っこは座敷に通された。三匹の猫たちも入ってくる。
「玉さん、あと玉さん、また玉さん、みなお元気で」
猫好きの桑っこは三匹の頭をなでた。
虫下しと入道が座敷に入ってきた。開け放たれた縁側のお膳の上に団子が盛りつけてある。青磁の花瓶にススキがいけてあり、その脇に鉢植えにされた吾輩が置かれた。
座敷の縁側沿いに、四つのお膳が並べてあり、上に鉢物、皿もの、杯、箸がのっている。右端に虫下し、左端に八間入道が座って神妙な顔をしている。
「いらっしゃいましたわよ」
細君が二人をつれてきた」
「おじゃまします」
桑っこが尊敬する虫下しの隣に座った。
「こりゃあ、八間先生、久ぶりです」
木琴が座ると、入道より頭一つ上にでる。
「玉、お酒をお持ちして」
女中の玉が、燗につけた銚子を四本もってくると、それぞれのお膳の上においた。
「今日は手酌ですぞ、皆様方、いい句をひねりながら、ちびりちびりとおやりください」
細君がまた入ってきて、「お皿の上は吾家の畑でとれたキュウリのぬか漬け、鉢のものは、シメジを煮たものですの」と説明した。
入道がぼそっと、「肉気が欲しいの」と言ってしまったのを、耳ざとく聞いた細君は「あ、そうでした、田づくりがありました、玉、もってきて」
「奥様、猫のしかありません」
「煮干に、猫用も人用もなくてよ、紫にちょいとくぐらせて、火にあぶってもっていらっしゃい、入道さんには特別に二匹お願いよ」
「はい、奥様」
「それでは、ごゆるりと」
虫下しが銚子を持ち上げた。
「まずは一杯、今日は茸がお題ですぞ」
最初の一杯をみなが口にした。
木琴が鉢植えの赤い茸に気がついた。
「茸の鉢植えたあ風流ですな」
「よく枯れませんね」
桑っこが不思議そうな顔をした。虫下しが得意そうに、「私のアイデアでしてな、手水場の脇に生えておりまして、今日の月見の会に持ってこいと思ったわけで、茸が今日のおだいですからな」と杯を傾ける。
「先生は茸がお好きなんですね、最初の本も茸のおっぽ」
「いや、さほどではないな」
「このシメジはうまく煮てある」
入道がほめた。そこへ、それぞれお膳の上に薬包紙にのせられた煮干しが配られた。
「この、薬包紙というのはしゃれてますな」
木琴が珍しそうに見た。配っていた女中の玉が「先生の、虫下しを小分けにするために、奥様が病院から分けてもらったものです」と説明した。
入道は一匹にかみついた。
「猫になったようだ」
そう言いながら、今度はキュウリを食った。
「句も考えてくだされよ」
「うん、まだ少し明るいな、月がさえない」
入道はそれでも、持ってきた紙にさらさらと書いた。
木琴も桑っこも筆をとった。
しばらくはちびり、ちびりと飲みながら筆を動かした。八間入道は銚子をすでに三本も空にしている。
「虫が鳴いていませんな」
いきなり木琴が不思議そうに尋ねた。
「確かに鳴いていませんよ、うちの方じゃうるさいくらいにクツワムシが鳴いていますよ」
桑っこはそう言いながら紙をにらんでいる。
「わしの家じゃ、すずむし、こおろぎ、大合唱だ、酒」
入道も赤い顔を茸にむけた。
言い終わらないうちに、女中の玉がとっくりを運んできた。
虫下しが玉に「うちは虫が鳴いていないと皆が言うんだが、どうしてか知ってるかい」とたずねた。
「はい、一昨日、奥様が、虫を追い払う薬を買ってきて撒くようにおっしゃいましたので、そうしました」
「庭の虫は死んだのか」
「わかりません、かわいそうに思ったので、撒く前に、殺虫剤撒くよ、お逃げと言っておきました」
吾輩はなんてことをすると少しばかり顔を赤くした。
「どうして殺虫剤などを」
木琴が解せないと、長い顔をますますのばした。
「旦那様にまた虫が付くといけないとおっしゃってました」
「実野さんは旦那思いだなあ」
八間入道がしみじみという。
桑っこは狐に摘ままれたような顔をしていたのだが、木琴がスーイッチョンと鳴いた。まねをしたのである。それでこの件は落着した。
虫下しがまたもやお銚子を空にすると、どうやら大きな月が庭の真上に輝いた。
「いい月ですな、もうみなさんできましたかな、そろそろどうです」
虫下しの声で、「よかろう、だがまだ飲むぞ」入道はまたお代わりの催促だ。
「それじゃ、木琴さんいかがですかな」
「ははあ、まあやりましょうか」
木琴が短冊を手に取った。
「秋の夜や、庭の茸も月かむり」
「なかなか風流ですな、茸の傘が月の光で黄色い帽子になってるなんざ、おつですな」
虫下しがほめると、木琴が目を細めた。吾輩は黙って聞いていた。やけにまじめな句だ。
「もう一句、風涼し、茸も歌う、虫の音に」
入道が杯をおいて「虫は死んじまったじゃねえか」
と毒づく。桑っこ君が「木琴さんが、ご自分でカマドウマまになって鳴きました」と助け船を出した。
「そりゃあ、カマドウマじゃないよスイッチョンは馬おいってんだ」
虫下しが訂正した。
「それじゃ桑っこ、やってみろ」入道はだいぶ酔っぱらっている。桑っこが短冊をもった。
「名月を、茸とともに、杯で飲む」
「そりゃあ、土瓶蒸しのことか、だけど、ここはまったけの土瓶蒸しはでてねえぞ」
「はい、想像で」
「いや、いいですな」木琴がほめた。
とんでもない、茸の人生がにじみでていない。吾輩はつまらなくなってきた。
「ではもうひとつ、葉隠れに、そっと覗くは一夜茸」
「さすが詩人」
虫下しがほめる。こちらを見て吾輩を詠め。
「では、八間さんどうぞ」
入道はいきなり大きな声で詠んだ。
「今宵また、誰ぞとわからぬ、松茸と、次、あなたとは、今宵限りと、一夜茸、また次ぎ、寝ていれば、臍の当たりに茸はえ」
「八間さんは、遊郭の句ですな、字はすばらしい」
虫下しは何とかほめた。これが句かい。遊郭いっても相手にされないくせに。
「ではあたしが、輝きの月のあばたに茸はえ、次、しいたけと、滑子にえのき、そばの上」
桑っこがなにか言わけなければと思ったのだろう。
「先生の句はミステリアスですな」とほめた。どこがミステリアスだ。
「おい、飯はでないのか、ニボシでもいい、もっとくれ」
「玉さん、飯をたのめるか」
奥から玉が出てきて、「煮干しは猫がぜんぶ食べました、ご飯も味噌汁をかけて猫が食べました、炊かないとありません」と言った。
「実野はどこにいった」
「いつものように、おやすみになっていらっしゃいます」
「そうか、もう九時過ぎか」実野は九時には猫と一緒にねどこにつく。
「腹が減った、どうだ、あの茸食ってみないか」
八間入道の目が赤い。
「毒ですよきっと」桑っこが恐ろしそうに言う。
「真っ赤ですからね」木琴もうなずく。
「ご不浄の近くにはえていた」
「諸君、泰西では回転式短銃に一発実弾を込め、銃創を回転し、皆が頭に銃を当て引き金を引く、と言う話だ、運試しだが運が悪いと死ぬ、この茸でやってみようじゃないか」
「なにをするんで、玉さんにこれから醤油の煮しめを作ってもらう、椎茸はあるかね」
「椎茸はまだあります」
「そうじゃ、椎茸の頭だけを煮る、この茸の頭も醤油で煮る、赤いが醤油で煮てしまえばわからなくなる。煮た茸を蓋付きの器に入れ持ってきてもらい、酒とともに食う。玉さん用意してくれ」
虫下したちはびっくりしているが、入道が玉さんに命令した。
それを聞いた吾輩もびっくりした。頭を取られる。といってもすでにからだである菌糸からは切り離されており、あと数日でかれる運命だ、どうにでもしやがれ。
「はさみを持ってきてくれ」
入道の大声で玉が断ち切りばさみを持ってきた。
入道は鉢植えの吾輩のところにくるとはさみを広げた。
なみあみむだぶつ、波阿弥陀物、今度生まれてくるときは、一夜茸になれますように。
はさみが吾輩の頭をちょきんと切った。
吾輩の頭は玉さんが台所に持って行った。
「本当に食うんですか、僕帰ろう」
桑っこが立ち上がろうとした、
「おい、弱虫、それが天下の早稲田の卒業生か、詩を書くには、死をかくごせにゃならん」
そういわれては座るしかない。木琴もそわそわしている。
「木琴はさすがに偉大な作曲家だ、茸ごときにびくびくしてない」
入道にそう言われてあきらめたようだ。探偵小説作家の虫下しは以外と平然としている。
「ではできてくるのを待つあいだ、辞世の句を詠んでおこう」
入道がそう言ってしばらくすると、できたと短冊をあげた。
「当たるも八間、当たらぬも八間、この夜は楽し、あの世も楽し、さようなら」
なんだか聞いていてバカバカしくなってきた。吾輩茸は体中が目で耳だ、頭がとられても、きこえるし見える。
「辞世の句は死んでからにします」
桑っこが言った、虫下しと木琴もうなずいている。
こいつら本当に学士たちなんだろうか。死んだあとどうやって書くんだ。ゾンビか。
玉が蓋付きのお椀に茸の醤油煮とお銚子をそれぞれの膳においた。
「おおきたきた、それじゃ、隣同士でお椀を取り替えよう」
入道がそう言って、入道は隣の木琴と、虫下しは桑っこと取り替えた。
「さて誰から食べるか」
入道は杯を傾けながらいった。
「責任上、あたしから」
そう言って、虫下しがお椀の蓋をとると、平然と茸を箸ではさまむと口の中に入れた。
「椎茸だ」
そういって、噛み砕き飲み込むと、酒を飲んだ。
桑っこはなかなか蓋を開けない。
「ほら、男らしく食え」
入道が大声を上げた。びくっとした桑っこはパカッと蓋を取ると茸を食べた。
「椎茸だ」涙を流した、
さて、木琴である「神様神様、アーメン」
胸に十字を切るとお椀に箸をいれ、口に入れる前に茸を取り落とした。木琴はにこにこして、今度は落ち着いて箸で落ちた茸を拾うと口にいれた。
「椎茸です、匂いでわかりました」
木琴はにこにこして八間入道を見た。虫下しも、桑っこも見た。真っ赤だった入道の顔が青くなっている。みんな何もいわずに入道を見つめている。
入道が銚子ごと酒を飲み干すと、ふるえる手で箸を持ち椀の蓋をとった。目がうつろに宙に浮いている。
「椎茸の匂いがしない」と言いながら、茸を口にいれ一度しか噛まずに飲み込んだ。とたんゴロリと横になると、痛い痛いと言いながら腹を抱えた。
「救急車、救急車」
叫びながら桑っこが八間の背中をさすった。
「助けてくれえ」
入道が大騒ぎをした。
虫下しは「おかしいなあ、玉、どうしたんだ」と女中の玉に聞いている。
「言われたとおりにしました」玉はぶすっとしている。
「どうしたのです、そうぞうしい」
細君がおきてきたとみえて、寝間着に羽織をはおってはいってきた。猫もついて入ってきた。
「入道が茸を食べて苦しみだしたんだよ」
「あんな茸で大げさな、毒茸でも一つ食べただけで死ぬことはありません、入道は子どもの頃から恐がりで、大げさなのです、こうすれば直ります」
細君は入道のほっぺたをばちんとひっぱたいた。周りの三人がびっくりするほど大きな音だ。
入道の顔に赤みが差してきた。三匹の猫が入道の顔をぺちゃぺちゃなめた。
「玉、あと玉、また玉、汚いからやめなさい、それじゃ、みなさんごゆっくり、入道はほっとけば大丈夫です」
実野さんはまた奥にはいっていった。
入道は大の字になっていびきをかきだした。
「先生は度胸がありますね、茸を平気で食べておられました」
桑っこが言うと「すごいですな」と木琴もうなずいた。
「いやはや、みなさん、私は探偵小説家、トリックですよ、みな椎茸にしなさいと書いた紙を玉にそうっと渡したのですよ」
「さすがですね先生」
大したトリックじゃないでしょうに。
「それじゃ何故入道さん腹が痛くなったのでしょうな」
「緊張でしょう」
木琴が木琴のようにころころ笑った
「玉、赤毒茸の頭をもってきておくれ」
虫下しに言われて、入道が切った茸の頭を持ってきてお膳を下げた。
月が大きくなった。庭が明るくなった。
「元に戻しても意味がないが」そう言いながら、虫下しが吾輩に頭を乗っけた。
おー醤油が沁みる。だが虫下しにちょっとばかり感謝をした。吾輩は戻ってきた頭をふるわせた。醤油に沁みた赤茶色の胞子が漂った。
しばらくすると、虫下しも桑っこも木琴も大の字に寝てしまった。入道はいびきをかいている。
吾輩は毒茸ではない。いや毒茸の一種か。吾輩を食った動物は急に眠くなるのだ。胞子を吸っても眠くなる。
月光を浴びて四人の愚人がいびきをかいている。秋の風が部屋にはいってきた。四人の上を渦巻いている。虫下しがくしゃみをした。きっと風邪を引く。愚人は夏の虫、飛んで火に焼く。
第二章 妾横丁の祝玉
吾輩は茸である。名はまだない。いやずーっとないかもしれない。今生えてきたのは、下町の一軒家で、一年ほど前まではとある商家のお妾さんの住んでいる家だった。しかし、お妾さんは流行病で亡くなり一年空き家となった。その家を借りたのは前衛書家であり、随筆や絵をそこここの雑誌に載せている八間入道である。ちょいと羽振りがよくなったものだから、しょんべん長屋から出ることにしてここに移ってきた。小さいながら庭付きの家である。ここにはいくつかの家があり、どの家にも妾がすんでいたので、妾横丁と呼ばれている。
空き家だった一年間、鼠たちの格好の棲家になっていた。屋根裏はもちろん、袋戸棚の中、台所の食器棚の後ろ、いたるところに鼠たちがいた。
八間入道が荷物を持って玄関を開けると、鼠の夫婦がそろってお出向かいをした。
「お、おお、鼠どん」と入道が大きな顔をつきだしたものだから、鼠の夫婦は「なんちゅうでかい顔だ」とおそれをなして退散してしまった。
「鼠どん、にげんでもいいに」
と入道は家に上がり、自分の仕事部屋と決めていた六畳にはいった。その部屋の床間にも鼠がいた。
鼠は入道を見ると固まってしまった。
「鼠のおきものがあるのう」
入道が床間にきて手をのばしたものだから、鼠ははっと気がついて、その手に飛びつき、ぴょんぴょんと入道の頭に上ると、立ち上がった入道の頭のてっぺんから欄間に飛び移り、天井隅の穴から天井裏へと逃げていった。
「いい部屋だ」
入道が満足げにうなずくと、玄関の方から「まいりやした」と声がした。
「おう、今いく」
玄関の前にはタンスやら布団やらを積んだ大八車が一つ止まっていた。引っ越し荷物が届いたのだ。
「こっちに入れてくれんかい」
運んできた若い男に荷物を部屋に運ばせた。
前の長屋では一部屋だったのが、今度は一戸建て、三つもの部屋がある。贅沢というより仕事のための部屋がほしかったのだ。
若い男が荷物の一つを仕事部屋に運ぶと子鼠が天井からぽたりと落ちた。
「きゃああ」
その声で入道が飛んできた。
「どうした」
部屋をのぞくと若いのが畳の上で頭を抱えている。
「テンカンか」
入道はときどきとんちんかんなことを言う。
「ネズミ」
男がそう言うと、またもやもう一匹ぽたりと天井から落ちてきた。
「ひゃ」
「かわいいのう」
入道が言うと、男は「さいなら」と帰っちまった。仕方ないので、机やらちゃぶ台やら、自分で運んだ。そう言えば大八車がおきっぱなしだし、手間賃も払っていない。得したなと思っているところに、男が戻ってきた。
「へい、五十銭でございます」
入道はあんまり物事を深く考えない。
「ああ、ごくろうさん」
「これはおまけで」
五十銭もらった男はそう言って一銭を入道にわたした。
「なんだいこれは」
「へえ、鼠代で」
入道がほけーっとした顔で、
「そうか、鼠の餌代くれるのか」と、返事をした。
男は「くさ、まいど」と大八車を引いて帰って行ってしまった。
入道はちょっと暇になり、腹が減っているのに気がついた。
さて今日は蕎麦をとるか、そば屋はどこだ。となりの家に挨拶がてら聞きにいくことにした。
隣も同じような作りの庭付きの家である。このあたりは同じような小作りの家が集まっている。どの家も木塀に囲まれ、目立つ木が一本植わっている。入道が借りたところは背の高い柿木があるが、隣はゆすら梅だ。反対隣は枇杷の木がある。裏は無花果が植わっている。入道の家はゆすら梅、枇杷、無花果の家に囲まれた柿木の家だ。
さてどの家に行くか考えた末、順番でやはりゆすら梅だろう。彼は引っ越しの挨拶の品を持って家の前にたった。表札はかかっていない。
「おたのみもうす」
大きな声を張り上げた。ほどなくがらりと戸を開けて出てきたのは、色白丸顔のころっとした女である。手ぬぐいを姉さんかぶりして、エプロン姿、大きな目で入道を見た。
「はい、どなたさんでしょうか」
「これは、隣に越してきた八間ともうします、よろしくお願いします」
入道は持っていたものをその女に渡した。
「ごていねいさまですこと、よろしうに、梅でございます」」
渡したのは、虫下し先生の探偵小説「茸のしっぽ」である。表紙の題字は、入道が書いたもので、引っ越し挨拶にそれしか思いつかなかったからだ。
包みを開いた女は「あら、探偵小説、しゃれたものを、うれしゅうございますわ」
「ワシが、その題字を書きました」
「書家のお方ですの、どなたが住まれますの」
入道は意味がわからず、わしですが、と答えると梅と名乗った女は「あーあら、ご本人も一緒に住まわれますのねえ」
とやっぱりわけがわからない。
「いえ、わし一人で」
「あら、お妾さんと一緒かと思ったわ」
お梅さんはお妾さんらしい。妾家業は生半可な女には務まらない。教養、知性、感性をよく磨いた人の家業だ。入道は頭をかいた。
「あのう、それで、このあたりに蕎麦屋はありませんかな」
「大通りにでて、左にいくと三軒目が蕎麦と天ぷら屋ですのよ」
「そうれはどうも、これからもよろしく」
そう言って早々にひきあげ、枇杷の木の植わった隣に行った。
でてきたのは、やっぱり丸顔色白の肉付きの良い女だった。梅さんと同じようだ。こういうタイプを好む男が多いようだ。入道が挨拶をして虫下しの本を渡すと、
「書家の方でございますか、枇杷でございます、よろしゅうに」
そのあと自分は何を言おうかわからなくなった入道は、また蕎麦屋はないか聞いてしまった。
「はいはい、大通りを出て左に曲がりますと、角から三軒目にございますよ」
と教えてくれた。
裏の家に行くと、出てきたのはやはり、小柄で丸ぽちゃの女だった。まただ。
「無花果でございます、よろしく願います」
と頭を下げられた。
鈍重な入道も、ここにきて住んでいる女子たち誰もが、庭に植わっている木と同じ名前をもっていることに気がついた。名前と同じ木の植わっている家を探すのは大変だっただろうな、との思いを持って、入道は長屋から大通りに出た。
角から三軒目と、あった、蕎麦処こぶ八と書いた暖簾がでている。こんなに近いなら、出前でなくとも食いにくればいい。
戸を開けると「らっしゃい」と威勢のいい声がして、白髪あたまに手ぬぐい鉢巻をしたじいさんがこっちを向いた。ひょうたんのような顔の右頬に大きなこぶがぶら下がっている。
入道は、なるほどと思いながら椅子に腰掛けた。
品書きを見た入道は、どら、今日はちょっと張り込もう。天ぷらに酒をたのんだ。
「へい、熱いほうで、ぬるで」ときくので、熱いのだと入道が叫んだ。
じいさんは銚子を薬缶の湯にいれ天ぷらを揚げはじめた。
入道が見せの中をぐるりと見渡し終わったところに、熱燗とともに出来立ての天ぷらがスーッと置かれた。じいさんの後姿が目に入った。早業だ。美味そうじゃないか。
「今度、そこに越してきてね、よろしく」
入道がこえをかけると、じいさんは次の天ぷらを揚げている手を止めて、「どこにで」と聞いた。
「すぐそこのわき道を入ったところだよ」
キスの天ぷらを口にして、うまいと思いながら、入道は酒を流し込んだ。こりゃいい店だ。
「あの妾横丁か、柿の家だろう」
「うん」
「家主が、借り手がなくて、人さがしてたんだよくはいったね」
「何しろ安いからね」
「そりゃ、そうだ、前にすんでいたお岩さんは流行病(はやりやまい)にかかって、頭の毛は抜けるわ、かわいそうに、とうとう死んじまった。旦那だった人は、それでもちゃんと弔ったのだが、幽霊がでるという噂が立っちまって、女の人ははいりたがらねえ、何せあのあたりはみんな妾の家でね、本当は男なんていれるこたあないんだが、借り手がつかなくて、お宅さんがはいったってわけさ」
入道は安いわけがよくわかった。
「するてえと、ゆすら梅、枇杷、無花果、みな妾さんかね」
「そうだよ、家主のやろうの妾もいるよ、はずれの石榴のいえだ、皆違う木が植わっているだろう、妾の旦那が家をまちがうといけねえから、そうしたんだ」
家主の家には家賃を置きにいったが、小柄な貧相なじいさんだった。
「俺の家には柿の木だ、前にいた妾は柿じゃなくてなんで岩っていったんだ」
「そうだなあ、柿だったらあんなにならなかったかもしんねえな、石屋の妾だったいい女だったのに、病だか毒を盛られたのかわからねえが、ひでえ顔になっていたな、岩ってえのは本名だ」
「梅も琵琶も無花果もほんとの名じゃねえのか」
「あったりめえじゃねえか、だんながよ、家に帰って寝言でついつい女の名前をいうこともあるだろう、果実の名前なら安心じゃねえか、それでよ、庭に植わっていた果物の名前でよんでいるんだよ、石屋も岩さんを富有と呼んでたぜ」
「富有柿か、なるほど」
やっと入道にも妾の仕組みがわかってきたようだ。
「天ぷらうまいね」
「蕎麦は俺で三代目だ」
「そばは終わりに食うよ」
「引っ越し挨拶にゃ蕎麦配るがやらんのかね」
「ありゃ、そういもんだったか、俺は本をくばっちまった」
「何の本でえ」
「探偵小説だよ、表紙を俺が書いたんだ」
「なにやさんで」
「書家だ」
「そうかね、この品書きゃあ、ワシが書いたんだが、専門家に書いてもらった方がいいかもしれんね」
入道が改めて壁に貼ってある品書きを見た。
俺よりうまい、こりゃ、まいった。
「いや、いい味の字だ、素人でも自分が書いたものの方がいい」
「そうかね、わしゃ、字などまともに書いたことがないが、品書きだきゃあ、おやじの書いたものを見よう見まねで書いたんだ、書家の先生にいいといわれたりゃうれしいね、蕎麦はあっしのおごりでさあ」
ということで、入道は最後のざるそばをせしめた。
「うまかった、またくるから」
「まいど」
元気に店を出たがちょっと気が滅入っていた。本当に俺の字より味があると思ったのである。蕎麦も逸品だ。まけ。
家に戻ると、六畳の部屋にはいって天井を見た。
あれはどこの地図だ。
天井にうっすらとだが、地図が書かれている。西洋でも東洋でもなかった。
天国、煉獄、地獄と西洋では言うそうな。あの世とこの世。黄泉の国と現世、どこにある国か場所か。ふと入道は思いあたったところがあった。
ちゅう国だ。鼠の国だ。鼠の国の地図をネズ公たちがしょんべんで天井裏に描いたのだ。どんな国なんだ。行ってみたいものだ。
オット、気がついたのは、その天井の地図の端から、黄色い茸が、傘の頭を下に向けて、生えている。
ずいぶん長い柄だ。頭のてっぺんの目玉がこっちを見ているじゃない。入道が目をこすった。茸がウインクをする。
とたんに鼠王国にやってきた。八間入道はさっそく矢盾から筆をとりだし一句まいった。
「深川の、妾横丁、わが新居、天上世界の、草片のぞき」
「なんて、つまらないの」
入道の耳に声が聞こえた。
誰だ。ネズ公か。辺りを見回しても誰がいるわけではない。どうも自分で思ったことが、耳から聞こえたのか。
「わたしよ」
「どこだ」
「あんたの頭の上」
入道は天上からでいる茸の声であることがわかった。このあいだ虫下しの家でやった句会で、変な茸を食わされたためにおかしくなったのか。入道には椎茸だったことがまだ伝わっていなかった。
「どうして天井から生えたんだ」
「天井から生えたのじゃないの、天井裏の鼠の糞から生えて節穴からでてきたのよ、天井は天上なのよ」
「なんて茸だ、それじゃ、天井裏の鼠どもは神々か」
「まあ、人間よりは神にちかいかもね」
「お前はなんていう茸か、鼠のくそ茸か」
「我が吾輩は茸、だが、まだ名がない」
「なんだそれは」
「石っころでうがいをして、歯が全部抜けてしまった作家の小説の文句よ」
「ふーん、そんなやつがいたかな」
「ねええ、ここは妾横丁よ、そんな家に、入道さんが入るのはいけないわ」
「そうだなあ、だが店賃が安くてな、大家さんが言いといったからいいんだ」
「私はお妾よ」
「どうしてだ」
「鼠の糞に養われているの、それでこの家にいるの、私の家なのよ」
「変な理屈だ、鼠が主人か、それでどうしようって言うんだ、でてけとでもいうのか」
「いいえ、仲良くしましょう、ってこと」
「勝手にしろやい」
挿入道が言うと、「おほほほほ」、と茸はするする天井裏に吸い込まれ、節目の穴が黒く開いた。そこから、鼠の糞がぽとりと入道の目の前に落ちてきた。
「糞、落ちてきやがった」
入道はひょいと摘まみ、鼻先で匂いをかいだ。その後、指でぴんと弾き飛ばした。いつも鼻くそを丸めてそうやっている。鼠の糞はぴょいと飛んで、床の間に落ちた。
入道は酒の酔いも回ってきてそこで寝てしまった。
明くる朝、といってもだいぶ日が昇ってから、入道は起き上がり、台所で顔を洗って、さて飯だとおもったのだが、もう長屋ではなかった。竈に火をおこし、火が強くなる前に、米を洗って釜にいれた。火にかけて、さて、味噌汁をとおもったのだが、味噌がない。塩はあるから、塩で食うしかない。幸い竈はもう一つある。湯を沸かした。茶を入れるのだ。
飯ができるまでちょいとかかる。長屋だと、隣の家の竈を借りたり、時にゃできた飯をもらったりできたものだ。味噌などはずいぶん借りっぱなしで出てきてしまった。一軒家とは不便なものだと天井を見ると、鼠が一匹柱にとまってこちらを見ている。
同居人の鼠はなにもしてくれぬ。飯炊き女を雇うこともできぬことではない。だが、住み込みはこまる。なぜ困るかというと、部屋を一つ取られると、長屋と同じになってしまう。大きな作品を作りたくて、この家を借りたのだ。それに便所がある。共同じゃない。入道は考え事をしながら、便所に座っているのが好きなのだ。おかげで足腰が丈夫だ。
通いできてくれる飯炊き女はおらんだろうか。いや朝の飯を探すのがいい。そうだ、そば屋のこぶ八に相談してみよう。
その日は、塩で朝飯を食べ、近所を歩いて、八百屋、魚屋、雑貨屋、それに大事な酒屋の場所を確認し、酒を一升買った。金を払ったら驚かれた。このあたりは皆、掛け売りのようだ。それで、妾横丁に越してきたことを言うと、独り者の男が借りたことに大いに驚かれた。今まで家主さんはいくら長い間借り手がなくても男には一切貸さなかったということだ。こぶ八の主人の話をきいて、入道は理由を知っていた。ところが、酒屋の主人は、
「へえ、きっと、安心な方だとおもったからでしょうな」
と言った。どのような意味だろうと入道が少しばかり考えてると、
「へい、八間さん、妾横丁の旦那衆と同じに掛け売りでよござんすよ、それに月に十升より多く買う方にゃあ、五分ほどやすくして差し上げます」
「おおそうか、それじゃ、次からそうしてもらおう」
掛け売り帳に自分で名前と場所を書いた。
「たいそうお上手で」
「わしゃ、書家じゃ」
「どうりで、ただのお方ではないと思いましたな、だから、家主さんも貸したたんでしょうな」
「ところで、ご主人、なんという」」
「へい、わたしは燗平ともうします」
「燗平さんか、妾横丁は本当はなんというんだろうか」
「水菓子横丁というんで」
「ほう、珍しい」
「あの家主さんの名前はご存じないので」
「うむ、家賃を払いに行ったが、名前を聞かなかった」
虫下しが紹介したのである。というより、顔の広い虫下しの細君、実野さんの父親、大日本女頼神教司祭が家主さんを知っていたのである。
「水菓子安次という土地持ちで、親しい大商店やお役所の旦那方に安心して妾をおける町を作ってほしいと言われ、あそこに家を建てましたんで、私ら酒屋、魚屋、米屋、八百屋は水菓子横丁を頼りに店を開けた者たちで」
「ほー、食い物屋もみなそうか」
「蕎麦天ぷらの、こぶ八はその前からありましたが、ほかの店は横丁ができてからです」
「そうか、朝、飯を食わせるところはあるか」
「こぶ八は、早くからやってますが、他にはありませんな、妾横丁にすんでいるお妾さんたちにはかならず女中さんがいまし、朝昼晩飯の用意をしますから、食べにでるようなことは致しません、ときに旦那と歌舞伎座などに行く姿がありますが」
ということで、次の日からはこぶ八で朝飯を食べることができると喜んだ。
家に戻って、仕事ができるように部屋を整えていると、床の間にひょろんとした茸が生えている。
「なんだこんなところに」
そう思って、茸に手を伸ばすと、
「やだよ、とっちゃ」
と声が聞こえた。
茸の頭に目ができた。
「なんだ、また茸か」
「あんたが、昨日、鼠の糞をここに飛ばしたでしょう、おかげで生えてくることができたのよ」
天井裏から鼠の糞から生えた茸が出ていたのを思い出した。
「茸じゃ飯炊きできないな、掃除もできない」
「おや、確かに飯炊きはむりだけど、掃除は毎日して差し上げますことよ」
「何じゃ、茸に手足があるわけじゃない、できるわけはないじゃないか」
「なにさ、手足なんて邪魔なものいりゃしない、鼠の糞を吸い取ってあげるのよ」
ということで、畳の上の鼠の糞は茸が処分をしてくれることになった次第でした。
次の日の朝、入道は起きるなりいきなり家をでて、こぶ八に向かった。朝といってもなかなか起きない入道が目を開けたのはかなり日が昇ってからだ。
入道がこぶ八の暖簾をくぐると、
「おはようございます」と黄色い声がした。入道、暖簾を払い、奥を見ると、若い女が絣の着物を着て茶を運んでいる。客は一人しかいない。
「ここは、飯も食えるのですかな」
入道が聞くと、奥からこぶのあるじいさんがでてきた。
「先生、昨晩はありがとうございやした」
「いや、こちらこそうまい蕎麦を馳走になった、朝は何時(なんどき)からやっているのかちょいとのぞいてみた」
「へえ、朝と昼は娘が手伝いにきますのでな、朝はお天道様が上がってちょいとたってから、そばはねえが飯はあります、昼は飯と蕎麦、夜は蕎麦と天ぷらてなことで」
「それはいい、これから朝飯はここでたべよう、掛売りでよいかな」
「へえ、それが夜はよござんすが、朝と昼は娘の領分でして掛け売りはしねえんで」
「それじゃ明日の朝からきますかな」
本当は食いたかったのだが銭をもってこなかった。
「今日はいいでのですかい、先生」
どうも親父は台の上の握り飯を入道がちらちら見たのに気がついていたようだ。
「うーん、ちっとしか食わなかったから、食いたいことは食いたいが、銭をもってこなかった」
「あーそそれなら明日一緒でいいでがすよ、といってもこの時間になると、結びも残りは少ないのですが」
娘もうなずいている。ひょうたん顔のじいさんと違って、丸顔色白の真にかわいい娘である。
「それなら、必ず明日払うから、そこの握り飯、いくつかもらおう」
「へえへえ、ほら、空(そら)、八間入道先生だ。妾横丁の柿の木の家にきた書道の先生だ」
「あーら、男の妾」
それを聞いて、入道の目がひゃっという丸目になった。面白い娘だ。
「ばか、先生すんません、こいつ言いたい放題の女で、空と申します」
それを聞いて入道は大笑い。
「おおいに結構、おおかた親に似たのであろう、よろしくたのみます」
「こちらこそおねがいします」
娘はにこにこと笑窪を寄せて白い歯を見せた。よい店だ毎朝来るぞ。
前に出されたのは白い塩結び、梅干結び、沢庵結び、それに野菜の漬物の結びである。
熱々のお茶に、入道は結びをほおばった。
ひゃ、うま、うま。
味噌汁が少し残っているので、これはサービスです」
娘が味噌汁の椀をもってくる。
「それはありがたい」
入道は最後の結びを口にいれたところだ。
「これは旨い、空さんもうひとそろえいただけぬかな」
空が笑顔で一そろいもってきた。
「これはおまけです」
味噌で焼いた結びを一つ加えてくれた。
「これはなぜ売り物にはいっておらぬのですかな」
「いえ、いつもはあるのですが、あいにく味噌が味噌汁の分しかなくなってしまって、今日は作らなかったのです、味噌汁ももう残りはほとんどありません」
「仕事に行くやつらが朝早くから食いにくるから、この時間だと残りものになっちまってね」
父親が説明した。
「いや、うまかった、本当に毎日きますぞ」
入道はありがとうございましたという娘と親父の声に送られて店を出た。
その足で酒屋にまわると昼間から一升ドックりをつるして家に戻った。
「どこにいってたんだ、朝から酒か」
玄関の前に虫下し先生が立っている。細君の実野さんまで一緒だ。竹で編んだ籠をもっている。西洋式にいうとバスケットだ。
「いや、ちょっと朝飯と買い物にな、これは夜の楽しみじゃ、実野さま、虫下し殿、いろいろ世話になった、鼠がいていい家だ」
この家を世話した二人には頭が上がらない。
「あら、そうだと思った、それでこれもってきたのよ」
細君がバスケットをもちあげた。
「なんですかな」
「子猫よ」とふたを開けると、「ふにゃ」と鼠色の子猫が顔をのぞかせた。ひしゃげた顔をしている。
「あ、そりゃあ、こまる、猫は困る」
入道が断っても、もうおそかった、子猫はバスケットから飛び出すと、入道があけた玄関から中に飛び込んだ。
「鼠がいるなら、餌代もかからないでしょう」
「いや、いや、実野さん、鼠ドンはワシの友達でして」
「入道、子供の時、猫大好きだったじゃない」
「ええ、そりゃ、でも大人になったら、鼠の方がワシに似ていて相性がいいと思うようになりましてな」
「鼠はねずみ算でふえるもの、毎日一匹食べても、減らないでしょう」
実野は笑いながら、
「この猫、もらってくれといわれたけど、もう三匹いるでしょ、どうしようかと思ったら、この人が入道の引っ越し祝いを持っていかにゃと悩んでいたから、それにゃらと、ひきとって、もってきたでごにゃいます」
「実野さん、猫にならんでください」
「名前は引っ越し祝いの玉、祝玉よ」
「いや、名前はどうでもいいんですがな、鼠が食べられると困ります」
「餌をちゃんとやれば満腹して鼠も取らないでしょう」
細君はしゃあしゃあとしている。
入道が子猫を追いかけて家に上がると、虫下し先生と実野さんも入道の後についていく。入道が部屋にいくと子猫の祝玉が床の間で首を下げている。
「玉やどうしたの」
実野が近づくと、大きな鼠が祝玉の頭に足をのっけている。
「なにやってるの」
実野がおこって、鼠を追い払おうとすると、鼠は祝玉の尾っぽをくわえて、床に開いていた穴の中に引きずり込んだ。
「あ、祝玉が誘拐された」
虫下し先生も驚いた。
あわてて床の間に行くと、穴の中には鼠も猫も見えない。
「どこにいったのでしょう、入道大変、大変」
実野があわてていると、入道はほっとした顔で、
「さあ、いずれ戻ってくるでしょう、まあ、それまで、どうぞ座っておまちください」と座布団を用意した。
「茶をいれてきますでな」
入道が台所に行くと、実野は虫下しに、
「あなた、あの玉はどうなるのでしょう、鼠にかじられ痛い思いをしているのじゃないかしら、心配だわ、こんなところにつれてくるのではありませんでした」
「さあて、子猫と鼠とどっちが強いかわからんじゃないか」
「まあ、頼りのないお返事ですこと、耳をかじられたら痛いでしょうね」
入道が戻ってきた。
「やっと竈に火がつきました、湯が沸くまで、茶をいれることができないということを知りましたわい、ちょっと待ってくださいよ」
「このあたりは静かだね、周りの人はどうかね」
虫下し先生が庭を見た。
「妾ばかり住んでいる」
「入道は誰のお妾なの」
虫下しの細君は蕎麦屋の娘と同じ発想だ。蕎麦屋の娘よりもっと天然そのものである。
「妾になるには頭が良くなければだめだ」
虫下し先生がいうと、「そうなの、入道はだめね、小学校では一番びりっけつ」
これまた驚く単語が飛び出した。虫下しが目をむいた。まだなれていない。
そのとき、床の間からからからと音が聞こえた。
三人がそちらのほうを向くと、穴の中から猫の耳がでてきた。
「あ、祝玉もどった」
実野が大声を上げると子猫が床の間に飛び出した。
「無事かえ、こっちにおいでおいで」
鼠色の子猫が実野さんの方へ歩いてきた。すると、その後ろに同じ色をした子鼠がついてきた。
「祝玉、鼠がいますよ、食べなさい」
子猫は脇に来て実野さんを見上げた。子鼠もその隣に来て実野を見上げた。
「ほら、玉、くっちまえ」
実野の言葉とは思えない。それを聞いた入道が思わず実野の顔を見て身震いをした。こわこわ。前にそーっとお茶をおいた。
「もう仲良くなりましたな、これなら、猫をいただいてもいいですな」
入道の顔は安堵の目をして、子猫と子鼠を見ている。
「猫と鼠が仲がいいなどというのは前代未聞、小説が書けそうですな」
虫下しが笑っている。
「今度は鼠のおっぽでしょうかな」
実野が床の間の茸に気がついた。黄色い柄の長い茸である。
「あそこの茸、先ほどはなかったのに今生えたようですわね」
鼠の糞から伸びている。
「こやつは、昨日天井から生えていた奴、ワシの歌をばかにしよった」
入道が説明をした。
「茸がしゃべるのですか」
「ような気がしたのですかな」といったとき、祝玉が一目散に床の間に駆け寄ると黄色い茸を食べた。子鼠もかけていった。
「あれ、祝玉、そんな黄毒茸食べたら死んでしまいますよ」
実野が玉をつかまえたのだが食べてしまったあとだ。
こうして黄色い茸は、黄毒茸という名をもらった。
黄毒茸を食べた子猫の玉は、実野の手から離れると、ひょいと床の間の穴に飛び込んだ。子鼠も後についた。また鼠の世界に遊びに行ったのだ。
「いずれ帰ってくるだろう」
入道は安堵して、またお茶をもってきた。
「ところで、八間さん、引っ越したばかりじゃ何ですから、しばらくしたら、ここで句会を開きませんかな、ちょっと鼠の匂いが強いが」
「おお、それがいい、鼠に行儀を教えておきますからな」
ということで、我々は虫下しの奥さんから「黄毒茸」という名をもらい、その上、やがて、八間から「鼠クソ茸」という迷惑な名前をもらうことになった。
さてこうして八間は、妾横丁に越してきて、子猫の玉の世話と蕎麦屋通いの生活が始まったのである。何せ掃除をしない、おかげで転がっている鼠の糞からいつでもどこでも、我々、茸は生えることができた。
ただ困ったことには、虫下しの引っ越し祝いの「祝玉」が我々に食らいついて食っちまう。百間は、「こら、食うでない」としかるのだが、祝玉はがぶっとかじってしまう。
ところが二月ほどすると、大人になった祝玉は、八間が買ってくるメザシの味に目覚め、隙を見るなり、入道の酒のつまみのメザシを失敬するようになった。そのころは子鼠も大きくなり、国際人となった祝玉は鼠国の友人にメザシを運ぶようになった。
おかげで我々黄毒茸はメザシを食した鼠の糞から生え、二晩の一生をつつがなくおくることができるようになった。その間、八間の行状はちくいち見ることができ、胞子に蓄えられた記憶は代々共有することができたのである。
祝玉はというと、メザシばかりではなく、八間の飲む酒の味を覚え、酔っぱらってメザシを土産にして屋根裏の鼠たちの巣をおとずれ、一眠りして下におりていくようになったのである。時々めんどくさくなった祝玉が、寝たまましょんべんをして、客間の天井に鼠のつくった世界地図を完成させてしまったのであった。
「祝玉、メザシを盗むな、鼠クソ茸を食え」と八間は言うのだが、玉は知らんぷり。
「すこしゃ仕事をしろ」という目で、八間を横目で見て、天井裏の鼠の友のところに行ってしまう毎日である。
さて、そのような日が続き、ある日、外にでて戻ってきた八間が客間兼居間の鼠の糞を拾い集め、床の間においてあるゴミ箱に捨てた。八間が掃除するとは何かがあるに違いない。おいらたちはゴミ箱の中に捨てられた鼠の糞から頭を出して、ひょろりと伸び上がると、ゴミ箱から少しばかり顔を出した。居間の様子が逐一観察することができる。
案の定、明くる日、来客があった。
「さ、さ、どうぞどうぞ」
八間入道が玄関から招き入れたのは、妾横町のお妾さんたちだ。梅、枇杷、無花果のお隣さんがなにやら持って入ってきた。
「この臭いは何でございましょう」
三人が立ち止まって顔を見合わせた。
八間が戸惑っていると、祝玉がのっそりと入ってきた。そのころは妾横町の大ボスになっていた。
「あ、この猫、先生のでしたの、うちの庭をのしのし歩いていますことよ」
梅が言うと、「あら、私の家の庭も」、「うちも」と、枇杷と無花果が言った。
「だからですわね、この猫ちゃん、うちの鼠をみんな追い出してくれたのよ」
「うちもよ」「うちもよ」
「鼠をみんな食べちゃうから、このお部屋、鼠の臭いがするのね、猫ちゃんありがとう、今度鰹節もってきましょうね」
三人が、祝玉の頭をなでた。祝玉もまんざらではなさそうで、ふす、っと大きな鼻息を出すと、フニャっとした目で妾さんたちを見た。お綺麗で。
「はあはあ、そういうことで」
本当は祝「玉が隣近所の鼠をひきつれて、住みやすい八間のうちに呼び込んだのだ。
「さて、それでは、はじめましょかの」
床の間の前に硯と筆が用意してある。
三人は、持ってきた紙をそれぞれ広げた。
「これにお願いします」
昨日、町にでたときに絵師の家から出てきた三人と八間がでくわしたのだ。
「おや、このようなところで」
と話しかけると、絵師に花の絵の手ほどきを受けているという。
そこで、描いた絵を見せられた八間が「これまたみごとな、軸にすれば床の間が華やぎますぞ、旦那方も喜ばれる、花の脇にちょこっと、句の一つも読まれて書けばなおのことすばらしい」など、おべんちゃらを言った。
「あら、でも書はからっきしでございます」
「ならば、句を作っていらっしゃれば、私が書いてしんぜますぞ」
そんなことを言ってしまったのだ。
「でも、句をつくるのも」
躊躇するお妾さんたちに、「私は差し上げた本の、探偵小説作家の先生たちと句会も開いております、形にならずとも、思う言葉を書き添えるだけでよいではありませんか、そこはお手伝いしますぞ」とそそのかした。
それならばと、旦那に喜ばれたいという一心から、描いた絵をもって八間の家を訪ねたというところである。
まずは梅さんが披露いたしました。
「梅も桜もみなあなた」
それを聞いた八間入道、こら大変と思った顔を隠すため、やたらとにこにこと「旦那さん思いですな、羨ましい」といって、少しばかり考えた。
「五七五になおしてみましょうかの、庭の梅、花も実もみな、包む人、これで梅さんのいいたいことは同じですな」
「ほんと、すてき」
「それじゃあたしのお願いします、枇杷の実を、むいて、あなたの手のひらに」
わ、こりゃもっと大変と思っても、「あ、五七五にはなってますな、また旦那ですか、そりゃ素直な気持ちで、うらやましい、そうですな、枇杷の実の、皮をむく手に、色うつり、などいかがですかな」
「いいわあ」
「わたしのは、無花果を、切れば、甘い汁がでる」
わああ、なんだこりゃと思いながら「その通りです、正しい情景ですな、ちょっと直しますぞ、無花果の、密の香りの、指の先、枇杷さんに少し近い句ですが、旦那さんが喜びますぞ」
「ええええ、すてき」
「さて、それじゃ、絵の脇に字を入れて差し上げましょうかの」
八間は、墨汁でいいだろうと、小筆を持ってきて、いつもの豪快な字ではなく、くずし字ですらすらと絵の脇に書き入れた。
この絵ならこんな句でもよかろう、思いながらしたためた割にはうまくかけた。
そこで床の間からがさっと言う音が聞こえた、みんなが振り向くと、ゴミ箱から黄色い茸がにょきにょきと延びてきて絵をのぞき込んだ。
そして「きゃはははは」と笑った。
我々茸とて、絵や句の知識は少なからず持っている。何千年もホモサピエンスとつきあっているわけだから、あたりまえである。茸の菌糸は脈々と知識を蓄積している。
驚いたのは三人のお妾さんたちである。床の間をみたら、鼠たちが整列して笑っていた。様に見えた。ほんとうは茸が笑ったのである。
今度はお妾さんたちが「きゃー」っと叫んで、我先に居間から飛び出た。
八間があわてて絵を持って玄関に追いかけ渡すことができた。
それ以来お妾さんたちにあっていない。
ある日、玉が捨てられていた紙屑を三つ拾ってきた。
八間が広げてみるとあの絵だった。
畳に落ちていた鼠の糞から鼠クソ茸が延びてきて、「ききき」と笑った。
吾輩ハ茸。八間はさぞ怒るだろうなと楽しみに見ていたらこんなに驚いたことはなかった。
八間がさめざめと泣いている。
どういうことだ。吾輩は傘をのばして広げた紙をのぞいてみた。
なるほど。絵の脇に八間の書いた字を、朱で誰かが直していた。三枚ともである。
だんなが直したのだろう。
まあいい薬だろう。これでしばらく掃除などしないだろうから鼠の糞だらけになり、吾輩の天下になるのだ。
祝玉は大きくなって、それは猫だましの得意な相撲取りみたいだ。他の雌猫たちの憧れの妾横丁の大親分。鼠もいい友達。八間は猫と鼠には大いに好かれていた。
第三章 玉だらけ
「困ったわね」
珍しいことに実野が書斎にはいってきた。探偵小説の構想を練っていた虫下しの目の前に、大きなねずみ色の猫をつきだした。猫のやつは両足をだらーんとさげ、虫下しを大きな目でみつめた。
「どうしたんだい」
「この猫、飼わなきゃいけなくなりましたの」
「見たことのない猫だな、ずいぶんきたない」
「大きくなった玉ですよ」
「こんな玉がいたっけか」
「覚えていらっしゃらないのですか、八間の新居のお祝いに持って行った祝玉ですよ」
「子猫だったよ」
「あなたなに言っているの、猫は6ヶ月で大人よ」
「それにしちゃあでかいな」
「八間に似たのでしょう」
「それで何でここにいるんだ」
「それがあなた、八間の使いの人がつれてきたのです、八間、また住むところを変えて、そこでは大家さんが猫嫌いなので飼えないそうですわ」
「それで。なぜ八間が来ない」
「急な引っ越しで忙しいということですわ」
「それでその汚い猫飼うのか」
「仕方ないでしょう、この祝玉もうちの猫にします」
「玉、後玉、又玉、それでこいつはなんと呼ぶんだ、もどされたんだ、祝玉じゃおかしくないか」
「そうですねえ、八間玉じゃいやでしょう」
「よごれ玉だな」
「それはかわいそう、大玉にしましょう、女中の玉に洗ってもらいます」
野実が大玉を下におろした。名前が変わった大玉は虫下しの足下にくると、見上げて「にゃごご」と鳴いた。
「こやつ、主人が誰だかわかっているようだ、頭がいいようだな」
虫下しが、頭をなでようとしたら、指をかぷっとかんだ。甘噛みのつもりだったようだが、虫下しがあわてて手を上に引いたので、大玉の歯がひっかかった。
「いて、噛みおった」
「違いますよ、甘噛みですよ、あなたが指を勝手に大玉の歯にひっかけたのですよ」
血はでていない。そうなのかと虫下しも納得してもう一度頭をなでた。大玉がごろごろとのどを鳴らした。
「いい、猫だ」
この家で初めて、虫下しを主人と認めた猫である。
「玉」
細君が女中を呼んだ。女中の玉が「ハーイ、奥様」と台所から飛んできた。
「この大玉を洗ってくださいな」
「へ」
女中の玉は牛のように虫下しの椅子の下にうずくまっている大きな灰色の猫を見た。
「これをですか」
持ち上げられるかどうか心配だったようだ。女中の玉は大玉のそばによると、顔をのぞいた。ひしゃげた大きな顔は煤にまみれたようにくすんでいる。灰色の髭がピンと長く延びていて、大きな口はすぐにでもかみつきそうである。
さて持ち上げようかと、両手をだすと、大玉は立ち上がって、女中の玉の手にこすりついた。こいつが餌をくれる奴だとぴんときたようだ。
「おいで」
女中の玉が呼ぶとあとについていった。女中の玉はよかったと胸をなで下ろし、大玉は、ゴマすって旨いものにありつこうと下心を込めて、にゃああごよと、鳴いた。
「風呂場にいらっしゃい、洗ってからなにかあげるから」
女中の玉は風呂場に大玉を誘い入れた。猫を洗うのは奥様に言われて、しょっちゅうやっているのでなれている。ただこの家にいるのは雌猫三匹でおとなしい。押す猫は初めてなのだが、あまり気にしていないようだ。
金盥に昨日の湯をくんだ。女中の玉は引っかかれるといやだと思い、猫の両脚と両手をそれぞれもって、背中から、じゃぼんと入れた。ところが大玉はおとなしくしている。玉は猫の手を離した。大玉は予想に反してたらいのぬるま湯の中でゆったりすると、女中の玉を大きな目で見て「にゃご」と鳴いた。洗ってもらいたいようだ。洗濯石鹸をつけ、ゴシゴシ洗った。水が真っ黒になって五回も取り替えなければならなかった。
洗い終わった玉は手ぬぐいで拭かれて、陽のあたっている縁側に出された。薄汚れていたのがただの灰色になった。
実野が見に来た。
「おお、大玉、きれいになったわね、今日からうちの猫、あとで他の猫に紹介しますよ、茶虎の玉と、白の後玉、それに三毛の又玉です、私の部屋で遊んでいますから、乾いたらいらっしゃい」
そう言って奥に入ってしまった。
その様子を庭の椿の下でずうっと吾輩は見ていた。
縁側から大玉が吾輩を見ている。
吾輩は白い茸であるが名はまだない。
大玉が縁側から庭に降り、のしのしと吾輩のそばによってきた。洗濯石鹸の匂いがプンと臭う。
いきなりがぶりと吾輩にかぶりつく、引っこ抜かれて縁側に運ばれた。
そこへ虫下しの奥さんの声がした。
「大玉やもう乾いたでしょ、奥の部屋においで、玉たちに紹介しますよ」
大玉は吾輩をくわえると奥の部屋に行った。
部屋の中には手鞠やら、腰紐やら、虫下しがアメリカ屋であつらえた帽子やらが転がっていて、玉、後玉、又玉が、転がしたり、じゃれたり、かみついたりして遊んでいた。
「ほら、これから一緒に暮らす大玉よ、仲良くしてくださいね」
細君が言ったので、大玉は吾輩をくわえて中にはいると猫たちのまん中においた。
この家の玉たちに比べて、大玉の大きいこと、倍もあろう大きな顔を、玉、後玉、又玉にむけて、「みやげだ」と一言言った。奥様に般彌にゃにゃにゃにゃ、としか聞こえなかったはずだ。
畳の上に突然現れた白い茸をみて、玉たちの目が輝き、集まってきた。
「これは何か知ってるか」
大玉が他の玉に聞くと、玉が「知らない、去年床の間にあったのは赤い茸で、赤毒茸と奥さんが言っていた」と答えた。
猫同士の話が分かるはずもない奥様は、白い茸を大玉が持ってきたのに気がつくと、
「白毒茸なんぞ、とってきてはだめでしょう」
そういって畳の上で横になっていた吾輩をつまみ上げると屑入れに放り込んだ。大玉は何だつまらん、という顔をして鏡台の前で丸くなった。他の玉も大きな玉のからだに自分たちのからだを押し付けて丸くなった。
「もう仲がよくなったのね、女中の玉をつれて、買い物にいきますから、おとなしく寝ていなさいね」
ふすまを閉めると部屋から出ていった。
奥さんが虫下しに「出かけて参ります、大玉はもうみんなと仲良しでございますよ」と声をかけた。
しばらくすると玄関が開き閉まる音がした。
奥さんの部屋では大玉がムックリと起きあがった。何かが始まる予感。
吾輩はゴミ箱から傘を出した。周りがよく見える。
玉、後玉、又玉も目を覚ますと大玉の周りに集まった。無言の三分間。
大玉は吾輩に目もくれずに奥さんの部屋のふすまを、前足でちょいちょいとあけると、今度は鼻を突き出して、とうとう押し広げてしまった。「ちょっくらでるぜ、どうだいあんたら」と小さな声で三匹の猫に声をかけた。人にはにゃにゃ,と小さな猫の声として聞こえただろう。三匹の玉は、おおこんな芸当があったね、と大玉を見直した風情、三匹とも大玉の後をついていった。
猫は音を立てない。虫下しの書斎の前を通っても気づくわけがない。しかし玄関は開いていないはずだ。吾輩はさすがに大玉も外には行けないだろうと一瞬思ったが、いや待てよと考えなおした。あの大玉の右腕の太さはただ者じゃない。八間入道の家で飼われているとき、隣近所の家の戸を押し開けていたに違いない。
音がしたのは玄関ではなかった。座敷の縁側の重いガラス戸が開く音がした。やっぱりやつがあけたのか。いつもは開けっ放しなのだが、虫下しを一人にするときには閉めていく。虫下しがいきなり出かけてしまうことがあるから不用心なのだ。しかし、一番はずれのところは鍵をかけない。それは奥方が玄関の鍵を持って出るのを時として、いやよく忘れるからだ。
猫たちは外に出て行ったと、庭に残っていた同胞の茸の胞子が部屋までただよってきて伝えてくれた。
何をしていたんだ、と胞子に聞いたところ、大玉が椿の木の下を掘って、大きなウンチをしているのを、三匹の玉が眺めているということだ。物好きな猫たちだと仲間に行ったところ、三匹の猫が見ていたのはウンチじゃなくて、しゃがんでも土の上にはみ出していた大きな大玉の玉を不思議そうに見ていたそうだ。そういえば、玉、後玉、又玉は雄の猫のけつを見たことがなかった。みな玉なのに玉なしである。
その後、大玉は三匹の雌猫を連れて塀の外に出て行ったということだ。
猫たちはほどからぬ時を経て戻ってきた。
開いたままのガラス戸の隙間から、まず大玉が飛び込んできて、三匹が続いた。大玉の口には二匹の赤鼠がくわえられていた。三匹の玉の口には一匹ずつ子鼠がくわえられていた。どうも鼠家族を連れて戻ってきたようだ。食うわけではないことは、妾横丁の茸たちが教えてくれた。
大玉が親鼠を廊下に下ろした。三匹の雌猫も子鼠をおろした。
大玉がガラス戸を閉めると、大玉は奥さんの部屋に向かった。その後を鼠家族、三匹の雌玉がつづいた。
細君の部屋にはいると、大玉が猫の家族に家の様子を見に行くように言うと、子鼠を残して父親と母親は虫下しの家を調べに行った。まず天井に駆け上り、小さな穴を前歯であけると、ちょ路利と天井裏にはいた。
父ちゃんと母ちゃんが天井に穴をあけるのと眺めていた子鼠に、大玉が、
「よくみとけよ」と言った。
三匹の雌猫も、すごいわねえ、と感嘆の声を上げた。
親鼠が行ってしまうと三匹の子鼠は玉、あと玉、また玉と走り回って遊んだ。
やがて、家中をのぞいてきた親鼠が戻ると、子鼠は父親から、家の様子を聞いた。
ここの主人の書斎の天井はとても住むにはいいところだそうだ。だが、あの女中の玉がいる限りは越してこれないということだった。
また三匹の子鼠は三匹の雌玉と走り回ったり、じゃれあったりはじめた。
わあわあやっていると、廊下で物音がした。
大玉と雌猫たちはあわててそこここで丸くなって寝たふりをした。鼠たちは猫のおなかに潜り込んだ。
部屋の戸が少しあくと虫下しがのぞきこんだ。
「おお、仲良く寝とるか」と四匹の猫を見ると、台所に水を飲みに行った。きっと原稿が進まなくて机から離れたのだろう。
虫下しが自分の書斎に戻ると大玉がむっくりおきあがった。腹の下にいた親鼠もちょろりとでてきた。他の玉たちも立ち上がり、子鼠が下からでてきた。
大玉が細君の部屋の戸をあけた。
「鼠どんいくぞー」と鼠たちを従えて台所に行った。三匹のねこもついていく。
土間の入口脇に生えていた茸からの連絡がはいった。土間の棚の下にジャガイモの入った袋がおいてある。鼠は早速袋にに潜り込んだ。猫たちは鼠がジャガイモをかじっている袋の中を覗き込んでいる。
「じゃがいもは鼠たちの好物だ」
大玉が他の猫に説明している。
食べたいだけ食べた鼠は袋から出てくると、土間の壁際で糞をした。糞からは明日には我々の仲間が生えてくるに違いない。
鼠たちはそれからひとしきり猫と遊ぶと、土間から外に帰って行った。
「あなた帰りました、デパルトメントにいきました、ほら、スカートとブラウス、買ってしまいました」
「あなたも洋装をする気になりましたか」
「はい、これも買いました」
奥方はズロースを見せた。
「それにあなたにも」
「真っ赤なパンツをだした」
「なんです、赤など、はずかしい」
「あら、泳ぐとき、赤ふんだと、おっしゃったじゃないですか」
「あれは、学生の時の規則です、今は海水パンツというものを売っています」
「あら、川は海じゃないから海水パンツではおかしいでしょう、ふんどしです」
細君は赤いパンツを虫下しに渡すと自分の部屋に行った。
「あら、なにやら臭いですね、なんでしょう」
猫たちは丸くなって寝ている。
「玉たちおとなしくしていたようね」
奥方は猫たちの前で着物を脱ぐと、まずズロースをはいた。大玉はちょっと目を開けたがすぐ閉じた。見たくない。吾輩は屑箱から顔をだして眺めていた。もうすぐしおれなければならない。見納めだ。と言っても、胞子の中にはこの情報を詰め込んでおこう。
シャツを着てブラウスを着る。スカートをはいた。これから流行ると言われて、短めのスカートを買ったのだ。鏡の前で、「なんだか心許ないわね」と下を見た。自分の脚が見える。大根みたいだ。吾輩はすべてを見てしまったが、和服というのは女性にとって中身を隠すすばらしい着物だと改めて思った。
奥方は鏡に映して悟ったようだ、ブラウスやスカアトを脱いで、ズロースまで脱いで、普段着の和服を着た。
女中の玉を呼んだ。
「なんでしょう」
「おまえこれを着てみないかい」
「え、今日買った奥様のお洋服ですか」
「いいから着てみなさい」
「はい」
もんぺを脱いでスカートをはいた。ズロースはもうはいていた。上衣をぬいでブラウスを着た。
背の高さは奥様と同じほど、15歳だけど胸は大きく、脚は程良く太く、何せ秋田だから色が白い。吾輩はすてられたゴミ箱の中から傘を出して見とれてしまった。これこそいい見納めである。女中の玉に感謝。
軍配はとうぜん女中の玉に上げざるをえない。
「玉にそれをあげます、お客様が見えるときにはその格好をしなさい」
玉は驚いて「だけんど、こんな高いもの」
「いいんです、私にはもっと上等の服を買うべきだったと思ったのです」
自分のことがよくわかっっている。女中の玉はまた作業着に着替えると、ブラウスとスカートをきれいにおり畳んだ。
「それより奥様、台所に鼠がでたようです、ジャガイモがいくつかかじられています」
「四匹も猫がいるのに、どうしたのでしょう、そうか、寝ていたものね」
玉たちは丸くなってぐっすり寝ていた、ような振りをしていた。時々耳をぴくぴく動かす。おっぽだけがパタンパタンと動く。
鼠取りをかけておいてちょうだい。
「はい、中になにをおいておきましょう」
「ジャガイモはもったいないし、おや、ほら、ここに白い茸がある、白毒茸だけど、鼠は毒かどうか判りゃしないでしょ、頭のいい人間ですらわからないのだから」
なんと頭の悪い人間だ、いや人間は頭が悪い。と思っていたところに、女中の玉の手が吾輩をつかんでゴミ箱からとりだすと台所に連れて行かれた。
こうしてしなびはじめた吾輩は鼠取りの中に閉じ込められたのである。
虫下しと奥方がぐっすり寝ている、その夜のこと。
吾輩が台所の棚の下におかれた鼠取りの中で、退屈しのぎに歌謡曲「黒いくさびら」を口ずさんでいると、土間の戸が少し開けられ、灰色の猫の手が見えた。とたんに鼠が八匹なだれ込んだ。四匹の猫たちも入ってきた。猫と鼠のご挨拶。
大玉がそこにあるのは鼠取りだから気をつけろと言っている。鼠たちは、はい、と返事をして、ジャガイモの入っているヅタブクロをかじって穴を開けた。
「ゆっくり食いな」
大玉はジャガイモを取り出し、他の猫たちに配った。猫たちはジャガイモを喰らうわけではない。三匹の雌猫はジャガイモを転がして遊び始めた。
鼠たちはジャガイモを夢中になってかじっている。猫たちがジャガイモを突き飛ばすと、鼠がそばにきた奴を一かじりしてけっ飛ばす。
「ジャガイモはおいしいのかしら」
玉が鼠の娘にたずねると、「ええ、ヒゲがおちそう」とのこと。
「みなたべてみるかえ」と他の玉に声をかける。このしゃべり方、実野さんの天然がうつっているとみえて、後玉も又玉も「食べてみますかえ」などと言って、ジャガイモを少しばかりかじった。
「うーん、ふかせば美味しいかもねえ、生はからだによくないかもしれないわね」
「私は、大丈夫よ、おいしいわ」とかじりだしたのは一番若い又玉である。だがかじっただけで、飲み込まないから周りにジャガイモのチップができた。
後玉もすこしばかりかじった。だがひとかじりでやめてしまった。
吾輩は鼠取りの中からその様子を見ていたのだが、どうも体の調子がよくなくなってきた。乾燥してきたようだ。そろそろ寿命だろう、ここで胞子をとばしておこう。
白い胞子を台所にもうもうと撒いてやった。ほらとんでいけ、ジャガイモの袋の中にも、まな板にもみんなくっつく。台所というのは菌糸になるのにいい湿度だ。
大玉が吾輩に気がついた。
「白い茸が胞子をとばしておるな、どうしてネズミ捕りの中などにいるんだ」
鼠のこどもが、「そりゃあ、おれたちに食わせるものさ、そんな食うわきゃないじゃないか」とのたまった。
「そりゃそうだ、だがなぜ茸どんだ、鼠は茸を好むのか」
「家の奥方がやったんだ、鼠が俺を食べたくて仕掛けに引っかかると思ったようだ、それに毒茸だと好都合だと思ったらしいぜ」
俺は少しばかり力を振り絞って話した。
「お内儀のやりそうなこった、それでなぜお宅は家の中に生えたんだ」
「おぼえてないかい、おまえさんが庭に生えていた吾輩をがぶりとやると、家に持って入ったじゃないか、洗濯石鹸の匂いをぷんぷんさせて」
「あ、そうだそんなことあった、石鹸で洗われるなんてことされたことがなくてな、石鹸の匂いに当てられて、お前さんにくらいついてしまった、すまん庭に返してやろうか、ふっくらしていたのが痩せたな」
「いいや、もういい、寿命だからな、今胞子をだした、この家中に白い茸が生える、みんな吾輩だ、お前さんのおかげだよ」
「そういうもんか、だが、そんな中でくたばるのは忍びない、少なくともどこかやわらかいところに横たえてやろう」
「おい、鼠の子どもら、この中の茸の旦那を取り出すのはどうしたらいいかな」
「そりゃ簡単さ、茸に触れればちんと蓋が降りる仕掛けだから、大きなジャガイモを入口に転がしておけば、蓋が落ちたときにはさまって開いたままだ、そうしたら茸どんをはずしてあげるよ」
「おお、頭がいいの、大きなジャガイモは俺が運んでやろう」
ということで、大玉がジャガイモの大玉を持ってネズミ捕りの入り口におき、鼠たちがネズミ捕りに体当たりをしてふたを落した。蓋がジャガイモをはさんで半開きになった。「そーれ」と掛け声とともに子鼠たちがなだれこみ、白い茸をすくいだした。
「おお、ありがたや、ではジャガイモの袋の中にいれておくれや」
鼠たちがジャガイモの袋に白い茸を運んでくれた。
「これから芋を甘くしてやるからな」
大玉が「あんたさんはどうなるんだね」と聞くものだから、吾輩は茸の輪廻をといてやった。
「胞子が菌糸をのばして、茸になって顔をだすのだがな、胞子にも菌糸にも吾輩の経験すべてが記憶として入っておってな、茸が生まれてから今までの世界中の記憶が詰まっておる、ともかく虫下しの家に菌糸がはびこり、たくさんの吾輩がでてくるのだよ」
「それで、どうやってジャガイモを甘くするのかね」
「吾輩がバラバラになり、アミノ酸となって、ジャガイモをおおうのだよ、うまみが増える、あしたの夜をおたのしみじゃな」
吾輩はそういってジャガイモの中に身をうずめた。
「それじゃ、俺たちも終わりにするか、鼠たち、明日も戸を少し開けてやるからおいで」
鼠たちはバイバイと尾っぽを振って出ていった。
「それじゃ寝ようかね」
大玉の後を三匹の猫が後をついていく。大玉が奥方の部屋の戸をそうっと開けるとみな中に入り、大玉が後を閉めて、奥方の布団の裾で丸くなった。
朝早く、女中の玉が「大変です、奥様、泥棒が入りました」と台所から大声を上げた。
奥様と言ったのにでてきたのは虫下しである。
「どうしたんだ、玉」
虫下しはパジャマのまま台所に走ってきた。
「あ、旦那様、見てください、ジャガイモが袋からごろごろと飛び出しています、これは泥棒です」
「玉、ほら、ジャガイモがかじられているじゃないか、鼠がでたんだよ」
「あ、泥棒は鼠です」
「他にはなにもとられていないのだろう」
「鼠取りの中の茸がとられました」
虫下しが鼠取りを見ると、「こりゃ、ジャガイモでふたが閉まらなかったようだな、ふむふむ」
さすがに探偵小説作家である。
「茸を盗まれたのだな、いらんじゃろ」
「はい」
「それなら、朝食の用意をしてくださいよ、私はもう一度寝てきますからね」
「はい、すみません」
玉があわてて、竈に火をおこす準備を始めた。
虫下しが寝室に戻ると、こんどは奥方がおきてきた。
「なんです、玉」
「鼠がでて、茸を持って行ってしまいました、ジャガイモもかじられました」
「おいしい茸だったのかもしれませんね、今度生えたら食べてみましょう」
そう言ってまた部屋にもどっていった。
その日の真夜中のことである。月明かりに照らされて、台所の外でなにやらうごめいている。大玉が奥様の部屋からそうっと出てきた。他の玉は寝ている。台所の土間に降りると土間の戸に足を引っかけた。
戸が開くと外で行列をしていた子鼠たちがぞろぞろと入ってきた。
「今夜はまたたくさんだな」
「うん、おいしくなったジャガイモの話をしたらみんな来たいって言うんだ」
「いいよ、だけど、少し残しときなよ、今朝のおみおつけはジャガイモとタマネギだから、ジャガイモなくなっちまうと女中の玉がかわいそうだからな」
「どうして」
「虫下しの奥さんにしかられちゃうのさ」
「そうか、それじゃみんなに言っとくよ」
子鼠たちは麻の袋からジャガイモを取りだした。
今日は鼠取りが二つ置いてある。一つには人参が一つには大根がはいっている。
「紅白にしたってだめだよね」
子鼠がみんなで鼠取りをけっ飛ばした。とたんに蓋がしまってもう使えない。
「これうまいな」
子鼠がジャガイモをかじりはじめた。
「昨日の白い茸がおいしくしてくれたんだね」
「そうだよ、茸はうそを言わない」
大玉の言ったことにまわりから、「うんうん」と小さいな声が聞こえた。
なんだと周りを見たら、白いぽっちが壁や柱、天井、至る所に顔を出している。見ているとだんだん大きくなっていく。
大玉は虫下しの家を歩いてみた。白くて小さな茸が玄関の方まで顔を出し始めている。胞子がずいぶん飛んだようだ。やけに成長がはやいが、いかがしたのかと、大玉が小さな茸に聞いてみると「鼠の匂いが我々の成長ホルモンになったようだ」と答えた。
大玉はそんなもんかと台所に戻ると玉が起きてきて顔を出した。
大玉は「おお、おまえ一匹か」と玉の背中に乗っかった。玉が声を上げそうになったので、大玉がシーっと言った。
ことが終わったところに、後玉がやってきた。
大玉は「よお、ちょっと顔かしてくれ」と後玉を玄関につれていくと、また乗っかった。おわると奥さんの部屋にもどって、一匹で寝ていた又玉をこづいておこし、乗っかった。三匹の玉は何が起こったのだかわからずぼーっとしていた。奥様とおなじだ。
大玉が台所に戻ると、子鼠たちが「おいしかった」と帰り支度をしていた。
「おじさん何していた」
「ちょっと食事だ」
「おいしかった」
「まあまあだ」
「それじゃ、また、ばいばい」
子鼠が外に出て行ったので戸を閉めると、大玉はあくびをしながら奥さんの部屋に帰り、奥さんの枕元で丸くなりいびきをかきはじめた。
「うるさ、虫下し」
寝ている奥さんが大玉の頭をたたいた。大玉のいびきが一瞬止まったが、また響き渡った。だが奥さんは目を覚まさなかった。虫下しを夢の中でいびって楽しんでいたのだ。
朝になると白い小さな茸の子供が家の中にはびこっていた。
女中の玉は竈でご飯を炊き、味噌汁を作っている。
子鼠たちはジャガイモを食い散らかさずにきれいに食べたので、玉は袋の中のジャガイモが少ないとは思ったが、食われたことには気がつかなかった。
いつもの時間に虫下しと奥さんが起きてきた。
お膳には、海苔と卵焼き、それにおつけがすでにそろえてあった。
「おまえ今日は一人かい」
細君は虫下しをちらりと見ると、
「あなたと二人じゃありませんか」
と、とんちんかんな返事をした。
「いや、いつも猫たちがぞろぞろ、おまえの後をついてお膳を取り囲むじゃないか」
「おや、そうですね、そういえばまだ寝てましたね」
「四匹ともか、珍しいな、夜遊びでもしたか」
「そんなことありませんよ、大玉なんかいびきかいてました」
玉がお櫃を運んできてご飯をよそった。
「奥様、鼠取り閉まっていましたが、中にはなにもかかっておりませんでした」
「そうかい、地震でもあったのかな、そのままおいておきなさい」
虫下しが「今日のジャガイモはうまい」
と、おつけを飲んだ。
細君も一口飲んで、ジャガイモを口にいれると、
「玉、おいしく作れるようになりましたね」とほめた。
「ありがとうございます」
女中の玉も最近は標準語に近くなった。
玉が台所にさがるとき、廊下の脇に白い茸が延びているのに気がついた。庭に生えていたのと同じようだ。触っていいものかどうか躊躇して、二人が食事をしているところにもどり、廊下に白い茸が生えていることを伝えた。
そういわれて、虫下しも箸を止めた。自分の目の前の畳に白いものが見えたからだ。床の間を見ると小さな白い茸が三本生えている。
「あそこにも生えてるな、こりゃどうしたことか」
「白毒茸ですね、玉あとで掃除しておくれ、胞子が飛んだのでしょう」
「はい、奥様」
奥方が珍しく科学的なことを口走った。
玉は他の部屋にいってみた。座敷から虫下しの書斎まで白い茸が生えていた。
吾輩はこの家の全てをいっぺんに見ることができるようになっていたのだ。泥棒だって入れないぞ。
奥方の部屋では四匹の猫がまだ丸くなっていた。
女中の玉が布団をあげに入ってきた。
「あんれ、まんだ猫っこさ、寝てるだべさ、ほれ、おきれ」
一人だと秋田丸出しだ。
玉が思い切り布団をはがした。大玉からみんなごろごろと畳の上にころがった。
乱暴な娘だ。大玉がぶすーっとした顔で女中の玉を見た。女中の玉は自分のほうを向いた大玉の頭を思い切り引っぱたいた。これから家中を掃除して茸を取ってしまわなければならない。虫の居所が悪いようだ。
大玉はこういう女子の扱いにはたけていた。なにしろ妾横丁の家々の妾さんに美味くかわいがられてきた猫だ。
ふにゃ、といって女中の玉にこすりつき見上げた。
女中の玉ははっとして、「ごめんな、あとでにぼしやっから」と猫のために座布団をもってきた。大玉が真ん中に座ると、三匹の猫が寄り添った。そのまま四匹は丸くなってしまった。
「ようけ寝ること」
女中の玉は布団を押入に押し込むと、生えていた白い茸を引っこ抜き、ゴミ箱に入れた。奥様の部屋から出て、虫下しの部屋にいって机の上をきれいにふくと茸を採り、座敷からトイレ、風呂場、厨房、掃除のあとに全ての茸をとった。
「奥様、白い茸はどうしたらいいでしょう」
まだ食べていた奥様に聞きに行った。虫下しはもう部屋に下がった。
「捨ててしまいなさい」
袋いっぱいにとれた茸をゴミ箱に捨てた。
ところが吾輩はまだまだこれから生えてくるのだ。茸の生命力を思い知らせてやる。
そのようなことがあり、三匹の雌玉は寝てばかりいるようになった。
一方、大玉はと言うと、昼間は家でごろごろしていることもあったが、夜になると、出歩くことが多くなり朝方になり家に帰ってきた。
「奥様、猫たちがご飯をたくさん食べるので、鰹節がすぐなくなります」
「よいですよ、鰹節くらい、いくらでも買ってらっしゃい」
奥様はそういって女中の玉を乾物屋に走らせた。
しばらくすると、玉も後玉も又玉もみなころころと太ってかわいくなった。と奥様は満足していた。大玉にいたっては他の玉の倍どころではないほどの大きな猫になってしまった。
「大玉は八間入道の血を引いてるのね、大きくなって、あやつにそっくりじゃないの」
奥様はちょっとばかりじゃけんに扱う。だがなぜか虫下しはかわいがった。大玉がすぐこすりつくからだ。
吾輩は、今、虫下しの部屋に三つ、奥様の部屋に二つ、あと玄関、廊下、座敷、居間、台所に一つ小さく目立たないように生えている。だから虫下しの家のこと今でも見ている。
大玉の奴が、時たま書斎にはいり、原稿を書いている机の上に飛び乗って、虫下しの顔にこすりついたりする。明らかにゴマをすっているのだ。虫下しはよくなついたいい猫だと、のどの下をさすったりする。それをすると調子がのって原稿が進むようだ。そうなると女中の玉に鰹節をご飯にかけて大玉にやるように命じたりする。大玉の思う壺だ。
相変わらず大玉の指導のもとに、子鼠たちが夜中に台所に来て満腹して帰る。そしてとうとう、子鼠は大人になり、子供を作り、その子鼠がみんな一緒になって、虫下しの家の台所に食事に来るようになった。
さすがの女中の玉もおかしいと気づき、台所の裏口に南京錠をつけてくれと、奥方に懇願した。
大工が来て、台所の戸に南京錠がついたが、大玉が戸を片手でごしごしやると、少し間があいた、鼠たちは戸の下の方をかじって通れるほど隙間を広げた。鼠たちが食べ終わり、外にでると、大玉がぴちっと戸を閉めた。隙間がめだたなくなり、戸の下にちょっとかじった傷が見えるくらいで、女中の玉は気付くこともなかった。
あれから二ヶ月。玉、後玉、又玉のお腹がぽっこりとたれさがった。
「玉、このごろ玉たちがやけに太りましたね、餌のやりすぎではありませんか」
奥方が女中に苦言を呈した。
「へえ、奥様、注意します」
女中の玉はまだまだ子どもだが、実家で猫を飼っていたこともあり、妊娠のことをよく知っていた。
「だんが、もしかすんと、子供が生まれんじゃなかろかな」と、自分の母親が言っていたことを思い出して思いっきり秋田弁で言った。ところが奥様は、
「うちの猫はそんなにふしだらじゃないわよ、ことばをつつしみなさい」
としかられてしまったのである。
しかししかしだ。次の日の朝早く三匹の玉は、奥さんの部屋で子供を産み落とした。
吾輩は柱の脇から生えておったのだが、玉と後玉と又玉に、頑張れや、ほれもう少し、気張れ、気張れと声をかけ続けてやった。玉は三匹、後玉は二匹、又玉は一匹の子供を産んだ。おなかが大きくなっていたわりには子どもの数が少ない。初産の時には往々にして出産数は少ないそうだ。
ちうちう鳴いて母猫のおっぱいを吸っている。
そのころ大玉は虫下しの書斎で丸くなっていた。
奥さんは「なんですそうぞうしい」と、目を覚ますと、部屋の隅の座布団の上で、玉たちが子猫に乳をやっている。
「あえれええ、だれか」
奥方がかなきり声を上げた。女中の玉と、虫下しがあわててやってきた。
「実野どうした」
障子を開けると、奥方が呆然とたちすくしていた。見ると猫たちが赤子に乳をやっている。
「ありゃ、いつのまに」
「産婆さんを呼んでください」
実野が慌てふためいている。
「生まれちまったんだから、産婆はいらんだろう」
「それじゃお医者様を」
「猫医者呼んでも仕方なかろう、玉、ミルクをやりなさい」
虫下しはさすがに動物のことをしっている。疲れた母猫にはミルクが一番だ。
「すぐ買ってきます」
牛乳屋は早くからやっている、配達にもくるが、一本じゃ足りなしと、女中の玉は思ったのだ。
奥方は落ち着くと、今度は猫のそばに行って「かわいい」「かわいい」「かわいい」の連発である。
「ほらあばばばば」
人間の赤ん坊のようにあやしている。
「まだ目も見えんし、そんなことしてもだめですよ」
虫下しに言われて、今度は数をかぞえた。
「六つもいますよ」
どうなるのやらと、虫下しが思案にくれていると、今度は怒り出した。
「この猫たちはいったいどこでなにをしているのでしょう、いったい誰が腹ませたのです」
そういって、虫下しを見た。
「あなたじゃないですよね」
「なにをいっとるんだ、この玉たちが外にでなかったとしたら、相手が入ってきたとしか考えられんだろう」
探偵小説作家じゃなくともそのくらいのことは気がつくだろうに。吾輩この先どうなるのか楽しみになってきた。
「どこの猫か責任をとってもらいましょう」
そこへ、大玉が何事かと顔をだした。三匹の玉が、乳をやりながら顔を上げ、大玉を見た。
ぎょっとした大玉はあわてて戻ろうとした。
「大玉どこ行くの、おまえなら、玉たちの相手を知ってるでしょう」
奥方がそう言いながら、大玉の後ろ姿を見てはっとした。そこにも玉がある。
「あなた大玉は雄ですか」
「雄だよ、見ればわかるだろ」
「でも、一緒に住んでる猫にそんなことしませんわよね」
「大玉にきいてごらん」
奥さんは後を追いかけると、大玉を捕まえた。かかえて、目の前に大玉の顔をもってくると、
「あの子猫はおまえの子じゃないよね」とにらみつけた。
「にゃい」
大玉が返事をすると「あなた違うそうですよ」
大玉を放した。とたんに、大玉は走り出し、虫下しの書斎に逃げこんだ。
「なにを言っているのです、家にいる雄は大玉しかいませんよ」
「まったく、いつのまに、しかも、三匹とも手込めにするなど、とんでもない、八間に文句を言いましょう、あの人の教育がいけなかったのでしょう」
「ともかく、六匹の子猫があなたの部屋にいます、一月もすればちょろちょろ歩き回るのですよ」
「うれっしー」
今怒っていた奥様はおおはしゃぎ。
そこへ女中の玉が牛乳を三本かかえて戻ってきた。奥さんはひったくるようにとると、「さあさ」と皿に入れた。親猫たちは、子猫をおいて立ち上がると、牛乳を飲んだ。
あっという間に一月が過ぎた。奥方は子猫じゃ子猫ジャと、毎日まいにちおおはしゃぎ、
子猫たちの目もちょいと開いて、外がわかるようになった。そうなったら子猫の本性、家の中を駆け回り、庭に降りて大はしゃぎ。
名前を聞いて驚くなかれ、やっぱりみんな玉である。ただ今度は色分けがされた。真っ白の猫は白玉、黒いのは黒玉、抹茶色は茶玉、白と黒は白黒玉、三毛は三毛玉、虎は茶虎玉と相成った次第である。
奥様は子猫たちをだきあげ、「大玉のようにねずみ色はいませんね、本当に大玉の子なのでしょうか」と可愛がり、顔の隅を引っかかれても喜んでいる。
今までいた玉、後玉、それに又玉も、大事にされているのは言うまでもない。
その六匹の父親である大玉の運命が奥様によって下された。
女中の玉に、「大玉を八間にかえしてらっしゃい、もし引き取らなかったら、捨てておいで」と申し付けた。
さて、女中の玉がどうしたらいいかと考えて、やはり虫下し先生に相談するのがよかろうと判断した。懸命なお女中である。
女中の玉は虫下し先生に、いきなりこんな風に尋ねた。
「先生はどうして、お妾さんをつくらないのですか」
鈍感な虫下しは「玉は妾の意味をしっているのかい」と聞き直した。
「作家の先生はみなお持ちのお道具のようなものと、申しておりました」
「だれが」
「八間先生が、虫下し先生も妾横丁に家でも借りればよいものを、とおっしゃっていました」
確かにうちに来ていたときにそんなことを言っていた気がする。
「何でそのような話をしたのだい」
「奥様に、大玉を八間先生に帰すか、捨ててこいと言われました、それでいいですか」
遠まわしに本題に入るなど、その辺の人にできる業ではない。女中の玉は誰にそんな方法を教わったのだろう。吾輩は虫下しの書斎の隅に生えた茸。ちょっと驚いている。
「ふむ、それはよかない」
虫下しは、それは困る、大玉がいると原稿がはかどる、とそう思った。かわいそうでもある、八間のところは無理だから、女中の玉が言うようにどこかに囲わねばならないかもしれない。
「八間先生が借りていらっしゃった家がまだ空き家と言うことをいってたで、そこに大玉を囲こったらどうだべ」
この十六歳の娘はなかなかの才女だと虫下しも驚いた。
「よし、わしも一緒に八間のところにいって、八間にもう一度、あの家を借りるように言おう、そこに住まわせる。わしも家賃を半分だして、ときどきその家で小説を書くことにする」
と虫下しの気持ちは固まり、大玉の運命は明るい光がみえてきた。
虫下しは八間にそのことを話し、大家に会いに行ったのである。
喜んだのは借り手ができた大家さんだけではない、大玉と仲のよかった妾横丁の鼠たちであった。
こうして、妾横丁の八間が借りていた家は大玉が住むことになった
虫下しは週に何日か小説を書きに大玉の家にいく。八間も餌をもってやってくる。鼠のにおいの大好きな八間は大喜びなのだ。女中の玉も掃除にしにいく。気分転換だとよろこんでいる。
こうして、大玉は虫下しの囲い猫になったのである。
第四章 妾横丁の大玉
鼠たちの匂いがぷんぷんする。
リンゴ箱に入れられた猫の大玉は、リヤカーに乗せられ、運び屋に引かれて妾横丁の柿の木のある家にもどされてきた。
虫下しと八間は先について雨戸を全部開け、家の中に風を入れていた。
「くさいぞ」
虫下しが言うと、八間は「鼠がたんとおるからな、大玉は鼠と仲がよくてのう」と、玄関先に置かれていった、りんご箱のふたを開けた。
大王が顔を出して、周りをみまわした。いきなりとろんとした目がきらんと輝き、箱からずどんと飛び出した。ここでおおきくなったのだ。
大玉は懐かしさあまり、たたみのうえでごろごろころがり、床の間の柱にこすりついた。祝玉とよばれているころのことだ。
「やけに喜んでいるじゃないか」
虫下しが驚いていると八間がうなずいた。
「そりゃのう、鼠の香りは大玉にはマタタビより良く効くんじゃ、今夜は鼠とかけっくらじゃ」
「それじゃ鼠が減らんな」
「ああ、隣近所の鼠はそこいらの家で食事をするとな、夜はうちに集まって大玉と遊んでおってな、周りからは鼠が減ったと喜ばれておる」
「なにしてあそぶ」
大玉が子鼠を前足で転がすんだ。子鼠はおおよろこびだ。
「鼠くわんのか」
「食われちゃこまる、わしも鼠には恩がある。鼠八百の図というのを蔦屋から頼まれておってな、鼠を見て描いておったんだ、それでな、それができあがって引っ越したわけだ」
「家主が猫を嫌っていたのではないのか」
「実は、蔦屋が引っ越せともうした、今度は女百態だそうだ」
「字を書かずに、絵ばっかり描いているな」
「それでな、女百態はことわったんだがな、ぜひやってくれということで、まあ金につられてやることにした」
「だけど、この家でもかけるだろう」
「いやな、手本にする女が通ってくるんじゃよ、蔦屋が申すには、この家は鼠の糞の匂いが強くて女子(おなご)が来てくれぬ、ということでな、新しい家は蔦屋が借りてくれたんじゃ」
「それで、大玉が追い出されたのか」
「そういうことだ」
大玉はかって知ったるもとわが家、家の中をうろつき回った。灰色の大きな体を揺らしながら、大きな目をむきだして、髭をふるわせひくひくさせている。
ついつい柱に向かって片足をあげようとしたので、八間が頭をぴしゃりとたたいた。
虫下しも部屋を見て回った。鼠の糞が落ちている。
こりゃあ、部屋を掃除させなきゃならんな、一通り部屋を見た虫下しは、厠の近くの四畳半を自分の仕事場にすることにした。
「ところで虫下し、猫の餌はわしがもつが、買いに行ってやる時間がとれん、なんとかならんかな」
「俺が週に三日ほどくるから、そのときもってきてやろう、俺がこないときは女中の玉にこさせて、ついでに家と庭の掃除をしてもらう」
「そりゃあいい、玉さんが忙しくなるがいいのかな」
「国への仕送りをふやしてやるさ」
「秋田だったな」
「ああ、あの玉は、偶然風呂場を見てしまったが、色は白いしなかなかの玉だ」
「そうだと思ったよ、一枚ぬがしゃ相当だと踏んだ」
「八間が絵を描くときによいかもしれん」
「それじゃ、蔦屋に言ってみる」
「だが、実野がいいというかどうか、うちの実野が親代わりとか言っておるからな」
「わしの家の掃除にきてもうらうのならいいだろう」
「そうだな」
「周りの家にはなじみの妾さんたちもいるからあいさつ回りはわしがやっとくよ」
ということで、周りへの挨拶は八間に任せた。
その日はもってきた猫の餌をおくと虫下しも八間も家に戻った。
吾輩ハ鼠の糞から生えた茸である。八間が住む前からこの家に生えておる。いままで八間と大玉がこの家で何をしていたのかも全て知っておる。今度は虫下しが加わって、こいつらがなにをするのか大いに楽しみにしているわけである。
家にもどった虫下しは八間とのやりとりを実野に話すと、
「あーら、大玉の世話と掃除ならかまわないことよ、玉さえいいというのなら、あなた給金をはずんでやってくださるのでしょ」
細君は自分の懐が痛まないのならかまわないと思っているようだ。
「ああ、そうかい、だけど、おまえが追い出したのだから、少しはだしておくれ」
細君は少しばかり考えていたが、言われてみれば元はうちの猫だったわけで、そうじゃけんにもできない。
「それじゃ、あなた、餌代はうちのほうからだしましょう」
それを聞いた虫下しはほくそ笑んだ、「そうかい、そうしてくれるとたすかるなあ」とか言って、「おまえは猫にすかれるわけえだなあ」などと、おべんちゃらもくわえた。
餌代は八間がもつといっているが、それはだまっていたのだ。
虫下しは別宅で小説書きができるのを、ちょっぴり新鮮に感じていたのだが、別宅の借賃を払わなければいけないのは痛い。餌代はそちらに回せる。
今「犯人の探偵」に連載している毒茸の話「茸十夜」の原稿料はすべて借家の費用に消えていく。新しい探偵小説を書いてやると、虫下しとしては少しばかり珍しく意気込んでいる。
「お妾さんはだめですよ」
実野がぴしゃりといった。だがもてっこないとも思っていた。
女中の玉をよんだ。
「これから、妾横丁の旦那様の家に猫の世話と掃除にいってくれないかしら、別払いにするから」
女中の玉は、
「へ、だけど、このお屋敷の猫は九匹もおります、その世話にかなりの時間がいるんでございますよ」
「うちの猫の世話は私も手伝います」
実野はいつもそういうのだが、結局女中の玉にまかせてしまう。
女中の玉がもじもじしているのを見て、「給金そのものもあげてやるよ」と虫下しが言った
「へえ、そこまでおっしゃるなら、行ってもええですが」
女中の玉の本心は、家の中で働くより外にでたくてしょうがないのだ。奥様の買い物についていくのがいままでの唯一の楽しみだった。
「毎日いくのでしょうか」
「いや、わしが週に三日ほど、朝行くが、行かない日に掃除と大玉に餌やりをたのみたい、いずれ入道の家の掃除も頼みたい」
「あんりゃ、結構てえへんですな」
そういいながらも、最後にははいはいと返事をかえした。
さて、吾輩は虫下しの別宅で、一つ落ちていた鼠の糞の中で菌糸をのばした。菌糸とて周りは見えるし声も聞こえる。
昔懐かしい家に戻れた大玉は、床の間のある客間をねぐらにして、鼠たちをよびよせていた。
「よう、久しぶりだな、ちゅーこう」
大玉がはいってきた鼠に話しかけた。
「あんたが噂の大玉か、久しぶりじゃない、はじめてあった、あんたと仲のよかった俺のじいさんは、妾横丁の大家が仕掛けた鼠とりにはまって死んじまった、あたらし好きのじいさんだった、天敵の猫と友達になったのはじいさんの鼠離れした、無鉄砲さだな、たいしたもんだよ」
「おお、そうだ、鼠のほうから話しかけられたのははじめてだったな、それも、ここの前の住人だった八間が鼠好きという変な人間だったからだ、あやつはわれわれ猫が鼠を追いかけるのを見て、遊んでいやがると思った、どはずれなやつだ」
「だけど、鼠にはよくしてくれたよ」
「おお、猫にもな」
「今度の借家人はどっちだ」
「虫下しは、八間ほどじゃないが、俺が手懐けたから、いずれあんたたちとも仲がよくなるさ」
鼠は床の間の隅に糞をした。新しい糞だ。空中に舞っていた俺の兄弟胞子がそいつにとりついた。あっという間に菌糸をのばした。
「ところで、ここでは美味い物は手にはいるのかね、大玉の親分」
「虫下しは午前中しかこない、お茶しか用意していないようだ、だけど八間もくるから、きっとなにかもってくるだろうよ、虫下しの女中の玉がくるが、あの娘っこは鼠を嫌っておるから近寄るなよ」
「そうか、そのうちおちょくってやる」
そこに一ダースの子鼠たちがはいってきた。
「ちゃん、あそびにきた」
「いいぞ、すきにして、ほら、大玉の親分さんにあいさつしろ」
「でっけえ猫だな、おれたちを食うことはないだろうな」
「でえじょうぶだ、この家を借りた八間の知り合いの猫様だ、いや昔ここの主だったこともあるそうだ」
大玉がそこで目をぎょろりと向けて子鼠たちを見た。
「大猫のおっさん、よろしく」
子鼠たちは、家の中をかけ回り始めた。辺り一面、子鼠の糞がちりばめられ、子鼠臭が充満した。
「いい匂いになってきた」
大玉が髭をふるわせた。
「大玉のだんな、この長屋も人がだいぶ変わってますんで、ちょいとほかの家をのぞいておいたほうがよかないですか」
「そうかい、前には何匹か美形のおねえがいたが、いなくなっちまったのか」
「三つ先のお桃さんのところの猫はまだいますぜ、三毛猫三匹だ」
「桃の木の家か、俺の子どもをずいぶん産んでくれたやつだ」
「子どもはお桃さんがやるか捨てるかしちまったから、三匹の親しかのこっていねえ」
「そうかい、ともかく、もどってきたことの挨拶にいかにゃなるめえ」
ということで、「おまえたちは遊んでいなさい」と子鼠にいいきかせ、大玉をつれた鼠の親は、虫下しの別宅をでた。
隣の梅の木の家は夜遅くにも関わらず、一つの部屋に明かりがともっている。鼠のおやじと大玉は庭の木からひさしに移り、鼠がかじってあけた穴から天井裏にはいりこんだ。
ほらほら、鼠が天井の節穴から下をのぞいて、大玉に見るように促した。
「なんでえ、人間のさかりか、見てもしょうがんねえ」
「へえ、だけんど、ああやっているときゃ、おおきな隙がありましてね、のんびりと台所の芋などをかじれるもんで」
「確かにな、鼠どんは横丁の殿様だなあ」
「いやいや、そんなこたあありませんがね、人間観察には年季が入ってやすから、なんでも聞いてくださいよ、この横丁には、夜には必ずああいうことをするための家が集まっていますんで、安心して侵入できまさ」
「そうだな」
なにやら声がする。なんだとみると、天井裏の柱のわきから黄色い茸が鼠の糞から生えてこちらをみている。
「なんで、お茸さまじゃねえか」
鼠のおやじが声をかけると、
「鼠の大将、わしらはオタクたちの糞がなけれ生えることができねえ、恩に着るぜ」
「黄色い茸はいつも見ていたが、今まで口をきいたことがねえが、どうしたんでえ」
「俺たちも進化して、鼠と猫と話ができるようになった」
「そりゃ、便利だ、どうでえ、糞を提供するから、うめえ物のある家を教えてくれ」
「たやすいこと、できれば糞を天井裏だけじゃなく、家の中におとしてくれれば、人間の動きがみやすい」
「そりゃそうだ、みんなにいっとく」
「そういやあ、あのお桃さんの家では、今日新しいジャガイモを台所にしまっていた」
「そりゃ、ありがてえ、いってみらあ」
二匹は妾横丁の家々をまわって、お桃さんのうちにやってきた。やっぱり旦那が泊まってお桃さんとしっぽり濡れております。
すぐさま台所に行くと、土間の隅に買ってきたばかりのジャガイモがしまわれないで、新聞紙の上にころがっている。
「大玉の大将、あっしはこれから仲間を呼んで、おじゃがをいただいていいでしょうか」
「おお、そりゃいいさ、みんな呼んでやれよ、俺はやることがある」
「へへ、しっぽりとですか」
鼠の大将は大玉が天井裏から、一つの部屋をずーっとのぞいていたのを見ていた。
大玉がその部屋に忍び込むと三毛猫がすやすやと寝ております。あっという間に首筋にかみついた大玉は三毛猫をものにし、いきようようと虫下しの別宅にもどったのでした。
別宅ができて三日後の朝、虫下しは原稿用紙を風呂敷に包み、玉が作った弁当と猫の餌をもって妾横丁に行った。引越の次の日に女中の玉が大玉のえさをやるついでに、部屋をきれいに掃除してくれている。
虫下しは玄関を開けて驚いた。玄関から続く廊下が見違えるようにぴかぴか光っている。
八畳の客間のガラス戸をひくと、少し毛羽立ってはいるが畳が朝の光にてらっている。床間には黄色の茸がいけてある。女中の玉の奴、茸を生けるのが趣味になってしまったようだ。
書斎はきれいに片づき、机の上にやっぱり茸を植えた植木鉢がおいてある。
「こりゃちとじゃまだ、仕事ができない」
虫下しはぶつぶつ独り言をいいながら、鉢をもちあげ本棚の空いている一番上にのせた。
「よくきれいにしてくれたものだ、玉に芋でもかっていってやろう」
さて、あの大猫がいない。土間をのぞいても、餌入れの皿がころがっているだけだ。虫下しは持ってきた餌を皿に入れた。
奴さん、クソでもしにいってるんだろう。虫下しは仕事部屋にいくと、机の前に腰掛けた。目の前に庭が見える。隣の家の庭も見える。
原稿用紙をひろげ、じっと四百字の桝をにらんだ。万年筆のキャップをはずし、また考えた。なにを書きゃいいんだ。毒茸だ、今回はベニテングタケだ。赤くてきれいなやつで毒がある。だがなんにもでてこない。ともかく一字でも升目に入れればはじまるだろうと、最初の行の一段下に、一の字を書いた。升目に一の字がない。なんだ、と万年筆をみた。万年筆を見たからと言って、文が出てくる訳じゃないが。あ、いや、と思った。虫下しは万年筆の胴体を回してはずすと、ああそうかと納得した。スポイトの部分に全くインクが入っていない。万年筆はシェーファーだ。インク壷を開けて万年筆をつっこみ、スポイトを摘まんではなした。なんだ、インクがはいってこない。インク壷を見ると、全くインクがない。だから文が書けないんだ。納得した虫下しは立ち上がった。
インクを買いに行かなきゃなるまい。後にするか。さて、どうするか、庭にでもでてみるか。
虫下しは客間に行くと、ガラス戸を開け庭にでた。お隣の庭は庭師がはいっているとみえて、庭木がきれいな形に整えられている。睡蓮鉢がいい具合に富士のような形の石のわきにおかれている。それに比べて、我が借りた家の庭はどうだ。木の枝は伸びほうだい、草も好き勝手にはびこっている。柿の木なんぞぐにゃぐにゃ天に延びてすき放題だ。
隣の家のガラス戸が開くと、女性がでてきた。寝間着のままで、裾が割れて白い腿までのぞいている。
ぎょっとした虫下しは一歩下がって、相手に見つからないように軒にはいった。
そうかここは妾横丁だ。
そのとき足になにかぶつかった。なんだ。
下を見ると大玉がこすりついて、顔を上げ、にゃむ、と鳴いた。
「なんだ、どこいってたんだ」
大玉はよけいなお世話だと、縁に飛び乗り、空いていた客間に入っていった。
「そうか、えさか、台所にいれといたぞ」
虫下しも縁に上がると、客間から台所に行った。
大玉はすでに土間に降り、餌の器の前でまっている。
「ほら」
今日は特別だといいながら、女中の玉が用意してくれていた、煮干しを皿の上においてやった。
大玉はオヤッという目で、煮干をガチャガチャと食い、大きな伸びをした。
虫下しが見ているのも無視をして、土間から台所にとびあがり、廊下を歩いていく。これから鰹節飯を作ってやろうと表いた虫下しは、ずいぶん小食だと思いながら、大玉のあとについた。大玉は結局虫下しの新しい書斎の中にはいりこみ、つんであった座布団の上にとびあがった。虫下しが眠くなったときに強いて布団にしようと、用意しておいたやつだ。
「何だ、朝から眠いのか」
大玉はちょっとばかり顔を上げて虫下しを見たが、すぐにくるっと丸くなり、右手で顔をかくしてしまった。
おりゃあ、猫だぜ、それによー、昨日、三件先のみけちゃんと忙しかったんだ、あいつおとなしそうな顔をして、なんと激しい奴だ。朝までつきあわされて、こっちゃくたくただ。
大玉はそういいたかったようだ。
虫下しは書斎の机に向かった。どうもいかん、白い足がちらちらする庭にでたら探偵小説が艶體小説になりそうだ。しゃれにもならん。
万年筆をひねくりまわしてもインクがないんじゃ書ける訳はない。空白の白い原稿用紙を見るとおとなりの白い足がちらつく。今日はだめのようだ。家に帰って茶でも飲むか。
虫下しは家にもどった。
「あら、もうおもどりですか、なにか忘れものでも」
細君がでてきた。
「いや、大玉がやけに甘えて、仕事にならん、今日はやめた」
かなりのうそをついた。
「大玉は元気なのですね」
「うん」
虫下しは書斎に閉じこもった。
妾横丁の別宅と同じように、机の上に原稿用紙をおいた。
万年筆にインクを補充した。
キャップをとると、なんだか書けそうな気になってきた。
玉の冒険、とタイトルを書いてみた。どの玉を主人公にするのがいいのだろう。考えながらふと天井の隅を見ると、白い茸が垂れ下がって生えている。大玉を妾横丁に運ぶ少し前に、たくさんの白い茸が生えたことがある、そいつがまだ生きているようだ。
そうか、毒茸の話を書かなければならぬのだ。茸十夜だ。
ベニテング茸の覗き見とタイトルを変えてみた。まてや、覗き見とはピーピングトムじゃないか、変態だ。余りよくない行為だ。だが探偵は小さな穴や隙間から人間の動きをのぞきみる。真理を探究するには必要なことでもある。観察じゃあ味気ない。探偵というのを行為としてとらえればいいわけだ。まてよ、茸を推理する探偵にして、猫が実証をする科学者の役割のほうがいいか。だが、茸十夜は幻想小説だ。探偵じゃ駄目だ。
虫下しは玉も茸も消してしまった。また考えよう。
そこに、お昼の用意ができましたという女中の玉の声が聞こえた。
細君が猫たちに囲まれてすでにお膳の前にすわっている。
「あなた、みかけ横丁はどうでしたの」
「みかけ、じゃない、めかけだ」
「あら、めかけってお妾さんみたいね」
そこで虫下しも妾横丁の本当の名前がなんだったか忘れていることに気がついた。
「いや、誰もが目をかけるほどいい横丁だ」
天井裏に生えている俺は白い茸である。節穴からこの家のことはみんなみえてしまう。江戸川乱歩の天井裏という作品は、俺たち茸が乱歩にヒントをやったんだ。
それにしても、虫下しの嘘つき。
「あれ、あの家はそんなにいい家でしたっけ」
入道にあの家を世話したのは細君の父親の関係だ。一度引っ越し祝いを持って行ったことがある。
「家は古いがな、静かなんだ」
「それでは、お仕事がさぞすすんだのでございましょう」
「ところがな、大玉がやたらとくっついてきてな、遊んでやっていたら、時間が過ぎてな」
猫の子どもたちが虫下しの周りによってきた。みな大玉の子どもだ。父ちゃんのことを話しているのがわかったのかもしれないと、虫下しが膳の上のじゃこを一匹ずつ子猫にあたえた。
猫たちはお行儀よく列を作ってじゃこをくわえ、また奥方の周りにあつまった。そこには母ちゃんの玉の集団がいる。
「あなた、午後に女中の玉をあなたの別宅の掃除にいかせますけど、足りないものはありませんか」
「そうだ、こんど、長屋で句会をやろうとおもうのだが、いつもの連中を集めるので、茶の茶碗をいくつかもっていっておいてもらおうかな」
「はい、申しておきましょう、木琴、桑子、入道ですね」
「ああ、そうだ、そのときおまえも来るか」
言われた細君も虫下しと似たり寄ったりで大事なことを思いだした。
「あなた、わたくし、父の後をつごうとおもっております、父も年ですし、兄は英語講師、今はロンドンであがいています、ということで、跡継ぎが居ないことを心配しています」
父親は大日本女頼(にょらい)神教の教祖で、御年九十九である。当時としては珍しく、女性をうやまう宗教で、女性の家事を手伝い、子育てをになうことで、男はあの世で楽をすることができるというものだ。ところが信者は女性ばかりで、男は数えるほどしかいない。それでは父親の老玉(ろうぎょく)はなにをしているかというと、信者の女性たちに、男は単純でこうやれば自由にあやつることができると、ありがたい説教をしてきかせる。老玉の奥さんは早くになくなり、信者たちが世話をしているという。
実野はアメリカでは、協会で歌を歌うと言うことを聞いて、まえまえから父親に、せっかく女性がたくさん集まっているのだから、大日本女頼神教の合唱団をつくりたいと言っていた。
父親の老玉は協会の賛美歌を連想したようで、それはよいよいと、ついでに教祖の座も実野にあけわたすことにしたのだ。
「これから毎日、実家にまいりまして、父親の代わりに朝のお説教をしなければなりません」
「おまえがなにを説教するんだ」
「はい、こった肩のほぐし方、偏頭痛の治め方、腕の疲れのほどき方、等々女性のかたがたにお教えします」
自分がいつもやっていることだから、まあ、そのようなことなら、細君にもできるだろうと、虫下しは、
「それはいい、がんばんなさい」とはげました。
「それに、合唱団をつくりますの」
「ほう、大日本女頼神教に賛美歌なんかあるのかい」
「わたしが作りますの、木琴にも手伝ってもらいます、ほら、アメリカの協会のようにゴスパラはどうでしょう」
「なにかね、それは」
ゴスペルのまちがいも気づかない。
「ほら、教会音楽よ」
「ゴスペルかね」
「そうそう、それ、だけど、ブルースっぽい方がいいかもしれませんわ」
「ブルースってなんだい」
「アメリカの黒人の労働歌ですわ」
虫下しは歌のことには興味がない。
「まあ、がんばんなさい」
そういったことで、実野は朝ご飯を食べると、朝のお勤めにでかけるようになったわけです。
虫下しは妾横丁にかよい、大玉と遊んで、原稿用紙に一行ほど書いて帰ってくる。
女中の玉は奥方が留守するようになり、かなり自由になった。せっせと午後は妾横丁の虫下しの別宅掃除に通い、夕食の準備にもどってくる日課になった。
「句会はいつだったかな」
別宅で虫下しが原稿用紙にむかってうんうんいっていると、八間入道がはいってきた。手には酒をつるしている。
「一週間後だ」
虫下しが原稿用紙に見飽きたときだったので、これ幸いと客間にでてきた。
「昼間から酒か」
「うん、蔦屋に絵を何枚か渡したら、たいそうな金をくれた。女百態にするにはまだ時間がかかるが喜んでくれてな」
八間が壁を見て、「黄色い茸がまだ生えてくるな、ここは鼠の匂いがしてよいわい」とあぐらをかいた。
壁には引っかかった鼠の糞から吾輩が生えている。たたみからも一つ吾輩が生えている。女中の玉が畳をよく掃除しているが、隙間に詰まった鼠の糞はおいそれとぬぐいきれない。
吾輩は虫下しの家で起こっていることをすべて見ているのである。
虫下しは妾長屋の自分の部屋にはいると、ともかく原稿用紙に向かう。この習慣はたいしたものだが、タイトル一つ書くのに何日もかかる。これは別に悪いことでも何でもない。頭の中で整理がついてうまく乗ると、どんどん書けるが、それまで時間がかかる作家はいくらでもいる。
ただ、このごろちょっくら頭の中が変わってきたようだ。原因は隣の家のお妾さんの梅さんだ。おくての虫下しにとって、まじかにみるはじめての、色気のある女性である。奥さんの実野さんとて、かなりの美形なのだが、美形と艶っぽいのとは違う。艶っぽさは男に対する意識のありかたから生じるのだろ。それは目にでて、肌にでて、動きにでる。それが男を、ぎょ、だか、わ、だか、ほにゃ、だかしらないが、おどろかし、どきどきさせる。
お隣のお妾さんは、虫下しを男として意識して動いているのではない。囲ってくれている旦那に対してなのだが、艶っぽさがはみ出て、ほかの男の目を引いてしまうのである。
こういったできごとも、作家にとってはいい刺激になる。きっと虫下しは以前だした探偵小説より、大人の探偵小説を書けるようになるだろうと吾輩は見ている。今書いている茸十夜にもいい影響を及ぼすだろう。幻想小説には想像の思いが必要だからだ。梅さんの白い肢は幻想を作り出す。
虫下しはそのような調子だが、午後にやってくる女中の玉は、虫下しの家にいつときとは全く違う様相を呈する。吾輩が胞子を飛ばしたくなるようなことをしている。
女中の玉は虫下しの別宅につくと、窓を開け放ち、まず、大玉にえさをやる。大玉は妾横丁の親分猫になって、あたりの猫をとりしきっている。大玉は玉の足にこすりつく。時に足裾の中に頭を潜らせて足をなめる。ともかく餌をくれる大事な人であるから、大玉としては大サービスをしているつもりである。
女中の玉は「ありゃ、また大玉はいやねー」などと、大人になった女のような声をだして、大玉のしっぽをたたく。大玉が裾から顔を出すと、着物がわれて、女中の玉の白いふっくらした大腿がのぞく。誰も見ていないと思っているのだろうが、吾輩が見ている。胞子を飛ばしたくなるほどの足である。
女中の玉はそれから部屋の掃除をして、厠の掃除、台所の掃除を終わらせる。
猫餌は八間が買って別宅にとどけてある。それは虫下しも知らぬことだ。八間入道は女中の玉が来ている時間に顔をだす。それは八間入道の家でやっていることの続きをするためである。
女中の玉は八間の家にいくことがある。そこで何をするかというと、女百態の手本、いうなればモデルになる。横座りになったり、正座をしたり、寝ころんだりしていた。
虫下しの別宅にやってきた八間は「玉さん、すずやの饅頭買ってきたよ」と玉に手わたすと、「ありゃ、いつもすまんこってす」と、玉はお茶の用意をはじめる。
座敷のちゃぶ台の上に饅頭とお茶がおかれ、向かい合いに玉と八間がすわる。いつものことだ。
「ここの饅頭は餡がうめえです」
「そうだな、こんどは菊屋の梅饅頭を買ってこような」
八間が茶を飲むところなど想像もできないと実野さんはいうだろう。
「玉さんの家は農家だったよな」
「へえ、田圃も畑もやっとります」
「おやじ様はいくつだい」
「へえ、もうすぐ五十になりますだ、あたしが七人兄弟の末っこですからなあ」
「そうか、心配しているだろう」
「なにをですか」
「そろそろ嫁にいけなんて言われておらんか」
「いえ、上の姉たちもまだなんで」
「おお、そうか」
などと会話をして、お茶を飲み終えると、
「今日もいいかな、手間賃はいつもの通りでたのみたいが」
「へえ、そんなら、お茶をかたづけてきますで」
女中の玉は急須やら、お茶茶碗を台所にもっていき、洗い終わると八間のところにもどった。
「それじゃ、たのむな」
玉が座敷の床の間の前で横座りになる。このころになると、横丁のどこぞで昼寝をしていた大玉がもどってきて部屋の中に入ってくる。
「すそをひろげてな」
八間は筆をとり紙を広げる。
玉が裾をわって足を露わにします。
八間は筆をささっと動かして、玉の横座りの姿を書き写します。
「もちょっと足が見えないもんかな」
「こうかね」
玉がふぁっと裾をめくると、白い足が根本の方まで露わになります。
八間の目がとまってしまいます。
「もっとかね」
八間がだまったままだから、気を利かせたつもりで玉はもっと裾を大きく開きます。
八間なにもいわずに、やっと筆をとり、乱れた裾の玉を絵にします。大きな入道の身体がどきどきゆれている。
やっと玉をみると、「きれいじゃの、襟をほどいてくれんかな」
玉は着物をゆるめ胸をあらわにした。
やっぱり八間はみつめるだけ。
「もちょこっとだよ」
玉は乳を半分ほどみせた。
八間はやはりさっと絵にする。
「やっぱりのう、ちょっと中途半端だのう」
のらりくらりと八間がいうものですから、玉は「ええよ」と袖をはずして、上半身をはだけます。外からは十六歳の子どもにしか見えなかった玉の白い胸に、はちきれんばかりの乳が白く盛り上がっている。
「あ、あ、そのまま、そのまま」
八間は女中の玉のからだを紙の上にうつしとる。
「た、玉さん、きれいだのう」
玉はこれからどうしたらいいかと思案にくれていたようですが、そう言われたので、
「もっとかい」と、立ち上がると、着ていたものをずりおとし、きんきんにはった、だけど、桃の皮のような肢体を八間の前にさらした。
ぎょっとした八間は、「て、手間賃は倍にいたすから、そのまま、そのまま」
何枚もの紙の上に筆を走らせます。
ちょっと疲れた玉がたち膝をして、両あしをかかえ「つかれたな」とつぶやくと、
八間、「ありゃ、ちょいとそのまま」とまた筆をはしらせる。
玉がまた横座りになると、八間は「つかれたじゃろう、横になっていいぞ」という。
玉は上向きになり、思い切り足を延ばすと、胸の乳がふるふる動き、八間はすり寄っていくと、そこで絵を描いた。
「眠くなるなあ」
玉があくびをすると、「よいぞ寝てよいぞ、よい絵がかける」
とうとう玉は目をつむって、寝いってしまいました。
八間は玉にちかよると、上から脇から、頭から、足のそこから玉をながめまわし、たくさんの絵を描いた。
やがて、玉があーあと、伸びしをして、目を開けると、八間が足の底の方からのぞいている。
「触りたいんかね」
玉がそう言ったものだから、おどろいたのは八間。
「あ、いや、あ、そうだな」
とどもると、玉は「村の男の子らあ、みんな触りたがったんよ、だから、ちょっとだけ触らしてやった、男ってそんなもんじゃろ」
まだ子ども子どもしていた玉にそういわれた八間は、おおいにあわてて、「玉さん、嫁さんになってくれ」と言ってしまった。
「なんじゃ、嫁さんにしないと触れんのかい」
玉はおきあがり、「ええよ、まんまをたくのはできるでよ、ほらさわりなよ」
八間の前に裸体の玉がすっくとたった。
八間、なにもいえず、ぼーっとしていると、玉が八間の手をとって自分の胸に当てた。
もうあとはなんだかわからない。玉の「八間先生のはドジョウみたいじゃの、村の男の子のはナマズの子どもくらいじゃ」という声が聞こえた。
吾輩はあとはみていられなくて、全身の目をつむったのである。
大玉はじいっと見ていたらしい。なにやってんじゃ、うちの主人はと、生えている吾輩をみつけて小声でうなった。
「なんじゃ、今日はだめなんか、嫁さんにならなきゃできんか」
茸にゃ意味が分からない玉の声が聞こえた。
「次は奥様にもらった銀座の洋服をもってくるかい」
女中の玉はさっさと着物を着て帰り支度をした。
「八間先生、またあさっていくでよう」
そう言うと虫下しの別宅をでた。
あとには入道がでっかい図体で、葛餅みたいにボーっと座っていた。ちゃんと戸締りしろよ。
鼠の糞から生えた吾輩は虫下しの家ばかりじゃなく、妾横丁の家の出来事をみんな見てしまって、少しばかり嫌気も差してきているのである。こんなことばかりしてやがる。もっと世界的な活動をせよといいたい。吾輩たちは地球の裏側の茸たちとも情報のやりとりができるんだ。
まあ、日本に根を生やした茸だから仕方がない。ともかく妾横丁の虫下しの別宅での出来事をこれからも報告しようじゃないか、退屈でもあるからな。
終章 女中、玉の運命
今日は珍しく客人がある。妾横丁の別宅では初めての月の句会である。集まるのは木琴、桑子、それに八間入道である。
虫下しは昼飯用に朝から持参した握り飯とたくわんをかじっている。午前中は原稿用紙に向かって、句のお題はなににしようかと考えていて、それで時間がすぎた。足下に大玉がきて、猫にしようかと思ったら、大玉が大きなあくびをしたので、あくびがいいとやっときまった。それでほっとして握り飯である。
玉が煮物やらを用意して家から運んできた。酒は入道が持って来るだろう。
「ご主人様、奥様は大日本女頼教がお忙しいんで、こられんそうです」
虫下しはそうかとうなずいた。
「秋田から親が茸を送ってきましたで、茸の煮染めを作りました」
「そりゃいいな、秋田のように甘くするなよ」
東京育ちの虫下しは甘辛い北の食べ物を好まない。そんなことは女中の玉はよくわかっている。
「へえ、薄い醤油味で煮っころがしたで」
虫下しはその方が茸やジャガイモの味が引き立つと思っている。
虫下しが握り飯を食い終わり、茶をすすっているところに、はやくも八間入道が酒びんと煮干しをたくさんつるしてやってきた。
匂いをかぎつけた大玉は入道に向かって飛んでいった。
「虫下し、じゃまするぞ、この猫はわしを主人だと思っておるな」
大玉が大きな目で八間を見上げると、入道は頭をさすった。ただ煮干がほしかっただけである。
「玉さん、酒持ってきたから、座敷においておく」
「はーい」
玉が台所から跳んで出てきた。
「あれ、煮干もかね、大玉にやるんか」
「玉どの、わしも好物なのでな」
「大玉にあやかるのかね」
と煮干と酒を受けとった。
虫下しは何の話かわからずに、
「いつもはやいな」
と玄関に顔を出した。
八間がずかずか入ってきた。
「ここであうのは久しぶりだな、ずーっとこなかったのか」
虫下しが聞くと、八間はちょいとばかり間をおいて返事をする。
「そうだな、お主がいないときに、たまに大玉の餌をもってきておるがな」
実際は女中の玉の絵を描きにやってくる。
女中の玉がお茶を持ってくると、八間が「久し振りだ玉さん」
わざとらしく声をかける。
「へ、昨日」と玉が言おうとしたとき、八間が口に人差し指をあてて、しー、といった仕草をした。
玉はつづけて「昨日、餌がおいてあったでよ」
「ああ、わしが買っておいていった」
とまあ、二人はできていたわけだ。
「今日のお題は、あくび、にした」
「ほほう、それはまた、虫下しにしてはおもしろい題を思いついたものよの」
入道がめずらしくほめた。
「女百態はどうだね」
「おお、うまくいっとってな、もうすぐできあがる、蔦屋もよろこんでいてな」
「蔦屋が選んだモデルがよいのだな」
八間はちょっと迷ったようだが、
「いや、蔦屋がよこした手本の女はだめだ、美学校で学生の前で裸になっている奴らだ、泰西の形の女はわしにはむかん」
「それじゃ、どんな女がモデルになってるんだ」
「玉さんだ、なかなかいい」
週に一度、女中の玉が八間のところに言っていることを虫下しは思い出した。へ、っと言う顔をして、
「秋田の十六になったぐらいの子どもがいいのか」
と言った。
「いや、そうだ、泰西ずれしておらん」
「うーん、そんなもんか、あの秋田なまりを聞いておると、女に見えん」
「虫下し、そりゃ偏見だ、改めよ」
ちょいと八間はいきどおった。そこへ、玉がはいってきて、
「八間さん、おかんがよござんすか」
と言ったものだから、虫下しは、あれ、と言う目で玉を見た。今日は髪をおかっぱにきれいに揃えている。色が白く、目ははっきりとして、柔らかそうな腿のような頬がしっとりとぬれている。確か八間の言うとおりかもしれぬ。虫下しは袖からでている玉の指先をみた。白くて細い。うーん、とうなった。
「玉さん、それをお願いするよ」
玉はうなずいて台所にひきさがった。
「虫下しはなにうなってる」
「いや、八間の言うとおりかもしれんと思ってな」
「目の肥えた男は女を見抜けるんだ、小説家はそうじゃなきゃな、虫下しももっと男になれ」
大玉がいつの間にかそばにきている。そういっている八間を見上げて、ふゃ、なにいってやがる、と猫語で畳の中にはびこっているわれわれ菌糸につぶやいた。大玉の言うとおりだ。吾輩もちょっと頭を出した。
八間にはニャアと聞こえたようだ。
「何だ、大玉いたのか、おまえにしてはずいぶん小さな声だなあ、元気がないか、そうだ、煮干しを玉さんからもらいなさい」
まあ、親切に言ってくれるのだからと思い、大玉はあぐらをかいている八間の足の上にのった。
「それにしてもこの猫は重いの」
「このあたりじゃ一番でかい猫だ」
虫下しも大玉が妾横丁の親分猫であることを知っているようだ。
女中の玉が、煮干しをいって暖めた酒とともにもってきた。
「おーすまんのう」
玉は八間に酌をした。
虫下しはそれをみていて、「八間、近頃は猪口で飲むのか、前は、湯飲み茶碗で飲んでいたではないか」
「いや、酌をしてくれる人がおれば、猪口で飲む、虫下しもどうだ」
虫下しは首を横に振った。すぐ眠くなる。
「玉が酌をするのを始めてみたな、どこで覚えた」
「あれ、そんですか、八間さんが、酌をするところを絵にしたいと言ったで、練習しましたで」
女中の玉もだいぶすれてきおったな。
「ああ、そうか、玉は八間のもデルになっておったな、楽しいかい」
「はあ」
玉はそう返事をしただけだが、この部屋で大いに楽しんでいるのを見ている吾輩は、虫下しにちくってやりたくなったが、胞子をとばすぐらいしかできぬので、ちょっと残念だ。猫ならば大鳴きするとか、爪を立てることができるのに、大玉はなにもやらぬ。
「八間、句会まではまだある、わしゃ、向こうで原稿をかいておるから、かってにやってくれ」
「ああ、かまわんでいいよ」
虫下しは原稿を書くのではなくて、虫下しの書斎にしている部屋の窓から隣の家の庭でときどきみえる、となりのお妾さんの艶姿が見たいためだ。原稿が進まないのはそのためもある。
虫下しが書斎に言ってしまうと、八間は左に大玉、右に女中の玉と、玉にはさまれている。
玉が酌をすると、「おっとっと」などといって、にたにた顔の八間が玉をみる。八間が玉の足に触ろうと手を伸ばすと、
「今、だめ」
女中の玉がぱちんとたたいた。そのすきにと大玉が八間のまえの膳に載っている炒った煮干しに手を出す。やっぱり玉が、
「今、だめ」
と大玉の手をたたいた。
なにやってやがんだ、猫も人間もかわらないじゃないか、と吾輩は床の間の隅からもう一本顔をだした。今日の句会は退屈になりそうだ。
女中の玉は歌会の準備をしなきゃ、一人で飲んでねと台所にさがった。大玉は煮干しをくれるものとついていった。
女中の玉は土間に降りると、竈の脇の調理台においてあった袋から、煮干しを一つ取り出して大玉の前になげた。
「大玉、みな内緒にしておくれ」
煮物をつくりはじめた。
見ているのは猫だけじゃないぞ、吾輩、茸だってみんな見ているのだから、煮干しはいらないが、鼠の糞は残しておいてくれよな、と聞こえないかもしれないけど玉にささやいておいた。
夕方になると、最初に木琴がやってきた。
「久しぶりです、虫下し先生はこのような家を借りたんですか」
木琴は玄関からあがるなり、出てきた虫下しに挨拶した。
「ここは八間がすんでいたところでな」
大玉が玄関まででてきた。
「おや、この猫は飼ったんですか、家の方にもたくさん奥方が飼ってましたね」
「大玉は八間にやった猫で、ここで大きくなったんじゃが、あいつが家を移ると返してきてな、うちじゃ猫が多くなりすぎで、ここを借りたわけだ」
「ほう、この猫のために借りたのですか」
「まあ、わしの別宅によいしな」
「でも、お妾さんがこの猫じゃ、さみしいですな」
虫下しはよけいなお世話だと、だまって座敷に案内した。
「おや、八間さんが寝ている」
座敷に案内された木琴は、開け放たれた庭のよく見えるところに、自分で座布団を運ぶとあぐらをかいた。
八間はもってきた酒を飲んでしまうと寝てしまったのだ。
虫下しが八間の尻をけっ飛ばした。
「うーん、玉さん、なんだい」
「ねぼけておる、なにいってんだ、ほら木琴がきたよ、句会の準備だ」
「ふや、あーあ」
大きな口を開けあくびをしながら、八間がおきあがった。動きが大玉にそっくりじゃないか。
「ほら、あくびがでた、句をつくるには状況をつくらにゃあかんからな」
八間がおきあがると、女中の玉が「床の間に生けるはなはなににしましょうか」といってきた。
「庭になんぞないかな」
「さがしてきます」
玉が庭に出ると、白い茸が生えていた。秋田では至る所に茸が生えているが、東京は少ないと思いながら、いつぞやは赤い茸を床の間に飾った、きっと茸がいいのだろうと、白い茸をシャベルで土とともにとると、ふちの欠けた湯飲み茶碗にいれた。
「これはどうでしょう」
座敷に持ってはいると、八間が「おー、玉さんはなかなかいい目をしている、しゃれたものをとってくるのう」
なにがしゃれているんだ。吾輩はあきれてみていたのだが、茸を飾ろうというのは、見上げたものだ。床の間にあうのは万年茸ばかりじゃない、どのような茸だってよく似合う。
「それでよいよ」
虫下しもうなずいた。
木琴が「これ、買ってきました、実野さんが好きでしたな」とみやげの包みをわたした。
包みをみた女中の玉が「紀ノ国屋のおまんじゅう」目を輝かせた。
「女房は父親の跡を継ぎましてな、大日本女頼教の教祖になって、今日はお説教だそうで、ここにはきません」
「おや、そうでしたか、それなら玉さん食べてください」
女中の玉はえくぼを寄せて「ごっつぁんです」と、八間の言い方でお礼をいったので、虫下しも木琴もぎょっとした。
そこに桑っこがきた。
虫下しが玄関にむかえにいくと、
「先生、久しぶりです、いい書斎ができましたね」
とおべんちゃらを言った。
座敷に桑っこを通し、みな思い思いのところに座った。庭には手入れがされていない木が枝を好きなようにのばしている。
「詩は書いてるかね」
「ええ、双子社からもうすぐ本を出します、探偵小説の編集長が、先生の小説をまちわびでいますよ」
双子社は虫下しが雑誌に連載をたのまれている出版社だ。探偵小説と詩の雑誌を双子の編集長が出版している。虫下しが紹介したところ、桑子の詩が初めて活字にたったことから、桑子は虫下しをとても尊敬している。
「そりゃあたいしたものだ」
「私も、作曲したシンホニーがオーストリア管弦楽団で演奏されることになりました」
「それはめでたい」
八間がお祝いを言った。
「わしもの、蔦屋から女百態をだすことになった」
「みなみなおめでとうございます」
桑子が手をたたいた。
虫下しは俺は何だ、とふと思ったが、まあいいかと手をたたいた。
「今日のお題はなんですか」
桑子が床の間を見ると、白い茸が湯飲み茶碗にうわっている。
「また茸でしょうか」
「いや、あくびだ」
八間がどなった。そこで退屈した大玉があくびをした。
「食べ飽きて、あくびとおくびがはちあわせ、てなところですかな」
「さすがくわっこ、いいできだ」
八間が笑った。ここの句会は季語などなくてもかまはないようだ。
「それじゃ、そろったことだし、そろそろはじめるか」
みなは二つのちゃぶ台のまわりにすわってうでぐみをした。
八間がなかなか筆を動かそうとしない。
最初に手が動いたのはやはり詩人の桑子である。
次は木琴が万年筆でさらさらと書いた。
八間が筆をとる。最後にやっと虫下しが鉛筆で書いた。桑子はもういくつかできたようだ。前に書いた句に直しを入れている。
八間があくびをした。それが移って虫下しもあくびをした。桑子はもう手を動かしていない。
「できた方からどうですかな」
虫下しが三人の顔を見回した。
「それじゃ、私から」桑子が句を読んだ。「葉の上の桑子あくびで下におち」
「なんだい、それは、おまえさん葉の上にたかっていたのか」
八間が笑った。
「お蚕さんが、桑の葉を食べ飽きて、あくびしたとたん、おっこっちまった」
「なるほど、葉の上の、かいこ、あくびで、羽がはえ、にすると、食欲から生殖の相手を探したくなる、本能の変化、虫の変態となるのではないか」
そう虫下しが評をする。
「食べるのに飽きた蚕があくびをして、大人になって、女を捜す、さすが探偵小説作家、の解析はたいしたものです」
桑子はそこでも虫下しをもちあげる。
「わしゃ二つ読むぞ」
八間の句である。
「月もなし、酒もなくなり、おおあくび、あくび猫、髭を引っ張り、ふにゃらがお」
大猫の大玉が八間のところによってきて大きなあくびをした。摘まんねえと思っている。ひでえ句だと吾輩も思う。
「この猫、よくわかっているな」
勘違いした八間があぐらの上に大玉を引きずりあげると、大玉はめんどくさそうに、足の上で丸くなった。
「わかっとらんよ、わかっとったら、あくびしないだろ」
虫下しが笑うと、大玉が虫下しの方を向いて、大きな口を開けてあくびをした。
「なんだこいつ、人の顔を見てあくびをしおった」
虫下しが大玉をにらみかえすと、大玉は首を落として寝てしまった。
「おまえさんは眠くなる顔なんだ」
「それじゃ、わたしが」
と木琴が読んだ句は
「オペラ歌手 あくびの方が 声がいい」
「そんなやつがいたのかい」
桑子がきく。
「そうなんだ、声がのびないやつでね、そいつが練習の途中で、あくびをしたら、その声がずいぶんのびて、ホールに跳ね返った」
「本番じゃあ、どうだったんだ」
「だめだったね、ホールの真ん中へんで渦巻くだけだ、はねかえらなかった」
「そいつは首だね」
「それが、とりまきの女たちが、大きな拍手をして、それを新聞記者が、ほめたたえて、有望な歌手と書きやがった」
「そんなもんだよ世の中は、新聞記者が悪くする」
桑子が言って、みんなが笑った。
「それじゃ、私の句」
虫下しが読んだ。
「原稿の 升目にただよう、またあくび」
「虫下し先生は原稿書きに苦労してるんじゃな、次の作品はいつごろだい」
八間は気を病んでいる虫下しに遠慮がない。虫下しは胸が痛くなり、押さえるまねをする。
「虫下し、あくびたまって、胸つかえ、だな」
八間の即興に周りが笑った。そのほうが面白いじゃないか。
虫下しは苦笑いして苦虫になった。その後、はちゃめちゃな句がみんなの口からとびだして、句会というより、あくびだじゃれ歌の会になった。
朝顔に、つるべとられて、あくび虫
ご隠居さん あくびながやの はじまりだ
朝になり、あくびもでない、ふんずまり
明日こそ、あくびをださない、寄席の席
八間が
あくびさえ、でてこないぞと、腹の虫
と詠み、虫下しは、
「それじゃそろそろ、おわりにしますかな、玉や、そろそろ、用意してくれないか」
台所の方に声をかけた。
ハーイと言う返事とともに、茸の煮しめをもって女中の玉が座敷にはいってきた。
「おや、あの女中の玉さんか、大人になったなあ」
「ほんとだなあ」
木琴も桑子も女中の玉を見た。
「おほほほほ、今燗をつけて参ります」と台所に向かう玉をむぎゅうと見つめたのは八間の目。わからないのは虫下しばかり。
「さて、茸の煮しめをつついてくだされ」
虫下しの声で、膳の上の煮しめをつつきはじめた。
「こりゃ玉さんがつくったんだな、なかなかうまい」
八間が湯飲みの酒をぐいと飲んで、舞茸の煮つけを口にいれた。
「おや、八間さんが食い物の感想をいうとは、こりゃまためずらしい、久しぶりにお会いしたのだが、どうかされたかな」
八間は浜納豆だけは旨いと言って食うが、ほかの物はただ口の中に放り込んでいるだけという印象だ。
「よほど、女百態がうまくいったんだな」
虫下しが酒をちょっぴり口にいれた。
「それでな、虫下しにたのみが二つあるんだ」
「二つもあるのか、なにして欲しいのだ」
「ひとつはな、おれはこの家が好きでな、女百態も終わったし、ここに戻りたいと思うんだ」
「この鼠臭い家がすきなわけだ、わしもここにいてもなにも書けんので、やっぱり家の方がいいと思っていたところだ、大玉もおまえの猫だしな」
大玉はどうやらわかっているようで、にゃう、とないて、床の間に植えられた俺たちを見た。
俺はよかったじゃないかと大玉に言うと、大玉はごろごろいって、八間の股ぐらの上にむりむりのっかっていった。
「だが、ここだと、モデルがこないといっていたじゃないか、女百態の次の本はださんのか」
「いや、これからも続きは出すことになっている、ついでに猫百態もだす」
「鼠の平気なモデルがみつかったのか」
「いや、かみさんをもとうと思ってな」
虫下しだけではなく、木琴も桑子もおどろいた。この面度くさがりが、どうなったのだと不思議だったのだ。
「それで二つ目のたのみってなんだ、金がいるのか」
「金なら心配はないわい」
むかしから見かけとは違い、懐具合はゆたかだった。書に関してもなかなか知られている男だ。
「それじゃなんだ」
「たのむ」
そういって、大玉を足の上からほうり出すと、畳にはいつくばって、虫下しに頭を下げた。大玉そっくりだ。
虫下しはまたびっくりした。周りの連中もおどろいた。
「玉さんを嫁にくれ」
「どの玉だ、みんな実野の猫だ」
虫下しのとんちんかんにはなれている木琴も笑いだした。
「何だ、女中の玉さんか、さてはもうなにかやらかしたな」
虫下しがぎょっとした。
「女中の玉は秋田の両親から預かった者だし、実野がどういうか」
「そこをたのみたい、実野さんに言ってほしい、きっと反対される」
「うん、言ってみる、今は大日本女頼神教の教祖になって忙しい、玉さんがいなくなっても、身の回りは信者たちがやっているから、大丈夫だろう」
「それはありがたい、あれほどきれいな女体は日本広しといえど一人としておらん」
「それはいいが、玉がうんと言わなきゃだめな話しじゃないか」
「そのー、来春には子どもが生まれるでな」
これで句会どころじゃなくなった。
「玉、ちょっときなさい」
虫下しが台所に声をかけた。
「へえ、なにかもっていきますか」
台所から玉が返事をする。
「燗をつけてもってきてくれ」
「へーい」
すぐさま暖まったとっくりを四本運んできて皆の前においた。
「なあ、玉、八間がおまえさんを嫁さんにしたいといってるが、どうなんだ」
「おや、八間やっといったのかい」
玉が八間をみると、下を向いて「うん」と返事をした。
「まあ、八間はいくじなしで、前からはやく先生にいっとくれと言ってましたんで」
そのもの言いに、みなあぜんとし、改めて三人は女中の玉を見ると、確かに美形、こりゃ八間にゃもったいないと、ちらと思ったりした。
「実野にはなしてやろう」
虫下しが言うと、女中の玉は、
「へえ、実野さまには相談したで、したら、八間は一人じゃ決められねえ、突っつかなければだめだ、とおっしゃってまして、私もそういうもんかと思ったんです」
「なんだ、実野は知っておったのか、八間、わかったよ、そういうわけだ、わしの出る幕はない」
八間もそれをきいて、びっくりして、玉をみた。玉がにこっと笑って、八間にウインクをした。
「あ、それならば、虫下しにたのむのは、この家をもどしくれということだけじゃ、よろしく」
ということで、虫下しは妾横丁をでることになったわけである。
虫下しが家に帰ってからのことである。
「実野、玉のことを知っておったんだな」
「あら、旦那様、ご存じなかったのですか、玉にとっても、八間にとってもとてもよいことと思いましたが」
虫下しは「そうだな」とうなずくしかない。女はわからん。
「おまえ、玉が絵のモデルになるのをずいぶん心配しておったじゃないか」
「あの弱い八間に玉が困るのではないかと思ったからですよ、玉がうまい具合に八間をたぶらかしたので、結果はよかったでしょう、私は玉に女頼神教の教えを授けたのです」
ひゃ、おー、こわ、と、茸の俺もこの様子を胞子のまま聞いておった。
やがて、俺は風呂場の隅に茶色の茸をはやし、また胞子をとばし、虫下しの家中に胞子をまきちらしてやった。茶色になるぞ。
そういうことで、虫下しは入道にたのまれ、秋田の玉の親のところに行った。驚いたことに、玉の家は農家ではあるが、宿屋を営んでいた。虫下しは両親に入道のことを偉大な書家で、画家であり、本もたくさん出していて、将来有望の男であることを説明した。今忙しく八間はくることができないが、虫下しが責任をもって二人に所帯を持たせることを約束した。親は朴訥だが、教養のある人物で、本人がよければそれで良いのでよろしくと、虫下しに全てを任せてくれた。帰りに珍しい茸をたくさんもたせてもらい、虫下しは平和な気持ちで、東京に戻ってきたのである。
「あなた、玉の祝言はわが家で執り行います、大日本女頼神教の皆さんも手伝ってくれます、もちろん、木琴と桑っこもです」
実野さんは大いに張り切って準備を指図した。
それから準備でばたばたと、二ヶ月が過ぎたのでありました。
祝言の当日である。
豆腐屋の三吉が肴豆腐をかついできました。この豆腐はそのまま食べても酒の肴になるほどうまい豆腐でそうよばれております。
「へい、坊ちゃん久しぶりでございますな」
今日ばかりは実野が女中の玉の気付けなど世話を焼いておりますし、料理は信者の女性たちが用意をしていることから、虫下しが台所でうろうろしております。
虫下しは三吉から豆腐をうけとった。学生時代から三吉には世話になっている。三吉も連れ合いをもち、子どもも三代目として豆腐づくりの修行をしている。
魚屋の源さんが生きのいい鯛を塩焼きにしてもってきた。
「あ、どうもありがとう」
虫下しが受け取ると、いくつになったか、かなりの年になったはずだがまだまだ元気な源さんが、
「坊ちゃんが作家の先生たあ、鼻が高いね、お嬢さんの祝言おめでとうさんで」
そういって、
「猫の玉のご家族にもほれ、もってきやした」と、魚のあらがはいったバケツをおいた。
「そりゃすまんね、猫も実野も喜ぶぞ」
虫下しに子どもはいないが、女中の玉も家族同然、娘のようなものだなと、虫下しはうなずいた。
「あーた、猫たちのごはんたのみましたよ」
自分の部屋で女中の玉に化粧をしている実野が虫下しに言った。
玉、後玉、又玉と、大玉との間に生まれた六匹の子どもたち、そうぜい九匹が、実野の部屋からぞろぞろとでてきて、台所に一列にならんだ。
それぞれの猫の前に皿をおき、虫下しはもらったばかりの魚のあらを盛り付けた。
猫たちは「あうあうあう、うまうまうま」とかぶりついた。
「きょうはよろしく」と玄関から声がした。八間がきたようである。
「おう、あがれ」
虫下しが玄関にいくと、紋付き袴の八間が大きなからだを丸めて玄関に立っています。左手の袖が大きくたれています。
「なんだ、その袖は」
虫下しがそういい終わらないうちに、大玉が顔をだした。
「こいつが来たいと言うもんでな」
大玉は袖から飛び出すと、かって知ったる虫下しの家、いい匂いがすると、台所に走っていった。
台所では、大玉の複数の嫁さんと、その間にできた子どもたちがうまそうな魚のあらを食っている。
「おれにもよこせ」とばかり、玉の皿にくびをつっこもうとしたら、玉にぱちんとひっぱたかれた。後玉、又玉にも同じ仕打ちをされた大玉は、子どもたちの皿にいくと、みんなしてうー、とうなられた。なにしろ、奥様の猫たち、女頼神教の教義をたたきこまれております。女は強くしっかりと世の中をただすのだあ、と玉の子どもたちも尾っぽをおったてた。
大玉はすごすごと隅にたたずみ、雌玉一族がおいしそうに魚のあらを食べているのをみている。
台所に生えていた吾輩はちと大玉がかわいそうになり声をかけた。
「土間を見ろよ、ほら、バケツの中だよ」
「お、茸どん、どこにでもいるんだな、なんだいバケツの中は」
「いきゃあわかるさ」
大玉は土間におりた。竈の周りで女頼神教の信者たちが宴会の用意をしている。
大玉がバケツをのぞくと、うまそうな魚のあらが残っている。
「おお、ありがたや」
大玉は吾輩のほうを向いて、一礼すると、くびをつっこんで、うま、と一口食べて、ひゃ、っと皿から飛びのいて、いてててて、と踊りだした。鯛の骨は太くて丈夫。それが顎にささった。両手を口の中につっこもうとしたが、なかなかとれない。二本足でひょこひょこおどり。
「ばかだね、あんたは」
玉が大玉のそばによってくると、あたまをぱちんとたたいた。
大玉の口から、ぴょいと鯛の骨が飛び出して一件落着。それからは、大玉は子どもたちの一番後ろからくっついて歩くようになった。
吾輩は大玉に悪いことを教えてしまったようだ。主従逆転を目の当たりにして、宗教は強い、時として戦を引き起こすからな、と歴史を振り返ったのである。
食事の終わった玉たちはぞろぞろと、実野さんの部屋にはいっていった。
大玉もあとをついていく。
実野の部屋では奥様が、「玉にはおしろいはいらないわねえ」
と言って、女中の玉のえりくびなどに化粧水をぬっております。玉は色が白いのだ。
玉たちは女中の玉がいつもと違う着物を着ているのにびっくりした。
大玉は猫語で他の玉たちに言っています。
「女中の玉は、なんにも着ていない方がきれいなんだ、八間なんかみとれちゃって大変なんだ」
「そうなの、じゃあ、着なきゃいいじゃない」
「人間は毛皮をもっていないから寒いんだ」
「ここの奥様もきれいよ」
「だけど、ほら、足をみてみろよ、玉さんのは細からず、太からず、なんともかじりつきたくなるだろう」
「おまえさんは雄だからだろう」
「だがよ、奥様のあの大根をかじりたくはないぞ」
「そんなものかえ」
猫の玉と大玉の会話などわかるはずはない実野奥様は
「猫がやけにあまえごえをだしてるね」
とお門違いのことを言っている。
宴会場の座敷では、木琴と桑子もきて、すでに並べられているお膳の前に座っている。
八間がもってきた自分の本をみなにくばっている。
開いた虫下しが、「おお、よく描けている、こりゃみんな玉さんか」
「うん、結局、蔦屋が紹介してくれた女たちの絵は使わなかった、全部、玉どのだ、なにしろきれいでな」
「のろけるな、だが、絵は確かにいい、女が描けてる」
木琴がほめると、桑子もほめた。
「絵の女は、どれも、人生の詩を口ずさんでいるような」
「ほほ、そうか、虫下しどう思う」
八間が聞くと、虫下しは
「みんな、着物を着ているじゃないか」
ととんちんかんな、感想をのべた。
「女百態の2をだすのだが、それは裸体だ、きれいでな、床の間においておきたいほどなのだ」
「なにをだ、その本か」
虫下しは話がかみ合わない。いつものことだ。
「玉さんしか目にはいっとらんのだよ、八間先生は」
木琴がフォローした。
女頼神教の信者の女性たちができた料理を膳の上にならべた。
「あーた、支度できましてよ」
実野さんが座敷にやってきた。
「それじゃはじめるか」
「玉さんをつれてきますよ、八間、ほら、床の間の前の婿さんの席に座ってまってなさい」
実野さんは小学生の同級生だった八間には命令口調である。
「あい」
八間は婿の席に座った。
実野さんが玉の手を引いて座敷にあらわれた。
「うおー」と最初にうなったのは虫下し、「おっ」「ほりゃ」と木琴と桑子が声を出し、八間は「きれいじゃあああ」と後ろにひっくり返った。
玉さんは、実野が銀座であつらえたウエディングドレスに身を包み、しずしずと座敷にはいってきた。
吾輩は、ウエディングドレスにしてはなにかが違うと見ておったのだが、そうかと気がついた、裾が短い、と言うより、膝の上までしかない。こりゃ未来のウエディングドレスだ。ミニスカートとやらは未来にはやるもので、今の日本の男がみたら、男どものああいう反応になるわけだ。きれいな素足が丸見えだとどぎまぎしたのだろう。
隣に玉さんがすわると、スカートが少し短くなり、白い脚がもっとあらわになった。八間の目は白い脚にくぎづけだ。
「おい、八間、真っすぐ前を見ろ」
虫下しにいわれ、あわてた八間、「それでははじめます」と言ってしまった。
「おまえさんが言うんじゃないわい、仲人のわしがいうんだ」
虫下しがしかった。
「それじゃ、八間と玉さんの婚礼を祝し、一言」
虫下しは書いた物をだすと読み始めた。
吾輩はばからしと目をとじた。
ここに書くのも時間の無駄の、長たらしい虫下しの話が終わり、祝宴になった。
あまり酒の強くない虫下しが、緊張のあまり話し終わった後に一気飲みをした。舌がもつれている。
「あーた、もうお酒はやめにしときなさいよ」
細君に言われて、「教祖様の言うとおりにします、この煮しめはうまい」
椎茸をつついた。
「だが、玉さん、きれいですな、お祝いにひとつ歌をしんぜます」
木琴が立ち上がり歌い始めた。なかなかの声量。さすが音大の教師だ。
「いいな、そりゃたまたま婦人というやつだな」
泰西の音楽に疎い八間がいうと、音楽学校出身の実野さんが
「なに言ってるの、八間、タマタマ婦人じゃありません、チョウチョウ婦人じゃないの、ちゃんと働いて玉さんを幸せにしなさいよ」
としかった。
「はは、奥方さま」
八間が酔っぱらった振りをして、隣の玉さんにもたれかかった。
「ばか」
ばちんと大きな音がした。
みなびっくりして前の席を見た。お嫁さんの玉さんが、八間の大きな顔を思い切り平手打ちをしたところだ。
「八間、でれでれしないの、しゃんとしなさい」
大玉が大丈夫なのかという目で八間を見た。
八間は嬉しそうに、赤くなったほっぺたをさすっている。マゾッケたっぷりだ。
「夫婦げんかは、犬でもくわぬ、猫はよろこび、庭駆け回る」
でたらめ言葉を桑子が声高らかに発した。
それを聞いた、大玉が「いくぞ」と声をかけ、もっとも人間には「にゃあご」ですが、玉たちがそろって、ぞろぞろと庭にでた。
今日はどうしたことか庭の植木の下に茶色の茸がたくさん生えています。
吾輩の仲間であり、吾輩でもあるわけだ、と、吾輩は成り行きをおもしろく見ていた。
桑子の言ったとおり、猫たちが庭を駆け回りはじめた。
酔っぱらっていた虫下しが、目を開けて、「お、庭にうまそうな茸がある、あいつを料理してくれ」
と叫んだものですから、実野さんが「あれは毒です、茶毒茸」と、その茸に名前をつけた。吾輩の名前だ。
「だが、俺は喰う、みなも食え」
椎茸の煮しめは食ってしまった。
「つくってやろか」
と言ったのは、ウエディングドレスに身をつつんだ玉さん。
「おおお、玉さんの煮しめはうまいんだぞ、もう食えなくなるとは残念だ、是非あの茸を煮しめにしてくだされ」
虫下しが立ち上がり、よろよろと庭にでていく。玉たちが走り回る中を、庭木の下で、茸摘みを始めた。
八間もおぼんをもって下におり、虫下しと一緒に茸採り。
お盆にはずいぶんたくさんの茶色の茸がのった。
「もういいな」
虫下しと入道が上に上がってきた。
「玉さん、わしも煮しめづくりをてつだいますぞ」
「そりゃあいい、夫婦一緒に煮しめづくり、それぞ本当の結婚式だ」
酔いが醒めない虫下しが叫んだ。
「確かに確かに」と木琴と桑子もうなずく。実野さんは知らん顔。
やがて、庭の茸の煮しめが膳のうえにでてきました。熱燗がそそがれ、
「うまいうまい」とみんなが食べると、実野さんも「そうかえ、それなら、少し」と口に入れた。
「こりゃ、うまいな、玉さん」
八間が玉さんにかたりかけた。
「うんだ、うめえな」
玉さんも口に運んだ。
大玉や猫たちが庭からあがってきて、人間を取り囲んだ。
そのとたん、虫下しがわはははは、と笑い出した。続いて、八間、木琴、桑子もわはははと笑う、実野さんも、玉さんも大声で、わはははは、わはははは。
笑い声は庭から外に伝わり、町の中でうずまいた。近隣の人たちが虫下しの家のまわりにあつまりはじめた。
大玉、玉、後玉、又玉、子どもの玉たちは、なんたるざまだと人間たちを見ている。
床の間に生えている吾輩は、猫たちに、
「みんなが食ってる茶色の庭の茸は大笑い茸の仲間で、笑ってごまかし茸だ」
と教えてやったのである。
この茸を食べると、少なくとも二日は笑っていることになる。
わはははははははは
主人公は猫じゃない、吾輩茸だ。なみあむだぶつ、あーめん。
完
原案作成日
2023年2月22日(ニャンニャンの日)
吾輩ハ茸


