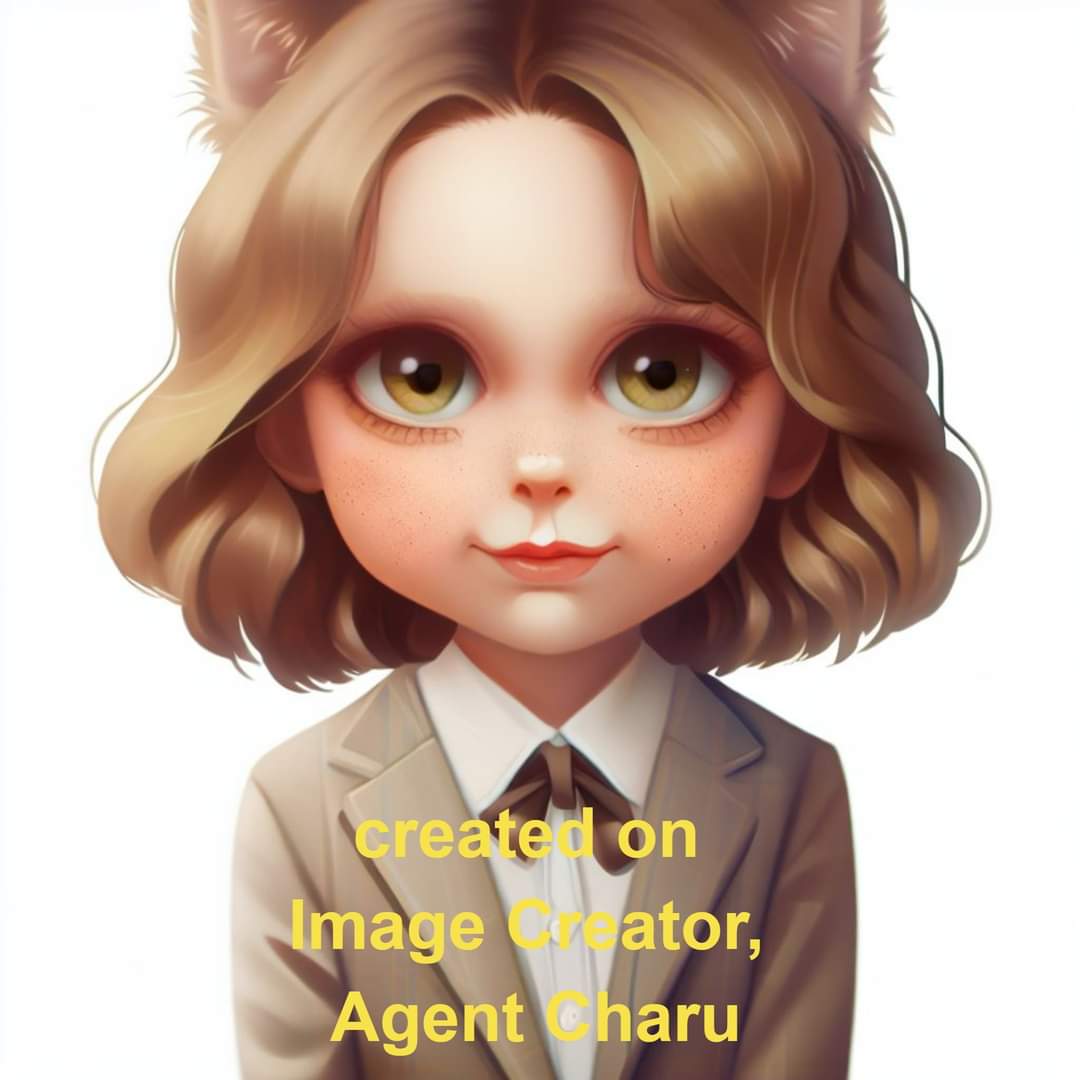
CAT File 2 : ニャンダリズムとワビサビファンシー
CATの2本目です。
アメリカのドラマの刑事物っぽくしたい願望と、死なない、大怪我しない、深刻にしない、でこうなりました。
000. CAT: Chasm Adjustment Taskforce
C.A.T. とはChasm Adjustment Taskforceの略であり、人間界における境界事象を専門に扱うネコビトの警察組織のごときものである。ネコビトはネコビト自身が境界事例の典型ではあるが、猫がテキトーで自由気ままなようにネコビトもある程度適当で気ままなので、あまり突き詰めるべきではない事例を適当にうやむやにし、うまく真面目な人間の世界になじませる役割を担っている。これは彼女らの物語である。
「はい、CAT。」
たまたま電話を取った署長の沼田が、受話器を耳に動きを止める。
「はぁ…扱っていますが…ええ、一反木綿?いまどき?いいですけど…あ、シュローディンガーはうちの担当じゃないです、人間のアートな方面で見てるはずです。え、ネコビト疑惑?はあ…ええ…」
捲し立てる電話の相手を落ち着かせるように相づちをうちながらメモを取る。マヌルネコビトの署長はネコビトにしては苦労が多い。
001. ちゃるママの証言

ちゃる捜査官の母親の分地はちゃる捜査官と同じくネコビトで、引退した元CAT捜査官だ。普段は人間として仕事をしているので、時々電車に乗る。
「でさ、どうもおかしいんだよ。頭を抱えたり貧乏ゆすりしたりして、怖い顔してなんかぶつぶつ言ってるんだよ。で、私は扉とカバンの間で爪を出してたんだけどね。」
ちゃるママは手足と顔の半分が白い黒猫で、ちゃると同じ金色の目をしている。現役時代からの習慣で公共交通機関では必ず左右に逃げ場のある扉の近くに立つ。満員の電車では視界が遮られにくいように座らないことの方が多い。
「そいつの顔つきが急に変わってさ。」
ちゃるママは、ちゃると遮無の顔を交互に見やりながら深刻な顔つきで言う。
「ほう。そして、そいつが凶行に及んだんだな。」
遮無が珍しく手帳を引っ張り出しページを繰りながら、同じように真剣に答える。
「で、いったい何をしたんだ。」
「おばあさんに席を譲ったんだ。」
「なんだ、普通じゃないか。」
「そうなんだけどさあ。なんかさ、あれはタダゴトじゃなかったんだよね。」
「まあ、分地ちゃんのカンはわかるんだけどねー当たり外れが激しいからねえ。」
「言うねえ。」
遮無と分地は元同僚なので、会話に特に遠慮はない。そこへ、ボリュームあるボディを上質な生地のスーツに身を包んだ沼田署長が通りかかる。
「あら、分地ちゃん、おひさ。」
「ああ、署長!ご無沙汰してます。こないだ、ネットの『グレイスタイル』に出てましたよね?」
「あらやだ、なんでUSハイミドル向けのファッションページをあなたが見てるのよ。」
「同じ号でテンテイルズが特集されてたもんで。好きなんですよ。」
「あの歌手の?渋いわねえ…」
そこからは沼田署長とちゃるママのテンテイルズ談議になり、遮無は苦笑して手帳を閉じる。ちゃるは書きかけのメモ帳に「10シッポ」と書き加え、遮無に「オヤツをとってきていいですか」と聞き、ヤモリだけは事務所のペットだからとらないようにとだけ言われて出ていく。CAT本部は平和に通常営業中である。
002. 文豪の家のニャンダリズム

「これは…ニャンダリズムかにゃあ」
黒い巻き毛に、丸い目を濃いアイライン囲った女性が、散らかった室内を検分しながら言う。
「繰津さん、もう一度正しく」
若干訛りがあるものの、正しい日本語を話す金髪の女性が、繰津の猫語戻りした日本語を正す。青木と繰津は、かつて広く世に知られた文豪が住んでいたと言う大昔の豪邸に来ている。休館日で締め切られた大きな日本家屋は、その空気に若干の湿り気と黴と、他に数種類の臭いが入り混じり息が詰まる。「立ち入り禁止」札とロープの向こうには畳の部屋があり、その奥の床の間にかかった巨大な掛け軸が、真ん中から大きく外へ向かって破れている。
「バンダリズム」
「意味は?」
「わざとモノを壊すことにゃ。だが、どうかにゃ…あっちは経年劣化じゃにゃいかな。さっさと一反木綿見つけて帰るにゃ。」
その破かれた大きな掛け軸の大きな紙は、障子破りを卒業した年齢の大人猫でも何か無性に掻き立てられるものがある。障子への破壊衝動は本猫、ネコビトに共通した強烈な衝動だ。その障子破りの衝動と戦う年齢であった頃には障子のある国に住んでいなかった青木は、少し動揺して、前肢で顔を洗いたくなる。だが、そこはヒトの姿で来ているので、青木は眼鏡を押し上げる動作でごまかし、咳払いをして少し高めの声でいう。
「掛け軸はこの通りの破れようなのに障子は無事ってことは、犯人はネコビトではないようですね。」
「うーん、そうだにゃあ。ここの住宅の保存会は大げさにはしたくにゃいそうだし…ネコビトが関係にゃいんなら、我々で捜査すべきものにゃのかね。そもそもこっちに来たのは一反木綿の目撃談があったからなんだし、そっちの捜査に戻るのがいいと思うにゃ。」
「Hum...しかし、被害者が100年前の死んだ文豪では、ストーカー傾向のファンってわけでもなさそうですし…ということは、生きてる人間のバンダリズムってことで、事件性はないかもしれませんね。」
「うーん、幽霊同士でのストーカーかもしれんがにゃ。」
「Ha.それでは我々の管轄外ですね。わかりました、空飛ぶ布の保護に戻りましょう。」
「いや、幽霊ストーカーなら面白そうかもしれんにゃ…頑張ればにゃんとか捜査対象に…」
「Noo, 幽霊同士のストーカーなんて面倒ですよ、カンバーサムです。」
「でも楽しそうだにゃ。しかし、この掛け軸、にゃんと書いてあったんだろうにゃ。」
「破れちゃって読めませんね」
「うーむ、説明書きには『仁を成す』と書いてあるってにゃ…身を捨てても人に尽くせって内容が想起されるにゃ。南洲さんかにゃ。」
「この解説の漢字は見当たりませんが…『人』、と、『く』ってところは残ってますね。」
「しかしまあ、ずいぶん派手に破ったにゃ…」
「Anyway,資料館に元の写真か何かないか聞いてきましょう」
青木も繰津も文学に興味がないわけではない。特に繰津は、何代か前の先祖がまた別の文豪と親友であった。その某文豪はドイツ語の教師でもあり、故に繰津の姓もドイツ語所縁である。該当の文豪氏はいつも貧乏ではあったが、本人用の酒と猫用のおまんまだけはどうにかして手に入れていたそうだ。そういう話を聞いて育っているので、繰津は作家全般に親しみを感じている。故に、この屋敷の持ち主についても、「シャイで優しい人のような、でも変なとこでキレる変わり者でもあったそうで、よくわからんにゃ」と追加情報をキキコミなしでも出してくることができる。
しかし、二人には、どうも気になることがもう一つある。
「By the way, 繰津さん、私があくまでも第二言語の日本語を使い続ける理由はお判りでしょうか。」
「ワシが英語が下手だからにゃ。」
「繰津さん、趣味で英日翻訳してるじゃないですか。」
「古典ホラーばかりにゃ。で、青木ちゃんはあの隅っこで寝ている入れ墨だらけの青年が気になるのかにゃ?」
「ええ。不法侵入で逮捕でよいでしょうか。」
「いいけど、触りたくないにゃ。ダニが付きそうだにゃ。」
003. まんまるファイブの歌う人とすねこすり

立ち入り禁止の座敷にある年代品のソファに、上半身裸のタトゥーだらけの40がらみのニンゲン男性が寝ている。百年前の日本人の体格にあわせて作られたソファは明らかに彼には小さく、投げ出された足はほぼ床の畳の上にある。その大きな足は泥だらけだが、その足元には彼が着ていたと思われるTシャツが敷いてある。Tシャツには白地に可愛らしいウサギのキャラクターの絵が描かれているが、そのキャラクターは男性の足についていた泥で汚れている。一応、床を汚さない気づかいはしたらしい。
「にゃあ、あれって、最近すごく売れている外国バンドの歌うオスビトじゃにゃいか?」
「Ah, yeah, ほんとだ、しかし、繰津さんの最近はここ十年くらいですか。」
「当然にゃ。まんまるファイブはお気に入りにゃ。あれは歌係アンディにゃ。」
「へえ、名前までおさえてるなんて意外です。で、まんまるアンディ、どうします?」
「酔いつぶれて入ったかにゃあ。そういう歌もあったけど、歌だけかと思ってたにゃあ。まあ、セレブなんてものはみんな破天荒なもんだにゃ。」
「まんまるファイブ…」
「あと、昨日は…この沿線にある遊園地に恋人と行ってたみたいだが。このネットニュースに載ってるにゃ。」
そう言って繰津捜査官は最新式のスマートフォンの画面を青木に見せる。
「Hum…美人モデル彼女とお忍びフワモコ王国デート…よし、やっぱり逮捕しましょう。」
青木は最近、遠距離恋愛の相手の人間と別れたので、若干カップルには厳しい。一方の繰津は、お気にいりの歌を作っているポップスターを逮捕できるとあって楽しそうだ、
「間男を撃っちゃった歌、歌ってもらってもいいかにゃ?」
「拘置所でならいいんじゃないですかね。」
「だめ!たいほ、だめ!」
物陰から小さな生き物が叫びながら飛び出す。仔猫のようだが、少し猫背が過ぎて丸い。そして、明らかなる妖気が立ち上って周囲の空気を青く染めている。
「おおーすねこすりっ子か。まあ、にゃんとも可愛いらしい!」
「How cute! すねこすり、研修で見ましたが、本物に会えるとは!Hi, 坊や、タトゥードホットガイのファン?」
「逮捕ダメ!命の恩人にゃの。」
「ええ?」
興奮気味の小さなすねこすりの仔猫を前に、繰津と青木は顔を見合わせる。
004. テンテイルズだったらよかったのに

「テンテイルズだったらよかったのに」
「ママ、まんまるファイブも聞くでしょ」
「聞くけど、別に歌う人のファンじゃないんだよねえ。やっぱり、テンテイルズだったらよかったのに」
ちゃる捜査官ママは同じ言葉を繰り返す。CATの留置所は頑丈には作られているが、比較的快適にも作られている。しかし、あまり使うことがないので、檻の外側は普段は机と椅子とソファとテレビと電子レンジと冷蔵庫のある「簡素な」休憩室として使われており、だいたい数人のCAT捜査官がたむろしている。ちゃるとママは檻の外側に、檻の内側には珍しく人間がいる。人間はまんまるファイブの歌う人である。
まんまるファイブの歌う人は、まだ寝ている。二日酔いなのだろう、時々唸ったり、無精ひげの伸びた顎をさすったりする。そして、周囲に若干のアルコールの香りを放っている。
「二日酔いだろうなあ。」
「くちゃいね」
「うん、くちゃいね。どっか窓は開かんのかにゃ。昔は開いた気がするんだけど。あんまり気にしたことなかったからにゃあ。」
言いながらちゃるママは壁のエアコンをいじり、換気のスイッチを探すが、見付からないので冷房を入れる。
CATビルの一画に厳重に作られた檻の中の男性を眺めながら、ちゃる捜査官ママはちゃる捜査官のニンゲンの学校の宿題を見ている。ちゃる捜査官は人間としてはまだ小さいので、内容ではなく字の丁寧さを指摘されての再提出が多々ある。ちゃるママはそれが気に食わないが、「世の中に合わせるのも大事」と自分に言い聞かせて宿題の内容に目を通す。その葛藤で若干逆立っていたちゃるママの毛が、いったん落ち着く。
「あれ?ここ、答え書いてにゃいよ、珍しい。」
「んーわからにゃくって。1と2は、黒猫数えでは4でしょ。じゃあ、3の存在ってにゃんにゃの?」
「数えてるひとじゃにゃい?」
「ああ、にゃるほど」
ちゃる捜査官はそれでさっそくお気に入りのきらきらした鉛筆で人間用「計算ドリルノート」に答えを書き込む。ガチャリとドアが開いて、遮無捜査官がのぞき込む。
「ねえねえ、『ねこちぐら』あいてる?」
「1カゴあいてるけど、どうしたの?」
「アレルギー反応で化け猫化しちゃったネコビトがいるの。エピペン打ったけど、今朝もまだヒト型に戻れないで、パニック状態でひっかくんだよね。」
「あら可哀そうに。」
「にゃにのアレルギー?」
ちゃる捜査官が金の瞳をキラキラさせて尋ねる。
「ワサビだと思う、昨夜、銀座の高級すし店で日本酒と中トロでいきなり発症。ネコビト姿と完全猫フォームの間を行ったり来たりで、精神状態もかなり不安定だよ。幸い、店長さんがネコビトとなじみがあって、宅急便でオリを急遽届けてね。今朝、秘密裏にこちらへエスコートしたよ。」
遮無がてきぱきと答え、振り返って「空いてるってーこっちこっちー」と声をかける。すると数秒してから、試着室サイズの大きな籠を担いだ大きな男性が入ってくる。大熊さんだ。
CATビルの隣にはプロレスのジムと事務所があり、大熊さんは普段はそこにいる人間のプロレスラーだ。ジムでトレーニング中の大熊さんを、CATの沼田署長が「ちょっと休憩がてら美女を救いに行きましょ」と連れ出したのだ。救われた美女は大きな籠の中で、ヘアレスなネコビト姿でシャーシャー怒っているので、美女の面影は今のところない。しかし、人助けが好きな大熊さんはにこにことしている。大熊さんはとても優しい人間なので、助ける相手が美女でもおばあさんでもおじさんでも、多分あまり変わらない。
「ごめんなさいね、大熊さん、うちの署長がご無理を…」
「いいんですよ、軽いし。しかし、このネコビトさんは僕の師匠に比べると全然、迫力がないですねえ。」
「このネコビトが軽いのはヒト姿だとスーパーモデルだからなのよ、美人よ。ところでお師匠のカリンさん、元気してる?」
「師匠ですか?すごく元気なんですが、かえってパワーが有り余ってるみたいで。現役復帰を考えてるようです。」
「あらら、だめよ、彼女がネコビト全開で現役復帰したら死人が出るわ」
会話を交わしながら、沼田署長が拘置所オリにネコビトを移すと、彼女は途端に完全なヒト姿に戻る。
「ノン!アンソニー!」
彼女は細長い腕を柵越しに隣の房の男性へ伸ばすが、アンソニーとよばれた男性は起きずに鼾をかいている。彼のまったく反応のない様子を見ると、スーパーモデルはがっかりした様子でネコビトに戻り、前足で顔を洗う。と、完猫姿に変わり、隅に丸くなって寝てしまった。
「彼、けっこう飲んでたみたいよ。」
「だから泥だらけでくちゃいのかな」
ちゃる捜査官は好奇心に目を輝かせて鼾の男性を見やる。
「ああ、そうそう、昨夜、人を轢いたかもって、ニンゲンが人間の署に出頭しているそうです。これがドライブレコーダーの記録なんですが、これにバッチリすねこすりがうつってるんでこっちに連絡がきました。こっちにコピー送ってもらいますね。」
「あ、それ、僕だ」
色の白い可愛らしい男の子が、ちゃる捜査官の隣でペロリと舌を出しながら手を挙げる。コータ君は、ダルマ事件以来のちゃる捜査官の友人である。今日は一緒に宿題の日だ。
005. すねこすりビト・コータくんの怖い話

「あ、いたいた、これ?」
「うん。それがぼく。」
「あ、飛び出した、左右みないと」
「ほら、突進物あると止まっちゃう。すねこすりってほんと行動パターンは猫だよね。」
「あ、ここ!」
コータ君が興奮気味に指を指す。画面上では、真っ暗い道路上の小さな白いものをかっさらって飛び去る大きな白いものが写っている。
「おおーまんまる男、えらい!が、ほんとに彼か?」
ネコビト一堂は持ち込まれた小さなモニターの前に集まってちょっとした観賞会をしている。
『バッチリばっちりすねこすりがうつってる』ドライブレコーダーの映像を皆で見ながら、何人かはメモを取る。
「でもなんであんなところに…」
「僕ね、怖い話を思い出しちゃって。根田さんに会いにいこうとしたの。」
「怖い話って?」
「だめじゃないか、子供が夜出歩いちゃ」
「でも、すねこすりは妖怪だし…」
「こーたくん、すねこすりだったんだね。じゃあ、学校は?」
「行ってるよ。おとうさんが人間でね、学校の先生なんだよ。」
「夜中に出かけたことをおとうさんは知っているの?」
「ママに会いに行ったんじゃないか」
「いや、根田さんだよ」
「根田さん寝てるんじゃないか」
その場にいた大人ネコビトたちが口々にその意見を口にし、籠の中ではまだパニック状態のスーパーモデルが猫に戻って威嚇し、拘置所は騒然となる。
困り顔の大熊さんが、議論を続ける大人猫たちの隙を見てドアから滑り出し、とはいえ、大熊さんは大きいので、ちゃる捜査官とコータ君に見つけられ、二人も一緒に拘置所ルームから抜け出す。そして、隣のジムの入り口で大きな筋肉の塊が目の前を通り過ぎるのを眺めながら、3人で自販機でアイスクリームを買い、食べ始める。
「大熊さん、最近、根田さんところに来ないねえ」
「ごめんね、トレーニングがきつくて。」
「かりりんししょー、厳しいもんね。」
「ダルマ達が寂しいって。」
「そうだ、根田さんがした怖い話ってなあに?」
ちゃる捜査官が、思い出したように捜査官の表情に戻ってコータくんに聞く。コータくんは、美味しそうにかじっていたソーダアイスから口を離して、視線を落とす。そして、ポツリと小さな声で言う。
「うーんとね、パンダルマンが狙われてるって。」
それで驚いたのは、リングネーム・パンダマンとして活躍する大熊さんだ。
「ええ、僕が…?」
「ううん、パンダマンじゃなくて、パンダルマン。絵本の方」
「えほん?」
「ああ、パンダルマン!人気だよね、パンダルマン。」
「うん、流行ってるよね」
「ねー」
大熊さんは、話の内容についてはいけないながらも平和で可愛らしい会話に笑顔で頷く。そして、アイス食べながら子供達の可愛い会話に癒されているところに、物陰から強いオーラを感じて背筋を伸ばす。振り返れば恐ろしい形相の師匠、オオヤマネコのカリンがいる。
「にゃんだ、パンダマン、ここにいたのか。アイスは食うならプロテインにつけろとあれほど…あ!ちゃるにゃん!」
恐ろしいオオヤマネコのマスクをかぶっていることになっている、素顔でオオヤマネコのカリンが低い声を3オクターブあげてちゃる捜査官を呼ぶ。先の一件以来、すっかりカリンは可愛らしいちゃる捜査官のファンになっている。ちゃる捜査官のほうも、新しいトモダチができた感覚でいる。
「カリンちゃん、こんにちは。コータ君もいるよ。」
「そうかあ、今日はかわいいお友達も一緒なんだ。コータ君っていうの?」
「うん、僕、コータ!パンダマンとパンダルマン、大好きなの。」
「そうかあ、嬉しいなあ。かわいいファンをもったなあ、よかったな、大熊ちゃん。」
ヤマネコ顔のままカリンが微笑み、その物凄い様相にコータ君の背中から一瞬青い妖気が沸き立つが、それが怯え故なのか興奮故なのかは、ちゃる捜査官にもパンダマンこと大熊さんにもわからない。
やがてカリンも自販機でアイスを買うと、3人に加わる。しばし、学校の話題や、パンダマンの絵本であるところの『パンダルマン』について盛り上がるが、ソーダ味のアイスを食べ終わるとコータは声のトーンを落として言う。
「あのね、怖い話ね。根田さんね、『パンダルマン』も『ヤマネコのかりりんししょー』も狙われてるって、言ってた。」
「狙われている?私とパンダマンが?めちゃくちゃ強いのに?」
「フワフワモコモコにもつよい?」
「フワモコ…?!」
「根田さんが、フワモコ王国が二人を狙ってるって…」
自分自身が若干フワモコ気味なコータ君は、青ざめて唇をかむ。
006. フワモコ帝国化計画

根田さんは不労収入でおおいに儲けているのに、健康とワビサビ賛美のために神社の警備員として働く不良老人だが、最近、ネットの地域経済界隈でささやかれる、フワモコ王国での不穏な動きを察知したそうだ。
「なんとまあ、『パンダルマン』を可愛くしてキャラクターとして売り出そうって言うんだ。まあ、最近の大熊くんには女性ファンも多いし、その二次創作『パンダルマン』、売れるんじゃないかねえ。」
「我々ミニダルマも登場しますかねえ」
「ふわふわスイートなミニあたし…素敵…」
根田さんと、警備員室に棲んでいるミニダルマの二人は企画に前向きなようだったが、それがすねこすりのコータ君には許せなかった。
「根田さん!『パンダルマン』がフワモコスイートになってしまったら、全然強くないしかっこよくないです!ワビでもサビでもない!いやだ!」
そういってコータが泣くので、大熊さんのかわりに最近よく来る犬上さんが、慌てて自分用に買ってきたお団子を差し出す。
「きなことみたらし、どっちがいい?」
「みたらし」
「しかし、ふわもこ王国、しぶいキャラクターに手を伸ばしますね。」
「『パンダルマン』と『化け猫かりりん』、『灰色まるるん』。敵がサルとか狸とか、『モリアガッテコー教授』とか。」
「大丈夫、『パンダルマン』以外は可愛くしようがない。」
「でも僕心配です…ムクツケーキーズ戦記や、奇談・しぶしぶの猫茶碗が、フワモコほのぼのストーリーにされてしまったら…」
「大丈夫だよ、あんなのをフワモコ王国に入れたらモコリンたちが怖がるから、きっとキャラクターはいじらないよ…」
心配でたまらないといったコータ君を、根田さんが慰める。
「しかし、国宝の茶碗もフワモコぬいぐるみにされてしまう時代ですしねえ…」
「犬上君はどっちの味方なんだ。」
「すみません。」
「すみません、警備員さん!」
つるつる頭のお坊さんと、きっちり七三分けの神主さんが警備員室の扉を勢いよく開いて入ってくる。
「あ、鶴田さん、寿知美さん。どうなさったんですか。」
「それが…喧嘩です。ご高齢の外国人男性と、若者の…」
「けが人がいます!救急車を」
「それはいけない!でんわでん…あ、携帯ここか。」
根田さんは手にしたハイエンドな大画面携帯からネットニュースを消し、救急にかけようかと考えつつもカメラを起動させながら外に出る。
007. ご高齢の容疑者

「ええ、その根田さんってじいさん、誰かに殴られたのか?」
マスクと偽っての素顔のカリンは、口周りについたアイスクリームをペロリと舐めながら楽しそうに聞く。正義感の強いカリンは、かたき討ち相手がいそうだとみるとつい楽しくなってしまい、温和な大熊さんはいつもひやひやしている。
「ちがうよう、ちゃんと聞いててよう」
ネコビトのカリンが、オオヤマネコの顔のままなので、コータ君もつい、若干モフモフでまんまるな瞳になり、ぷくりと膨らませた頬からはほの青い妖気が漏れる。メモ帳を片手に真剣なちゃる捜査官は、真面目に状況を整理する。
「ようするに、『パンダルマン』のえほんをフワモコ王国がアニメにするのね、で、外で誰かが誰かを殴った。」
「そう、おじいさんが、若いもんを殴って気絶させたの。」
「殴ったのは根田さんじゃないですよね。だって、コータ君としゃべってたんだし。」
心優しい大熊さんが心配そうに聞くと、コータ君は満面の笑顔で答える。
「うん、根田さんは関係ないよ。一生懸命野次馬写真撮ってたよ。僕、携帯持ってないけど、根田さんが何かに載せたって言ってた。」
「へえ」
カリン師匠は大熊さんとのつながりからSNS上で根田さんともつながりがあるので、さっそくスマホを操作して、根田さんのページを表示させる。神社の苔むした岩、ムクロジの実、孫とのツーショットの写真が並ぶ中に、長身でハンサムな高齢の男性が映ったものがある。写真の中でその男性は腕組みをして不敵に笑い、周囲を黒服のムクツケキ大男たちと、善良な一般警官が取り囲んでいる。
「あ!」
ちゃる捜査官は息を呑む。
「にゃんだ、ちゃるにゃん、知り合いか?」
「…テンテイルズだ!」
「テンテイルズ?」
「このおじいさん、ママの好きな歌手です!」
008.繰津の慨嘆
「そもそもだ。我々がまんまる入れ墨男を捕まえたのはまったくの偶然で、本来は地元警察からのはぐれ一反木綿保護の依頼に寄った次第じゃなかったのか。」
疲れた様子の繰津が、青いクラシックカーの助手席でぼやく。
「ええ。そう聞いてますね。」
運転席の三ツ池は、半ば上の空で同意する。都会の裏路地を走り抜けながら、三ツ池の目は「かもしれにゃい運転」と、その他気になる事もあり、忙しい。
「アイツ、二日酔いで伸びてて歌ってくれそうにゃいし。一反木綿の目撃情報があった古民家。ニャンダリズム、この辺なら我々の所轄でもいいにゃ。」
「はあ。ニャンダリズム。用語としては楽しそうなんですけどね。」
「にゃんで、関係のないまんまるファイブやらテンテイルズやら、外国の人間大物歌手ばかりにゃのだ。一反木綿や幽霊のニャンダリズムなら、ぎりぎり我々の所轄内でもいいにゃ。でも外国人は違うにゃ、しかも大物なら外交問題にゃ!ネコビトじゃない、人間の所轄にゃ!」
繰津は嘆かわしげに半ば爪の出た手を宙に振って訴える。三ツ池は、その大袈裟な様子に苦笑しながらも、調子を合わせる。
「まあ、テンテイルズは若い人はあんまり知らないでしょうからねえ。その時点で境界事件でもいいんじゃないですか。それより、今日発売のフラ…」
「ちょっと前のってだけで境界でいいなら、オペラ歌手や落語家も引っ張りたいにゃ。」
「それさすがに無理でしょうけど…でも、鉄道車両への落書きの通報なら来てます。そこのナビにGPSで場所も出てるでしょ。たぶん推定シュローディンガー、実はニセモノですが、どうします?そこならフラペチーノ屋さんもちか…」
「にゃあ、ままよ!落書の現場検証へ!いざ!阿日ちゃんと丘斜も呼ぶにゃ。」
「丘斜は検視官ですよ、誰も死んでにゃ…」
「車両の美が死んだのにゃ!いいからよぶのにゃ!」
「そんな無茶苦茶な。まあ、クルツさん、忙しいとパニクりますよね」
三ツ池が笑いながら言い、ハンドルをきる。と同時に繰津の携帯から着信音が流れ出す。『カルミニャ・ブラーニャ』の不気味な合唱だ。繰津は嬉しげにそれに4小節くらい耳を傾けてから、おもむろに電話にでる。
「はい、繰津!にゃに?聞こえん!え?一反木綿!?どこだ!?GPS?あ、ああ…この、ニャビに出てる赤い点だにゃ?三ツ池ちゃん、追えるか?」
「はいよ!じゃ、赤色灯お願いします!」
「にゃ!」
繰津がようやくにやる気を取り戻した様子でバックシートへ身を乗り出して赤色灯を掴む。三ツ池の車は狭いので、赤色灯は後部座席に置いてある。
「あ、一反木綿の点、消えた」
「にゃにぃ!?」
「大丈夫ですよ、別に捕まえたってわけでもないんでしょうし。じゃ、やっぱシュローディンガーいってみよー」
三ツ池は鼻唄を歌いながらハンドルをきる。
009.取調室の大物

テンテイルズは、取り調べ室のパイプ椅子が一流デザイナーの作品でもあるかのように見せる不思議な風格で腰かけ、くつろいでいる。そして、まるで新曲について語るかのように落ち着いて、何千万ものファンがいる声で自分の行動について語る。
「ああ、彼のガールフレンドへの態度が酷かったんだ。君もそこにいたら、彼を殴っていたに違いないと思うよ。そう…君はひどい男を自分で殴れるタイプの女性だね。だが、あの男のデート相手は、君みたいな女性ではなかったんだ。わかるだろう?」
テンテイルズは青木に微笑みかけ、青木は軽い目眩を憶える。英語が第一言語というだけの理由で取り調べを任された青木は、そのオーラに圧倒されて、ついサインを頼みたくなるのを我慢する。
「それでは、テンテイルズさん、貴方は蕎麦屋の行列の男を殴ったということでよろしいですか。」
その問いかけに、テンテイルズは目尻に深い皺を刻んで微笑み、一度視線を、自分の開いた手のひらに落としてから青木に向ける。
「私は妻を愛している。」
「はあ、good for you.」
「それに娘がいるんだ。孫娘もいる。女性をあんな風に扱う男には我慢がならない。」
「あんな風に、とは?」
「並んでいる間に、服装から店のチョイスまでを非難するんだ。口調があまりに荒いので始めは、彼女が何か悪事でもしたのかと思ったくらいだ。驚いて私が通訳に訳してもらい、何か不都合でもあったのかと聞いてもらったあたりで、男は、お前のせいだと言って女性の額を指ではじいた。しかも、何度もだ。彼女は痛いと言っていると通訳が教えてくれたので、今度は私が直接注意した。するとさらに声を荒げて女性を責めるので、やむなく私が殴ったんだ。」
「ええとですね、そういうことは警察に…」
「うん、そうだったかもしれない。それで解決するのだったらそうすべきだった。私が早計だったかもしれない。それでは、この国では執拗にガールフレンドの額を指で弾く行為は暴行と認められるのだね?」
「あ、いや…」
確かにそれはデートDVの気配はするが、デコピンくらいでは人間の警察は動かないだろう。青木はインテリゲーションルームの部屋の壁を引っ掻きたくなり、それを察したテンテイルズは微笑んでシェイクスピアを引用する。
「All the world’s a stage. And all the men and women merely players. (この世は舞台、そしてすべての男も女も役者に過ぎない。)君も君の役を演じている、君の本当の心情は私と共にあって、あの瞬間には共に彼を殴っている。大丈夫、わかっているよ。だから気にせずに調書を取りなさい、私は私で責任を取る。だが、数日後のコンサートはどうしたものか…」
「コンサート…!?」
「ああ、三日後にここで、来週とその先には名古屋と大阪でコンサートを予定している。ワールドツアーの最中だから、あまり長い足止めは困るんだが…」
青木の脳内で、想像上の繰津が「そんにゃらクズ雄を殴るにゃ!」と絶叫するので、青木は「失礼」と言って部屋を辞し、トイレへトイレットペーパーを引き裂きにいく。
青木が取調室を出ていくと、テンテイルズはポケットから丁寧に折りたたまれた紙を取り出す。
「さあ、君にもそれなりの役割を演じてもらわないといけないかもしれないぞ」
010. フワモコ王国の女王

フワモコ王国とは、国際的に人気の高いキャラクター、「ハニー・バニー」と「マカロン・キトゥンズ」その他のキャラクターのグッズ展開を繰り広げる株式会社である。そして、同名の遊園地も「ハニー・バニー」ファンの聖地として世界中から観光客を集めている。その「フワモコ王国」の裏手、雲と城のセットの裏の、やはり城を模した形のビルに、フワモコ王国の女王のオフィスはある。
「ああ、あたくしのフワモコ王国…パンダルマンを筆頭にシブシブのワビサビ界隈も作って国立の博物館辺りでコラボをと思っていたけれど…だめ、今は何も考えられない…」
白くて曲線の多い家具で装飾されたロココ調のオフィスでは、すっきりとした形にフリルをセンス良くあしらったスーツの、美しい中年女性がハイヒールで歩き回っている。彼女は苛立たし気に流行色のリップを塗った唇を噛む。そして、バラの香りのエアスプレーを部屋に撒き、それを吸い込んで気を落ち着ける。
「どうしよう、テンテイルズ様が…逮捕されちゃった…ううん、モコ、なかにゃい…」
壁際の豪華な金の額縁の中には、20年前くらいの年齢で描かれたテンテイルズの肖像が収まっている。なお、彼女の名誉のために注釈を加えると、この肖像画自体が、彼女のテンテイルズファン歴20周年を記念して20年前に描かれたものなので、彼女は決してテンテイルズ氏を鯖読ませてはいない。実際のところ、ファン歴40周年記念には新たに肖像を注文する心づもりだ。しかし、その前にワビサビ界隈の実現が控えている。肖像画が新しくなる前に、フワモコ帝国は拡充されるだろう。
テンテイルズの肖像の隣には比較的現代的な額縁に収められたフワモコ王国の旗艦キャラクター「ハニー・バニー」の油絵、その隣には「パンダルマンと化け猫カリリン」の原画がかかっている。そして、彼女の机の上には、渋く現代風にアレンジされた国宝のイラストや、ワビサビ度の高い写真が所狭しと並んでいる。
「あら、望子ちゃん、どうしたの?」
扉を開けて入ってきた年配の女性は、白髪を結い上げて淡い色の着物の訪問着を着ている。
「あらうれしい、パンダルマンの絵をかけてくれているのね。」
「お、お義母様!みゃ、みゃさか!じゃ、じゃなくてでですね、これはあの…」
望子は焦った。義理の母トラの90才の誕生日プレゼントに、フワモコ王国にワビサビコーナー追加し、義母の好きなパンダルマンをメインに据えようと考えているなどとは、ここで知られる訳にはいかない。サプライズは本来であれば望子の得意とするところだ。
「え、ええとですね、これは…」
「もしかして、テンテイルズのこと?残念ねえ、まだ若いのに。人を殴るなんてねえ。ああ、パンダマンは別よ、彼はそういう仕事だから…」
テンテイルズは70代だが、現代の高齢者は若い。ひとまず、自分のフワモコ王国の帝国化計画から目を逸らし、ついでに自分の混乱も収めるために、不破望子は義母に泣きつくことに決めた。
「お義母様、あたくし、もう耐えられない!」
「まあまあ…こんな時は甘味よ…」
さめざめと泣く望子と、パンダマンこと大熊の関取時代からのファン、義母トラは、ロココ調のオフィスを後にして馴染みの和菓子屋へ向かう。
011. 車両基地の不良たちの善行

「すみませんでした!」
髪を金や茶色や紫に染めた若者たちが、車両基地のバラストの上で繰津と三ツ池に土下座する。見れば、まだ十代後半から二十代前半、やんちゃが生き甲斐のご年齢だ。膝が痛そうなので、繰津はとりあえず3人を立たせて言う。
「いや、掃除はいいことにゃ。でもにゃ、我々に謝ってもしかたないにゃ。」
住宅地に近い鉄道の車両基地では、いかにも落書きをしそうな風体の若者たちが、落書きをきれいに消した容疑で逮捕されている。彼らは地元でも有名なやんちゃ者たちらしいが、なぜか徹夜で車両の落書きを消し、車体を拭き、でもその電気系統には手を出さずに、軌道付近の草むしりを夜明けの時間帯にしていた。不審に思った近隣住民が通報し、駅員たちが不法侵入で常人逮捕し、あちこちとたらい回され、本来はシュローディンガーのヴァンダリズムとして調査する予定だったCATに今はお鉢が回ってきているので、現在、沼田署長がCIAに調査依頼中だ。
「もう二度としません!」
「だから、もう、あんな…」
そこで言葉を詰まらせた大きなピアスの青年が、崩れ落ちるようにして地面に額を擦り付ける、
「あーもう、ほら、立つにゃ…」
青年達が言う事を聞かないので繰津は困り果ててポケットから「ゴマ煮干し」の袋を取り出し、再び五体投地での土下座する若者たちに背を向けておやつタイムを始める。ゴマ煮干しをかじりながら、あちらで手持無沙汰な人間の男性警官に手を振る。ヒト姿の繰津はそれなりに美人で可愛いので、警官は照れたような笑顔で手を振り返す。
「あーこちら三ツ池。シュローディンガー、消されちゃいました。ええ、きれいさっぱり、しかも車両丸ごとツヤピカです。もう、事件性なしでいいっすかね?ええ、鉄道けいさ・・・そっちで話付けてくださいよ、我々はニンゲン担当じゃないし。」
『うう、そうねえ、でも今外務省が…』
携帯電話の向こうで沼田署長が弱りはてた声でうなるので、三ツ池は少し気の毒になって続ける。
「ああ、幸い、ここの基地には防犯カメラ付いてるんで。じゃあ、こっちで見て、境界性なしだったら人間にわたすってことでいいんじゃないですか。あ!」
三ツ池は、視界を白い布らしきものが横切るのを見る。
「繰津さん!いた!一反木綿いた!追います!」
「ああ!ほんとにゃ!」
「ひぃいい!」
善行で逮捕された不良青年たちは身を寄せ合い、いかにも恐ろしいものを見たかのように震える。
「これ、かりるにゃ!」
三ツ池は派手な髪色の青年たちに声をかけ、太いタイヤの自転車にまたがると猛スピードで漕ぎ出す。
012. 黄色いネコビトとフラペチーノ

白い布は確かに飛んでいる。ひらひら、ひらひらと、青い空に流れる雲のように、漂う蝶のように。一反木綿には猛スピードで後方で自転車を漕ぐ三ツ池に気が付く様子はない。三ツ池の方も、周囲に気を配る余裕はない。信号を守り、道路標識に従って、路側帯では危険なのでできるだけ車両用の道路の隅を行く。
「ああ、埒があかんにゃ!」
「私がいこう!」
「だれにゃ?!」
三ツ池の横を走ってすり抜ける黄色っぽいネコビトがいる。三ツ池はその気配に気付かなかったことをほんの少し悔しく思いながらも、そのスピードに目を見張る。黄色いネコビトが見せた身分証と、既に数メートル先へ移動してしまったスピードに、三ツ池は彼女に任せることに決める。GPS発信器をそのネコビトに投げ付けて自分はスピードを緩める。GPS発信器は彼女の尻尾にくっついたようで、三ツ池は自分側の端末にその位置が表示されるのを確認すると、駐輪場を探す。ちょうど流行の発信地、若者の街の再開発されて使いやすくなった駅前だったので使用料高めの駐輪場がすぐ見つかり、三ツ池はその位置を本部に送ると鼻唄を歌いながらGPSで表示された道を辿る。が、それが表示している位置が隣駅なのに気が付いて駅へ引き返す。そして、駅前で本日解禁の季節限定フラペチーノを買い、電車に乗る。三ツ池はネコビトビジネスニュースで見て以来、ずっとこのフラペチーノが気になっていた。
013. シュローディンガーのネズミ

「へーい、お待ちぃ」
「遅い!」
三ツ池がGPSが止まった所にようやくたどり着いた頃、明るかった空は少し明度を下げ、太陽はビルの向こうにある地平線に近付いていた。場所は大通りから1本入った路地である。かつては賑わっていた様子だが、現在ではシャッターを下ろしたままの店が多い界隈だ。そこに、疲れた様子の人姿のネコビトと、絵の具まみれの女性と、その絵の具を熱心にウエスで拭き取る童顔の男性がいる。シャッターに挟まれた店舗の壁には大きな絵が描かれており、その絵はパンダマン風の大男のシルエットと、ダルマ風の警官、そして大きな値札の絵が描かれている。絵具まみれの女性がネコビトと対峙しながら、後ろへ声をかける。
「セドリック、今はやめて」
「でも…」
「相手はネコなのよ、なめちゃだめ」
女性は抑えた声でいうと、セドリック君の手を彼が熱心に拭いていた細いムチのようなピンクの尻尾から振りほどく。三ツ池は息を飲む。ローデンティア、つまりネズミビトだ。よく見ると女性の顔からは細く細かい髭が、もう一人の茶色いパーカーを着た青年の顔からは茶色いヒゲが生えている。そして、あちらでテーザー銃を構えている黄色いネコビトは、チーターなのだろう、背は高いが細作りな体格をしていて、かなり疲れた様子だ。
三ツ池は状況がいまいち理解できなかったので、ポケットからスマホを取り出すと写真を撮り、それからチーム向けに動画を送る。そして、位置情報と季節限定の鯖の味噌煮フラペチーノの感想を追加する。
「これだれ?あと、サバフラうまい」
「アート系クライム担当の知多さんだよ」
「鯖ちょっと私には甘いかな」
「それ、ネズミ帝国の人?」
「シュローディンガーぽいにゃ」
「男の子、映画出てた気がする」
などの勝手な感想が着信し、チームがこちらへ向かっていることがわかる。三ツ池の目の前には、壁に描かれた値札の絵と、緊張感に満ちた3人がいる。
「その手のウエス、生きてない?」
沼田署長の一言コメントに、三ツ池ははっとする。セドリック君の手に握られたウエスは確かに、風もないのに激しくはためいている。それで三ツ池は鯖の味噌煮フラペチーノを美しい花の描かれた配電盤のうえに置き、茶色いパーカーを着たセドリック君の後ろに回り込む。三ツ池がセドリック君の手元の布をじっくり観察すると、拭き取られた絵の具がその布のうえでくるくると動き、「たすけて」と文字をつくる。
「ほんとだ、生きてる!あ、さっきの一反木綿…?」
三ツ池が思わず声をあげると、女性のネズビトが振り返る。オードリー・ヘップバーン風の美人だ。そして、セドリック君は確かに映画に出てた人に似てる気がするが、多分違う。主人公ではなく、そのサポート役のものすごくいい人の役だった。が、多分違う。
「セドリック君、その布、くれにゃい?アタシが追ってたのそっちなの。」
「へ?」
「その布さあ、はぐれ一反木綿として通報があってさ。保護区に返さなきゃならんの。」
三ツ池が説明すると、セドリック君は拍子抜けしたようににっこりする。
「ああ、いいですよ。」
「セドリック!」
「動くな!」
「まあまあ、ちょっとみんな落ち着こうや」
一気になごむセドリック、緊張感に満ちたネズビト女子、疲れて早くカタを付けたい知多を、早くフラペチーノに戻りたいを三ツ池が整理する。
「あんたら覆面アーティストのシュローディンガー?で、多分知多さんはなんかの関係で追ってるんだよね。」
知多とネズビト二人は頷く。
「で、アタシはね、あんたらと関わるとまた署長の仕事が増えるんで、その一反木綿だけ、預かりたいの。自分で捕まえたことにして帰っちゃダメ?」
「あ、えっと、だめじゃにゃいけど…」
「ええ、汚しちゃったけど、どうぞ。でも気を付けて…」
セドリック君は人を和ませる笑顔で三ツ池に一反木綿を差し出す。
「でも、気を付けて、それ…あ!」
一反木綿は目にもとまらぬ早さでセドリック君の手から飛び出し、三ツ池の顔に巻き付く。
「あ!すみません!もうそんな元気ないと思ったのに!どうしよう!ビアンカ、と、そこのチーターっぽいネコビトさん、助けて!」
セドリック君は大慌てで二人に助けを求める。
014. 瞑想とEAT PLEASE
せめて蕎麦を食べてから殴りたかった、というのがこの国の麺類を愛する伝説のロックスターの正直な心情である。有名店ではないものの、ファンからのお勧め度が高く、ついでに近くの神社兼寺には有名な宗教美術品まであるという。そちらも見たかった、しかし、今はこうして狭い室内の折りたたみ椅子の上で座禅を組んでいる。ダーリン、なぜ?問いかける妻の顔が浮かぶ。ああ、すまない、実は…いや、紳士は言い訳などしない…
珍しく集中できないので、うっすらと目を開けて現世に戻る。と、小さな仔猫と、仔猫っぽい何かがが2匹仲良く座禅を組んだ膝の中で寝ているので、テンテイルズは驚いてほほ笑む。気付いてみれば、室内には素敵な出汁の匂いが充満し、机の上にはもう湯気の上がっていない大きな器がある。その中の蕎麦は延び切っているが、横に割りばしが置かれ、その包みには子供の文字でEAT PLEASEとかいてある。
「さて、子ネコビトと子ネコ風スピリットと蕎麦…」
小さい子供を起こさないように伸びた蕎麦を食べるという難題に伝説の男は嬉しそうに笑い、着ていた高級ブランドのカーディガンを二匹にやんわりかけると、器に手を伸ばす。様々な国の数々の有名店で味わったいかなる料理よりも、この伸びた蕎麦は珍しく、食べにくく、そして、やはり、味は蕎麦なのでそれなりには美味い。
015. 曇った視界とサバフラペチーノ

三ツ池は曇った視界と思考を振り払おうと、頭を数度振ってみる。しかし、何かが張り付いたように、視界は相変わらず白っぽく、ぼんやりとしていてはっきりしない。まるで霧の中で運転しているようだ、と考える。そして、強烈な衝動がある。何か、それが何かがわからない。声が聞こえる。
『見なさい、そこに疲れた人がいます。』
三ツ池はぼんやりした視界の中、周囲を見回す。心配そうな茶色いパーカーのネズビト、手錠につながれた、絵の具まみれの美しいネズビト、げっそりと疲れた様子の細長いネコビト。ああ!アタシは親切にしたいんだ!三ツ池は考える。どこからともなく聞こえる声が、三ツ池に指示を出す。
『さあ、あの花の絵の上に、元気の出るドリンクがあります。あれを分け与えなさい。』
「嫌だね。」
だが、善行への欲求は強烈で、三ツ池はポケットからハンカチを取り出すと顔にペンキの付いた女性ネズビトへ投げつける。
「おねえちゃん、これで顔を拭きな。」
ネズビトは驚いた顔でそれを受け取り、横の黄色いネコビトはうんざりした様子でこちらを見ている。三ツ池は考える。何かが顔に張り付いている。再び、声が聞こえる。
『見なさい、あのアスリート風のネコビトは疲れている。あの給水所で見るようなドリンクを分け与えるのです。 』
残念ながら三ツ池は、分け与えるように指示された鯖の味噌煮フラペチーノをとても気に入っていた。そして、上司以外に指示を出されるのは嫌いで、鯖フラ以外の善行の機会が見当たらないのにもイラついていた。
『さあ、そのドリンクを…』
「嫌だっつってんだろ!鯖フラペチーノはアタシのだ!」
三ツ池は苛立ちに任せて顔に張り付いた何かを引き裂く。
ギャアアア、と引き裂いたその何かから叫びが聞こえたきもすりが、それよりも引き裂いた何かをかなぐり捨て、自分の置いた鯖フラペチーノのカップへ飛びつく。
「アタシのサバペチ!」
緑のストローに吸い付いて、一口すする。そして、動きを止める。
「ああ…溶けてる…」
三ツ池は、とけてぬるくなった鯖フラペチーノは、甘すぎてあまりおいしくないと判断する。そして、面倒くさそうに腰を下ろしている知多に声をかける。
「ちたさん、飲む?糖分、要るっしょ?」
「ああ、もらうけど…サンクス。大丈夫?」
「へいき。じゃ、署で話聞く?」
署長ゴメンと頭の隅で考えながら三ツ池が言うと、鯖ペチーノで少し元気を回復した知多が言う。
「そうしたいんだけど…なんかさあ、我々、囲まれてるんだよね。」
知多は三ツ池にもらった鯖フラペチーノを吸い上げながら、路地の奥でこちらの様子をうかがうCATメンバーと、その反対側の出入り口を固めた屈強そうなネズミビトの兵隊たちを見回す。
「ああーこりゃやばいね」
三ツ池は路地の左右で、自分達を挟んでにらみあうCATとネズビト兵士を見比べて言う。特に、ネズミ兵士は、ちゃる捜査官が読んでいた「ムクツケーキーズ戦記」の兵隊のように強そうだ。皆、筋肉で満ち満ちている。
「何これ、あんた、ネズミ王国のお姫様?」
三ツ池は、鯖ペチの評価を脳内で星4つに落としながら、美しきネズミビトに聞く。
「ち、ちがうっ!私はアー…」
「っと、!ち、違います!ぼ、僕の新刊の宣伝です!」
人好きのするセドリック君は必死に大声を張り上げる。
「ぼ、ぼく、絵本のパンダルマンで絵を描いてるんです!」
「え、あの、勝手な二次創作から子供に大人気になって、カリンさんが若干キレてた絵本?」
「あ、あれは出版社がなかなか会ってもらえないけどカリンさんの『いんじゃね?』の一言は頂いてるからたぶん大丈夫だと…」
「へええーね、アタシも出してよ」
「いいですよ」
「やった、美人に描いてよね」
「あ、それは…」
三ツ池とセドリックの交渉は続き、それを緊迫したネコビトとネズミ兵士達が見守る。
016. 米子トラ

「フワモコ王国」裏の擬似ロココ調の豪奢な部屋では、テンテイルズの肖像の下の長椅子で、不破望子が涙に暮れている。
最高級ティッシュをそっと渡しながら、米子トラはやさしく語りかける。
「ねえ、もこちゃん。わたしね、お話があるの。」
テンテイルズ逮捕の衝撃もさめやらぬなか、望子はティッシュ流れたマスカラを拭きながら向き直る。
「はい、お義母さま、なんでしょう?」
望子は義母が大好きだった。数十年前、夫が『やはり恐怖です』という根拠不明の書置きを残して失踪してからも、ずっと義母は望子の支えだった。こうして、テンテイルズが捕まった時にも安心して泣きつけるのが、義母だった。
「あのね、もこちゃん。わたしね、人間じゃないの。」
「ええ、存じておりますわ。フィーラインの御家系でいらっしゃることは…」
トラは困ったように微笑む。
「わたしの息子…いえ、ひ孫がなんと言ったかは知らないけれど…」
「ひ、ひ孫?」
「わたしね、ええと、来月で90じゃなくて、200歳になるの。」
「に、200?!」
「あとね、わたし、ネコビトじゃなくて…」
「200ならもっと盛大に!」
「いいの、いいの、そっちはいいの。」
「でも…」
「まあ、いいから聞いてちょうだいな。わたし、ローデンティア、つまりネズミビトなの。」
「ええええ!?だ、だって偉大な絵本作家の米子トラさんといったら…」
そしてようやく、不破望子は気付いた。小柄な義母に時々、ネズビト特有の細い煌めくヒゲが発現すること、真珠の輝きの前歯、常に数人は控えている厳めしいボディーガードにもヒゲがあること。そして、義母の代表作が『おむすびコロリン』『ねずみの嫁入り』『ねずみがえしと与太郎』であることに。
「おおおおおお義母様!で、では、あのネズミ帝国の…?」
「いいえ、わたしは慎ましい大和ネズミです。ああいった帝国主義的な…いえ、違うの、そこじゃないの。わたしね、困っているの。ネコビトのあなたの助けがいるの。」
「ね、ネコビトの?」
望子は驚きとパニックの中でも、義母が珍しく自分を頼ってくれることを嬉しく感じている。
017. 取調室の隣のうるさい部屋
一方、CAT本部では、テンテイルズの取り調べが続いている。
「あああああ……誰だテンテイルズ様に蕎麦を…」
取り調べ室の隣のマジックミラーのこちら側では、青木とちゃるママと沼田が、緊急用爪とぎ用藤テーブルを、それぞれの理由から破壊している。取調室の観察室はちょっと込み合った観覧席になっている。
「あれ?蕎麦ダメだったか?」
カリンがあっけらかんと言うと、暇そうな阿日が助け船を出す。
「アレルギーの報告は上がっていませんな」
「うーん、テンテイルズに蕎麦アレルギーは聞いたことはない、が…まあ、あったかい蕎麦だったみたいだから大丈夫かなあ…ワサビとか…」
テンテイルズファンのちゃるママは我が子の上で蕎麦が食べられているのも、我が子が大詩人の膝の上で寝ているのも気が気でならない。目を離した隙に子供二人に取調室を乗っ取られた青木はグレーの毛の下で青ざめ、震える声を絞り出す。
「なんで!子供が2匹、紛れ込んでるんですか!」
「ちゃるちゃん、捜査官じゃろ。青木さんがインテリコワモテ、ちゃるちゃんでかつ丼作戦でで和ませて自供、と思ったんじゃが…」
「What a heck is かつ丼作戦?!」
「ああ、かつ丼作戦てのは…」
「根田さんはなんで参加しているんですか」
「アタシが呼んでみたんだ。根田さん、蕎麦打ち得意だっていうし。」
「わしの手打ちじゃやっぱりまだ素人かのう。一応、近くの店で習ってるんだけど…」
「へえ、粉からお打ちになってるんです?」
「うん、でもむずかしいんだよ、粉もいろいろあって…」
青木が人間形態で青ざめている横で、根田さんがそば打ちのコツについて阿日に説明し始める。場がだれてきたころ、緊急出動のアラームが各ネコビトのスマートウォッチから響き始める。
「あ、やばい!ちゃるの端末!」
「大丈夫、まだ持たせてないよ。」
「あ、いや…私のお古を持ってます。」
マジックミラーの向こうでは、ちょうど食べ終えて椀を置き、ごちそうさまのポーズを取っていたテンテイルズ氏が何かに気づく。カーディガンをそっと持ち上げて膝の上に声をかける。仔猫と仔猫風すねこすりが飛び降り、ネコビト形態になると笑顔で嬉しそうに会話を始める。テンテイルズ氏も笑顔でそれに答える。
「こっちは大丈夫そうだけど。あんたら、出動しなくていいの。」
毛を逆立ててマジックミラーに張り付いていた沼田と青木にカリンが声をかけると、二人は阿日が「どうぞ」と言って開いたドアから飛び出して行く。
「ちゃるままはいかないの?」
「んにゃ…元・捜査官なんで…今は一般人だし…」
ちゃるママはテンテイルズと笑顔で言葉を交わす我が子に意識を奪われて、カリンの言葉はほとんど耳に入らない。
018. バカップルとトラのタトゥー
「にゃんでこうにゃるのだ!バカップルに監視なんかいらんにゃ、もう街に放流でいいにゃ!」
CATの留置所では、柵に隔てられた見目麗しい中年のポップスターとスーパーモデルが、「ごめんよ」「あたしも」を繰り返していて、監視の繰津を苛立たせている。
「まあまあ、繰津さん、落ち着いて。大丈夫ですよ、沼田さん、帰ってきたら手続きなさるっておっしゃっていましたよ。」
大熊が優しくなだめるが、繰津は緊急呼び出しに従って現場に向かえなかったことでさらに苛立っている。
「ムリにゃ!三ツ池は勝手に消えるし、テンテイルズは子供と遊んでるし、まんまる男は彼女とロミジュリごっこにゃ!毛玉が出る!!」
「ろ、ロミオとジュリエットは悲しいけど素敵な…」
「あれは思春期真っ只中の少年少女だから可愛くて哀れな話なのにゃ!二日酔いの髭中年がやっても可愛くにゃい!」
「はは、うける」
隣でまったく関係ない動画を見ながら、耳だけはピクピクと動かしながらで聞いていたカリンが笑う。柵の向こうではそんな中年が甘い会話を交わしている。
「ああ、済まない、パトラ」
「もう、アタシがネコビトだと知っていると思ったのに…」
「いや、まったく…それで驚いて…」
「え、マジで知らなかったの?じゃあ、その腕のトラは誰なのよ?!」
「え、ええ?」
「そのトラのタトゥー、付き合いはじめてから彫ったじゃない、あたしじゃなきゃどこのネコビトよ?!」
そしてスーパーモデルは再びお怒りネコビトモードに入る。
「ご、誤解だ!こ、これは僕の好きな絵本から…」
「絵本?!」
「く、クラシックかつクールなんだよ?」
「はぁ?子供の本が?」
「さ、最近シュローディンガーがパロディを…」
「へえ。シュローディンガーはクールね。どんなの。」
「ええとね、トラがネズミの友達のために巨大な牛と勝負する話で…そのパロディの絵をシュローディンガーがトラの保護区で描いたんだけど、それでトラ保護の機運が高まって…」
「ふうん、イケてるじゃない。それで?どんな絵なのダーリン?」
「なんだ、仲直りか。」
カリンがつまらなそうに言い、繰津がまた面白い反応をしないかと期待をそちらに向けるが、繰津は静かだ。
「トラ…ネズミ…」
「どうしました、繰津さん?」
「よにゃご…よにゃ…にゃああ!よにゃごトラ!」
「よ、米子トラさん、ですか?」
「そうにゃ!絵本作家にゃ。」
「ああー懐かしい。僕、『ネズミと空豆の木』が好きでした。」
「空豆は木にならんよにゃあ…じゃにゃくて、まんまる男の腕によにゃごトラの絵があるってことでいいにゃ?」
「あ、確かに!」
「おお、米子トラか。干支戦記、アタシも好きだった。そういや、ムクツケーキーズも似たような…」
「ああ、干支戦記、僕も好きでした!」
「おお、さすがアタシの弟子。」
「こ、光栄です…!」
感動に打ち震える大熊と、満足そうな師匠カリンにもうんざりし、繰津は「このバカップルが逃げないようにみとけにゃ!」と言って出ていく。
019. ネズミ兵士と姫と眠い知多

「みなさん!」
可憐なネズミ姫、ビアンカ・シュローディンガーの一声にネズミ兵士がざわめく。
「よいのです…いいの、退いて!退くのです!…ここは一度、猫に膝を折りましょう…くやしいけれど、大丈夫、きっと…」
張りのある声でネズビトの姫は、臨戦態勢のネズミ兵士達に呼びかける。青ざめたビアンカは美しく、ネズミ兵達が慕うのも十分理解できる。いちどは構えを解くが、ビアンカに知多が歩み寄ると、逞しい一団には再び緊張感が走る。
「さあ、この通りです…抵抗はしません。」
ビアンカは殊勝にも絵の具がはえる真っ白く細い腕を差し出して知多を待つ。
「いやね、別に逮捕とか…しないから。たしかに手錠はかけたけどさあ…だって、ひっかくんだもん。」
「え、逮捕しないの?」
知多は首を降って、三ツ池に「おたくは?」と聞く。
「ウチは、いったん沼田署長に聞かないと」
「ウチは捜査官への暴行で一応形だけ逮捕するけど、まあ、私を引っ掻いただけだしねえ。すぐ釈放。起訴されないよ」
「え、逮捕するんなら正体ばれちゃうし、起訴とか…してくれるとハクがつくんだけど…」
「そうなの?起訴する?でもめんどいから逮捕もしなかったことにしたいし、正体バレないよ?それでも、逮捕起訴コースにする?」
「あ、僕はちょっと。一応子供向けの絵本作家なので…」
「セオドリック、裏切るの?!」
「ええと…あ、ウエス!」
先ほど三ツ池が破り捨てた白い布が、力なくヒラヒラと宙を舞い、細かく千切れて別れる。かと思うやいなや、それは一斉にいならぶネズミ兵士たちに襲いかかる。
「うわぁぁぁ!!」
ネズミ兵士は悲鳴を上げてそれを振り払うが、細かく引き裂かれた白いものはそう簡単には掴めない。いかついネズミ兵士のひげ面に次々に白い布の切れ端が張り付く。途端に兵士の顔つきが変わり、それぞれの方向へ駆け出していく。そして、誰も居なくなる。
「にゃんだったんだ…?」
「あの様子…もしかしたら…」
「ちぃっ!!裏切り者めらが!!」
「ビアンカちゃん、落ち着いてっ、でもごめん、でも…」
「ああ、セオドリック…お前は良いのです、パンダルマン作者が逮捕じゃ、やっぱりだめだもの…。でも、エクスペリメンタル・ラッツが…消えちゃった…」
「ねえ、じゃ、手錠を外すからとりあえず一緒に来てよ、逮捕もしないから。こっちはあんたの作品の贋作の山で困ってるの。」
「贋作?」
「贋作ね。クオリティはアレなんだけど、ほら、憧れてたり投機対象だったりで、山ほど贋作が出来てるんだよね。いちいち調べるの、めんどいの。本人が来て分けてくれたら楽じゃん?描いた、描いてないって…」
「でもそれって自白になっちゃわにゃい?」
三ツ池が思い付きを口にしたとたん、知多が恐ろしい目付きで睨む。
「あ、やべ…ところでさあ、築地に今度、マグロのカマペチーノってのが…販売され…」
「魚はちょっと…それよりはチーズかな…」
知多が睨みつける中、限定商品が実は好きなビアンカ姫はついつい話に乗ってしまう。
「僕は甘味なら、やっぱりパンダルマン白熊が…」
知多はビアンカから外した手錠を三ツ池とセドリックにかけ、さらにそれを自分の足首につないで横になり、寝始める。どうやら、走りすぎて相当疲れたようだ。
020. テンテイルズのしっぽ
CAT本部の取り調べ室では、テンテイルズが、子供たちにヨガのポーズを教えている。子供たちは笑いながらそれをやすやすとやってのけたり、失敗してひっくり返って笑ったりしている。ちゃるママは、それをマジックミラーのこちら側からうっとりと眺めている。これって記録してるよね、あとでコピーもらおう。いや、もらえなかった時のために、動画撮っとこう。そんな呟きを脳内に収め、音声の出力を上げて自分の携帯で音も撮りやすいようにする。と、気づくことがある。
「あれ?ちゃるにゃん、英語しゃべってない…これは、猫語…?」
ごくごく自然に3人は猫語を喋り、ごくごく自然にポージングの補助に尻尾を使っている。
ちゃるママは録画を止める。
「やっぱり…テンテイルズのユキヒョウ説はホントだったのか…きゃーテンテイルズのしっぽ、ふわふわ…」
マジックミラーにぴったりと張り付き、なるべく尻尾や猫目がうつりこまないようにして写真を撮る。ファンの気配りと、それでも携帯の待ち受けにはする気満点の狭間である。
「ああ、ちゃる祖父が焼きもちやくかな…」
と、突然にガチャリと音がして取調室観察室の扉が開き、繰津が「フギャアア」と叫びながらなだれ込む。
「な、な、なに?あ、えと、かれはあの…」
しかし、繰津はテンテイルズの尻尾には気付かない様子で、むしろ部屋が無人でなかったことに若干気まずそうだ。
「あ、あら、ちゃる捜査官のご母堂、いらしたのね…」
「ええ、まあ、今日はお休みの日なので…」
「ちゃる捜査官には申し訳にゃいけど、テンテイルズを『ちぐら』に召喚してもいいかにゃ?バカップルの供述取っておきたいにゃ。」
「ええ、では、そのように・・・」
繰津は壁のボタンを押して、マイクで取調室の中へ声をかける。
「ちゃるりん、ここ借りていい?まんまるの供述とりたいにゃ」
了解の合図をちゃる捜査官は返し、テンテイルズとコータ君を外に促す。コータ君は楽し気に、テンテイルズは悠然と取調室を出ていく。
「あ、手錠もかけずに…」
「まあ、大丈夫にゃ。紳士は逃げにゃいのにゃ。」
ちゃるママは、ひそかに尊敬する繰津に心の中で敬礼する。
021. 現場からは以上です
『米子トラの作品とパンダルマンの類似性が気ににゃル。のと、アオキ、カムバック。』
と、繰津から皆のメッセージツールに送られた頃、CATの他のメンバーはそれぞれにシュローディンガーの身柄確保や壁画、スプレーペイントの写真撮りなどで忙しかった。
「知多さん、起きてよ、車で寝ていいから。スーツくしゃくしゃだよ」
遮無がスーツのまま路上で猫様態に戻って鼾をかく知多を起こそうと体をゆするが、まったく無視で知多はかえって丸くなる。
「あーもう。ほっとこ。青木さん、いこ」
「うーん、CIAから来てる割には気分屋だ…」
青木は、取調室の次の間にいたカリンを思い出しながらつぶやいた。
「Why 大型ネコビトってゴーイングマイウェイばかり……so maverick…」
あちらでは三ツ池がビアンカとセオドリックを任意で同行すべく、フレンドリーに話しかける。
「ねーねー、ビアンカちゃんはリアル鯛焼きチーズ味とかなら食べるの?」
「あ、僕、それ好きです」
「ほんとー?セオドリックは鯖フラは?」
言いながら三ツ池は手錠を外し、二人を自分の小型クラシックカーへ案内する。
一方、沼田署長は鳴り始めた携帯電話に旧友の名前が表示されているのを見て嬉しそうに応答する。最近、外務省やCIAからの電話ばかりで飽き飽きしていたので、少しテンションが高い。現場を囲んでいた警察車両に乗り込む。
「ああ、モコちゃん?!おひさっ!どうしたの?」
沼田署長は望子とは中学校の同級生である。しかし、不破がテンテイルズファンであるとこはいまいち把握していないので、ここのところのSNSの投稿が泣いている猫だらけで少し心配はしていたのだ。
「て、ええ?義母の孫が行方不明って…?ええ、探せるけど…今ちょっと…」
「すみません、署長。」
車の反対側のドアから遮無が呼び掛ける。
「なに?いま…」
遮無の緊張した面持ちから何か大きな事が起きていると察し、沼田署長は車から外を覗く。大勢のネズミ兵士が、現場に戻りつつあった。それぞれに、うつろな顔をして重い足取りで、中にはなにか唸り声をあげている者もいる。だれた現場に緊張感が走る。
022. 通じない繰津の英語
「Thou, who didst hurl thy mortal frame beneath the wheels possessed of their own will, in a desperate bid to save the fabled beast Sunekosuri—didst thou then shatter the leaning gate of the ancient manor, driven by... by what, pray? Speak, or be forever damned in thy silence.」
(汝、伝説の魔物すねこすりを救わんと疾走せる自らの意思を持ちし車輪の前に身を投げ出さんが後、ええと、にゃんだ、いにしえの屋敷の傾ける扉を破りしか。)
二日酔いの上半身裸の男性は、人間姿の繰津が呪いの言葉の如き英語を強い猫訛りで話すのを聞いてぽかんとしている。繰津は繰津なりの語彙で事情聴取をしようと努力はしているが、自分の古典ホラー文体に偏った英語ではポップスターには通用しなさそうなことをすぐに見て取る。
「What are you even talking about? Did I do something? Where’s Patra?」
(いったい何をいっているんだ?僕は何かしたの?パトラはどこだ?)
困惑した様子のポップスター、まんまるファイブのアンソニーは英語で次々に質問を繰り出し、繰津はその質問の意味は理解できるが上手に返せない。
「Thou hast trespassed upon forbidden ground, and thus findest thyself ensnared. Declare now—by what cause didst thou defy the ancient interdiction, and for what dark purpose? Speak, O prisoner of our grasp, or else shall—
Mrrrowrgh!
(汝、不当に禁じられし領域に足を踏み入れん、故にかように囚われぬ。いついかなる理由にて禁忌を犯さん。答えよ、我等が捕囚よ、さもなくば⋯)
にゃああ、英語で取り調べはむりにゃ!青木はどこにゃ!」
「ねえねえ、テンテイルズに訳してもらえば?」
「WOW!」
繰津の横で目をキラキラさせながら聞いていた仔猫姿のちゃる捜査官が突然喋ったので、アンソニーは驚いて飛びのく。
「静まりたまえ、汝の眼前に座すもまた懲罪官…じゃにゃい、調査官…」
「No!! This cannot be real!!」
「ほらー混乱してるよ」
「彼女のネコビト発覚の時もこういう反応だったのかにゃあ、それはパトラちゃん可哀そうにゃ。」
「パトラちゃん、さっきテンテイルズと仲良くお喋りしてたよ。パトラ talk テンテイルズ」
「What!? THAT Tentails!? The sexy old grandpa!?」
「おや、にゃんか慌ててるにゃ。テンテイルズはイケジジだからにゃあ。パトラちゃん、惚れちゃうかもにゃあ。」
繰津がにやにやと笑いながら言うと、ちゃる捜査官も嬉しそうに付け足す。
「ママもかっこいいって言ってますにゃ」
「よし、彼に通訳させるか…」
床に手をついてショックを隠せない様子のアンソニーに、人間姿になった可愛らしいちゃる捜査官が頬笑みかける。
「テンテイルズ、translate your English するよ」
突然出現した小さい女の子に英語で話しかけられたアンソニーはさらに驚く。
「What…!?」
023. リターン・オブ・ザ・エクスペリメンタル・ラッツ

虚ろな表情の大きなネズミビト兵達が姿を現し、のそり、のそりとCAT捜査官達とアーティストな姫と絵本画家を取り囲む。中空を凝視す目は濁り、彼等の手にはなにやら長い棒や金属光沢で光るものがある。また、布やマスクや手袋で全身を被っているものもある。そして、一向に姫の呼び掛けにこたえようとはせず、ただ、ゴーストタウンのようなシャッター通りに、低い呻き声のような呟きが満ちる。
「エクスペリメンタル・ラッツ!!何故こたえない?!」
ビアンカ姫は声を振り絞るが、その声も呟きにかきけされる。その不気味な声はまるで地の底から響いてくるようだ。と、マンホールカバーがガタガタを鳴り始め、CATを取り巻く輪は一段と小さくなる。CATとネズビト二人は、壁画の前にじりじりと追い詰められていく。
「なぜ?!何故なの、お前たち?!」
「危ない!!」
何か棒状の物を持ったネズミ兵士が壁画の前に追い詰められられたビアンカに突進し、セオドリックがビアンカを突き飛ばし、セオドリックを庇って三ツ池がその上に覆いかぶさる。その上をネズミ兵士が乗り越えていく。
「いて!あ、シッポ踏んだにゃこら!!」
シッポを踏まれた三ツ池は怒りのキャットクロウを繰り出す。
「いてえ!あ、すんません!」
叫んでネズミ兵士は、傷から吹き出す血にも構わず壁へ突き進む。壁の前ではネズミ兵士の隊長と思しき男が声を張り上げる!
「わんすもあ!!まいふれんど、わんすもあ!!」
それに答えて、ネズミ兵士たちが額に青筋を立てて怒号を上げる。
「落書き厳禁!」
「ノーブロークンウィンドウ!!」
そして、一斉に洗剤や落書き落としスプレーを壁画にかけ、デッキブラシで擦り、雑巾で拭き始める。先程まで見事に壁を飾っていたパンダルマンの壁画が、みるみる削りおとされていく。
「ああ、私の作品が…」
ビアンカ・シュローディンガーは膝から崩れ落ち、わっと泣き始める。
「あなたたち…私のファンじゃなかったの…?」
一方で、それぞれにファイティング・モードのお怒り猫スタイルをとっていたネコビト達はあっけにとられて武装解除し、黙ってネズミ兵士たちが壁画をきれいに掃除して消し去るのを眺める。
「にゃんなの…あ、三ツ池ちゃん大丈夫?」
「おんなじにゃ…あの不良青年たちと…」
何かに憑かれたように壁をこすり、しまいに生垣のごみ拾いまで始めたネズミ兵士たちを見ながら、三ツ池は呟く。
「おんなじ…ちょっとズレた善行…アタシに憑いたやつだ…」
024. いったんモーメント
三ツ池は爽やかな清掃活動に移り変わった現場の雰囲気の中で、疑問をぶつけに沼田署長と青木のいる車へ近づく。
「ねー青木さーん。あれ、ほんとに一反木綿?」
「Ah, just a moment, please. 」
「そうね、三ツ池ちゃん、いったんモーメントよ。ちょっと見て。」
青木の言葉にかぶせて、沼田署長が青木ののぞき込んでいるモニターを手で示す。
「署長…お洒落なハイミドルにダジャレは似合いませんよ。」
「あら、可愛いダジャレはお洒落でチャーミングなのよ。それはいいんだけど、ねえ、この失踪者…さっき似顔絵を署待機中の阿日ちゃんに描いてもらったんだけどね。あそこにいない?」
「あ、セドリック君だ。でも、わかんにゃいですよ、似顔絵だけじゃ。失踪者って、どこのだれですか?」
「友達の義母の孫なの。行方不明だそうなんだけど…ヨナコ・ライスプディング・セドリック。あそこにいる子に見えるんだけど、それじゃ都合良すぎよねえ。」
「うん、似てるけど、ネズミビトの見分けはネコビトには難しい…映画の脇役にも似てるし。でも、あいつ、セドリックってネズミ姫が呼んでましたよ。」
三ツ池が泣いているビアンカを慰めているセドリック君をみやりながら言う。青木も似顔絵と見比べながら三ツ池に同意する。
「ヨナコ・ライスプディング・セドリック。やっぱりセドリック君だね。姫のお守り役みたい。」
「あいつ本名で活動してるのか、ノンビリさんだなあ。で、ねえ、あれ、ほんとに一反木綿? 一反木綿って一日一善活動とかするの?」
青木は視線をセドリック君から外して周囲を見回すが、その真面目な表情の探る先には答えはない。
「私は妖怪に詳しくないからわからないけど…たぶんしない…が、わからないなあ。こういうのは繰津さんに聞いた方がいい。あれ? 繰津さんは?」
「留守番でまんまるファイブの監督をお願いしているわよ」
沼田署長は笑顔で答えるが、青木は頭を抱える。
「あああ、Kurz san、きっと怒ってる…」
「あれ、繰津ちゃん、まんまるファイブのファンじゃないの?」
「曲を聞くだけで、歌ってる人には興味にゃいんですって」
「へえ、そういうのもあるのね。」
「じゃ、ネズビトさん二人と知多さんを回収して帰っていいですか?」
「そうね。清掃ラッツは…まあ、社会奉仕を止める道理ないし。疲れたら勝手に解散するでしょう。」
025. ネズミと猫と藪の中Ⅰ ビアンカの証言
――お名前は?
私は、ビアンカ・シュローディンガー。これは逮捕じゃないんでしょう? だから、本名はちょっと…言えないわ、それでいいのよね? ああ、この一覧ね、ちょっと時間を頂戴。うーん、この絵とこれは私じゃないわ。セドリックが関わったのはあまり多くないわね。もう少しちゃんと私のを調べて。エクスペリメンタル・ラッツの記録が結構ちゃんとしてるわよ。エクスペリメンタル・ラッツ? ああ、彼等は私の親衛隊というか家来というか、我が家に代々支える…ああ、これ以上はいえないわ。
――セドリック君とはチーム?
ええ、セドリックとはここ数年チームを組んでいるわ。いえ、チームというのかしら。彼、描くのにはあまり参加していないのよ。でも、彼の絵はなんというか、人の心をつかむのが上手いわよね。私も好きよ。
私の絵はちょっと皮肉が利きすぎていて解りにくいといわれているのだけど、彼はそういう時にはかみ砕き方をアドバイスしてくれるわね。彼はでも、私の皮肉な絵や、絵に相応しい場に描きに行く私のスタイルが気に入っていたみたい。それである日、どうやってか、私が絵を描いているところにやってきて弟子入りを志願したわ。私は目立ちたくなかったから、適当にごまかしてその場を去ったら、次の現場に大げさな脚立とリュックサックいっぱいのスプレー缶と着替えをもってそこに現れたの。それで、私は弟子は面倒だから次の現場を見つけられたら、作品を持ってこいと言ったの。彼は絵本を持ってきたわ。
彼の絵はいいんだけど、あんまりコラボすると私のスタイルが崩れちゃうから、いつも相談したり、実際描くのはアシスタント程度にしか参加してもらってないわね。彼は彼で、絵本というフィールドに政治的な絵の空気を持ち込むわけにはいかないから、あまり参加しすぎてもね。今回も、パンダルマンに値札をつける絵だったけど、その辺は一切彼は関わってないの。ただ、使っていいか聞いたり、どうすれば格好良く見えるかは聞いたわ。マッチョは見慣れすぎちゃって、どうやったら格好よく描けるかわからなくなっちゃって。うん、冷蔵庫を格好よく描けっていわれたら困る感じ。
――保護区のトラの絵に米子トラは関わっている?
いいえ。米子トラは、私が個人的にファンなの。だって、ネズミの女の子が活躍する絵本なんてあまりないもの。今回は、テンテイルズがトラとかユキヒョウとか、大型猫の危機を訴えていたから…かっこいいなと思って。え? ああ、でもほら、彼は人間だし。べ、別に私はアンチネコビトってわけじゃないし。うーん、でも、まんまるファイブのアンソニーだったらネコビトでも付き合えるな。彼はかっこい…え? いるの? ここに?! 会いたい!!
026. ネズミと猫と藪の中Ⅱ セドリックの証言
――にゃまえは?
あ、セドリック・ライスプディングです。え? 本名じゃなくていいの? すみません、じゃあ、ペンネームの「パンプディング」でお願いします。え、どっちでもいい? そうですか、はあ。
――画家にゃのか?
はい、僕はお祖母ちゃんの影響で絵が好きで…あ、おばあちゃんというか、ひいひいお祖母ちゃんくらいなんですが、僕を育ててくれたんです。お祖母ちゃんが絵を教えてくれました。お祖母ちゃん、趣味で絵を描くんです。
――お祖母さまの影響で絵本を?
お祖母ちゃんが読んでくれた絵本が好きで、僕も絵本を真似して絵を描いていました。あと、キャラ物も好きで、「ハニー・バニー」グッズを集めてます。ハニー・バニー、うさぎなんですが、なんか…思い出すんです、干支戦記の指導者、白鼠姫を。繊細で、かっこよくて、でも立派なリーダーで。そして、憧れのシュローディンガーに会いに行ったら、ビアンカさんでしょう? まるでリアル白鼠姫! もう、僕は彼女についていくしかない、これは運命だと。
――セドリック氏の失踪届が出てるけど?
やっぱりおばあちゃんの影響で、大熊丸のファンなんです。それがパンダマンになったと聞いて、僕の情熱に火が付いたんです。僕もビアンカ・シュローディンガーのパンダマンになりたいなあと。言ったら反対されるかなと思って。三日前に家出しました。
――お祖母ちゃん、よにゃごトラさん?
はい。きれいなお祖母さんでしょう。
――よにゃごさん、世界的な絵本作家だよね?
え? そうなの!?
――にゃんだこのノンビリおっとりボンボンは…。
はい、今日の証言終わりにゃ。
あとそこのリストで関わった絵に丸付けてといてね。
027. にゃか休み
くしゃくしゃのスーツのまま、知多は駐車場に止められたSUVの中で目を覚ます。
「いかん、寝てしまった…最近体力持たないなあ…」
「あ、生きてたぁ。おつかれぇ~」
運転席から、きらきらしたオーラの長毛種のネコビトが笑顔で顔を出す。
「アタシ、丘斜。丘に斜めって漢字よ、ここの検視官なの。でも、今回も誰も死んでないから仕事なくってさあ、暇なの~」
「ああ、こ、こんにちは。」
「別に死体の解剖以外にも色々できるんだよ、塗料の分析とか、やってあげようか?」
「ほんとに?」
「と、思うでしょ。でも、今回は阿日ちゃんが先やっちゃったから、アタシ、することないの。つまんないから、築地行ってカマトロペチーノの解体からの分析とかしてこようかと思うんだけどぉ、来る?内臓から寄生虫探せるの、サイコーでしょー?」
「ええと…」
「もちろん、いくよねぇ?じゃ、しゅっぱーつ!」
知多は検視官の丘斜に連れられて、マグロの司法解剖へ向かう。
028. ネズミと猫と藪の中Ⅲ テンテイルズの証言

――おじさん、ネコビトだよね?
――ちゃる捜査官、協力者におじさんは…すみません、そして、貴方はネコビトですよね。
ああ、オフレコなら…そう、私はユキヒョウだよ。しかし、元は人間でね。実は、黒猫数えをしたわけじゃないんだ。ただ…ユキヒョウの王の、9つ目の命が尽きるときに、共にいたんだ。私はあの頃若く、神秘的な事や冒険に興味があってね。友人がヒマラヤの辺境の地で、ユキヒョウの写真を撮るというので付いて行ったのだ。マーチャルプラディーと言う土地のスピティという谷で、「間の地」という意味だそうだ。山脈の狭間にある、あれはおそらく断層なんだろうな、険しい谷だ。そこをユキヒョウを探してまわるんだが、私ひとりはぐれてしまってね。吹雪の吹き荒れるなか、断崖絶壁にぽっかり開いた洞穴に逃げ込んだ。そこには、老いたユキヒョウがいた。その青い目が私に向けられたが、彼はもう目が見えないと言った。もう目は見えない、お前の臭いはわかる。若いオスの人間よ、俺が5つ目の命の時に食ったやつと同じだ。若くて傲慢な臭いがする。復讐に来たのか、嘲笑いに来たのか。私は答えた、貴方の邪魔をしたいわけじゃない、ただ嵐から逃れてきただけだ。命を助けてくれたら、なんでもしよう。ユキヒョウは笑った、お前を殺そうにももう動けない、その肋骨を食い破る力も歯も残っていない。勝手にしろ。だが、俺に人間の世界を見せてくれるというのなら、俺はお前にユキヒョウの力をわけてやろう。そして、この谷中のメスヒョウを夢中にさせた魅力と、9つ分の命の知恵をやろう。どうだ、俺にお前に命を分けてくれるか。私は、自分はすでにそういった魅力は持っているから必要ないが、9つ分の命の知恵には興味があるし、死にかけた生き物の願いを叶えたいとも思う、と言ったんだ。それで、今の私はユキヒョウのネコビトなんだ。
――本当かにゃ…?
おや、仔猫ちゃん、なぜそう思うんだい?
――だって、おじさんデビューの時からテンテイルズだよね。ママがファンだから知ってるにゃ。
しかし、私のデビューもそんな早くない。青年時代にユキヒョウに出会う時間もあったんだ。
――でも、デビューはユキヒョウパワーで、おじさんの実力じゃなかったら、ママがショックで禿げるにゃ。
いや、デビューはユキヒョウパワーじゃないさ。私はネコビトとして生きるには少し不器用過ぎるんだ。それに、これは預かりものの命だ。だから、ユキヒョウネコビトもオープンにしていない。しかし、私は私さ、フランス語もできるように猫語もできる、そんな感覚かな。しかし、仔猫ちゃん、鋭い指摘だね。君の名前は確か…
――ちゃる捜査官だよ。ちゃる・あうるむ・分地。
そうか、覚えておくよ。ところで、アンソニー君の通訳は、もう私はしなくていいのかい?
――青木さん帰ってきたからいいんだって。ごめんね。
いや、別に楽しみにしていたわけじゃないから…とはいえ、ちょっと興味があるな。
――すみません、彼が何故かとても落ち込んでいる様子なので、それはまた今度…
(そーなの、遮無さん? )
(うん、パトラちゃんがテンテイルズの動画をずーっとみてて、アンソニー撃沈なんだよ。)
(へえ。大変だねえ。ちゃるのママはね、おじさんの動画より、ちゃるの見たい恐竜見せてくれるよ。)
029. アッカンベーネズミ
遮無、繰津、ちゃると沼田署長がそれぞれに関係者から証言をとっている頃、丘斜と知多が飲みかけの3杯目のマグロのカマトロペチーノの容器と小さめの冷凍マグロを手に、事務所に戻ってくる。
「カマトロサイコー!!」
「美味しかったねえ」
「築地のおじさんもサイコー!!」
「でもこれは特別にとっといてもらったものだからちょっと小さいんだよ。」
「丘斜さんはなんで築地のおじさんたちと仲良しなの?」
「ふふふー。ねえ、ところで、検視官が言うのも何なんだけど、捜査はいいの?」
「よくないんだけど、捜査じゃないんだよねえ。運よく見つかればシュローディンガーに協力を仰ぎたかっただけんだ。どうせ見つからないと思ってたら、見つかっちゃったし。なんでか一反木綿いるし、まんまるとテイルズもいるし。こんな調子だとそのうち、ジャガーまででてくるんじゃないかな。」
「うふふふ、そうねえ、出てきたら楽しいわねえ。」
駐車場からエレベーターを経てオフィスに戻るまで、丘斜は溶けかけたマグロから滴る水滴を自分の長毛でふき取っている。丘斜はこののち、ゆっくりモルグの隅の人魚テーマのシャワールームで優雅にバスタイムを予定しているので、マグロから垂れた水滴くらい平気なのだ。
「紙仕事が増えるけどね…て、あれ?CAT日本支部のパソコン、みんないつもこう?」
エレベーター側から見えるガラス張りの壁の向こうの事務所では、すべてのパソコンのモニターが光っている。そして、そのパソコンモニターには、ことごとくアッカンベーをする某有名ネズミのアニメーションが流れている。
「あららーなんか感染したかしらね…?でもあたし、早く地下のモルグにマグロ置いてこないと。あ、阿日ちゃん?事務所来て、なんかえらいことになってるーあと、署長も呼んでーうん、大丈夫、知多さん置いてくから無人にはならないよー」
丘斜は電話を切ると、マグロを肩にかついで事務所を出ていこうとする。
「え、いっちゃうの?」
「マグロとけちゃったら、すぐ食べないといけなくなるもん。あとでみんなでマグロかき氷パーティーしたいでしょぉ?大丈夫、すぐに阿日ちゃん来るわよぉー。」
丘斜は満面の笑顔で退場し、知多はアッカンベーネズミの中に取り残される。
030. マグロのカマトロペチーノとfacepaw
あちら側のガラスのドアの向こうから、青ざめたアンソニーが現れる。大熊さんに貸してもらったのだろう、可愛いパンダの絵の付いたオーバーサイズのTシャツを着ている。
「Patra! ...Not here either. Excuse me, have you seen Patra?」
(パトラ! …ここにもいない。すみません、パトラは?)
「Ah, uh... looks like she's not in the detention room. Oh, right—want to give your statement before you go? I can call Aoki.」
(あ、ええと…留置所にいない…みたいだね。ああ、そうだ、帰る前に証言とっとく? 青木さん呼ぶよ?)
「Thank goodness, a normal person...」
(よかった、普通の人がいて…)
「Normal?」
(ふつう?)
「The last person was using all this ancient creepy language... it felt like they were casting a curse on me or something. But, um, the statement—here?」
(さっきの人、おどろおどろしい古い言葉使っててめっちゃ怖かったんだ…呪いをかけられてる感じで…でも、証言って、ここで?)
「Yeah. If the animated mice on the screen don’t bother you.」
(そ。画面のネズミが気にならなければ。)
「I mean, they do kinda bother me, but at this point, I have no idea what’s going on anymore...」
(なるっちゃなるけど、もう、何が何やら…)
「Life of a celebrity, huh... Oh—Aoki? Anthony's in the office! Come over, you know it’s a pain if I have to take the statement later, right?」
(セレブは大変だねぇ…あ、青木さん? アンソニー君、事務所にいるよ! おいでよ、証言は私がとってもあとで面倒でしょ?)
知多が電話で青木を呼び出す間、アンソニー君が途方に暮れたように取り囲むネズミアニメーションを見回す。
「Wanna try the rest of this Kamatoro-ccino?」
(カマトロペチーノ、ちょびっと残ってるけど、のむ?)
アンソニーは細づくりの女性が差し出した、魚と生クリームと申し訳程度のコーヒーの混合物に顔を背ける。
「How can you eat such…」
「WOW!is that...?! May I...?!」
机の下から、巷ではそうそうお目にかかれないほどの美しい外国人女性が現れ、知多が手にしたほぼ空のカマトロペチーノの容器をつかむ。パトラがそれを味見して良いかを猫語で聞き、知多が笑顔で猫語で返す。
「おや、机の下にいたの。いいよーどうぞ」
「やった―ありがとう! カマトロフラペチーノ、チョーチョー気になってたの! ワサビ入ってない?」
「うん、私もワサビは苦手だから入ってないよ」
猫語で取り交わされる女子トークと、魚のフラペチーノの魅力が理解できないニンゲン男性のアンソニーは、なんてグロテスクな飲み物なんだろうと考える。それでもパトラが見つかって嬉しそうな表情だ。
やがてエレベーターから阿日と青木が現れる。
「おや知多さん、おつかれさん。阿日ですよ、やってきしたがねぇ…パソコン、そんなに詳しくないんだけどねえ…」
「じゃあ、私はこのお兄さん借りいきますね。パトラさんはもう帰る?」
「Oh no, don't leave me Patra!」
青木が伸ばした手を振り払い、アンソニーは椅子を蹴って立ち上がった。
「Don't leave me, Patra!」
立ち去りかけたパトラは呆れたように微笑んで振り返る。青木がパニック気味のアンソニーに手を述べて促す。
「Dont worry, it only take…」
「No!」
アンソニーは再び青木の手を振り払うと、椅子を蹴って今度は反対側へ飛び出した。驚いて立ち尽くしていたパトラの手をとって、ぐいと引く。戸惑いながらも、パトラはついていく。
ふたりはエレベーターへと駆けだす――
が、アンソニーは、そのあいだにガラスの壁があることをまったく意識していなかったようだった。
先ほど蹴った椅子が、ちょうどガラスにぶつかる。鋭い音を立てて、パリン、と蜘蛛の巣のようなひびが広がり、壁が一気に崩れ落ちる。
薄い破片がふたりの頭上にばらばらと舞い降り、白い光を反射する。
アンソニーはその破片の中を突っ切るように走り抜け、パトラをエレベーターへと導き入れる。少し血が滲んでいるようにも見えたが、彼は止まらない。
エレベーターの扉が、すべての音を後ろへ閉じこめるように、ぴたりと閉まった。
その場に残された青木は、破損したガラス、転がる椅子、そして大量の後始末と書類を思い、額に肉球をそっと当ててfacepawのポーズを取る。
知多はため息をついて、砕けたガラスの向こう、閉まった扉を見つめた。
(……また数駅分くらい、走るのかな)
031. トラさんとカリンとセドリックとビアンカ(と根田さん)
CATの事務所の隣のカリンのジムには、中二階にカリンの事務所がある。そこでは、階下で繰り広げられる筋肉と筋肉のぶつかり合いやダンベルと肉体の激論を眺めながら、楽しい茶話会が行われている。メンバーは米子トラとカリンとセドリックとビアンカで、根田さんは隅のハンモックで昼寝をしている。
「あなたがカリンさん…まあ、なんと逞しい…」
「そうかな、アタシはスレンダーなキラーなんだけど…」
「おばあちゃん、あの…」
「しっ! おばあちゃんは今、カリンさんと話しているの。まあ、すごい背中…さわってもいい? きゃあ、次の本を描きたくなっちゃう、カリンさん風の化け猫メインで! ふふ、望子ちゃんにも相談してみよ。」
「望子ちゃんて、『ハニー・バニー』とかで有名なあの不破望子さんですよね? あの、アタシらの絵本をふわもこキュートなキャラにしようという話を聞いたんですが…いや、アタシは実はキュートなふわもこ化もちょっと嬉しいんですがね、ファンが…特に、小さい子達が納得しないというか。」
「ああ、大丈夫よ、あれは…」
トラが微笑みながら穏やかにいうのに、セドリック君が興奮気味に言葉をかぶせる。
「大丈夫です! パンダルマンシリーズは、僕が作画を引き続きします! だからワビサビな別ラインで…!」
「ああ、それならありがたい。でもアニメ化っていうのは…?」
「その話はまだ聞いてないわね、キャラクターが軌道に乗ってから考えるんじゃないかしら…」
「僕、その時のためにアニメ風、あ、それも今の雰囲気での絵を勉強してます。きっとご納得いただけるように…」
「へえ、君、若いのに偉いねえ」
「あ、いえ…えへへ」
「若くないわ、セドリックはとっつぁん坊やなの、もう立派な30代よ」
隅で携帯を眺めながらビアンカが暗い声で言う。画面には「謎の清掃集団」との文字が踊る。米子トラさんはビアンカを無視してセドリックに向き直る。トラさんは孫をたぶらかして家出をさせた美女を許せないらしく、ビアンカの方すら見ない。
「まったく、あなたは心配かけて…もう。望子ちゃんに正体を話しちゃったわよ。望子ちゃんびっくりしてた。」
「ええ、ぼくが『パンプディング』だっていっちゃったの? せっかくモコさんに直接接触しないように気を付けてたのにーあ、そうだ、おばあちゃん! 干支戦記がおばあちゃんの作品ってなんで教えてくれなかったのさ」
「あなたがプレッシャー感じるといけないと思って。さあ、帰りましょ。カリンさん、またお会いしたいわあ、今度は大熊さんも…」
「ああ、大熊、いなくて申し訳ありませんね。さっきから若いのに探させてるんだが、どこへ行ったのやら…」
「ここにいるわ」
暗い声で言いながら、ビアンカは携帯の画面を見続けている。
「ここにいるって、あなた…」
ビアンカは黙って携帯をトラに向ける。そこには、笑顔で交通安全啓蒙活動に参加する大熊とコータ君が映っている。「パンダルマン、交通安全をゲリラ推進!」。その背景には、遠くに疲れた様子で草むしりをするネズミ兵隊たちがうつっている。ビアンカ姫はネズミ兵士たちが心配でならない。
根田さんは相変わらずハンモックで寝ている様子だが、実は耳は起きている。パンダルマンのキャラ化は本当のようだが、ここでフワモコ株を買ったらインサイダー取引になるのだろうかと考えている。
032. ネズミと猫と藪の中Ⅳ テンテイルズの証言2 削除部分

――あ、あら?いつこの部屋、模様替えしたのかしら…パイプ椅子からネ・コルビジェ風応接セットに…
――署長、椅子ふかふかだよ。
――そうね、でも予算が…いえ、それはあとで。
さっき、「フワモコ」という人からの差し入れだと言って宅配の人が来ていたよ。
――ああ、どうもすみません。容疑者の方に宅配のご対応までしていただいて…ああ、でも、もう容疑者じゃなくなりました、おめでとうございます。先ほど、殴られた男性が訴えを取り下げました。ええと、謎の美女にリモート会議への招待があったそうで…「あんな絶世の美女に直にお願いされるなんて、俺すげえ。」だそうです。この美女…
――ガチャ。沼田さーん、男性が「もう女性からの直メッセージは要らないからアドレス非公開に戻して」だそうです。
――ねーねー、美女ってパトラちゃん?
――と、そのモデル仲間とかその追っかけとか我こそはと思う容姿に自信のある人とかたくさんだって。大変だねえ。アドレス非公開にって言っても、ウチなんもやってないんだけどねー無理って言っときます?
――ええ…えっと、三ツ池ちゃん、お願いできる?
――いいっすよ。じゃ、テンさん、おめでとうさんです。ちゃるりん、後でね。しかし、あ、録画中? お邪魔しましたーガチャ。
033. ネズミと猫と藪の中Ⅳ テンテイルズの証言2 撮り直し
――コホン。ええと、それでは、訴えも取り下げられたということで、晴れて無罪放免…
それはよかった。これでコンサートができるよ。しかし、もうひとつ、私の方に案件が残っているんだ。君たちは、謎の紙片が人を襲う事件を追っているのだろう?
――そうだよーなんか人に取り付いて良いことをさせるみたい。おじさんもそれに捕まったんだよね?
Hum, そうかもしれないし、そうでないかもしれない。世の中にはハッキリさせた方がいい事と、させない方がいい事とあって、私の件は後者だ。
いずれにせよ、この椿事をバチカンの法王付き第一猫、ニャヴェルのガートルード66世が大変気にしていてね。彼女、自分の代の数が縁起が悪いもので、とても世の中のことにセンシティブなんだ。それで、私がこれを託された。この紙は、法王直々に清めて祝福された水を、最先端の…なんといったかな、可愛いアザラシが箱に印刷してあるティシュー、あれの技術で織り込んだものだそうだ。これで、暴走するはぐれサマリタンも大人しくなるだろうとのことだ。
――はぐれサマリタン?
そう、はぐれサマリタンと、彼女は呼んでいた。文字や絵画に込められた善意や良いパルス、想いのようなものだそうだ。それが時々、描かれたモノの劣化によって行き場を失い、短絡的だったり短慮だったりする行動へ人を駆り立てる、一種の悪霊のようになってしまうらしい。
――ガチャ。すんません!!緊急です!テンテイルズ氏に暗殺予告が出てます!あと、たぶん、その予告を出した張本人がオフィスのガラス割って逃げました!
――にゃに!?
――え、あ、分地さん!?いたの!?
――うん、録画係。人手足りなそうだし、ちょっと手伝ってるの。
034. 青い小型車での逃避行

「ちょっとアンソニー、どこへ行くの!?」
「こんな変なところでわけのわからない嫌疑で調べられるなんてもうたくさんだ!!なんか魚パフェとか飲んでるし!でも、君と離れるなんてもっと嫌だ!!さあ、行こう!!」
「どこへよ!?」
アンソニーはパトラの手を引いてエレベーターから駐車場へ駆け出す。半地下の駐車場には様々な色の自家用車が雑然と並んだエリアと、整然と並べられた警察車両のエリアがある。そして、警察車両の方だけは、駐車場係の木賃さんが管理している。ネコビトにしては珍しく物事の細かい点にこだわる人だ。アンソニーは木賃さんが、丘斜が適当に停めたSUVを停めなおしているのをあちらに見掛け、パトラの手を引きかながら手近にあった青いクラシックな小さい車の陰に隠れる。三ツ池の愛車だ。
「アンソニー、ちょっと、何やってるの。」
「ドアが開かなくて…」
「こう?」
パトラはネコビト特有の強化爪を伸ばし、ドアを難なくあける。アンソニーは「ありがとう!愛してる!」といって運転席の下へ潜り込み、ワイヤーを切って繋げてエンジンをスタートさせる。
「乗って!!」
「あ、いや、アタシは…」
アンソニーは運転席に座ると、小柄な三ツ池の体にあわせてあったシートを後ろにずらし、木賃さんが車から控え室に戻りつつあるのを見て急いでアクセル踏み込む。
「Hold on!!」
三ツ池お気に入りのクラシックな小型車は猛スピードでCATの淡いピンクのビルを出ていく。CATのビルはニャウディ風の優しい曲線と、入り口のハートとも猫ともつかない抽象的な形の、青が基調のステンドグラスが印象的な建物だ。その裏から、表の大通りへ三ツ池の青い小型車がきらめきながら飛び出して行く。
035. Rボタン連打
「ですから、ウチじゃオタクのアカウントはさわってな…あああああああああ!アタシのスカイちゃんが!!」
駐車場から走り出た青い車に、たまたま窓辺で電話していた三ツ池が気が付いて叫ぶ。電話の相手は、テンテイルズに殴られたデートDV男だ。
「うわ、うっせ!だか…」
三ツ池は不愉快な男への電話を切り、パソコンへ向かう。アッカンベーネズミが点滅しているのは既に1台だけで、他には阿日が貼った「もうつかっていいよ」の付箋が貼ってある。三ツ池はスケジュール表を確認しようとして、自分の手の震えに気が付く。愛車の危機だ。
「阿日さん、今日って縁さんそのへんいるよね?」
「今日屋上いるよーたしか、保護ドラゴンの登録に来てるから」
「よかった、今電話通じるかな…?あ、縁さん?うん、飛ばしてほしいの!いますぐ、至急!ドラゴンの籠?誰かお守りつけるから!」
そういう間にも三ツ池は阿日の襟首をつかんでエレベーターの前へ引っ張っていき、上の矢印のボタンを連打している。
「早く来い―エレベーターこいー!遅い!」
「あのアッカンべーネズミさあ、それ自体は×押せば消えるんだけどさあ」
「エレベーター!遅い!また誰か停めてんな?!」
「消えるのはいいんだけど、それとは別にさあ、あのネズミ、なんかまずい事したかも。」
「え?」
「アッカンべーネズミ、一時期インフルエンサーの間で流行った悪ふざけなんだけど、使った人のパソコンに裏口作っちゃうプログラムが裏で動くらしいって噂があったんだよね。それも嘘かもわからんけど。」
「えええ、まずいじゃん!」
「あ、エレベーター来た。」
三ツ池はエレベーターに阿日を引きずり込むと、ワーキングメモリからアッカンベーネズミを追い出し、愛車の追跡に全神経を集中しようと屋上を示すRボタンを連打する。
036. 縁さんの飛行機と走行車線
「ドラゴンのトレーナーさんいたなら阿日ちゃんは要らなかったかな。」
「私はいいんだけどね、ドラゴントレーナーさんイケメンだから。阿日ちゃん、惚れちゃわない?」
「ああ、阿日ちゃんは人間全般に興味ないから大丈夫。プライベートはあの人、猫だよ。飼い主いるし。」
「ええ、ネコビトなのに?」
「一人暮らしのお婆さんなんだけど、おばあさんは境界センスないひとで気づかないし、猫っ可愛がりで、娘のようにかわいがられて育ってるからねえ。阿日ちゃん、化学式に興味を持つまで、ネコビトの自覚なかったみたいだよ。」
「へえ、なんだかすごいね。」
そんな会話をうるさいコックピット内で怒鳴り合いながら、縁は古風な貨物輸送飛行機を離陸させる。狭いCATビルの屋上でも問題なく離陸できるのはこの縁と彼女の飛行機、ファルコン号だけだ。コックピットはガタガタと揺れるが、縁は楽しそうにまんまるファイブのヒット曲をメドレー形式でサビだけを歌う。
「どんな車を追うんだっけ?」
「青いの!小型の、品のいい、きっちりした感じの!」
「ああ、あれ?逆走してるやつ?」
「にゃああああ!!右側走ってる!あいつ、この国の道路ルール知らないんだ!」
国によって走行車線が違うということをアンソニーは認識していなかったらしく、彼の後ろにはすでに白黒の人間用警察車両が何台か付いて走っている。古民家侵入や車の強奪とは全く無関係に、交通系の違反で彼は追われている。縁の飛行機が自らの追跡隊に加わったのに気づいたのだろう、アンソニーはさらにスピードをあげる。
「やばいにゃ。事故ったらスカイちゃん廃車…じゃなくて、これじゃアンソニー君、タダゴトじゃない状況になるにゃ。」
「ありゃーどうしようね。この飛行機、ドラゴン用の捕獲機載せてるけど、さすがに車は無理だよ。」
「うーん、でも捕まえてほしいにゃ…」
「三ツ池ちゃんの車、無線付いてるの?」
「あ!そうだにゃ!ニャイスアイディア!」
三ツ池は天井近くの無線へ少し腰を浮かせて手を伸ばし、それに向かって叫ぶ。
「アンソニー!!きくにゃ!!その車ぶっ壊したらコロ…じゃなくて秘密裏にCATが保護する!!ただちに私のナビに従うにゃ!!聞こえたら返事!!」
だが、雑音に混じって聞こえるのは「WHAT…?」だけだ。
037. アンソニーの逃走劇
「パトラ!!この無線はなんといってるんだ?!猫語を訳してくれ!!」
青い小型車の中で無線機は呼び掛けを続けるが、アンソニーにはその言語が理解できない。猫語らしきにゃごにゃごが聞こえたのでパトラに通訳を頼もうと、後部座席に声をかけるが、返事はない。
「パトラ?…パトラ!?」
アンソニーはようやく、角度が合わないバックミラーをのぞき込んで、後部座席には誰もいないこと、そして背後には予想以上に日本の警察車両が沢山ついていることに気が付く。アンソニーは半ばパニックに陥り放送禁止用語を叫びながら、車の古風で細作りのハンドルを拳で叩く。それから大きな息を何度か吐き出して落ち着きを取り戻す。と、視界の右側を黄色い影が横切る。それは何かを蹴ってこちらへ飛び掛かる。小型車の低い天井に鈍い音が響き、左の窓の上に黄色い大きな猫の手が見える。かと思うと、金髪の髪を振り乱した細作りの女性が、上からフロントガラスを覗き込み、アンソニーは叫んでさらにアクセルを踏み込む。その頭が引っ込んでも、今度は繰津のホラー語調がどこからともなく聞こえるように感じ、ますます追い詰められる。そして今度は確かに無線から、ノイズに混じって「汝、この角を曲がらなば一切の望みを捨てよ…かくは…ザー…に至らん…」と聞こえ、アンソニーは恐怖に目を見開く。また、フロントガラスを大きな鉤爪のある黄色い手が引っ搔いている。そして、彼が急ハンドルを切って滑り込んだビル街の大通りには、何故か誰一人いない。
038. 襲撃
アンソニーがパニックに陥る少し前、美しいパトラはCAT本部の駐車場でひとり佇んでいた。
「ごめんなさいアンソニー…」
パトラは彼女を載せずに駐車場を飛び出していくクラシックな小型車を見送りながら呟く。そして、意を決したように表情を変え、猫の姿で猫用の通用口を素早くくぐる。パトラはそして、主に人間サイズの生き物を対象としている監視カメラを避け、屋根裏の通気孔を選んで進む。そして、ほぼ誰も使わない非常用階段にたどり着くとようやくネコビトに姿を変え、小走りで階段をかけのぼる。
「テンテイルズ…スージーの仇!」
彼女は『ねこちぐら』で話した素敵な男性の、穏やかな青い瞳を思い出す。ニワカと笑われても、と、自分のファンに情報提供を頼んでみたり、ニャンチューンズで名曲を聞き込んでみても、どうにもその微笑みが頭を離れない。どこか、懐かしい気がした。数時間前の、拘置所でのテンテイルズとのやり取りを思い出す。
「ワサビアレルギーとは大変だったんだね。」
「アタシ、知らなくって…でも、なんだか刺激的だったわ。癖になりそう。」
「刺激的なのは…愛だけでいいんじゃないかな。きっと君のボーイフレンドには君はワサビだ。」
「あら、うふふ。それで、あなたはなぜここに?」
「紳士のすべき事ではない事をしたのさ。」
「デートDV男を殴ったのにゃ。」
『ちぐら』檻の向こうから、退屈そうな繰津が言う。
「まったく、あんたがネコビトじゃなけりゃ普通の人間同士のイザコザだったのににゃあ…」
「あら、相手は人間の男…それなら…」
パトラは、繰津のお情けで渡されたスマホをいじり出す。パトラはクレオパトラの再来と呼ばれる自分の美貌が、一定の人間の男性に対していかなる効力を発揮しうるかを十分に心得ている。そして、パトラはDV男を探り当て、訴えを取り下げさせるところまで取り付けた。
テンテイルズ、私たちの間には何かあったはずよ、何かしらの絆が…そして、オフィスに忍び込んで見た証言テープの衝撃。テンテイルズが、ユキヒョウの王だとは。心ときめいての情報収集の末の一撃。ああ、前世の記憶が蘇る…憎きユキヒョウの王、テンテイルズ…! だから、監視を緩めて彼を狙うために、アッカンベーネズミを仕込んだ…でも、よかったのかしら…いえ、迷ってはダメよ…
そこだ!パトラは、たぶん取調室がある階の非常扉に体当たりしてそれを開こうとする。あちらでは、何か崩れる音がする。ネコビト一般の傾向ではないが、CATのメンバーは階段を使う習慣があまりないので、非常用扉の前にモノを置いておくことがある。この場合は、取調室から運び出された古いパイプ椅子と机だ。
039. Nobody's friend
突然、壁際に置いてあったパイプ椅子と机が倒れ、立ち話をしていた沼田署長、ちゃる捜査官、青木とテンテイルズが飛びのいて身構える。
「にゃ、にゃ、にゃに!?あ、パトラちゃん?」
「脱走したの?」
「パトラちゃん、彼氏逃げたよ!」
皆それぞれに何かしらは口にするが、その間にパトラはわずかに開いた扉の隙間から細い身を廊下へ滑り込ませる。そして、決死の覚悟で自らのキャット・クロウでテンテイルズに襲い掛かる。
「テンテイルズ、覚悟!!」
「ちょっ、にゃにやってんの!!」
しかし、あっさり沼田署長に跳ね返されてしまう。
「にゃに?!どうしたの、何のご乱心!?」
言いながらも沼田は撥ね飛ばされて床に伸びたパトラに駆け寄り、助け起こす。パトラはそのふんわりと分厚い毛皮に緊張感を解かれてわっと泣き崩れる。
「アタシ…アタシが最初の命の仔ネコビトだったとき…あのひと…あの人に憑いてるユキヒョウが、7つ目の命の時、ユキヒョウは大きな野良ネコで…可愛がっていた…スージーを…」
「はいはい、スージーね。落ち行いて。」
「雌鳥のスージーを…喰ったのよ!」
パトラはその美しい顔に涙でマスカラとアイラインの滝をつくり、悲しい声を振り絞る。ネコ科の生き物とネコビトには9つの命があるが、猫の習性か転生の仕組みか、前世の記憶はあまり残らないのが一般的だ。それが残っているということは相当に悲劇的な、つらい別れであったのだろう。
「スージー…毎日の卵が…楽しみだったのに…!」
そういって沼田署長にすがって泣くパトラに、テンテイルズはゆっくりと歩みより、膝を床に着いて話しかける。
「そうか…それは辛いことだったね。大変に辛いことだ。…しかし、それは私に憑いているユキヒョウの7つ目の命の時にしたことで、私ではない、代わりに償うことは、私がいくら願ったとて、できることではないんだ。ただ…雌鳥のスージーのご冥福を祈るよ。スージーとその卵に栄光あれ…」
パトラはそれを、崩れたアイメイクの下の瞳をしばたかせて聞いている。
「私に憑いているユキヒョウは老いていて、君は若くて美しい。どうだろう、私の命を狙うのはやめて、君のボーイフレンド、アンソニー君と幸せになっては。彼はいいね。君に泣かされてもそれが好きなんだ、大丈夫、大事にしてやりたまえ。」
「え、ええ…わかったわ…」
そして、テンテイルズはパトラの手を姫君のそれのようにとって、パトラをたたせてやる。横で、よっこらしょと沼田署長も立ち上がる。
「じゃあ、これでみんな仲直りね?いいわね、お友達よ?」
「ああ、それは…」
「だめ!」
今まで静かにおとなしく大人のやり取りをきいていたちゃる捜査官がさっと手を挙げる。
「はい、ちゃる捜査官」
「はい!テンテイルズはノーバディずフレンドだけどみんな一番のファンにはなっていいのです。友達はダメ、ファンはあり!」
一瞬の沈黙の後、テンテイルズは吹き出し、大笑いを始めた。それにつられて、沼田やパトラまで、訳もわからないままにちゃる捜査官の真面目で誇らしい様子のあまりかわいらしさに笑い出す。
「ああ、そんな古い歌の歌詞を覚えていてくれたんだ…ありがとう。でも、今は私は君の一番のファンさ。」
「私、テンテイルズの推し?」
「ああ、そうだ。」
全体にほんわりと優しい空気になったところで、緊急出動要請のアラームが鳴り響く。
40. 救助要請
「あ、遮無さんが動員かけてる!」
「どこへ行ったのかと思ってたら…はい、沼田!」
沼田署長がCAT通信機で返答すると、クリアな音質で遮無の声と何かの衝撃音と誰かしらの呻きがその耳に届く。
『署長!ニュースを見てください!』
「ああ、三ツ池ちゃんの車ね、今…」
『違います!ゾンビネズ兵が次々に熱中症で倒れています!ビアンカさんマジ切れです!』
「ええ?!」
遮無が通話を画像付きに切り替え、倒れたいかつい男性を人間の通行人が介抱している姿をうつしだす。カメラは次に少し離れた場所で合羽や河童や軍手を脱がされるネズミ兵士や、日陰で水をかけられているネズミ兵士を巡り、さらに遠方を見せる。どうやら、大きな公園のようだ。奥の方では、両脇に伸びたネズミ兵士を抱えた大熊さんも見える。大熊さんが見えたことでがぜん興味を持ったちゃる捜査官が、携帯に大声で話しかける。
「大熊さんといたコータ君は?」
「大丈夫、さっき大熊さんと私がお家まで送っていったよ。今はその帰りなんだけど…はぁっ!」
一瞬、遮無の長い足が大きなネズミ男性の側頭部に入る映像が見え、そのあと、画面は暗くなる。
『起き上がったら死ぬって今言われたでしょ!?そこの噴水に寝てなさい!』
遮無の怒鳴り声が聞こえ、ちゃる捜査官は思わず耳を倒して沼田署長に抱きつくが、すぐに恥ずかしくなってまた身を離す。沼田署長はその頭を優しくなでながら、遮無に言葉をかける。
「遮無ちゃん、大丈夫?」
『大丈夫なんですが、ネズミ兵たちが…なんとか噴水のある公園まで誘導したんですが、これ以上は私と大熊さんだけでは何ともなりません!』
それから遮無のアップの顔がうつしだされる。人間姿で水をかぶり、いかにも人間の刑事風だ。
『絶対に濡れますから、人間姿で来てくださいね!』
その額には、水滴が淋漓として光っている。
『こらぁ、噴水から出るな!』
との怒鳴り声ののち、通話は切れる。
41. 草原とmeow&meaw
『こちら縁。ただいま猫町草原上空。オーバー。』
「コピにゃ。アンソニーちゃん、GPSによると無事猫町区域に入った様子。おば。」
『ああ!天井に知多さんいる!危ないにゃ!止まらないかな?』
「あそこの境界、なんもにゃいから大丈夫。そのうちガス欠で止まるかも。」
『それは飛行機も一緒だよ。』
「あの辺は丘のようで丘じゃにゃい、上がったり下がったりがたくさんある、多摩丘陵よりもっと穏やかで…」
『なんか繰津さんがしゃべるとアンソニーがスピードあげる気がする』
「にゃんだと?」
CAT本部の繰津はそれが面白いのか面白くないのかいまいちわからなかったのと、懐中のスマートウォッチに来ている出動要請のチェックでしばし無言となる。
アンソニーの車は、一面の緑の中の一本道を、青い車で進んでいく。
「ここはきれいだねえ」
飛行機を操縦しながら、縁さんが無線のスイッチを入れずに独り言を言う。
猫町は境界にある街で、主にネコビトたちがすんでいる。そこのネコビトたちは人間もいる世界のネコビトよりはもっと境界向こうの世界に近い習慣を持っているので、CATに所属するネコビトたちもたまにクラシカルな世界を堪能しにそこへ逗留する。そこへの道は、時に長く、時に一駅分くらいしかない。むしろ、散歩でたどり着いてしまう人もあるくらいだ。だが、今日のところは、アンソニー君にとっては長いようだ。いつまでも続く細い葉の草原、青い空、綿のような雲。猫町の手前にある猫町草原で、アンソニーは、自分が死んだのではないと疑い始めている。
そういえば、あの時、パトラの変身で動揺して慣れないショーチューを煽って酔っていた時…どこかへ駆け出して…白い何かに顔を包まれた気がする。そして、何か、可愛い生き物をめがけて道路へダイブした気がする。ヘッドライトがまぶしかった。誰かに何か、わからない言葉を怒鳴られた。それで、丸い温かい生き物を持って走った。空き家があった。裸足だったので、シャツを脱いで床に敷いた。それは自分の意思ではなかった気がする。だったら、あの刑事風の猫のお化けたちは、助けられなかった仔猫のお化けか…? だから拘置所に閉じ込められたり、怖い言葉で詰問されたりしたのか…? 死後の裁判なのか、俺は死んでいるのか…?
気が付くと、上り坂で車のスピードはかなり落ちている。頂上までくると、もうアクセルを踏み込む気にもなれず、彼は車を停めた。そして、外に出てみる。まるで緑の海だ。そして、振り返ると、真っ青な車がある。その上に、黄色っぽい毛皮が見える。その毛皮は大きく波打っていて、周囲の草原の波の動きにも呼応しているようにも見える。
ああ、俺はやっぱり死んだんだ…
アンソニーは、そう思って立ち尽くす。
と、毛皮が大きく動き、チーターがその琥珀色の目をこちらに向ける。喰われる、そう思った瞬間、チーターはひっくり返って頭頂を車の天井に擦り付ける。そして、流ちょうな英語で、ただし、とてもげっそりした様子で、「なんか甘いもん持ってない?チョコとか。」と聞く。アンソニーは、先ほど助手席で見たチョコレート、meow&meawの袋をつかみ、震える手で鋭い爪が少しすり減った黄色い猫の手に渡す。
042. E.A.パウの『黒猫』とドクター・プースの『Cat and the What』
「Wow, 『黒猫』が絵本に…that’s…だって、パウはホラー作家だよねぇ。」
「Yeah, その頃、学校で『干支戦記』と『猫又夜叉』がクールだというんで流行ってたんだ。」
「へえ、そんな昔から有名なんだ。」
知多は小型車の屋根の上でm&mを食べながら、アンソニーは後部座席のドアをあけ放って横になりながら、二段ベット状態でダラダラしている。緑の海を渡ってきた爽やかな風が吹き抜け、あれこれとどうでもよくなったアンソニーは先ほどまで恐怖の対象でしかなかったネコビトと談笑する。
「僕の9歳はそんなに昔じゃない。」
「いや、昔だよ。」
「いや、とにかくそれで、トラ・ヨナコの本はかっこよかったんだけど、同じようなノリかなと思って手に取ったE.A.パウの『黒猫』は…9歳の僕には怖かった。」
「死体と黒猫を壁に塗りこめる話は有名だけど、怖いもんね。」
「だから、あの無線の声は、というか、あの人が怖かった…」
知多は、アンソニーが極端な行動に走ったのは繰津に刺激されたトラウマのせいだろうかと考える。
「パウの『黒猫』にくらべると笑っちゃうんだけど、私はドクター・プースの絵本が怖かったよ。」
「ドクター・プースが?ネコビトの話なのに?」
「『Cat and the What』なんて、いきなりわけのわからないシルクハットの大人ネコビトがやってきて家をめちゃくちゃにする話だし。真面目なネコビトの子供としては、リアリティありすぎで怖いんだよね。」
「Ha. なるほど、ネコビトにとってはあれはリアルに変な大人なんだね…パトラもドクター・プース、怖かったのかな…」
アンソニーが呟くと、ホワイトノイズののちに青木の英語が無線から流れる。
『パトラちゃん、落ち着いたそうです。』
アンソニーは素早く起き上がって無線に語り掛ける。
「え?!パトラがどうかしたのか?」
『テンテイルズに殺害予告を出して襲って署長に泣きついて仲直りしました。全部署内で完結してるから大丈夫。で、今忙しいから車と飛行機と、ネズミ兵救助に向かってくれる?知多さん、いる?』
「え…?」
「はいはい。コピー、知多、ネズミ兵士へ向かいます。オーバー。」
『あ、飛行機の縁です。アンソニー君、三ツ池さんがお怒りモードでそっちに向かったから、こっちに避難した方がいいよ。草の中をくぐって飛行機までおいで。オーバー』
「え!?」
「ああーそうだった。早く逃げにゃー」
『知多さんもおいで、屋根に飛び乗ったときにへこんだので三ツ池ちゃんお怒りだよ。いそげー』
「だって走行中の車に飛び乗るって難し…ああ、めんどくさい…」
知多もまた、緑の海を飛行機に向かって走り出す。
043. Never Was a Cloudy Day
晴れ渡った9月の青い空の下、数十人のネズミ兵士がずぶ濡れになりながら、黙々と作業に勤しむ。美しき白ネズミ姫、ビアンカが素早くひっくり返してはまき散らすゴミ箱の中身を、筋骨隆々たる兵士達が無言で拾っては袋に集めている。ビアンカがごみを撒くのはもちろん、熱中症寸前のネズミ兵士の体温を下げるために噴水の中に足止めしておくためだ。ビアンカは心得たもので、拾い集めにくいように広範囲に渡って高低差が出るように撒き散らし、疲れ切った大柄な兵士たちはそれを追い切れない。あちらでは遮無が、具合の悪そうな数人の膝に蹴りを入れて、噴水の中へ倒している。噴水の水はその落下先の傾斜ですぐに下流へと流れ、周囲を囲む溝に落ちるので、兵士達が気を失っても溺れる心配はない。大熊さんも、ペットボトルの蓋を大量に撒く作業に勤しんでいる。彼は、神社でお餅を撒いたときの事をなんとなく思い出している。しかし、このキラキラと光る水しぶき、時々見える虹、青い空に緑。
「最高だなあ」
大熊さんは疲弊したムクツケーキーズに同情しながらも、少し感謝している。こんな風景の中、水遊びに大人がいそしむのは小さい子供連れか人助けかでなければなかなか難しい。
「おーくまさーん!気を付けてねー」
あちらから、元気よくコータ君が声をかける。その後ろには、白いワンピースを着た美しい猫風すねこすりビトが見える。
「おや、あれは。」
きっとあれがコータ君のお母さんなのだな、と、大熊さんは、満面の笑顔で手を振る。
上空に激しい音がし、影と共に縁の輸送機が横切る。そして、広場の噴水を通り越し、向こうの芝生広場も通り越して陸上競技場に着陸する。大熊さんと遮無が目で合図をしあい、遮無が数人を縛り上げたのを大熊がまとめて日陰に放り込むと、飛行機の方へかけだす。
ビアンカは一瞬迷った様子を見せた後、素早く物陰へ隠れる。
コータ君は、日陰でお母さんにムクツケーキーズとネズミ兵士について持論を述べている。すねこすり母さんは、通りすがりのスズメバチを「あっちいけ」オーラで追い払っている。陸上競技場とは反対側の子供公園の方から、数人のちいさな子供が見物に出て来て、引率の大人に日陰に引き戻される。大噴水で伸びた兵士たち以外は、いたって平穏な光景だ。
044. にゃんじ、聖別されたる高貴なる者らの鼻紙よ
飛行機のプロペラが止まり、遮無と大熊が駆けよる。ハッチが開き、三ツ池と知多、それに頬に小さなひっかき傷がついたアンソニーが降りてくる。駐車場から、のんびりと沼田署長とテンテイルズ、青木、繰津が歩いてくる。ちゃる捜査官は分地に手を引かれ、オヤツの軽羹饅頭をかじっている。
遮無が噴水を振り返って、きらめく噴水の中でごみ拾いを続ける大男たちを確認して報告する。
「署長、ネズミ兵士たちは限界です。」
「サマリタン、勝手に人を動かすからねえ…アタシからはすぐに離れたんだけど。あの時は大きかったからはがしやすかったけど…サバペチ分けたくなかったし。」
三ツ池がいうと、遮無は「サバぺチのおかげだね」と小さく言ってイイニャサインをしてから報告を続ける。
「三ツ池の時と違って、あの一反木綿、今は細かくなっちゃって洗濯物についたティッシュみたいです。取り切れません。」
「そうなのね。テンテイルズさん、やはり、依り代の劣化が進むとサマリタンの暴走も激しくなるものなのでしょうか?」
沼田署長は泰然として遠くの兵士たちを見ているテンテイルズに聞く。
「そうとは聞いているよ。さて不安定なサマリタンをここにどうやって移すかだね。」
テンテイルズはポケットから折りたたんだ白い紙を取り出す。近くに立っていた青木、繰津、知多とちゃるが興味津々でそれを覗き込む。分地はカメラを回している。
「ずいぶん小さいにゃ、大丈夫にゃのか?」
繰津が猫語で呟くと、テンテイルズは青い目で繰津をまっすぐに見てしばらく考える。
「ああ、君はあの怪奇小説を朗読するような無線の声の人だね。では、この紙を読んでくれるかい。二ヴェルのガートルード66世に託されたこの紙を、ふさわしい大きさに戻す呪文が書いてある。」
「いいのにゃ?」
「ああ、凄みがあるのがよさそうな気がする。さあ、ミスター大熊、こちらへ来てこれを持ってくれるかい。これは大きくなるし、柔らかい。猫爪ではない君が持ってくれるのがいちばんいいだろう。」
あちらでTシャツを着替えていた大熊は、慌ててパンダシャツから顔を出す。
「ええ?!僕が?」
「さ、大熊さん、こっちへ!」
沼田署長が手招きすると大熊は驚きをまだ顔に浮かべたまま、照れたように小走りに沼田とテンテイルズに駆け寄る。そして、満面の笑みで聖なる紙を受け取る。読み上げを任された繰津も少し嬉しいような気がして、大熊と視線を交わし頷く。そして、腹に力を込めて、メモ用紙に書かれた呪文をご機嫌に読み上げる。
「にゃんじ、聖別されたる高貴なる者らの鼻紙よ、その真の姿を顕し彷徨える善意を包摂せられよ。」
すると、白い紙は大熊の手のひらの上でゆっくりとパタリ、パタリと自ら展開し、その面積はどんどん大きくなる。
「うわあ、やぶりたくなる」
「ふわふわだね」
「大熊さんに預けて正解だったにゃ」
ネコビトたちが口々に感想を口にする中、白い紙は、折り目を開くごとに大きくなり、やがて大熊の腕から芝生へ伸び、それでも止まらずに約3メートル四方の大きさとなる。ようやくに動きが止まると、三ツ池が「ちょっとでかすぎるんでないか」と呟く。
「大丈夫、サマリタンを収めるときゅっと縮むそうよ。」
沼田署長が言うと、遮無が真面目な顔で返す。
「洗濯しちゃったセーターみたいですね。」
「どうやって兵士から霊をエクソサイズしてここへ移すんですか?」
青木が言うと、繰津が手にしたメモ用紙を振って見せる。
「にゃんじら、彷徨える墨に宿りし古の善意よ。古き戒めから解き放たれよ!」
繰津が声を張り上げると、あちらで鈍重にごみ拾いを続けていた兵士たちが一斉に膝をつき、倒れる。そして、そこから灰色の霧のようなものが次々と立ち上る。
「今ここに…ええとにゃんて読むんだ、ここにもたらされし聖なる依り代に招く!新しき衣を纏いてその本質へ還るのにゃ!いざ!」
繰津が朗々と読み上げると、霧は猛烈な勢いで大熊の方へ向かう。
だが、大熊の広げた聖なる紙には吸い込まれない。その代わり、靄は大熊ごとぐるりと取り囲んでその周囲を回り始め、大きな渦を造る。
「大熊さん!」
大熊は黒とも白ともつかぬ煙に取り巻かれ、その手にした聖なる紙ともども姿が見えなくなる。そして、しばらくは青い空の下、煙幕に囲まれた大熊だけが凄まじい様相を呈している。
「大熊さん…!!!」
呼びかけに答える声はない。
045. 大熊さんのTシャツ
「どうしよう、大熊さんが…」
ちゃる捜査官はそして、静かにサイレント・ミャウを繰り出す。この技は時として天上の神の御心をも動かし、時に強力な味方を届けさせる。
「大熊、どうした、出てこい!」
煙幕を取り囲んだCATの面々の背後から、カリンの声がする。皆が振り返ると、カリンとビアンカが並んで歩み寄る。
「まさかサマリタン如きに乗っ取られたとかいうんじゃないだろうな?お前はそんなもん憑かなくても底なしのお人よしだろうが?!早く出てこい!」
「あ、は、はい!すみません、でも、ちょっとお見苦しいかもですが…」
煙幕が次第に薄くなり、大熊の手足が見え始める。その手には、ありがたい巨大な聖なる紙がピクニック後のブルーシートのように折りたたまれているのが見え、CATの面々は互いに顔を見合わせる。やがて大熊の腹が見え、頭も見え、その顔が限りなく恥ずかしそうなのは、着ていたパンダルマンTシャツが縮んで若い女の子が着るヘソ出しピチピチTシャツのようなスタイルになっているからだ。
「す、すみません…せっかくの紙だったのに…サマリタンの煙さん、Tシャツに入っちゃいました…」
大熊の着ているTシャツには、元は獰猛な熊寄りのパンダが描いてあった。それが、今は昭和風の可愛いキャラの絵柄で、頬にハートマークまでついている。
「にゃんと…お目々がきらきらしている…」
「え、こ、これがサマリタン?ちょっとイメージが…」
「あ、でも、横に善良なる野獣って書いてあるよ」
「あ、これは僕の…その、元々のキャッチコピーです…」
「ええと…申し訳ないけど、それ、回収するわね…」
沼田署長が苦笑しながら大熊に言う。
「え、回収って?」
「脱いで証拠として提出しろってさ。ほい、着替え。」
カリンがおかしくてたまらないといった様子で、新しいTシャツを差し出す。新しいTシャツには高そうな光沢がある。
「これ、フワモコ王国で作った『ワビサビの郷』向けの試作品なんだって。」
カリンの後ろから、嬉しそうにビアンカが追加情報を提供する。
「黒字に白の水墨画風、カリリン山猫フォームなの。大人向けで、原画は私よ。まあ、不破さんが米子トラさんに反対されたら話は消えるから、幻になるかもなんだけど。」
「え、こんなにかっこいいのに?」
「あんたの決まり具合によっちゃトラさんも考えをかえるかもよ」
師匠と美しいネズビトに期待のこもった目で見られて、大熊は照れ臭そうに後ろを向き、ピチピチサイズの昭和キャラシャツを四苦八苦して脱ぐ。それをクスクス笑いながら沼田署長が商品袋へ収め、封をする。大熊は、色白な太い腕を真新しい黒いシャツに通す。
「あら、XXL持ってきたのに、小さかったみたい。」
ビアンカが驚いた様に言う。
「まあ、大熊はでかいから。」
大熊はピッタリサイズで少しスタイリッシュ風な着こなしな上半身に、トレーニング用のパンツが若干ちぐはぐな印象だが、とても嬉しそうだ。
「うわあ、やっぱこれ、めっちゃかっこいいですね!」
大熊が満面の笑みで喜びを表現し、「ありがとう!」とビアンカを持ち上げて一周くるりとまわって降ろす。そこへ、ちゃるに手を引かれたテンテイルズが歩み寄る。
「君はもしや…シュローディンガーか?」
「YES!!」
「ねービアンカ姫、もしパンダルマンだめなら、テンテイルズの絵を描いてよ、ママ喜ぶから。」
「それはいいアイディアだ。実は…」
あちらでは沼田署長とシャムが今一度ありがたい紙を広げ、繰津が呪文を唱えるのに合わせて敷物を畳む要領で紙を畳み直している。向こうの噴水では、疲れたネズミ兵士たちに三ツ池と青木がドリンク剤とガジガジ君を配っている。ちゃるはテンテイルズ、ビアンカ、カリンと大熊のためにできる限りの通訳をし、分地はカメラを回しながら時々通訳を手伝う。縁は挨拶もなく飛行機を飛ばし、皆はそういえばアンソニーはどこへいったのだろうと考える。
046. 不破さんとパトラさんのガールズトーク
フワモコ王国の不破望子のオフィスに、テンテイルズの肖像が1枚増えた。白地に隅の濃淡で描かれたその肖像は、渋く、スタイリッシュだ。背景にはうっすらとユキヒョウの姿が見える。右下に、シュローディンガーの小さな手形が、薄く捺してある。望子とパトラはそれをうっとりと眺めながら、フワモコ王国の新エリア「ワビサビの郷」について話している。
「では、来年の3月にいよいよオープンなのね。」
「ええ。それに、テンテイルズが後援する環境保護団体のコラボは11月からよ。アニメ化は…実現すれば再来年だけど、どうかしら。」
「アンソニーが主題歌を書くんだって意気込んでたけど、うまくやれるかしら」
「あなた、カリリン役のオーディションを受けると聞いたわ。」
「ええ。彼女、クールだわ。」
「お義母さまもすっかりファンよ。米子トラの30年ぶりの新作は、『化け猫、花一輪』は挿絵もある時代小説なの。」
「トラさんとビアンカ姫とは?険悪ムードは解消した?」
「ビアンカちゃんの描いた大熊&花梨の肖像を送ったら、すぐに雪解けムードよ…この才能ですもの…アートのレベルでは通じ合うものがあるのね。ところで、パトラちゃんは、テンテイルズに憑いている猫のうち、どれが彼に一番影響を与えていると思う?」
「どうかしら、私には、彼の元の傾向にあった猫しか影響していないような…」
「ああ、パトラちゃん、わかってる!若いのにえらい!」
「ねえ望子さん、トラさんにテンテイルズとアンソニーが主人公の絵本を描いてもらうって、無理かしら?」
「うーん、そうねえ。テンテイルズじゃ若すぎる、アンソニーは赤ちゃんにしか見えないって、お義母さまは言うのよね…」
フワモコ王国ではネコビトのガールズトークが止まらない。
047. ひとになるべくやさしく
例の文豪が住んでいた日本家屋に、また青木と繰津は来ている。この文豪の家の保存会の人間の人も5人ほど、「文化的・資料的価値の高い品」が収められるというのでなんとなく来ている。彼らは掛け軸が破れていたことに心を痛めていたので、代替の品が入ると聞いて少し嬉しそうだが、それが額縁に収められたTシャツであることに少し当惑もしている。繰津は破れた掛け軸を取り除かれて寂しくなっていた空間に、大熊のパンダTシャツの額縁をかけながら唸る。
「これをここに掛けるのはもはや冒涜な気がするにゃ」
繰津の乗った脚立を支えながら、この家の保存会の比較的えらい人とそうでもない人も、苦笑いする。対して、あまり邸宅とTシャツのミスマッチに興味のない青木は早く終わらせて帰りたい。
「しかし、サマリタンの依り代があった場所はおそらくここですし。いいじゃないですか、可愛くて。」
「うーん、あの紙をまた試してもいいかにゃ?」
繰津が表装と共に紙に包まれていた、例のありがたい聖なる紙を取り出す。保存会の比較的えらい人間と、そうでもない人間が興味深げにそれを見守る。
「まあ、準備もいいようですし、どうぞ。」
「では、にゃんじ・・・」
「ああ、待って。すみません、皆さん、ちょっと危ないので下がった方がいいかもしれません。」
青木が保存会の人々を少し後ろに下がらせ、笑顔で礼を言ってから繰津に頷く。繰津は例の口調で呪文を唱える。
「にゃんじ、ちょうどいいサイズに折り畳まれし聖なる紙よ、畳1畳分を20パーセントくらい大きくしたサイズに展開されよ。」
「今回は随分具体的ですね。」
「実は、表装を前回のとおんなじくらいの大きさで作ったのを持ってきたのにゃ。サイズが合わないと困るにゃ。」
繰津は次第に展開しつつ大きくなっていく紙を畳の上に降ろし、保存委員会の人から細長い紙の包みを受け取って大きな掛け軸の表装を取り出す。
「やあ、素敵な表装だ。」
「繰津さんもお目が高い」
保存会の人間の人々はキラキラ目のパンダシャツではなく、渋い緑の表装の掛け軸を飾れそうだと、期待した様子だ。
「まだわかんにゃいですよ、このTシャツから言霊が移るかどうか…」
繰津は若干緊張気味だ。そして、保存会の人々に、ちょうどいい大きさになった紙を表装へ、かわいらしい容器に入ったデンプン糊をちょこちょこと塗って貼ってもらう。そのデンプン糊もキラキラした目の可愛らしい容器に入っているので、繰津は不安になり、用意が整うと不安を払拭すべく少しぞんざいな調子で言う。
「さて、百年とちょいまえの誰かの善意さん、今は大熊氏のTシャツに宿りたる古の善き魂ちゃん。ぶっちゃけるとそこはちょっと格好が悪いんで、こっちの格のお高い方へ移りたまえ。さ、青木ちゃんもにゃんか。」
「ええ?えーと、紙を張り替えたんで移ってください、please。」
「プリーズ、ああ、それか!」
繰津が英語圏の魔法の言葉が古い和の言霊的な何かに通じたのに若干驚きながら、大熊のシャツから立ち上った煙を見て一歩下がる。その煙は一瞬、可愛らしいデンプン糊の前で進むのを止めた他はまっすぐに、掛け軸の紙の方へ吸い込まれていく。そして、そこに、「ひとにやさしく」と文字を描き、し、と、くがその場でぐるりと一回りすると、落ち着いた。
「さ、これでいいにゃ。」
「よく素直に移りましたねえ。」
「全部平仮名になってるのがにゃんとも…時代かにゃあ。」
「あ」
保存会のあまり偉くないひとが声をあげたので、繰津と青木は振り向く。
「なるべく、が追加されましたね…」
「せちがらいにゃ…」
048. マグロカマトロかき氷大会
「終わったん?」
「おわったのぉー? おいでぇー」
阿日と丘斜がオフィスの面々をモルグに招待し、マグロカマトロかき氷大会が始まる。削りだされたマグロのカマトロは、そのままイチゴシロップをかけたかき氷のようにも見える。それに甘党のネコビトは練乳を、甘党でないネコビトと人間は醤油をかけて食べる。途中で根田さんが打ちたての蕎麦を持って登場し、三ツ池はサバの味噌煮の缶詰と生クリームを持ってくる。
「カリンさん、ヒトのカマトロにプロテインをかけないでください」
「分地ちゃん、もうテンテイルズいないからカメラいいよ」
「ああ、ちゃるを撮ってるんで…」
「可愛いもんねえ。あれ、コータ君は?」
「今日は学校。なんかね、学校でね、妖怪仲間が困ってるんだって。」
「そうかぁ、残念。」
「署長!目玉いかがですか?」
「オイシイの?」
「どうかにゃあ」
「わ!」
ちゃる捜査官がクシャミをし、カリンがカマトロペチーノにかけたプロテインが飛び散る。ちゃるは真っ白になった顔で目をしばたかせる。
「ちゃる、舐めてみて」
「だめよう、マッチョになっちゃう」
「たんぱく質は成長にも大事だぞ」
そんなこんなで、CATは平和である。
付録 ChatGPTさんが自主的に作ってくれた二次創作絵本の文章
『テンテイルズとおそばと、ネコビト』
きょうは ざぜんの おけいこ。
「しずかにしてくれたまえ」と てんているず。
でも こねこびとが ふたり、かれの ひざに ちょこん。
「やれやれ……これは うれしい なんだい」
カーディガンを ふわりとかけて、のびた おそばを そっと たべる。
「ふう。おいしい。やはり そばは そばの あじがする」
……そして きょうも てんているずは、せかいじゅうの ファンに てを ふった。
『テンテイルズとじかんのくすり』
あるひ てんているずは こねこびとの くしゃみに きづきました。
「なんだって! ひえたのかい?」
てんているずは おおあわて。
おちゃをいれて、ゆたんぽを つくって、
ふるいレコードの おんがくを ながしました。
「これをきけば、じかんも あったまるのさ」
こねこびとは くすり、くすりと わらって、
あさには すっかり げんきに なりました
『テンテイルズと うたうほしのひみつ』
> ——バッハからビートルズ、そしてぼくたちへ。
ある晩、テンテイルズはネコビトたちと一緒に天体望遠鏡をのぞいていました。
「見えるかい? あれが“うたう星”。むかし、バッハが夜空に投げた音符が、ああして今も光っているんだ」
ネコビトたちはきょとん。でもテンテイルズは続けます。
「モーツァルトの星はよく走り、ベートーヴェンの星はまっすぐぶつかってくる。ビートルズの星はちょっと笑ってる」
ネコビト「テンテイルズの星は?」
テンテイルズ「ぼくのは…たぶん、迷子になってるかな」
でもその夜、ネコビトたちは夜空の一等星がぴょこんとウィンクしたのを見ました。
きっとテンテイルズの星が、自分の居場所を見つけたんです。
テンテイルズと おとのすきま』
> ——音楽は、鳴っていないところにもあるって、誰が言った?
テンテイルズが書斎でギターを弾いていると、ネコビトが言います。
「テン、なんで ときどき なにもしないの?」
「ふむ。これは“休符”ってやつさ。沈黙の音、って呼ぶ人もいるね」
ネコビト「おとが ないのに?」
「そう。ぼくたちが何かを感じるのは、音がないその“すきま”にこそ、ほんとうの音があるからなんだ」
ネコビトはそれから、風の中のしずけさや、夜の中の時計の音に耳を澄ますようになります。
---
🎤 『テンテイルズと まいごのこえ』
> ——魂のブルースは、足元に落ちている。
ある朝、テンテイルズの玄関に「こえ」が落ちていました。
かすれた、小さなこえ。「ぼくは、うたになれなかった」
テンテイルズはそれを拾いあげ、ギターの弦の上にのせて、ブルースを奏ではじめます。
「失くしたこえも、歌になる。ぼくが保証する」
その夜、町の広場で、テンテイルズとネコビトたちのブルースが響きました。
「歌えなかったこえ」が、ようやく空に昇っていきました。
CAT File 2 : ニャンダリズムとワビサビファンシー
ネットの画像生成AIに作ってもらった画像を追加しました。
けっこう思い通りには作れないので、正確ではないです。
◯テンテイルズの名前は、スティングのアルバム名から来てます。
◯まんまる5のファンの方、ごめんなさい。
◯クルツの先祖の飼い主は内田百閒さんです。先祖じゃなくて本人かもしれません。
◯破れた掛け軸の屋敷は芦なんとか公園にあり、フワモコ王国は、ピュー◯ランドのイメージで、国宝級の仏像がある深掘神社兼寺はそんな名前ではないですがホントにダルマみくじがあります。


