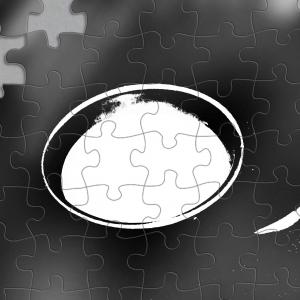「水面めまい」
一
白百合が泣いたかと思った。
少女の瞳は一つ夕暮のなごりを白い翼に一すぢ零し流れて染まった曙を待つ夜明け色、しかしもう一つは躑躅の花。生れつき春の扉を知らぬままの降る雪の白を温もりに溶かしたら、何處へ行こうか見誤るのに恐れを抱くあの祝福の色に、誰が千切ったか今では分らぬ蒼い健気の紫陽花の光を雫にして手紙した涙を落しかさねて絞った柄の姿、赤でも白でも黒とも言えない自然には先ず無い姿で咲いている。
病気、呪い、吉兆不吉、進化変化突然変異、とやかく少女は推察されたが答えはいつも出ないもの。彼女は捨てられ樹の下で半殺しにされて、一族他人共の記憶から殺された。
何て言う樹だろう。片目が自分の頭から流れる血で花弁に染みていくのをぼんやりみながらぼんやり想った。
「雪の樹だよ。」
そっか、私の名前、雪斗って言うの。似ているね。あなたの声、なんだかオルゴールみたい。
「オルゴヲルを聞いたことあるの?」
花のワルツ。手で回す小さい木箱に入った物。
「もう一回聞きたくない?」
聞いていたいけれど、もう眼がだんだん開けられない。
「じゃあ聞かしてあげるから、今はゆっくりお休み。」
うん。ありがとう、雪の樹さん。あなたも、…寒く…ないかしら……。……
「ほんとうの寂しがりやはね、寒い方が好きなんだ。」
少女は唇に氷の藤花の欠片を一つ齎され、記憶無いうちに命を莟に留められた。
二
かつて桜の樹は人に見られる鑑賞の樹であった。暑い夏と寒い冬を終えた後に咲く、喜びや祝いの花々とされて、春になれば人は不思議に桜に惹かれて花見に行ったし、好きな花は人の数違えれど、桜となるとどの人もまあ嬉しがって興じるものだった、人々は顔も紅に染めて笑ったり寝転がったり遊んだり「春の陽気」がぴったりの眺めを一生懸命に造っていた、桜にそう動かされているとも分らずに。
分らぬまゝに笑っているだけの幸せを、やがて人は不幸と定義しその言葉に皆興じた。楽しい不幸自慢は大衆の油の脳ミソに火を点けて巻き戻しの出来ぬ種族のくせにやたらとオイルを目から零した、それに足を取られ滑って目覚めた心算の人が元凶を断とうと躍起になって燃える身体ごと植物に投げつけた、他所から見れば馬鹿の真似事自分等の内では特攻殉職、胸に搖らがぬ誇りを焚いて赤い炎白一筋に……言っておくが日本の国旗は燃えるためにあるのではない。植物は冷然と自らの帽子を脱ぎ始め、やがて植物の正体は火が本来の働きを忘れるような雪の姿だと打ち明けた、この雪はどうしても溶けない。
人々はようやく植物を恐れることを思いだしたのだが、その矢印の方向が如何にしても不味かった。植物の世界と人の世界をまあ完全に分断して一切関わりのないように(と思い込んでいる)暮らし始めた、植物は悪、人類の仇を標語にしてよくある一致団結も素晴らしく。
そんな世界でかの少女が生まれたのだ、どう扱われるかは理解るであろう。
三
「ねえ、雪の樹さん。」
「なあに?」
「ずっと此処で独りなの?」
「雪斗が来てくれたからもう独りじゃないよ。」
「じゃあ私が来る前は?」
「その前はね、桜桃が居たから、やっぱり独りじゃないよ。」
「桜桃?」
「今はあなたを探すのに疲れて眠っているの。」
「どうして私を探していたの?」
「かわいいから。」
「!」
頬にぴしゃりと付いたまゝの血の色が、頬を染めたかのように見えた。夜明け待の人の瞳と、人の知り得ぬ淵の花の瞳が、もじもじと迷う北極星。
「そんな言葉、雪の樹さんしか仰有らないの。」
「かわいいから、私の傍に居てほしい。」
「あなたは虹が好きじゃないの?」
「虹より花や蟲の方が好きかな。」
「ふゝ。」
「?」
「やっぱり寂しがりやさんなのね。」
「私は嘘が吐けないのさ。」
「じゃあ一緒ね、仲良くしましょう。」
「結婚はしてくれないの?」
「人の結婚は時間が掛かるらしいの。それに私達二人だけでどうやって式を挙げるの?」
「私の友達を呼べばいい。桜桃だけでもないのさ。」
「神父様や牧師様は?」
「月の女神にお頼み申そう。」
「じゃあ決まり!結婚しましょう。」
二人は互いに口づけを。
四
かなしいとは何かしら。ずっと雪が森々と降るのはかなしい景色なのかしら。恍惚と両眼を散る白藤に傾けて、雪斗は雪の樹の膝の上、疲れたように横たわりながら結界の内の光景の一つ。一言も発さないまゝ心でぐるぐる考える。記憶を大切にしちゃうのは何故かしら、記憶を簡単に捨てられるのはどうしてかしら、どっちも全く気づかないまゝに。私には大事な記憶なんて無いし、捨てたい記憶だって持ってない。…あゝ、何故何故どうしてと探すだなんて人間みたいで嫌になりそう、センスが無いわ。
放っときましょう、今はくたびれたから余ることを考えたゞけ、そのまゝにしておけば腐って風に払われてしまう死体なんて、放っとけばいいのだもの。
あーあ、雪の樹さん早く帰って来てくれないかしら。お留守番って最初は楽しくてわくわくするけれど、しばらくしたらしゅんとする…。
五
雪の樹は友である蝶々の姿を借りて結界の外へと出ていた。
「やあ、こんにちは。」
「こんにちは。」
気兼ね無いやりとりを幾つ交わしたことだろう、鳥も蟲も植物も小川も土も、空に至る迄雪の樹に祝福を咲かせない者は無い。
「奥様は一緒じゃないの?」
「お具合が悪いの?」
遜色無い情けの声々に雪の樹はゆっくり首を振る。
「いゝえ、約束したオルゴヲルを聞かせたくって。」
それは彼女をようやく見つけられた逢瀬の日。身内から瀕死にされ傷を散々浴びたのに雪斗はぼんやり樹の名前を想っていた、恨むことも怒ることも嘆くことも悲しむことも彼女の心には無かったのであろう、私の名前とオルゴヲル、自分のことも痛みも感じぬ心で感じていたのはその二つへのことばかりで雪の紫陽花は日に眩しく月に哀しく果敢無く輝く切なさよ。惜しい恋よ、愛しい涙よ、花でも人でも分けられない夢のような命の娘よ、どうかその心を一度も人間に傾けることの無いようにと浅間しい祈りと君への安堵、二つの憂いを溜息に零せど君には氷清らかな藤の魔除けとなるばかり。
せめて君への返礼に生きる為に交わした約束を叶えなければ私は樹として失格だ。
六
人が人として暮らすには、植物の無い箱庭はまあ最適解であったろう、肉食動物の真似をして、人間が人間を喰うようになってしまったのは酸素足りぬ身で一生懸命考えた不眠症の解答用紙、一夜漬の其と変わらないので頭ごなしに馬鹿だと思っても糾弾しても褒められぬ。
褒められることをしよう。それは人間を一番成長させる。怒鳴りも文句も嘆きも簡単である。せっかくなら快楽を貪り従順に命を返すより、誰にも知られない難しいことを一人で貪りふてぶてしく使い込んで返してしまおう、うん、それがいい。
けれど箱庭の住民どもは褒められることを良しとせず風前の塵芥の如き憂いと涙を美徳だと、太陽は人の為に在ると信じ込み、血反吐をぶちまけ日光に曝すのを良しとした。あゝ、傍観者は退屈だ。
さて目当てのオルゴヲルだが、―これがまた厄介な場所にー雪斗の家の庭に埋められていればまだしも、屋根裏に錠を下ろして仕舞われて居たのである、陽光を一切漏らさぬ低い天井とぶ厚い壁は楚歌の勢いでオルゴヲルに迫り死なゝいのかと真顔で待つ様、銀に青の細工を手毬の虹の糸の雫二垂らし流れる小川一筋へと、腐った蛤を混ぜようとするその醜さは人の溜息と変わらず恨めしい。
だがオルゴヲルはつッと澄ますーその横顔見覚えがあるような。
胡蝶となって飛んで来て、木の葉に変って入り込んだはいいが、さてこの遊々たる手回しの木箱どうやって結界のうちまで連れようか?などと手順を考えるのは人の用事、雪の樹はオルゴヲルに片頬ひたりと流れに浸し
「帰ろう。」
と一言だけで済ませるのは是植物の動き也。
七
ねえ雪の樹さん、あなたの名前は何と言うの?
「そんなこと聞いたらあの人嫌かしら。」
雪斗は桜桃と名の付いた桃色の蛾と話をしている。桜桃の大きさは一・三メートルと人の子よりはやゝ低いが人の知る蟲としては規定外で想像すらしない姿であろうが、その羽の模様はとてもやさしく、ふわりと空を撫でる度に甘い魔除けの匂いが雪どけのように肌に沁む。
貴女が呼びたいように呼んであげたら喜ぶと思うけれど。
「んー…あの人もきっとそう想ってるわ。」
名前は人間が理解出来るように付けたものだから…
「でも私自分の名前気に入ってるの。」
親に貰ったの?
「いゝえ。私生まれた時から名前持ってたんだって。」
じゃあ雪斗は人間から何も与えられていないのね。
「そうみたい。北極星は生き方を変えることはないから、捨てられたんだって。頭打たれた時に誰かがそう叫んでた気がする。」
あの子のことだけどね、
「雪の樹さん?」
いいえ、……その誰かのこと。
「覚えてないわ。」
わたしは知ってるの。
「どうして?」
泣き顔を覚えていたから。その誰かはね、男の子だった、とてもきれいな横顔をしていたの。
「…私ね、覚えていないの。」
えゝ、分っているよ。
「思い出そうとしてみるのよ、暇な、時、とか。桜桃、不思議ね、雪の樹さんと初めて逢った日のことばかり想い出して、人の世界で生活していた時のこと、人影も、物音も、全部やさしい葉で覆われてしまうの。とてもあたゝかいわ。」
そうね雪斗…
「でもその誰かの声だけは覚えているの、何故かしら?」
「雪斗。」
なつかしい声仰げばいつものように微笑んでくれる夫の姿。
「お帰りなさい!雪の樹さん!」
八
そのオルゴヲルは少女によって造られたものだった。人の世界、箱庭に生きる少女によって。
少女の名前は日毎日毎で変わっていた、春斗、若葉、瀟花、朧雪、夢、庭兎…移ろわないものはない、そしてまた手繰りかえす、だから今の糸と言う名前は結構自身でも気に入って居た。
糸は役所勤めである。人々が明日食べられるか分らない不安を千切り憂き世を愛き世として捉え始めたのは植物と袂を分けてから、所謂「精一杯一瞬を生きる」と発火物のように跡形の無い生き方をこぞって始めたは良いものゝ、如何せん睡眠不足が国民病となってしまい、「起きるな、寝ろ!」と叫ぶスローガンを国が掲げたほどである、故に必定宮仕えの者の急務は安定したお休みを供給する運びとなった。
彼女は幸い手先が器用で、オルゴヲル職人の父と母を生まれてから見て来て居たのも祝すべき、鉄の音をかろやかにさみしく弾くことに於いては恵まれたものがあったのだろう。けれどもその才に関わらず、曲選びは限られており、植物を連想させる語の含まれた曲は一切禁止、そのような譜はまとめて赤本と呼ばれるファイルに閉ざされ、保管場所は国家最重要機密其の三百六十四頁として今も現役である。
いくら蓋をしようと空気が型にキチンと納まる筈も無しと云ふが、此処に一つ断っておかねばならない、糸は赤本を合法違法問わず入手した訳ではないので、生れた時から彼女は花のワルツを知っていた、また断りをせねばならぬが両親は禁忌の曲を用心深く口遊まず、子が生れる前もその後もなんなら彼等自身が生れる前もその後も花のワルツは暮らしの中に存在しなかったのだから。
けれど糸は花のワルツのことを誰にも聞かなかったし話さなかった造らなかった、この一人きりの寂しさがオルゴヲルを照らしてあげられると幼な心に信じて居たのがまたもや糸の大切な幸い。内には数多の白い花々だけど唇淡桃にふっくらと品良く微笑む糸は立派な職人の肩書き。
北極星がこの町に降るまではね。
人々は雪斗を恐れた、生れて初めて与えられる筈の名前をもう少女自身が既に抱いて居たから、もう運命の歩き方を知って居たからである。名付けられない存在に人は戸惑い彼女は直ぐに捨てられたその時あの花が産声代りの雫をひとひら散らせたのである。
糸はその滴する音が聞こえてしまった、だからオルゴヲルを密かに急ぎ拵えたので、人が雪斗を殺すより前に自分がその仕事をしたように見せる為。
まだ曙はほの淡く眠り桜の霞しっとりと空気に覆う時分、見慣れぬ人形のぱちぱちと瞳瞬く雪斗の手をとり糸―その日は春斗と言う名前―はそっと箱庭を出た。
「何処行くの?」
「これを聴いていなさい、でも私から離れないで。」
雪斗はすなおにオルゴヲルをくるくると回し花のワルツが宙に咲いたが、人間の眠りを植物の手は妨げないので皆はまだまだユグドラシルの夢の中、誰一人雪の樹の存在など心に留めることも無く。
「着いたよ。」
かわいい妹のような子が、春斗を見つめて微笑んでいる、樹の足元にストンと座り、急拵えで粗造だのにオルゴヲルをずっと抱いて居たが、春斗の胸に渡す前、チュッと鈴蘭食むように接吻した。
雪斗の背中から靄をなだめる日の光。
叫んでいた言葉はうろ覚えの住人の其を真似たゞけ、殴り方は近所の人達の其をこれもうろ覚えに真似たゞけ、オルゴヲルは我が子殺しに来た両親に冷めた風の目で返したゞけ……大人達は笑って安堵の溜息臭く箱庭へずんずん帰った。
名前を変えなきゃ、とだけぼたぼた歩く。
九
花のワルツはくるくると遊んでいる、雪頭冠する水無月の紫陽花が少し低いなめらかな歌声、雪斗は桜桃に抱っこされながら楽しそう。
ねえ雪の樹さん。ほんとうの名前を教えて?
歌に編み織るいたづらの丈、こう訊けば夫が困ること百も承知で。オルゴヲルの旋律に散る羽の翡翠模した躑躅の花、樹を仰いではまたクスクス。
「名前なんて無いよ雪斗?私は樹だから、他の生き物みたいに特別に名付けられることは無いんだから。」
ランランラン…
妻の我儘に困じた樹はふむ、と一息考えた。
「じゃあ雪斗が与れないかい?」
ツン、と横顔澄まして外らす、歌はオルゴヲルだけになってしまった。こうなるときっと宥め賺しは雀の涙、友の蛾にそっと視線を送ってみても術は無しとでも言いたげな触らぬ逆鱗何とやら。無いものは無いと言い切るのは容易いがそれでは彼女の気は済まぬ、こういう時はどうしたものか、こんなに、だれかが…怒った…時、は。
「春斗。」
今は違います
「あゝ、じゃなかったえっと、糸。」
はい、私は糸なのです
「何でしょう?」
糸は上司の呼び掛けに返事をし、そつ無くオルゴヲル業務をこなし始める、受けた要望は「虹の歌」と名の有る童謡、彼女の横顔は嬉しそう。
「私、虹が大好きなの。」
「そうなのかい糸ちゃん?」
夜自宅の室にて糸はぬいぐるみと一人遊びをするのが常であった
「えゝ、だから今造っているオルゴヲル、虹って含まれていて楽しいの。」
「良かったね糸ちゃん。明日は何て名前にするの?」
ふわふわの月ノ輪熊はもひもひ動く
「あなたの名前から取って、月輪にでもしましょうか。」
かわいいものがだぁいすき。
「ねえ雪斗、明日塔を見に行こうか。」
星がキラリと瞬きを。
十
焦げた夏を冷やすてあての露草が素足の裏を傷付けぬようにとまろく転げる野原を見つむ、月眠る灯火のぬくもりまさに白雪、薄羽を冬の陽炎と咲かす夜に星は水色人には見えね天ノ川。水辺には牡丹も咲けば蝶も踊ろう羽音は水面と唄うだろう穏やかな時刻、箱庭から追い出された世界に体温低い少女は佇みその両頬は薔薇の熱。歩み分らぬ彼女に添うは桜桃と夜の雲となって箱庭欺き視界をぼやかす彼の夫。三人が仰ぐ塔は他に訪ねるものも無く雨中の道のようにひっそりとしている。
此の場所は図書館であった、かつては人が足繁く往来をしたものであったが、紙は植物が生みの親であるからとデータ化されない本達は箱庭への在留を認められず追いやられ、塔にし整備を始めたのは外界のもの達なので。では何故焼き捨てられる前の館の姿にしなかったのか、それは館という手段が僅かに気に食わなかったとのことで。
図書をおさめる とは鎮魂である。慰霊は塔がよく似合う。
雪で飾って雪で飾ってやがて樹の外壁は白く沁み込み、泣く象牙のような塔となった。
紫陽花の情けを込めた水晶にパチリパチリと閃くのは天ノ海の好奇をピタリと戒めたラピスラズリの文字盤で示すは方角、針は輝々と銀に眩ゆく壁にぽつ、ぽつと茎のように人を待つ、時間の区切りから離れたものは佇んで何をみるのだろう、想いは何処へしまうのだろう、川から放され翼を持たされて生きる魚達は、ヴァイオリンの郷愁では物足らぬくらいに……。
「此処にずっといたいけど」
「人の身体では耐えられないだろう。おい、さっさと行こう。」
「そうか…そうね。じゃあ……ごめんね。」
謝るなら本達のこと捨てないでよ
図書塔は月夜に灯るのが最も美しい。記憶は泉下に泡となってもそのかなしみは色失せぬ。けれど
「もうだいじょうぶ。私達が居るからね。」
塔におっとりともたれて微笑む雪斗、温かい霞とその友人も少女の傍を離れない。
「たくさんの話を教えて。」
図書塔は月夜に灯るのが最も美しい。
十一
本達は捨てられた後、輪廻を経て人間の世界で幸福に生きている、箱庭ではそう教育しているのです、そしてその物語を信じている。物語を信じるとは人間に与えられた救いです、救いに縋る姿はかなしいもの、慈しむもの、責められる姿ではありません、その怯がる背中を撫でてやるのが本達の役目…
それでも人は本を捨てるのです、確かに在った一瞬の燐光を燃えさしとして水のバケツに投げるように。忘れる、とはなんと残酷なことでございましょう。眠ることを忘れてしまった、図書をおさめる本分を忘れてしまった、かなしむことを忘れてしまった、これらはみんな優しすぎるからで、人は最も凶悪性から程遠い地球の生き物だったのに。箱庭は生まれてしまった、とても楽しそうに生きている。
真実や事実と称される者達を見つめて発狂するくらいなら、そんなもの見なくていい、見たところで誰も彼も救えないのに、それらを忘れてしまうことの方がよほど苦しめてしまうだろうに、どうして、どうしてこんなに優しすぎる⁉
本は涙をはらはら零す、それを抱きしめ撫でる雪斗の瞳、たじろぎもせずうつくしい両眼は何を射る。
「雪の樹さん。」
「雪斗、」
「止めないで、あなたが嫌なら桜桃に頼みます。」
「それは」
「あなたとはもう、これっきり。いいの?」
「私の方から願い申した結婚を如何して此方から捨てられましょう、我が雪月花…!」
「では叶いてくださる?」
「言わなくても分るよ。赤本の三百六十五頁が欲しいんだろう?」
スッと細めた三日月の清廉を籠めた青宿す瞳、踊るのを愉しみに待つ。
「塔で皆と本を読んでいなさい。直ぐに戻って来るからね。」
「雪の樹さん。」
蝶々の姿に泳ぐ夫に一言、
「その時、きっとお名前教えてくださいね。」
十二
「若葉。」
昨日糸と呼ばれた少女は慌ただしい声に振り向く。
「昨日赤本が盗まれた。」
少女は
十三
真っ赤な椿の古い幼子胸に抱き、雪躑躅の精霊は歌を舞う、真っ赤な靴に真っ赤なカチュウシャ、夫が結んだ夜会の髪、凍る白藤ひらひらとワンピイスに裾遊びながら水に搖籃う生贄の娘。湖深き結界は太古の大樹に繋ぎ留められて、少女は愉しく雪を降らす。抱きしめた本をペらりぺらりと捲っては微笑みほゝえみ千尋の雪とワルツを踏む。
くるり、くるり。水面は回る、禁忌の音符をぱしゃぱしゃと跳ねさせて、くるり、くるり。迷子の歯車のように、けれどもそれも水の中。
「可哀相な若葉。」
緑の色濃き一葉が、みるみるくるくる回り始める。
「ずっと続けてなんかいられないのに、あなたは。」
「若葉!聞いているのか?」
誰です、あの女の子。
「緊急だが異常でもある、我々は無闇に保管庫へ近づかないように。」
あんな子、知らない。
「今国民にも避難を呼び掛けている、声明が発表されたから、君も指示に従ってー」
あんなほゝえみ、私は知らないー
“拝啓
残暑がまだ駄々をこねてどう扱えば宜しいか首を捻っておられますでしょうか。わたくし達の居ります場所は雪がずっと止みませぬ、それも道理で、熱いのはあなた方だけなのですから。
ですがわたくし達はそれを深く情け無いとは思いはします、けれども責め立てたり蔑ろにする心積りでは御座居ません、だって熱は太陽の他許されているのは人間達だけなのですもの、如何してわたくし共が拒めましょう。
我々の嘲笑を受けるのは一つの場所、赤本と名付けられた頁を閉ざすその場所です、其処は鎮魂の為されるものではない。
だから、物語は物語の在りたい場所に帰します。
それではどうぞ、ごきげんよう。“
はつ恋のように本が輝く。あゝ、温かい。
「若葉、早くこっちへおいで。」
「若葉、君も早く避難しなさい。」
どうして私を知っているの
いくらでも呼んであげる、若葉が嫌なら糸にしてあげる。一番呼ばれたくない名前はなあに?
私は若葉よ糸じゃない
「若葉!若葉!」
そうです若葉です
「泣いている場合か!これは外の、植物達の我々への侵略だ!今にも攻めて来るぞ、早く避難するんだ!お前は私と向かうエリアが違うから……何を?」
かわいい若葉に教えてあげる。
「止めろ!キ様、私は上官だぞ!」
桜の花は
「助けて!――――」
散らないでは綺麗な新緑にはなれないの
「…………」
そして紅葉になって雪に戻るの憶えてる?
カツン、カツーンと靴の音、定時に帰るよな背姿、後には折られた枯枝一つ。
十四
少し瞳を開けてみる。
塔の上、迷わず立つは水晶造りの風見鳥。羽は透明なれど鶏冠は忘れぬ朱色、その一念は花と咲き、白牡丹を贈る蓮華躑躅の跪く。
もう少し瞳を開けてみる。
追放された塔は生まれ変わって人間の元になど居なかった。冬の胎動はやがて秋を産む、いとも簡単に紅を描く果ての無いカンバス、けれど其処に人は無く、一輪の精霊が冠もかろく微笑まし。
くるり くるり
ワルツの音色。
ランランラン…
あの子の歌声
きらきら
すてきな瞳
「待って。」
くるんと走り去るのが分かったから、手を伸ばして呼んでみたかった。
「雪斗。」
生まれた時のまゝで良かった貴女を。
「瀟花は眠ったかしら?」
幼い姉のような少女の額を撫でながら雪斗は夫に尋ねる。
「あゝ、もう起きることも無いだろうし、直に小枝にでもなるだろう。そしたら君のように覚めるのを待てるようになるからね。」
「あの子の好きな熊のぬいぐるみも連れて来なきゃ、夜泣きしたら可愛想だわ。」
「名前月輪にしたがっていたけれど、そっちは如何する?」
「好きにさせましょう。呪いじゃないんだから。」
しばらくは明日のまゝで、…来ない明日を迎えに行けるようになるまではね。
十五
凍月は雪を降らす、氷の雨。花は陽光の薄絹をかむり、花々の姿へと身を溶かす。
その心は、麗しき。
瀟花は塔の中の机の上に仰向きに横たわって居た。両手を組み、白装束に纏う肌はほんのりうつろに透きとおるも唇だけは誰かにキスされたかのように色めいて、瞳はその正体を知りたげにぱちぱちと恒星めく。
「起きたのかい、瀟花ちゃん?」
ぬいぐるみが頬にかぶさる、もふもふとしたその頬ずりは月ノ輪熊のあの子に異ならず、もひもひとした裏声は誰かが連れて来てくれたので。
かわいいものだだぁいすき。
「おはよう。お腹が減ってはいない?綺麗な水がたくさんあるよ。」
その顔は熊ちゃんに隠されて分からない、その声も
「階段を一つずつ下りておいで。此処は食事をする場所ではないからね。」
瀟花に背中を見せないように後歩きで話し続ける。くるくる回る螺鈿の階段、ことりことりと高い駒下駄で下りてゆく、この足音はどちらのものだろう、などと。
「瀟ちゃん瀟ちゃん、何を食べるの?」
綺麗な水辺がたくさんあるんでしょう
「そうだよ、こっちこっちだよ。」
じゃあ雪がたくさん居るんだ。
「いっぱい咲いてるよ!」
それならいっぱい食べられる!
「想い出した?想い出した?」
水は雪から降るのだっけ?
「それでもいいよ。そのまんまだよ。」
約束したわ、約束したの、あなたはそのまゝに生きなさいって。
ことんことん。かつんかつん。螺鈿はやがて水面の鏡に戻り始める。
わたしに逢うためにあの子は駈けて来たのに
私はあの子に何をした?
「あ」
鏡がとうとう湖になって、逆さまに水中の樹をなぞる。
十六
幹は泡の魚の鱗のようにそっと触れゝば消えてしまう、けれども弾けた後から後から光を引いて伸び続ける。根も無いまゝに佇む巨木はくるりくるりと繁みを降らせ眠りの莟を落さぬように気をつけながら幾夜幾夜もの花を散らす。
その花びらは金魚になった、小鳥になった、破片になった。
目を光らして瀟花を射る、その瞳を知っている。
「
「呼んじゃだめよ、瀟花。」
ひとさしゆびが唇にふれる
「教えてあげない呼ばせてあげない。わたしの名前は秘密だもの。」
氷のようなその体温
「分かってあげない許してあげない。あなたはずっと此処で笑ってたらいい。向こうの世界なんて似合うものか。」
待って
もう一度
名前を呼ばせて
「わたしの名前は何でもいいの。」
あ、いや、またその、微笑みなんて
…こっちはそういう世界だったのに忘れたのね。
ごぼりと吐いた泡の息に、霞んで霞んであの子が見えない。
十七
「似たようなとおい物語を知っていますか。
其処では妖精が暮らして居るのです、そして役目を終えた存在はその国の土になるのだと描かれます。
あの子もやがて、雪になって降るのでしょう。その時きっと、空を見上げてみてください。うつくしい青白の北極星が在ることでしょう。」
パタンと閉じる表紙の無い本。躑躅の瞳が此方を見やる。
ねえ、あなたは私たちに何を願った?
終
「水面めまい」