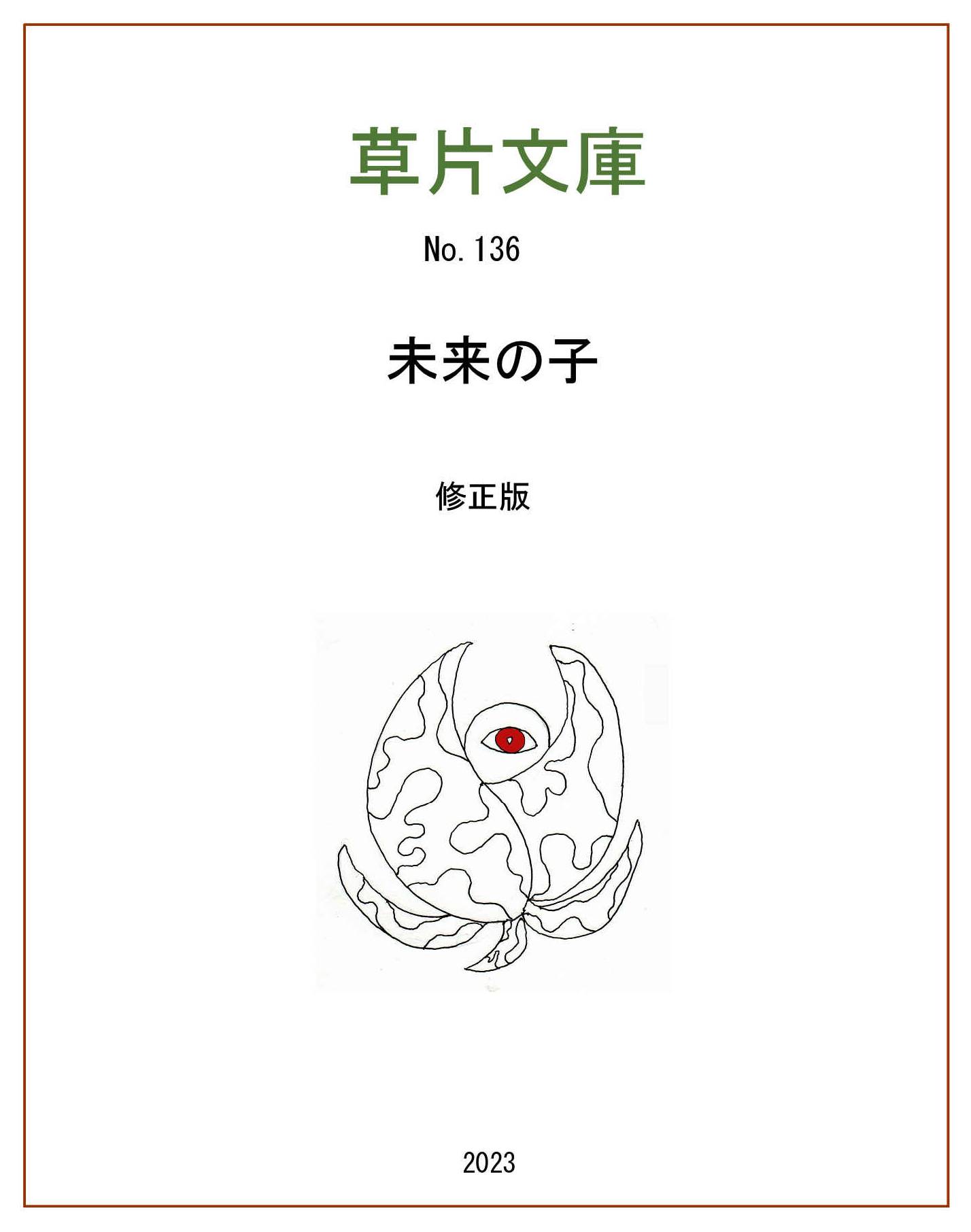
未来の子
遠い未来の話しです。
地球の表面には海と陸。陸には山と平野、そこには川が流れ森や林が整然と並んでいる。川沿いには土手が築かれて土の丘になっていて草が覆っている。その大昔、土手はコンクリートという野蛮な物質で覆われていた。しかし、今はそれも取り除かれて、どこにも見ることができない。森や林には小道ができている。しかし、石段も木でできた段々もない。山に登れば見渡す限り、一見自然にできた物に見えた。確かに、動物たち、昆虫たちは自由に生活を謳歌している。
地球の表面は自然に任せられている。ように見えた。実は地球の気候はコントロールされており、台風もくるが、川が氾濫するほどの大きい物は、何十年に一度のことで、水かさが堤防すれすれになる程度の雨を降らすだけ。風も所々で木が倒れる程度である。
海も程々にあれ、あれた波が陸に打ちつけられるにしても、大きな損傷をもたらすことはない。
人類は地下に潜っている。地上の様相は科学的にコントロールされた大気により、理想とされた自然の状態に保たれているのである。
地下のよさをみつけた人類は、地下を掘り進める科学を発達させた。大きな穴を掘り、まるで蟻の巣のような、何層にも重なった生活空間を地下奥深くまで作り出した。それが町として機能しているのである。
人工太陽と人工の空気の流れにより人々の健康は維持され、昔の人間が見たら理想の体型を持つ進化の頂点に立つ生物になっていた。
しかし、あるとき、人類は昔と変わらない生活形態が最も良いものとして、維持することにした。家庭、夫婦の概念は変わってはいる、社会の最も小さな単位として存在していた。家庭は夫婦と呼ばれる複数の人間によって構成され、子供を育てる場所としての機能があった。
「やっと送られてきたわよ」
地下の町の中のありふれた一つの家庭に荷物が届けられた。
女性が自動配達ロボットから受け取った荷物を一つの部屋に運んだ。
荷物には人口調整局発とある。
部屋には真ん中にテーブルがおかれ、三つのソファーがその周りを囲んでいた。部屋の一方には大きな窓があり、人工太陽の光が射し込んでいる。地下の人間の住居では24時間周期で天気がかわる。雨が降ることもある。
女性の声で二人の男性が入ってきた。
「どうだい」
女性は荷物をテーブルの上においてほどいている。
合成樹脂でできた箱を開くと、中では赤い顔の赤ん坊が目をつむって、寝息をたてている。
「男なのかい、女なのかい」
二人の男がのぞきこんだ。
女は赤子の産着をはだけ、足の間を見せた。小さな陰茎が横を向いている。
「こんなパンフレットが入っていた」
箱の中から女が説明書をとりだした。
時短育成とある。
「なんだい」
一人の男がパンフレットを読んでいる女にきいた。
「一年で18歳だって、ただし、特別食が必要なようだわ」
「高いのかい」
「そんなに高くない。それを申し込もうか」
二人の男はうなずいた。
「前の子供は18になるのに二年かかったからな、一年で職業に就けるのはいいね」
「そうね、たくさんの子供を育てられるわ」
「男か、どんな子に育てたいんだ」
一人の男が女に聞いた。
「前の子は宇宙飛行士になったわね、今度はエンターテイナーはどうかしら」
「どんな領域がいいんだい」
もう一人の男がきいた。
「相撲取りはどうかしら」
女が答えると、男が
「子育て条件に相撲取りを入れておいたのかい」
相撲取りはとても人気の職業だ。
「いれてなかった」
「それじゃ無理だな、今回はおまえの希望の子どもだ、どんな職業をいれといたんだ」
「科学者、医者、歌手、野球の選手」
希望の職種を書いて赤子を申請すれば、それに適した遺伝子を持つ子どもが送られてくる。
女は看護師の資格を持ち、市の病院に勤めている。一人の男は宇宙船建造会社の宇宙船設計士、もう一人は歌手である。
前に育てた子供は、宇宙船建造会社に勤めている男の希望で、宇宙飛行士や惑星開発技術に適した遺伝子の赤ん坊を送ってもらった。その子は希望通り、宇宙飛行士になって、太陽系巡回挺の船長になっている。
女が子供用の移動ベッドをもってきた。寝ている赤子を移し薄い紙をかぶせた。上掛け布団だ。和紙のような薄いものである。そのころの人間にとっても脊椎骨は大事なもので、寝るときには程良い堅さと柔らかさを持った布団に相当する物を敷かないといけなかった。上掛けは保温の役割だけなので、厚い必要はない。温度自動調節機能をもつ紙をかけて寝る。
子供用の移動ベッドは、赤子の体の状態を把握するセンサー機能がそなわり、体重や身長などの形態的なことから、体液の状態、内蔵の状態を観察している。必要な項目は連続的に記録されベッドに設置されている情報箱にしまわれる。異常の時には、すぐ親たちが気づくようになっている。少し高いが特別装置を備えて置けば、子供の情報は育児情報センターに送られ、監視もしていてもらえる。
ミルクは送られてきたものをベッドの脇のタンクに入れておけば、自動的に飲む料だけ暖められ、吸い口が自分で判断して赤子のところまでノズルをのばす。
「この赤子キットは一月で二歳になるみたい」
「それじゃ、学校に通うようになるのは二ヶ月後か」
「そうね、四歳から小学校だから生まれて二ヶ月、十歳から中学校だから五ヶ月後、十四歳から高校だから七ヶ月、九ヶ月、十八で職業訓練学校、十二ヶ月、二十四歳で独立だって」
この時代、大学というものがなくなっている。職業訓練学校の中で、教養と専門を学び、教育職、研究職、工学、商学などにわかれていく。絵を描いたり小説を書いたり、歌を歌ったり、楽器をかなでたりするのは、卒業まで誰もがやらなくてはならない必修教養事項である。それは大人になり、脳のストレス抑制する大事な能力だからだ。子どもはどれをやってもいいし、途中でかえてもいい。もちろんいくつ学んでもいい。スポーツというのは健康教養のなかにふくまれ、競技会などもあるが、参加自由である。見せるスポーツはプロスポーツコースにはいって、将来どこかのプロチームにはいればいい。もちろん、これは教養の延長であり、遺伝子に依存しているもので、誰でもがプロに進めるわけではない。
「ずいぶん早く育つね」
「脳の発達を促進させる物質を使うことが許可されたようね」
「そりゃ楽しみだ」
それから、その家庭では女が中心になって一年の子育てがはじまった。
家庭には必ず動物たちがいた。猫犬鳥、そのほかあまり大きくない動物たちが飼われていた。その家庭を構成する人たちの希望により、動物局より貸し出され、一生生活をともにするが、飼い主が死亡すると、動物局に引き取られ、動物たちは寿命まで飼育される。
この家では女は犬と鳥を飼っていた。宇宙船設計士の男は猫と鼠、音楽家は雅美鳥とオポッサムを飼っている。それらの動物たちは三人が育てる赤子をそばで見守っている。
赤子が泣くと雅美鳥がベッドの脇でいい声をあげる。猫が寄り添う。
家族とペットが一丸になって子育てをする。
女と男たちも、役割分担をし、お互い協力して、赤子の管理にあたる。だれかがお風呂に入れ食事の世話をする。子供のキットを送ってくれた会社から大人になるまで必要な物資は届き、必要なときには相談員が訪ねてくるなど、子供が大人になるまで見守ってくれている。
赤子は医療的処置を受けることもないほど問題なく育ち、一週間ではいはいをはじめ、十日目に二本足で立った。
それからは女と男たちと一緒に食事をし、自分の部屋があてがわれ、そこですくすくと大きくなっていった。小学校にはいるまでは家族と育ち、友達は動物たちだけである。
二ヶ月たち、子供も四歳になった。近所の小学校から入学許可証がきて、毎朝、迎いののバスがきて、十分ほどはなれた学校にかよいはじめた。ここではじめて人間の友達ができる。もちろん家庭で保育教育の中で、他人という人間がいて、地球の上で一緒に生きていくことを教わり、コミュニケーションの方法は親から自然と伝授されていく。
小学校では一つのクラスに数人の担任がいて、子どもたちをみる。どちらかというと、遊ばせているといった方がいいかもしれない。母国語の使い方を教わり、ほとんどが工作と遊技の時間である。そこで、個々の子どもたちにはどのような特性が発現しているか、担当教師が判断し、通知簿として親に連絡がいく。
その子は、コミュニケーションは優秀、理学的発想や音楽的発想がすぐれているということだった。
通知簿を見た女が、「きっとミュージシャンになるわ、どんな楽器に興味を持つかしら」と男たちに言うと、音楽家の男は「どうだろう、音楽やるのはみんな個性が強くてね、この子は穏やかな職業に就いた方がいいのじゃないだろうか」
男の働く音楽領域はかなり深刻そうだ。
「今大変なの?あなた疲れていない、サイコアナリストに相談したらどう」
女が男を見て心配そうに言った。
「いや、あのサイコアナリストっていうのもくせものでね、何百年も同じ電子回路使っているから、リアルな人間からずれてきているのかもしれないな」
音楽家は作曲家である。演奏家に頼まれて、リアルな人間が書いた音楽を作っている。町で流行っている音楽は、ほとんどAIがつくったもので、若い人はそれで身体が動かせればいいようだが、じっくり聞きたいという人にはどこか落ち着かない音楽である。そこは人間が作った音楽にはアンモニアの匂いがして、それを好む人たちがかなりいる。年取ってくると、そういった手作り音楽を聴きたくなるようだ。だが、手作り音楽の作曲家は、なかなかヒット曲は作れない。結局AIに手直しをしてもらう。AIの手が入らない音楽は、ヒットすれば途方もない収入になる。
実はサイコアナリストもほとんどがAIで、AIが必要と判断したときに、リアルな精神科医が相談を受ける。精神科医は確かにAIとは違ったコメントをくれるが、医者の性格に偏ることもあり、患者に合わない場合もある。音楽家の男も何度かスランプでアナリストの解析を受けたが、まだリアルな医者に診てもらったことはない。AIがそこまでひどくないと判断しているので、紹介してくれないのだ。AIアナリストの紹介がないと、人間の精神科医に会うことができない。
子どもはともかく正常な成長曲線の上をなぞるように大きくなっていった。
やがて、五ヶ月になり、中学校に入った、年齢にすると十歳である。脳の大きさは大人の大きさだが、神経回路が完全に完成したわけではない。脳の中の機能に関して身体と違って、成長促進薬の効果が出るのは遅い。どうしても環境からの情報量に依存するので仕方がないことである。それでも二十世紀頃の人間の脳に比べたらはるかにすすんではいる。
中学に入った子どもは送迎バスに乗って毎日元気にかよった。中学になると遊びから学びにかわり、教師は電子版の教科書を生徒に渡し、自分のブースでPC画面を見ながら、ヘッドホンで講義を聴く。講義は人間の教師が話をしているが、音声の裏に記憶を促進させる超音波がだされていて、脳の奥の記憶のメカニズムに要点を植え付ける。中学生で、二十世紀の大学の教師ほどの知識が植え付けられるのである。中学で教えるのは、その知識をどのように自分の頭の中でつなぎ合わせ、新しい考えを作り出すかということである。それが基礎教育の基本だった。
中学の時期に思春期を迎えるのは、二十世紀の人間とほぼ同じである。従って、恋愛感情をおぼえるようになる。その機能はこの世紀でも重要視されている。というのも、生殖に関わるからではなく、コミュニケーションの脳内メカニズムを進歩させ、複雑な対応ができるようになるからである。相手の気持ちを推し量ろうとする努力をこの時期にすることがいかに重要か、いろいろ検証されている。
家族である女と男たちも、自分たちが育てている男の子がどのような娘に興味を持っているのか知りたいと思っていた。
子どもが家に帰ってくると、必ず、そこにいた男か女が「学校どうだった」とたずねる癖ができあがった。
中学校に通い始めた頃は「うん、音響物理学がおもしろかった」とか、音楽の時間では「ピアノより、ギターがいいな」などと報告してくれたが、半年もすると、「うん、まあまあ」とか「ああ、なんとか」などとあまり話をしないようになった。
男と女は子どもの変化にきがついていた。自分たちにも思い当たるところがあるからだ、女は中学一年の時にある男の子を格好いいと思い始めた。そのとき、おやに聴かれたことに対して、返事が面倒だったことを覚えている。頭にその男の子のことがいつもあったからだ。宇宙船を設計している男は、中学二年になってから、一人の女の子に目がいくようになり、音楽家の男は中学一年の後半に、ちょっと突っ張った女子に気持ちを引かれていた。そういうときには、親のこと、まわりのことなどあまり考えないものだ。
女と男たちは、子どもがクラスのどの女の子に興味あるのか聞き出そうと、子どもと話すたびに探りを入れた。クラスの名簿が電子版で届けられており、子どもたちの顔写真ものっている。
女が学校から帰ってきた子どもに、飲みものを用意しながら、「今日は音楽部の活動があったんでしょ、どんなことしたの」ときいた。
男の子は面倒くさそうに
「俺、エレキを先生からおそわった」と答えた。
「どんな局を習った」
「古くさい曲だった、ベンチャーズというグループのもの」
「あら、古典音楽ね」
男の子はなにも言わずにうなずいた。
女はキッチンのPCに音楽部の名簿を開いた。
「女の子たちはどんな楽器をやってるの、この子はなにひくの」
音楽クラブには五人の女の子がいた。女は一人一人指差した。
男の子は横目で見ながら、バイオリン、フルート、ピアノ、ピアノ、ピアノと答えがたが、最後のピアノのこのときだけ、PCの写真を長くみつめた。
女はもしやと思った。
男の子はテーブルのお菓子を食べ終わると自分の部屋にいってしまった。
それから一月の間に、男の子の態度がかわっていった。
学校から帰ってきても何もいわず、自分の部屋にいってしまった。
女が子どもの部屋にジュースをもってはいっていくと、「だまってはいるなよ」
大きな声で子どもに怒鳴られた。
「ごめんごめん」
女はジュースを置くと部屋を出た。
「なんだい、今の大きな声は」
驚いた顔で子ども部屋を出てきた女に二人の男もなにがおこったのかとソファーから立ち上がった。
「おどろいた、あの子目を細くとがらしていた」
「なんだい、そりゃ」
音楽家の男がきいたが、宇宙船設計士の男は理由をよく知っている。
「そりゃあ、つり目というんだ、二十五世紀頃までは人間もそういう目をすることがあったようだ、怒ったときだ」
「怒ってもそんな目をみたことないぞ」
「そうなんだ、今の人間は怒ってもそこまでいかないんだ」
「目にでないわけね」
「そうなんだ、怒りの遺伝子が弱くなっていてね、自律神経系にあまり影響しないんだ。ストレスを軽減するには精神的な活動と自律神経系との神経連絡を少なくすればいいということがわかってね、我々の脳はそのように進化したんだよ」
「だけどあの子の顔は怖かったわよ」
「彼女とうまく行かなかったのかな、すぐなおるだろ」
そこに子どもが出てきた。
「計算機室つかうぞ」
さっきの怖い顔はしていないが、親と顔を合わせないままコンピューター室にむかった。一家に一台は量子コンピューターがある。
「なにするんだい」
宇宙船設計士の男が訪ねると、それでもたちどまって、
「部屋の音響効果を測定する、自分で作曲した曲を録音するから、部屋の改造する」
そうぶっきらぼうにいった。
「改造するなら、業者にたのむからいってくれな」
男がそういったのだが、子どもは何もいわずにコンピューター室に入っていった。
「作曲か、俺に似たのかな」
音楽家の男はちょっと嬉しそうだ。
「あいつの彼女はどの子かわかったのかい」
宇宙船設計士の男が女にたずねた。
「うん、まだはっきりしないけど、ピアノを弾く三人の女の子の誰かだと思うんだ」
「先生にきいてみろよ」
中学の先生は誰もが思春期学をおさめていなければならない。誰が誰を見初めたかなどを知っていることになる。プライバシーの問題なので外に言っていけない事項だ。しかし家庭には教えてくれるはずだ。ただし、相手やその家族に直接接することは禁止されている。本人同士の問題なので、第三者は先生であろうと、親であろうと口をだしてはいけない。そういう罰則付きの法律がある。
「そうするわ」
「あいつ作曲をして、その子といっしょに演奏したいんだろう」
子どもの三人の育ての親は、なかなか立派な親といって良さそうだ。
女は子どもの担任の先生に直接会いに行った。そういったプライバシーにかかわることはメイルなどでは相談できない。二十世紀の頃より、むしろきびしくなっていて、親は子供のことなどは直接先生に会って話をする。
「子どものことで、どうも好きな子ができたようなんですが、どの娘が相手なのか知りたいと思いまして」
「息子さんは何か変わったことがありましたか」
「ええ、ちょっとぴりぴりしているようで」
「ぴりぴりしているのですか」
「ええ」
「そうですか、一般的に好きな子ができると、ぼんやりするもんですけど、ぴりぴりは別の原因じゃないでしょうか」
「そういうもんですか、作曲などはじめてます、主人の一人がそっちの方をやっているので喜んでいます」
「そうでしたか、音楽クラブでは、エレキをやってますけど、部活の先生がとても中学生だとは思えないほどのテクニックを持っていると言ってました」
「音楽部に相手がいるのだと思ったのですが」
「そうですね、お母さんのおっしゃるとおりです、エレキピアノのうまい子ですね」
担任の先生が音楽部の生徒の写真の中の一人の女の子を指さした。女は名前も教わって家に帰った。
その日、いつもの時間に子どもは中学校からかえった。
「お帰り」
子どもは何もいわずに自分の部屋に引きこもった。
まもなく出かけていた男二人が相次いで帰宅した。二人とも自室で家庭服に着替えると、キッチンにおりてきた。
二人とも帰るとすぐに古典的飲み物であるコーフィーを飲む。女はい何種類もあるコーフィー豆の瓶から「今日は伝統味でいくわよ」
と一つの瓶から豆を取り出し、これも超クラシックな鉄でできているコーフィー引きにいれた。
「なんだい、キリマンジェロかい」
「モカにする」
「ああ、いいね、酸っぱいのも好きだよ」
音楽家の男が言って、もう一人の男もうなずいた。三人はクラシックな飲み物のコーフィー同好会で知り合い、家庭を持つことにしたのだ。
待つこと十分、女がカップに入ったコーフィーを男たちの前に置いた。
「おお、うまいね」
男たちは満足げにうなずく。
「今日ね、学校にいったわ、担任の先生に会って話をしたの、あの子、学校ではうまくやっていて、成績もいいみたい」
「そりゃよかった」
「それで、音楽部のことはきいたのか」
「ええ、あの子の相手も教えてもらった」
女はテーブルの上のPCを開いて、音楽部のメンバーを画面に出した。
「この子よ、あんまりぱっとしない顔してるけど、エレキピアノは上手みたい」
男も食い入るように、女が指さした自分の子どもの初恋の相手を見た。
「眼鏡かけてるのか、あか抜けないね」
宇宙船設計士の男が言った。音楽家の男も「たしかにな、隣の子の方がかわいいじゃないか」
と言って、コーフィーを飲み干した。
そのとき、背後で何かがきらりと光った。
二人の男と女の首が床の上に落ちた。
子どもがキッチンの入り口で血の付いた包丁をふりあげていた。
「なんだおまえらは、ばかにしやがって」
そう言ったのだが、床の上に転がってる男と女の耳にはもう聞こえなかった。
すぐに、セキュリティー会社のガードマンがかけつけた。部屋の中で異様な動きが見られると、セキュリティー会社に連絡がいく。
ガードマンが見た物は、テーブルにうつ伏せになっている首のない二人の男と女がいすに腰掛けていた。そばでは、包丁を持った中学生が、開かれたPCの画面の初恋の女の子の顔をみつめていた。
ガードマンは警備局に連絡し、中学生を捕獲した。
中学生は遺伝監督庁の検査室に寝かされていた。
研究主任が「おどろいたな、この子どもは反抗期がでたようだ」と周りの研究員に言った。
「反抗期に関わる遺伝子はすべて抑えらえているのじゃないですか」
「そのはずだったし、この子どもにも反抗期を形成する遺伝子群は相互に繋がっていないから働かないはずだ。人間には別の形で反抗期が生じさえせる神経メカニズムがあるのかもしれないな、いやこの子だけのことで、反抗期の神経回路が発達してしまったのかもしれないが」
昔の子どもは思春期周期と呼ばれる時期、ちょうど中学生から高校生にかけて、親に反抗する子供が現れる。反抗期とよばれ、精神の発達にどのような役割を持っているのかわかっていないのだが、今の人間には不必要だと遺伝子操作でつぶしたのだ。
「反抗期というのは大人になる家庭で必要だったのかもしれませんね」
「だが、反抗期をしめさないこどももかなりいたようだし、なくてもいいものなのだろう」
「この中学生の遺伝子を詳しく調べる必要があるね」
研究者たちはこの中学生の細胞を培養液に入れた。
「この子どもはどうなるのです」
研究者の一人が主任に聞いた。
「殺人者だから、分解になるだろう、ここ数百年、人殺しはおきていないからな」
研究者主任がいったとおり、法務局ではこの子どもを分解刑に処した。
中学生は分解され、使える物質は再利用されたが、ふつうアミノ酸はそのまま利用されるのだが、遺伝子異常だったこともあり、さらに分解され、無害にして海に放出された。
未来の子


