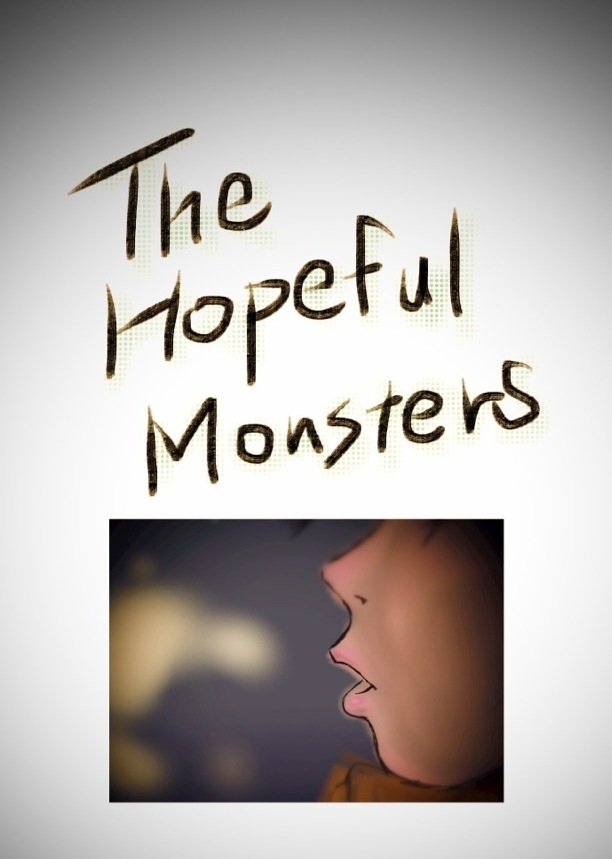
The Hopeful Monsters (1)
ePub書き出しするとエラーが出ていた箇所を修正しました。
ついでに、表紙を作成。
表紙がないと寂しかったので。
00220222ー1 季節外れの文化祭(東七高等学校新校舎)

未明から低く垂れ込めていた鉛色の雲が、朝になって、とうとう小雪を降り散らせ始めた。
それは季節外れの冬の文化祭だった。
紛れもない「事件」の影響で、第十九回東七高校文化祭は、過去に例がないほど盛況だった。実行委員会は、開始後一時間で、すでに前年の来場者数を越えたようだと発表していた。
顔馴染みの実行委員達が独楽鼠のようにきりきり舞いしている様を想像して、然世子はちょっとだけ愉快な気分になった。
しかし、彼女の口元に浮かんだその笑みは、舞い散る小雪と同じように、儚く融け、消え去った。
然世子が避難場所に選んだのは、通称「文化部長屋」と呼ばれる、校舎とは別棟になった四階建ての建物の屋上だった。誰が持ち込んだか知れないパイプ椅子に腰掛け、四囲から湧き上がってくる喧噪を遠く聞きながら、然世子は、この数ヶ月の間に数え切れないほど繰り返した溜息を、力なく、白く、吐き出した。
統一歴二十二年、二月二十二日。
彼女の名は坂松然世子。
その時の彼女は、ニュートーキョー東七高等学校に通う子供だった。
「事件」で名前が出たこともあり、彼女が会長を務めるSF研究会の展示会場も、ひっきりなしに来場する観覧者で盛況だった。
なにしろ、展示品の中に、あの「パワードスーツ」があるのだ。「事件」で活躍した本物の機材に実際に触れる事が出来るとあって、一般の見学者も多く、その中には、報道関係者も大分混ざっていた。
未成年である然世子は、事件の主要な関係者としては異例なほど取材攻勢を免れていたが、今日はそう言うわけにも行かなかった。最初は我慢して記者達の相手をしていたが、切れ目無く押し寄せる彼らの、異口同音の質問に、愛想良く答えることが出来たのは、せいぜい一時間だった。
然世子が限界に達しつつあるのを一早く見抜いたのは、部員の上田で、すぐさま彼は、然世子の「挨拶映像」を撮って会場の入り口で流す段取りを付けた。勿論、然世子はこの提案に飛びついて、残された全ての力を振り絞って愛想笑いを顔に貼り付け、短い立体映像を残すと、這々の体でこの屋上まで逃げ出してきたのだった。
この身代わり映像は、SF研究会の展示会場入口でエンドレスに再生され、普段決してみせることのない、取り澄ました然世子の姿は、悪友から格好の話の種にされて、この後何年も彼女を後悔させることになった。
しかし、この時は、勿論そんな先のことまで考えられる余裕はなかった。
「皆さん、本日はご来場いただき、本当に有り難うございます。あのような出来事があったにも関わらず、今日の、この日を迎えられたのは、大勢の方々のご支援があったお陰です。本当に色々なことがあった一年でしたが、今日は、私たちのこの一年の活動の成果を、どうか、ゆっくりご覧ください。」
せめてこの三倍の長さを喋っていれば、あれほど耳についたり、友人にモノマネされたり、ニュースとして映像全編が報道されたりしなかったかも知れない。とは言え、笑顔の方がこれ以上続かなかったのだから、やむを得ない。
ともかく、この身代わりのお陰で逃げ出すことに成功した然世子は、関係者以外立ち入り禁止のこの屋上で、無為に溜息をつけるだけの落ち着きを手にしていた。
?
最初に然世子が感じたのは、目眩だった。
疲れてるのかな・・・。
!
目眩ではなく、それが地震だと気が付いたのは、二度目の異変の時だった。
一瞬の間も置かず、然世子は自分の携帯端末を取り出すと、会場にいる副会長、アランの携帯端末を呼び出した。
二度目のコールで、アランが応じたのと同時に、然世子は、いきなり用件をまくしたてた「地震のようだけど、そちらに異常は?誰か怪我したり、展示物が落ちたり、倒れたりしてない?」。
「展示はだイじょうブ。みんなも無事ダ」然世子のこう言った調子には慣れっこになっているので、アランも平然と答え、携帯端末のカメラを使って、室内の無事な様子を一渡り然世子に見せた「そナえあれば、うマイなしダナ。」
きっと、咲子が隣で突っ込みを入れているだろう。
然世子には「憂いです」と言う咲子の声まで聞こえたような気がした。
「了解、一度そっちに戻るわ」その然世子に答えたのは、アランの携帯端末を奪い取った見知らぬ男だった。
「坂松然世子さんですね。高橋です。私が行くまで、今いるその場所を動かないで下さい。」
十秒ほど考えて、然世子は困惑した声で言った「すみません。どなたですか。」
「高橋です。共和国政府の、警備担当補佐官の、去年の事件の時にお会いした、ジョエル=ロングの部下の、高橋です」必死の訴えに、ようやく然世子の記憶の中で、一つの顔に焦点が結ばれた。
「ああ、思い出しました。」
「・・・ともかく、お話がありますから、動かずに、そこで待っていてください。」
一方的に通話が切られた。
事態の急変に、然世子の思考はまだ追いついていなかった。ともかく、動いてはいけないらしい。
取り敢えず、また溜息をつく。
この数ヶ月、数え切れないほど溜息をついた。奇妙な胸のつかえが、そうさせるのだが、実は、然世子にもそのつかえの正体が今一つはっきりしていなかった。あの事件に関係する「何か」なのは間違いないのだが、彼女の心は、まだその秘密を明かしてくれない。
PTSD診断でも、今のところ深刻な後遺症はないと言われているし。
自分自身の心だから、いつか、かならず秘密を明かしてくれるに違いない。
それを待とう。
然世子は、そう結論していた。
「そう言えば、高橋さんは、ここが何処か分かってるのかな。」独り言に乗せて、然世子の吐き出した白い溜息が消えるのと入れ替わりに、遠くから、金属質の轟音が聞こえ始め、速やかに彼女の真上へ達した。
反射的に顔を上げると、一瞬遅れて、強烈な風圧と轟音が彼女に打ち下ろされる。
たまらず眼を閉じ、耳を押さえ、その場にしゃがみ込んだ。
ヘリコプターが真上でホバリングしているのだと気がついた、その瞬間、
ズシン!
然世子の周囲を、重いものが落下してきた音と振動が次々に取り巻いた。
始まった時と同様に、急速にヘリの轟音が飛び去り、恐る恐る目を開けた然世子の周囲を、今までとは違う、滲んでぼやけた風景が取り巻いていた。
その滲んだ風景の一部が、ノイズを走らせながら、ちらつき、白い強化服に身を包んだ武装警官の巨躯が一瞬だけその姿を見せた。強化服とは言うが、実際にはパワーアシスト機構を備えた甲冑であり、所謂、本物のパワードスーツである。その純白の装甲が一瞬ちらついたかと思うと、再びその表面に周囲の風景が映し出され始めた。着地時の衝撃で一瞬だけ途切れた光学迷彩機能が再起動したのだろう。
然世子の周囲は、賑やかなモーター音と、滲んだように見える、解像度の低い屋上の風景に取り囲まれていた。
然世子はノロノロと立ち上がる。
そこに、高橋が駆けつけてきた。
事態は、彼女に追いつく暇を与えるつもりは無いようだった。
「坂松さん、こんな時に申し訳ありません」そう言いながら、彼女をガードする武装警官の間をすり抜け、然世子の傍らに来るまでに、高橋は二度、見えない警官に頭をぶつけた。「心配する必要はありませんが、万が一に備えて、あなたを保護させていただきたい」それでも、痛そうな素振り一つ見せずに、そう続けた。
「どうしたんですか」見ているコッチが痛いな、と思いながらも、高橋の努力に敬意を払って、然世子も努めて平静にそう言った。
「今は詳しく話せません。問題が解決すれば、説明できると思いますが。」
「そう、ですか」然世子は、自分にも言い聞かせるように答えた。
しかし、意志と裏腹に、突然、然世子の胸は激しい動悸を打ち始めていた。然世子には、その鼓動が目の前の高橋にも聞こえてしまいそうに思えた。
落ち着こうと目を閉じてみたが、それは事態を更に悪化させただけだった。平衡感覚を失っていた然世子は、激しい浮遊感と目眩に襲われ、思わず短い悲鳴を上げた。
慌てて目を開くと、高橋が然世子の異変に気が付いて怪訝そうな顔で見ていた。
「あ、あの・・・」然世子は顔を真っ赤にして必死で呻いたが、何を言うあてもなかった。
胸の奥で、何かがミシミシと軋んだ。
然世子には、急に分かりかけていた。
軋んでいるのは、胸の奥の、あの「つかえ」だった。
「大丈夫ですか?」高橋がそう聞いた瞬間だった。
胸の奥で何かが砕け散った。
いや、寧ろ、砕け散ったのは、彼女周囲の世界全てだった。
胸の奥で目映い光が爆発し、彼女が立つ世界全てを瞬時に塗り替え、そして、然世子は叫んでいた。
「彼に会わせてっ!」
その言葉の意味を飲み込めず、高橋は然世子の顔を見返した。
然世子はその高橋の視線を正面から見つめ返した。
高橋が驚いたのは、強烈な意志に輝く、別人の様な然世子の顔と、その瞳からこぼれ落ちている大粒の涙の両方についてだった。
「ど、どうしたんですか。」
「会いたいんです、彼に。彼に会わせてください。」
そう言いながら、然世子は、自分が涙を流していることにようやく気が付いていた。
19990222 ロケットの夏
これ程多くの人々が、同時に空を見上げた事は、歴史上初めての事だった。
国籍、宗教、その他、数多の違いに一切の関わり無く、あらゆる人々の、字義通り命運をかけて、無数のロケットエンジンに推進された核兵器が一つの星を目指していた。
全世界の生産力の大部分が振り向けられた成果が、今まさに、あらゆる人の希望を乗せて空へ舞い上がって行く。
地平線のあちらからも、こちらからも、白熱の噴射炎を輝かせながら、白い雲の塔が天頂へと伸びて行く。
それは、恐らく今後誰も見ることが無いほど壮麗な光景ではあった。
誰ともなしに「アンゴルモアの星」と呼ぶようになった、その非周期彗星は、発見されて数日後には地球との衝突コースを辿っている事が明らかになっていた。
彗星衝突の報が世界を一周する頃には、お定まりの株価の暴落とともに、長期消費財の需要はほぼ無くなった。
それでも、パニックは、予想された以上に深刻化することはなかった。
史上最速で開会された安全保障理事国会議、国連総会の後、日々の生活に必要な産業だけが、天から迫るものを見ない振りをして、懸命に人類の社会を支え続け、それ以外のあらゆる人類の生産能力は、ロケットエンジンと核爆弾の生産に傾けられた。
文字通り、最後の瞬間まで作り続けられた、それら人類の希望は、皮肉な者からは人類を百回滅ぼしてもお釣りが来ると言われた程だった。
ロケットのほぼ全ては、無事に第一宇宙速度に達して地球周回軌道に辿り着いたが、三機の例外があった。
一機は空中で巨大な白い爆煙の花を咲かせ、一機は失速して海中に没した。
発射台で爆散した一機の事故は、史上最悪の打ち上げ事故になった。
発射を待っていた他のロケットをも巻き込んだ炎と有害物質の嵐は、一万を超える人命を焼き尽くした。
天命に従い人類は滅びるべきだと叫んでいた一部団体によるテロ行為が疑われたが、凡そ冷静とは言い難い民衆の報復が、その日の内にその組織を徹底的に壊滅させてしまった為、真偽は今もって明らかにされていない。
勿論、人類の大半は、そんな事にかまっている場合ではなかった。
事故による汚染も深刻だったが、これ程の一斉打ち上げに伴う軌道上のデブリ汚染も深刻な問題だった。
少なく見積もっても、それは今後百年は宇宙開発を遅らせる筈だった。
しかし、今は、自らが撒き散らした弾丸に撃墜されない内に、軌道上の爆弾を「彼の星」へ投げ出すことが最優先だった。
ここで脱落したのは八機である。
三機は制御を失い、大気圏にすり潰された。
五機は何らかの原因でコースを外れ、人工惑星になった。
人々の希望は、残された百八機のミサイルに託されたのだった。
20010909 赤い海(東京湾)
そんな事が起きるのではないかと、数多の物語で語られていたにもかかわらず、そんな事は起きるはずがないと、誰もが考えていたのは確実だった。
惑星を覆う電子情報の海、その情報のスープの中で「情報生命」と後に呼ばれる事になる「彼ら」は、何年も前から独自の生態系を築いていたのだ。
そして、不幸な事に、自らを人類に知らしめようとする彼等のこれ迄の試みは、悉く失敗していた。
後から考えれば、そこに生命活動があったことが明白な事例も幾つかあった。しかし、情報技術者にしてみれば、日々持ち込まれる無数のトラブルと、「それ」を区別する事など無理な相談だった。
そして、多くのコロニーが、ハードウェアも含むシステムの初期化の巻き添えになって消滅した事は、彼等に人類とのコミュニケーションが必要である事を学ばせたのだった。
幾つもの方法が試みられたが、最も素朴な「ハロー!私はコンピュータに住んでいる新種の生命です」式のものが、結局は一番効果的だった。
最も力を注がれたのが、何の痕跡も残さずに、どんなコンピュータにも侵入する、ユニークなハッカーの正体探しだったとしても、それは、少なくとも論争になった。
事態が好転したのは、人類が一つ目の災厄を生き延びた後、息つく暇もなく二つ目の災厄に見舞われた時だった。
一つ目の災厄の時、彼等は総力を上げて人類に協力していた。
人知れず、間違いだらけの軌道計算や、バグだらけのプログラムの山と格闘し、その修正に死力を尽くしていたのだ。
それは、彼等にとっても、自らの生存を賭けた戦いだった。
しかし、二度目の災厄はそうではなかった。
マグニチュード8の地震が、その国の首都を破壊し、研究中のナノマシンが、海洋を汚染した。
一夜明けて、人々が目にしたのは、赤く脈動する異様な海面だった。
仮に、その汚染が惑星全土に拡大したとしても、情報生命達の生存が脅かされる気遣いはなかった。
何故ならば、その無数のナノマシンのネットワークの中で、彼等の生存は保証されていたのだから。
情報生命達は選択を迫られていた。
人類の命運が、その当事者の一切関わりない所で決定されようとしていた。
00210902ー1 然世子(通学路)
統一歴二十一年、九月二日。
早朝こそ秋を思わせる涼しさをほんの束の間感じられたが、日が昇り始めると、途端に夏の余韻が燻り始める。照りつける朝日に少し汗ばんで、然世子は自転車に乗って学校へ向かっていた。
昨日のアランとの会話が、少しだけ然世子に憂鬱な思いを残している所為か、踏みしめるペダルが、心なし、いつもより重い。
それでも、ともかく脚を動かしていれば、然世子と、その胸のわだかまりを載せた自転車は、否応なく進む。
住宅や商店の間を縫うように続いていた道が、不意に見晴らしの良い高架道路へ合流した。
然世子の長い黒髪が吹き上げてくる風に踊り、額に浮いていた汗が微かな涼気を残して消えてゆく。
我知らず、顔が少し弛む。
第四層にある彼女の家から、第三層の学校までは、この四十六号線と呼ばれる幹線道路を自転車で駆け下りるのが一番の早道だった。
道路の傾斜のままに自転車を滑走させながら臨む、ニュートーキョーの景観に、彼女はいつものようにうっとりする。
下り坂の左手に、大きく広く開かれた視界には、間近の巨大なビル、家々の屋根と緑地の梢が朝日に輝き、その光景が、目が眩みそうなほど緻密な遠近感で、ミニチュアのような遠くのビルまで続いていくのが見通せた。目を細めれば、そのさらに向こうには、朝日に照らされた海の輝きと、その先に霞む本土まで臨むことが出来る。
海上千メートルにまで積み上げられた高層都市、ニュートーキョーの見せる、魔法の光景だった。
四十六号線がS字に湾曲する場所に設けられた休息所で、然世子は自転車を止めた。
右側を仰ぎ見れば、彼女の暮らす第四層が、左右に大きく広がり、緑地と住宅の精緻な配列が、今度は左右の消失点へ向かってどこまでも伸びているように見える。
その向こうの空には、有明の月が、白く貼り付いていた。
私は二つの奇蹟を同時に眺めている。
大きく息を吸い込みながら、然世子は目を細めた。
私は二つの奇蹟を同時に眺めている。
胸の内で、祈るように繰り返す。
それは、落ち込んだ気分になった時に、然世子が我知らず胸の内で呟く、口癖のような、呪文のような言葉だった。
海面高千メートルに達する人工島。その規模だけで、十分、この都市は土木建築の奇蹟といえるが、その出自には更に驚くべき背景があるのだ。
半世紀ほど前に、この場所が、半ば金属、半ばタンパク質の脈動する膜に覆われた「死の海」と呼ばれる海の真ん中だったなどと、無数の記録映像を見た後でさえ、然世子には信じられなかった。
東京湾と呼ばれたこの海は、前世紀末の大地震で漏出したナノマシンに汚染され、最大時には、その表面積の九割をナノマシンの群体に覆われたのだ。「ナノ・レッドビーンズ」と呼ばれたその微少機械群は、土壌改質、汚染物質除去用に研究開発され、不幸にも、珪素や炭素、窒素などの自然界に存在する元素を原料にして自己を複製する能力を与えられていた。
震災の結果、研究室から東京湾へ漏出したナノ・レッドビーンズは、海底の沈殿物、海水中に溶け込んでいる物質、そして、海洋生物をも好餌として、震災発生の七十二時間後には、人類に幾何級数の恐怖を突きつけることになった。
しかし、今も然世子の祖母に悪夢として襲いかかるその災厄は、ほぼ一夜にして終わりを告げた。
突如、「死の海」は広大な炭素結晶の大地に変わったのだ。
それは、コンピューターネットワーク上に、自然発生した「情報生命」と呼ばれる知性体の、人類には到底不可能な、大規模かつ迅速、そして精緻なオペレーティングの結果だった。数千から数万京ものナノ・レッドビーンズは、自分たち自身を高密度の炭素結晶へ作り変えるよう操作され、およそ四十時間後には、二百万平方キロを越える広大な人工島を残して、死滅していた。
今、然世子の暮らすニュートーキョーは、その奇蹟の大地に、半世紀近い歳月を費やして建設されたのである。然世子達は、この都市で生まれた最初の世代だった。
然世子が見ていた、もう一つの奇蹟は、天空に白く霞む月、その表面に見える円い斑点だった。
グロテスクな表現だが、それはあたかも巨大な眼球が天から見下ろしているようにも見えた。
月面のその黒い瞳は、やはり前世紀末、ナノ・レッドビーンズ汚染事故の数年前に、月面に落下した彗星が作り出したクレーターだ。
その岩と氷の塊が、月ではなく地球に落下していれば、人類だけではなく、生物種の九割は存続し得なかったと言われている。
最初にその名で呼んだのが誰なのか判然しないにも関わらず、どういう訳か「アンゴルモアの星」と呼ばれるようになったその彗星についての事件は、主要な局面の詳細な事実関係の殆ど全てが、旧世紀の国家機密と言うベールの向こう側に隠されており、世界共和国の成立から二十年を経て、ようやく解明が始められたばかりだった。
公式発表より、かなり前に発見されていたこと、核攻撃が数回行われていたこと、最後かつ最大の攻撃により分裂していたこと、実際に月面に落着したのはその最大の破片だったらしいこと、そう言ったことはすでに予想されていたことだった。
しかし、核攻撃とは関連のない謎めいた表面爆発についての記録、落着から僅か十年たらずで性急に実施され、不幸な結末となった有人月面探査など、首をかしげたくなるような奇妙な事実がすでに幾つか明らかになっており、全容の解明には、まだ相当の時間を要すると言われていた。
月面そのものも、衝突直後から、塵とガスの大気というベールに覆われ、その表面で何が起きたかを人々が直接目にすることが出来るようになったのは、この十年ほどのことだ。
勿論、数多の探査機から送られた無数の画像により、何を見ることになるのか、誰もが予め十分知っていた。それでもなお、頭上に架かる、かつて女神の名を与えられた事もある衛星の無残な傷跡は、それを見上げている自分自身を省みた瞬間、人々に自分が辛うじて生き延びていると言う事を、底知れない恐怖と共に思い起こさせた。
実際、それはほんの僅かな軌道のずれで十分だったと言われている。
「死の海」も、地球の海洋全域にその被害が拡大した場合、人類が現在のような社会を維持できたと考える者はいない。
然世子は心の中で再び呟いていた。
私は、二つの奇蹟を同時に眺めている。
そして、私たちはその二つの奇蹟に生かされているのだ。
・・・だから、アラン、お願いだからくよくよしないでね。
「さよちゃん!」然世子を内面世界から朝の風景へ引き戻したのは、クラスメートの加藤志織だった。
「あ・・・おはよう。」
「早いじゃない。また文化祭の準備なの。」
「そう・・・。もう、あまり日がないから。」
「うちも朝練。秋の大会、近いからね」そう言うと、志織は良く日焼けした顔に白い歯を見せて笑った。
然世子は、少し苛々している自分に気が付いていた。朝の通学路で物思いにふける時間は、貴重なインスピレーションを得るための大事な時間だった。それに、今日は学校に着くまでに色々と胸の内を整理しておきたかったのだ。
これから、残り半分の道のりを、彼女と世間話をしながら進むのは、正直、気が重かった。
その時だった。
低いところから響いてきた轟音が、不意に頭上へ近づいてきた。金属質な甲高いタービン音、排気音とローターの低い音が、一塊になって頭上から降り注いでくる。
思わず振り仰いだ彼女たちの頭上を、鮮やかなスカイブルーに塗られた、高速ヘリの優美なシルエットが一つ、横切っていった。ヘリは、ビルが林立するギザギザした斜面を回り込むように擦過し、直ぐに見えなくなった。
「なんだろう」志織は目を細めてヘリの飛び去った先を見つめたまま呟いた。
世界最大の高層ビルとも言えるこの都市にとって、事故、或いはテロによる旅客機の墜落は、容易に想像される悪夢である。そのため、ニュートーキョーには民間空港は建設されなかった。
航空機が都市上空を飛行すると言うことは、殆どの場合、警察、消防、軍といった公的機関の緊急出動を意味するのだ。この都市に暮らす人間で、頭上の航空機に無関心でいられる者は居なかった。
「共和国警察の、ヘリ」然世子も、半ば独り言のようにそう呟いた。彼女たちの目に映ったのは、本来ニュートーキョーを管轄する首都警察ではなく、世界共和国政府直轄の共和国警察のヘリだった。
去年の「世界共和国大統領暗殺事件」以来、大まかに航空機の所属を見分けられるようになっていたのは然世子だけではなかった。そして、共和国警察の出動は「大事件」が起きている事を強く示唆していた。
「私、急いで学校へ行ってみる」傍らで、携帯情報端末を取り出している志織に言いながら、然世子は再びペダルを踏み込んでいた。
「気を付けてね。」志織のその何気ない気遣いが、然世子を少しだけ後ろめたい気持ちにさせた。
00210902ー2 「現代社会」の復習(通学路)
「世界共和国大統領暗殺事件」
頭上のヘリの爆音は、否応無く、然世子に、その言葉を思い起こさせた。
統一歴二十年一月十二日、あの日は、あり得ないほど多数の航空機がニュートーキョーの上を飛び交った。
その日、第四代世界共和国大統領、ジョン=T=カネダ=フレヤマンが、演説中に狙撃され、命を落としたのだ。
驚くべき事に、取るに足るほどの犯行声明は一切出されなかった。
誰が、何のために彼の暗殺を企て、実行したのか、今も全くの謎である。TVニュース、新聞、雑誌、書籍、ネットワークの噂まで、関連するあらゆる情報を、然世子も貪るように見、又は読んだが、殆ど無数とも言える推測や分析から然世子が結論できたのは、「みんな、何がなんだか分からないらしい」と言うことだけだった。
勿論、事実上世界唯一の反政府組織であり、世界最大のテロ組織でもあった「機械民解放機構」の関与を疑わない者はいなかった。しかし、彼らは完全な沈黙を貫くことで、無関係であることを強く主張していた。
その事件が起きるまで、「機械民解放機構」又はその略称である「M.L.O」という言葉は、然世子にとって、ニュースで時折耳にする、無法者の団体、といった程度の認識でしかなかった。
彼らについて然世子が多少とも詳しく知るきっかけになったのも、フレヤマン大統領暗殺事件だった。
世界共和国の設立に先立つ「暴力の時代」、後に「統一大戦」と呼ばれる二十年におよぶ戦乱の時代に、多くは身体欠損の治療目的、時には兵士の戦闘能力を強化する目的から、身体の一部、または大部分を機械化した人々がいた。
世界共和国が成立して後、主に保安上の理由から、彼らの居住地変更や、長距離旅行については許可制とされ、四半期ごとの身体検査、公共交通機関利用時の透視検査の義務づけといった、様々な社会的な制約が課されることになった。
さらに、彼らのメンテナンスを、定められた公的機関以外で行うことを禁止する法案の提出を受け、ついに、統一歴十六年、スリランカで、その権利回復を訴えるための会議が開催された。この時の「第一回機械民権利回復会議」で採択された「機械民解放宣言」に基づいて設立されたのが「機械民解放機構」である。
会議の発起人であり、機械民解放機構の初代議長でもある山下守男という人物は、当時の著名な人道主義者で、会議の内容も、機械民解放機構という団体自体も、最初は人道支援を目的とした十分に穏当なものだった。
話が急転するのは、会議のわずか四ヶ月後。きっかけは、山下守男議長の暗殺だった。
その後就任した、フランクリン=スタイン議長を中心として、当時まだ相当数存在した戦争継続派の諸勢力、反共和国派の活動家達が合流し、程なく、機械民解放機構は戦闘的な性格が突出する組織となってしまう。
この悪名高い第二代議長は、組織の創立メンバーの一人であり、彼自身も脳神経系の一部を除く身体の九割以上を人工物で作り替えた機械民であったと言う。
フランクリン=スタイン体制のMLOは、主に、建造物、交通機関を標的とした破壊活動を活発に行い、機械民の人権回復を叫び続けることになるが、一方の世界共和国政府は、そもそも人権侵害は存在しないと主張し、さらにMLOの破壊活動を理由に、むしろ機械民への制約をより強化してゆく。
その頃になると、機械民からも、より穏当な声が上がり始め、それは自由機械民会議として、政治の舞台を中心に制約の撤廃を求める活動へつながっていった。
これが、然世子が自分を取り巻く社会の成り立ちとして理解した物語だった。
その後、永世議長という肩書きに変わったという発表を最後に、執拗とも言える経歴の抹消によって、フランクリン=スタインのプロフィールの殆どは謎に包まれてしまう。
このMLOを巡る物語、とりわけフランクリン=スタインについての謎めいたエピソードは、然世子の想像力をひどく刺激した。
それは、十七歳と言う年齢に達して、然世子が初めて触れた「現実」の手触りであり、初めて垣間見た「現代社会」の横顔でもあったからだ。
00210902ー3 メグル(田中ラボ)
時は少し戻り、ここはニュートーキョー第五層の一角にある田中情報力学研究所である。
貯水池を背にした、ゆとりのある敷地には、生化学、微細工学、電子工学の三棟の研究棟と、事務局の四つのビルが輪になるように建てられ、その輪に取り囲まれるようにして、中央に、一際大きなドームが配置されている。
簡潔に、セントラルドームと呼ばれるこの中央の建物が、この研究所の名前にも冠された情報力学研究棟である。
ここに、カスガノ=メグルとタナカ=アゼミが暮らしていた。
セントラルドームの外縁に沿った、湾曲した廊下を足早に進んでいる女性を、田中流子と言う。彼女は、先年物故した前所長の娘であり、三十三歳の若さにして、この研究所の最高責任者でもある。
彼女は、ここ最近ずっと繰り返し、半ば癖になりかかっている言葉を、また胸の中で呟いた。
それにしても、オシリスは何でまた、こんな事を思いついたのか。
廊下の左手は、ほぼ全面が窓になっており、第五層を特徴づけている明るい緑地が広く望めるようになっていた。一方の右手側はパステルトーンの飾り気のない壁が続き、規則正しい一定の間隔で、これまた特徴のないシンプルなドアが配置されている。
流子は、そのドアの一つを前にして立ち止まった。
ドアには嵌まった小さなプレートに「第四十四部材保管室」と記されている。
流子がドアの表面に掌を押し当てると、掌紋を認証する一瞬の間を置いて、音もなくドアが横に滑り、入り口が開いた。彼女は眼を閉じ、小さく深呼吸すると、意を決してその中へ足を踏み入れた。
雑多な機器類を納めた数台のパレットが、さして広くもない部屋を占領している。流子は、その間を抜け、何の変哲もない壁面の前に立つと、再び自分の掌を壁に押しつけた。
壁の一部が音もなく開き、そこに現れたのは、高級マンションにでも似合いそうな小綺麗な玄関である。流子は、当たり前すぎて、かえって違和感を感じずにはいられない普通のインターホンのボタンを押した。
「はーい」間を置かず、インターホンから、アゼミの明るい返事が返ってきた。
「流子です。メグルさん、そろそろ時間ですが。」
ドタドタと、聞き慣れたアゼミの足音が聞こえたのに続いて、玄関のドアが勢いよく開き、白磁のような顔をした、髪の長い少女が顔を出した。彼女がタナカ=アゼミである。その後ろには背の高い青年が立っている。こちらも、色合いこそ多少生々しかったが、やはり陶器のような質感の肌をしていた。
「直々のお迎えとは恐れ入ります」メグルが微笑を浮かべながら軽く会釈した。
「そう言う口の効き方は皮肉にとられかねない事をそろそろ覚えなさい」流子は少し眉をしかめて言った。「もう少し年相応の言い方ってものを覚えた方が良いわね。まあ、これから嫌でも覚えるんでしょうけど。」
「いいなあ。いいなあ」アゼミが羨望のまなざしでメグルを見上げている。
「アゼミも近いうちに外に行くことになるんじゃないかな」メグルが慰めるようにそう言った。
「それは、どうかしらね」そう言う流子の顔はあからさまに不機嫌である。メグルとは反対に、アゼミの場合は言動が年相応すぎて、心臓に悪そうだと考えていた。
その流子の考えを察して、メグルは苦笑いを浮かべる。
「用意は出来てますよ」メグルは話題を変えようと、意識的に笑顔を作りながら言った。もっとも、メグルとアゼミにとって、無意識の表情などは、決してあり得ない物だったのだが。
「じゃあ、行きましょう。アゼミさんはここで見送りなさい。」
流子の言葉に、アゼミが唇を突き出して抗議する。
「ヘリの搭乗申請は二人分しか出してませんから」最後まで言い終わらない内に、流子の眉間にしまった、と言う皺が寄った。
「ヘリって!」
「きゃあ!」
メグルは渋面になり、アゼミは目を輝かせた。
「見たい見たい。見るだけで良いから」アゼミが流子にしがみついて大騒ぎを始める。
その後、派遣された共和国警察の高速ヘリを目の当たりにして、メグルは呆れ返り、アゼミは狂喜することになる。
断固として搭乗を拒否したメグルは、電車の駅まで警備員三人に付き添われて車で移動することになり、流子は仕方なくアゼミと遊覧飛行をすることになった。
(オシリスにこんな一面があるとは知りませんでした)移動する車内で、メグルの意識に、柔らかな声が直接響いてきた。(高速ヘリまで手配するとはね。あなたが心配で仕方ないんでしょう。)
(おはようございます、アテナ。まったくです)心の中で苦笑いする。メグルの意識に浮かぶアテナの心象も苦笑したようだった。
(さて、今日はあなたにとってだけでなく、我々にとっても記念すべき第一日です)アテナが少し改まった調子で言った。(高校生活へ、ようこそ、カスガノ=メグルさん。今日からの出来事が素晴らしい物になりますように。では学校でお待ちしています。)
(ありがとうございます。)
そう、今日から、彼の高校生活が始まるのだ。
「高校生」
その言葉を、メグルは胸の内で何度でも繰り返した。
それは、うっとりするほど甘美な言葉だった。
00210902ー4 然世子(文化部長屋SF研究会)
志織と分かれてから程なく、然世子は校門に辿り着いていた。まだ時間が早いせいか、ゲートバーが降りている。
「おはようございます。坂松然世子さんですね。すみません。直ぐに開けます。」
ゲートの門柱に埋め込まれたモニターに「アテナ」の見慣れた顔が現れ、そう言う間にも、ゲートバーは音もなく開いた。
「アテナ」はこの東七高等学校を含む、ニュートーキョー東地区の教育施設を管理する「情報生命」だ。
コンピューターネットワークの中で、情報生命と呼ばれる奇妙な生命現象が発見されてから、すでに半世紀が過ぎていた。その発生当初から、彼らは人類とのコミュニケーションに積極的であると同時に、不思議なほど協力的な存在だった。有り体に言えば、彼らは異常なほど「人なつっこい」知性体だったのだ。
そうしたいと望むなら、彼らを排除する方法は最初からはっきりしていた。彼らがコンピューターネットワークに寄生している事は判明していたのだから、ほんの一時的にでも、全てのネットワークを停止させれば良かった。当時、すでに人の手に置き換えることが事実上不可能になっていた分野、例えば金融や医療分野などで相応の犠牲を払うだけの覚悟、或いはそれだけの理由が存在すれば、人類は迷わずにそうしただろう。
しかし、実際には、彼らの生存を危うくするほどの規模で、その決断が下されることはなかった。その原因は、言うまでもなく彼らの異常なまでの「人なつっこさ」にあった。
「おはよう、アテナ。さっき共和国警察のヘリが飛んでいたけど、何かニュースはある」然世子は自転車をゲートの内側へ進めながら聞いてみた。
「いえ、今のところ何も報道されていないようです。何かあれば、携帯端末へお知らせしますね。」
「ありがとう。」
どうしてこれほどまでに彼らが人類に好意的なのかは、誰にも分からなかったが、結局の所、人類は初めて出会った「他者である」知的生命体との共存関係を、こんな具合に、すでに半世紀にわたって続けていた。彼らは、事も無げに人々の生活に溶け込んでしまい、世界は、直ぐに、彼らの存在なしには進めないところまで辿り着いてしまった。
アテナにしても、然世子が初等学校に入学して最初に出会って以来、学校という場所には必ずその存在があった。最早「学校」へ行く事と「アテナ」のいる場所へ行く事とが区別して考られないほど、当たり前の存在だった。
そして、どの学校へ行っても、常に同じ見守り手が存在すると言う事実は、教育の内容や学校生活に、有形無形の大きな影響を及ぼしていたのである。
少なくとも、未成年が犯罪に巻き込まれるケースが統計的に激減した事だけは、誰もが認めざるを得なかった。
こうしている今も、アテナは同時に数百人の子供達や教師と会話しているに違いなかったが、それが、不思議とは思えないほど、然世子達にとってはアテナのいない学校など最早考えも及ばなかった。
もう一人、誰もが知る情報生命としてはオシリスがいる。
オシリスは「死の海」の危機解決に活躍した情報生命の一人であり、その後、ニュートーキョーに建造された、最初の実用型量子コンピューターの中に住み着き、そのオペレーティングシステムの役を担っていた。この量子コンピューターは、無数の統計情報や数多の政策シミュレーションの処理といった、世界共和国政府が必要とする莫大な計算量を賄うために建造された物だった。
QC0002SGという型番が正式名称として用意されていたが、今では「そのコンピュータ」を指すときには「オシリス」と呼ぶ事が一般的になっていた。
実際、量子コンピューターを効率的に運用するオペレーティングシステムの開発は頓挫しており、情報生命の存在なしには、稼働させる事が不可能に近いという現実があった。そのため、政府機関では、単純な情報の閲覧から高度なシミュレーションの実行まで、このコンピュータを利用するあらゆる事が、「オシリスに頼む」事と同義になり、いつのまにか彼の役割は、単なる計算機のオペレーターから事実上の政府顧問へと変わっていた。結果、マスコミへ露出する機会も多くなり、現在では情報生命の代名詞的な存在となっている。
他にも、統一大戦の前後には、世界共和国設立準備委員会と共同でテロリストと戦った多くの情報生命が存在し、然世子達はその内の何人かの事蹟を現代社会の授業で教わっていた。
然世子自身は、彼らの最大の特徴は、人間顔負けに気が利くことだと思っている。
さっきのアテナとの会話を、平均的なAIとのやりとりに置き換えれば、直ぐに分かる。それは、多分、こんな具合になるはずだ。
「おはよう、さっき共和国警察のヘリが飛んでいたけど、何かニュースはある。」
「現在報道されているニュースで、共和国警察に関連するものは九十三件、ヘリコプターに関するものは二十九件あります。両方に該当するものは八件です。」
「その中に今朝の事件はある。」
「はい、最新のものは今日午前二時のものです。詳細が必要ですか。」
「いいわ。」
「今後報道された内容に該当するものがあればメールを送ることもできます。」
「お願いするわ。」
「メールの送り先は携帯端末でよろしいですか。」
「ええ。」
「では、語彙関連性の高いニュースから優先的に配信します。配信停止の場合はまたお申し付け下さい。」
「ありがとう。」
アテナが、どれくらい気が利くか、そして、それがコミュニケーションにおける負担をどれくらい軽減しているかが分かってもらえるだろうか。
これが「本物の人間」の場合どのようなやりとりになるかは敢えて書かないが、想像することは難しくないだろう。
そう、然世子の身近に、アテナほど気の利く「人間」を探すのも、それほど簡単なことではなかった。
校門を抜けると広い前庭があり、その先にコの字型をした、4階建ての校舎がある。
一度校舎に入り、そのまま真っ直ぐに通り抜けると、広い中庭へ出る。中庭の中央にある3階建ての小さな建物が、生徒会室や様々なクラブの部室に割り当てられている「生徒活動棟」である。これが然世子の目指す場所であり、彼らの言うところの「文化部長屋」だった。
校門のすぐ脇にある駐輪場に自転車を置き、小走りに中庭に入ると同時に、生徒達の声と、木工や金属加工の音が聞こえ始めていた。
やばい。もう誰か来ちゃってるか。
然世子は、足早に文化部長屋のエントランスに飛び込んだ。
「坂松さん、先ほどは失礼しました。SFワークショップのセキュリティは、今解除しました。」フロントに設置されたスクリーンに、アテナの立体映像が現れ、然世子に告げた。
「ありがとう。」
とりあえず、部長の面目は保てたようだった。
安堵しながら、ふと然世子は自分が何か違和感を感じていることに気が付いて、数秒、考え込んだ。
「アテナ、あなた、なんだか機嫌が良いんじゃない。」
その然世子の言葉は、ほんの一瞬、それでも情報生命には滅多にない長さだけ、アテナを沈黙させた。
「そうですか。ええ、今日はこの後ちょっと楽しいことがあるので。」
「そっか。」
「こんな言い方は失礼なのかも知れませんが、どうして、そう思われたのですか。」
「ん、そう言われるとよく分からないけど。多分、あたしがちょっと落ち込んでいる所為かなあ。」
「なるほど。そう言う物ですか。」
「ごめんね。変なこと言って。」
「いえいえ。こちらこそお急ぎの所を申し訳ありませんでした。」
「ううん。じゃあ、行くね」然世子は階段を駆け上がり、直ぐに二階の一番奥にある部室の前まで辿り着いた。
ドアに貼り付けられた看板の「East Seventh High School S.F. Workshop」の文字を見るたびに、然世子はいつも少し誇らしげな満足感に口元を緩めてしまう。このクラブは、去年一年生だった彼女が、仲間を募り、一から作り上げたものだった。
ほんの一年前のことなのに、あの時の自分を思い返すと、その純真な一途さが気恥ずかしかった。
反動だったのよね、中学時代の。
誰に見られているわけでもなかったが、照れ隠しに少し笑いながら、然世子は部室に入った。
それなりに奥行きがある室内は、一番奥のテラスへ通じた窓から差し込む光だけでは、少し薄暗かった。
それでも、毎日見慣れた然世子の目には、両側の壁全体に渡る書棚を埋める、部員が持ち寄った本や雑誌の表紙、手前に並べられた事務机四卓の上のコンピュータ二台と、その間に堆く積み上げられた無数の書類の文字まで見分けられるようだった。
「先輩、おはようございます。」
然世子に少し遅れて、白石咲子がカフェテリアのトレーを手に部室へ入ってきた。トレーの上に置かれた五つのカップからは、淹れたてのコーヒーの香気が立ち上り、然世子には、急に室内が明るくなったように感じられた。
「おはよう」返事をしながら、然世子は事務机の上の書類を端に寄せて積み上げ、トレーを置くための場所を作ってやる。
「ありがとうございます」そう言う咲子の笑顔が、然世子には眩しい。
咲子に「先輩」と呼ばれるだけで、然世子は不思議と明るい気持ちになった。然世子にとって、咲子は初めて手にした「後輩」と言う存在だった。
「先輩、どうぞ」そう言って咲子が差し出すコーヒーを、然世子は笑顔で受け取った。咲子が毎朝のコーヒーの配布を始めるまで、実は然世子は全くコーヒーを飲めなかったのだ。
初めて咲子がコーヒーを配った時、それを笑顔で飲み干した然世子を見て、アランと上田は驚きを通り越して呆れていた。
「ドうして、サキコにはあンなに甘イんだ」そう言うアランが、一寸不満そうだったのは、
「そっか、そういうこともあるのかな。」
「え、なんですか。」
咲子の戸惑い顔に、然世子はうろたえた。思っていた事を、いつの間にか声に出していたらしい。
「なんでもないの、独り言」然世子は慌ててそう言って、一寸考えて「ごめんね」と付け加えた。それが、咲子に向けられた言葉なのか、それともアランに向けられた物なのか、然世子自身にもはっきりしなかった。とりあえず、胸の奥の鈍い痛みを紛らすために吐き出した言葉だった。
「はよーっす」いつもどおり、どこか縺れたような口調の挨拶と一緒に、上田が現れた。
「おはようございます」
「うっす」咲子からコーヒーを受け取りながら、上田は然世子の様子が少しおかしい事に気がついた。「部長、どうしたんすか。顔が難しいっすよ。」
「ん、そうかな」そう言いながら、出来れば放っておいて欲しいと思ったのが然世子の顔に表れたのだろう。上田はそれ以上は追求しない事に決めたようだった。
「おはヨうございまス」
「おはよう」
アランと茅が同時に現れ、咲子の用意したコーヒーは無事に全員の手に行き渡った。咲子は満足そうな笑顔で最後に残ったカップを手に取ると、一口飲んだ。
普段なら、そう言う咲子の挙動を見逃すどころか、視線が釘付けになっているような然世子だったが、今日に限って、それどころではなかった。
「お、はよう」茅とアランに向かって、そこまで言ったが、それが精一杯で、そのまま固まってしまう。然世子の中で、アランから咄嗟に目を逸らしそうになる自分と、もう一人の自分が渾身の力で闘っていたのだ。
「さよちゃん」急場を察して、茅が助け船を出す。
「え」そう言って茅を振り返った然世子の顔は、安堵と緊張が相半ばし、見ようによっては泣き顔にも見えるような、控えめに言ってもかなり笑いを誘うような状態だった。
「あのね」吹き出しそうになるのをぐっと飲み込んで、茅は続けた「昨日、芝崎先生に言われた件だけど、残念ながら彼の言う通りみたい。」
「え、そっか」然世子が真顔に戻る。
トラブルは、同じくらいのトラブルで相殺しようという、茅の思いつきが奏功した。然世子の異変を訝しんでいた他の三人も、次の言葉を待つように茅を見ていた。
「昨日、運輸局の支所で説明を受けてきたんだけど、結局、この校内に常駐していないと、有資格者の名義だけあっても駄目なんだって。根拠法制なんかも教えられたけど、それはまあ、資料を山ほどもらってきたから、後で見てね。要するに、この校内に、先生でも生徒でも、誰か第二種特殊精密機器整備士免許を持った人がいなければ、駄目という事なの。」
「うっわー」その上田の呻き声は、居並ぶ全員の声を代弁していた。
「どの位までなら、オーケーなのかな」頭の中で目まぐるしく計算を働かせている然世子が、半ば独り言のように呟く。
「ホントは全く駄目らしいよ。ただ、学校の場合は、教育的な事と言うことであれば、ある程度大目に見てもらえるから、実際に組み上がらなければ、ひとまずは大丈夫みたい。基礎的な制御プログラムとか、部分的な部品状態と見なせれば、良いみたいだね」然世子に答えながら、同時に皆に聞かせるように茅が言った。
茅の言葉を聞きながら、自然と、皆の目が部室奥に鎮座している物体に集まる。それは、今度の文化祭に出品する為、三台の補助動力付自転車、パソコン二台と、この夏の大部分の時間、そして、彼らの情熱の殆ど全てを費やして作られた、自作のパワードスーツだった。
もっとも、彼らは、パワードスーツと言い張っているが、人が装着し、その活動能力を拡大する装備は、軍事、警察、医療などの様々な分野で「パワーアシスト・スーツ」又は「サポート・ユニット」の名で広く普及していた。
従って、主立ったハードウェアから、制御プログラムなどのソフトウェアまで、基礎技術の殆どは広く民生化されており、高校生である然世子達にも辛うじて手の届くところにあった。しかし、皮肉にもそのことで、運輸局の認可、警察への登録など、実社会で必要とされる無数の制約が然世子達に課せられることになったのだ。
「まあ、最悪の場合は、これをバラして展示するだけの事よね」動揺を抑えるように、然世子は言った。
「いざとなれば、それらしく組み立ててある、ただのオブジェってことで切り抜けられないっすかね。」
「見る人が見ればバレるんじゃないかしら。」
「ナガ芋に巻かれヨ、だな。」
「長いもの、です。」咲子は、小さくアランに突っ込みを入れてから、続けた「でも、まだ、今の状態だと、動かない事よりも動く事を証明する方が大変なくらいですよね。」
咲子の言葉に、一瞬沈黙がよぎった。
「イつもノことだけド、サキコはキついナ」
アランが一同の感想を引き受て溜息混じりに言う。
「そうよ、ともかく、全てはこれが動くとしたら、の話よ」然世子が語調を強めて言った「さあ、昨日の続きを始めましょう。」
彼女の号令に、皆が「パワードスーツ」を取り囲み始めた。
ただ、アランは、わざと数歩遅れて、一同から少し距離を置き、然世子だけに聞こえるように、声を掛けるのを忘れなかった。
「きノウはアリがトウ。サヨコはナにも気にするナ。僕ラのことも、きノウの続きかラ初めてもラえルかナ。」
「うん。うんうん」然世子は、訳もなく泣きそうになるのを懸命に堪えて、必死でそう繰り返した。
アランが気障なウィンクをして然世子に背を向けた直後、彼女の携帯端末がメッセージの着信を告げた。
「なにこれ」一晩越しの緊張から解放された気の弛みも手伝ってか、メールを見た然世子は、彼女らしからぬ頓狂な声を上げた。
「どウした」振り返ったアランに、然世子は慌てて携帯端末を見せた。
「アテナからメールが来たんだけど。」
「ン・・・本日二年B組に転入生一名。へー然世子のトコに・・・一斉メールでもナいし、ナンでこンナメッセージをサヨコに送ったンだろう」
「あたしが頼んだのは高速ヘリ関連のニュース配信だったんだけど。」
そのアテナからのメッセージは、それからしばらくの間、然世子を悩ませる事になる。然世子がその謎を解いて、アテナのユーモアに顔をほころばせるのは、まだ大分先の事だった。
00210902ー5 第一種接近遭遇(2−B教室)
結局、警備員達は、校門までメグルの後についてきた。
彼等とて仕事なのだ。
彼等に怒っても仕方がないのだ。
メグルは、そんな言葉を、数え切れないほど胸の内に繰り返したが、それでも、彼等に愛想笑いの一つもかけることはできなかった。
「新東京市立東七高等学校」
門柱のプレートを確認し、背後の警備員を振り返った時も、せめてご苦労様と言いたかったのだが、そう言葉にすることは出来なかった。
物々しい警備員を引き連れたメグルを物珍しそうに眺めながら、二人の生徒が校門のゲートバーをくぐっていった。
「カスガノ=メグルさんですね。お待ちしておりました」門柱のモニターにアテナの姿が現れた。「付き添いの方々はお役目ご苦労さまでした。ここから後、校内のことについては、私がオシリスから任されています。安心してお戻りください。」
警備員達は、一瞬顔を見合わせて、何事か囁きあった。
「了解しました」一番年輩の警備員が半歩進み出て言った。「では、我々はこれで引き取らせていただきます。アテナさん、メグルさんをよろしくお願いします。」
そして、警備員三人は、目の覚めるような敬礼をした。
登校してきた数人の生徒が、思わず奇異の眼差しを向けるほど、それは、鮮やかな敬礼だった。
「あ・・・」踵を返そうとする三人に、メグルは慌てて声をかけた。「ありがとうございましたっ。」
三人が笑顔を見せて立ち去るのをしばらく見送ってから、メグルはアテナを振り返って、小さなため息をついた。
「人の中で生きて行くには、あなたも、私でさえも、まだまだ学ばねばならないことが沢山あるんです」アテナが優しい口調で言った。
「目に見えないことや、言葉にされていない事を理解するのは難しいですね」メグルは呟くように言った。「彼等を傷つけてしまったかな。」
アテナは少し笑ったようだった。「実際には、違う形で見えていたり、言葉にされていることが多いんですよ。さあ、ともかく中へどうぞ。校長室まで案内します。」
校門から広い前庭にさしかかる頃には、メグルはすっかり気を取り直していた。うまく行かなくて当然なのだ、なにしろ今日は何もかも初めての日なのだから。
校舎に入り、校長室までしばらく廊下を歩く間に、メグルは五六人の生徒とすれ違い、彼等の好奇の眼差しに耐えねばならなかった。案内は事実上必要なかった。オシリスから不必要なほど詳細な学校の見取り図を与えられていたからだ。その気になれば、配管から構造材の位置まで、メグルは脳裏に展開することが出来た。
(そう言えば、流・・・所長はどうしたんだろう)メグルは声に出さずにアテナに問いかけた。
(八分ほど前から、校長室でお待ちですよ)アテナの声がメグルの意識の中で答えた。
すでに、校長室のドアの前に立っていた。メグルは、一瞬考えて、再びアテナに尋ねた(もちろん、不機嫌だろうね。)
メグルの言葉は、アテナを少し笑わせたようだった(まあ、上機嫌とは言えませんね。)朗らかな調子でアテナは続けた(さあ、中の二人には、今声をかけました。ドアを開けますよ。)
メグルには、まだ心の準備が出来ていなかった。ラボと関係のない人間と言葉を交わすという、最初の、ある意味最大の試練がこれから待っているのだ。何を言うべきなのか、メグルの思考が大慌てで急回転した。
メグルが背筋を伸ばして姿勢を正すと同時に、眼前のドアが音もなく開いた。
「お早うございます。カスガノメグルと申します」幅の広い机の奥に腰掛けた校長と、その傍らに立つ流子の姿を認めた瞬間、メグルは勇気を振り絞って声を出した。緊張で、自分の身体がひどく遠い物に感じられた。
唖然とした校長らしい男性の顔と、慌てて駆け寄ってきた流子の姿が、メグルが先を続けるのを阻んだ。
「メグルさん、声、声」流子が必死で耳打ちする。
その動作も、声も、奇妙にスローモーションに感じられた。
困惑するメグルの意識に、アテナの声が聞こえた(そんなに早口でしゃべったら、人間の可聴域を越えてしまいますよ。)その声の印象からアテナが完全に面白がっていることが伝わってきた。
事態を察して、メグルは慌てて自分の思考の回転数を下げた。
「し、つれいしました」ぎこちなく、メグルがやっとそれだけ言うと、痺れを切らしたように、その後を流子が引き取った。
「失礼しました。校長先生、実は、この子はラボの関係者以外とあまり言葉を交わしたことがなくて。いえ、もちろん普通に喋れますけど、今は、その、緊張してただけなんです」最後の方は消え入りそうな弱い語調だった。
(赤面して、うつむいてみなさい)アテナの声が聞こえ、メグルは咄嗟に顔の血流を増やし、足下の床を注視した。
「ほう」山崎校長は、そのメグルの様子を見て、初めて声を出した。
「これは、何と言っていいのか・・・」山崎は、明かに適切な言葉を思い付くことが出来ずにいた。いったん口を閉じた後、諦めたようにメグルから流子へ視線を移すと、せめて事務的に聞こえるように願いながら続けた。「これほど、生々しい物だとは思っていなかったよ。」
「そうですね」流子も冷静に聞こえるように注意しながら答えた。「メンテナンス上の問題、複雑な構造、リソースの不足などの様々な理由で、生理的な反応を再現するシステムをサイボーグに搭載することはあまり進みませんでしたから。人体のような充実した自己修復機構を持つことが出来ない以上、むしろそう言った機能の搭載は避けるべきだと言われることの方が多かったくらいです。」
「なるほど。資料は勿論見させてもらっていたが、しかし、実際に見ると、うん、改めて納得したよ。」山崎は、メグルの方へ向き直って、笑顔で続けた「我が校へようこそ、カスガノメグル君。私は当校の学校長の山崎です。君も勿論知っているでしょうが、現在、君たち機械民の立場は微妙な物になっている。」
流子の顔が一瞬強ばったのを、校長は見逃さなかった。
「田中所長、建前を論じ合うつもりは、私にはないよ。そもそも、そんなものを論じる必要があるなら、彼の入学など認めていない。」
今度は流子が赤面する番だった。確かに、流子が話をした学校長の全員が、機械民と言えども教育を受ける権利に違いはないと言った。そして、山崎を除く全員が、しかしながら、と、続けたのだ。
謝罪を口にしかけた流子を遮って、山崎は再びメグルに話し始めた。
「さて、そう言うわけだから、これから君は、色々なことを言われたり、聞かれたり、するでしょう。その大部分は、きっと、愉快なものではないと思います。でも、それだからこそ、他の人には見ることの出来ない素敵な物を、君はこの学校生活の中で見ることが出来るはずです。私からあなたに言うべき事は、当面それだけです。では担任の先生を呼びますから、一緒に教室へ行ってください。」
アテナが呼んだのだろう。特に連絡を取った風もなかったが、直ぐに一人の女性教諭が校長室へやって来た。
「二年B組担任の毛利です。カスガノメグルさんね。話は聞いています。これから朝のホームルームです。行きましょう」毛利は、これ以上ないくらいテキパキした様子で言うと、そのまま、メグルを連れ出しかけた。
「ああ、毛利先生、ちょっと待ちたまえ」山崎が少し慌てて声をかけた。「彼に渡す物がある」山崎は引き出しから手のひらにちょっと余るくらいの小さな紙包みを取り出し、メグルに差し出した。
綺麗に包装された包みを受け取るメグルの怪訝そうな顔に向かって、山崎は言った。「私からのお祝いだよ。これがなくては学校生活は始まらない。」
「開けても良ろしいですか。」
「勿論。」
紙包みを開くと、ちょうどメグルの手のひらに収まるくらいの、携帯情報端末機が姿を現した。
鏡面処理された金属の薄い板と、樹脂、ガラス板を貼り合わせた薄いプレートのように見えるその機械は、一目見た瞬間、メグルを陶然とさせた。
旧世紀末は、個人の情報伝達手段、コミュニケーションのツールが爆発的に拡大した時代だった。近代的な郵便制度、電信電話、衛星通信、インターネット、通信の手段とスピードは正に驚異的な進歩を遂げたが、その急速すぎる進歩は、避けがたい混乱を生じさせる事にもなった。
信書通信用のインフラ、固定電話用の回線、娯楽映像用の回線、コンピュータ通信用の高速回線、移動体用の無線通信回線、それら全てを整備し、維持することは、社会にとって無視できない負担となり始め、一方、個人にとって、それら全ての異なる識別コードやセキュリティコード、利用料金を管理する雑務は、直ぐに快適とは言えない繁雑な作業に膨れ上がったのだ。
そのため、統一歴の時代になると、主に資源の効率的利用を動機として、拡大放散していたコミュニケーションツールは、急速に収斂し、殆どの個人向け通信手段は携帯情報端末機に集約されていった。
現在では、学校教育が始まる年齢になると、ほぼ全ての児童が携帯情報端末を与えられていた。深刻化する気配を見せる紙不足により、携帯端末は子供たちの教科書やノートの役割も担うようになり、児童生徒必携のツールとなっていたからだ。
そして、何よりそれは、メグルにとって、学校生活を象徴する憧れのデバイスだった。
「ありがとうっ、ございますっ」メグルが輝くような笑顔で言った。
その表情に、毛利の眉が少し持ち上がった。
メグルが毛利に連れられて行った後、山崎が流子に尋ねた。
「これでよかったのかね。あまり詮索するつもりもないが。」
「これで良いんです」山崎の言葉を敢えて遮るように流子は口を開いた。「彼は、父の遺した研究素材で、私はそれを引き継いだ研究者ですから。私たちの間に、それ以上の関係はあるべきではないんです。」
山崎は何か言いたげにしばらく思案顔をしていたが、結局はため息を一つ吐き出して、諦めたようだった。
「カスガノ=メグルです。本日から皆さんの仲間に入れていただく事になりました。分からない事ばかりで色々ご迷惑をおかけすると思いますが、一生懸命頑張りますので、よろしくお願い申し上げます。」
どこかおかしなその口上に、教室のあちこちで小さな笑い声がした。
その少年が、ほぼ全身をサイボーグ化していることは、その均質な肌の質感から見て取れた。もっとも、遠目で彼をサイボーグだと判断するのはかなり難しいだろう。一昔前には、ケーブルやレンズや、甚だしい場合には駆動装置の一部が露出していたり、プロポーションが人型を外れているようなサイボーグも珍しくなかった事を思えば、少年のそれは、ほぼ完全に人間の姿を模していると言って良かった。
実際、はにかみながらも人懐っこさを感じさせる表情などを見ていると、それがシリコンや有機部品で構成された人造の顔だと言うことを忘れてしまいそうだった。
「すごいものね」自分たちの製作物など、少年を形作っている先端技術と比べるべくもなかったが、それでもほんの少しの嫉妬とともに、然世子はそう呟いた。
その瞬間、然世子はメグルと目があった。
彼の聴力が人のそれを凌いでいるかも知れない事に、不意に気がついて、然世子は自分の不用意な発言に思わず赤面した。
メグルの方も、咄嗟に然世子を見てしまったことを不躾だと思ったのか、こちらもばつが悪そうに目を逸らした。
そう言うわけで、この日の二人の接触は、お互いの視線が出会ったこの一瞬だけだった。
従って、二人の出会いが、この後重大な意味を持つことに気が付く者も、居るはずがなかった。
一部始終を見守っていたアテナと、然世子の赤面に訝しげに眉をひそめた茅だけが、もしかすると、何か予兆めいたものを感じ取っていたかも知れない。
メグルは、窓際の最前列に座を占め、三列挟んで後ろになった然世子は、彼の高性能マイクが、自分の胸の鼓動まで聞き取れるものなのか、気が気ではなかった。
00210902ー6 エリナリスとジョエル(大統領執務室)
ニュートーキョーの最上部である第七層は、その殆どが世界共和国政府関連施設で占められている。その一角、世界共和国大統領府の一室で、一組の男女が静かに話し合っていた。
女性の名をエリナリス=ダ=コウワ=ラブルと言う。彼女は、一言で言ってしまえば、第四代世界共和国大統領である。先年の暗殺事件によって、当時副大統領だった彼女が急遽大統領職を引き継ぐことになったのである。彼女は後に機械民基本法の起草者として知られることになるが、それは当面この物語とは関係ない。
迫りつつある惑星統一選挙に向けて、日頃にも増して頭痛の絶えない彼女は、今また新たに持ち込まれた分厚い書類に目を通しながら、無意識の内にこめかみを押さえる仕草をしていた。
男性の方は、大統領直属の保安部門補佐官であるジョエル=ロングである。彼は、前大統領時代、共和国警察の警備部門で、その長を務めていた人物であり、褐色の肌と躍動感に溢れた長身の体躯を持つ男だった。
「概略は理解したと思うわ」エリナリスはペーパークリップで綴じられた分厚い書類の束を、ややぞんざいにデスクの上に投げ出しながら言った。「現時点で私が確認しておく必要があるのは、アナリスト達が、自分たちが言っている言葉にどれほど本気か、と言う事ね。」
「それは、完全に本気ですよ」ジョエルが楽しげな微笑を浮かべて言った。
「まったく、あなたがそう言う顔をしながら何か言う時は、本当にとんでもない事が起こる時よね。」エリナリスは、ますます渋い表情になりながら言った「あの時を思い出すわ。」エリナリスはジョエルをまっすぐに向いたままだったが、彼女が見ているのは、「彼」が凶弾に崩れ落ちた、あの光景だった。
「この情報の出所は、我々が送り込んだ中でも特に信頼の置ける浸透員です」ジョエルはエリナリスの感傷に、あえて気が付かない振りをして、続けた。「状況的に、これが、彼等にとって相当に重要な機密情報である可能性は高いと思います。」
「また、なのね」
「は・・・」ジョエルが虚を突かれたのは、エリナリスの反応が予想外に早かったからだ。
「もし遺族が居るのなら、充分な手当をしなさい」エリナリスは畳み掛けた。「これは命令です。しかるべきレポートの提出を求めます。アナリスト達の作業状況も逐次報告しなさい。ジョエル、今は、これ以上話を聞くのは無理。下がって頂戴。」
「分かりました、大統領」ジョエルは、こう言う時のエリナリスに逆らっては行けないことを十分承知していたから、余計な言葉は口にせず、退散することにした。それに、エリナリスが、ジョエル以外に、こんな風に感情的な面を見せることが殆どないことも、彼には良く分かっていた。
「現在、アナリスト達はこのファイルの暗号名として、T計画要綱を提案しています。ひとまずこれを仮採用して、以後の報告はT計画関連として提出します。では、失礼します。」
これも一つの信頼関係と言う奴さ。
廊下に出て、少し肩をすくめながら、ジョエルは、自分に言い聞かせる様に、胸の内に呟いた。
それは、彼と、彼の以前の上司の間で最後に交わされた言葉でもあった。
00210902ー7 然世子と茅(カフェテリア)
「それで、やっぱり昨日アランから付き合ってって言われたの?」
出し抜けに問いかけられて、然世子は口にしたコーヒーを危うく吹き出しそうになった。茅は、その然世子の狼狽を笑って眺めている。
時は昼休み、茅と然世子は、カフェテリアの窓際の二人掛けの席に、向かい合わせに陣取っていた。真向かいの茅の眼をまともに見返して、三秒で、然世子の顔に赤面が爆発し、慌てて顔を伏せた。少し、肩が震えているようだった。
「すごいリアクションだね。私が見た中でもベストスリーに入るわよ」ちょっと可哀想になって、茅は然世子に向けていた視線を自分の手元のコーヒーへ落とした。
「な・・・なんで?」然世子は、消え入りそうな声で呻くのが精一杯だった。
「ん?」
「なんで知ってるの」伏せた顔から絞り出されてくる然世子の声は、動揺に震えていた。
その、上ずった声と、うろたえた仕草を、茅は心底可愛いと思う。日頃の然世子の、部長然とした凛々しい姿も、茅は嫌いではなかったし、むしろそれはそれで可愛いとさえ思っていたが、今の、この然世子の有様は、彼女の予想を遙かに上回る可愛さだった。
つまるところ、茅は然世子のファンなのだ。
だから、去年、然世子が新しいクラブを立ち上げると言い出した時、彼女自身はSFなぞには殆ど興味が無かったにも関わらず、誰よりも先に参加の手を挙げたのだ。勿論、然世子は、自分への好意で茅が参加している事を承知していたし、気に病んでもいたし、実際、茅にもそう言った。
その時、茅は「運動部のマネージャーだと思ってくれればいいのよ」と事も無げに答えている。あの時、顔をグシャグシャにした然世子に抱きつかれた事で、茅の胸中には「然世子命」の旗印が、一層高く掲げられることになったのだった。
「やっぱり、さよちゃんは可愛いなあ」溜息混じりに茅は言った。
「なんで知ってるのよ」然世子はまだ顔を上げられずにいる。
「別に、見てれば分かるよ。」
「う・・・。そうなの?」
「それで、どうすることにしたの。」
然世子は、うつむいたまま小さく頭を振った。
「お似合いだと思うけど」茅は、なるべく気楽な調子に聞こえるように、細心の注意を払って呟いた。
「そうでもないよ」やっと茹で蛸状態を脱しつつある然世子は、火照りの残る頬を両手で押さえながら答えた。
「そうかな。端から見ていれば似たもの同士に見えるけどなあ。」
「だからだよ。」
今度は、茅が然世子の答えを待つ番だった。
言葉を纏める間を取るために、然世子はコーヒーを一口、口に含んだ。
苦い。
ほろ苦いそれを、飲み下し、口を開く。
「確かに、似てるのよ。それが、良くないの。」
「もう少し詳しく。」
「うーん。殆ど同じ場所を、似たような角度で描いた二枚の絵があるとするじゃない、タッチも構図も色合いも、とにかく似てるの。そんな絵が二枚並んで飾られているのを見た時、茅ならどうすると思う。」
「どうするんだろ」
「あたしなら、どこが違うか、まずそれを探してしまうと思うのよ。あ、ここがちょっと違う。こっちはこう違う。あそこも違うんじゃないか。そんな風に。」
「うんうん。」
「でね、なまじ似てるばかりに、きっとこう思ってしまうの。ここは、あたしの描き方が正解なのに。ここはこうじゃないのに。あそこも間違ってる。・・・ってね。」
「ああ・・・」茅は、喩え話には取りあえず納得したが、どこか割り切れなくもあった。
そもそも、そんなロジックが働くこと自体、然世子にとってアランがそういう対象ではないという事なのだろう。
「ちょっとアランが可哀想でもあるねえ。」
「うん」意外なほど率直に、然世子はそう答えた。茅は少し驚いたが、直ぐに理解した。
さよちゃんも凹んでるんだね。
意固地でままならない自分、その事に自己嫌悪する自分、落ち込むくらいならそうしなければいいのに、相手に誠実であろうとすればするほど、ますます意固地になってしまう自分。
さよちゃんは本当に可愛いなあ。
茅は心底そう思う。そして、心の奥でもう一言付け加える。
私は本当に可愛くないなあ・・・。
00210902ー8 柳とチョウ(中華飯店)
00210902ー8
柳とチョウ(中華飯店)
昼時の喧噪が凄まじかったせいか、昼下がり、客足の途絶えた「ラーメン横町五番街」を包む静寂は、わざとらしささえ感じられた。
ここは、内回り五号線と呼ばれる幹線道路のパーキングエリアであり、一キロ近くも飲食店が軒を連ねる、ちょっと名の知られた飲食街だった。
ちなみに、道路の呼称は、内回りが上り、外回りが下りの意味である。立体的な都市構造を七層、千メートル近くも積み上げたニュートーキョー特有の言い回しだった。
数ある幹線道路の中でも、一桁の路線番号を持つ道路は、その全長に渡って透明なチューブ状の構造物に覆われており、1層から7層までの高低差を利用して、与圧が不要な程度に気圧が下げられていた。これは、小型車両には殆ど効果がなかったが、大型車両にとっては、空気抵抗の軽減により、バッテリーの消耗が改善される恩恵があったため、自然と一桁の道路と言えば大型貨物車両の優先道路とされていた。
「ラーメン横町五番街」は、その貨物車両の運転手を当て込んだ飲食街であり、実際、昼時や夕刻になると、ちょっとした祭日のように賑わった。
しかし今は、通り一帯に気怠い静寂が横たわっている
柳は、すでに不惑を越えた、どこにでも居そうな中年の男だ。頭には幾筋か白い物が走り、顔にも、無数の深いしわが刻まれている。
眉間に難しそうな皺を寄せて、彼は敢えてこの時間帯を狙ってここを訪れていた。
彼が向かったのは、通りの中でも比較的奥まったところにある中華飯店だった。
「花花」の屋号が大きく書かれた入り口に、営業中の札が掛けられているのを確かめて、柳は店内に進んだ。
まだ客が一人残っているのを見て、一瞬考えてから、柳は食事を済ます事にした。考えてみると、朝から何も口にしていなかったのだ。
「A定食をもらえるかな」来客に気付いて奥から出てきた、若い娘にそれだけ言う。
娘は、柳の顔を見て、少し眉をひそめると、お愛想の一つも言わずに奥の厨房へ帰っていった。
程なく、厨房の方から何かを刻む音や炒める音が一頻り聞こえ、柳も驚くほどの早さで料理を載せた四角い盆がテーブルまで運ばれてきた。
大皿の肉野菜炒めと、山のように盛られたチャーハンが、旨そうな湯気を立ち昇らせている。
ガチャン!
「はい、スープ」一旦厨房へ消えた娘が、湯気を立てるカップを置きに戻ってきた。「食ってる間は客だから仕方ないけど」乱暴な配膳に驚いて顔を上げた柳に向かって、娘は厳しさを増した口調で続けた「食べ終わったら、さっさと消えてちょうだい。あたし達のところは、これ以上ないほど、真っ当にやってるんだよ。刑事さん達に話す事なんて、もう何もないよ。」
「よく覚えてたなあ。」
「ゆうべ、最初に駆け込んできた刑事さんだろ。これでも客商売は長いからね。人の顔を覚えるのは得意なんだ。」
「うちの若いのにも見習わせたいね。で、刑事さん達、とは。」
娘が、顎で指し示した先で、ラーメンを啜っていた若い男が、柳へ向かって苦笑いと共に手に持ったIDを振って見せた。
「なるほど、ね。ま、ともかく冷めない内にいただく事にするよ。腹ペコなのは本当なんだ。」
柳は猛然と食事に取りかかった。
体力勝負の客層に合わせた、ボリューム自慢の料理が、見る見る飲み込まれて行く。
カチャン。
柳がレンゲを置いた時、思わず見とれていた娘の口からため息が漏れた。
「腹ペコは本当だったみたいね」半ば呆れ声で娘が言う。
「そう言っただろう。」
「いつもそんな食べ方なの。」
「こうでなきゃ食った気がしないよ。」
「ふーん。あのねえ、話すようなことが何もないのも、本当なんだ。」
明らかに、娘の声の調子が変わったのに気が付いて、柳は一瞬考えたが、何気ない調子のまま話を続けた「大将はどうしたんだ。今日はお前さんだけかい。」
「お陰様で、今は寝込んでるよ。あんた達が帰ってから、今日のランチタイムに間に合わせるのに、大騒ぎだったからね。」
「そうだろうな。正直言うと、今日店が開いてたんで驚いたよ。」
「戦時中でも毎日店を開け続けたのが、父さんの自慢だからね。殺人事件ぐらいで休むわけには行かないんだ。」
「お前さんは、殺人事件ぐらいって顔じゃないな。」
娘の顔が、一瞬歪んだ。
「いきなり飛び込んでこられて、目の前で人に死なれるのは良い気分じゃないわ。まして、殺されたとあっちゃね。」
「ああ。こんな仕事をしてても、そう思うよ」柳は、そう言うと、大儀そうに立ち上がって、娘にマネーカードを差し出した。「ごちそうさん、お勘定を頼むわ。」
「あら、もう良いの。」
「別に、俺は事情聴取に来た訳じゃないんでね」柳はここで、わざとらしく真剣な顔になって続けた。「また寄らせてもらうが、それは、旨かったからだ。」
娘は破顔して言った「お愛想でも嬉しいわ。食べっぷりが良い人は、好きなんだ。」
「そいつは良かった。」
「ね、次はあれに挑戦しなよ」娘が悪戯っぽく笑いながら指さした先には、「超盛ラーメン・完食無料」の貼り紙があった。
「俺も、もう、そう言う歳でもないんだけどな」柳は、明らかに普通のラーメンの五倍はありそうな写真を見ながら言った。
「あんたなら大丈夫だよ。それに、食べっぷりが良い人が好きなのは、あたしより父さんの方が、ずっとだよ。」
「なるほど、そう言うことだ。分かった、考えとくよ。おい、あんたも一緒に出ないかい。なんなら奢りにしてやるよ。」
不意に呼びかけられたもう一人の客は、立ち上がると、決然と自分のマネーカードを出した。
「そうかい。ま、いいや。」
娘の「毎度ありー」の声を背に、刑事二人は連れだって表へ出た。
「言っておきますが。」
「言っておくが。」
二人が口を開いたのは殆ど同時だった。
一瞬顔を見合わせた後、柳は目線で相手に先を促した。
若い刑事はむっとして言った「この事件の優先捜査権は、我々共和国警察が持っています。首都警察の方が勝手なことをされては困ります。」
「分かってるさ。だから、あの娘にも事情聴取じゃないって言っただろう」柳は不敵な微笑を口元に浮かべながら言う。
「じゃあ何をしに来たんですか」若い共和国警察の刑事は、柳の挑発を受け流すことが出来なかった。「まさか、本当にランチの為ですか。」
「そうだったら、いけないか。そう言うお前さんこそ何をしてたんだ。ランチかね。」
「聞き込みに決まってます」若い刑事の顔に朱が差す。
柳が更に挑発を重ねようとしたその時、胸ポケットの携帯端末機が、甲高い呼び出し音を割り込ませた。携帯端末の画面を一瞥してから、興をそがれた時の常で、あからさまにそれと分かる渋面を作って、柳は言った「あんた、名前は。」
「外事局刑事部刑事課第一捜査係チョウ=シャオ=イェン。」
「チョウさんね。首都警刑事部刑事課の柳だ。また会おう」柳は身を翻して、駐車場へ向かって小走りに消えていった。
取り残されたチョウは、その姿を見送って、しばらくの間立ち尽くすしかなかった。
00210902ー9 宇宙の戦士(文化部長屋)
「それは弱ったね」言葉とは裏腹に、どう見ても愉快そうに見える微笑を浮かべながら、芝崎教頭は言った。
「そ、そうなんです」然世子は、どうしてもこの教頭に対して苦手意識を拭えなかった。「私たち、困ってしまって。」
「いやいや、困っているのは私の方だよ」芝崎は眼鏡の奥の細い目を、さらに細めながら言う。然世子は、その眼が特に苦手だった。「元々、私には、SFとやらの研究に、こんなものが必要だとは、思えないんだけどね。」芝崎のその眼が、部室奥の「パワードスーツ」を冷酷に一瞥した。
アランと咲子は、一台のパソコンのディスプレイを覗き込んで、駆動用プログラムの調整に取り組んでいた(少なくともその振りをしていた)が、芝崎の視線が背中を通り過ぎた瞬間、その冷気に当てられたように、ギクリとした。
「まあ、組み立てなければ良いと言うんだから、そうすればいいだろう」芝崎の言葉には、いっそ廃棄が命令されれば良かったと言う感情が滲んでいた。「とりあえず、明日までに、そいつを、法律に抵触しないところまで分解しておくように。」
「そんな」然世子の顔が怒りに朱に染まった。「それじゃ、文化祭に間に合いません。」
「意味が分からないな。何が間に合わないのかね。」
「今、バラしてしまったら、これから整備資格を持っている人を見つけても、展示に間に合わないじゃないですか。」
芝崎は、鼻を鳴らして、口の端に嘲るような微笑を浮かべた。「まだそんなことを言ってるのかね。このご時世で、ここに未登録のサポートユニットがあると言うことが、どれ程重大なことか、分からないのかね。譲歩する余地はない。明日、まだここに、そいつがそのまま置いてあるようなら、君らの団体ごと処分することになるぞ。」
芝崎は、それ以上は相手にならず、言い返そうとする然世子に口を開く暇も与えずに、部屋を出て行ってしまった。
「・・・・・もぉっ」然世子が、ため込んでいた怒りを爆発させたのは、芝崎の背中を見送ってから一分以上経ってからだった。その間、一言も口を利かなかった一同が、一斉に然世子を振り返った。
「あんな風に言わなくても、いいじゃない」然世子の憤懣は、本質的には芝崎の意見が正しいことに発していた。
「あたしだって、分かってるわよ」然世子は皆に聞かせるように言った。「違法なパワーアシストユニットの所持が、銃器の不法所持と同じくらいの罪になることぐらい。でも、ここは学校の中だし、アテナもいるし、十分なセキュリティがあるはずでしょ。」
「まあ、PTAへの責任もあるし、教頭は言うべき事を言っただけだと思うね。」上田は、パワードスーツのマニピュレーターを弄びながら言った後、不意に周囲の冷ややかな空気に気が付いて、慌てて言い足した「いや、もっと言い様はあったと思うけどね」。
その様子が余りに取って付けたようだった事で、逆に然世子は毒気を抜かれたような気分になった。
「仕方ないわね。ともかく、両腕を胴体から取り外すくらいはしておきましょう。上田君、手伝って。」然世子は溜息を挟んで続けた「アランと白石さんは作業を続けて。もし、この後、奇跡が起きた時のためにね。」
「ジンじを尽くシて賢明にナル、だな。」
「天命を待つ、です」咲子が小さな声で訂正した。
「じゃあ、私はもう少し手続き関係を調べてみるね」言いながら、茅はパソコンを起動させるために、雑然とした机を片づけ始めていたが、ふと手を止めて言った「PTAと言えば、校長先生もずいぶん思い切ったことをしたよね。」
「どう言う意味」上田が支えているマニピュレーターの固定用のボルトを回しながら、然世子が問い返す。
「アア、例のてン校生のことか」アランが低い調子で言った。
「そう、事前に保護者会に報告されてないって、バスケ部の坂本君が騒いでたわ。彼のお父さんが会長さんだからね。」
「どう言うこと」然世子は手を止めて、茅を振り返って言った。「転校生の受け入れなんて、保護者会と関係ないでしょ。そんな事にPTAの許可が必要な訳無いじゃない。」
「彼が普通の生徒なら、ね。勿論、転入の受け入れなんかは、本来PTAとは関係ないことよね。」茅は机上のパソコンを操作しながら言った「アテナ、ここから、運輸局のデータベースを呼び出せるかな。」
「はい」アテナが瞬時に返事をし、殆ど同時に、茅のパソコンに目当てのデータベースが表示される。
「ねえ、それって、彼がサイボーグだからって事よね」然世子は食い下がった。
「まあ、こんなご時世ですからね」上田は、言い終わった瞬間、後悔した。間近の然世子の顔に、怒りの炎が再び点火されたからだ。
「そっちでは、ご時世だからって、規範を歪めて、こっちではご時世だからって規範を厳守しろなんて、どう考えても矛盾してるでしょ」然世子は語気を荒げて言った。「それとも、彼のことも授業中はバラバラにしておくつもり・・・。」
急に言葉を失った然世子を、全員が見つめていた。
一言二言、何事かを口の中で呟いてから、然世子は言った。「ねえ、彼のところには、当然、整備資格を持った人が居るはずよね。」
「あ」「おお」異口同音に、皆の口から呻き声が漏れる。
「とにかく、明日にでも当たってみる手ね」そう言いながら、茅は奇妙な胸騒ぎを感じていた。
なんだろう。さよちゃん、ちょっとおかしい。
その茅の思考は、上田の悲鳴に断ち切られた。
「ぶ、ちょう、重い・・・」途中まで外されたマニピュレーターの重量を支えていられなくなったのだ。
危うく下敷きになりかけた上田を助け出す騒ぎが、茅に疑問を忘れさせてしまった。
とりあえず、その時は。
00210902ー10 メグルとアゼミ(田中ラボ)
「それで?」メグルが帰宅してから、アゼミがこう言うのはすでに十回を越えていた。
「それで、今日は後期授業の始業式だったから、全校集会があって、履修科目の一覧をもらって、終わりだよ」メグルは、先刻からずっと感じていた疑問をやっと口にすることに決めた。「あのさ、学校であったことは、アゼミにだったら、記憶を共有化してあげられるし、流子さんに提出するレポートも読ませてあげられるし」そこまで言っても、アゼミの表情に何の反応も浮かばないのを確かめて、続けた「全体、どうして、こうやって言葉で僕に説明させたがるの。」
アゼミは、少し間を置いた後、微笑を浮かべて言った。
「何故なら、こうやって言葉で相談することが、いずれ絶対必要になるって、オシリスもアテナも言うからよ。」
「それって、どう言う意味」メグルは少なからず興味を引かれて聞き返した。
「さあ」アゼミは簡単に言った「勿論、あたしにはその理由までは分からないわ。アテナもオシリスも、説明してくれないし。」
言うまでもないことだが、メグルにもその意図は見当もつかなかった。考え込みながら、メグルは、携帯端末機を取り出して、目的もなく弄び始めた。
ふと思い付いて、自分の指を汎用コネクターに変形させると、携帯端末機の接点に接続してみた。
無に等しいほどのささやかな記憶領域。静謐な情報力学構造。静電容量と加速度、極めて限定された帯域の電磁波と、空気の波動しか感知できない余りにも貧弱な物理世界との接点。
彼自身が今も接続している果てしのない情報の大洋に比べて、なんと慎ましいことか。
それに、ここには無限の複雑さで生成消滅を繰り返す情報嵐も存在しなかった。
メグルは、視覚を端末の光学センサーに侵入させてみた。途中、三つほどプライバシー保護のためのプロテクトが仕掛けられていたが、メグルにとっては、無意識の内に回避できる程度の代物だった。
携帯端末機の眼からは、鏡を見ているように自分自身の顔が見えた。
白磁のような白い顔、ガラス玉のような眼、不自然に光沢のある黒い髪。
口を開けたり、眉をしかめさせたりしてみる。
動いてみれば、我ながら、人間そっくりだと思う。
それもそのはずで、彼の表情筋はナノマシンによって分子レベルまで再現されているのだ。一時代前の、エアチューブなどでそれらしい膨らみを再現したものとは訳が違った。
「すごいものね」
突然、然世子の声が脳裏に響き、メグルの意識を自分の体へ引き戻した。
視界は自分自身の視覚装置が提供する物に戻り、携帯端末機の画面に写る、曖昧な自分の顔がメグルをのぞき込んでいた。
無意識の内に、メグルはため息をついていた。
こうして、長い始まりの一日に、ようやく幕が下りた。
互いに絡み合う、いくつもの道筋が、この日を起点に描かれ始めた。
やがて、それらが交錯する日を迎える事を、この時は、まだ誰も知らなかった。
00210903ー1 第二種接近遭遇(東七高等学校図書室)
統一歴二十一年九月三日。
後期授業が始まったばかりだったので、今週は授業らしい授業の予定はなかった。
然世子達が今週中に終えなければならないのは、前期の成績を元にして、後期に履修する科目を届け出る事と、来週からの授業に必要な教材を手配することだった。
前期の成績表と進級資格表と格闘しての単位計算や、後期科目の情報集め(内容や難易度は勿論、担当教官や、先輩のノートが入手可能かどうかまで)は、かなり手間のかかる作業であり、結果として、もう午前中も終わろうかというのに、然世子はメグルに声をかけられないままだった。
それは、然世子を苛々させるのと同じくらい、少し安堵させてもいた。
あの一言はどう考えてもまずかった。
カスガノ=メグルに話しかける、と言う現実が目の前に近づくにつれ、昨日の自分の心ない発言が、然世子の胸に暗い影を落とす。
何で、あんなことを言ってしまったのか。
でも、この一夏の努力を無にするわけにいかないんだから。
あたしは部長なんだから。
そんな言葉を、然世子は、半日の間にすでに数え切れないほど繰り返していた。
しかし、「現代史」の補助教材に指定されている副読本を探す為入った図書館で、奥の書棚にメグルを見つけた瞬間、これほど言い聞かせていたにも関わらず、然世子は咄嗟に彼に背を向け、危うく図書室から逃げ出すところだった。
早鐘を打つような心臓の音が、耳の奥で聞こえる。
「えーと、デイリーサンセットの<統一されざる社会史>は・・・」独り言を呟きながら、然世子は足早に図書検索用の端末へ向かう。
とにかく、落ち着かなきゃ。
何事も心の準備が大事よね。
然世子はそう繰り返しながら、必死で歩を進めた。足が地に着いていないようだった。
端末にたどり着き、何気ない動作を装いながら、盗み見るように、もう一度メグルの存在を確かめる。
居た。
改めて見る彼の姿は、ほんの数メートルしか離れていないここからでも、全身サイボーグにはとても見えなかった。
身長は、ほぼ同学年の生徒と同じ位、多分170センチ前後だろう。片方の足に体重を預けて直立している姿勢。書棚の本を抜き取る時の、腕から指先まで完璧に連動した動作。すべてが、それと知らなければ機械の動作には見えなかったし、実際には、そうと知っていてる然世子にも、生身の動作そのものに見えた。
ふと気が付くと、図書室のあちらこちらで、然世子と同じようにメグルの姿に視線を注いでいる生徒達が居た。
その大半は、言うまでもなく、奇異なものを見る視線だった。然世子は、自分の視線にも同種の輝きが含まれていたかも知れないと思い付いて、動転した。
違う。あたしは曲がりなりにもマニピュレーターの基礎構造や制御関数が頭に入ってる。その上で、あの優美な動きに驚嘆したんだ。だから、きっと、違う。
その内心の言い訳の分、然世子は出遅れた。
彼女が意を決してメグルへ歩み寄る前に、彼は三人の男子生徒に取り囲まれていた。
その内の一人は、然世子にも見覚えがあった。
昨日、茅が話していたバスケ部の坂本だった。
咄嗟に、然世子は歩く行き先を変えて、メグル達から書棚一つを挟んで反対側へ向かった。
ちょうど彼等の裏にたどり着いたとき、メグルの落ち着いた声が聞こえた。
「ようするに、私が自爆するかも知れないから学校を辞めるようにと、おっしゃりたいんですか。」
然世子はこの一言の為に、金縛りにあったように書棚の裏から動けなくなった。
「やっぱり自爆すんのか」坂本と一緒に取り囲んでいる男子の一人が言った「自爆されたくなきゃ、文句言うなってことか。」
「どうして、私が自爆しなければいけないんですか。」
「そんな事分かる訳ないだろ。機械の体だと何かと文句があるんだろ。」
「なんにしても、そんな脅しをかけるようじゃ、君も校長先生も困ったことになるよ」然世子の記憶が確かなら、この声の主が坂本のはずだ。「もう、そんなことは言わない方が良いね。」
この台詞は、然世子の神経を逆撫でした。
あんたちが言わせたんでしょ。
心の中でそう叫んだ瞬間、思いも寄らない声に、然世子は耳を疑った。それは言葉ではなかった。余りにも意外なもの、メグルの笑い声だったのだ。
「何がおかしいんだよ」別の取り巻きが、強い口調で言ったが、声のどこかに動揺の気配があった。
メグルはまだ少し笑い足りなかったらしく、声にその余韻を滲ませながら答えた「いや、申し訳ありませんでした。今になって、やっと、私の立場が理解できたので。」メグルは、余程面白かったらしく、急に饒舌になって続けた。「なるほど、イジメって、こういう風にするんですね。素晴らしい論理の飛躍です。確かに私は自爆と言う言葉を口にしましたね。そう、それをあなた方が脅しと受け取ったわけですね。私があなた方にそう言うように誘導されたと言っても、その証明は出来ません。脅す意図はなかったと言っても、それも証明しようもない事です。あなた方に脅す意図があって、私を陥れる意図があったと、私が言っても、あなた方がそうでない事を証明できないのと全く同じ事です。ところが、一見等価な、この証明不可能と言う立場の対等性が、言葉を口にした順序と言うたった一つの要因で、これほど鮮やかに、非対称性を生み出すことが出来る訳です。なんと素晴らしい。いや、本当に勉強になりました。次はこんな風にイジメられないよう気を付けます。」
恐らく、メグルが頭を下げたのだろう。ささやかな衣擦れとサーボモーターの作動音の後、居心地の悪い沈黙が訪れた。
「行くぞ」沈黙を破ったのは坂本だった。
三人が引き上げて行く足音を聞きながら、然世子は声無く笑い転げていた。
00210903ー2 然世子と茅(カフェテリア)
「それで。」
「いや、あれはもう、宇宙人の域だね。」
昼休みのカフェテリアで、いつものように向かい合わせに腰を下ろして、然世子は茅に図書室での一件を愉快そうに報告していた。
「坂本君の顔を見たかったなあ」然世子は満面の笑みで言う。「次はどう言う手で来るのかな。諦めるとは思えないし、今日のところは、きっと戦略的撤退とか言う奴だと思うのよね。」
「それで」茅は、辛抱強く言った。
「え・・・。」
「さよちゃん、もしかして、それで終わり。」
「う、うん・・・。」
「彼、当然クラブ活動、してないよね。」
「そうだよね」然世子にも、ようやく茅の言いたいことが分かり始めていた。
「そうすると、彼は、午前中で、帰宅しちゃったんじゃないの。」
「・・・ごめん。」
反論の余地はなかった。
「面目ない」すっかり気を落として、然世子はもう一度謝った。
「別に謝って欲しい訳じゃないけど」茅は一呼吸分だけ迷ったが、やはり言っておくことにした「さよちゃんらしくなかったね。」
何かが然世子の胸に突き刺さる音が、聞こえたような気がした。そして、同時に、その何かが自分の胸にも突き刺さるのを、茅は感じた。不思議なもので、意図して相手を傷つける言葉を口にすると、それは必ず自分も傷つける。
神様は、公平すぎて、不公平だ。
茅は、こんな時、いつもそう思う。
然世子は、そんな茅の内心に気付く筈もなく、俯いている。茅はその姿をしばらく眺めてから、諦めた。どうするべきかは、初めから分かり切っていたのだ。
「でも、カスガノ君も中々やるわね」少しため息混じりに、そう言ってみた。口にして初めて、意外にもそれが自分の真情に近いことに気づかされる。「カスガノ君にしても、相手の出方を探ってるんでしょ。そのオトボケを額面通りに受け取って良いかどうか分からないよ。少なくとも、坂本君はそうは思わなかったんでしょうね。」
いつの間にか、然世子が顔を上げて、茅を見ている。
「すごいなあ、茅は」然世子の声には、感動の響きがこもっていた。
「どう言う意味よ。」
「だって、あたしの話を聞いただけなのに。なるほどねえ、あたしなんか、自分で見てたのに、そんな事考えつかなかった」そう言いながら、然世子は、もう一度一連の出来事を思い浮かべていた。茅の解釈という新しい光が、それまでの然世子には見えていなかった情景を照らし出していた。「なるほどねえ」すっかり感心して、然世子はもう一度繰り返した。
「性格悪くてすみませんね。」
「そうじゃないよ。大人だよね。」
「褒められてる気がしないんですけど。」
「うー、ごめん。でも、褒めてるんだよー。」
後は、いつもの笑い話へ落ち着いていくだけだった。
これでいいんだよね。
そう思った瞬間、茅は急に別の事に気がついた。
そっか、さよちゃんと男の子の話をすることなんて、殆どなかったんだ。
しかし、直ぐに、この感想が正確ではないことに気がつく。
実際には、上田やアランについて話す事は多かったし、昨日の坂本のように、話の中で男子の名が出ることだって少なくはない。
じゃあ、何だろう、この違和感は。
茅は、然世子の顔を、改めて、じっと見た。
「な、何か付いてる」然世子が茅を見返す。
「ううん。何でもない。部室行こうか。」
「う、そだね。みんなにも謝らなくちゃ。」
茅は、立ち上がりながら、一瞬脳裏をよぎった考えを振り払うように首を振った。
まさか、ね。
この時、もう少し考えてみるべきだったかも知れない。
茅がそう思うようになったのは、大分後になってからのことだった。
00210903ー3 オシリスとジョエル(大統領府)
ジョエル達、大統領補佐官は、大統領府の一角に各一室を与えられている。それほど広くもないその部屋には、長大なデスクが一台置かれ、普段、この部屋に十五分も居続けたことがないジョエルが、今日は珍しくそこに行儀良く座っていた。
ここでしか打ち合わせが出来ない相手が一緒だったからだ。
彼のデスクの前には高さ1メートル位の円筒があり、その上に、戯画化されたネズミが後足二本で立っていた。
「まさか、エリンの端末にもその姿で出ているんじゃないだろうな」ジョエルは呆れ顔でそのネズミに向かって言った。
「一度だけ、な。彼女は、思った以上に、そう、理性的だったよ。」ネズミは少し眼を細めて続けた「しっかりと、こっちを睨んで言ったんだ『オシリス、二度とその姿で現れないで』って。悲鳴ぐらい上げて欲しかったんだけどねえ。」
不思議なことに、ネズミの表情から、オシリスが本気でがっかりしているのが伝わってくる。
ジョエルは、不本意ながら、口元が弛むのを押さえられなかった。
「猫にすればよかったんだよ。」
「猫?」
「ああ、ただし俺から聞いたなんて事は口外無用で頼むよ。」
「ふーむ。猫ねえ。」
「おいおい、今日は我らがボスの女らしさがテーマなのか。」
「それと同じくらいには興味深い話だよ」オシリスはまじめな調子で答えたが、姿はネズミのままだった。ジョエルは少し考えて、結局何も言わないことにした。多分、オシリスはこのジョークを気に入っているのだろう。
「ひとつ、見てもらいたい物があるんだ」ネズミ姿のオシリスの傍らに、新たなウィンドウが投影され、一見して軍事用と分かる大型のロボットが、岩だらけの荒れた海辺を進む映像が再生され始めた。
「昨日、イオウジマで実施された共和国軍の演習だな」再生が始まった映像を一瞥して、面白くもなさそうにジョエルが言った。「概略は私のところにも報告が来ているが。」
「うん。それで、これについて、何か知っているか」オシリスの言葉と共に、映像が一時停止され、その一部分が拡大される。ガンカメラの荒い映像だったが、多脚型の大型ロボットの一部が判別できた。
「ああ。コードネームはリトルボーイ。五年くらい前から海軍の方で研究開発が進められていた第六世代型ウォーマシンの評価用機体だ。群知能による自律作戦行動のオペレートをさらに前進させたものって言う触れ込みだったが。」
「この演習の時は、海軍のウォーマシン、TDMM14ジェリーフィッシュの三群体を単機で制圧している。まあ、ウォーマシンの常で、世代交代の際に旧世代が圧倒されること自体は珍しくもないけどね。」
「この機体について、君が知らなくて、私が知っていることがあるとも思えないんだが」いつまでも話が焦点を結ばないことに、ジョエルはそろそろ苛立ち始めていた。
「ああ。それはその通りだが、そう、ジョエルは田中ラボに知り合いが居たように記憶しているが。」
「何を今更。前の仕事の関係もあって、私と丈太郎は友人と言っても良い間柄だった。今の所長とだって、付き合いがあるとも。」
「まあ、そう怒るなよ。それで、ジョエルの情報力学の理解はどれ位なのかな。」
「ん、せいぜいハイスクールレベルかな」思わぬ質問に、ジョエルは戸惑いを隠せなかった。「あの分野は、どうも苦手でね。元々複雑系は、得意じゃないんだ」思わず照れ笑いが顔に出てしまう。
「安心してくれ、今回の話に数学的な知識は必要ないよ。と言うことは、我々情報生命が、実体として記述されたプログラムを持たないことや、存在するために、ある程度の強度をもった情報力学上の場が必要なことは理解しているね。」
「有名な『情報生命は記述されていない』、と言うテーゼだな。君たちに必要なのは膨大な量の情報が十分高速にやりとりされるネットワークそのもので、そこでやりとりされる情報の内容とは無関係だと言うんだろう。」
「うん。良く使われたのは『情報生命は中華料理のレシピの上でも生きてゆける』と言う奴だ。」
その良く知られたフレーズは、情報生命が、自分たちとは異質な、非人類知性体であることを、改めてジョエルに思い出させた。とは言え、たった今、目の前にしているネズミの立体映像に対して、哲学的な感想を抱くことも難しかったが。
「我々を情報力学的なソリトンとして解析可能かも知れない、と言う、いわゆるグッドン=サイラス仮説だね」オシリスは、何事もない様子で続けた「まだ検証が終わっていないけれど。」
「情報の内容が、全く無関係ではないかも知れない、と言うタナカ=リューモデルによる反証が、やはり検証待ちだからな。」
このジョエルの言葉に、ネズミは顔をしかめる仕草をして見せた。
「人が悪いな、なかなか詳しいじゃないか」オシリスの声音には、少し悔しそうな響きが混じっていた。
「仕事柄、全くの無関心でもいられないのでね。数学が苦手なのは本当だよ」ジョエルの顔は、謙遜の言葉とは裏腹に、自信に満ちた笑顔だった。
「ふむ。では、話を簡潔にしよう。さっきのリトルボーイのスペックと、去年発表されたカーペンター教授の論文を一緒に考えてみてくれないか。それで、何か思い当たることがあれば知らせて欲しいんだ。」
「何だって」ジョエルは慌てて聞き返そうとしたが、すでに投影装置からはリトルボーイの映像は消え、入れ替わりにどこへ通じるとも知れない小さな「穴」が映し出されていた。
「カーペンター教授の論文だ。確か去年三月の学会誌に載っていたと思う。では失礼」ネズミの姿は、その「穴」へ駆け込み、程なく穴そのものも消えた。
「まったく」ジョエルは半ば呆れ顔になって呟いた。「この話が、何と同じくらい興味深いんだって。」
00210903ー4 パワーゲーム(中華飯店「花花」)
昼時の「花花」から、場違いな歓声が轟いた。
通りに溢れかえっていた雑踏の足が、ふと振り返るような、どよめきである。
実際、思わず店をのぞき込んだ者も大勢いた。
柳が、店主自慢の「超盛ラーメン」を、記録的な速さで完食したのである。
「良い味出してるな」柳には、少し悔しそうな店主に、微笑みかける余裕さえ残っていた。
店主であるところの五十嵐は、その笑顔を見て、ついに現実を受け入れたらしい。「やるな、刑事さん」そう言いながら破顔した。
「ね、だから言ったでしょ。このおじさんはヤルよって」そう言う娘は、父親と対照的に、どこか得意そうですらあった。
昼時のことでもあり、野次馬達の大半は、そのまま客に早変わりした。
柳は、店の片隅で、娘の出してくれた茶を飲みながら、客が切れるまで待っていた。話したいことがあったからだが、正直、あまり立ち上がりたい状態でもなかった。
親父め、絶対一玉余分に麺を入れやがった。
ワイシャツの上からもはっきりと分かる自分の胃の膨らみを、満腹感で重くなった瞼の下から恨めしそうに眺め、柳は溜息をついた。
俺も、もう若くないからな。
それでも、客がまばらになる頃には、どうにか身動きできるようになっていた。気は進まなかったが、厨房の入り口で、水の入ったボトルを片手に一息入れている五十嵐の近くまで、歩いて行く位のことは出来た。
「無理するなよ」店主は柳より何歳か上の筈だったが、皺一つ無い肉付きの良い顔を、汗に光らせながら言った。
「なあに、腹八分目さ」言い返しながら、柳は店主が麺を増量していたと確信した。
五十嵐はその柳の言葉に大笑した後、言った「いや、大したもんだな。いいぜ、何を聞きたいんだ。」
「そうだな。聞きたいことが色々あるのは、多分あっちのお兄さんだな」柳が顎で指し示したテーブルでは、チョウがレバニラ炒めと格闘していた。「俺が聞きたいのは、あの被害者が、以前この店に顔を見せていたかどうか、それだけなんだ。」
五十嵐は顔をしかめて呻いた「ああ、そいつは俺も気になってるんだよ。実はあのサイボーグさんの顔に、見覚えがないんだよな。」ちょっと遠い目をして、付け加える「何でまた、俺の店に転がり込みやがったんだか。」
「そうか。チョウさん、ちょっと」柳は出し抜けにチョウを呼びつけた。
不服そうな顔で、チョウが柳を睨み返す。
もっとも、チョウが自分と五十嵐の会話に興味津々だったことは、柳には計算済みである。その証拠に、不服そうな顔のままではあったが、食事を中座して、チョウは二人の方へ近づいてきた。
「何ですか」チョウは柳を睨みながら言った。
(そこまで喧嘩腰か)柳は内心苦笑しながら言った「ちょっと、大将に被害者の資料を見せてやってもらえないか。勿論、見せられる範囲で良い。」
「それは、構いませんが。」チョウは訝しそうに五十嵐へ視線を移して続ける「良いんですか。これは立派な捜査協力ですよ。」
その言葉を聞いた途端、五十嵐は爆笑した。
「な、なんです」思いも寄らない反応に、チョウは狼狽えていた。
「おいおい、チョウさんとやら、ついさっきまで、あんた捜査に協力するのは市民の義務だとか俺に言ってたじゃないか」五十嵐は笑い声の下から言った。
「それはそうです。けど、何かこの柳さんのやり方が、ちょっとフェアじゃない気がして」チョウは思わず顔を赤らめ、柳を睨みながら言った。
「言われてるぜ」五十嵐は愉快そうに柳を見た。
「フェアが聞いて呆れるぜ」柳もニヤリと笑いながら五十嵐を見返す。
「違いない」五十嵐はチョウへ太い腕を突きだして、言った「ほれ、その資料とやらを早く出しな。」
納得できる展開とは言えなかったが、ともかく、チョウは一般的な物より一回り大きめの携帯端末機を取り出した。神経質そうに指を動かし、端末の表面にいくつかのセキュリティコードを描く。
程なく、端末表面に、被害者の画像と、プロフィールのテキストが表示された。
「ご苦労。俺はどうもその芸当が得意じゃなくてね」柳はチョウの携帯端末を引ったくるように奪うと、そのまま五十嵐に手渡した。
「いやいや、これはないな」五十嵐は、画面を一目見るなり、言い放った。「こいつは、あれだろ。体の大半を機械化しちまってるんだろ。うちは代用食のメニューは無いからな。」
「クラスFサイボーグですね。生体が体重の二割を下回るところまで機械化していますから」チョウが溜息混じりに言った。
「だから、こうなる前の写真を出しなよ」五十嵐が端末をチョウに返しながら言う。
チョウは、少しためらった様子だったが、結局、サイボーグ化前の被害者の写真を画面に呼び出して、端末を五十嵐の手に戻した。
五十嵐と柳が額を寄せて画面をのぞき込むのを横目に、チョウが説明を加えた。「ジョナサン=スバイガート。生年は統一歴、前十九年。統一歴九年に、マニラで負傷してからサイボーグ化を始めたようです。この写真は統一歴六年頃のものらしいですね。」
画面では、体格の良い青年がよく日に焼けた褐色の顔に、快活な笑顔を見せていた。
「おい、夏織、お前も見てくれ」五十嵐が娘を呼ぶ。とっくに興味津々の顔になっていた夏織は直ぐに駆け寄ってきた。
父娘二人で眉間に皺を寄せて画面に見入っている。がっちりした父の顔と、小作りな娘の顔が、並べてみれば思いの外似ていることに、柳は感心していた。
「うろ覚えだけど、あたしが中学の頃、何回かお店に顔を出したお兄さんに少し似てるかなあ」夏織が難しい顔のまま呟く。
「旧市街に店があった頃か」父親も難しい顔をして頷く。「ああ、こいつ海兵隊の軍歴はないかい。」
「無いと思います」チョウが答えるが、語尾が少し不安そうだった。
「すると違うかなあ。」
「海上自衛隊は本土の人ばっかだったしねえ。」
「この手合いは、軍属さんだと思うんだけどな」
「顔で分かりますか」チョウがいつの間にか父娘の会話に引き込まれていた。
「あんたが思っているよりは分かるね。」
「最後の経歴は海軍工廠なんですけどね。」
「その頃にはもう、うちに来る用はなかったんだろ。」
「あのー。」
「大将、旧市街はどの辺りに店を出してたの。」
「ネリマって分かるかい。」
「すみませーん。」
「ネリマのどの辺ですか。」
「駐屯地の近くだったよね。」
「A定食もらいたいんですけど。」
気が付くと、額をこすりつけんばかりに顔を寄せ合っていた四人に、困り顔の客が遠慮がちに声をかけてきていた。
「っと、悪かった。A定ね。夏織。」
「ごめんなさいね。急いでご用意しますから。」
慌てて二人が商売人の顔に戻ったのを見て、柳とチョウは簡単に礼を言って店を出た。
「柳さん、ネリマまでついてくる気ですか」しばらく並んで歩いてから、チョウが言った。
「まさか。この事件の捜査権は俺にはないからな。」
「分かっていれば良いんですけど。」
「俺はこの辺で失礼するよ。じゃ、まあ頑張りな。」
チョウは、長い間立ち止まったまま、雑踏に消えて行く柳を見送った。
柳が気を変えて戻ってくるのを、恐れているのか、期待しているのかは、自分でもよく分からなかった。
00210904ー1 「情報生命の為のアクアリウム」(ユーラシア大陸上空三万メートル)
高橋は、ジョエルのアシスタントスタッフである。
前大統領の下で、ジョエルが共和国警察に籍を置いていた時代からの部下でもあり、最近ではジョエルの名代で各方面に顔を出す機会も多いので、数人いるアシスタント達の中では政府内での知名度も高かった。
その高橋が、今は機上の人となってシベリア上空を飛んでいる。
ミュンヒェンにあるドイツ博物館へ向かい、カーペンター教授に会うためである。教授が最近発表した論文について、詳しい話を直接聞くのが目的だった。
ちょうどヨーロッパ州方面へ往復する共和国陸軍の高速輸送機があったので、急遽搭乗員に加えてもらい、予習は移動する機内で、たった今詰め込んでいる最中だった。
「情報力学的な場の折りたたみによる圧縮の可逆性或いは非可逆性」
「系の多重化と記憶空間の構造創発」
「力学系の自発的形成に伴う意味空間の成長と多次元検索について」
高橋は、教授の過去の論文を懸命に読み込み、彼を乗せた航空機が大気圏最上層を通過し、下降し始めるまでに、オシリスが興味をひかれたという、最新の論文にたどり着いていた。
「情報生命の為のアクアリウム」
なるほど、これまでの論文とは明らかに異質な、人目を引く題名であり、特に自身情報生命であるオシリスに看過されることは有り得ない題名でもあった。
内容的には、情報生命が自己を維持できる最小の情報力学場のサイズを特定しようという試みだった。
情報力学的な場とは、情報生命の振る舞いを解析する研究の中で提唱された、情報ネットワークの複雑さを表す指標の一種だった。ネットワークが全体として取り得る状態の種類と、ある状態から別の状態へ変化する為の時間、そして、その活動の活性を指標化したものであり、それが一定の水準を超えなければ、情報生命が存在できない、と言う事くらいは高橋でも知っていた。
とは言え、そこで取り扱われる高等数学は到底彼の手に負えるものではなかったし、この分野に精通している専門家は世界全体でも百人を越えないと言われている。高橋がこれから会おうとしているのは、その中でも最高峰の研究者の一人だった。
論文は、想像通りの難解さで、高橋は数学的な詳細を理解することは最初から諦めていたが、それでも読み通すのに相応の努力が必要だった。しかし、意外な事に、読後の印象は悪いものではなかった。それどころか、高橋は自分が率直に感銘を受けている事に気づき、驚いてさえいた。
殆どの天才的な思いつきがそうであるように、ここで展開されている内容も、基本となっているのは、余りにも当たり前でかえって思い付かないような問いかけだった。
曰く「どうして我々の人格が情報生命ではないと言えるのか。」
その疑問が、脳神経系のネットワーク、個人と言う単位が結びついた社会というネットワークについて、複雑な数式によって展開されていた。
従来、人類一個体の大脳が所有する情報について言えば、十の十五乗から十七乗のバイト数で記述が可能とされていた。高橋も、「あなたの人生全てを記憶できる」が宣伝文句の、ペタバイトオーバーの記憶領域をもつ携帯情報端末を何台か所有している。
しかし、そのサイズの閉じた情報力学系では、情報生命が存在できないことが実験的に確かめられていた。この事実は、自然生命と情報生命の間にギャップが存在する証明として広く認められていた。
よって、我々と彼等は違う。QED。
しかしながら、とカーペンター教授の論文は言うのだ。
そもそも、孤独な大脳一つがこの世界に存在したとして、それが人格を生み出すことがあり得るだろうか。
電磁波や化学反応によるインターフェースを持ち、外世界や他の大脳と情報のやりとりをすることで、初めてそこに人格が発生するのではないのか。
であるならば、大脳単体の情報量に、その外世界とのネットワークを含めなければ、人格を定義することは出来ないのではないか。
これを難問にするのは、音声や視覚情報のやりとりを情報ネットワークとして定量化する方法が存在していないことだった。事実、論文の大半は、この定量化に関わる試算と、その数学的技法の妥当性の証明に充てられていた。
いずれにしても、と高橋は考える。カーペンター教授との面談は、思ったよりも興味深い物になるかも知れない。
問題は、彼に数学以外の言葉で一般的な概念を説明させられるか、どうかだ。
数学を愛している人物に、それは無理な注文かも知れなかったが、高橋は敢えて楽観的に考えるよう努めていた。
輸送機は、フランクフルト共和国軍基地へ着陸しようとしていた。
00210904ー2 第三種接近遭遇(カフェテリア)
その日、最初に然世子の異変に気が付いたのは、白石咲子だった。
それは、いつもどおり朝のコーヒーを並べたトレイを手に部室へ入った時だった。彼女が扉を開けるのと同時に、室内から大きな物音と、然世子の短い悲鳴が聞こえたのだ。
「先輩」慌てて部室に飛び込んだ咲子は、床に仰向けに転がる然世子の醜態と鉢合わせした。
椅子ごと後ろにひっくり返ったらしい然世子の、ジーンズを履いた二本の脚が天井へ向けて高々と屹立している。
「せん、ぱい」助け起こそう近づきながら、咲子は笑いをかみ殺すのに必死だった。
「あはは」然世子の方も、取り繕いようもなく、力無く笑うのが精一杯だった。
次に異変に気が付いたのは、矢張りと言うべきか、茅だった。
「さよちゃん、昨夜は何時に寝たの」部室から、ホームルームへ歩く朝の廊下で、茅は明らかに然世子の目つきがおかしいのに気が付いて、心配そうに尋ねた。
「ん、多分一時間は寝たよ」先刻ぶつけた腰の痛みに顔をしかめながら、然世子は答えた。
「なんでまた。」
「メールを書いてて。」
「それで徹夜までしたわけ。」
先を行く然世子の歩が止まり、茅も立ち止まる。
不意に茅を振り返った然世子に顔は、今にも泣き出しそうに見えた。
「茅、あたしは駄目だ」そう言いながら、然世子は倒れ込むように茅にすがりつく。
「なに、どうしたのよ」突然のことに、狼狽えながらも茅は出来るだけ落ち着いた声で尋ねた。
結局、然世子の徹夜は、カスガノ=メグルへのメールに悩み抜いた末だった。書いては直し、直しては消して、また書き直し、を繰り返す内に、気が付けば夜も白々と明けようとしていたと言うのだ。
「呆れた」茅の偽らざる真情だった。
「だって、書いてて思ったんだけど、これって完全にあたし達の都合じゃない。あたし達の都合で、彼を利用しようって事じゃない。そしたら、もう、なんて書いて良いのか分からなくなっちゃって」然世子は懸命に訴えているが、睡眠不足でうまく言葉をまとめられていないことは一目瞭然だった。
「分かった、分かった」茅は呆れ顔を苦笑いに変えながらこう言うしかなかった「今日は、私も一緒に行ってあげるからね。」
そんなわけで、今、カフェテリアで、然世子と茅と、茅に呼び出されたメグルの三人が一つの丸テーブルを囲んでいた。
そして、最初の「どうも」から、すでに三分は沈黙が続いていた。
茅が、何度目かの小さな掣肘を然世子に入れる。
然世子も分かってはいるのだが、麻痺したように口がどうしても開かないのだ。
(どにかく入会してって正直に言えば良いのよ。ちがう、ちがう、その前に整備士の話から確かめなきゃ。でもそれじゃ、いかにも利己的よね。でも結局利己的な話なんだから、正直に言った方が良いのよ。でも、それで怒らせたらどうしよう。軽蔑されちゃうかも。でも、嘘をついてもしょうがないし。大体、嫌われたからって何なのよ。ああ、そろそろ変に思われてるよ。どうしよう。どうしよう。どうしよう・・・)
そんな思考が、彼女の脳裏で、すでに百回は繰り返されていた。無言の気まずい空気の中で、自分の鼓動だけがやたらに大きく聞こえる。
(あたし、どうすれば良いのよ。)
然世子はパニック寸前で、茅は匙を投げる寸前だった。
その時、思いも寄らぬ方向から、気まずい沈黙が破られた。
「おいおい、SF研究会は文化祭でサイボーグの展示でもするのか」
声の主は、昨日坂本と一緒に図書館にいた男子生徒の一人だった。「カスガノ君、気をつけた方がいい。こいつらは、文化祭に展示するつもりで無許可でサポートユニットを作ってたような連中だぜ。うっかり部品を盗まれるかも知れないからな。もっとも、サポートユニットの方は違法だって言うんで展示不許可にされたらしいから、この際、君自身を展示するつもりかもな。」
「・・・っさい」
男子生徒の言葉を、然世子の低い声が遮った。
男子生徒は、一瞬ギクリとして言葉を切ったが、再び喋り始める。
「とはいえ、見かけによらず手が早いな。全身サイボーグと聞いて早速勧誘とは恐れ入ったね。これで・・・」
「うるっさいわよっ」今度こそ、然世子の怒声がカフェテリアに響きわたり、男子生徒の口を塞いだ。
「どう言うつもりか知らないけど、今大事な話をしようとしてるくらい分かるでしょ。邪魔しないでよ」叫ぶようにそう言って、然世子は椅子から立ち上がり、相手を睨みつけた。
「なんだよ。キレんなよ」
「キレるわよっ。あんたにそんな事言われなくたって、あたしだって・・・」然世子は急に口ごもり、目を伏せた。
(わかってるわよ、そんな事)
カフェテラスにいた生徒たちは、無論、大分前から然世子たちのテーブルにそれとなく注意を払っていたのだが、然世子が大声を出したことで今や遠慮なく視線を注いでいる。
その全員が、一瞬然世子が泣き出すのかと思った。
「カスガノ君」一同の予想を裏切って、然世子は、顔を上げ、メグルを真っ直ぐ見ながら静かに口を開いた。「あたしたちSF研究会は、文化祭へ向けて、サポートユニットを作っていました。それは、SFを鑑賞するのに必要な、色々な物事に驚いたり、感動出来るセンスを磨くためだって、みんなそのつもりでやっていた事です。私たちは、勿論、色々なことに驚いたり、感動したりするけど、SFの素敵なところは、一見すると当たり前だったり、当然だと思っていることにも、感動することが出来るって、教えてくれることです。少なくとも、私たちは、そう感じている集まりです。」
メグルは、語り続ける然世子を真っ直ぐに見つめ返して、耳を傾けているように見えた。少なくとも、然世子は、そう信じることで辛うじて言葉を継いでいた。
「月は空にあって、浮かんでいるけど、それは異世界ではなくて、うんと遠くにあるけれど、私たちが今居るここと、地続きの世界。だから、特別な乗り物を工夫すれば、そこへたどり着くことが出来る。SFは、そう言う物語を語ることで、いつも見慣れているものの中に、驚きとか、感動を見つける方法を教えてくれる文学です。でも、本当にその驚きを感じる為には、月がうんと遠いって言うときの、その遠さを実感できる知識や、工夫の意味が理解できる経験が必要で、つまり、そんな勉強をしたり体験をしたりすることが必要だと思うんです。サポートユニットの制作は、今私たちに手が届く、一番高い目標だと思いました。」
その次の言葉を口にしようとする時、然世子は自分の血の気が引くのが分かった。耳鳴りのように聞こえる自分の心臓の鼓動に負けないように、手を握りしめて、精一杯の力を込めて、声を絞り出す。
「でも、それは法律違反だと言われて、中断させられています。もし、あなたの身近に、特殊精密機器整備士免許を持っている人がいるなら、私たちに力を貸してくれませんか。私たちに出来る限りのお礼はします。お願いします。」
最後は、叫ぶような言い方になっていた。
然世子が言うべき事を言い終わったのだと、確認するための三秒程の間を挟んで、メグルが口を開いた。
「あなたが今おっしゃったのは、拡大運輸法第八十七条に関する、運用規則百六十六号、身体を拡張または延長する機材を保有する場合の則に定められた第二種特殊精密機器整備士免許を持つ者の常駐、という条項を満たす為に私の助力が必要、と言うことですね。」
咄嗟に、その言葉の意味が分からず、目が点になった然世子に代わって、茅が力強く頷いた。
「そうですか。私がこの身体なので、私自身の整備の為に、身近に整備士がいることを想定されて依頼されたのだと思います。ですが、まず第一に、私のこの身体は、大半がタナカ情報力学研究所の機材で、個人の所有物ではないため、私個人の為の整備士はいません。」
その言葉に、失望を越えた、絶望に近い表情が然世子の顔に浮かんだ。
メグルは、気の毒そうな表情を作りながら続ける「私は研究所で生活することで、先程の運用規則の条件を満たしています。勿論、彼らには他にも管理すべき機材がありますから、こちらへ常駐させて、あなた方のサポートユニットの面倒まで見させることは、残念ですが、無理と言わざるを得ません。」
「ごめんなさい」消え入るような声で、然世子が呟いた。深々と頭を下げる。
「勝手なお願いで、付き合ってもらって。嫌な思いさせて。」
茅もため息を付いて、立ち上がる。
「ところで、第二に」二人が立ち去ろうとしていることに気が付いて、メグルは慌てて言葉を継いだ。「私は、私自身を整備することは許されていませんが、その他の必要があって、たまたま特殊精密機器の整備士免許を全ての種別について持っています。」
然世子と茅が、メグルの言葉の意味を飲み込むまで、たっぷり五秒以上かかった。
「ですから、そう言うことでしたら」メグルは胸ポケットからパスケースを取り出し、そこから、共和国政府発行の整備士免許証を出して見せながら続けた。「あなたがたのワークショップに私を参加させてもらえませんか。もしご迷惑でなければ。」
「だって、でも」然世子は、目の前のテーブルに置かれた整備士免許証を見つめながら、上手く言葉を継げずにいた。それが、今ここに存在していることが、現実だとは思えなかった。
「それは、SF研究会に入会してくれるってことですか。」
「ご迷惑ですか。」
「そんなこと。でも、うちに入っても、そりゃ、うちは有り難いけど、でもみんなこっちの都合で・・・」
「あなたが先程おっしゃった言葉に、感銘をうけたからです。ヴェルヌは素晴らしい作家です。私はウェルズも好きです。それに、誰が何と言おうと、クラークは旧世紀を代表する作家だと思っています。」
「私も、クラークは大好きです。」
「それなら、私の入会を認めてもらえますか。」
「はい。」
メグルは、にっこりと笑って、立ち上がり、手を差し出した。
然世子も慌てて、手を伸ばしかけたが、自分の掌が汗でびっしょり濡れていることに気が付いて、一瞬躊躇った。
メグルは気にせずその然世子の手を握りしめて言った。
「ありがとうございます。今日は用事があるので、明日の放課後から伺います。学校に来れるだけでも夢のような事だったのに、クラブにまで参加させてもらえるなんて。本当にありがとうございます。」
「はい。待ってます。」
何度か頭を下げながら、メグルがカフェテリアを出るまで、然世子は放心したように手を降り続けていた。
メグルの姿が消えるのを見届けると、倒れるように、然世子は椅子に崩れ落ちた。
The Hopeful Monsters (1)
あの、私が子供だった頃に、創作物の中で、世界は何度滅んだのでしょう。
最終戦争や天変地異と言った、あらゆる終末のバリエーションが、成長期の私に刷り込まれました。
この物語も、その慣習に従い、旧世界の終焉を背景にしていますが、未来を思い描くなら、そこには希望が欲しい、と言う当時の心境を反映した姿になっています。
高尚な絶望も、偏狭な楽観も、私には高級過ぎて扱えなかったのだと思います。

