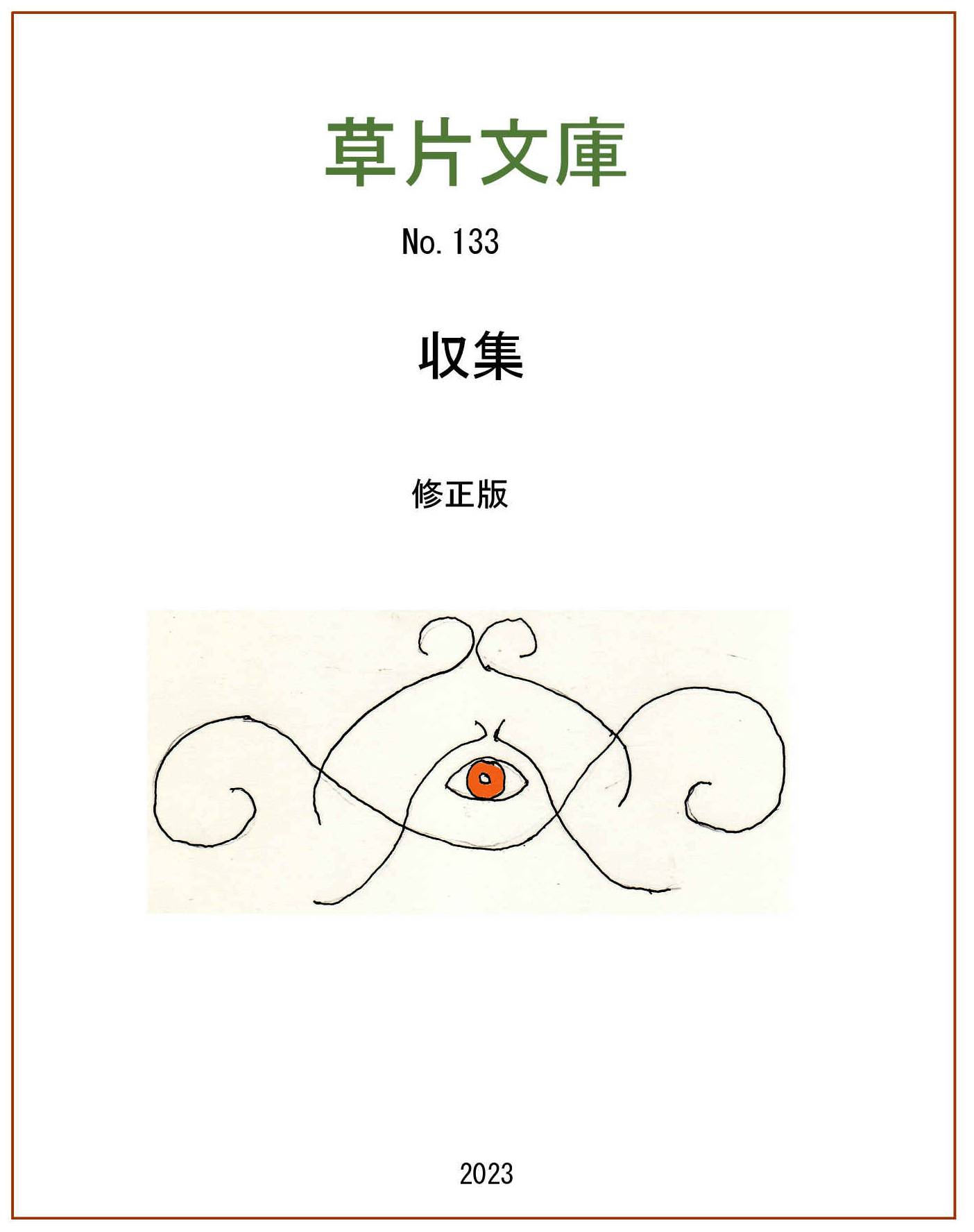
収集
ちょっと怖い話です。
知り合ったばかりの四人の男が自分の集めた物の話をしている。四人とも自分の持っている物を皆に見せたいのだが言い出せないでいる。
それは集めるということが個人的なものであることを自覚しているからだろう。というのも、四人とも違うことに興味があり、集めて楽しんでいる物が違っている。同じ物の収集家が集まれば、みせてほしい、と誰かがいうにきまっているし、見せようか、とも言い出しやすい。興味のない物をみせられても、集めたことへの賞賛をするくらいで、かならずしも集めた物を楽しくながめることができない。簡単な例として、二つの古いお酒の瓶がおいてある。ウイスキー古酒に興味を持っている人がみると、まったく同じラベルに見えるものでも、一本には「特級」と書いたラベルがあり、もう一本のものには書いていないことに大いに目を奪われる。ある時期まで酒税法で特級、一級、二級とクラスをわけ表示しなければいけなかった。二つの古酒は同じものでも作られた時代に相違がある。古酒の収集家はその二本を所有していることを自慢したいのだが、古書を集めている人間がみても、古酒収集家の気持ちはわかっても、その違いに感激をするわけではない。
ここに集まっているのは強すぎるほど物に愛着を持ち、好きな物を集め続けている男たちである。集まっているのは、文学者、生物学者、心理学者、それに社会学者である。実はこの四人、今、とあるテレビの番組で一緒に出演したことから知り合いになった。その番組は「知の収集」というタイトルで、四人ともそれなりに名の知れた研究者たちである。
番組の中では、自分の研究の端緒となったことや、研究を進めていく課程の話、新しいことを発見をしたときの感激などが話された。この中では研究に必要な資料、実験結果をいかに集めたかということに主眼が置かれた。
そのような研究の苦労話終わって、司会者がこんなことを言った。
「この番組の収集というは、調べて、または実験をして、得られた知識を元に、新たに研究を進め、そこで得られた新知識をもとに、さらにすすめ、と、新たな知識が、結果として集まるものですが、そういったことの最前線にいらっしゃる先生方にお集まりいただいたわけです。一方、生活の中で、個人に目を向けると、旅をしたり、専門とは関係ないことを追及したり、なにかを収集することに没頭する人がいます。好きになった物をわき目もふらず集めるということがいます。収集癖をもった方たちですね、今日お集まりの研究者の先生方は噂では、別のことに熱中していらっしゃる、特に物を集めていらっしゃるという噂を聞いてお集まりいただいています。そのところをこれからお話いただけますでしょうか。」
文学者が「たしかに、研究者の中には何かを集めている人がいますね、私の領域では、本が研究対象になっているので、好きな作家なり、ある年代のものだったり、本の収集家がいます」というと、司会者が「先生もやはり、本を集めていらっしゃいますか」と聞いた。
「本は研究に必要な物は買いますが、個人的な趣味としてはウイスキーボトル集めですね、古い本もいいですけど、古酒の瓶のラベルがとても好きで、集めています」
この人は英文学が専門で、確かにイギリスというとスコッチだろう。
「瓶を集めると置き場が大変じゃないですか」
「ええ、それでミニチュア瓶を集めてます」
ウイスキーばかりでなく、ワイン、ブランデーなど他の酒類でも、販売促進、試飲用に30ー50mlのミニチュア瓶もつくり、サービスにつけたする。今ではそれ自体も販売され、世界にはかなりのコレクターがいる。
「どうして、人間はそういうものを集めたがる人がいるのでしょうね」
司会者が心理学者に話しをふった。
「人間は生まれながらに、物を集める癖はありますね、子供の動きをみても、好きな色のおもちゃを手元に集めたり、動物の好きな子は動物のおもちゃ、絵本に出てきたり、自分の買っている猫や犬のおもちゃを集める、好きな物を手元に置いたりするところを見ると、身近に気にいったものを集めるということは子供のころからのものです、自分の目と手のとどく範囲に好きなものを置いておく、すぐに手で触れることができますから、それに他の人が自分の気に言っているものに触れると、嫌がったりします、とられるとおもうからでしょうね、ともかく好きなものは自分の物にしたいという欲望があるのは生まれつきのものでしょう」
「子供の頃から、集めることをするのですね、先生はなにかあつめていらっしゃいますか」
「本を読むことが多いのですが、やはり、特定の作家の本が好きですね」
心理学者は異常心理学の専門家で、今まで特異的な性犯罪の解決に寄与してきた。
「先生の専門で行くと、乱歩とか溝口などの推理小説ですか」
アナウンサーは一般の人が考える推測をした。
「うーん、いや、心理学、精神医学の専門用語になった、マルキドサドとマゾッホの著作を集めてます」
「あ、発禁本ですか」
司会者はそう短絡した。
「それもふくまれます、この二人の作家の著作は、フィクションですが、人間の一端が見えるのです、みなさんの心の奥深くにもあるものなんです」
「そういうものですか」
生物学者が口を開いたので、話ががらっとかわりもとに戻った。
「集めるという行動は、動物たちが生き延びるために本能の一つとして所有している大事な能力ですね。ドングリなどの木の実を冬の餌のない時期のために集めて隠すリスの行動は脳の中に生まれながらに組み込まれている命を保つための仕組みでしょう。
それだけじゃなくて、集めることは遺伝子を残しやすくするためにも役立っています、顕著な例は雄が雌をあつめてハーレムを作るトドなどはよく知られていますね、自分の子孫を安定的に残すために必要な行動として、やはり脳にその仕組みを発達させています。特に雄は」
「そのためですか、男性の方が収集家が多い気がしますね」
司会者が社会学者に話をふった。
「確かにね、収集家というので目立つのは男性ですな、それは今まではどの国でも男性優位の社会が築かれていったので、貨幣を用いるようになって、男が多くの金を使えるような社会だったから、男がめだったかもしれないですね、だけど、今はずいぶん女性でもコレクターがいますよ、貨幣制度とお金を稼ぐのは男という社会だったから目だったのでしょう、集めるということは必ずしも男だけではないですよ」
社会学者は社会制度と歴史が専門である。
「ところで、先生は何かを集めていらっしゃいますか」
「大それた収集家じゃないけど、コインを集めていますね、特に古代のコインですか、日本の硬貨の収集家はたくさんいるし、金貨ばかり集めている人がいますが、私はいまはない古代の国の貨幣などが好きでして、仕事で国外に行くと、探して購入してきました。まあ、研究にも関係してきます」
「それでで、研究室にかざってあるのですか」
「いえ、研究費で買うようなことはしていませんので、あくまでも趣味として、自宅にならべてあります」
「人では集めるという行為が必ずしも、生きることと子孫を残すことに直接つながらないわけですね」
司会者の問いに生物学者がまた口を開いた。
「そうですね、人になると個人個人の収集は癖という言葉でくくられるのでしょうね、集めることに喜びを感じている人に対して、収集癖があるということばを使う。他人に意味がない物を集めたりする、満足することで、気持ちが平らかになり、平和感がうまれ、その個人にとって、ストレスが減り、体まで正常になる。病気の予防にもなるわけです。大脳新皮質の発達に伴って、収集の意味もほかの動物とは異なるわけです、生きることや子孫存続に必要だった収集という行為は発達した脳の働きを正常に保つための行為になってきたわけです」
社会学者が口を開いた。
「いい面ばかりではありませんよ、過度に物を集めることで、個人の経済破綻、家族生活の破綻にまで追い込まれてしまうことがあります、ほしい物を盗んだり、だましてとったりする人間もあらわれる」
「そうですね、過度の収集はこまりますね、でも他人に迷惑をかけない収集癖であれば、その人は心安らかに平和になりますね」
司会者が時計を見た。
「おや、もう予定時間になってしまいます。今日は著名な研究者の先生方にお集まりいただいて、研究のデーターの収集の方法やご苦労されてきたことをお聞きしてきました。研究領域により、収集の仕方の違いがよくわかりました。それぞれに大変苦労な去った結果、まとめとしての著作ができあがっていくわけです。それに、先生方の息抜きとしての収集する物がおありのこともわかりました。今日はどうもありがとうございました」
これで収録はおわった。生物学者は自分の収集に関しては聞かれなかった。時間がきてしまったからできなかったのだ。
テレビ会社のロビーにでると、心理学者がほかの三人に「今日は面白い話ありがとうございました。どうでしょう、お近づきにどこかで、コーヒーか酒かちょっと飲みませんか。趣味の収集の話でもしませんか」と言った。みな始めて顔を合わせる人たちだった。
さすがに心理学者で、生物学者が自分の収集のことを聞かれなかったので、ストレスになってるのではないかと考えたのだ。実はほっとしているようでもあったのだが。
「いいですね」
最初に言ったのはウイスキーのミニチュアボトルを集めている英米文学者だった。ほかの三人もうなずいた。
「それじゃ、どうです、銀座にボトルをいれてあるところがありますが、つまみもなかなかいい物を出してくれます、ちょっと飲みませんか」
そういって、ビルの外にいたタクシーを指差した。
こうして、四人は銀座のはずれ、東銀座に近いところの、ちょっとしゃれたウイスキーパブにいった。
こじんまりとしているが、いい木を使ったカウンターをしつらえた落ち着いた店だ。
「先生、いらっしゃい、ちょっと古いディンプルが手にはいりました。これです」
四人が腰掛けると、カウンターの中の若いバーテンが、文学者に棚からウイスキーのミニボトルをわたした。黒くなった金網のかかった三角形のボトルである。それを手に取った文学者が目を輝かした。ラベルは薄汚れはがれかかっている。
ほかの三人は、それがイギリスのディンプルまたはピンチと呼ばれる有名なウイスキーのミニチュアなことはわかった。
「Dimple scots、とあるじゃないか、こりゃ古いものだよ、高かったんじゃないかな」
「ええ、二万しました、もしよろしければそれでおゆずりしますよ」
「もらいます、五万だっていい、こんなめずらしいものが手にはいるとは、今日は私がおごります、マスター勘定に一緒につけといて」
「はい、わかりました」
「英国の古いウイスキー会社、ヘイグの作った傑作ですよ、三角のでこぼこの瓶はエクボ、ディンプルとよばれ、アメリカではつねったようなので、ピンチと呼ばれたんです、ティンキャップがとれないように、金網が張ってあるんです。ミニボトルで金網があるのも珍しいのですけど、ほらみてください、scotsとかいてあります。今はscotchとかくでしょう」
「スコットランドのといういみではないのですか」
心理学者がたずねた。
「そう言う意味ですけど、スコットランドまたはスコットランド人、その中でもスコッツは民族意識の強い表現ですね、Scotsというゲールからきた民族です、デインプルのヘイグ社を始めたヘイグの祖先はゲールから5世紀にやってきた人で、ゲール族ということなんでしょうな、だからこの一本はかなり古い時期に日本に入ってきたものでしょう、今までこう書いてあるディンプルはみたことがない」
「かぶせてある金網も真っ黒だし、残っている中身もずいぶん黒っぽくなってますね」
生物学者の観察である。
「いや、こんな物が手にはいるとは思っていませんでした、感激ですな」
サドやブロッホの著書を集めている心理学者もうなずいた。
「わかりますよ、その気持ち、僕もある有名な人が持っていた、サドの直筆の手紙を手に入れたときには躍り上がって喜んだ」
「そうですね、僕はポンペイの遺跡を見学したときに、偶然拾ったものが、古代ローマの貨幣だった。もってきちゃいましたよ、昔ですけどね、それが集める引き金になった」
社会学者もうなずいた。
自分のコレクションに珍しい物が手には入ったときの感激は収集癖の強くない人でも嬉しいものであろう。
「ところで、今日の座談会面白かったですね、みなさん苦労の仕方が違うが、楽しく苦労していらっしゃる、僕もですよ」
文学者のことばにみなうなずいた。
「司会者は悪くなかったが、生物の先生への趣味の収集の質問時間がなくなってしまって残念でしたな、先生はなにを集めていらっしゃるのですか」
白髪の混じった前髪を長くたらし、目が弱くなっているのでサングラスをかけている生物学者が「いやいや、たいしたものではなくて」と笑顔で右手を振った。謙遜であるのか、本当なのか。
「生物学だからやっぱり昆虫ですか」
心理学者が話をつなげた。
「いえ、子供の頃は魚をあつめていましたが、今集めているのは、まったく自然の物ではありません」
「それじゃ、焼き物、動物をかたどった」
社会学者が想像した。
「いえ、箱なんです」
生物学者の返答にみな驚かなかった。文学者はたばこの空箱を思い、心理学者はジュエリーボックスを想像し、社会学者は箱根寄せ木細工のからくりボックスを思った。
「どんな箱なんです」
文学者が聞いた。
「結構大きいんです」
「大きい物を集めるのは場所がいるのに大変でしょう」
「高尾山に山荘がありまして、そこに飾ってあります」
「興味がそそられますな、是非みたいですな」
文学者は大乗気である。
「いや、きっとがっかりされるし」
生物学者はそう言っただが、心理学者は
「行ってみたいです、どんなものか知りたいし」
というと、三人とも「お願いしますよ」と酒の入った口調で生物学者につめよった。
「明日は土曜日で用事はなにもないんですよ」
文学者が言うと、二人もうなずいた。
生物学者はあまり嬉しそうな様子ではなかったが、
「それじゃあ、いらっしゃいますか」と三人に言った。
「そりゃうれしい、どんな物が見られるのか、そのときまで、おあずけですな」
「今まで、だれにも見せたことがないんです」
「密やかな楽しみですな」
「集めることにご理解のある先生方ならお見せします、ただ、このことはご家族には言わないでいただきたい、明日、私が車でお連れします、それとかまわなければ、集められている物の中で一番のお気に入りをお持ちくださって、お話の種にしていただけると、目の保養にもなります」
「そりゃあ、いいね、私も大事な物をもっていきますよ」
三人は京王線高尾山口で生物学者の車を待つことにした。
文学者、心理学者、社会学者が高尾山口の駅前ロータリーで待っていると、大きな四角い黒塗りの車が止まった。見ていると、運転席が開いて、降りてきたのは生物学者であった。片手をあげて「お待たせしました」とおじぎをした。
古い車だ。もしかすると箱型の車の収集家と三人は思った。
生物学者が後ろのドアを開けると、三人はとても驚いた。一つは後ろの席は、余裕を持って三人が座れるほど広いこと、シートが総革張りであること。地味だがとても洒落た車なのだ。三人は顔を見合わせながら車にのりこんだ。
「先生、すごい車ですね」
「ええ、箱型の車です、イギリスの車を改造したものです」
「これも箱のコレクションですか」
「まあ、箱が趣味ですから、家はここから20分ほどです、でこぼこ道ですみません」
「驚きましたな」
社会学者のつぶやきに、二人がうなずいた。
街中をぬけると、車は細い山道に入り、しばらく行くと、驚くほど大きな洋館が現れた。ヨーロッパ風でもあるが、アメリカの要素も入っている木でできた、簡素とも言える形の家である。三人は箱のようだと思った。車はその洋館の玄関前に止まった。コフィン館と墨で書かれた板が玄関の上に張り付けられている。
三人はこれを見てびっくりした。この生物学者はなんて金持ちなんだろうという、一致した思いである。
三人が降りると、生物学者は玄関の重厚な木製の戸に、大きな鍵を差し込んでまわし、押し開けた。家の中は広い玄関と、それに続く広い部屋になっていた。
「いや、遠いところをよくいらっしゃいました」
「先生すばらしい家をおもちですな、ここから大学までかよってらっしゃるのですか」
「いえ、ここには週末しかきません」
「それじゃ、今日は土曜ですから、ご家族がいらっしゃるのですか」
「いえ、私独身です」
「そりゃ失礼しました」
玄関をあがると、目の前に、かなり昔のものと思われる石棺が、わざわざしつらえたと思える重厚な木の台にのっている。
三人は棺であることはすぐわかったが、なぜここに飾ってあるのかはわからなかった。
「先生、これは」
社会学者が聞いた。
「これは作り物で、ご存じでしょう、古い映画ですが、ロミオとジュリエットは1936年にアメリカで白黒映画になりましたが、1954年にはイギリスで初めてカラー映画として作られました。監督はレナート、カステラーニなんですけど、そのとき使われたものです」
「映画も趣味でいらっしゃる」
文学者が驚いている。
「箱を集めているって、もしかすると、棺ですか」
心理学者は仕事柄、勘がいい。
「はい、棺を集めています。箱型だけじゃなくて、桶もあります、壷もあります、しかし、やはり箱型が中心です」
生物学者はちょっぴりはずかしそうにしている。
文学者は入り口の「コフィン館」の札の意味が、集めているものそのものだったのだとやっと気がついた。すぐ気がつくべきだったと反省した。コフィンは棺の英語である。
「何で棺を集めたのですかな」
社会学者には変な収集家としか考えられなかった。
「まあ、ちょっと部屋の方でお話ししましょう」
生物学者は三人を客間に案内した。広い部屋には真ん中に絨毯が敷かれ、木製のテーブルと椅子があった。一方の壁は棚になっており、標本瓶が並んでいる。みると、どれもが魚の標本だ。フグのようである。生物学者の専門はフグの毒の解析で、最近それが薬になることがわかって有名になった。
紅茶とチョコレート用意されていた。
「昔からのお家ですか」
「いえ、とんでもない、おやじは地方の市役所の役人でしたから」
「だけどこんなすごい家」
「しがない大学教員、とてもこんな家建てられるわけはないですよ」
「しかし、ここにありますな」
「白状しますとね、十年前に宝くじが当たりましてね、この家を建て、箱の収集展示を始めたのです」
「この部屋の魚はフグですね、先生の研究材料でしたな、座談会でそう言っておられた」
「そうです、世界の箱フグの標本です、子供の頃、浜に打ち上げられている、干からびた四角い魚を拾ってなんだろうと家に持って帰り、調べたら箱フグだった。それからフグ毒のことを知り、研究の道にはいったんです、箱フグは骨の箱に覆われているんですよ、英語でボックスフィッシュですからね、ある詩人が、箱フグは死んでから入る自分の棺をいつも背負って生きている、と書いていたのを読んだことから、棺に興味を持ちました。ジュリエットが本当に毒を飲んで死んでしまい、棺に入ているシーンが映画にあって、英国の古道具屋に頼んでおいて、やっと見つけたのが玄関にある棺です」
三人は納得いったが、やはり棺を集めるということには首を傾げるばかりである。
「この家は公開しているのですか」
「まさか」
生物学者の一言である。
「みなさんの収集品を見せていただく前に、集めた棺をごらんになってください」
生物学者が立ち上がった。
「荷物は、ここにおいておいても大丈夫ですよ、最も大切なものですからお持ちになってもかまいません」
と生物学者がいったのだが、誰一人そこに荷物をおかなかった。三人とも荷物を持ったまま立ち上がった。一番大事なコレクションが入っている鞄である
一階も二階も十の展示室がある。それを見て回ることとなった。
「ごらんになって、一番お好きな棺があったら教えてください、収集の参考にします」
それぞれの部屋にはテーマがあった。日本の札がある部屋には江戸時代の墓場から掘り出された、崩れかけている大名の棺、町民の棺桶などが並べられている。
「これはどうやって手に入れるのです」
「歴史学者や民俗学者による発掘調査が行われています。最近では江戸時代屋敷あとの発掘がさかんです。出てきたものは調査をした後、展示するもの盛りますが、かなりのもの捨てられます。そういった物をもらったり買ったりします」
「ここにあるのは、ずいぶん立派な棺桶ですね汚れていない、再現したものですか」
まるで、西洋の磨かれた家具のような木の肌をもった棺桶である。
「いえ、本物です、ある大名家の末裔の家の倉に残っていたものです。その大名家の主が自分の為に、とても豪華な棺桶を用意させ、使われなかった物が残っていたのです、クルミの木を使っていますから、何となく西洋風に見えます。これを燃やしてしまうのはもったいないですね」
「その主人は別の棺桶をつかったのですね」
「末裔の方が、黒柿で作られた棺桶を使ったという記録があるということをいっていました、黒柿の方がずっと高価ですね」
「私はこの棺がきにいりましたな」
英米文学の先生が言った。
ヨーロッパのフランスの部屋では宝石がちりばめられている、古い石棺が飾ってある。
「向こうでは棺桶は燃やさないので、こう言う装飾をつけたのでしょうね」
「でも一般家庭では土葬でしょう、高貴な家じゃないとこういうものは使えなかったでしょうね」
「そうですね、これはフランスのルアンで購入したものです、どこの城からでたのかわかりませんでした、おそらく盗品でしょう、この蓋にはめ込まれているのは本物のルビーではなくてガラスです、今のものじゃない、当時としては高価なものですね」
「僕はこの棺がいいな」
サドとマゾッホの本を集めている心理学者はそう言った。
中東の部屋にはエジプトで盗掘されたミイラのはいっていた棺などがいくつもあった。
「ピラミッドが正式に調査されるようになる前には、盗人たちがミイラを薬にするために掘り返し、金目の物はみんなもっていって、ヨーロッパに売りさばいてしまったんです、そういった物が、流れ流れて、私の手になったということです」
「石棺はもっていかなかったわけですな」
「そうですね、ふたは壊されている物が大部分です、蓋が壊れていないものを探して買いました。エジプトだけではありません、インドの王家の血筋の家に、タージマハールのように、白大理石でできているものがあったので買い求めました」
「高かったでしょう」
「そうですね、没落貴族で、お金を必要としていて、希望の額より高く買ってあげたら喜びました」
「入るのなら、こういう棺もいいですな」
コインを集めている社会学者は気に入ったようだ。
十の部屋の棺を見て回ると、さすがに三人の先生方も疲れてきたようだ。
生物学者はそれに気がつき、「どうです、むこうで、一休み、お昼にしませんか、みなさん夜はご家族とお食事でしょうから、お昼にちょっと豪華な物を召し上がっていただこうと思って、珍しい料理おだしますよ、お酒もお好きな物をどうぞ、先生方の大事なコレクションを見ながらどうです」
三人は棺から解放されるのを少しばかり喜んだ。
案内されたのは地下の一室である。
「地下室もあるのですね」
「ええ、晩餐用の大広間があります」
降りていくと、客間の倍もあろう大きな木のテーブルの上に食事の用意ができていた。
「どうぞ、お好きなところにお座りください」
「お飲物はどうなさいます、のどがおかわきなら、地ビールが冷えてます」
「そうですな、まずビールをいただきましょうか」
文学者の声で、生物学者はピッチャーを持って回り、ビールをそれぞれのグラスに注いだ」
「どうぞ、今日は僕のコレクションを見ていただいてありがとうございました」
生物学者が乾杯の音頭をとった。おいしいビールだ。つまみに干したフグがでてきた。
「先生方のコレクションを見せていただきましょうか」
三人の先生が鞄の中からコレクションを大事そうに取り出し、テーブルの上に載せた。
「これは、ムンローのキングオブキングスのミニチュア瓶です、この王の横顔のマークのミニチュア瓶は世界でもほとんどないでしょうな」
文学者が陶器の小さなウイスキー瓶をだした。よく知られているウイスキーだ。
心理学者がテーブルの上に一冊の本と、帖にはいった原稿らしきものを広げた。
「サドが牢獄で書いたソドム百二十日あるいは閨蕩学校、1785年の初版、それにレオポルト・フォン・ザッハ、すなわちブロッホの毛皮をきたビーナス1871年原稿です」
サドの翻訳者で著名な渋澤龍彦やブロッホの翻訳者である種村季弘もこれを見たら目を輝かせるだろう。
「私はもうお話ししたイアリアの古いコインを十種類もってきました」
コイン帳のリーフを取り出した社会学者はどこででたものかを説明した。
お互いに交換しあってじっくり眺めた。三人とも他の人の集めた物には興味をもったがやはり心に響くようなものではない。生物学者も集める人の気持ちはよくわかった。だが、三人には生物学者の箱のコレクション、棺の面白さはわからなかったようだ。
文学者が「棺のコレクターというのは他にもいるものですかな」と生物学者に尋ねた。
「聴いたことがないですね、だけど、死んだ人が入るための箱というのは魅力があります」
三人はうんうんと一見、興味がありそうにうなずいた。
「箱というとオルゴールを集めている人もいますが、あれはいいものです」
心理学者のことばに社会学者もうなずいた。
「ジュエリーボックスもきれいなものです、コレクターがたくさんいる」
「先生はここを公開して、棺のミュージアムにするといいですな、高尾山の名所になりますぞ」
社会学者のいったことに、生物学者は苦笑しながら、首を横に振った。
社会学者が「棺に興味を持つ人はよほど歴史を知っていたり、小説を読んでいた人でしょうな」
と生物学者をみた。
「そうですね、だから、自分だけで楽しんでいます」
生物学者はにこやかだが、この議論は嬉しくないようだ。
「まあ、コレクションは個人のものですから、他人からどうのこうのと言うものじゃないでしょう」
生物学者がそういうと文学者は
「おっしゃるとおりかもしれません、同じ収集仲間と見せ合う楽しみもありますが、競うことは苦しみもありますからな」とちょっと批判めいた口調だった。
心理学者が見かねたように
「いや、生物の先生がおっしゃるように、研究と同じで、興味は人によって違いますからな」と援護したつもりだったが、生物学者は棺のコレクションなんて面白くないとはっきりいわれているような気がした。
いきなり、生物学者がたちあがった。目が少し怒っているようでもある。
「私がつくった、箱フグのつまみをもってきますのでお待ちください、うまいですよ」
と奥にはいっていった。
三人はなんとなくきまずくなっていると、生物学者は、おぼんに三つの皿を乗せて持ってきた。
皿の上には箱フグがのっている。目の前に出された箱フグは背中が開かれ、具が詰められている。
生物学者がにこにこしているので、三人はちょっと安堵したようだ。
「これは、箱フグの料理で、味噌焼きです。長崎の五島列島などでよく食べられているもので「かっとっぽ」と呼ばれます。箱フグは本当はとてもうまいフグで、これは身に味噌と薬味をまぜたもので、僕が調理したものです、ビールにも合いますが、日本酒でもウイスキーでもなんでもいいですよ、お好きなお酒をもってきますよ」
文学者はウイスキーを、心理学者はワインを、社会学者は焼酎を頼んだ。
生物学者が奥からワゴンに乗せてそれらの酒をはこんできた。
それぞれの前に置くと、自分はビールで乾杯をした。
「箱フグには毒はないのですか」
文学者が箸をもって恐る恐るたずねた。
「あります、ふつうのフグ毒はテトロドトキシンで、卵巣にあり、それをとれば問題ないのですが、箱フグの毒はパリトキシンという毒で肉にも含まれます。ただテトロドトキシンほどではありません、死ぬほどの毒ではありません、だから、かっとっぽ、という地元の珍味として食べられているのです、僕が使った箱フグは大丈夫ですよ」
心理学者はかっとっぽを口に入れた。
「おお、うまい、先生は料理もされる、それはすごい」
「たしかに、棺のコレクション以上にすばらしい」
社会学者が、思わずそんなことを言ってしまった。生物学者の顔が少しばかり白っぽくなった。だが、三人はかっとっぽを食べていて気がつかなかった。
「箱フグの刺身がまたうまいので、ぜひ食べてみてください」
奥に行った生物学者はまたビールと刺身をそれぞれの前においた。
三人は箱フグの味噌焼きに舌鼓を打ち、ウイスキーやら焼酎やらを楽しんで、ビールで刺身をつついた。
食べ終わると、部屋の壁際にあるソファーをすすめられた、三人の前に食後酒のはいったグラスがおかれた。
「私が作った箱フグひれ酒です」
三人はこれは珍しいとおもったのだろう、すぐ手をのばして口にした。
「お、うまい」
そう言った心理学者が、がくっと首をたれた。すぐにほかの二人も首を脇にたらした。三人とも目はまっしろである。
「箱フグは棺を背負って生きているんだよ、棺に行く準備をしてくれるフグなんだ」
生物学者は淡々と独り言をつぶやいた。
「好きな棺ににいれてあげますから」
首を垂れた目が真っ白な三人を見た。
生物学者は文学者の死体を、もってきた小型のストレチャーにのせ二階の江戸時代の部屋に連れて行った。クルミの木でできた棺の蓋をあけると、文学者をその中に横たえた。彼の持っていた鞄からキングオブキングのミニチュアボトルを取り出すと両手に持たした。隙間を少し開けて蓋をした。
次に心理学者をヨーロッパの部屋に運び、イギリスの王族の石棺に横たえた。胸の上にサドとマゾッホの著作を載せ、両手をその上に乗せた。三人目の社会学者はエジプトの石棺にいれ、コインを胸の上に載せやはり両手をその上に乗せた。蓋を少しずらした。
生物学者はエアコンを操作し、それぞれの部屋の温度を5度に設定した。さらに除湿のスイッチもいれた。
生物学者は部屋から出ると、一月でミイラになるだろう、と一息をついた。
「おれのフグ毒はよくきく」
一週間後、三つの棺の蓋を開け、「まあまあ、うまくできている、あと三週間だ」と笑った。中にはミイラになりかけの三人が服を着たまま横になっていた。胸の上には一番大事なコレクションをかかえて。
「集めたものを人に見せるなんてコレクターじゃない、密かに自分で楽しむもんなんだ」
生物学者が独り言を言った。
これからも集めた棺にミイラをいれるつもりである。
やはり死人が入っている棺のほうがいい。
収集


