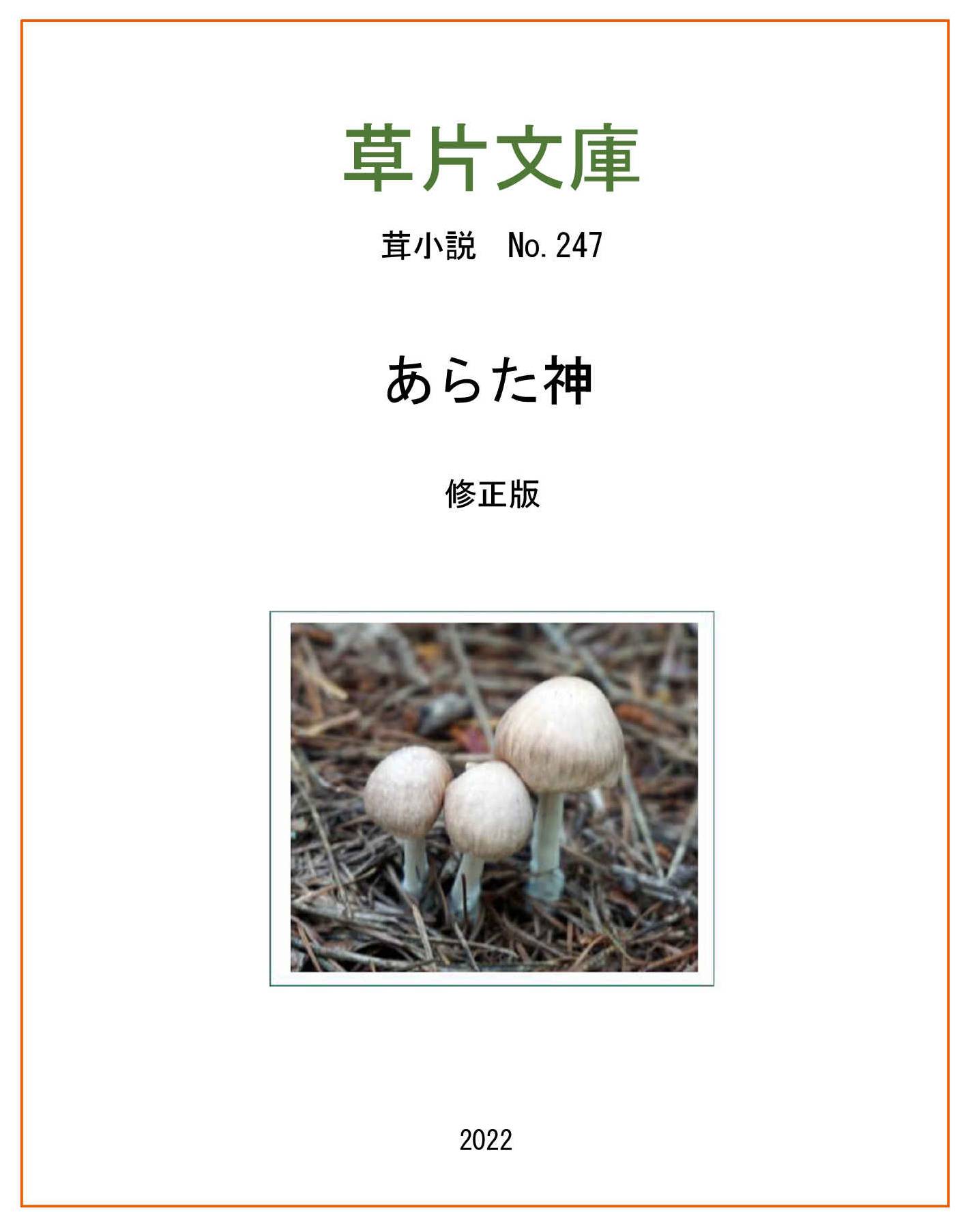
あらた神
茸伝承小説です。
人間には支えが必要である。生きるために、ということは、体を維持するために、水と血肉を作る栄養がいる。それを得るために狩りをし、野原で食草をつみ、実をとり、森で茸を採り生きてきた。
現代では会社など組織の中で働くことで、代価として報酬をもらい、報酬である金で体を維持するための食料を買う。そういった社会の中で、頼りにするのは会社であり、社会を運営する人たちということになってしまう。裏切られることはままある。
一方、人間は体が維持できれば満足するかというとそういう動物にはならなかった。言葉を持って考えることができるようになった人間に、安心を与えるのは食料をくれる組織だけではなく、もっと強い、気持ち、心と言い換えることもできるが、を支えるものが必要になった。信じるものが必要であった。宗教が発達したわけである。大脳新皮質の発達した人間にもっとも必要とされた安心感である。自分を信じればそれでいいという人はいないことはない。だが、多くの人間は宗教に支えられている。
世界をながめると、宗教は数限りなくある。山をあがめる、海をあがめる、そういった原始的な宗教心はだれにでもある。ある意味では人間の本能の一つかもしれない。やがて本能である「あがめ」から、自分の安心を得ることを覚えた人の心をつかむ者がでてきた。それは集団となり、組織として発達してきて、救いも問題もたくさんある宗教というものになっていったのだろう。
現代の日本ですら、政府に登録された宗教法人なる者が二万弱あるという。その組織は信者の寄付によって運営され、その長や組織を維持する人が、一つの組織に平均して何人いるか計算したこともないが、たとえば三人いるとして、六万人は信者が体を動かし稼いだものを寄進してもらうことにより生きていることになる。
大学で宗教学を学んだその男は、大学院には行かずに、高校の教師になった。社会学を教えながら、じっくりと、その地方の宗教を調べてみたいと思っていたからである。
九州出身の男が選んだのは寒い地方の公立高校である。さすがに一年目には自分が雪と地域に慣れることで精一杯だった。仕事では、講義のノートづくりや、高校生との付き合いに時間がとられ、その地方の宗教についての探求を始めることができなかった。
二年目になってもその地方の人たちの、風習、考え方などは男の頭の中には整理されていなかった。どのような宗教観をもっているか、それは、その土地が作り上げるものだろう。そう思っていた男は、土地の人たちの集まりには極力参加し、観察し、知ろうと努力していた。
高校の社会クラブの顧問にもなって、生徒とともにその地方にたくさん見られる縄文人の生活跡などの調査や、地理の調査にいった。宗教に関心を示す高校生はいなかったが、一緒に歩き回った男にはそのあたりの昔の人の暮らしぶりが少しはわかるようになってきた。三年目に入ってようやくスタート地点に立てたと男は思った。
農業に従事する家が多いその町の人たちは、自然に対する恐れとともに、多大な敬意を払っていることが感じられた。おそらく日本だけではなく世界のどの国でも作物を作る人たちは同じだろう。
米の収穫、畑の野菜、すべてお天道様、雨や川からの水の恵み、土からの養分のおかげである。ただ、この町の人たちには、農業に従事する人ばかりではなく、市役所に勤める人、町の商店街の人、工場の人たちの意識の中に、他と少しばかり違う面が見られた。
酒、味噌、醤油、納豆、さらにはチーズなどなどの生産が盛んな地域では、菌の発酵の働きのすごさを知っていることもあり、そういうところの人たちは菌のことをよく知っているものである。
男が赴任した町でも、酒をはじめ味噌醤油は通に好まれる物が多く、通信販売では全国に購入者がいた。ただ不思議なのは、この町の発酵食品に従事する人たちに、雑菌に強い拒否感がないことであった。自分の生まれた九州の町では酒が有名だった。友達の家も作り酒屋だったが、雑菌が入ることを嫌っていたことを覚えている。
酒に雑菌がはいれば製品にならない。ましてやカビが生えれば大変である。余計なものが樽などにはいらないように気を使うことは大変なことだった。
この町は、意外とからっとした気候のためもあるのかもしれないが、他のところのような雑菌に対する神経質な気遣いがあまりみられない。
そんなことを、町の作り酒屋に聞いてみたが、店主から
「そりゃあ、気は使ってますよ、だけど、あらた神の入り口をふさいじゃ、いけないしね」
という答えが返ってきた。
「新の神様ってどのような神様ですか」
男はこの町独特の宗教の糸口が見えてきたと思った。
「目に見えない神様でね」
神というのは目に見えないのが普通だが、何か意味があるのだろうか。
「いつ頃から、その神様のことをあがめるようになったのですか」
「いや、あがめるなんて大げさなものじゃないけど、ほら、神棚を見てくださいよ」
酒屋の神棚には黒くすすけた板に天照大神様とある。氏神さまの総元締めだ。どこ家の神棚にもある。家を守るわけである。その脇には新神(あらたがみ)様と書いた板があった。日に焼けて茶色にくすんでいる。
「百五十年も昔のもんですな」
「新神がはいるというのはどういう意味ですか」
「むかし、酒ばかりじゃないが、味噌造りでも、樽の蓋をちょっとあげておくと、新神がはいって、それまでとは違った、うまい味にしてくれるという言い伝えがありましてな」
それでは雑菌を呼び込むようなものだ。
「うちのことじゃないんですがね、その昔、ある家で味噌を樽二つほど仕込んでおいたら、一つはいつものようにそれなりにうまい味噌だったのだけど、もう一つは、それは不思議な味の味噌になっていたそうなんですよ、その味噌は旨いだけじゃなく、それで作った味噌汁にしろ、ぬか味噌漬けにしろ、食べるととても元気が出ましてな、どうしてか後に調べたところ、その味噌の樽の蓋が割れていたそうで、神様が割れたところからはいって、うまくしてくれたという話になったということです」
「おもしろい話ですね」
「新神はこのあたりだけですけどね」
この作り酒屋の主人の話から、教師になった男は新神の存在を知って、これこそが自分がもとめていた、地域の宗教のめばえだと、研究心を燃やし始めた。
町に住んでいる高校生たちも新神について知っていた。隣町など他から通ってくる生徒は半数ほど知っているだけだった。それを知っていたこの町以外の生徒の大半は親や祖先がこの町の出身だった。
男は生徒たちに、新神のことを親や祖父母に聞いてくれるように頼んだ。
そういった働きかけをつづけていくと、その返事が集まり始めた。結果としては、男が直接町の老人たちから聞き出したことも、生徒たちが聞いてきてくれたことも、ほぼ同じで、新神は名前の通り、新しいものを授けてくれるというものだった。農家の家では新神ではなく、新田神と書くところがかなりあった。田圃が増えるように、また、新種の稲が生えますようにと神を祀っているという。
一人の生徒がおもしろいことを書いてきてくれた。その父親は市役所に勤めており、今は林業から離れているが、曾祖父の時代には茸の栽培や味噌造りをしていたという家であった。
曾祖父は江戸生まれで明治に亡くなった人だという。その曾祖父が書き残したものの中に椎茸の栽培について記載があった。
古くなり、使えなくなって積んでおいたほだぎから、おかしな形の茸が生えていた。
曾祖父が自宅用に作っていた味噌樽からもその茸が生えていて、味噌がだめになったかと蓋をあけてみると、いい香りがしてきた。味噌をちょっとなめてみると、とても美味い味噌になっていた。という話だった。余りにも美味いので、茸栽培から味噌屋になってしまったという話だった。
その文書を見せてもらったが、細かなことがかいてはなかった。日記風の物にすぎなかったので、どのような茸だったのかもわからなかったが、茸が新神を運んできた。と一言書いてあった。
ということは、そのころすでに新神という信仰があったということなのだろう。興味深いことである。
ある土曜日の午後、数人の社会科クラブの生徒とともに、大昔、炭焼きが行われていた場所を調べに行った。今ではほとんど行われていない。
炭焼き小屋のあったところはかなりの山奥である。といっても、町から歩いて一時間ほどだろう。すでに炭焼きの窯や建物などはなく草原になっている。盛り上がっている土塊が草原のなかにあるが、炭焼き釜の崩れたあとだろう。そういった場所の草を少しばかり引き抜くと土の中に炭の小片が混じっている。
現在炭焼きあとは三カ所ほどはっきりしている。どれも、高校の社会部が見つけたところで、その調査は、炭焼き小屋チームと呼ばれる後輩たちに受け継がれ今になっている。
新任の男より炭焼き小屋チームの生徒たちの方が炭焼きには詳しく、生徒たちに教わりながら山道をのぼっていった。道の斜面下に小さな流れがあり木陰から見える。そういった山の道を歩くだけでも気持ちのよいところである。
炭焼きの小屋のあったところまであと半分というところまでくると、山の斜面の木々の中に小さな小屋のようなものが見えた。草で隠れていてよく見えないが、古いもののようだ。
男は隣を歩いていた女生徒に「あれ、焼いた炭をおいておくところじゃないの」ときいた。
「ちがうよ、炭焼きは大昔だから、小屋なんて残っていない、あれは、じいちゃんが見ちゃなんええ、っていってたよ、安産を祈るとこだって」
その女性徒の家は代々米屋を営んでいる。九十になるおじいさんがいるという。安産祈願はどこでも見られる風習である。男はのぞいてみたかったのだが、その日は、生徒の目的である炭焼き跡の調査に直行した。
炭焼きのあとは山の斜面の木々に囲まれた小さな草原になっていた。大昔といっても江戸時代ぐらいだろうから、三、四百年も前のことだろう。生徒たちは新たなところを見つけようと調査範囲を広げていた。そういったところを掘ると、炭焼きたちが使った湯飲みや酒の徳利なども埋まっていたりする。その当時の炭焼きたちの生活を知るにはだいじなものである。生徒たちは、縄文あとなどを調べる学者の気分になって、炭焼きのあとを調べている。考古学に興味を持つ人間をそだてるにはとてもよいトレーニングの場所でもある。
次の日の日曜日、男はもう一度同じ道を歩いた。安産祈願の小屋を見たかった。
草を踏みながら、林の中を上って見ると、朽ち始めているが、木の開き戸のある小さな小屋であった。小屋の中に石でできた像が立っている。お地蔵さんのようだが、地蔵なら見ていけないわけはない。
壊れている戸を持ち上げながら開くと、中には石でできていた陽物が大小五つほどならんでいた。陽物信仰だ。それで見るものじゃないよと、女高生は言われたのだ
陽物信仰はアジアにはよくある。韓国で盛んだったようだが、日本にもいろいろなところにあった。男も学生時代歩いた地方でたまに見かけた。別段珍しいものでもない。
女性徒のおじいさんにゆわれを聞いて見るのが一番いい。写真を撮りながら、石像に字が彫られていないかくまなく探したが、みつからなかった。だいぶ崩れているので、かなり古くに作られたものであろうことは想像できた。今まで見てきたものから類推すると、二、三百年近くは経っているのではないだろうか。
小屋の周りには白い小さな茸がぽちぽちと生えているくらいで、特に珍しい物をみつけることはできなかった。あまり大事にされていない。ということは、今これを信仰している人はいないかもしれない。
その後、男は社会部のその女生徒の祖父と会うことになった。
「あんたさん、あれ見ましたか、若い頃、わしらは春になれば山菜取り、秋になると茸とりを楽しみにしておりましてな、仲間とあのあたりを通って山の奥にいったもんですわ、ある時、仲間の一人がしょんべんをしたくなって、道から外れて林の中にちょっと入ったんです、そいつが、なんかあるぞ、って叫んだものだから、俺たちも行ってみると、道の近くの木の下に、石像が五つ立っていましてな、そいつは男のあれの形のようにも見えたし、茸のようにも見えました。わし等よりちょっと低いくらいの大きな物ですよ、古い物だったが、不思議と汚れていない。
そんな石像のことなど聞いたことがなかったから、当然誰が作ったかもわからない。
そのとき、しょんべんをしたかったやつが、その石像にしょんべんをひっかけたんだ、いつもやんちゃなやつだったからな。
そのときはそれで、茸を採る山までいったんだが、しばらくたってからだったな、しょんべんをひっかけたやつが、死んじまってな。あそこの物がかちかちになって、しょんべんがでなくなって死んじまったんだ。今なら、陰茎ガンてやつだったんじゃないかとおもうが、そのころ癌なんて知らなかった。悪いできものだよ。それで、一緒に茸取りに行った仲間が、あの石像にしょんべんかけたからだろうといいだして、みんなして、あの林に行きましたよ、するとおかしなことに石像がない。
誰かが盗んだのかと騒いだが、あんな物をもっていく奴はいないだろう。林の奥に行ってみますとな、ありました。五つの石像が同じ形で立っていました。誰かが移動させたのか不思議でしたな。しかし、そのときは仲間の一人が死んじまったんで、その石像を丁寧に洗いました。そのときも男のもののようにも見えたし、茸のようにも見えたな。
しばらくしてからでしたな、死んだ奴の供養もかねて、その五つの石像に小屋を建てて祀ろうといいだしたやつがいて、いつもの山歩きの仲間とその林に行きますとな、また石像がない。おかしなことです。だが、皆で探し回ったら隣の林にありました。石像が移動していたんです。
ともかく不思議だ、とますます、我々はその石像に畏怖を感じるようになり、木の囲いを作り、屋根をかけ、お供物をおいて祀った次第ですわ」
「小屋を造ってからは移動しなかったのですか」
「動いたというのは我々の錯覚だったのかもしれませんな、それからは小屋にありました、だけんど、仲間もみんな死んでしまって、わし一人長生きしちまってましてな、手入れもできんし、若い衆にはたのまれんで、そのままになってます、だけど、孫娘が炭焼き場の調査などはじめたので、あれは見ちゃなんええぞって、言ったわけでして」
「陽物信仰で、男のあれの形をしているので、見ていけないと言われたのかと思ってました」
「このたりに陽物信仰はないね、村だったころ、子供がたくさんいましたよ、今でもそうだと思いますよ、ここの女性はみな安産で、よく子供を産む、うちの孫は4人兄弟ですからな」
そういえばこの町には子供が多い。小学校のクラスも一学年六組あるときいた。今時は大きな都市でさえ三組くさいしかない。
「とすると、あの石像の由来はまったくわからないわけですか」
「うーん、わからんですな、わしには茸に見えますな、仲間には酒、醤油や味噌をつくっている連中もおったんで、そいつらは、あれは新神じゃないかと言っておったな、うちは米屋だったので、新田神を祀っていたから、酒屋の新神とはちょっと違っていますな、新田神は畦にいると思っていましたな」
「それはどういうものでしょう」
「新神がうまい味噌を作るという話はご存知でしょう、だけど、米を作っている連中は、稲を枯らす虫が新しいものを運んでくると考えていましたな」
「やっぱり菌でしょうか」
「そうなりますかな、新神も新田神も読みかたは、あらたかみ、ですしな、昔は同じものだったのかもしれませんな、まあ、あの石像が新神と関係あるものかどうか、全くわかりません」
この話はとてもおもしろい。この町の神の由来を調べる大事な手がかりになるだろう。あの石像をもっと調べてみよう。
男は日曜日ごとに林に通った。他にも石の構造物が残っていないか調べてみた。石はよくある花崗岩のようだ。石像の頭の部分を調べると、二つは確かに亀頭に似ていなくもなかったが、外尿道の切れ目はなくつるんとしている。三つはもっと釣り鐘型で、開く前の茸にそっくりである。しかし頭の下に茸のような襞はなくつるんとしている。幹のところを見ると、中程が少し膨らみエンタシスで、陽物か茸かわからないが、柄が傘にめり込むようになっているところは、どちらかというと茸である。根本は土に埋まっているので、少しばかり掘ってみた。どうも壷のような膨らみがある。男はこの石像は茸を模したものという結論に達した。
年代がわかる印が見つかるといいのだが、文字や記号まったく彫られていなかった。驚いたのは全体的に汚れてはいるが、欠けたところがなく、指で触れてみると、予想に反してつるつるしている。
これだけ手がかりがないと、いつ誰が作ったのかわからない。男は林の中をくまなく歩き回った。何度も同じところを歩いて見落としがないか探った。それが功を奏して、五つの石像よりかなり離れている草むらの中から土器の破片のような物が突き出ているのに気がついた。堀りだしてみると、土器の破片のようだが、縄文時代ほどの古さはありそうだ。そ野周辺を掘って見ると、同様の破片を拾うことができた。それを専門家に見てもらえば、石像が建てられた場所がどのようなところだったのかわかる。大昔の特殊な用途の場所であったとすれば、石像を建てた理由の一端が見えるかもしれない。
男は土器のかけらを整理して、母校の縄文時代を研究している先生に鑑定をしてもらった。
「確かに縄文時代の物だよ、縄文初期だね」
「すると一万年ほど前の物ですか」
「そうだね、他になにかでてこなかった」
「もっと探せばあるかもしれませんが」今は
「何でそこを調べたの」
「茸のような石像が五つあって、それを調べる目的で行ったんです」
教授に写真をみせた。
「石像はいつごろのものなの」
「まったくわからないので知りたいと思いまして、ただおそらく江戸時代のものと推測しています」
「町の人はいわれを知らないの」
「ええ、石像のことを知っているお年寄りには聞きましたが、誰が作ったか、いつごろのものか知っている人はいません、どうも陽物だと思っていたようです」
「安産の祈願か」
「そうです、しかし、子供が昔から多い地域で、安産祈願の必要はないようです」
「そういうところだからこそ、子供ができない人はそういうものにすがりたくなるよ」
「それは否定できないですね、ただ、頭は茸の笠に近いように見えます」
拡大した写真も見せた。
「そうだね、安産祈願かどうかわからないけど、やはり何かを祈願したんだろうな、個人が、自分の願掛けのためにつくったものだと、その人の家族親族がいなくなると、由来はわからなくなるからね、ただ、そういったものを作った場合、安置する場所は意味のあるところにおくよ、きっと、縄文時代から、その場所を何らかの目的でつかっていたのだろうね」
「縄文時代に宗教らしきものは芽生えていたのだと、僕はそうぞうしていますが、どうでしょう」
「あると思うよ、棒石、茸石などは祀りごとにつかわれたのだというからね、周りを発掘して何が出てくるか調べたらいいよ」
先生の言うとおりである。
土器の土器を拾ったときから、あの石像が縄文時代からも続いている信仰に関係あれば面白いと思っていたのだ。原始宗教は自然のものが信仰の対象になり、感謝の気持ちから儀式になり、祈りは人の気持ちを静めてくれる。
茸に感謝した石像だろうか。ちょっと飛躍しすぎだろうか。それはそれでおもしろいが、町のあらた神とはつながらない。
男は女性徒のお爺さんにもう一度会いにいった。あの石像が茸らしいこと、それにあの場所から縄文土器がでたことを話したのである。茸が町にとってどのようなものだったか尋ねた。
「茸はこの町だけじゃなくて、このあたりの山々ではよく採れますな、町のだれもが茸好きですよ、味噌醤油の新神は菌類ですしな、田畑の新田神もそうですな、だから茸はあらた神のなかまですな
縄文土器がでるところはたくさんありますが、あそこから縄文土器がでたというのは始めて聞きました、じゃが石像は新しいものでしょう、誰が作ったか知りませんけどな、茸なわけですかね、茸の信仰は聞いたことはないけどね」
もちろん教員仲間にもその話をしたのだが、誰も石像については知っていなかった。ただ、この町で生まれ、山の麓に家のある音楽の先生が、秋になると、あの林のある山に鵺(ぬえ)が現れるという話をしてくれた。フクロウはよく鳴くが、シューと喉がなるような声で鳴く鳥がいると言うことだった。鵺はぎゃあと血を吐くような声でなく架空の鳥である。それを考えると鵺ではないだろう。そんな話をすると、
「そうですね、得体の知れない声をきくと、みんな鵺の声だと、年寄りが言っていましたけど、本当は何の声だかわかりませんね」
そう説明してくれた。面白いのは石像のあるあたりの山から聞こえるだけで、他からは聞こえたことがないと言う。
秋も深まった頃、教員室で音楽の先生が、前の晩にシューという鵺の鳴き声が聞こえたと言った。生物の先生にどんな鳥か聞いたことがあるけど、喘息の喉の音のような鳴き方をするやつはいない、獣じゃないかなと言うことでしたわ、と笑っていた。
男はどんな生き物がいるのか興味をもった。あの石像のあるところは、縄文人が出入りしていたところである。住んでいたと言うより、祭りの場か宗教の場であるとすると、他のところと何かが違ったに違いない。いろいろな動物もすんでいたりしていただろう。
秋の十五夜も過ぎて少したった頃、天気の良い夜に、石像のある林に行った。街灯があるわけではないが、月の明かりが道を照らしてくれて、ヘッドライトなどいらないほどである。
このあたりには熊などの危険な動物はいないので、男は気楽に山道を歩いていった。
途中から、シューというかピューといった、今まで聞いたことのない音が断続的に聞こえてきた。かなり大きな音である。音楽の先生が聞いたというのはこの音だろう。確かにあの石像のある場所のほうから聞こえる。
男はその雑木林に入った。石像がはいっている小屋の扉が開いている。
あっと思った男はその場に立ち尽くした。
茸の石像が小屋の外で輪になっている。だれかが移動した。それしか考えられない。
いや人が移動したのじゃない。男はぞくっとして体が冷えてきた。
石の茸の頭が開いている。開いた傘の下に襞がみえる。
シューと大きな音がした。茸の襞から煙が上がった。
胞子をだしている。
胞子が男を包んだ。
男の目の前が真っ暗になった。眼の先に明るい光が見える。男はそこに向かってひっぱられていく。足を動かしていくと光は大きくなり、男は一瞬気が遠くなり、林の外に弾き飛ばされていた。
どのくらい立ったのか。空の月がだいぶ移動している。
男は林の脇の道に立っている。林の中を覗くと月の明かりで小屋が見えた。石の茸が小屋の開いた扉からすべるように中に入っていく。
男はおそるおそる林の中に足をいれてみた。何も起こらない。こわごわ歩いて小屋の入り口にくると扉を開けた。なかには五つの古い茸の石像がたっている。
石像に手を伸ばしてみたが一度はひっこめた。しばらくして、意を決した男は石像の笠に指先を触れた。石像はホカホカと暖かかった。運動をしてきた後のからだのようだった。いや子供を産んだ後だ。
夢を見ていたのか。
男は山を下りた。
借りている家にもどると、風呂をわかし、湯に浸かった。男はつかりながら、天井を見た。一匹の蜘蛛が歩いている。目をつむった。
だが、蜘蛛が天井をはっていくのが見えた。
不思議に思って、もう一度目をつむろうと思った。天井の蜘蛛が見えなくなった。
だが、風呂の湯の中の自分の体が見えた。湯の中の足の先も見えた。
目を閉じよう。そう思ったら、明るいだけでなにも見えなくなった。
目を開けよう、そう思った。風呂場が全部見渡せた。湯の中も風呂場の中もいっぺんに見えた。
両手を湯から出して顔をぬぐった。左の人差し指を顔に向けた。自分の顔のほくろが大きく見えた。
指先を左目に近づけたら、指先も左目も大きく見えた。
男は背筋が寒くなり、二つの目をつむった。つむった自分の目が見えた。
なにが起きたのかわからなかった。二つの目を開け左人差し指の指先をみた。小さな目が指先にあった。
目を閉じ、指先の目も閉じるように念じた。天井またでてきた蜘蛛が見えた。
左指先の目を開けるように念じた。自分の指を頭のてっぺんにもっていった。自分の髪の毛の中に大きめの目が一つあった。
からだに鳥肌が立った。夢だろう。風呂から上がって、ぱじゃまになった。布団に入って、顔の目を閉じるように念じた。布団の上の左手の指の目が、周りをみている。頭の頂上にある目がベッドの頭のところを見ている。その二つの目も閉じると念じた。やっと自分の四つの目を閉じることができた。
そのまま寝てしまった。
男は茸の石像に起こったことは夢の中の出来事として覚えていた。
高校の授業中に黒板で字を書いていると、後ろにいる生徒たちの様子をみることができた。まるで頭の中に眼があるようだ。自分の勘が良くなったことを、教師として慣れてきたと男は理解した。
今では男の体の表面は目で覆われていた。体の表皮細胞の間に無数のミクロの目が生じた。体中が目になり、情報を脳に送り、必要な情報だけを選び出して、判断、反応することができるようになっていた。それに対応する複雑な脳も持つようになった。
男は自分も大人になったのだと自覚していた。
男は新たな生き物の祖先になった。彼が結婚して、子どもができて、その子供に遺伝し、新たな感覚をもった人類が誕生することになる。
このように、林の中の茸の石像は生き物のあらた神であることが、男が身を持って証明したことになったわけである。もちろん本人が知るわけではない。
菌類の子供を産む組織である茸は人が生まれたときから生活に新たなものを導き出してきた。
新たな物を生む茸に縄文人が祈りをささげていた。その結果、茸が大きくなり、やがてたくさんの胞子をまくようになり、石のように硬い形になり胞子をまいた。胞子は味噌や醤油にあらたな進歩をもたらし、田畑にもあらたな作物を作り出した。茸があらた神になったのである。神というのは人間の祈りから生まれたものである。
あらた神になった茸の像は触れるものを新しいものにする力を持った。
この町はあらた神のすむ村となり、町となり、新しいものを生み出す風土となった。そこに男がやってきた。男はあらた神が胞子を生み出す瞬間に立ち会い、触れることで新しいものになる力を授けられた。
あらた神は進化途上で停滞していた人間をやっと先に進めることができたのである。
男がどのようにこれからを生きるか、そこにニンゲンの未来がかかっているのである。
あらた神


