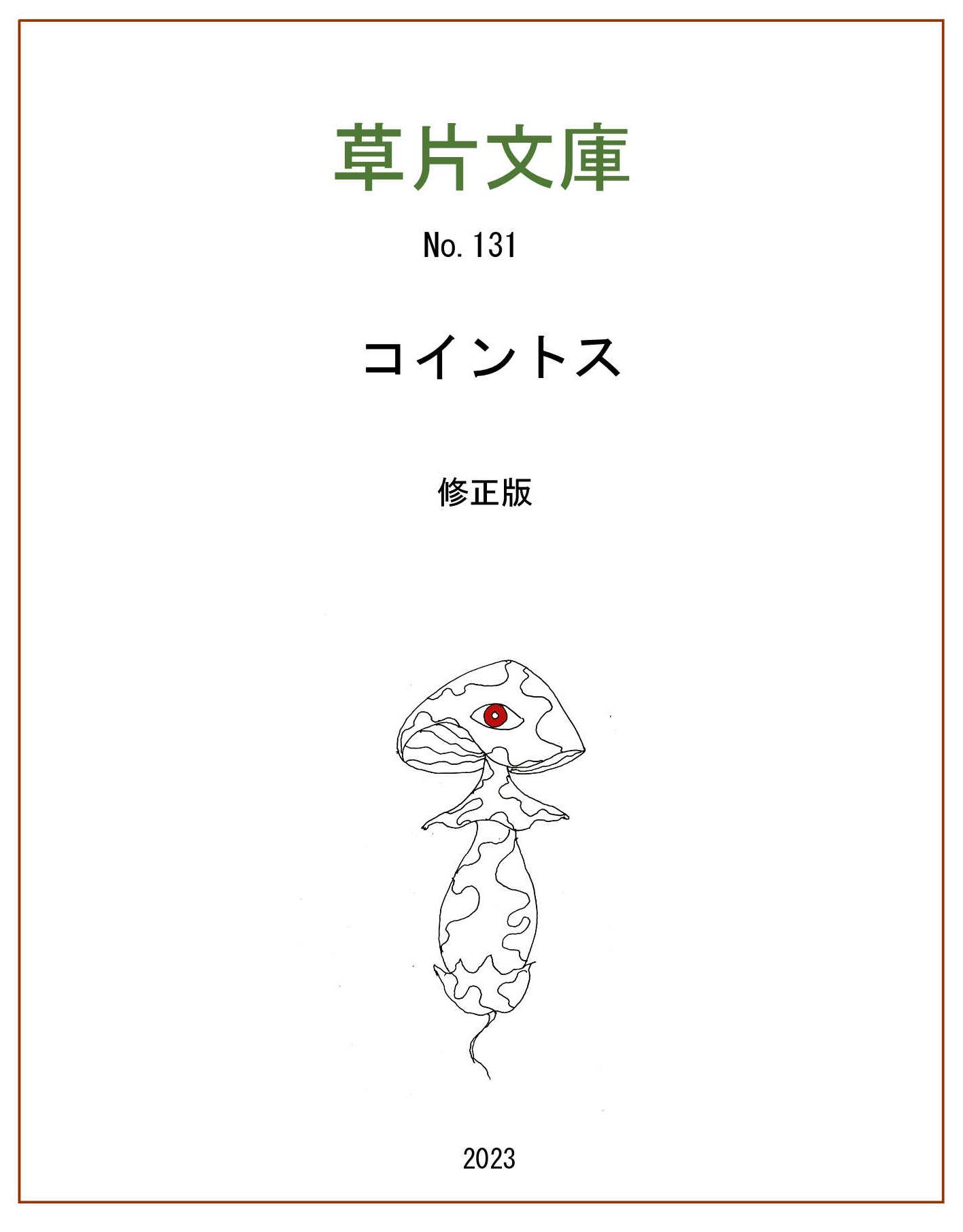
コイントス
チョットコメディー小説です。
この男は大学病院で診療している精神科医である。鬱状態、統合失調症、精神的な過敏症、痴呆に至るまで、様々な精神疾患のなかでも、なかなか治りにくい悪い癖、たとえばクリプトマニアやギャンブル症などをこの精神科医は上手に治療した。
癖を治す治療方法は学術的にもそれなりに発達してきた。しかし心の問題である。薬や器具機械にたよらず、医師の患者に対する見立てが最も重要な治療の柱になる。患者の生い立ちや仕事や家庭、様々な背景をくみとり、患者の性格をわきまえて、言葉により患者をいい方向に導く。
複雑な人間の脳の働きに対する判断力を必要とする難しい診療領域と言ってもいいだろう。患部を切り取れば治ると言うものではない。
いま目の前にいるどちらかというと背の高い患者は、「小さい」といわれると、無性に腹が立ち、ひどくなると、周りの物を破壊する行動をおこす。今日は二回目の診察だ。最初は時間をかけて、仕事や家庭、子供の頃のことを聞き出した。まだ独身で事務系の仕事をしている。仕事はうまくいっており仕事環境には全く問題ない。
なぜ患者は「小さい」に怒るのか。背が高いのに小さいと言われて興奮するのではない。その精神科医の解析の結果、原因は子供の頃に小さい子がいじめられているのをただ見ているだけで止めることができなかったことのようだ。いじめていた子が怖かったからだ。ところが一緒にいた女の子が、いじめていた男の子にくってかかり、小さい子を救ってやった。その女の子が「あなた小さいわね、弱いわね」と患者に言ったことがトラウマになって、小さいという言葉をいわれると、自分に対して怒り、周りの物を壊してしまうようになったのである。至ってまじめな男性だった。
一回目でそこまでわかったのだが、さてこれからどのように治療をしたらいいか考えた。
子供の頃に植え付けられてしまった、自分に対する羞恥心のようなことがらは脳の中に根を張っていて、引っこ抜くのは大変だ。
嘘をつくかどうしようか迷った。
嘘というのは、脳の中に問題があるので、薬を飲めば治りますよ、という嘘である。ビタミン剤でも飲ましておけば、うまくいくと比較的早く治る。
一方、まっとうに、何度も会話を重ね、羞恥心の根を少しずつ掘り出して、枯らしてしまうことである。とても時間がかかる。
その医師は、「ちょっとこれをみていてください」と患者に脳の絵が描かれた一枚の紙をわたし、自分は席を立ち、医師の控え室に行って、ズボンから五百円玉をとりだした。
表なら、会話による治療、裏なら、MRIと思って、右手の親指で五百円玉を上にはじいた。
右手で受け取って、左手の手の平に乗せて、右手で覆った。
右手をどかすと手の平の上の五百円玉は裏をむいていた。MRIだ。
五百円玉をポケットいれると、患者のところにもどった。
「脳の形わかりましたか」
「はい、脳のことは岩波新書でよんだことがあります」
「そうですか、あなたの問題になる部分は、記憶を司る海馬という部分、恐れや怒りと関係する扁桃体というところ、それから、最も大事な人間で一番発達してきた大脳新皮質、特に前頭葉と言うところです」
そういって、それぞれの脳の中の部位を指差した。
患者はうなずいている。
「もしかすると、それらの部位のちょっとした不具合によるものかもしれません」
「どんな不具合になってしまったのでしょうか」
男は医師を見た。真面目な男である。
医師はあまり関係ないなと思いながら、
「微細損傷などです、MRIで調べてみましょうか」と言った。
誘導である。
患者はうなずいた。脳に興味を持ってくれた、うまくいくかもしれない。
「MRIはやったことがありますか」
「いえ、病気は風邪をひいたくらいで、MRIなど受けたことがありません」
「それでは、看護師がわたす書類を持って、地下の検査室に言ってください」
患者は立ち上がり地下の検査場に行き、ほどなくMRIを受けて戻ってきた。
コンピュータの画面に映し出されたのは、とても健全な脳であった。精神科医はくまなくチェックすると、たまたま、薄い白い点があった。
これだと思った医師は、それを指さして、このあたりちょっと弱いかな。とよくわからない指摘をした。
患者はそれだけでも、自分の怒り性は、それが悪いためなのかも知れないと思ってしまう。
「どうしたらいいでしょうか」
「そうですね、脳の血流をよくする薬を飲んでみますか」
そういって医者は本当に血流を向上させるビタミン剤を一月分だした。
一月後に薬の効き目を調べるため来てもらうこということにした。睡眠を良くとるように言って患者を帰した。
一月後にやってきた患者は、なんだか体が暖かくなったようで、気分が良くて、仕事がはかどりますと顔がほころんでいた。薬は効いていると医者はにこやかに「改善してますね」と言った。
小さい、といわれると、どうなるかはきかなかったし、しらべもしなかった。そんなに早く治るわけはないと思い、刺激を避けたのだ。
三ヶ月分薬をもたした。
三ヶ月後、言葉が気にならなくなりましたと、患者のほうから医師につげた。相当な効果だと信じられないほどだった。
半年後にはほぼなおっていた。
MRIの画像はもちろん異常はやはり見られず、患者の言動は明るかった。
「もういいですね、薬は一日おきにして半年後は終わりにしてください、問題なければそれで終わりです」と三ヶ月分血流改善の薬をもたした。
その患者はもうこなかった。
プラシーボ効果は精神的なものである。薬も使いよう。患者もビタミン剤の経費ほどで治ったし、医師も評判が上がるし、悪いことは何もなかった。
一人の若い女性の患者がきた。その精神科医は女性の顔を見て、どのような症状なのかわからなかった。
「どうしました」と聞くと、女性は
「猫が好きになりたい」とうったえてきた。
よくよく話しをきいていくと、好きな彼氏ができたのだが、その男は動物好きで、特に猫をかわいがっていた。一方、その女性は両親とも虫が嫌いで、猫や犬もほとんど興味を示さず、むしろ避けていた。その影響のためか、それとも、好きなアイスクリームを食べているときに、猫がよってきたので、おいはらったら引掻かれ、アイスクリームを落としてしまったことがあったかもしれないが、ともかく猫は猫きらいだった。
「一生付き合える彼とあったの、そんで猫が好きになりたいけどだめなんだ」
「ウサギやハムスターもだめですか」
「猫だって、見るだけならいけど、さわれない」
見るのがいやとなると大変だが、これなら脈がある。
嫌いな物を好きにさせるにはいろいろな治療方法があるが、よく行われるのは、宣伝コピーとおなじように、頭の中に猫はかわいいものだと言うことを植え付けるのである。
もう一つある。反対のことを言って、自分から積極的に猫を飼おうという気にさせるのである。
この娘にはどっちが効果があるのだろう。かなり親の影響を受けている部分がある。動物にならすことから始めようか。
いや、ちょっと気の強そうな部分もあるから、あなたは変わることが難しいから、彼氏をあきらめろと言う、逆の効果をねらって会話をしていくか。
その精神科医は、ポケットから五百円玉をだして、コイントスをした。表なら、動物にならすことからはじめる。裏なら彼氏をあきらめるように言う。
手のひらの上の五百円玉は裏を示した。
彼氏をあきらめるように言うのは難しい。効き過ぎて本当にあきらめてしまう可能性もある。
それで、まず彼のいいところを聞いた。
「たくさんあるんだ」と娘は、長々と説明した。悪いところを聞くと「顔は三流かな」とうつむいた。
こりゃあかなり男に首っ丈だ。
「だけど、彼が猫をさわっているときの顔、とても幸せに見えて、私も幸せになるんだ」
「あなたを見ているときの顔よりいいの」
彼女はうなずいた。
「それじゃ、彼をあきらめて、猫の嫌いな男を捜したらいい」
そういったら、娘は「いや、あんなに暖かい人いない」
と反発をした。こりゃいいぞ。
「でもあなたが猫を触れないのなら、あきらめたほうがいいね」
そんな会話を何回かするうちに、「彼と動物園に行った」とか「ペットショップに行った」とか、言うようになり、「猫の頭さすった」とか「だいじょうぶそう」と診察にこなくなった。きっとうまくいったのだと、精神科医は納得した。
来年108になるおばあさんが、長く生きすぎた、死にたい死にたいと言っているのだが、なんとかならないかと、その息子が相談にきた。
おばあさんを病院につれてきてもらったほうがいいか、息子さんにおばあさんの扱い方を話した方がいいのか迷った精神科医は、500円玉をはじいて決断した。裏がでたので、おばあさんに診察にきてもらうことになった。お嫁さんがつれてくるように言っておいた。
おばあさんは車いすなどいらないほど元気だった。お嫁さんには診察室の外で待ってもらうことにした。
「あたしゃ、なんで、きちがい病院になどこなきゃならなくなったのですかね」
結構気が強い。
「きちがいということばは、今では使ってはいけないんです、差別用語になってしまいました」
「精神科というのはわかってるが、言葉を換えたって同じこと、気がおかしくなった者がくるところじゃろ、きちがい、というのは昔の小説家がやたらとつかってたがだめかね」
そう、言っていることは正しい。頭はかなりしっかりしている。
「そうですね、これは内緒の話ですが、本当は息子さんを治してあげたいと思ってます、それでお嫁さんにおばあさんをつれてきてくれるように頼んだんです」
ちょっと嘘だ。
「息子がきちがいかね」
「いえ、きちがいじゃありません、ただ仕事にちょっと疲れていて、今の生き甲斐は、おばあさんがギネスに載ることだそうです、お嫁さんから聞きました」
「あれ、あたしゃそんなこと知らないよ、あたしがギネスにのるっちゃどういうことなんで」
「世界で何でも一番になると、ギネスという会社が、あなたが一番という賞状をくれるんです」
「それでどううなのかね」
「息子さん鼻が高くなると思いますよ、お母さんを元気にさせたって」
「みんなが知ることになるのかね」
「もちろんです、いまでも、日本の女性が長寿世界一で、ギネスにのったと、テレビに映されたり、新聞に顔写真がのるのですよ」
「そんなことがあるんか」
「息子さんはそれを楽しみにしているんです」
「そりゃ、知らなかったな」
「いえ、内緒にしておいてください、あと少なくとも10年たてば、ギネスにのります。息子さんはそのとき50代後半でしょう、きっと大喜びなさいますよ」
「そんなことなら簡単だ、ただ生きるのは詰まらんとおもっとったが、それだけで息子が喜ぶなら生きてやろう」
「もちろん、お嫁さんもよろこびますしね、お母さんが、息子さんに、長生きしてやるというと、息子さんは張り合いが出て、仕事もうまく行くと思いますよ」
「そうだったか」
そういうことで、そのおばあさんは、早く死にたいと言わなくなった。
このように、その医者はコイントスを頼りに生きていた。診察に関してばかりではない、なにごとにつけ、コイントスをして決めていた。
そんなある日、こんな患者がきた。30半ばの男である。
「先生、結婚したいのですが、なかなかできないんです」
最近の若者は仕事が忙しすぎで、異性とつきあう暇もなく、年を重ねていく。結婚相手を探すのは婚活会社に依存する者が多いようだ。
昔のお見合いを親の決めた結婚なんてやだ、と親との縁を切っても、好きな相手と駆け落ちする女性が出てきた頃とは大違いだ。
だが、結婚ができないことを精神科に訴えに来るとはどういうことだろうか。
「好きな人がいるのですか」
「いえ、そういう感情はなかなかわかないんです、結婚相手はふつうの女性でかまわないのですが、なかなかきまりません」
「お見合いをしましたか」
「はい、何度も」
「向こうから断られるのですか」
その男性の履歴をみせてもらったが、どこといってわるいところはなにもない。健康は優秀の部類にはいる。収入もそれなりにある。容姿は並より良い。
「そこまでいきません」
「というと」
「僕が決められないんです」
「気持ちの問題ですか」
「あの、すべてのことに自分で決められないんです」
「だけど、そのお年で係長になっていますね、自分でいろいろ決めなければならないこともあるのではないですか」
「はい、それで」といいながら右手をズボンのポケットに入れた。
それを見ていた精神科医はハッとした。どこかで見た動き、いや、自分だ、自分を見ているようだ。医者の目が大きく見開いた。
患者の男はポケットから五百円玉をだした。
右手の親指でコインを上にはじいて、落ちてきたコインを右手で受け取ると、左手の手のひらにおいた。
自分のやっているいつもの動作だ。
「こうやって、物事決めていくんです、仕事の方ではほとんど問題なく、コイントスでやってきました、お見合いや婚活で、これはと思う相手と結婚を申し込んだ方がいいかどうかコイントスをすると、必ず裏がでるんです、ノーということです、一度も表がでません」
思い当たる節があった。それでこう言った。
「裏がでたら、イエスという条件でコイントスをやったらいいかもしれませんよ」
「先生、いいことに気づかれました、まるでコイントスを使っている人のようですね、すでに僕もそれをしました。そうすると、表がでて、ノーということになってしまうんです、それで、結婚を申し込むことができません」
医師は自分ではできないことを患者に言った。
「コイントスをやめて、自分で決めるようにしたらどうでしょう」
「自分で決められないからコイントスをしているんです」
「コイントスで、裏がでたらコイントスをやめる、としてやってみてください」
男は上手に五百円玉をくるくる回して上にあげた。
結果は表だった。
「ほらだめです」
医者もよくやってみるが、なぜかやめない方にでる。
「それじゃ、結婚に関しては他の人に決めてもらうということで、コイントスをしてみたらどうでしょう」
「やってみましょうか、表がでたら、おやなり誰かのいう人と結婚する、とします」
患者がコイントスをした。裏がでた。だめだ。俺もよくやるんだ。精神科医は密かに思った。
「コイントスをやめて、自分で決断できるようにしてほしいんです、それで先生のところにきました」
自分で直せないことを、他人にできるだろうか。
「ちょっとまってて」
医者は控え室に行って、ポケットから五百円玉をとりだし、はじきあげた。手のひらに受け取ったコインを乗せると手を開いた。裏だった。
この患者を治せるなら表、だめなら裏のつもりだった。
この患者はなおせないとでた。
どうしたらいいだろう。精神科にはたくさんの先生がいる。他の先生に回した方がいいかどうか、コイントスをした。
答えはノーだった。
患者は治せない。だけど他の先生に回すことはできない。
この矛盾をどうやって解決したらいいのだろう。
この精神科医は医者をやめることにした。
患者の男性のところに戻ると、申し訳なさそうに言った。
「悪いけど、あなたのコイントス病は治せない、僕はもう医者をやめます」
患者は同情するように言った。
「先生もコイントスで生きてきたんですね、どこに行くのかと思ったのですけど、僕がよくやることなんです、人と話していて、どうしても何か決めなきゃいけないとき、裏にいってコイントスするんです、あ、同じだなと思いました、僕はあきらめます、ずーっとコイントスで生きていきます」
「僕はなにになったらいいでしょうね」
医者がそう言ってため息をもらした。
「コイントスが一番いいですよ、医者をやめるかやめないかコイントスで決めるといいですよ」
患者は自信を持って、帰って行った。
医者はコイントスをした。
やっぱり、精神科医をやめるだった。
コイントス


