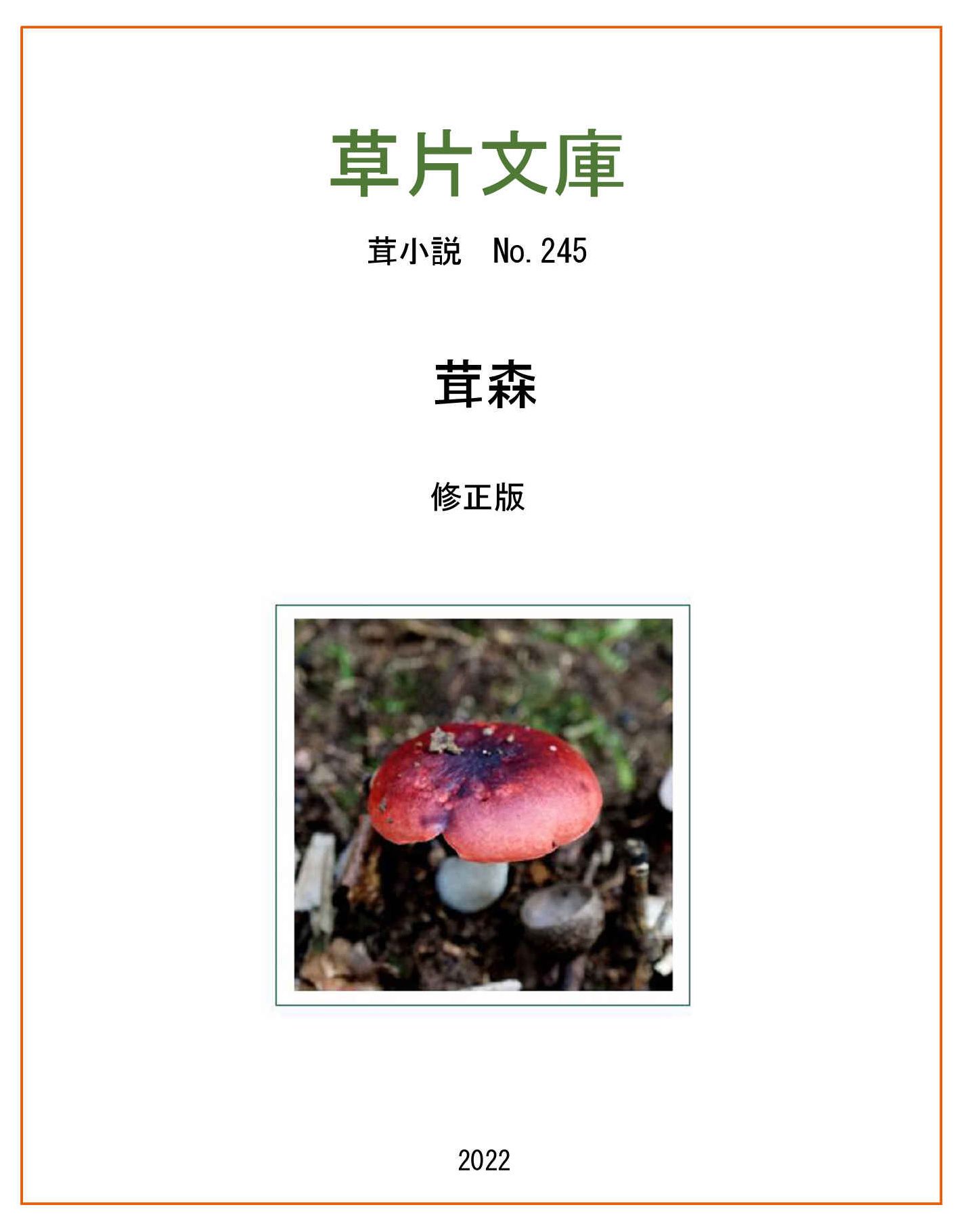
茸森
茸ファンタジーです。
男は森の中で卵茸を集めていた。
今年もかなりはえている。この森は食べられる茸がたくさんとれる。ただ不思議なのは、この森の茸は傘が開かない。開く手前のものしかない。それだからか、どの茸もうまい。ただ、傘の下の襞で胞子が熟すはずだが。
男は斜面にある大きな岩の近くにきた。このあたりでいい茸に出会うことが多い。
ふと見ると、岩の脇に大きな穴があるのに気付いた。人が入れそうだ。入口は木の枝と背の高いシダに覆われていて今まで気がつかなかった。動物が掘った穴か、自然にできた穴か。どちらにしろ、かなり古そうだ。入り口の縁には薄緑の地衣類が砂埃にまみれて汚らしく干からびている。
大きな八角形の蜘蛛の巣が入り口をふさぐように張られている。それにしてもやけに大きい。なんだか餅を焼く大きな金網のようだ。巣のところどころに引っかかってぐるぐる巻きにされた獲物がつり下がっている。よく見るとカメムシや蝶、それに、トンボたちだ。綺麗好きな蜘蛛ならば、体液を吸い取ってしまった残り滓は切り離して下に落とす。この巣はあたかも獲物の展示場のようだ。これを現代アート展にかざったら一つの作品になる。
蜘蛛は巣の端にいて、糸が揺れるとすぐさま獲物に近づき糸を巻き付ける。どこかに蜘蛛の巣の端にいるはずだ。
いた、穴の右上にあたかも血を吸ったかのような赤い腹をもった大きな蜘蛛だ。いくつもある青い眼がこちらをみてい。いや、俺をねらっているはずはない、男はそう思って記憶の一部を探そうとした。鬼蜘蛛、女郎蜘蛛、草蜘蛛、蜘蛛の図鑑だ。小学校のときから図鑑はおおきくなっていない。数種類の名前しか出てこない。
こんな蜘蛛は知らない。形は鬼グモに近いが、この腹は鮮血がそのまま固まったようなみごとな赤だ。芸術蜘なんて名前を付けてやろうか。そんな風に蜘蛛を見ていると、芸術なんて言葉は食えねえ、とどこからか聞こえてきた。あんた、芸術って言葉嫌いなはずだろ、そうだった。
蜘蛛の巣を払ってまで、穴に入ろうとは思わなかった。今日はすでに沢山の卵茸がとれた。
蜘蛛が動いた。はやい、八角形の巣の上にのぼってくると、さささと動いた。くっついていた死体を運び、脇に寄せ、人が通れるくらいの穴をあけた。
はいれといっているのか。いや、取り払われて壊されるのがいやだったのか。入る気はなかったのに逆に入ってみようかという気になった。
蜘蛛はさっさと、隅にひっこんで、石のくぼみに身を隠した。背中の黒い色が石に同化し、蜘蛛の姿が消えていた。もしかすると、石の表面にたくさんある窪みに、蜘蛛の仲間が潜んでいて、そうっと自分を観察しているのかもしれない。
入れというのなら入ってやろうじゃないか。卵茸の入った籠を下草の上に置くと、穴をのぞいてみた。入り口は背を丸めないとは入れないが中は広い。これは人が作った穴だ。それにしても蜘蛛の巣が穴の内面のいたるところに張り巡らされている。
正面の壁に人形(ひとかた)のレリーフがみえる。壁は土のように見える。レリーフの周りも蜘蛛の巣がからんでいる。右を見ても左を見ても、蜘蛛の巣に死んだ虫がくっついて、ブランブランとゆれている。虫は穴に入って自分のねぐらにでもしようと思ったのか。ねぐらどころか永久の眠りになってしまったじゃないか。男は自分が蜘蛛の巣に引っかかったようなきもちになって、中に入るのに躊躇した。顔に蜘蛛の巣がからんだときのなんともいやな気分を思いだした。森の中には蜘蛛の巣が五万とある。下を向いて茸を探しながら歩いていて、ふと顔を上げたときに木と木の間の蜘蛛巣に顔を引っ掛けることがある。いい気持ちがしないものだ。レリーフの人形の顔のへこんだ二つの目と自分の目が合った。そのとき男の足が穴の中に踏み出していた。もう進むしかない。だが虫の死体はいやだ、そう思った男は手で蜘蛛の巣をはらいのけようとした。
男がそう思ったとたんである。腹の赤い蜘蛛が無数に現れ、男の足元をすり抜けると、穴の中の蜘蛛の巣にのぼり、くるくると前肢でからみとると、きれいにかたずけてしまった。
男は奇妙に思う前に、よかったと安堵の気持ちで、巣の中に入った。身長180の男が楽に立つことができる。男の気がつかない間に、蜘蛛たちは男の足元をすり抜け、そとにでていった。
正面のレリーフは風化がすすみ、手足が削られてはっきりしない。コケシにもみえるし、茸のようにも見える。壁には絵も字も書かれていない。壁に触れてみると砂がぱらぱらと落ちて、白っぽくなった。男がそこを指で押した。
石じゃないか。周りの壁も触ってみた。土の穴かと思ったら石である。前にある大きな岩の続きだ。石に穴を開けたのだ。
周りの壁には凹みがへこみいくつか等間隔に並んで掘られている。いくつかの凹みには小さくなったローソクが置かれている。
人形のレリーフの上にもへこみが掘られていた。かなり古い。やっぱりローソクのようなものがあるが、蜘蛛の巣が周りを取り囲み、なんだかわからないような状態だ
男は手を伸ばしてそれを取り出した。ローソクではない、持った感じはもっと硬いものだ。蜘蛛の巣とほこりを払った。
男はおやおやと思った。
ワイングラスじゃないか。手で表面をこすると、いきなりきれいに透き通った。水晶のようだ。中に赤黒っぽく乾いたものが重なっている。レリーフがどのようなものか分からないが、祀られた神か何かなのだろう。ささげられた酒を入れる器か?
江戸後期か明治のはじめのころのものだ。古いものの好きな男の眼がかがやいた。これは俺がみつけた。俺のものだ。男の頭の中ではそんな理屈をつけて、はあたりまえのようにそのグラスを自分のものとした。
それにしても誰が、何のために、こんなにか大きな石をくりぬいて、何を祀ったのか、石窟を作るのに、何年かかったことか、なにを願うためか。
茸採りは森にはいったことも忘れて、石窟をでると、卵茸の入った籠を拾って、数年前に購入した、森の脇の別荘にもどった。
小さいながらもしゃれた別荘には、集めた古いガラスの器が大きなガラス棚にならべてあった。
華やかなグラスはない。どれも模様はほとんどなく、ただ、海のように透き通って綺麗だ。輝いている江戸切り子や薩摩切り子のカットグラスも、玄人好みのしっとりと落ち着いたたたずまいのものばかりだ。そこが男の眼の高さだったのだろう。
男は卵茸をざるに乗せると、森の石窟からもってきたワイングラスをボールにいれた生ぬるい温水につけた。グラスの中に入っていた赤黒く乾いたものが解けだし、次第に水が赤くなっていく。
男は決してグラスの中をスポンジなどでこすろうとはしなかった。温水をとりかえてまたつけた。底にこびりついていた赤黒いものはほとんどとけだしていた。
そんな作業を何度か繰り返すと、柔らかな布巾で内部をふいた。外もそーっとふいた。
現れたのは形の整った小振りのワイングラスだった。水晶でできているのかと思われるほど、硬質で透明だ。持つ手に冷たさが伝わり、グラスのきらりと柔らかく反射する外の光は男の眼を刺した。
この透明度はなんだ。
男の趣味の虫はこのグラスを誰かにみせたくてしかたがなくなった。
そうじゃない、その前に、このグラスで飲みたい。うまいぶどう酒が飲みたい。
男は決して贅沢をしなかった。いやできなかった。程々の収入があり、妻子には苦労なく生活をさせてきたつもりだ。だから、集めたものも、年に二三個、高価なものではなく、気に入ったグラスを買い求めてきた。
ぶどう酒だって、ある程度の知識があったが、そんなに高価なものを飲んだ経験はなかった。舌が肥えているわけでもなくそれでいいと思っていた。
明日、妻が東京から来る。息子夫婦も子供を連れて車でくる予定だ。食料を買って来ることになっている。
男は長男に電話をした。ちょっと名の知れたボルドーの赤ワインと、ロックフォールチーズを買ってきてくれるように頼んだ。パンは妻が石窯で焼いたバケットをいつものパン屋から買ってくるはずだ。
一枚の天然木でできたテーブルの上におかれた、石窟からもってきたワイングラスは、天井からつるされた灯りの下で、ワインを入れてほしいとせがむように赤い光を反射し、男の眼をいった。
玄関の呼び鈴がなった。
たまに近所の別荘の人が茸のお裾分けや、晩ご飯への招待でおとずれる。
男は玄関を開けた。
「こんばんは」
そうか、もう日が落ちているのだ。いつの間に。
青いブラウスをきた、ジーパン姿の髪を頭の上で結わえた女が立っている。このあたりでは見たことがない。
「どなたでしょうか」
女性は白い腕をのばして、手に持っているものをさしだした。粉を吹いたような白い肌にくっきりとした眉毛、大きな目で男を見た。
「その先に越してきました、これからもよろしくお願いしますわ」
えくぼをよせて、「お口にあいますかしら」
と言った。
見るとボルドーのワインだ。1974という数字が見える。かなり古いものだ。男にもこれが相当なものだということがわかる。
「貴重なものです、ワインがお好きなんですか」
女はこっくりとうなずいた。
「軽く冷やしてありますのよ、赤は冷やさない方がいいなんて、そんなことはありませんわね」
男は女の名を聞くのもわすれて、「どうですか、ご一緒に」と、生まれてこの方一度も女性に対して言ったことのないようなセリフをくちにした。
「よろしいのかしら」
男の頭の中には、テーブルの上の石窟からもってきたワイングラスがあった。
女は部屋に通され、テーブルの上を見ると、あっと言った。
「すてきなグラス」
男は何もいわずにうなずいた。
「どうです、そのグラスでお飲みになりますか」
「いえ、ほかのグラスがございますか、このグラスはご主人にお似合いのようです」
女はそう言った。
男はほっとして、ガラス戸棚から、ベルギーの古いワイングラスをだして女の前においた。
「これも古いものですわね、よろしいんですか」
男はうなずいて、キッチンに栓抜きをとりにいった。
「普通のチーズしかないのですけど召し上がりますか」
「いえ、ワインだけで」
「今日は森で卵茸を採ってきたのですが、まだそのままで、ソテーにでもしましょうか」
「あら、すてきですこと、生でいただきたいわ」
卵茸を生で食べる。大丈夫なのか。男は笊にいれたままもってきた。傘が開いておらず、饅頭型の真っ赤で綺麗な卵茸である。
男は赤ワインの栓を抜いた。
女のグラスに少しばかり注いだ。女がちょっと口に含み、
「だいじょうぶですわ、おいしい」
と男を見た。
女のグラスをみたし、あの石窟からもってきたグラスにもそそいだ。
ぶどう酒をつがれたグラスが震えた。ぶどう酒の表面が波打っている。
「あら、グラスが喜んでいる」
女はまた男を見た。
男は女の顔を見ることもなく、女の前にこしかけて、
「それでは、いただきます」とグラスを持ち上げた。
ぶどう酒が口の中でからみつき、喉をなでさすりとおりすぎていく。胃の中に一滴おちた。心臓がドクンとなった。うまい。
「おいしいですね」
女は茸に手を伸ばした。
男は空になった女のグラスにワインをついだ。自分のグラスにもついだ。
女は卵茸を卵のところからちぎると口にいれた。
「よくできた茸ですこと、さすがに茸森ですね」
あの森が茸森と呼ばれていることをはじめて知った。
女がワインボトルを引き寄せると、持ち上げ男のグラスについだ。
「すみません」
男はグラスをかたむけた。一気に飲み終わると、自然と小さなため息がでた。
「おいしい」
男が空になったグラスをテーブルの上においた。
男がそのグラスを見て、あっと言った。
グラスの縁から一本の黒い茸が生えてきた。細い枝に襞のある黒い傘。
「すてき」
女が言った。
「すてきな茸」
もう一度そう言いながら、茸が生えたグラスにワインを注いだ。
「茸も一緒にお飲みにって」
男は女のいうがまま黒い茸が生えているところに口をあて一気に飲んだ。
これはうまい、うまい、うまい、そう思いながら男は飲み干して空になったグラスに赤い液体を吐き出した。男はグラスをテーブルに置こうと手を伸ばした。
「静かにグラスを置いてくださいね」
男はグラスをおくと、自分の頭も静かにテーブルの上にのせ目を閉じた。
女は頭の上で止めてあった髪をおろした。腰までも伸びている髪の一本一本がうごきだし、女のからだを覆った。
その中から細い蜘蛛が這い出して、テーブルに上ると、男の首の上にはっていった。
蜘蛛の口が男の首にくいついた。
蜘蛛の腹が赤く膨らみ、再び色の白い女にかわっていった。
女はグラスをもって男の家をでた。
星空の下で、長い髪を風に揺らした女が茸森にはいっていった。
森の中は静まり返り、茸の子供たちの頭が下草の中から女を見上げている。
石の入口にいた蜘蛛が女を見ると、張ってあった蜘蛛の巣をどかした。
「あたらしい血でございます」
女は男の血のはいったグラスを、レリーフの上にある窪みにおくと、レリーフが盛り上がり、茸の形になった。石でできた茸の傘が開いた。襞から出た胞子は上に上り、やがてグラスの中に降り注いだ。
無数の蜘蛛たちが穴の中に入ってきた。石の穴の中は再び蜘蛛の巣で満たされた。その下では、大きな赤い腹の蜘蛛にもどった女が子供を産んでいた。色々な形をした小さな茸がつぎつぎと石窟から茸森へ蜘蛛の子を散らすようにでていった。茸守の蜘蛛女は子供を産み終わると死んだ。
一匹の蜘蛛がグラスの血をなめた。やがて、その蜘蛛が茸を産む茸守となる。こうして茸森の茸の子どもたちは何処の森でも見られないほどうまい茸となって、人間を誘うわけである。
茸森


