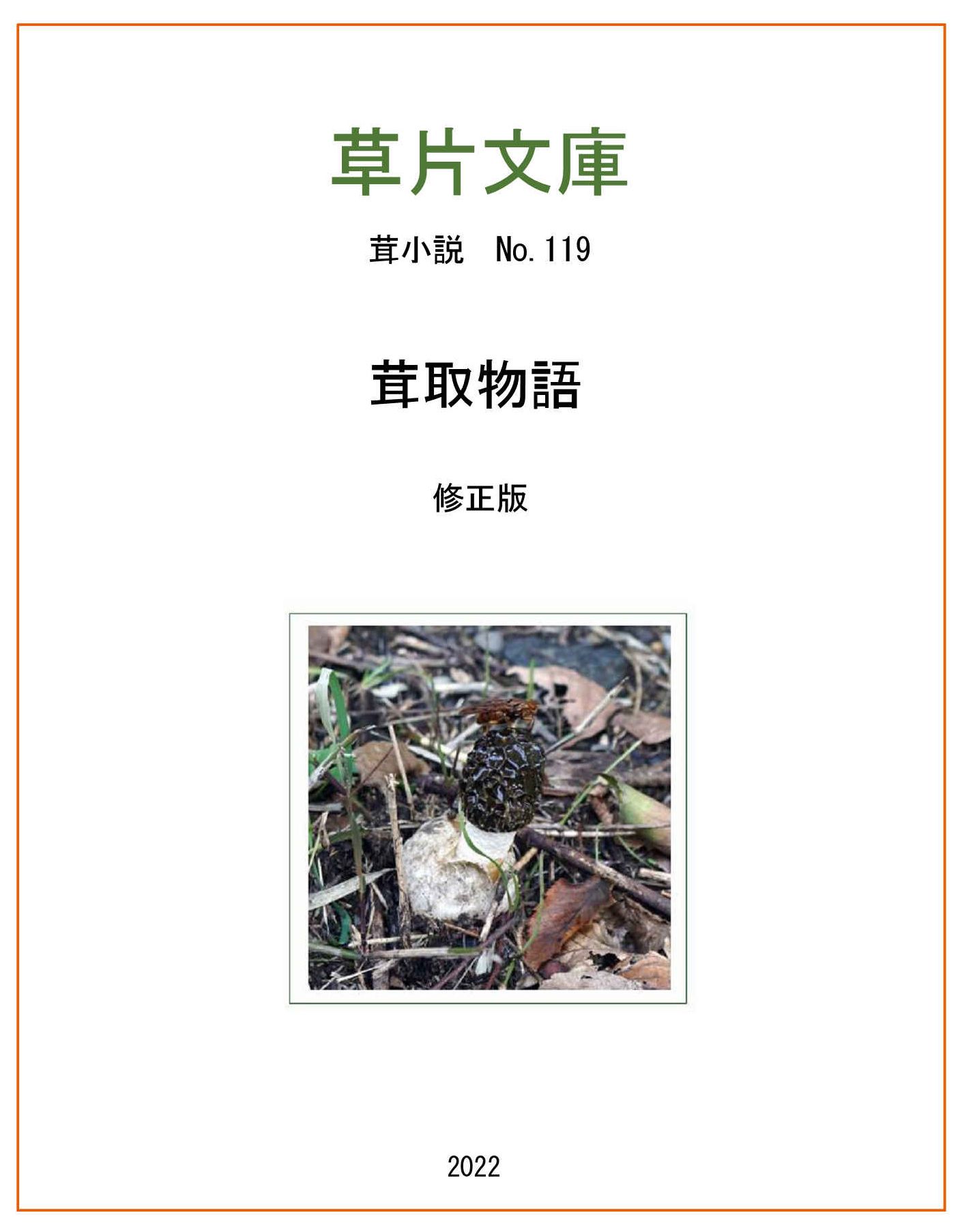
茸取物語(たけとりものがたり)
竹取物語異説ホラー童話
「かぐやひめがでてくる物語は知っているじゃろう」
爺ちゃんはそう言って話し始めた。もちろん僕は頷いて、「知っているよ、教科書にあったし、おじいさんが竹を割ったら、中から奇麗なお姫様が出てきて、大きくなったら、月に帰っていく話だろ」
「そうじゃ竹取物語と言うんじゃ、だけど、本当は違う話だったのじゃよ」
「どういう話しだい、爺ちゃん」
「もとはな、そうじゃなくて、もっと怖い話しじゃった」
「聞きたいな」
「夜中におしっこに行きたくなっても行けないほど怖いぞ、それでも聞きたいか」
僕は頷いた、六歳だから、もうすぐ小学生だ。
「よし、それじゃあな、夕ご飯食べたら、おじいちゃんの部屋においで」
爺ちゃんは、離れの家に一人ですんでいる。
「それじゃ、今日は爺ちゃんのところに泊まる」
「お母さんとお父さんがいいといったらな」
こうして、夕ご飯のときに、お母さんとおとお父さんに話しをしたら、いいよっていってくれた。
ご飯を食べた後、お母さんが僕の布団を離れに運んでくれた。
「お父さん、この子、よろしくお願いします」
「ああ、ああ、だいじょうぶだよ」
おじいちゃんは笑いながらお母さんに答えていた。
お母さんは、「おじいちゃんの言うことをよくきくのよ」、ともどっていった。
僕はなんだか、違う世界に来たようでうきうきしていた。
爺ちゃんは寝巻きに着かえると、布団の上であぐらをかいた。天井の電気を消すと、枕もとのぼんやりした電気をつけて、さあ、話してやるから、布団に入れ」
と僕に言った。僕はパジャマに着替えて、布団に入った。天井の板の木目のところに黒い節が二つあって、なんだか、目玉のようだ。
「竹やぶの中に入ったことはあるかい」
一度、お父さんと、山際の竹やぶに行ったことがあった。背の高い大きな竹がたくさん生えていて。下にはふかふかした竹の葉っぱが覆いかぶさっていた。そこで竹の子を掘ったのだ。これはおじいちゃんの竹やぶなんだよと、お父さんが言っていた。このあたりの山は爺ちゃんのものだそうだ。
「あるよ、竹の子を採った、お父さんが、葉っぱの下にカブトムシの幼虫がいるといっていた、それに、白くて奇麗な茸が生えていた」
「そりゃあ、絹笠茸と言って、茸の中で一番奇麗なやつだ、レースをかぶったようだったろう」
「うん、奇麗だった」
「竹の子も旨かったろう」
「うん、採ってきた竹の子を、焚き火の灰の中に入れて、醤油かけて食べた。おいしかった」
「そうだな、だけど、このお話は、もっともっと山奥の、大きな竹藪の中でのお話じゃ、孟宗竹といってな、日本で一番大きくなる竹じゃ、高さは三十メートルにもなる、隣の駅の前に出来た、マンションがあるじゃろ、あれほどの高さになる」
昨年、この地方では始めてマンションというものが隣の駅前に出来た。一度見に行ったが、見上げると雲に届きそうだった。だけど、山より小さいと思った。そこにたくさんの人が住むということだった。
「それにな、直径が30センチにもなる太いのもあるんじゃ、ふつうのもので直径が20センチじゃ、お前の頭が入っちまうほど太いってことよ」
「すごいね、だからかぐや姫が入れたんだね」
「そうだな、さてと、本当の竹取物語はこうなんだ」
爺ちゃんは話し始めた。
「昔々の話じゃ、あるところに、爺さまと婆さまがすんでおった」
ここまでは同じだ。
「ある日、おじいさんは、おいしい竹の子が食べたくなってな、朝早く籠を背負って、山を登っていった。いくつもの山を越えていくとな、とても大きな竹の林にでた。これは、きっと大きなうまい竹の子が出ているじゃろうと、竹の林の中にはいったそうだ」
「それが、孟宗竹というのだね」
「そうじゃ、それでおじいさんがその竹林に入ると、お日様が照っているにもかかわらず、その中は暗くて、寒いくらいじゃった。しかし、中に入っていくと、思ったとおり立派な竹の子の頭が顔をだしておって、爺さまは喜んで掘り出そうとしたんじゃ、ずい分長い間掘っていたのだが、なかなか出てこない。これはおかしいと思っていると、あたりは真っ暗になって、月が竹林の上にでてきた。あたりがどうやら見えるくらいの明るさだ。ずいぶん時間がたったものじゃ、大変大変。
爺さまは立ち上がったのだが、出口がわからなくなっちまった。さて、どうしようかと迷っていると、竹の間にボーっと白く光るものが沢山あってな」
少年はきっと、幽霊だと思った。しかし違った。
「爺さまは近づいてよく見た。すると、白い茸だった。竹林に生える茸で、さっき話した絹笠茸じゃ、あまり生えないので珍しいもので、奇麗な茸だし、とてもおいしいのだ。しかもそこの竹林のものはとっても大きくて立派だった。
これはしめた、里に帰れば高く売れる、と喜んで採ろうとした。すると、絹笠茸の中から声が聞こえた。
私を採らないでください。私はこの中で大きくなって、月の世界に帰るのです。月の世界では、私たちを待ち望んでいる殿方がいらっしゃいます。
爺さんははて、面妖な、茸の中に女子がいる。それで茸に話しかけた。
「月の世界で待つ殿御はどのような人なのだ」
「月の世界の王様のお子たちでございます、八人のお王子様が、私たちが大きくなるのをお待ちなのでございます」
爺さんは、月の世界の王様なら、さぞお金持ちだろうと考えたのだ、それで、この茸をとって、家に帰って、育ててみようと思ったわけだ。竹やぶの中より、竹やぶから出して大事に育てれば、早く大きくなって、月の王様から褒美がもらえると欲が出たわけじゃ。
それでな、まず一つ持って帰って、やってみようと思うてな、絹笠茸を一本ひっこぬいたそうだ。
それを籠に入れて持って帰るとな、婆さまにことに次第をはなした。それで、婆さまは器に水を入れて持ってきて、これに入れなされと差し出したんだ。立派な絹笠茸を水の中ににいれた。
すると中から声が聞こえた。
「竹薮でないと死んでしまいます」
爺さまと婆さまは水につけときゃ大丈夫と思って、そのままにしておいたそうだ。あくる日、起きてみると、器の中の絹笠茸は萎れていたそうだ。
それで、爺さまは、絹笠茸を半分に裂いてみたんだよ。するとな、死んで黒くなってしまったお姫様がころっとでてきた。
爺さまがどうしたもんかと、考えあぐねていると、婆さまが「水に砂糖を入れなかったのがいけなかったんじゃろ、まだ七つのこっとると言っておったじゃないか」と言った。
それで、爺さまはそれもそうだ、また一本とってこようということで、竹薮に行くと、また、一本立派な絹笠茸を引っこ抜いた。やっぱり、「連れて行かないでください」と中から声がしたそうな。
それでも、それを家にもって帰ると、婆さまの言うとおり、砂糖水にいれた。
しかし朝になると、萎びていて、裂いてみると、死んで黒くなった小さな姫様が転がり出てきたそうだ。
婆さまが、今度は塩を入れた水の中に入れるように言ったのじゃよ。それで、またとってきてな、絹笠茸を塩水につけて、一晩置いたそうだ。やっぱり、絹笠茸はしなびておった。黒苦なった死んだ姫様が三人になった。
こうして、毎日、採ってきた絹笠茸を酢を入れた水、味噌を入れた水、酒を入れた水、違うものに入れて、育てようとしたのだが全くうまく行かなかった。
「婆さま、あと二つだ、どうしよう」
爺さまが婆さまに相談すると、
「爺さま、きっと、砂糖と、塩と、酢と、味噌と、酒を全部入れればうまくいくべえ、二本とも持ってきてみろや」というものだから、最後の二本を採ってきて、全部入った水の中に舌してみた。
すると、次の日、二本の絹笠茸は枯れずにしゃきっとたっていた。
「婆さまうまくいきそうじゃ」
「それは良かった、二人でも早くお姫様にしてやれば、月の王様も喜ぶだろう」そう思った爺さまと婆さまは、毎日新しい水に取り替えて、絹笠茸を育てた。
確かに七日ほどたつと、絹笠茸が大きく育ち、ぱかっと割れると、中から金色の光がさしてきて、二人のお姫様がころがりでた。
まだ二人の姫様は小さいかったので、爺さまと婆様は大事に育てた。
それから、十日もすると、二人のお姫様は見目麗しい女性になり、かぐや姫と、かくや姫と言う名が付けられ周りに評判になった。
すると、その評判を聞きつけた、いくつかの遠い国の殿様が、自分の二人の息子の嫁に欲しいといって、爺さまと婆様のところに使いをよこした。
この辺の話は同じようじゃな。
二人の姫にそのことを話すと、かぐや姫とかくや姫は「月にかえらなければなりません」とその結婚話をこばんだんじゃ。
それで、爺さまと婆さまは、月の王様がどのくらいのお金をくれるものか、二人の姫に聞いてみた。
「月には金がありません、きっと月の石を二つ持ってくるに違いありません」と答えたのだ。
支度金をいくらくれるか遠い国の使いの者たちに聞くと、それは大変なお金だった。
爺さまと婆さまは、月に帰すと損をすると思った。
そこで、爺さまと婆さまは嫌がる二人の姫を、無理やり、たくさんお金をくれる二つの遠い国に送り飛ばしてしまった。
二人の姫を売ったお金を何に使おうか相談しているところに、金色の服を着た男がやってきた。
「月の姫君を受け取りに来た月の使者だ、お渡し願おう」
とその男は言った。
はて、爺さまと婆さまは、二人の姫様を売り飛ばしたとは言えないし、これは困ったと思っていると、ふと、死んでミイラになった六人の姫を押入れしまったことを思い出した。
それをだしてくると、月の死者に「姫様たちは、悪い病気に係り、このようになくなってしまいました」
と差し出した。
月の使者はおどろいて、涙を流すと、
「後二人はどうしましたかな」
と聞いた。
爺さまと婆様は「へえ、別の病で、溶けてなくなってしまいました」と答えた。
月の使者は、うなずくと、六人のお姫様のミイラを大事にかかえて、月に上って行った。
爺さまと婆さまはほっとして、十五夜の準備をした。お金も入ったし、ゆっくりと団子でも食べようと思ったのだ。
団子を食べながら煌々と輝く月を見ていると、月の表面から白い煙が噴出した。見る見るうちに月にあばたが出来た。
庭を見ると、二つの絹笠茸があらわれると、「嘘を申したな、許しておくわけにはいかぬ」と言う声がすると、ぱかっと割れて、中から、一つ目の赤と青の鬼が現れた。
鬼は爺さまと、婆さまの襟首をつかんで吊るすと、ぶらりぶらりとゆすりながら、山を越え、竹薮にやってきた。
「お前達は干からびるまで、竹の中におれ」
こうして、爺さまと婆さまは孟宗竹の中に閉じ込められてしまったのだ。
その周りに、また八つの衣笠茸が生え、八人のお姫様が中で育っていたんだ。
絹笠茸は爺さまと婆さまの養分を吸い取って、大きくなっていった。そして無事に八人のお姫さまが誕生して、月にかえっていったそうだ。
こういうお話で、最初は、茸と言う字を書いて、茸取物語といったんだそうだよ」
「じいちゃん、売られちゃった二人の姫さんはどうしたの」
「それがな、月からの使者が、その遠い国の殿様のところに返すように言ったそうだ、その殿様は賢明な人だったから、姫様が帰りたいといったなら返すという返事をしたそうな、すると、かぐや姫は帰りたいといって、かくや姫は、そこが気に入ったから居たいと言ったそうな、それで、かぐや姫は牛車にのって月に帰ったそうな。かくや姫は駿河という国に売られのだが、そこにはきれいな富士の山があったために、月に帰りたくなかったのだそうだよ、駿河と言うのは、今の静岡じゃ」
「ふーん、面白かったけれども、でもあんまり怖くないや」
そう言うと、おじいちゃんが立ち上がって、押入れを開けた。
「その話は千年も昔の話なのだがな、わしがもっている竹薮で起こったことなんじゃ、去年、竹薮の竹を切っていたらな、中からこんなもんがでてきたんじゃ」
爺ちゃんは押入れの中から、箱を取り出すと、
「みてみい」と中の物を見せてくれた。
それは半分に割った竹の中に入っている、おじいさんとおばあさんのミイラだった。
爺ちゃんを見ると、大きな絹笠茸になっていた。
僕は布団をかぶって、怖いようと言ったのだけれどもそのままわからなくなってしまった。
朝日差してきて、おじいちゃんが「ほら、もうおきな」と言っているのが聞こえた。恐る恐る布団から顔をだすと、おじいちゃんが笑っていた。
茸取物語(たけとりものがたり)


