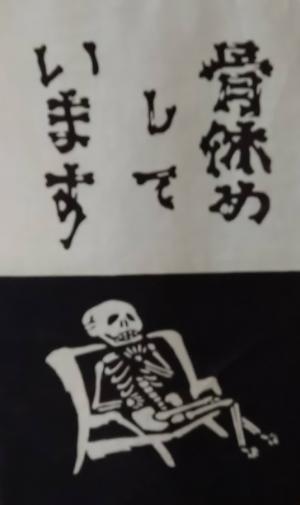才、極まる
かなり昔にWord上で書き上げたものをそのまま貼り付けているため、ところどころ読みにくい箇所があるかもしれません。申し訳ないです。このサイト、縦書きにできたりしないのでしょうか。
小説家、山村時代の才能は留まるところを知らないと噂されている。
「彼の中の文章には一点も曇りはなく、仮にそれがあったとしても、それは山村による意図的な曇りである。」と専門家たちは息巻いている、甚だ押しつけがましい評価な気がしてならないが、一物書きの私にも、山村の意図を組むことができるのだから彼の文才は本物なのだといえよう。
彼の小説をメディアは完成された世界観であると絶賛した。本来、小説というものは作者がその作品の世界観を形として完成されたものをいう。小説家に与える賛辞としては少々不適切な気もするが、不思議と彼の作品を読んでいると、「完成された」という言葉は確かに妙にしっくりとくる。
山村時代が二十三歳で芥川賞を受賞し、文壇に立ってから、彼の学生時代から書き続けられた作品たちが、次々と書店に並んだ。それらの売り上げは平均して百万部をゆうに突破した。マンモス作家の誕生である。当時、文芸雑誌のルポライターをしていた私が山村時代のインタビュアーに抜擢されたのは、彼が二十六歳の時であった。
何故私が抜擢されたのか、と混乱したのをよく覚えている。当然、私も山村時代の作品を読んではいるのだが、短編三作、長編二作ではとても彼のファンは名乗れない。私の勤める出版社にも山村の信者は大勢いる。そもそも読んだ長編の一作は山村信者の後輩から無理くり渡されたもので、インタビュアーに選ばれたときは心底羨まれた。
ファンにインタビューをさせるのも、問題があるのはわかるが、変わりたいなら、変わって貰いたいのが、当時の私の一心である。あのご時世ではとても言えたものではないが、私は山村時代の小説を好き好んで読んだことは一度だってなかった。はっきり言えば彼の作品を通して、彼のことが嫌いだったのである。断っておくが、私は世間が言う彼の才能がわからないのではない。しかし文学というものは最終的には波長の世界なのである。
山村のインタビュー担当を任命された夜、私は編集長に飲みに誘われた。そもそも件のインタビュアーを私に任せたのはこの男である。
焼鳥屋でつくねを器用に箸で串から抜きながら編集長が口火を切った。
「君はさ、山村時代の小説をどう思っとるんだね。」
この質問が予想できなかったわけではないが、いざ答えるとなると上手く言葉が出てきてくれないもので、私はたいそう口ごもってしまった。まだビール一杯すら空けていないのだから当然である。何一つ無礼講な気分になれない。
「快く思ってないだろう。今の彼のさ、ご身分が」
間髪入れず、
「嫌いだろう、山村のことがさ。」
あんまり一方的に無茶苦茶なことを言ってもらっては困る。脳が逆さまにでもなったのではないかと思わんばかりに血の気が引いていくのを感じながら、私はゆっくりと焼き鳥を置いた。平静を保つためである。そして軽い咳払い。「御冗談を」とはにかむためである。
しかしはにかむより先に、編集長が手のひらを突き出した。「まあ待て」のサインである。編集長は既につくねをすべて抜き終えていて、不思議なおちょぼ口でつくねを一つ口に入れた。そしてそのまま箸をくいっと自身の胸に向けた。
「私もだよ。」
ホーッと細い息を吐きながらのセリフであったため、少し聞き取りづらかったが確かに編集長はそう言った。察するに思いのほかつくねが熱かったのだろう。煙草の煙のようなか細い言葉だったが、嫌に私の頭を離れなかった。やはり煙草の煙のような妖しい言葉だった。
そこから先は長々と山村時代の作品で感じた不快さや、山村を神のように讃える信者たちの醜悪さについて存分に語っていた。酒も随分進んだ。山村時代を語るうちに今までぼんやりとしていた彼に対する嫌悪感がはっきりとしていく気がした。編集長の言う通り、私は彼を神格化する世の風潮に苛立っていたのかもしれない。
編集長もまた、彼の才能を認める中で、彼の作品は不気味であると繰り返した。
「あれはね、文学とは呼べんのですよ。奴は数年前に芥川賞を取って世間を賑わせたが、厳密にいうとあれはね、違う。奴は芥川賞を取ったのではなく、取らせたのだ。」
今一つ編集長の言葉が呑み込めない私をよそに彼は続けた。
「山村は『蛇行』を書いた瞬間から、これが芥川賞を取ることが分かっていた。その為に文を構築し、物語を考えた。審査員の好む形に完成させたのだ。新人の花道である芥川賞受賞でこんな流行作家のような事をされたらば敵わんではないか。審査に当たった作家どもは何も気づかない。『いい作家を発掘しました』とでも言わんばかりのしたり顔をしているのが何とも哀れで、滑稽じゃないか君。」
私はやはり編集長の主張が今一つ理解できずに、それでも「この男をしらけさせてはいけない」という一念で必死に返事をひねり出した。思い返してみるに、この時の私は上司の接待というよりも、初めて出会った反山村時代派の人間との会話を円滑に進めたかったのだろう。そのためなのか、この時の私の言葉は馬鹿に鮮明に覚えている。
「山村はつまり、いわゆる己の主張だとか自分のこだわりだとかを掲げてないということですかな、自分の作品に」
奇妙な倒置法を使い合わせてみるが、編集長は首を振らない。
「それは分からない。だが私も君とは同じ意見だ。中身があるのに無いように感じる。山村が作る世界観には。」
倒置法。口調は以前のように強い調子の冗談じみた様子だがこの時の編集長はどこか悲しそうな眼をしてお猪口の中の自分を見ていた。
「しかし編集長。彼の完璧で計算されつくした作品が嫌にカルト的人気を得ていても、やはり我々のようにその作品に踊らされない者もいるではないですか。」
編集長を沈ませまいと口走ったものの今思えば大半の反山本勢力は、あるいは我々も単なる逆張りに過ぎなかったのかもしれない。この時の私は小説にどこか泥臭い一匹狼のような生意気さを求めていた。大衆に迎合したものが悪く、自分だけが作れる孤高の世界を作り上げたものこそ至高。というほど極端には凝り固まっていなかったが、俗にいう文学的世界には波長という不確かなものがあり、その薄い線で紡いだ感覚だけの才能がある。こう信じていた。
編集長はそんな私に一目もくれず、呟いた。
「えらく楽観的だな。」
「はい?」
「私もそう信じていたい。彼の作品をこうしてけなしていることが、私自身の意志であると、しかし私にはこれすら彼の才がなせる業に思えて仕方がないのだよ。君、考えてみてくれ。流行りものについていく者がいる。それに逆らい、いっちょまえに作品を批判する者がいる。陽と陰。これは世の常ではないか。山村は自身の才能で陽を作ったと私は述べたね。彼の受賞する賞は作品を生み出した時から、端から狙い撃ちされたものだと。私はこれと同じ要領で奴が陰を作り出している気がするのだよ。」
編集長の口調にずいぶんな熱がこもった。一方の私はというと編集長の辻褄が合っているのかどうかすら怪しい説に次第に苛立ちを覚えてきた。
「しかし、文学というものは波長の世界でしょう。それだとまるっきり洗脳になってしまう。我々の波長が合わないことすら彼の計算なのだとすれば、彼を毛嫌いするものはみんな似た感性を持っていることになってしまいます。」
「君は山村時代が怖くないのかな。」
「怖がる道理がないでしょう。奴は単なる流行作家にすぎませんよ。ここまでの流行っぷりは初めてでしょうが、若者が見るアニメやら映画やらでは度々社会現象みたいなものが起こっているではないですか。」
「やはり君に任せたのは正解だったようだ。同じ山村嫌いでも君と私は捉え方がずいぶん異なる。」
そこからは他愛のない話ばかりでどこか盛り上がりに欠けながら飲みの席は終わった。山村のインタビューが終わってからもしばらくここで働いていたが、最も編集長と密着した時間だった。しかし距離が近いばかりで私たちの会話はどこかすれ違ってばかりだった。
山村のインタビュー当日。私は自分が嫌になるほど高揚感を覚えながら、会場に向かった。その道中、山村の新作を宣伝するポスターを見かけた。「山村時代 最新作」の黄色い文字の横であごに手を当ててあらぬ方角を見ている山村。私は苦笑した。インタビュー直前にもかかわらず「やはり私はこの男が嫌いだな」ともう一度鼻で笑いながら、あごのひげを撫でた。
妙な緊張感を与えてくる長机の前で山村を待つ。私たちが座って間もなく、山村が入ってきた。
特徴のない目鼻立ちに額と耳を覆う程度の黒い髪、茶縁の不格好な丸眼鏡をかけてやんわり頭を下げる山村はどこまでも普通の男だった。あごに手をかけていたポスターの山村の方がなんというか、らしかったかもしれない。あえて作家で表すならば堀辰雄に近い雰囲気であった。
つつがなく始まったインタビューはつつがなく進み、つつがなく終わった。何もないならないに越したことはないのだが、やはりどこか拍子抜けした気分だった。数十分ほど前までやたら斜に構えていた私が何となく間抜けだ。
インタビューを終えた私は拍子抜けした気分のまま山村と共に席を立った。行先は喫煙所である。山村が喫煙者だったのは意外だった。予期せず二人だけの空間が出来上がってしまった。
突如訪れた沈黙の空間に耐えられなくなったのは意外にも山村の方であった。
「私の新作ご覧になられましたか」
インタビューの時と同じ、ゆったりとした口調だった。
「ええ勿論。素晴らしい作品でしたな。」
私は執拗にうなずきながら返した。うなずきながら、私はここまで明るい声が出せるのかと内心驚いたのをよく覚えている。私はこの時、山村という男をたった数十分のインタビューですっかり侮りきっていた。今まで彼に抱いていた嫌悪感や苦手意識は晴れ渡るように消え失せ、私はとても安らかな気持ちで彼に幻滅していたとでもいえば適切だろうか、とにかく私は初めとは全く異なる高揚感を抱いていた。
この感動を終わらせまいと私は続けた。
「ボキャブラリーの宝庫ですな。あなたの小説は。深く繊細でまるで本が映写機になって読者の脳に映像を直接映しているようですよ。」
ここは読者ではなく私たちと言った方がよかったか、などと考えながら私は内心ほくそ笑んだ。
「あんまりほめてやらないでください。」
と、山村はおどけるような声色で苦笑した。
そして「あんまりねぇ、あんまり」とぼそぼそ呟いていたかと思うと突然、ポツリと「映写機ですか」と小さくしかしはっきりとした声で言い、下手くそな愛想笑いのままこちらを見つめた。
その時私の中にあった幸福感にちらりと影が差した。微笑む山村の中にただ事でない何かを感じたのである。
晴れ渡っていた私の気分は一転してもやもやとしたわだかまりに侵略された。おそらくこのわだかまりのようなものは山村のインタビューを開始した時から私の心のどこかに存在していたのだろう。急に現れたというよりもシミが広がったという感じだった。
「本条さんは私に世間で言われているような才能があると思いますか。」
山村の言葉に私は内心大いに動揺した。勝手に優位に立ちそして勝手に立場を逆転された。返事には少し間が開いたが、表面上は涼やかに見せることができたと思う。
「まるで自分には才能がないなんて言い出しそうな口ぶりですな。私のような半端なものが語ってもあまり参考にはならないでしょうが。近年見た作家の中では確実にトップに位置するベストセラー作家ですよ。何より世間がこれを証明しているじゃないですか。」
半分以上本心からのセリフなので、つっかえずにすらすらと口にすることができた。
「そう言っていただけると、作家冥利に尽きます。しかし私は時折、本当に私が自分の意志で小説を書いているかどうか不安になるんですよ。勿論ゴーストライターを使っているわけでもないですし、自分には才能がないと嫌味な謙遜をしているわけでもありません。ただ、小説の中に自己が見当たらないというか。自分と自分の作品がリンクしないんです。」
山村の強い視線と言葉に私は何も返すこともできず、相槌すら忘れてただ呆気に取られていた。このキツネにつままれた感覚は編集長との飲みの席のことを思い出させる。
山村は続けた。
「あなたは先程、私の小説を映写機に例えてくださいましたが、私の中では自分の頭こそその映写機なのです。いえ、やはりここでは自分の文才と言っておきましょうか。小説を書くためにプロットを書くでしょう。本文をキーボードで打つでしょう。その時の私の頭からは次から次へと文章が、まるで流れるように猛スピードで構築されます。その速さについてこそいけるものの、本当に自分がこの文章を考えたのか不安になります。言っている意味が分からないという顔ですね。そうでしょう。私自身この思いをどんな言葉にすればいいか、困ったことにこんな時には私の文才は生かされないようです。正直な話、私は自分の中にもう一つの人格か何かがあって、それが私の頭に文を流し込んでいる気がするのです。」
山村は尚も強い視線で私に己が苦悩を打ち明ける。
「いわゆる多重人格者ですか。」
そろそろ何か返さなくてはまずいと判断した私は、とりあえず唯一理解できた部分で話を合わせることにした。とんだヤニ休憩である。
「私もそう思いましたが、しかしあくまで、それは執筆にのみ現れて他では一切存在感を出しません。それに先程自分と作品がリンクしないと言いましたが、確かに私の書く小説はどこかで私が思い浮かべた出来事やどこかで知りえた知識が用いられているのです。おそらく私には皆様が言うような秀でた文才があるのでしょう。しかしその大きすぎる才能は私の意識下すら超越してしまったのではないでしょうか。」
「それならいっそ、本を書くのをやめてみてはいかがでしょう。」
咄嗟に出した私の提案は今思い返せば、お得意様に対してあるまじき暴論である。
「ごもっともなご指摘です。しかし私は中学に入ったころから頭の中に気がどうにかなってしまいそうな量の情報があふれだしてくるようになりました。そしてその情報の唯一の発散方法が小説を書くことでした。それにおそらく世間は私が小説家をやめることを止めてはくれないでしょう。私はもう自分の文才から逃れることはできません。」
私はどう返せば山村の心労を癒してやれたのだろうか。曖昧な生返事ばかりで、気の利いた言葉など思いもつかない。そんな私を察してか、山村は煙草を捨てながら私に言った。
「あまり深く考えなくて大丈夫ですよ。こんな話に付き合っていただいただけでも、十分ありがたいことです。それにこうして話していると私の中のわだかまりが小さくなっていくように思えます。私の立場上、あまり精神科なんかに行くのも難しいですからね。本条さんもどうかこのことはご内密にお願いします。そういえば何故、私は本条さんにこんなことを話す気になったのでしょう。初めて会ったのにこの人なら話を聞いてくれると思ってしまったのかもしれません。」
それではと会釈して、山村は喫煙所を後にした。私は今回聞いた山村の話と、居酒屋での編集長との話を交互に思い浮かべながら、ガラス越しに映る山村の姿を改めて眺めた。彼は作家特有のノイローゼのようなものを抱えているのだろうか。もしくは何か超自然的なことに巻き込まれてしまっているのではないだろうか。インタビュー時と比べ、心なしか晴れやかになった山村の顔を眺めながら、私はまんざらでもない心地でもう一服した。呑気というか単純というか、山村の弱みのようなものを知りなおかつ彼の助けになったことに私はすっかり得意になっていたのである。
そこから私は山村の作品を追い続けるようになった。あの日の山村との約束を律義に守り、一切の他言をせず、彼の作品をとことん読みふけり山村時代の世界に入り浸った。彼の完璧な文章を読むたびに、彼はいまだに自分の文才に手をこまねいているのかと思うと、以前の不快感など影も残さず消え失せていた。
しかしこの時の私には少しの疑問があって、それは去り際に山村本人も抱いていたものだったが、何故山村は初対面で、それでも山村側の人間であることには違いない私に件の話を聞かせたのであろうか。精神科医は無理でも恋人や友人なんかに話せばよかったのではないだろうか。
この問いに対する明確な答えは今現在も出ていないが、疑問を抱き始めたころの私は、単なる気の迷いであろうという、彼を侮り切った答えにたどり着いていた。自分が文学の波長というアバウトな概念を信じていたのに対し、山村に対しては愚鈍なまでにリアリストだった私は、せっかく打ち明けた彼の悩みを全く理解していなかったのである。
今現在、私が導き出した仮定の結論は、全て山村時代による計算だったのではないか、というものである。「山村が」の可能性もあるが、彼の言葉通りに解釈すると、「山村の文才が」である。編集長の受け売りだが、山村は選考委員に芥川賞を取らせるように作品を仕上げた。これは山村の作品によって他者の行動が決定させられたということでもある。私が言う山村による計算とは、出版関係の人間に(しかもごく少数に)本能的に山村を受け付けられない人間を生み出し、さらにその男に山村のインタビュアーをまかせ、山村が例の話を打ち明けられるようセッティングしたのである。何のためか。これまた推測に推測を重ねることになるが、主人である山村の抱える不安を拭いたかったのではないだろうか。
というのが、私が今現在、導き出した山村の謎の答えである。何故、こんな超自然的な仮説を立てたのか。それは山村が自身で己が文才で人を操れてしまうことを証明してしまったからに他ならない。
それはインタビューから五年と二ヶ月が経過したころであった。なおもその人気を揺るがさず文壇に君臨し続ける山村が、唐突に自身の半生をそのまま小説に仕上げたような作品を発表したのである。タイトルは『壊れゆく才』。発表からいたるところで大いに取り上げられ、宣伝されたその作品は他の山村作品と比べても頭一つとびぬけた売り上げを記録した。私はというと、山村のインタビュアーに返り咲くことはなく、単なる一読者として山村の活躍を見届ける形になった。発売当日に新作を購入した私は、その日中に読み上げてある得体のしれない不安に駆られた。作中では最後に山村を模したであろう主人公の小説家が、絶頂の中で非業の死を遂げたのである。睡眠薬を過剰摂取し深い眠りにつく主人公。作中で彼は自身の中にある深い絶望から解放されたような心地で一生を終える。
山村の完璧な文章で儚くも壮大に描かれたその死は、私を含め、様々な読者の心を打ち付けただろう。そして発売からおよそ四週間が経過した午後二時四十三分、山村は路上で暴徒に刺され死亡した。暴徒は熱狂的な彼の信者であった。
山村の急逝を受けて、私はようやくあの時感じた不安の正体が分かった気がした。その正体はまるで山村からのメッセージのように作品からあふれ出ていた。
「どうです。本条さん。私の文才がなせる業ですよ。」
そんな山村の声が聞こえた気がした。
この一連の騒動は山村が仕組んだことなのだろうと私は思う。山村の文才がなした業には違いなくとも、今回の計画の根幹は彼の意志にある。つまり今回おそらく初めて、山村は自分の意志で自分の才を使用したのである。これは文才から逃れるための大掛かりな自殺なのだろうか、それとも彼と彼の文才の激しい闘いの結末なのだろうか。
山村の死から十五年が経過し、彼の存在が時代の陰に消えた今日に、私が書き上げ人知れず公表したこの文章は、おそらく誰の目にも止まることなく、海のような情報の中で藻屑になるだろう。それでも私に残す以外の道はない。山村時代の才が極まったあの日の出来事を。
才、極まる
特に参考にした作品
『怪、刺す』原作:木原浩勝 刺し絵:伊藤潤二(竹書房) ※タイトル