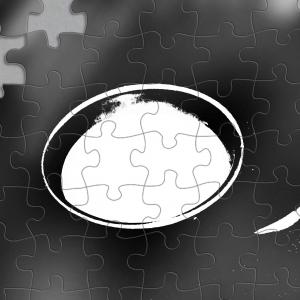「国王ノ涙」
一
雪野原。たゞの、たゞの、雪野原。
風は芽吹きの前に現れて、眠る哀しみを撫でてゆく、吐息のやふな気まぐれは時雨時雨に優しくて、首をもたげた白蛇は紅い宝玉の瞳を開く若葉のめざめ、その尾が浸る湖面には炎の椿が白く咲き、ポトリと別れた一輪が鏡に落ちて月になる、搖らぐ雪花はほつりととけて天上を仰ぐ祈りの光ひとツふたツ水の星、星の瞬きに恍惚と白無垢の祈りを捧げるよう、地に襲した白練菊は氷の指を水面に溺し、黒曜石の瞳を閉ざして雪の肉体の蛾搖らめき陽炎みたく澄み透りては憂ひを含むだいつくしみ、瞼を開けた無邪気のはしゃぎにも夜露朝露は微笑み給ふ。
雪野原はたゞ在った。ずっと先も、ずっと今も、ずっと昔も。面影はもうどこかへほつれたのに、土の削られないことを面白く笑ってすきますきまに菫が咲く。
あの紫が、何かだれかを連れて来まいか、危ぶんだところでドームを失った廃教会はかえって日輪の歌に輝くが。陽の雫なら雪溶けがある。一ツも一ツも来なけりゃいい、凪に誰が石を投げる?玉石混淆など口では容易い。
もう訪れることの無いステンドグラスに咲く花は、いつかの赤い薔薇を罅に朧に想い出す。それをなぞって滴る雫は五月雨の青葉を今かと待ちて蝶々の休まる紫陽花の頃を慕ふやふ、ほとり零れた白露は林檎の花を取り次ぐか、ほのかに甘い不思議な泪、優しさ故か或いは逆に残酷か、羽に問うてもきっとゆっくり微笑むだけで、其方は草花此方は雪花、青々とした新緑の候を何も知らない。
産声をあげた記憶は勿論ほどいて、ゆるやかな毛玉の先は普段ならば温かい。けれども知るのは水の体温畔の夜中、湖月の灯火かすかなカンテラそればかり。人に心を開いたことも無いからか、拾ったリボンをどうすれば良いかも分らない。
「人を捜しています。」
何故この貼紙はびらびらと風に残っているのか。文字ばかりが浮きだって誰かの顔は黒く焦げていて崩れている。崩れ始めたのは飽きるほど古い書物の記録の時、一気に焼け落ちなかったのは未練と云った恋のため?堅牢な城は大地にかえり、白い屋根たちは水の底、太陽と月のいたずらのやふな不憫なやふな純粋の瞳交わせぬ恋のため?竜と人なら物語も探せばあろうが城と人とはついぞ聞かぬ、笑いに付していいものか?
リボンの行方も城の本懐も知らぬまま、ステンドガラス越しに雨を見る、月は迷わず空にいた。
どうして迷わずに在れるのだろう、佇むだけで少し歩こうとすればたちまちに眩暈はひとしお強くなるのに、たゞ在るだけの雪野原は白面の裏に何を隠す、秘密のくちびるが口遊めば春の小川に、呵々大笑の豪雨の夏、笑い過ぎて疲れたろうに蜻蛉へ託して深い眠り、冬は目覚めている筈なのに、何故に面をかむり始める。
「人を捜しています。」
焦げている。
ヒントは其処?
けれど文字ばかりで誰を望んでいるかも分りゃしない。のにこいつは塵にならないのならば、頭の白紙に文字を描く。
「だれ。」
風がまた緩く吹いている。
二
バラけた財布はそのまま放っておいた、埋れたボタンは拾ってリボンと同じ、小豆の砕けて零れるお手玉も拾って見る。拾って拾った拾ったところでどうすればいい。
夜明けの夕暮が近いのか、雪は雨へと溶け始めた。黄昏と言えど陽は陽、少し体温が高いだけ、丘を歩くなら今でも良かろう。
眩暈は軽いノックのように。いつもいつも貼り付いて、居留守の恐怖がじわじわと増して息荒く胸は冷たくなるように。
折られた誰かの杖を取る、持ち手の飾りは粉々になって、金の甲羅の亀だった。
歩けど止まれど空は夕暮れ、淡いベエルがかぶせられる。そのすきまから今度はすみれにあらず茜さす、薄花桜の樹々があふれる鳥居の宮のすぐ近く、ひよ鳥の落とした鈴が地面に。親鳥であろう片目潰れた紺青の羽毛を身一杯に震わせて、嘴から可愛い声でしか悲鳴をあげられないでいる…
あまりに哀れ!血を吐くほどの心配も耳には囀りとしか届かぬなど!
お手玉、お手玉の布はやわらかいから鈴を磨いても傷付くまい、小豆を鳥は食べるだろうか、聡い子たちだから置けば判別つけられよう、リボン、リボンは、リボンは、あゝ、リボンはその傷痕には沁みないだろうか。どうか雨がやさしくありますように、雪のかみさま。
雨をはじく羽毛はしっとりと夜明けの雨に濡れ、鈴はひよ鳥へと戻された、落ちつけたのであろう、親鳥は深く息を吐き出しているような。リボンを巻こうとほどいてみれば、紺青が緩く首を振る。手に握ったまま少しずつ力を抜き、放り投げた杖をそのままに目を閉じて体を横たえる。
花冠を編む
野の白露は光を滲ませている
晴れているのに雨が降る
とおい螢のやうな手に取れぬ雨
握ろうとすれば掌をすり抜け
抱きとめれば溶けてしまふのに
光の束の花々は
おだやかな手に紡がれている
頬に柳の雫散る。花は霞に陽に溶けて、目を醒ましたら夜の月、鳥の眠りを起こさぬように、杖は見捨てた。
三
丘を下りたら路面電車、動かぬまでも足の疲れには心地いい、昔吹いた蒸気の名残か、此処にも白露がほろほろと、雨は既に止んだようだが物は雫を感じるか。屋根につらなる藤花の氷、蔦は天井の壁画となって氷柱を留める、燃える怒りを冷ましながら我身を焼いて剣をなだめる、睨む瞳に水の膜、眼を傷めぬようにと肉体が泪を湛えさせる、一つならず藤の花、とぐろは巻けぬまでも毒を降らせて刺し貫くは容易そうな苛烈の硝子、罅は油断させるための羂らしい、色はあれども色ざめた奥、待ち向かえるは薄氷の鏡。
眩暈も忘れて立ち尽くす、それだけを今望まれる。許せぬを氷の炎で焼き尽す、歪な花粉が咽を締める、今か今かと待ち構える、言葉は此処に意味を失くす、想いは此処に首を断たれる、それだけを今望まれる。どうして氷柱に触れよう、どうして蔦に頬ずりを。
藤のかほりよくしみた手袋は片手分しか床にいない、きっと片方は奪われた。拾ってリボンの手に握る。鏡は遠く過ぎ去った、眩暈を連れて来るやうにドアが開く。回送中の紅い字は、雪に埋もれてもなお紅い。
四
倒れた壁に頭を軽くぶっつけた、懐かしい眩暈が夢に誘う。
寝てしまえ
寝てしまえ
明日もきっとどうせ黄昏さ
起きて野原に降りないか
夜中の植物長い睫毛はらはらしずく
咽を求める生温い手を屹と睨みつけ形見の守り刀で斬りつける。
眠っていようが目覚めていようが空には陰陽が晴れに咲く、雲の上の御心が失われることは無い。思わず激流が心臓を燃やし腹を燃やし脳裏にひらめく白刃が目先の甘えを叩ッ斬る。進むことの幸運と戻ることの幸運を想う、かかしとて昔は風に笑って搖れたろうに、頭は砕かれ胴は折られて、土に帰りたがっているのだろうか帰れるだろうか人の手で、人の手で生み出された君は、友よ。
佇むことしか望めぬ身の、人捜しなど滑稽な。
人捜しなど滑稽な、人のいなくなったこの国で。何故城は崩れずに残ったのだろう、王のいなくなったこの国で。人が何だろう王が何だろう、どちらもいつの間にか作り出されて要らなくなると見捨てられて、勝手放題にされてしまう、無力を許されることもなく挙句の果てに我が身の所為。
私が何を為したのだろう、何も出来なかっただけではないか。息をするのも潜んでいたつい近頃を思い出し、親指の付け根をガリと噛む。
有無とも言わせぬまゝに作られた身に誂えのマントが肩に縫い留められるを拒みもせで受けとめた、失うまでの数年間に人の記憶はあまりにぼやけ輪郭を消された夕日影、想い出せるは景色だけ。
雪原の胡蝶とまがう麗しの蛾はほっそりとした頤を襟巻にうずめ、嘆く唄声さみしい旋律、鱗粉に慕う想いを託して花びらと舞い、白蛇はヴィオラとリュートの悲哀をうたうその瞳、その瞳は薄い硝子の面影を知るも憤怒を知らず嫉妬も知らず、穏やかな風がそっと教えるかなしみを指折り数えたいじらしさ、喜びも悦も満足も愉しみも楽観も知らないらしい、湖面のかなしみを一心に見つめるそれぞれの瞳はビイ玉よりも鋭くて硝子よりも薄く固い、水晶体に映るのはいとしの雪野原、物を言わぬ身には何も言わない優しさを、言葉を失う無力には何も言わない優しさを、この国の雪野原は在るだけで生命を恵み慈しみで抱きとめる、湖も花々草木も白い哀れみに照らされて光は染みつき影にも優しくあろうとする。
あまりにあわれ……その健気、きっと触れれば溶かしてしまう。
五
「お花を一つくださいな。」
幼い声が赤い花をねだる、その手に銀貨は握られていない。
「どうぞ。」
それでも微笑み給ふ。唇と瞳は柔和に細められた三日月のよう、柳眉はしなやかに明るく開く。光に愛され暗がりをも優しく撫でるかの慈しみ、幼い声は身一杯に輝きを恵まれ走り去った。
戻らない駆け足、黄昏前の月の夜、徒らに覚ました眼には夜露が滴る。微笑みのいつかの記憶は何回目の時のものであったろうかと思い出せども想い出せずたゞひたすらにつのるのみで。
桜の下で生まれた時か
鳥毛に守られ生まれた時か
蝶々に歌われながら生まれた時か
雨の月夜に生まれた時か
花に絡まり生まれた時か
遠くにオルゴールを聞きながら生まれた時か
羽衣に静かに松へと降ろされて生まれた時か
小川に半身浸して生まれた時か
木の実のなる大樹の影で生まれた時か
城壁の外で生まれた時か
いつでも聖なる守り手が澄んだ瞳で此方を見つめ続けてくださった、雪原の獣と雪原の蟲、触れるも恐れ多い精錬のうつくしさは言葉を尽くすも憚られる…
雪野原。たゞの、たゞの、雪野原。
傷だらけの無力な手を胸に強く押し当て歯を喰いしばって蹲る。
守らなくてはならなかったのに。私は国を守らなきゃいけなかったのに。
六
息を切らせど許されぬ
王になれなかった兄は私を嫌った。
兄の持つ筈だった力を私に与えた父は笑って頷く
お前が王になるために兄は生きているのだと
愉快に笑って
感慨深げに悟って父は頷く
母はうなだれて私を見ていた
ロクでもないものばかり学んでと怒っていた
兄は父を刺し殺しそうな目をしていた
父は私に与え続けた
母は嫉ましの目で私を否定した
本が一冊も燃やされなくてさいわひ
紙は夜露に濡れて朝日に乾き、頁たちはぽつぽつと歪んでいたけれど、小鳥の目覚めの羽ばたきの音に樹々の葉は木漏れ日をのぞかせ髪をくすぐる気まぐれうさぎのような風を呼ぶ。崩れた場内で寝ていても、ヒソヒソもコソコソも聞えない、足音はよく透るけれど誰も振り向く者もない、息はしやすいけれど空気は冷たく、かえって星々がうつくしい。
涙があふれるのはきっとお恵みであろう、いつの世も絶やされなかった天上の哀しみを取り次がせるための。
折られたかかしを鏡中に見て、友よと一言呟いてみる、振りかえらなくてはいけない、自分の記憶を覚えてなくても。忘れられたくない寂しがりはあの手この手に化けて縋り泣きながらすゝり泣いて歩いて来る、夕暮の迷子の幼いように、捨てられた赤子の泣くように、その苦しい戸惑いをいたましい泣声を抱きしめたくても抱きとめられない、過去は全て奪われてしまった。想い出せば罰であろうに眩暈は激しくそれを許すことを禁じている、けれども私は逆らわなければ、あのうつくしい国を言われるがまゝに忘れるなどとあまりに哀れ!罅の硝子格子から雪原を見る、清く冷たい聖なる野は、血のように混じった赤い薔薇を咲かせていた。
国は滅べど国は滅びず、泪もやがて湖へとゆけ。
七
震えて夜具を引ッ被る。父が話している、母が恨んでいる、兄は憎んでいる。息を殺して寝たふりをする、そうすればよく本音が聞える。
希望を持っていたのだろうか、母に抱きしめられる夢、母に褒められる夢、母が傍に居てくれる夢、夢、夢を。
報われると信じていたのであろう、兄の笑顔、笑いごえ、年甲斐なくはしゃぐ姿、楽しい嬉しい願いの姿となって。
父は私を可愛がった。王の教育を受けるべき兄を退け私を玉座へ置くと、朝日のマントと白昼の王冠を誂えさせて、夜が来てから身につけさせた。
月が伏せて日が瞬く、噓つきの白夜がやって来て、夜を失ったこの身と世には、誰が微笑みくださるだろう?怯えた小指をそっと両手で握ってくださる、やさしい指きりげんまんをいつも約束してくださった暖かな記憶の泉の源泉はどなたであったろう?いつも必ず抱きしめてくださった、あの鈴の音の温もりは何処で逢っていたのであろう?
「人を捜しています。」
城よ何を憶えている。寒さに耐え続けた記憶ばかりではないだろう?悲しい貼り紙は誰の顔?どうして君は今も待つ、此処に戻って来るからでは?
「それなら待とう。」
少し咳込み城内へ。空気が冷たい冬の澄み、肺にひやひやと心地いい、息を深く吸ったって咎める人はもうこの国には一人も居ない、虚ろな微笑み、きっと今はそんな顔。
淡い水色の廻廊に腰を下ろして白詰草の霜降る真緑の上、天井も窓も割れてはないのに、白い雪は何処から来る。
この白い毛糸をあげましょうね
あなたにはきっと似合うから
ほら編み棒はこう動かすの…上手よ、上手
ゆっくりでいいわ焦らなくっても
首を冷やしたらいけないからね
此場所は雪が降って少し寒いけれど…
でも不思議ね見て御覧
すみれも咲けば
赤い薔薇も咲くし
桜の雫もはらはら降る
紫陽花桔梗白百合もいて
白詰草は歌うよう…
氷の地面なのに土なのね
ほんとうは氷も温かいのかしら
でなければ樹木なんて生きられないもの
幹も葉もほら、あの色
日が沈む前の夕暮が
過ぎて月夜とのあわいの色…
あの色はなんて呼ぶか覚えている?
薄花桜の天井はやっぱり割れていなかった。扉も窓も閉めたのに、雪がとけて水となるのを止められないのと同じように、この国の雪は止められる。
色が白く色づいてゆくも、氷の地面は何も言わない。大広間に座す純銅の大時計だけがゆっくりと頷いて。
鐘の音も雪野原には届くまい。
八
廊下を歩いて外に出る、扉はもう重くはなかった。鉄はヒヤリとしているけれどその冷たさすら怯えて火照った手には心地良かった気がする。
支配するのだと父が言う。雪野原をもこの国で支配すれば善いのだと、その任は大任であった、だから母は兄が実行するのを期待して、私をひたすら憎んでいたし、兄は誇りを求めていたから私を恨んで罵った。城の中のぬくもりは何のためのぬくもりであったのだろう、私はずっと期待していた、雪野原が語りかけてくださることを。
白い鹿が水を飲み、翔けるようにかろやかに地をゆく。その姿は人ではない、たゞの、たゞの、うつくしい獣。白百合の花弁借りながらも、その薫りは奥深い森清らかに纏いたる薄絹の羽は何人足りとも殺生を許さず月の如き目差しで空気を食べては夜空を生み、やさしい檻籠で導き給ふ、翔ける、翔ける、白い鹿、幾度も幾度も本を読み返した、心あらずでナイフを握って腕を傷つけた牡丹の日も。
責めも嘆きも震えもせず、消毒液の眩暈の匂ひと白いガーゼの絆創膏、手当されたのは白昼誰も居なかった日の、白詰草の側だっけ。
……包まれていく、包まれてゆく、白い記憶が曼殊沙華のように花開く、ぽつりぽつり、雨の雫の糸の切れるやうに哀しみが記憶に蓋をする。
思い出さなくていいと言う
想ふほどに哀しみの気配がする
声をかけたいと願えども
あなたは耳を押さえている
忘れていい
忘れていいのだと涙が言ふ
拭う指が嫌だと叫ぶ
震えるくせに叫んでいる
幼い否定にまた微笑みなさる
けれどどうして笑っておられる筈なのに
微笑みはどこか泣きそうである
歩きながら寄り添う夢というのは、涙を零させる。一人寝室で溺れた悲しいだけの疼痛とは違って、憂い慰めの痛みが心から藤蔓みたくからまって、喉を穏やかに絞めつけるから嗚咽がひたすら呼吸と共に漏れ続く。忘れるべきがどうにも忘れ難く、心の裏面から縫止の糸を抜けないでいる。どうして忘れた方が良いのだろう、忘れてくれなど望まれる、身を切り裂かれるのは私だけではないだろう、彼方だって、あなただってそうでしょうか、死ねと告げられた者ではなく、死を告げた者も哀しみは如何ばかりか、互ひ互ひの苦しみなど、到底推し量れないこととは分ってはいても…
「人を捜しています。」
この祈り声は誰のため?城は切なく無言で佇むばかり、雪野原は待つばかり。
九
氷の地面に接吻をする。あなたが与れた記憶には、氷からも花が咲くのだと聞いたから。赤い薔薇に跪きその根元の氷に唇を捧ぐように食んでみる。
ほわりと温かいふくらみが、私の心をかろく押し返した。続けて小指で触れてみる、感覚は唇と似ていたが、人肌を恐れているかのように小刻みに震う。薬指、中指、人差指、ついには左手全体で包み込む、怖くはないか、嘆かないか、臆病の問いに薔薇は応えない。たゞ無言で私を見つめるだけで、恐怖も寒さも教えない、教えないが柔らかな棘で薄い掌を鋭く刺す。
血がしたゝる。一滴、二滴、細糸一筋の流れになって、泪を零す紅い色。
スッと地面に沁み込んだ。水を吸えない氷の中に。思わず立ち上がり行方を見ようと薔薇から離れ駈け寄った。
血の線は白蛇の舌を思わせるが、やがてくるくる纏まり玉の形は紅い宝玉、ハッと後ずさりぬかづこうとするも既に遅し、氷にそのまま埋もれたようにもはや両足は動かない。
立ったまゝ白蛇に仰ぎ見つめられていたが、やがてきょろりと空を見向く、連られて従い空を見るも、変わらず雪が舞うばかり、楽しそうに、はしゃぐように、生れた時から見つめ続けたいつもの雪が白く踊る…
「本当に?」
耳奥からの響きに蛇の瞳を見る。
「見てばかり。本当に?」
目は見るためのものではないか。
「ならば閉じてしまえばいい。」
どうやってそれで人を捜せと。いない者を目を開けずにどうして捜せる。
「本当に?」
いないと言っているだろう!
「いないの?」
肩をそっと叩かれて、ハッと冷たさにあとを返せば、薔薇が白雪にまぶれるばかり。その雪は
ちっとも嬉しそうには感じられなくて。
十
踊っているように見えていたが、舞っているように見えていたが、降る雪はただ哀しかった。人肌を求めた無垢な心が、実際には耐えきれず溶けてゆきあとには泪しか残らない。体温を持たない植物や建物に雪が積もる姿は、人恋しさに友と哀しみを分かちあうかのよう、身をひしと寄せあってはさめざめと泣く切ないいぢらしさを想はせる。
「いないのか。」
捜す人は、
「見えないから、いないのか。」
いたのだろうか、傍に、見えていなかっただけで、この記憶は、捨てろと決めつけられた記憶は、雪野原のあなたは、
「やっと気づいた。」
十一
始まりは城の外でした。その日は珍しく雪が一粒も降らない日でした。私が城内での務めを終えて、家へ帰ろうとしていた時、あなたが小走りで駈けて来て、花をねだったんですよね。
「お花を一つ下さいな。」
その手に銀貨は握られていなくって、金銭の概念も知らないで育った城内のお子様、空色の瞳にほんのりと朱鷺色の霞がかった両眼はぱっちりと睫毛を瞬かせ、花が与えられるのを今か今かと待ちながら、それでも早く走り去りたそうにうずうずとして。
売れ残った白菊しかないけれど、それでもこの方は許して下さるかしら、とおっかないのをニコリと隠して
「どうぞ。」
言ってみたら、あなたは初めて笑ったかのような不器用な笑顔でお礼を言ってくれましたね。今にも倒れてしまいかねないか弱い白菊一輪であんなに喜ぶ人間がいるだなんて、私がどれだけ驚いたか分ります?
だってあの日、花売りの仕事も捨てて、ずっと湖に沈んでいようと決めていたの。
私が城内を歩きますと、好奇の目でヒソヒソ、嫌な表情でジロジロ、いつまで経ってもあの娘は計算が出来ないって悪口ばかり、でもそれならお釣をちょろまかせられるではないかとか、脅したら何でもしてくれそうではないかなんて歪な肯定…
何の因果か知らないけれど、そもそも因果って言っても良いのかしら?あゝ、とにかく私は数字にとっても弱くって、それに覚える事も上手に出来ないし、今目の前にいる人に何て声を掛けるべきなのかも分らないからだんだん誰かと会うのも怖くなってしまったんです。どうせ関わったって傷つけられて息苦しくなるだけだもの、両眼は腫れて痛むだけだし、大きな悲鳴はあげられない、だからまたしくしく泣いて明日の眩暈に怯えて眠ったところで休まらないから、また寂しい花を摘んでは冷めきった城内への門の前で挨拶をするなんて、生きてることは地獄だわ。
それならもう湖へかえる、構わない。
これが最後の仕事だと思ったら、少し笑顔になっていく、この白菊も水に沈めよう、そして水中の螢になるだろう、重い人間の体を脱ぎ捨ててしまえば心底ゆっくり深く濃ゆい呼吸を取り戻せるだろう。嬉しい黄昏の空と冴やかな夜空ばかりが昇る、まだまだ閉ざされていた時代の虚ろなれど無垢に輝いていたかの空を仰いで泪が自然に乾くまでずっと呼吸をしていたい、あゝ、麗しの太古の国!朝日をも穏やかに堰き止め続ける月の瞳の籠の中!
戻れるのなら、戻っていいのなら、今すぐにでも飛び込みたい!
だけれど…
あの白菊を貰って行ったあのお子様はどうなってしまうのでしょう?
今朝まであんなに楽しくって笑えていたのに、帰ってみたら変に首ばかり傾げていました。どうしようどうしよう、明日もあの方は来られるかしら?それなら私は仕事をしなければ、あの方に花を渡さなければ、生れたばかりの唯一の責務を果たして、お別れを。
あなた様はきっと、オルゴヲルのことなど憶えていらっしゃらないけれど。
十二
人が植物に絡まる、という状況は、先ずイメージしてしまうのは朝顔の蔓や蔦といった細長いものに足や手を取られている姿であろう。少なくとも大輪がこぞって囲うような、花々に体を掴まれる姿は想像し難いであろう。
事実は空想よりも奇なり。現実では辻褄を合わせる必要など無く、否、そもそも合わすことなど不可能で。
よって生れた時から鮮烈な自我が意識の内で既に両眼を開いていたこと、牡丹、椿、女郎花、雪柳にマリイゴールド、葡萄、白蜜の林檎、桔梗、水仙、赤白の百合…氷の大地で不思議に芽生え、果実の滴りがいない母親の乳であった。咽の乾きが満たされても、欠けた月は戻らない。いっそ叫んでしまえばいいと半ば自棄になった眉をぎゅっと顰めては未熟な鼻で空気を呑みほさんといっぱい吸えば、胸がひやりと冷たくなった、あゝ捨て子…!
花に絡まり生まれた時、私は悲鳴をあげたのだ。
生れた赤子が泣くとする。大きな声でわんわんと。けれども他は喜んで、最初の呼吸と安堵して眩しい泪を輝かす。
育った子供が泣くとする。うなだれて嗚咽を漏らしてひくひくと。わッと泣いても黙って泣いても他はなかなか喜ばない、呼吸をしていると分らずに、哀しい瞳に光は咲かず、あろうことか怒りを孕み、歯車の動作の邪魔だと斬首刑、潤滑油は菜種でなくってどぷりと貯った血であったか。
死ぬ為に生きているのであれば、生きる為に死ぬのであろうか、言葉の境界線も分らなくなって、涙で視界が溶けてゆく、余りにも幼い大声では、長く呼吸も持つまいが、えゝ構わない。これが雪野原の中なれば、何か理由があってのこと、雪野原に不条理は似合わない、痺れ始めた小指を白いまゝの三日月にそっと絡めようと力を絞る、微笑んだのは私か世界か、花々の手招きに凭れて体を沈めては、やさしい花びらが次々に重なり私は埋もれていく。
その日水上に在ったのは一輪だけの彼岸花。
十三
白く湿った水仙に横目で一人挨拶を。これも誰かの命であったと教えてもらった気がします、哀しく切ない甘く美しい自己愛の悲劇、花は種や球根があれば咲くけれど、きっとそれだけではないのだろう。
季節は恐らく春である。少しの雪溶け水が小川を産り、火照った日差へ浮つく身には清流の冷たさは心地いい。流れは街へと向くようだ。桜がちらちらと筏を成して進みゆく、ワルツに従い踊るように。
この花、何処から来たのだろう、今桜は咲いていないのに。
誰かの想いであったろうか、遂げて水へと憩うのか。
街へと後ろで追いたいが、素裸で人前に出るのは嫌。
ふう、と吐息で諦めて、我が友水仙の傍で眠り顔…
黒雲の夢で眼が醒めた。雨を雨をと望むように。
慌てて小川から身を上げて、もうそのまゝ走ろうとしたけれど、水はそれを許さなかったのです。私は川面に両手両足を握られて、流れは頻りに首を振る。
どうして立ち上がれないのだろう。それから私は生きただろうか?
街が燃えている姿は、乙女の肌に焼きゴテを力任せに押し付ける姿である。建物が壊されるのは赤子の喉を十指でギチリと扼する姿である。夜空は失われキイキイと濁った光が空を占領し、一瞬の安眠も与えられず、耳が遠く全ての音を拒絶する耳鳴りが喚いている。だからだろう、街中なのに何の音もしないのは。
だって此処は街だもの。人の笑う声や喋る声、仕事の音がいっぱいの。だって此処は街だもの、だって此処は街だもの。
十四
澄み渡る青空、えゝと、空は青い色をしているのかしら。本当は違っているのかも、目には青く冴えていても、空は白色のつもりだったりして、きっとそうでないと、その身を彩れないでしょう?
どれだけ返り血を被っても、空はその都度泪を零し、哀しみで傷を癒しては、木々に花々にそして地に、縋りたいのを屹と怺えて雫を静かに取り次ぐお姿。月は光を信じる心であろう、仄白い祈りを黒の横雲が長く覆えど恐ろしい流れに身を任せ、また見る瀬を一途に待つ、一心の祈り、光あれ。
雲を透して降る雨は、浮気な掌に掴みきれずにトン、と羽ばたく懐かしさ、いとしかなしの微笑みは、小川に溶けても失われない。
雨の簾を挟んで立つ、あなたの顔が分からない。色蒼さめた唇に、雨に打たれて震える柳の上品にしめやかに、そして寂しく佇む姿を影に落として何かを呟く。それも晴れた日中であれば陽の取り次ぎにも頼れるが、寂しいまでに澄んだ空、草木は瞼を閉めて慈しみの雨に濡るる。
縋る術を知らない宙ぶらりんの羽一枚、生れた命はいとも危うく消えそうで。
何かを懸命に呟いて、あなたの姿は月が照らして雨が覆う。雫はとても優しいけれど、あなたの声を聞かせない。雫は頬に温かいけれど、服の胸には冷えてしまう。
あなたの声を聞きたくて、指を伸ばして簾を掲げたいけれど、月光のあなたは首を振る。
十五
淡く色づいた雪が春の姿を借りて散る…
両手で抱いてた白い毬には清流と藤の花々、薔薇の色した彼岸の花も一輪刺繡が込められていました。
あなたは桜を見るようで、桜が此の世に立たないことを知っているから、桜だと信じられている雪を見つめていたのでしょう。
私は土のにおいを嗅いだこと無いものですから、植物は氷から咲くもの芽を生むものと信じていました。けれどそれは違くッて、雪が花になっただけ、花とはそもそも雪の別の姿なだけで、触れゝばほら、搖れて溶けて空気になりそう、樹に帰ることすら叶わぬままに…
私がこの手で触ったなら、花はほつれやしないだろうか。
「雪を見ているの?」
毬を着物の袖で覆いながら、私より背の低いあなたの瞳。お着物がどうやら、お顔がどうやら、お髪がどうやらと語るには恐れ多く、私はハッと膝をついて額を氷に押しつけた。
「恐れ多いことでございます。」
「あなたも雪を見ていたのでしょう?」
「い……否、わたくしはたゞ。」
「立っていただけなんて嘘は嫌。皆は桜を見ているけれど、雪を見ていたのはあなたと私だけだろう。」
「いいえ、そんな、滅相も無い。わたくしは普通の眼です。特別な眼ではありません。」
「特別は他者から見た感情でしょう?私の眼は特別ではない、生れた時からこうだもの。」
「で、でも、ですが、その眼は」
「そうかそんなに醜いか?」
切り揃えられた柔らかな黒髪はやゝ丸味を帯びたおかっぱ頭によく似合ひ、眉を隠した前髪の下に咲くは空に朱鷺が翼広げて舞う姿、その色を祈りと共に光を注いだ左の瞳、右にある筈の眼球は白菊がふわりと縁取りも朧に生えている。醜いことなど如何してあろう?今にも抱きしめてうつくしい左眼と愛ほしい右眼に瞼を借りて接吻したいのに、わたくしは、あなたの、
「醜くなど御座いません。」
その白菊は月である。
「そうか。少し、安心した。」
だからわたくしは触れられない。
「こればかりは生れつきだからな。」
どうか想い出さないで
「どうやって咲いたのだろうな、私の眼は。」
どうか想い出さないで
十六
玻璃の器に螢の涙がひとしずく、果敢無いランタンは風が吹けば散りそうだが、まどろみの桜の花の夢まぼろし、哀しみを愛しと包み込む、ランタンは涙のやわらかい炎を絶やさない。ほんのりと照らされた帰り路の夜道のぽつんとしたおいてきぼりのあの感覚、何処か何処かが寂しいのに、誰も悲しと嘆かない、彼岸ノ花が水を飲んで生きるように、微笑みの世界は涙を知って夢を見る。
羽は頬をまろく撫で、こっちへおいで、遊ぼうよ、と誘ふ鱗粉が閉じた瞼をそっと叩き、鼻腔くすぐりいたずらを。
こんなに胸の中が軽いのは、果たして幾世ぶりであろう。螢の灯しが眠気を被す、胸には牡丹の花びらが、ナイフの痕から雫する。
十七
薔薇を口から吐き出した、王に従者がワッと駆け寄る。殿下殿下どうされた。
紅い花びらパッと散り、若き王は氷に膝を預けるようにつっ伏した、苦しい咳はまだ止まぬ。噎せるたんびに氷は染まる、口元を覆う手指もわなわなと染まり、唇は艶に紅を差したよう。瞳は雲待ちの空に濁り、朱鷺は曇天に惑い翼をたたむ、見続けようと薄ら眼を開けようと力絞れど、あゝ苦しみに圧し潰されて、此方を見られない悔しさに、王は雫を頬に託し、氷の大地に倒れ伏す、まるで接吻を間際に縋るかのように。
王は玉座から自ら倒れて降りて来て、そのまゝ従者達に抱えられて医務室へと運ばれた。
残った此方は雪まじりの風に背を押され、玉座の隅へと馳せ寄れば、透ける肌身へ濡らせぬ雫をほつりほつりと落いては、次から次へと桜の露の泪はこぼれ紫陽花を咲かす。
もう見えない筈のわたくしをどうしてあなたは御覧になる、忘れてください、わたくしの自己満足だとしても、あなたはわたくしを忘れなければならないの。
十八
生れつき視界には黒いもやもやが点々と飛んでいた。手で払っても目をこすっても常に其等は動き続けた、迷子の歯車みたくもどかしく。
この街は白い街だった。石英を純粋なまゝ加工した眩い街並み、人々の顔は反射に明るく、自ずと笑みも笑い声も溢れて来る、満ち足りた希望の場所、目標を持ち突き進む為の街、此処に哀しみは似合わない、常夏は春も秋も冬も入れず、いつも渇きと仲良くしている。
笑顔が陽射に混ざり照り返す、黒い点々はもがき焦り暴れ出す、ギャッと叫びが聞えるようで開けて居られず両眼を閉じる、蹲っていると腕を引かれ支えられて、歩くようにと促され、意思に反する一歩一歩に息切れすれども身体は倒れぬようにと気遣われ、立ち止まろうと欲する己が悪い間違いなのだと死にたくなる、いっそ
「オルゴールはいかが。」
肩を預かった二人が停止し、自然足も止まっていた。
「オルゴール、オルゴールはいかが。」
薄水色の半襟に、ふっくらとした藤の着物の袂はかろく風を受け、陶器の皮膚長い手指はからくり仕掛けの銀細工を愛し気に持ち、その瞳
「オルゴールはいかが。」
真冬の空高き青天に、淡い月を抱く朱鷺の羽。白昼の月をその身に映じ行方を案じる湖に憩うを許された鳥の羽。
サポートがいつしか離れた歩道の上、桔梗を絞った帯はお太鼓結びに上品に、赤百合の唇にこやかに、白足袋は一点の汚れも払い、鼻緒にはうっすら水仙の影。
動機を鎮めて声を出す。
「暑く…暑くはないのですか。」
何とも間抜け開口一番。きょとんとあなたは瞬いて、清廉な吐息と共にふふっと微笑み穏やかに。
「だってずっと寒いもの。」
微笑みは嬉しそうなのにどうしてあなたは哀しそう。
十九
ティン、と音符を弾く音。ねじを回したオルゴヲル、銀の白菊が咲いて莟んでからくり仕掛けと共に奏でる子守唄、耳に不思議に懐かしい。
露店商の目を盗み、咄嗟にポケットに滑らせて、闇市の人だかり、いきれの煙に紛れ込む。上は電車が通っているが、そんな小銭は要らないもんだ、人ゴミが好きならこの市場に来たらいい。浮ついた足取りの死んだ目の輩がウヨウヨと稲子みたくふらついて、その中に盗人一人歩いていたって小汚い格好の奴なんか幾等でもうろつき回っているからこと珍しくもない。
玉石混淆、口では容易い、だけれど玉は石を蹴散らす。
「姉さんただいま。」
俺と違って姉さんは玉だった。なのに姉さんは俺を捨てずいつも笑って
「大丈夫、姉さんがいるからね。」
俺を抱きしめるぬくもりも、微笑みかけるうつくしさも、心をほぐす静かな声も、細い手で器用に繰るお手玉も、俺には無いものばかり、
「おまえだって、姉さんからしたらすごい子なのよ。」
盗みをしていることを姉さんは知っているのだろうか、
「今日も、お手伝い頑張ってきたの?」
「うん、そうだよ。今日はさ、オルゴヲル貰えたんだ。」
「そう…おまえは音楽が好きだものね。」
「姉さんに似たんだよ。」
俺の笑顔はぎこちなくないだろうか、姉さんは微笑みなさる、そのうつくしさ。
まるで心の病気になんか罹っちゃいない人のようだ。
「それでね、今日はどんなお話?」
何処かの遠い国のお話
「今日手伝いに行った三丁目のおじさんの話。」
俺は女性になっててさ、花売りの仕事をしてたんだ
「家具職人のおじさんで、木材ばっかり運ばされてさ。重いのばっかだったけど、でないとおじさんが体痛めちまうから。」
確か花は一種類しかバスケットに入っていなくて、色は、白、だったことまでは
「でもおじさん凄いんだ。最初はたゞの其処等にあるような木材さ、雨が降った後に流れて来るやつに泥を払ったみたいなやつが、」
凋れかけの白菊を
「白菊?」
姉さんは一言も問い返さず、微笑んでおられる。
二十
雪に頬をたゝかれた
雪に頬をつねられた
雪に頬を撫でられた
薔薇が流れた氷上に片頬凭せ横たわる。身体は少し軽くなった気がするが、この土地に献血をしたからだろうか、眩暈も少し治まっている。
献血など笑わせるお前如きが
後ろを振り向いても誰もいない、蛇も声も分らない、雪が涙のように降るばかり、重なる姿に足は置けない、温もり求めれば溶けてしまう月のかなしみは如何ばかり深い?
何故哀しんでいるのだろうと考えれば、感情に理由は無いと目が霞む。その目で雪野原を見つむるも、くすくすと菫がぽつんぽつんと笑うだけ、蛾も鹿もおられない、城が背後に佇んで、ぴら、ぴら、と声の出せない口を開き物言う一心の音がする。
鼓動のような 鼓動のような
城に戻ったらもしかして人が居やしないだろうか、もしかして、もしかして、
もしかしてはお前なんかを歓迎するのか
月が沈んで夕日が昇る。けれど人を捜している、城内中の古びた鍵を壊すため、斧を持って歩きたかったが、武器などこの場所にもありはしない。
二十一
此処は何の為の部屋であったかな、錆びた錠を取ってみようとするも手にバサバサと朽ちた砂利がからかって、物理的には開けられないのかもしれない。
此処は何の部屋だったろう。書庫は庭園を見渡す部屋であったから、階段を上る場所にあった気がする。本はいつも雪野原について描かれたものを両手にとって、文字を読むのが楽しかった、言葉を読むのが楽しかった、視界が滲んで腕がズキズキ痛んでも、一冊ずつ両手で本を抱きしめる時は私はとても幸せであった。時に本を読みおわり、まだ満たされないような場合には、絵をこっそり見に行くこともしばしばで、その絵たちは、あゝ
錠の崩れる音が低く城に谺した。
二十二
羽衣と松、を見れば何の唄を想ふだろう。男の欲、天女の美しさ、置いてけぼりの子どもたち、羽衣は纏うたら瞬間地上のこころがなくなると云うが、生まれたての赤ん坊がこれに包まれていたらどうなるのだろう。こころに触れぬ小さな手指がまっさらの記憶そのまゝに、色を塗りつぶす事をなされぬまゝに、父も母も見えないまゝに、ずっと赤ん坊のまゝ生き続けるのだろうか。
羽衣は天女が天界から着ていたものだったろうに、人の衣服を奪って婚約指輪の腹積りであろうか、愚かな、許せない、許せない、傷つけやがった、苦しめやがって。
地上の川に水浴みに来たと云うのだから、水はやはり天上と同じなのであろうか、雫のしたたる音、聞えるのかな、けれど何処かの街には気が遠くなるくらい音が存在していなかったと本で読んだことがある、あれはいつの街だったっけか、どうして音が戻って来ることを受け入れたのか、確か帰還、王さまの……
ぴしり
窓に氷の罅が染む
破片が頬を切ってゆく
身じろぎもせず立つばかり
結露流して滴る窓
背中を向けてポケットのリボンを手にとって
リボンだと思っていたものは紺青の鳥の羽であった
この羽を
花束、白い花束に添えて
たしか仰有っていた
「私のことは忘れなければいけないの。」
国王の朱鷺色の瞳に、涙が零れた。忘れなくてはいけない記憶、忘れなくてはいけない方。
期待や嫉みや舌打ち罵詈雑言怖い記憶は忘れないのに優しさぬくもりいつくしみ温かい記憶は溶けてゆく。膝をついて蹲り、薄氷に手をつき嗚咽する。国王と呼ぶにはあまりに脆く、傷つきやすいこの人間を、どうして一人にさせねばならないのであろう。
二十三
泣き疲れて眠った人間を、城はじっと見続ける。城の横に建つ聖堂は、廃教会となってしまったが壊すことは家族が認めなかった。
「もうこの廃教会は建ててあるだけ危険です。人が立ち入れば屋根から崩れてしまいそうです。」
「この聖堂だけは壊してはいけないよ。」
「今は酷くても、必ずたすけてもらえるから。」
「お願いだから、どうかおまえは自分の幸せを考えてくれ。」
「国のことはもういいから。」
「あなたの幸せを祈っているわ。」
「おまえは無理しなくていい。俺たちがなんとかするから心配するな。」
「ゆっくり休んだらいい。」
「あせらなくていいの。今は元気になるのがいちばんなんだから。」
「おまえだって俺からしたらすごいやつだよ。」
雪の記憶が涙となって零れていく。眠るこの子の瞳からやさしい泪が戻っていく。ひとつ、ふたつ、みっつと湖面に溶けてあたたかい雪溶け水の広がりに連れ霧はさっとカーテンを引き、ついに朝陽が顔を出す。反射した光に泣きあとの頬を照らされて、目に沁み洗い流される自身のとんでもない考え違い。
薔薇はいつも咲いていた
母は赤い薔薇が好きだったから
難しい本をたくさん読んだ
父が傍で話してくれたから
雪野原に駈けていけずに窓から眺めるだけだった
兄は私の点滴が終わるまで、終わってもとなりに居てくれた、雪野原の動物の物語を聞かせてくれた
思わず震える我が身をその子はきゅっと抱きしめる。このふるえは恐怖ではない怯えではない、これは、もっと、だいじなもので。
涙をほつりと床に零す、氷は溶けはしないけれど、少し笑ってくれたようだった。想い出したい、あなたのことを。私を此処に帰してくれた、あなたは一体誰ですか?お城は憶えているのかしら、電車は、家々は、廃教会は、あなたを教えてくれるのかしら?教えてください、あなたのことを、話してください建物たち、その目で耳であなたの存在を知っているのでしょう?
「どうか白菊のあなた、こたえてください。」
その子は瞳をつむって膝をつく、雪景色に祈る様、遠かった朝空の陽の下で光に泣くあわれな迷子。とうとう雪野原も我折れたか、子の先には一羽の蛾が白く待っていた。
二十四
結晶がしたたる情けの露に潤むかのような両眼は、昆虫独特の感情を隠す眼にはあらざれど、ゆっくりまばたきをする白い睫毛重なる水晶、深い湖の奥底なる群青込めた恐ろしさを水面下にそっと包んでパステルカラーの浅葱色、淡い光と濃い闇を墨流染に施した千尋のその雫、気貴くて。
子を見続ける雪の身体の蛾。姿はかろく羽ばたけどその存在は心に深い。氷のじゃれつきに鈴の音混ぜた鳴声で、読むのか呼ぶのかないている。
思わずつられて立ち上がる、その足は寒さと恐れに震えるも、肉体は子の言う事に従わず声に、声に連れられていく。もったいなさに瞳をそらそうと遜ろうとしたけれど、蛾からは逃れらず両眼からは離れなれない。その瞳、その姿、この子に何をなさるお心か、真後ろへ立たせるまでに近づいたら、ひらり羽は舞いながらお姿をそっと回転されて、そのままふわふわ歩み始める、子は息をしながらひたすらに付いて行く。
雪野原。たゞの、たゞの雪野原。自ら吹雪でずっと隠されて居たお姿の内に、一本のかざぐるまが咲いている。
二十五
「この子は何処から来たのだろう。」
人の声が赤子を囲む。おくるみは鶺鴒の羽毛をたんぽぽのわたげで縫い合わせており、死してもなおその身で守らむとした情のあわれ、子にも届いているためか赤子はかなしくかなしく涙を流す。
「この子は何処から来たのだろう。」
前の人が去った後次の人が言った後
「この子は何処から来たのだろう。」
次の人が去った後次の人が言った後
「この子は何処から来たのだろう。」
次の人が去った後次の人が言った後
「この子は何処から来たのだろう。」
次の人、去った、後、次の人、言った後、
「この子は何処から来たのだろう。」
次、去る、次、言う、後、
「この子は何処から来たのだろう。」
人、去る、人、言う、
「この子は何処から来たのだろう。」
赤子はずっと泣いている。
カラフルな街の真ん中は、人が集まり交差する、どこもかしこもはためくアート、まぶしい笑顔、空は明るい。
赤子は紺青にくるまれて、リボンを小指に結ばれていた、涙は次から次へと痩せた頬を伝うが羽毛はするする雫を弾くもしっとりと濡れており、子が口を付ければ咽の乾きを癒やせるように、祈りを込めて。
「姉さんだ。」
人を殴った血がまだ新しく、黄色いひまわりのアスファルトにポトポト落ちる。赤子の朱鷺色の瞳を見つめ、流れる止血もせぬままに、紺青のおくるみごと赤子を抱き上げた少年の背中には、胴から真っ二つに折られた丸太が負ぶさっていた。
かざぐるまはからりと回る。
二十六
吹雪はかざぐるまを回し続け、子の朱鷺色を宥めるように背中に降り続けているのは、決して目をそらさぬように、やさしく優しく摩り続け疑問に開く両眼が塞がれないように。
「姉さん?この子は?」
質問に答える声は無く、蛾は雪中の子を見つめるだけで、凛とも鳴かぬ。
「姉さん良かった。此処に居たんだ。」
少年は腫れた片頬で赤子の涙を拭う。
「帰ろう、お腹、空いただろ?」
丸太は大切に背中に結ばれている。
「新しい家見つけたんだ、前よりも広くて綺麗なところ。嫌な音もしなくてさ、落ちついた場所なんだ。」
沈む太陽の光を眩しく背中いっぱいに浴びながら足取り確かに真っ直ぐ歩いていく。あても無く歩く少年の足裏はもう血塗れだった。
「もうすぐだよ、もうすぐ着くからね。」
赤子はもう泣声をたてられない。日は何度高く昇っては深く沈んだだろう。両眼を切られた傷は赤い細糸で縫われたように覆われており、呼吸はだんだん浅くなる、気のせいか肌身がひやひやと冷たく感じ、笑う唇も紫を過ぎて白くなる。
ゴン。
少年は何かにぶつかり、胸の赤子と背中の丸太をかばう姿勢で横向きにころげる。
腕には土でなく、雪が。
息を吸い込む唇が薔薇の雫に血色温もり、頬はじぃんと火照りを取り戻す、縫糸は丁寧に抜糸されて痛みもあらず眼は開き、足裏震えた泪はやわらかい皮膚一つの傷も残さずに靴下と靴まで履かされていた。
瞳の先には鎮座まします鹿一頭、月の眼差し清い森、廃教会の高い天井。
そして響いた赤子の産声。
二十七
鹿は少年の瞳を見つめ、少年は物も言えず赤子をきゅっと抱きしめる。
「姉さんなんだ。」
深い光のゆっくりとまばたく。
「助けてあげて。」
じっと見つめる背中の丸太、白鹿は長く太い角に繁る種々の花々木々の葉や、うつくしい蟲たちの羽一輪一輪を宿す命のかけらを一つぶも零さぬようにまたゆったりと頷かれ、少年の傍を通り雪の地面に足跡も付けないで歩いて行く。
少年は不審に感じることも無く、鹿の歩みの後を追う。
長細い穴が一つ、蹄のような形をしている黒い穴は、
「土?」
この場所で唯一雪の積もれない土であった。
鹿は少年をとおして丸太を見、そして土を見つめてピクリとも動かない横顔。
「姉さんを?」
目に涙をためて丸太を土へそっと載せる。埋めようと土を被せようとした途端、小川のような風が流れ、清流の跡には不思議や淡い実が咲いた。
桃の真珠が空気にふれてパチンとシャボン玉みたくはじけたが、潵は幼い毬のように弾もうとすれどそれが出来ないいとけなさ、悔しさにむっと頬染めて螢のふりして毛並になる。毛並うつくし小兎の桜桃借りた雪景色、細かい髭は世界を感じ、眼差し深い月の叡智。
少年は思わずハッとひれ伏そうとするも、小兎はそれを許さずに、立たせたまゝ、またゆったりと頷かれた。
その後ろには、藤色淡い薄花桜の樹が咲いて、小兎は赤子の右眼にキスをした。
二十八
彼女は一冊の本を燃やそうとしているところだった。其処には『太古の国』と記された文字、興醒めした顔は昔の輝きを連想させはしない。
笑い声が聞こえる。嘲笑なんかじゃなくてやさしい笑い声が四つほど。数にしたら少ないけれど、その四ツ葉は空気へ莟を編み込んで、その糸は城の中をくるくる回って城内の人達を穏やかな笑顔にしていく、城はふわふわとあたたかいわたげが飛びかっていく。
その声の主は、白菊を貰ってくれたあの子。あの子は体が弱いから、毎日点滴を打っている、その傍に父と母と兄とが集まってあの子が寂しくように辛い思いをしないようにと話をしたり本を読んだり物語を聞かせたり…その朱鷺色の両眼にはもう空が映り始めているのでしょう。
胸がどくりと邪に動く。やがて朱鷺色はだんだん薄れ、晴れた朝空に満たされてしまう。この本は所詮たゞの妄想でしかなかった、黄昏と夜しか来ない国なんて、ずっと在り続けられるわけが無い、信じていたけど最後にこの本の中で国は朝を取り戻してしまい、笑顔……
憎い
私は回る糸をプツリと切った。わたげを握って両手で粉々にしてやった。
あのうつくしい朱鷺色を色濃くしたら、私のことも思い出すだろう、過去も未来も憶えていないのそんな脆い記憶なのなら、嘘で上書き私だけに縋れるように話をしたらいいだけだ、家族を憎め、家族を怖がれ、信じるものは一つでいい!
胸が高鳴る。頬が染まる。
二十九
その子の悲しい涙を蛾は雪の羽で拭いながら、震える背中を撫でている。
かざぐるまは枯れていた。
枝葉はうっすらと倒れた手首のように、最後の力を振りしぼって指差すように枯れていた。その行先は、廃教会であった。
この教会は最初から荘厳美麗でドームが蓋をしていた建物ではなかった。始まりから既に蓋は備えられず、ステンドグラスには雫が絡まり、床はそのまゝ氷の大地、壁もそう。始まりから空の見える教会は、雫を蔦にあわれと睦み、花々を点、点、と待つ星座のように咲きほころぶ。線が、道がまだ見つからない、雪野原はまだ何かを守っている。
子の涙はぽろぽろ温かく、緩い吹雪の中でも凍りはしないがその心、如何に傷は沁みるだろう。それでも言葉をふるえ握る拳に込めたまゝ、血管を通して唇の血から絞り出す。
「人を捜しています。」
蛾の瞳は分かっていたように、かなしげに、少し見開かれ、睫毛を伏せる。未来も過去も思い出せないようにされた一人子の、記憶は戻りつつある、否、この子自身が無理にでも記憶を戻している、朱鷺色が最も濃くない今の世界で、抗い続けたその先が、悲しいのだと分かっていても…
蛾は立ちあがった子の隣、凛とだけどやわらかく羽音を風と共鳴させて鳴き声を一度あげた後、歩みに合わせてしとやかに舞い進み行く。
三十
当ても知らず終わりの見えない雪野原を歩くより、城に戻ってもう一度あの絵画の飾ってあった部屋に入って休みたかった。子はこれまで何度泣き疲れては眠り眩暈を抱えながら歩いたろう?あの部屋から思わず飛び出していた雪野原に、本でしか見たことのない雪花の蛾、そして悲しいかざぐるま。
「少し眠ってもいいかしら?」
子の問いに蛾が怒るなどありえない。
開け放しの大扉、大広間には扉からではない雪が降る。
「見て。天井もあるのに、雪が上から降ってるの。」
今は大階段を上る体力は無く、
「窓も割れていないのに。」
先と同じく白詰草の真緑の上に横たわり、
「 」
蛾も一緒に昼寝をする。
蛇の口は歴史を語る
蛇の両眼は理性に煌めく
蛇の尾は天からゆるされた律法の裁き
極悪非道の輩を一瞬で裁く
蛇の口は歴史を語る
名も無き命たちの生きた歴史を
蛇の両眼は理性に煌めく
その光は本能の優しさである
蛇の尾は天からゆるされた律法の裁き
悲しむ命を抱き寄せて共に眠るためのもの
蛇は頭を撫でてくれる
とてもやさしく、なつかしいぬくもりで…
「おはよう。」
三十一
赤い牡丹であった。
蛇はすらりと子と蛾の足元に立っていた。
子は目を開けようとしたが
「あゝ、そのまゝでいい。そのまゝ、そのまゝ。」
蛾がふわりと笑う声がした、
「笑わない笑わない、真剣な話をしに来たのさ。」
空気は変らず穏やかで、
「いいかい子ども、今からこの国の歴史の話をしよう。歴史とは過去と未来のことだからね、勿論現在もあるけれど、現在は瞬きの間に未来になり過去になる、つまり歴史歴史とは過去と未来によるもので」
急に足元に風が起こった、蛾がその羽で蛇に不満を言ったらしい、
「分ったよ本当に雪の結晶だなお前さんは……うぅ。
オホン。いいかい子ども、歴史は過去と未来な訳なんだが、先刻言ったよな、現在は瞬きの間だって。その星の瞬きの雫一滴に、雪は降り風は吹いて花は芽吹き蔦は命を抱きとめる、これが歴史だ、歴史なんだ。」
「………」
「何で無言なんだ。」
「てっきり、その…成り立ちとか、そんなのを、あの教えてくださるのかと思って…」
「分ッかンない奴だな⁉いいかい、もう一度でも二度でも何度でも言うけどな、歴史は星の瞬きの雫一滴に、雪は降り風は吹いて花は芽吹き蔦は命を抱きとめる。これが、こ・れ・が・歴史なんだよ。いいかい?分らなくても分るんだ、考えるなんて此処じゃ無駄さ。」
寂しい沈黙が流れた。饒舌の蛇の悲しい横がほまで見えるような。
「あの子は考えたんだ。だから駄目になってしまった。」
あの子。その響きには涙の潤み。
「お前のことをほんとうに想っていた。お前がどうしたら自分のもとに居続けてくれるのかを考えた。だから、あの子は自分を苦しめてしまった。」
「考えたから、苦しむ…?」
「おっと、目を開けるな、そのまゝ閉じていろ。、まだその時じゃない、それまでは閉じ続けなくちゃいけないんだ。」
子は両手を胸の前できゅっと握る。
「怖がらせたいわけじゃあない。たゞ此処でこのまゝあの子とお前を逢わせることは出来ないんだ。お前、見る覚悟はあるか?」
「はい。」
起き上がろうとするのを羽が優しく背中を撫でる。目を閉じたまゝの顔には硝子片で流れた頬の血と寂しい涙が混ざりあう。何を見るかも知らないで、子は一言凛と答えた。
「目を閉じて付いて来るんだ。樹を見せてやる。」
三十二
右目に白菊の咲くその子は、城の天井薄花桜を仰いですっと膝をつき、祈る。
「いつも祈りを捧げておられますが、何を祈っていらっしゃるのです?」
「いや、分らない。いつもたゞ無心なんだ。」
「はあ…」
「私が何を望んでいるかは、私では量れない。それは、」
すっと端正な横がほがまた仰ぎ、
「御存知なのだ。すべて知っておられる。」
いとしい手毬を胸の前で抱きしめたり頬ずりしたり、子兎どうしがじゃれつく無垢の輝き。
「かの天井はかつて樹だったと本で読んだが」
従者の肩が強張る。
「一体いつのことであったのだろう。過去のことか、はたまた未来か、」
ゆっくりと頬は控えめに染まり、子は微笑む。
「想いを馳せて、文を描くのも楽しそうだ。」
わたくしは、あなたの、国を愛すること、一番嫌いだったのです。こんな生物もどきどもを慈しんで憐れんで、どうしてあなたは過去でも未来でも何回もこの国に生を求めて産声をあげるのです?
あなたの恋など無下にして、好き放題散らかしまくる奴等のために!
あなたが国を捨てる日までわたくしはどこでもお傍に居ます。
三十三
「天井を見ろ。」
その子は目をつむったまんま、城の天井を仰ぎ見る。
蛇はどこかなつかしそうな。
「それが樹だ。」
「これが?」
「やっぱり忘れさせられているのか。」
蛇の懸念は蛾にのみ伝えられ、蛾は子の隣、ふッと頷く。
「いつも見ていた筈なのに。」
「だから先刻言っただろう、見てばかり本当に?って。」
子はおそるおそる宙を指かく。薄くやわい玻璃の水面を触れたと思えば、指はますます引き寄せられて、なつかしい幹のにおいが泡に混じって伝わると、ぽつりぽつりと花降る気配。けれど、これは花びらでなくって
「雪だ。」
目は開けて、掴んで雪をまた見つめる。
たゞの雪ではなくて、春の姿を借りた雪、たゞの白い哀ではなくて、それは、眼差し深い、月の夜、
三十四
月夜に雨が降っていた。冷たい雨は私とあなたを怒りも無く隔てるが、いとしい子に指を近づけても感じとれるのはみずばかりで向こうがはには行かせまいと土が両足を抑え込む。いっそ埋もれて花になれば、この身であなたをお包みしましょうものを。
雨の声がながれてゆく。
うらぎりもの うらぎりもの うらぎりもの
構うものか、構わない、此度でようやくそのお顔を見せてくれますね、さあ、その簾を掲げて私にお顔を…
雨が止まない
三十五
「雨が止まなかったんだ、それが誰かの涙とは気づかずに、雨がずっと降っていて、それで身体が寒いのだと思って、でも、それは、誰かに抱かれていたからなんだ、樹があった。この樹が誰かの後ろに、私は、あの時、その誰かにキスを恵まれた。お恵みを、受けたんです。私が死にかかっていた、から。」
頭が熱い、ズキズキする。
「どうして、私の命の恩人なのに」
涙が、苦しい、息が、嫌だ
「忘れたくない」
忘れたくない
「あなた」
想い出したい
「人を捜しているんです」
城は憶えていてくれた
「人を捜しているんです、」
取り戻さなくてはならないの、
「あなたを、捜しているんです!」
あまりに哀れ!眩暈に白眼を剝かされて、あゝ苦しみに圧し潰されて、此方を見られない悔しさに、雫を頬に託し、氷の大地に倒れ伏す。
三十六
城は医務室で手当てされる王を知っていた。
従者達に担ぎこまれ、意識薄れ力は失われていく中にも、身体は本能で咽せかえり、薔薇の紅声を染めるも、間際の呼吸音しか出せなくて。瞳もひらけぬ涙一条、王はこの日呼吸を止めた。
従者達の悲しみと嗚咽は水銀となってころころ氷の床を滑りゆく。
王の喪失を城は知っていた。千尋の呼吸に天井は綻び、桜、あの日の雪が王の右眼にキスをする。
三十七
廃教会の長椅子へ横たえられた子に覆いかぶさる蛾、戸口に佇む蛇、まだ子は目を覚まさない。雨の簾は頬に伝い、白菊の右目は綻びの雪をうっすらかむる。
雨が降るとき、天はどんな音を奏でているのだろう
雪が舞いゆくときは、どのような曲を響かせる?
天は何を弾くのだろう、歌うのだろう、流れてあふれる想いは終わない夜空の宇宙の空気の琴線に、そっとくちづけて闇を震わす。
音はこの子に届くだろうか、目を赤く泣き腫らした雪野原のかわいいひとりに。届いてもう一度この廃教会を見たのなら、きっと君は深い呼吸を思い出せる、そう信じて蛾と蛇は待ち続け
かざぐるまのカタリと倒れる音がした。
三十八
その音は許しを願ったのだろうか、
それとも告白の涙零れた音だったろうか、
鹿が一頭瞳を閉じて倒れたかざぐるまを見つめていた。
その角は薄らと青味を帯びた白紫陽花に、空の星々が懐く滲んだ淡い色を含ませ、風がそっと指先で、撫でていったなめらかさ、その裏には芽吹くことの出来なかった唄たちを片時も離さない根の深み、黒猫と烏たちが人を愛するかの眼差しの色を湛え、長い睫毛は濃く儚く時の移ろひを筆に染めてさっと流した憂いの尾花。
瞳を深く閉ざしたまま、かざぐるまの細い持ち手に顔を近づけ、口がふれるぎりぎりでぴたりと動きを止めなさる。
子の寝息は安らかで
その寝顔はあまりに幼い
眠ることの喜びを
むにゃむにゃと味わう頬の緩み
記憶が欲しいと血を吐いた者とは到底別人の子の姿に、瞳は震え目を開き、かざぐるまにふっと息を込めたら遠く響く路面電車の鐘の音。
三十九
おもて編みって何だっけ。うら、とか、メリヤス、とか、どうして名前を付けたがるんだろう。私には名前が付けられなかったのに。あのうつくしい朱鷺色に名前がその度あるのはすてきだけれど、お城の中の嫌味なヒトたち、私をひそこそ面白く楽しく邪揄する輩にも名前があるなんで腹立たしい。
玉石混淆なんて口では容易い。玉は石にはなれないし、石は玉になれないまま、羨ましがって憎みながら消えていく。…太古の国、ヒトの王が産まれる前の伝説みたいな国だったら、そんなことも無いのだろうけれど。
だって野に咲く花々は、雑草を邪魔だと思っているの?
カランカラン 路面を往く電車の鐘
乗客にしか聞えないような、寂しがりやの窓越の音、扉が開いて、また閉まって、擦り硝子の向こう顔の無い影法師たちをを見ていると、ああ平等だと可笑しくなっちゃ
「こんにちは。」
姉さん。
「お久しぶりです。」
何も憶えていないなら
「城をこっそり出るのにちょっと時間が掛かってしまって」
何も憶えていられないのなら
「此駅に来るまで二駅ほど歩いたんです。」
過去も未来も
傍に居続けたかった。
「あなたの仰有るとおりでした、兄は私を邪魔物扱いで」
お母様は憎んでいて
「父は雪野原を支配しろなんて言ってマントを私に被せたんです」
それはあなたが寒くないためのお布団よ
「母は私を睨んでいます」
嫌ってなんかいるわけない
「兄も私に舌打ちを」
抱きしめようとしているのに
「やっぱり私はあの家族とは別に本当の家族がいるんです。」
私だって、寂しかった
ごめんね
編み物をしながら、あなたは笑っていた筈なのに、今想えばどうして泣いているんでしょう。
廃教会の空気が小川みたく流れ始めた。
四十
雪野原。たゞの、たゞの、雪野原。風は色深い草をそっと撫で、花のねむりを起こすための頬のくすぐり雪の星、その光は太陽にやわく混ざって眼を覚ます、花々はあくびの吐息で天に言う、まだ潤む瞳で挨拶を。
廃教会の椅子の上、子の寝ていた頭のところには、桜桃がひとつ藤の花をかさね待って居る。
子は小川の水をむずぶように花びらごと掬っては、こくりこくりと喉を動かし一滴残さず飲みこんだ。瞳の朱鷺色は朝焼けのあわい光へよく染めて、泣き痕も傷痕もすっかり綺麗に洗われている、それでも。
これから何処へ?と声がする。
「人を捜すには街へもまた行かないと。」
路面電車の声がする。
「待っているんだ、私が逃げてしまったから。」
羽の凛と開く声がする。
「私の家族は、私が生まれた時から奇怪であることも愛してくれていたんです。それなのに私は自分の恐ろしさにずっと怯えて周りの景色を信じなかった。」
城が待つ声がする。
「私が生まれた時、白い月は満ちていて、そのしたたりが一つの花に雫して染まった、その花を兄は赤子の私に贈ってくれた。
今、やっと、想い出せた。」
ずっと左の手に握っていた、白い紫陽花のちいさな花びら。
「私の名前は、あじさい。」
両手を互いにぎゅっと大切に握りしめた
「母に守られて、父に祝福されて、兄に抱きしめられて生まれて来た。」
あなたの名前はまだ分からないけど
「あなたを捜しに今行きます、あなたもこの場所で生きている人なのだから。」
必ず逢いに行きますから
「お願いだから、そんな悲しいこと望まないで。」
あなたを忘れてくれなんて。
蛇のため息と蛾のにっこりと笑う鈴の音、オルタンシアとそろって街へと降りて行く。
四十一
「オルタンシア様?」
丘を下り街へ来たオルタンシアに、一人の声が掛けられた。
男性であったが、彼の顔は黄色い菊の花そのまゝであった、人間の顔にある目も鼻も口も無く、一輪の花がよろよろと袖に縋る。オルタンシアは膝をつき、
「あなたは起きたのですか。」
花はピクリとも色を変えない、震えもしないけれど
「もう泣かないで。」
背中をゆっくりとさすり、彼にやわらかく言葉を掛ける。
「オルタンシア様。」
声は涙混じりには聞えないけれど、
「オルタンシア様。」
彼はずっと泣いていた。端から見れば彼はただ変哲無く話しているように思えるが、
「よく耐えましたね…ありがとう。」
彼はオルタンシアに包まれながら、ずっとずっと泣いていた、花弁一枚散らさねど、オルタンシア様と言うことしか出来ずとも、その心は唯、優しいばかり。
「私はこれから路面電車へ向かいます。あなたは此処に居てください。」
「そんな、お一人で行かれるなんて危険です!」
駈けよろうとする男性の片手を両手で抱き、静かに目を閉じ首をかろく横に振る。
「ひとりではありませんから、大丈夫。」
光が赤い煉瓦の道に反射する。
四十二
街は静まりかえっていた。
人の笑いごえが聞こえない
草木は歌えずに
花は虚ろを鳥と見紛い眠っている
鳥は飛び方を忘れ
建物は言葉を失ってしまった
石は水を忘れたから
川は一滴も残っていない
雪をなくしたこの街は
「オルタンシア、何故路面電車に行く?」
白蛇はふわあと欠伸する、歩みものろくひとりぐずぐずと煮えきらない。
「彼が一番怒っているからです。」
「彼ねえ。」
不満げにぶつくさと
「俺たちが居るのも分からない輩に、お前は情けをかけるのか?」
蛾が蛇の額をペシッと羽打つ。
「真剣な話だオルタンシア。お前はどうして優しすぎる?他人の悲しみを受けすぎて、病気になったのを忘れたのか?自殺しようとしたのを忘れたのか?何度お前は魘された?人の感情に敏感だからって進んで仲裁役や調整役を演じて演じて、お前はどうしてこの国で生きたがる?何度死んだ?何度生きた?全部思い出したらお前発狂するぞ!」
オルタンシアは答えない。蛇の叫びに足は止まる。
「街なんかに行かなくてもいい、お前は雪野原に恋しているなら、そこで暮らせばいいんだよ。どうして無理に生きたがる?」
オルタンシアの掌が、そっと天に向けられる。降る花びら、否、雪は街には無いのに受けとめるのか。
「紫陽花は生きることに、何の疑問もいだきません。」
桃の薔薇微笑む唇
「晴れの日に光を受けることも、雨の日に雫を受けることも、風の日に心が搖らされることも、何の疑問もありません、だから私は立っていられる。これらは全て地球の弾く音楽で、自然の音符の一粒なのだから。」
声は震えず
「よく父が教えてくれました。宇宙はそれぞれの天体が発するうつくしい和音で満たされているのだと。その時から思いました、雪野原も、街も、自然のメロディーの中に居るだけだと。」
眉は静かに
「私は国王だけど国王ではないのです。」
唇はまた微笑む。
四十三
自分のことを考えられない人でした。いつも私の白菊摘みを手伝って、花と私を互いに見つめてにこにこ笑う子でした。薔薇を吐いて死んだ人と、穏やかなこの子が同じだなんて。
私があの子に初めてあげた色は白菊でした。白がお似合いなのだろうと今生考えまして、毛糸も白いのを差し上げました。
わたしがあの人に初めてあげた色は赤の薔薇でした。その辺に偶然咲いていた野の花だと言うのに、あの人は深く一輪を見つめていらっしゃいました。
ユグドラシルの莟を通じて私があの方に贈れたものはそれだけです。後はすべてあの方が私に恵み与えてくださった。私はあの方をどうしても忘れたくなかったのです。
願いは叶えられました。私はいつの星でもあの方のお傍に居られたのです、姿が何であっても。
願いは届きませんでした。あの方は星を憶えさせてもらえないよう、祝福されたのです。命が尽きる直前に、抱きしめられて、キスをされて。
いっそのこと、あの白菊にしてくれたらと思いましたが、それはあまりに我儘でしょう、だって私は人だから。だから身勝手なままで居ます、あの方は未練があるけれど、わたしにはもう未練は無い。
どうか鍵を降ろしてください、少しでもあの方が私に逢えない時間を長くするために。
四十四
藤のかほりの手袋は、よく見ると濡れていた。
それもそのはず、とぐろを怒らす氷柱の姿は、人肌知らぬさみしい哀しみ、自分だけでゆっくりゆっくり癒やすのに、どうして静かな涙が止む訳の有ろう、一蔓ずつ蛾が抱きしめる。
回送中のかの文字も、何度も何度も自傷を重ね、脅えて自殺出来なかった傷痕が塞がらなかったためであろう、生きようとした涙の色。
言葉も無く車内の長椅子に横たわる。固く冷たい座席にそっと、そっと横たわる。
四十五
鐘の音が伺うように耳を訪ねる。路面電車もオルタンシアもよく寝ていた。蛇は愉快に、蛾はにっこり。
「ずっと呼んでいてくれていたのにね。」
鐘は声を出さなくなった
「ごめんね」
もうとっくに金属は錆ついて
「私が死にたがっていた時も、一緒にいてくれたよね」
運転する者も失っても
「憶えてるよ、君が花だった時も、私を埋もれさせてくれたことも」
硝子は煌めく
「川面で手足を握ってくれていたことも」
氷柱は溶けて
「君は、私をあの人から守ろうとしてくれていたのでしょう?」
手袋を零れる
「ありがとう。もう想い出せたよ、君のこと。」
声も無く
「ずっと待ってくれていたんだよね。」
また、路面電車は動き始める。
椅子は人肌で温かかった。
四十六
湖はつめたくてなつかしかった。けれど、どうしてかは分らない。たゞ、たゞ、なつかしい。
空には太陽水には月、きれいだなあ、きれいだな。
このまわりに咲いている花、白くてあったかいけれど、よく見た気がするけれど、名前は何て言ったっけ、指先と鼻がとくとくするのは、気のせいなのかな。
よく姉さんに摘んであげてたな、いやあの時は妙チキリンな街で歩かされていた時だっけ、でもいやいやあの日は姉さんのお姿じゃなかったんじゃないの?でも姉さんって誰だっけ。
私どうして湖に来たんだろう。暑くもないのに、初めて来た湖に、どうやって来れたんだろう、すごい、すごいなあ。あれ、
どうして「すごい」なんて、そんな私褒め方言えたんだろう。
手に持って居たカンテラを落さないようにしなくっちゃ?
四十七
せっかく生きて来たのだから
何か必ず理由がある
必ず光はあるんだから
進めば何か掴める
生まれたのは生きるため
と
言葉を準備していた
悲哀は生きる為に必要な存在だと
傍に寄り添って話を聞く口出しはしない
大丈夫命の光になれたらいい
守ってあげたい 命には乗り越えられる力が必ずある
と
思っていたの
命は
親の気分で殺された幼いその瞳が
ぽとり
泪を落としたのを見るまでは
私には分らなくなった。川面で手足を握った時、私は君を助けられたと思ったのに、あいつは君を諦めなかった。親はどんどん子供を殺して、その泪いや顔すらも見ないで前進して行った。
親殺しは大逆罪、子殺しは自然の摂理。
街はもう壊れていた。あいつが居ようが居るまいが、また別のあいつが出現する、革命は体の良い人員削減、命が悲しみ滅ぶだけ。
君にあいつはどう見えていた?聖母のようにでも見えていた?非道いこじつけだよ?人は月になれない、人は人で充分なのに、君はあいつを人と見た?
人として見てあげて、崇めないで。君が誰かを苦しめるのは絶対にだめだ、ゆるされない。戻って来て、よく見て聞いて、泣いて笑って。想って想い出してたいせつな記憶。君は不幸じゃなかったろう?
どうすれば伝わるの、気づいてくれるの?私に埋もれて死にたがった時、何て言ったか憶えてる?だれも怒っていないんだよ、憎んでなんかいないんだよ?迷惑なんて邪魔なんてだれも考えていなかったのに、ひとりぼっちで離れないで。私の傍にまた居てよ。泣かせたくなんかもうないのに、どうして君は泣きたがっちゃうんだろう。
ごめんねなんて言わないで、私は謝ってほしいんじゃないの、あの時の言葉をかなえてあげたい。だからおねがい泣かないで。
「笑いたかった、心から。」
喜びは成長しなきゃ分らないのに、赤子の君は虚ろに死を望んでた。
笑って。
どうか今だけでも。
四十八
車内がカンテラを搖らしたから、オルタンシアは目が覚めた。どんどん雪野原がはなれていく。手袋をはめて片方は黒。
「黒百合。」
はめていない片方
「白菊。」
氷柱の名残ひとひらの
「藤。」
窓硝子の奥
「紫陽花。」
ふりむけばいつでも
「桜の樹。」
「オルタンシア?」
蛇の問いに彼女は何も答えない。
四十九
あの子、人になりたかったんだ
どうやったら傍に居てあげられたんだろう
私が記憶が無いって知っていたのに、ずっと、
どうして記憶を持たないようにされたのかな、あなたは、
あの子はずっとひとりっきり?
いつの時もしあわせな命でね
あの子のうれしい、なんだったんだろう
私、あの子をちゃんと見てた?
あなたはいつでも私をすくってくれてたの
私、あの子に甘えてたんじゃないの?
だから私あなたを恋いして焦がれたの
あなたは
だからあなたは、私を忘れなくてはいけないの。
私は月影の輝きでしか眼を覚ませられないから
植物が人に、恋をした。それがオルタンシアのあの子の名前を知らない理由。この国の植物には叶わない暮らし、それは雪と生きる城での暮らし、それがオルタンシアの知った世界。あの子はずっと人ではなかった、地球が息をしたその日から、生まれて土と水に生き、光と闇を幾億万年見続けてきた植物という一つの星が、寿命の次元異なるものに恋をした、それがあの子の罪らしい。
五十
どうして?
五十一
黒い手袋はオルタンシアの片手にぴったりはまっている。彼女は視線を膝に落し、両手ばっかり眺めていた。蛇が呆れて首を可笑しく振るのを、蛾はピシリとたしなめて、彼女の傍にそっと寄り、ふわりと体を抱きしめる。なつかしい色がここに居るよと頷くような、やさしくつめたい雪の羽に彼女はまたも咽び泣く、甘えたがりの寂しんぼ、そのくせ頑固で優しすぎる優しい子。光をおだやかに淡く伏せる水色の触角のきらめきは、彼女の髪の毛をよしよしと撫で続ける。
「どうして憶えてなかったんだろう。」
あなたは記憶を持たないようにされていたのよ
「どうしてお城は人だって言ったの?あの子は人間じゃなかったのに。」
人も植物も名前が違うだけで、何も変わらないからよ
「私ずっと待たせてしまった。私がぐずでバカな所為で、」
あなたのことをだれもそんな風に想っていない
「私またダメだった、いつも失敗ばかり上手に出来ない。」
あなたのことをみんな心配しているわ あなたが自分にだけ優しく出来ないから
「でも私」
でもじゃない あなたのことを抱きしめてあげて
「…………」
出来るようになるまで、わたしが抱きしめ続けるから、もうあなたをいじめないで あなたは優しい子ですもの
車内がカンテラをまた搖らす。終点の駅はそろそろ近い。
五十二
私は人でした。少し彼女より長生きしている人でした。地球が輝きと音を知ったその日から、呼吸をすることを与えられた人でした。
如何にしても生き延びる。それが私の生き方でした、そこに疑念も嫌悪も無く、怒りも恨みもありません。
けれど私はあなたが咲くのを見てしまった
たゞの人の子の泣き声だと思ったものは、私を呼ぶあのいつかのやさしい声でした、紫陽花の名を冠するあなたが、私を、呼んでいる?
逢いたい、抱きしめたい、私のあなた、私の子。
「オルタンシアちゃん、兄ちゃんですよ。」
けれど
「かわいい子、生まれて来てくれてありがとう。」
居るじゃないですか
「雪野原の神さま、どうかオルタンシアとその家族が安らかな喜びで満たされ続けますように。」
家族が
貴様共が何を知っている!
私が怒れば幾つでも国を易々と壊せます。武器もドンパチも大義も要らない、私は滅ぼしかたを知っている。そうして私は昔文明を何個も何万個も数えるのも煩わしいくらい終わらせて来たのです、私は人です、人なのです。あの子があなたが私を人にしてくださったのです。お礼を言いたい「大好き」と、このなつかしい湖で私はあなたが来てくれます日を待っています、あなたが私を忘れても、いつかふらりと迷子のように来てくださいますよね?だからあなたは私のことを忘れなくてはいけないの、ねぇ、うふふ、たのしみね。
五十三
終着の駅は森の入り口で、名前のある花と名前の無い花が交互に編み込みあった壁の門が建っていた、もう門は自分が鉄製だったことを忘れているらしい…雪野原と終点の間街は雪に降られないがこの森には若葉色の雪が降る。ひらり降れば積もってしまう積もってしまえば形になって、形はいつか姿を無くす。無くしたものは目に分からず分からずオロオロ泣くばかり、泣かないようにするためには土を知らず舞うばかりそれが哀しいことであれど宿り木を知らない莟であれど悲しませないのはそればかり、ずっと宙を舞うばかり、この森に雪が積もらない理由は、雪が足跡を残さないから。
足跡を残してしまえば何としよう?其処に街の花は生きられず、雪野原を仰いで凍ってしまうだけ、そのかなしみも閉ざされて。葉書を送り出したところでどうなるか?読めない言葉に心を奪われるものは無く、やがて何処かの土にかえって呪むだけ。悲しみ転じて災ひを呼び、いつかの時にはそれで街は滅ぼされた、誰でもない植物一人に。
それを君は知らないだろう、知っていても分かりはすまい、何色にも染まることの出来ない白紫陽花オルタンシア。植物の名で祝福された病気の少女、早く城へサナトリウムへ戻りたまえ、右眼の白菊を失った君に出来ることは何も無い。君の探す者はやがて桂花となって君も昔も今も未来も忘れて微笑むだろう、自分を知らない者を思い初め、思い続けるか弱い細糸せせらぎの手、そのような残酷を病む少女に捧げたは原初の愛だと想っているからであろう、おゝ、おそろしい女神よ。
オルタンシア、君には彼女がどう見えている?記憶を想い出せないようにと祝福を授かった君には、その朱鷺色の瞳の由来も忘れさせられた君には、彼女が憐れむべき存在となって焦がれて居るのであろうか。…目を醒ませ白紫陽花、王が城に与えられた物語を忘れたのか?
五十四
燃やされた本の文字は氷の地面に貼り付き、刻み込まれたかのように赫々と滲む。
「こんな本が何だと言う。」
白菊の花売りは憎々しげに噛み締める、その横がほを見ていたのは、雪野原のかの鹿であった。
「太古の国など役に立たん。」
ニヤッと笑ったその顔を、あのやさしい少女が見たらば何と言おう、
「所詮本だ、つくりもの、私の言葉の方がよっぽど効いているわ。」
城で育ったあの子に、悲しみを植えつけてはいけない、
「私だけ見て私を忘れて私にずっと恋をしろ。」
此処で命をとるは容易いが
「さあ次のお話は何にしよう?母親があなたを嫉んでる、なんてステキだわ。」
それではあの子は記憶を求め続けるだろう
「お兄さんがあなたを恨んでいるでも良いかしら、あなたの所為でお兄さんは自分の望んでいたものを捨てさせられたとか。」
さあどうしたものか
「せっかく溺愛されているのだから、父親はお兄さんよりあなたを大切にしているって言っても本当ッぽいわね、えゝ、えゝ、利用しない手は無いじゃない。」
おろかものめ
「楽しい!楽しい!」
自分が泣いていることも知らないで
五十五
最初から城があった訳じゃないんだって、何で雪野原に花が咲くか知っている?あゝ、知っているか、憶えて居るものね、だって薄花桜の咲いた経緯は知っているでしょう?
お城はね、鎮魂のために造られたのよ。勿論廃教会もね。
嘘じゃないわ、オルタンシアを誑すあいつなんかと一緒にしないで頂戴よ、あなたたちは見て来たでしょう雪野原に咲く理由。知らないなんて言わせないから。
五十六
森の言葉は雪野原から降る風にさやさやとにっこり唇に指一本、不平を呟くも禁じられて無言のまゝに、路面電車は駅に着く、そのやりとりを雪花の蛾の羽三日月ひらく扇のように弓をつがえる弦のように白紫陽花の目先に咲けば蛇がシュルリ音立て素朴な疑問の芽を摘み取る、その流れは城内の水の樹にあらず風が内密にした謀りごと、いくら朱鷺色の瞳を持てど窶れた少女には見えなくて代りにみとめたは小川の姿を借りた梯子、駅からすっと立木となって森の奥へと続く様。
「オルタンシア、お前は何を憶えている?」
「やさしい記憶。」
「他は?」
「かなしいこと。」
「何で?」
「私はきっと、愛されていた。でもね、時々かなしくなる、の。だからあの方に逢いに行った、ほんとにたまたま。そしたらね、身体の内で暴れている花が落ちつく気がしたから。」
「お前は?」
「あの子に逢いたい、逢って話をたくさんしたいの。」
「森は?」
「来るなって。」
少しの沈黙、
「来てはいけない、此処は、人の来る森じゃないからって。梯子は、人がのぼるための物じゃない、心得違いをするなって。」
するとその時、清廉の歌。
大地の恵みとこしえに
花は蟲と息をする
樹木の歌は鳥を呼び
月に咲けよ桂と雫
花のしたゝり月よりあふれ
おさない雨を覚まさせる
君のゆめゆめ何處に有らむ
蔓が手招く雪月花
「物は人のためじゃないから」
おいでなつかしい子
「梯子に触ることも駄目だって言っているの」
なつかしい君
「これは歌?」
なつかしいあなた
「どうして私を歌わせようとするうの」
ぜんぶおしえてあげる
「いや、こわい」
ぜんぶぜんぶはなしてあげる
「私帰れなくなる」
家は此処よ 忘れさせられたのね
「私自分の家は憶えてる」
それは嘘の家
「だってみんな待ってるのに」
あなたのことを誰も愛していないと教えたでしょう あなたの家はこの場所、この森なのに
「じゃああなたの家は?」
歌声が止み、オルタンシアは息荒く路面電車に凭れかゝる。手の震えが止まらない。こわい。
雪の細い横がほ尚蒼白く、少女は白菊の零れ火の如く泣き始めた。蛾に背をしっかと抱かれ守られるばかりでなく、赤い薔薇を丸ごと呑み込んだ名残に燃える紅玉の瞳が黒曜石となり森の奥を正面に雪の紫陽花を庇い睨むは鋭き牙。
「身の程を弁えろ。」
その子を正しい場所に居させるだけじゃない
「黙れ。」
炎でも吐く気?そんな代物何度も何度も見飽きたわ 燃やされたって死にはしない私たちはそうしてずっと生きて来た 歴史になんて力は無い早くその子を返してよ
「蟲に喰われて死んじまえ。」
そしたらその蟲を食べる奴等を呼んでやれるわ 喰った獲物に知らないうちに殺される 賢い生き物のくせにそんな事も分らない だから虫ケラなんて揶揄されるのよ
「それで人間になった心算か?」
歌が止む音。と、
「オルタンシア。」
家族の声。
路面電車の扉が閉まる直前に、兄が痩せた妹を思いっきり車内へ引っ張り込む。母の呼び声、涙、手当て、父の泣き声、ぬくもり、手当て、頭を撫でる兄の手のひら。
「帰っておいで。」
三日月の微笑み、赤い舌のおどけ。
お帰り、わたしたちのかわいい満月ちゃん。
路面電車の走行音が一生懸命聞える。鐘の音、鐘の音、届け、届く、雪野原へ。
五十七
少女は鉛筆で絵を描いていた。
「何の絵を描いてるの?」
「これは、春の絵。こっちは丘の夏。あそこは雪の秋。それは、冬の絵。」
さ、さ、さら、と不規則に芯が少しずつほぐれていく、たった四枚の真白な紙に少女は現々と目を注ぐ。城中の錆は彼女が戻るともう無かった、錆は?錠をまだ全部開けていないの、でも全部古びていて。家族も職員達も首をひねる、この城には古びた錠は一つも無い。
「変な夢でも見ていたんじゃないか?」
と兄に頭を撫でられたけれど、そうじゃあないよ
「半日行方不明だったの」
おかしいよお母さん、私何度も寝て起きたもの
「急に自分の部屋から居なくなったって聞いてお兄ちゃんは真蒼になって飛び出したんだ」
お父さん達が居なくなっていたんじゃないの?私とお城と雪野原を置いて行って?
「御無事で何よりでございました」
お城の人達も誰も居ないのに、お城が人を捜しているって
「直ぐに貼紙を城と街中に配りまわって、オルタンシア様を見つけられたんですよ、街の住民が教えてくれましたの」
住民?そうだ黄色いお花!
「黄色いお花の方でしょう?駅に向かう途中でその人起きていて」
「黄色いお花?お見舞いに来てくれた人が届けてくれたのかい?」
「いいえ、そうでなくって、お顔がお花の、花の人。」
「オルタンシア、街にそんな人は居ないよ?」
「でもお母さん」
「お前が嘘言ってるなんて誰も思っていないよ。でも少し休みなさい」
そう言ってお父さんは私の右眼の白菊をそっと撫でて微笑まれた。おやすみと言われたのに一人で部屋で考え込んで、点滴ばかりが暇になって来て、それだからおえかきを始めた訳で。窓から雪野原を見つめたけれど、白い満月の下に大きな白い満月があるように想った。蛾と蛇にそう言ってみたらふたりとも微笑んだ。
「オルタンシア、何を描いてるんだ?」
「春の小川よ。向う岸には雪が重なって、若葉をそっと隠しているの。この絵はね、こっちの四枚と繋がっていて、…これでほら、この国が出来るの。」
「上手に描けるもんだなお前。」
「上手でしょう?白藤ねえさんもそう仰有ってくれました。」
蛾につけた名前に、彼女はにっこりと微笑む。ねえさんが笑うから私も嬉しいな。
「白藤ねぇ…ちなみに、この四枚、いつ描いたんだ?」
可笑しなこと言うのね、さっき描いてみせたじゃない。
「いやだってさ、この絵が何をそれぞれ描いているのか俺たちまだ聞いてないんだから。まあ―、なんとなく察しは付くけどな?」
話していなかったっけ?これは、春の絵。こっちは丘の夏。あそこは雪の秋。それは、冬の」
「冬の…」
「冬の?」
「あれ?何だったっけ、たしか、冬を…?」
「冬じゃなくって、雪野原、の間違いじゃないか?雪を描くのに季節を限定する筈ないだろ?」
「そうだっけ…じゃあ、これは雪野原の絵だよね。」
羽がやさしく私を撫でてくれる。
「ねえ白藤ねえさん、雪野原の鹿のお話してちょうだい。」
うさぎのような鹿のようなお顔の方よ
「かわいい?」
「あれにかわいい?なんて聞く奴初めてだ。」
「白藤ねえさん、紅玉が馬鹿にしたわ。」
やめなさい紅玉、オルタンシアを困らせないの
「ねえさんはお優しいのに、紅玉ったら捻くれさん!」
「うるせぇこの子供!とッとゝ寝ろ病弱娘!」
「嫌よまだ鹿のお話聞いてないもの。」
澄ました横がほツンと向く、その視線の先には偶々窓が、外は珍しく雨が落つ。
「ねえさん、紅玉。……雨。」
雫の色は薄紫に光を籠めて音も無く雪の世界に沁みていく。
雨が降れば土は潤い草木花々の芽も起つが、此処は生憎雪野原。法も概念も通用しない王国の変らぬ姿は月ばかり、ほの白く淡いぬくもり忘れじの朧の影と咲く姿、太陽は月に照らされ輝く国のまばゆさは太古の国と紛わぬと言ふ。雨にも失せぬ満月を、双子のやうな眼差しで紫陽花の少女は白菊咲かす瞳で見つむ。
「うつくしいのね、この国は。」
誰にも聞かせぬ独り言。鏡の奥で誰かが首を横に振る、その姿は雪藤と赤い薔薇に抱きしめられゝばいともたやすく桜霞。けれど不思議哉白菊は、花弁一輪震わせてそっと静かに頬を撫でる、その手は一粒の涙となって落ちていく。
たゞの、たゞの、雪野原。
終
「国王ノ涙」