
霞ゆく夢の続きを(2)
【あらすじ】
文学新人賞に落選し続ける赤井かさの君は、駅で自作の小説本を配布することを思い立つ。結果は惨憺たるものであった。道行く人、誰も受け取ろうとしないのだ。お手製の本を処分して自暴自棄になっていたところ、やがて彼に一通のメールが届く。
メール発信者の男と駅で待ち合わせすることになった赤井君。現れた長身の箱村という男は、話す内容がやたら現実離れしている。赤井君はただただ当惑するばかりである。箱村と連れ立って職場の雑居ビルの一室に到着すると、花菱という名の太った男がソファーに寝そべっていた。部屋に充満する怪しげな煙に赤井君は酩酊し、幻覚らしきものを見る。花菱も箱村同様に話すことが意味不明で戸惑ったが、帰りぎわ日当名目で二十万円渡されたことで、途端に気分を良くする赤井君である。
さて、夜の街に姿をあらわした懐あたたかき彼。誤って入ってしまった場末のSM店にて、カナというSM嬢に会い、すっかり恋の虜となってしまうのであった。SMを理解することはできないものの、彼女目当てにこれから何度もこの店に通いつめようと彼は決心する。
翌日職場に来てみると、相変わらず花菱が太った体を横たえていた。てっきり今日から本格的に仕事に入るものと踏んでいた赤井君である。ところが花菱はしょっぱなから訳の分からない冗談や文学論を延々と語りはじめ、一向やめる気配はない。僕は何しにここに来たのか、と茫然自失の彼ではあったが。
(11)
「ほんで、ワシ、なに話しとったんかいな」と花菱が間の抜けた声をあげた。
「あれですよ、下読みがどうのこうのって‥‥‥」
「おう、そうだった、そうだった。いいか、評価するってのは採点するってことだ。マルペケ作業をして点数化して最終的に値打ちを決めることだ。そんなことアイツらしてんのかぁ? どうせドンブリだろう。まあアレだよ、ドンブリならドンブリ違いで悪しからずと洒落を利かしてドンブリ飯ぐらい出てこりゃいいが、そんな気風のよさはないんだろう。落とされようと選ばれようと、どっちに転んだって結局飯は食っていけねえんだ。どうせ食っていけないのなら、賞に受かった落ちたなどと、そんな詰まらない尺度で自尊心を満たそうとするのはやめな。アイツらにとって君らは道端に転がってる石ころと同じなんだ。赤井君は箱村と違って、ちょっと変わった形の石ころではあるが、向こうにしてみれば、そんなことどうでもいいのさ。ただ会社の方針に従うだけじゃ。ザルならザルらしく、せめてザル蕎麦でも振る舞ってやればいいものの、何一つ恵んでくんない。箱村もそうだが、何であんなちんけな賞が垂涎の的なんかになっちまうんだ。ドンブリ飯やザル蕎麦に涎を垂らして、君ら、そんなに食いしん坊なのか。アイツらはザルなんだ。いくらザルで水汲んだって全部落ちてくだけだろう。いくら作品を出したって全部落とされて徒労に終わるだけだぞ。あんな猿芝居に振り回されるな。なんでそんなタラップをのぼりたがる。飛行機が落ちたらどうすんだ。純文学なんて今にも墜落しそうじゃないか。落とされるのは君の作品だけじゃないぞ。アイツら自身も少しずつ落ちていくんだ。ヘロヘロでフルマラソンの荒い呼吸音が聞こえてきそうだよ。可哀想なぐらいだ。君はしぼみゆくジャンルといっしょに心中するつもりなのか。なあ、今さっきワシが赤井君の作品の秀逸さを適切に評価してやったろう。どうだ、まったく文句はあるまい。あれが作品の精髄を見極める眼だよ。あれが全てだ。他の評価は全部インチキだよ。一瞬にしてワシの鋭い心眼は作品の真贋を見ぬくんだ」
‥‥‥‥またまたぁ、心眼と真贋を掛けてる。よほど言葉遊びが好きらしい。ああ、腹減った。ドンブリ飯とかザル蕎麦とか、そんな涎が出そうな話はもうよしてくれ。 ヽ(≧Д≦)ノ ハラヘッタ!
「あの、一つ質問があるんですが」
「おお、ウエルカムだぞ、なんでも答えてやる。もっと乗っかってきていいぞ。なんだ? 言ってみろ」
「小説に点数なんかつけられるんでしょうか。結局好き嫌い、合う合わないがあるだけでしょう。一つの作品でも、それを読む人の数だけ違った作品になる。誤字脱字があったらマイナス一点、とかやるんですか?」
「彼らはこの作品はどれだけ銭になるかで点数化してんだよ。要するに商売になる商品かどうかだ。評価軸がまるっきり違うんだよ。そんなの本来あるべき姿じゃないだろう。全員がおかしいから、誰もおかしいとは思わない。かえってワシみたいに正論を吐く者がいたら、そいつ一人が狂ってることにされちゃうんだ。彼らにワシのような作品の芸術性を見ぬく心眼はないよ。そのくせ商売人としての哲学や理論はしっかりしたものを持っている。なにも動物的カンだけで作品をえらんでるわけじゃないぞ。そこにはちゃんとした商売人の目利き力や分析力がある」
「それって、いけないことなんですかねぇ。あの人たち、教育者でも公務員でも政治家でもない、ただ民間会社が儲けようとしてるだけでしょ? だから好きなものを好きなようにどう選んで売り出そうが自由でしょう。一民間企業が賞を誰にくれてやろうと、他人様にとやかく言われる筋合いじゃない。コネだろうが大衆迎合だろうが、数字がとれりゃいいんだ。結果オーライ、勝てば官軍なんじゃないかなぁ。聖人君子じゃないんだから、法律にさえ触れていなければ、何でもありの世界でしょう。純文学も垣根を取っ払って、どんどん大衆受けしそうな作品を出していったらいいんじゃないかと思うんですけど」
そう不用意に発すれば、「なんだと!」と花菱が声を荒らげてギロリと睨んだ。
言葉をさえぎったところをみると、かなり癇に障ったらしい。感情を逆なでしてしまったようだ。怒気の熱量が半端ない。理性のメッキがはがれて、制御できない苛立ちが顔に露わになっている。
「いえいえ、そう言って反論する馬鹿も世の中にはいるだろうな、と」
「そうかそうか、そういうことなら、よろしい」
憤懣やるかたないといった表情が一気に和む。
‥‥‥‥やばい、やばい、この人は出版業界に恨みがあるらしきことを忘れていた。今後、本音をあからさまに出すのは禁物だ。
しかしこの社長、最近の新人の作品はつまらんとか言っていたが、どれぐらい最近の小説を読んでいるのだろう。かつての文学華やかなりし頃にいまだに生きていて、最近の若者の作品など興味がないのではないだろうか。昭和の頑固な書評家の愚痴を聞かされているかのようだ。若者が何を書こうと、ろくに読みもしないで叩きにかかる。オールドファッションが度を越して線香の匂いがしてきそうだ。来し方ばかり振り返っているので、お頭が経年劣化している。シーラカンスか。アンタの価値観は苔が生えている。古色蒼然とし過ぎていて、時代に周回遅れだよ。そう言ってやりたい。
考えれば考えるほど、花菱の見方に異を唱えたくなる赤井君である。最近の作品はたいしたことないの一点張りだ。たとえばあのパクリ騒動になった北条裕子の『美しい顔』など、花菱の好みに合いそうな作品ではないか。あれを最初から最後まで読んでいたのであれば、少しは若者の作品への認識があらたまり、違った言葉を口に出していたのではなかろうか‥‥‥そう考えて赤井君はくやしがる。
盗用の部分を除いて読んでみても、結構この作品はいけてるんじゃないか、と赤井君は感じている。どうやら彼にはこの作品が強い刺さり方をしたようだ。彼は思う。‥‥‥これはひいき目で見ているだけなのだろうか。直後の文芸評論で絶賛する人が多かったことからして、純文学として秀逸なのは間違いないのではなかろうか。というのも文芸評論家が全員提灯持ちだとは考えにくいし、考えたくもないからだ。疑惑が浮上してもなお評価する作家等がいたほどの作品ではないか。
けれども赤井君の場合、本人は気づいていないが、作品を気に入ったというより北条裕子の顔を気に入っているだけのことなのだ。いい女だと思うから、いい作品に見えてくるのである。悲しき男の性、丸出しだ。かりに赤井君が出版業界にそれなりの力を持つ人物だったとしたら、彼女にどれだけ肩入れしたか知れたものではない。北条裕子が男だったとしたら、こんなに持ち上げているかどうか怪しいものだ。
赤井君は、彼の北条裕子への評価は自分の価値基準や審美眼から導かれたものだと疑わない。だが実態は種族保存の遺伝子に操られて導かされたものに過ぎないのだ。もっとも彼は絶対にそのことを認めようとしないだろうが。
得てして素人の評価なんてこんなものだ。女に色ぼけた赤井君も、若い才能から学ぶことのできない古ぼけた花菱も、いきつくところ作品の評価者としては不適格だということなのである。
赤井君などは相手が美人だと見るや、すぐ頭のなかで理想の女につくりあげてしまう。実際がどうかなんてお構いなしだ。彼は女に対して致命的な弱点が二つある。一つは、相手の内面や本質を知らず、また確認もせずに、外面だけで判断して容易に信じ込んでしまう愚。もう一つは、いったん囚われてしまうと、そこからなかなか逃れられないという愚である。
そのとき誰かの声がした。自分の頭の奥の方からその声は聞こえてくる。
───赤井くん、ちょっといいですか?
何だ、何だ。アンタは誰だ。
───赤井くん、君は小幡亮介という作家を知っていますか? だいぶ昔のことだから、今じゃ思い浮かぶ人はほとんどいないでしょうね。彼は「永遠に一日」という作品で文学新人賞をもらったんですよ。なにか潜水夫の話だったような覚えがあります。私もそのとき同じ新人賞に応募していたもんですから、雑誌を買って受賞作を読んでみたんですよね。正直、才能がある。受賞作がこれなら仕方ないかもな、という気持ちになりました。しかし読み進めていくにしたがって、一つの例をいうと、安部公房の作品に出てくるのと同じ比喩なんかが散見されるんですよね。誰だって傾倒した作家には文体が似てきますよね。私だってそうです。それは分かります。しかし、一つや二つなら偶然ということもあるんでしょうが、そっくりそのままが結構な数あるんです。しかもありきたりな表現ではない。当時としては誰もが思いつかないような安部公房独特の前衛的表現が、一字一句違わずこうも続けて出てくるのは一体どういうことなんだろうか。“おや? 文学賞のストライクゾーンってこんなにも広いのか”というのが当時の感想でしたね。より高みを目指したのでしょうが、そこまでして作品の完成度をさらにグレードアップさせる企みも許されるんだ、と。その一方で、私も君と同じで、投稿した全作品が一次で落ちて、一度も活字になって一般公開されたことのない身であったので、“なるほど、そうか、これぐらいのしたたかさがなければ、作家にはなれないんだ”と、ひがみとも受け取られかねない妙な納得感も残りました。
ところが後にこの作品に剽窃騒ぎが起こったんですよ。開高健に似てるとかなんとか。そんな話があちこちの紙面で盛り上がってるわけです。「おいおい、開高健も確かにあったけど、やっぱしメインは安部公房だろう。みんなちゃんと全文読んでから批判しようぜ」などと重箱の隅をつついてみたり、「これは作品を売らんがための話題作りで、ぜんぶ誰かが上の方で仕組んだ道化芝居なんだ。みんな壮大なヤラセにはハメられてるだけなんだ」などと途方もないことを無責任に考えてみたりもしていた私でした。当時は若くて世間知らずだったので、ビジネスなら儲けが見込めればそれぐらいしかねないだろうな‥‥‥‥そんな軽い気持ちでディスっていたのです。この業界はたいして綺麗な世界ではない、表に出ないまでもこれと似たような理不尽や不公平は他にも一杯あるに違いない───そういう思い込みが、小説家になりたいという情熱を急速に冷ましていったのもこの頃です。むろん実際がどうだったかなど分かりようがありません。これはただの未熟で無知な若者の主観に過ぎないのです。一方では“よもやそんなことは”という気持ちもありました。しかしながら塗装が剥げ落ちていくのは抑えようがないのです。これは感情の問題で、理性ではどうにもなりません。とはいえ今ふりかえれば、この業界にねじ曲がった逆恨みや根深い嫉妬心を抱く前に、バッサリと物書きになる夢を切り捨て得たことはむしろ幸運だったと思います。幸運───紛れもなくそれは幸運だったのです。地獄への扉は、一見華やかな、あたかも天国と見えし場所にあるからです。変な言い方になりますが、その意味で小幡亮介は私の恩人の一人でもあります。
小幡亮介本人の身になってみれば、あっちこっちから辛辣な矢が飛んできて相当苦しんだんじゃないでしょうか。彼が私でなくてよかったですよ。かたや一次も通してもらえず、かたや受賞した。実力の差と言われてしまえばそれまでですが、私がまかり間違って受賞していたらどうなっていたことでしょう。さいわい既存作家のコラージュ的作風ではなかったので剽窃問題には至りにくかったにせよ、それに代わる不幸が訪れたに違いありません。世間の耳目を引かんがために、あるいは虚栄心をさらに満たそうと、号砲が鳴るやいなや一人だけ無理して全力疾走でとび出すマラソンランナーにでもなっていたのが落ちでしょう。背伸びした挙句、数キロ先で息が切れてダウンすることは目に見えています。まともな人なら最初から先頭は走らない。余力を残して後ろにつく。それができなければ他と並んで走る。当時は若くて歪んだ自己顕示欲があり、そんなこともできなかったのではないかと疑います。ともあれ互いに不完全な欲得まみれの人間どうし、実力ある物書きの表現力を見せつけられたら、何とかそれに肖りたくなる気持ちは分かります。いけないことと知りながら、かすめ取ってやれという悪意が生じても詮方ないことなのかもしれません。私に縁がなかったから救われた、それが全てなんです。当時は必死で種を蒔いていたつもりなのですが、たまたまそこが相応しい場所でなかったので花は咲かなかったのです。人なんてみんな同じです。業縁が整えばどんなに高潔な人でも悪事を働かざるをえません。私が新人賞に応募していたときは、生活に困っていて藁にもすがりたい思いでした。彼がお金に困っていたかどうかは知りませんが、こういう切羽詰まったとき人はどういう心理状態になるか十分理解しているつもりです。誰だって落ちかねない落とし穴がそこにあるんです。彼のことをアレコレ非難する前に、彼は自分なのだということ知り、戒めるべきなのです。今おおむね安全地帯にいることができるのは、あのとき縁が一顧だにせず素通りしていってくれたおかげです。
生きていくのに最低限の金は必要ですが、名声は不要です。名声は今流にいえば承認欲求ですか。世の中には承認欲求を煽って商売に利用したり、誰かを槍玉に挙げて面白がったりと、そういう仕掛けが至る所に張りめぐらされています。赤井君、ゆめゆめそんな作為に乗ってはいけません。細々と拙くても自分なりの表現を求めていったらいいんです。書くこと楽しみたいのなら自己完結しなさい。多くの人に気に入られるような作品を書こうとしてはいけません。そんなことをしても君には土台無理です。自分を広い土俵に立たせるほど万全の準備をするのが難しくなり、我が身を守りにくくなります。苦しみは自分の評価を他人に委ねはじめた時から始まるんです。本来、人は他の人から評価されなければ生きていけないような、そんな惨めな存在であろうはずがありません。君はむしろ、意図して人が読みたがらない雰囲気の小説を書くヘソ曲がりぐらいで丁度よいのです。他人のためでなく自分のために書くのです。なぜなら自分のあり方に満足すればするほど、他の人の評価に頼らなくてもすむようになるからです。目立たなくしていれば大丈夫だと思いますが、それでも君のネガティブな感情を煽って面白がる人も出てくるかもしれません。が、赤井くん、決して動じてはいけません。そういう人は病んでいるので、したいようにさせておけばいいのです。しっぺ返しとは言わないまでも、近い未来か遠い未来にふさわしい場所に必ず赴くことになります。そんなことより君は書くことが今面白いですか? 面白がるべき人は、他人ではなく君自身なのですよ。
それから小幡亮介は他にも二作ほど文芸雑誌に書いていたようですが、その後のことは知りません。一度も一次を通過したことのない私が言うのも僭越ですが、安部公房や開高健等の大家、そして彼のせいで賞を取り逃がした人には悪いのですが、みんな当時は木を見て森を見ていなかったんじゃないですかねえ。彼は賞をとったのに単行本を出してもらってません。北条裕子は『美しい顔』を本にしてもらってますね。この差って何なんでしょうか。時代の変化? 男でなくて女だから? それとも作品の出来が特別つきぬけていると評価されたから? だけどこんなことをぐだぐだ考えたところで、今となっては何の意味もありませんね。万々が一、女だからという理由で本が出せたのだとしても、いろいろ内輪の事情もあろうことですし、人の世なんてそれぐらいの偏りはどこにでもあります。だからといってもう二度と文学賞に応募することのない私が、何を言える立場にあるというのでしょうか。新人賞をもらっても本を出してもらえない作家は他にもいるとのことですし。
私も心身ともに老いを感じはじめる歳になりました。老いてきたと感じたら、もう恥ずかしい姿を世に晒すべきではありません。死んでしまった思いは、もう二度とよみがえらないのですから。老いたなら遠くの場所から眺めるだけにとどめるべきなのです。ちょうど君、そして私のところにあの時やって来た作家たちのように。若き頃の情熱はもはや夢のまた夢‥‥‥‥いいなぁ、君はまだ若くて。
声は消えた。今のは何だったんだろうか。もしかして今この小説を書いている作者? 書いてる途中で、どうしても言いたくなって、厚かましくもしゃしゃり出てきたとか。あらあら、そりゃ掟破りの禁じ手だろう。あり得ない。やっぱり花菱社長だな。耳の具合が一時的にちょっと悪くなっただけなのかも。
「社長、嫌ですよ。急にそんな丁寧な話し方になって。驚くじゃないですか」
「何トボケたこと言ってんだ。丁寧な話し方? ワシの話し方は今も昔もこんなんだ、変わりゃしないよ。心ここにあらずで、ボーッとすんなよ、ここからが重要なポイントなんだからな。ちゃんと聞けよ。赤井君、君が神様だったら、自分の作品を選考者に気に入ってもらいたいなんて思うか?」
「そんな、分かりませんよ。僕、神様なんかじゃないから。神様に訊いて下さい」
「違うよ、そういうことじゃないんだ。ワシの意図はこうだ。物事は高い視座から見ることが大切なんだ。それからもっと視野を広げることも大事だ。純文学小説の場合は特別そうだよ。これだ、ワシの言わんとしていることは」
「視野を広げるって?」
「つまりだ、つまり君が何年かぶりに母校の小学校に行くとするか。すると『小学校の校庭ってこんなに狭かったのか。あの時はあんなに広く感じたのに』と思う。これが視野が広がったということだ」
「狭く感じるようになったのに、広がるんですか?」
「何つまらんこと尋ねてくるんだ。山場に入ってきたのに、変な質問して水を差すなよ。言葉の綾だ、綾。君にはどうやら巧みな言いまわしは通じないようだな。具体的に言ってやるよ。たとえば大正から昭和初期に活躍した芥川龍之介がこの令和の時代に生きていて、出版社の新人賞に『河童』という作品を送ったとする。『河童』じゃバレちゃうかもしれないから『蛙』という作品名にしとくか。もちろん忖度させないために、芥川龍之介という名前を伏せてだ。『蛙』は見事、賞をゲットするかな。しないよ。断言できる。君らと同じで一次で落とされるか、あれでも二次まで進めるか。いずれにしても賞は取れない。だけど芥川は屁の河童だろう。いま純文学の賞に芥川賞なんてのがあるにもかかわらず、だ。これは何を意味するかだな」
「ますます分かんなくなりました」
「分かんないのは、君が何故瞑想するのかという答えを求めて瞑想しているからだよ。これ、すなわち迷走という」
またまた空気を読まない駄洒落の連発だ。クソ面白くなくても我慢して愛想笑い、愛想笑い。でも「この程度のジョークに笑うなよ」と笑われてしまいそうな気もするし。
「それって“メガネがないから、亡くしたメガネが見つけられない”的なトートロジーですか?」
「トートロジー? 何や、それ。そう言えばよく出てくる言葉だな。え~と、うん、確かにトートロジーだ。ワシみたいなインテリがその言葉を知らないわけないぞ‥‥‥‥トートロジーをな、そんなありふれた用語ぐらい‥‥‥」
花菱がしどろもどろだ。トートロジーならぬトロトロジジイになっている。
「いえ、なんとなく勢いで口をついて出ただけで、気にとめないで下さい」
どうやら二人とも言葉の意味をよく分かっていないらしい。赤井君も意味が分からないまま、だだフィーリングで使っているだけのこと。知ったかぶりで、お馬鹿モロ見えの御両人である。
「けど、大正や昭和初期に芥川龍之介がいなくて今いるとすれば、今の芥川賞もないはずですよね」
「なんの話だ」
「『河童』、いや『蛙』の話です」
「ああ、そこにもどったのか。芥川賞のことだな。なに細かいこと言ってんだ。SFだったらそんな枝葉末節も大事だろうが、これは譬え話だ、SFじゃないんだ。君に純文学の精髄を諭すための対機説法だよ。いいか、よく聴けよ。売ろうとした時点でアウト。赤井君、君だって選ばれようとした時点ですでにアウトなんだぞ。そうなった時点で、もう純文学じゃなくなってる。クソみそに言われようが無視されようが、そんなの関係ない。誰も本を買ってくれなくたって、そんなの関係ない。それが純文学ってもんだよ。彼らも銭を追うようになったら、もう純文学をあつかってるとは言えんな。だから『蛙』は通らない。なんて説明したらいいかな。そうだな、たとえば若い絵描きはたいてい貧乏だろう?」
「はい、なんかそんなイメージありますよね」
「“僕はここまで芸術性を突き詰めたぞ”ってな具合に、むやみやたら純文学的に自分に酔ってるだけの君の作品が、銭になると思うかね。だから彼らは落とすんだよ。鼻につくんだよ、君のアーティスト面が。芸術性とか文学性とか、そんなんじゃなくて銭なんだ。だけどなぁ、彼らにも、もともと力のない者が必死こいて絞りだした作品であることぐらい感じとれてるはずなんだ。なんで一次で落とすかねぇ。情ってものがないのか、情ってものが。やっぱ商売人だよ。なにより数字が大切なんだ。“商売してんだから利害で評価するのはアタリキだ、企業の使命は効率優先・利潤追求、それのどこが悪い”と開き直られたら、こっちも返す言葉がない。奴らはそれを知ってるんだ。だから痛くも痒くもなく堂々としてられんだ」
「そうか、怖いもの無しか。だから堂々としてられるんだ」
「いやいや、さすがのワシでも心ん中までは見えないけどな‥‥‥‥君も彼らを見習って、百万回落とされようが痛くも痒くもない、作品を誰も読んでくれなくても痛くも痒くもない‥‥‥一日も早くそういう心境に至れ。そういう環境を手に入れろ。落とされる度にオロオロ、駅で配っても誰も読もうとしてくれなくてオロオロ、そんなんじゃいかん。男一匹、情けないぞ。出し続ける限り、箱村みたいに永久に落とされ続けるぞ。そんなことも分かんないのか。もし彼らに君らを拾い上げる気が少しでもあれば、どれか一つぐらいあえて二次まで進ませて、唾をつけておくぐらいのことはするよ。つまり『お前らの作品はいらん、もう送ってくんな。ただでさえ忙しいのに仕事を増やしてくれるな』という意思表示だ。特に箱村、アイツの作品は何だ。どれもこれも話の展開だけ目まぐるしく変わっていくのみで、心理描写も風景描写もなおざりもいいとこだ。細密なタッチがどこにもない。長ったらしいのをダラダラといっぱい書きゃいいもんじゃない。いい加減あんな大雑把な画風は変えなきゃ駄目だ。味も素っ気もない。修飾語一つない。馬が走った、空が青い、川が流れる、お花が咲いた‥‥‥主語と述語だけ。なんだアレは。もう少しぐらい耽美的になったらどうだ。もう少しぐらい言葉を編めないのか。小学校低学年の作文か。余韻も何もあったもんじゃない。登場人物の内面の陰影がまったく描けてない。作品に血が通ってないんだよ。おまけにいつも勧善懲悪、水戸黄門のラストだ。一番大切なものを置き去りにしてどうするんだ。あんなの中身を食っちまった後に残った、カラッポ弁当殻だ。よくあるじゃろう。小説が面白かったから、それを映画化したものを見た。全然面白くない。セリフもストーリーも全く一緒なのに。そういうことがよくあるじゃろう。心理描写や風景描写が小説の命だ。映画やドラマでは表現しえないものが命なんだよ。セリフやストーリーだけで引っ張っていこうと思ったってうまくいくもんか。そんなの劇の台本と一緒だろう。前もいったが、ストーリー展開だけなら絵付きの分だけ漫画や映画の方が格上だっちゅーの。しかもこの世のありとあらゆるストーリーは、もう既にすべて出し尽くされちまってるよ。二人とも‥‥‥いや君はちょっと違うかもしれんが、とくに箱村なんざ中に入り込んでしまって、こんな単純なことにすら気づいていなかったんだ。本真物のアホだ。本バカだよ」
「僕はいいんですけど、箱村さんにはちょっとボロカス過ぎません?」
「あの石頭にはこれぐらい言ってやらなきゃ分かんないんだ。いいか、誰の人生だって、十ほしいものがあったら、そのうち一つか二つ、手に入れば御の字なんだぞ。そういうもんなんだよ、もちろん一部の特別に優遇されてる人たちを除いてはだ。もっと突き放して、客観的に事実だけを分析してみろ。そしたらホントのところが見えてくるから。君は田舎もんだから、地下商店街ではぐれて地上に出ても、やっぱり迷子のまんまかもしれない。じゃが大所高所から見るのは大切だ。できるだけ高いビルの屋上にあがって見おろすんだ。山で道に迷ったら下りるんじゃなくて上れ。あせって下ろうとするから、獣道に呑まれて遭難しちまうんだ。ワシみたいに頂上から全体を見渡せ。そうしたらおぼろげながらも君の選ぶべき道が眼下に見えてくる。箱村みたいに敗北を認めて、早いとこ重荷を下ろすんだ。徳川家康みたいに“人の一生は重荷を負うて遠き道を行くが如し”なんてのんびりしたことを言ってるようじゃ駄目だ。一生を台無しにすんな。人生なんてアッという間だぞ。ジジイになっちゃう前に、そんな重荷はほっぽり投げちまえ。いま君はここにいるじゃないか。これが君の運命だ。ありのままを受け入れろ。君が運命を嫌えば、運命も君を嫌うぞ。おっとなかなかのフレーズが出て来た。おい、箱村! スマホかタブレット持ってこい! 忘れないうちに録音しとかなきゃ‥‥‥なんだアイツ、いつも肝心なときにいない、アジャパーだ‥‥‥ほんとに奴ときたら、いざ使うときに何処に行ったか分からないテレビのリモコン野郎だ。時間が消し去った記憶の文字は、もう二度と読めないんだぞ。あら、またまたシャレたのが出てきたぞ。ワシは天才じゃないのか、こんな時に即座に録音できないなんて、どーなってんだ、くそ!」
「読めないって、それ黒板の文字なんですか、それともホワイトボード?」
「なんじゃ、それ。言うに事を欠いて、なんておバカな質問を真顔でしてくるんだ。あまりにも質問がバカっぽいんで、かえって君が賢くみえてくるじゃないか。どいつもこいつも何だ。せっかく出てきたワシの珠玉の表現をぐちゃぐちゃにするつもりなのか」
「じゃあ、もう一つ前の話に戻します。花菱社長は小説を応募するのやめろと言いますが、僕にも僅かながらも積み上げたものがあるんで、ほっぽり出せと言われても苦しいもんがあります。物語を完結させないまま途中で逝っちゃうみたいで‥‥‥毎回それなりに落胆してますし‥‥‥どうしたらいいんでしょうか?」
「なんだなんだ、こんな緊急時に。また変な質問しやがって」
「“何でも質問しろ、答えてやる”と言って下さったので」
「ああ、クソして、まだ拭き終わってないんで気持ち悪いってことか。便所にオシュレットはないのか。ケツぐらいワシが拭いてやる。ここにいて、ちゃんと言う通りにしときゃ、ちゃんと尻拭いはしてやる。いいか、人生はハザードマップ、至る所に危険な場所があるんだ。ちゃんと胸の奥に畳んでしまっとけ。おいおい、またいいのが閃いたじゃないか。今日は名言が出すぎだな。なんでこんなときに箱村がいないんだ。スマホとかICレコーダとか、録音するもんがいるんだよ! どこ行った、まったく」
「あっちの部屋でなんかしてたような‥‥‥あれ、いない」
「そうだろう、どこにドロンしやがった。職務専念義務違反だ!」
「なんですか、それ?」
「何も知らないやつだな。それより録音したいんだよ。どうしてくれるんだ、箱村の野郎!」
「リアル鬼ごっこじゃないですか、逃げたんですよ。どっちが鬼になって追っかけまひょか。僕? それとも社長?」
「なんでこんな時にボケるんだ。コラ、お尻、ペンペンするぞ」
「ぺ~ン、ペンのぺ・ヨンジュン。なに言うてまんねん、ほなアホな」
「何でここでそれを使うんだ。タイミングは今じゃない、今じゃ」
「こんなのにタイミングなんてあるんですか?」
「あるんだよ、伝統芸には。そんなことより箱村はどこへ失せやがった」
「葬式はいつにしましょうか」
「おいおい、殺すなよ。そうだ! 君、今スマホもってないか? ちょっと貸してくれ‥‥‥そうかあ‥‥‥トホホ、ギリチョンでやっとこさ生きている君が持ってるわけないよな、アジャパーだ。今どきホームレスでもスマホで話してるぞ。住所の無いホームレスの通話料がどうなってるのか知らんが」
「そこらへんにメモっときゃいいんじゃないですか?」
「ダメなんだ! どこにメモったか忘れちゃうんだよ」
「僕が社長にかわってメモっときましょうか?」
「いや、立場の弱い非正規社員の君にそこまでやらすわけにはいかん」
「ここに正規とか非正規とかの区別があるんですか? たった三人しかいないのに」
「君は日当で箱村は月給だろう」
「それだけですか?」
「それだけだよ。ほかにも何やかんやあるんだろうが、小難しい法律のことは知らん」
「経営者なのに?」
「小賢しい口を利くな! まだ大学生なら大学の図書館でそんなことぐらいは調べろ。下らんことに話を持ってくな。せっかく大事なことをレクチャーしてやってる途中だったのに」
「そうですか。それじゃレクチャーの続きを。花菱社長のお話はためになります」
「ためになるってか? 嬉しいこと言ってくれるじゃないか。謙虚でよろしい。いいか、落とし穴は落とし穴に見えないから落とし穴なんだ。赤井君、こんな時こそ、胸の奥にしまってあるハザードマップを開くんだ。僕の小説を選んでちょうだい、なんてラブコールはもう送んなよ。みっともない。そんなの自ら危険区域に踏み込むことだ。小説家なんて実力があることはもちろん、偶然が山のように重ならなきゃなれないんだ。自分の作品はいつも一次で落とされる───そういう事実だけちゃんと見て、それにとらわれるな。いつまでも雑誌社の賞に応募し続けるような間抜けなことしてたら、いつか落とし穴におちるぞ。己の名前は己でつけられないだろう。生まれたての赤ちゃんが親に向かって“木村太郎はやめて、木村拓哉にして”と嘆願するのか。あくまで作品の価値を決めるのは彼らなんだ、君じゃない。ダメと言われたら何処までいってもダメなんだ。自分の生き方を問い直せよ。どんな疫病神に憑依されて、小説なんか応募しようと思いたったんだ。そんなの本来の君じゃない。何をどう書こうが、作品は作品だよ。君自身じゃないんだ。小男の君が地球儀をいくらグルグル回そうが、ビッグな男にはなれないんだ。世界地図をひろげて邪悪な野望に燃えるのは、習近平かプーチンぐらいのもんだ。凡人を絵に描いたような君に何ができるっていうんだ。地獄ってのは何も遠いところにあるんじゃなくて、心の中にあるんだぞ。小説で一山当てたいとか、目立って馬鹿にしてた奴ら見返したいとか、そういう気持ちは心に巣食う鬼といっしょだ。桃太郎のお供でもして鬼退治しなきゃ。もちろん桃太郎はワシだぞ。君は大人しいから一番弟子の犬にしてやる。きび団子の代わりにちゃんと日当は渡してるだろう。箱村は二番弟子の猿だ。キャッキャッといちいちウルさいからな。分かったな、それが鬼ヶ島で人生の宝物をゲットする最良の方法なんだよ。利口に利口と認められたら嬉しいだろうが、アホにアホの烙印を押されたところで何を落ち込むっていうんだ! 分かったか!」
「いくらなんでもアホは言い過ぎじゃないかと‥‥‥」
「君らから見れば利口がもしれないが、ワシから見れば出版社も作家連中もアホだ!」
「僕にとって利口なら、ダメ作品の烙印を押されて落ち込んでもおかしくないんじゃないでしょうか」
「何まどろっこしいこと言ってんだ! 機を見るに敏な彼らは、おいしそうな話を耳にするや触手を伸ばす。なぜわざわざやって来るのか。何らかの行動を促すためなのか、それともからかい半分なのか。君自身が経験しているから見抜けるはずだ。いいかな、馬に収穫した人参の見張りをさせたら、我慢できなくて齧じっちゃうだろ。君は馬なみに扱われてんだよ。分かんないのか。彼らは赤井君のことを、いつ人参を齧るか見てるんだ。反応がなければ、たまにお尻を棒かなんかでツンツンとやって面白がっている。そのために来てるんだよ。自分の神経が少しづつ削り取られていく自覚がないのか。君は箱村みたいに鈍感じゃないから、嫌というほどあったはずだ。でも程なくして足は遠のく。いくらツンツンしても反応がなければ興味を失って去っていくんだ。もうからかい甲斐がなくて面白くないからな。もう遊んでやんないってなる。飽きて二度とやって来ない。君は力がないからツンツンされても何にもできない。彼らが飽きるまで我慢することぐらいしかできない。そうだ、ワシも昔、立場こそ違え似かよった目に遭ったよ。箱村だって同じだ。アイツは天然だから気がついてないけどな。馬はまだ杭に繋がれているから何をされても動けないと錯覚している。どうして気がつかない。杭はワシが抜いてやったじゃないか。さあ逃げろ。呪縛をとっぱらえ。そんなとこに、じっとしてるな。不幸になるだけだ。君は杭を抜かれてもその場を離れられないサーカスの象さんか」
「さっきから僕、犬になったり馬になったり象になったり、ちょっとおっしゃる意味が何のことだか」🐕、🐎、🐘‥‥‥(・・?ハテナ
「ワシのあり難き話に、君はずっと馬の耳に念仏だろう。やっぱり馬じゃないか。家畜は“この人達はなんで餌をくれるのだろう?”と我が身の顚末を予想できないだろう。ありていに言えばね、君はその家畜の一匹にされようとしているということだよ。つまり飛んで火にいる夏の虫だ。君は虫けらでもあるんだよ」🐜🐛🐝🐞‥‥‥‥ムシムシムシムシ
「でもそれ、ちょっと被害妄想がすぎるんじゃないでしょうか」
「君はIQが足らんからしょうがないか。彼らはそういう具合に、五十年前も同じことをしていた。何十年経とうが変わらない。今も同じ。だから少しずつ地盤沈下していくんじゃよ。んで、列車に乗っても、みんな文庫本を読まず、スマホばっか見てるってことになるんだ」
「スマホで電子書籍や投稿サイトの小説を読んでるのかも‥‥‥」
「君はなんでそう、出版社や作家たちの肩を持とうとするんだ! 賄賂でももらってるのか! 日本人のくせに判官贔屓のメンタリティーはないのか。最近の若い奴らといったら、まったく‥‥‥‥もういい! 結論だけ憶えとけ。結論はさっき言った通り“アホにアホの烙印を押されても気にすんな”ってことだよ。アホの烙印おされたら、明石家さんまバリに『アホちゃいまんねん、パーでんねん』と笑い飛ばしてやれ。そしたらワシがチョキを出してやるよ。どうだ、バッチ、グーだろう」✊✌✋‥‥‥oh crazy!!
‥‥‥優しさは十分わかるが、そんなシッチャカメッチャカなギャグで同情されてもなあ。余計なことを言って、さらに虫の居所を悪くされては困るので、この際、スルーして話題をかえよう。
「ところで僕の本、どうやって手に入れたんですか」
「ふう、やっとまともな質問に戻ったか。箱村の奥さんが、駅で君から直接受け取ったんだ。それを見せてもらっただけだ。つまり赤井君はすでに箱村の奥さんと面識があるということだな、気づいてないだけでね」
「そうなんですか、知らなかったなあ」
「赤井君のことを、こんなものが書ける人は化け物とか‥‥‥‥いや化け物じゃなくてサイコかな、なんかそんな風にいってたそうだ。失礼しちゃうな、こんな可愛い男の子に向かってサイコとはね。あの程度のおどろおどろしさは巷にあふれてるのにな。だいたい世界の歴史に名を残す偉大な作家は、みんなサイコじゃないか。日本の作家先生たちみたいな、ちまちました常識人じゃないだろう。なんせあのベッピンさんは無菌状態で育って、グロい小説を読んでないから仕方ないのよ。しかしアレだ、何であんないい女が箱村みたいな遊び人にホの字になったのかね。ワシみたいな金持ちが男やもめだって言うのに。アイツなんか髪結いの亭主じゃないか。あんにゃろう、イケメンはいい思いしやがんなあ、クソ!」
「男やもめ? そうだったんですか、以前結婚されてたこともあるんですか」
花菱の過去に少し興味がわく。バーコードになりかけたハゲ頭にスキャナーをかざして、この人の生きてきた全ヒストリーを読み取りたくなった。盛るだけ盛った厚化粧の人生ドラマが見れそうだ。
「なんだ、それ。ワシが結婚してたのがそんなに意外か。結婚したってロクなことはなかったよ。子供もできなかったしな、畜生! もう大昔のことなんで全部忘れちまったよ! いま妻も子供もいないってことは、そんなもんワシの魂の学びにとってもう必要ないってことじゃ! 神様は魂の向上に必要でないものは与えないんじゃよ!」
負け惜しみっぽく花菱はそう毒つくと、溜息をついた。続けて、
「それにしてもアイツなんか、行き当たりばったりの風来坊だろうが。木枯し紋次郎気取りでいやがんの。股旅物の旅がらすか。イケメンたって、あそこまでいい男じゃねえよ。奥さんに食わしてもらって、いいご身分なこって。ゆらゆら揺れる昆布みてえなヘッピリ腰野郎だ。穀潰しのくせして、よくもまあ、あんな能天気にひょうひょうと生きてけるもんだ。なに食ってあんなにデカくなったんだ。デカけりゃいいってもんじゃないんだよ、デカけりゃ!」
花菱は煙草を灰皿にもみ消し、たるんだトランポリンのような顎の皮をもてあそび出した。灰皿は吸殻の山であふれそうだ。今はイケメン箱村への嫉妬心で頭が一杯のようだ。
「スマホかタブレット持ってこい!」の件は完全に忘れている。そのうち何かの拍子で、浮かんだお気に入りのフレーズを忘れてしまったことに気づいて、思い出そうとするが思い出せない。ところがしばらくすると、思い出そうとしていたことすら忘れてしまう。
そんなふうにして、人はどんどん過去の記憶を消しながら老いていくんだろうな。赤井君は花菱を見ていて、そう思った。
‥‥‥‥そういえば昔、木枯し紋次郎というヒットしたテレビドラマがあったっけな。主演のイケメンって誰だったっけ? 忘れちゃったな。ドラマは見たことないが、確か新潮文庫で一、二冊読んだことがある。
沈黙。自分がブサメンなことによほど失望しているのか、沈黙が顔に放心の仮面をかぶせている。メランコリーって柄かよ。その肢体も花菱のパンツのゴム同様、倦怠と惰気にダラリと伸びっぱなしだ。イケメンだろうがなかろうが、そんなに変わりゃしないのにな。何もそんなアンニュイな表情しなくても。別に芸能人でもあるまいに。そんなに長く生きてきて、こんな当たり前のことにも気づいてないんだろうか。
‥‥‥‥思い出した! 前から花菱が誰かに似ていると気になっていたが、ここに来てやっと思い出した。円描いてチョン、チョンチョンチョンと素人でも似顔絵が描けそうな、特徴の無いこの丸顔。ドリフの高木ブーだ。彼にそっくり。しかし似ているのは外見だけで、中身は高木ブーと正反対、箱村に劣らぬとんでもないお喋り男である。そう言やぁ、高木ブーも結婚して子供も孫もいるな。この人が結婚したことがあるとしたって別におかしくないのかぁ。だからって、それがどうしたという話だが。
そんな小さな発見に喜ぶのも束の間、花菱の沈黙はいつまでも続いた。次の一手に長考するプロ棋士にでもなったつもりか。プロ棋士なら沈黙の間、頭脳はめまぐるしく動いている。けどアンタの場合は完全に停止状態だろう。指示待ち態勢の僕はどうしたらいいんだ。
そのあいだ仕方なく、灰皿から立ちのぼるタバコの煙に、振られた男の写真を細切れに破り泣きながら灰皿で燃やしているバーのホステスや、その背景にある愛憎劇などを勝手気ままに想像していたが、やがて妄想のネタも尽きてしまう。毎回おなじようなストーリーの昼メロはもう飽きた。
業を煮やした赤井君が「僕は何したらいいんでしょう」と水を向ければ、
「今は何もしなくていいよ、好きにしとけ。そのうち活躍してもらう。君たちはワシの駒だよ。だからワシの言う通りにしときゃいい。なんで駒かって言うとな、企業家としてのマインドも発想力もてんで無いからだ。たとえて言えばだな、君が前に住んでた学生アパートの小説工房な。そうだそうだ、君が毎日少しずつ物語を彫刻していったあのタコ部屋のことだ。あそこネズミが這いまわってたんじゃろう(『女と』)。ああそうか、今住んでる物置小屋もおんなじか。時代遅れの電化製品が年がら年中冬眠してるあの物置にも、ネズちゃんが‥‥‥」
「え? 何でそんなことまで知ってるんですか? まさか﨑田の野郎の正体は社長さんの差し金だったりして」
「なんじゃい、その﨑田の野郎ってのは。そんな男なんて知らん。ワシが言いたいのはネズミのことだ。君らなんかネズミを見たら、ただキモッって思うだけだろう。じゃがワシのような一流の企業人はネズミを見たら見たで、ただ気持ち悪いと思うだけじゃなくて、ネズミで一儲けしてやろうと頭を働かせるんだ。そうだな、ワシだったらネズミにワイヤレスの超小型カメラ取り付けて、そのリアルタイムの映像から倒壊した被災地の建物や瓦礫に閉じ込められた生存者たちを探すことができないかな、なんて考える。うん、我ながら並々ならぬ着想力だ。箱村もそうだが、君らにそんな発想は浮かばないだろう。だから駒になってワシが指すがまま従ってりゃいいんじゃ。なされるまま、お気に召すまま。空気にふれて色を変える林檎にでもなっとけ」
「ほんとに何もしなくていいんですか?」
「ワシが“しろ!”と言ったら、すりゃいいんだ。いいか、君ら凡人たちの人生は麻雀や双六やポーカーと同じで、運や偶然に支配されっぱなしのゲームだ。だけどワシの人生は将棋やチェスだ。要は頭脳だけで勝負、運や偶然にほとんど支配されない。だからワシが鵜匠で君ら鵜だ。餅は餅屋って言うだろう。鵜匠が操る通りアユを飲みこんでくりゃいいんだ。指図はワシがする。指図されないときは、好きにしとけ」
「鵜飼いの鵜ですか?」
「そうだ。君は聞き上手の話し下手だから、今はワシの機知に富んだスピーチを聞いてるだけでいいんだ。鵜飼いと言ったって、鵜を紐で縛って魚を獲らせるような野蛮なことはしないぞ。君ら部下に目配りはすれども、だからといって束縛なんかするつもりはない。天皇陛下やエリザベス女王といっしょだよ。君臨すれども統治せず、がモットーだ。それが経営の極意ってもんだ」と花菱は誇らしげだ。
‥‥‥‥それって、もしかして社員が何千人もいる大きな会社にだけ通用する話じゃないの? たった三人しかいないのに。エリザベス女王ももうお亡くなりになってますよ。
「なんだ、妙な顔して。納得いかないか? いいか、こういうことだ。騎馬戦で上に乗る人は軽い方がいいだろう。そのほうが俊敏に動ける。経営もそうだ。ライバルに出し抜かれないように機敏に動かにゃいかんじゃろう。かつぐ人は軽くなくちゃな。司令官は怒鳴ってばかりの重たい奴じゃだめだ。アレしろコレしろといつも小言ばかりじゃ部下は嫌になるだろう。『やってられるか、アアもう動きたくねえ』になっちゃうじゃろう」
‥‥‥‥よく言うよ。その体型はどう見ても重いだろう。小言はいわないけど、充分お喋りだし。
「いまは何にもしなくていいよ、好きにしとけ。働かなくていい、気にするな。冷蔵庫のなかのものは勝手に取り出して、食ったり飲んだりしていいぞ。安心しろ、ちゃんと日当は払う」
「けど、何もしないでお金もらうなんて、ちょっと‥‥‥。気にするなと言われると、かえって気になります」
「君もしつこいな。だから言ったろ、活躍してもらうって。クレバーなワシが譬え話で解説してやるよ。なぜ君らの作品は一次も通らないのか? 選考している連中はみんな食わず嫌いだからだよ。君の作品は強烈すぎるだろう。最初の数ページ読んだだけで、その異様さに口に入れたら思わず吐いてしまいそうな気がしてくるんだな。『何だ、こりゃ、気持ち悪う』と生理的に毛嫌いする。彼らは嫌いな野菜は皿に残したまま箸はつけない。君の作品は残飯として直、処理されるんだ。『箸もつけずに食べ残された我が身はどうなるんだ! 不公平にも程がある。せめて野菜屑にでもして肥料の代わりに使ってくれ!』───赤井君、ノホホンとしてないで、腹いせにそれぐらいは言ってやれ。もっと怒れ、何あっけらかんとした顔をしている!」
「はぁ、もともとこういう顔だもんで。で、それと僕の仕事内容とどういう関係が‥‥‥」
「だから、だからなんだよ。アイツらがしないんなら、ワシが廃物利用してやると言っているんだよ。君はなにも考えずに、ただ頭に浮かんだことをそのままワシにたれ流せ。浄化処理はワシが責任を持ってしてやるよ。その方が君自身にとってもよほど安全だ。あんな文学賞なんていう狭い通り道に大勢が殺到するから、ちょっと古いかもしれんが、明石花火大会歩道橋の圧死事故みたいに押しつぶされちゃうんだ。どうだ、少しはワシの言わんとしてることが理解できたか」
「理解できたというか、そのお‥‥‥」
「なんだ、まだムンクの『叫び』みたいな表情だな。なら、さらに噛み砕いて説明してやるよ。タランチュラっていうデカい毒グモがいるだろう」
「はい、有名ですね、知ってます」
「赤井君の作品はタランチュラみたいに毒が詰まっている。その毒気の強さで、読み出した人は暗い気持ちになるんだな。だから敬遠されてしまうんだよ。引いちゃって投げ出しちゃうわけだ。だけどな‥‥‥だけど毒蜘蛛タランチュラみたいな嫌われ者だって、哀れかな、カンボジアなんかではスナック菓子やら何やらの食材にされちゃってるんだ。プロテインやビタミンがいっぱいなんだってよ。栄養食品だ。いかにも食物連鎖の場外にいる人間のやりそうなことだな。今じゃ見つけるのがとても難しい。なぜって皆が食っちまったからだよ。価格も高騰して大変だ。すなわち、みんなが怖がっていた毒グモも、バラバラに刻んで調理すれば、いちやく人気者というわけだ。ワシはこれを赤井君の作品に応用しようとしているんだ。解体して、旨そうなところだけバラ売りするわけだ。いわばコペルニクス的発想の転換だな。花より団子、形より中身といったところだ。そのうちリング内に上がってたっぷり闘ってもらうよ。どうだ、ワシの解説は分かりやすいだろう。池上彰レベルだな。今日もワシゃあ、切れ切れだ」
‥‥‥どこが分かりやすいんだろうか、チンプンカンプンだ。これは禅問答か。象形文字でも読まされてるのか。そんな変テコな譬え話の羅列でなくて、ど真ん中に直球で答えてくんないかなぁ。脳ミソのサーバーがパンクしそうだ。 (・・? ワカンネエ~
「蜘蛛だけじゃないぞ。アフリカや南米では、コオロギなんかが重要なタンパク質やその他の栄養の供給源になってることぐらいは、いくら無知な赤井君でも知らんことはあるまい」
「はあ、どこかで聞いたことがある気がします」
「そうだろう。虫チャンは育てるのに土地も水もあんまりいらないんだ。温室効果ガスもほとんど排出しない。家畜よりよっぽど優秀じゃないか。地球に優しいスーパーフードだ。どうだ、こういう話は面白いだろう」
「はぁ、面白いようなそうでないような‥‥‥」
「よし、それならもっと面白い、取って置きの話をしてやろう。中国じゃあ、今でもゴキブリをすり潰し、錠剤にして漢方薬局で売っているんだ。肝臓や心臓の病気に効くんだってな。いっぱしの健康食品だ。ゴキブリをそのために養殖する産業まである。知らなかったろう。田舎では油で揚げてそのまんま食ってる。ゴキブリの姿揚げだな。洒落てるじゃないか。ワシャな、この度のビジネスのために薬草の花とか薬になる虫とかを詳しく研究してんだ。驚いたろう」
🌷🌸🌻🌹ハナハナハナハナ‥‥‥🐜🐛🐝🐞ムシムシムシムシ
「あの、昆虫の話もいいですけど、僕の仕事内容の話はどこにいっちゃったんでしょうか‥‥‥」
花菱は自分の話に熱中するあまり肝心なことを忘れていたといった、いかにも頓馬な表情をした。しかしここで忘れていたことを認めるわけにもいかず、なんとか取り繕おうとする。
「しかし何かね、ここまで解説してやったのに昆虫の大切さが分からんとはな‥‥‥‥いいかね、鳥だって魚だって爬虫類だって両生類だって昆虫を餌にしてるんだ。昆虫がいなけりゃ彼らは飢え死にだ。そしたら鳥や魚を食べている動物たちも、ワシら人間様たちだって困るだろ。シドニー大学のサンチェス・バイヨ博士はその研究論文で世界の昆虫の数が年間約2.5%減少していると述べている。十年で25%、四十年経ったらどうなる? ワシの言わんとすることはそういうことだ。どうだ、わが博覧強記ぶりに舌を巻いたか」
「はぁ〜、でもちょっとそれ」
「おっとっと、そうだった、そうだった。君は小説のことを聞きたがっとったんだな。確かワシ、虫の話の前に君の作品の話をしとったな。ワシとしたことが‥‥‥小説のことは忘れとらんぞ。どこにも行かん、ちゃんとここにある」と、花菱はわざとらしい。
小説の話も虫の話もいいが、一番聞きたいのは僕がどういう仕事をするかということだ。
「なにも君の作品をゴキブリ扱いする気はないが、このままじゃ駄目だ。発想を変えんとな。赤井君、そこそこポテンシャルはあると過信してるかもしれないが、このまま同じことに励んでいても一生、芽は出ないぞ。いくら頑張っても子供に恵まれないなら、人工授精しなきゃあ。文学新人賞なんざ、お仏壇にでも供えとけ。どうせ供えたところで願いは叶わないよ。だから鼻で笑っときゃいいんじゃ」
「はぁ?」
人工授精? お仏壇? 譬えが飛躍し過ぎていて全くピンとこない。コイツは僕の仕事内容の話をどこでしたつもりになってるんだろう。まだ何も具体的なことは言ってないだろう。話した端から全部忘れていっちゃうんじゃないのか。いったい小説の話をしたいのか、昆虫の話がしたいのか、何の話しがしたいんだ‥‥‥‥‥ちょっと待てよ、コオロギやゴキブリは明らかに昆虫だが、蜘蛛って昆虫に属すんだったかな? どうだったっけ?
そんなどうでもいい枝葉末節が気になりだし、赤井君が考え込んでいると、
「ワシの修辞法がハイレベル過ぎて、ついて来れないか」と花菱の勝ち誇った顔。
「いえ、そのお‥‥‥」
「ついて来れないのなら、ちょっと赤井君はIQがタランチュラ!」
‥‥‥ん? 足らないとタランチュラを掛けたの? あちゃ~、ズッコケた。こりゃあ寒い。空転だ。滑りたい放題の不良品スタッドレスタイヤか。
笑ってあげるべきところを笑わなかったせいで、気まずい空気になってしまった。さしもの花菱も極まり悪いのだろう。自ら言った駄洒落を自ら笑ってごまかそうとしている。照れ隠しの自作自演か。売れない芸人の悲哀感を、そっくりそのままを見せつけられるのは切ない。
‥‥‥‥申し訳ない、沈没させる気なんてさらさらなかったんだが。せめて気のない薄ら笑いぐらい洩らしていれば‥‥‥‥花菱社長、もう僕の仕事内容なんて分かんなくていいです。
居心地の悪さを振り払らおうと「さすが社長、心憎い。多彩なユーモアがおありで‥‥‥」と、遅ればせながら、歯の浮くようなお世辞でフォローする。
「いやいや、それ程でもないよ。話が分かんなくても、やってくうちに見えてくるよ。気にすんな。最後の最後までスキームが見えてこなくたって一向かまわん。知略にたけたワシに全部まかせとけ。することなくて暇だったら、エッチ本を買ってきて、ここでオナったっていいぞ。ワシはもうとっくに種なしだから、みじめに指をくわえて見ててやるよ」
ズッコケたと思った駄洒落が褒められたせいだろうか、それとも猥褻ジョークで弾みがついたせいだろうか。何がなんだかわからないが、イケメンに嫉妬してヘコんでいたはずの花菱がすっかり気を良くして、いつしか本格的な笑い声になっている。赤ん坊のように喜怒哀楽がコロコロ変わる奴だ。感情の気圧変化がそうまで激しいと、こっちのホルモンバランスまで崩れてきそうだ。
「やっぱり一人エッチは嫌か。男だから嫌だよな。なら、今からお風呂に行ってもいいぞ。金は昨日ぜんぶ使っちまってスッテンテン‥‥‥‥なわけないよな。まだ残ってるだろう。お風呂と言ったって銭湯じゃないぞ。間違えてお湯のなかにアレ浮かせて恥かくなよ。さては昨日の夜にソープランドに行ったな。頭に綺麗な天使の輪ができてるからバレてるぞ。昨日はフケで火山灰まぶしたような髪の毛だったからな。でも、いくら若くたって、昨日の今日じゃ貯まるまで実弾射撃できないか。ソープに行くのはいいが、チョロチョロとたれるだけなら、女の子に馬鹿にされて笑われちゃうもんな。まさか赤井君のアレは未だにルーズソックス状態じゃないだろうな。そんなの恥だぞ。アレがたまるのを待って早いとこ筆下ししてもらえ」
昨日の夜のことが蘇り、少し屈辱的な気持ちになった。花菱はソファを叩いて呵々大笑だ。でっぷりした腹がさらに膨らんで揺れている。どこまで下ネタが好きなんだ。
「僕ってそんなにおかしいですか?」
「ウブな赤井君に、ちとお茶目がすぎましたかな。笑われるのがお気に召さないのなら、泣いてやってもいいぞ。赤井君、赤井君、にらめっこしましょ、笑うと負けよ、アップップのプウ」
そう言いながら花菱は大笑いだ。太鼓腹が揺れている。そんなに笑うなんてアンタは丸ごと膝小僧か。
「あの、白状すると、昨日の夜、歓楽街をたまたまブラついてると‥‥‥‥」
「たまたまソープがあったんで入った、だろ? 大当たりか。ほんでもって、その“たまたまブラつく”っていうの、駄洒落だろう。アソコのアレがブラブラ揺れているのと掛けてんだな、目新しさはないにしても上出来だぞ。短時間で腕を上げたな。君みたいなオカマっぽい男の子が、突然スケベをかます方がかえってムラムラ感が出ていい」
‥‥‥え? これってシャレなの? 気づかなかったなぁ、それにしても寒い。
「ご褒美にしゃぶってやろうか、そこ」
「エ、え~~~えッ?!」
「冗談だ、冗談。本気にする奴があるか」
花菱は僕をからかって上機嫌、さっきから笑いっぱなしだ。この下品な笑い声をぜんぶ袋に詰めてどっかに持っていってくれないかなぁ。細い目の端から涙を流しながら笑い転げている。泣くほど可笑しいということか。歳でだいぶ涙腺がゆるんでるんだな。誰でも歳をとれば涙腺がゆるくなる。なぜ? それだけ悲しいことを一杯経験することになるから?
「さて生粋の大阪人ならこれをどうやって褒めるか、だな」
「なに言うてまんねん、そなアホな‥‥‥‥ですか?」
「うん、そうだぁ。こういう時にこそ使うんだ。飲みこみが早いじゃないか。若い奴らはいいな、どんどん吸収する。何でもかんでもすぐ憶わる。ワシらなんざ全然憶わらないんだ。日々、入ってくるより出ていくもののほうが多くなる。そのうちカラッポになるんじゃないかねぇ。ああ、諸行無常が身に沁みるよ」
「そんなことないですよ、十分いまでも聡明でいらっしゃる」
「嬉しいこと言ってくれるじゃないか。何はともあれ、そうかそうか、筆おろしは無事済んだか。筆下しはプロにお願いするに限る。でも分かってるだろうが、結婚する気がないならくれぐれも素人娘には手を出すなよ。赤井君はつまみ食いのつもりでも、向こうは赤井君に全人生をくれてやったと思うぞ。私の全てを与えたんだから、それに見合うものを返せとなる。返せないだろう。返せと言われたって、今の赤井君がそんな価値あるものを持ってるか? 悪くすると修羅場になるぞ。まあ男は子だねが無尽蔵にある一方で、女の卵は数が限られてるからな。一回のセックスの重みが違ってくるんだよ。男女の性に隔たりがあるのも無理はないってことだ」
蘊蓄のあるところを披露しているつもりなんだろう。花菱はしたり顔で、のべつ幕無し喋りまくる。よく話すネタがあるもんだ。けど、どれもこれも何処かで聞いたことがあるようなテンプレ話なので、途中で少々飽きてきた。全く余白の無いこの話は、果たしていつまで続くのか? 開かずの踏切の、いつ果てるとも知れない警報音だ。だんだん気に障ってきたので馬耳東風を決め込む。
しばらく上の空のまま花菱を眺めていたら、そのでっぷりした腹に妙に関心がいった。想像のうちに花菱のワイシャツのボタンを一つ一つ外していく。すると中から金ぴかの大きな金属球が現れた。
面白がって、その金ぴかの球を磨きあげ、自分の顔を映してみる。顔と体が溶け合ってブヨンブヨンに引きのばされている。カーニバルの魔法の鏡にうつし出される像。鏡の向こう側の世界に自分の後ろ姿が迷い込んでいくかのようだ。
それとも、事によるとその腹は張り子で中空になっていて、僕は小人になってそこに入っている。腹の中は暗く、プカプカ空に浮かぶ飛行船の内部にいる気分だ。広げた蝙蝠傘や黒く大きなテントのような天幕が上からおおいかぶさってくる。やがて視界がおおわれ、周囲は闇に包まれる。この世の終わりを見るかのようだ。
そのまま時が経ち、退屈した僕は腹の中でチューインガムを膨らまし、もう一つの小さな中空をつくった。爪を立てては破裂させ、破裂させてはまたチューインガムを噛んで膨らます‥‥‥そういうことを何度も繰り返して遊んだ。
そのうち飽きてきた。何を思ったか、僕は周囲の黒い幕をナイフで逆V字に大きく切り裂いた。幕がめくれる。幕のむこうには真っ赤な世界が広がっていた。初めそれを夕焼けだと思った。だかそう思う間もなく、夕焼けの世界がこちら側にあふれ出してきたのだ。
血だった。反射的に大声をあげる。血はどんどんあふれ出し、目の中にも、口の中にも、鼻の中にも流れ込んできて息ができない。まもなく僕は、もがき苦しみ死んでしまう。死体は廃液に浮かぶ魚さながら、血の海にポッカリ白い腹を出して、永遠に漂いつづける。
(12)
「よお」
その声は箱村だ。視野を彼の細長い体が縦に区切っている。
「ボーッとしちゃって、また何か見てたのか。いいイメージだったら、忘れないうちに何かに書き留めとけよ。しかしなあ、今日はショボくねえな、パリッとした服を着てるじゃないか。なかなか粋な着こなしだ。高かったろう。オートクチュールじゃねえだろうな。靴もいい。昨日の小便臭い、くたびれたズック靴はちゃんと処分しただろうな。今日は無粋な昨日と大違いだぞ。いくら何でもあれはダサ過ぎだったからな。ゴミステーションに捨ててあった古作業着をはおっていたかと思ったぜ。モテたきゃ、オスは孔雀の飾り羽みてえに着飾らなきゃいけねえ。この勢いで次はいっちょ、羽織袴姿で来るか。程度の低い女は身なりで男の価値を見積もるからな。とはいえモテるならどんな女でもいいって訳じゃないか、さすがのお前さんだって」
相も変わらず、ざっくばらんによく喋る。しかしその口の悪さはどうにかならんものだろうか。箱村も花菱も同類の臭いが漂っている。二人とも口から先に生まれてきたに違いない。脳ミソでなく反射神経で喋っている。口数の多い者ほど話す中身は薄くなる。「最も知る者は最も語らない(Who knows most, speaks least)」と英語ことわざ辞典にも載ってるじゃないか。中高生のころ学校で習ったろう。哲学者は寡黙だというが、確かにそうだ。それに引き替えコイツらは頭に浮かんだことを咀嚼もせずに、反射的に次から次へと垂れ流す。いちいち流さないと、下らない思い付きの汚物で便器が詰まってしまうからなのか。
「この服、ぜんぜん高くないです。ぜんぶ三千円均一の特売品で揃えました」
また腹の中と違うことを、しゃあしゃあと言葉にしてしまっている。我ながら情けない。
「なにもバラすこたないぜ。さすが“さとり世代”はつつましいな。言わなきゃ分かんねえだろうが。せっかくの粋が野暮になっちゃうじゃないの。やっぱりお前、世渡り下手だな。正直者が馬鹿を見る、の典型だ」
なんとも不思議な香りが辺りにただよい始めた。部屋の空気が澱んでいるせいだろうか。昨日の匂いとは別だが、これまた不安定な感覚をの脳みそに強いる匂いだ。空っぽの頭のなかに観念の芯のようなものが出来上がり、頭を振るとそれが鈴のように鳴りだしはじめる‥‥‥そんな気がしてくる。どうやらその匂いは箱村の手に握られている湯呑から出ているらしい。
「この服が買えたのも社長さんのおかげで‥‥‥」
と、花菱を見れば彼はもう目をしょぼつかせていて、コックリと頷いただけで瞼を閉じてしまう。やがてデカ腹が、その分厚い脂肪組織を上下に大きく波打たせはじめる。とんだ寝虫野郎だ。気づいたらいつの間にか眠っているところまで高木ブーそっくりである。
「もう話しかけない方がいいかもしんねえな。こう見えて社長は不眠症なんだな。ジジイになると、みんな眠れなくなるのかいな。思いのほか繊細で笑っちゃうだろう。だから眠れるときに寝ておこうという、勝手気ままなライフスタイル。少しでも眠くなったらいつもこの有り様だ」
「こうやっていつもダラダラと寝てるから、夜に寝れなくて不眠症になるんじゃないですか? 実は過眠症だったりして」
「言えてるかもな。狸寝入りっていうか、豚寝入りっていうか。まあ、日光東照宮の眠り猫ってとこだな。眠ってるように見せながら、いつ飛びかかってくるか知らねえぞ。よく見てみろ、薄目を開けてるだろう‥‥‥‥‥アハ、これは冗談。半分寝て半分起きてるって感じかな。さっきお前がこの部屋に入ってきた時に思ったとおりだよ。どうしてお前の考えてたことが分かるかって? そりゃわかるさ、何でだと思う?」
「さあ」
「お前は俺自身を映す鏡だからさ」
「???」
「もっと分かんなくなったか。まぁいいよ、要するにお前と俺は一心同体ってことだ」
「眠り猫って、社長は嘘寝してるんですか」
「ガハハハッ‥‥‥ビビりだな、本気にしてやんの。このヘタレにいちゃんが。鼾でもかいて寝てなきゃぁ信用できないのか。嘘寝は簡単だが嘘鼾は難しいから、とでも屁理屈をこねるのかい? 眠り猫はギャグだよ、ギャグ。それにしてもギリシャ神話の眠りの神、ヒプノスは美青年だったはずだがな。あれまあ、それがこんなに太っちまったらおしまいですな」
「シーッ、聞こえますよ」
「聞こえちゃいないよ‥‥‥やっぱり聞こえてるかな? どうでもいいよ、そんなこと。ケツの穴が小さいな。さてさて社長の駄洒落連発の洗礼は受けましたかな。どうだった、アイツのズッコケ具合は? 下らなかったろう。笑わせてるつもりで笑われてるのが分かんねえんだ」
「いえ、いろいろとタメになる話を聞きました」
「話がタメになったって言うかぁ?! 笑わせてくれるねえ。そっちの方がよっぽど観客席に受けるボケだ。爆笑の渦だよ。おっと忘れてた、それより何より、お前、これ飲みな。冷めないうちに」
「いったい何ですか、それ」
「いいから。そんな木で鼻をくくったような言い方すんな。そんな邪険に背中を向けんなよ。せっかく淹れたんだから口ぐらいつけろや」
「お茶にしては独特すぎる匂いですね、まさか都会ではびっこてる幻覚剤とか麻薬とか、そんなんじゃないですよね」
「まさか。俺みたいな謹厳実直な人間がどんなルートでそんなもん手に入れると言うんだ。特製ブレンドだよ。俺たちは夢茶と呼んでいる。何を隠そう、名付け親は俺だぞ。いろんな草花やキノコを絶妙に配合してある。ぜんぶこの日本で採れるものばっかりだ。俺のオリジナルだ。箱村ブレンドだ。誰にも真似できねえ、すごいだろう。レシピはまだ教えられねえ、アンタはまだ昨日きたばっかりだからな。万が一にも産業スパイだったら困るんでな。そんなことより飲め。お前、男だろう。ちゃんとタマついてんだろう。ぐちゃぐちゃ考えんな。そんな頭なんか取っちまえ。高級ダージリン紅茶だと思って飲め。子供じゃないんだろう、駄々コネんな。右脳がフル回転、感覚がアップグレードされるぞ。俺も飲むからさ」
‥‥‥‥そんなこと言われてもなあ。夢茶? なんじゃい、そりゃ。どうせ眉唾物だろう。こんなところで度胸試しさせる気かよ。飲んだら最後、いよいよ底なし沼にズブズブだろう。
手渡された夢茶に表情を忘れた顔が浮いている。

「飲まされると思うな、自分のために飲むと思え。お前の潜在力とこの夢茶の相互作用で、ブッ飛んだのが浮かんでくるぞ。ほらほら、ケツの穴が小さいな。こんなつまらない事で臆病風に吹かれるな。ほら、しかめっ面すんなって」
「苦虫噛み潰したよな顔にもなりますよ。少し無茶振りキツすぎませんか。飲みたいなら、ご自由にどうぞ。だいたいどこの間抜けな産業スパイがそんな馬鹿々々しい技術を欲しがるんですか。欲しがるのはせいぜい社会の底辺でシンナーでも吸ってるゴロツキぐらいのモンでしょうがぁ〜~~ツ!!」
熱くなって言い過ぎてしまった。とはいえ窮鼠猫を噛むだ。誰だって窮地に追い込まれたと思うんじゃないの、このシチュエーションなら。
当然腹を立てるだろうと思いきや、箱村はしょげ込んでしまった。気圧されてしまったのだろうか。青菜に塩だ。実は体が大きい分だけ気が小さい。恐竜だって大型種はたいてい草食系だ。豪放磊落な性格に見えて、本当は繊細だから、こんなときフォローに困る。表向きには長調のメロディーを高らかに歌うが、心の内ではいつもウジウジと短調のマイナーコードを奏でている。
「すまん。ホラ吹いてた。噛みつかないでくれ。そんなに沸騰してカッカすんなよ。正直に言うと俺のオリジナルじゃないんだ。実はひいお婆さんのオリジナルで‥‥‥」と、気落ちした表情の箱村。内心忸怩たるものがある様子だ。
おいおい、そっちかよ。言いたかったのはそっちじゃないんだが‥‥‥。
(・_・)ヾ(^o^;)ナンデヤネン!
「ひいお婆さんのオリジナルで、小っちゃいころ田舎の山奥に家族が住んでて、俺が病気になってどこかが痛いとき、作って飲ませてくれたんだ。匂いだけでも結構効くが、飲ませてもらうとな、さらに効く。不思議にいい気持になって痛みがとんで無くなった。こう、頭ん中が空っぽになって、それから色んな奇妙な妄想や時には奇怪な情景が浮かんでくる。すごくリアルにな。まるで夢を見てるみたいだ。それが夢茶と名付けた所以だよ。箱村家の秘伝だからな、俺には名付け親になる権利がある。俺は子供の頃、何十回と飲んだぞ。まったく副作用はない。タバコのような常習性もない。ニコチンやアルコールよりずっとマシだ。中毒性はまるで無し、俺が再び飲みだしたのも、社長と会ったちょっと前からだ。それまでずっと飲んでない、長い間忘れてたよ。ましてや禁断症状で指先が震えるなんてこともないぞ。後腐れなしだ。今だって俺の故郷では隠れて使っている奴もいるそうだ。どっかで秘伝がもれたんだろうな。漢方ではどんな草でも何かの薬になると言うそうじゃないか。調合や量を間違えなきゃ大丈夫だ。どうせ俺たちゃ、根無し草人生。草と縁があるんだよ。流されちゃおうぜ。そら、試してみろって、頼むから」
ここまで熱心に勧められると、飲まなきゃ悪いような気がしてくる。なにかの暗示にかかってしまったのかもしれない。なにやら警戒心が溶けていく。
‥‥‥‥飲む飲まないぐらいで、すったもんだするのも大人げないな。もう既にこの匂いだけでかなり朦朧としちゃってるから、いっそのこと飲んじまうか。毒を食らわば皿までだ。
そう思うと肝が据わってきた。湯呑を持つ指先に緊迫感が走る。絡みつく糸が手首に条をつけているような妙に張り詰めた空気。だが思い切って飲んでみると意外に癖がない。ほんのりと甘みすらある。樹木に頭を突っ込んで甘い樹液を吸っていると、知らない間に不安定な幻覚の世界になだれ込んでいく。そんな味だ。
眠気が襲ってきた。底なしの闇に吸い込まれていく意識。僕の影が黒い紙となってヒラヒラと舞っている。
ふと我に返る。眠り込んでしまったのか。箱村がいないことに気づいて、待つこと数分。酩酊する不安定な眼界を縦に仕切る影。箱村だ。彼はテーブルに一冊の本をそっと置く。表紙には、ほとんど裸の女がベッドに仰向けに寝た写真。体を硬直させ、まるで白チョークに布きれを絡ませたような痩せた女だ。幾本もの男の手が四方からその女の裸身を撫でている。男たちは手だけが見えて、それ以外は表紙のフレームの外だ。女は目をむいていて、嫌がっている様子だ。悪趣味といえばそうである。だがアダルト系男性誌特有の、劣情を煽るよくあるパターンであることも確かだ。
「なんですか、これ」
「やってこいよ」
とても長い筒を通して聴いているように、箱村の声がくぐもって感じられる。
「何をですか?」
「アレをさ」
「冗談でしょう」
「いや、マジで。アレした後はアルファ波やシーター波が優勢になり、ほぼ瞑想状態なることを知らんわけでもあるまい。もうすでに夢茶でかなり来てるだろう。互いに作用しあうんだ。相乗効果だよ、相乗効果。もうちょっと待ってみろ、覚醒と睡眠の境界あたりに近づいてくると、いいものがドンドン湧き出してくるぞ」
箱村の声が、いよいよ頭骨の内部を反響してまわる。耳の穴が奥深い洞窟に変わり、そのなかを言霊がエコーを曳いてどこまでも鳴りひびいていく。
「そんなむちゃくちゃな。やれと言われて、すぐやれるもんじゃない。」
花菱がもうこらえきれぬと言わんばかりに、含み笑いをし始めた。肩が始動したエンジンのように揺れている。僕たちの会話に笑っているのか、それとも夢を見て笑っているのか。
「やれるさ。やったら死ぬわけでもないだろう。いつもやってるくせに。そんなに若いくせして、なに泣き言っとる」
思考力を失いつつある僕は、半覚醒状態のままエロ本を掴むと、よろよろと言われるまま歩きだしだ。果たして今見ているこの情景は本物なのだろうか、こんな非現実的な話が実際にありうるのだろうか、と思いながら。
(13)
洗面所の鏡に映った僕の顔は青白く、意識の天井にはエロ本表紙の痩せた女が吊り下がり、嬌笑していた。頭を振りその幻影をふり払おうとする。夢茶を飲んだせいだろうか。ふり払えない。頭蓋裏側のスクリーンに鮮明に映写され続ける。自分で自分が制御できない。意思の力が麻痺している。
「たのむから消えてくれ!」
そう叫びながら、思わず両手に握りしめたナイフを女の腹に突き立てていた。銀の牙が虚空の暗幕を切り裂き、その先端が今、たっぷりと血を吸い込んだ。ほとばしる鮮血。長く尾を引く悲鳴‥‥‥‥え? 僕はなんて恐ろしいことをしている。このナイフはどこにあったんだ? なんでそんなものを握りしめてる。
女は苺を潰すように血走った眼玉をむき、「この小心者め」と罵った。開いた唇から口奥がのぞいた。無限の官能によじれた舌が、唾液に溶けていた。
とつぜん女が顔に鮮血を吐きかけてきた。血はガラスをつたう雫さながら、角膜を流れ落ちる。赤い電流に顔じゅうの筋肉が痙攣する。
目が見えない。宇宙が巨大な炎となって頭上から落ちてくる。僕は糞尿をしぼり出されている馬のように、フロアーの上をのたうち、転げまわる。無形の黒い何物かが、そんな僕を見下ろしている。
「救けてくれ、死にたくない! 殺さないでくれ!」
だがいくら恐怖に打ち震えようが、無形の黒い何物かは決して制裁の手を緩めることはないだろう。永遠に‥‥‥‥‥
洗面台の蛇口をひねる。水がホーロー製の洗面ボウルに落ちる。水とともに眼球もぬけ落ちて、水受けにはじけた。真珠のような虹色の光沢、はじけ飛ぶ二つのガラス玉。
ハンカチで手を拭き、ドアを開けて‥‥‥‥と、そこは長い長い、とても長い廊下だった。少女の手のひらに下りてくる手品師の紐のようにどこまでも続いている。一瞬にしてステッキに変わってしまいそうな紐‥‥‥‥いやそんなことより、あの部屋はどこへ消えた? あったはずの部屋がない。眼前で部屋の角がどんどん取れて、だだっ広い荒野に変わっていく。思考がその荒野を当てどもなく浮遊している。鏡でできた球体にでも閉じ込められているかような錯乱が襲ってくる。
目を凝らすと廊下の奥、ずっと向こうに男が立っている。マッチ棒にも似た、直立するその姿。箱村だ。どうして廊下にいる、それもそんなにも離れたところに。いつの間に部屋を出たんだ。箱村の影はワックス塗りの廊下の上を、とろけかけのアイズバー状にこちらに向かって伸びている。
影の伸びる方向に足ばやに歩きだす。足裏の感覚がない。水中でもがいているかのように体の動きが重い。後ろからエロ本の女の唇が追いかけてくる気配がする、女陰そっくりのあの濃紫の唇が。正面は箱村、歩を進めるごとにその微笑が近づいてくる。
そのとき突然、雷鳴に重ねて閃光の剣が天から振り下ろされ、僕の頭蓋骨を胡桃そのままにパリンと割った。
「やけに早かったじゃこざいませんの? ホントにしてきたのでございまちゅか?」
「途中の記憶が抜け落ちてます。これってホントに現実なんでしょうか。今ここで話している僕は、ホントの僕ですか? 今いるこの世界はホントの世界なんですか?」
「ホントのホントのホントって、そんなのありでちゅか? 面白いざあますわね、おぼっちゃま」
箱村の顔と首がモディリアーニの絵画そのままに細長く、異様なプロポーションを示している。画面上を縦に指でビューンとスワイプされてしまったかのようだ。僕を見つめる黒目の色も薄くて、ほとんど瞳が無いに等しい。
「今度はマスはマスでもマスマティクスのマスでこざいますよ、準備はよろしいですか、おぼっちゃま」
おぼっちゃま? 姿も変なら話し方も変だ。こいつ、ホントに箱村か?
「あら、またホントが出たわね、おぼっちゃま。ホントにホントにホントにホント‥‥‥いったいどれだけ続くのかしら」と言いながら、箱村はテーブルに目線を投じた。
テーブルの上には一枚の紙がのっている。無数の蠅や蚊を潰してくっつけたような数字がぎっしり詰まった紙。
「これ何ですか。クレペリン検査の用紙みたいですが。今度はこれをやれってこと? 意味が全く分からない」
「マスの後もやっぱりマスでちゅよ。マスのマスのマスのマス‥‥‥‥いったいどれだけ続くのかしら。知らないわ、そんなこと! ともかくおやり!」
モディリアーニの細長い顔が白目を吊り上げて怒り出した。事態を飲みこめないまま、遅々と紙上に鉛筆を走らせる。
四プラス七は十一‥‥‥二プラス七は九‥‥‥四プラス八は十二‥‥‥八プラス七は十五‥‥‥
一行目が終わり二行目にさしかかったところで、並んでいる数字の一つ一つが分解し、散りじりになって紙面を這いまわりだす。
眉間の裏側が沸騰しだした。血液が眉間に集中して渦を巻く。さながら赤い毛糸玉にも似て‥‥‥。
脳みそに少しずつ指を押し込まれていくような圧迫感もある。バターの表面にじわじわと沈んでいくスプーンの腹。腹を割られた魚の、ぐにゃぐにゃした半透明のはらわた‥‥‥今の僕の脳みそは、そんなはらわた同然だ。
頭蓋の内側に白い膜があって、それをピンとはじくとシワシワの糸が指に絡みついてきて‥‥‥やがてこの身も砂となって崩れ落ちていく‥‥‥そんなイメージの波に浸りつつ、いつしか意識が深い眠りの底に沈んでいた。

(14)
「俺はそんなこと言ってないし、やってもいないぞ。マスはマスでもマスマティクスのマスだって? 大笑いだぞ。最低最悪のギャグだ。お前が幻想の中で勝手にストーリーをでっち上げ、それを事実だと信じ込んじまってるだけだよ」
箱村は笑いのツボに入っているようだ。いつもながらの豪傑笑いに身をよじっている。
「冗談じゃないですよ、女の人をナイフで殺しそうになったし、女の人も僕を殺そうとした。ものすごい悲鳴だったんですから。怖いも怖くないもあったものじゃない。とつぜん真冬の寒波に襲われたのかと思いましたよ。自律神経がどうにかなっちゃいそうです。すごくリアルだった。あれ、いったい何なんですか?」
なおも箱村はゲラゲラ笑い続ける。
「自律神経って、閉経間近のオバチャンじゃねぇんだぞ。お前の頭ん中で起こったことを俺が分かるわけねえじゃねぇか。いま住んでる物置に、またネズミでも出るのか。その気持ち、分かるぜ。出て来たネズミより、それ見たカミさんの叫び声の方がよっぽど恐ろしいもんな。うちのカミさんにもまして、化け物女の悲鳴は怖かったろう。で、それはそれとしてだ、その化け物女のこと、忘れないうちにどっかに書いとけよ。そいつは使える。そら、そこにメモ用紙があるだろう、そこに書いとけ。マスかき話は書かなくていい、笑えるけど、いらねえ。マスに受けねえ。言っとくけど、こっちのマスはアレのことじゃなくて、大衆って意味の方だぞ」
なにトンチンカン言ってる。鈍感な奴だ。こっちの身にもなってみろ。どうせ書いている間、待ってられなくて途中でベラベラ話しかけてくるんだろう。書いとけと言うが、書く暇がないじゃないか。
「おっと、やっぱ書くのは今でなくていい。それより俺の話に付き合え。な、いいだろ? いろは歌って、知ってんな」
思った通りだ。まだ話したりないでいるな。ヤレヤレあんたの構ってちゃんぶりには呆れるよ。俺が上司だとばかり、我が物顔で僕に話し続ける気だ。
「ええ、いろはにほへと、ちりぬるを‥‥‥でしょう」
「お前って、あれの最後の件がそのまま当てはまるよ」
「僕、最初のほうしか覚えてないんです」
「それでも日本人かよ。浅き夢見し酔ひもせず、で終わるんだよな。思い出しただろう。お前って、いろは歌だな。酔ってるわけでもないのに夢を見ちゃってる。あ~んな夢茶ぐらいでな。もとの意味はそんなんじゃないんだろうけど、俺的にはお前はアレだ、いろは歌ニイチャンだよ。本格的に酔っぱらったらスゲーもん見るんだろうな。期待大だ」
「それ、いろは歌のとんでもない珍解釈なんじゃないですか。ペーパー試験だっだら当然バッテンがつくでしょね」
「昨日お前、俺と駅で初めて会った時、婆さんから飴玉もらってたろう。口をアーンとあけた馬鹿面して、飴玉放り込まれてたろ? この部屋でほんのちょっと煙を吸ったぐらいで妙なぐらいトリップしたのはだな、きっとあの飴玉に強烈な幻覚剤が練り込んであったんじゃねえか?」
「え? あんな優しそうなお婆さんが? そんなことしないでしょう。なんでそんなこと分かるんですか」
「実はあの婆さん、俺たちとグルなんだ」
「え~~~ッ! そんな馬鹿な!」
箱村は壁を叩きながら笑いに笑う。
「慌てふためきんさんな。海より大きな海坊主は出ないぞ」
「え? な、なんですか、それ」
「気にすんな。何となく口から衝いて出ただけだからよ。許せ」
「僕、幻覚剤を使っちゃったんですか?」
「んなわきゃないだろ。お前を薬物中毒にでもしようってのか。小説やドラマの世界なら、そういうの有りだと思うけどさ。さすがにそんな見え見えの伏線は張らないよ。やるならもっと巧妙にやるよ。体質だよ、体質。ガキの頃な、そう、小学校や幼稚園に行く前の幼い頃だ。誰でも空想と現実の区別がつかなくなっちゃうことがよくあるだろう。昨日から観察してると、お前、それだな。そんなガキの頃のまんま、成長せずに大人になっちゃってる。だから背もあんまり伸びなかったんだな、おっとこれは関係ねえか、失礼しやぁした。脳ミソが普通と違って特異なんだろうよ。ちょっとどっかのネジが緩んじゃってるんだな。夢茶ったって、ただの草や葉っぱや花ビラを混ぜてるだけなんだぜ。正常な人間にそこまで効果はないはずだよ。けど一度ゆるんだネジはなかなか締めなおせないな。なんせネジは頭ん中にあるんだからね。簡単にパカッと開いて締めるわけにはいかないもんな。工場労働者のバイトしてなくてよかったねぇ。幻覚みてる間に、お前が運搬物の代わりにベルトコンベヤーで運ばれていっちゃうぞ。それに引きかえ今の仕事、天職なんじゃねえ? ありがたいじゃねえか、こんなピッタリはまる変ちくりんなバイトがあって」
「なんかまだ頭んなかがスッキリしません。虚脱状態です。まだ自分で自分の死体をかついで歩いてるような気がする」
「粗忽長屋の熊五郎かよ」
「はい?」
「落語だよ、今度きいてみな。そうすりゃ意味、分かるから」
部屋は暗くなりかけていた。花菱はまだ眠ったままだ。窓から流れ込む照り輝く黄金の蜜。花菱はその黄昏時の光の粒子の海に、風船のように浮かんでいる。
‥‥‥いつまで寝てるんだろう。白雪姫になりたきゃ化粧でもして女装で寝なきゃあ。でないと王子様はいつまで経ってもキスしに来ないぞ。だけどこんな不細工じゃあ、いくら化粧しても王子様もキスしたがらないか。やっぱりアンタは目覚めないでそのまま寝てろ。でも寝てられたんじゃ、日当もらえないな。昨日いっぱい貰ったから今日はいいか。こんなので金もらったら給料泥棒だ‥‥‥。
「しかしお前の見る幻覚はおもしれえなあ。見たやつ、忘れないうちにパソコンに打ち込んどけ。今日、残業してやっといてくれ。これは上司からの職務命令だ。このアホ社長みたいに、忘れるなんてもったいないことをするなよ。大丈夫だ。残業代は社長に払わせる。これからはいつでもタブレットかアイフォーンでも持って歩きな。幻覚が出て来たと思ったら、その都度それに音声入力するんだ」
すっかり上司気取りだ。
「まあ、座りなよ」
箱村はそう促しながら壁のスイッチを押し、蛍光灯に明かりが灯った。明かりの眩さがコンクリートに包まれた部屋を砂漠にする。影が熱せられた砂粒そのままに、薄っすら床に焦げついている。
「俺もアンタと同じ年くらいの時にいろんな出版社の新人賞にバンバン応募したよ。送れども送れどもぜんぶ一次選考でアウトだ。閉塞感っていうのかな。どんどん滅入ってくるわけよ。そのうち選考にたいして不信が募ってくる。そういう奴は多いと思うよ。俺は力があるのに、なんで分かってくれないんだ、なんでいつも凡作の烙印を押すんだってね。応募作品が没になったとき、たいてい当選作と自分の作品を突き合わせて比べるだろう。そうすると俺の方が劣っているとは思えないんだよな。そう思ったのは村上龍が『限りなく透明に近いブルー』で新人賞を取ったときだけだ。これってどうなんだろうか。俺以外の人が十人いて、彼らが当選作と俺のとを読み比べれば、十人が十人とも当選作のほうが優れているって思うんだろうか。もちろんその答え合わせなんてできない。けど仮にその答えがイエスだとすれば、人ってのは自分を過大評価するものだとしか考えようがない。人は栄冠は俺に輝くもんだと信じ込んでる。実際は通行人のチョイ役なのに、自分は主役だってな顔してさ。で、自分を高く見積もり過ぎた結果、そんな不満が生ずるんだな。ほんとは大したことないかもしれないのによ」
「ダニング・クルーガー効果ですね」
「何じゃい、そりゃ」
「コーネル大の心理学者、ダニングとクルーガーの認知バイアスの仮説ですよ。“能力が低い人ほど自己評価が高く、能力が高い人ほど自己評価が低い”っていう」
「おい、そういうとこだぞ、お前の鼻持ちならないとこは。なけなしの知識を隙あらば披露したがる‥‥‥卑しいぞ、ちょっと」
「いや、これ有名な話ですって。みんな知ってる、だから‥‥‥」
「そういう風に薄らとぼけるとこが、ますます卑しい」
「こりゃ、まいったな」
「けどそいつ等の言うこと、まんざら的外れでもないな。確かに力のない奴ほど、すぐ自惚れる。しかし大学の偉い先生でなくても、そんなこた誰だって過去を振り返れば思い当たる、何も御大層に論文なんかにしなくてもよぉ、何も。待って、それって自分を過大評価する俺が無能だって暗に言ってるのか? おい、馬鹿にしてんのか!」
「まあまあ抑えて、僕だって同じですから」
「おうそうか。なるほど俺もお前もそうなんだな。みんなそうなんだ。だったら合点がいく」
「何なら僕が箱村さんの作品と当時の当選作とを読み比べてみましょうか。身びいきせずに公平に評価します」
「お前じゃ駄目だ」
「どうして?」
「だってお前は色ボケしてるだろう、作品の評価者としては失格だ」
「????」
「で、俺なに話してたんだった? お前が横からチャチャ入れるから忘れちゃったじゃないか」
「出しても出しても一次で落とされるから不信感がわいてきたっていう話」
「うん、そうだった、そうだった。ほんで始めのうちは勢いがあったんだが、やがて書きためていたプロットのネタがぜんぶ尽きちまったんだ。仕方ないので同じ作品を出版社の賞という賞に手当たり次第に送った。さすがにまるっきり同じじゃ芸がないと思って、出版社ごとにストーリー展開を少しだけ変えるというあくどさだ。あわよくばどれかに引っかかって、二次選考まで進めないかなあと思って。“二兎を追う者は一兎をも得ず”と言うけど、どれもこれも追いかければ一兎ぐらいはなんとかなるとね。たぶんバレたんだろう、もちろん全滅だ。ネタはこれ以上湧いてこない。もう書けない。そうなると不信感を昂じさせるあまり有害な想念が次から次へと発芽してくる。いくら洗っても黒々とした感情は洗い落とせない。まるで殺人犯が必死で手に付着した血液を洗い流そうとするけど落ちないようにだ。そのうち憎しみの根っこが張って、ちょっとやそっとで抜けなくなっちまった。万事休すだ。赤井、こういうの四字熟語でなんて言うんだ」
「なんでそこで四字熟語の話になるんですか?」
「いいから。俺のちょっとしたこだわりなんだ」
「そうですねぇ、疑心暗鬼とか‥‥‥‥他には、え~と‥‥‥」
「おう、それそれ、疑心暗鬼だよ。疑心暗鬼を生じちゃって苦しいんだ。どうやら不信とか憎悪とかってのは、長い時間をかけて少しずつ溜まりに溜まっていくもののようなんだ。そのとき考えたよ。人生なんて思うがままにならないのが普通だろう。全部落とされたと言ったって、そりゃ起こるべきことが普通に起こっただけのことだ。なのに同じ作品をダブって違う出版社に送るなんて‥‥‥‥お前はそこまで自尊心を貶めてまでして、小説家になりたいのかって。そういうのを身の程知らずって言うんじゃないのか、ってな。“もっと公平に俺の作品を評価してくれ”と傲慢なことをほざいたとしても、だいたいこの世に完璧な公平さで作品を評価できる奴なんているのか。そんな奴、一人もいねえよ。同じものを見ても、誰一人完全に同じ見方はできない。誰が評価したって不公平になるんだ。かりに俺やお前が評価する立場になっても、やっぱり不公平になるよ。むこうは専門家だから俺たちより少しはましかもしんねえが」
「専門家だから柵がいろいろあって、かえって公平にできないとかあるかもしれない」
「そりゃ分かんねえけどよ。いずれにせよ、もう誰かさんが俺の作品をどう品定めしようが、そんなの関係ねえの児島よしおで行くことにしたんだ。上げようが下げようが好きにしなさんな。俺は自分の作品を信頼している、それで十分だって。もう自分の意志だけでコントロールできるものしか信頼しない。自分の手の内にあることだけにしか時間を使わない。他人様の評価の奴隷になんかなるもんか。小説家がナンボのもんじゃい、やめちまえって。本当に力のある奴は、自分に力があるなんて思わない、もっと謙虚で、客観的に自分の実力を分析している。冷静で向上心がある反面、俺らよりずっと貪欲ときてる。勝てねえよ、才能以前の問題だ。だいたい作家になりたい奴が作家になれる確率ってどれぐらいなんだ。普通預金の利率よりはるかに低いと思うぜ。今になって振り返ると、応募して選ばれなかったと怒ることの馬鹿さ具合は、宝くじを買って当たらなかったと怒るのと同じだな。しかも選ばれた奴にしたって、そのうちの何パーセントが生き残れるかどうか。50人に一人か、100人に一人か‥‥‥‥地球の歴史を一年だとすれば人間の歴史は大晦日の最後の一分間ぐらいだ、ってよく言うだろう」
「天文学者のカール・セーガンですよね。あの番組、面白くて僕もテレビで見ました」
「おいおい、それ四十年ぐらい前の話だろ。なんでお前が生きててテレビを見てるんだ」
「どうしてかな、時々そういうことがあるんです」
「ま、そりゃいいわ。何であれ言いたいことは、俺らがいっぱしに小説家様と世間から呼ばれるようになる見込みは、それぐらいちっぽけだってことだよ」
「一昨年も宝くじ一等に当たって、去年も一等に当たって、今年も当たっちゃったぐらいの話かな。都会の中心街を歩いていると、上から飛び降り自殺者が落ちてきて下敷きになっちゃうぐらいの確率かな。もっとひねった言い方をすれば、魂がこの世に肉体をもって生まれ出てこられるぐらいの確率かな。コマーシャルにのせられて気安く宝くじを買うな。はしゃいでいるのは当たった奴だけ。外れた大部分はどっ白け。中には逆恨みする者まで出てくる」
「うまいこと言うじゃないか。冷静になって考えれば、そんな感じだな。宝くじ業界って大衆の夢を餌に商売してるわけだろう。バクと一緒だな。大衆の夢を食べて生きているんだ。小説家になりたいっていう夢もおなじだぞ。バクに食われるだけだ。もっともバクは悪夢が好物だと言うから、食われた方がいいかもな。今お前は悪夢を見てる。ついでにいつも大口たたいているどこぞのデブ社長の法螺もバクに食って欲しいぜ」
「宝くじは基本、当たらない。小説もそれと同じで、書いて出したってデビューどころかたいてい世間の目にふれないまま右から左に消えていく。そこを踏まえてないと。芸人や歌手になりたい人と一緒だ。理想と現実には落差があるのが普通ですもんね」
「そうなんだ。ペンネームもクソもない。その名も、闇から闇太郎だな。だから今はこう思ってるよ。あのころ俺は溺れそうになってたんだって。溺れそうだったら自分が救われることしか考えられないだろう。他人が溺れかかってるかどうかなんて眼中にない。だから自己中で、やれ選考がどうのこうの、やれ受賞者の作品がどうのこうのと不平を言い出す。だけど誰が溺れかかってるかなんて神様にしか分からない。人の心は読めないからな。選考者や受賞者の中にだって辛くて溺れかかっている人がいたかもしれないだろう。お前、日本で一番不幸な人って、誰だと思う?」
「さあ、僕みたいに社会の底辺にいる連中かな?」
「なに言ってんだ。まだ若いじゃねえか。死はまだ遥か彼方にある。ジジイやババアはどうなっちゃうんだ、余命いくばくもないジジイやババアは。残り時間はあまりないんだぜ。チクタク、チクタク‥‥‥‥人生の終末時計は刻々と進んでいく。しかも流れ去る時間は若い頃よりずっと速い。まあ、ご老人のなかには、生きながらも仏にすくい取られて天に昇っていける人もいるにはいるが、きわめて稀だ。若者の未来は薔薇色、老人の未来は灰色じゃねえか。老人にはただ過去の思い出があるばかり、もう未来はほとんど無いに等しい。そうだろう、贅沢いうな」
「そうなんだ、言われてみれば。じゃ誰かな」
「俺は一番不幸なのは内閣総理大臣と天皇陛下だと思うぜ。みんな、うらやましがってるけどな。作品をいっぱい応募していた若い頃、自分と比べてあの作家の才能がどうのこうの、その作品の出来がどうのこうのと、選考にいちゃもんつけたりしていたが、何事も実際に自分がその立場になってみなけりゃ、その大変さは分からない。すべては上辺どおりでない。作家ってのはただ自分の書きたいものを書いて、それを売って読んでもらうだけの仕事じゃないと思うぜ。他にも表面に出てこない神経を逆なでするようなグダグダが一杯あって、それにも耐えてかなきゃなんないんだろうよ。なれないことは百も承知だが、かりに俺がその立場になったとすれば、その時はじめて才能うんぬん以上の、彼ら彼女らの敬意を払うべき凄い点が見えてくることだろうな。そういうリスペクトすべき点がなけりゃ、とてもあんな割の合わない過酷な仕事をやめずに続けていけるはずはねえ。てか、今となってはそういうふうに考えないと救われねえ」
「グダグダって例えば?」
「すぐには浮かばないけどアレだよ。小説ってエンタメだろ? 演劇やってる劇団員とかオーケストラの楽団員だって自分でキップを売ってたりするだろう。エンタメじゃないけど、通訳だってただ言語を訳してりゃそれでOKってワケじゃない。売り込みもしなきゃいけないそうだぜ。作家だって書店で自分の本に一生懸命サインして客に渡してるじゃねえか。ありゃAKBの握手会といっしょだよ。そういう昔ながらの戦略はそれなりの効果があるから生き続けている。だから恥ずかしくてやるのが嫌な、内向的な人もやらないわけにはいかない。それにアレだよ、アレ、この前の芥川賞の授賞式なんか、記者の意地悪な質問に受賞者が相当ストレスを感じてるように俺には見えたな。可哀想なぐらいだよ。あんな感じのが他にも一杯あるに違いねぇ。華やかな仕事でも、いや華やかであるほど実際には便所掃除、ドブ掃除がついてくるとしたもんだ」
「う~ん、そう言われてみれば確かにいえてるかも」
「だろ? だからいくら作家になりたくても、ならない方が幸せなんだ。欲しいと思うことの若干を持たずに生きていくことこそ、人生の最大幸福を享受できるんだぞ。そっちの方が全てを手に入れた人よりずっと幸せなんだ。もっとも全てを手に入れる人なんて、実際にはいないけどな」
「ごもっとも。箱村さん、ずいぶんと哲学的じゃないですか」
「こんなことを考えてみな。天気予報が雨だったので傘を持って出かけた。ところがずっと晴れていたので、傘をどこかに置き忘れた。責任があるのは気象予報士かお前か?」
「置き忘れた僕でしょうね」
「そうだろう。もともと小説家になろうと決めたのは自分じゃないか。だったら全部一次で落ちて惨めな思いをしたとしても、その責任は自分にある。それを選考がおかしいなどと他人のせいにするからダメなんだ、ってね」
「なるほど。でも何というか、そうは言うものの、ずっと書き続けていれば何かの拍子で棚ボタも‥‥‥待てば海路の日和ありで、ずっと待ってればある時たまたま強烈に推す選考者が出てきたりして‥‥‥」
「たいした楽観バイアスだぜ。待つって、どれだけ待つんだ。ずっと書き続けていても痛くもかゆくもない奴なら、それもいいだろう。実際にいるよ、そういう奴は。『登山と一緒で苦しいけど楽しい、やめられないんですよね、書くことが』って奴が。人によるな。書くことでどれだけ精神にダメージがあるかに依るよ。俺は駄目だ。赤井、お前はもっと駄目だ。ヤバイぞ、お前。相当ヤバイ。鋭い奴なら作品を読めばわかる。自分を鏡に映してみろ。なんか黒々したものが、上から重くのしかかっているのが見え隠れしてるぞ。書き続けたら必ず逼迫した挙句、ねじ伏せられる。いつか追い詰められてプッツンいくぞ。そのことを見抜ける鋭い奴があんまりいないんだよな。幸運だぞ、見抜ける俺に逢えて。いざという時、ライフジャケットになってやれるからな」
「立ち直りが遅いタイプなんで、そりゃ少しは情緒不安定になりますけど、そこまでダメージがあるようには………」
「やせ我慢すんな。お前は心の傷を甘く見ている。体の傷ならすぐ治る。だけど心は傷つきやすい上に、一度傷つくとなかなか治らない。そのうちジワーッとくるぞ。苦しくてたまらなくなる。誰かがその苦しみを引き起こしてるんじゃないぞ。逆恨みすんな。もちろん神様が引き起こしてるわけでもない。自分で自分自身を苦しめることになるんだよ。俺が通ってきた道だから分かるんだ」
「だけど箱村さんは無事だった」
「俺はタフガイだからな。いくら撃たれても弾の当たらないシュワちゃんだよ。だけどお前は弱っちいから駄目だ」
「タフというより鈍感だからじゃぁ‥‥‥おっと」
「実は社長もそれを見抜いてる。あの野郎、見抜いていながら芸術至上主義気取りで、知らんぷりだ。前例があるのによ」
「前例?」
「あッ、それはこっちの話だ。こだわるな。こっちよりそっちだ」
「そっちって?」
「アホの花菱の話だよ。そ~だねぇ、それはつまり‥‥‥‥芥川龍之介の小説に『河童』ってのがあるだろう。読んだことあるか」
「中学生のとき、図書室にあったので昼休みに読みましたね。思い出があります。内容はどんなんだったか、忘れちゃったけど。なんか精神病患者の主人公が上高地で河童を追いかけて、それから河童に国に行って、しばらく経ってまたこっちに戻ってきたって話。たぶん河童の国というのは心の病の主人公の幻覚でしょね」
「よく覚えてるじゃないか。そっか、お前にとっちゃ、中学生なんて少し前のことだもんな。あれ短い小説だろう。なんか懐かしくてさ、昨日ひさしぶりに読み返してみたんだ。今はネットの青空文庫なんかで簡単に読めるだろう。そしたらさ、トックっていう河童の詩人がでてきてよ、花菱の野郎と同じこと言ってやがんだよ。“芸術は何ものの支配をも受けない、芸術のための芸術である。したがって芸術家たるものは何よりも先に善悪を絶した超人でなければならぬ”と、そんな感じだ。いってえ何様のつもりだ。相手は生身の人間なのによ。とくにお前みたいな作風は危ねえよ。おまけに超繊細ときてる。ともかく書くつもりなら、もっと歳くって感性も鈍り、才気のカケラも無くなってから書きな。人生、回り道もいいもんだ、ちょいと大まわりだけどな。ジジイになっちまったらこっちのもんだろう。もう危うくない、安全だな」
「そうですか、考えときます。それはそうと箱村さん、我慢しましたね。“連戦連敗、しかもぜんぶ初戦で”はさすがにキツイと思う。何回走ってもいつも予選落ちするなんてツイてない人生ですよ。人間は感情の動物だから。たまには決勝で走りたいですよね」
「それ裏返すと、今第一線で活躍してる作家はツイてたから活躍出来てるってことか? それにくらべて俺はついてないだけだと」
「箱村さんはねぇ‥‥‥‥運がつかない、人目につかない、愚にもつかない、除夜の鐘つかない、餅つかない‥‥‥ついたのはケチと疫病神だけ」
「何ごちゃごちゃ言うてまんねん、尾ヒレつき過ぎでんがなwwwww───けど第一線で活躍してる作家はツイてただけってのは、ちょいと嫌味が過ぎるな、不公平な言い方だ」
「ツキも実力のうちと言うことで。あの人たちは人間力があるからツキもついてくるわけで‥‥‥」
「うまいことスカすじゃねえか。投げられても受身がうまいな‥‥‥‥待てよ、それって俺が人間ができてないってことになんない?」
「そういうことになっちゃいますかねえ」
「馬鹿! 人間力なんてどうでもいいの井伊直弼だ。運も不運もそのまんま受け容れちまえ。ツイてない人生こそが、本当はツイてる人生なんだよ。このパラドックスが分かるか?」
「どういうことなんです?」
「皆から注目されて、皆がやりたがる仕事ってのは、たいてい外と内が真逆だよ。もっとも小説家先生達はだんだん影が薄くなって、今じゃもう花形職業ってわけにもいかないかもしんないけどな。だいたい有名ナントカカントカなんて言われてキラびやかな世界にいる人なんか、外からは羨ましがられるけど当の御本人様は大変だ。スポットライトを浴びて見えるのは客席からだけで、実際は過重労働、過剰ストレス、過当競争と、いくらでも並べられる有り様だ。馬車馬のように働いて、こま鼠のように追いまくられてる………こういうの四字熟語で何ていうんだ?」
「またまたぁ。羊頭狗肉ですか? 看板に羊の肉ってあったから、買って食べたら犬の肉だった、みたいな」
「言いたいのはそっちの方じゃないよ」
「いったいどっちなんです?」
「羊頭狗肉の方じゃねえんだ。クイズ番組じゃねえから無理して四字熟語にすることもないんだが。A型だから型にはめなきゃ収まらない性分なんだ。あれだよ、あれ………なんて言うかなあ、しっくりくるのが出てこないなあ。まぁ出てこないから人権蹂躙でいいや」
「人権蹂躙ですか!?」
「いや、そんな御たいそうなモンじゃないんだが、老化で言葉が出てこないもんでな。言葉はアレだけど、仮にまかり間違ってお前みたいに平凡のど真ん中にいる奴が、流行作家になんかになってみろ。一瞬にして自分と言うものがなくなっちゃうぜ。ひと昔のアイドルみたいに朝から晩まで過密スケジュールのなかを操り人形になって引きずり回される。疲れ果てるぜ。でもそういったのも長くは続かない。すぐマスコミからも大衆からも飽きられる。でな、それからが大変だ。本来、小説家っていうのは今までなかったものをゼロから作り出さなければいけない。たとえば工員だったり事務員だったら何にも創造しなくていい。仕事が面白くなくても陰で文句言ってればいい。やることはお定まりだから、我慢してただ同じことをチンタラやっていけばすむ。だが小説家ってのは作り出さなければいけない。いくらヤル気があっても、アイデアやイメージやストーリーが出てこなければ話にならない。若いうちはいいが、老いてくると誰だって頭が固くなって出てこなくなる。それでも自分と家族の生活がかかっているから、ガチガチになった頭からもう一滴も出ないというぐらいに必死で搾りだす。ところがそれを出版社に持ち込んだら、年下の編集者から『こんな使えないものを持ってこられても、ウチではちょっと載せられませんね。旬な頃ならいざしらず』って言われる。屈辱だな。それどころか、もともと依頼されていたものを書きあげて持って行っても、やっぱりこれ面白くないからヤメだ、ってご破算になることもザラだって聞いたぞ。業界の慣わしで事前に契約書もとりかわしてないから、そう言われたってお手上げだ。最悪、原稿料も出ない。最悪でなくても出ない。それでも書くこと以外能がないなら、逆らって干されたら困る。あそこの玉を握られてるのと一緒で、文句も言えない。年取ってから辞めて堅気になってもロクな仕事にはありつけないからな。最悪だな。飼い殺し状態ってとこだ。なんでこれに自分の全人生を委ねちゃったんだと後悔したって時すでに遅し。お前、それでも小説家になりたいって言うのか? 何だかんだ言ったって、出版社と作家の上下関係は親企業と下請企業、雇用者と契約社員の関係だよ。いわゆる優越的地位ってやつだ。人によっては、どんな横車を押してくるか分かんねえぞ。お前、どんな無理難題を要求されてもそれに唯唯諾諾といちいち従うのか。」
「いや、今んとこはちょっと回答保留ということで‥‥‥いま小説を奪われると、魂までいっしょに奪われちゃう気がして‥‥‥」
「え? それでも作家になりたいって? 世間的に見栄えがいいからって、わざわざピンヒール履いて歩くこたねえだろう。作家なんて、そんなに見栄えがいいか? あんな商売、不安定で危なっかしくて、最初からコケるのが分かってるのに、何でそんなもん履きたがる。背が高くなるからか、脚が長く見えるからか。ちょび髭が生えてるくせに、そんなにニューハーフになりてぇのか。やめとけ。もともとあの業界、閉じた世界だろう。どんなパワハラ、セクハラが待ち受けてるか分かんねえぞ。オカマSMかよ。お前、わざわざ家賃の高い東京に出て、ホテルに缶詰にされて書くことを強制されたいってことか。あんなもんロクなもんじゃないぞ。いかれてるのか。オウム真理教の修行をさせられてるわけじゃあるまいし。そんなの完全にブラックだろう。ケージ飼育されて卵を無理やり産まされるニワトリじゃないか。やっぱし人権蹂躙だよ。バナナよろしく人権の叩き売りだ。そんなもんになりたいとはねえ。女王様にでもひっぱたかれてろ。後から嫌になったって、『アンタを売り出すために会社がいくら使ったと思ってるんだ。どれだけの人間がアンタのために頭を下げたと思うんだ』と言われてみろ。辞めたくてもやめられないぜ。そんなの完全に奴隷だろうが。かりに、だ‥‥‥かりに作家になれたとしてだ、売れるかどうかなんて分からないぞ。むしろ売れないことの方が圧倒的に多い。そんな分の悪いギャンブル稼業で生きてくのか。ぜったい若死にするぞ。聞くが、お前だってあの作品のうち一つでも一次選考を突破したのがあるのか」
「いいえ、箱村さんと同じです」
「なあんだ、お互い様だったのか。なら五十歩百歩、あえて言わせてもらえば同じ穴のムジナじゃないか。純文学なのか? お前の作品のあの化け物級のおどろおどろしさは、さて私小説のつもりなのか怪奇小説のつもりなのか。どれもこれも狂いに狂った文体や展開や雰囲気なんで分かんないよ。なんて言ったらいいのかなぁ。とち狂ってんだよな。“冷奴豆腐にかけるのは醤油だろう。なんでコイツ、ソースをドボドボかけるんだ”って感じだ。あれって純文学なの? 定義が今一つピシッとしないんだよな」
「一応、純文学のつもりですが」
「あれがか」
「ええ」
「なら俺とまったく同じじゃねえか。ダメだ、ダメだって。お前が女だったら少しはマシかも知んねえが」
「女の方が選ばれやすいんですか? そんなことはないでしょう。男女平等でしょう。仮にそういう傾向があったとしても、ただ女の応募者が多かったからだけじゃないんですか?」
「甘っちょろいな。女は男にも女にも厳しい。男は男に厳しくて女には甘い。男女の人口はだいたい同じ。選ばれる確率はどっちが高い?」
「なんか変な理屈‥‥‥‥男が女に甘いのは仕方ないでしょう。男は“女と子供を守るんだ”が遺伝子に組み込まれているから。だから戦地に兵隊として行くのもたいてい男だし‥‥‥」
「考えてみな。純文学は自分の生き様を売り物にしてる人が多いだろ。超平凡で、しかも男のお前に目はないよ。勝負にならない。純文学なんだからと、いくら自分の恥部をさらけ出そうと、お前ごとき平凡な男の恥部なんて、誰が同情したり感情移入したりするんだ。受け入れられるもんか。恥かき損だよ。だからお前が女だったらちっとは違ってくるかもしんねえけどな、って言ったんだ。だって女の読者は多いからよ。女は女の書いた小説を読みたがるんだ。そのうえ美人であれば、普段小説なんて読まない野郎まで本を買う。いっそ性転換手術して女にでもなるか。今はついてるからどうしょうもないよな。女は生活者だから小難しい作品も駄目だ。“それってあるある”の共感型でなきゃあ。芸術性うんぬんかんぬんの作品は敬遠されるだけだ。だからお前の作品も俺の作品も敬遠されるだけちゅうことだ。選考する奴らが俺らの作品に後ろ向きになるのも無理はねえ。よく読者層の嗜好を理解してるよ。やっぱ商売人だ」
「箱村さんって小説で芸術性なんか追究してたんですか? 花菱社長の言ってたのと違う。江戸四十八手とか種なしのカウパーとか‥‥‥‥」
「え? あんにゃろう、そんな失礼なこと言ってたのか! どうせダラダラと長ったらしいのを書きやがってと腐してたんだろう。アイツは俺が普段から喋っていることが、そっくりそのまま小説になってることに気づいていないんだ。だから長いんだよ。何ぬかしてやがる! ふてえ野郎だ!」
「たしかに体は太いですけどwwwww‥‥‥」
「あの糞ジジイめ。ぶった切って、俺も腹切って死んでやる!」
「うわっ、いつの時代の話してるんですか。ね、そんなに熱くならないで。聞き間違いかも知れないし‥‥‥多分そうでしょう」( ̄ー ̄; ヒヤリ
「ああ、わかった。どっちにしたってよぉ、結局お前も俺もエキストラの一人にすぎないんだよ。だいたい何かのレアケースで、俺らがどっかの雑誌の文学賞に選ばれたとしても、そこはゴールじゃない、ようやくスタートラインに立ったばかりだ。前途には過酷な道が待ち受けている。これから生き残りをかけたサバイバルゲームが始まるんだ。俺らに個人店舗の経営は務まらないよ。特に作家みたいな水商売はな。なあ、作家って水商売だろう。人気商売と言ってもいい。幸運にも小説家の暖簾を出せたところで、客が来なくて計画は頓挫、すぐ店じまいだな。なぜ店を潰すのか。商才やタレント性がないのは言わずもがな、それより何より団交権なしのフランチャイズ店主だということを忘れてるからだよ。真っ先に親会社から締め出しくらって使い捨てられるな。アレだよ、アレ、生け簀の鯉だよ。はじめは気持ちよさそうに水槽の中を泳いでいても、そのうち掬い上げられて活け締めだ。お前、いくら指図されても自分の好き勝手に書くだろう。どういうふうに書かせれば人気が出て売れるかなんてのは、編集者の方がよっぽど熟知している。せっかく音がズレにズレたピアノを調律してやろうというのに、当人が意固地なこだわりや美意識を持ってそれを許さない。『そりゃ、ちょっとキツいですよぉ。勘弁して』とかなんとか言って、妥協せずに逃げ回るだろう。テレビだったらナマでない限り編集されるのが当り前、“ここカット、そこカット”なんて日常茶飯事だ。どうして小説だけそんなワガママが許される。可愛げがあれば鳴かず飛ばずでも使ってやろうって気にもなるが、そんなんじゃあ、まったく使う気になれない。商業ベースに乗せようにも乗せられないからな。採算性ゼロの奴を誰が囲っておくもんか。そのうち構ってもらえなくなる。遅ればせながら作品を持って行っても、必ずといっていいほど突き返される。ダメ出しして部分的に書き直させれば少しは売れるものが仕上がるかもしれないな───そう思っても、もうコイツにかける意欲がわかない。嘘でも『使って下さい』っていう姿勢を見せなきゃあ。ヨイショの一つでも言え。だけどお前はそんなことしねえな。何故かって、俺もしないからだよ。俺とお前はニコイチだろ? 二人ともそんな芝居は打てねぇ。作家になれたということは『書かせてもらえる、読んでもらえる』ということだ。『書いてやる、読め』じゃないんだな。そこらへんを俺たちゃ勘違いしてるからズッコケるんだよ。売れなくなった芸人や歌手と一緒で、仕事がもらえなくなって終わり。てか、ずーっとこのさき開店休業状態だな。いわゆる“干される”ってやつだ。バックがいてくれなきゃけりゃ、俺たちのロゴの入った暖簾なんざ、ただのボロ切れだ、親の支援がなけりゃ、子は死ぬしかないんだよ。頭をフロアーにこすりつけて『干さないでください』と泣きつくか。そんなことできねえな。え? やろうと思えばそれぐらいの演技なんてできるって? できたとしてもしない。なぜってそんなの情緒的恐喝じゃないか。まともな神経の持ち主なら、反対に干すほうがメンタルやられちゃうだろう。俺は水に落ちた犬を打っちまった、ってなるからな。相手が魯迅じゃあるまいし、俺たち甘ちゃんにそんな逆恐喝ができると思うのか。たとえ無理してそこまでしたとしても、いつかは使い捨ての紙コップだ。俺たちだけじゃない、ほとんどがそう。残るのはほんの一握り。アホらしい、やめちまえ、やめちまえ。それでもまだ自分の可能性を信じているのか。信じるのは勝手だが、気づいた時には満身創痍だぞ。もういいかげん目覚めろ。だいたいなあ、万に一つでベストセラー作家になれたとしても、だ。それは『印税でたんまり金はくれてやるが、そのかわり今後も秀逸な作品を書き続けなければ許さない。そのストレスであんたの命を削らせてもらうぞ』と約束させられたのと同じだぞ。金と引き換えに寿命を切り売りする、なにかの童話のストーリーにでも出てきそうだな。政治家や大学の先生やテレビのコメンテーターかなんかに転身しちゃう作家が少なくないだろう。きっとそういったプレッシャーが辛すぎたんだろうと俺は勘繰るな」
「ある夕方、自宅のドアを開けると、部屋の隅っこに死神がうずくまっていた。死神は言った。『お前の望みどおり作家にしてあげよう。ただしそれと引き換えにお前の心をいただくよ』と。作家になった途端、自分本来の日々は送れなくなる。死神と取引するな。作家になることは、自分の人生を死神に売り渡すことだ。そう言いたいんですよね、箱村さんは」
「急に物語バージョンが出てきやがったな。まぁ、言いたいのはあらかたそういうことだよ。でもそれって俺の知ってる童話のストーリーとはぜんぜん違うんだが‥‥‥あれ? 童話じゃなくて落語だったかな。人々の寿命になぞらえて、何百、何千もの蝋燭の炎が周囲にいっぱい並んでるやつ‥‥‥」
「あっそれ、落語の死神かグリム童話か、どっちかの記憶が残ってるのかもしれない。『樹に首でもくくろうかと思っていると、後ろから死神に声を掛けられた』ってやつでしょう。最後に死神から自分の命の蝋燭を渡されて、『あぁ消えちまう、消えちまう、ほら消えた』で舞台が暗転する古典落語。この落語は有名だから知ってます。僕は悪魔メフィストフェレスと契約して魂を奪われたファウストになった気分でいました。ゲーテの戯曲です。こっちも超有名」
「お互い有名どころに便乗してたってわけか。人の作品に酔いしれて、脱線するのはよそうぜ。大事な話なんだ、ともかくもう書くな、諦めろ。結論はそれだけ、他はない。言い切るぞ」
「はぁ」
「煮え切らないなあ。何だ、その生返事は。いいか、人は成功しようとするなら、どっちかを選ばなくちゃなんねえのよ。他人様の出来ないことをするか、他人様のやりたがらないことをするかだ。ここまではいいな?」
「はい、なんとなく」
「お前の大間違いは、小説家になれるとすれば、それは他人様の出来ないことができたからだと考えてるとこだ。てな訳で、偶然小説家になれたらとしたら小説家になれた俺様は偉えんだって勘違いすることになっちまう。だけど今まで言った通り、小説家になるってことは他人様の決してやりたがらないことをやらされる、ってことなんだ。出だしから取り違えてんだよ。そのままいったら『あれ? こんなはずじゃなかったんだが』と嘆き苦しんだ挙句、終いには手前の命が『消えちまう、消えちまう、ほら消えた』になるぞ。だから忠告してるんだ。理想ばかり描いてるから、ボケちまって現実が全く見えてない。まぁそれも仕方ないかもな。俺も気づいたのは、ずっと歳くってからだもんな」
「箱村さん、今日はやけにサエてるじゃないですか。一応話の筋は通ってます。わかりました、諦めます。もういいかげん骨身に染みてますし」
「よぉ、潔い負けっぷりじゃないか。よく言った。ヨッ御両人、力もなければ華もない、無い無い尽くしで打つ手なし。登山じゃないが、途中でやめるのも勇気だ」
「僕の周りにもう死神は見えなくなったでしょう」
「そりゃ分かんねえな。また心変わりしそうな気もする」
「はぁ」
「でもなあ、骨身に染みたなんて自分をおとしめるような言い方はやめような。自信を持てよ。自分を信じるから自信って言うんだぞ。俺みたいに自分をもっと信じろよ。小説はまあ、アレだけど、さっきの話じゃないがトータルの人間力では結構いい線いってるぞ。お前にとっての小説とはこういうことなんだ。日よけのつもりで庇を借りたら、『のぞき込むな!』とケンもホロロ。庇を借りても母屋を取る気なんてさらさら無いのにな。ところが急に雨が降ってきた。玉のような雨粒が肌に当たる。けれども傘がない。お前にあるのは、遠い昔の赤い傘の想い出だけ。その傘から見え隠れする女の人は一体誰なんだ? 初恋の人か? それとも母親か? どっちにしろ、ただの想い出じゃ何の役にも立たない。だからやむなく雨宿り。『あっち行け』と咎められても動けない。それが小説をやめられないお前の心境だ」
「なんなんですか、それ?」
「この絶品のレトリックも分かんねえのか。出色の出来栄えなのによ。呆れたねえ、もっと俺から学ばねえとな。こういうことだよ。雨に降られなきゃ、虹も見えてこない。そのうち雨も上がって、空に架かった七色の橋を渡りゃあ、お前も気持ちのいい日光に包まれるさ。言いたいのはそういうことだよ。それでも今どうしても雨に濡れたくないなら、雲の上を悠々と歩け。雲の上にいりゃ、絶対に雨は降ってこないぞ」
「ますます分かんなくなっちゃいました」
「馬鹿だなあ。ぜんぶ超越しちまえ、ってことだよ。小説とか新人賞とか、そういう諸々の鬱陶しいものから、突き抜けちまえってことだ。いいか、骨身に染みたっていう、配ってた例の本もな、結局こういうことだと思うんだ。繁華街でポケットティッシュが配られれば皆もらうだろう。お前の本も受け取ってくれた人はいるだろうが、ポケットティッシュとは違う。ポケットティッシュは使ってもらえる。ただ配っただけ、書いただけで誰も読まない、それがお前の本だよ。どれだけ刷ったか知らんが、結構あまっただろう。そうそう女神はほほえんでくれない。だけど腐るなよ。最近じゃあ、ベストセラーだってみんな話題性でちょっと買ってみるだけで、最後まで読む奴は半分もいないと思うぜ。老人は目が悪いから読めない、最近の若者も活字を追うのがしんどいんだよな。漫画や動画の方がいい。だから骨身に染みたって言ったって、落ち込むことはない。今さっきも言ったけど、よく売れてる作家が大きな書店かなんかでトークショーとかサイン会とかするだろう。作家の本にサインいれてもらうために、客が並ぶよな。あれだってその本が読みたいんじゃなくて、有名人のサイン入りの本がほしいだけなんだろうな。読むための本じゃないんだ、友達に見せびらかすための本なんだ。だけど最初の二十ページぐらいしか読んでなくたって、わざわざ並んでサインまでもらった本なんだ。友達に本の中身を悪くは言わないよ。それが数珠つなぎに口コミで広がっていって販売部数につながるっていう寸法だ。選挙と同じでドブ板戦法でいかなきゃ、どんな才能のある奴がどんな秀作を書いたとしても、本っていうもんはなかなか売れるもんじゃない。かの養老孟司だって書店で本にサインして客に渡してたんだ。でなきゃ『バカの壁』があれだけの大ベストセラーにはならないと思うぜ。そういうドブ板の努力も何もせず、突然駅で配っただけのお前の本に誰が興味を示すと言うんだ。興味を示すのはせいぜい俺のような超目利きぐらいのもんだ。だから自信を持てよ、へっちゃらだ、へいちゃら」
「なるほど言われてみればそんな気もする、自信をもっていいんですね」
「当り前だ。幸運の扉は最初、なかなか開かない。お前が住んでるガレージといっしょだ。最初は引き戸が重くて、出入りが大変だったろう。だけど慣れて要領が分かってくる。今じゃ開け閉めが造作ない。人生もこれと同じだよ。ただし、だ‥‥‥‥ただしクドイようだがこれは小説以外での話だぞ。小説の扉には頑丈な鍵がかかっている。どれだけやっても絶対に扉は開かず、自信もつかない。いつまでも自信がつかないのは、自分が絶対できないことを奮闘して是が非でも成し遂げようとしているからだよ。人には器のサイズがそれぞれ違う。大きくていっぱい入る器もあれば、小さくてあんまり入らない器もある。おんなじ分量の水を入れても、あふれちゃう器もあれば、まだ余裕で入る器もある。自分の器のサイズをよく知って生きてくことだ。お前、スモールサイズだろう。もう溢れそうなのに、どうしてまだドボドボ水を注ごうとしているんだ。たとえばお前みたいなチビに『NBAプロバスケットリーグでダンクでいっぱい得点しろ』と言ったって絶対無理だろう。ダンクにチビは致命傷だ。それでも血反吐をはく思いで必死に努力する。それがお前の小説だよ。ダメなものはダメなんだ。今からいくら牛乳をがぶ飲みしようが鉄棒にぶらさがろうが、背は伸びないだろう。小説はお前にとってダンクシュートと同じだ。いつまでしがみついていても絶対に自信はつかないぞ。必ずいつか燃え尽きる。“為せば成る”なんてのは、ある種の驕りだな。この世には、励めば励むほど自信をもつ人と、励めば励むほど劣等感をもつ人がいる。自信は自信を呼び、劣等感は劣等感を呼ぶ。小説に関していえばお前は完全に後者だ。どうしてそんなふうにお前はなっちまったか。シンプルなことだ。これまで諦めると決意することができなかったからだよ。諦められるというのは、幸せでいるための大事な条件だ。上手くいきそうもないときは、“自分には別の道を行く運命が定められているのでは?”と考えてみろ。まずは別の方角に第一歩を踏み出しなおすことだ。どうしてあいつ等の仲間に入りたがるのか。はねつけられたからか。はねつけられた理由を知りたいのか。そんなの知らなくていい、知らない方がいい。ここ掘れワンワン、ポチがへたに掘り返すと土まみれになるぞ。お前には違う居場所がちゃんとある。小説に狂っていた自分は遺影にでもして神棚に飾っとけ。お前はちょっと前まで出版社の新人賞に必死で応募していたんだな。そんなの黒歴史だぞ。そんな記憶は全部、矢沢永吉になったつもりで黒く塗りつぶしちまえ」
「ああ、永ちゃんのあの『黒く塗りつぶせ』って歌ですね」
「お前、あんな古い曲をよく知ってるな」
「なぜか、ふっと分かることがあるんですよね。なんだろう、過去と現在と未来が互いに交信し合っているというか。心の深い水底からポッカリと遠い想い出の気泡が浮かび上がってくるんですよ。次第に輪を広げながら‥‥‥‥ずっと昔と今とがシンクロしてるみたいに。僕がいないはずの遠くの過去から突然、自分の声が語りかけてきて教えてくれるよな、そんな感じ」
「誰かがお前の想い出に別の記憶を塗り重ねているってわけか。塗り重ねてるのはもう一人のお前だったりして。お前、そいつ見たことある?」
「夢茶を飲んだとき、確か自分を見たような………」
「自分自身の姿を自分が見る、それってドッペルゲンガーじゃんか」
「ちょっと待って下さい。すいません、混乱してきました」
「いや、悪い、悪い。からかってみただけだよ。そんなことより、小説に関してはな、お前は『なあんだ、俺ってこれっくらいの実力だったんだ』と悟ることが大事なんだよ。本当の自分の力量は期待したほどではなかった、今だって出来過ぎぐらいなんだ。そう思うことさ。人間はその力量よりでっかい生き方はできねえ。そのことを認めて丸呑みしちゃうことだ。そうすれば自分にがっかりすることも焦りまくることもなくなって、楽に生きていける。これまで実際にできたことだけがお前にできることだ。そこがリミットだ。お前はお前なんだよ。な、分かるよな」
「そうかあ、冷静に考えればそういうことになるんだ。でも前々から『やめろやめろ』って、箱村さん、まさか出版社とか文壇とかそういうところからの差し金なんじゃないでしょうね」
「アホ言うな。俺は﨑田じゃねえよ。そんなことよりお前、生きていくことがたまらなく不安になって憂鬱な気分になることがよくありゃしないか?」
「うん、まあ、確かにそうですが」
「不安で気がめいるのは、お前が今、真に求めているものと違うものを手に入れようとシャカリキになってる証拠だよ。お前の心の奥深くにいる本当のお前は、そんなもの求めてない。小説家になりたい? そんなの、お前の魂が本当に求めている生き方と異なる生き方だ。本来のお前と上辺のお前が異なる生き方をしてるから心がキリキリ痛んで気が滅入る。また裂き状態だよ。だからうまくいくはずのものも、うまくいかない。そろそろ悟ったらどうだ」
「それってキルケゴールですか?」
「はん? キルゲーロゲロ? なんじゃい、そいつは。どこの蛙だ。柄にもなく衒学ぶりやがって。気取ってんじゃねーぞ」
「いえ、そんなつもりじゃ‥‥‥‥」
「ともかく今にぎりしめてる一切を手放しちまえ。お前よりずっと長く生きている俺が言うんだ、だから間違いないぞ。素直に耳を傾けろ。良薬口に苦し、って昔から言うだろう。ためになる忠告ほど耳が痛いんだ」
「そうかぁ。のぼせていたんだな、僕としたことが‥‥‥勉強になります」
「いま、勉強になるって言った?」
「はい」
「いいねぇ、そういうとこ。感じのいい若者だ。そういう素直なとこ、いいぞ、お前。また話を聞いてくれな。迷惑がるなよ。俺、いつも浮いてんだ。言いたくねえけど鼻つまみ者だ。話し出すと、みんな逃げてくんだ。最近じゃ、話を聞いてくれるのはお前ひとりだよ。誰もまともに聞いてくれねえ。お前とは言葉のキャッチボールができるから、うれしいよ。また二人で話そうな。頼んだよ」
(15)
しばらくぶりのブラウンの受付には人がいなかった。カウンターに置いてあった卓上ベルを手の平で叩くと、チンと呼び出し音が鳴り、ややあって例の男が出てくる。用足しにでも行っていたのか、それとも訳あってわざと隠れていたのか。
「カナちゃん、指名でお願いします」
男は一瞬嫌な顔をしたが、すぐにいかにも嘘っぽい事務的な笑顔を取り繕った。
「いや~ぁ、カナちゃん、辞めちゃったんですよね。お客さんみたいにカナちゃんを指名する人が次々とやって来て、正直ウンザリなんですよねぇ」
「え! カナちゃん、やめっちゃったの?」
わが耳を疑うのは赤井君である。心の小枝がポキンと音をたてて折れた。カナちゃんが辞めちゃったって!?
一瞬身体が硬直する。さっきまでウキウキしていた気持ちが、見る見るうちに凍りついていく。まるでさっぽろ雪まつりの雪像にでもなってしまったかのようだ。あのカナちゃんとのほんのひと時の思い出が、やがて溶け落ちる雪となって、大地に沁み込んで消えていく。
「他にももっと若くて可愛い娘いますよ、どうですか」
味もそっけもない対応だ。受付スタッフは早くも、女の娘のプロフィールとボカシ顔写真の例のファイルを赤井君の前に出し、めくりながら選ばせようとしはじめる。
「どうしてやめちゃったの?」
「さあ、どうしてでしょうか。私が辞めたわけじゃないから知りませんよ」
受付の男はうそぶいている。
「そんなぁ。何か知ってることがあったら教えてください。お願いします」
「さあね、ぷいっと来なくなっちまいましてね。ある日、退勤したきり、その後音沙汰なしですよ。舐められてるんです。あの娘ら、私たちを屁とも思ってないんですよ。それよりこの娘なんかどうですか。イチ推しですよ。待望の爆乳ギャルが、ついにこのブラウンに降臨いたしました。カナちゃんよりずっと若くて、美人で、ボインですよ。おまけにドMときてる。お客さんの趣味とピッタリだ」
「僕のこと覚えてるの?」
「覚えてますとも。営業トークじゃありませんよ。ナイスなボケで笑わせてくれた人でしょう。忘れるもんですか」
「カナちゃんでないとダメなんです。やめちゃってもう来ないんなら、連絡先の電話番号だけでも教えてください。お願いします」
「またまたお得意のジョークですか。この業界、女の娘の居場所なんか言えるはずないじゃないですか、お分りでしょう。さて、この娘がお気に召さないとすればと‥‥‥」
「店をかわったんなら、新しい店がどこか教えてください。頼みます」
「そこまでおっしゃるのなら特別にこの娘を紹介してあげましょう。特別ですよ。清楚な外見からは想像もできない、でも仮面を外した裏の顔は超、超、超ドM。最近の若い娘はすごい、本能むきだしで狂いに狂いますよ。まぁ~女というのは怖いこと、怖いこと‥‥‥」
「ちょっと、おたくでは話にならない。店長、呼んでくれませんか。店長を」
「私が店長ですよ」
「えっ?」
「別に人手不足で私がここにいるわけじゃありません。実は受付というのが一番、全体を見渡せるんですよ。まあ、コロンブスの卵と言いますか、コペルニクス的転回といいますか、そういった逆転の発想です。店長が奥に引っ込んでるようじゃあ、何にも分からないし、商売もうまくいかない。店長の私がカナちゃんの行方を知らないということは、だから、多分この店にいる全員が行方を知らないということですよ」
カナちゃんがいないとあれば、こんな変態の巣窟には用はない。もう関わりたくないので、そっちはそっち、せいぜい楽しくやってくれ‥‥‥‥‥。
(´Д`。)クスン
華やぐ歓楽街。昼間は殺風景で墨絵さながらの街並みも、夜ともなればコンピュータ・グラフィクスで描いたように鮮明な色彩が躍動する。所かまわず乱舞する猥雑なネオンサイン。商売女たちの吐息も極彩色に染まり、都会の夜を湿らせている。光の装飾に紛れて、半ば捨て鉢になってうろつきまわっている赤井君の姿が見える。店の執拗な呼び込みや路上キャッチ行為をかわすのに、ずいぶんと難儀しているようだ。
カナちゃんに巡りあって、暗い倉庫の自宅に灯がともった気持ちになっていた赤井君である。最高の気分だった。何でも軽々とやってのけることができる気がした。しかしそんな高揚感は長くは続かなかった。首ったけになった分、そのショックは大きい。色とりどりのネオンとは対照的に、心はブラックホールに吸い込まれていた。たった今まで全てを受け入れてくれそうに見えた周囲との関係が、縺れに縺れてしまったかのように感じられる。
彼は今、栞を入れ忘れて読みかけの本を閉じてしまった心境である。いったい何処まで読んだものやら後から辿ろうにも辿りようがない。本ならはじめから読み直せばすむことだが、カナちゃんの場合はそう簡単にはいかない。このだだっ広いネオン街を前にして、何とかカナちゃんに追いすがる手立てはないものか。見当もつかない。
頭の中は焦土と化している。焦土と化した大地で、ただカナちゃんの姿や声だけが渦を巻いている。自分勝手に色々な架空の物語を夢想しては、それが現実でないことに落胆する。彼女のことを考えれば考えるほど、赤井君は虚脱感にさいなまれる。その一方で、自分のふがいなさに捲れないレジ袋なみの苛立ちを覚えるもう一人の彼もいる。なんとも捉えどころのない複雑な感情である。
「シックスセンス」という映画をご存じだろうか。有名な映画だそうなので、知っている人も多いに違いない。ブルース・ウィルス演じる医師は、自分が既に死んでいることに気づいていない。気づかないまま自分にまったく無関心になった妻の愛情を取り戻そうと必死になる。死んで姿のない彼が妻から無視され続けるのは当然なのにもかかわらず、である。
今の赤井君はこの医師に似ている。カナちゃんにとって赤井君は亡霊のような価値しかない。死人と同じ、いてもいなくてもどうでもいい赤の他人である。けれど赤井君のほうは寝ても覚めても頭のなかはカナちゃんのことばかり。完全にイカれてしまい、どこかでバッタリ出くわさないか、出くわさないまでもせめてニアミスぐらいはしないかと、わずかの希望をたよりにこのネオン街を当てどもなくほっつき歩いている始末だ。
力なく、まるで水面に落ちた一枚の葉っぱが、風に吹かれて不安定に漂っているかのようだ。この世とあの世の境目をフラフラと抜け殻になって徘徊している。生きているのに死んでいる、存在しているのに存在していない‥‥‥その表情を忘れた惨めな風貌は確かに亡霊と呼ぶにふさわしい。生きたまま死んでいる男が街をうろつく───さまよえる屍、まさにゾンビだ。人間に噛みつくことしか頭にないゾンビ。ゾンビ同様に赤井君にはカナちゃんしか頭にない。完全に心をわしづかみにされている。浮かぶのはカナちゃんのことだけ。もしここでカナちゃんと遭遇しようものなら、感激のあまりゾンビよろしく本当に噛みついてしまうんじゃあるまいな。
完全にきれてるんだよ、終わっているんだ───今の赤井君にいくらそう言い聞かせたところで、のぼせあがっているので耳に入らない。迷える魂はカナちゃんを天使だと信じ込み、犬のように舌を垂らして愛情を求めている。
「これにて一件落着」なんて嫌だ!───そんなこと言われたって、まだ色恋沙汰にかすりもしていないのだ。カナちゃんにしてみれば、終わっているどころか何にも始まっていないじゃないの、という話である。赤井君はただの通りすがりの者でしかない。自分ひとりで恋愛して自分ひとりで失恋している。カナちゃんがこれを知れば「何なの、それ」と呆れかえるに違いない。種族保存の本能に操られた一過性の心の病にいちいち付き合わされては身が持たない。
万一、偶然に出くわしたとしても、赤井君にとっては天使でも、カナちゃんにとっては薄気味悪いストーカーである。金や名声と同じで、女は追えば追うほど逃げていく。女経験の乏しい赤井君にはそのことが理解できない。男脳を通して女脳を推測しているからだ。たぶんSMといっしょだろうよ。どこまで行っても彼には理解できない。自分の尾っぽを追いかけて、永久にグルグル回転する馬鹿犬に成り下がっている。
妙な仕事にありついてから三週間以上たつ。毎回夢茶とやらが出るので飲んでいるが、箱村が言うように依存性は皆無だ。もうすっかり順応してしまった。麻薬は常用しなくなると、意欲低下やうつ状態や情緒不安定などの禁断症状が始まると聞くが、夢茶に関してはそういうことはない。これなら煙草のニコチンのほうがよほど依存性があるなと赤井君は考える。
夢茶を飲んで幻覚をみた後は、虚脱感がのこるどころかムラムラと下半身が性的に騒ぎだす。夢茶を飲み出してからどうも性欲が増進したようだ。若いので性欲があるのは当然だし、思いがけないバイトで懐が温かくなり栄養が体に行き届いたせいもあるかもしれないが、それにしてもこの心のうずきは何なんだ。性欲が高まるということは、体に害があるどころかより健康になったということだ。夢茶は粗悪品の緑茶やウーロン茶といった味で、とてもおいしいとは言えない。だが良薬口に苦しという。より健康になったということは、夢茶は麻薬どころか良薬に近いということではないのか。飲まなくてすむならマズいから飲みたくはないが、かといって飲むのが苦痛だというのでもない。高額な日当をもらうためなら、仕事と思って少々マズいものを鼻をつまんで飲んだとしても、どこが問題なのだろう。金にもなり健康にもなるのなら一石二鳥ではないか。ことほどさように妙に納得してしまう赤井君なのであった。
夢茶のせいで相変わらず幻覚は出てくる。最初幻覚の中身を居残って紙に書き出していた赤井君も、どうも途中で眠って忘れてしまうことが多いので、幻覚を見ながら同時中継のようにパソコンに音声入力することにした。入力したものを後で読み返すと、とても日本語とは思えない代物であったため、なんとか日本語らしく手直しして花菱に、花菱が寝ていれば箱村に渡した。
花菱はろくに読みもしないで「今日もバッチ、グーだな。帰っていいぞ、金を持ってくの忘れるなよ」、箱村も「やるじゃないか、持ってくモン持って帰りな」と毎回判で押したようなセリフ言う。日当はいつも出口近くの所定の場所に置いてあった。最近では横着になって後から手直しすることもなく、変な日本語のままプリントアウトして渡している。彼らは何ひとつ文句を言わない。なんという気楽なバイトだろうか。いくら胡散臭げに思えても、うまくいっている間は騒ぎ立てずにそのまま従う───多分これが一番賢いんだろうな。赤井君は今そう考えている。
行くあてもなく歓楽街を漂流する赤井君は、カナちゃんのことが頭から離れない。だからといって夢茶の性欲増進効果のせいで変態SMに目覚めたわけでは勿論ない。もう一度カナちゃんに頭を洗ってもらいたかっただけなのだ。そこらへんは庶民的である。あっちの方は手っ取り早く自家発電ですますことができるが、洗髪の方はそうはいかない。あの時カナちゃんの頭を洗う指先から深い愛情の恵みが自分に流れ込んできたと本気で信じ込んでしまっているのである。馬鹿と言うか、哀れと言うか。波打ち際、砂に描いたカナちゃんとの相合傘‥‥‥そんなもん、アッという間に波にさらわれてしまうに決まってるじゃないか。
立て続けのストライクでピンがド派手にはじけ飛ぶように、狂喜乱舞の賑わいをみせる風俗街。そんな喧騒を裏道へと避けながら、トボトボと路地から路地へと歩き続けているうちに、赤井君はゴロンと溝に落ちて転がるボウリング球よろしく怪しげなピンクゾーンに吸い込まれていくのであった。迷子はどこに行こうとしているのやら。いよいよ危険水域に達しつつあるのも知らずに。

(16)
「にいちゃん、いい娘がいるよ。安くしとくよ」
ネオンに照らされて一人うろつく赤井君に近寄り、そう耳元で囁きかけたのは、歳のころ六十四、五のお婆さんだった。
同じキャッチでも男より女が、若者より老人のほうが危険度は低そうに思える。この人に任せてみるか。ずっと夢追い人でいるわけにもいくまい。この界隈で偶然にカナちゃんに巡りあう可能性がどれぐらいあると言うのだ。逢えるはずないのを知りながら、やみくもに歩きまわるような惨めなことはもう止めよう。このままじゃ挙動不審で怪しまれかねない。いいかげん、ここらで息子孝行してやらなけりゃ。
という訳で、お婆さんのあとをノコノコついて行く赤井君なのであった。
昼間なら灰色にくすんでいる欲望エリアも、夜ともなればライトアップされて彩られる。風俗店ひしめく花の舞台。床屋さんのサインポールが幾つも並んでいるかのように、クルクルと目眩だにしてきそうだ。LEDが夜の街に定着して久しい。歓楽街のイルミネーションも一層鮮やかになり、その狂乱ぶりを際立たせている。
赤井君が連れていかれた店は、その電飾の海の中にあって、ひときわサイケデリックな毒々しさを放っている。いかにも裏通り的露骨さがサインボード上にむき出しになっていて、ドン引きしたくなるほどだ。どれだけ悪趣味な文句を並べようが、周囲の店も五十歩百歩で、警察も注意しようにも何処から手をつけたらいいか分からないに相違ない。どれだけ低俗であろうが、どれだけ淫猥であろうが、目立ったもの勝ちの世界である。スケベな客を引き込めさえすればいいのだ。一般大衆からいかに顰蹙をかおうと、儲かれば一向に構わない。
そういえば小説だって、書店にきた人に本を手に取らせ、それをレジに持って行かせるまでが勝負だ。その意味では風俗産業に似ている。話題性の花火を景気よく打ち揚げて大衆の注目をひかないといけない。金があるならステマもバンバンやっちまえ。本の出来がどうかはその次に来る話だ。今は浮き沈みのサイクルが速いから、作者への興味が次回作を出すまで続いてくれるとも限らない。風俗嬢がブスであろうとなかろうと、まず客を店に引き入れなきゃ始まらない。リターン客に期待するな。小説もそれと一緒なんだよな。ナウ・オア・ネヴァーの精神で、というところか。
しかし‥‥‥‥と赤井君は考える。しかしいま得すりゃいいとばかり、無理やり客を店に引き入れたとしても、ただ幻滅させるだけだったら、その客は二度と来てくれない。そういうことを繰り返していれば、常連客を取り逃がすどころか、悪評も広まりかねない。そのうち客はどんどん来なくなって経営は火の車だ。そうなったら店を畳んで別の店を出しますか。新しい店を出しても、また客のスケベ心につけ込んで騙すわけだから、同じことだ。こうして、とどのつまり業界全体が衰退してしまう。
‥‥‥‥ひょっとして出版業界もおんなじなんじゃねえ? ドドーンとぶち上げていくら好奇心をあおったところで、中身がそれについて来なかったら、そのうちジリ貧になっちゃうじゃん。店を畳んで新たな店を出すみたいに、作家を次から次へと取っ替え引っ替えとはいかないでしょう。え? いくの? そんじゃあ誰かがケツ持ちしないと‥‥‥‥‥そうかぁ、そうなんだ、本人は覚悟の上だから、ケツ持ちもしなくていいのかぁ。そりゃ、そうだ。どうせ水商売、売るためには何でもありだ。民間会社なんだから外野がガタガタ言えた義理じゃない。
そんなことを何だかんだ考えながらも、そのうち「もう僕にはそんなこと関係ないな」と開き直り、開き直ったかと思ったら、今度は心のもう片方で「風俗業界等を見習って、駅で小説を配ったときサクラの一人や二人、噛ましときゃよかったかもな」と知らず呟いてしまっている‥‥‥‥そこは赤井君、持ち前のこすっ辛さである。
店内は真っ暗だった。真っ暗な中、ギンギンなロックの大音響が鳴りひびいている。店に入り気づくと、いつの間にやら赤井君を連れて来たお婆さんは消えていた。ヌエみたいな婆さんだ。皮膚呼吸でもしてたのか。周囲の闇と見分け難いほどの存在感の薄さだ。なんせロックの音がやたら大きいので、いついなくなってしまったのか見当もつかない。これじゃあ火災報知器が鳴っていても誰も気づかないな、と余計な心配をする赤井君である。
「お一人様、ご来店。ご案内して、さあ御案内して」
男のマイクの声がした。受付からの声か。暗いのでその受付が何処にあるのか分からない。‥‥‥‥受付なら受付らしい仕事をしたらどうだ。料金システムはどうなってるのか。分からないことだらけだ。
闇に紛れて誰かが赤井君の左腕を両手でむんずと掴んだ。強い化粧の匂いがする。女のようだ。
「にいちゃ~ん、いらっしゃい。楽しみましょうね、ヒイヒイ言わせてちょうだいね。期待してるわよ」
しゃがれ声を聞く限り、若い娘の色香は感じられない。まさかとは思うが、この人もあの客引き同様、お婆ちゃんではなかろうな。
ロックのボーカルが歌いだした。変な歌詞だ。同じ攻撃的なフレーズが永遠と繰り返されるだけ。
───やれ~、やれ~、やれ~、いてこませ。やれ~、やれ~、やれ~、いてこませ‥‥‥‥
女は腕を掴んだまま赤井君を引っぱっていく。相当な馬力だ。顔は暗くてまだ見えない。ぶよんとした指の肉付き。体が太めなことだけは確かなようだ。
細くて長い通路の左右に小さな個室が幾つも並んでいる。女はその個室の一つに赤井君を半ば強引に引き入れた。ドアを閉めた後も、ロックベースの重低音だけは遠慮なく流れ込んでくる。部屋の中は暗く、照明はあってなきが如しだ。それでも暗がりにだんだん目が慣れてきた。部屋は三畳、左手にベッドらしきものがあり後は板張りだ。殺風景な部屋。ただ一点、壁に張ってある映画ポスターの美的なトーンだけが浮いていてる。そこだけ色彩があるかのようだ。
ダスティ・ホフマン主演の映画「卒業」のワンカットシーンだ。手前に伸びる女のむき出しの脚が大写しにされて、その向こうにはポケットに両手を突っ込んだダスティ・ホフマンの姿。彼は白いドアを背にして、小首をかしげている。マニアには垂涎モノのポスターだろうが、如何せんこの部屋にはまったく似つかわしくない。
‥‥‥「卒業」かあ、懐かしいなあ。あの騒々しいロックはどこへやら、頭の中にはいつしかサウンド・オブ・サイレンスが流れている。はて? 僕っていつ「卒業」を見たんだっけ。ずいぶんと昔のような気がするが。でもそれじゃ歳が合わないし‥‥‥‥
「にいちゃん、何ポケーッと見てんの? あのポスターの男? 自分と似てるなと自惚れてんでしょう。ちょっとそのマスク外してごらん。見てあげるから」
女はそう話しかけてきた。やっぱり若い娘の声質ではない。
「いえ、いまコロナですから。エチケットとして‥‥‥‥」
「どこから見ても似てないわね。マスクしてても分かる。似てるのは体がちっこいとこだけよ」
女の体はうっすらとタバコの匂いがする。
「いや、このポスターの色あせ具合が、過ぎていった年月を物語ってると思って‥‥‥‥」
「なに気障なこと言っちゃってんの。あんちゃんにそのセリフは釣りあってないわよ。ほ~ら、なに退屈そうな顔してんのよ。あんちゃんのマスクはアクビ隠しなの? ねえ、タバコ吸ってもいいかしら?」
案の定だ。
「どうぞ。気にしないですから」
「あら? あたしったら、ライター持ってくるの忘れっちゃた。そこのマッチ取ってくれない? にいちゃんの後ろの小っちゃなテーブルの上に店のマッチが置いてあるでしょう」
‥‥‥今でもタバコに火をつけるのにマッチを使う人もいるんだな。使うのはマッチ棒パズルぐらいのもんだと思ってた。
「あったよ、ほら」
「ちょっとぉ、手が届かないじゃないの。にいちゃんがマッチを擦って、あたいのタバコにつけてよ」
闇のなかにマッチを擦る。黄金色の光球をのせた僕の手のひら。炎が風に震えるスカートのように揺れている。タバコをくわえた女の顔が炎に照らされて見えた。
‥‥‥なんだ、狐顔のオバチャンじゃないか。どうも態度がオヤジ臭いと思っていたら睨んだ通りだった、トホホ。親父ギャルならぬ婆さんギャル。マスクをずり上げて目隠ししたいぐらいだ。このオバチャン相手に務めを果たすのか。絶望的だ。息子もしょげ返っている。
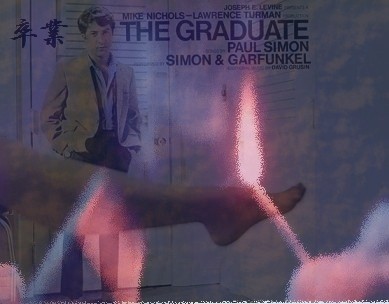
それにしてもオバチャンはエチケットというものを知らないんだろうか。意図的に吹きかけてるわけじゃないだろうが、吐き出す煙がまともにこっちの顔に当たる。このタバコは何という銘柄なんだろう、暗くてよく見えない。吐き出す煙の刺激が強すぎて、妙に喉にいがらっぽさを感じる。よほどの粗悪品ではないだろうか。バラの棘か何かが僕の口奥で絡まっているんじゃないかと思わせるほどだ。マスクの上からでも喉がヒリつくのでたまらない。よもやコロナを発症したんではあるまいな。
「ねえ、この服、似合うかしら」
アンタが新垣結衣や綾瀬はるかだったらな、と思わず厭みが口から出そうになった。露出度限界の派手な衣装を着ている。
「吸い終わったら、ゆっくり脱がしてね」
「あ、いいです、いいです。そのままで」
「何なの? あんた」
狐オバチャンは不満げだ。
「いえ、そのままの方が色っぽいです」
「な〜んだ、そうか。御上手を言うじゃない。スケベ丸出しが恥ずかしいのね。ニイチャン、かわいい」
紫煙をくゆらし終えた狐オバチャンは、ドッコラショと座り込み、ズボンのチャックを下ろそうとする。おい、そりゃないぜ、いきなりかよ、前戯なしか。恥じらいがないというか、はにかみがないというか‥‥‥‥
思った通りオバチャンの体はふくよかだった。顔は狐でも体は豚ちゃんだ。体脂肪率は何パーセント? その首、太すぎねぇ?
「あ~ら、若いのに元気ないわね。あたしが元気にしてあげる。キスしてあげよっか」
‥‥‥‥うぇ、あんたとベロリンチューするの? 嘘やろう。勘弁して。
「恥ずかしがっちゃって、ウブなのね。なら、ちょっと仰向けに寝てごらん。すぐ元気になるわよ」
暫くさせたいようにさせてはいたが、言うまでもなく息子はいつまでたっても股の下のプニュポニョだ。どんな嘘つき男でも息子だけは正直に反応する。
「ダメねえ~、若いのに。アンタ、やる気あんの?」
継続すること数十分、狐オバチャンがイライラしだした。焦燥感がひそめた眉にあらわれている。若い頃のように客が昇天してくれないことに常々から鬱憤が溜まっているのかもしれない。‥‥‥‥無理言わないでくれ、ピチピチのギャルに握られてるんじゃないんだぞ。ビチビチのオバチャンに握られて、息子が言うことをきいてくれるわけないじゃないか。栄枯盛衰は世の習い。誰だって時の流れに逆らえない。沙羅双樹の花の色、盛者必衰のことわりを表すだ。諦めて受け入れなよ。
「どうなってるの、この粗チン。も~う、癪に障る」
苛立ちを抑えられないようだ。ますます強くしごいてくる。怒りが頂点に達するのもそろそろだ。
「この、インポが。インポ! インポ!」
「ちょっと痛いんですけど、おねえさん」
正気に戻ったのか、オバチャンが手をとめた。
「くたびれたわ」
今、オバチャンは座って再びタバコを吸い始めている。おねえさんという呼びかけが効いたのか、怒りはとうにクールダウンしている。ア~アと溜息をつくと呆然と天井を見つめている。
「ねえ、あんた感じいいから、超特別に入れさせてあげてもいいわよ。アタシ、今日はあの日じゃないからスタンバイOKよ、ねえ。ロマンチックにいきましょうよ」
‥‥‥そんな、ロマンチックって言われたって、オバチャンとハメハメハ大王ってわけなの? 悪いけど、本番だけはお許しのほどを。失礼だが、あんたのイソギンチャクに捕食されるのは嫌だ。それにしても、あの日じゃないって!? そんなに見栄はらなくてもいい、気持ちは十分わかるよ。でも言われてみれば、そのお腹、臨月みたいにも見えますな。
「それもアリですけど、どうですか、攻守ところを変えるというのは。僕がおねえさんを攻めちゃいましょう」
「そうね、それもアリか。アンタ、カッコいいとこあるじゃないの。そうね、男は攻めなきゃね。そうね、やってごらん。だったら勃起するかも。そうそう、そうだったんだ。男は攻めなきゃね」
おねえさんという言葉がふたたび功を奏したのか、狐オバチャンはまんざらでもなく、完全に笑顔がもどっている。
「あたしも久方ぶりに、心のなかで欲情の李が熟してきちゃったみたい」
それ、美女が言うならかなり挑発的なセリフなんだろうが、オバチャンが言うと何となく気色悪いな。ベトベト・グチュグチュ感たっぷりで引いちゃうよ。種馬ででもなけりゃ、セリフを聞いてますますお辞儀をすること請け合いだ。でも、もう立ってくれなくても安心だな。一難去ったことだけは間違いない。
「丸裸より服着てたほうが色っぽいかな?」と、狐オバチャン。
‥‥‥もちろんそうだ。頼むから裸にならないでくれ。
オバチャンはベッドに寝っ転がった。ア~ンとか言って妖艶さを演出している。満腹感でゲップがでそうだよ、そんなことはもうやめてほしい。赤井君はとても上からのしかかる気にはなれない。
‥‥‥こっちがサービスする側か。やれやれ、どっちが客なんだ。とはいえ僕にはカナちゃん直伝の必殺技がある。あいにくバネを緩めた洗濯バサミはないが、そんなの指のつまみ具合で調節すりゃいいんだ。洗濯バサミも指も変わるもんか。オバチャンの体で、女経験の少ない僕の、テクニックを磨く修行をさせてもらおう。
赤井君はビクつきながら、触り慣れていない女体を足先からつまんでいく。いざつまみ始めてみると、プレッシャーがハンパない。やっぱり道具を介さず肌と肌が直接ふれあうと違う。もしかするとカナちゃんの時の失態がトラウマになっているからかもしれない。
幸い狐オバチャンの体はブヨブヨで、筋肉質で引き締まったカナちゃんの体とは別物だ。肌がぷよっと弛んでるから面白いように簡単につまめる。最初は痛気持ちいいようにと、恐る恐る一つまみごと、力の入れ方に細心の注意を払っていた赤井君だが、あまりにも容易につまめるので段々と調子づいてきた。
‥‥‥うまくつまめるじゃないか。こりゃあ、いい。しかし女ってのはつくづく不可思議な生き物だ。こんなのに感じるとはねえ。
オバチャンは「このニイチャン、いったい何をしはじめたか」といぶかる様子を見せていたが、やはり職業意識からか、今はア~とかウ~とか喘ぎ声を合いの手のように入れている。それでハードコアのつもりか。どう見てもコメディだな。
そのうち自分の喘ぎ声に興奮してきたのか、「いきそ~」とか「死ぬ~」とまで言い出した。オバチャンが死ぬもんか、三途の川を泳いででも戻ってくるだろ?
赤井君は前回のリベンジ戦だとばかり、テクニック向上に必死である。つまんで、つまんで、ハイ、つまんでえ‥‥‥
しばらく経つと狐オバチャンは嬌声をあげなくなり、静かになった。身じろぎ一つしない。完全に冷凍マグロ状態だ。退屈で寝てしまったのかもしれない。まさか突然死ではあるまいな。ブタだけにトン死? おいおい、そりゃよしにしようよ。嘆息ぐらいはもらしてくれ。寝てる間に心臓が停まっちゃったとか。ネンネンコロリで逝くはずが、マサカのマサカでピンピンコロリに‥‥。心配になった赤井君が声をかける。
「ねえ、オバチャン。これって気持ちいいの? オバチャン、生きてる? ねえ、オバ‥‥‥」
‥‥‥あっ、やばい! 物の弾みでオバチャンと言ってしまった。
狐オバチャンが目をひらく。無表情だ。
「は~ん? 生きてちゃ悪いのか。ちょっとトイレ。トイレいってくる」
そう言うが早いか、バタバタと部屋を出ていくオバチャン。体のわりに俊敏というか何というか。バタ~ンと強烈な音をたててドアが閉まった。アンタにそんな躍動感があろうとは。高性能の偵察ドローンが写真を撮るなり空に消えていったかのようだ。何も呼び方ぐらいで、そんなに腹を立てなくても。
‥‥‥♪ちょっと待って、Play back play back 今の言葉、Play back play back‥‥‥‥♬♪♬ヾ(´□`* )ノ
オバチャンの歳なら、この歌よく知ってるでしょう。ちゃんと言い直すからさあ、ちょっと待ってったら。やれやれ、途中でトイレに行かれるようじゃ、僕のテクニックもまだまだだな─── そう反省する赤井君なのであった。
映画ポスターのダスティ・ホフマンを放心して眺めつつ、どれくらいの時間がたっただろう。狐オバチャンは戻らない。 ‥‥‥‥ここって時間制だよね、システムを説明してもらってないから困っちゃうよな。このままどんどん時間がたったら料金はどうなっちゃうんだろう。
そんなことをアレコレしばらく考えて待っていると、ドアを力まかせに叩く音。それからドスの効いた凄みのある声がドアの向こうから聞こえてきた。
「おい、ちょっとツラ貸せ。事務所に来い。事務所は店の入り口の近くだ。逃げようとしたって無駄だぞ。ちゃぁんと見張っているからな」
おやおや迂闊だったな。文字通り狐につままれるとはこのことだ。ドジを踏んでしまったらしい。狐オバチャ~ン、物陰から吹き矢でねらうようなこと、すんなよ。ここで飛び道具はずるい。消えたはずの偵察ドローンが、まさか神風ドローンになって戻ってくるとは思わなかった。反撃をくらってしまったようだ。叩いてくるなら宣戦布告してからにしてくれよ。潮目が変わってしまったな。あれよあれよの予期せぬ展開である。
(17)
「アンタ、ちょっとあくど過ぎるんじゃないのか? あんなの蛮行だぞ。女の娘が大人しくしてるのをいいことに、全身を思い切り抓りあげたそうじゃないか。どっかにペンチでも隠し持っていないか? 泣いちゃってるぞ。どうすんだ、ポル・ポト政権や北朝鮮、あのイスラム国だってこんなむごいトーチャーはしないぞ。極悪非道のテロリストめが。このクソ外道があ! 血の池地獄に浮かびてえのか! いったいどう責任とるつもりだ ! 」
‥‥‥怖っ。のっけからこれか。すごい剣幕だ。いっぱい並べやがったな。ふんどしツイートか。そこまで罵ることはないだろう。言いがかりもいいところである。女の娘だって? オバチャンじゃないか。泣いてる? 泣きたいのはこっちの方だよ。
「トーチャーだって言うんですか。ひどいですよ。僕はただ感じてもらおうと思っただけで‥‥‥‥あの、まさかこれって前もって仕組んでたんじゃないんでしょうね」
「冗談じゃない! 何すっとぼけてるんだ! 吠え面かきてえのか! 大切な商品に疵をつけられたとあっちゃあ、黙って見すごすわけにはいかないぞ。落とし前をつけてもらおうじゃないか、若造!」
穏やかでない。男はすごんでいる。四角四面の顔だ。そういえばコイツと似た顔の奴に以前遭ったことがあるな。
「落とし前? それ何? それより、いっしょに八木節で踊りませんか、四角四面の櫓の上で。‥‥ハア~(^^♪」
「何お気楽に歌ってやがる。てめえ、泣きを見たいのか! ふざげたこと言ってると、それが、てめえの遺言になるぞ!」
‥‥‥‥なかなか捻りの効いた脅し文句を言う奴だ。どこで仕入れた。ヤクザ映画にでもハマっているのか。それはさておき火に油を注いでしまった。知らず、鼻歌を声に出していたようだ。櫓はあっさり崩落だな、トホホ。
そんなふうに何だかんだ考えては、すくみあがる小心者の赤井君である。蛇に睨まれた蛙、切迫感に姿勢を正して背筋も伸びている。領海侵犯でロシアに拿捕された漁船乗組員の気分だ。
‥‥‥‥墓場でもないのに肝試しかよ。こけ威し野郎が。肝試しはカナちゃんと行きたかった、お前じゃない。こっちだって平静を装ってるが、日本刀を舐めているような緊張感で、わきの下から冷や汗が出てるんだ。♪ハア~、ちょいと出ました三角野郎があ~♪‥‥‥(>д<*)コワイ‥‥‥
ところが、である。ところがこの男が次に放った言葉というのが────
「慰謝料5万円、耳をそろえて払ってもらおうじゃないか!」
‥‥‥‥なんだ、目的はやらずぶったくりだったのか。凄みのある脅し文句のアレコレ、全部ここに持ってくるためだったんだ。それにしても慰謝料5万円? 微妙な額だ。恐喝にしてはいささか安いような気もするが。警察沙汰にしようかしまいか悩ましい金額だ。普通この程度の額なら、赤恥かいてまでして警察に届けないだろうと‥‥‥。計算しつくしてるな、巧妙なやり口だ。
「今いくら持ってるんだ。改悛の情を示せば、なんなら4万に負けてやってもいいんだぞ。なあ、いま懐にいくらあるんだ、正味の話。黙っていないで正直に言え。なんならブン殴って気絶させて、いくら持ってるか確かめてやってもいいんだぞ。てめえ、フルボッコにされてえのか!」
険悪な目つきでゲンコツに息を吹きかける仕草をしている。赤井君は息を呑んだ。もう一声、3万五千に負けて‥‥‥と言ってやりたいところだったが、調子に乗って本当に殴られたらたまらない。ここはやっぱり、背に腹は代えられぬということで‥‥‥‥。
「ああ、お金ね。結局解決するには金なんですよね。払いますとも、ほら、5万円。あ~あ、オケラになっちゃった」
ところがどうだ。あに図らんや、金を渡したその途端、あれだけ息巻いていた男の態度が手の平返しで変わったのである。あまりにも唐突すぎて腕の関節がよじれそうだ。鬼の形相から急転直下、恵比須顔。ヒャッ、ヒャッ、ヒャッと薄気味の悪い笑い声をもらしている。この変わり身の早さには開いた口が塞がらない。地獄の沙汰も金次第。真四角な顔してるわりには相当のクソ狸だ。
現金もらったら、商売人モードにころっと早変わりってこと? 現金な狸には現金を。そんなの迷惑オヤジの言葉遊びにもなんねえぞ。自分に有利に事を運ぶために、あえて脅しでこっちの恐怖や緊張を高めていたんだな。そんな人の道に外れたやり方は厳禁だ(ゴメン!(^_^)ペコッ)。
谷底をのぞかせて、相手がすくんだところで利益をかっさらう。瀬戸際外交ってやつだな。金正日、金正恩の専売特許じゃないか。お前こそ北朝鮮だろう。
「テヘッ、失礼をば致しました。こちらも商売ですんで‥‥‥そこでちょっと耳よりの嬉しい情報があるんですよ。お客様のようなSMを知りつくした、玄人はだしの愛好家だけの限定商品です」
と、舌の根も乾かぬうちに打って変わって営業スマイル。たいした二重人格ぶりだ。名刺を渡しながら猫なで声で呟きかけてきた。いよいよもって魂胆が透けて見える。この四角顔男はたった今、丸っこいクソ狸に豹変したばかりだ。どうやら急に丸まって人を化かすのが得意らしい。なんとか丸め込まれないようにしないと‥‥‥
「これは闇ルートの話ですから他言無用ですよ。今ならたったの10万円で、12時間もの長きにわたって超ドM女を拘束しようが連れまわそうが自由。もちろん通常の過激プレイもO K 。スゴイでしょう。題してドM女連続12時間、いたぶり放題コース。聞くだけでイチモツがウズウズしてきたでしょう」
そう話す狸野郎自身の鼻息も荒くなっている。余計なお世話だが、お前もゲテモノ料理がいける口なのか。ミイラ取りがミイラになりそうな熱の入れようだ。
「やってみたいという貴重な女の娘がいる今だけ、今だけですよ。またとないチャンスです。いま経験しておかないと次があるかどうか分かりませんよ。女心と秋の空、いつ女の娘の気がかわって『もうや~めた』ってなるかしれませんよ。闇ルートですから外に秘め事は絶対に漏れません。どうです、乗ってみません? どうしました? 興奮し過ぎて女の娘の心を傷つけるんじゃないかと心配してるんですか? オタクみたいな通が何を恐れておられる。相手は超ドMだ。ズタボロになりたがってるんですよ。徹底的にズタズタボロボロにしてやりましょうや。何もしないほうが、かえって失礼だ。行き過ぎてヤバイときは逃げりゃいいんです。都会の迷路にドロンしちまえば、もう大袈裟に書いてもらった診断書もって脅迫には来れないですって。ヤクザ連れてお礼参りするったって、行き先がわからないんじゃ、何処にどう御礼参りするってんですか」
‥‥‥‥なんてこと言い出すんだ、恐ろしい。このクソ狸が。ウジ虫みたいな奴だ。「狐は七化け、狸は八化け」と諺にもある。人を化かすのは、この狸野郎の方があの狐オバチャンより上手かもしれん。油断するな。急に愛嬌をふりまき出したが、騙されないように気を引き締めよう。
「やっぱりその女の人、ヤーさんと係わりがあるじゃないですか。怖くてそんな話には乗れません」
「どうなされたんですか、そんな及び腰で。お客さん、こんなこと聞いたことないですか? アルゼンチンのある小さな町で数日間、夜中すべての街じゅうの明かりという明かりをシャットダウンした。どうしてそんなことしたかっていうと、長雨と高温のおかげで虫が大量発生してしまったから。街の灯りが周囲から虫どもを大量に集めてたんですよ。けれど住民が数日間真っ暗な夜に耐えてくれた結果、虫の発生数は劇的に減少したということなんです」
「それとこれとどういう関係が‥‥‥」
「だからぁ、都会の暗闇の中にしばらく身を潜めて、目立たないようにしてりゃ、社会の毒虫どもは近づいてこれないってことですよ。分かります? お客さんもヤリ逃げした後は数か月、隠れて大人しくしてることです。そうすりゃ奴らは手も足も出ない。またすぐ歓楽街にノコノコ出てきて派手に遊ぶから、痛い目に遭って、海に浮いたりするんですよ」
‥‥‥‥なんだ、どこで仕入れた話か知らないが、ほとんど関係のない話じゃないか。それにしても恐ろしいことを言う狸だ。さて、どうやってこの場から離れたものか。
こっちが黙っているのをこれ幸いと、狸野郎は話し続ける。
「私たちソドムやゴモラの住人、色情狂どうしじゃないですか。背徳の肉欲で神の怒りに焼き払われちまいましょうや。焼け野原にはもう何一つ証拠は残りませんよ。ね、上手いこと言うでしょう。なので、ね、大丈夫だから」
‥‥‥‥ソドム? ゴモラ? ありゃあ、狸がインテリぶりやがったぞ。敬虔なキリスト教徒でも新約旧約ぜんぶ読破した人はそれほど多くないのに、なんで狸ごときがあんな分厚い聖書を読むってんだ。どうせカモになりそうな男全員に同じ口説き文句を言ってるんだろう。
「だから心配ご無用ですって。女の方も好きでやってるんですから。私は性癖の合う者どうしを結びつける恋のキューピッドです。幸運ですよ。おたく様のような、こだわりの強い真の趣味人のご要望に応えられるプレースポットは、日本広しといえどもウチだけだ。犯罪にならない程度に、合意にもとづいて二人でしっぽりと楽しんでもらえば。あとは自己責任ということで」
「待って。その娘、ひょっとしてカナちゃんって言うんじゃないの?」
「カナちゃんって、あ~た、それどっかの店での呼び名でしょう。運転免許証でも見たんですか? 免許証とか保険証とかで本名をちゃんと確認してから言ってくれないと分かるわけないじゃないですか。カナなんてお嬢はどこの店にもいますよ。どこの店のカナちゃんなんですか」
「ブラウンの」
「ブラウン? そんな店、知らないなあ。忘れちゃいなさいな、そんなバカ女」
「カナちゃんでないなら、僕、もういいです」
そうそっけなく断ると、読みが外れたためだろう、狸野郎はあたふたしだした。慌て顔だ。当惑の色がノシよろしく顔にはり付いている。
「そんなつれない事、言っちゃあ身も蓋もない。ああ思い出しました。そうでした、そうでした、ブラウンのカナちゃんね。失念してました。そうですよ、あのカナちゃんですよ。お目が高い。このたびカナちゃんが、12時間いたぶり放題コースに挑戦したいと言い出しましてね。あの娘は筋金入りのドM嬢だ。見上げたもんじゃないですか。プロ中のプロだ。ここら界隈でも彼女の勇気に称賛の嵐ですよ」
「あれ? これって闇ルートじゃなかったの? なんで称賛の嵐なの? なんで表沙汰になっちゃうの?」
何気なく投げた牽制球が効いた。虚をつかれた狸野郎は言葉に詰まってしまった。動揺の色を隠せない。墓穴を掘ったな。狼狽して目を白黒させている。狸の分際で、背伸びして豹変したりするからボロが出たんだ。お前が豹の器か、つうの。
「あの、その、お客さんもお人が悪い。言葉の綾ですよ、綾。それくらい天晴だってこと」
‥‥‥‥しどろもどろだ。コイツ、第一ラウンドでは脅しすかしの切り替えの妙で風俗業界百戦錬磨の手だれ風に見えた。けど第二ラウンドで見事にコケたな。海千山千の古狸とおぼしきや、案外ぬけてる馬鹿狸だ。人間に化けたつもりでいても、お尻から尻尾がビロ~ンと見えている。
「信用しないわけではないんですが、カナちゃんって、まだ高校生でしょう。この前も重そうな学生鞄もってたから。大丈夫なんですか? JKに風俗をやらしたら風営法で営業停止になっちゃうんじゃないの?」
「そこんとこは任してください。こっちも年季が入ってるんですから。摘発されるようなヘマはしませんよ」
‥‥‥‥なんだ、嘘がバレバレじゃないか。まことしやかに何、ハッタリかましている。カナちゃんには大きな子供までいるんだぞ。こんなペテンにかかろうもんなら、カナちゃんどころか女狐オバチャン第2号が化かしにやってくる。カナちゃんはPCRテストで陽性になって来れないとかなんとかかんとか、どうせ嘘八百を並べたてるに決まっている。またカモにして、10万円巻き上げるつもりなんだろう。統一教会の霊感商法の方がまだましだ。
店内に鳴り響くロックミュージックの歌詞よろしくヤレヤレと煽るだけ煽って金を払わせた挙句、どっこいヤラすつもりはサラサラない。ヤレヤレ詐欺の手口ありありだ。同じ手に二度とのるものか。
(18)
そのとき猛烈に事務室のドアを叩く音がした。叩き破らんばかりの勢いだ。つづいてドアノブをガチャガチャ鳴らす音。不意を突かれて状況がよく飲みこめない。大きなトングで、急に頭をつままれたかのようだ。どこぞの酔っ払いが殴り込みに来たのか? これはなんの騒動なんだ。プーチンのウクライナ電撃侵攻か。
「こりゃあ! オヤジ、開けろ。なんで鍵なんかかけてやがる。舐めてんのか! 開けろ、ボケ! 殺すぞ!」
狸野郎は眉をひそめて「しまった」と一声。ドタドタと大急ぎでドアを開けにいく。大慌てで終電車に走り込む酔いどれサラリーマンの慌ただしさだ。かなり狼狽した様子である。狸野郎がサムターンのつまみを回すやいなや、図体の大きい二人組が乱入してきた。同時に、開いたドアからロックの耳障りな音も流れ込んでくる。あっけにとられて声も出ない。
二人とも目つきが鋭く、ただならぬ雰囲気が漂っていた。一方の細身の男は顔に傷痕があり、雪駄履きで、日本刀の白鞘らしきものを持っている。もう一人の男は派手なスカジャンを着込み、半グレ風でスニーカー履き、金属バットを左手に握っていた。よりによって物騒な奴らが飛び入りで参加してきやがったなあ、まったく。一難去ってまた一難だ。
「くそぉ~、オヤジ、勝手に引きこもりやがって。息の根を止められてえのか!」
と金属バット男は怒りで青筋を立てている。
「そなた、店荒らしに来たとかいう狼藉者はどこにおるのだ。探したが何処にもおらぬぞ。おのれ、とり逃がしたのか!」
続いてそう言ったのは日本刀男だ。なんだコイツ、侍にでもなったつもりでいるのか、とそのクレージーぶりに赤井君は息を呑む。“さあてお立会い”と蝦蟇の油売りの口上でも始まりそうだ。蝦蟇の油売りは偉ぶらないと逆に品物の値打ちが下がって売れないとばかり、あえて態度をでかく見せるという。お前もその口か。
「てめえか、お邪魔虫は!」と金属バット男の怒鳴る声。早々にガンを飛ばしてきた。不穏な空気、しばし。一触即発の状況だ。
四六の蝦蟇よろしくダラ~リと油汗を流す赤井君の後ろにまわり込み、オロオロする顔を覗き込むや、
「なんだ、コイツ、まだガキじゃねえか。いいか、ガキがこんなとこに来るもんじゃねえ。ママのおっぱいでもしゃぶってろ! おい、震えてんのかよ、情けねえ」と気の抜けた表情に変わる金属バット男。
「まさかコロナにかかって震えてるんじゃないだろな。てめえ、俺にうつすなよ。ちゃんとワクチンは打ったか。ワクチン、チン、チン、チン、チンコに打ったか。バカかぁ、てめえ。あそこに打ったら痛えじゃないか。使い物にならなくなったら、どうしてくれるんじゃ。男はたってナンボ、女はたたせてナンボじゃい」
そういうが早いか、だしぬけに金属バット男が馬鹿笑いをしだした。ひとしきり笑うと、今度は急に怒った顔になり、
「この野郎、ふざけんな! 何が可笑しい! 殺すぞ、コラ!」と怒鳴り声で吐き捨てると、床をバットで強打するという暴挙に出た。
粗暴この上ない。音が大きすぎて床がぬけるかと思った。
‥‥‥‥なんだ、なんだ、これは地震か? 揺れが尾てい骨に響いたぞ。それにしてもずいぶんと手荒なことをする奴だ。肝をつぶしたじゃないか。とても正気の沙汰とは思えない。
下品なギャグに大笑いした直後、今度は突然そのギャグに怒りだして床を思い切り叩く。気でも触れているのか。ギャグを言ったのはお前自身じゃないか。興奮し過ぎてブチ切れか。鎮静剤でも打ってもらえ!
怖気づきながらも心の中で必死に抵抗する、半分やけっぱちの赤井君である。
「ちぇ、面白くねえ」
男は事も無げにそう言うと、今はケロリとした顔に転じている。
‥‥‥‥コイツ、意外と冷静だ。演技している。窓ガラスを叩き割ると外から目立って、パトロール中の警察官が介入しかねないので、あえて床に一撃を加えたな。見た目のわりに姑息でずる賢い手合いだ。どうせお前もヤクザ組織の虎の威を借る狐なんだろうが。スカジャンの虎の刺繍も嘆いてるぞ。さっきから散々っぱら狸や狐の尾っぽを見せつけられてるんだ。貴様の虎の尾ぐらい、いくらでも踏みつけてやらあ。あらあら、それにしてもここら界隈は狐や狸やトラなど、動物がいろいろ出没しますこと。
「ガキが自分の頭で考えず、チンコを野放しにするからこんなことになるんだ。チンコに自由に考えさせ、おもむくままに行動させた貴様が悪いんだよ。チンコに好き放題にさせたらどうなるかぐらい分かるだろう。分かんねえのか。そうか、てめえはお頭が軽すぎて考えることができねえのか。おい、何でもかんでもチンコに任せっきりかよぉ、情けねえ。自分の息子だろう、息子の不始末は親の責任だ。男なら潔く腹を切れ」
再び金属バット男は大声で笑い出した。笑ったり怒ったり忙しい奴だ。どっちかにしてくれ。
怖がるほどに虎は大きく見えてくる。怖がるな、コイツは仔猫だ。そう必死に士気を鼓舞しようとする赤井君ではあったが、
「お主の切腹の介錯をして進ぜようか。」
今度は日本刀男が赤井君に睨みを利かしながらそうスゴんできた。本人は自分に酔って、歌舞伎の大見得でも切ったつもりになってるのだろうが、せっかくの「にらみ」も顔面神経麻痺にしか見えない。
コイツ、そんなに白目をむいて何に悶絶してんだ。緊張し過ぎた反発だろうか、思わずぷっと噴き出してしまいそうになってしまった。サイコパス感がぜんぜん足りない。下手っぴな演技だ。もっともこれが演技であればの話だが。
状況的には十分緊迫の度は深まっているはずなのだが、人というのは極度に追いつめられると笑い出してしまうものらしい。プレッシャーから心を守るために、脳の安全装置でも働いたのだろうか。怖いのに笑いをこらえるというアンビバレントな事態に赤井君は戸惑う。自分が心の中に二人いるかのようだ。
「こやつにもしばらくぶりに血の味を思い出させてやらなくてはならぬ」
そう呟くと、男は鞘から半分刀剣を抜き出してみせ、ゆっくりとまた鞘に収めた。刀の放つ鈍い光が背筋を凍らせる。
‥‥‥‥抜けば玉散る氷の刃ってかぁ〜~~ツ!! 一触即発、こりゃピンチだ。ボルテージ、マックス。
南総里見八犬伝のつもりか。そこで犬士にでもなってキャンキャン吠えてろ! どうせお前も僕と同じポチだろう、吠えるだけで噛みつけない小者のくせして。そんな威嚇射撃なんて怖くないぞ。本物のヤクザなら、そんな御託を並べる前にとっくに一刀両断、切り捨ててらぁ!
日本刀男の顔面麻痺につられて、ついにこっちの脳ミソまで麻痺してしまったのか。戦慄に武者震いしていたはず感情が、知らぬ間に逆切れしている。許容範囲を超えてヒューズがついに飛んでしまったらしい。ここに至って破れかぶれの居直りを見せるのは、いよいよフルカウントに追い込まれた赤井君である。
‥‥‥こうなりゃ、矢でも鉄砲でも持って来やがれ!
ただし情けないことに、これは心の中だけの叫びだ。理性の電流はまだ細々と流れている。いくら強がってみても、しょせん小心者は小心者、太鼓の曲打ちのように心臓が次第にバクバクと高鳴りだした。もはや緊張感は限界に近く、背中が硬直してつりそうだ。千切れそうなほど弦をパンパンに張りわたした弓がしなりにしなっている。ピンとはじくと今にもプッツンしてしまうんじゃないか。息遣いも少々あらくなってきた。体の反応にはブレーキのかけようがない。動悸にあらがえず、どんどん弱気になっていく赤井君である。
‥‥‥なんてこった。狸野郎に絞られていた時、緊張と恐怖のあまり頭に浮かんだあの日本刀が、再び目の前に登場してくることになろうとは。なんという仕打ちだ。実際にこれから日本刀を舐めさせられるんじゃあるまいな。僕の頭が目の前にゴロリ───冗談じゃない! 万事休すだ。
( ゚Д゚)ソンナ~、ヒドスギ
苦しまぎれに赤井君はカナちゃんが言っていたメタ認知のことを思い浮かべた。‥‥‥‥そうだ、こういう絶対的ピンチのときは、霊魂のように自分がら離れて、俯瞰で見おろすんだったな。そうすれば平常心が取り戻せる。そう、鳥になれ、鳥になって自分を空から見下ろすんだ。鳥の眼になるんだ、そうすればこの衝撃もやわらぐはずだ。そうだ、その調子、自分の姿を遠くから双眼鏡で眺めているように‥‥‥
ところがどうだ。「霊魂になって体から出ていくぞ」といくら号令をかけようが、赤井君が恐怖のあまり自分で自分をガチガチに握りしめているせいで、一向に肉体から霊魂さんが出ていってくれる様子はない。狐と狸の動物霊に憑依されて金縛りにでもあってしまったらしい。おまけにワン公まで出てきやがって。とても自分を客観視する余裕などない。
突としてカナちゃんの言葉が甦る。
「もう限界って時は、あたし、お花さんや虫さんになるんだ。もし虫だったら、縛られてどんなに恐ろしいこと言われたって、ただ空気が震えてるぐらいにしか感じないでしょう」
‥‥‥‥おいおい、僕に虫になれっていうのか。ふざけんな。そんなことしたらコイツらに踏み潰されちゃうじゃないか!
さあ殺せ殺せ、と赤井君が開き直っていると、
「で、で、電話してご足労かけましたが、この人はいいんです。上得意さんになりそうなんです。だからこの人はよかったんです。間違えてました、スンマセン」
やにわ狸野郎が間にわり込んで助け船を出してきた。慌てふためいている。さすがのアンタも店内で刃傷沙汰に及ぶのは嫌か。わざわざ口を挟んでくれるなんて、もしかしてコイツ、いい狸なんじゃねえ?
♪証、証、証城寺、証城寺の庭は。つ、つ、月夜だ、みんな出て来い来い来い。おいらの友達ゃあ、ポンポコポンのポン(^^♪‥‥‥‥雨降って地固まるで、意外とこの狸野郎とも友達になれちゃったりして。でもこうやって必死で守ろうとするところをみると、僕からもっとふんだくれると踏んでいるのかもしれない。
「おっさんが電話してくるから、来てやったんじゃねえか。久しぶりに暴れてやろうと思ったのによお」と金属バット男は不満げである。
日本刀男は日本刀男で、「笑止。こやつ、犬侍の分際で今ごろ何を戯言を言うておるのじゃ。小童ごときに呼び出すなど不埒千万じゃ!」とご立腹である。もう完全に武士になりきっている。‥‥‥‥そいつは狸だ、犬はお前の方だろう。あきれたもんだな、偉そうに。だけどそう言う僕だって、さっきまでカナちゃんの愛が欲しくて舌を垂らす哀れな馬鹿犬だったもんな。人のことは言えない。
「ちゃんと毎月、みかじめ料を払ってるじゃないですか、今日のところはご勘弁を。大事にしないでください。こらえて下さい。どうぞこのままお引き取りを」と、動揺の色を隠せない狸野郎。
必死の懇願の甲斐あってか、二人は「チッ、時間と手間をとらせやがって」と捨て台詞を残して去っていった。帰り際、日本刀男が狸野郎の耳元で囁くのが聞こえた。
「オヤジ、糞ババアにブリブリとぶりっ子させて、あくどい商売すんなよ、知ってんだからな。いっぱしに反社気取りで、こけおどしてんじゃねえぞ。アイツまだ小僧じゃないか、いじめ過ぎんな。少しは手加減してやれ」
二人が消えたあとも赤井君はしばらく椅子から立ち上がることができなかった。怖気づいて腰が抜けたわけではない。あの暴力団二人組がまだ表の方でうろついているような気がしたからである。急いで店の外へ出て、また鉢合わせしたくはない。狸野郎は初っぱなの威勢のよさはどこへやら、チキンゲームの敗者みたいに落胆して何も話そうとしない。そらみろ、僕に口三味線を弾いたせいで、バチをその身に当てることになったんだ。いじけてしまったのか、情けない顔でうつむいたまま身じろぎひとつしないでいる。信楽焼きの置物だ。相当へこんでいる。
20分ほど経過したのを見計らって、赤井君はこっそり事務所のドアを開け外に出た。あのイカれた音楽が耳に障る。するとその時、にょきっと狸野郎がドアの間から顔を出して、大音量に負けないぐらいの大声で赤井君に叫んだ。
「で、さっきの話、名刺の番号に電話してくださ~い。すぐ手配しますんで。またとないチャンスですよ~おッ。御返事、待ってまあ~す」
どこまで商魂たくましい狸だ。さっきまでの沈鬱な表情はどこへいったのやら。この程度の騒ぎは日常茶飯事で蛙の面に小便だったか。やっぱし友達なんかにはなれない。世知辛いなあ。この世の中、証城寺の狸ばやし通りにはいかないのか。
店から通りに出ると、泣いているはずのさっきの狐オバチャンが、鳩時計の鳩よろしく窓からひょっこり顔を出してこっちに愛想笑いをしている。よく臆面もなくしゃしゃり出てこれるもんだ。今ごろ何のポッポッポだ。ここで愛嬌ふりまいたって遅いぞ。
あれから化粧直ししたみたいだな。改めて見ると何かの毒々しい染料に顔を浸したような濃厚メイク、細い目に原色の照明が当たって歌舞伎の隈取りに見える。ネオン街のケバケバしさにも劣らぬ出来映えだ。
その分厚いツラの皮によく化粧がのったもんだ。そんなに盛ったら顔認証、パスしないぞ。たいした抽象画の展示物だぜ、まったく。化粧する前に顔修正アプリでも使ったらどうだ。チンドン屋めが。ハイカラなネオンの重ね着をした菊人形にでもなったつもりか、お前サンはあれほど優美じゃないぞ。そんなとこにいないで表に出てこい。ほんでもって法被でも着て、きつねダンスを踊るか? すごくサイケな絵柄だぞ。アンタが踊ったら豚ダンスだ‥‥‥‥と腹立ちまぎれにあらん限りの罵詈雑言で皮肉る。
その一方で、なんだか少し可哀想な気がしてきた。悪態をならべるほどに自分が惨めに思えてくる。今のこの立場で、この人をこきおろせるのか、お前も同類じゃないか。そう心の声が聞こえてくる。
オバチャン、何とかまともな道に戻ってくんないかなあ。いいオバチャンに思えたが、とんだ食わせ者だったか。まったく揃いもそろって、なんなんだ、コイツらは。
近くにタクシーが停車していたので一目散、なりふり構わず逃げ込んだ。この辺りは百鬼夜行そのものだ。いつ危険人物に出くわすか知れたものではない。臆病風に吹かれたわけじゃないが、何はともあれこの場所から遠くに離れないと‥‥‥
「お客さんどこまで?」
「どこでもいいです、ともかくここから遠くにやっちゃって。急いで、早くして」
歓楽街を脱け出してしばらく行ったところで、無理を言って高架橋の路肩にタクシーを停めさせ、降りた。何とか初乗り運賃でまかなえる距離だ。ポケットにジャラつく小銭でかろうじて料金を払うと、本当にスッカラカンになってしまった。自宅にはここから歩いて帰るしかない。とりあえず市街地中心部からはかなり離れた。高架橋からは遠目に歓楽街の辺りが見渡せる。腫れた扁桃腺のように歓楽街の上空だけがネオンに薄っすら爛れていた。盛り場の喧騒も遠のいている。下車してすぐ、狸野郎からもらった名刺は、中身も見ずに道端に破り捨ててやった。
気持ちを張り詰めていたせいで首のあたりが凝っている。緊張で口の中もカラカラに乾いている。その場で軽く柔軟体操をした。上体を反らして背骨をしならせると、ちょうどビルとビルの間から月がのぞいているが見えた。けばけばしいイルミネーションから遠ざかったためだろう、夜空にくっきりと浮かんでいる。月は骨の切断面のように青白く、夜に貼りつけられたブリキ板のように薄っぺらに見える。
月光が反り身になった顔に雪のように降り注ぐ。雪の光は落ち葉に変じ、地面に触れたとき、耳には聞こえないほどの微かな音を出す。赤井君はぽつねんとステージに立ち、月光の紙吹雪が舞っているのを見渡す。
今宵は十五夜か。巨人が蹴上げて夜にはり付いた白いボール。大きくて、それでいてペランペランに薄くて軽くて、今にもひらひら落ちてきて地面に砕け散ってしまいそうな、まんまるお月さまである。粉々になった月の欠片を拾う手がひんやりと冷たい。欠片の面に映る僕の姿。指を浸すとその先から同心円の輪が幾重にも広がってゆく、僕の姿をゆっくり崩しながら。
月に都会は似合わない。雲間に冴える月に似つかわしいのは、やっぱりススキの平原だな‥‥‥‥と、風流を解する余裕をみせてみたものの、所詮ポーズはポーズでしかなく、内心の憂いはとめどない。
フルムーンのおかげで辺りはいつもより仄かに明るい。降り積もる月の淡い光、闇夜を照らす桜の花明かりのように。街が月の発する青白く淡い光の波に洗われている。立ちすくむ赤井君のシルエットも背後の月明かりに滲んでいる。こんな月夜は、獲物を狙って色と欲にうごめく獣どもの影もことさら浮き立つ。なるほど狸や狐がウジャウジャと出て来るのも無理はない。
月光が氷の帯となって頭上から降り注いでくる。月光が顔にも手にも青白く貼りつく。薄明りの中、虚しさが宙に漂う。月もこの無様な姿を見て笑っているかもしれない。降り注ぐ月のシャワーを浴びつつ溜息をつけば、自然と泣き言が口をついて出る。
‥‥‥‥まるで動物園だ。さもなくば奇人変人大集合か。“水商売、何でもあり”ったって、ありゃヒドすぎだ。いずれにしてもこんなドタバタ劇はもうたくさんである。もとはと言えば、ふつふつと湧き上がる度しがたい情欲を何とか鎮めようと、フラフラと夜の街にやって来た僕が悪い。とてもアイツらに何かを言える立場じゃなかった。自業自得、ツケを払わされたまでのことだ。要はどうやって情欲の処理をするかだな。いっそ得度して修行僧にでもなるか───寂しげに肩を落としながら、自嘲気味に苦笑いする赤井君なのであった。虚しさと月明かりが溶け込んだその笑みは薄暗い。
大きな月を背負って、彼はトボトボ歩きだす。人の世のうら淋しさが押し寄せてくる。この寂寞感は何だ。逃げたい、逃げてしまいたい。死ぬ間際、自分の魂が抜けていく感覚が、今まるで我が事のように想像される。
この先、辛いことがあっても透明人間になって耐えていくんだ。誰の夢の中にも現れない存在感ゼロの透明人間に。この灼熱地獄の中、いまだ渇きは潤わない。「砂笛の孤独」‥‥‥人生は苦しみの砂漠だ。

(19)
行きかう人々が慌しく蠢動する都会の通勤時間帯。想像すれば、コンクリートの路面を踏む何千何万もの人々の靴音が、少しずつ自分の心の底に溜まっていくような気がしてくる。通勤している人々の絵が見える。引きも切らず流れる人波。一様に表情は流れ落ち、どの人にも顔がない。
ひしめく群衆の喧騒から遠く離れて、このビルの一室だけやたらゆっくりと時間が流れている。職場にいるにもかかわらず、ノッポとチビの二人組が朝っぱらから怠惰なスローライフを満喫していた。

箱村が嬉しそうに話し始める。
「無断欠勤だ、けしからん。今日は、お喋り高木ブーは来ないようだな。ぐだぐだスカタンを並べる奴がいないと、朝もスッキリさわやかだ」
やれやれこの男、自分のことは棚に上げている。
「社長だからいいんじゃないですか? 花菱社長は好き放題やってますね、羨ましい」
「どうせ家でグースカと寝てるか、ラッシュアワーに巻き込まれてアタフタしてんだろう」
「ソウル繁華街のハロウィーン事故みたいに将棋倒しになってなきゃいいんですけどね」
「そりゃ分かんねえぞ。鈍臭い奴だからな。くたばりそうで、なかなかくたばらない。いっそ押っ死んじまったらいいんじゃね。あんな奴が来たら、ややこしくて内輪もめの元だよ。来ない方がいい。とうに八十歳超えてんだから、もう老醜をさらすのはよせよ。あのお喋りペリカン野郎は嘴を紐でくくって、家で毎日じっとしてりゃいいんだ。お前だけでいいよ。お前は真夏の木陰みてぇな男だからな。地頭が悪くてボーッとしてるから、一緒にいてホッとするんだよな。これ、一応褒めてるんだぞ。さあて、おさぼりタイムのスタートだ」
今日はノッポとデブのコンビの掛け合いは見れないんだ───そう思った赤井君は少しがっかりする。
「アイツがいねえと部屋の空気がきれいだろう」
「ヘビースモーカーですもんね。お年寄りがあんなに吸っちゃあ、体に悪いですよ」
「アイツはタバコと一体化したタバコ人間だよ。タバコやめたら、逆に死ぬんじゃねえか」
朝陽が開け放ったドアから差し込み、そこに微細な埃が舞っている。
「そろそろ僕、掃除でもしときましょうか。埃も目立ってきてますし。ほら、あそこの陽が射してるあたり‥‥‥‥」
「お前、それが見えるのか。いいなぁ、若い奴らは。俺、かなり白内障が進んじゃってるから全然見えねぇのよ。若いころ本を読み過ぎたせいかなぁ。そろそろ手術しなきゃと思うけど、おっかなくてよお」
「体が大きいくせにビビリなんですね。白内障の手術した人が日本に何人いると思ってるんですか」
「いつか眼科に行かなきゃと思ってんだけどな。でないと運転免許更新の視力検査で落っこちちゃうだろう。落とされるのは小説でもうこりごりだ。落ちたらアイツが俺の愛車をスクラップにしちゃうじゃないか‥‥‥‥ああ、人生は無常だよ。歳はとりたくねぇな」
「見た目のわりに結構歳くってるんですね。あえて御歳はお聞きしませんが」
さっきから箱村は社長専用のソファに寝っ転がっている。そのくつろいだ様は、温泉宿に一泊してるがごときだ。暑苦しいのかリラックスしたいのか理由はよくわからないが、靴下をテーブルの上に丸めて脱ぎすてている。何もわざわざそこに脱ぎ捨てなくても。さすがの赤井君も多少目障りに感じるのは否めない。
「社長、突然やって来るかもしれませんよ。そんなふうに靴下を脱ぎ散らかしちゃっていいんですか?」
「足裏の下にあれども靴下とはこれいかに」
欠伸をしながらそう言う箱村。まるで会話がシンクロしていない。
「なあ、どう考えても靴上だよな、靴下じゃなくて」
裸足になってソファに体を沈める箱村の足の裏は、あらためて見ると規格外にデカい。
「あ、それ、よく小話に出てきますよね。でも靴中じゃないかなぁ? 足を覆って靴の中にあるから」
「まぁ、靴下って言うもっともらしい理由があるんだろうけどよ、そんなのどうでもいっか。下らなくて調べる気にもならねえや」と、箱村は投げやりになる。自分が最初に投げたボールぐらい拾いにいってほしいものだ。ふてぶてしく寝っ転がってるようじゃ、拾いにもいけないか。
「いつもいつも、こんなんでいいのかな。日本一、楽な仕事だ。普段着姿でチンタラやって来て、ストレスフリーの奇妙奇天烈な仕事をチョコチョコっとして、普段着姿でチンタラ帰っていく。みんなが知ったら羨ましがられますね。おかげで最近、ほどよいクッションのような生活させてもらってます」
そう言う赤井君の頭は寝グセがついたままだ。働き出して最初の一週間は花菱からせしめた金で買ったパリッとしたスーツ姿で通勤していた彼も、今ではだらけたジャージ姿だ。貧乏性のせいで一張羅を通勤着にするのがもったいなくなったのである。ジャージじゃ、破れかけたあの電器店の作業着と大して変わらない。
「チンタラで結構。食事の準備が億劫だったらコンビニ弁当を買いに行く。コンビニ弁当の食べ終わったトレーの始末がめんどうだと言うなら大衆食堂に行きゃいい。庭の草取りが嫌だったら便利屋やシルバー人材センターに頼む。家の掃除をしたくなければ、ちゃんとそのために代行業者がいる。チンタラ大いに結構、怠惰が経済を回してるんだ」
「ものは考えようですね。何でもかんでも自分に都合のよいように考えちゃえばいいのか」
「そういうことだ、ちゃんと学んだな?」
「はい、学びました」
そう言いながら赤井君は思わず知らず冷蔵庫の扉を開け、中をチラ見してはすぐ閉める。箱村のコンビニ弁当や大衆食堂というワードに、パブロフの犬よろしく、また条件反射している。今朝から何度開閉したことだろう。椅子と冷蔵庫の間を等間隔に行ったり来たり‥‥‥いつから彼は振り子になったのだろうか。その無意識サイクルの正確さは全自動家電なみだ。すっかりダラダラ感が板についている。
「ちなみにお前、『ちいさい秋みつけた』って童謡、知ってんな」
「知ってますよ、♪小さい秋、小さい秋、小さい秋、み~つけたぁ〜~~(^^♪‥‥でしょ?」
「幸せってな、何てことない生活の中に小さい秋を見つけることだと思うんだ。♪小さい幸せ、小さい幸せ、小さい幸せ、見ぃつけたアア~~~(^Q^)♬ ってな。今のお前のほどよいクッションのような生活、そういうのが本当の幸福ってもんだ。これといっしょだ、これと」
自分が寝そべっているソファの縁をポンポンと叩きながら、箱村はそう言う。
「箱村さんってさあ」
「何だ」
「音痴なんですねえ」
「お前がよく言うよ、音痴どうしじゃねえか」
「同病相憐れむ、といきましょうか」
「いいか、幸せってのは自分の両手の中に今あるんだ」と両の手の平をゆっくり開いてみせる箱村。足だけでなく手も異常にデカい。
「いけね、空っぽだったか。一万円札でも中から出てくると思ったか、残念でしたなあ、赤井くん」
「そう言えば村上春樹の言葉で、なんかそういうのありましたね。ほら、中国や台湾、それから韓国のKポップなんかで流行ってる言葉、日本のオバチャンたちにも受けてるアレ‥‥‥なんだっけな」
ゴムの緩んだジャージをズリ上げつつ、思い出そうとしている赤井君に箱村が答える。
「小確幸だろう、『うずまき猫のみつけかた』の。小さいけれども確かな幸せってやつだ。うん、俺が言いたかったのもそれだな。幸せは手の届かないところに見つけるんじゃない、確実に手の届く自分の周辺に見つけるもんだ」
「思い出した、それそれ」
「お前にはすごく教訓的な話だろう。甚だしく不幸にならないコツは、分不相応な甚だしい幸福を求めないことだ。不幸にならないようにちょっと注意して平凡に生きていく労力と、周囲を蹴落とし皆が羨む名誉や栄華を手に入れる労力とを比べてみろ。どっちが得かよ~く考えてみな。衆目を集めるような高いところに駆け上がって、下界を見おろしたいなんて考えんなよ。ヘトヘトになるまで努力してその場所についに到着したけど、そこで見る景色なんざ一週間で飽きる。そうだろう」
「それも村上春樹が言ってるんですか?」
「いや、そうまでは言ってない。これは俺の脚色だ」
「な〜んだ、村上春樹がそう言ってるんなら説得力あるけど、箱村さんの脚色じゃねぇ‥‥‥」
「みんな、名声や肩書、享楽や財産を求めるだろう。そんなもん求めるより苦痛の無いほどほどの生活を求めるべきなんだ。どうして皆そうなっちゃうかってぇと、それらをいかにも甘美なものに見せかける世間の粉飾のせいなんだな。いかに華やかに見える芸能人や社長やセレブ、お前のめざしてる小説家様をそこに入れていいか分かんねえけど、そんなのは看板・装飾こそ立派だが、中身は空っぽで喜びはほとんどなく、ただ追いまくられるばかりで、日々苦しみだらけってのが真実さ。けれどメディアを先頭に、世の人々は至る所でそれをきらびやかに粉飾し、お前みたいなノーテンキな奴を誤った道に引きずり込んでいくんだ。そういう試みは妬みやあこがれを強烈に刺激するから、抜群の効果があるんだよ。だから騙されんな。いいな、運命というのは何千何万の選択が積み重なって作られていくもんなんだ。たった一つのボタンの掛け違いが後々まで尾を引き、取り返しのつかない事態を招くこともあるんだ。だから軽々しく非現実的な夢を追うのはやめろ。ちなみに言っとくけど小学校じゃないぞ、ショウカッコウだ。似てるからって間違えんな」
赤井君にふと小学校の印刷機を無断借用して自分の本を刷ったことが甦ったのは、箱村の小学校という言葉を聞いたこの時である。
‥‥‥‥なんであんな悪いことをしてしまったんだろう。あの朝たまたま会った校長などは善人の塊みたいな人ではなかったか。あんな人達を騙すなんて。あれから何の音沙汰もない。学校側はまったく気づいていないのだろう。事務のアイツも仕事が忙しすぎて、もう忘れかけているに違いない。バレなかったらいいという問題ではない。誰にもバレないまま忘れ去られたとはどういうことか。誰も見ていなかったと同じことなのか。いいや、誰も見ていなくても自分が見ている。自分が見ていると言うことは、同時に神や仏も見ている。そしてそういう時こそ、神や仏が特に目を皿にして見ていたということなのだ。誰もそのことを知らなくても、自分だけは知っている。そしてそれはずっと残り続け、いつか自分を苛むことになる。僕はそういうことをした人間なのだと。
突然のフラッシュバックに反省することしきり。そんなキャラでもないのに良心の呵責に胸を痛める赤井君である。
「どうした。急に落ち込んじまって。ああそうか、悪い、悪い。別に作家の夢を追うのを責めてるわけじゃないんだ。気にしないでくれ。そんなことより、まずは駄弁ろうぜ。油の売り放題、与太の飛ばし放題。思いっきり無駄話だ。この前の続きだぜ。なあ、夢を追うのはいいけどよ、何度も言って押しつけがましいが、お前は作家にだけは絶対なれない。どうしてだか知りたいか。知りたいだろう」
「ええ、そりゃあ、まあ」

最後までお読み下さりありがとうございました。なお気にする方は少ないと思いますが、作中に広告その他が挟まれていても作者とは無関係です。念のため。
赤井かさの(ペンネーム、挿絵も)
霞ゆく夢の続きを(2)

