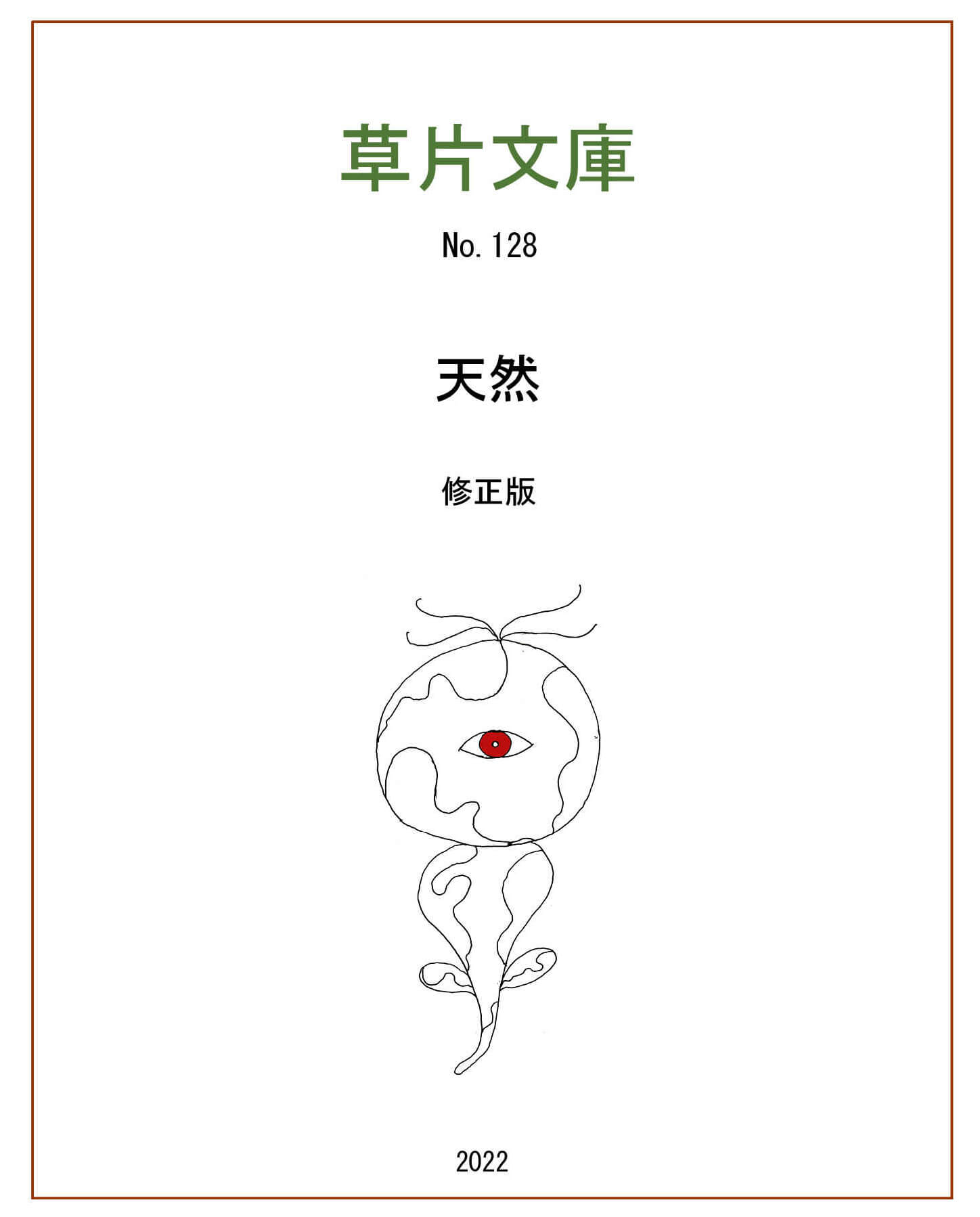
天然
へんちくりんなお話し。
とうとう杖を買った。杖というものとは縁がないと思っていたのだが。からだは頑丈だ、と信じている。年をとると仕方がないですよと医者は言う。頭は全く元気だ。これも自分ではそう思っているのだが、他人に言わせると、頭のどこかがとても弱いらしい。家内にだけじゃない、友人にまで言われる。
「おまえはなー、天然なのだよ」
一番仲のいい、小学校からの友人が面と向かっていう。この年になるとさすがに言われないが、若いころはよく言われた。
「女なら、かわいいと思うがな、男だと、アホにしか見えないんだよ、本当はおまえは他の奴よりずーっと頭がいいけどな」
だそうだ。
何というか、男の天然への差別ではないのか。女天然はかわゆくて、男天然はあほか。女から女の天然はかわいいらしい。松浦理恵子の「愛する子ども」に出てくる天然の女子高生は、仲間から顔をもみくちゃに触られてかわいがられる。女からみた男の天然はどのように見えるのだろう。抜けてる奴としか思われないのか、それともかーわいいーといわれるのか。顔を触ってもみくちゃにされたいものだ。
家内にきいてみた。
「あはは、やっぱりかわいいとこみえるわね、だからあんたと、暮らしているじゃない」
だって。
かわいいのか。それでか、どうも女房は、俺と猫と同列に扱っているようだ。
ほらおぼけ、ごはんだよ。
その声に、おぼけと名付けられた、大きな雄の虎猫は、猫皿のおいてあるキッチンによたよたとあるいていく。
ほら、あなたもよ、ごはんだよ。
と僕も呼ばれるのである。そういやあ、猫のほうがいつも先だ。
ご飯の時間が、小学校の時から大好きだ。それで、いそいそと、キッチンにはいる。
「ちらばさないように たべなさいよ」
猫に言っているのかと思ったら、食事をしている僕の方を見ている。年を取っても目玉だけはでかい女房だ。
椅子に腰掛けると、前掛けをもってきやがる。渡すのではない、かけてくれるのだ。これは親切なのだろうか。渡すだけではめんどくさがってやらないだろうと言う配慮からだろうか。後者だな。
早く食べたくて仕方がないのに、前掛けなどやっている暇はない。と思っていることは確かだ。
「ねえ、今日映画見に行ってきていい」
だめとは言えるわけはないだろう。うん、と、首をこっくりさせる。目の前には目玉焼きがある。はやく食べたいじゃないか。
「お昼は一人で食べてね、前掛けするのよ」
はやく食べたい。家内が話しているときは顔をみていないと、機嫌が悪くなる。
「うんうん」
と返事をかえす。ここでやっと、女房は箸を取って食べ始める。
自分も箸で目玉焼きを挟み、口に入れる。口に入る前にテーブルの上におちた。
あれ、と、もう一度、箸で挟んで、やっと口に入った目玉焼きをかみながら、今度は、白いご飯を口にいれる。これがおいしい、いくつかの米粒は、前掛けにくっついたり、テーブルの上に落ちる。
おいしい。かんでいると、また米粒が口から飛び出す。
「猫の方がずーっときれいに食べる」
とは、女房がいつもいうことで、ああ、そう、と、聞き流している。
そうだ。忘れていた。なぜ、杖を買ったのか。
左足をくじいたからだ。足を痛めたのは生まれて始めてだ。大したことはないのだが、ちょっとでも痛いのはやなもので、おそるおそる歩いていたら、女房が杖を買いなさいという。
「天然のがいいな」というと、女房は
「あなたが天然だから、そのほうがいいかもね」
と言った。どういう意味だ。
「そのほうが相性がいいでしょう」
なるほど。
ネットでさがしていると、「どんなの探しているの」というので、「勝さんのようなの」と答えたら、ばかみたいいう顔をして、「あなた目はみえるのよ」と、言われてしまった。
「仕込み杖がほしい」
それを聞くと女房はきゃははとわらった。八十過ぎのばばあのくせに。
「座頭一になれるならなってごらんなさいな、天然の座頭一なんて、いないわよ」
とほざいた。
「おまえねー、いくら天然のおれでも、刀を仕込んだ杖なんて買う分けないだろうに、傘の仕込み杖だよ」
といってやった。
「あら、そうね、そりゃ悪くないけど」
俺の勝ちだ。
ネットにあった、傘のはいったステッキだ。女房も見て、「いいわね、ずいぶん細い感じあなたに使えるかしら」
「おれだって、傘ぐらい使えるよ」
「そうじゃないわよ、あなた、八十五にもなっているのに体重いくら」
「八十八」
「そう、体重は米寿でしょ、杖もつかしら」
そうか、たしかに。
「ふつうの頑丈のにしたら」
ということで、ドイツ製の太めのしっかりしたものになった。まあ、ちょっと気に入っている。神戸のステッキ屋に注文した。
まもなく、ステッキはとどいた。確かに頑丈そうで、僕の体重でも支えられるだろう。
さて、これをついて、格好良くあるくか。杖じゃなくてステッキと言ったほうが格好がいい。
さっそく、パン屋にパンを買いにでかけた。毎週、朝食べるパンを買いに行く。とてもおいしいパンだ。最近はここあそこに、しゃれたパン屋さんができて、一時騒がれる。僕のいくパン屋さんはそういう店じゃない。しっかりした味のあるパンがおいてある。いつも買うのはイギリスパン一斤、ブドウパン一斤、たまにチョココロネやクリームパン、塩パンなど。
朝八時からやっている。
行ってくるよと、声をかけて、ステッキを持って玄関をでた。おぼけがのたのたと外に出てきた。
「おまえにもステッキかってやろうか」
ステッキの先で、おぼけの尾っぽをつついた。おぼけが振り向くと にゃ、と鳴いたのか、ぼけ、といったのかよく聞こえなかった。
「今なんていった」
とステッキに体重をかけて、猫の顔をのぞき込んだら、ステッキが小石の上に乗ったようで、つるっと滑って、僕は玄関先の咲き誇るアカンサスの茂みのなかにころがった。
おぼけがそばによってきた。
「おこしてくれよ」とはいったが、おぼけはただ見ている。いや、笑っていやがら。
「なーにがおきたのよ」
女房が玄関からでてきた。
「なにやってるの、怪我しなかった」
僕は、なんとかおきあがろうと、ステッキにつかまった。痛い左足をかばって、起きあがると、ステッキがすべって、またすってんころりところがった。
「やだ、アカンサスの花折っちゃって」
自分の手を見ると、アカンサスの花を握っていた。
「痛いねこの花は」
ちくちくする。
脇を見ると、アカンサスの葉っぱにナナフシがいる。
「おい、ナナフシガいるぞ」
女房がよってきて「あら、久しぶりね、あなたつぶさないでね」
ナナフシが固まっている。
「はやくおきたら」
「おこしてくれよ
「重くて無理よ、ほら」
家内がころがっていた杖をもたしてくれた。
やっとのことで起きあがると、女房は、僕のことはお構いなしで、ナナフシに「気をつけるのよ」などといっている。どっちが天然だ。
女房がふりむいた。
「あら、あなた、まだいたの、パン屋に行くのじゃないの」
「右足も痛い」
「そっちもくじいいたの」
「いや、それほどじゃないが」
「じゃあ、行くのやめたら」
「うん」
結局杖をついて、また玄関の中に入った。
おぼけもついてはいってきた。
手を洗って、居間の椅子に腰掛けた。
女房はなかなか入ってこない。しばらくして戻ってきたので、なにしてたと聞くと、アカンサスを元のようにしてたのよ、とおかんむりだ。
「パンはあとであたしが買ってくくるわよ」
というので、「いや、痛みが収まったら自分でいく」と主張した。
「そりゃいいけど、アカンサス痛めないでよ」
といわれた。
植物の「天然」とはなんだ。よく考えると「天然」の言葉は人間にしか使えない。人間以外すべて天然だからだ。いや、人が管理している家畜や作物というのは天然とはいえないのだろうか。天然でいいのだろう。人間だってからだは天然だと思ったが、入れ歯が気になった。やはり天然じゃないのか。
僕が言われている「天然」とは、反応が単純で、考えずに返事をしたり、行動したりする人のことのようだ。うそはつけない、要領はちょっと悪い、だからかわいいのか。そうか、赤ちゃんと同じ反応をするからかわいいのか。だけど、ボケたじいさんやばあさんは赤子と同じような反応をしてもをかわいいとは言われない。年をとるとかわいそうなもんだ。「天然」とは生まれ持った脳に起因するようだ。
ともあれ、僕は「天然」という人類に分類され、86年生きてきた。天然の自分が、天然の自分を見て、解析をしようとしてもわからない。ただ、高校、大学の時、天然といわれていた女の子のいることは知っていたし、僕の目から見ても、かわいいように見えることは確かだった。頭がいい子だった。それじゃ、男で「天然」はいただろうか。おっとりしたやつはいた。ゆっくりものを考え、ゆっくりものを言う。だが、男から見て「かわいい」とは思わなかったし、周りの女の子も、その男の子を「かわいい」といった目で見ていたようには思えない。僕もそうであった。先生にいきなりさされて、答えを求められたとき、じっくり考えて、ゆっくり答えた。他の生徒より倍の時間を必要としただろう。だが、先生も急がせるようなこともなく、「ああ、そうだ、それが正しい」とか、むしろほめられることの方が多かった。
まあ、周りともめたりしたこともなく、周りに無理を言うわけではなく、自分のできる範囲で、自分のペースで生きてきた。生活はとくに苦労せずに今になった。
そう言えば、今まで、何かを頼りに生きてきたという意識がない。自分の二本足で、ゆっくりだが歩いて、いつの間にか社長の地位になり退職を迎えた。
それが、はじめて、杖というものを頼りにすることになった。杖は自分と相性がいいだろうか。パン屋に行こうとして転んだので、まだ一緒に道を歩いたことがない。いやまてよ、杖がなかったらころばなかった。ということは、もしかすると、この杖は僕を好きじゃないのかもしれない。
杖、いやステッキか。どっちでもいいものをじっくり見た。
何の木でできていたのだっけ。
「おまえ、何の木だ」
杖に問いかけたときに、家内がはいってきた。
「杖になに言ってるの」
「いや、杖がなければ転ばなかった」
「杖がなかったら、もっとひどく転んだかもね」
そうか、そう言う考え方もあるんだ。思い出した、杖は樫の木だ。
「右足大丈夫そうだ、あとでパン屋に行ってくる」
「本当に大丈夫」
そう言って奥にいってしまった。
パン屋に行くには玄関をでて、通りを左に曲がって、ちょっとした坂を下っていく。いつも行く道である。その日、玄関をでて、さて左に行こうと思ったときである。持ち上げた杖が、道の右の方に動いた。頼りにしていた杖が右に行ったので、自分のからだも右の方向を向いた。
そこで、左に向きを変えようとしたら、左足の捻挫したところが痛い。しょうがないので、右の方に進んだ。こっちの方からもパン屋にいけないわけじゃない。そう言うことで、杖に従って、右の道を行き、別の坂を下に下りた。
団地の中の一軒の庭から猫がのろのろと道にでてきた。
すると、杖が勝手に猫の方に動いた。しょうがないから、自分もそっちに動くと、猫は杖のところに来るとこすりついた。杖もなんだか猫にこすりついている。
「なにやってんだ」
猫に言ったつもりだが、杖ががたがたとゆれた。どうもがたがたいうなということのようだ。
杖が勝手に猫の尾っぽをなでた。というか、僕の手が杖を動かして、先を猫の尾っぽをさすった。
猫が、ごろにゃんと、道の真ん中で転がって、杖にすがりついた。
あれと思っていると、杖は僕の手から放れて、猫のおもちゃになっている。
猫がひとしきり杖にまとわりつくと、杖が勝手に僕の手もどってきた。おそらく一分かそこいらの出来事だ。
ままよと、そのままゆっくり歩いて、パン屋にいくと、いつもの店員さんが、どうされましたときいた。左足をくじいたことを言うと、
気をつけてくださいよと、丸いブドウパンを一つおまけにくれた。
パン屋をでたところで、バックが揺れて、もらったブドウパンがバックからとびだした。前にころころ転がった。止めようと杖を前に出すと、ぐさっと刺さった。
かがむのも面倒くさいのでそのまま家に帰った。それを見たかみさんが、
「なにやってるの、杖は楊枝じゃないのよ、パンを突き刺してどうするの」
僕を軽蔑の目で見たので、
「いや、これは、杖が勝手にやったんだ」
というと、
「なにいってるの、こんなおいしいブドウパン泥だらけにして、50円無駄でしょ」
「あ、いや、もらったパンだよ」
「ただだからって、泥だらけにしていいわけないでしょ、せっかく得したのに」
かみさんは、杖から丸いブドウパンをはずすと、「食べるるのはやっぱり無理かもね、」と、キッチンのおぼけの皿の上にのせた。猫だって食わんだろうに。
次の日、まだ痛いのでいつもの整形外科に行った。
「こうさわって痛みますか」
医者が左足首を握った。
「はい、実はよくなっていたのですが、杖を買って、パン屋に行こうと玄関をでたら、その杖が石にあたって滑って、またころびました、それで治ったはずの左足首がまだ痛いんです」
「もうしばらく強くテーピングをしましょう、杖の使い方は知っていますか」
「はあ、まあ、少しは
「ちょっと杖をみせてください」
杖を手に取ると、あっと言う顔をして、「いい立派な杖です、だけど、先のゴムがとれてしまいましたね、石にぶつかってとれたのですか」
どういうことだろう。
「ゴムなどありませんが」
「杖の先にすべり止めのゴムがついていませんでしたか」
「イギリスの映画を見ても、ステッキにそんなものつけていませんが」
「それは映画で、しかも古い時代でしょう、今ステッキを買えば必ずついてきますよ」
医者は不思議そうな顔をした。
とそこで、ステッキが長い段ボール箱に入れられて、家に届いたときのことを思いだした。
「ステッキとどいたわよ」
かみさんが、居間のソファーに腰掛けていた僕に、黒猫から受け取った荷物を持ってきてくれた。捻挫したての時である。
僕は喜んで箱をあけると、ステッキをとりだした。カバーのようなものを取り払って、見ると、なかなか立派ないいステッキだ。
まてよ、あのステッキの先を汚さないようにしてあったカバー、あれのことなのかな。いらないと思ってすてちまったか、いやまだ箱にはいっている。
僕はステッキが届いたときのことを医者に話した。
「ありゃ、それですよ、それはすべりどめ、それつけておかないから、すべったのですよ」
医者は笑い出しそうなのを我慢している。
それから、左足首を包帯ぐるぐる巻きで樹脂で固定された。
タクシーを呼んでもらって家に帰った。
家の中でも杖を使わなければ動けない。
おぼけが餌をほしがった。棚の餌を採ってやろうと、立ち上がって杖をついたら、おぼけが、ぎゃあああとないて、飛んで外に出ていっちまった。
ちょっとたってから、杖の先が尾っぽを突き刺したたらしいことに気がついた。石なら転んでいるかもしれない。
悪いことをした。
そうだ、先にゴムをつけなければ、ステッキが入っていた箱は寝室に置いたままだ。いくとあった。中をみると確かに黒いゴムがあった。てっきり送るためにつけたものだと思った。
ステッキの先にはめてみた。たしかにすべらない。
これはいい。杖をついて廊下にでた。
先に行こうとしたら、杖が廊下の板から離れず、前につんのめって転んだ。上向けに廊下にころがった。杖が廊下に立っている。杖の先のゴムが床に吸いついたようだ。
廊下の上を見たら、大きな蜘蛛がぽたっとおちてきた。ひゃあ、とからだを動かそうとしたら、左足が廊下の壁に当たって、痛いどころではない。泣きそうになるのを我慢していると、どうやら一時の痛みは弱くなったので、腹這いで突っ立っている杖のところに行った。
ありゃ、杖の上に蜘蛛が乗っかっている。大きくて気味が悪い。杖を揺らして蜘蛛を落とそうとしたら、蜘蛛が杖の上からぴょんと離れて僕の頭の上にのった。
ひゃあ、もうなにがなんだかわからない僕はとうとう気を失った。
「あなた、死んでるの」
かみさんが僕の顔をのぞき込んでいる。
「よく寝た」
「何でこんなところで寝てるのよ」
そういえば何をしたんだっけ、思い出した、
「医者に行った、こんなにされた」
「あら、でもなぜここで寝ていたの」
それで、杖が床に吸いついて、蜘蛛が顔に落ちてきたことを思い出した。そんな話をすると、「もう、三時よ、お昼食べなかったの」かみさんが言うので、
「まだ食べてない、はらへった」とやっと体をおこすことができて、そばに落ちていた杖を頼りに立ち上がった。
「杖の先のゴムをとっちまったんで、すべったんだ」
「あら、わたしも気がつかなかった、あなた、はずして使ってたの」
かみさんは同情しているようなことを言っているが、心の中で大笑いしているに間違いなし。
杖の先にゴムがついたことでとても幸せに感じた。そのためか、その日の夕食のおいしいこと。
そういうと、かみさんは、「そーを、よかったわね、捻挫して、すぐのときもおいしいおいしいって言ってたわよ」
「そうかな、この涎掛けがないともっとおいしい」
「そうね、こぼさないようになったらはずしていいわよ」
と言われちまった。
ともかく、その日は気持ちよくベッドにはいった。
夜中の三時、いつものことだが、尿意をもよおして、目が覚めた。夜中に一回おしっこにおきる。
暗がりの中、ベッドから降りて、一歩足を出したら、何かを踏んで、ごろんところがりそうになり、あわててベッドの縁を左手でつかんだ。
だが、からだがぐらっときて、左手首がぎゅうとまがった。いてええ、と、今度は体がベッドの上にころがった。左足首に痛みが走った。
いてててて
叫ぶと、隣のベッドで寝ていた家内がのったりと上半身を起こした。
「どうした、心臓か」
「手、手、足、足」
家内が電気をつけた。
「ありゃ、これふんづけたの、どうしてこんなとこにおいたの」
家内はベッドの脇にころがっていた杖をもちあげた。それを踏んだらしい。
「おれはしらんよ、玄関の傘立てにいれたぞ」
「昨日家の中で使ってたでしょ、気をつけなきゃ、おしっこ大丈夫」
そうだ、おしっこを思いだした。
「しておく」
「歩ける」
そういって杖をわたしてくれた。
「朝医者につれてってあげる」
かみさんはまたベッドの布団にもぐりこんだ。
ぼくはそうっと右足をベッドの下におろし、右手で杖をもって、なんとか立ち上がった。
二階の寝室のとなりにトイレがある。二階にトイレを作っておいて良かった。
トイレにはいって、さて、右足だけで立って、なにもつかまらないと、だすものがだせない。
ぐずぐずしていると、家内が寝室から、「おしっこできた」と声をあげた。
「おしっこをだすものがとりだせない」
「ばかね、腰掛けてやりなさい」
そういわれたので、腰掛けて、右手でパジャマのズボンとパンツをおろした。
そうかこうやればだせる。
何とか終わらせて寝室にもどると、かみさんは明るいにもかかわらず、もういびきをかいている。
壁のスイッチをけして、自分もベッドによこになった。だが、なんでこんなところに杖があったのだろう。
体を動かすと左足首にびびっと響く。手を動かそうとするときりっと痛い。目をつむった。なかなか眠れない。
だが、いつの間にか寝ていたようだ。
周りが明るくなったので何となく目が開いた。
「あ、起きたの、痛い?」
「いや、動かさなければ痛くない」
「でもあなた、なんで杖と一緒にねているの」
笑っている。
右手のところに杖がある。いっしょに布団にはいってしまったようだ。
「二階からおりられるかしら」
ベッドに腰掛たら、そんなに痛くない。
「だいじょうぶだ」
僕は杖を持って、階段のところに行った。けんけんで降りるのはちょっとつらいと、ちゅうちょしていると、
「おしりからおりなさいよ、杖は私がもっておりるから」かみさんの声がした。
階段にこしかけて、右足を二つ下の段におろし、右手でおしりを一段おろし、を繰り返し、何とか下にいった。かみさんが杖をわたしてくれた。
右手で杖をもち右足で歩いた。
歯磨きと顔洗いをなんとかすまし、キッチンに用意されていた卵焼きとトーストを食べた。
「着替え居間に持ってきておくからね、9時になったら、タクシー呼ぶから、電話は私がかけとく」
ともかく、左足首をまた痛めて、頭を汚して、整形外科に行った。
かみさんのやつ。結局僕をタクシーにおしこむと、
「あなた一人で、大丈夫そうね、私、映画見に行くから」
と結局ついてこなかった。
「おやまたですか、こんどは左手首も、どうしたんです」
「寝室に転がっていた杖をふんじゃって」
医者が笑っていいのか、どうしたものか困った顔をした。
「夜中トイレに起きたときに、ベッドの脇に杖があったんです、僕は玄関においておいたつもりなんですけど」
「はあ、ともかく、杖にけつまずいて転んだということですか、レントゲンをとりましょう」
レントゲンの結果、足も手もどちらも骨そのものには異常がなかった。よかった。
「腱が伸びてしまってますね、くせになったのかな、だけど、前ほどひどくないですからよかった、だけど無理をしないでくださいね、松葉杖を貸しますから使ってみてください」
「いまの杖じゃだめですか」
「かまわないですけど、松葉杖のほうが楽かもしれません、使いやすいほうでいいですよ」
「杖を持って帰るのはちょっとたいへんで」
「お一人でこられたんですか」
「家内はでかけていまして、タクシーを呼んでいただければ」
「看護婦に言いましょう、無理をしないようにしてください」
それでタクシーで家に帰った。
家内がいないので、いただきものの高級お茶漬けのりでお昼を食べた。おぼけがご飯をほしがったので、缶詰をあけてやった。
夕方、家内が帰ってきた。
「ごはんできている」
どういうことだろういか。
「あれ、ご飯頼んでなかったけ」
お昼にお茶漬けを食べた残りは一人分である。
「一人分しかないよ」
「私、あんパン買ってきたからあなた食べて」
夕食あんパンだけですますつもりなのだろうか。
家内は大きな紙袋の中からごろごろとあんパンをとりだして、テーブルの上に積み上げた。
おぼけがテーブルの上に飛び上がってきて、あんパンの匂いをかいで、何だという顔をして飛び降りた。
杖がとどいて二週間、役にたったというか、なれた。もう左足首、手首の痛みもほとんどない。あれから庭より外にでなかったので杖をつかっていない。
かみさんは今日も映画を見に行っている。公園にでもいってみるか。
玄関をでて鍵をかけると、転ばないようにアカンサスの前をとおりすぎて、門から外にでた。
公園は道を右に行くとある。さていくかと、杖を持ち上げると、杖が左の方におりた。と言うことはからだが左向きになり、結局左の方向にいくことになった。
まあ、そっちからも行けないことはない。
左に行き広い道にでて、左に折れた。軽い坂道だ。今日はスムースに歩いている。杖が前にすすんでいくような感じだ。杖に体重をかけると、軽々と次の一歩を誘導してくれる。
足の調子がいいなと有頂天になって歩いていくと、いつの間にやらまたパン屋にきていた。
まあ、いいや、公園で食べるお昼のパンでも買うか。中にはいると、店員さんのいらっしゃいませと言う声がきこえた。ここのサンドイッチはフランスパンにハムやら、蒸し鶏などを挟んだおいしいものだ。
二種類のサンドイッチを買うと店を出た。出たところで杖が小石の上にのってつるんと滑り、僕はあわてて、杖を手元に引き寄せて体重をかけた。ぼきっつという音とともに、道路にたたきつけられた。頭を打って左足の捻挫したところに強い痛みが走った。痛ててて。買ったパンがつぶれたようだ。
店の中から見ていたのだろう、店員さんが出てきて、おじいさん大丈夫ですかと、よってきた。頭がずきずきしているが意識はある。
「あ、すみません、タクシーよんでいただけますか」
「救急車じゃなくていいのですか」
ときくので、「行きつけの医者にいきますので」と救急車を断った。
店員さんは店の中に駆け込むと、奥からパンづくり職人の男性をよんできた。
がたいの大きいパン職員は僕をよっこらと抱き起こしてくれ、
「立てるようなら、店の中の椅子にこしかけていてください」とひきずるように連れて入ってくれた。
「すみません」
僕は店の中の椅子に腰掛けた。女店員さんが、「やっぱり救急車呼びました」と僕に言った。
五分もすると、救急車がきた。救急隊員が店員に様子を聞いている。僕のところにきて「指を見てください、何本見えます」と目の前に指を一本差し出した。
「みえますか」
「はい」
「何本ですか」
「一本です」
「とりあえず大丈夫ですね、車の中で、頭の傷の消毒します」
担架に乗せられた僕は私立総合病院に運ばれた。
救急医は頭の傷をもう一度チェックし頭と足首のMRIをとるため、手はずをととのえた。
がっっがっが、とっとっと、ぎっつぎっつっぎとMRIの中で電子音楽を聞き終わり、足も撮影され、救急診察室にもどされた。
医師は「頭は大丈夫です、ちょっとした切り傷だけです。左足首に骨折はありませんが捻挫がひどい、なんどかやってますね」
と言った。
「はい、やっと治ったところです」
「どこのお医者さんにかかってましたか」
僕は行きつけの整形外科医院の名前をいった。
「頭の消毒も終わりましたし、足首はとりあえずテーピングしておきます、応急処置です、今までのことを知っているお医者さんのほうがいいでしょう、明日で大丈夫ですから行ってくれますか」
「はい、そうします、あの杖がありませんでしたでしょうか」
「ありますよ、所持品はまとめてあります、杖は折れています、使えませんね」
杖は真ん中当たりからボキッと折れている。
「足が折れなくて良かった、家の方をお呼びしましょうか」
家内は映画に行っている。
「いえ、今うちに誰もいません、タクシーを呼んで、一人で帰ります」
「玄関にタクシーはいますから、看護師が車いすでお連れします、頭の怪我は毎日消毒だけはしてください」
そういうことで家にもどった。
丈夫なたよりになる太い杖はおれちまった。
かみさんが帰ってきて、ぼくのありさまではなく、杖のありさまをみて、「あーあ、高い杖まで壊しちゃった」
と悪態をついた。
「市民病院で見てもらった、頭も打った。だけど大丈夫だって、明日整形にいくから」
「また、杖を買わなきゃね」
かみさんは杖をきにしている。
そう言うと外にでていった。
何しにいったんだと思っていると、「ほら、いいもの拾ってきた」と戻ってきた。
家のからしばらく歩いたところに丘があり、自然歩道がある。かみさんはそこにいって、落ちていた枝を拾ってきた。杖になりそうな太さの木である。
「あなたとおんなじ、天然よ、桜の木の枝がちてたの」
雑巾でごしごし拭いている
「長さもちょうどいいわね」とベッドに横になっている僕にわたしてくれた。確かにまっすぐで、杖になりそうだ。
「よく落ちてたな」
「私ついているからね、ほらこの杖はただよ」
その枝をついてベッドからたってみた。おおよいよい、使えそうだ。かみさんもたまにはいい拾いものをする。
そういうと、「二度目よ、あなたのつぎ」と言った。
そうか、俺もただでかみさんに拾われたんだ。
明くる日、タクシーでいつの整形外科に行った。
医者が、またですかという顔をして、左足のテープをはがすと指で触った。外くるぶしの周りを押されたら飛び上がるほど痛かった。
「全く同じところをひねったんですね」
サポーターだけじゃなくて固定しておきましょう。頭の傷も見てくれた。
「これは擦り傷だけだから消毒しておけば大丈夫、骨にヒビでもはいったら大変でしたよ」
まったくだ。
「歩くのは良いことだと思いますけど、気をつけないとね、おや、杖はどうしました」
「折れちゃったんで、かみさんが枝を拾ってきてくれました」
桜の木の枝を見せた。
医者はぼうっきれを持って、「まあ丈夫そうだが、ずーっとこれじゃあぶないかもね」といった。
「また三日後にきてくださいね、無理をしない程度に体を動かすのはいいですよ」
そう言われた。
「歩いて帰ってもいいですか」
「うーん、お年もお年だから、無理をしないようがいいですよ」
そういわれたのだが、整形外科病院の外にでると、急に公園にいきたくなった。昨日公園に行くつもりがパン屋に行ってしまったのだ。
病院から公園は近い、ちょっとのぞいて、そこからタクシーを呼べばいいだろう。
そう思って、ゆっくり歩いて公園に行った。池の畔にベンチがおいてある。しばらく陽を浴びて帰ろう。
腰掛けて池を見ていると、ほとりに生えているがまの間を糸トンボが飛んでいる。ここで見るのは初めてだ。糸トンボなど子供のころに見ただけで、大人になってからは見たこともない。
アメンボが水面を走っている。
いいもんだ。
眠くなってきた。
桜の枝の杖を両手で抱えて、居眠りしていると、手のところでもぞもぞする。
右手をどけてみる。枝の幹にいくつかの穴があいていて、白いきときと虫の顔がのぞいている。白いまあるい顔に、芥子粒のようなちいちゃな目が僕を見ていた。
こいつら大きくなったらなにになるのだろう。蠅か蛾かカミキリムシか、ともかく思いつくものを想像していると、一匹が枝からおちて、土の上を這って、草の中にに消えていった。
また、きときと虫が顔を出した。次から次へと蛆虫たちは出てきて土の上に落ち、とうとう穴からみんなでてしまった。
水辺に赤い糸トンボが飛んできた。赤い糸トンボ!。珍しいじゃないか。
新発見かもしれない。枝を杖にして立ち上がると、池の畔にいって、枝を支えにして、水の上をのぞき込んだ。
ぼき、と言う音がした。あ、自分の骨が折れたのか。と思ったとたん。もんどりうって、僕は水の中に落ちた。
やっぱり眠かった。そのまま寝てしまった。
水深は六十センチメートルだ。
それで、僕は死んだようだ。
池の上に浮かんで、水辺の赤い糸トンボを見ている。池の上には、ちょっと前に折れた樫でできたドイツ製の杖が宙に浮かんでいる。
僕はなんだろう。あ、これから黄泉に行くのか。その前は何だ。幽霊か。そうか、生涯唯一たよりにした杖が折れてしまったので、黄泉の国にいけないわけか。だけどなぜ折れた杖が浮かんでいるんだ。そうか、こいつも杖の幽霊か。
天然は幽霊になりやすいのだろうか。
僕は折れたドイツ製の杖を手にとった。そのとたん杖はまっすぐになった。僕はその杖にまたがった。
杖はすーっと、空を飛んで、我が家についた。そのまま、寝室に行った。
かみさんが寝ている。折れた桜の木の枝も一緒に寝ている。
長男と長女が下の階で話をしている。
「お母さん、ケアーハウスの方がよくない」
「そのほうがいいな、もう102歳だものな」
「お父さん死んで何年になる」
「もう十年だよ」
ああそうだ、家内は俺より六つ上だった。
「あの桜の木の枝をお父さんだと思っているようだわね」
「ぼけたけど、一人暮らしできるんだから、たいしたもんだ」
「お母さんも天然だったわね、天然ってかわいいのよ、女ばかりじゃないのよ、男もそうよなんていって、桜の枝を離さないんだから」
「おやじも、桜の枝もお母さんが拾ったんだから」
「私もかわいいかしら」
幽霊の僕は幽霊の杖をついてうなずいた。
俺の血が入っているからな
そろそろ黄泉に行くことにしよう。かみさんに見つかると、ついてきそうだからな。
天然


