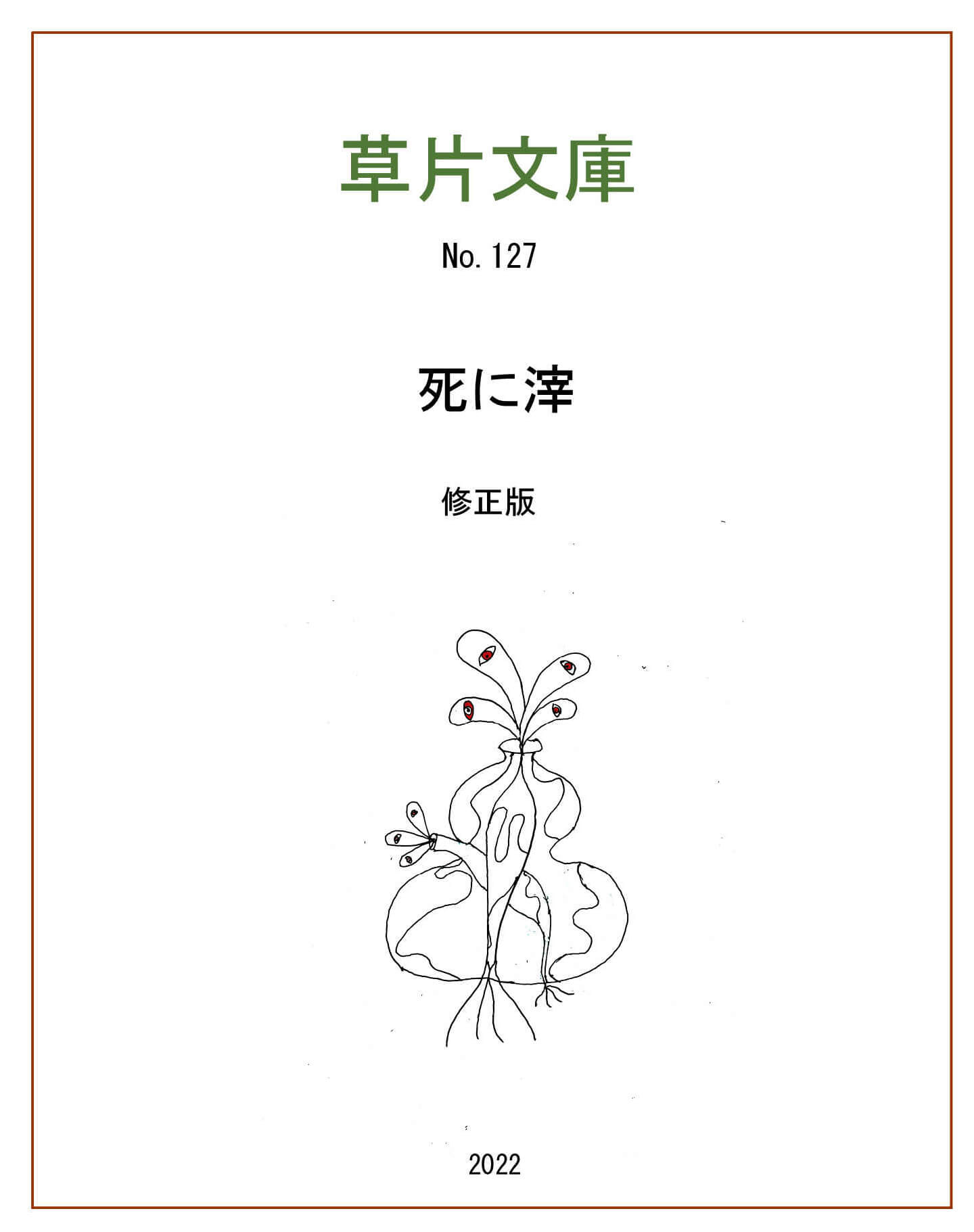
死に滓(かす)
幻想小説です。縦書きでお読みください。
田園調布の広い敷地をもつ昔ながらの家の中。
老人が静かに息を細く長く吐き出す。ため息でもあるようだが、ほっと一息ついたときのようでもある。そのあと、その老人は息を吸うことがなかった。
91年の生涯を大きくなった孫も含めすべての家族の前で閉じた。
私もこんなに静かにしねるかね、89才になった老妻は、老人の脇で話しかけるように死顔を見た。
八畳の客間の布団の上に老人は寝かされている。
呼ばれたかかりつけの医者が死を確認し、あとで死亡診断書をとりにくるようにとつげ帰った。
ほどなく、家族はそれぞれ自分の思いに従って行動をはじめた。
しばらくしてから、玄関の呼び鈴が鳴った。鈴は昔ながらの音を響かせて誰か来たことを知らせる。長男の嫁が玄関にでた。黒い礼服にぴしっと身を包んだ、白い手袋をした初老の男がたっていた。
「お電話をいただきました、葬儀社のものですが」
長男の妻は夫がどのようなときにしろ、行動の早い人であることを知っていたことから、不思議に思わず、ごくろうさまですと部屋に上げた。
その男は畳の上の布団に寝かされているご遺体の前に座ると、もってきた白い布を顔にかけ、やはりもってきた線香に火をつける。
ご遺体に向かって深々とお辞儀をしながら、鞄の中の桐の箱から透明の数珠をとりだし、ご遺体に手を合わせる。線香の煙が部屋に漂うと、親族のだれからからすすり泣きがおきる。
長々と手を合わせていた男は、振り向き、喪主とおぼしき人に向かって「それではむこうでこれからのことをお話ししたいと思いますので」と、数珠を小さな桐箱にしまうと、たちあがる。
これからしなければいけない、公的な届けでなどのことを話し、坊さまの手配などを聞き、通夜のこと、さまざまな棺と祭壇の写真を見せ、また葬儀のコースの選択を促し、相手からの質問に親切丁寧に答え、教える。
男は電話を葬儀会社にかけ、要求された棺と祭壇を運ぶように指示する。
男にとって、桐の箱が相当大事なようだ。彼は近くの道に止めておいた車にもどると、運転席の小物入れの中に桐の箱をいれた。
ただそれだけのために、その家を離れたのだ。
男は家の玄関に忌中の紙を貼り、再び家に上がった。しばらくすると、会社の車が到着し、二人の従業員がおりてくると、棺やら、葬儀のための一式をおろし、寝ている遺体の前で、男と同じように線香をたむけたあと、祭壇の組み立てをはじめた。
そのとき、すでに男はその場にいなかった。
男の運転する車が谷中の一つの墓地のお堂の前に止まった。
八角堂はよほど古いものであろう、壁の板の間に砂がたまり、壁の漆喰はひび割れている。だが太い大きな柱は、作られたときにはさぞ立派なものだっただろうと想像させてくれる。
桐箱を持って車を降りた男は、入り口の重そうな扉を軽々と引いた。扉を開けると、正面に誰の作だかわからないが、菩薩像が柔和なほほえみをうかべている。堂の中にはただそれだけしかないが、蜘蛛の巣が縦横無尽に張っていて、何かがいっぱい詰まっているように見える。はたして、こんなに巣をつくって、小虫がそんなにはいってくるものだろうか。
男は中にはいると、ぎしぎしと靴音をたてて、菩薩の後ろに行った。前からは隠れて見えないが、下に降りる階段の入り口がある。男は蜘蛛の巣をうまくよけ、壊さないように下におりた。
降り立ったところは広々とした地下の空間だった。かび臭い匂いと、それに混じって漂っているのは、血が発酵した墓の匂いである。
目が慣れてくると、中は地中に掘られた土と石で作られた空間であることがわかってくる。壁には石が積まれ、床は土のまま、木の根が縦横無尽に絡み合い天井をつくっている。ここでも至る所に蜘蛛の巣がある。どの蜘蛛の巣もきれいで、虫がかかったあとがない。
外にでるとわかるが。墓場の真ん中に一本の古い棗の木が植わっている。幹はさほど太くはないが、空高く育ち、毎年、沢山の実をつるす。そんな一本の木が墓場の下に空洞を作っているとは誰も想像ができないだろう。地衣類のはびこった墓石の裏を見ると、書かれている文字が崩れ読めない。かろうじて慶長という漢字がみえる。六百年も前のものなのだろうか。
男はほとんど明かりのないところを真ん中まで進んだ。そこには、首の高さまであろうかという大きな壷がおいてあった。
男の足がするすると伸びると、今日のは青いと、独り言を言いながら、壷の上にかぶせてあった木の蓋をとった。
いきなり、地下室に明るすぎるほどの光が満ちた。
壷の中から光がほとばしり出ている。
男が壷の中を見ていると、光は次第におさまり、壷の中にはどんよりと濃い緑色の液体の表面が波打っているのが見えるようになった。
「いらぬものは出たな」
男は独り言を言った。光のことを言ったようだ。
今度は液体を見て、
「うむ、良い具合だの」
そう言ってうなずくと、もってきた桐の箱から数珠をとりだし、端の青みがかった石を一つ取り外し、壷の中にぽとりと沈めた。
緑色の液体が渦巻き、どす赤黒い血の固まりのように変化したところで、男は壷に木の蓋をした。
また、暗闇が訪れた。男の足はもとにもどると、階段を上がり、八角堂の菩薩像の前にたたずんだ。
「渋谷にまいります」
こうべをたれて、男は八角堂をでた。男ののった車は渋谷に向かって走り去った。
夜中の1時。
渋谷のホテルの立ち並ぶ路地。そこには入らず、車は有料駐車場に入れた。
男は桐の箱をもつと一軒のホテルにはいっていった。三階の二号室。エレベーターにのり、躊躇することなく二号室にはいった。
乱れたダブルベッドには、うつ伏せに倒れた女がいた。まだ下着のままだ。首にはバスローブの紐がきつくまかれたままだ。体はまだ暖かい。
男は部屋にはいると「25年の死に滓か、小ちゃな滓だ、この世に未練がある滓は質がよくない」
などと独り言をいって、桐の箱をとりだした。
桐の中の数珠を手にすると、女の近くに立って拝んだ。なんと黄色っぽい死に滓だ、とかつぶやいている。
数珠を箱の中にいれると蓋をして、
「殺したやつのところにもいかなきゃな」
と、2号室を出た。
男は、車にもどるとエンジンをかけ目白にむかった。
「目白のマンションEMUか、なんだこのEMUってのは」と毒づきながら車を走らせ、こぢんまりとした目立たないマンションの脇にとめた。
男は5階の3号室の扉を開けた。鍵がかかっていたはずなのだが、男の指が取っ手に触れると、かちっと音がして鍵がはずれる。そういえば、あのアベック用の渋谷のホテルでもそうだった。
部屋の中はきれいにかたづいていた。
浴室をのぞくと、男が天井からつるされた綱に首をからませてぶらさがっていた。
「ここの死に滓もまだ未成熟だな、30年か、同じ黄色か」
男は数珠を取り出すと、それを高く掲げて、目をつむった。
浴室から部屋にもどり、テーブルの上の紙に目をやった。
「殺すつもりはなかっただと、こんなこと書くためにもどったのか、その場で死んじまえば、二人分の死に滓がいっぺんにとれて楽だったのによ」
男は部屋から出ると、車で谷中の墓地にもどった。
先ほどと同じように、八角堂の菩薩の後ろの階段をおり、蓋をはずして、光を放つ大きな壷の中を覗き込んだ。光が消え緑の表面が落ち着くと、数珠を二つはずして放り込んだ。緑色の液体が赤黒くうずまくと、だんだん静まっていった。
男は菩薩に挨拶すると、八角堂をでて、となりの墓守の家の玄関をあけた。
「今日の仕事はおわった」
部屋にはいった男のそばに寄ってきたアシダカクモに言った。
「お役目ごくろうさんだね」
アシダカグモは男のズボンの裾にはいると、足を上り、股間をまたぎ、胸の真ん中にべたっとはりついた。
男は着ているものを脱ぐと、胸の上の蜘蛛の目をみながら風呂場にいった。
アシダカグモを胸につけたまま湯船につかった。湯の中でアシダカグモの体が膨らみ、大きな蜘蛛となり、水面に顔をだすと女に変わった。
男はそのまま女とともに湯船にしずむと静かに眠りについた。浴槽の底には水蜘蛛が作った巣の中で、アシダカグモが水蜘蛛と抱き合っている。
男にとって、一日というリズムはない、その日の仕事は男の気分で決まる。
その日、男の車は中央高速道路を走っていた。河口湖の案内板が見えたところで、砂煙が上がっている。みると一台の車が大破している。さらにもう一台ひっくり返っている。
男は路肩に車を止め、桐箱から数珠を取り出した。ひっくり返っている車には気を失った初老の女性が運転席で逆さまになっている。
男は携帯で110番をした。すぐに、ぐちゃぐちゃに壊れた高級車に近寄ると、数珠を高く持ち上げた。四人の若者の体が押しつぶされている。轍を見ると、女性の運転していた軽自動車を猛スピードで追い越して、そのまま路肩に衝突した。若者の未熟な運転がそうさせた。その後ろから軽自動車がぐちゃぐちゃになった超高級車にぶつかり、横転した。そんなところだろう。
「四人の死に滓か」
馬鹿な色だ。四つあわせても灰色にしかならない死に滓か。親父の何千万もする車をもちだしてぶち壊しか。
男は数珠を桐箱にしまうと車に戻り、再び運転をはじめた。これで四つの数珠を使った。松本の病院で一つ必要だ。そのあとは、南アルプスで一つ使う予定だ。
松本に着くと男は老人ホームによった。
今、百になるおばあさんが息を引き取ったところだ。背広をきた男は花束を持って、おばあさんの寝かされている寝台にちかよった。ベッドの上に花束をおいた。
赤い死に滓が部屋の中で漂っている。すぐにでも天井からでていくところだった。最後は老人ホームだが、とても充実した生涯だったようだ。
男は数珠を持って拝むと、すぐに部屋から出た。
「親戚の方ですか」
施設にはいるとき、入り口で看護師が不思議そうな顔をした。おばあさんに身寄りはないときかされていたからだ。
「いえ、ボランティア団体から派遣されました」
男は金一封を看護師に渡した。
「そうでしたか」
看護師は男の後ろ姿を見送った。
男は車に乗ると南アルプスにむかった。
運転する男の格好は、いつ着替えたのか、ベテラン登山者のそのものであった。
男は有名な山の麓に車を止めると登山口からのぼりはじめた。男の歩きぶりは、山道を歩く人の様子ではない。朝、ビルの建ち並ぶ東京のオフィス街を、自分の机に向かって急ぐ通勤者の歩き方だ。せっせと、ただ目的の場所だけを頭に描いて、周りをなにも見ていない。登山をする人なら、山々の様子を楽しみながら上るだろうに。男の歩き方といったら、まるですべっている。足が地に着いていない。実は誰もみていないと、いつもこうだ。
空中だって飛べるだろうに。人の眼があるようなところではそうしない。東京からここまでだって、空中を飛んでくればあっという間だ。しかし、空中を見上げる人間は必ずどこかにいる。夜中だってそうだ。迂闊に空中に浮かぶことはできない。大昔から、死に滓集めの人間は、ついつい空を飛んでしまった。それをちらっとでも見た人間は、神が降りてくる、UFOが飛んでいた。と言いふらす。空中を飛びたくなるのだが、男は自分をいましめ、車をつかっていた。
日本では年に百万人と死んでいく。三日に一人以上だ。その死に滓を漏れなく集めることは不可能だが、その昔からそれに携わる生き物は墓地の数だけいる。墓地は数え方にもよるが80万もあろうか。それだけいるわけだ。小さな墓地であっても、地下には必ず、死に滓をいれる壷があり、死に滓管理人としての生き物がいる。そこで集めた死に滓を発酵させる。
死に滓の管理人、地球上に最初に生まれた人間は一人である。とある雌猿の腹から生まれた。その人間が死ぬとき、死に滓管理人が生まれた。地球上の最初の一人の人間が死んで、死に滓がただよったことから、それを管理する生き物が選ばれた。蜘蛛である。
猿から生まれた最初の人間は女だった。その後、男の猿がその女に子供を産ませた。生まれてきたのは類人猿だった。類人猿の死に滓はでるとすぐ消滅する。集める必要はない。類人猿のときには死に滓管理人はいなかった。管理人の仕事は、類人猿がホモサピエンスに進化したときに始まった。
その間に、死に滓管理人だった蜘蛛は、いろいろな種類に進化し、今の水蜘蛛になってしまった。それに、アシダカグモが手助けの役割をになうようになった。死に滓管理人の蜘蛛はたくさんいるにしても、とてもすべての死に滓を集めることはできない。どの死に滓を集めるか、死に滓管理人にまかされている。
死ぬと、心名残、いい思い出、そんなものが人の死体からとびでる。それは短い間だが、死体の周りに浮遊し、管理人がいないと、宇宙の彼方にとんでいく。そこに死に滓を吸収するホールが存在する。
この男は、身辺から偏りがないように死に滓を集めている。なかなか目のいい管理人ではある。
岩山の下に落ちた男の死体があった。落ちたばかりである。ご来光を拝んで下山する途中に、迂闊にも小石に足をとられ、三百メートル下に落ちた。高校生のころからの山登りの趣味だ。勤め人になってからも、休みを利用して山を登っていた。ずいぶん慎重な人間で、危ないところには行かない。それが、たった一つの道に落ちていた小石が登山靴の底でちょっと動いた。それでバランスを崩しおちたのだ。
男の死体からでた死に滓はまだ近くに漂っていた。山の空気を吸いたいらしい。緑色だな。男はそう思いながら、数珠を手に掛け、男に向かってあわせた。
趣味に埋もれて死ぬのは人間のもっとも贅沢な死に方かもしれない。死に滓集めの男は、俺には人間のような趣味はない。死に滓管理人の遺伝子を持った水蜘蛛は、遺伝子の命ずるままに動くしかない。虫の行動は遺伝子で規定されている。決まった行動しかとれない昆虫は、大きな環境変化があると絶滅する。
趣味を持つと言うことはどういうことなのか。死に滓管理人の水蜘蛛にはわからないことであった。
男は山を下りると、車で東京に向かった。
八角堂の地下で、六個の数珠を壷の中に入れた。
壷の中の死に滓は九分目ほどまでたまりどろどろと渦巻いている。
ずいぶん発酵がつよいな。
死に滓管理人は死に滓の匂いが赤んぼうの匂いに近づいてきたことを感じた。
蓋を閉じると、階段をあがり、蜘蛛の巣をひっかけないようにして、菩薩の前にたたずんだ。
「赤ん坊の匂いがするようになりましたでございます」
大仰な言い方で、菩薩に向かって手を合わせると、深くお辞儀をした。
「しばらく、お休みさせていただきます」
そう言って六角堂をでた。
墓の脇の事務所兼自宅にもどると、もんぺ姿のショートカットの女性が、日に焼けた顔にえくぼを寄せて、「おまえさん、おかえり」と玄関にでむかえた。
「やすみをとるんだろ」
「ああ」
男は、女性の格好をちらっとみると、「なんでえ、もんぺなんて、よせや、せめて、モガになれ」
なんぞというのだが、そんな会話、はたで聞いていてわかる人なんぞいるわけがない。
「せめて、昭和のバブルのころにしておくれよ」
「ああ、それでもいいぜ」
男がいうと、女は白い綿のティーシャツと黒い短いスカートの姿になった。白い太股がまぶしい。
「極端だな、おまえは」
「ほほ、モガとミニスカートとどっちがいい」
苦虫をかんだような顔をしていた男も、とうとう笑いだして、「おまえになんな」
というと、女はアシダカグモになった。
それじゃ、俺もと、男は大きな水蜘になり、女と連れ立って、風呂場にいった。
「しばらく、どこかにいくか」
「また、水の中かい」
「おまえの好きな武家の屋敷でもいいぜ、おまえは武家屋敷に似合うからな」
そういいながら、水蜘蛛とタカアシグモは抱き合いながら、湯殿に沈んでいった。
明くる日、墓守の家の玄関をたたくものがいた。
「おまえさん、いらっしたようだよ」
和服の格好の墓守の奥さんが旦那に声をかけた。
「そうだな」
作務衣をきた死に滓管理人であり、墓守は玄関を開けにいった。
「いらっしゃい」
外で待っていたのは、戸立グモと草グモだった。
「お世話になります」
戸立グモは玄関にはいると産婦人科医になり、草グモは産婆、助産婦になった。
「よろしくおねがいします」
「いつもごくろうさまです、それじゃごいっしょに」
墓守とその女房は六角堂に二人をつれていった。
「いつもきれいにしていらっしゃる」
二人は六角堂の中の蜘蛛の巣だらけの様子を見てほほえんだ。
そう言えば、ここの蜘蛛の巣はどれもきれいな六角形をしていて破れていない。
階段を下りて地下にはいると、死に滓管理の男は大きな壷の蓋をとった。
壷からでた光が洞窟の中に充満した。やがて光は落ち着き、壷の中の解けて混ざった死に滓は透けて無色となった。
二人の来客は再び戸立グモと草グモの姿になり壷の表面をのぼっていった。縁で立ちがった二匹の蜘蛛は壷の中に飛び込んだ。なだらかだった表面に二匹の蜘蛛が浮かんだ。
蜘蛛は大きく口を開け、熱くどろどろした死に滓を吸い込んだ。
壷いっぱいにあった死に滓は二匹の腹に収まってしまった。
墓守の二人は水蜘蛛とタカアシグモに姿を変え、壷の下でまっていた。
草グモと戸立グモがおりてきた。
「今回の死に滓は透明度が高いですな、いい人生を送る薬味になるものですな」
「お役目ご苦労さまです」
「また、五十年後にまいります、お二人はどこぞへ休養にまいられますかな」
「はい、諏訪湖のほとりにでもまいります」
「それはいい、それでは」
草グモと戸立グモは八角堂からでていった。
発酵させた死に滓は、生まれてくる赤子の産湯に一滴たらされる。死に滓を集める管理人が50年間の休みをもらっている間におこなわれる。
戦争を挟んで50年に集められた発酵した死に滓は、恨み、悲しみ、妬み、などの混入がおおく、それを与えられた子供は少し不幸でもある。じじつ、日本ではその時期に経済発展こそ大きなものであったが、人間としての美徳の向上はかならずしもよくなかった。
江戸時代をみてみよう。300年の歴史があるが、最初の50年には戦国時代のものも混じり、発酵した死に滓は必ずしも質のよいものではなかった。しかし、その後、50年間隔で集められた死に滓の質は向上し、人間としての文化が花開いたわけである。
質のよい発酵した死に滓のはいった産湯に浸かったこどもは、国をとませる財産となる。
谷中の死に滓管理人に集められたものは、かなり質のよいものであった。それをもらいにきた二匹の蜘蛛は、神代の時代よりこの管理人とタッグをくんでいた。
二匹は背広姿の男とスーツ姿の女性になると、山手線に乗って渋谷で降りた。代官山に行くと、一つのビルの三階にいった。エレベーターをでると、蜘蛛に変身し、産婦人科の受付から壁を伝わって診察室に入り、天井の片隅に居座った。
このビルのあったところには、昭和の中頃まで、南京じたみの西欧風建物が建っていた。やはり産婦人科である。今のビルの産婦人科の院長のおじいさんがやっていた医院だった。そのころ、戸立グモは建物の土台のところに巣を作っていたし、草グモは庭の草原に住んでいた。庭のない今は、やむなくはや診察室の天井がすみかだ。
患者がはいってきた。
診察をした医師がいう。
「順調ですね、お茶の水の病院に紹介状を書きましょう、来月が産み月ですから、そちらにかよってください」
二匹の蜘蛛は、カルテに書かれている患者の住所を頭の中に記憶する。よなよな、患者の家を回り、妊婦の様子を見る。出産のために入院するときにはついていき、子供が産まれ、看護師が産湯につける前に、湯の中に一滴、管理人が発酵させた死に滓をたらす。それにより子どもの人生が芳醇になる。それがその個人の幸せにつながるかどうかはわからない、ただ社会に大きな力を及ぼすようにはなるだろう。大政治家になるか、著名な博士になるか、世界に知られる小説を書くか、はたまた、大強盗になるか、殺人鬼になるかそれはわからない。ただ、世に知られる人間になる。
「明日いくとこは、珍しいことに、妊婦が自宅で子どもを産むのよ」
草グモが戸立グモにいう。
「うん、そうだよな、駒込の一軒家だな」
「少しはやくいって、庭の草原で月見でもしませんこと」
「そうするか」
二匹はその妊婦の家に行った。
古い家で、必ずしもきれいとはいえないが、庭は草花がよく手入れをされており、今は桔梗がさかりだった。
家の中では、大きなおなかを抱えた独身女性が一人、本を片手に出産の準備をしている。両親はこの家を残して死んだ。お腹の中のこどもの父親は外国に帰った。一人で産んでやる、一人で育ててやる。女性の気迫が伝わってくる。
医者からは大病院への紹介状をもらった。しかし、病院にはいかない、自分で自分の子供をとりあげるつもりでいた。女性はからだに対する知識が豊富だとは思えない。戸立グモと草グモはいざとなったら、手助けに出て行く。これも一つの役目である。
「今日あたりいきそうだな」
「そうね」
二匹の蜘蛛は、駒込の産婦の家にはやめにいった。部屋の中に入り込むと、女性の振る舞いを天井の隅から見ていた。
「冷や汗をかいているわね」
「怖いんだ、病院に行けばいいものを、金だってあるようじゃないか」
「男や世の中に復習するつもりなのよ」
「産まれてくる子供になにかあったら、子供がかわいそうじゃないか」
「そうね、だけど、この女性もひどい目に遭ってきたのじゃないかしら」
「確かしにな、だが、心に余裕のある人ならこんな無茶はしないさね」
「それはそうね、どうしようか」
「うまくでないようなら、我々が補助するしかないだろう」
「久しぶりに人間の形をして、人間の子供をとりあげるのね」
「そうなりそうだな」
女性は布団の上で、陣痛をこらえていた。産まれた赤子を包むバスタオルが何枚か、自分の尻の下にも何枚ものバスタオルが敷かれている。
脇には湯が木のたらいに入れてある。
気丈な女性だな。二匹の蜘蛛は天井から様子をみている。まだ陣痛の間隔が生まれるタイミングではない。だが、妊婦の精神状態でどのように変わるかわからない。
かなりの痛みがきているようだが、なかなか我慢強い。少しばかり声が漏れる。目が白目がちになる。
「ちょっとあぶないかもしれないな」
天上にいた戸立グモが草グモくに下りることを促した。
「おまえの死に滓をいれておいておくれ」
戸立グモが草グモに促すと、草グモは用意されていた産湯の中に尻をつけた。
それにつかると、体中で味を感じるようになり、人生に味が出てくる。
「あ、ちょっと多めにはいったわ」
「いいさ、それも生まれる子の味になる」
二匹の蜘蛛は医師と看護婦になった。女の目には見えていないようだ。もうすぐ気を失う。
看護師が「でーるでるでるでる」と低い声で耳元にささやく。女がいきむ。
看護師が携帯で救急車を呼ぶ。
医師がゴム手袋をはめた。
「もう少しだ」
女は最後の我慢の時を終えると目を閉じた。
「男の子だよ」
戸立グモの医師は、赤子を持ち上げると尻をぶった。赤子はおぎゃああと大きな声を上げた。
草蜘の看護師が受け取ると、産湯につけた。赤子が片目を開けた。
「元気な子だこと」
看護師は産湯の中から赤子を引き上げると、用意されてあったバスタオルにくるんだ。
その後、母親の胸の上に赤子をおいた。赤子は母親の乳首をさぐりあて吸いついた。
救急車の音が聞こえる。近くになり、音が止まると、玄関の呼び鈴が押された。救急隊員は鍵のかかっていない玄関を開けた。
「失礼しますよ」
返事がないので、救急隊員は部屋の中にはいってきた。
「子供がもう産まれてます、自分で処理したようです、母親は気を失っています」
隊員は親子をチェックして、もう一人の隊員に伝えた。
担架が運ばれ、気がもうろうとしている母親に、「赤ちゃん元気ですよ、しっかりしてください」と声をかけた。母親は赤子とともに救急車に運ばれた。
すでに蜘蛛の姿に戻った産科医と看護師は天井の隅で様子を眺めていた。
「そろそろ帰ろうか」
戸立グモが草グモに言ってその家から出た。
「あの男の子なにになるのかしら」
「若い母親があれだけ根性あるのだから、世直し頭として育っていくだろうね、明治維新のころの骨のある男にね」
「そうすれば、日本もよくなるわね」
また人間の姿になった蜘蛛たちは腕を組んで、月明かりの道をすべるように、自分の住処である、駒込の産婦人科のあるビルへともどっていく。
ビルの入り口脇の植え込みの中に入ると、椿の木の根本の穴の中にはいっていった。
穴の中で、二匹は二人になると、抱き合って土のベッドの上に転がって眠った。
明日、荻窪の妊婦とともにお茶の水の大学病院に行く予定である。
これから50年、どのような子供たちが育つのだろうか。今までの五十年間に集められた発酵した死に滓によって味付けされた子供たちである。
死に滓(かす)


