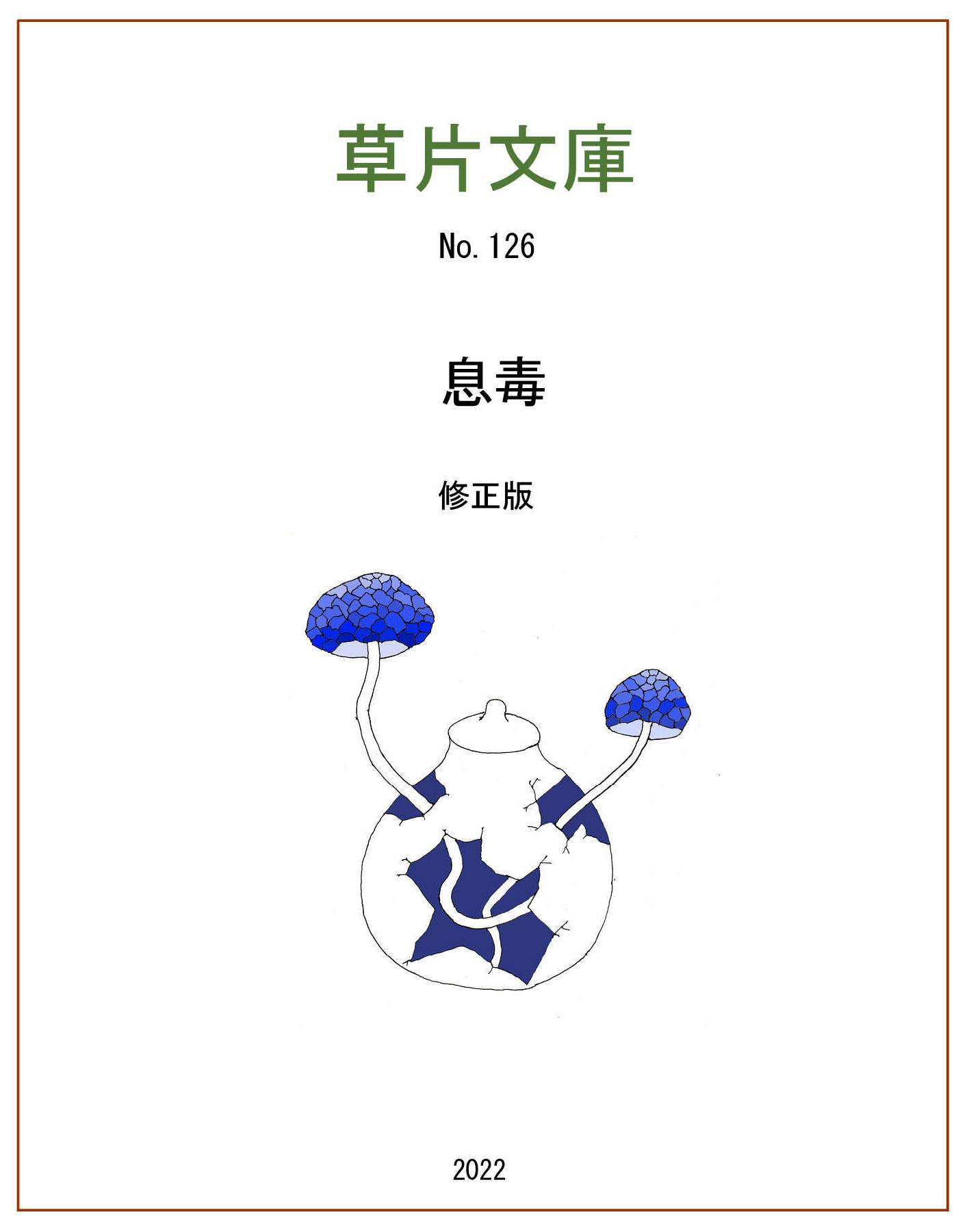
息毒
探偵小説です
寄手(よりた)憲一郎は京都の大学の法科大学院卒業時に司法試験に合格した。その後、埼玉の司法研修所に司法習復生として採用された。憲一郎の実家は東京下町で精密機械工場をいとなんでいる。埼玉の研修所は少し遠いが通えないことはない。父親のすすめもあって、実家から通った。
司法習復生は、1年間に基礎と実地の勉強をし、修了試験が通らないと、裁判官、検事、弁護士など法曹界にはいることができない。憲一朗は3週間の基礎プログラム、実務実習、集合研修をうけ、裁判所で実際の訓練をし、最後の試験にも問題なく合格した。
憲一朗がストレートで司法試験に受かっていることもあり、教官からは判事になることを進められたが、弁護士になる道を選んだ。人を裁くより、人を庇護する立場になりたいと思っていたからだ。
街弁ということばがある。町の弁護士で、何でも取り扱い、住んでいる住人の悩み事を解決するという立場である。町医者のようなものだ。憲一郎はそういう仕事をしたかった。
そのためには、はじめどこかの事務所で数多くの経験をつむ必要がある。東京弁護司会に登録をし、家から通える中堅どころの弁護士事務所に入ることになった。刑事事件も扱う大きな事務所である。八十名近くの弁護士がいて、地方にもいくつかの支所をもっている。
その事務所に入って二年間、先輩弁護士について、刑事事件から医療過誤、離婚から会社の倒産処理などを経験した。事務所の忘年会のときだったかに、将来街弁になりたいようなことを話したら、その次の四月に、手の足りなくなった奈良の支店にまわされた。彼に多くの経験を積ませようという配慮だろうと、憲一郎は喜んで転勤に応じた。喜んだ理由はもう一つある。奈良は大学生だったときに住んでいたところである。
奈良の支店では、十人の弁護士が働いていた。刑事事件の担当者は二人いたが、残りは個人からの依頼を受ける街弁に近い仕事をしていた。その地域としては支所といえど、かなり大きな弁護士事務所である。会社関係が得意な人、医療関係の人、離婚訴訟専門、いろいろな人がいた、憲一朗はどれでもいいと考えていたが、医療関係の依頼が多かったことから医療の担当になった。
病院での家族の死が納得できなかったり、産まれてきた子供の病気が医師の不注意だと訴えたりいろいろあった。確かに病院の不注意もあるが、そうばかりとは言い切れないところもある。しかし依頼人の申し出にそって、満足な解決をしなければならない。特に医療関係だと、訴えた側、訴えられた側、両者を納得させる解決案を提案しなければならない。人生経験の浅い憲一朗は先輩の意見を聞きながら苦労してなんとかこなしていった。
奈良の弁護士事務所にはいり五年がすぎた頃の話である。憲一郎がそろそろ東京に戻り、自立の道をと考えて、情報を集めていたときだった。とある民間病院から依頼があり、憲一郎がその病院に行くことになった。
入院している九十になる女性が点滴のあとに死亡したことから、患者の家族から、医療ミスとして訴えられたということだった。
院長、主治医、病棟主任、看護長、その場に立ち会った看護婦に話を聞いた。主治医の話だと、すでに癌がからだにまわっていて、患者が痛いためうめくようになると、点滴で痛み止めの薬を投与していたということである。記録を見ても、時間をおいて薬を投与しており、投与量も多いわけではなく、間違えようのない仕組みのもとで行われていたことがわかった。
「なかなか納得してくださらなくて、まだ流動食は口からとれる状態でしたので、胃ろうは、口からとれなくなってからと申し上げておったのですが、胃ろうにしていたらもっと長生きしたとか、点滴の痛み止めをもっと早く投与すべきだったとか言われています。
息子さん夫婦と奥さんは納得してくださり、もう火葬もすでにすませた、ということです。お孫さんが納得されないようで訴えられました、第三者に解剖検査をお願いできない状態です。当時担当の看護師はとても優秀な人で、どの患者さんにも慕われていました」
二十九才の浅井鈴美看護師は俯いたままだ。
相手方の弁護士からの書類を見ると、訴えは確かに孫さんの名前だった。
「あいては京都の個人事務所の弁護士で、医療関係でこういう件をやっている人です、医療関係者ではよく知られていて、ほどほどの金額で手を打つ人です、一度向こうの意向を聞いていただけませんか、こういうことに時間をとられていると、病院の医療が手薄になります、その方が患者さんにはよくない、担当してい浅井君は気にしすぎて、いまカウンセリングをうけていますよ、裁判になったら負けませんけど、そういう状態を続けるのはよくないので」
看護師が顔を上げた。かわいらしい顔をしている。「お願いします」と頭をさげた。
「そうですね、向こうの弁護士に会って、様子を聞いてみましょう」
憲一郎は患者側の弁護士に連絡をした。向こうも会いたいということで、憲一朗が京都の事務所をたずねた。一人でやっている町の弁護士だった。
「どうも、こちらから行かなければいけないのに、来ていただいてすみません、なにせ一人でやっているものですから、できるだけ事務所を離れたくないもんで、お座りださい」
予想とは違い低姿勢の人だ。六十近い弁護士である。
「いえ、訴えられた方が、出向いて当然です」
「依頼主は病院がわに落ち度があったと申しております、お分かりなっていると思いますが、依頼主は患者の奥さんや子どもではなく孫のかたです。お孫さんは胃ろうのことを問題にしていますが、胃ろうをつくらなかったということは、患者さんの子ども夫婦は、すなわち依頼主の両親は了解しています、依頼主はその場にいたわけではありません、胃ろうを作らなかったことに病院に落ち度はないでしょう、となると、点滴が死亡に関係しているかということです。点滴のタイミングと、投与の量に焦点がしぼられます、科学的な検証をしなければならないでしょう、裁判になると時間がかかります」
「そうですね、患者さんのお子さんや奥さんは担当の医師や看護師について、よくやってくれていた人だと言っていますね、すぐ火葬にされたので、解剖などはもうできないし」
「そうなんです、おっしゃるとおりです」
「訴訟を取り下げるお気持ちはないでしょうか」
それを聞いた弁護士は相好を崩した。
「示談にされたいのですか」
憲一郎はうなずいた。
「可能でしょうか」
と彼の方から聞いた。それは訴えられたほうから言う言葉だ。言いたい事を憲一郎は理解した。
「どの程度で手をうってくださるのでしょうか」
「150万ほどで、いや100万ほどでいいかと思います、依頼人は500万と言っていますが、いま寄手さんがおっしゃったようなこともありますから、私の方から納得させます、慰謝料として」
500万なら、着手料が5%として、25プラス5万、30万程度、報酬量はもし500万なら68万か、100万で手を打つとなると、妥協させるために10万と諸経費ほど弁護士事務所に払うことになるのか。ここの事務所の計算はわからないがそのようなものだろう。個人の事務所だから金額は自由になる。
「わかりました、病院の方にその話をもっていきまが、もし訴訟を取り下げていただき、その金額をお見舞い金として払うと言うことはできますでしょうか」
弁護士は憲一朗をみて、何も言わずに深くうなずいた。
「どうぞよろしいくお願いします」
そう言われて、憲一朗はそのまま奈良の病院に行き、病院長にその話をした。
「そうですね、あの弁護士はわからないところがありますから、うちはこういう経験はあまりないが、やり手で裁判に持ち込まれると、やっかいな人だということですよ」
「今回のことは、勝てないことがわかっているようです、慰謝料として、100万で手を打ってほしいと向こうが言っていました、孫の両親は胃ろうのことも了解していること、点滴のこともなにも問題にしていなかったこと、すぐに火葬に伏したことなど言ったところ、示談できないかということでした」
「100万ですか、少なくとも200から300万要求されるかと思いました。向こうの人はそれで大丈夫なのでしょうか」
「納得させるようなことをいっていました、訴訟を取り下げて、その金額を見舞金としてだすことはどうか、と話をしました、もしそういうかたちで、百万をわたせるのでしたら、そうしますが」
「それは、ありがたいことです、そうなれば、なによりも現場のものたちがほっとするでしょう、特に浅井君は気にやんでいましたからね、大喜びしますよ」
院長は周りの者たちに気を使う人だ。
「それでは、すぐにでも、あいての弁護士に連絡しておきます」
弁護士には電話でそのことを話し、今後のことを相談した。
この訴訟は取り下げられ、相手方の弁護士が、病院のほうに見舞金を取りにきた。代理人による見舞金の受け取り証をおいて帰ったということである。うちの弁護事務所は規定の弁護料を受け取り、院長から私にお礼にとホテルのレストランに食事に誘われた。
レストランは主治医と事務長それに浅井鈴美を始め数人の看護師と一緒に食事をしたが、みな晴れやかで、憲一郎は何よりもそれが嬉しかった。
憲一郎はその件を最後に、東京の下町で弁護士事務所を開いた。
弁護士になってはや八年もたつだろうか。奈良の事務所の五年間の経験は彼に自信をつけさせた。東京本社の仲のよかった先輩方に相談もし、後押しもあって決断をした。
実家の近くの地下鉄で一駅のところのビルに一室を借り、一人で仕事を始めた。
多い相談は計理に関してのものだった。憲一朗はあまり経験してこなかった分野である。そのことで、町工場を営んでいた父親と話をすることが多くなった。話しているうちに、我が家のお金のやりくりは大変だったのだなと、改めて父親の苦労を理解した。なんども倒産になりそうだったようだ。そう言うときの対処について相談したのだが、その話はずいぶん役に立った。親父も憲一朗と話せるのがうれしいようだった。工場はすでに、妹の主人が後をついでいて、順調にすすんでいる。妹は工場で働いていた男性と結婚した。彼は精密工として日本の大会で準優勝したまじめな男である。憲一郎は安心して自分の弁護士活動に専念できた。
お兄ちゃん、そろそろお嫁さんもらったら、と妹にも言われるようになった。憲一朗ももう三十半ばをすぎた。
そんなとき、母親が肺炎にかかり、行きつけの医者から紹介され都心の病院に入院した。憲一朗が見舞いにいくと、四人部屋に「寄手さん、検温です」と入ってきた看護師が、「あっ」と声を上げ、憲一郎に「あのときにはありがとうございました」と頭を下げた。
憲一郎はだれだろうと、彼女をよく見ると、奈良の最後の仕事で会った看護師だ。浅井鈴美という名を思い出した。
「この病院に勤務されたんですか」
「はい、もともと東京でしたし、母の具合が悪くなったものですから、二年前にうつりました」
憲一朗の母親に体温計を渡しながら言った。
母親はなぜかうれしそうに「おまえ、看護師さんと知り合いなのかい」
と聞いた。
「うん、奈良で担当した病院にいたんだ」
「とてもよくしてもらっているよ」
脇の下からとりだした体温計を浅井看護師にわたした。
「お世話になっています」
あらためて、憲一朗は頭をさげた。
「いえ、私こそ、あの時にはお世話になりました。私、やっと一人前になれたかとちょっと自信が出てきたときにあんなことがおきて、何か失敗したんじゃないか心配になって、とても落ち込んでいたのです、先生のおかげで元気になりました」
「あ、いや、病院にはなにも手落ちはなかったので、いい院長先生ですね」
「はい、あの院長先生は、病院内の隅々まで気を使われる人ですから」
「どうですか、東京の病院は」
「大きいですね、治療方法も最新のもので、勉強し直しました、田舎の私立病院とは大違いです、あそこも大きい病院だと思っていたのですけど」
と笑った。笑い顔もなかなかかわいらしい。
「お母様だったのですね、とてもよくなられているので、2ー3日で退院できると思います、ごゆっくり」
そういって病室をでていった。
「いい看護師さんだよ」
母親がまたいった。
実家に母親がもどってきたその日、憲一郎が仕事を終えて家に帰ると、最初に言った言葉が「憲一朗、見合いしないかい」だった。
「元気になってよかったな、いきなりなんだい」
「お見合いしなよ」
「そんな話どこからきたんだい」
「わたしがみつけたんだよ」
父親が「帰ってきたら、そのことばっかりいってるんだ」と笑った。
「どこのひと」
「あの看護婦さん」
浅井鈴美だ。
「お袋が勝手に決めてもだめだよ、もう相手がいるかもしれないじゃないか」
「いないよ、わたしゃ、みんな聞いたんだ、息子と見合いしないかってきいたら、先生さえその気なら私は喜んでだってさ、おまえのこと先生ってよんでさ、もう結婚されているのだと思ってたんだとさ、落ち着いていたからだと、まだちゃらちゃらぼうずなのにね」
と母親は笑った。勝手なことを言いやがって、と思いながらも憲一郎も笑った。
「病人にいやだとは言えないだろう、病気が悪くなると困るから」
「そんなことないよ、そういうときには、残念、私もう彼がいるんです、というもんだよ」
さすが年の功、お袋の方がぱっと言い返す。
自分はどうも人のことをきちんと読めない。そう言ういことからすると、あまり弁護士としてむいてはいないのかと思ったことがある。
大学の頃、珈琲を一緒に飲み、たまに一緒に映画を見て、くらいの女性友達はいた。司法試験の準備が大変とってもそのくらいの時間はある。その相手とは一度口づけをしたことがある。公園の暗がりだった。だが、その後その子は急に青白い顔になって、その場にしゃがみこんだ。貧血だろうか。救急車呼ぼうといったら、首を横に振って、「気持ち悪くなった、タクシーでかえる」と、立ち上がったのはいいが、すぐにでも倒れそうで、かかえてタクシーの拾えるところにいった。
「いっしょにいこうか」というと、「ひとりでいい」と一緒に乗るのを拒否され、気をつけてと送り出したことがある。それ以来、なぜか大学で彼女に会わなかった。スマホにも反応はなかった。その娘は文学部の学生だった。女性のことはよくわからない。それいらい、女性と付き合うようなことはしなかった。学生時代、バイト先の弁護士事務所の社長には、弁護士は遊ばないとだめだよといわれたりもしたが、憲一朗にはできなかった。
そろそろ親のいうこととでもきくか、と憲一郎は「かあさんがそういうなら、一度会ってってもいいよ」
と答えた。
「そうかい、そいじゃ、明後日病院にいく日だから、あの看護師さん探してみよう」
大乗気であった。
そして金曜日、事務所に母親から電話があった。
「次の月曜日、何時頃帰ってこれる」
ここのところ少しやっかいだが、大きな仕事をたのまれ、いろいろかけずりまわっている。たまたま次の月曜日は大丈夫だ。
「次の月曜日はおそらく六時には家に帰ることができるよ」
弁護士事務所は朝9時から5時までになっているが、依頼を受けたものの調査で、時間通りに帰ることができるのはそんなにない。日曜日は休みの日だが、日曜日しか調べることのできないこともある。
「そうかい、鈴美さん、改まったお見合いはしたくないと言っていたので、それじゃ、うちにきて、ウナギでもとろう、いったら、あ、それがいいです、私の分ははらいますだと、家族みんなで食べるんだけどいいですかといったら、もちろんですだと、いい娘だね」
どうもお袋の方が娘にしたいようだ。
その日ウナギを食べながら、家族のように座の中にとけ込んだ浅井鈴美は、憲一朗にも好ましく思え、父親や妹夫婦も喜んだ。
その後、二人で食事をして、結婚を前提につきあうことになり、憲一朗は鈴美の実家に出向いた。鈴美のうちは八王子で床屋を営んでおり、両親も大層喜んだ。
二人の希望で、大それた結婚式は行わず、ちょっと名の知れた店で、両家の顔合わせをおこなった。後は二人にまかせるということになった。お互い忙しいこともあり、結婚式のようなものはできる時にするとし、きりよく一月後の鈴美の誕生日に籍をいれることとなった。そのときに三日ほど休みがとれるということで憲一朗も仕事を入れないようにした。
病院と事務所のちょうど真ん中ほどにあるマンションを借りた。
鈴美の誕生日に初めて入居ということにもなる。
その日、二人、区役所に結婚届をだし、昼を食べて自分たちのマンションにいった。
「あわただしかったね」
部屋は多くの物が買った時のままになっている。新婚は片づけから始まった。
「うれしいわ、わたし」
鈴美は荷物をほどき始めた。
「ゆっくりでいいから、今日は外で食事しよう、僕は忙しいときは忙しいけど、依頼がないときは時間があいているから部屋の中はととのえるよ」
「うん、私も非番の日や、あいている時間があるからやるわ」
憲一朗はまだ鈴美にふれてもいない。鈴美を寝室に連れて行くと腰に手を回した。
「昼間よ」
「うん」
憲一朗がてれた。鈴美から憲一郎の口をもとめた。まだキスの一つもしていない。初めてである。軽くキスをすると、鈴美が「あっ」といって、ふらふらと、ベッドに腰掛けると、「おかしいわ、ごめんなさい、ちょっとまって」
そういうと、自分の荷物のなかから、小さな機械をとりだして指に挟んだ。
「おかしいわ」
またいった。「酸素の量が70まで下がっている」
憲一朗は「だいじょうぶなの」と指に挟んだ四角い機械を見た。
「なにこれ」
鈴美は少し調子がよくなってきた。
「オキシメーター、血液の中の酸素量をはかるのよ、家に一つあると便利なの、八王子の家には私が買ったからあるけど、先生の家にないでしょ、もう一つあるから今度持って行くわね、でもなぜこんなに低いのかしら、休みがあけたら、病院で調べてもらうわ、いつもは98前後よ、貧血かしら」
「働きすぎかな」
「もう大丈夫」
そう言って、そこで鈴美は憲一郎を受け入れた。
ただ終わった後、鈴美はかなりあらい息をしていた。
「肺炎でも起こしたのかしら」
「忙しかったから、急に休んで疲れがでたんだよ、ゆっくりしたらいい、なんだったら、明日病院に行ったらいいよ、僕も休みだからついていくよ」
「うん、そうします」
次の朝、憲一郎が眼を開けると、鈴美はもう起きていて、朝食を作っていた。
「元気になったの」
「ええ、はかったら98だったわ、普通の状態よ、病院は行かなくて大丈夫」
「緊張したのかな」
憲一郎が笑った。
その日は二人で横浜に遊びにでた。その夜、行為のあと鈴美はぐったりした。
「やっぱり65しかない」オキシメーターを見ている。
「朝になったら様子見て病院行くわ」
「そうだね」その晩はそのまま寝た。
朝、8時、憲一朗がとなりの鈴美の手を握ると元気に握り返してきた。憲一朗は鈴美をもとめた。鈴美がおうじたが、やはり行為の後は苦しそうだ。顔色が悪い。
「このまま、病院に行ってみる」
9時になろうとしている。
「うん、僕も行くよ」
二人は着替えるとタクシーで鈴美の勤める病院に向かった。
病院につくと、鈴美は自分の担当である呼吸器科病棟に行き、主任看護師に様子を話すと、当直開けの先生に見てもらうように計らってくれた。
診察室からでてきた鈴美の顔色はだいぶよくなっていたがまだ少し青白い。
「一酸化炭素中毒の可能性があるって、採血してくださってこれから結果がでるまで待っているの、よくなってきたから一人で帰れるから、憲一朗さん先に帰っていてもいいわよ、朝食まだだし」
「一酸化炭素中毒って、部屋でそんなものでていたのかな、」
「おかしいわね、火をつけたものはないし、一酸化炭素なんてでないわよね」
「血液検査の結果がでるのはいつになるのかな」
「一時間かかるけど」
「それじゃ、売店でサンドイッチでも食べてくるよ、君はたべなくていいのかい」
「私は結果を聞いてからにするわ」
憲一郎は病院の中にある売店でサンドイッチを買って食べ終わると、呼吸器病棟にもどった。
まだ20分ほど待たなければならない。
「血液検査ってなにを調べるの」
「血液の状態をみんな調べるの、赤血球の数、白血球の数、赤血球の酸素の取り込みなんか」
「もしおかしかったら入院するの」
「そんなにひどくないから、自然になおると思うわ、それより、今までこんな状態になったことないのよ」
「そうだね」
浅井さんと呼ばれて彼女は診察室にはいった。
すぐにでてくると、「私の血液は問題ないって、一時間もすると元にもどるでしょうですって、むしろ部屋の換気などを調べてくださいっていわれた」
「まあ、よかった」
二人はタクシーでマンションに戻った。
部屋にはいると憲一朗が鼻をひくつかせて、「ガスの臭いしないよね」と言ったら、鈴美が笑った。
「一酸化炭素は臭わないのよ、計測器を使わないとわからない」
「どうしたらいいだろうね、管理人に相談してみようか」
その後、管理人に様子を話したら、三日後にガスの専門家が来てくれることになった。しかし、ガス器具の状態は全く問題ないということだった。部屋の中も調べてくれたが特に異常は発見されなかった。
それから、鈴美はたまに気分が悪くなったが、すぐに回復し、問題なく仕事を続けていた。憲一郎もそれなりに忙しくなっていた。ただ憲一朗は夜の行為の後に鈴美の調子が悪くなることに気付いていおり、気になっていた。おそらく鈴美もわかっていたのだろう。行為に時間をかけないようになった。
そんなある日、事務所に警視庁から電話があった。話したいことがあるので警察官がマンションに来たいということだった。憲一郎は自分の仕事のことかと思ったのだが心当たりはない。あいている日時をおしえた。
指定した日時に、若そうな男性警察官が私服でやってきた。警察手帖を出して、二人に見せ、
「宙夜央と申します、捜査支援課の分析官をしております、ちょっとお聞きしたいことがありましてまいりました、寄手憲一郎先生ですか」
ずいぶん丁寧な話口調で自己紹介をした。礼儀正しい。
「はいそうです、どうぞこちらに」
来客用のソファーに案内すると、大きな鞄を開けて書類をテーブルの上に出した。
「どのようなことでしょう」
憲一郎には想像がつかない分だけ心配になった。
「一酸化炭素中毒のことなんですが」
そこまでいったところで、憲一朗が、
「家内のことですか」
と言った。それを聞いた宙夜が驚いて、
「奥様になにかあったのですか」と逆に聞き返した。
「ええ、結婚して三週間になりますが、結婚した当日、気分が悪くなり、病院に行ったら一酸化炭素中毒だろうと言われました、それで管理人に話してガスの状態など検査してもらいましたが、一酸化炭素のでるようなものはありませんでした」
「奥様は病院で治療をしたのですか」
「ええ、すぐ回復しまして、元気に看護師をやっております」
「それから同じようなことはおきませんでしたか」
「ええ、病院にいくほどじゃないのですが、たまにそうなります」
「今もですか」
「はあ、軽いものですけど」
「ところで、宙夜さんが、私のところにこられたのは、家内のことなのでしょうか」
「いえ、奥様のことは今知りました。実は私どもの捜査支援分析センター分室、第八研究室には、未解決な通常では考えられないような変わった事件のデータが集まります。それを解析して、その事件の解決だけではなく、同じ事件が起きないように注意するのはもちろんですが、新しく起きた事件の解決の糸口にします。
一酸化炭素中毒の事件が年間かなりの数あります。家庭におけるものは、だいたいが車の中や、室内の器具不完全燃焼、火事によるものが多く、あとは狭いところでの工事、たとえばトンネルだとかマンホールのなかですが、自殺者を含めて、年間1500人ほど亡くなっています。
データが沢山ある中で、原因がはっきりしているものをのぞいていくと、いくつか原因不明のものが残ります。それをさらに追求していくと、珍しい一酸化炭素中毒事件がわかります。たばこの吸いすぎで亡くなった人がいます。たばこは火をつけて乾燥したたばこの葉を燃やすわけですから、一酸化炭素もつくられます、それが原因でした。そういったものをのぞいていくと、さらにおかしなものが残ります。はっきりしているのは一酸化炭素中毒であるということだけで、どうして一酸化炭素を吸ったかということになります。
二つあります。一つは一酸化炭素を故意に吹きかけられた。もう一つは意外なところから一酸化炭素がでていた。ということです。
故意に吹きかけられたとすると、被害者は恨みか何かがあったことはわかりますので、その線で調べることができます。もし面白がってやるような犯罪だと一度ではなく、連続で起きますので、それも調べていけばわかります。そうやってつきつめていくと、それでもわからないものが残ります。
それは以外なところからでていた一酸化炭素を吸い込んだ、ある意味では事故です。被害者の環境を調べたりして解決することもあります」
憲一朗はこの捜査官はとても細かくてロジカルだが、自分との関係を全く話してくれない、とちょっともどかしくなった。
「あの、それはよくわかりますが、なぜわたしのところに」
宙夜が顔を上げた。
「あ、すみません、そうですね、実はもう十年ほど前になりますが、奈良で二人の女性が自分の部屋で、一酸化炭素中毒で亡くなっています。一人は学生で、一人は飲み屋のマダム、どちらも部屋には一酸化炭素中毒を引き起こすようなものはなかったのです。
一酸化炭素中毒はひどいときは、そのときは治っても、しばらくしてから亡くなることもあります。その人の体のコンディションによりますから。
飲み屋のマダムはチェーンスモーカーだったようで、しかもお酒もだいぶはいっていた、それでたばこの吸いすぎという結論になっていました。もう一人は京都の大学の学生さんでした。自分のマンションで心臓麻痺でなくなっていましたが、血液の一酸化炭素量が正常値をこえていました。甘利毬といいます」
それを聞いて、憲一朗はどきっとした。
「甘利毬は知っています」
「そうでしょう、調べました、ほんの短い間だったようですけどお友達でしたよね」
「はい、深いつきあいではありません、彼女いつの間にか大学で姿を見せなくなりました」
「何人かの男友達がいたようです、寄手さんもその中の一人です、もう一人のマダムという人は赤木美子です」
「その人は知りません」
「そうでしょう、寄手先生が学生さんのころアルバイトしていた弁護士事務所の社長さんと付き合っていた人です、社長さんは彼女から借金があったのですが、亡くなったその日に、すでにお金は彼女の銀行に振り込まれていました。それに、その日社長さんは他の女性と一緒であることがわかっていますので、彼女が死んだことに直接関わりはないでしょう、それで寄手先生が何かご存じないかお聞きにきたのです」
それを聞いて憲一郎は思い出したことがあった。
「もしかしたら、名前は知りませんでしたが、弁護士事務所に来た女性に家に連れて行かれたことがありますが、その女性でしょうか」
「そうですか、そのときのことをお話しいただけますか」
「はい」
憲一朗は大学時代のことを話した。
「高校のとき、父親が珍しく進学については口を出しまして、僕は関東の大学の方が家から通えていいと思っていたのですけど、地方の国立にいけと言われ、それで京都の大学をうけました、、下宿は京都ではなくて奈良にしました」
奈良から京都、大阪は近い。両親は憲一朗が大学にいる間、四度ほど彼が借りているアパートに泊まりにきた。2DKの部屋だが、二人が泊まりにきても困らないほどの余裕があった。彼のアパートを起点に、奈良京都大阪の見物にでかけたのだ。観光を終えると、必ずこれは宿泊代だと、ことわる憲一郎にお金をおいていく。本などは自分のバイトのお金で買っていた憲一郎にはありがたいことではあった。
当然のこと、憲一郎は遊びにお金を使うことはなかったしできなかった。友達に誘われればつきあいで映画を見に行くことぐらいはした。飲み屋にも行かないわけではなかったが、バイトの収入内で許される範囲だった。
バイトは大学が紹介してくれた京都の大きな弁護士事務所の雑用係である。これはとても勉強になった。法律関係で食べていこうと思っていた人間には実践的なよい学びの場である。
弁護士事務所の社長は、憲一朗に遊ぶことも大事だよ、弁護をするのに人間の生活を見ておかなければ依頼人の意に添うことはできないよ、とよく言っていた。社長は司法試験を何度も失敗して、自分の父親がやっていた弁護士事務所を引き継いだのはいいが、結局自分は受からずに、社長業をやっているだけである。ただ抱えている弁護士は優秀で、関西で顔が売れているつわものぞろいだ。それは社長の采配が世間をよく見ていることと、勤めている人たちの性格をよく知っていて、話を良く聞く人だったからだと、憲一郎は今になり思っている。その当時はそう感じていなかった。社長はまっとうなことを憲一郎にいうのだが、本人の遊び癖はかなりのもので、女癖もよいとはいえない。憲一郎はそういう男だから、社長は自分のやっていることを正当化しているだけじゃないかと、反発をもしていた。
憲一朗が大学二年生のそんなある日、一人の女が事務所を訪れた。社長に会いたいという。受付の女性が社長は今日いらっしゃいません、とことわっている。女性の着ているものは、勤め人が着るような普通のスーツだが、どこかこなれていない。ちょっとした表情、手のしぐさが会社勤めの女性とはちがう。目が怒っている。
受付のすぐ近くのデスクで、頼まれた計算をやっていた憲一郎の耳にも話が聞こえてくる。
社長に電話を入れてくれ、とか、返してもらいたいものがあるのよ、とかだんだん言葉遣いがぞんざいになってくる。やっとこの事務所を探りあてたんだから、とも言っていた。
三十をちょっと越えたほどの女性だった。落ち着いたきれいな人だ、と珍しく憲一郎は思った。
受付の女性はほとほとこまっていると、奥のデスクから、一人の弁護士が、かわるよと、受付の女性をたたせ、彼女の前に座った。
弁護士の楠ですと自己紹介して、女性に話をうながした。社長あたしに五百万かせば二年で倍にするといってもっていったのよ、店によく来る人で、いい客だったので信用したのが悪かったんだわね、二年たったころからぱったりこなくなった、それからさらに半年過ぎたのよ、もらった名詞は嘘の名刺、それで探偵に調べさせたら、ここの社長だということがわかったのよ。弁護士なのね、驚いたわ。
楠弁護士はどこの探偵社ですかと聞くと、女性は知り合いよ、としかいわなかった。楠弁護士は、お話だけではうちの社長かどうかわかりません、連絡の方法を教えることができないんですが、と断っている。
もっと粘るのかな、と思っていると、女性は、そうね、仕方ない、また来る、と帰っていった。
楠弁護士は、憲一朗をみて、笑いながら、うちの社長がそんなことするわけはないけど、飲み歩くことは好きだから、全て否定もできないし、困ったもんだよなーとつぶやいて、自分のデスクにもどった。
四時、バイトを終わらせて弁護士事務所をでたところ、その女性がつーっと、憲一郎のそばによってきた。
「あんた、事務所の人でしょ、ちょっとつきあってよ」
女は憲一朗の腕をつかんだ。話し方が事務所のときと全く違う。
「こないと、大きな声で叫ぶよ、あんた、痴漢でつかまるよ、それは困るでしょ」
脅され憲一朗は、どうしたらいいかわからないまま、引きずられるように、連れられて、とまっていたタクシーに押し込まれた。
「五条通りの烏丸五条交差点でおろして」
女は運転手に命じた。タクシーの運転手はすぐに車を出した。烏丸五条交差点なら遠くない。
「なにするのですか」
「だいじょうぶよ、心配しなくていい」
女は指を一本あてて、しゃべるなというしぐさをした。社長の知り合いのようだが、あまり芳しくない関係のようだ。しかし、社長のためにも女にさからわないほうがいいと、憲一郎はそう判断した。
タクシーを降りると、女は「ついてきて」と歩き始めた。小さい道に曲がり、しばらく歩いて、かなり時代が古いがしゃれたマンションの前で立ち止まった。女は入り口にある機械に番号を入力すると、エントランスから階段で二階に上がった。十世帯ほどの小さいマンションだ。
「さーはいって」
憲一郎が部屋にはいると、ソファーに座らされ、女も隣に腰掛けて、たばこに火をつけた。
「あんた、あそこの事務員さん」
「アルバイトです」
「そうだと思った。あんたはまだ大学生でしょ」
「はい。大学二年です」
「社長も弁護士なの」
「いえ、違います」
「そうでしょうね、でも法律のことよく知っていたわ、それでだまされて、五百万貸してしまったんだ、返してほしんだ、あなた社長の携帯知っているでしょう」
女は二本目のたばこに火をつけた。かなりのチェーンスモーカーだ。
スマホには社長の電話番号が登録されている。
「ねえ、教えてくれたら十万円上げるわよ」
女は憲一朗のすぐ耳元で言うと、たばこをもみ消して立ち上がった。
キッチンからビールをもってきた。
憲一郎は「飲めないんです」と断った。
「あんたいくつ」
「十九になったところです」
女は何もいわずに、ビールをソファーの前のテーブルにおくと一人で飲み始めた。
「弁護士事務所の社長がお金を騙し取るとは、よほど経営がたいへんなのかしら」
「いえ、とても有名ないい探偵事務所です」
「やり手の経営者ってところか」
女はキッチンにいってウイスキーをもってきた。それも一人で飲み始めた。たばこはひっきりなしに吸っている。自棄酒っていう感じだ。
「電話番号教えてくれないの」
「だめです」
「あんた、ジュースでも飲む」
「いえ、いりません」
憲一郎が逃げだそうとすると、女が飛びついてきた、がむしゃらにソファーに押しつけられた。
「逃げられないわよ、電話番号を教えてくれない限り」
女はまた奥にはいっていった。逃げだそうとすれば、部屋から出てきて飛びかかってくるのだろう。ここのところはおとなしくしていよう、そう思った彼はソファーに腰掛けたままでいた。
かなりの間があり、彼は女がなにをしているのかと気になり始めたとき、部屋にもどってきた。女は太股も露わになるほどの短い黒いスカートをはき、白い薄いブラウスに着替えてきた。胸が透けて見える。きれいな顔立ちをした女だ。憲一朗の前のソファーに座ると、またたばこに火をつけ、ウイスキーを手にした。
「いつもの格好なのよ、あの社長こういうのが好きなんだ」
そういいながら女は足を組んだ。
ちらっと見た憲一郎はどきっとしたどころではない。女の経験もないどころか、まだまともに恋をしたこともない。
「社長さん、うちではやさしかったのよ、つい信用してお金をあずけちゃった」
「きっと返してくれますよ」
「だけど、本名じゃなかった、やっとあの探偵事務所見つけたんだから、事務所に電話をじゃんじゃんかけてやろうと思ったけど、わたしも世話になったわけだし、すこしはほの字だからね、着慣れない格好をして事務所に会いに行ったわけよ」
女はたばこを強く吸うと、灰皿におしつけ、憲一朗の隣に座った。
「あなた、恋人いるの」
憲一朗は首を横にふった。
「キスの仕方教えてあげようか」
女は憲一郎をソファーに押しつけ、彼の顔を両手で押さえると、彼の口に自分の口を合わせて舌を入れてきた。憲一朗はどうしていいかわからず、息をはいて女の顔から自分の顔を離した。そのとき、女は「気持ち悪い」と言ってソファーにうつ伏せになった。手はいつの間にか、上着の内ポケットにいれておいた憲一郎のスマホをにぎっていた。
それに気がつくと、憲一郎はあわててスマホをとりかえし、後ろもみずに部屋をとびでて、マンションをあとにした。タクシーを拾い、京都駅につくと、奈良に行く電車に乗った。心臓がバクバクしていたのを覚えている。
自分のアパートにつくと、やっと一息ついたら疲れが出た。風呂にはいり、汗だらけの下着を変えて、パジャマになりベッドにもぐりこんだ。社長の電話番号を教えることなく帰れてよかったと安堵をしてすぐに眠ってしまった。
朝、その日は一日大学に行く日だ。事務所にあの女が行くのではないかと気になったが、まじめに授業にでた。アルバイトはない日だが、授業が終わって事務所によってみた。
「どうしたの、憲法ちゃん、今日はバイトのない日でしょう」
彼は憲一郎なので、事務所で憲法ちゃんと呼ばれている。
「ちょっとこっちに用事があったので、よってみました、昨日の女の人がまた来たのか気になって、社長さんには女性のこと言ったのですか」
「こなかったわよ、わたしもくるかと思っていたのだけど、社長もこまったものね、でも憲法ちゃんは気にしなくていいのよ、あんなこと社長には言わなかったわ、社長のプライベートのことよ、楠弁護士におまかせ」
「それならよかったです、明日は午後からきます」
「わざわざごくろうさま」
受付の女性は笑って憲一郎を見送った。
憲一郎は何となく安心して、いつものように買い物をしてアパートにもどった。
次の日、大学の授業を受け午後に探偵事務所に行った。
「憲法ちゃん、社長さんには楠さんが注意をうながしておいたようよ、女性が来たことを聞いた社長さん、あっそうとしか言わなかったみたい」
「はい」
そこに楠弁護士がきた。
「憲法ちゃん、今日は統計処理をしてほしんだ、データはこれにはいっている」
USBメモリーをわたされた。楠弁護士が実質の社長のようなもので、十人いる弁護士の頭である。
「はい」
彼は自分用のPCをたちあげUSBを差し込んだ。
「データはAからJまでの10群でエクセルに入れてある、それぞれの有意差、全体として意味があるか、統計にかけてくれないか」
「何のデータですか」
「性格と心理傾向のだよ」
「弁護のためのデータですね」
「そうだよ、だけど、弁護士には役に立つけど、直接弁護の証拠にはならないんだ、これはここの弁護士たちで今まで弁護した人を解析したものでね、心理学者が論文に書いたものは根拠にできるけど、我々がやったのじゃ審理の参考として取り上げてもらえない。だけど我々が弁護を引き受けたときには役に立つこともある」
「そうなんですか」
「我々の積み重ねのものだよ」
「すぐやります」
もう一人の弁護士が警察からもどってきた。坂本さんという。
「昨日の一酸化中毒は、たばこではないかという結論になったらしい」
そういった。憲一朗は何のことかわからない。
「なにかあったんですか」
楠弁護士が昨日の朝刊の京都版のところを開いて、憲一郎に見せた。
「酒によった女性が一酸化中毒で自宅で死んでいたんだ、外傷もなにもなくてね、自殺する原因もなかったので、他殺の線も調べていたようだが、我々には関係のない話だけど、場所がちょっと近くだったから、気になっただけなんだ、坂本さんが警察に行く仕事があったんで、聞いてきてくれたってこと」
「そうなんですか、たばこで一酸化中毒ってなんですか」
「たばこの葉が燃えると、一酸化炭素がかなりでるようだよ、だからたばこのみは一酸化炭素をかなりすっているんだ、女はチェーンスモーカーのようで、女が吸ったたばこの吸い殻がかなり残っていたようなんだ」
坂本さんが説明してくれた。
憲一郎の頭に昨日の女性のことがちらっと浮かんだが、頼まれた統計のことを考えていたこともあり、すぐに忘れ去った。
奈良に住んでいる憲一朗のとっている新聞に京都の小さな事件は載っていない。
「ともかく、統計処理頼むな、急ぐ仕事じゃないよ」
「はい」
憲一朗は弁護士仕事に統計処理は重要なものだと大学の教授陣から聞かされている。統計学の基礎は一年の時履修した。今、大学設置の科目である中級の統計学を、ほかの学部生に混じってうけている。勉強になる仕事だ。
次の日、午後に事務所に行くと社長がきていた。
「よう、憲法、勉強してるか、しないと俺のように、司法試験浪人10年生になっちまうぞ」
笑って声をかけてきた。
「だけど、遊ばなきゃいい弁護士にはなれんしな、ところで女がきたことは知っているだろう、行き違えだな、女には金を返したたところだったんだ、利息付けてな、まあ、忘れてくれ」
とも言った。そういうと社長室にいってしまった。
憲一郎は女の部屋に行ったことはいわなかった。言いそびれたというのが本当のところか。
そういったことを、刑事に話した。
「そんなことがあったんですか」
話を聞き終わった宙夜はうなずいた。
憲一郎は宙夜の話から、あの時一酸化炭素中毒で死んだのが社長の愛人だったことを知った。ずいぶん昔の話だ。
「それで、友達だった甘利毬さんが大学からいなくなった、最後にあったときに、どんなでした、はっきりききますが、体の関係はありましたか」
「いえ、最後にあったとき、ちょっと、その、キスぐらいは、そうだ、そのとき、気持ち悪いとタクシーに乗って一人で帰りました」
「すみません、プライバシーの中に踏み込みました、でもこれではっきりしました」
宙夜は鞄からなにやら機械をとりだした。スイッチをいれると、数値が機械の表示部分に30PPMとでた。
「寄手さん、これに息を吹きかけてもらえますか」
憲一朗は息をかけた。
機械の数値が300になった。
「僕がかけてみましょう」
そう言って宙夜が機械に息を吹きかけると、31とでた。変化がない。
「これは、一酸化炭素検知器です、量販店でも買えるものです、ふつう50PPMより少ないはずです、だけど寄手さんが息をかけると300にあがった。200PPMぐらいでも頭痛などがおきます、相当に高濃度の一酸化炭素が寄手さんの息に含まれているのです」
どういうことだろう。
憲一郎はいきなりそういわれて、どういったらいいのかわからない顔になった。
「できたら検査を受けていただけますでしょうか。結果がどうであれ、今お話しした事件に関しての責任とかそう言うことは問いません、奥さんが一酸化炭素中毒になられておりますので、それを解決する糸口が見つかるかもしれません」
「僕の息を調べるということですか」
「そうです、どうして一酸化炭素がでるのか、そういう体質だとすると、どうなっているのか調べます」
「ぜひお願いします」
憲一郎にもその深刻さがわかってきた。鈴美のからだに悪い影響を及ぼしていたのかもしれない。それを治さなければ。
「人に向かって息をかけないようにしてください。こちらで、検査の準備を整え、連絡します」
「あ、ありがとうございます」
宙夜は納得したように一礼して事務所から帰って行った。
家で鈴美に警視庁から刑事が来たことを話し、内容を説明した。
「あなたの息から一酸化炭素でているなんて、そんなことあるのかしら」
鈴美も半信半疑だった。憲一郎がそばによるのをためらっていると、大丈夫と手を引っ張られた。
それから一週間ほどして、宙夜から電話があった。都合のいいとき、ただし、午後に呼吸器専門の医師に会ってほしいと言うことだった。喜田弘という、お茶の水の大学病院の教授だそうである。
時間のとれるときに連絡をいれアポイントメントをとった。鈴美にきいたら、肺の酸素の取り込みの研究では、世界に知られているそうである。
その病院はよく知っている公立病院で、たずねたのは研究棟であった。
入口の受付で名前を言うと、先生がおまちですと教授室の番号を教えてくれた。八階のエレベーターホールからすぐのところに教授室はあり、奥は実験室のようで、白衣の人が廊下を行き来している。こういうところには入ったことがなく、ちょっと緊張していた。
ドアをノックして、名を言いながら入ると、背が高いまだ童顔の若い男がデスクから立ち上がった。三十代だろう、自分とそんなにちがいがないが教授か、すごいんだろうなと憲一朗はそれだけでちょっと身を引いてしまった。
「喜田です、どうもわざわざすみません、宙夜君にたのまれました、彼とは大学の時の知り合いです、警視庁の捜査支援課で活躍している男です」
「寄手です、街弁をしております」
教授は、えっ、という顔をした。
「弁護士事務所をなさっているとききましたが」
憲一朗はああ、そうかと言い直した。
「すみません、町医者のように個人でやっている小さな弁護士事務所を街弁とよぶことがあります」
教授は笑顔になった。
「ああそうですか、どうぞおかけください、話の概要は宙夜からきいています、不思議なことです、からだから一酸化炭素を出すなんてことがあるのか、信じられませんでした、ご本人のためにも、調べて差し上げたほうがいいと宙夜にいわれております。
調べる費用はいただきませんが、学会の発表などにデータを使わせていただくことだけご了承ください、個人はわからないようにいたします」
「はい、それはかまいません」
「何回かきていただく必要があります、お忙しいのはわかっていますが、先生の都合のよいときでかまいませんのでお願いします」
「家内が呼吸器科の看護婦をしておりまして、よく調べてもらうようにいわれました」
「ここの病院ですか」
「いえ、国立病院です」と名前を言った。
「ああ、あそこの教授はよく知っています、そうですか」
「今日はなにかするのでしょうか」
「お時間はいつまで大丈夫ですか」
「夜中まで大丈夫です、家内は夜勤ですし」
喜田教授は笑顔になって、「お疲れにならない程度にお願いすることにします、実験室の方に担当者がいますのでいらしてください。
教授に案内されて実験室に行った。
広い実験室には、研究者のデスクだろう、ずらっとならんでいて、機械類が所狭しとおいてある。
中にはいると、一人の若い白衣をきた女性が教授のところにきた。
「荒井純子医師です、研究チームのリーダーです、すでに、調べさせていただくことは検討してあります、概要をいいますと、どのくらい吐く息の中に一酸化炭素だされているのか、息以外に、体の表面からもでていないか調べます、次にどのようなときに沢山でるのか調べることで、神経調節が行われているかどうか知ろうと思います。疲れたときか、ストレスがかかったときか、いろいろあります。
平行して、肺のどの細胞で一酸化炭素がつくられるのか生化学検査をして、呼吸器系にかかわる遺伝子の調査をします」
ずいぶんたくさんやるのだなと言う顔をしていたのかもしれない、荒井先生が、
「検査はそう頻繁には行いません、寄手先生のご都合にあわせておこないます」
といった。
「荒井君、今日はお時間があるようだ。血液の採取と、肺活量や、息の中の一酸化炭素の量、あと皮膚からでているか、そんなことを調べさせていただいたら」
「はい、わかりました」
「これからは、直接、荒井君に連絡して下さい、私も時間のとれる限り参加します、今日、木曜日は、教授会なんていうつまらんものがありまして、これから行かなければなりませんので、荒井君とおねがいします」
憲一郎は荒井先生につれられて、実験着に着替えさせられ、呼吸器系の検査室に行った。吐く息の採取、皮膚のテストなどをおこない、血液検査室、MRI室などをまわった。
帰るときに荒井先生が、一酸化炭素は皮膚からはでていないので、吐く息だけ注意すれば大丈夫ですと言ってくれた。
家に帰り、夜遅く仕事から帰ってきた鈴美にそのことを言うと、
「あら、残念だわ、憲一朗さんの一酸化炭素集めて売ろうかと考えてたのに」
言われ、憲一朗はぽかんとしていた。
「冗談です」と鈴美が憲一朗の顔を見て笑った。鈴美の初めての冗談だ。やっと、憲一朗も笑って、「ごめん」とあやまった。
「ほっぺだけならだいじょうぶよ」と鈴美が憲一路の頬っぺたに口を寄せた。憲一朗もおかえしをした。
「先生が一酸化炭素をとめてくれるわ、それまではほっぺ」
なんだか鈴美が明るくなった。よかった。
それから、何度か検査をうけ、二ヶ月後には、緊張すると一酸化炭素が増えること、二酸化炭素から、一酸化炭素にする酵素が肺の細胞にあること、ヘモグロビンが一酸化炭素より、酸素に結合しやすい性質を持っているので、肺に一酸化炭素が遊離しやすいこと、さらに憲一郎の血液には一酸化炭素を吸収して無害にする化学物質が血液にあること、それらに関係する特殊な遺伝子をもっていることが明らかになった。簡単に言えば憲一郎の肺が一酸化炭素を作り出しているが、自分には影響がないということらしい。
憲一郎の血液の中の一酸化炭素を吸収する物質があきらかになると、一酸化炭素中毒者を助ける薬ができるかもしれないことなども荒井先生から報告を受けた。一酸化炭素毒の毒消しだと先生は笑っていた。
これからは一月に一度血液検査を受けることになった。鈴美にいわせるとただで体の状態を調べてもらえていいねということだった。
なぜ自分だけがそんなからだになったのだろうか。
子どもの頃、おまえは口が臭いねと母親に言われたことを思いだした。それで懸命に歯を磨き、口をすすいだことを覚えている。小学校六年の頃だっただろう。食後に必ず練り歯磨きで歯を磨いたためだろう、校医さんにはきれいな歯をしているねとほめられた。だが、家では、母親が何でだろうね、一生懸命磨いているのに、おまえの口は匂うね、とあいかわらず言っていた。今思うと、無神経な母親である。いうだけでなにもしてくれなかった。父親はなにもいわなかった。
中学、高校生になっても母親は口が匂うとたまに言った。しかし歯は表彰されるほど綺麗だったし、風邪もあまり引いたことがないほど体が強かったので、そのままになっていた。一酸化炭素は臭わないはずだが。
大学病院に通うようになって半年たった頃、警視庁の宙夜がたずねてきた。
「寄手先生、ご協力ありがとうございます、喜田先生とは連絡しています、いろいろわかってきて、喜田先生も喜んでいます。あそこの荒井先生が論文にまとめています。寄手先生が協力してくださるので感謝しているといっていました」
「それで、大学の時の事件、私の息が二人の女性の死因につながったわけで、私にも責任がありますね」
「いえ、僕は犯人さがしのため寄手先生のところにきたのではありません、もう二つの件はおわったことです。原因が明らかになると、ご本人にとってよいことであると思わなければ、昔解決されたことをほじくり返すようなことはしません、今回もとても不思議ですが、こういった出来事を探っていったことで、人間の体に今まで考えられていなかった仕組みがあることがわかりました。基礎的な生命科学の進歩に寄与したことになりますので、警視庁の支援室の室長もはじめみな喜んでおります」
「そういってくださると、ありがたいことです、宙夜さんは、喜田先生と大学のご友人だそうですね」
「ええ、喜田先生は医学部でしたけど、ぼくは理学の地質、特に結晶を研究していました」
「年は同じなんですか」
「いえ、彼は二つ上で、いま四十ですね、われわれ化石クラブでいっしょになったのです、僕はアンモナイトが好きだったんです、彼は恐竜の歯を集めていました」
宙夜が笑った。
憲一朗と同じ世代である。大学時代はサークルにも入らず、司法試験の準備だけだったような気がする。奈良の弁護士事務所の社長が言ったことが思いだされる。これからでもおそくない、弁護師活動以外のことにも目を向けなければ。
「ところで、一酸化炭素で亡くなった二人の女性からよく私がわかりましたね、それより、その前に、あの件をよく私と結びつけたものですね」
憲一郎がいうと、宙夜は笑った。
「膨大なデーターが我々の研究室にきます。おかしな事件、不思議な事件、未解決な、そういった事件のデーターです。見ていると浮き出てくるのです、何かおかしい、引っかかるデータだとね、他のものは霞んでいく、それを拾うんです、それで、やはりなにかありそうだと調べていくと、今度の場合は奈良の弁護士事務所、京都の大学、それをつきつめていったら、寄手さんにぶつかったのです、東京で弁護士をしていることがわかり、警視庁からそんなにはなれていない、ちょっと来てみたわけです。その結果です」
「私のような体をもつ人などもいるのですか」
「ええ、最近は黒子に毒をもつ人がみつかりました」
その言葉は私をほっとさせるものだった。
宙夜はもうこの件は終わりですと礼を言って帰って行った。
看護婦の鈴美は母や父、それに妹の息の一酸化炭素を調べた。だが、一酸化炭素はでていなかった。鈴美は憲一郎に「あなたの体のこと、みんなが心配するといけないから、だまっていましょうね」
と言った。憲一郎がお茶の水の病院にいっていることを両親は知らない。
鈴美に子どもができた。
「生まれてから息をふきかけないでね」
そう言われた憲一郎は一酸化炭素除去の薬の完成が待ち遠しかった。薬が開発されたらいつでも治研者になると荒井先生には言ってある。そう思いながら、今も病院にかよっている。まだ先のことのようだ。
息毒


