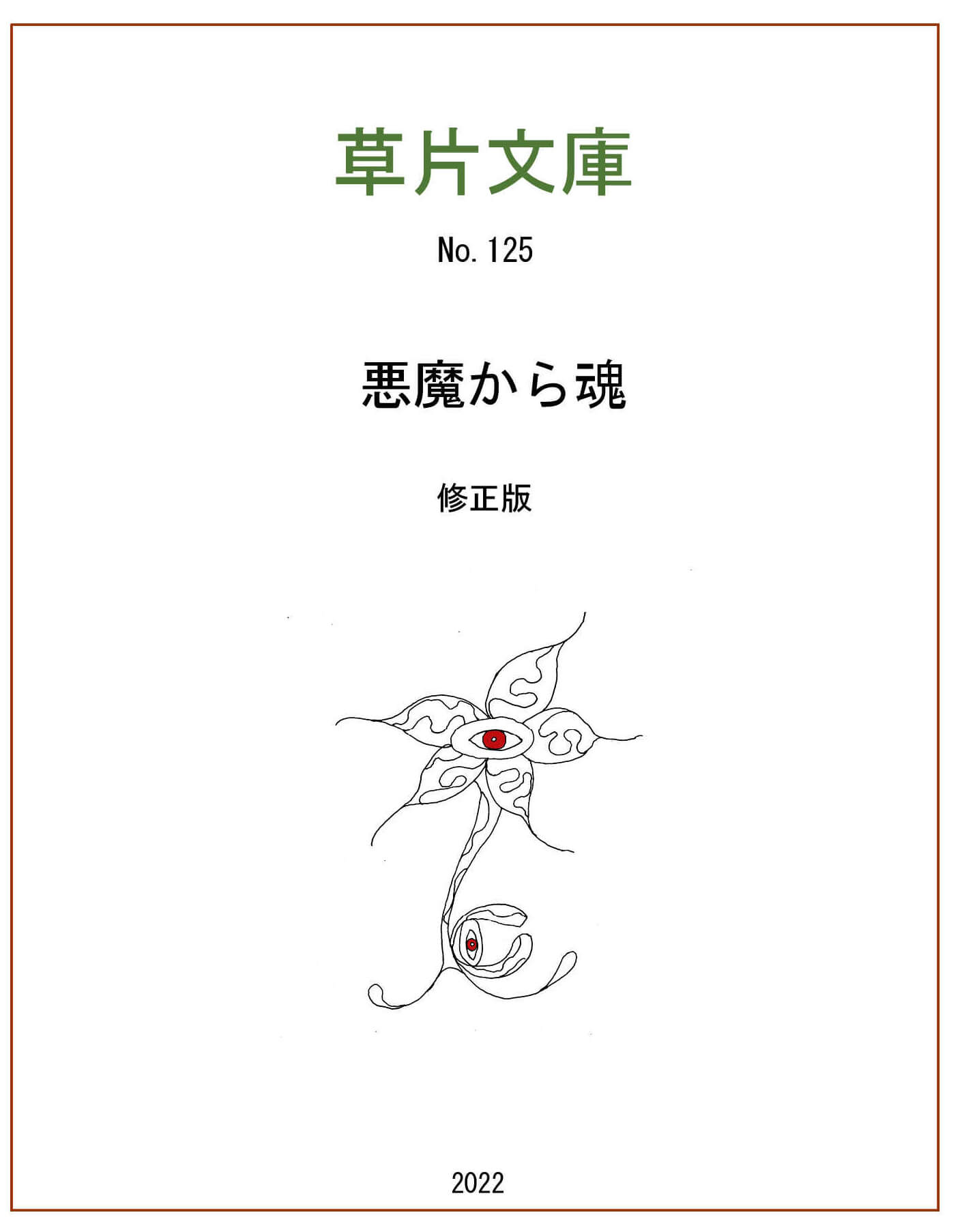
悪魔から魂
悪魔の話。縦書きでお読みください。
悪魔から魂を買った.
パガニーニはバイオリンの技術うますぎて、魂を悪魔に売った代償だと言われたそうだ。悪魔は魂と引き替えに優れた能力を授けてくれるという大衆の思いこみなのだろう。
実は悪魔は違う。
ほら、やってきた。
猫ほどの大きさで、二本足で歩いているが、あっちにふらふら、壁にぶつかりそうになって、壁に悪態をついている。まるで酔っ払いだ。悪魔の顔は何度か泥足の猫の足の裏を拭いたよう雑巾のような色をしている。
壁に向かって、こんなところにいるなと、市長が酔っぱらったときのようなことをいう。
「こっちだよ」
と呼びかけると、やっと私に気がついて、ひょこたりひょこたり飛び跳ねてきた。
「いいでものはあったかい」
「最近はプーチンの魂を手に入れた」
だから、あの国はあんなになっちまったのか。
「それでその魂はどうした」
「二束三文で売れた。何でもキャベツの肥料にはなるようだ」
「それで、悪魔、あんたはなにを買ったんだ」
「シジミ貝のおつけだ」
「日本でか」
「ああ、宍道湖のシジミの味噌汁うまかった」
舌は肥えているようだ。
「私にはなにを売りたいんだ」
「どうだろう、レイの魂だ、たかいぞ」
「レイチャールズか」
「いや、レイブラッドベリーだ」
「それはすてきだ」
雑巾色の悪魔は小さな目を私のほうにむけた。目の中は墨流しだ。黒目がめちゃめちゃ。
「それで、なにがほしいんだ」
悪魔から何か買うときは金では買えない。それに関して巷で言っていることは正しい。ただ、かならずしも命や魂との引き替えではない。
「炎がほしい」
「どんな炎だ」
「手をかざすと、手のひらが虹色になるくらい暖まる炎だ、ここのところ手がかじかんで冷たい」
悪魔は冷たくない。暑すぎるほどの体温だ。常温が55度だそうだ。
「それはむずかしい、でも探してみる」
レイブラッドベリーの魂が手にはいると、きっと見える物が、みな幻想色に染まり、自分が書いている小説が、まともなものになるのではないだろうか。
ずいぶん昔になる、若いころだ。化学の世界に身を投じようと考えていたころだ。いくつかの薬品を混ぜ合わせ、溶液を作っているときだった。NaClと間違えて、KClをいれてしまった。ごくごく初歩的なミスだ。塩化ナトリウムを入れなければならないところ、塩化カリウムをいれたということだ。
初恋の女が離れていったときだ。そんなことで動揺していたのだから、科学者なんぞになれるわけはないのだ。
溶液が紫色になって、間違えたことに気づいた。特に危ない溶液ではない。ただ捨てるだけでいいのだが、あまりにも紫色がきれいなのでみとれていた。この液体の中では、本来はNaが反応する物にKが反応してこうなったのか、それともほかの物質が合体してこうなったのか。
見ていたら、ビーカーの中で紫色が凝縮して、アメフラシのようになってきた、紫のナメクジといってもいいい。紫色は形をかえ、ひょろひょろとした二本足の形になり、顔らしきものを溶液の表面から飛び出させた。
「よう、だしてくれよ」
そいつは、僕を見上げたので、ガラス棒をいれてやると「つかまりにくいな」といいながら、それでもしがみついた。
ガラス棒をビーカーからだすと、そいつはすとんと実験机の黒い表面にとびおりた。ダルトンの実験机だ。
「売りたいものがあるんだ」
そいつが言った。
「なんだ」
「黄泉の国からちょいともってきた、いくつかあるから選んでいいよ」
「それでなんなんだい」
「夏目漱石、内田百件、ポーの魂だ」
「何の役に立つんだ」
「そりゃわからん、買ったやつの好みや、資質にもよるさ、買ってからのお楽しみってやつだ」
「金ないよ」
大学院生のころだから金があるわけはない。
「金がない、化学者の魂はないのか」
将来化学者になるつもりだったからそう聞いた。
「今はない。黄泉の国にいったら、たまたま猫の会をやっててな、魂が集まってたから、三つばかり、とっつかまえて持ってきたんだ、みんな作家の魂だ、密輸入のようなものだ、現世で売るわけだ」
「それでいくらなんだ、そうか、それよりその前に名を名乗れ」
「おっと失礼、日本じゃ悪魔と呼ばれている、メフィストだとか、リリスだとか、いろいろあるが」
「それじゃ、俺の魂と引き替えかるか」
「あんたの魂もらってどうする、海の物とも山のものともわからんし、だいたい、悪魔の食い物じゃない、俺がほしいのはうまい茶漬けだ」
「下宿にいけば、お茶漬け海苔がある」
「おお、それでいい、それじゃ、下宿にいこう」
悪魔のやつ俺のふさふさした髪の毛の中にもぐりこんだ。今日はナトリウムとカリウムを間違えるほどひどい日だ。実験はやめた。器具を洗うと、下宿にもどった。
それ以来、化学は遠い国にとんでいっちまった。月より遠くなった。覚えたことは、使った物は、次の人がすぐ使えるように、きれいに洗っておきなさいよと言うことぐらいだ。まあそれは人生のなかでかなり役に立つことではあった。
下宿で、悪魔のやつ、箱に入れておいた鮭茶漬けをみつけた。
「お、いい、いい、それで、どの魂がいい」
夏目漱石の吾輩ハ猫デアル、内田百件のノラや、ポーの黒猫、みな猫だ。猫は好きだが、さて、どの魂がいいかとなると、考えたこともない、今ならポーを選ぶだろうが、文学など東西の壁の反対側だと思っていたので、ともかく、日本の作家、それも読んだことのない、内田百件の魂と取り替えることにした。
悪魔の奴、ふっとおれと同じ大きさになると、勝手に茶漬けをつくって食った。
「うまかった、またいつかな」
そういうと、ぐずぐずと紫ナメクジになって、台所の流しの下水管の中に身を投じた。
それから、なぜか小説を書き出した。江戸川乱歩の二銭銅貨からヒントをもらった。十円銅貨はとあるミステリー雑誌の新人賞候補になり、漱石の草枕から考えついた、箱枕は佳作になり、室生の蜜のあわれと森茉莉の甘い蜜の部屋に着想を得た甘い蜜の泡でやっと優秀賞をもらい、初めての本をだした。悪魔に百閒の魂をもらったので、偽作吾輩は猫であるを読んだところ、こういうことになった。みんな偽作である。おかげで、偽作作家という喜ぶべきか、憂うべきかわからない評判をもらうことになった。
だから、当然、悪魔から百閒を買った時点で大学院はやめ、文章を書きながら、アマゾンで荷物の仕分け作業をやっ、生活費を稼いでいた。それが今は、偽作作家で食べていけるようになった。こうなりゃみな偽作だと思い、今まで出版した本はどれも、有名な作家の作品をもじったタイトルがついている。最初が「甘い蜜の泡」、二冊目は泉鏡花の偽作「茸のまいまい」、三冊目は「虚無への供養」。これはいわずとしれた中井英夫の偽作である。てなぐあいで、まあ、ともかく小説らしき物を書き、時としては、バラエティー番組に出演したりしている。
もしあのとき、ポーの魂を選んでいたら、違う世界になっていただろう。本格的な幻想、またはミステリーを書きたくても、今はみな偽物になってしまう。今度悪魔の奴がきたら、別の魂を買いたいと念じていたところ、悪魔の奴から連絡がきたのだ。
連絡係は藪蚊だった。今では山梨の田舎の一軒家で、偽作を書いて生活をしている。昔の農家の家でとてもすみごこちはいいのだが、夏になるとたんまり蚊がおしかけてくる。
蚊取り線香をたくこともあるが、めんどくさいので、電気香取をつけている。電気だと抜け道がたくさんあるのだろう、寝ているところに藪蚊がたずねてくる。
藪蚊がきたら、俺の血を吸うと、吸血鬼になるぞと脅すのだが、お構いなしに吸いやがる。かゆくてたまらん。そんな夏のある日、鼻の頭に止まった藪蚊が
「おい、悪魔が会いたいんだってよ」
といった。
「どこにくるっていってた」
ときくと、
「新宿のガードした」というじゃないか。
まだあるかどうか知らないが「いつだ」ときくと、明日の夕方八時だという。
それで、わざわざプリンスホテルに宿を取り、会いにきたということなのだ。
そして、冒頭に書いた通り、炎と交換にレイブラッドベリーの魂をくれるという。もう自分も六十をこしている。もっと言葉をあやつって、読者の脳の中に、えもしれぬ幻想の色と香りをにじみ出すような小説を書いてみたいものである。そう、偽作作家を辞めたい気持ちなのだ。
新宿の地下街で、「炎を食べるのか」と聞いたら、「炎に水をまぜたらおもしろい、マヨネーズは酢と油をうまくミックスしたら、すばらしい調味料になった。炎と水で食卓がよりいっそう華やかになる調味料ができる」
確かに酢と油のマヨネーズができたのなら、火と水を混ぜることができるのかもしれない。
「できたら、ブラッドベリーの魂をもってきてやるよ」
悪魔の奴は、そういって、新宿地下道の壁に消えていった。
それいらい、火と水を混ぜるという、禅問答でしか解決できないような事柄が、頭のなかにこびりつき、それにはどのような炎がいいのか、いつも考えるようになった。
おかげで、自分で書く小説は炎と水がでてくるようになり、七十になるまで、炎の作家と呼ばれるようになった。作品は「雨が作る炎」と題した虹の小説、「一輪の聖火」はゴンドワナ大陸でのオリンピック小説、「人の影の炎」は太陽のコロナが地球の物に影を作り、もう一つの世界が地球に存在する小説、などなどである。
しかし、レイブラッドベリーのような物は書けない。悪魔のほしがる、調味料になる炎をみつけ、融合する水とともに提供しなければ、レイの魂をもらうことはできない。
八十になって炎の作家と呼ばれていたが、何でも焼いてしまうので、放火の作家と呼ばれるようになった。名古屋城に隕石がおち、天を焦がす炎からのがれるために、金の鯱が月に上る話、国会議事堂にニホンザルが忍び込み、禁煙のはずの会議室でくすぶっていたたばこをくわえて走り回り、カーテンや絨毯が燃え上がり、国会議事堂から、日の丸が炎に包まれる話、東京テレビ塔の上で、自衛隊の大型ヘリコプターの燃料タンクから燃料が流れおち、テレビ塔がオイル浸しになったところに、雷が落ち、炎に包まれる話、など、よく考えると、いや誰が考えても愚なこった。
いやになる。九十近くなり、まだ悪魔のほしい炎はみつからない。
華氏451度。未来の世界では、本を読むことで公平さが失われることから、本をもっていてはいけない。梵書である。本を燃す炎、それを燃やすためのファイヤーマン。本に水をかけるのではない。燃やすオイルをかけるので、炎と水ではない。
いったい、悪魔はなにを要求しているのだろう。
私ももう九十九である。小説らしき物より、エッセイのような物しかかけなくなった。
100まで生きるだろうか、今、体中にガン細胞がうごめいている。幸い痛みなどはない。
100歳の誕生日の一月前、私の命は燃え尽きた。生きているということは炎である。命を燃しているのだ。どんな炎をあげていたのだろうか。悪魔はそれぞれの人の一生の炎を見ている。そうか、それを水と混ぜるのか。死がマヨネーズの酢のかわりだとすると。
今、棺桶に入っている私が燃え始めている。末期の水は孫がのませてくれた。SF作家になりたいと言っている奴だ。死ぬ1時間前に、好きだったウイスキーを、一口のませてくれた。ふと死体の私は横になっているとなりを見た。悪魔が笑ってあぐらをかいている。
ウイスキーとあんたが燃える炎で、うまいものができそうだ。約束のレイブラッドベリーの魂をやろう。
死体の私は今もらってもな、と思っていると、悪魔が、まあ、おまえの血筋のだれかにやっとくよと、言って消えそうになった。
まごにやってくれよ、と心の中で思うと、「そうしてやる」
悪魔は私の死と私が燃える炎を混ぜ合わせ、眼の中に吸い込んで消えていった。
悪魔から魂


