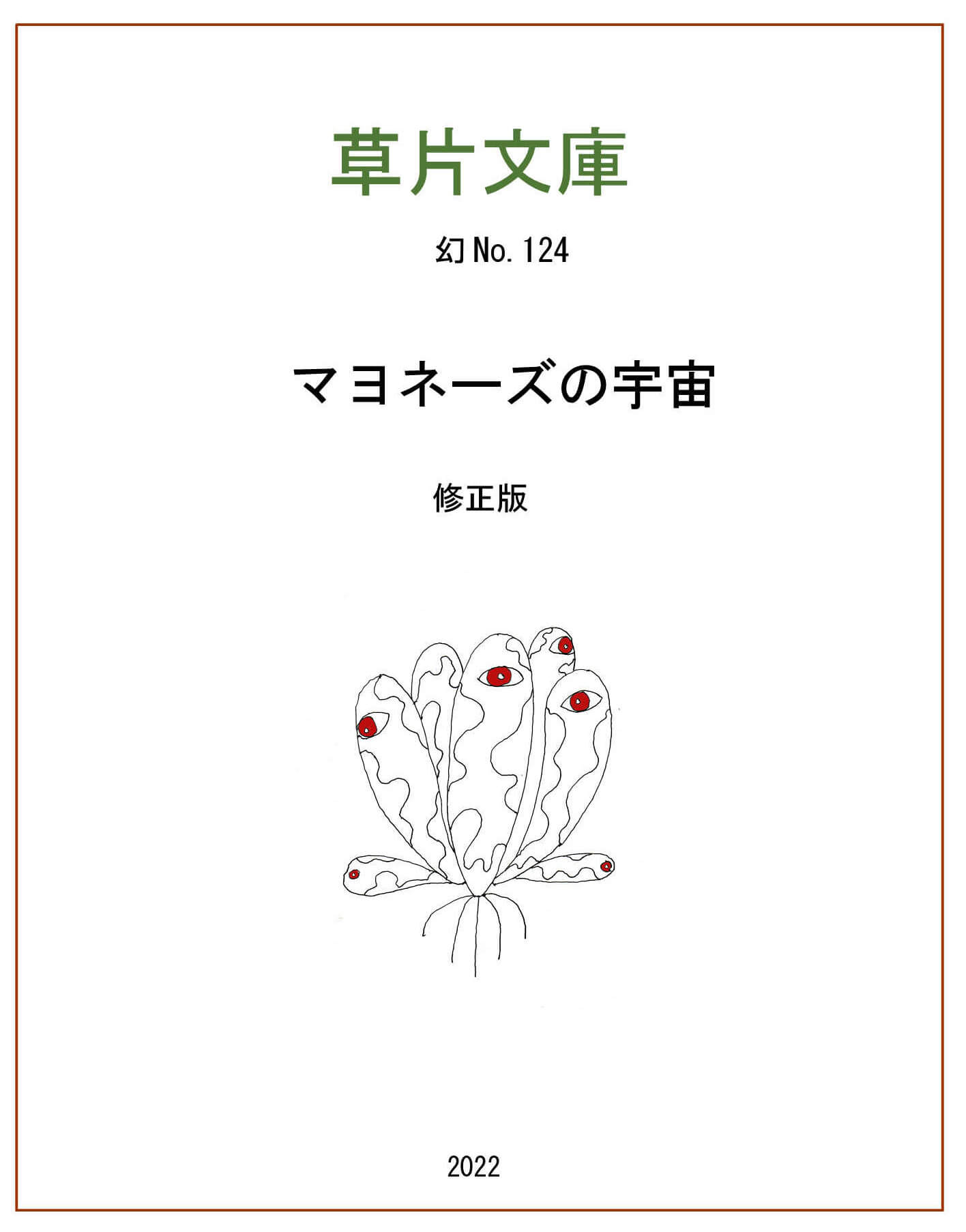
マヨネーズの宇宙
変格SFです。縦書きでお読みください。
マヨネーズを作り出した人にはノーベル賞をあげたいくらいである。わたしは小さいながらもマヨネーズの生産工場を営み生計を立てている。大手のマヨネーズ会社の日陰になりながらも、好んでくれる人に支えられて、細々と、だが堂々とマヨネーズをつくっている。
ここは渥美半島の中程、田原市の三河湾に近いところである。豊田から豊橋鉄道渥美線で三河田原駅で降りて、田原街道をいくが、車でちょっとかかる。藤尾山の麓には農業高校があり、団地も開発されていて、小学校もある。環境はいい。会社はもっと三河湾よりである。長興寺やその周りの池に近い山の麓になる。会社はかなり広い土地を所有している。先祖が残してくれた土地だ。
社員は二十名、鶏の管理とマヨネーズ工場の管理に携わっているのは農業高校出身者が多く、開発部門には自分と数名の化学と生理学を研究してきた人間がいる。それに栄養学を学んだ家内と料理学校の卒業生という構成である。マーケッティングはもっとも苦手なところだが、販売は商学部を卒業したいとこを中心として、鶏の世話からマヨネーズ工場での作業を一通り経験した者の中から数人が担当している。
マヨネーズは卵黄と油と酢で作られる。卵黄と油は科学的にも同類であり、混じっても不思議ではないと思うが、水と油ほどに違いのある酢をそこに加えてマヨネーズを作りだしたきっかけはいったいなんなのだ。
名前はどうもフランス語のようだが、つくりだされたところなどは諸説あって定まっていないようだ。
スペインのメノルカ島に由来するというものがある。メノルカ島のマオンという地域で作られている所のソースが、マンオンソースがそのスペルからマヨネーズとなったという。
それにしてもどうして酢を加えてソースをつくったのだろうか。高速でかき混ぜて乳化させないと、分離して酢と油が分かれてしまう。
どうしてできたかはわからないが、酒や醤油、味噌、豆腐といった料理の基礎となるもの、なるべくしてできあがったということなのだろう。人間の飽くなき食に対する欲が、成し遂げたことなのだ。
ロシアではなににでもマヨネーズをかけて食べるほど好まれているという。日本でもマヨネーズの好きな人はかなり多い。そういう人をマヨラーというらしいが、大手のマヨネーズの歴史が余りにも古く、日本人の中にその味が浸透しきってしまっているので、なかなか、違う味のマヨネースを探し求めるような人はいない。そういう中で、我々のつくるマヨネーズの味の良さをしってもらおうと、努力しているところである。
それじゃどんな違いがあるのかというと、鶏の鳥の育て方が大きいかと思う。ともかく、充実した卵を産んでくれるのである。卵が他とは違うのである。最近は赤い卵だとか、ある物質を含んだ卵などと、餌にいろいろ混ぜて、工夫をして卵そのものを売り出しているが、そういうものともちがう。鳥の育て方はいたって自然である。牧場に放している牛のような飼い方をしている。朝鶏の牧場に放ち、夕方鳥舎に戻ってもらう。牧場には草が生え、そこで鳥たちは好きなように過ごす。ただこういうことをしている。その年は鶏牧場の半分しか使用しない。ここは海がちかいこともあり、海苔を作っている会社があり、そこの廃棄する部分をもらってきて、休ませてある半分の牧場の土に撒く。さらに渥美半島特産のメロンの捨てる部分、それに貝の殻を粉砕して、土を耕すのである。一年後には、ミミズも育ち草が生える。次の年はその半分のところに鶏を放す。ミミズと一緒に草をおいしく食べてもらっている。必ず卵の殻を砕いて撒くことも忘れない。この方法を五年前にとりいれた。
それともう一つある。それは、我々のマヨネーズの会社、渥美食品工房の入社式のことを話すとわかってもらえるだろう。
五年前、十周年記念のため、十五人だった社員を二十人に増やすことにした。それがこの会社の大転機になったのだ。九月一日、関東大震災の日は我が社の入社式だった。そのときのことをここに紹介しよう。それで我が社の特徴がみえてくるだろう。
毎年一人か二人採用してきたが、その年は五人でとった。二人ばかり関東に売り込む担当を作ろうと考えていたからだ。ネットでの販売もやっているが、やはり県や市のアンテナショップや、デパートの食料品売場を回ってもらうと大きなチャンスがまわってくることがある。応募者はそれでも十人ほどいた。農業高校から二人応募してきている。鳥の管理と工場での仕事である。二人推薦を依頼してあるので、ある意味では形式だが、そこが重要である。残りの八人から工場の管理、販売の要員三人を採用する予定だった。
応募には朝9時から30分ごとにきてもらい、一人づつ面接を行う。その様子は普通の会社と少しばかり違う。
面接会場は応接室。テーブルを囲んでソファーがおいてある。
面接官はわたしと、家内、工場長、鶏の飼育長、それと事務長の人で行う。工場長は化学者の35の男性であり、鳥の飼育長は31になる女性である。獣医の資格を持っている、動物園飼育係経験者である。
面接の日、9時から10時は、推薦されてきた高校生の面接である。最初の男子高校生を、事務長の女性がつれてきた。高校生を我々の前のソファーに座らせ、彼女が応募者の名前、出身学校、年齢などをわれわれにむかって言った。通常の面接だと、本人に受験番号や名前を言わせ、お辞儀をさせたりするが、あれはだめだ。緊張せいて本当のことを言えない。名前などは履歴書を見ればわかることだ。
最初に、事務長が、社長の長田ですと、受験生に僕のことを紹介した。
「長田です、よろしく」
僕が声を出すと、高校生が驚いたような顔をして、「おはようございます」と答えた。これはいい。普通は名前をいって、抱負など言い始める。それでは練習してきたということがみえみえだ。
「家で動物飼ってるの」と鳥の飼育長がたずねた。
「はい、にゃんこが一匹います」
これもいい、本当の動物好きだ、普通なら、猫がという、にゃんことは、いつもかわいがっているからだ。
「これをちょっとなめてみて、どれが一番おいしいかしら」
家内が用意しておいた三つの皿を冷蔵庫の中から取り出し、彼のテーブルの上に置いた。皿の上にはマヨネーズがだしてある。彼は匙で一つ一つなめた。
「わからなかったら、わからないでいいのよ」
家内が言った。
少年はどうしようといった顔をして、しばらくすると、「すみません、わかりません、どれもおいしかったです」
と言った。最高の答えだ。ここで、半分はクリアーした。実はすべてうちのマヨネーズでみな同じものだ。
答えた最後の部分、どれもおいしかったですという言葉は、会社に入ってもらってよい答えだ。
最後のテストだ。
事務長が、テーブルの上のものをどけて新聞紙を敷いた。そこに飼育長が雌のハクショクレグフォンをつれてきた。
新聞紙の上に載せると彼に言った。
「寝かせてみてくれる」
ちょっと驚いた顔をした彼はゆっくりと手を下の方からのばすと、後ろの背中を柔らかくさすった。
鶏はちょっとびっくりしたが、すぐになれ足を折りたたんだ。
最高の出来だ。
「君は動物が好きだね、うちにはいったらなにがしたい」
わたしがそう聞くと、「鶏の世話をしたいです」といった。
高校の内申書を見ると、学業は悪くない、普通の上ぐらいだろう。妹がいるようだ。農学校では畜産のことを主に学んでいる。
「催眠術って言うのは聞いたことがあるだろう、興味あるかい」
首を横に振った。
「どうして興味ないのかな」
「やらせだと思います」
なかなかはっきりしている。
「うん、テレビのバラエティー番組などでやっているのは、そう言っていいけどね、気持ちを静めるプロはいるんだよ、臨床心理学を学んだ人だとできる人がいる、人間だと言葉を使って相手を落ち着かせ、眠るまでいかないまでも、ゆったりさせることができる、動物に対してもできるんだ、ただ、言葉は使えないから、こちらの動きやタッチだね」
「動物の扱い方を高校でならいました」
「そう、それが動物の催眠術のようなもんじゃないか、鶏にはもっと本当に眠気を誘う動きがあるんだよ、飼育長にやってもらうからみていてごらん」
飼育長は雌鳥をどかすと、雄鳥を持ってきた。ずいぶん大きい。大きな鶏冠がプルプル震えて、険しい目で周りを見回した。
「みててごらん」
飼育長の女性が、左手の中指と人差し指を鳥の目の前にだした。鳥がそれを見ると、彼女は少し指をふるわせ、ゆっくりと鳥の目に近づけていった。右手で背中をそうっとさすった。雄鳥はだんだんと身体を沈めて、テーブルの上に座ると目を閉じた。
おとなしくなった。
ほら、あばれんぼうの雄鳥でも寝てしまうだろ、これを一日何回か雌鳥にやって気持ちをを和らげるんだよ、するとね卵をよく産むんだ。リラックスするとね、いい卵を産むんだよ、これは企業秘密なんだ。
この話をしたからには、君は会社には行ってくれるね」
そういったら、高校生はやっぱりびっくりして、すぐにはいと返事をすると、うれしそうな顔になった。
きっといい飼育員になるだろう。二人目は女の子で、ニキビ丸出しの赤ら顔の子だ。ちょっと緊張している。
事務長が先と同じように私を紹介すると、もじもじと、自分の名前を言って、よろしくお願いしますとお辞儀をした。
内申書を見ると、内気、話をすることがにがてだが、じっくり考えて答える。とある。悪いことではない。畜産ではなく農業のコースを学んできた子だ。
「動物は好き?、家で何か飼っているの」ときくと、首を横に振って、「飼いたいけど」と考えて、「家ちっちゃい」と答えた。
うん、わるくない。
さっきの男の子と同じように、家内が三つのマヨネーズののった皿を、「どれが一番おいしいか、いってみて」とその子の前においた。
なかなかスプーンをとろうとしないので、家内が、「食べてちょうだい」というと、はっとして、匙をとり、ゆっくりと、マヨネーズをすくうと口に運んだ。口元がゆるんだ。次の皿にいくのかと思ったら、最初の皿のだいぶ残っていたマヨネーズをまた匙ですくって食べ、三階ほど繰り返してきれいにぜんぶなめてしまった。それから二皿目にさじをいれた。また同じようにきれいに食べてしまった。そして最後の皿も同様、全部食べ終わって、やっとその娘はうれしそうな顔をした。
「どれがおいしかったかしら」
そう家内が聞くと、その娘は困ったような顔をした。
「どーお」間があった。
「みんなおいしくて、わからなかった」
といった。それでさらに、「いつもうちで食べているのと違う」といった。
「どうちがうの」
「おいしかった」
「マヨネーズはどこで買ってるの」
「ドラッグストアー」
最近はドラッグストアーでも賞味期限が近い大手のマヨネーズなど、食料品を安い値段で提供している。
この子は完全に採用だ。
飼育長が鶏を持ってきた。そのときかしこまっていた女の子は、手を伸ばして鶏の背中に触れた。こちらから要求しないうちに、鶏は新聞紙の上に足をおりたたんだ。
生き物は相当好きそうだ。
後は、さっきの男子生徒と同じように、催眠術の話をして、飼育長が雄鳥を持ってきてやって見せた。その子は自分でも鳥の前で指を二本だして、背中をさすった。雄鳥はいやがりもせずおとなしくしていた。
二人の高校生には、終わった後、我が社のマヨネーズをおみやげに持たせた。
いい生徒を推薦してきた先生にもそのうち挨拶にしにいかなければと思った。
後の七人の面接は午後からである。志望者は他の業種で勤めていた人や、大学新卒の者たちである。面接の方法は高校生と同じことに加え、色々な会話をしてその人を知る。
その時の結果として、採用は三人だが、二人だけ入ってもらうことにした。その二人について書いておこう。
七人のうち五人は大学の卒業予定者だが、みな背広を着て、返答は一律、特に地元に近いところの大学生は鶏なんてという顔をしている。それにマヨネーズはなんでもいいようだ。驚いたのは大都会で育った学生は、むしろ鶏をおもしろそうに触っていた。しかし、受験した大学生にうちの会社にあうような個性を持った者はいなかった。結局合格にしたのは転職者で31の男一人と39の女一人である。
二人ともさすがに経験は豊富で、マヨネーズの試験で、同じものとしか感じられないと言った。鶏をまえにして鳥に二人とも話しかけた。動物たちに話しかけるというのは以外と重要なことで、言葉の意味より動物たちは話しかけた人間の表情、動き、声の抑揚、そういったもので、自分の行動の判断を下している。もちろん本能的なものではあるが。
その二人、男の方はうれない漫才師で、相方がスナックか何かを開くということになり、自分は都会から離れて、農業でもしようと考えていたところに、うちの求人をみたという。女性の方は、旅の雑誌の編集部にいて、その雑誌が廃刊になり、やはり地方の会社の広報に入ろうと考えて我が社の求人をみたわけである。彼女は言葉に長けていて、少なくとも十数カ国の挨拶などの基本的な言葉がすぐに口からでてくる。コミュニケーションには重要なことである。
ということで高校生の原田友之と相田白子、漫才師だった栗田啓治、恩田睦子が社員になり、その五年後の今、かれらは我が社の中心となる人物へと育ってきたのである。
一つには、卵の味がさらによくなり、栄養分の多いものとなった。高級料理屋からの引き合いもあり、そちらの部門も独立させることになった。もちろんマヨネーズの材料として使用した残りを卸すわけである。マヨネーズそのものの売れ行きがとてつもなくよくなり、もう一つラインをつくり、今年はそちらの要員を補充した。
なぜ売れ行きがよくなったか。、そのときはいった原田と相田の飼育の改革と、工場の生産ラインの改変である。鳥の牧場の半分を耕す方法を考案したのは相田である。原田はというと、農業高校の後輩を工場でアルバイトさせてくれといってきて、それが定着して、工場の稼働が増えたのである。さらに栗田と恩田の宣伝力である。恩田のSNSと紙媒体の宣伝力、栗田の大都市への売り歩きのおかげである。
そして、これからの話が、会社の秘密でもあり、会社が永久に続く保証となったできごとである。
栗田は我が社のマヨネーズをもって、東京や大阪の地方の名産品展で販売をのばしていたのだが、勤め始めて三年目、おかしなことを報告してきた。
「社長、東京でも大阪でも、我が社のマヨネーズを必ず店の開店と同時に買いに来る女がいますよ、おそらく同じ女だと思うのだけど、いつも何人かの女性をつれてきて、爆買いするんです」
「なに、その爆買いって」
「一人で百本とか買って、手提げ袋に入れてうれしそうに持って帰るんです」
「そうなのか、一回展示会があると、数百本ほど売れるので不思議だと思っていたんだ」
以前は百本も売れればよく売れたと喜んだものである。我が社のは五〇〇グラムで千五百円のものと、千円のものをだしている。それぞれに無塩と通常の物の二種類がある。二日で百本売れると、10万から15万の売り上げで、デパートに納める費用と出張費などを考えると、お涙ほどのもうけだが、名前と味を知ってもらうとてもいい機会になる。それが、五百本だと相当な儲けが出る。
不思議なのは無塩の物が売れる。全く塩が入っていないので、自分で塩味を調整できる。スパイスを目立たない程度加味しているので、無塩でもも食べ気になるので、無塩食を余儀なくされている人には喜ばれる。それにしても、通常の三倍ほどの価格の物をなににつかうのだろう。うちのマヨネーズの賞味期限はながくない。一月ほどである。
「展示会が次にいつ行われるか必ず聞いてくる女性がいます」
広報担当の恩田が言った。
「どこから」
「どこでしょう、わかりません、わが社のホームページの質問欄ですけど、署名がありません」
「返信はできるんだろ」
「ええ、必ず、わかっている限りのイベントを知らせています、送り先を教えてくだされば、サンプルをお送りしますよと書いたことがあるのですが、それに関しては返信がありませんでした、それで、SNSでは住所や名前を書きたくない人もたくさんいるので、我が社の住所と、電話、それに、広報の私の名前などを書いて送ったのですが、連絡はありません」
「女性ってわかるの」
「ええ、書き方が、女性言葉です、今の若い女の子の文章の書き方ではありません」
「栗田のイベントに来る女性と同じなのかな、栗田はその女性と話したことあるんだろ」
珍しく栗田が困ったという顔をした。
「それが、ないんです、連れてきた女性たちは一生懸命買うのですが、その女性は、その場から離れてしまうんです、それで、買ってくれた女性にどこからいらしたのかきいたんですけど、ただ微笑んでいるだけで、何もいいません」
「いつもそうなの」
「そうなんです」
「買う人たちはどんな感じの人たちかな」
「うーん、年は30代ほど、すごい美人ではないのですけど、みなそれなりの整った顔をした人たちで、色は白い方ですね、背丈は百六十前後、買うとそそくさと離れて待っている案内してきた女性のところにいってしまいます」
「恩田君も栗田といっしょにいったことあるだろ、見たの」
「ええ、私も声をかけようとは思ったのですが、そういう雰囲気じゃないので、イヤに思われるとまずいから、見ているだけにしていました、私は、ネットで問い合わせてくる女性に間違いないと思います」
「その女性は買う人たちより若そうかい」
「若いですね、観光旅行のツアーガイドさんのようにみえました」
「社長、会社に直売所を併設しませんか、恩田さんとも話していたんです」
栗田が言った。
「便利なとこじゃないけど、客が寄るかな」
「小さくてもいいとおもうんですよ、メロンなども農家さんに一緒においておいてもらうと、なおいいと思いますよ、それに、鶏牧場や工場の見学もいいでしょう」
「そりゃあいいかもしれない」
その二人のアイデアを、会議の時に話したら、マヨネーズレストランのアイデアまで飛び出した。
いきなり、そこにいくのは早いだろうが、いずれ、それも面白いかもしれない。マヨネーズソフトクリームなんて言うアイデアもでてきた。それぐらいなら直売店でできるかもしれない。
田原街道ぞいに百坪ほどの土地を手に入れた。会社から歩けないことはないが、ちょっとかかるところだ。観光客目当てなら、街道沿いにつくったほうがいい。さらに、地元の工務店に頼んで、壊す予定になっていた築二百年の屋敷を移築し改装することにした。そのようなことも地元では評判になり、しかもマヨネーズだけではなく、地元のメロンや海産物を、個人に限り場所を貸して販売してもよいことにした。マヨネーズソフトなるものもつろうと広報と料理の連中がアイデアをだした。地元で評判になるとだんだんと広まるものである。駐車場は広くとった。
会社のある藤尾山は二百メートルほどの小さな山だが、自然歩道もあり、歩く人も多い。頂上からは太平洋遠州灘が一望できる。衣笠山などほかの山にも連なっていて、気楽にいけるいいハイキングコースである。また渥美半島の先には観光地もあり、車で行く人も多い。知多半島から連絡船もくる。利用する人も多いだろう。そういった人が立ち寄ってくれるようになればいい。これは広報担当の栗田と恩田による計画である。
半年後、ふたを開けてみると、考えている以上に盛況だった。はじめは地元の人が多かったのだが、一年経ったときには、テレビの旅の番組や、肥料を使わない農作物が話題になるように、昔ながらの放し飼いの鶏牧場が知られるようになり、県外からも、車で訪れる人が増えた。もちろん渥美半島の観光を兼ねてくる人たちである。
栗田はそのあとも、大都会のデパートや大手スーパーでの出張販売をやっていた。もう一人ではなく、後からは行ってきたスタッフを連れて回った。
名古屋のデパートで、渥美の特産展をやったときである。会社では、月末の決算の帳簿合わせと、次へ向けての戦略会議をしていた。恩田はもちろん、事務長、飼育長、工場長、研究部門長、それに家内と、数人の補佐役たちが残っていた。終わった後、タクシーを呼んで町の飲み屋に食事にいく。毎回違う店に行き、マヨネーズをもっていって宣伝もしてくる。
今月も売り上げはのびていた。
「調子がいいね」
「まだ、生産ラインはフル活動していませんから増やせますよ」
「卵の方はどう」
「かなりの数、料亭に卸していますが、マヨネーズにまだまだまわせます」
「それじゃ、広報の方よろしくたのみますね」
「ええ、海外のみやげにどうかと思って、今中部空港で試し売りをしています。もちろん試食もしてもらっています」
そのような話をしていると、名古屋まで行っていた栗田が車で会社に帰ってきた。
「ごくろうさま、どうだった」
「いや、やっぱり七百近くも売れました」
ついて行った新人も「びっくりしました」と本当に驚いている顔をした。
「たりたの」
「ええ、何となく売れそうな気がしたんで千本もっていきました」
会社の車は冷蔵装置がそなわっている。
「相変わらす、勘がいいね」
「社長、いつもくる女性がやっぱり五人の女性をつれてきて、たくさん買っていきました、今回こそは話をしようと思っていたら、あっちの方から声をかけてきました、直売所の案内を持ってわたしの方にきたんです、なんだか怖いような気がしました」
「なんで」
「なんででしょう、冗談が通じそうにもない、ちょっとおにんぎょさんのような」
「まあいいや、それで、どうしたの」
「ちょっと、小高い声で、ここでもマネズ買えますか」といって、パンフの直売所を指さしたんです。
それで、「ここで作っています」と写真に写っていた隣の工場を指さしたんです。そうしたら、珍しくにこっとして「明日いきます」
と離れていってしまいました。五人の女性たちには、こいつがうまく売ってくれました」
「そりゃごくろうさん、どんな感じだった」
「話をしませんでしたけど、指さして、百、百って言うもんだから、五本おまけにあげたら、もう五十っていうから、さらに五本のおまけをあげました」
「こいつのおかげで、いつもよりたくさん売れましたよ、おまけってのはおれも気がつかなかった」
「そりゃいいね、おまけ用の小さいのもつくろうか」
「いい、アイデアです」
「それでその女性いつ来るんだろう、明日って言ってましたが、いつも一番乗りだから、開店時間に来るんじゃないですか」
「まあ、よかった、それじゃ、会議を終わらせて、食いにいくか」
会社を上げての月一回の打ち上げ会である。
私と家内、それに当直の者のためにタクシーを呼んだ。多くは町のなかにすんでいるので自分の車で帰り、予約しておいた店に八時に集まっていつものように食べ飲んだ。
そろそろお開きと言うときに、ドン大きな音とともに、レストランの建物がゆれた。
「なんだ」
店の中の客がみんな立ち上がった。建物の揺れはそれ以後起きない。
店長が店の中に出てきた。
「地震じゃありません、店の物がたまたま外にでていたら、空から火の玉がとんできて、消えていったのをみたということです。どこかに落ちたようです、ここは大丈夫です、今テレビでやると思いますので、わかったらお知らせします」といった。
恩田がスマホをあけた。テレビのモードにしたようだ。
NHKの番組に字幕がでた。渥美半島上空で火球が見られ落ちた模様、とあった。
「ほんとにこの辺のようですよ、落ちたようですね」
消防車のサイレンが聞こえてきた。
「火事でも起きたのかな、店長、どっちの方角に落ちたかわかりますか」
会計をしながら聞いた。
「山の方ですよ」
「そりゃ大変だ、うちの工場のあるほうだ、みんなはとりあえず家に帰ってよ、なんかあったら連絡するから、なにもなければ連絡しないから安心して寝てください」
わたしはそいう言ってみんなを帰し、家内と当直の連中とタクシーで家に向かった。自宅は工場に隣接している。
救急車が何台か藤尾山の方に向かっていく。会社は麓である。
乗ったタクシーの後ろから救急車がきた。
「事故があったのかな」
家内に話しかけると、タクシーの運転手が「連絡では家が燃えているとか、人が怪我したとかはいってなかったよ」
と教えてくれた。
タクシーは会社の脇についた。セキュリティー会社に委託している守衛さんがでてきて、鶏牧場や工場は問題ありませんと、つたえてきた。
「ごくろうさま、ありがとう」
救急車は会社を通り越して、先にすすんでいった。消防車も走っていく。
家内と自宅にいき、テレビをつけた。ローカルチャンネルではケーブルテレビ局の中継車が映っている。緊急中継とある。
消防車が集まっている前で、アナウンサーが、「隕石のかけらが、藤尾山に落ちたようです、空中で小さな爆発があったようで、いくつかに割れた可能性があるようです、家や人に何かあったという報告はありません、まだ詳しい情報がはいっておりませんので、様子が分かり次第お知らせします」
と言って宣伝になった。ありゃ、内のマヨネーズの宣伝だ。
長い宣伝が終わると、消防車が持ち込んだ投光器が山の中腹を照らしている。
「斜面の木がなぎ倒されているようです、隕石が落ちた跡でしょう。警察に確認したところ、しばらく立ち入りを禁止するそうです、自然歩道はしばらく入れません、すでに隕石の専門家がこちらに向かっているということです、火事も起きていないことから、中継をここで中断します」
という現場のアナウンサー殻の報告だった。
「だいじょうぶのようだね」
「どのあたりかしら」
「海側の斜面かな、明日いってみよう」
明くる朝、家内と隕石が落ちたところにいってみるつもりで車ででかけた。消防車はもうなかったが、市や県の名前のはいった公用車が何台か止まっていた。道の脇に止めて山を見上げると木がなぎ倒されているところが見えた。
藤尾山には神社などもあるが、そいういったところには影響がないようだ。
山の中から数人の人がでてきて、市の車にのりこもうとしたので、そばによって近くに住むものだと言ってはなしかけた。市の環境課の人だった。
「あ、マヨネーズの社長さん」と、わたしのことを知っていた。
「高さが三メートル、幅や奥行きも三メートルほどの大きな隕石で、とても珍しいということです。研究者がすでに到着して調べています、市としては、市の自然文化財にして、観光資源にする予定です。しばらくは人が入らないように柵を作る予定です、
なんでも、小惑星のかけらのようで、珍しいもののようです」
「そうですか、いずれにしても被害がなくてよかったです」
様子が分かったので家に戻り、出勤時間に会社に行くと、すでにきていた恩田と栗田が「大変です」と顔色を変えて走ってきた。
「隕石なら見てきたけど、被害はないようだよ」
と教えたのだが、栗田が、
「さっき、ご自宅に電話をしたのですけど、隕石を見に行ってたんですね、うちの直売場の前の広場に高さ1メートルほどの石がめりこんでいましてね、コンクリートの破片が飛び散っているんです」
彼らは通勤に田原街道を通って来る。
「隕石が落ちたんです、ニュースでも空中で割れたようだといってましたよね」
たしかにそういっていた。
「行ってみよう、どのみち栗田が言っていた女性が来直売場にるんだろう、何時頃くるかわからないよな」
「ここでも一番乗りですよ、かなりはやくくるんじゃないかないちばんのりですよ」
栗田と恩田といっしょに直売場にいった。まだアルバイトの人は来ていない。
移築された古民家の前の広場に黒っぽい石がでんとめりこんでいる。
「こりゃ、隕石だな、誰の物になるのかな」
「隕石は、公道なら拾った人のものになるようですし、私的な土地なら、その土地の所有者になるようですよ」
恩田が説明してくれた。
「なんで知ってるの」
「隕石には興味があって、ちょっと前に千葉の方に落ちたことがあるでしょう、かけらがマンションの庭でみつかったりして、そのとき、誰の物になるのか調べたことがあるんです」
「それじゃ、これ我が社のものだね」
「そうですね、言い宣伝になります、そのまえに、これが昨日落ちた隕石の一部だということを証明してもらわなければいけません」
「すぐ、市の方に連絡してよ、環境課の人が藤尾山の隕石をみにきていたよ、市の記念物にするんだって」
「わかりました」
恩田がスマホですぐに連絡をいれた。数分で市の車がきた。さっき藤尾山の隕石落下現場であった人がのってきた。
「あ、先ほどはどうも、ちょうど市役所に帰るところでした、市の方から連絡がありましたので、よりました」
向こうから挨拶してきた。石を見ると「こりゃ、隕石ですね、先生」、と車の中の人に声をかけた。
その人たちが車から降りると、環境課の人が大学の先生だと紹介してくれた。
「おー、立派な隕石だな」
二人の先生は石に近づくと、「サンプルをとらしてもらっていいですかね」ときいたので、「お願いしますというと、目立たないところにかなづちのようなものを使って少し削った。
「建物には被害がなかったのですね」
「ええ、建物そのものは大丈夫そうですよ、まだ中を見ていないけど」
我々は鍵を開けて中に入った。並べてあった商品がちょっと乱れていたが、特に問題はなさそうだ。
「藤尾山をさがすと隕石ののかけらがおちているな」
専門家の先生はそういいながら車にもどった。
「詳しいことがわかったら、お知らせします、それまでこの石にはさわらないようにしていただいたほうが助かり」
「ええ、周りにロープを張りますよ、ここに置いておいていいなら、管理を厳重にして、展示しておきます」
彼らは市役所にもどっていった。
「すごい贈り物ですね、いい宣伝材料になります、これを見にくる人もいますよ」
栗田がよろこんでいる。
「隕石マヨネーズとでも名前をかえますか」
「いや、いままでどおりでいいよ、自然と噂が広まって、そんなふうに呼ばれるかもしれないけどね」
アルバイトの主婦たちがやってきて隕石を見て驚いた。野菜やメロンを運んできた農場の人たちもびっくりしている。
やがて、開店の時間になると、栗田が、あれ、と驚いた顔をした。
田原街道を女性が歩いてきて直売場に向かってくる。
「あの女性だ、歩いてきたということはどういうことだろう、バスでもなさそうだし、車を他のところにおいてきたのかな」
彼は女性にちかよっていった。
「よくきてくださいました」
女性の方も気がついたようだ。
「ここですか」
「はい、こちらが社長の長田です」
栗田は私を紹介した。
「いつもありがとうございます」
私は名刺わたしおじぎをした。
彼女うけとるとちょっとぎごちなくおじぎをしたが、にこやかな表情ではない。
「ここのマヨネーズはすばらしいものです、わたしどもつくることもできません、これからもお願いしたいのですが、どのように作っているのか見ることはできないでしょうか」
「ここは直売所で、会社は車でちょっと行ったところです、そちらにいきますか」
会社の場所をパンフレットの地図でおしえようとすると、
「はい、わかっています、お願いします」
とうなずいた。
「車ですか」
「すぐに行きますので、先にいっていていただけますか」
女性はそいういうと道の方にもどっていこうとしたので、
「昨日の夜、隕石がおちたのはごぞんじですか」
と聞くと、ふりむいて、「ええ」と簡単に答えて道路に出て行った。
我々は狐に摘ままれたような気持ちになって車にのった。道に出て女性の姿をさがしたのだが見当たらない。
「どこにいったんだ」
栗田が首をひねっている。
「なにできたのかしら、興味ね」
恩田がなんだか心配そうに車の後ろを見た。
直売場から会社まで車だと二分とかからない。
会社の前の駐車場に車を止めると、入り口のところに女性が立っている。
「もうきていますよ、どうやってきたんだろう」
「車もありませんね」
私は背筋がちょっとぞっとした。ともかく車から降りて彼女の方に歩いていくと、彼女は「よろしくお願いします」とまたおじぎをした。
「材料はどのようなものを使っているのですか」
そう聞いてきたので、「新鮮な、元気な鶏の卵をつかってます、よければ、鳥の飼育場をごらんになりますか」
そきくと、うなずいたので、相田を呼んだ。今では飼育場長として、いい鶏をそだてている。それに工場を案内してもらうために原田を呼んだ。私は、五周年記念の年に入った四人を田圃の四人衆とよんでいる。私の名も長田なので田に親近感がある。栗田も恩田もみな名字に田がつく。今では彼らがこの会社をもりあげていてくれる。田を耕す四人である。
「相田といいます、彼女が鳥の牧場長です、それにマヨネーズ工場の管理をやっている、原田です、うちはマヨネーズに加える物は企業秘密ですが、あとはすべてお教えしています」
「楽しみです」
「それじゃ、えーと、お名前は」
名前をきいていなかった。
「星田です」
田がつく、いい名だ。
「星田さん案内してくれるかな、丁寧ににね」
相田と原田に彼女をまかせた。
相田は星田という女性を鶏の放牧場と鳥舎に案内した。
鶏たちはクローバやヘビイチゴのはびこっている放牧場で、歩きながらミミズをつつくもの、うわっている繁みでやすむもの、砂場でうずくまってからだをこすっているもの、いろいろいる。
「この鳥は特別なものですか」
星田が聞くと、相田は「いえ、普通のハクショクレグホンです、ただ放牧地の土にはいろいろな物を加えて耕したものです。放牧地の半分は新たに耕して一年おいておいて、次の年はそちらに放牧します。
女性は隅々まで見て回り、鳥をだきあげるた。鶏はしずかにだかれていた。
「おとなしい鳥ですね」
「催眠でおちつかせています」
「それはなにですか」
相田は鶏に施す催眠術について話した。
そのあと原田にバトンタッチした。原田は、工場の中を案内した。白衣をつけてもらって、みなが働いているところをみてもらった。
「油や酢を入れるタイミングなどは機械がやっていますが、そのときそのときによって、勘で調整しています。いつも同じ食用油と酢を使っていますが、配合などはいつも同じとはかぎりません、菜種油と酢は知多半島の物ですが、購入したときに必ず出来上がりの状態を聞いて、調整のためのデータとします、機械は人のいう事を良く聞いてくれますが、自分では考えてくれません」
「勘はどうするとよくなりますか」
「前の担当者と一緒に長い間働いて覚えました。そのあとは、機械の廊下具合なども関係するので、自分で新たな勘をつくりあげます。今若い人と一緒にやっています」
「催眠術と勘でマヨネーズをつくっているのですね」
「はい」
工場の中を細かく見て回った女性をつれて、相田と原田が事務所に戻ってきた。
「ごくろうさん」
二人に声をかけて、「どうでしたか」と女性にたずねた。
「大変参考になりました、催眠術と勘が重要なことがわかりました、おねがいがあります」
「なんでしょう」
「相田さんに催眠術をかけてもらいたいのです」
「ああ、ここでもできますよ、鶏つれてきて」
と相田に声をかけると、星田さんは「いえ、わたしにかけてください」
とまじめな顔をして私を見た。
かなりびっくりしたし、それを聞いた恩田と栗田もヒャといった顔をしている。
ところが相田が「いいですよ」とうなずいた。
「それじゃ、向こうの会議室の方で」
彼女を会議室に連れて行った。。
相田に「だいじょうぶかい」とこえをかけると、「鶏と同じようにします」とけろっとした顔で言ったのにはに、なんとも頼もしいと、尊敬の目で彼女を見てしまった。
女性はいすにこしかけると、相田は彼女の前にこしかけた。
「それでは、私の日本の指を見ていてくれますか」
「はい」
女性は差し出された相田の人差し指と中指をみた。相田は指を微細に振動させ、少しずつ女性の目の前の方に近づけていった。
すると女性の目が見開かれた状態になり、まばたきをしなくなった。と、みると、鼻が顔の中にめり込んでいき、耳も、口もみなただの穴になった。目まん丸な穴になっている。
私は目をこすった。一緒に見ていた恩田と栗田が声を上げられない状態だ。
「もうやめなさい」
私もやっと相田に言った。相田がはっと気がついて、手をもとにもどすと、女性の顔は、前の女性の顔だった。みんな催眠術にかかったようだ。
女性が言った。
「催眠術はすごいですね、頭の中がすーっとして、みなわすれてゆったりしてしまいました。私を見ましたでしょう」
その言葉に、我々は顔を見合わせた。
「この会社の無塩のマヨネーズを、一年間で一千万本購入契約できますか」
といった。
「あの、星田さんはどこの会社の方なのでしょうか」
「会社じゃありません、アリャリサリという星です、意味は地球と同じです」
なにを言っているのだろう、と私だけではなく皆思った。
すると、その女性の顔がさっきみた、卵形の顔にに目鼻口耳に穴が開いただけのつるんとしたものになった。
どうしたらいいのだろう、逃げるのか、誰も動けない。すると、
「もしかすると、隕石と関係があるの」
恩田が言った。
「あなた方が、この星で初めて異星人と接した初めての人となるのです」
星田と名乗った女性は地球人ではないのだ。
「恩田さん、よくわかりましたね、あの隕石はただの隕石ではありません、我々が目印のために落としました。小惑星の一つです、中に通信装置が組み込まれています、我々がこれから地球にくるときの誘導波が発せられています。
「あなたの乗ってきた宇宙船はどこにあるのですか」
「宇宙船はここの太陽系の外に浮かんでいます。そこから、着陸船にのってきますが、人の目にはみえないでしょう、我々をおろすとすぐに母船にもどります」
「東京や大阪のデパートにきたときもそうですか」
「はい、十人乗りの着陸船です、観光客をのせて地球にきました。もう大昔からきています。いろいろなマヨネーズを買いましたが、この会社のマヨネーズは特別です、連れてきた観光客はおみやげに必ずたくさん買いました」
「わたしには意味がよくわからないのですが、なぜ地球にきてマヨネーズを、しかも無塩マヨネーズを買うのですか」
「どのように使うのかお見せします。一本もってきてくださいな」
栗田がとってきた。
星田さんは立ち上がると、マヨネーズをロボットのようなつるつるの手のひらに出すと、手をこすりあわせまんべんなくまぶすと、またマヨネーズを手のひらに出して、顔に塗り、毛の間にもぬりこんだ。腕まくりをすると腕や肘のところにも塗った。
「匂いもとてもいいものです、それに、肌や関節にとても効果のある化粧品です」
化粧品と言った。なんだ、それは。
「我々の身体は、地球で言うと金属に属するような化学物質でできています。地球人のからだの細胞は脂質、蛋白などででえきていて、水を媒体としていますね、我々の細胞は金属物資の化学反応で生きています。体の表面はさびないように油がでるような仕組みにはなっていますが、補完する化粧品は大事です。化粧と言うより、健康維持といったほうがいいかもしれませんね、アリャリサリ星では、地球で作られるマヨネーズがとてもいい健康保持のための薬になるのです、観光ガイドを長く務めてきましたが、われわれの星で主人がマヨネーズ輸入会社を設立しました、ゆくゆくはわたしどもでも作りたいと思います、この会社のマヨネーズはとても高く売れます。それで輸入したいのです」
それを聞いていた我々はただ唖然としていた。しかし栗田はこのときとばかり、
「いくらでもお作りして、お売りしたい、だけどおっしゃった数は、新たに工場をつくらないとつくれません、出資していただけるなら作りますよ」
と商談をはじめた。
星田さんは、「我々の星は、金がたくさんとれます、地球にきたときはそれを売って、お金に換えています、ですから新しい工場を作る資金はいくらでもできます」と言った。
「わかりました、とりあえず、その工場ができるまでは、今の工場ををフル活動させますので、できたマヨネーズは買い上げてくれますか」
「もちろんです、いまここに一億円あります、とりあえず、手付け金です、卸値で無塩マヨネーズを売ってください」
と、鞄から一万円札を一万枚机の上に載せた。
「本物ですよ」
と彼女は言った。
「本当は私の星で、マヨネーズを生産したいと思っていたのですが、土が金属ですので、鶏はここのように放し飼いできません、地球の土を運び、草を生やさなければなりませんのでちょっと難しいと思いますし、大気には肝心な酸素は少ないので、基本的に無理です。金属の身体を持った我々には、酸素があるとさびがでるので危険です。我々の体の中は金属元素の放射性同位元素により、発熱やエネルギー生産をしています。地球の原子力発電のようなものでしょうね、全く違う世界です」
「地球では、会社の収入にたいして、納税義務もあります、そういった問題はどうしましょうか」
「まだ、私たちの星の存在は黙っていただいた方がいいと思います。全国のコンビニやスーパーに安くおろしてくだされば、我々が買いにいきます、移動は瞬間にできますので、もんだいありません」
彼女がそういったとたん、三人の異星人が目の前に現れた。みなに多様な顔をした女性だ。
「こんにちは」と挨拶をした。
「隕石の中の誘導装置は、地球上ならば、我々個人を目的のところに移動させてくれます。そのためにあの隕石をおとしたのです」
「それじゃ地球が簡単に乗っ取られる」
恩田が小声で言った。
「私たちは、宇宙条約で、開発途上星の進化をじゃましたり、その星を占領することを禁止されています。それを破ると自分の星は破壊され種族はほろびます、ですからそのようなことはできません。地球は進化の第一段階のレベルです。百のレベルまでいくと、宇宙連盟にはいれます」
なんだかSFの世界になってきた。
どうしたらいいのだろう。
原田が「それで、我々に、お金以外の何か利益がありますか」と聞いている。
「あの、催眠術というのは我々にはわからない技術です、どうでしょう、その技術を、我々の星で、広めてくれませんか、リラックスしますので、これも健康のためにいい、リラクゼーションの会社がつくれます。我々の星にきてみれば、この星にない技術などもあると思いますから、それを拾得すれば地球の進化がすすむのではないでしょうか」
「私いってみたいな」
相田が目を輝かせた。
もう自分にはついていけない。
「わかりました、この四人の田にまかせますから交渉してください」
四人の異星人と、四人の田が会議室で協定のはなしをはじめた。
「お茶をいれてくるよ」
私はその場から逃げた。いてもなにもわからない。
会議室からでて、給湯室にいこうとすると、事務をやっていた女性社員が、「なんでしょうか」ときいたので、「お茶を入れにいくんだ」というとびっくりした顔をした。
「社長、わたしがやります」と彼女が立ち上がった。私はそれを手で遮って、「いや、これからはわたしの仕事はこれだよ」
美味しくお茶を入れるにはどうしたらいいんだろう。
マヨネーズの宇宙


