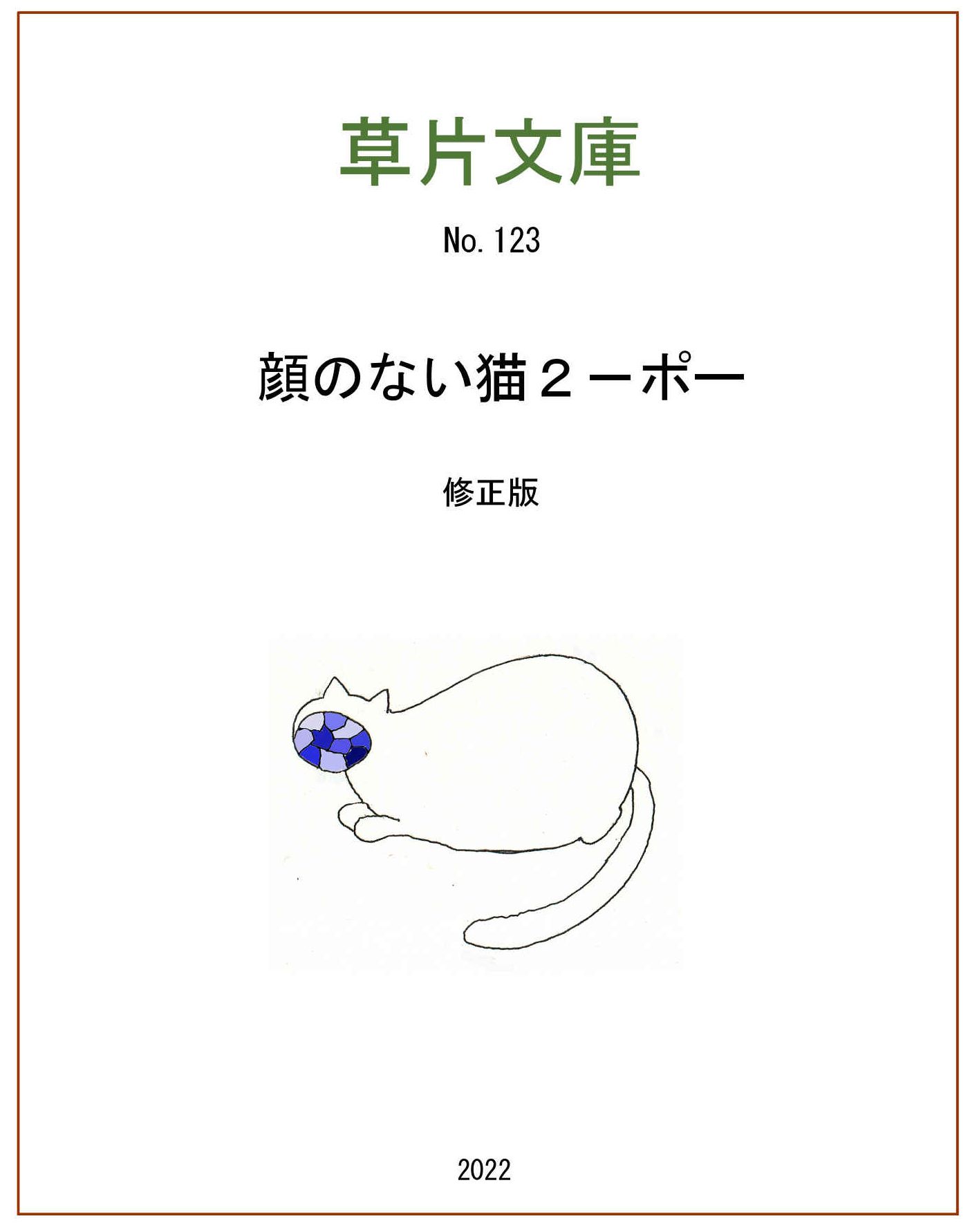
顔のない猫2 ポー
不思議な小説です。縦書きでお読みください。
真夜中のことである。廊下をなにかが歩く音がする。いや、音はほとんどしない。音がしないのだが何かがあるいている。そう、猫のような存在だ。玄関も鍵がかけてある。窓もすべてロックしてある。我が家に泥棒が進入しようとたくらむなら、玄関の鍵をうまくあけるか、ガラスを切り抜くかするしかない。ということは、泥棒が入れないことはない。もし泥棒が入ったとしたら、しかしいくら音を立てないように歩いたとしても、五十年経っている我が家の廊下は、ミシミシまでいかなくも、みし、くらいはいうだろう。ともかく、今廊下を歩いているのは人間ではない、ほかの生き物だ。
とすれば猫だけだろう。犬があんなに足音を忍ばせて歩くことは無理だ。
だが、猫がどうやって我が家にはいれるのだ。小ちゃい庭付きの一戸建て。五十年前に両親が買って、その両親はもういない。一人っ子の僕は、自由気ままにこの家をつかっている。
僕は図書館に勤めている司書である。司書になるということは、文学を目指して大学にはいったと思われるかもしれないが、生物学、特に動物生態学に興味を持もって、生命科学を勉強した。先生にでもなろうかと教職課程をとったのだが、いろいろやらされる中で、それとは別に、司書の資格をとるためのコースがあり、それも受講した。中学校の先生、もしくは図書館の司書になり、できれば自宅から通えるところに勤務先を探して、やっかいな家庭など持たずに、好きなことをして老いていくのがいいなどと、そのころの若者らしくない考えにはまっていた。というより、社会性のない性格であることは自分でもわかっていた。ということは、教師には向かない。なぜ動物生態学者にならなかったのか、と聞かれたりもするが、能力もないが、何よりも動物生態学者に必要な、体力、筋力がない。今はファーブルのように、庭先の虫を観察して、生活費をかせげるわけはない。山に登って、穴の中にはいって、未発見の動物を探すとか、好きなカマキリを全国に追いかけて、藪の中にはいっていくとか、大変な作業である。
体力の面からいえば、図書館で本の整理をすることはできる。だが、今度はそちらの知識が必要である。本を読むことは好きであったし、理系の本を整理するには僕のような勉強をした者も役に立つだろう。本の装丁にも大変興味あった。
それが、幸運にも、大学卒業の年、家から通えるところにある、市立の図書館のポジションに空きができ、市の試験にも合格して、うまく潜り込めたのである。そこでわかったことは、本は重いと言うことである。やっぱりどこに行っても筋肉の力は必要だなと思った。
勤めて五年目、図書館の本についてはかなりわかってきたし、面白そうな本はずいぶん読んだ。そこで自分でも自分の家を、自分の気に入った本で埋めたいと思うようになった。
幽霊や心霊現象の本は、子もだまし程度のものや、金儲けの為に書かれたものはたくさんあるが、そうではなく、そこに人間の奇妙な生態が読めるような本が面白くなり、集めるようになった。ともかく、若い頃より、本の知識はふえたし、筋力だって前より強くなっただろう。だから泥棒なんて怖くはないが、音のしない生き物の気配はやっぱり怖いものである。
怖いというのは自分の中にあるものだと、自分に思いきかせて、電気をつけずに、ゆっくり、音を立てないようにベッドから降り、鍵のかけてない自分の部屋の戸を少しあけて廊下をみた。
おっと、黒い影が自分の足下から、しゅっと部屋の中にはいってきた。
猫だ。やっぱりそうか、と安堵した。どこかの窓を閉め忘れたのかもしれない。
黒い影は、ベッドの脇で、上を見上げ尾っぽをあげたたずんでいる。
何を見ているのだろう。
どこぞの家の飼い猫か。雄猫は往々にして、夜中に歩き回り、自分の家より居心地のいい家に居着いてしまうことがある。よく聞く話である。
影の猫がにゃあとないた。おなかが空いているのかもしれない。
部屋の電気のスイッチを押した。
やっぱり立派な黒猫だった。立てていた尾っぽを下ろしている。長い黒い蛇が床に伸びている。おちゃんこだ。こっちを向いたようだ。目を凝らしたとたん、生まれてはじめて、「きゃー」と声を上げてしまった。「うわ」「え」「なに」でもなく、ともかく喉から「きゃー」がでた。鳥肌が立った。
黒猫の首から上がなかった。頭があるように見えたのは自分の思い込みのようだ。顔がなにもないんだ。首の切り口が見える。図書館の解剖の図を思いだした。気管の穴の後ろには、食道の穴があった。大小さまざまな穴は血管の穴だろう。赤い血が詰まっている。
首のない猫がたちあがって、ドアの脇で突っ立っていた自分のほうに歩いてくる。そばにきた。足に何か擦り付けられた。見えない猫の顔だ。
ということは、顔はあるんだ、という事を認識した。
顔が透明なんだ。
手を猫の頭の当たりに当てると、あった。猫の毛の感触だ。耳も触れる。両手で顔を包んでみると、髭も鼻も皆振れることができた。触れるということは安心するものだ。自分の気持ちが落ち着いた。
なんで頭が透明なのだ。
黒猫はにゃあとまともに声をあげて、またこすりついた。
何か食べたいのだろう。猫用の餌などはないが、鰯の缶詰や削り節などは常備してある。
「おいで」と、猫によびかけて、廊下にでて電気をつけた。首のない黒猫は自分のあとをついて、一階のキッチンにおりてきた。
缶詰をあけて、皿に出してやったら、「うまうまうま」と声を上げて食らいついた。長い間食べていなかったのだろうか。人になれているから飼い猫だったことは確かだ。よく聞くのは、長距離トラックの荷台に入り込んで寝てしまい。何百キロも離れたところに連れて行かれてしまった猫のことだ。それでも自分の家に戻ることがあるという。そういう迷い猫の可能性もある。写真を撮ってネットに乗せて、飼い主を探してやろう、そんなまともなことを考えたのだが、顔がない。写真は撮れない。
顔のない猫が迷い込んだなどと言うと、おかしくなったんじゃないかといわれちまう。
なぜ顔が透明なんだ。異常現象の本を読んでいると、透明になることなども出てくることがある。しかし、顔だけだ。何が起きたんだ。
お皿に首を突っ込んで、鰯のオイルづけを無心で食べている猫を見ていると、口に鰯が入ると透明になり、首の切り口の食道の穴のところにくると、ぐちゃぐちゃの鰯がはいって、ぷくっと膨れる。そして見えなくなる。
あっという間に一缶食べおえると、顔を洗う動作をはじめた。片一方の前肢が顔があるだろうと思われる空間をこする。すると、首の切り口のところに薄い膜ができて、食道や気管、血管などの姿が見えなくなった。どうしてだ。
生々しさがちょっと消えた。
今度は前肢をなめているようだ。左前足の先が持ち上がり、毛が濡れてすじになる。おいしかったのだろう。
僕は夜中であって、寝ているところを起こされたことを思い出した。三時だ。今日は月曜日、図書館は休みだ。いくらでも寝坊はできる。もう一度二階の寝室にいこうとキッチンをでた。黒猫は好きなところで寝てくれていいと思っていると、あわてて自分ののあとをついてきた。追いつくと、僕と一緒に部屋に入った。ベッドにはいると、黒猫も飛び上がり、足下でうずくまった。
掛け布団の上から、足下の黒猫を見ていると、気持ちよさそうにぎゅーっと伸びて、ふすーと寝息をたてた。くるっとまるまった。両前足をぎゅうっと首の上、おそらく顔をだきしめた。前足が十字に組まれて宙をしめつけている。
僕もねむくなってきた。
朝の目覚めは気持ちがよかった。天気がいい。朝日がカーテン越しに部屋をてらす。
よく寝た、もう八時半である。
ふっと思い出して、足下を見ると、首のない黒猫が、びゅーっと伸びていた。顔が見えないと、なんだか死体のようでいやなものだ。それに表情がわからない。毛に覆われた猫の顔でも、目の動きで表情はわかるものだ。いかに顔、特に目が大事なのかわかる。毛のない人間はさらに顔の表情筋がその人の気持ちを露わにする。それなのに人の気持ちが読めない人が多いのには、まだまだ人間は進化の途中も途中ということだと思う。先は長い。
パジャマをぬいで着替えをしていると、首のない黒猫がベッドの上に起きあがり、前足をそろえて伸ばし、お尻をあげた。気持ちが良さそうだ。
黒猫は我が家に居つくつもりのようだ。
そうか、猫の餌も買いにいかなければいけないな。コンビニが近いが、少し歩くがドラッグストアーの方がいいだろう。
今日も自分用のツナフレークの缶詰をあけてやった。ずいぶんよく食べる。人間用の缶詰をやっていると、猫用の餌を食べなくなるといけない。早く買いに行こう。
食べ終わった黒猫をだきあげてみた。グニャンと重い。子供の頃猫を飼っていた。よくこうしたものだ。だっこされた黒猫は僕を見上げているに違いないが、顔がないとものたりない。
よくなれた猫だ。
朝食を済ますと、さっそくドラッグストアーに行った。猫用の食料がこんなに種類のあるものだとは思っていなかった。どれを選んだらいいのかわからない。缶詰がいいのか、乾燥した餌がいいのか、パックづめのものある。なんとおやつまであるじゃないか。
一つの会社の缶詰だって、まぐろとかつお、まぐろとしらす、まぐろと鶏肉、白魚、白魚とマグロ、なんだ人のものより種類が多い。なにがいい。わからん、しょうがない、五つの会社の、同じものを比較のために買おう。共通している「まぐろとかつお」をそれぞれ一缶づつ、これで五缶、次に違う種類のはいった小袋入りの箱、パックも「マグロとかつお」のはいったものを五つの会社ごとに、最後に、細長い袋いりおやつ。ちゅっちゅと吸うらしい、こいつを五種類。それに自分用の、やすいチョコレートやクッキー類を買った。
大きなエコバックいっぱいだ。肩に担いで帰ると、黒猫がいない。まさか、一泊しただけなのか。となると、こんなに餌を買っちまってどうする。顔のある猫をどこからかもらってくるか。
まあ、しょうがない、とりあえず、コーヒーを飲むことにしよう。今日はめんどうだから、粉のブレンドコーヒーでいこう。フィルターに粉をいれ、沸かした湯をそそいだ。ドリップコーヒーのできあがり。
居間にもっていって、窓の外を見ると、ガラス窓に黒猫が伸び上がってこちらを見ている(おそらく)。顔のない黒猫が、両前足をガラスにかけて、デッキのうえから立ち上がっているのだ、そんな姿を想像してみてごらん。格好としては、首のない毛をむしられたチキンが立ち上がっている雰囲気だ。
本当は気味悪いところだが、僕は超常現象の本を読みすぎたせいか、それともそういう性格なのか、以外と平気のようだ。もちろん昨夜は驚いたが。
なかに入りたいか、ガラス戸を開けてやると、ニャアといいながら入ってきた。やっと、腰を下ろしてコーヒが飲めた。猫はソファーに腰掛手居る僕のわきでおちゃんこしている。どうも見上げているようだ。まだ十時半だ、猫の食事は朝夕二回でいいだろうなどと思っていたが、おやつを売っているということは、時々やってもいいのだろう。おやつにしようか、餌にしようか迷ったが、乾いた餌をやることにした。きっちんに行き、さらにいれてやると、黒い猫はカリカリと音をたてて食べた。
首が少し伸びたようだ、と思ったら、付け根から少し上のところまで、毛が生えている。首が現れてきたようだ。餌を食べると顔が現れるのだろうか。
まてよ、顔を触れるということは、毛に粉をつけたり、絵の具で塗れば、顔があらわれるのではないか。
それはいい。僕は墨汁をもってきて、カリカリ食べている猫の頭の上に少し塗ってみた。しかし、頭は透明のままだった。色を塗ったりしてもだめなことがわかった。
餌を食べ終わった黒猫は、顔を洗い始め、それが終わると、見ていた僕の足元にこすりついた。はいていた白い靴下に墨汁がくっついてしまった。こりゃいけないと、タオルで、猫の頭をふくと、墨汁で真っ黒になった。余計なことはするものじゃない。自然に任せておいた方がよいようだ。
おなかのくちくなった黒猫は、いつのまにかいなくなっていた。出口は開いていないのに、どうしたのだろう。入るときは戸を開けてやった。頭が透明な猫のことである、僕たちにはわからない何かがあるのだろう。
黒猫は夕方になると、戸を開けてやらないのに、どこからか家に戻ってきて、餌をほしがった。マグロとカツオの缶詰めをあけてやると、あうあうあう、といって食べた。口にあったようだ。よかった。
その晩も僕のベッドの上にきて、足下で丸くなった。
次の朝になると、黒猫もいっしょにおきて、キッチンで、一緒に食事をした。黒猫の顔が耳の後ろまでみえてきた。餌を食べると、だんだん顔があらわれてくるんだ。
僕は、昼の餌を皿にたっぷり入れると、「変な人に見つかるなよ」といって、玄関の鍵を閉めて仕事に行った。
顔が透き通るような現象が書かれている本があるか、空いている時間に探してみた。神秘、伝説、呪術など、サブカルチャーのコーナーで探した。だが透明にするような呪いや、魔術に関してはみつからなかった。姿を消してしまうような呪いの儀式はあるようだが、この図書館には般向けの本しかおいてない。西洋の古い革装の本などを集めている古本屋の方が知っているかもしれない。国会図書館で検索するのもいいが、顔を透明にするなどという、キーワードで検索しても、透明人間関係のSF書がでてくるのがせきのやまであろう。
「主任、服に黒い猫の毛がついてますよ、飼ってるんですか」
カウンターにいた新人の女の子がきいた。
「うん、迷い猫がうちに来て、とりあえず、餌をやっている、いつかどこかに行ってしまうかもしれないけど」
「迷い猫って、SNSに出すと、飼い主が見つかるかもしれませんよ」
確かにそうだが、顔がない猫とはいえないし、返事にとまどっていると、
「主任飼いたくなっちゃったんでしょう、かわいくて手放したくない」
彼女が笑ってそういうもんだから、「うん、そうなんだ」とうなずいておいた。
「探し主がいないようなら、飼っちゃえばいいですよ、雄猫って、結構よその家に行ってかわれちゃうことがあるんですって」
彼女の言葉に、安心して、笑顔になったら、彼女も納得したようで、それ以上の詮索はしなかった。
いつものように五時に仕事場をでて、夕飯のレトルトカレーを買うと、家に戻った。
黒はいなかったが、キッチンの猫の皿の餌がきれいになくなっていた。結構大盛りにおいておいたのだが、全部たべてしまったようだ。
ジャガイモと人参、それに凍らしてある唐揚げ用のもも肉をいくつか、水をいれた小鍋に入れ、ガスにかけた。あとでレトルトカレーをいれると、少しまともなカレーになる。それに生野菜を用意する。レタス、トマト、などである。
週に二日ほどこうやってカレーを食べる。
用意しているところに、黒猫が帰ってきて「にゃにかくれ」と言った。いや、にゃーと鳴いただけだ。
今日は猫缶詰をあけてやった。がつがつたべている。顔の後ろ側が黒くなった。餌を食べると、だんだん顔が戻ってきているようだ。どのくらいで、もとにもどるのだろう。
どうしてそうなったのかも不思議だが、戻るようなら安心だ。うちにきて今日で二日目だ。食べ物ではなくて、うちにいれたことで顔が戻っているようなら、うれしいことである。この分でいけば数日で顔があらわれうことになるのではないだろうか。
そういえば、名前がない。黒としか呼んでいないのはちょっとかわいそうだ。何という名前を付けようか。
外国では黒猫にたいして、いろいろな思いがある。悪魔とされたりして、塔の上から投げ捨てられたり、足を切られたり、逆に幸運の猫とも考えられたり、それこそ、僕の興味のある本にはたくさんでてくる。小説もそうだし、絵画にもたくさん登場する。日本で黒猫の扱いは西洋と同じである。それに対して、真っ白の猫は、黒い猫ほど、うとまれたりはしない。どちらかというと、純白のほうが好まれる。
僕はというと、虎でもミケでもなんでもいいし、白と黒とどっちがいいなんて、あまり意味がないようなきもする。そうだ、名前だ。黒猫というとポーの黒猫だ。誰だって黒猫というとすぐ頭に浮かぶ小説である。じゃあ、こいつは、アランか、ポーか、どっちかにしよう。
顔が見えないので、ぴったりした名前を付けることが難しい。のんびりたし黒ちゃんがいいな、となると、ぽーっとした黒か、ポーがいい。
ポー、呼んでみた。
黒猫がこすりついてきた。
ポーでいいようだ。
「ポーはどんな顔なんだい」
そういったら、にゃーと鳴いた。
カレーができた。自分の食事だ。食べていると、テーブルの上にとびあがってきた。目の前でおちゃんこをした。猫がテーブルにあがるとしからなきゃだめだ、と何かでよんだ。猫のしつけの本だったか。つまらない本だ。自由にさせてやるんだ。猫には猫の世界がある。猫はペットになった振りして、人間と対等に生きている唯一の動物だ。
だけど、猫がカレーは食べないだろう。匙にすくって、ポーの前に持っていってみた。匙を透明な、おそらく鼻先でつんつんした。でも食べない。と思ったら、いきなり、匙の上に乗っていたカレーが消えた。
ポーがくちゃくちゃかんでいる。カレーを食べる猫なんているのか。驚いていると、自分の前のカレーの皿にポーが顔をつっこんでいる。顔が見えないので、手を伸ばしてさわってみると、明らかに皿の上にポーの頭があって食べている。カレーを食べる猫だ。辛くないのかい、たくあんを食べる猫はきいたことがあるが、カレーを食べるとは。三分の一ほど残っていたカレーライスをみんな食われちまった。
食べ終わったようで、顔を洗っている。透明な鼻先に自分の鼻を近づけてみると、カレーのにおいがした。うまかったならそれでいい。
僕はコーヒーをいれた。
コーヒーは飲まないだろう。そう思っていたら、コーヒーカップに頭をいれているようだ。
ありゃ、ペチャペチャ音がする。猫舌だろうに、大丈夫なのか。しょうがない、自分用に別のカップにコーヒーを入れた。
ポーのやつ、みんな飲んじまった。
あれ、なんか、頭が白っぽく煙っている。カレーとコーヒーが刺激で、顔があらわれるのだろうか。
そう思っていると、急に走り出して、キッチンから出ていってしまった。
なんだ、トイレにでも行きたくなったのだろうか。
まあ、しょうがないか。
さて、ポーはほっといて、いつもの夜を過ごそう、今日は月曜日、テレビのニュースのあとに、ヨーロッパの旅の番組を見よう。それから本を読むか、DVDを見るか。
ポーは自分が寝る頃には帰ってきて、ベッドで丸くなるだろう。
ところが、いつもの夜を過ごし、寝室に入ったのだが、ポーはもどってこなかった。カレーを食べてコーヒーを飲んだので、刺激になって、ほっつき歩いているのだろうか。まあ、いつか帰ってくるだろう。寝室のドアをきっちり閉めないで、ベッドに入って、本を読むことにした。だがすぐに眠くなり、寝てしまった。
朝、目が覚めたとき、足元を見たのだが、ポーはいなかった。どこからか来た顔のない黒猫。顔が戻り始めたかと思ったのだが、戻ってこなくない。なんだか寂しくなってきた。明日になったらもどるかもしれない。仕事に行った。
帰っていることを期待して家に帰ったが、黒猫はいなかった。
顔が現れるまでいてほしかった。どんな顔をしていたのか見てみたかった。
土曜日になっても戻ってこない。
土、日は図書館が一番忙しいときである。本を返す人、また借りていく人、お母さんと一緒に子供もくる。平日は勤めでこれない人がくる。平日は退職した人や高齢の人が多い。そういう人は土日も来る。だからいっぱいだ。
日曜日、カウンターの受付を手伝っているときだった。子供を連れた一人のお母さんが、僕をみて、ぎょっとした顔で、あわてて図書館からでていってしまった。
なんだろう、僕を見たから逃げていったようにみえたが、そうじゃなくていきなり、何かを思い出して家にでも戻ったのだろうか。
そのあとも、本を返しに来る人が続いていたので、その母親と子どものことはすぐに忘れてしまった。
その日も忙しく一日が終わり、家に戻った。
家の前に背広を着た男の人が立っていた。
「星さんですね」
と私の名前を呼んだ。
「はい、なんでしょう」
「今、図書館からお帰りですか」
「はい、いつもこの時間に帰ります、なにか」
「ちょっとお話をお聞きしたいのですが」
男は背広から手帳を出した。警察手帳だ。
「刑事さんですか、なんでしょう、今、鍵を開けますから、中にどうぞ」
「あ、そりゃどうも、それじゃ、中で」
刑事が玄関で話をしようとしたので、居間へ通した。
「あの、ちょっと変な話で、ただ、私どもとしては、訴えがあった以上、一応調べなければならないので、うかがったのですが」
僕は刑事をソファーに座るように進め、自分ももう一つのソファーに腰掛けた。
「仕事から帰ったばかりですみませんな、実は東町団地の住人から訴えがありましてな」
東町というのは、自分の家のある団地から、図書館を挟んで、反対側にある新しい団地である。個人住宅と集合住宅が混ざっている、若い人たちが住んでいるところである。
「それが、夜、窓から覗く男がいるということでしてな、ガラス越しだったり、ちょっと開いている透き間からですな」
「風呂をのぞく痴漢ですか」
「それが、一件は風呂だったのです、小学生の男の子が風呂に入っているとき、ちょと開けてあった窓に男の顔が見えたので、声をあげたら、母親が来たらその男がにげたというものです、あとは、居間だったり、寝室だったり、ガラスに顔をつけて中を覗いていたそうなんで」
「それで僕に関係があるのですか」
「実はいろいろ調べさせてもらいました。そういった訴えがあった日にちに、その家の近くの防犯カメラの映像を調べたのですが、男の映像はありませんでした」
「あの、なんで僕が関係あるのですか」
「実は今日の朝、夜中に家をのぞいた男が、図書館で働いているという訴えがありまして、それがあなただということで、調べさせてもらったわけです、しかし、このあたりの防犯カメラにもその時間にあなたは移っていないし、周りの人にちょっと話を聞いたけれど、とても評判はよい方だったんで、私らもわからなくなって、直接うかがったわけで」
思い当たる節があった。図書館にきた子供ずれの母親だ。僕を見ると、急に図書館から出て行った。
「近所に聞き込みをしたわけですか」
変な噂が立たなければいいが。
「いや、探偵事務所で、結婚話があって、相手の方から頼まれてと言ってあります」
それにしたって、結婚しなければ、何でだめだったのだろうと、噂になる。
「僕は夜中にでたことはありません」
「そうでしょうそうでしょう、こちらも調べました。おそらく星さんに似た男だと思いますので、もしや、似ている人を知っていたらとおもいまして」
むちゃくちゃだ、なんだか、刑事コロンボが言うようなせりふだ。刑事はそういって、僕が犯人かどうか見極めにきたのだろう。
僕は首を横に振った。
「東町はかなり離れているし、駅にも近いので、変なのが出入りしますから、そっちをあたっていましたが、訴えがあったので、ともかく調べなければならないので、すみませんな」
「いえ、それで、ぼくはどうしたらいいでしょうか」
「いえ、なにも、訴えた母親には、違う人のようだとはいっておきますが、何せ、絶対あの人だというもんで、頑固な人はいる者です」
僕の顔はどちらかというと、平凡な顔である。同じような感じの人がいないわけじゃないだろう。
刑事さんは、ぺこぺこしながら、帰って行った。お茶のいっぱいも出せばよかっただろうか。
その日はなんだか、さっぱりしないで、ベッドにはいって本を読んでも読みとれなかったり、集中できていない。電気を消してもなかなか寝付けない。
夜中の二時になる。まだ目がさえている。
おや、廊下を何かが歩くような気配がある。そうだ、一週間前に、ポーが部屋には行ってきたときと同じだ。デジャブじゃない。黒猫が帰ってきたのだ。猫がいるとこういうときはいやされる。僕は電気もつけずに、あわてて起き上がるとドアを開けた。黒猫のポーは「にゃ」と小さくなくと、僕の足をすり抜けて、ベッドの上に飛び上がった。
「よく帰ってきたな」
電気をつけた。
ポーが僕を見た。顔があらわれていた。
ひゃあああ、僕はワーッと声お上げてベッドの上にすわってしまった。
黒ねこの顔が僕の顔になっていた。
これですべて理解できた。
ポーは自分の家を探しに東町まで行ったのだ。家々をのぞいたのだ。昔東町で飼われていたのだろう。
さて、これからどうしたら猫の顔に戻すことができるのだろう。この顔で歩き回られたら大変だ。
ポーを見た。自分の顔をした猫はだっこしたくならないものだということがわかった。アイドルの顔ならいいだろうって、ばかいっちゃいけない。猫の顔の方がずーっとかわいい。猫は猫の顔がいいのだ。本人も不幸だ。
もう一度カレーをたべさせてみようか。
とりあえず、頭をなでた。僕の顔がごろごろいっている。
やだ。
寝よう。電気を消した。明日になって考えよう。
顔のない猫2 ポー


