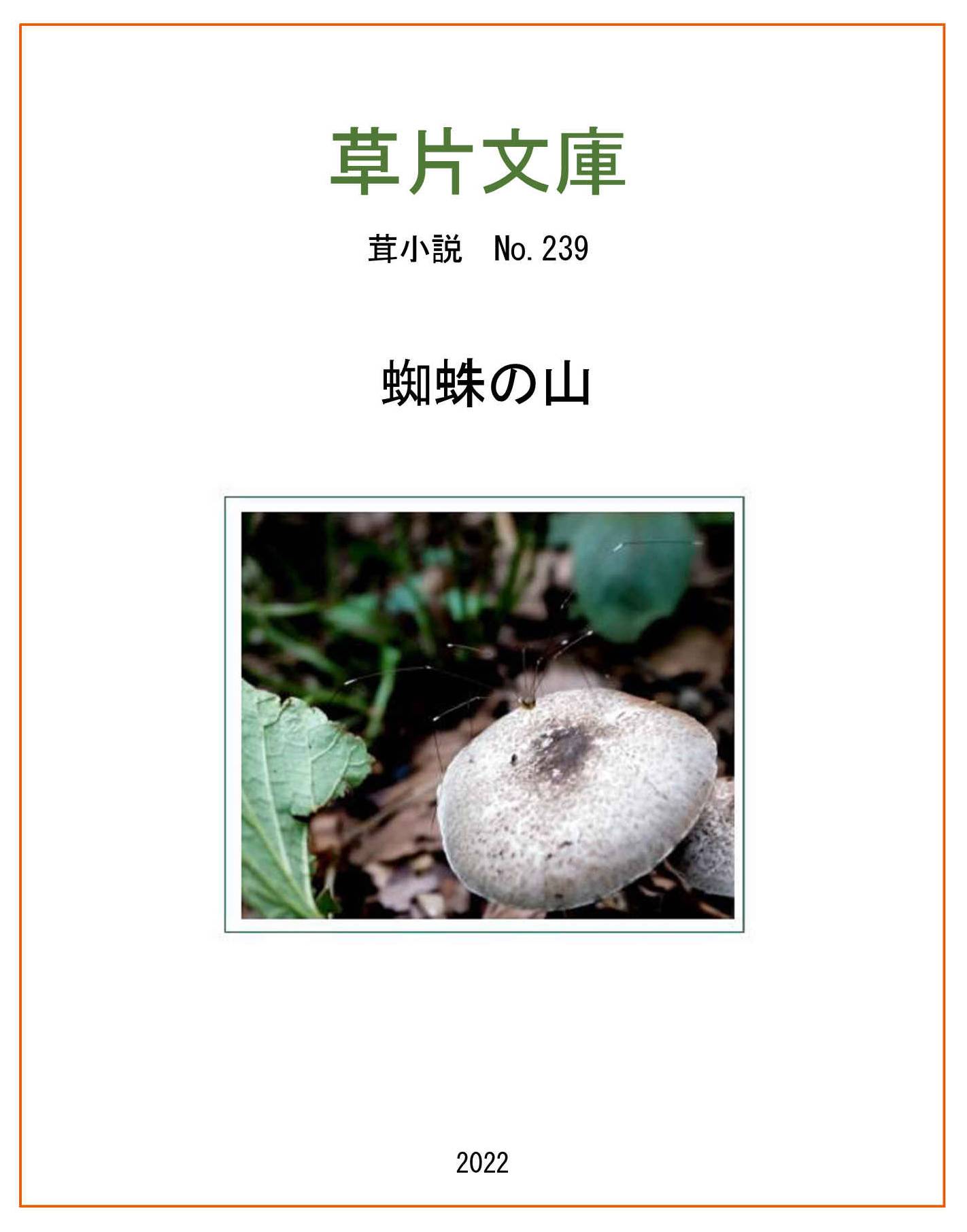
蜘蛛の山
茸ミステリーです。縦書きでお読みください。
今年の秋は茸の味が一段とよい。
うちらが住んでいる楠木村は、赤瀬川両岸に発達している赤瀬市の赤瀬町からバスで四十分ほどかかる。赤瀬町も中央線の駅からバスで二十分ほどのところだから、かなりの山奥である。
湯の里で、特に天然茸が豊富、茸のうまさでは日本一だと村の者はおもっとる。実際に遊びにきた客たちは、湯もほめるが、なにをさておき、茸の料理のうまさは絶品と口をそろえる。信州の山奥のあまり知られていない村である。
大学の偉い菌学とやらの先生が、肥沃な土と適度な湿り気、それに日の光と暖かさ、それが日本の中で、茸のためにもっとも整っていると、太鼓判をおした。
村の衆は総出で山の管理を行っている。間伐、枝きり、昔から一年間の決まった行事を欠かすことがない。林の中は適度な光が入り、適度な湿り気がたもたれ、茸にはこれ以上の棲みやすい場所はないだろう。
ところが、村の周りを囲む山の一つ、大蜘蛛山の茸は、同じシメジが生えていても、ほかの山のものとは味に雲泥の差がある。うまくない。専門家の先生に調べてもらったところ、そこに生える茸のアミノ酸が、同じアミノ酸でも、壊れやすい性質を持っているのではないかということだった。口の中に入ったときに、おいしいと思われる成分を構成するアミノ酸が、どこかおかしいので、おいしさがでてこないということだ。
それじゃ、どうしてそうなったのか、専門家の先生は、光の入り具合、湿度、周りの草の種類、それに一番大事な土の質をしらべたのだが、隣の山と違うところをみつけることはできなかった。
大蜘蛛山に隣接している山々には、それは見事な茸がはえる。村人たちは大蜘蛛山は茸に関してはあきらめているのだが、必要な枝は払いや、伐採を書かすことはない。周りの山々の茸に影響があるといけないからだ。そのおかげで、大蜘蛛山には秋になるとアケビ、春には山菜類だ、他の山に負けず劣らず、とても豊富で立派に育つ。
村は僻地といっていいほど、都会とはかけ離れている。ところが以外と人口が減らない。それはおいしい茸や山菜が採れ、緑の山に囲まれているし、村の端にはきれいな流れもある、自然に恵まれているなどと改めて言うのは恥ずかしいほど、住むと自然に溶け込んでしまう場所なのだ。今注目のテレワークとやらで、家でも会社の仕事ができるので、越してくる家族も多いし、自然の中に刺激を求めるアーティストたちの卵がどんどん移り住んでくる。それは若い人が村長になってくれたおかげでもある。
私は役場を退職してから、この村だけではなく、この地域一帯の伝説伝承を老人から聞きとり、文章に起こし、まとめていくのを趣味としている。
「四月から村の小学校に来る校長先生は、まだわけえのに、校庭の生き物っちゅう本を何冊もだしているんだ、石田のおやっさんと話があうべ」
だいぶ前だが村の教育委員長をしていた、八十になる三部のじいさんが、私に言った。私より十も上なのに、まだ茸採りや山菜採りと元気に毎日を楽しんでいる。
「ファーブルのようだな、校庭の虫を観察して本にできるなんてたいしたもんだ」
「放課後に、子供たちと一緒に、虫ばっかりじゃねえ、蛙やかたつむり、トカゲや蛇、池の魚、それに草や木なんぞを観察して、たいそうたくさんの面白いことをみつけているそうだ。それで、一緒に観察した子どもたちの名前も本には書かれていて、なんと、印税は、みんなで山分けだそうだ。みんな著者ということだ。子どもたちは、中学生になった頃に、印税もらって、おお喜びさ、一冊千五百円の本で印税は二割の三百円、五十人の名前があれば、一人六円、だけどな、日本にいくつ小学校があるかしってるかね」
「二万だったかな」
「おおそうよ、石田のおやじさんよく知っておるわ、すなんだ、半分の一万の学校が、図書館に本をいれたとすると一万部、一人六万円じゃ、小学生百人が著者になったって、一人三万円、それをもらったら、喜ぶじゃろう、その先生は、いくつかの小学校をまわって、それぞれのところで、一冊本を出してきたんじゃ、そういう人が、この村に来たんだ、楽しみじゃのう、面白い本を作ってくれるぞ、このあたりには変な虫もいるからな、校庭だけじゃなくて、こどもたちと茸採りに行って、茸の本を出してもらうべ」
「なんつう、先生なんで」
「湯本先生じゃ」
「うちの小学校にも本はありますかのう」
「たぶんはいってるじゃろう」
「こんどみせてもらいにいきますよ」
「それがええで、湯本先生が来たら、会ってみたらええ」
四月になって学校も始まった。全校で六十人、一学年十人という小さい小学校だが、二階建ての校舎は以外と立派だ。理科室だって充実している。中学校は町まで行かないとないので、茸を調べにくる大学の先生なども使えるように、立派な実験台をそなえてある。もちろん顕微鏡などもふつうの小学校にはない高級機だ、大学で使うようなものがおいてある。茸の村だから、そういった研究施設がほしいと県に言ったのだが、それは無理だが、小学校の理科室に補助金をだしてくれたので、専門家も使えるようにしたのだ。校長の湯本先生もそれを見たら喜ぶだろう。
小学校は土砂崩れなどを心配して、山際からかなり離れた村の中心地にある。町役場、医院なども近くにあり、村唯一のコンビニもある。宿屋が経営している個人のコンビニで、都会のような二十四時間営業じゃないが、朝五時から夜十二時まであいていて、このあたりじゃ、珍しく長い経営時間だ。それも旅館の人がやっているからできることだ。文房具もお菓子もあるので、子どもたちの社交場にもなっとる。
わしは学校が始まってはじめの土曜日に、教育委員会の知り合いを通して、湯本先生に会う約束をとりつけた。
学校に行ってみると、湯本先生はGパン姿で、校庭の入り口にある楠をながめていた。あらかじめ顔写真をみていたので、湯本先生だと言うことがわかったので、そこで初めての挨拶をした。
「石田です、さっそく、虫の観察ですか」
「あ、湯元です、ええ、まあそういうことですが、こりゃ古い楠で、蝶がきそうですね」
「ああ、青い筋のあるアゲハがきてますな」
自分が小学生の頃から、きれいなチョウチをこの木でみかけたものだ。
「アオスジアゲハですね、小学校に楠を植えたのはなにか目的があったのでしょうか」
湯本先生にわたしが郷土史の編纂をやっていることが伝わっているようだ。
「戦後に作られた小学校ですが、その前は神社があったところで、そこに植わっていたのだと思いますよ、神社はあっちの大蜘蛛山の麓の方にうつりましたんですよ」
わしはそんなに大きくない山を指差した。
「大蜘蛛山って面白いなまえですね」
「ええ、ちょっと変な山でしてね、このあたりは美味しい茸の採れるところですが、あの山だけは、どんな茸でも美味しくない、それで専門家にも調べてもらったんですが、理由はわからんだったです、茸の成分がちょっと違うなんていってましたけどな」
「おもしろいですね、いつか聞かせてください」
「先生は校庭の虫を、生徒と一緒に調べて本にされていますが、ここでもぜひお願いしたいと思いましてね」
「もちろんです、楽しみでここにきました、なかにどうぞ」
湯本先生はもう校舎の中を知り尽くしているようだ。さっさと、先に立って校長室に行った。
「校舎のことはよくおわかりになっているようですね」
「はい、全部見て回りました、テントウムシやカメムシ、蜘蛛いろいろな虫が校舎の中にもいますね、子供たちはみなれているのでしょうけど、虫眼鏡で見てみると面白いですよ、あいつ等の顔つきは、なにかいいたそうにしていたり、考え事をしているようだったり」
生物学者のはずだが、文学系の表現だなと思った。湯本先生は角の取れた三角形の顔をして、好奇心でいっぱいの丸い目をしている。
「先生は、この学校を希望されてきたのですか」
「もちろんです」
「茸がお好きなんですか」
「茸も好きですけど、動物植物みな大好きです、それに私が生まれたところだし」
え、っと思った。
「この村で生まれたのですか」
「いえ、赤瀬町の方ですけど、だから小学校は違います、中学までいて、高校は東京都内の私立にいきましたので、寮生活でした」
赤瀬町というのは赤瀬市の中心で、甲州街道から道わき道がのびている。赤瀬川に近い市の中心地である。ここも温泉がでるところで、昔は県道そいの小さな宿場町だった。
「そうでしたか、それじゃ、今はご実家からかよわれているのですか」
「ええ、中学生の息子と娘がいまして、町の中学にいっています、両親も健在でして、父はまだ仕事をしています」
「そうでしたか、やはりお父さんも先生をなさっていたのですか」
「ええ、母は小学校の先生でしたが、父は大学の生物学の教授でした」
「それで、先生も生物学をなさったわけですか」
「父の影響はあまりありません、父は生物学といっても、遺伝子のほうだったので、化学のようなものです、ぼくはもっと、生き物をみていたいほうでした、母は国語の先生だったので、まあ、僕も本が好きでしたね」
「あ、すまんです、関係ないことをお聞きしてしまいました」
「いいえ、村の方たちには色々教えていただきたいので、自分の生い立ちはオープンにしています」
「このあたりの伝承のことに関しては、村誌にまとめてあります、校長室のどこかにあると思いますので、見ていただければと思います、私が関わっていますので、もし何か興味のおありなことがありましたら、なんなりとおききいただければ」
「ああ、村誌はあちらのスチール本棚にありました。湯本さんの名前も必ず出てきましたので知っていました」
まだ一週間なのに、もう調べている。すごいエネルギーだ。
「町のお生まれなら、この村の茸がおいしいことはご存じですね」
「もちろんです、町のマーケットにでている茸はこの村のものでした。母親はよく雑茸というのを買ってきましたよ、とても味がいいと言っていました」
雑茸とは、村でとれた茸の中でも、ナメコ、シメジと名の知れたものではないもので、ときどき、知られている茸形の悪いものが雑多に混じっ手居る、名前の通り雑な茸である。しかし、煮染めにしても、佃煮にしても、そばうどんにいれたり、それはおいしく食べられる逸品なのだ。村民が採ってきた茸を、茸の目利きが、食べられるものを選び、さらに旅館やホテルに卸せるものを除いた茸である。茸採りは村のじいちゃんばあちゃんの小遣い稼ぎになっていた。
「先生は茸はよくご存じで」
「いや、知らないので知りたいですね、子供の頃、いろいろな虫や植物を身近にみていけど名前も知らない。親父は生物学者だったけど子供には生き物ことを話してくれませんでしたね、そんなことで、是非この村の小学校にと希望したのですよ、これからは茸のことも教えてください」
「それはいい、茸じいさん、ばあさんをを紹介しますよ、実は私が今日先生をたずねたのは、校庭の虫の本ばかりではなく、茸の本も子供たちや、村人と一緒に出してもらいたいと思いまして」
「それはこちらからお願いしたいことです、よろしくお願いします」
「大蜘蛛山の虫や植物も調べると何か出てくるのではないかと、私は思っているんです」
「どういうことでしょうか」
「あの山の茸は他の山のものに比べて美味くないのですよ、学者さんが調べたけど理由がわからなかった、それに他のところとでは見ることのできない虫や草があるんです。それが、あの山の茸の味が他のところと違うのではないかと、私は思ったりするんです」
「そりゃあ、すごい、理学者の発想ですね、いずれ大蜘蛛山も歩きたいと思います」
「小学校をつくるとき、この場所にあった神社を大蜘蛛山の近くに移したんです、その場所はその大昔に神社があったところで、もとに戻したという方が正しいのかもしれんです」
「小学校の歴史にのっていました、草片蟲神社とありました」
「面白い名前でしょう、昔から茸がよくとれたから草片にしたのだとおもうのですが、蟲がついているのが不思議です、神主はよう知ってる人ですが、由来はわからないといってますな」
「大蜘蛛山の名前の由来はわかっているのですか」
「それもわからんです、あの一帯は、いやこのあたりは縄文人もすんでいたところで、かなりの歴史があります。江戸より前の時代の様子を知ることのできる古文書はみつかっていません、江戸時代のものは神社などにあります。しかし、大蜘蛛山に関しての言い伝えなどは知られていません」
「昔からの家にも残ってないのですか」
「そうですね、村人たちには調べてもらいました、古い空き家なども、遠くに住んでいる持ち主に許可を得て調べましたがありませんね」
「そうですか、この村の一番近くの地域というのは、僕が住んでいる町中だけですか、山のどこかに集落などなかったのでしょうか」
「小さな集まりはありましたけど、炭など焼いている連中の家でしたかな、戦後はいなくなりましたな、大蜘蛛山に続く奥の山です」
「そういった昔の大蜘蛛山にいた人はいないものでしょうか」
大蜘蛛山の後ろの方に集落があった。炭を焼く仕事をしていた人たちの部落である。
「わしも調べましたが、いませんな、炭焼きの部落は細蟹(ささがに)と呼ばれていましたけどな、戦後直後、炭の需要があるときは、何軒か炭作りの家がありましたけどな、だんだん消滅して、いつのまにかなくなりました。そこの人たちは、この楠木村を通って、赤瀬町の方まで買い出しにいってました。私が子供の頃はまだあったとおもいます」
「それは面白い名前だ、今はどうなっています」
「そのまんまで、家は崩れたまま、山奥の茸を取りに行くときなどは通りますけどな」
「持ち主はいないわけですか」
「ようわからんですね、市のほうに聞いたことがありますけど、戸籍だとか、そういうものが残ってないようです」
「ささがに、というのは古い言葉で、蜘蛛のことを意味しますよ」
「ありゃ、わしゃ、調べもしなかった、山すその小さな流れなどに沢蟹なんかがおったから、そのことかと思ってました」
「おもしろいですね」
「先生、もう一度市の方に行ってしらべてみます、考えもしなかったことで、迂闊でした。ありがとうございました、私の家は村役場からすぐのところです、茸のことなどもありますから、お時間のあるときいらしてください」
「私の家のほうが市役所に近いし、私も調べてみます」
私は、自分の家のところを黒く塗った村の地図を渡し小学校からでた。
細蟹が蜘蛛の意味であることを教わった。調べようとしなかったからいけないのだが、やはり若い頭にはかなわない。頼れる人が村に来てくれてよかった。
次の日、さっそく、赤瀬町にでて市役所に行った。土地台帳をみせてもらい、山奥の細蟹集落のあたりの土地や建物がどのように登録されているのか調べた。前はそこまで調べようとしなかった。しかし、今の台帳には、そのあたりは県有地になっており、建物はないことになっている。残っている残骸は本来県が除去しなければならないものであることがわかる。担当の者もその部落の細蟹の意味は知らない。
「細蟹のことはようわからんねえ、集落ができたのは江戸のはじめの頃だろう、それも大した数じゃないし、ずいぶん山奥だし、市でも調査したことねえな、市の図書館の資料室にないかな」
「あるかもしれないな、わたしゃ、図書館にはよくいくけど、細蟹について調べようとしなんだ、うかつだな、こんど村の小学校にきた湯本先生にいわれたんだ、細蟹は蜘蛛のことだと」
「ああ、湯本先生ね、あの人のお父さんが偉い人だったよね、どこかの大学の教授でさ、湯本は中学をでると東京の私立高校にいっちまったな、中学の時同じクラスにはなったことないけど、同年生だ、感じはよかったよな」
基本台帳の管理をしている市役所の担当者はそういって台帳をもとのところにもどした。
その足で市の図書館に行った。
「細蟹の資料っていうのあるかな」
いつもいくので図書館の人とは顔なじみだ。
「石田さん、そりゃなんですか」
図書館の人も市の生まれだが知らないようだ。
「楠木村の山奥に昔しあった部落だが、部落の名前は細い蟹って書く」
「ああ、あれ、ささがにとよむのか、そう書いてある古い地図はありましたよ、楠木村の資料のとなりの棚にあったと思いますけど」
「誰がその部落を仕切っていたのか知りたいんだけど」
「書いたものがあればいいけど、調べたことがないから、中に入って調べていいですよ」
資料の保存室は閉架式の管理になっているので、一般の人は許可がなければ入れない。図書館の事務所の中を通り、地下におり、楠木村の資料の棚のところにいった。何度か入っているので場所はわかっている。楠木村の資料はかなりの数になり、棚の二段目と三段目をしめていて、そこのものはかなり目を通した。しかし、下段の箱の中のものは、重要ではないと判断されたものがはいっている。それでまだ見たことがない。
その箱を資料室内のテーブルの上におき、蓋を開けた。何が書かれているのか分からないような赤茶けた紙が雑につまっている。中にやはり茶色くなった和紙につつまれたものがあった。表に墨で「炭焼き」とある。
もしかすると、細蟹の部落のことかもしれない。期待して開いた。
墨で簡単に書かれた地図もはいっていた。これは貴重な書類だ。炭焼きの場所が記されているようだ。家々の印もある。確かに細蟹の部落だ。箱の下のほうには、当時の町にあった炭の問屋の帳簿もあった。細蟹部落から炭を買っていたようだ。ということは、その問屋の末裔が誰か調べると、手がかりが得られるかもしれない。卸問屋の名前は篠井安佐衛門とある。それ以外に関係のありそうな文書はなかった。細蟹の由来などが書かれているようなものはみつからなかった。
江戸時代には町は小さいながらも宿場だったので、炭の需要は大きかったにちがいない。
地図と問屋の帳簿はコピーをさせてもらおう。その二つをとりだして、箱を棚に戻し、別の棚に行って、江戸時代の赤瀬町の街道の地図を探すことにした。これは容易に見つかるだろう。案の定、宿場町の時代の資料はかなりあった。街道の地図もある。開いてみると、赤瀬宿とあり、街のなかほどにはいくつかの商店がなら日、両脇にいくつかの宿がかかれていた。、その中に篠井と書かれた大きな家がある。大きな宿なら今でも子孫は残っているだろう。
店の大福帳でもあれば、なにかわかるかもしれない。宿屋として店が残っている可能性はほとんどないが、市役所の担当者なら何か知っているかもしれない。
担当者のところに行って、コピーをしたいことを告げると、全部やってくれた。
「石田さんだからただでいいですよ、楠木村の村誌に書く資料でしょう、こちらからの提供とかいていただければ」
コピーをもらい、図書館をでて、もう一度市役所に行った。
市役所の土地管理担当者が笑顔で、
「おや、もどってきたんですか、熱心だなあ」と笑った。
「ねえ、県道沿いに江戸時代にあった篠井という宿屋なんだけど、今はないよね、店じゃなくとも、篠井さんという古い家知らないかな」
担当の彼はうなずいた。
「篠井さんは古くからの家ですよ、市にも色々協力してくれてます、消防署の隣のガソリンスタンドをやってます」
そう教えてくれた。ガソリンスタンドの裏に昭和の初めに建てたという古い家があるという。
「それはありがたい」
「篠井という人を捜せばまだまだいるかもしれないけど、街道に沿ったというと、その人だけかな、あのあたりの土地はその人のものですよ」
「電話番号などわかるかな」
「うーん、わかると思うけど、最近個人情報を勝手に教えることはできないんです、消防署の先のガソリンスタンドを目指していけばすぐわかりますよ、ガソリンスタンドの電話番号なら、市役所でてすぐの電信柱にエッソガソリンスタンド、直進と書いた看板があって、そこに電話番号も書いてあります」
「あ、いやそれだけわかれば、いつもありがとう」
「いや、石田さんのまとめている、楠木村の歴史は我々も重宝してます」
ガソリンスタンドに向かった。
電話をかけると、ガソリンスタンドに社長はいなかったが、家のほうにいるので、来てくださいということだった。ガソリンスタンドの裏手の家は大きな屋敷で、宿屋のような作りである。入り口の松の木は枝振りからすると相当年のいったものだ。玄関には毛筆で篠井と書かれた古い表札がかかっている。
呼び鈴を鳴らし、玄関を開けると、はげ上がった六十代の男性が作業服をきてあらわれた。
「篠井です、楠木村の役場の方とか、なんでしょうか」
「石田と申します。むかし楠木村の小学校に勤めておりました。いま役場のだしている村の通信に歴史を書いています、細蟹部落のことを調べていたら、そこで作られていた炭が、篠井安衛門という人の卸問屋に集められていたことがわかり、今、市役所でおそらくこちらの家だろうと聞いたものですから、伺った次第です」
名刺を渡した。篠井の顔がほころんだ。
「茸の美味しいところですな、どうぞお上がりください、確かに篠井安衛門はうちの祖先です」
客間に案内された。古い町の写真がかかっている。
「いや、私も細蟹部落は面白い名前だと思ってましたな」
「ご存知でしたか」
「篠井安衛門は三代目です、千七百年中頃です、それから二百五十年ほどたちましたか、私は十一代目です。ガソリンスタンドもやってますが、備長炭など、炭の取り寄せもまだやっています」
「このあたりは宿場町でしたが、卸問屋をやっておられたのですね」
「卸問屋というより、宿屋でした。炭は必需品で、細蟹村からいれていたわけで、それで卸問屋の役割もしていたのです」
「宿屋をやっていたというと相当な財力がおありになった」
篠井さんはそれを聞いて笑った。
「このあたりの子供は小学校や中学校で、この町が宿場町として栄えたって教わるもんだから、みんな甲州街道沿いや中山道などの宿場町を連想して、さぞ立派だったと思っているんですがね、石田さんもそのようですね、甲州街道から離れている、こんなところまで足を延ばすのは面白いことがなきゃこないでしょ、女郎屋のようなものだったんですよ、まあ篠井は炭の卸をやっていましたから、中でも羽振りはよかったかもしれませんけどね、ちっぽけな安宿が集まっていたわけですよ」
ここでも、あ、そうか、と改めて、自分の地域を贔屓目で見ていることに気づかされた。
「この建物は、宿屋があったところに、明治時代に立て直したもので、そのころになると、安井の何代目かが、江戸からいろいろなものを取り寄せて売っていたので、この辺では大きな店になっていました。もちろん女郎屋などはなくなっていて、だけど数軒の宿はありました、うちの宿はかなり大きくなっていて、女郎宿じゃなく、湯と食事の宿としてやってました。前のガソリンスタンドがあるところまで宿の建物があったんです、相当大きな宿でした」
篠井家はかなりのやり手だったようだ。
「私は、このあたりの伝承などをあつめてもいますが、そういったことを書いたものがあったら、見せていただきたいと思っておたずねしました」
「ええ、もちろんあるものなら全てお貸しします、古い書き付けは茶箱にしまってあります、それ以外にも探せばあるかもしれません、そういったものは、図書館なり市役所にわたそうと思っていたところです。むしろ整理をしていただけると、ありがたいですな、納戸にあります」
すぐにでも見たいところだが、そうはいかないだろう。
「またうかがっていいでしょうか」
「納戸にあるものをお宅に送りましょう、お使いになってその後、何処に寄付したらいいか助言いただければこちらとしても助かります。じつは今、会社を広げようと、ちょっと忙しくなっておりまして、私自身も調べてみたいとは思いますが、何年先になるかわかりません」
「大変なんですね」
「世界的に電気自動車になるので、日本でも、このあたりでも充電スタンドが必要になります。水素自動車もでてくるので、水素のスタンドも必要になります。そういった総合ステーションを作る予定です。まだガソリンも必要ですし」
相当なやり手だ。
「茶箱は送ります」
「いえ、大変だと思いますので、わたしのほうでなんとかします」
「うちの石油販売車が楠木村にいっています。それに積んでいかせますよ、ご自宅でも、村役場にでもとどけますが」
「それはたすかります、それなら、役場が預かるということで、伝えておきますので」
「すみません、これから経営の会議がありますもんで、よろしくお願いします」
「こちらこそ」
篠井さんは、私と一緒に彼の家をでた。ガソリンスタンドからちょっと道沿いに歩くと、バス停があることを教えてくれた。
ずいぶん充実した一日だった。
それから数日後、村役場から電話がかかってきた。石油屋さんが石田さんに荷物をおいていったということである。
「もうとどいたの」
「会議室のテーブルにのせてあります」
村役場の広報の坂井さんが私を見ると叫んだ。席から立ち上がると、会議室までいっしょにきた。
「これなんですか」
興味の眼で茶箱を見ている。坂井明美は村のたよりの編集をしていて、私の資料集めの手伝いなどもしてくれている、国立大学の文学部を出た才女である。
「細蟹部落の資料が見つかるかもしれないんだ、赤瀬町にあるガソリンスタンドを経営している篠井さんの家が、江戸時代は炭の卸問屋もやってた宿屋で、部落の炭を買って売りさばいていたんだ、家に昔からあった資料をかしてくれたんだ」
「だから、エッソの石油屋さんが運んできたんですね」
「うん、なにがでてくるかおたのしみだ」
「宝物を見つけたような顔をしてますよ、石田さん、開けるの手伝いますよ」
彼女は茶箱の葢をもちあげた。
中には昔の宿帳や和とじ本がつまっていた。篠井家や篠井家のもっていた宿屋の家の図、昔の赤瀬町の地図、宿の備品の一覧、書き付け類や、古文書類があった。
さしあたり地図と古文書を調べてみよう。
「明美ちゃん、この資料、リヤカー貸してもらっていいかな、家に運ぶ」
私は免許をもっていない。こんな辺鄙な村で車を持っていないのは珍しいのだが、どうも車にがてである。昔から自転車で小学校にかよっていたし、今も自転車で来た。
「石田さん、私の車でもってってあげますよ」
「ありがたいな」
彼女が台車をもってきたので、二人で茶箱を乗せ、彼女の車まで運んだ。
「石田さん、自転車で先にでてください、私、事務長に断ってから行きます」
「悪いね」
私の家は自転車だと十分ほどの山の麓にある。家内もいないし、子供たちはよそで独立しているので一人暮らし、猫とのんびり暮らしている。
坂井さんの車はすぐに来た。
二人で結構重い茶箱を玄関に運ぶと、茶虎の猫、おとらがでてきた。もう二十近くなるじいさん猫だ。
「おとら元気ね」
明美ちゃんにだっこされた。彼女も猫好きである。
「お茶でも飲んでく」
「まだ、仕事中だから、そろそろ来月の村のたよりのゲラがくるから、もってきます」
「そう、どうもありがとう」
明美ちゃんは、月に一度か二度、仕事のことで我が家に来て、お茶を飲んでいく。猫にさわりたいようだ。彼女は我が家とは反対方向の、若い人たちが移り住んでいる地域で、やはり古い民家を借りて暮らしている。
早速茶箱の中から、古そうな町の地図をとりだした。江戸初期の頃のようだ。甲州街道から分かれて、山の中に続く続く道が書いてあり、その先がちょっとした町になっている。これが古い赤瀬町だろう。町の中の道の脇に宿屋がいくつか描かれていて、篠井宿がちょっと大きくのっている。昔の遊びの宿場町風情である。そこから、さらに細い道が山の奥にのびており、その先が楠木村とある。その当時から、山奥にしてはは家がかなりある。棚田が作れる条件のところだったからだろう。
細蟹の名前があった。大蜘蛛山の裏になり、楠木村から行くには、大蜘蛛山の二つ隣の谷川に沿った道を上っていき、その奥の山の隣の斜面になる。ぐるっと回ることになるが、大蜘蛛山の裏につながる山だが、大蜘蛛山が他の山より少し高いことから、細蟹部落の山は村からはほとんど見えない。大蜘蛛山を上って降りればいいのだが、、以外と急な斜面もあり、道はつくられていない。今でも山の奥に茸取りに行くのは、大蜘蛛山を通らない。昔からの道を通って、細蟹部落に行く道をつかう。
細蟹部落の地図は、図書館の資料室でコピーをした。これで、全体像が把握できる。たいへんありがたい。
茶箱には、炭帳と書かれた束がたくさんあった。篠井宿の大福帳のようだ。炭は細蟹部落から買っている。篠井安衛門の名がある古い帳面には、炭を買っの個人の名がかかれているが、地名はすべて細蟹とある。かなりの個人名があることから、そのころはそれなりの家族が炭焼きをしていたのに違いない。図書館でコピーした細蟹部落の地図と照らし合わせると、住居の数は大体一致する。
売り先の多くは町の宿屋だが、甲州街道沿いの大きな宿にもおろしていたようだ。あとは個人の名前がかいてある。町に住んでいた人たちなのだろう。楠木村では直接細蟹部落から炭を買っていたのだろう、売り先に楠木村の名前はない。
この部落はどういう人が炭焼きを始めたのであろうか。楠木村で仕事のない人間が、何らかのきっかけで、山奥に行って炭焼きをはじめたのか、他の地域からきたのか、その辺の資料はなかった。ふと、柱時計を見るともう八時である。食事の支度をしなければ。残りは明日からすこしずつしらべることにした。
あくる日、村役場に行くと、ゲラができてきたと、明美ちゃんに渡された。いつもなら届けてもらって家で校正をするのだが、村役場の会議室で目を通すことにした。チェックをしていると、明美ちゃんが小学校の湯本先生が来たとつれてきた。
「先生、この間はありがとうございました、細蟹部落の意味をおそわったので、市役所や図書館でもう一度調べたんですよ、そうしたら、エッソのガソリン屋さんが、昔旅館で、古い資料がたくさんあって、貸してくれました。面白いことがたくさん分かりました、もしご覧になるならいつでもどうぞ」
「はい、ありがとうございます、石田さんがご覧になって、教えてください、僕はこども達と校庭の虫や植物の観察をはじめることにしました」
「早速ですね、いいですね、ところで、今日は役場に用事ですか」
「ええ、書いた原稿もってきたんです」
明美ちゃんが
「新しく来た校長先生に、これからのことを村のたよりに書いてもらったんです」
「あー、それはいいね、先生、小学校どうですか」
「いい環境です。やはり山に囲まれているだけあって、今までの小学校の校庭より、たくさんの虫がいますね、子供たち一人に一種類の虫を観察させようと思っているのですけど、虫が多いので子供たちの数がたりなくて、やりたい子には二種類以上の虫の観察をしてもらうことにしました。残りは僕がやります。面白いんですよ、特に蜘蛛の種類が多いですね」
「へー、私どもは虫のことは気にしたことがなかったから、気がつきませんでしたね、茸だけは誰もが気にしてますけどね、もしかすると、大蜘蛛山には蜘蛛がたくさんいたんですかね」
「僕もそんなこと考えました。それで、日曜日をつかって、山の虫、特に蜘蛛を調べてみようかと思います、何かわかったら、石田さんにも知らせます。面白い本が作れるかもしれない、楽しみです」
「私の方も細蟹部落のことがわかればお教えします」
湯本先生は原稿を明美ちゃんに渡すと、
「それじゃ、僕は学校にもどります」
会議室を出て行った。
入れ替わりに村長の松茂さんがはいってきた。四十そこそこの村長である。松茂さんが村長になって、若者が町にはいるようになってきた。やっぱり若い頭を持った人がいないと過疎地になるという見本である。
「石田さん、とてもいい人が小学校にきてくれました、それで坂井さんとも話したのですが、村のたよりに、毎回、湯本先生とこどもたちに虫のことを書いてもらおうと思っています、一つよろしくお願いします」
松茂村長はこの村出身で、IT関係の会社に勤めていたのだが、ローカルエリアにIT網の整備をしたいと会社を興し、村に本拠を構えた人である。仕事も軌道に乗り、八十だった前の村長がやめ、立候補して当選した。五年前である。
「いい考えだね、私も細蟹部落のことをもっと調べて、町おこしに役に立つようなことがあったらと思っているところです」
「おもしろそうですね是非お願いします、歴史的に意味のあるところだったりすると、文化庁などが腰を上げます、すると村がテレビなどに取り上げられて、助かります」
村長もやり手でたのもしい。
ゲラの校正を終わらせて家に戻り、また篠井家の古文書整理を始めた。
今日は宿帳をひっぱりだした。古いものはあまり丁寧に書いてない。女郎宿では宿帳に名前など残さないかもしれない。それでも篠井の宿帳は何冊もあった。書かれて
ているのは名前だけのものも多いが、どこの者か、何泊かなども記されているのがある。
茶色くなった壊れそうな古い宿帳の中で、ちょっと厚手の表紙のものがあった。宝暦の字がみられる。それをひらくと、泊まった客の名前が書かれた字が、他の宿帳と比べるとかなりちがう。達筆である。表紙に、松の間とある。今でいう特別室に泊まった客なのか。字からすると、武士や商人のようだ。紀州とかかれている。紀州から江戸に行くのにわざわざこのあたりを通る必要があるのだろうか。江戸に行くなら東海道の方が楽だ。もう一つ不思議なのは、越中というのがあった。こんなところにどのような用事があったのか。松の間を利用していたのは、ほとんどがその二つのところから来た人だ。ときおり江戸がまじる。筆跡からすると紀州も越中もそれぞれ同じ人が泊まっているようだ。しかもみな二泊している。こんな田舎になじみの女郎がいたということはなかろう。むしろ定期的な用事で町を拠点としたということなのではなかろうか。
夕飯の後も調べを続けたが、江戸後期の宿帖をみても、特にかわりがない。松の間と書かれた宿帳は一冊しかなく、最後に書かれているのは越中の者で、文久となっている。
明治になってからも宿屋はやっていたということだった。そのころの宿帳は紙が違った。随分上等な和紙をつかったもので、松の間と記された宿帳はなく、泊まった客の名前の最後に、部屋の名前がかかれている。建物を新しくして、割烹旅館のような形にしたのかもしれない。そのあたりは篠井さんにきいてみよう。
紀州と越中の商人、侍らしき人たちの宿泊の目的をこれから探ってみよう。
湯本先生が山を歩いたと言ってきた。
「いや、実に生き物の豊富なところですね、僕の見たこともないような虫や蜘蛛がたくさんいます。市や小学校の図書館に昆虫図鑑や植物図鑑をもっと増やしてもらおうと思います、とても名前は調べ切れませんね」
「どの山に行ったのですか」
「一番近いところです、篠山です」
篠山は村役場からも一番近いところで、それでも茸はよく生える。村人が手軽に行って、ちょっと茸をとってきて、晩ご飯の添え物にする。
「まだ茸にははやいけど、手軽な山でいい林ですね、子供たちと行っても大丈夫そうですね」
「あそこなら迷子にもならんしね、大蜘蛛山は裾のところはいいが、上の方には子どもは気をつけないとね」
「まだ行っていないのですけど、そのうち僕だけでいこうと思っています」
「ああ、私も行ってもいいですよ、だいたいのところはわかるから」
そんな話をして、数日後に大蜘蛛山に行った。
「やっぱりこの山の中も明るいですね」
「下草も手入れしてるからね、茸をはやすにも程良い光が必要だし」
「この山の茸がおいしくないと言うのは不思議ですね」
そんな話をしながら先生と登った。
「うーん、ずいぶん座頭虫がいますね、ほら、これはアカザトウムシ、これはヒラタザトウムシ」
みんな同じ蜘蛛だと思っていたのに、先生は区別できるようだ。
「昔からこの蜘蛛はたくさんいますよ、メクラグモって言ってますけど、家にもたくさんいる。物置や風呂場なんかにもでてきます」
「これは、蜘蛛に近いけど、蜘蛛じゃないのですよ」
「え、糸を張らない蜘蛛の仲間だと思ってました、こいつら、ゆくり歩いているけど、いざとなるとはやいですよ、この細い足をよくあれだけ早く動かせると思うくらいです」
「そうですね」
「こいつらなに食ってるんだろ」
「雑食で、ミミズや死骸、それに茸もたべます」
「周りにたくさんいるので、皆同じだと思っていたし、こんな細くて長い足でどうやって獲物をとっ捕まえるのか不思議でした」
「それにしても、多いですね、この山は篠山よりたくさんいるみたいだ、それに、他の蜘蛛も多いですね、登り口のあたりに随分たくさんのジョロウグモと鬼蜘蛛が巣をつくっていましたね」
ジョロウグモと鬼グモはよく知っている。
「家にもたくさんいます」
「あ、これは知らない蜘蛛だな」
湯本先生は羊歯の上にじーっとしている白い蜘蛛の写真を撮った。
「蜘蛛も種類が多いので、知らないものが多いけど、ざっとみただけでもかなりのかなりの種類の蜘蛛がいますね」
「蜘蛛が多いので大蜘蛛山かもしれない」
「そうそう、これは私が感じたことなんだけど、メジロがこの山には多い気がするのですよ」
「麓や神社に蜜の出る椿なんかが多くありませんか」
「そういやそうだな」
「それだけじゃないかもしれない、メジロは巣は枯れ枝やなんかをひろってきてつくるんですけど、蜘蛛の糸を接着剤として利用するといわれているから、蜘蛛の多い大蜘蛛山に多いのかもしれない」
「ほー、そりゃしらなかった。
「それで、篠井さんの箱からは面白いものはでてきましたか」
「茶箱の中には炭帳、宿帳、地図くらいです、篠井さんのところにまだあるかもしれない、またきいてみるつもりです、ただ、江戸の初期から、紀州や越中の侍が良く泊まっています、何かあったのかもしれません」
「ほー、このあたりに何かお目当てのものがあったのかもしれませんね」
「これから調べるところです」
「おや、この蜘蛛面白いですね、しおれて崩れそうな茸にいる。これも知らない蜘蛛だけど、きっと小バエや小さな虫をねらっているんですね」
金茶の小さな蜘蛛がとろけそうな茸のひだの間にかくれている。
「テレビでやってましたけど、茸って、胞子をとばしたあとに、このように崩れて、匂いを出して、茸を食べる虫をあつめ、残っている胞子を運んでもらうんだそうですね、その虫をねらって、巣を張らない蜘蛛がとろけそうな茸にかくれるってわけです」
茸は食べることしか考えていな買ったので、なるほどと感心するしかない。
観察しながらゆっくり登っ手居るので、まだ途中だ。
「今日は、全体をみようと思ってきたのに、すみません、ついつい、見たことのない虫にあうと、じっくりみたくなってしまいます、さー上のほうにいきましょうか」
湯本先生は首をあげて歩き始めた。
「山そのものは単純だから、難しくはありません、ただ、裏の方に行くと、いろいろな山と連なるので、方向を間違うと、わからないところに行ってしまいます」
「裏の麓というのは細蟹部落のあるところになるわけですね」
「そうです、細蟹部落は裏の山の斜面です、もちろん大蜘蛛山の裏にもかかります、その地図のコピーが家にありますからさしあげます」
「大蜘蛛山から細蟹部落に行くことはできるわけですね」
「はい、上って降りていけばいいわけです、だけど、麓からぐるっと廻っていく道があって、そっちを使います」
「どうして、細蟹部落に遠回りしていったのでしょう」
そういわれると、確かに大蜘蛛山に道を作れば近い。それに大蜘蛛山の裏側の方は、今でも山の手入れをしない。昔からの慣わしで、楠木村に面した南側だけに人が入り間伐をおこなう。どうしてだろう。手入れをしたほうが山としてはいいはずだ。
「考えたことがないですね、その点は奇妙ですね、あまり茸がうまくなかったので、通らなかったのかな」
「焼いた炭を担いで、いくつかの山を遠回りして、楠木村に来るより、道を作った法が楽なのに、そうしなかった理由がありそうですね、大蜘蛛山の北側に何か秘密がありそうだな、こういうときは、宗教的なものか、危険があったのかということでしょうか」
湯本先生の指摘は確かに興味のあることだ。
もうすぐ頂上だ。
「あれ、これ見てください」と、湯本先生がしゃがみ込んだ。
春でも条件がよければ茸は生える。木の根元に茶色の茸が三本頭を出している。それぞれの傘にきれいな蜘蛛の巣がかぶされているので、白い網網のレースがのっているようだ。
「これ、蜘蛛がわざわざ茸に巣をかぶせたみたいだ。茸にくる虫をとるのかな、蜘蛛がみあたらないけど」
見ていると、一つの茸の傘のしたから赤っぽい蜘蛛が自分のかけた巣の上にでてきた。
「あ、でてきた、面白いですね、見たことのない蜘蛛だ」
湯本先生は何枚も写真を撮った。私も蜘蛛の巣に絡まれた茸など見たことがない。
「茸に蜘蛛の巣張って、虫をとろうということでしょうか」
「そうかもしれませんね、茸に虫がくるからそれを捕まえる、そういう守勢のある蜘蛛かもしれません」
湯本先生はカメラのレンズを取り替えてまた撮影した。
「マクロレンズより、もっと接写のできる特殊なレンズです。あとで科学博物館などの専門家に送って、種類を同定してもらうのに、蜘蛛の細かなところまで写しておいた方がいいものですから」
「捕まえて標本にしなくていいのですか」
「そうもしますが、ほんとに少ない種類だと、殺してしまうのは数を少なくするのでよくありませんから、僕は蜘蛛のけんきゅうしゃではないし」
湯本先生はあくまでも観察が中心の生物学者というところのようだ。
「虫が一匹もかかっていないんです、巣をかけたばかりなのかな、それに、においませんか、茸の匂いじゃないようだ」
私も顔を近づけて匂いをかいだ。
「たしかに匂いますよ、樟脳のようだ」
「僕もそう感じました。茸でそのような匂いをだすのがありますか」
「いえ、しりません、いやな臭いにおいのものはいくつもあります、虫が来る奴で、スッポンタケなんかです」
「ええ、僕もその茸はしっています、だけど、この臭いでは虫がこなくなる可能性もありますね、虫除けの匂いですから、それに茸がだしているのか、蜘蛛の巣が出しているのか分からない」
「そうですね」
「いや実に面白い、そのへんも卒業した大学の研究室か、科学博物館にたずねてみます」
そのあと、大蜘蛛山と頂から、周りの山を説明して、今日のところは下におりた。普通に歩けば、上るのに一時間半ほどだろう、そんなに高い山ではない。標高だと千メートルほどで、楠木村そのものが四百あるから、実際は六百メートルほどの高さだろう。
五月の連休になると、湯本先生は、校庭はもちろん山の中を、一人、または子どもを連れて虫観察に励んでいた。
私の方は、篠井さんと会ってわかったことを報告した。細蟹部落の炭の問屋だったことから、宿場町だった町と、楠木村の関係が少し見えるだろうと思ったかことから、その辺のことを、篠井さんに楠木村の便りに書いてくれないか頼んだ。
「忙しいことは知っていますので、かけたときで結構ですからお願いします」
「そうですね、わかりました、いつになるかわからないけど、それでいいですか」
「もちろんいいです、それと、もう資料はないでしょうね」
「うーん、もしかすると、何か出てくるかもしれません、戸袋の奥とか、明治時代の古い金庫みたいなものもあって、開けることができないんです、金目のものはないと思いますが、そのころの篠井の先祖が書いたもの残していないかとも限りませんね。金庫は明治になって建てた家の居間の隅におかれていました、その時の主人はいろいろ整理をするのが好きだったようで、家系図などもその主人が作ったものがもとになっています。お渡しした茶箱もその部屋の押入にしまわれていたものです」
「もし、何かありましたら、また見せてください」
「はい、石田さんにお渡ししますよ、それと、頼まれたことですが、文章はなれてなくて、石田さんが目を通しててくださいますか」
「あ、それは心配しないでください。役場の村のたよりの責任者の坂井さんは、文学部出身の人で、その人が直してくれますよ、もちろん時代考証的なことは私も少しはお役にたてるかもしれません」
そんな話をして家に戻ると、留守電に、湯本先生から大蜘蛛山で見つけたいくつかの蜘蛛はまだ名前のない種類だとはいっていた。特に茸を巣で包んでいた蜘蛛はゴケクモのなかまのようだとあった。昼休みに電話をくれたようだ。
小学校の終わる四時になって電話をかけた。
「湯本先生、ゴケグモってなにかね」
「石田さん、ちょっと前に話題になったアカゴケグモって覚えていませんか、港の近くの住宅の側溝にいたんですが、外国から来た毒グモでかまれると痛みや筋肉の麻痺などがおきるんです、だけどおとなしい蜘蛛ですし、牙は人の皮膚を通さないほど短いものなので、かまれてもほとんど影響ないようです、大蜘蛛山のゴケクモも心配いらないでしょう、それに毒があるかどうか分からないし」
「他のも毒グモですか」
「いや、違います」
「ゴケグモは巣を作るんかな」
「そうみたいです、ただジョロウグモのようなきちんとした形のではなくて、三次元の不規則なかたちをしているということです、だから、茸を取り囲んでも不思議はないかもしれません、ワラジムシやアリなどつかまえるようですよ」
その電話で、湯本先生は大蜘蛛山から、下におり、細蟹部落に一緒に行ってくれないかといった。次の日曜日に天気が良ければと約束をした。
日曜日は晴れた。湯本先生が車で私の家に来てくれて、大蜘蛛山の入り口に連れて行ってくれた。湯本先生は連休などに一人で大蜘蛛山の表斜面は何度も登ったようだ。
「ずいぶん蜘蛛の写真も撮りました。虫もいろいろいますけど、蜘蛛にはかなわないでしょう。やっぱり大蜘蛛山は蜘蛛の宝庫ですね、それで、蜘蛛の巣に囲まれた茸をずいぶん見ましたよ」
六月だがそれなりに茸が生えている。
「秋になったら、たくさんの茸が蜘蛛の巣に囲まれると思いますよ」
「だけんど、今まであんまり見たことがないですね」
「山の上の方でよくみかけました、これからいく裏の林の中にはたくさんあるかもしれませんね」
その日、先生は写真も撮らずに、ただ頂上に向かい、一時間ちょっとで上についた。私も足には自信がある。頂上には木が密に植わっていて、見通しはよくないが、反対を向けば村の方がよく見える。反対の北側をのぞむと山の連なりがみえる。本来ならば、そちらのほうから細蟹部落に行くのだが、今日は北斜面を降りていく。私も行ったことがない。
「この上には何度か来ましたけど、北の斜面も見た目には表斜面と同じようで、降りるのは大変ではなさそうです」
今では湯本先生のほうが私よりよく知っている。
確かに下を見ると、斜面は急でもなく、手入れはされていないが下草も丈が高いわけでは。当時、部落の人がなぜここを通らなかったのか、ふたたび疑問がわきおこる。 「あ、ここにも蜘蛛の巣のかぶった茸があります」
赤い茸に白っぽい蜘蛛の巣が絡んでいる。下に行くと、ここにも、ここにも、とゴケグモの仲間による蜘蛛の巣が茸にかかっていた。
「北側の方が蜘蛛が多そうだ、特にゴケグモだ。茸に巣をつくていないゴケグモもうろうろしている。」
「こんなにいるのだから、いずれ捕まえて、研究者に見てもらいます、毒があるか調べましょう」
隣の山の間には小さな谷川がある。そこに向かっておりていくと、斜面にいくつか穴があった。人がかがめば中に入れる。動物の穴ではなさそうだ。いつごろからあるのだろう。縄文人がつくった可能性もあるが、このあたりに縄文人が居たという話は聞かない。ただ、居たとしても不思議はない。もう一つの可能性は、細蟹部落の住人が何かの目的で掘ったということである。
湯本先生がのぞき込むと、
「うわ、ゴケグモがうようよいる。ザトウムシもたくさんいますね、確かに蜘蛛の多い山だ。蜘蛛の専門家に来てもらわなければいけないな」
三つほど穴があったが、どれにも蜘蛛がたくさんいる。特にゴケグモである。
谷川まで降りると、水の流れは少なくて、反対側の山の麓に石伝いにわたれる。綺麗な水だ。
「反対側が炭焼きの人が住んでいた山なわけですね」
「そうです、ほら左手の方に登るみちがあるでしょう、あれをいくと、いくつか山の中腹を通り、大蜘蛛山を迂回して、村の道のほうにでられるんです」
「炭を運んだ道ですね」
「そうです、林の中に炭焼きの跡や、住居跡が残っていますよ」
「大蜘蛛山を通れば、ずいぶん簡単に、部落までこれますね」
湯本先生が降りてきた林を見上げて言った。その通りである。
「そうですね、なぜ部落民はそうしなかったのでしょうね」
「ほんとうに」
細蟹部落はその山の中腹にある道の斜面に広がっている。谷川をわたって、見上げると、木々の間によく見える。半分崩れた家が転々とあり、炭焼き釜のあともみえる
一つの家に行ってみた。おそらく茅葺きだったと思われる崩れた家の中を覗くと、皿や茶碗やひしゃげた薬缶、それにガラスの小さなビンがいくつも汚れたままころがっている。
「明治時代になると、もう人はいなかったんでしたか」
「そうですね、炭の需要は昭和になってもありました、だから、誰もすんではいなかったと思うけど、楠木村の住人などが、炭が必要なときはここに来て、利用して、炭を作って、もって帰ったりしていたとおもいますよ」
「江戸時代のものは残っていないでしょうね」
「どうでしょう、少しは残っているかもしれませんね、建物もなおしながらつかったのでしょう」
「炭焼きだけの為に部落ができるとい言うことは、素人から見ると、なんだかおかしな感じです、今、石田さんがおっしゃったように、一時ここに来て、炭を作ればいいわけですからね、こんな厳しいところで生活したのにはほかのわけがあったのかもしれませんよ」
そういわれればそうである。炭を焼くだけで部落ができるということはまれなことだろう。
「年中炭を焼いている必要があったのはなぜでしょう、町の方だってしょっちゅう雪かきしていた記憶があります、あまり冬に炭焼きというのはきいたことがないですね」
「そういえばそうですね、雪の季節のために、炭を作ってしまっておくのが普通ですね、だけど、ここの部落の人は冬でもここからでなかったわけだ、考えてみなかったな」
笹蟹部落が盛んだったころ、冬にそこの者が楠木村にものを買いに来たり、話にきたりということがあったのかなかったのか記録にはない。
壊れかけた家の中にも蜘蛛がたくさんいた。巣を張っているのもあるが、土間にはいると、ゴケグモやザトウムシがあわてて逃げていった。
部落の家々を見て気付いたことだが、家のまわりに焚火の跡がたくさん残っている。寒いから当たり前かもしれない。一つの家にいくつもある。草の中に炭のかけらもたくさん落ちている。
一軒、当時としてはかなりしっかり建てられていたと思われる家があった。図書館でコピーした笹蟹部落の地図にも、その家ははっきりと書かれていた。リーダー格の者の家かもしれない。
家の軒下には積まれていたと思われる炭が崩れている。それだけではない、庭に積まれた炭の山もあった。もうばらばらになっている。
「おかしいな、なんで、炭を庭においておくのだろう、野積みにしておいては、売り物にならない」
家の軒下においてあった炭から、白っぽい茸がひょろんと生えている。
「炭に生える茸だ」
「ああ、それはヤケアトツムタケっていって、楠木村でも焚火の跡によく生えていたものですよ、今は焚火をしなくなったから見なくなったけど」
「名前は知ってましたけど、実際に生えているのを見るのは初めてです、でもヤケアトツムタケは焚火の跡の土から生えるのではないのですか、炭からはえますか、これは炭の茸だ」
そういわれるとわからなくなる。
「そうだね、先生がいうように、炭じゃないかもしれないな、それに茸の色は茶色だったな」
湯本先生は写真を撮った。
「ゴケグモが炭の茸にのぼってますよ」
炭の茸にゴケグモが登りはじめたところだった。湯本先生は写真機を映像撮影にきりかえた。
その家の裏にいくと、また炭から生えている白い茸があった。湯本先生は炭ごと茸を採ると袋に入れた。
「この茸も研究者に調べてもらいます、このあたりは虫だけじゃなくて、茸も新しいものがありそうだ」
「茸はこの村だけじゃなくて、日本の茸の多くが名前がまだつけられていると言われてますからな」
茸、虫、蜘蛛新しい種類のものが見つかると、楠木村も知られるようになるだろうし、細蟹部落のことがわかると、さらに有名になるだろう。湯本先生がきてくれたおかげで、私も歴史を調べる張り合いがでてきた。
それから一週間ほど経ってのことだ、湯本先生から、先生の卒業した大学の先生が、蜘蛛を直接調べにくるという連絡がはいった。一緒に行くかという誘いの電話である。研究者は何かを見つけるとその場を動かなくなる。それに付き合うのはかなり体力と精神力が必要になる。今回はことわって、村の歴史の調査に専念することを話した。
ガソリンスタンドの篠井さんの校正すみの原稿もできて、時代考証も私のわかる限りはチェックをした。その校正を坂井さんが届けるというので、車で一緒に篠井さんの家までいった。
「いや、こんなことでよかったでしょうかね」
篠井さんは恥ずかしそうに、直されたものを受け取った。
「わかりやすく、内容がよく伝わりました、直したのは誤植と、てにおはだけです」
明美ちゃんが言った
わたしも、「おかしなところはほとんどなかったですよ、図書館にあった細蟹村の資料と照らし合わせて、とても面白いことに気がつきました。もしかすると、篠井さんの炭問屋と細蟹村が同じ頃にできたのではないでしょうか」と私見を言った。
「ほお、そうなりますか、確かに炭を作るところがあって、それをほしいところがあるわけだから、炭を必要とした宿屋のうちが卸を始めたのですかね、泊まる人に広めることもできるわけで」
「そうですね、何か資料でもあればはっきりしますが」
「そうだ、うちの戸袋の奥に押しつけられていたものがありました、読んでもわからんので、石田さんに渡そうと思っていました」
私と明美ちゃんは座敷に通され、篠井さんが戸袋を開けると古ぼけた文書竹籠をとりだした。
「手前にたくさんの掛け軸おいてありましてな、古道具屋に見せたら、たいしたものありゃせんというのでやっちまいました。ところが、高く売れたらすこしくれるなんていってましたらな、一本、一千万のものがありましてな、そいつ半分くれよりましたよ、この竹籠の手文庫は掛け軸の奥の隅にあったんですわ、掛け軸は明治のはじめに七代目あたりが集めたんですな、七代目が手文庫を奥にいれちまって、掛け軸をしまったようですね、竹かごの中のものは掛け軸よりもっと古いもんでしょう、安衛門と書いてあるから三代目あたりが書いたものかもしれんです」
「いいものがみつかりましたね、読ませてください」
新たな資料もかりることができ、我々は篠井さんの家を出てた。坂井さんが車でいえまでおくってくれたので、すぐに手文庫の竹籠を開けた。八冊の薄い冊子がはいっていた。一番厚いのを手に取ってみると、篠井炭問屋覚え書きで、これは安衛門の名があり、安衛門の祖父が炭問屋をはじめたときのことから、自分の代での出来事を書き綴ってあった。とても貴重な資料だ。読み始めてしまった。
篠井宿は湯屋からはじまっていて、すぐに芸子をおく宿屋になっていったことが記されていた。安衛門のときに、紀州の大商人が立ち寄り、火鉢につかっていた炭を見て、このあたりではよい炭が作れるのではないかといったとある。楠木村の山には樫の木が多いからである。その商人は樫でつくった備長炭を江戸におろしていたが、あらたな炭を探していてこの町によったらしい。江戸に出るついでによい炭がとれそうなところを見て回り、炭を作らせたりもしている紀州の殿様の息のかかかった店だと書かれていた。三島才造と言うその商人は、安衛門にいい炭を焼けば買うといって、炭作りをすすめたとあった。それをうけて、樫の木の多い大蜘蛛山の反対側に下りると樫の木が多い山が連なり、むかしから細蟹と呼ばれるあたりに、炭焼きをする場をつくったとある。
ということは、細蟹部落は三代目篠井安衛門によって始められたということになる。炭焼きに、楠木村の民をやとい、家を与えたとある。これは細蟹が楠木村とつながる歴史の証拠として大事な文献である。
もう一つの資料にも思わず、ウオッと声をあげてしまった。
表紙には炭草片とあった。秘の赤い字が見える。ページを開けると、越中薬師、名護茶貝(さがい)様よりお聞きしたことを書き留めておく。安衛門とある。
さらに開くと、重なった炭から茸がでている絵があった。茸にはゴケグモが傘の上に乗っている。
まさに、大蜘蛛山にいるあの蜘蛛だ。それに、細蟹部落の炭のあとから生えていた茸だ。
そのあとは茸の説明らしい。炭草片とあり、炭よりはえる茸で、傘も柄も色は白く、柄は細い。長さ一寸、傘の幅半寸、毒はあるが、一つ食すくらいでは、軽い口のしびれがある程度で、どんぶりいっぱい食すと、体がしびれ、動けなくなるので注意すべし。とあり、細蟹部落の炭に生えていた茸は毒茸の仲間のにようだ。次に柄の炭草片の上に乗っている蜘蛛の説明があった。ゴケグモのようだ。ただ茸に巣はかかっていない。
この蜘蛛の名前は草片細蟹とある。草片細蟹は炭焼場の反対側の山の斜面に多くおり、特に穴の中にたくさんすんでいる。茸の汁を吸い、茸に糸をかけるものもいる、とあった。
草片細蟹は人に害を加えるようなことはなくよく増える。この蜘蛛を利用して、炭草片から毒を採る方法を茶貝から伝授を受ける。
茸の生えている炭を一カ所に集め、山より草片細蟹をつかまえ、炭の上に放ち、茸の汁を吸わすと猛毒の細蟹となる。かまれても痛みはしょうしょうあるが、死ぬようなことはない。茸が枯れる前に細蟹を集め濃い酒につける。一日おいたのち、上澄みをすくいとる。この酒は猛毒の液である。万倍に薄めると、心の臓を強め、心の臓の病で胸に痛みが生じしときには強心薬となる。原液をもちいれば、矢の先など塗布し、野獣を捕らえることができる。
細蟹部落では、冬の間は、こういった作業をやっていたのではないだろうか。
炭草片が鳥兜の根が同じような働きを持っているわけである。それをゴケグモの仲間の蜘蛛を利用して集める工夫をしたことになる。
さらにこの宿に越中から宿泊の旅人が多いわけがわかり、炭をつくることで、ヤケアトツムタケの仲間と思われる炭に生える毒茸を培養し、縄文人のすんでいた穴にたくさんいた茸蜘蛛を利用して毒を吸い取り、それを越中の薬屋が買い取っていたと思われる。
笹蟹部落ではこの蜘蛛を大事にふやすために、大蜘蛛山の北斜面、裏の林は通らないようにしていたのではなかろうか。これで細蟹部落に大蜘蛛山を迂回していく理由がみえてきた。
大発見だ。それで、もともと蜘蛛が多く、この辺では目立つ山なので、大蜘蛛山と名付け、蜘蛛をまつる神社をつくって、豊作と蜘蛛の豊猟を祈ったのだろうか。
だが疑問がわいた。
炭草片そのものを酒につけて、毒を抽出してもいいのではないだろうか。
この話を篠井さんと湯本先生に伝えた。湯本先生は、数日前に、大学の蜘蛛の先生をつれてきて、大蜘蛛山の蜘蛛の調査をおえたところである。
「すごい文献ですね、大蜘蛛山にはいろいろな蜘蛛がいて面白い山だと大学の先生がいってました。それで、大蜘蛛山のこちら側にも茸蜘蛛はかなりみられました。巣を張るのは雄、張らないのは雌ということがわかりまいた。雄蜘蛛はうまそうな茸に蜘蛛の巣をはって、雌をさそうのだそうです、巣は虫をつかまえるためではありません、とても不思議な蜘蛛です。雄も雌も茸を吸って生きています、おいしい成分をみなすってしまうので、大蜘蛛山の茸がうまくないのだろうという結論になりました」
「それじゃ、その蜘蛛が他の山に行ったら茸の味が落ちちまいますな」
「大丈夫だそうですよ、あの山の北斜面、特に縄文人の穴のあたりが一番蜘蛛にとって住みやすいのですが、それ以外ではあまり増えることもできないし、ひろがることはないだろうといっていました。特に夜に出歩く蜘蛛で、南斜面にきても、昼になると多くは北斜面のほうにもどるようです、僕たちが調べた結果も、北の方にたくさん蜘蛛の巣のかかった茸がありましたね」
先生は依然調べたときにもたしかにそういっていた。
「それでは、蜘蛛が広がることは心配しなくてもだいじょうぶですね」
「異常気象でどうなるかわかりませんが、少なくとも、今まで通り、山を丁寧に管理していれば問題ないと思います」
そこで、草片細蟹の疑問点を話した。なぜ蜘蛛にわざわざ茸の汁を吸わせて、毒の液に仕立てたかという点である。先生はいとも簡単に答えてくれた。
「調べなければわかりませんが、茸の毒は水にも酒に溶けにくいもので、薬に作りにくいものなのではないでしょうか、あの蜘蛛に吸われると、その成分が酒に溶けやすいものとなり、毒性が強くなるのではないかと思われます」
科学者の知識はこういうふうに解析することができるのかと、改めて感心した。
「いや、先生がここの小学校に赴任してくださったので、わからなかったことが解決しました。ありがとうございました」
「とんでもない、こんなにすごい自然のあるところに戻れたのはとてもラッキーです、石田さんがこの村の歴史を丹念に調べてくださったからだと思いますよ」
「校庭の生き物の絵本はおだしになるのですか」
「もちろんです、子供たちも一生懸命しらべてくれています、出版社のほうから、是非出してくれと言っています、それだけではなく、こどもたちと草片細蟹の観察をつづけて、絵本を作ることも考えています、茸の観察もいいですね、それも子供たちとやりたいですしね」
湯本先生はとてもうれしそうだ。
「それはたのしいですね、楠木村の財産です」
「茸細蟹は茸蜘蛛という名にしたほうがわかりやすいとおもいますので、そうします、新種ですので、茸の専門家が和名をそれにするといってくれました。それに炭からでる毒茸は世界的な発見ですよ、これも大学の先生が学会で発表すると思います、そうすると、世界から蜘蛛の専門家がやってくると思いますよ、楠木村に蜘蛛の自然博物館でもできるといいですね」
「あ、それはいいですね、村長に話してみましょう、それに、篠井さんにも、あの人は新しいことをどんどんする人です、手助けしてくれますよ」
その後、茸蜘蛛のことは、テレビや新聞でも報道され、楠木村の名前をよくみるようになった。村では蜘蛛の自然博物館の構想が本格化し、篠井さんが、村に宿まで作る計画をたてた。ただ、自然を壊さないように、古い家を利用したりしようということになった。
私も、細蟹部落の歴史を本にすることになった。実は楠木村の負の部分も見えてきた。楠木村や赤瀬町は甲州街道から離れていたが、街道に関わる古文書に、追い剥ぎの記述があり、その正体が楠木村に関係のあることがわかった。旅人が悪いものを飲まされ苦しんでいる間に、金品を盗む犯人が楠木村の出であったそうである。
毒茸の汁を吸った蜘蛛からとった毒を利用して、悪いことに使ったのではあるまいか。村の歴史を正直に書こうと、来年に向けてまとめているところである。
最後に、大蜘蛛山の北斜面にある三つの穴が、縄文人の穴であることが調査で明らかになった。一つの穴に調査隊がはいったのである。入り口は狭くなっていたが、中は広く長いもので、縄文人の骨と、縄文人がもちいたとおぼしき土器類が残されていることがわかった。まだ、そのままの状態にしてあるが、いずれそのままの状態で保存し、観察のできる通路を作るという構想がある。土器のいくつかには、茸と蜘蛛絵が描かれている。
いずれ大蜘蛛山を含め、細蟹地域が保存地区に指定され、楠木村は観光の名所にもなるだろう。
蜘蛛の山


