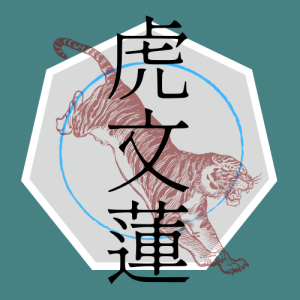名も無き日々のカケラたち 1
すりガラスがはめ込まれた木製の引き戸を勢いよく開けたフユキは、憂鬱そのものといった表情を浮かべていた。濃紺色のブレザーの下には厚手の黒いパーカーを着ており、被っていたフードをやや乱暴に脱ぐと明るめの茶髪が露わになった。
「まーたお前か」
「またとはなんだよ、またとは」
教室内の一角には、先客とも言える黒髪の少年が椅子に座ってフユキを見つめ返していた。フユキと対等な勝負ができそうなくらい、その表情はくもりに満ち満ちている。ブレザーの下には、学校指定となっている緑色のジャージを着込んでいるのだった。
「ミカゲはさあ、そんなに俺と一緒に補習受けたいわけ?」
「んなわけねえだろうがよ」
「じゃあなんでここにいるんだよ、しかも二週連続じゃん?」
気だるそうな足取りで、室内履きのサンダルをぺったぺったと鳴らしつつミカゲの近くにやってこようとしたフユキだったが、ミカゲはというと一瞬だけその眼差しを鋭くした。
「待てこらぁ! ちゃんとドア閉めろって!!」
言って、半分ほど開けっぱなしになっている引き戸をビシッと指差したミカゲは続けた。
「せっかくここ暖房かかってんだから、ドアはちゃんと閉めろや」
「……ちっ」
いちいちうっせーな、とぼやきながらフユキはもと来た道を引き返す。ドアに手をかけようとしたところで、ビクッと肩を震わせた。
「あれ、ヤマちゃんせんせー……?」
程なくしてパタパタという足音が教室の外から響いてきたかと思うと、あらあ、という楽しげな女性の声が聞こえてきた。
「二人ともちゃんと来てるわね、えらいえらい」
「ヤマちゃんせんせーだ、あれ、なんで?」
彼女を見つめるミカゲは、きょとんとした面持ちになっている。
教室内にやってきた若い女性は、二人の学年の数学科目を担当している教師だった。ツヤツヤとした長い黒髪が印象的で、小柄な体型をしている。
「そういやいつもならシロせんせなのに」
ミカゲと同じように疑問を抱いたのか、フユキも口を開いた。
「シロゾノ先生は、午後から校外の用事で早退したから私が代わりに来ました」
「そーなんだ」
「シロゾノ先生からは課題を預かってるから、これをやってね」
席についている二人へ複数枚のプリントを渡すと、ヤマちゃんせんせーは羽織っていたチェック柄の肩かけブランケットを直しながら言った。
「私はこの後職員会議だから、ここにはいることが出来ないの。終わったら様子を見に来るわね。会議は、一時間もかからないとは思うけど」
ヤマちゃんせんせーは、二人ともがんばってね、とにこやかに言うと教室を出ていった。
その姿を見つめながら、ミカゲがぽつりと言う。
「なんかせんせーたちも忙しそうだな」
「そりゃあ十二月だしな……師匠も走るほどの忙しさ、だから師走、ってな」
「あっそ」
別に前から示し合わせたわけでもないのに、隣同士の席に座った二人はそれぞれプリントに目を通し始めた。
半分ほど結露した窓の外はどんよりとした空模様で、チラチラと白いものがちらつき始めていた。
「ミカゲ、シャーペン貸して」
「てめえ……手ぶらで来るんじゃなくて、ちゃんと自分のやつ持ってこいよ」
「何本も持ってんじゃん」
「ったく」
軽く舌打ちしつつ、ミカゲは隣にいるフユキに水色のシャーペンを渋々と投げ渡した。
サンキュー、と呟いて受け取ったフユキはプリント上部に自分の名前を走り書きして、ちらっとミカゲの方を見た。
「ミカゲさあ、なんで今回補習になったの?」
「俺だけ答えるのも癪だから、まずはお前が先に言え」
「はあ? ……ま、いいけど。復習とか全然やらなかったし単純に解き方もわからなくて、ほぼほぼ白紙で提出して見事赤点になったから」
「へえ」
軽く相槌を打ったミカゲは、持っていたシャーペンをプリントの上に放り出したかと思うと、妙にわざとらしく大きなため息をついて腕を組んだ。天井を仰ぐその横顔はきれいだが、角度が演技がかっているようにも見える。
「聞いて驚け、見て騒げ」
「なんだよいきなり」
「俺はさあ、最後まで解答できたんだよ。奇跡的に。これで今回の期末は赤点回避できるって自信満々だったんだよ……」
言って、ミカゲはおもむろに眉間へそっと手を当てた。役者モードに入っているのかと言わんばかりの振る舞いだった。
「それがなんということだ、その解答の記入欄が全部ずれていた。こんな悲劇があるか?」
「まあ、ミカゲのいつものお得意パターン、つまりお家芸ってやつ? 何回目だよもはや」
「うるせえ!!」
カッと目を見開いたミカゲは、フユキに向かって感情のままに叫んだ。
「最初から諦めモードで何も書かないお前とは雲泥の差だ!! これでも俺はベストを尽くした!!」
「いやいや、全問解答できたけど結局見直しないで悦ってるお前もどうかと思うよ」
「んだと?!」
鼻で笑うフユキに掴みかからんとしていたミカゲだったが、ギリリと歯軋りをしたかと思うと唐突に机に向かって突っ伏した。
「……もうやだ、数学嫌い」
それまでの勢いどこへやら。
ミカゲの力ない呟きに、シャーペンを片手で華麗に回し続けるフユキは言った。
「お前さあ、俺よりは遥かに地頭はいいんだからさ。そういうちょっとした凡ミス減らしたら、いちいちこんな苦労しなくて済むんじゃねーの」
「……ぐすん」
「ぐすぐすすんな。終わっちまったもんはしょーがねえ」
フユキはプリントの端っこに小さな落書きをしながら続ける。ふにゃふにゃとした線で、等身のバランスがめちゃくちゃな某猫型ロボットの絵が次々と出来上がっていく。
「次回同じようなミスを繰り返さないためにも、反省するところは反省してだな。次、頑張ればいいじゃん」
「こういう時だけ正論を話すんじゃないっつーの……」
むくっと顔を上げたミカゲは、フユキの方を見やった。
「お前だって、赤点続きじゃあ成績やばいんじゃねえの?」
ジト目のミカゲをチラッと見たフユキは、相変わらず飄々としていた。
「まーな、連続赤点達成の歴代校内レコードを保持する俺のことだからな」
「ふんぞり返って自慢することじゃねえぞ、それ」
「まあまあ。次の期末試験では、九回裏ツーアウト満塁のところで代打逆転サヨナラホームランばりの最高な展開を見せつけてやるよ。震えて待ってろ」
「そんな上手く行くもんかよ」
はああ、と無駄に大きなため息をつくミカゲは、シャーペンを握り直して設問に取り組み始めた。
二人で取り止めもない話を紡ぎながら、そろそろ一時間ほどが経とうとしていた。窓の外は、陽が沈んでだいぶ暗くなってきている。
「そういやヤマちゃんせんせー、来ねえな」
「会議、長引いてんじゃねえの」
「ふうん……ミカゲ、そういやお前」
「何」
「進路、どうすんだよ」
区切りのいいところでシャーペンの手を止めたフユキは、体を後ろへ傾けて椅子を前後に揺らしながら尋ねるのだった。
「……まだ決めてねえよ」
プリントに視線を落としたままのミカゲの口調は、重かった。
「この前三者面談あったじゃねえか。その時はなんか具体的な話、したわけ」
「ぶっちゃけると平行線、だったな」
「へえ」
「親の希望と俺の希望が全く噛み合ってないからな。担任のツカちゃん、俺たちの言い争い見てずっと困った顔してたなあ……」
ははっ、と笑ったミカゲは自虐的な笑みを浮かべる。
「親はどうしても、俺のこと私立の大学に入れさせたいみたいだけど……俺はそれが一番良い選択だとは思わないんだよな」
「前に言ってなかったっけ、お前の希望する学科と親の希望が合ってないって」
「それな」
やれやれ、といった様子でミカゲは肩を竦めた。
「結局お互い譲らないからさ、平行線、もしくは衝突して話し合いが中途半端に終わっちまうんだよな。途中から熱くなって感情的になるのも、いけないのかもしれないけど……」
「そのこと、他に誰か相談する相手とかいるのか」
「この前の三者面談の時の口論で、ツカちゃんには状況が知れただろうしな。あとは、どうだろう。他にいないと言えばいないかな」
設問の解答を終えたらしく、ミカゲはシャーペンを机の上に放った。かつん、という乾いた音が室内に響いた。
腕組みをしたフユキが言う。
「考えられるとしたら、進路相談室の先生に話してみるとか?」
「それは俺も思った。親がああいう態度だから、説得材料を見つけるための相談とか、できたらいいけど」
「確かに。……あとは」
フユキは、少し言葉を区切った。
「なんかあったら、俺に言ってもいいんだからな」
「え?」
顔をはっと上げたミカゲは、隣に座るフユキの方を見た。
「愚痴とかいくらでも聞いてやるし。親と喧嘩して家にいるのつらかったりしたら、俺のとこに来てもいいから」
まっすぐな眼差しで静かに伝えるフユキを前に、ミカゲはぎゅっと唇を噛み締めた。
「お前は、お前が納得できる方向に進むべきだと俺は思うよ。絶対妥協すんじゃねーぞ」
「言われなくても、わ、分かってるって……」
と言って、ミカゲは咄嗟に机の上へ視線を落とした。どことなく、フユキの視線から逃げるような素振りにも見えた。
ちょうどその時、教室の外からパタパタという駆け足の音が聞こえてきた。
「ごめんねー! 会議長引いちゃって、こっち来るのが遅くなっちゃって……」
ヤマちゃんせんせーが室内へとやってきたのを見て、フユキは自分のプリントを手に席を立ち言った。
「お勤めご苦労様です」
「なんでヤクザ映画みたいな物言いなの、そこは」
フユキは、隣に座るミカゲのプリントも回収するとヤマちゃんせんせーへと手渡した。
「この後って、どうなるんです」
「シロゾノ先生が採点して、後日返却するって言ってたわよ」
「了解っす」
「二人とも、遅くまでお疲れ様でした」
じゃあ気をつけて帰ってね、と言うとヤマちゃんせんせーは教室を後にした。
ひらひらと手を振りながらその姿を見送ったフユキは、後ろを振り返った。使っていたシャーペンや消しゴムをペンケースにしまっていたミカゲと、目が合った。
「で、ミカゲ。この後なんだけど」
「?」
やや困惑気味なミカゲを前に、フユキは制服のポケットに手を突っ込んでスマホを取り出す。少し操作をしたかと思うと、フユキはその画面をミカゲに見せた。
「俺の奢り、って言ったら食う?」
「え……えっ?! 昨日から発売になったトリプルジューシービーフハンバーグ、ハバネロソース付きのセットが無料で食えんの?! マジで!! しかもポテトもドリンクもLサイズじゃん!!」
「最強無比を誇る俺のクジ運に感謝するんだな」
「最高じゃねえか。お前、そういうところはほんとクジ運いいよなあ……」
呟きながら、席を立ったミカゲの表情は幾分明るいものだった。
「じゃあせっかくだから、ゴチになるかな。腹も減ったし」
「おうよ、食え食え」
「人の奢りで食う飯ほど美味いもんはないしなー」
「あながち間違いではないけどな、それ」
そんなことを賑やかに話しながら、二人は教室から出ていく。
程なくして、各教室に、廊下に、階段に、そして校内全体に、下校を促すアナウンスが流れ始めたのだった。
名も無き日々のカケラたち 1