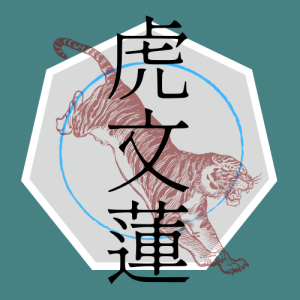あかくて、おいしい。
※作中に血液の表現が出てきます。
終業のチャイムが、静かに校内へと響き渡っていく。
授業の終わりと同時に、普通であればがやがやとした生徒たちの喧騒が生じるのであろうが、ここ━校内の一階に位置している保健室━はそういった環境とは無縁である。
ううん、というかすかな声が室内の一角から聞こえてきた。
「……今日も残りあと一限かあ」
天井から吊るされている生成り色のカーテンによって周囲を取り囲まれたベッドの上には、一人の少女が座っていた。なんともうんざりしたような、退屈そうな表情を浮かべている。セーラー服にプリーツスカートという姿の彼女が三角座りをした体勢で両手を上に向けて伸びをすると、腰まで届きそうな艶やかな黒髪がかすかにゆらりとゆらめいた。傍らには、それまで読んでいたと思しき教科書が開かれた状態で置かれていた。
足元には掛け布団が畳まれた状態になっており、その上に自身が使っている通学バッグを置いている。彼女はもぞもぞとベッドの上を移動して、通学バッグに手を伸ばした。
「よーこせんせー、いつ戻ってくるんだろ」
彼女が口にしたのは、この部屋の主である養護教諭のことだ。三十分程前に、二階の職員室に少し用があるからと言って保健室を離れているが、戻ってくる気配がない。
「ま、私は私で一人の時間が長くなるから気楽でいいんだけどね」
彼女がそう呟いて通学バッグから取り出したのは、ハードカバーの書籍だった。紙製のしおりが挟まれているそれは、彼女が数日前から読み始めていた小説作品であった。
ふんふーん、と鼻歌を軽く歌いながら彼女が読み始めたところで、保健室入り口のドアがコンコンコンと叩かれる音が響いた。
「……?」
咄嗟に顔を上げた彼女は、何かを探るような面持ちになる。彼女のいる位置からはカーテンによって外側を窺い知ることはできないが、それでも彼女は音の響いてきた方向をじっと見つめる。警戒心をあらわにして、用心深い眼差しで。
また、コンコンコン、というノック音が響く。さっきよりも、リズムを刻むテンポがやや速めになっていた。それから間を置かずガラガラと勢いよく引き戸を開ける音がしてきたので、ベッドの上にいた彼女は手元を見ることなく本を素早くパタンと閉じて、自身の後方に置いた。
そしてカーテン越しに、室内へと入ってくる人物へ向けて全神経を研ぎ澄ます。
(人数は二人。どちらとも、女子の生徒見たいね)
それと同時に、ゴクリ、と反射的に喉を鳴らすのを彼女は止めることができなかった。
(なんだかとっても……おいしそうな匂いがする)
「失礼しまーす! あれ、先生いないのかな?」
静かだった保健室の中に、やや切羽詰まった女子生徒の声が響く。
ベッドから両足を下ろし上履きを履いた彼女は、ひらりとカーテンをめくって自身の姿を表にした。
「……篠待先生のこと?」
彼女はそう言って、来室したばかりの生徒たちに目を向けた。彼女の予想通り、そこには自分と同じ制服姿の二人の女子が立っていた。二人の襟に縫いつけられたラインの色はどちらとも白色だ。対する彼女はというと、青色のラインの持ち主だった。
「あ、あの……」
「先生は職員室に行ってるみたいよ。すぐに戻ってはくると思うんだけど」
二人が後輩格の生徒なのだとラインの色で識別した彼女は、至極落ち着いたトーンで話す。
「そうなんですか。実はこの子がさっき怪我しちゃって……」
「あら、大丈夫?」
声をかけながら、彼女はすっと視線を移す。片手に、パステルトーンのハンカチを巻いてもう片方の手で上からぎゅっと握りしめたショートカットの女子生徒は、付き添いの生徒に促されて教諭のデスク近くにある椅子へと座らされたのだった。
そのハンカチのところどころには、真っ赤な染みが滲んでいる。
(ああ、なるほど)
その光景を見た彼女は、瞳孔をわずかに開かせた。
と同時に人知れず、自身の心臓が一段と高鳴るのを感じた。
「理科の授業で解剖をしたんですけど、器具を洗っている途中にメスで指を切っちゃったんです」
ポニーテールの髪型をした付き添いの生徒が話すも、指を切った当の本人はどこかぽかんとした表情のままだった。
「切り傷なのね。しっかり上から押さえてて。傷口は、心臓の位置よりも高くして……そう」
言いながら彼女はそっと自身の手を添えて、血の滲むハンカチに包まれた片手を肩よりも少し高い位置にして支えてあげた。
「あの! 私、職員室まで行ってきます! 先生のことすぐ呼んできますんで!」
付き添いの生徒はやや慌てた口調でそう言うと、ドアを開けて保健室を後にした。ポニーテールを振り乱して、まるで風の如き速さであった。
「……とても足の速い子なのねえ」
少々呆気に取られた彼女が見送りながら呟くと、くすくすとした笑い声が隣から聞こえてきた。
怪我をした生徒はようやくそこで、反応らしい反応を見せたのだった。
「あの子、とっても足が速いんですよ。陸上部の子なんです」
「そうなの?」
「でも、血はあんまり好きじゃないみたい……」
へえ、と上の空気味に相槌を打った彼女は、先ほどから鼻腔をくすぐる匂いに思わずごくっと唾を飲み込んだ。うっすらと、背中に汗をかく感覚にも見舞われ始めていた。
「メスで指を切ったんですって? 痛かったんじゃないの?」
「いえ、それが切った直後はあんまり痛みを感じなくて」
「そうだったの?」
「切れ味が良すぎたのかもしれません。切ったことにも最初気づかないくらいだったので」
そう話す生徒の表情は、いまだにどことなく実感が湧いていないような面持ちだった。深刻そうな色はその顔つきから見て取れない。
「自分よりか、周りの子達がびっくりして騒いでました」
「あらまあ……」
「みんな、すぐ保健室に行かないと! って」
怪我をした生徒はふふっと笑って、少しだけ身を捩った。しばらくの間片手を高めに掲げる姿勢を続けているためか、腕に少し疲労が溜まってきているようだった。
どうにもこうにも、自身の心臓がどくどくと速く脈打つのを抑えることができない。心なしか呼吸が浅く速くもなってきているのを認識した彼女は、何度か大きく瞬きをした。
(最後にご飯を食べたのは、いつだったかしら。ひょっとして、もう、一週間も前……?)
その事実に気づいた彼女は無意識に口を開きそうになって、途中で真一文字にぎゅっとつぐんだ。
(ここは、ここだけは、我慢しなきゃ)
(ああでも、こんなにおいしそうな匂いがするのに)
背中だけではない、もはや首筋にも汗をかき始めていた彼女は、頭の中でぐるぐるとした思考の渦に巻き込まれていた。
(無闇やたらに食べていいってものじゃないでしょう)
(でもこれはどう考えてもとびきりなご馳走の匂いじゃないの)
互いに相反する思考が大きな波となって押し寄せる。せめぎあい、ぶつかり合い、そしてその間に残酷にもからからと喉を干上がらせてしまう。
「ちょ、ちょっとごめんなさい……」
力なく絞り出した口調で、彼女はそう言ってゆっくりと両膝を床の上についた。合わせて、怪我をした片手を支える自身の両手も一緒に下がってしまう。
「どうしたんですか、先輩」
「……」
怪我をした生徒が心配そうに声をかけるも、すぐに応答することができない。
彼女は、両手に力が入らなくなってきていることに気がついた。小刻みに震えている。
(もうだめだ)
俯いたままの彼女は、観念したかのようにぎゅっと両目を閉じた。
(我慢、したかったのに)
そして今一度そこで、彼女の鼻腔を濃い血の匂いが掠めていったのだった。
「え、あ」
眼前にある豊かで長い黒髪が乱れた動きを見せた瞬間、怪我をした生徒は呆気に取られた声を出すことしかできなかった。
がばっと顔を上げ、血染めのハンカチを握って力のままに剥ぎ取ると、彼女は血の色に染まった生徒の素手を掴んで躊躇することなく自身の口元までぐいっと引き寄せて。
そのまま間髪入れず、ぱくり、とまだ傷口が開いたままの人差し指を口の中へと咥え込んでしまった。
「せ、せんぱ、い」
突然発生したこの状況をよく把握できず固まることしかできない生徒だったが、指先から伝わってくる熱の高さに戸惑って瞬きを繰り返すことしかできない。そして、傷口の近くを熱い舌がまるで生き物かのようにぬるりと蠢いて皮膚の表面をなぞっていく感覚に、息をするのも忘れそうになってしまう。
この間、わずか数秒の出来事。
人差し指から口を離した彼女はというと、すっかり上気した様子で顔を赤らめていた。先ほどまでと打って変わってまるでうっとりしたような表情になり、すうう、と時間をかけて大きくを息を吸い込んでは一度吐き出す。
熱を帯びた眼差しは生徒へと釘付けになり、長い睫毛を震えさせながらその瞳を爛々と輝かせた。
「……すごい……こんな味」
恍惚の中で放たれた彼女の言葉を、生徒は拾いきれていないようだった。
「ねえ、お願い、もっとちょうだい?」
吐息の混じった懇願の言葉で堰を切ったかのように、彼女は生徒の肩へ手を伸ばすとそのまま自身の方へと抱き寄せた。前のめりになる生徒の上体の、無防備に晒された首筋へと目掛けて大きく口を開いて。
「……ひっ、あ」
一思いに噛み付いたと同時に、短い悲鳴が生徒の口から漏れ出した。
か弱そうな外見の少女という姿からはおよそ想像のつかない、しっかりとした太さと鋭さを持つ白い二本の牙が、生徒の柔らかな皮膚を容赦なく突き破った。その直後、口内に流れ込んでくる新鮮な血液の味に体が劇的に反応して、手のつけようがないくらいに本能が暴れ回る。脳天に衝撃を食らったような、はたまたゾクゾクと背筋が痺れるような感覚がとめどなく彼女を襲ってきた。
呼吸が不規則になりかけ、心臓の動悸が興奮で速まっていく中で、全身がもっともっとと生徒の血を求めている。
(こんなに━こんなにもおいしい血が、あったなんて)
理性が吹っ飛ぶ、とはこういうことを言うのか。
精神的にも身体的にも初めて体感する感覚にただ身を任せながら、彼女はもう片方の手で生徒の首筋が逃げないように押さえつけて顎に力を入れる。
「う、あぁ……あ……」
生徒の弱々しい声音が耳に入ってきたところでようやく、彼女は両手にこめていた力を少し緩めた。その声によって、自身の中で行方不明になっていた理性が見つかったかのようだった。しばらく開きっぱなしだった瞳孔も、収縮して落ち着きを見せる。
最後に、ごくっ、と大きく喉を鳴らして口内に溜まっていた血液を残らず飲み干したところで、彼女は生徒の首筋から口を離した。
生徒の体を抱きとめたまま、何度か肩で荒く息をして呼吸を整えた彼女が耳元で呟く。
「……ごめんなさいね」
それまで恍惚一色だった表情が理性を取り戻してゆるやかに変化していく中、牙によって出来た丸い二つの傷へと彼女は唇を寄せた。傷口から溢れていた血を舌先で舐め取り、口付けてちゅっと音を立てて離れると、それまであった噛み傷はきれいさっぱり無くなっていたのだった。
自分自身の手で首筋へ触れ、そのことに気がついた生徒はぱちぱちと目を瞬かせることしかできない。
「あれ? なんで……?」
「もっと血を吸っていたら、あなたも危うく“私”みたいになるところだった」
「……?」
生徒の不思議そうな様子をよそに、彼女は履いているスカートのポケットから自分のハンカチを取り出すと、生徒の怪我をした指の箇所へと当てる。その時点で、怪我の箇所から出血はほぼ止まっていたのだが。
「どういう、ことですか」
「さすがにあなたを私の仲間にすることなんてできないわ」
(だってこの学校に、こんなにおいしい血の持ち主がいるだなんて思わなかったんだもの)
ひっそりと舌を動かして口内に未だ残る血の味を感じた彼女は、生徒の方を見据えて真剣な面持ちで言ったのだった。
「ねえ……ひとつ、あなたにお願いしたいことがあるの。これはあなたにしかお願いできないことなんだけど」
その日から、彼女と生徒との奇妙な関係は始まった。真っ赤な血によって結ばれることになったその秘密の関係がその後どうなっていくのか、二人は未だ知る由もないのだった。
あかくて、おいしい。