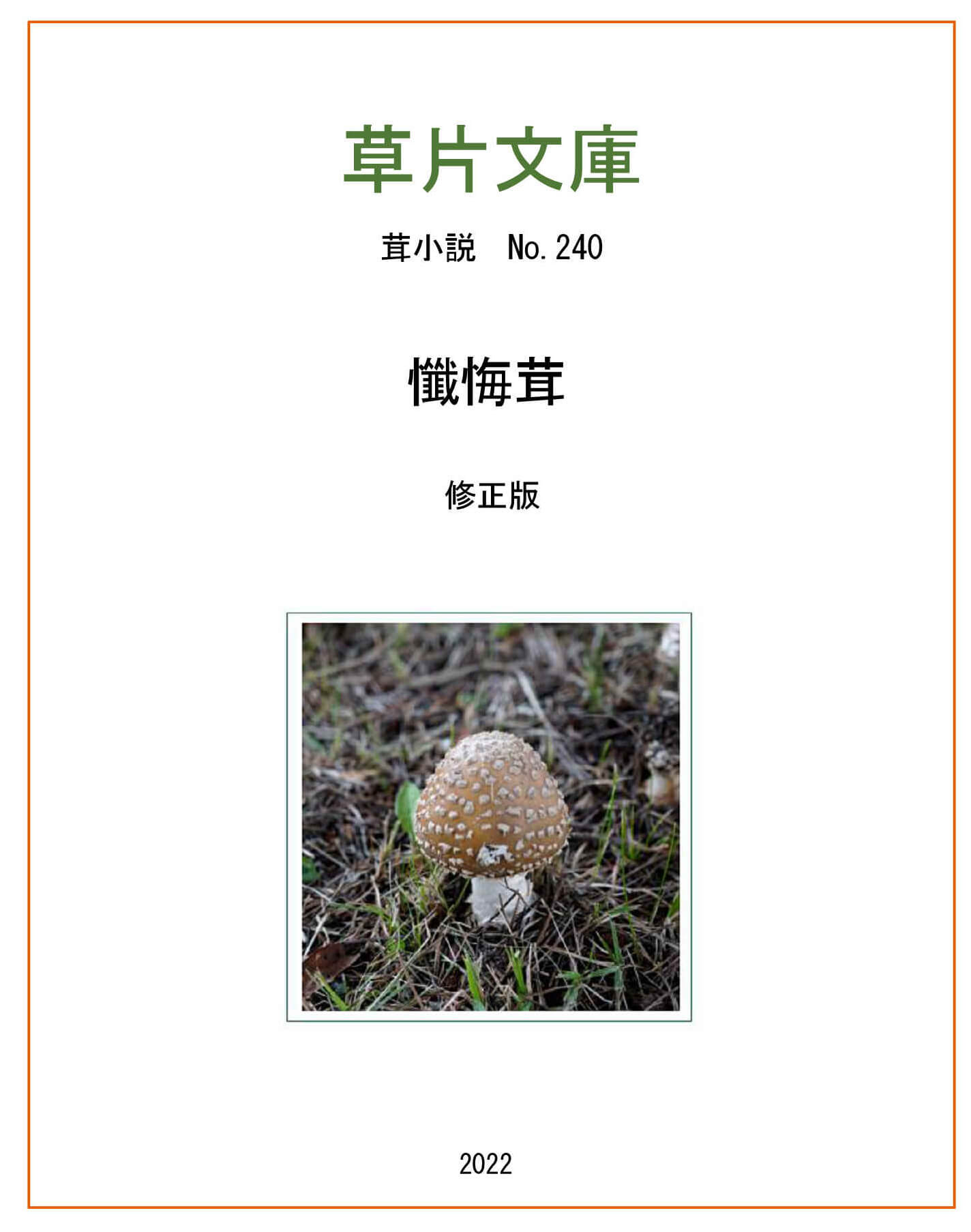
懺悔茸
茸のお寺の物語。縦書きでお読みください。
その寺院のあるところは京都の福知山である。松茸を始め、茸がたくさんはえ、そこにすむ人たちは、秋の茸を楽しみにしていた。
寺の名は正式の名を草片神寺院(くさびらしんじいん)という、神仏混交の不思議なものだった。その名前もそもそも珍しく、そのまま呼ばれていてもおかしくないのだが、人々は百八寺と呼ぶ。寺の最初の住職、土鏡(どきょう)和尚は煩悩をしずめる名人といったらわかりやすいのだろう、多くの人の救いの手となった。自分の欲深さに気づいた村人たちが懺悔に訪れ、土鏡が話を聞いて諭したあとは、まるで違うような人に生まれ変わったという。煩悩を鎮める寺ということで、煩悩の数、百八から百八寺と呼ばれるようになった。そしてある時、土鏡に事件がおこる。そのあと、土鏡が若兆と名を変えるほど、奇妙な、大それた出来事だったのである。
土鏡和尚の事件とはどのようなものであったのか、その寺に残る古文を開いてみたい。
草片神寺院ができたのは、そのあたりの山の持ち主たち七人の中の一人が、茸の豊作を祈願感謝するために神社を建てたいといいだしたためだ。七人のうちの五人は、寺がほしいと思っていたところから、寺にしたいと言った。そこで話し合った結果、神仏混交の時代のことであり、草片神の寺という奇妙な妥協の名前の寺院がつくられたのである。まあ、日本人らしい、宗教同士の争いがあまり起きないいい面がでた結果ということだろう。
住職には、京都のとある寺の次男坊に白羽の矢が立てられた。大きな寺ですでに長男があとを継ぎ、その次男坊は寺の畑で野菜作りにはげみ、周りの農家の家族と仲良がよく、長男より人気が高いという噂が流れていた。その話を山の地主の数人が聞き及んでいたためである。話がその次男坊にいくと、茸の豊作を祈る寺院ならば自分にぴったりだと、喜んで引き受けた。茸は土の鏡なり、とその次男坊は、自ら土鏡と名乗ることにした。
茸の豊作の占いや、豊作に対する感謝のもようしも、その寺院で行われていた。村祭りが春と秋の二回、境内で盛大に行われたということである。
そのような寺の来歴を記した物や日記の他に、懺悔録が残されていた。土鏡和尚は、自分の言ったことが本当によかったのかどうか、いつも振り返えるため、相談にきた村人が、アドバイスによりこうなった、ということを日記に記している。相談者の名前は書かれていない。女男歳職業程度のことはあるが、むしろ、その人間に対し土鏡が感じたことが詳しく書かれている。より正しく人を知ることができるように、と自戒の念を込めて記録されたことがよくわかる。
土鏡和尚が毎日そのような日記を残し、5年ほどたってから、突如として、懺悔録が書かれるようになった。それが土鏡和尚のできごとであり、草片神寺院と呼ばれなくなったことの理でもある。
その懺悔録は草片懺悔緑とあった。
草片懺悔緑
京都福知山、その一つの山の麓近くに建てられた、草片神寺院のできごとである。
わし、土鏡が住職になり五年が過ぎた。寺男夫婦も寺に近い川沿いに家を持ち、畑をしながら、毎日寺の修理、掃除から、境内の草取り、わしの食事の用意とよくやってくれている。村人たちも信心厚く、年に二度ある茸祭りは、村人総出で準備をすることから、わしの生活はなに不自由なく、皆には感謝しきれぬほどの思いがある。
村人たちは、心を開いてくれて、何事につけ、わしの意見をもとめてくる。相談のある者は、日がおちてから寺に来る。寺の本道の草片如来の像の前で、二人で顔をつきあわせて話をする。ある者は連れ合いのことであったり、子どものことであったり、自分の病のことだったり様々である。
村人は前もって告げてから相談にくるが、時として、突然くることもある。そういう人は心決まらぬ中で、突如として、その気になったときやってくる。そういう相談の方が、話がうまく行き、解決することが多い。本心がほとばしり出る時ほど、話ができるものである。
その御仁がやってきたのは、秋のはじめ、新月のときであった。真っ暗の中を、突然やってきたのである。
わしが書院で、油の明かりの元で、その日のことを書きつづっているとき、誰かが戸をとんとんとたたいた。突然相談に来る人は、誰もが、和尚さんいますか、とか、今晩わ、とか、入り口や庭から声が聞こえるものだが、そのときはいきなり、廊下から、とんとんと戸がたたかれたである。
狸は寺の周りにもうろうろおる。狸や狢が入ってくることはないとは言えない。だがあいつ等のやり口は、丁寧に戸をたたくようなことはしない。いきなり、戸をすーっと開けて、狸なら、ちょいとふっくらかわいらしい女子にでも化けて入ってくる。狢なら、すらりとした粋な女子に化けて、勝手にはいってくる。
そういうときは、「これ、ここに座れ」とどなりつけると、狸も狢も、ひょいと、自分に戻って、わしの前で行儀をただし、「何か食いたい」という。それで、「食いたければ、懺悔をせよ」というと、狸は「村のなにべえさんの家の畑の芋を食いました」と白状する。そこで、わたしは、「おまえたちは、山の中の茸や虫を食いなさい、だがせっかくきたのだから、これをやろう」と、古くなったお供え物を持ってきてやる。すると、狸にしろ狢にしろ、「おありがとうございます」と、くわえて帰って行く。
あいつ等は、食い物に困っているわけではない、村人たちと同じで、ちょっとした罪悪感をはらいたくなって、わしのところにくるわけだ。人も獣も思いは同じだ。
狸狢がなぜ女に化けるかというのは、男に対してだけのこと、女に対しては、いい男に化ける。それは、化かされる方の問題である。狸や狢は人の煩悩をくすぐって、そう見えるようにさせるのである。あいつらにとってわし等神仏に仕える者は、一番化かしやすい人間である。人のもっとも強い煩悩は、男なら女子、女なら男、である。村人たちは伴侶をもち、煩悩を鎮めることができるが、寺の坊主はそうはいかない。いくら修行を積もうが、煩悩がなくなることはなく、むしろ強くなる。気持ちでは押さえるが、夜になれば自然とわきでてくる。ということは、狸や狢がだましやすい人間は坊主ということになる。狸や狢が姿を変えるのではなく、奴らは、坊主の煩悩を刺激し、そう見えるようにしてしまうわけである。
前置きがながくなったが、その夜、とんとんとたたくので、「はいられよ」と声をかけたのだが、入ってこない。
またとんとんとたたく。狸や狢ではない、もちろん村人ではない、とすれば何者か。
わしは、なにがきたのか少しばかり興味がわいてきて、立ち上がると戸を開けてやった。
すると、真っ赤なものがとびこんできた。それにはちょっとあわてた。というのも、火、炎と思ったからである。火事になると危ない。
それは取り越し苦労で、赤い物はわしの座布団の前で揺れておった。
なんと、茸であったのだよ、ハエトリタケじゃった。紅天狗茸ともいうらしい。
なにが茸に化けておるのじゃろうと、わしも座布団に戻ってあぐらをかくと、茸を見たのだが、正体を現さない。獣が女に化けるのはわしの煩悩がそうさせるのだが、茸に対する煩悩などあるわけはない。あるのだろうかと、一瞬は自分を疑ったが、今はない。
まさか、茸が歩いてやってくるわけはない。揺れる茸の真っ赤な傘の白いぽちぽちを見ていると、うごきだすだし、目の前に赤い浴衣を着た見目麗しき女性が、よこずわりになっておった。
なんと、これはわしの煩悩だ。ということは、茸が女に化けたわけで、何かが茸にばけたのではない。
茸が歩いて、寺にやってきたということか。
「おしょうさま、その通りでござんす」
茸がそう言いおった。
「おいおい、浴衣がだいぶはだけできたぞ、おい、よせよせ」
浴衣が、胸の膨らみの中程まで見えるほどゆるゆるとおちてきた。
わしが後ろを向いて、また前を向いて女性をみたら、紅天狗茸が立っていた。
ちょっと安心して紅天狗茸をみやった。
「ちょいと過ぎまして、申し訳ありません、もう少しで、和尚様の茸が破裂しそうになり、あわてて元にもどりました」
よかったよかった。よくわかっている茸だ。
「それで、紅天狗茸殿、なぜ寺にやってきたのかな」
「わたしども紅天狗茸一族は、何人もの命をちょうだいしてしましました、なんとか毒を弱くする方法はないものかと、和尚様のところに参りました」
「そうじゃな、わしの寺でも、天狗茸を食って死んだ人の葬式をしましたな、皆流れ者でな、草片のことをよく知らぬ御仁で、無縁仏として葬りましたな、いつも茸を食っている村人には死人はおりませんぞ、ただ、馬鹿な若者がちょっとぐらいと思って紅天狗茸を食って、目を回したのがおりましたがな、いずれにせよ、お宅さんらが悪いのではないわい、心配するでないよ」
「だけど、できれば、人間サマを傷つけたくない思いでございます、茸は森や林の手入れは人さまが行ってくださるもの、それによって我々茸は繁栄いたします」
「たしかにそうじゃがな、逆に山の木を皆切ってしまうのも人じゃ、そうすると茸は生えにくくなる」
「はい、ともかく、なんとか、毒をのぞいていただけませんでしょうか」
「うーむ、そなたの懺悔を聞いて、よい答えに気づけば、教えてもやれますがなあ、イがすぐ、紅天狗茸から毒をなくせと言われても難しいの」
「我々、人さまに採られないように、目立たぬようにしたいのでございますが、紅天狗茸であるわたしどもは真っ赤であることから、目立ってしまいます」
「きれいでよいのう、なにかしてさしあげられればいいが、せいぜい、毒が抜けるように、護摩を焚き祈念するのみなのでな」
「なにでも結構です、私どもできることがあればお手伝いいたしまする」
「そうだの、皆で祈ったほうがききめはあるかもしれん、その前に準備をしなければ」
「護摩木は私どもで用意いたします」
「とってこれるのか」
「はい、天狗茸たちに、ヌルデの木を用意させまする」
「それはたすかるの」
「それからの、わが寺には、草片如来様がおられるが、不動明王とはちと違う、草片如来様がおまえさま方を変えてよいというかわからぬ、茸には茸のありようがあるので、毒も必要というかもしれぬな」
「はい、草片如来様のおっしゃるとおりにいたします」
「それをみなにつたえておいてくだされや」
「はい、では、護摩をたかれますとき、私ども紅天狗茸一族で参ります」
紅天狗茸は、白いぽちぽちのある赤い傘を、頭のように垂れて、寺を出ていった。
そのような次第で、わしは次の新月の夜、本堂の草片如来の前に護摩だきの用意をして、天狗茸族の毒が弱くなるように祈る準備をした。
星空の元、若い衆が寺の石段をあがってくる陰が見えた。本堂を開け放ってあったので、たくさんの男たちが茶色の着物を着て、無言で次から次へと本堂に入ってきた。
頭とおぼしき男が、護摩木を皆から受け取ると、「ここにおきまする」と、火炉の中に積み、残りをわしの脇に置いた。
男たちがわしの後ろに座ると、茶色の傘を持った天狗茸になった。
女たちが本堂にあがってきた。先頭の女が松明をもっている。懺悔にきた紅天狗茸のようだ。
「和尚様、火をつけてよろしいでしょうか」
「おお、たのむぞ」
護摩の火が草片如来の前に燃えさかった。女たちは護摩の火の両脇に座り、紅天狗茸に変わった。
「では始めるとする、みなもよくお願いするように」
「草片如来さま、ここにきております、天狗茸一族の願い、毒を消し去っていただけますよう、ここに、護摩の祈願をお願いする次第でございます」
「うむ、全ての毒がなくなるかどうか分からぬが、やってみよう」
わしは、どのように念じてよいかわからなかったが、ともかく、数珠をもち、毒よ去れ、毒よ消えよ、毒よ弱まれと、草片如来に願った。
夜も更けてきたが、わしとしても力のある限りと思い、汗をたらしながら祈った。すると、草片如来の顔が赤くなってきた。紅天狗茸は赤い浴衣姿の女になり、天狗茸は茶色の浴衣をきた男になった。
女も男も護摩の火にあぶられ、暑くなったと見えて、浴衣をはだけ汗をたらした。
わしは賢明に祈願をしていたのだが、横座り女たちの浴衣からのぞく足や、襟元にこぼれる膨らみに目がいってしまい、天狗茸たちの毒を消すことと、自分の煩悩を押さえるのに、やたらと汗を流した。
すると、草片如来が護摩の前に進み出て、ヒトの形になった茸たちに向かって話し始めた、
「汝等は毒があることの意味を存ぜぬであろう、草片の毒は、草片に色気をそえる重要な働きを持つものである。毒があることに誇りをもたっしゃい、毒茸は色っぽいのだ、それでなければ、ただヒトに食われるだけの茸になってしまうではないか、毒を持たねば、茸族の長になれぬ、それを捨てるとは、なんと愚かしい、天狗茸はヒトが食ってもおいそれとは死なぬ、触っただけでも死んでしまうほどの毒を持つように、日々努力をするように」
祈念とは逆のことをおっしゃった。
それを聞いた天狗炊けたちは、茸の姿に戻って、
「ははー」と傘を垂れた。
草片如来はわしを見た。
「これ、土鏡、草片どもの願いを叶えようと努力したことは見上げたものである、草片と気持ちを交えることができるようになったのは、草片寺院の住職として申し分がない、ほめて使わす、ただ、おまえさんの、煩悩はなかなか消せぬな」
草片如来が笑った。
「ははー、申し訳ございませぬ、修行がたりませぬ」
「ふーむ、修行をしてもだめかもしれぬの、どうじゃ、男の煩悩を消してやるかの」
「是非お願い親しまする」
わしは、足の間が突っ張ってきて、なんとかせねばとあせっておったので、如来に頼んでしまった。するとな、すーっと、その気が失せたのだ。天狗茸たちはまた人になっておった。しかし、女子たちをみても、わしはその気にならなかったのだ。
さすが如来様はありがたい、と思っているとな、自分の男の物がなくなっており、胸が大きく張り出して、はっと思ったときには尼になっておった。
なるほど、と思ったな、それで、後ろを向いて男衆の方をみたのだ。
男衆があぐらをかいて、またのふんどしの間から茸が見えておった。茸の茸じゃ。尼になったわしは、それをみて膨らんだ胸がかっかと熱くなってきた。
そうしたら、草片如来が言った。
「うかつだった、女になっても、その煩悩はきえるわけではなかったな、どうだ、土鏡、狸にでもなるか」
それを聞いたわしは、そのときは冷静だったな。
「それは、もう結構でございます」
とお断り申し上げた。
草片如来さまは、「そうか、それではもうよいな」
そういって、元のところにお立ちになった。
その間、護摩木をくべるもを忘れておってな、もう火が消えるところだった。
「和尚さま、どうもありがとうございました」
茸たちは茸の形になって本堂から出ると、星空のもと山に帰っていった。
如来に元に戻すよう願うべきだったと思ったときにはおそかったのだ。
それ以来、わしは尼になり、土鏡を改め、若兆と名乗り、草片寺院の住職として、勤めたのだ。
わたしは色気がほとばしりでている茸のことをよく知る尼として生涯を過ごした。
そろそろ寿命がつきる年になって、住職を若い僧に託し、自分の懺悔録を書きつづることにしたのである。
そういう懺悔録である。本当のことと信じられることは百パーセントない。これを書いた初代の住職は草紙物を書きかったのではないかと想像できる。というのも土鏡が名をかえ若兆が尼であったという記載は村に残されている古文書のどこにも書かれていない。それどころか、最初のところに狸と狢がやってきた話があるのは、これは物語だよといいたかったのではないだろうか。ただ、土鏡は生涯独り身であったことは事実である。
懺悔茸


