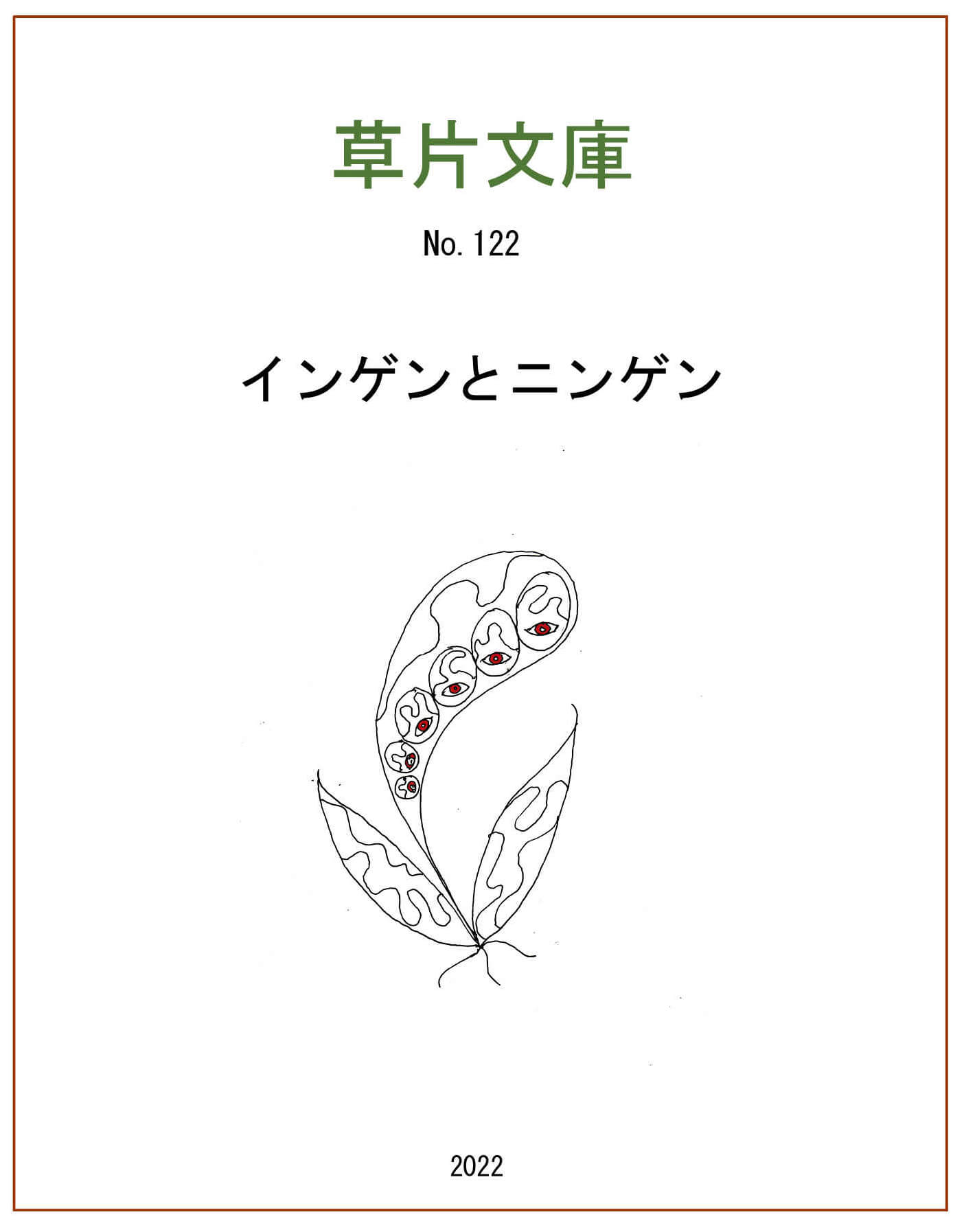
インゲンとニンゲン
奇妙な物語です。縦書きでお読みください。
ここに一人の男がいる。もう四十になる。保健所につとめていて、大学の時の専門は栄養学である。人が一生の間に、どのくらいの水分、糖分、タンパク質、脂質を摂取するか、長寿と短命の人ではどう違うのかを、厚生省の白書の統計値をよりどころとして計算した。
単純に水分、糖分などといっても、摂取の仕方、摂取した人の体質、生活環境、もろもろの条件で影響は違ってくるし、単純な総量でものを見ても、必ずしも正しくはない。本人もそれは重々承知している。
なぜ摂取の総量という単純な計算で比較したのかというと、大学の酒の席で、誰かが、俺は分解酵素がないから、一生涯アルコールは飲まないな。といったのにたいして、俺は一日、ウイスキーをダブルで十杯だ、一生にすると、どのくらいになる、といったことが頭に残っていたからだ。
自分は酒をどのくらい飲むだろう、高校の頃にも少しは飲んだ。今は一日にビールを一缶くらいだろうか。もし二十歳から男の平均寿命の八十一までだと、61×365日だから22265本になる。ビールの量とすると350ミリリットルをかけると、7792750ミリリットルになる。アルコール分5%とすると、38963.375ミリリットルのアルコールがからだにはいったことになる。おおざっぱにいって60年間で40リットルのアルコールだ。これくらいなら自分の体に悪いほどの量ではないと言うことだ。
NHKの番組に何でも金に換算して、可視化するという番組がある。一缶200円のビールなら、年に73000円、61年なら4453000円だ。こちらのほうが、それにしてもすごい値だと驚く。
大学三年の時だ。それで、一生の間になにがどのくらい必要なのか、適量なのかに興味を持ち、卒業研究のテーマにしたのである。単純な卒業研究だったと思うが、単純な数値であったことゆえ、自分の頭に残り、考える基準となった。そんなこともあり、育った市の市役所に、保健所希望で合格し、つとめるようになったのである。保健所に配置されているのではなく、市役所の中の保健所を監督する部署の事務職だ。
実家から通うことができるのでとても楽だし、ともかく、市役所の職員になったことを両親がとても喜んだ。お役人は恩給がいいと思っているのは、小さな民間会社で苦労した父親である。母親も市役所の職員というのはなんだか偉くなったような気がしていたようだ。大学の同級生は公官庁をねらって、公務員試験を受けていたことを知っている自分としては、両親ほどありがたみを感じてはいないが、就職難の昨今、いい職場であり、自分の住むところをよくしようと思えば、少しは張り合いのあるしごとである。
勉めて五年、両親は決して余裕のある年金生活ではない。家を買うのにも苦労したが、なんとか自分のものにしたし、年に一、二度の旅行に行けるほどの余裕はあった。
それでも庭の隅に畑を作り、トマト、ナス、キュウリなどを植えて、ぬか味噌漬けなどを作って喜んでいる。それをみていると、小市民が人間にとって一番いい生活なのかなどと思ってしまう。
春の連休が終わったとき、両親はスーパーの入り口に売れ残りがあったと、インゲン豆の苗を買ってきて植えた。サヤインゲンは初めて育てる。NHKのテキストを見て、ほっとけばいいのよ、と母親は水をやった。父親は、まてよ、このサヤインゲンはつる性だ、支柱をたてなければならんな、と母親よりは少し緻密である。でも、ほら、つる性の方がたくさんなるって書いてあるわ、しかも一月半も収穫ができるわ、母親にはそこが大事なようだ。もう採れる気になっている。
ところが、夏休み前のころになると、次から次へと紫の花が咲き、実がなり始めた。確かによく実が付く。母親は早く取って食べた方が柔らかくておいしいのよ、と朝取ってくる。確かに美味しい。ゆでてマヨネーズで食べるのもよし、いろいろな料理ができる。
ときどき弁当に入っている。いや、毎日はいっていた。ゴマとあえてあったり、ベーコンと炒めてあったり、母親は庭でとれた物を得意になって料理をする。
「あら、本当に毎日インゲンね」
同僚の女性がテーブルで昼食を食べている僕の弁当箱をのぞき込んだ。
「うん、庭でとれるから」
「サヤインゲンはカリウムが多いからからだにいわね、ミネラルもあるし、利尿作用もあるから、ベーターカロチンだって多いから、免疫によくて抗ガン作用もあるし、ビタミンAにかわって目にもいい」
その女性は栄養士さんである。新居友加里である。
「それは知らなかったな」
「でも、お母さん、毎日お弁当えらいわね」
「母親も庭の野菜畑の手入れと、とれた物の料理しかやることがないから」
「そうか、世界で一番平和な家庭ね」
「まあ、そう思うよ、生活の雑用が楽しみというのは一番幸せだな」
「そうね、奥さんもらうと波風が立って、平和が乱れそうね、がんばってね、いんげんにんげんさん」
女性はそういうと、昼休みの散歩に出かけた。
よく考えたら、よけいなお世話だ、とおこらなければいけないのだが、そうならないのが自分のようだ。これが平和思考だ。なにいわれてもストレスにならない。
しかし、最後の「いんげんにんげん」てなんだろう。そういえば、いんげんと、にんげんは、頭が、い、と、にの違いだけだ。しかし植物と動物という大きな違いがある。
いんげんってどうしてそういうのだろう。人間もそうだ、人と書いたり、人の間と書いたり、人は個人で、社会の中だと人の間で人間か、それじゃ、人はなぜそう名付けられたんだ。
人という感じは象形文字で、ヒトの形から作られたことは何かで読んだ気がする。漢字はそれでいいが、なぜ「ひと」「じん」というんだろう。気になって、ネットで調べたが、ぜんぜんでてこない。人間はやはりヒトとヒトとの間、コミュニティーが意味として加わっている表現のようだ。あまり意識して使っていない。カタカナのヒトは生物学上の分類である。
それじゃ、インゲンはと調べてみると、江戸時代にこの豆を、中国の「隠元禅師」さんがもってきたからだと書いてある。あまりおもしろくない。
だけど、なぜか、いんげんとにんげんが似て感じられるのは不思議なものである。緑色のヒョロンとしたインゲンをじっくり見ていると、歩き出しそうな気がしてきた。言葉が似ていると、その二つの物が互いに親密な関係になりうるような気がしてくる。
弁当の中の炒められたインゲンが、ニンゲンだったらどうしよう。ご飯が覆っている部分の上の隙間に小さなニンゲンがはいってい手、こっちを向いて食べて頂戴と言ったらどうする。
今日の弁当をあけた。インゲンの味噌和えである。と思ったら、ニンゲンが横たわっている。いや、やっぱりインゲンだ。なんだこれは、早く食った方がいいだろう。
インゲンの味噌和えを口入れ、白いご飯を押し込んだ。よく食べる味だ。歯の間にムキュっとサヤインゲンの感じが伝わってきた。匂いは味噌の匂いとインゲンの匂いが半々だ。
なにを考えているのだろう。唐揚げで残りのご飯を食べお茶を飲んだ。
彼女が、食堂に入ってきた。
「インゲン食べた」
何でそんなことを聞くのだろう。
「どうして」とちょっとうるさくなって返事をすると、
「はは、インゲンおいしそうだから」
彼女はそう言いながら隣に座った。
「わたしもお弁当作ってきた」
「やっぱりお母さんが作るの」
「作ってくれる人いないものね、一人暮らしよ」
新居友加里、小学校の給食管理をしている、市に三つある小学校のメニューを点検する事が主な仕事だ。もちろん衛生面のチェックもする。
「あれ、ご実家じゃなかったのですか」
「もう、両親もいないのよ」
弁当をのぞくと、サヤインゲンと豚肉の炒めた物が入っている。
「昨日の晩ご飯、豚の生姜焼きだったんだ、サヤインゲンを入れてみた」
今まで弁当など持ってきたことがない。いつもは何か買ってくるか、外に食べにいっていた。
「どうしたの」
「碓井君のお弁当のサヤインゲン見ていたら、作ろうかって気になったのよ」
「サヤインゲン好きなんですか」
「うーん、どうかな」
返事にとまどっている。
「サヤインゲンはまさか栽培したのじゃないですよね」
「まさか、マーケットで買ったのよ」
「新居さんが弁当を作るとは意外でした」
「そうね、わたしもそう思う、碓井君のインゲンが作れって言ったような気がするわ」
新居さんが箸でインゲンと豚肉を挟んで口に持って行く。インゲンがなんだかニンゲンに見えた。僕の形をしている。
どうもおかしい。今日はインゲンがニンゲンに見える。
「これから毎日弁当持ってくるんですか」
「どうかな、残り物があったときだけかもしれないし」
意外と小さな口だ。サヤインゲンが吸い込まれる。いや、ヒトだ、ヒトが泳ぐようにして、新居さんの口の中に吸い込まれた。
あ、かまれちゃった。
「なにかおかしい」
僕が口元をずーっとみていたからだろう。
「いや、おかしくないですよ、おいしいですか」
「まあ、まあね」
僕は食べてしまった自分の弁当箱を袋の中にいれた。
「お茶をとってきますが、いりますか」
「あ、そうか、お茶があるんだ」
「もってきますよ」
食堂で、お茶はいつでも飲める。
「ありがとう」
彼女は最後に残っていたインゲンを口に入れると、飲み込んで、お茶を一杯飲んだ。
「わたしね、来年の四月で市役所やめるんだ」
突然の話にちょっとびっくりした。
「どうしてです、仕事場が実家の近くで、とてもいいっていってたじゃないですか、僕と同じ状況ですよ、僕はやめる気なんてないですよ」
彼女は、「碓井君、おもしろいわね、インゲン的ね、なんとなく」
どのような意味なんだろう。
「来年結婚するのだけど、彼は会社のフランスの支店に行くの、今は東京だけど」
彼女につきあっている人がいるとは思っていなかった。たまに東京に行くのはそのためだったのか。遠距離恋愛か。
「それはおめでとうございます。パリの生活はたのしいでしょうね」
「パリじゃないの、ルアンなの、まあパリに近いけどね、フランスの空気を吸うのは楽しいと思うけど、フランス語まったくわかんないんだ、これから、簡単な会話教室にかようつもり、だけど、この町にはないから、土曜日に電車に三十分のらなきゃならない」
彼女は県庁所在地である大きな市の名前をいった。
「フランスではインゲンあるのでしょうね」
「あるでしょ、まだ調べてないけど、さ、ごちそうさま、ちょっと町に行くからお先に」
彼女は弁当箱をバックに入れると、食堂をでていった。
事務所に戻ると、市の一つの保健所に勤務している福原医師が来ていた。課長となにやら話している。
僕が戻ったのを見て、「碓井君、昼休みに悪いんだけどちょっときれくれないかな」
と声をかけてきた。
「はい、こんにちは」
福原医師とは顔見知りである。たまに保健所に行くが、何度か話をしたことがある。実直なお医者さんである。
「福原先生が保健所の敷地の中に畑を作りたいとおっしゃるんだけど、どうだろう、保健所長には話したとおっしゃっている」
質問の意味がわからなかった。この課長は、人に説明するのが上手ではなく、時々、なにをいいたいのかわからないことがある。
「いや、保健所の敷地はずいぶん広いでしょう、なんだかもったいないですよね、それで、この市のお年寄りは、身体は丈夫だけど、する事がなくて、年寄り年寄りっぽい人が多いと思うんですよ、市もお年寄りのために、演芸会を開いたり、折り紙教室や、陶芸教室などやっているけど、そういうのは、一部の興味を持っている人しか参加しないでしょう、もう少し筋肉を自発的に動かして、楽しめる物はないか、しかも集団で話ながらできることないかと、それで、畑を作って、みんなで野菜を育てるのはいいんじゃないかと思いましてね」
課長が口をはさんだ。
「今、先生がいったように、農家の人が多いので、自分のところに畑もあるだろうし、改めて保健所に畑を作って、そこで野菜を作る気になるかどうかわからないと、わたしは思うんだけど、碓井君はどう思いますか」
課長は、自分の意見に同意させて、めんどくさい手続きをしないですむようにしたいのだろう。いつもそうである。
「うちの両親も庭に畑を作っています。今インゲンがとれて、喜んでいます」
「そうでしょう、畑をやりたい人は、みんな自分の家に畑を作りますな」
課長は僕が同意したものだと思ったらしい。
「だけど、両親二人だけで、いつも会話は同じ、平和だけど、新味はなさそうだなとは思っていました」
「そうそう、外にでて、他の人と一緒に何かやるのはとてもいいことなんです、認知症の予防にいいですよ、それと、保健所でやっていると、わたしが様子を見ることができる、そんな利点もありましてね」
「課長、どうでしょう、市の老人クラブに、そういうサークルをつくって、保健所の敷地に畑をつくってもらうっていうのは、スティールの物置と畑の道具は市で用意して、農業になれている人が多いから、やってやろうという人がたくさん出てくるかもしれない、そういう人がやったことのない人を指導すると、両方ともいいですよ」
と僕はちょっと早口でしゃべった。課長はやな顔をするだろうなと思いながらである。
「いい考えですね」
福原医師が嬉しそうな顔をした。この人はいつも住人の為を思っている。課長は顔色一つ変えていないが、目は迷惑そうにして、それでも、
「文化課の課長に話をしてみます」
と、福原医師に返事をした。
「いや、どうもありがとうございます」
福原医師は、僕にもお辞儀をすると、事務所をでていった。
「いやはや、しょうがないな、碓井君、仕事と違うことで悪いが、この件、文化課と話をしてみてくれるかな」
「はい、わかりました、もし話が進んだら、他の二つの保健所にも同じように畑を作った法がいいですね」
「それもまかせるよ、ほかのところの保健所長の確認も必要だな、市の会議に出す必要もあるし」
「わかりました、やってみます」
そういうことで、僕は文化課と土地を管理するところなどと相談を重ね、市の会議でも、市の健康づくりの町というキャチフレーズにもあっているということで、認可された。
早速、文化課のシルバー会担当者に、人集めをしてもらって、新しいサークルをつくった。会長は農協の理事をしていた人がなり、それぞれの保健所に、畑の準備ができた。農家のお年寄りが喜んで、自分のトラクターを運び込んで、あっという間に畑にしてしまった。
福原先生の保健所に行ってみると、もう何人かの老人が苗を植えていた。
「なんの苗ですか」
「夏まきのインゲンの苗だはさ、つる性だからようなるよ」
植えていた老人が笑顔で答えた。畑をやっているのは軽い認知症の人だという。
「お、碓井さん、おかげでいい畑ができました、インゲン会もうまくいきはじめましたよ」
福原医師が外にでてきた。インゲン会ってなんだ。怪訝な顔をしていたら、「あれ、碓井さん知らなかったの、シルバー会のサークル設立の時、名前をどうするかという話になり、お宅の課長が言ったそうだよ」
どうしてインゲンになったのだろう。まあいいか。
「農家の人は出荷しなくていい物を作るというのは、こんなに楽しいのかっていってね、それで、農家じゃない人は、自分で作った野菜が食べられるのは楽しみだっていってますよ、それよりも何よりも、みんなで役割を決めて、責任を持つことになって、認知症なんてふっとんじゃいますよ、だいたい、認知症っていうのは現代病ですよ、医療で体が健康を保つようになって長寿になったけど、脳のケアが忘れられていましてね、脳は身体と一緒に使わないと」
まあ、ともかくうまくいってよかった。
そのことを、市役所にもどって、課長に報告した。ついでに、インゲン会と名前を付けた理由を聞いた。
「ありゃあ、新居さんがそういったんだ、なんでだか知らないけど」
課長は僕の弁当に必ずインゲンが入っていることを知らない。新居さんにお礼を言うべきか迷ったが、保健所の畑のことを話すときにちらっと言ったら、
「あら、そうよ、碓井さんが骨折って、作ったシルバー会だもの、いんげんよ」
とあっさりいわれてしまった。
うちに帰ると、畑が広がっており、新たにインゲンが植えられていた。
おやじが
「夏まきの苗を買ってきたんだ、春まきのやつはずいぶん収穫できたからな、まだとれてるけんどよ」と言った。
インゲンがぶら下がっているのを見たら、あっと思って目をそらした。なんだかニンゲンが何人もぶら下がっているように見えたからだ。
その夕食に出てきたインゲンの料理がみんな、ニンゲンに見えた。
夏休みをとらずに今までがんばったから疲れがでたのだろう。課長に休暇をもらおう。
課長にいうと、八月の終わりの一週間夏休みをもらうことができた。だいたい、有給だってだいぶたまっている。この夏はそれも一緒に長い休みをとるつもりだったのだが、シルバー会のサークル、インゲンの立ち上げに奔走したためこうなった。まあしょうがないか。
それで、一人でトレッキングの旅をすることにした。ちょうど台風の発生する様子もないし、もってこいだろう。
信州のちょっとした山をあるくことにした。準備のために、県庁所在地の大きな町に買い物に出かけた。山用の靴とリュックを買った。大学時代に使った物を持っていたが、リュックにはかびが生えていたし、靴は金具がとれていた。そこで新調したわけである。
たまには両親に何か買って帰ろうと、十階の物産展にいったら、北海道の駅弁大会をやっていて、カニの駅弁を三つ買った。次いで果物でもと思って、地下のマーケットに行ったら、野菜売場でインゲンが目にはいった。そのインゲンたちがニンゲンに見える。重傷だと自覚して、桃を買って外にでた。駅に向かおうとしたとき、いきなり、頭ががつーんときて、なにもわからなくなった。
気がついたら、病院に寝かされていた。
「先生、患者さん気がつきました」
「ああ、よかった」
白衣を着た先生らしき人が、自分の顔の前で指を振った。
「見えますか」
僕は、ハイと言ったつもりだが、声がでていないようだ。
もう一度先生は同じことをした。
「指がきちんと見えますか」
僕はうなずいた。
「目と耳は大丈夫ですね、名前が言えますか」
僕はやっと声を絞り出して、「碓井茂夫」と答えると、先生に笑顔がでた。
「どうやら外傷だけのようだ、二、三日入院して、傷が悪くならないようなら、家で療養すればすぐよくなるでしょう」
いったいなにが起きたのだろう。
看護婦さんが点滴を換えにきたときに聞いた。
「僕はどうしたのですか」
「あ、覚えていないのね、デパートの入り口からでたところで、上から落ちてきた人にぶつかったんですよ、碓井さんの頭に当たったの、でも脳に異常がなさそうでよかったですね」
「インゲンにぶつかったんですか」
看護婦さんはおやっという顔をしたが、すぐ、
「そうですよ、大変でしたね、だけどMRI検査では脳の中に問題はないようですよ」
「ここはどこですか」
頭がこすれたように痛い。
看護婦さんは県立病院の名前をいった。両親はこっちに向かっているということだった。
それからまもなく両親が顔を出した。
「茂夫災難だったな、でもひどいけがじゃないと先生がいっていた。今日中にうちの町の市立病院に移してくれるそうだから、我々も一緒についていくよ」
僕はうなずいた。うちの市立病院は我が家から歩いても二十分ほどのところで、市役所の近くである。それなら安心である。
親と一緒に、病院の車で自分の市の病院にはいった。
病室で、母親が「頭のけがだけだから、食べ物はなに食べてもいいと先生がいっていたよ、食べたい物があったらもってくるよ」
と、身の回りを整えて、おやじと一緒に家にもどった。
「買ったカニの弁当はどうしたのだろう」
担当の医者が病室にきた。
「災難でしたね碓井さん、まあ、頭の傷が治ればすぐ退院できますよ、ただ、後で脳に損傷があらわれることもあるので、とりあえずは一月に一度、脳と脊髄のMRIをとりましょう」
「インゲンが落ちてきてぶつかったと聞きましたが、落ちてきた人はどうなったんでしょう」
医者がおやっといった顔をしたが、
「女の人ですけど、自殺です、だけど、一命をとりとめました。碓井さんがクッションになって、路面におちたものですから、全身を強く打ちましたが、運良く頭を軽くしか打たなかったんです」
「僕でも役に立つこともあるんですね」
といったもので、医者が声を出して笑った。
「生涯感謝されますよ、数日、あまりベッドから動かないようにしてください。傷口から出血するとやっかいだから」
そういって、病室からでていった。
とうとう、山歩きはおじゃんになった。しかたがないか、とあきらめた。
両親が着替えのものやお菓子などをもってきた。
「僕が買ったカニの弁当どうした」
「荷物はお前の部屋に置いたけど、カニがはいっているのかい」
「うん、僕は病院の食事が出るから、三人前あるから、二人で食べてよ」
「親、ご馳走ね、今日は料理しなくていいのね、退院したら、美味しいもの作るからね」
両親はしばらくいると、インゲンに水やらなくちゃ、と帰っていった。彼は何を言っているのだろうという顔をした。
三日ほどたつと、頭の傷は痛みが薄れてきて、傷口がふさがり始めた。
「点滴は後一日でいいでしょう、MRIの結果も問題なさそうだし」
その日、新居さんと課長が見舞いにきた。
「災難だったな、ゆっくり休んでいろや、まだ夏休み中だし」
課長が珍しく親切なことを言った。新居さんも「大変だったわね、ニンゲンとぶつかるとはね」
と、二人して買ってきたくれた見舞いの果物を枕元においた。僕がぶつかったのはインゲンなのに、ニンゲンにぶつかったとはおかしな冗談だと、彼はそれがおかしかった。
「シルバー会のインゲンはうまくいっているわよ」
「みんな仲良くてよかったです、福原先生もよろこんでいるでしょうね」
「ああ、この企画はとてもよいと、市長が市の宣伝に使うみたいだ」
「へー、課長良かったですね」とおべんちゃらを言ってみた。
「みんながインゲン畑を世話している映像をとって、福原先生と、碓井さんにもでてもらおうということだけど、撮影は夏休み終わってからだから、治ってでてこれるでしょう」
インゲン畑って何てこと言うんだろう。彼ははじめきょとんとしていたが、
「ありがとうございます、今のとこと、頭の傷は順調になおっていて、おそらく近々退院できると思います。仕事にでるのは九月からになると思いますけど」と答えた。
「それなら間に合うわ、わたしもインゲンの栄養価について解説することにしているの、この町の最後の思い出になるわ、フランスにいったら、映像を見て思い出すことになるでしょうね」
インゲンへの栄養価だろう。
「フランス語でニンゲンはなんていうの」
「ユマン Humain よ」
「サヤインゲンは」
「アリコベール Haricots Verts]
「フランス語はまるっきりわからないや」
「それじゃ、碓井君、はやくよくなってでてきてくれよな」
課長と新居さんは病室をでていった。
それから数日後、僕は家に帰っていいことになった。ツクツクボウシが鳴く季節になってしまった。
「庭の畑のニンゲンも、もう終わりだね」
久しぶりに帰った家は何となく新鮮である。庭にでてみると、もう黄色っぽくなり始めた茎に、それでもニンゲンが何本かゆれている。
「おまえなに言ってるの」
「畑のニンゲン」
「おまえなんだかおかしいね」
母親はそういったが、そのときはそれで終わってしまった。
久しぶりに帰った夕ご飯は、生姜焼きだった。家のご飯はやっぱりおいしい。「おまえはまだだめだよな」と父親はビールを飲んでいる。僕は酒をそんなに飲む方じゃないが、ビールはたまに飲む。
「先生は、9月1日から仕事にでていいといってたよ」
「そりゃいいね、最初の日は疲れるから、無理しないようにしなさいよ」
9月1日になった。久しぶりに市役所にでた。
「やあ、無事でよかったよな」
同僚たちがよってきて、そういってくれた。新居さんと課長から様子は聞いているという。
「ニンゲンインゲンさんもどったわね」
新居さんがにこにこしてそばにきた。
「例の市の紹介ビデオだいぶ撮影が進んでいるの、わたしの分はもうとったわ、インゲンサークルができたときの説明の部分はこれからよ、福原先生と、碓井君がでるのよ」
ニンゲンサークルじゃないの。
「でもうまくはなせないな」
「今から原稿を書いておくといいわよ」
「どんなになるのだろう」
「碓井君が、福原先生のアイデアで、サークルを作った経緯をしゃべったあと、福原先生がどうして保健所に畑を作ることにしたか説明するのよ」
「それじゃ、原稿書いてみます、新居さん、みてくださ」
「いいわよ」
出勤した最初の仕事は、デスクで、話をする原稿づくりということになった。ほんの一分ほどのもののようだ。
こんな文だ。
市のシルバー会のニンゲンサークルは、保健所の福原先生が市の老人たちの頭の健康と体の健康の維持のために考えたもので、市にある三つの保健所の敷地内に、畑をつくり、農家の老人と未経験の老人がお互い教えあいながら、野菜をつくり、インゲン同士の結びつきを強くして、生活を豊かにするためにできたものです。
なかなかうまくまとまったと思って、新居さんのところにもっていった。
それを読むと、「よくまとまっているじゃない、だけど、これは冗談でしょう」
と、”ニンゲンサークル”と”インゲン同士”を指さした。
僕は新居さんのいっていることはわからなかった。
「ニンゲンサークルってなに」
「畑で、ニンゲンなどの野菜を作るサークルのことですよ」
はじめ笑っていた新居さんが、まじめな顔になった。
「インゲン同士って」
「我々インゲン同士はコミュニケーションをよくして社会をよくしていかなければならないでしょう」
僕がそういうと、新居さんは、ちょっと厳しい顔になった。
「わたしね、今日も珍しくお弁当作ってきたのよ、今日から碓井君でてくるっていうから、一緒に食べようと思って、碓井君もおべんとうでしょ」
僕は母親の作った弁当を持ってきているのでうなずいた。
「ちょっと、これみてね」
新居さんは机の上に自分の弁当の包みを広げて、ふたをあけた。
「これなに」
新居さんはおかずを指さした。
「やっぱりニンゲン入れてきたんだ」
僕がそいういうと、さっと、弁当を包み直してバックにいれた。
「ちょっと、これ読んでみて」
新居さんが、机の上で、マジックで字を書いた。
「インゲンサークル」
僕が答えると、これは、ともうひとつ字を書いた。
「ニンゲン」
「ウン正しく読めるのね」
新井さんはマジックで人の形を描いた。
「これなに」
「インゲン」
「碓井君、早引けして、病院にいったほうがいいわ、ちょっと、課長に説明してくる、碓井君もきて」
僕は新居さんにつれられて課長のところにいった。
「碓井君まだ治っていないみたいです、病院に行った方がいいと思います、ニンゲンとインゲンが逆さまになっています」
それを聞いた課長が、「なにそれ」と新居さんの顔を見ると、新居さんはさっき僕とやりとりしたことをその場でやった。
僕には意味が分からなかったが、新居さんが紙に人間の絵を描いた。
これなに、新居さんが言った。
「インゲン」
これは、また絵を描いた。
「ニンゲン」
「ほんとだね、ニンゲンとインゲンが逆さになったな、ご両親に連絡するよ」
課長が僕の家に電話を入れ、僕は家にもどされた。
その後、両親は僕を脳神経内科につれていってくれたのだが、僕には意味がわからなかった。
医者が僕に聞いた。
「ニンゲンてなに」
「野菜の一種で、豆科の植物です」
「インゲンは」
「われわれです」
「人はなにですか」
「われわれです」
「ふーん、理解は変わっていないようですね」
さらに、インゲンとニンゲンの絵を見せられて、そのものを言葉で紙に書かされた。
次に紙に書いた「インゲン」と「ニンゲン」を読んでくださいといわれた。
彼はインゲン、ニンゲンと読んだ。
「碓井さん、書かれた言葉を読んで、そのまま発音する機能は正常です、見た物を理解することも正常です、ただ一点、ニンゲンとインゲンのことばが全く逆転している。ニンゲンとインゲンの理解が全く逆になってしまっています。事故にあって、そうなったのだと思いますが、実は、記憶と関わりがあると思いますが、脳のどこに記憶がしまわれているかわかっていません、逆に脳を調べて、碓井さんの脳と他の人の脳のどこが違うかわかると、脳の言葉の記憶と理解の解明に大変役に立ちます。脳機能の科学が進歩します。どうでしょう、治療と同時に、研究に協力していただけませんか」
僕はともかくうなずいた。
神経内科の医者は前に撮ったMRIの脳の写真をみて、「普通のMRIではわかりません、ファンクショナルMRIで調べる必要があります、その機械は県立病院にあります。言語と記憶の関係を研究している先生が調べてくれます。元に戻す方法も考えるでしょう、連絡しますので、そのときは県立病院にいっていただけますか、治療費は無料です、それに協力金として、交通費や休暇を取ったときの給料分がでます」
「はい」と返事して立ち上がると、先生は、
「碓井さん、碓井さんのニンゲンとインゲンの記憶が逆になっていることを、いつも頭に置いていてください。我々はインゲンではなくて人間です。豆はニンゲンではなくてインゲンです。ニンゲンとインゲンを見たり、聞いたり、しゃべったりするときには、他の人と違うんだということ、それさえ知っておけば後は正常ですから、仕事もなにやっても問題ありませんよ、診断書をご両親や、仕事場の人に見せてください」
先生は笑顔になって言ってくれた。
そういうことで、家に帰って、両親に診断書を見せると、母親は「ニンゲンがインゲンにみえるのかい、それじゃ、お弁当にニンゲンはいれられないね」といった。父親は「庭のインゲンはもう終わりだから、かりとっちゃおう、インゲンにニンゲンがなっているのを見るのはつらいだろうからな」
と言った。しかし、彼はインゲンがなっているところを見て、人間がぶら下がっているようには見えていない。絵は正しく理解している。そこまでひどくなっていないことを、紙に書いて教えた。
「そうかい、また、俺がインゲンに見えるのかと思った」
と父親は笑った。
次の日、市役所に出勤して、診断書を課長に見せた。課長は診断書を課のみんなにみせた。
同僚たちは「碓井さん、仕事で手伝うことがあったらいってください」ととても親切だ。
シルバー会のニンゲンサークル、いやインゲンサークルに関しては、ぼくはもうかかわらないことにした。自分でも自分の脳の障害を理解したからだ。
それからは、僕の仕事は全く問題がなかった。一週間に一度、県立病院に行って、検査を受けている。
治る気配はないが、インゲンという字をみたら、我々の身体を連想して、ニンゲンという字を見たら豆科の野菜を連想するようなトレーニングを受けている。だが、なかなか難しいものだ。身体、いや脳に染み着いてしまっているのを変えるのは大変なことだ。
インゲンとニンゲン、アナロジーというのは、脳の中で何かしら意味のあることのようだ。
ニンジンとエンジン、キュウリと郷里、ハクサイとヒャクサイ、アンマとヤンマ、
やめようやめよう、また頭を打ったら、どれが変わるかわからない。一つ変わっただけでこれだけ大変なのだから、みんな変わったら、どうなるのだろう。子供の頃から頭の中に蓄えた情報は重要な物なんだ。もし間違えて頭の中に入っていたら、きっと、悪人になっているだろうな。
そういえば、僕にぶつかって一命を取り留めた女性は、回復したそうである。僕に謝罪の手紙をくれた。もう二度と自殺を考えたりしないとあった。自分の頭も少しは役に立ったんだ。
こういうこともあるが、普通に静かに暮らしているのが一番幸せである。
インゲンとニンゲン


