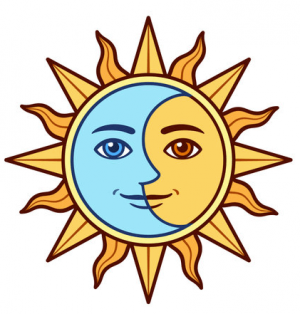沼のオフェーリア
目が覚めた時、私は沼のほとりで下半身を泥に埋もれさせた状態になっていた。
コンソールを作動させたが、うまくメインフレームには繋がらないようで、外部データが参照できなかった。現在位置を調べようと思ったけれど、GPS波をキャッチできず、そのあたりで私は私の実験の成功を確信したのと同時に、仮説の誤りにも気付かされた。悔しいけれどデラ・クセルの指摘は正しかった。私はデラのムカつく顔に泥が塗りたくて実験を強行して、挙げ句、ただ一人、こんな場所で泥に埋もれているのだ。
腰を前後させて少しずつ水を流し込み、可動域を広げていく。じゃぼじゃぼと水と空気が混じり合う音が大きくなり、そうしているうちにどうにか両足が動き出し、ついにようやく引き抜くことができた。ただし、左のブーツは抜けてしまった。腕をつっこんで引っ張ってみたが、どうにもならないので諦めて、沼から這い出した。あとで取りに来ればいい。
沼のほとりは斜面になっていて、つるりとした表皮の植物が群生している。根元はツタ状の枝か根が絡み合っていて、足場にすればどうに上っていけそうだった。ただ、あまり強度がないためにバキボキと折れ、上に登るのは難しそうだ。私はそのまま斜面を植物の根を足場にしながら、少しずつ上っていった。緑色だから葉緑素は持っていると思われる。形状はだいぶ異なるが、現代の植物とそう離れたものではなさそうだ。古生物学者を連れてきたら狂喜乱舞すると思うが、果たしてここが計算通りの十億年前の同じ場所なのかどうか、それはわからない。
夕暮れ前にはなんとか高台まで登ることができた。夕陽を背に、丘から顔を出して、私は言葉を失った。そこには朝日が昇るのが見えたからだ。地球ではない、とすぐに気づいた。あれは月ではない。沈んでいく太陽に比べて少し小さいが、恒星には違いない。ちょっと日差しの弱いもう一つの昼間がやってきたのだ。そうだ。この惑星には夜がなかった。
白夜っぽい光量ではあるが、夜という感じではない。沼の方を見ると、ディンギーはまったく見えなかった。サバイバルキットは一応積み込んでいたが、それすら回収できてない。腰のポーチには水質調査キットと大気成分分析器、コンソール(情報端末)、アーミーナイフがあるのみだ。とにかくディンギーに戻る必要はある。だが、あの粘り気の強い泥にまた入るのは危険だし、この弱々しい植物をアテにして斜面を下るのも相当怖い。丘の上は植物はあまり茂っておらず、沼の全景が見渡せた。夕陽側は沼があり、その向こう側には今立っているのと同じぐらいの高台があった。その向こう側は、外輪山をぐるっと回り込んで向こう側でのぞき込むしかなさそうだ。朝日側は相当遠くまで露地が広がっていて、この弱々しい植物はこの沼の周囲にしかないことがわかった。そして、見渡す限り一面に、私以外誰もいないことがわかった。そしてここは地球ではない。ディンギーは作動した。しかし計算は間違っていた。デラはあのとき、なんと言っただろうか。「どこに飛ぶかわからないものに乗るな」と言ったのか「やってみなければわからない」と言ったのか。いや違う。あの男は「それで正しいと思うのならやってみろ」とけしかけたのだ。それで私は引き際を失い、ディンギーを作動させるしかなくなったのだ。それは、私をこのような窮地に追い込んだ。絶望が足元から近づいてくる。
絶望は、腰まで上っている。かろうじてまだ正気は保てている。この何もない惑星であとどれだけ生き延びられるのか。まずは、水だ。沼まで降りる道を作ろう。弱々しい植物も、部位によってはそれなりの強度があることがわかった。長いと折れるが、短い場合は少し体重を乗せても折れたりはしない。特性はシダ植物に似ている気がする。あのブラッケンの若芽に近い。
どうにか階段状に斜面を下る道を作ることができた。底の泥を巻き上げないように、そうっと容器に汲んで、分析器にかける。数秒で結果が出る。いろいろな物質が混ざり込んでいるが、致死性のある毒性物質はなかった(あっても致死量以下)。そして微生物が検出できなかった。つまり現時点では飲用には適している。私は手ですくって飲めるだけ飲んだ。私が浸かっていたあたりは私自身が持つ大腸菌などの細菌が漏れ出しているだろうから、今後飲料に適さないものになる可能性はある。汚染範囲を広げないように手を打っておこう。水があれば数日は生きていられる。
水だけで生きていられるうちに、食料の手立てを考えなければならない。まず、尾根伝いに西側(夕陽の沈む方をそう呼ぶ)の丘に行ってみたが、その先は東側と同じで、荒野が広がっているだけだった。見える範囲には、山地も窪地も見当たらない。この星にはなにもない。この沼だけ。沼の水と周りのブラッケンモドキだけが私のライフラインだった。不幸中の幸いなのは、襲ってくる生物がいないことか。絶望と希望は紙一重なのかもしれない。絶望は鳩尾ぐらいに止まっていてくれたが、すぐに喉元まで押し寄せてきた。いよいよ空腹が厳しくなってきた。今なら何を食べても美味しいだろう。水だけでは空腹はごまかせなかった。ブラッケンモドキをちぎって口に入れてみた。苦味がひどくとても食べられたものではなかったが、そのまま噛み続けた。味はまったく変わらないが、だんだん細かくなってきて、少しずつ飲み込むことはできた。空腹が和らいだ気がした。消化できるのか、できないのか、それはわからなかった。できなければ、どこかで意識が途絶えて、死ぬだろう。だが、この植物から最低限生きるだけの栄養を摂取することはできたようだ。私は死なず、ただひたすらこの不味い植物を食べ続けることで、生きながらえることができた。絶望が膝ぐらいまで下がっていった。とにかく、今すぐ死ぬことはない。この宇宙のオアシスで生き続けることはできる可能性がある。生きていれば。生きていれば、何があるのか。助けが来るのか、来ないのか。今はいつなのか。現代なのか、何億年も航行できたのか。それとも未来か。夜が来ないので星が見えない。地球なのかすら判別できずにいた。歩ける範囲での捜索を試みたが、地平線まで、何も見えることはなかった。ろくに岩石も、クレーターもない惑星だ。この沼地だけが奇跡のように、ここにあった。ディンギーを沼の底で探してみたが、私の息が続く程度の深さでは見つからなかった。ディンギーさえあれば、帰ることができるかもしれないのに、それは叶いそうになかった。しばらくブラッケンモドキを食べ続けて気づいたことがある。この植物は増えない。どういう生命体なのかまったくわからないが、胞子で増えることもなければ、種子で増えることも、株で増えることもなかった。そして成長することもないことに気づいた。食べたら、それで終わりだということだ。絶望がまた、胃袋のところまで押し寄せてきた。死を選ぶにしても、死にかけたまま長く苦しむとしたら、誰も助けが来ないこの状況では、リスクが大きすぎた。そんな状況は望んでいない。それよりまだ、この前人未到の土地への好奇心が、私を生かしていた。ブラッケンモドキの残りがいよいよ数えられる程度に減ってきて、私は死が遠くないことを悟りはじめていた。なくなるまでには、なにかしらの次のステップが与えられると心のどこかで思っていた。だが、そんな発見や変化はまったくなく、私はただひたすらこの本当に不味いだけの植物を噛み、飲み込んで生きているだけだった。少量の大便は数日で乾燥しきって塵となって風に舞い、何も生み出しそうになかった。私から出ていく異物は、この惑星の巨大な懐にわずかな影響を与えることなく、ただ薄まって消えていくだけだった。沼の水は少しずつ減っていたが、ブラッケンモドキの減少に比べたら微々たるもので、水の心配などは無用に思えた。仮に干上がるとしても、私の死後だ。最後のブラッケンモドキの根を飲み込んで後、私は沼に身を浮かべた。私は異星でオフェーリアとなり、時の流れに身を任せた。
夢を見た。銀色の乗り物で猫が大勢やってきて、私を沼から引き上げた。猫は何かを私に聞いているようだが、猫の言葉はわからないの。ごめんなさい。何を言っているの? 私はもう死ぬわ。もう何もしたくないの。眠らせてください。そして私は、猫が何を言っているか、急に理解した。猫は言う。
「吾輩は猫である。名前はまだない。……名前は?」
そう言っている、と思った。私の名前、そう私には名前がある。伝えなければ。
「……私は、ヒロミ。ヒロミ・ヤナギサワ……」夢はそこで終わった。
***
エバーソン工科大学の爆発事故での行方不明者は結局、日本人の柳沢博美博士だけであることがわかったが、遺体のかけらすら見つからなかったことで、当局は同僚のデラ・クセル博士を爆発事件または事故の容疑者として身柄を拘束し、尋問を開始した。
クセル容疑者の説明では、柳沢博士は「タイムマシン」の研究を行っており、その実験機を勝手に作動させて爆発したとのことだったが、現場検証の結果、そのような乗り物の痕跡は全くなく、クセル容疑者が前日に柳沢博士と口論を行っていたことなどから、殺人と死体遺棄の容疑に切り替えて追及したが、一貫して供述を変えることはなく、証拠不十分で釈放された。その後、訴追されることはなかった。
クセル博士は事件後エバーソンを退職し、アリゾナの山荘で独自に研究を行っていたが、40年後に爆発事故を起こし死亡した。関係者の証言では、時空転送装置と、食用の遺伝子改造植物の研究をしているとのことだったが、いずれも論文などは一切発表されておらず、真偽は定かではない。
沼のオフェーリア