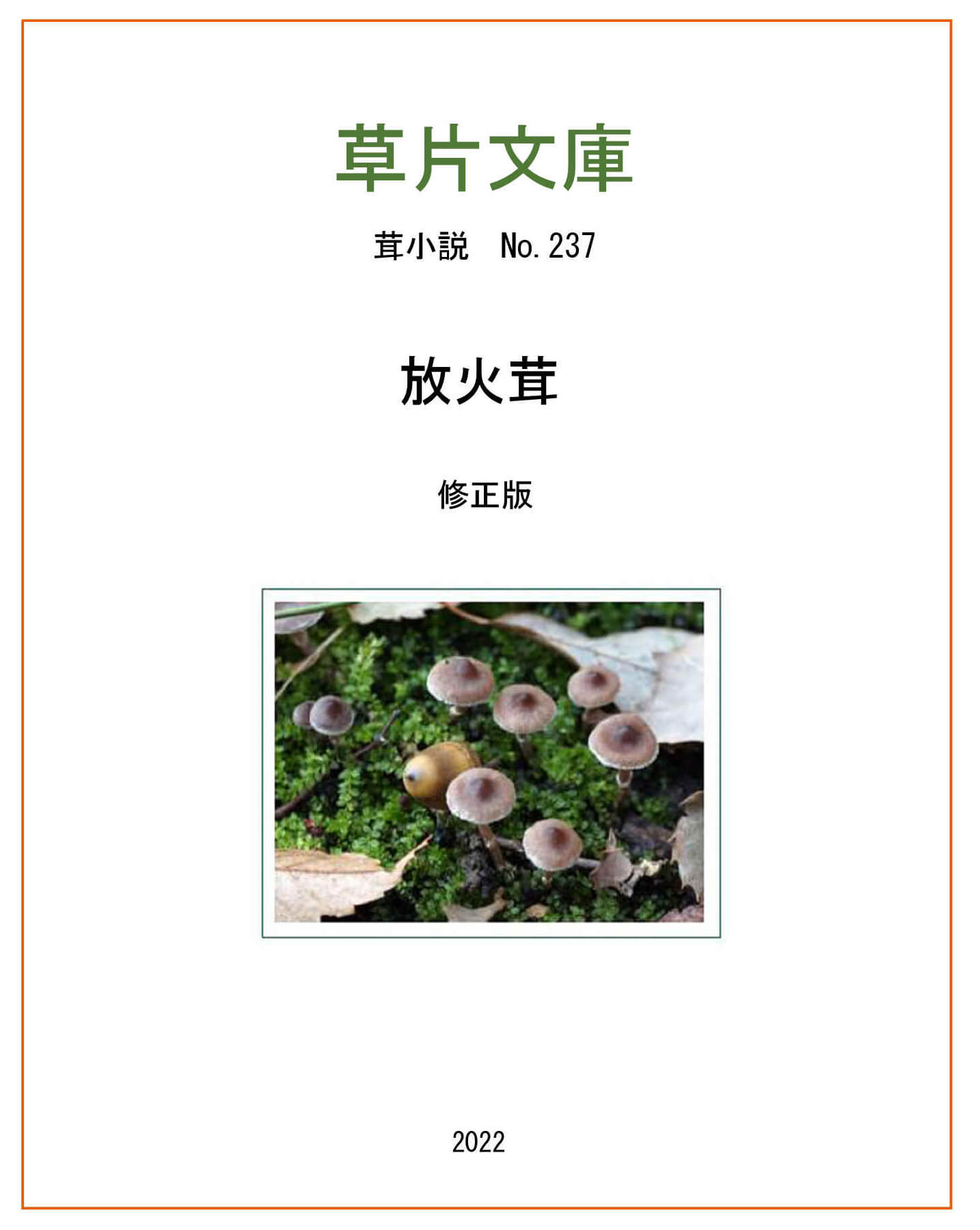
放火茸
ミステリーです。縦書きでお読みください。
やっと秋風が吹きはじめた。この夏はとてつもなく暑く、東京の人々も人心地着いたところである。そんなときに、私の住んでいる団地で、放火事件が数件起きた。多摩地区の緑の多い、丘に広がる大きな団地だ。団地には空いている土地がいくつもあった。その空き地の草が燃える事件がおきている。土地そのものは三十坪とか四十坪ほどの狭いところで、買ったが、理由があって家をたてずに十年二十年と放ってあるところだった。半分枯れた草に火がつけられたのだが、幸いに周りの家までには火が広がっていない。夜になるとちりんちりんという音とともに、消防団の消防車が家の前を通るようになった。犯人はつかまっていない。
家内が噂話で聞いてきたのだが、直接草にライターで火をつけたと警察は言っているらしい。犯人を特定できるようなものはみつかっていないという。
私は元刑事である。退職して三年ほどになる。警察をやめると、警備会社に再就職するか、マーケットの警備員アルバイトをするかである、私は次の職をもとめせず、毎日をのんびりと、探偵小説を読むなどしてすごしている。
「あなた、見てきたらいいじゃない」
家内にいわれ仕方なく重い腰を上げた。火をつけられた土地は、我が家からかなり離れたところだ。
行ってみると、草が焦げ、土が黒くなっている。草以外に燃えたような物は見あたらない。ふつう、このような放火は、軒下に置いてあった燃えやすい物に火をつけたり、止めてあったオートバイに火をつけたりすることが多い。自分がむしゃくしゃして、火をつけてすっきりしたいという愉快犯である。しかし、少し枯れているとはいえ、まだ緑の草に火をつけるのには時間がかかる。油を撒いた跡などはないようだし、ライターで火をつけたとなると、その場にしばらくいなければならない。しかもぱっと燃え上がるわけではなく、さっさとその場から立ち去ることができない。ただの愉快犯ではなさそうだ。なにが目的なのだろうか。いや、本当にライターで火をつけたのだろうか。
そういえば家内が言っていた。燃えた土地の隣の家の人が、ぱちんという、何かがはぜたような音を聞いたという。板などが燃えると、ぱちぱちとはぜる音がでるが、草ではそんな音はでないだろう。
犯人は歩いてきたとみえる。車やオートバイできたとなると、どこかに止めなければならない。そのような音を聞いたという情報もないようだ。自転車だって、それなりの音がでるものだ。団地の中の人通りは多くなく、通り抜ける車もメインの広い道以外は少ない。家の間の道にはそこに用事のある車が入ってくるぐらいのものである。
狭い空き地だから、前に立って見渡せばすべてが見みえる。土地の真ん中ほどに燃えた跡がまあるく黒くなっている。ふと見ると、そこに茶色っぽい茸が数本はえていた。やっぱり秋になったんだな、場違いな思いをもった。よく見るとこげてはいないいから、燃えた後に生えたようだ。
そこを見て、ほかの二ヶ所にも行ってみた。やはり同じように、草の燃えた跡があり、それ以外に焦げたようなものはなかった。火をつけた動機はなんだったのか、ちょっと想像ができない。
おやと思ったのは、黒い土の上に、最初の現場と同じ茶色の茸が生えている。張ってあるロープをまたいで中にはいり、よく見ると、皆同じ茸だ。茸を一本とると家にもどった。
「行ってきたよ」
「どうだった、なにかわかった」
「なんにもわからんよ」
家内は私が持っている物に目をやった。
「茸とってきたの」
「焼けた跡に生えていた」
家内は私の手から茸をひったくると、「食べれそうにもないわね」と返してきた。
「あなたが警察の人に話を聞いてくれたらいいのに、様子は分かっているでしょう」
「もう退職人間だよ、老人がしゃしゃりでるのは、若い人たちはいやがるだろうよ」
わたしは警視庁の本部勤めであった。このあたりの管轄署に知り合いはいない。
「犯人エスカレートしないといいけど」
「うん、直接家に火をつけるようなことはしないだろう。そうするなら、すでにしているからな」
「だけど、今まで、うまくいったから、今度はもっと派手にやろうって思わないかしら」
家内の言っていることにも理がある。往々にして、犯人の手口はエスカレートするものだ。
「これからの方が気をつけなきゃね」
「そうだな」
そんな話をして三日後だった。珍しく半鐘がなった。団地のはずれに、消防団の建物があり、半鐘が備えられている。昔ながらの景色だ。
夜の八時。外にでてみると、南の方がうっすらと赤い。犯人がとうとう家に火をつけたのか。
「ちょっと見てくるよ」
「気をつけてね」
私は出来ることがあったら手伝おうと思い、現場に向かった。
燃えていたのは団地の脇の雑木林だった。広いものではないが、ドングリやブナが植わっている林だった。散歩するにはいい林だ。市の管理地である。
小さな山火事のようなものだ。林が燃えていた。家でなくてよかったが、火の粉が飛ぶと危ないだろう。消防車がすでに到着していて、道を隔てて隣接する家にも水をかけていた。
消防車一台で消しきれるわけはない。そのあと何台か到着して、放水を始めた。
野次馬が遠巻きにしている。私もその中の一人だ。
「あぶないですから、家に戻ってください」
パトカーから降りた警官が叫んでいる。制服の警官のあとに、私服の刑事らしい男が降りてきた。
消防署の脇にいた老人に話しかけている。私も気になって、そばによった。どうもその老人が最初の発見者のようだ。
「家のガラス窓に赤い物がちらちらしていて、気になって窓をあけたんだ、そしたら、林の中に火のようなものが見えてね、外にでてみたら、炎があがっている、それがあっという間に木にうつったようで、火が上にのぼったので、あわてて家に戻って、電話したんですわ」
すぐそばのうちの人のようだ。
「7時半ごろでしたね」
「ええ」
「人は見ませんでしたか」
「いんや」
「また、お聞きすることがあると思います、大丈夫だと思いますが、避難できるようにしておいてください」
「ええ、ええ、もう、家内が荷物をまとめていると思います」
「ありがとうございました」
刑事が見物人の方を向いた。
「みなさん、危ないですから、お帰りになってください、お近くの方は避難のできるようにしておいてください」
なかなか気の回る刑事だ。
野次馬の私もみっともないかと、戻ろうとしたときに、その刑事が私のほうに小走りでやってきた。
「もしかすると、野間警部じゃないですか」
私は野間宏という。
刑事の顔を見て、あっと思った。
「やっぱり、警部でしたか、ご無沙汰しております」
私が警視庁をやめるときに、新米刑事だった男だ。伊沢正という。
「いや、お久しぶりです、今度、こちらの署に配属になりました。確か、警部がこのあたりにお住まいだということは覚えておりましたが、ここでお会いできるとは思いませんでした」
「いや、おはずかしい」
「家はこのお近くですか」
「うん、すごく近くではないんだけど、歩いて五分ほどかな」
「ここのところ立て続けに、放火がありましたよね、この林の火事もそうかもしれません、これから調べます、警部、なにお気づきのことはありましたか」
「いや、他の三カ所を見たけど、草だけが燃えていて、全く理由がわからない。草に火をつけるのは大変だよね」
「そうなんです、しかも、草の葉先から燃え始めたのではないようなんです、むしろ生え際のところから燃え始めています。それにわからないのは、ごらんになったと思いますが、丸く焼けていますが、どこに最初に火をつけたのかわかりません、同時に火がでているような感じを持ったのですけど、一応、ライターでの火付けということにしたのですが、本当は全く分かりません」
「家内も、ライターだと噂してたな」
「マッチの燃えかすもなければ、火をつけるために紙や木の枝をつかったようすもないんです、それで、火をつけたあとに、もって帰れるライターのたぐいとふんだわけです、台所で使う特に長い先のあるライターということです」
たばこに火をつけるライターではなかった。たしかにストーブやガスコンロに火をつける為の柄の長いライターがある、チャッカマンだ。
林の火がだいぶおさまってきた。
「警部さん、何か気づかれたことがあったら教えてください」
彼はまたそう言うと、煙だけになった林に消防署の人と一緒にはいっていった。
「ああ、ご苦労様、気をつけて、そのうち連絡しますよ」
彼の後姿に声をかけ、家に戻り、今のことを、家内に話した。
「一度うちにお呼びしたら、そのうち頼んでおいた茸がとどくかもしれないから、茸料理するわよ」
「そうだな、今日は忙しいだろうから、明日にでもここの警察に連絡してみるよ」
三日後の土曜日の夕方、非番だった伊沢は我が家にきた。
「おじゃまします、はじめておめにかかります、伊沢です、野間警部には大変お世話になりました」
玄関先で、家内に律儀な挨拶をしている。
「よくいらっしゃいました、うちの主人、退職してからぶらぶらしていて、なにもしないんですよ、お客様は伊沢刑事さんがはじめてくらい、どうぞどうぞ」
余計なことを言いやがってと思うのだが、ともかく、彼が部屋にはいってきた。
「この団地は眺めもよくて、駅までもそんなに遠くなくていいところですね」
「自然がありますでしょ、伊沢さんはどちらにお住まいなのですか」
彼は隣の駅のマンションの名前を言った。
「賃貸マンションです、またどこかに移動になるかもしれませんから」
「お子さまは」
「ええ、小学生と中学生がいます」
「奥様大変ね、今日はせっかくの非番だったのにおよびしてしまってすみませんね、お子さんもお父さんと一緒にいたかったでしょうに」」
「いえ、大丈夫です、うちのは警察官だったのですが、やめましてね、今マーケットの警備部に臨時雇いです、土曜日の夜は忙しいので家にいませんし、どっちの坊主も、子供のサッカーチームに入って練習です、みなあまり家にいないんですよ、僕のほうがいつも一人で留守番なんてことも多いんです、夕方はかみさんが帰っています」
「そうですか、今日はおくってもらった天然茸を料理しますから、伊沢さんお酒は」
「ほどほどです」
「おい、おい、酒は俺にまかせとけよ、食うもん出せよ」
かみさんをキッチンに追い立てた。
「ビールと、とりあえずなんかつまみくれ」
「はい」
「伊沢君、どうこっちの生活は」
「そうですね、前は都内の官舎でしたし、コンクリートに囲まれていたから、ずいぶん気分がいいですね、」
「警察署はどう」
「あつかうものが、家庭的になりました、こそどろや、車の接触事故、今度のように火事、本署にいたころは、かなりあくどい事件が多かったですから」
「そうだよね、外人が関わることもあって、国際的な物があるしね」
家内がびーるをもってきた。送ってもらったナメコの酢醤油だ。
彼にビールをついだ。
「すきなようなやって」
「ありがとうございます」
「ところで今度の放火の犯人は目安がついたの」
「いえ、全く、目撃者が一人もいないんです、現場でお話ししたように、草が根本から燃えているので、警視庁の鑑識にちょっと応援頼みました。現場にきてもらって、科学捜査をしてもらっています」
「そういえば、燃えたあとに、茸が生えてたな」
「捜査官も茸を採取していました。それにおもしろいことをいっていましたよ、かすかだが、ニンニクの臭いがするって」
「茸がにおうの」
「いえ、焼け跡と言うより、その場所がにおうといっていました」
「なにあの茸」
「ヤケアトツムタケっていってました」
「そんなのがあるんだね」
「たき火の跡などにでる茸だそうです、昔はよく見られたということです」
「たき火はできなくなったからな」
「捜査官がいうには、外国ですけど、山火事の跡に生える編傘茸の種類があって、おいしいのだそうです」
「編傘茸っていうのは知ってるな、でこぼこしたやつだろ、フランスなんかじゃ結構高い茸だってな」
「日本でも名前が知られるようになりましたね、モレーユっていって、おいしい茸ですよ、その焼け跡にはえる編傘茸は黒っぽいそうで、やっぱりおいしいそうです、捜査官がそういっていました、茸は一応科学博物館の研究所で調べてもらっているそうです」
その後、地元の警察署の話やら、私の老後の話やらをして、彼は帰っていった。
それからしばらくたったある日の夜、燃えた林の近くの家で火事が起きた。夜中だったので、現場に行かなかった。いけば伊沢がいたと思うが、邪魔になるといけないと思ったからだ。
とうとう家に火をつけるようになったかと、ちょっと心配になってきた。朝になり、見に行くと、ロープの張られた庭の中の家はほとんど燃えていて、黒い柱が数本残っているだけである。
見に来ていた老人が、芝生に囲まれた瀟洒な家だったが、あっというまに燃えてしまった、と話しかけてきた。
気になったので、庭を見ると、何箇所かまあるく芝生が焦げてたところがあり、建物の際まで連なっている。庭の芝生に火をつけたのだろうか。どうも不思議だ。
あ、もう茸が生えている。ヤケアトツムギダケだったな。
その足で、以前燃えた林にいってみると、もうロープも張られておらず、中を散歩することができた。燃え残った木が突っ立っているその下には、草がよみがえり始めており、白い茸が生えている。ヤケアトツムギタケではない。ちょっと中に入っていくと、真っ赤な茸がなんぼんもつったっている。毒々しい茸である。
家に戻って、家内に燃えた家を見てきたことをいうと、
「あそこの奥さん、家を自慢していたのにがっかりしているでしょうね」
とあまり同情的ではない。
「誰だって、困っているよ」
「きっとたくさんの火災地震保険かけていたわよ、すぐまた建つわね」
どうも周りから好かれていなかったようだが、それと火事は違うじゃないかといいたいが、ぐっとがまんした。一つ言い返すと、三言かえってきてうるさい。
電話が鳴った。
「あなたでてよ」
だいたいいつも家内の友達からで、長電話をする。だから、でないことにしていたのだが、台所で洗い物をしているようだ。仕方なしにでると、珍しく自分にだった。
「おはようございます、伊沢です、先日はごちそうさまでした」
刑事の伊沢からだった。
「今度は家が燃えたな、山火事にあった林が近くだよな、昨日も現場に行ったの」
「ええ、行きました。あの火事も火付けだと思うのですが、犯人は全くわかりません、話がかわりますが、実は昨日、科学博物館の研究所、研究所は筑波にありますが、研究施設で、ぼやがありました」
「なにそれ、団地の火事と関係あるの」
「それなんですが、ちょっと私には理解できないんです、筑波の研究者と警視庁の、火事の調査に当たった植物や茸に詳しい科学捜査官が、今度の火事の現場に行きます、私もいきますが、科学捜査官に野間警部のことを言ったら、一度捜査に同行したことがあるそうです、渋谷といいます、もしよろしかったら、野間警部にも現場に行らしていただいて、ご意見をいただければとおもうのですが」
今までに何人もの科学捜査官と仕事をしたので、顔を見ればわかるかもしれないが、名前を聞いてもわからない。
「今、散歩がてら現場を見てきたとこだよ、俺が行ってもじゃまになるだけじゃないのかな」
「いや、是非、ご予定が入ってなければ、ご一緒に見ていただきたいのですが」
「うん、いいけど、きたいするなよ」
「十一時頃、現場の家に行きます、とても奇妙な話があるのです、おそらく、警視庁も厚生労働省も、いや、環境省ものりだすかもしれません」
「ほー、すごい事件なんだ」
「それでは、よろしくお願いします」
いったいなにが起きたというのだろう。
「あなた、長電話ね、友達から電話かかってくるかもしれないのよ」
キッチンで家内が騒いでいる。携帯を持ってるくせに、家の電話で長話しやがる。携帯は自分の小遣いで支払うことになっているからだ。
「おわったよ」
「なに、宣伝じゃないようね」
「伊沢からで、燃えた家の検証につきあってくれとさ」
「あなた暇だからいいじゃない」
余計なお世話だ。
「十一時にでるよ」
「背広いるの」
そんな物いるわけないじゃないか、退職してるんだぞ、返事をしてやらなかった。
十一時五分前に家をでて、ほぼジャストに現場についた。伊沢と捜査官が燃えた家ではなく、燃えた芝生をほじくっていた。
「やーごくろうさん」
ロープをまたいで庭にはいると、かがんで焼け跡を調べていた捜査官が立ち上がった。
「あ、きみかあ」
「お久しぶりです」
日に焼けた顔にえくぼを寄せて、大きな目で私を見た。忘れられない顔だ。渋谷紀子といった。大麻の密売組織をあばいたとき、大麻栽培を行っていたマンションを、大麻の性質からいくつもみつけだした捜査官である。生物学出身で、特に植物や茸のことに詳しかった。現場を明るくしてくれる、記憶に残っている捜査官だ。
「警部お元気そうですね」
「まあ、まあ」
頭をかいた。
「この事件、真相が少し見えてきたんですけど、とんでもない犯人のようです、あとで、渋谷捜査官が説明します」
家の焼け跡を検証していた伊沢が寄ってきて言った。
「ここに犯人がいるそうです」
庭の土のはいった瓶をかざして見せた。
なんなんだ。犯人が分かっているなら俺を呼ぶことなんかないのに。
「渋谷さんが、警部に会えないかと言うものですから」
不機嫌な顔をしていたのだろうか、伊沢が細くした。私も調子を合わせなければ。
「渋谷君はあのときは活躍してくれたよね、今度もかな」
「そうなんです」
と伊沢がうなずいた。
「そんなことないですよ」
伊沢に言われて、彼女はまた笑った。こうやって、現場を明るくしてくれる。彼女は
「ここに生えている、ヤケアトツムギタケ、新種ではないのですが、生きるために大きく進化をしたようです」
と茸の説明をしてくれた。どういうことなのだろうか。
「警部、何カ所か土をとったら、署に帰ります、どうですか、ここの警察署ごらんになりませんか、警部はまだこられたことないでしょう、署長も会ってみたいといっています、そこで、渋谷さんから、放火の犯人のことをきき、これからの防犯対策について話し合う予定です。ご予定がなければ、どうでしょうか、警察署の親子丼を食べながらでも」
「犯人じゃないんだから」
と、笑いながら答えたのだが、とてもたのしそうだ、退職してしてからこのかた、こんなに気分が晴れているのははじめてだ。やはり、長い間の勤めから離れるのは、むずかしいものなのだ。警備会社に勤める連中の気持ちもわからないでもない。と思うようになった。
伊沢刑事の運転する車で、この町の中央署にいった。会議室に案内されると、渋谷捜査官がすでにきていた。
「やー」と声をかけたところに、署長がはいってきた。
「はじめまして、警部がこの町においでとは知りませんでした。警視庁でのご活躍はいろいろうかがっています、みなが上に行く人だと思っていたと言っていました、それが急にやめてしまって、驚いているということでした、残念だと言っているいるひとがかなりいました」
警視庁では、上昇志向の連中に囲まれていて、嫌気がさしたんだ。それで早期退職という道を選んだ。
「いや、もう気力がなくなったんだよ」
「柔道もかなりの段をお持ちだったと思いますけど、どうですか、講師料は少ないのですけど、うちの連中に手ほどきをしていただければ」
「もうなまっちまっているからだめでしょう」
「噂は聞いています、お願いできれば、あとでまた、お話しさせてください、今日は、放火の件でもご意見をいただけるということでありがとうございます、伊沢君に任せてありますので、この後はよろしくお願いします。本庁からは科学捜査官のベテラン、渋谷刑事に来ていただいています」
「いや、お役に立つかどうかわかりませんが」
「よろしくお願いします、食事もきますから、ごゆっくり」
署長はそういい終えて、部屋を出て行った。なかなか感じはいい、ああいう署長がいるなら、柔道の講師ならやってみてもいいだろう。
「野間警部、渋谷捜査官の話を聞くと驚きますよ、どのように我々は動くべきか、気がつかれたことがあったら教えてください」
「それで、犯人のめぼしはついたの」
渋谷捜査官が答えた。
「おどろかれますよ、茸です」
「きのこ?」
「警部の団地の庭や林の焼け跡にでたヤケアトツムギタケを、科学博物館の筑波の研究所で、調べてもらいました。やけあとつむぎたけそのものだったのですが、自分たちが増えるために、ある能力を獲得したのです」
「むずかしいね、その茸が新種になったと言うこと」
「うーん、新種というか、種は変わっていないのですが、新しい能力をもったんです、人間がテレパシーをもつようなものです」
「そりゃ新種じゃないの」
「かたちはそのままです、お酒を飲めない人が、急に飲めるようになったとする、それは、アルコールを分解する酵素が増えたか出現したことになります、これは、細胞の中の化学反応の能力が変化したことになりますが、アルコールを分解する酵素を作る能力が何らかの遺伝障害でなくなってしまったらどうでしょう、その人は全くお酒は飲めなくなります、それでも人間です。ある茸の細胞が、生き延びる為に、細胞の中に今までなかった物を作る能力を獲得したとしたら、茸の名前は同じです、ただ区別するために、新などという言葉を名前につけるかもしれません」
「なんとなくわかる」
「筑波の研究室で、あの団地の焼け跡のから採取した茸を培養していたら、培養装置が燃えました」
「そうらしいね」
「それが、茸が生える前に、火がでたそうです」
「茸が生える前って」
「培地に胞子をまくと、菌糸と言う糸のような細胞の連なりが広がります」
「うん、それは知っている、土の中で菌糸が蜘蛛の巣のように発達して、そこから茸がはえるわけだろ」
「はい、茸の本体は菌糸の集まったものです、菌糸は細胞です、細胞の中では生きるための化学反応が起きています。人間の細胞と同じです。細胞のエネルギーになるATPという物質があります。Pというのは隣で、燐酸という化学物質になります。有機リンです。骨の中の成分や、血液中の七割は有機リンです。燐は細胞の働きをいろいろな形で支えています」
「燐というのは化学記号でPというやつだな」
「警部のいうとおりです」
居やもう警部ではないんだがと思いながら渋谷捜査官の話を聞いていた。
「この化学元素Pの意味は、ギリシャ語の「光」のスペルの頭のPです。光に関係があります。リンには同素体といって、混じっているものによって、白リン、黒リン、紫リン、赤リン、紅リンなどがあります、赤リンは260度で発火するので、マッチの原料となります。怖いのは白リンで、60度で発火してしまいます。ただ、水のなかで静かに存在していれば発火はしません。
「刑事部長さんは黄リンマッチをごぞんじですか」
「うん、その辺にこすりつければ簡単に火がつくやつだよな、禁止されたんだろ」
「そのとおりです。その黄リンは同素体ではなく、赤燐が白リンの表面を覆っているような構造をしています」
「だけど、細胞にそのような物はないんだろ」
「はい、そのとおりです、ところが、ヤケアトツムギタケが、理由はわかりませんが、白リンを作るようになってしまったようです、そうなると、条件によっては、菌糸の先にたまった白リンが発火し、場合によっては、小さな爆発を起こし、草に火をつけることができます」
「え、それは本当なの」
「ほとんど、そうじゃないかと、科学博物館の茸の専門家の人が言っていました」
「だけど、何で、そんな茸になったの」
「燃えなければ、ヤケアトツムタケは生えないのです、自然に起きた山火事や、人のたき火によって、子孫を残すことができます、しかし、最近はたき火はしなくなったので、自分たちで、茸をはやす条件をつくらなければならなくなったのかと、専門家はいっています」
「それじゃ、自分たちが増えるために、火付けをする茸があらわれたってことか」
「はい、早く水をかければ問題ありませんが、知らないうちに、燃え広がってしまうこともあるでしょう」
「それで、それをどのように、国民に知らせるか、注意させるかなんです、警部いいアイデアないでしょうか」
「急にそういわれてもな、逆に利用しちまえ」
「あ、そうですね、それもありです、しかし、とりあえず、はびこって、我々の家が燃えては困ります」
「うーん、そりゃすぐ誰かがその菌糸が土の中にあるかすぐに検査できる機械を作るだろうし、そうしたら、菌糸がはびこらない薬をまきゃいいんだろう」
科学は弱い、しかし、その昔、人びとは科学を学んだわけではなく、自然の原理を生活の中で会得してきた。それで、自然の驚異にいろいろな形でたちむかってきた。今の子供たちは教わったことしか考えない。それでいいのだろうか。
どうも、変な方向に思考がいってしまう。
「警部のおっしゃるとおりです」
「毒キノコが生えたら、食べないようにおふれを出す」
「ええ、最近、火焔茸という、真っ赤な指のような茸がよく生えるようになり、新聞をにぎわしました。触ると皮膚はただれるは、食べたら死にます」
「怖い茸だね」
「だけど、真っ赤で、指のような形をしていて、とって食べようとは思わないからいいのですが、ヤケアトツムタケはヤケアトシメジといわれるくらい、食べられそうで、危険なのです、そのうえ、自分から火を出して、茸をはやすわけだから、茸をはやさないようにしなければいけないですね」
「水をかければいいのかな」
「雨が降っている間はいいと思います、毎日雨じゃ困ります」
「胞子は飛んでいくよな、それを防ぐことはできるかな、もうすでに飛んでいるだろう」
「そうです、町中の公園の木だって燃えるかもしれません」
「もっと、遠くに飛んで、富士のふもとの青木ヶ原が燃えちまったら困るな」
「そうですね」
「茸学者が考えてくれるだろう」
「もちろん考えてもらわなければなりませんけど、今警部がおっしゃったように、幅広く考えてもらう必要がありますね」
「その茸の菌糸だけ伸ばさないようにするのは大変だろうな」
「できないことはないと思います、専門的に考えれば、まず、発火させる白燐を作り出す化学回路を遮断する物質をつくりだすことです、うまくすれば既存の物質でよいかもしれませんが、そうでないと時間がかかるでしょう」
「だがな、白燐とかが作れる茸なら、寒いところでは大喜びだろうな、茸の暖炉ができる」
「あら、警部さんSFがおすきですか」
「読んだことはないよ」
刑事も捜査官も笑いながら顔を見合わせた。
「お昼です」
事務の人がお茶と、お昼の食事をもってきた。
「ほんとだ、親子丼じゃないや、カツ丼だ」
ふたを開けると、いい匂いがただよってくる。確かに腹が減っている犯人はほっと一息つくことだろう。それで、自白を始める。ドラマや小説の犯人に自白させる場面で、カツ丼が使われることは、意味のないことではないに違いない。
渋谷捜査官はカツ丼を食べながら、
「これから火事が多くなるでしょうね、それに乗じた犯罪も起きる、茸が火をつけるといって、どの程度国民がなっとくするでしょうね」
「学者さんに、そういった茸が見つかったことを、学術雑誌に出してもらって、そういう火事が増えて、ニュースが取り上げ、ワイドショウが取り上げて、やっと厚生省や環境省がのりだして、本気になるんだ、一年や二年かかるね、その間に何軒の家が燃えるか、山火事が起きるか、社会に浸透するのは時間がかかるね」
「警部さんの言うとおりでしょうね」
「茸爆弾も作れるな、その茸の胞子を巻くと、町中が火事になる。新しい焼夷弾だ」
「警部さん小説家にもなれますよ」
「探偵小説かチャンバラの本しか読んだことないよ」
伊沢刑事がお茶を飲みながら
「われわれのできることは、地元の人を守ること、茸のことは専門家に任しときましょう、どのように注意するか、保健所が考えてくれるでしょう」
これで、この事件は、警察としてとりあえずはかたがついたようなかたちだ。二人との話は面白かった。それに、柔道の講師も引き受けることになり、また柔道着を押入れから取り出した。
それから一年、一部の地域で、茸火事がおきるようになった。体温計ならず、地中温度計が作られ、庭のある家では何カ所かに設置した。地中の温度が高くなってくるとブザーが鳴る、そのときにはそのあたりの土に水をまく。当然公園や林も監視された。地熱発電の会社がヤケアトツムタケの研究を始めた。
だが人々の関心は長くは続かなかった。というのも、ヤケアトツムタケが全国的なものではなかったことから、火事も小規模でそんなに頻繁に起きることはなかったからだ。条件が整わなければ、茸は生えてこない。地中の温度計はあまり売れなかったようだ。
ヤケアトツムタケは自分の生える環境を整えるために進化した。茸の進化は動物たちの進化より早い。土の中をのぞいてみると、ヤケアトツムタケの菌糸は、燐の同位体を作るような変化を始めている。同位体とは元素の形の違ったものである。燐はPとあらわす、いくつかある同位体の中で、放射能を持つ同位体が知られている。32Pとよばれる同位体の放射能の半減期は三ヶ月半である。研究に用いられているが、ベータ放射線を放出し、体にはいるとたいへんな被爆被害をもたらす。Pは体には必須の物質である。それだけではなく、骨の中にたくさんとりこまれなかなか外に出ない。もし32Pが骨に取り込まれたら、その放射線は周りの細胞の癌化を引き起こす、死をも覚悟しなければならないほどの障害が起きる。
その32Pをヤケアトツムタケの菌糸がつくりだそうとしている。白燐を作るのは、自分の子孫を残す茸をはやす条件をととのえるためだということで、理解ができないことはない。だが、放射性同位元素を作ろうとしているのはなぜだろう。考えられるのは動物の死体を作り、新たな栄養源の供給と吸収システムを考えているのかもしれない。
これを誰に聞いたかっていうのかい。
最近、探偵やチャンバラものからSFのおもしろさを知って、ちょっと考えてみたんだよ。
放火茸


