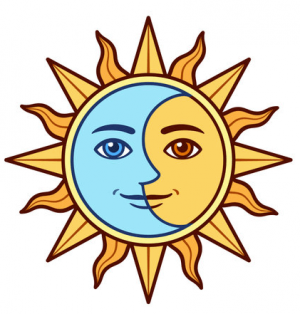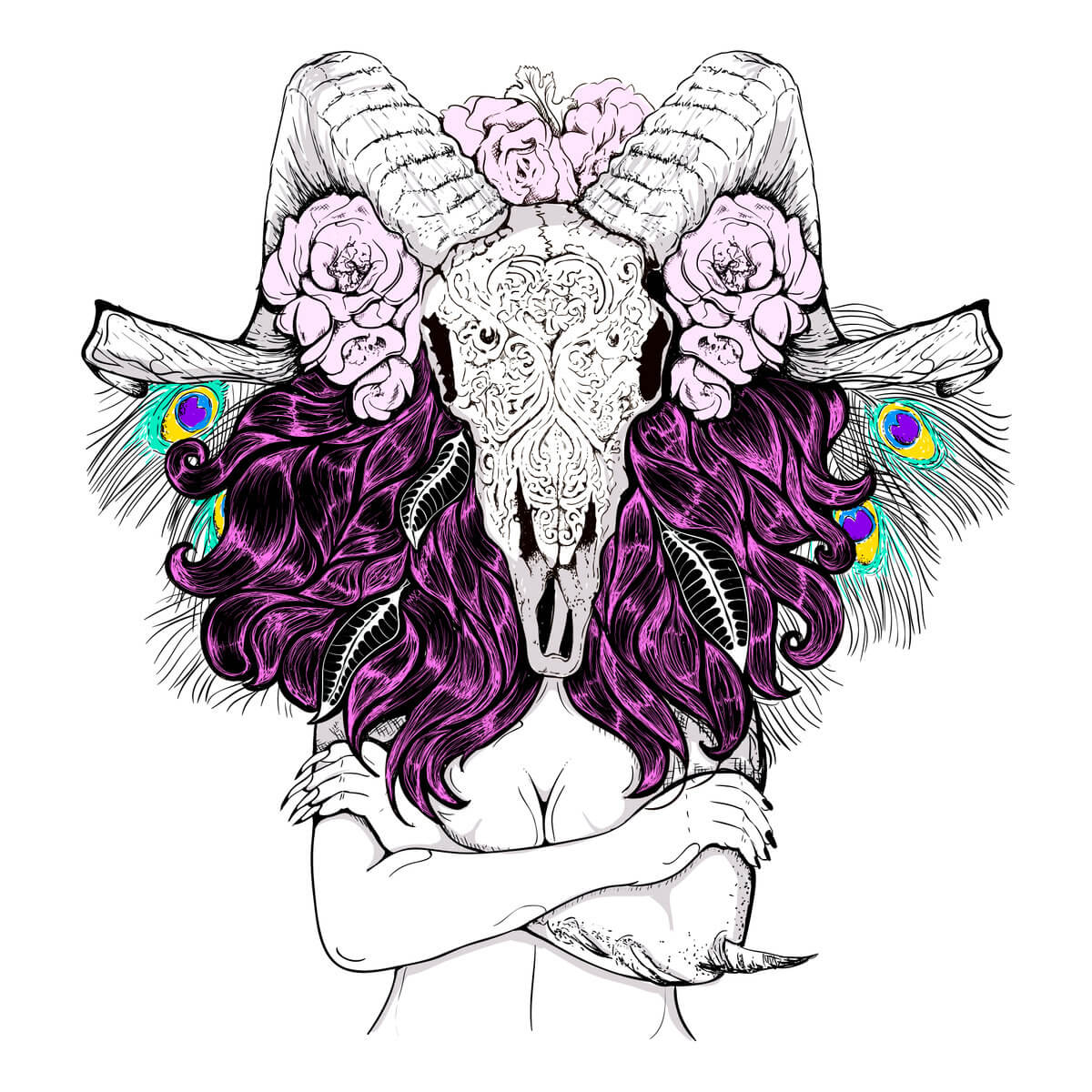
ギニアピッグ
「CVに逃げられたんだって?」
ケイヴィを限りなくケービーに近い発音に訛らせて、ハラヒラヒデフサが馴れ馴れしくタメ口で近寄ってきた。コーヒーが一気に不味くなる。苦い。
「ええ、しくじりました」
俺はあえて敬語で距離感を演出しつつ、正直に状況を述べた。反論しても面倒が増えるだけなので、大人しくしておくが、果たしてあれは自分の責任なんだろうか。トザマのメスがうまくやんなかったか、ごまかして逃がしたかどっちかだろう。そろそろあいつもクビだな。後任を探さないといけない。
今年度のノルマはまだ3人ある。残り1ヶ月を切っている。こっちはもうすでに30人獲られている。同じ数に合わせなければ、犠牲となった彼らに申し訳が立たない。なんとしてもあと3人のトザマを収容しなければならない。
ハラヒラヒデフサは実験部の人間だからお気楽なもんだ。CVが減ったところで仕事のノルマが減って喜びこそすれ、残念がることはありえない。ちょっかい出してくるのは、同期の俺の減点はやつのメリットだからに他ならない。人事査定ではまだ俺の方がリードしているはずだが、今年欠員を出したらどうなるかわからない。さてどうしたものか。
「ま、がんばってよ」
なんて、まったく真実味のない励ましだけをこの場に置いてハラヒラヒデフサはひょこひょこと去っていった。
本部でウダついていても仕方がないので、とりあえず街場に出かけることにした。こうなったら徘徊している野良のトザマをとっ捕まえて収容所に送るしかない。いつもだと厳しいが、ここしばらくは野良を入れていないので、ある程度数も回復していることだろう。ただ、しかし、どうにも3人というのは難しい。1人め、2人めはいいが、3人めともなるとどうしても警戒されて、めっきりトザマの気配がしなくなるのだ。だから一遍にまとめて複数を収容する必要があるのだ。
A原は、狩場としてはだいぶいい。近年はインバウンドも回復して、以前のように外国人が増えてきた。そうなるとドサクサに紛れて異星人もウロツクようになってくる。A原のコンテンツは地球上のみならず、宇宙にも認められているのだ。多くの異星人は、一度はこの街に来たいと思っている。
ゆえに。異星人を対象にしたショップも少なくない。銀河免税店というやつだ。地球はまだ正式には銀河連邦と貿易を行っていないが、民間ベースではそれなりに取引が始まっている。通貨のやりとりにはまだいろいろ不自由はあるが、物品を介して結構な量の経済交流が日々行われ、A原を起点に世界と宇宙は繋がれているのだ。この店、紅葉商店にも地球人に偽装したトザマがちょろちょろとやってくる。不文律があってこの店に手入れを行うことはできないが、出入りするトザマを記録し、動向を調査することまでは規制されていない。
ただし、トザマの中にもいろいろいて、政府高官とつながりがあるのもいるし、武装勢力の構成員となっているやつもいる。そういうのを下手に構うと、地球規模での危機が現実のものとなる可能性が少しあり、できれば避けたい。ちょうどいいのは、私費留学生だ。若いし、騙しやすい。あと高確率で金に困っているので、治験だとか言って時給を提示すればだいたいほいほいとついてくる。
「ちょっといいですか」
「え、なになに」
「ええと、来月の家賃をお支払いするんで、家まで追いかけていいですか?」
「え? キモ」
「そういう番組なんですけど、見たことないですか?」
「ばんぐ、み? ああTVプログラムね。わかるよ。ねえ」
「ああ、わかる。知ってる。なんか家までクルやつ」
「そうですそうです。どうですかね。二人は一緒に住んでいるんですか?」
俺はどこからどうみても美少女で、ペアルックの二人に声をかけた。巻き角を隠すために頭にすっぽりとフードをかぶっているが、俺にはわかる。こいつらはネムール人だ。足元もブーツで偽装しているが、中にはヒヅメがあるし、ふくらはぎにみえるのは実はかかとだ。ネムール人は群れで生活をするのが基本生態ではあるが、経済的な理由でだいたいツーマンセルぐらいで居住・生活している。危険なのは、こいつらが3頭以上いるときに頭数を計上しようとすると、強い催眠効果が発生して、無条件で眠りこけてしまう。しかし二頭であれば理論上は心配はいらない。
「一緒にスンでるよ。家賃高いけどイイの?」
「構いません。人気番組なんで」
実際には支払わないので全然構わないんだが、それは言えない。
「じゃあ、イイよー」
そういうわけで、俺はまんまとカモ2名を捕獲して、自宅に帰り着く前に黒いヴァンに押し込めて、研究所にお持ち帰りした。収容したあとはまったく接点はなく、無事なら生きたまま記憶を消して元の場所に帰すし、無事でないならあとどうなるかは俺は聞いていない。ただ、一つだけ知っているのは、俺たち収容班よりも、解放班の方が少しだけ構成員の人数が少なく、加えて稼働率が低いということだけだ。理由は知らないし、考えたこともない。
さて、どうしたものか。あと一人をどうにか用意しないと、政府が有権者に怒られて、局長が政府に怒られて、上司が局長に怒られて、その翌日に俺が上司に怒られる。年度はじめにそれをやられると1年間ずっと気分が悪いから、どうにかあと一人拾いたい。TVショー形式のピックアップは、どうやらTV局から本庁にクレームがあったらしく、当面禁止となってしまった。鉄板だったのに残念だ。誰か目撃してPoritterあたりに投稿したんだろう。めんどくさい。
いよいよ年度末になった。あと十六時間以内に今年最後の一人を捕まえてこないといけない。
「いよう。まだ足りてないんだって? 大丈夫なの」
このタイミングでいちばん見たくない顔が現れた。だがやむをえない。
「そうなんだ。もう間に合わないとは思う」
「諦めてるのか? 今までなんだかんだで足りてきただろうに」
「そうなんだが、毎回、もう無理だろうなって思っているよ」
「諦めが早いというか、いさぎいいというか」
ハラヒラヒデフサはいつものニヤケ顔をしてきたので、俺はいつものコーヒーを渡してやった。
「珍しいな、お前がおごってくれるなんて」
「そうでもない」
ハラヒラヒデフサはふうふう冷ましながら俺の淹れたコーヒーを飲み、いつものようにその場に倒れ込んだ。俺はいつものように担ぎ上げて、いつものように回収車のトランクに押し込んで、いつものように第三埠頭へ向かった。
埠頭では先に、ユスファが待っていた。
「毎年すまんな」
「こちらは構わないよ。多い分にはまったく問題ない」
こちらもノルマに足りていればそれで問題はない。お互いウィン・ウィンの関係というわけだ。ユスファのトランクには眠らされているネムール人が眠っていた。一頭だけならなんの脅威でもない。
「同居していた一族のが戻らないってうるさいから、そっちに送ることにした」
「ああ、先週ひっぱったやつらかな。一緒になるとちょっと厄介だが、まあ構わん」
「んー、そっちのはまたこいつ?」
「すまんね。いっつもちゃんと戻ってきちゃうんだよ」
「まあ我々は実験の内容は知らんし、仕方ないな。じゃあもらってくよ」
「ありがとう。いつも悪いね」
ユスファはそこはお互い様だろと笑って、ハラヒラヒデフサを担いで、俺が引き取ったネムール人の代わりにクルマに押し込んで、走り去った。俺は日没までに追加のネムール人を収容所送りにして、どうにか今年度のノルマを達成した。
「CVに逃げられたんですか?」
ケイヴィをケイヴィと発音する新人実験部員が俺に聞いてきた。
「ああ、しくじってしまったんだ」
「CVって逃げることもあるんですね。実験室でも気をつけないと」
俺はそうだな、と言って、かつてそこにあった顔を思い出そうとしたが、思い出すとコーヒーがまずくなると思ったので、ペンを見て忘れた。コーヒーは酸味が効いていて美味かった。
ギニアピッグ