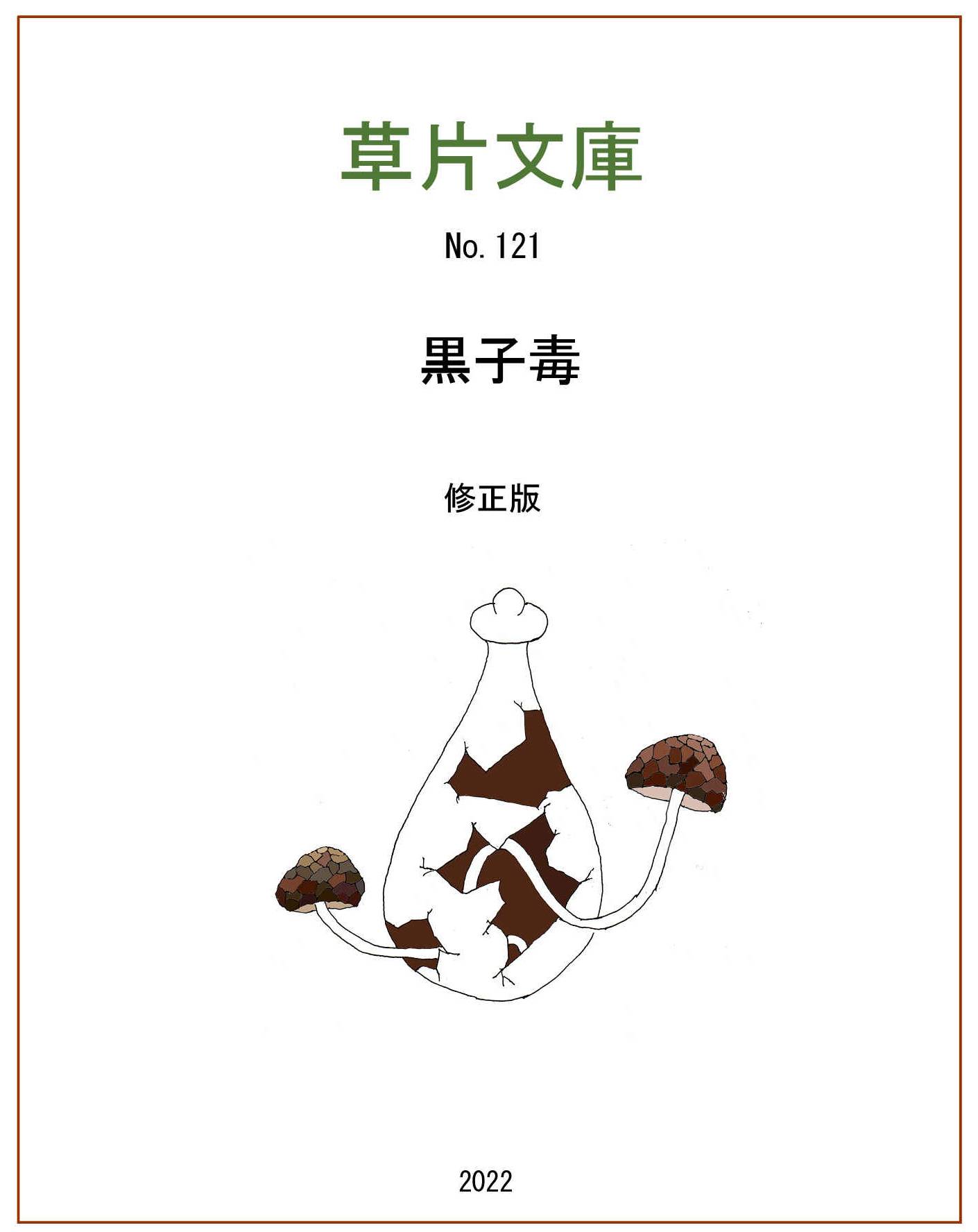
黒子毒
探偵小説です
この話は、昭和35年、東京下町の谷中で起きたできごとである。
高度成長期の始まりの日本、国民はだれしもエコノミックアニマルといわれるほど、会社につくし、懸命に働いていた。それにより個人も潤い、消費が増え、日本中どんちゃん騒ぎである。昔ながらの、日本のものを作る職人たちも、それなりの恩恵にあずかっていたが、中には眉をひそめる人間もかなりいたはずである。
三代目の提灯屋を営む、和久井五郎は、神社、寺院からだけではなく、飲み屋や演芸場から、さばききれないほどの提灯の注文をうけていた。五郎の作る提灯は、丈夫で、火の保ちがいいと評判だった。ちょっと揺らしたくらいでは消えない。
そのころ、蝋燭の提灯がまださかんに作られていたのである。もっとも、居酒屋や盆踊りの櫓につるす提灯には電球をいれていた。火事の心配をしたからだ。
五郎の父親は、五郎が高校をでて鉄道会社に勤めはじめて三年後に、脳溢血で死んでしまった。母親が何とか家業を継いでいたが、その母親が自動車事故で入院したことをきっかけに、五郎は家業を継ぐことにした。やがて嫁もきて、和久井提灯屋はまた昔のにぎわいを取り戻したのである。色の白い五郎は、顔ばかりでなく、体中に黒子(ほくろ)があり、黒子の五郎と呼ばれ、商店街の顔役となり、先頭に立ってそのあたりの祭りをしきっていた。
五郎が四十二になったときである。夏のある日、提灯張りをしていると、いきなり体がしびれ、意識を失い、病院に運ばれた。母親は父親と同じ脳梗塞ではと気が気でなかったのだが、そうではなく、心臓の急激な縮動のためであることがわかり、命は取り留めた。それが、昭和35年のことだった。
しかし、その原因がわからず、血液検査でも特におかしなところもなく、体そのものに異常はみつからなかった。
体調が回復した五郎は退院し、また提灯づくりにもどった。
そのようなことがあってずいぶんたってからのことである。五郎が入院した病院の医師である、旗井幸希が店までたずねてきた。そして、いきなりこんなことを言った。
「突然来て申し訳ありませんが、半年前に入院されたときの、和久井さんの血液の中に毒をみつけまして、うかがったわけです」
旗井は名刺を五郎に渡した。毒物学の医学博士である。
和久井五郎は驚きをかくせなかった。
「あっしが、毒をもられたんで」
「いえ、何かの不注意で口に入った可能性もありますし」
「人に恨まれるようなことはしていませんがね」
五郎は人に好かれることはあっても、いやがられたことは一度もない。
それにしても、半年もたって、なぜこの医師は直接やってきたのだろう。不思議に思うのは当然のこと、五郎は医師に尋ねた。
「入院したときの血液検査では全くおかしいなとこ、ないといわれたが、なんででしょうな」
「いや、電話もせずに突然きて失礼しましたが、電話をすると、不安をあおらせてしまいますので、いきなりきました、私は植物毒の研究をしていまして、原因がわからず中毒症状などを起こした人の保存されていた血液をしらべております、研究の一環でもありますが、何件か毒を検出して、ご本人が事件に巻き込まれていたことを明らかにしたこともあります。和久井さんからどうして、毒物が出たか、一応、明らかにしておきたいと思い、たずねたわけです」
「あ、そりゃあ、ご苦労さまで、おかげで、あれから悪くなることはありませんで」
「それはよかったです、検出されたのは、植物に含まれる毒でした」
「そりゃあなんで」
「鳥兜という草は知っていますか」
「名前は知ってるが、見たことないね」
「その毒が微量ですが和久井さんの血液から検出されました」
「そりゃどういったこってしょうな」
「昔から人殺しに使われたりしますが、薬にもなります、頭から足先まで毒を持っている草です」
「そりゃどういうこってす」
「いや、花、はっぱ、茎、根っこすべてに毒があります」
「そりゃおそろしいね」
「偶然、取り込んでしまうということもあります、家の周りには生えていないですね」
「くわしくはみてねえけど」
「ちょっと周りをみせていただきます」
旗井は、外に出ると、狭い露地はいりこんで、見てまわった。どの家も小さいながら庭があり、草花を植えていた。通りに面した店の入り口脇には、植木鉢に何らかの草が植えられていた。五郎もついていった。
「まわりにはなさそうですね」
「というこたあ、誰かにもられたってわけですかい」
「まあ、いまどきそんなことあるわけはないとは思うんですが、ともかく、アコニチンという毒が和久井さんの血液からみつかったんです、それが鳥兜のもっている毒でしてね、昔は痛み止めの薬などにも使われたものです」
「なんですかい、そいつは」
「アルカロイドといいまして、主に植物で作られます、キノコの毒、阿片のモルヒネなどもアルカロイドという仲間で、動物のからだではつくられない、蛙などで、あいてをやっつける毒としてつくるやつがいますけど」
「ふーん、いやそんなもの食った記憶がないけどね」
「いや、今お元気そうだから、大丈夫でしょう、急におじゃましてすみません、何かあったら連絡ください」
旗井は帰っていった。
おかみさんが出てきて、「誰」と聞いた。
「ああ、病院の先生だ、ほら」
もらった名刺をみせた。
「なんか心配だったんかね」
「毒がはいっておったんじゃと」
「なんに」
「俺の血」
「そりゃ、毒だらけだろ」
と言って、かみさんはけろけろけろと笑った。
その夕方、五郎は急に食べたものをはき、胃の痛みで病院にいった。
医者は食中毒の症状だからと、胃の洗浄をしたのだが、胃の痛みはなかなかおさまらず、吐き気もとまらなかった。
「胃の状態は悪そうではないんですけどね、夕方には血液検査の結果がでるから、なにかわかるでしょう」
その当時は、血液検査に時間がかかった。今は大病院なら、一時間で血液の成分の数値がでてくる。特殊な物質は別にして、一日もあれば物質が特定される。
その結果は、やはり食中毒であった。エンテロトキシンという、食中毒の菌が出す毒がはいっていた。
医者は「おかしいな、毒素だけで、便にも食中毒の菌はいないんだな」
なんでも、ブドウ状球菌とやらが犯人のようだが、そいつがいないのに毒があるということらしい。
和久井は胃の調子が戻ってきたことを感じて、いつ頃退院できるか医者に聞いた。
「うーん、胃の痛みと吐き気がなくなり、血液検査でオーケーとなったらいいでしょう、明日か明後日ですね」
医者はそう言った。
その夕方、主治医と一緒に、旗井幸希が病室に入ってきた。
「和久井さん、こんどは、エントロトキシンの一つが血液にみつかりましたね、前の毒とは違って、ペプチドといって、まあ蛋白の小さい奴です、それが毒素です」
「悪りいものを食った覚えはねえんですよ」
「そうらしいですね」
「血液の中の、エントロキシンはだいぶ少なくなっているので、明日あたりは退院できるでしょう」
「そうですか、俺も飯がうまくなってきたから大丈夫だと思ってました」
「退院したら手をよく洗って、うがいしてくださいね、食べ物ばかりじゃなくて、触ったものからばい菌がついて、それが口にはいったかもしれませんから」
主治医がそう言った。
ともかく、和久井は無事に家に戻ることができた。
それから一週間たった日曜日、また異変がおきた。
和久井は食事中、食べている物の味がおかしくなり、体に力が入らなくなって、その場にくずれおちた。
おかみさんが、あんたどうしたのと、救急車を呼び、ふたたび病院に入ったのである。
「腹も痛い」とうめいていた。
またも血液検査が行われ、点滴の針が腕に差し込まれた。今度も、毒物の専門家である旗井先生がやってきた。
「今度はどうしたんでしょうね、奥さん、薬缶や鍋はどのような物を使っています」
何でそんなことを聞くのだろうと思いながら、おかみさんは、
「アルマイトですよ」と答えた。
「うーん、匙なんかはどんな」
「え、匙?、匙はステンレスのですよ、どうしてかねえ」
「ご主人釣りはしませんか」
「ああ、しますよ、たまには」
「釣りのおもりにどんなのを使ってますか」
「そんなことあたしは知りませんが、もってきましょうか」
「いや、ご主人が元気になったら聞きます」
「何かおかしなことがあったので」
「血の中に鉛がたくさんありましてね、前に採った血液の残りを調べたのですが、鉛などなかったので、急に体に入ったようなのですよ、鉛は毒でね、昔、水道管につかわれたことがあって、その水を飲んでいた住人がおかしくなって、鉛管は使用禁止になったんですよ」
「だけど、とうちゃん、最近釣りにも行ってないし、そんなもん口にしちゃいないと思いますけどね」
「そうですか、まあ、急性の鉛中毒というのも珍しいんですよ」
次の日、和久井五郎は元気になった。
「鉛なんて口にしちゃあいねえな、釣りの鉛は物置においてあるけど、こんとこつかってないね」
「薬でからだから出すことができますから心配ないですけどね、ひどくなると脳にたまって、死んでしまいますから」
「またしばらく入院かね」
「そうですね、ちょっと不思議なので、警察の方にも、連絡しましたよ」
「どうして、警察なんかに」
「血液の中の鉛の量がこんなに多くなるのは、誰かが直接血液の中にいれないとならないでしょうから」
「そんなことするやついないねえ」
「そうは思いますよ、今回で三回目ですね、毒で入院するのは、本当に、恨まれたりしていないでしょうね」
「ぜったいねえな」
「まあ、退院したら、よく気をつけてくださいよ」
その後まもなく、和久井は退院した。
「私も気をつけるけどさ、あんたも気をつけてよ、なんだか気味悪いねえ、毒盛られているみたいでさ」
「うーん、おめえもわかってるだろ、誰も毒を入れようってのはいねえし、そんな機会だってなかったろ」
「そうだよね」
そんなことで、三日ほどは何事もなく過ぎて、提灯を作っていた。
ところが、四日目の朝、和久井五郎は床の中で死んでいた。
病院に運ばれて、体をくまなく調べられた。驚いたことに、血液の中に、アコチニン、ブドウ球菌の毒、鉛、それに加えて、ふぐ毒のテトロドトキシンがかなりの量ふくまれていた。
毒物の専門家である旗井幸希の所見である。
死因は四つの毒物による急性中毒死である。注射された跡や、無理矢理口に入れられたような様子はみられない、原因を調べるべく、病理解剖に付したところ、内蔵などに病変はたくさんあったが、毒物の影響と一致するものであった。
細胞レベルの検査を行ったところ、アコチニン、ブドウ球菌毒、鉛、テトロドトキシンが、腎臓や肝臓などの細胞にたくさん検出された。それにもまして、不思議なことに皮膚に多かった。この男性は色が白く、黒子(ほくろ)が多く見られる。皮膚の中でも黒子の中にその毒物が多く検出された。これは特筆すべきことである。
黒子の細胞を顕微鏡検査したところ、黒い顆粒のメラニンを作る細胞の半数ほどに、特殊な細胞内小器官がみられた。
細胞内小器官とは、細胞の中で細胞核以外の、細胞が生きるのに必要なことをしているいくつかの構造で、核よりかなり小さなものである。
普通の細胞の大きさは10ミクロンメーターほどである。1ミクロンは1ミリの千分の1だから、百分の1ミリの大きさしかない。その中にある小器官だから、もっともっと小さい。小器官にいろいろな働きを持つ化学的物質が存在している。そこに、普通の人にはない小器官がみられたが、何をしているのか全くわからない。
黒い色のメラニンは色素細胞の中にあり、皮膚を紫外線から守る大事な役割をもっている。一方黒子はメラニン色素細胞が異常増殖をしたもので真っ黒に見えるが、役割といったものはない。皮膚にとって必要なものではなく、異常なもので、医学的には良性の腫瘍ということになる。
ということで、黒子は目的があってからだで作られるものではない。せいぜい顔のチャームポイントになりうるぐらいだろう。
黒子はときとして皮膚ガンになることがある。その場合、大きく不規則な形をしていて、黒子のように丸に近い形ではない。それをメラノーマ(悪性黒色腫)という。これは白人に多い。日光に当たりすぎると生じることもあるが、光に当たらなくてもできるものもある。特に日本人のメラノーマはそちらだそうである。
ここまで細かなことを書いたのは、黒子ができる体質は、メラニンを作る細胞に異常が起きやすい可能性があるということを考える必要があるからである
旗井の所見は、黒子の細胞が毒を作ったのではないかということを示唆するものであった。
警視庁には、捜査に科学的な協力をする部署、捜査支援分析センターがある。その分室、第八研究室には、得意分野を持った個性豊かな分析官が働いている。分室室長は薩摩冬児警視正、それに四人の分析官がいる。誰もが得意分野をもち、個性豊かな面々である。
その中の一人、吉都希紅子はちょっと古い報告書を眼に留め、昨日からそれを読み解いていた。
「室長、バブルのころの医者の報告書に、黒子の毒のことがありますけど、なんだか気になります」
自分のデスクでふんぞり返って本を読んでいた薩摩はそれを聞いて、
「なんだい、それで、そいつを調べたいわけか、クッキーの顔の黒子がきになるんだな」
希紅子は色白で、顔に目立つ黒子がある。冬児に言われて、大きめの口をあけはははと笑って、
「まさか、あたしの黒子はおとなしいですから、室長、それで、黒子の毒を調べた病院が今も発展して、大きな病院になっているんです、いってみたいんですが」
「いいよ、調べ問いで、何ならこちらから連絡入れとくよ」
「はーい」
そのまま、希紅子は第八研究室を飛び出した。
1960年代の話だから、それから六十年経っている。旗井幸希博士がその当時三十でも九十のご高齢となる。
希紅子が病院に行くと、すでに薩摩のほうから電話がいっており、事務長がでてきて、丁寧に対応してくれた。
旗井博士は二十年ほど前に退職していたが、まだご存命であった。息子が都内に自宅を兼ねた医院を開業しており、そこに住んでいるということだった。
病院から連絡をしてもらい、会うことの合意をとり、話を聞く手はずをととのえた。
その日、旗井病院のある世田谷に希紅子は向かった。電車から降り、スマホの地図を頼りに歩いていくと、かなり広い敷地に、大きなコンクリートづくりの三階建ての建物が見えてきた。旗井神経クリニック、看板には、神経内科、神経外科、眼科(めまい)とある。院長名は旗井乾一とあった。旗井幸希の息子だろう。
受付に、警察から来たことを言うと、
「刑事さんですね、院長がお待ちしています、ご案内します」と受付の女性が、吉都を三階の院長室に案内してくれた。
部屋にはいると、デスクで書き物をしていた様子の、長面の白衣の紳士が立ち上がった。
「警視庁の吉都希紅子です」
と挨拶をすると、
「どうも、旗井です、父と話される前に、ご質問の内容を簡単に教えてください、父は自宅の方におりますが、九十をすぎてから耳が少し遠いもので、どうぞお座りください」
なかなかの紳士だ。ソファーを勧めてくれた。
「すみません、お忙しいところを、昭和35年に旗井幸希先生が、警視庁の方に情報をお寄せになった、患者の死の原因のファイルが出てきました、大変奇妙な事件のようですので、後学のために、少しお聞きしたいことがあり、お訪ねしました」
「どのような患者だったのでしょうか」
「アコニチン、エンテロキシン、亜鉛、テトロドトキシンの毒物により死亡した患者で、黒子にそれらが多く検出され、黒子を作る細胞の異常を旗井先生が調べたものでした」
「ああ、私が生まれてちょっとたった頃の患者さんですね、私が大きくなり医者になってから、父が話してくれたことがあります、私は脳外科医でしたので、強い興味は持たなかった記憶はあります、そのころ、父は自分の研究テーマとして、大学の毒物学の研究室にまだかよっていました。
父は今は足腰が年相応に弱っていますが、頭はしっかりしています、警視庁の方がくることは話してあります、なんだろうと言っていました、住居の方に案内させます、私の家内に一緒に行かせます、そのほうが話がしやすいでしょう、ちょっとおまちください」
旗井乾一はデスクに戻ると、電話をとって、案内する女性を呼んだ。
「家内には電話しときます、また同じような患者でもでたのですか」
「いえ、特殊な事件の分析室の勉強会で、将来のために、そういう事例をしっかり、調べておこうということになったものですから」
「警視庁にもそういうところがあるのですね」
そう言いながら、希紅子の名刺を見直した。
「おや化学の博士さんですか」
「ええ、有機化学のほうをやりました」
そこに、秘書らしき女性が入ってきた。
「先生、なんでしょう」
「警視庁の、吉都博士だ、父のほうに案内してくれないか、すでに伝えてある」
「はい、どうぞこちらです」
希紅子は院長にお礼を言って、その女性とともに病院の裏の住まいに行った。
秘書が「どうぞ」と玄関を開けると、女性がまっていた。
「どうぞ、どうぞ、あ、女性の方だったのですね、父が待ちかねています、話好きで、でも耳が悪いので、わからないところは私が伝えます」
「おじゃまします」
院長の奥さんだろう。看護婦さんでもしていたのだろうか、物腰が柔らかい。
希紅子が応接室にいくと、色の白い老人が、ソファーに腰掛けてまっていた。
「警視庁の吉都希紅子です、お話を聞かせていただくことになり、お礼申し上げます」
ここでも名刺をだした。院長の奥さんがうけとって、旗井幸希にわたした。
渡井幸希は丸い小さな顔をしわくちゃにして、
「そんな、堅いことどうでもいいんで、座ってよ、嬢ちゃん」
と笑顔になった。そのものの言いように、希紅子も思わず笑い顔になった。
「おとうさん、警視庁のかたですよ、じょうちゃんなんて」
希紅子はとうとういつものように大きな口をあけて笑った。幸希の前に座ると、
幸希は希紅子の笑い顔を見てつられて笑った。
「警視庁もかわったなもんだな、それで、和久井さんのことだそうですな」
幸希のほうから、和久井五郎の名前をだした。
希紅子は、警視庁で見たファイルのことを話した。
「ほう、それで、まだ同じことが起きたのじゃないのに、調べようということですな、医学の連中がそのくらいの知恵があればいいんですがな、全く興味を持ってくれなかったわい」
旗井幸希の声はとても若い。回りにしわこそたくさん寄っているが、目の輝きがまるで少年のようだ。
「旗井先生からみて、どんな事件だったのでしょうか」
「進化の証をみつけた事件でしたな」
ずいぶん飛んだ大きな言いようだ。希紅子には幸希の言ったことが理解できない。
「メラノーマというのはわかりますかな」
希紅子はうなずいた。黒子のガンだ。
「色素細胞の元の細胞は色素顆粒をつくるためでしょうな、ガン化しやすい、ホルモンをしっていますでしょう、ホルモンを分泌する内分泌器官というのは、ガンができやすい、女性のホルモンをだす卵巣などがそうじゃ、それはホルモンを作る遺伝子がいつも働いていて、エラーがおきやすいからなわけですな、むずかしいですかな」
「おとうさん、この方は化学博士ですから、大丈夫でしょう」
「あ、そんなにはわかりませんが、少しなら」
「色素顆粒を作る細胞もガン化しやすいわけですな、遺伝子がおかしくなりやすいといったらいいわけです、遺伝子が変化していくのが進化で、遺伝子の異常は進化のきっかけというわけですわ」
希紅子にもわかった。
「和久井さんはな、黒子に毒を作る細胞が生まれてしまったと、わしは思っています、学会で話そうと思っても、周りの医者どもが、そんなことはありえない、やめろと、と論文にもできませんでした、警視庁のほうがすすんどる」
「あの、黒子の細胞にあった、特殊な細胞内小器官ですか」
「おお、よくわかってくれましたな、そうなんだ、あれは、毒を分泌することのできる器官でな、ある意味では毒を分泌するガンといっていいわけでしてな、ご存じかな、乳ガンなどが女性のホルモンを作るようになったりする」
それは聞いたことがある。うなずいた。
「ほ乳類が毒を分泌するということはないが、進化の過程でもっと早くにそういうことが起きていたら、毒を分泌するほ乳類が出現していたかもしれないんですよ」
「とてもおもしろい解析で、すばらしいご研究だと思います」
「昔のそれに関する研究資料がありますから、みなさしあげましょう、電子顕微鏡でとった細胞の写真もあります、もし、こういうことを研究する人が現れたら、わたしてほしいですな」
「え、あ、はい、ありがとうございます、拝見させていただきたいと思います。生物学の人も知っていますので、話をきいてみます」
希紅子の旦那は、生物学の大学院をでている。今は探偵業である。
「そう、それがいい、生物学なら、基礎的なことを、しっかり解析できると思いますな、医者は患者を治すのが役割ですからな」
なるほど、と希紅子は思った。
「これからも、そういった患者さんがでる可能性があるでしょうか」
「あるでしょうな、今までもあったのだと思いますよ、心臓が弱っている年寄りに、黒子毒がちょっとでもでたら、命をおとすかもしれんでしょう、だけど、心臓病でかたづけられるだろうね」
希紅子はうなずいた。ある病でなくなったと判断されていても、本当の原因は違うこともかなりあるかもしれない。
「ちょっとまっていてくださいよ」
幸希が立ち上がった。
「どこにいくんです」
院長の奥さんも立ち上がった。
「部屋から、その資料をもってくる」
「手伝いますね、ちょっとお待ちくださいね」
しばらくすると、幸希と紙袋をつるした奥さんがもどってきた。
幸希はソファーに腰掛けると、袋を希紅子に渡した。
「これがあのときの資料ですよ、もっていってください」
「はい、電子化したら、お返しします」
「まあ、返してもらってもしょうがないが、そちらもいらなくなったら、もどしてもらいましょうか」
「ありがとうございました」
「役に立てばうれしいことですわ、わしももう九十をすぎて、まさか、この事件が面に出てくるとは思いませんでしたからな」
さらに、幸希はまじめな顔になり、こんなことをいった。
「どうして、あの提灯屋の和久井さんの黒子が毒を作るようになったか、本当に偶然なのか、それとも、提灯を作る時のなにかがそうさせたのか、わからくてね、動物の色素細胞をいろいろな刺激をして、ガン化を試みたのだけど、皮膚ガンにはなったけど、毒はつくらなかった。じつはな、吉都さん、それに美代子さん」
院長さんの奥さんは美代子さんというようだ。
「遺言書を弁護士に預けてあるが、それは知ってますな、書いてある資産のことは、一般とかわりがないのですがな、一つ、息子にもあなたにもいっていませんがな、わしが死んだら、わしの体を調べてもらいたいということが書いてある。皮膚のすべての黒子を遺伝子解析にかけてもらいたいとあるからよろしく」
「まあ、何でしょう、私にはわからないけど」
「息子はわかるだろう、吉都さん、ちょっとこれを見てくれますかな」
幸希老人は腕をまくった。腕に大きな黒子があった。右手の人差し指もつきだした。指先より一センチ五ミリほどのところに、米粒ほどの茶色の黒子があった。
「特に指先の黒子なんだが、提灯張りがやるように、たけひごを毎日しごいてみたんですわ、提灯張りは竹ひごに糊を塗り、紙を貼る。糊をしらべたのですが、つかっているのはでんぷんのり、これは関係ないと思いましてな、たけひごをしごいて、形を整えたり、紙を貼ったり、指に物理的な刺激が毎日続くわけで、もしやとおもって、同じことをしてみたわけですわ、そうしたら十年たって、指先に茶色の点ができましてな、老人だから、しみもできますが、指先などにはほとんどできない。と、しばらくすると、腕の方にも黒子が現れた、明らかに真っ黒な黒子です。これはきっとなにかあると思いましてな、わしが死んだら皮膚の黒子すべてを遺伝子検査して、比較してほしい、それが遺言に書いてありますのでな、もしかすると、なにかつくっているかもしれないからな、しかしなにもでないかもしれない、まあ、無駄かもしれんが、やってもらいたいということです」
と笑った。希紅子はなんと答えていいかわからなかったが、やっと、
「先生は、お医者さんと同時に、究極の研究者ですね、尊敬します」
「いや、警察の人にそんなに言われるとは思いませんでしたな、よろしくたのみますよ」
院長夫人も、真面目な顔でうなずいた。
「お父さんのおっしゃったこと、主人にも伝えます」
そんなことで、希紅子は資料をもって、警視庁の第八研究室に戻った。
室長の薩摩に、旗井幸希に言われたことを伝え、長男の奥さんが、もしそういうことになったら、結果は主人の方から、警視庁の方に連絡しますと言ったことも言い添えた。
「えらいひとだね、ガン化した黒子の細胞が毒を作り出すようになった結果の事件か、もし本当だったら、どこかで起きているだろうね」
「そう思います」
それから二年、旗井幸希が満九十三歳で、臓器不全でなくなった。老衰のようなものと、希紅子は考えたが、臓器不全とは多くの臓器全体の機能が低下し、特に心臓、腎臓、肝臓の協調が悪くなることのようで、やはり老化も一つのようだが、それだけではないようだ。
幸希の息子、旗井乾一が、第八研究室に報告書を送ってきた。
それによると、血液の中にわずかだが、アコニチンが検出されたとあった。さらに、遺言通り、皮膚の細胞の遺伝子の検査を専門家に依頼したところ、皮膚に広がるメラニン細胞には異常は認められなかったが、黒子を構成していた細胞には、アコニチンが多く存在し、ガンとまでは言えないが、異常があり、細胞内小器官の奇形がみられた。それが、アコニチンを形成しているとまでは証明できていないとする結果だと言うことだった。
「室長、人間の体の中でも、植物などにある毒物を作る機能が芽生えているのではないかと思うんですけ」
「うーん、否定できないね、今後、毒物中毒や、毒物殺人事件があったときには、そういうことを頭に置いておく必要はあるだろうね」
「黒子で毒が作られたらどうなるかしら」
「そんなうわさがSNSにながれてみろよ、黒子のあるやつは、みんなからのけ者にされる、おもてにはだすなよ」
「そうですね、でも、前もってそういう毒の毒消しを作っておくのも大事ですね」
「おお、いいこというね、キックーも少し大人になったな」
キックーと呼ばれている吉都希紅子は第八研究室の中で一番若い。
こうして、毒で死んだ提灯屋のファイルは閉じられた。しかし、紀紅子は探偵であり、生命科学を学んだ亭主の、吉都可也にそのことを話した。
黒子の毒について、可也の出身大学の教授が研究をすすめることになったということである。
黒子毒


