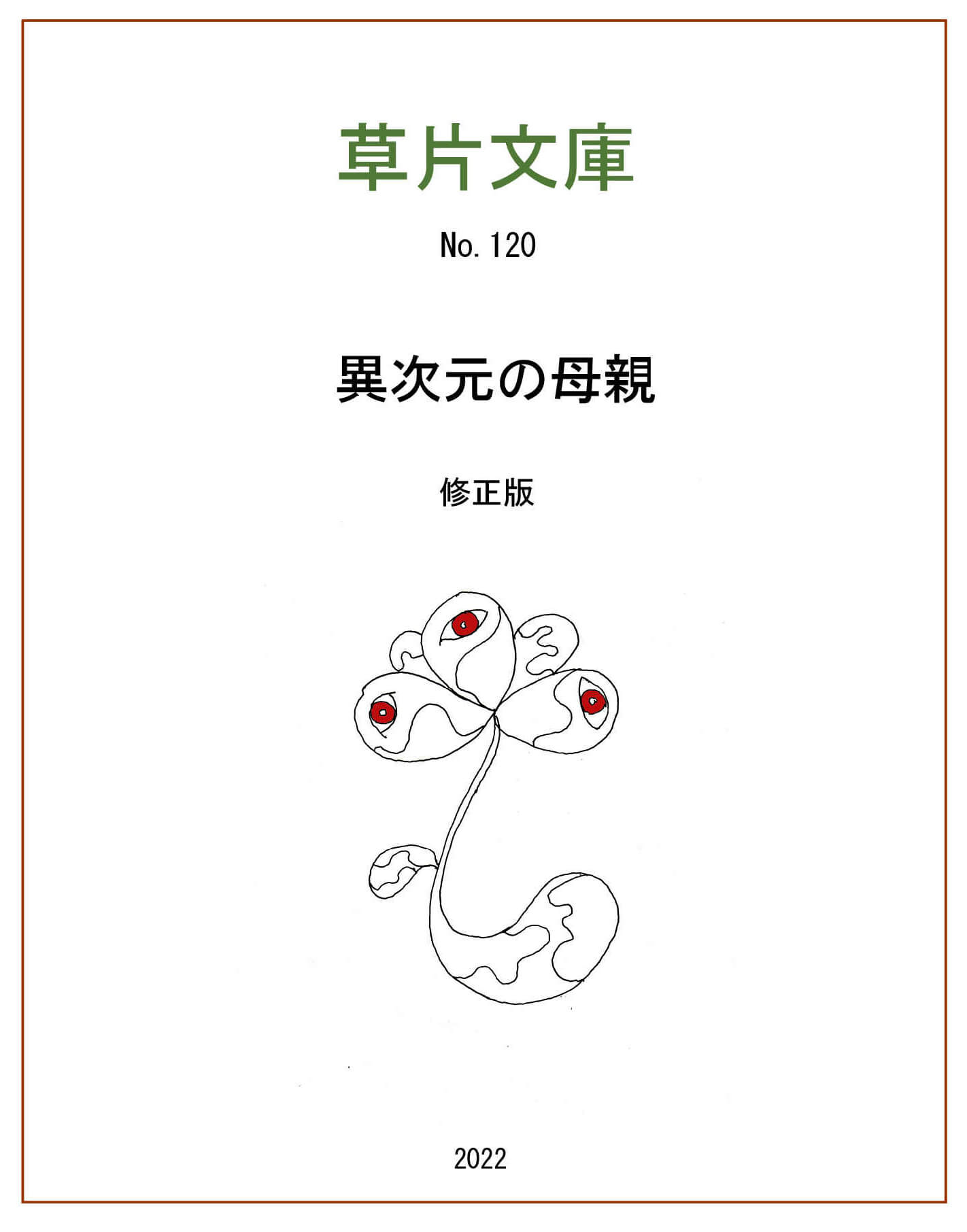
異次元の母親
SF掌編です。
私は産む。自分の母親を。この母親は私でもあり、妹でもある。だけど母親である。異次元の妹は、あっと言う間に大きくなり、私に乳を与え、私を育てる。
こんなことを書いても、だれも私の言っていることがわからないに違いない。
私自身もこんがらがっているのだ。肉体とは何かという、もうわかっているはずの疑問が頭の中に渦巻いているからだ。生きて子供を産むために身体や脳はできている。だが、今私が感じているのは、身体や脳はそのための装置ではないという疑問である。
ではなにか。
私の子宮は次元、時空を旅するための装置だ。HGウエルズがタイムマシーンといったものと、働きは重なるところがある。時限もまたぐが次元にまたがる乗り物で、構造は違う。もともと、人間の体の中にそなわっているものだったのだ。人間の女は誰もまだそれに気がついていない。いや、マリアという人は知っていたのかもしれない。
私がなぜそれに気づいたかというと、私に妊娠する理由もないのに、子宮の粘膜にポリープのような小さな膨らみができていることが、エコーでわかったからだ。
私は医者だ。しかも産婦人科医、何人もの妊婦の診察をし、出産に立ち会った。あまりの忙しさに、自分はこの年になるまで異性をしらない。だけど、血液の中のホルモンは妊娠を告知し、私は自分の手でエコーの機械を操作した。
子宮のポリープのような突起は、生きていた。新たな子供のようでもあるのだが、妊婦でいつも見る画像は違っていた。懐胎したときに見られる画像とは違う。卵と精子が合一して作られたたものではない。
自分の腹に機械を当て、コンピューターの画像を見ていると、むくむくとそいつは大きくなって、もう二ヶ月ほどの子宮になっている。
このころになれば臓器の原型がほとんどできあがる。画像だけをみていると、頭しかない。胴体も手足もない。頭も骨の組織がなく、うっすらとしか映らないが、脳だけのようだ。しかも、その脳は心臓のように鼓動をきざんでいる。子宮は胎盤を形成しているようだ。胎盤は母親の子宮の粘膜と、子供の組織から作られる。ところが私の子宮の中の胎盤は私の組織だけで、そこに胎児である脳から延びた四本の動静脈が胎盤に入り込んでいる。脳が私の子宮から直接酸素や栄養を取り込んでいる。ふつうの胎盤なら、子供の組織から、妊娠維持のホルモンがでて、母親の妊娠を維持させるはずであるが、それがでていないようだ。
脳だけの胎児。
なにを意味するのであろう。
私は正気に帰り、機械を止め、下着をつけた。
あと十分、午後の診察が始まる。
多忙な診察が終わったのは夜七時である。妊婦は誰もが期待に胸を躍らせ、ここに来ることで、たまっていた不安が八分目解消され、また不安がたまると、診察にくる。やがて、その不安もなくなり、医師などいなくても、一人でも子供が産めるようになる。もっとも今の都会の女性はそこまで成長できていない。最後まで産婦人科医や取り上げばばあによりかかっている。地球上で産婦人科医などがいないところでは、せいぜい母親をたよるだけだろう。
夜の診察が終わった私は、また下着をとって、診察台に横になると、エコーの装置を腹にあてた。
腹がだいぶ膨らみ、中を覗くと、もう大人の脳の大きさになった胎児が動いている。脳がどきどきと音を立てるように、拍動をうっている。私の腹のでかたからいくと、5ヶ月ほどであろうか。
脳の形が人間のものではないようだ。しわは同じように寄ってはいる。全体の形もよく似ている。しかし大脳も小脳もない、ただのしわの寄った固まりである。すべてしわのようだ。しかもそのしわは小脳のように細かなものである。脳のしわは表面積を広げるために進化したものだという。そこに神経細胞が並んでいる。だから広い方がたくさんの神経細胞を擁すことができ、複雑な機能をはたすことができる。人間の思考はそこから生まれる。
私の子宮の中の脳は、もし広げたらどうなるのだろう。どのくらいの広さになるのだろう。
次の朝、診察の前にまた、自分の腹にエコーをかけてみた。体型は八ヶ月くらいになっている。
胎盤の上に大きく膨らんでのっかった子宮にエコーをかけても、一部しか映らない。やっぱりおもったとおり、全部脳だ。お腹いっぱいに膨れた脳である。
起きたとき体重計にのったら、四キロも増えていた。脳の重さは1200から1300グラム、増えた分すべてが脳だとすると、少なくとも三千五百グラムほどだろう。
お腹がときときしているのを感じる。手を当ててみると、時々脳が動いている。この脳が生まれ成熟したら、世界中のスーパーコンピューターいくつ分のは働きをもつのだろう。
診察をしていたら、妊婦の一人が、先生ちょっとお太りになられましたか。と笑顔で言った。きっと私のお腹と同じくらいになりましたわねと言いたかったのだろう。
そうね、忙しいもので、暴飲暴食よ、と笑い返したのだが、妊婦は悪いことを言ったかと思ったのか、ごめんなさい、とあやまった。いいのよ、私は元気、あなたも元気にいい子供を産むのよ、と言い聞かせると、また明るい顔になった。
五十少し前になった私が妊娠しているとは誰もが思わないだろう。
妊娠すると浮かない顔をする女性もたまにはいる。だいたいは独身の女性だが、時には結婚している女性のこともある。そういう女性には、迂闊におめでとうとは声をかけられない。子宮の中の子供にはおめでとう、だけど、外にでてから大変かもしれない、がんばってねと声を出さずに声を出す。そういう妊婦は、おずおずと、あのー、と私の顔を見る。言いたいことはわかる。
「初めての妊娠だわよね、心配なことあるかしら」
ときいてみる。
近頃は体のことを知らない人が多い。女性に限らず男性もである。指を切れば赤い血が出ること、人間も生き物であることを、頭の中に植え付けられていないのだ。今の教育の問題だろう。だから体の中でどのようなことが起きるか想像もできない。不安が生じる、そういう女性の顔と、違う不安を持った女性の顔がある。違う不安の中にもさらに、金銭的な心配と、子供が産まれては困るという二つがあるような気がする。その最後の理由の不安が、「あのー」につながる。
「なにかしら」
それでも、なかなか言い出さないような人には
「子宮の中の新たな生命は、あなたの気持ちが育てるものなのよ」、などというのだが、それでも、なかなかはっきりしない子には、最後には
「予定外の妊娠だったりしないわよね」
と聞いたりする。うなずいたりしたら、
「どうしたの、周りには相談できないの」
そうやって、話すうちに、事情がわかってくる。もう私の責任で、そこは解決しなければならないと思っている。
堕胎は母胎に危険があるときや、体内の胎児に重大な生涯があるとか、条件があるが、認められる場合がある。
私のところは、婦人科で、大学病院と契約しており、産むときにはその病院で産んでもらう体制をしいている。認められている以外の個人的な事情で子供をおろすことはできない。しかし、そういうことを、してくれる医院もないわけではない、もし、それを望む妊婦をうちではできない、とただ突っぱねると、自分で産んで、ロッカーに捨てるとか、産んだあとに殺害して押し入れに隠したりとかしてしまう可能性もある。
私は、そういうことに寛容で、安心できる医院を「うちは、子供をしっかり産みたい人をケアーするところなの、どこどこの医院はとても腕のいいお医者さんよ、相談してみたら」と医院の名前をあげることもある。
子供を産むということは、心のケアーもからだのケアーと同じくらい必要とすることなのである。
私の子宮の中で育っている子供は、自分ではどう思っているんだろう。自問自答で、産んでみたいという結論になっている。コンピューターの画面には、手足のある胎児ではなく、脳がときときと脈動しているのが映っている。
十ヶ月になった。ずいぶん目立つが、私ほどの年になると、このように太ってもごまかしがきく。ただ、急なので、妊婦さんの中には、お医者さんに言うのはおかしいかもしれないけど、なんだか心配、調べていらっしゃるの、といってくれる人もいる。ええ、ええ、血液検査は正常なの、ちょっと飲みすぎかしらねえ、程度の答えを用意している。
十月十日といわれる妊娠期間もすぎた。お腹の中の脳が動いている。横揺れになった。脳が私の体から出てきたら、どうなんだろう。それを育てるとしたら、どうしたらいいのだろう。ちょっぴり不安がよぎった。
ちょうど日曜日、医院も休みの日、ソファーで、紅茶をのんでいるときであった。お腹がぐぐぐっとはってきた。
「今、地球の何年だ」
と頭の中になんだかなつかしい男の声がした。
「2022年よ」
私は声を出して、答えていた。
「でてもいいか」
そんなことをきいてきた。あきらかに、私の子宮の中で育った脳がしゃべっている。
いよいよ脳を産むのかと、紅茶を飲み干すと、ひとりで、住まいの方から医院の診察室に向かった。
私ははだかになると、出産の衣をきて、診察台によこになった。ここでは行わないのだが、大学病院に送る時間のない、緊急の場合、死んでしまっている胎児をとりだすことはある。掻爬である。この病院を立ち上げてから二度ばかりそういうことがあった。
「それじゃ、これからでていく、地球とはどのようなところか、しばらく、いさせてくれ」
脳がぼこぼこと子宮の中で動き始めている。
しかし、いっこうに下に降りてくる気配がない。
左の乳首のあたりがむずかゆくなってきた。五十近くにはなったが、まだ男が触れたことのない、張りのある乳房がはだけた衣からこぼれでて、ぶるんと、揺れ、乳首の先から、霞が漂い始めた。そのとき生まれて初めて、私はのけぞって、オルガスムの頂点に達した。
気がついたとき、診察台の脇に人影が見えた。
目の焦点が定まってきたとき、頭の中が混乱した。
そこにいたのは、尾ひれの付いた人魚の形をした男だった。目は一つしかない。
妄想を見ている。
「そうじゃないよ、地球の住人さん、この星には来てみたかったんだ、その大昔、とある星から、この星、地球に時空間を利用して旅をした男がいた。そのころ私の星でも時空旅行装置はできたばかりたったんだ、その男の星でも時空旅行装置はできたばかりだった。同じ装置をもった星に旅ができる。高度な星同士への旅行だ。もう二千何百年も前のことだ。とある星から我々の星に、時空旅行装置で、訪れたいとの連絡があり、お互いの技術の相互協力をすることにした。その男が時空旅行装置で我々の星にむかったのだが、どちらの装置も未熟で、男は我々の星に到着せず、どこかわからない星におりてしまった。それが地球だ。地球はまだ時空旅行装置など存在しない。これからですら数千年経たなければならないだろう。
その男はどこか違う時空に漂ってしまったのだろうと思われていたのだが、五十年後に我々の星に到着したのだ。そして驚くべきことを言ったんだ。地球という星の住人の体の中に時空旅行装置が育っている。そこに吸い寄せられ、地球についてしまったのだ。その男は降り立った過去の地球であがめられ、しばらく暮らしたのちに、また住人の体に入り、我々の星に到着したのだ。しかし、それ以来、地球に時空旅行装置があらわれることはなかった、男が到着した地球の時空装置を持つ女性は寿命がつきたのだろう。ところが、今回、我々の最新の機械は地球にその装置が発達し始めたことを関知した。その当時、地球の装置を、その星の男はマリアといっていた。だから、地球の時空旅行装置を我々はマリアとよんでいる。あなたのからだにどうしてかはわからないが、マリアが形成されたのだ」
人魚はそう言った。
「どこから来なすったの」
私は診察台で身を起こした。
「異次元の宇宙にある星からだ。この宇宙と時限をあわせ、この星と自分の星を同調させ、平行移動をしてきた。ここで、しばらくこの星を旅行して、また戻るつもりだ。そのときには、また、あなたのマリアにはいらせてもらう」
私はよく意味はわからなかったがうなずいた。
人魚の形をした異星人は、尾鰭をうまく動かして、前に進んだ。そのまま外にでたら、犬にほえられる、人には捕まえられ、と心配していたら、
「だいじょうぶ、私は光に隠れることができる、だから、この星の住人は私を見ることはないだろう」
頭にそういう声が聞こえた。
「でも私には見えた」
「あなたはこの星の住人でもあるが、体の中にできたものは時空旅行装置だ、だから、あなたそのものが付属の機械として、私を見ることができる」
理論はわからないが、そういうものなのだろう。
「いつごろもどるの」
「一月後かな」
「気をつけていってらっしゃい」
私は、その人魚がいとおしくなっていた。自分の子宮で育てた胎児であり、産んだ子供である。母性というのはこういう感覚なのか、わけはわからないが、いとおしい。
「怪我のないように」
「ああ、戻るまで、壊れないように」
異星人はそいういうと、病院の玄関からでていった。戸を開けずにである。
私は自分の乳房を見た。なにごともなかったように、ぴっちりと張っている。
エコーをかけてみよう。腹に当てて、子宮のなかをみた。大きくなった脳が時を刻んでいた。
そこで私は気付いたのだ。
私が今のマリアだ。
一ヵ月後、一人の男が私に求婚した。顔はあの異星人、人魚の顔だった。
私は承諾した。
私は彼に聞いた。
「地球はどうでした」
「私の星の原風景のようだった。私の星では住居はすべて地下です。地上は地球でいう、植物やほかの動物、菌類と同じような、進化の途中の生き物が自然に住んでいます。そこには、我々の地上の共同利用の住居があります。ほかの生き物のじゃまにならないように建ててあります、いずれ地球もそうなるでしょう」
「食べ物はいかがでした」
「空気は汚れている最中だな、あなたが方がいずれ気がつくか、ほろびるか」
「空気だけでいいのですか」
「はい」
「一つ聴きたいことがありました、昔、地球にきた人は、キリストといいませんでしたか」
「いいえ、地球人には姿が見えなかったと思う。ただ、マリアを持った女性が、親のない子をたくさん育てていたというから、その中の誰かかもしれない」
「おみやげはなにを買いましたか」
なんだか私はとんちんかんな質問をしたようだ。
「買うという行為はしない、それに私がみたものは皆に伝わる、それが土産かな、おもしろかった。こういう進化もあるのかと思った、何より、生き物の種類が多い、おどろくべきことだ。知っている星の中でいちばんだ、大事にしてください」
「またきますか」
「私の話を聞いて、来たくなる者がいるかもしれない」
私は顔が赤くなった。また子供を産むことができたら、あの快感をあじあうことができる。
その晩、私は始めて男に抱かれた。地球人ではない。
男が精を放った。快感が体中に走った。子供を産んだときよりさらに強いものだった。完全に気を失った。どのくらいたったのか分からない。目を覚ますと、隣に寝ていた男はいなかった。
卵管の中では男の精子が子宮を目指していた。
からだを起こしたとき、子宮の中がぶるぶると震え、やがて振動がおさまった。
男は自分の星に帰ったのだろう。
子宮はまだときときと動いている。
死ぬまで私はマリアをお腹の中に抱いている。これから何人の異星人が地球を訪れるのだろう。地球に来た異星人はみな私の産んだ子どもである。
異次元の母親


