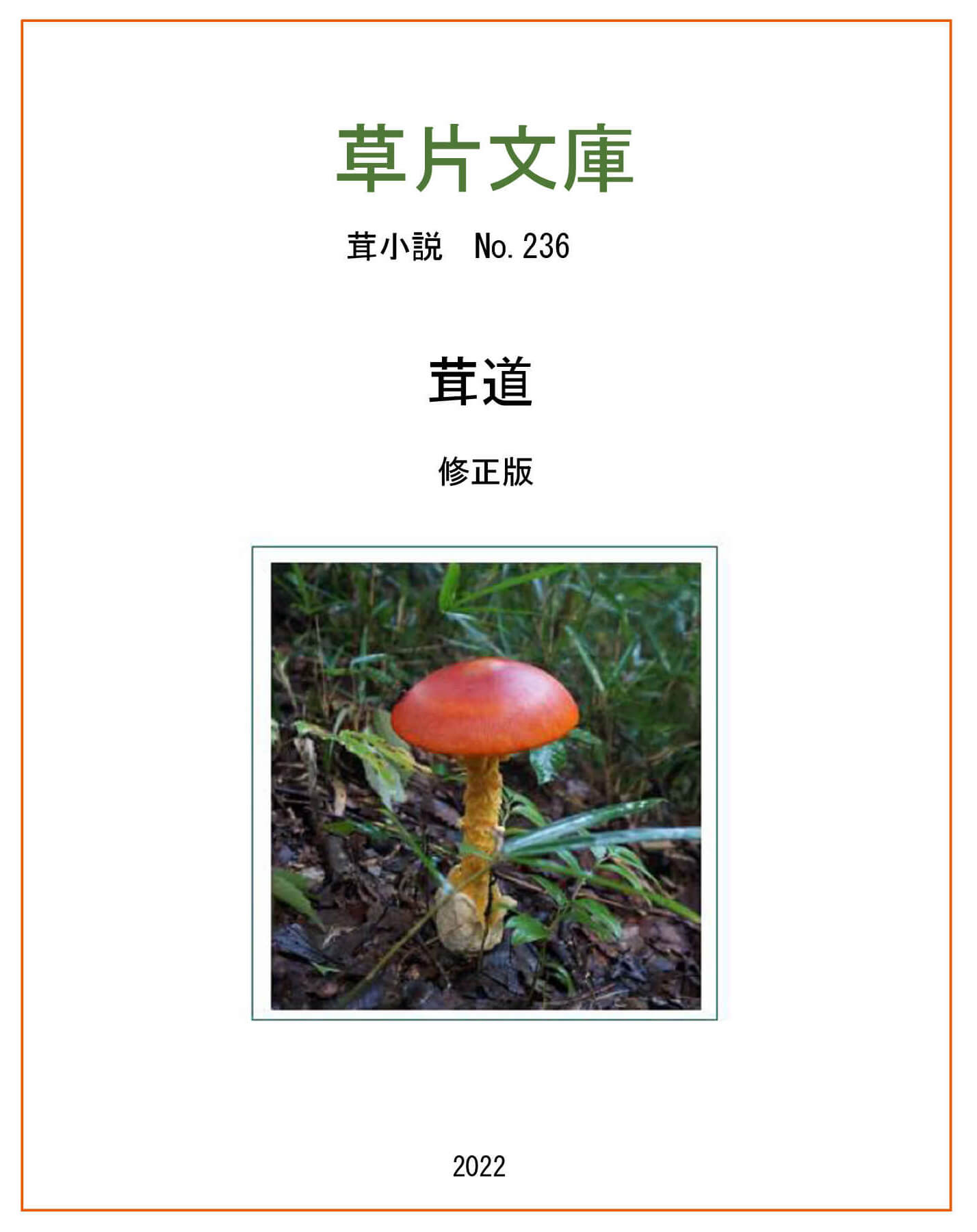
茸道
茸の不思議小説です。縦書きでお読みください
庭の浦島草が、長い髭を垂らして、隣の海老根の花に、いやがられながらも無理矢理に絡んでいる。
そんな様子をガラス戸ごしに見ていると、赤いスカートをはいた女性が、庭を横切った。
誰だ。いきなり、心臓がどくどくと胸を打ち、女の赤ら顔がちらりとこちらを見たようだ。目は真っ白だったような気がする。
若い頃なら、すぐ立ち上がって、ガラス戸を開けているに違いないが、八十になった今となっては、動悸が激しくて、立ち上がるのもやっとである。
今、夜の九時。庭は当然暗い。部屋の明かりが漏れて庭の木や草花が浮かび上がっている。そんなときに、誰だかもわからない人間が庭を歩いていったとなれば、当然気持ちが動転する。
我が家は多摩丘陵の、小高い丘の斜面に広がる団地の角にある。三方が道に面しているという特異的な位置にある。どういうことかというと、隣の奥まったところに二軒あり、その家に行くための道が脇にあるので、左右前、三方が道ということになる。我が家が突出しているわけである。
我が家は五十坪にも満たない小さな土地で、奥行きは広くないが、細長いことから、家の前に庭が延びている。何本かの木と、下には野草類が植わっている。狸が通ることもあったが知らぬ人が通るということは、ここに住んで五十年になるが一度もないことであった。塀の前の道を通った人を、見間違えたことの可能性もなくはないが、植わっている木などで、スカートまでは見えないはずである。
こちらを向いた女の目に瞳はなかった。真っ白である。明らかに、自分の頭がみた幻視である。怖かったのは自分の頭がとうとう末期になったのかという不安である。動機が治まるのにどのくらいかかったか。
よくあることだが、家内は友達と旅行に出かけていて、今日から一週間ほど一人暮らしである。まだ自分のことは自分でできるし、夜は定期的に総菜を届けてくれるサービス会社に依頼してあるので、ご飯を炊いておくだけでよい。朝は近くにおいしいパン屋があり、週に一度ほど買いに行けばことたりる。昼は残り物で食べる。
趣味の童話づくりもぽちぽちやっている。足腰は確かに弱ってはいるが、頭だけは大丈夫だと自信をもっていた。その自信を打ち砕く出来事である。
本当に人が通ったのならまだ救われる。しかし、あの白い目と、開けたら必ずきーっと音のする、門のところの、古くなった鉄製の扉が開いた様子はない。飛び越えたか、家の裏に回って、塀を乗り越えて隣の庭に入ったかしかない。しかしその様子もない。
やっと動悸が治まり、ガラス戸を開けた。なにごともなかったように、薄緑色の葉を広げた梅の枝と、元気に若葉を吹き始めた大手鞠が目に入った。花が終わった椿は濃い緑の厚い葉の間の、新しい葉の芽吹きが新鮮だ。沈丁花は白い花が盛りで、ここまで香りが漂う。
今年は三月が暖かく、どの植物も芽吹きが早かった。八角が大きなつやつやした葉を広げている。
家を囲む三方の庭には実の成る木が何本も植わっている。クローバやタンポポ、蛇苺が好きなように生えているので、虫も多い。おんぶバッタがたくさん発生するし、シジミ蝶やモンシロチョウ蝶が、もう少したつとひらひら飛び回る。レモンやミモザが植わっていることもあり、庭がアゲハチョウなどの蝶道にもなっている。
庭を見ていたら、ほっとして、今みた幻覚の恐怖がなくなった。
どうして、あのような幻覚をみたのだろう。若い頃は幻想小説ばかり読んでいた。幻想と現実の区別ができなくなっていくと、いずれ、自分がなにかもわからなくなる。そんなものなのか。
ガラス戸を閉めカーテンを閉じた。そのまま寝室のベッドにころがった。最近ネットで買った、雨月物語を読みながら眠りにつく。
雨月物語はいろいろな人が現代語に訳しているが、今手にしているのは、訳と言うより、秋成りの話を元にした創作である。いくつもそのような形の雨月物語がでている。みなそれなりに個性があっておもしろい。これは岩井志麻子の作で、新たな幻想を付加し、内容を高めているいい作品である。
朝はいつものように四時に起きた。目覚めはよい方である。
キッチンでトーストを食べていると、薄いカーテンをひいてある居間のガラス戸越しに、白いスーツの女性が庭を歩いているのが目に入った。トーストを持った手が震えた。細長い女性の顔がこちらを見ると、目は真っ白だった。
トーストを皿に放り、立ち上がると、ガラス戸に駆け寄った。女の後ろ姿は入り口を通って道にでると、隣の家の前の道を通って、消えていくところだった。蛇腹の鉄製の門が動いた様子がない。玄関に回ると、急いで門を開け道にでた。女はもういなかった。団地の上にでる道の石段も見えるが、そこにもいなかった。
家に戻ると紅茶を一杯飲んだ。トーストの残りを口に入れたがなかなか飲み込めなかった。
昨夜からなにが起きているのだろう。体の変調など感じられないし、多少飛蚊症気味だが、家の中のものはいつもの通りに見えている。目の異常はなさそうだ。精神的なものためだとしても、原因はわからない。家内はよく家を空けるので、一人で生活するのはなれている。まあ二十一年にわたりかわいがっていた猫の貧乏が老衰でいなくなったことか。だがそれにしても一月前のことである。
気持ちが落ち着いてから考えよう。
ゆっくりと食事をすませた。テレビの天気予報とニュースみると自分の部屋にいった。童話を書いたり、調べ物をしたりする。この年になっても、PCはよく使う。ネットでニュースを知る方がテレビよりも早いし、ちょっとしたことはネットで調べてしまう。
机の脇のガラス窓から庭をみると、浦島草が長い髭を自分の葉にからませている。
PCが立ち上がり、書きかけの童話を開いたが、気持ちが入っていかない。
昨夜と今朝の女性のことだ。本当に人が通ったのかどうか、それを検証するのが先だろう。ちょっと冷静になっている。
いつも使かっているカメラがあるじゃないか。机の上にある。
さて、童話の続きをどうするかと頭を切り替えようとしたとき、ふと黄色い陰が目に映った。庭を見ると、黄色い服を着た女性が部屋の前の庭を歩いていく。あわてて手元のカメラを庭に向けた。シャッターを押したときにはガラス戸から女性は消えていた。
ぎりぎりで写ったはずだ。再生のボタンを押した。画像がモニターにでて目を疑った。傘が黄色で柄の白い茸が半分写っている。
ずいぶん大きな茸だ。ふつうの大人の大きさがある。いや、目がおかしくなったのだろうか。
カメラをオフにした。もう一度つけ、撮った画像をよびだした。やっぱり茸が写っている。
いかん、何かがおかしい。
そのとき、門につけてあるドアフォンがなった。
居間にいき、ドアフォンの画像を見ると、若い女性だった。受話器を取り上げると「ちょっとお話があってまいりました」と言う。
だいたい、こういう感じの時は宗教の勧誘である。
「なんでしょうか」
「お宅の庭のことでお願いがあって参りました。昨日から通らせていただいています」
えっと思った。本当に人が通っていたんだ、それにしてもまた、なぜうちの庭を、そう思って、しかし、「はい」と答えていた。
玄関からでると、入り口のところに、三人の女性が立っていた。赤いスカート、黄色いカーデガン、白いワンピースの女性だ。昨夜から庭を通った女性たちのようだ。
「おはようございます、朝早くからすみません、ご相談がありまして」
「はあ、なんでしょうか、宗教関係だったらきっぱりお断りしています」
宗教に関わっている人は物事が多方面から見ることができない。そういう人たちとはまともな議論ができないから嫌いである。
「いえ、宗教とは全く関係ありません、あの、ご主人は私どもが見えるようで、ご説明をしておかなかければと思いまして」
どのような意味だろう。
門の鉄の蛇腹の鍵を上げ開いた。
「どうぞ、中で伺います」
口調だとまとものようなので、入ってもらうことにした。庭で立ち話もなんなので、三人を居間に通した。詐欺や悪さをするような感じではない。ここは自分の勘であるし、気持ちの中では、女性が庭を通ったのは幻想かと、むしろそちらを気にしていたので、そうではないらしいことに、安堵していたのである。写真のことは頭からすっかり抜けていた。
ソファーをすすめ、自分も反対側にこしかけた。三人とも整った顔をした、まだ三十代と思われる、美人に入る女性たちだ。姉妹でもなさそうだが。
「なんでしょう」
「私たち、茸なんです」
赤いスカートの女性が私を見た。
え、耳を疑った。また頭に靄がかかった。
「茸?」
最近の茸ガールのことなのだろうか。このあたりは茸がよく生える。今連休前なので、まだ春茸はあまりでていない。童話には茸をよく使うので、散歩をする道すがら、茸の様子をよく観察している。
「はい、お写真をお撮りになりましたわね、それで、お話をしなければと思い、まいりました」
「どちらから」
「隣の丘陵公園からですの」
白いワンピースの女性は、何とかという女優と似ている。
「あの、話がよくわからないのですが」
私もちょっと困ってきた。意味がつかめない。
「驚かないでいただきたいと思って」
そういって三人が立ち上がると、女性たちの着ている服が透明になってきた。
なんだ、と、ちょっと複雑な気持ちになったとき、前に現れたのは三人、いや三本の茸だった。赤いスカートをはいていた紅天狗茸、黄色いカーデガンの黄卵茸、白いワンピースの毒鶴茸、それが目の前にいる。
動機が激しくなった。いよいよおかしくなったか。家内に連絡した方がいいだろうか。
「だいじょうぶですのよ、奥様に連絡しなくても」
三人の茸は自分の頭の中を読んでいる。茸たちは柄を折り曲げて、ソファーに腰掛けた。
ちょっと血圧が高くなっている。
「詩川(しのかわ)さんには私たちが見えます、でもけっして、詩川さんがおかしくなったわけではないのです」
そういわれても、すぐに信じられるわけはない。昔から幽霊を否定していない。この宇宙の存在の意味が分からない限り、どのようなものがあってもおかしくないからである。と思い続けていた。しかし、目の前で、女性が茸に変わって、信じろと言われても気持ちの上でわかっていない。
「心配でしょう、わかります、信じられないのなら、白昼夢を見ているとお思いになって結構です、地球は、宇宙は、それぞれ個々の生き物の中に存在していて、その生き物が死ねば、宇宙もなくなるのです」
その理論は、昔から言われていることである。しかし、一つの心理でもある。霊魂の考えかたも一つであるが、霊魂より、宇宙は自分の一生とともに存在すると考える考え方の方が自分には理解できる。
私がうなずくと、赤い茸が「詩川さん、私たちは移動します、茸にとって通りやすい道があります、そこを通っていくのです、丘陵公園にすんでいる。いや生えている茸の代表は、必要におうじて、高幡不動尊のある高幡山にいき、そこで茸の会合を開いています。今、気候の変動が大きく、大移動か、からだの変容の必要性があると議論しています」
私もちょっと落ち着いてきた。
「茸は菌糸が本体、それは地の中にあり、茸ではなくて、菌糸が変化する必要があるでしょう」
私は童話作家になっているが、大学では植物学を学んでいる。昔、茸は植物と考えられていた時代である、当然茸のこともある程度は知っている。
「その通りです、いろいろな茸の菌糸が地の中にはびこっています。そのなかに、すべての茸の共通の菌糸があります、それは茸の世界にしかわからないものです、人の目には見えないでしょう。最も、詩川さんならば見えるかもしれない。茸の菌糸から派生した菌糸幹がそれこそ地球すべてのところにつながっています。それが通り道になります。詩川さんの庭の地中にはそれが通っているのです」
「茸はそこしか歩けないのかね」
「いえ、自分の菌糸の生えているところには、どこにでも行けますが、他の茸の菌糸は通れません。菌糸幹はどの茸も通れます」
「今日の朝、どなたか一人うちの庭から道にでて、上に行く道に消えていったが、あれはどういうことですかな」
「わたしでした」
毒鶴茸は、大きな目で私を見た。
「ちょっと、仲間ののところにいったのです、団地の一番上の動物園の境ところにいたのでそこにいきましたの」
成るほどと、私はうなずいた。
「菌糸幹は詩川さんの庭を通ると家々の下を通って、ともかく高幡山に行きます、詩川さんは私たちを見ることができる。そこでこれからも通るのでご挨拶をしておかなければと伺ったのです」
「でも、なぜ人間の格好をしなければならないのかね」
「いえ、詩川さんにはそう見えただけです。もし人間の言い方で言えば、私たち茸そのものが動いているわけではなく、菌糸の中を茸の魂が通っている、地中を通っているのですが、それが詩川さんには女性に見えたのです、幽霊に見える人もいれば、怪物に見える人もいます、それはおかわいそうです、詩川さんのように女性に見えるのは救われます」
「それじゃ、幽霊を見た人は、あれは茸の魂が菌糸の中を動いたのを見たということなのかね」
「そうです、理解していただけたようですね」
「いや、まだわからない」
「そうでしょうね、また、参りますから、それまで、お考えいただければと思います」
三人の茸が私を見た。とたんに目の前から消えた。
やっぱりおかしいのだろうか。
ともかく家内が旅行から帰ってくるまで、静かにしていよう。
その日からである。朝早く庭にでると、茸がひょこひょこと、庭の山野草のうわっているところを動いて、隣の家の方に消えていくようになった。夜中も茸たちは、動いているが、朝の六時頃までである。昼間は通らない。
いろいろな茸があるものである。よく通るのはイグチの仲間と紅茸の仲間、それに土栗や昇竜である。
毒鶴茸が目の前を通るとき、ちょっと私を振り返って、挨拶したように見えた。
うちの猫が死んでから、近くの猫が庭に入ってくるようになったが、その夜も庭に入り込んできた。
歩いていく茸を追いかけ、前足ですくおうとしたりするが、空振りでおわる。猫には見えているようだ。
卵茸がたちどまって、庭の椿の下からじーっと部屋の中を見ている。その前をいろいろな茸が歩いて、庭をでると、隣の家の中に入っていく。茸の道を通って、高幡山に行くのだろう。
卵茸はなぜか歩かない。
ずーっとみていてもしかたないので、キッチンに戻り、寝る前に薬を飲んた。ベッドで読む本を本棚から選び、二階の寝室に行った。紅天狗茸が好きでしょうがない堀という人が書いた新書だ。童話や絵本には紅天狗茸がよくでてくる。真っ赤で傘に白いぽちぽちのある茸で、絵本などでは茸が出てくると、必ず紅天狗茸だ。きれいな茸で、その茸に生涯を捧げようと思う人間もいるくらいで、そのような人が書いたものだ。自分も童話を書くので、紅天狗茸のことを知っておこうと思い買っておいたものだ。
茸にはうまみ成分もあるが、精神、すなわち脳と言うことだろうが、それに与える成分もいろいろ含まれているという。どこかでそのような薬物を向精神薬というということを聞いたような気がする。紅天狗茸にも幻覚、妄想を引き起こすような成分があるという。一般に言われているに、食べたらころっと死んでしまう様な毒物はないようだ。
なるほどと思いながら読んでいくと、眠くなってきた。茸はそういった科学的なものではないところにも、人の精神に多大な影響を与えているなと思いついた。あの形のものが、地面からニョッキリと生える。幻想的でもあり、滑稽でもあり、人の気持ちを動かす強い力がある。
そこで寝てしまった。
朝起きて二階のベランダにでてみると、庭の椿の木の下に赤いものが見える。
下におりて、居間のカーテンを開けると、昨日歩かなかった卵茸が生えていた。うちの庭で生えたんだ、だから昨日こっちを見ていたわけか。と言うことは、しおれるまでそこにいることになるわけだ。いや、茸魂は移動しているのかもしれない。
日が暮れて暗くなると、我が家の庭を茸が歩いていく。この地域にこんなにもたくさんの茸が存在するんだ。かご茸が歩いている。童話にかご茸を登場させたことがある。茸でもしのう菌類という、一般的な形をした連中とは違い、胞子の作り方が違う種類のものだ。おもしろい形のものがたくさんある。よく知られているのはスッポン茸や絹傘茸だろう。胞子に臭いねばねばを絡ませて、蠅やアブにはこばせている。毒鶴茸がやってきた。おととい女性になって我が家に訪れた一人だ。白いワンピースをきていた。毒鶴茸は、立っている卵茸になにやら話しかけている。
おや、全く動かなかった卵茸の頭がこっくりとうなずいた。
毒鶴茸は、ふたたび茸の行列に加わって、隣の家に消えていった。高幡山では集まってどのようなことを話しているのだろう。
そんなことを考えていたら、庭の卵茸の背がするすると延びて、椿の木を追い越して人間の大きさになると、まだら模様の橙色の柄のまん中に割れ目ができた。見ていると、ぺりっと割れ目が広がると、中から短髪の橙色の服を着た女性がでてきた。
居間のガラス戸越しに見ていたのだが、彼女はガラス戸前に来ると、笑顔になってお辞儀をした。どのような顔をしているかというと、表現がとても難しい。顔かたちは卵で、目も鼻も口も平均的な大きさで、顔の色も特別白くもなく黒くもなく。すごい美人でもなく、ただなぜか引きつけられる。
茸が人になって現れるのはもう気にならない。ガラス戸の鍵をはずし開けた。
「こんばんわ、おじゃまします」
卵茸は居間にあがってきた。橙色のハイヒールが庭に残っている。
「もう、真夜中の十二時ですのよ、いつもなら九時頃お休みになるのに、今日はずいぶん長い間、私たちをごらんになっていたのね、毒鶴茸の姉さんが、お相手してさし上げなさいと言ったので、来たのよ、そろそろおやすみになりませんか」
卵茸にそういわれて、壁に掛けてある時計を見ると確かに十二時をすぎている。
それじゃ寝るかと思ったが、卵茸を放っておくわけにいかないと思っていると、卵茸の女性が、私の手を取って、二階の寝室に引っ張っていく。
二階の寝室にはいると、私の着ているシャツのボタンをはずして、ランニングシャツを脱がすと、パジャマを着せてくれた。
ズボンのベルトをはずし、チャックをおろすと脱がしてくれて、ベッドの脇に腰掛けるとパジャマのズボンをはかせてくれた。靴下を脱がしてくれると、私をベッドに寝かして、じーっと見た。若かったら、女性にこのような扱いを受けたら、下半身がジーンとするどころか、緊張して大変だろうが、なんとつまらないことに、ただ横たわっただけだ。
卵茸の女性は夏掛けをかけてくれると、おでこの髪の毛の生え際をぺろっとなめた。
私はぐーっと眠くなって、寝てしまった。
明くる朝。四時に目がさめた。まだ暗い。一階に降り顔を洗って、キッチンに行くと、朝食がテーブルに用意されていた。紅茶、トマトにハム、焼きたてのパン。いつものだ。
テーブルに腰掛けて紅茶をカップにいれた。まだとても熱い。ハムとトマトをパンに乗せて食べた。
昨夜、女性が入ってきて寝る支度をしてくれたことを覚えている。そうだ、卵茸から出てきた女性だ。その女性が朝の用意をしてくれたとすると、まだいるのではないだろうか。
食べ終わって、居間を見たが、いない。用意して帰ったのかと思い、ガラス戸を開けて、庭の椿の下を見たが、卵茸は生えていない。茸がこのように消えてしまうことはない。いや、鼠にでもかじられてしまえばあるに違いないが、根本も残っていない。
と言うことはあの女性はまだ我が家の中にいるのかと、キッチンに戻った。いるわけはない。と浴室の方で何か音がする。行ってみると、ドアが開いて、女性が出てくるところだった。なんにもきていない。
「あら、おはようございます、すみません、このかっこうで、でももういいですね、このまま帰ります、お風呂ってとって気持ちのいいものですね」
そういうと、胸どころかすべて露わな女性は、「またきますね」と居間のガラス戸を開けると、外に出て行った。見に行くと、土の中から卵茸がせせりでてきて、柄が割れて、裸の女性はその中に入って行ってしまった。
また幻覚を見ていると、恐ろしくなった。キッチンに戻ると、残った紅茶もあるし、パンクズののった皿がある。
本当にあったことなのだ。
その日は、ぽちぽち書いている童話がずいぶんすすんだ。庭をついついみてしまうが、卵茸は元気に立っている。
夕方、総菜を運んできた女性がいい庭ですね、「茸がでていますね」、と言った。
「このあたりは茸がよくでるんですよ」
「今日の総菜にも椎茸の煮物がはいってます」
と笑いながら、パックをおいていった。
庭に降りて、卵茸をじっくりと見た。気がついたことは、傘がまだ卵の形をしていることだ。完全に開いていない。まだ若い卵茸だ。
食事は六時頃すませてしまう。その後、居間でテレビなど見て過ごす。
日が暮れると、鍵をかけないでおいた居間のガラス戸ががらっと開けられると、また卵茸の女性が入ってきた。え、っと驚いたのは、なにも着ていない。
「おふろいいでしょ」
私はちょっと赤くなってうなずいていた。
卵茸は、いや女性は風呂場に行くと、風呂に入ったようだ。かわいらしい声でハミングなどしている。
そうだ、わかしていないじゃないか。夏だから冷たくはないが、大丈夫なのだろうか。
しばらくすると、滴を垂らしながら彼女は出てきて、「気持ちいいのね」
私を見た。
「わかしてなくて大丈夫」
「あら、火をつけたら、熱くてはいれないわ」
そうか、茸は熱いとゆでられてしまうのか、昨日も沸かしてない風呂に入ったんだ」
「なにしましょうか」
彼女は裸のまま、ソファーに腰掛けた。
明らかに心臓がどきどきと脈打ってきた。
「ソファーが濡れるから、タオル使って」
私は、脱衣室から乾いたタオルともってきてわたした。
「あら、そうか、このままが気持ちいいんだけど、人間の住まいはだめね」
彼女は目の前で、タオルで体を拭きだした。
なんとも、八十何年生きていて、このような経験をしたことがない。もっと若いときならな、と思いながら、「あの、体に何かつけてくれないと、目のやり場にこまりますが」
そんなにあけっぴろげより、ミニスカートのほうがいいなどと、下世話な思いで、声をかけると。
「あら」と笑顔になって、
「人間のことまだおそわってないの」と、パンテェイとブラジャーがあらわれた。
それだけだと、もっと困る。
「昨日着てきたの似合いますよ」と言ってみた。
「ああ言うの、ちょっと窮屈だけど」と言いながらだいだい色のミニのワンピースになった。
もうちょっと短い方が似合いそうだ。
「こうかしら」
話さないのに通じたようだ。
ワンピースが超ミニスカートになった。まあいいか。
「また昨日の続きいいかしら」
そう聞くので、うなずくと、彼女は立ち上がって、私の手を取ると、二階の寝室にいった。
昨日と同じように私はパジャマに着替えさせられた。
彼女は私の頭を押さえると、額のところをなめ始めた。なんだか奇妙な気持ちになる。髪の毛をじょろじょろなめる。
「すてきね」
何で髪の毛のところなんだろう。
「他もなめてほしいの」と聞くから、どうしようか迷っていると、瞼の上をなめ始めた。だが、眉毛をなめ、結局、髪の毛をまたなめ始めた。そのころはもう半分寝ていた。
そのあとはわからなくなった。
目を覚ましたのは四時過ぎだった。女性はいなかった。下に降りると、やはり食事の用意ができていた。もしかすると、また風呂に入っているのかとのぞいてみると、いなかった。居間から庭を見ると、卵茸の傘が少し膨らんで大きくなっていた。
その夜訪れたのは、昨日の女性とはずいぶん違っていた。同じ女性であることは確かだが、肉付きが違う。果物で言えば熟してきた女性だ。裸ではなく、同じ橙色だが、胸元が大きく開いたパーティードレスである。
「よろしいですか、またおじゃまします」
話し方まで違う。
「ええ、もちろん」
居間でテレビを見ていた私は、テレビを消すと、
「何か飲みますか」
と聞いた。そういいたくなる雰囲気なのだ。
「お酒召し上がるの」
昔はよく飲んだ。今はほとんど飲まないが、たまにビールを飲むので、冷蔵庫に入れてある。まだ入っているウイスキーも何本かあることはある。
「ビールならありますが」
「お風呂使わしてくださいな、その後にいただきたいわ」
私がうなずくと、彼女は立ち上がって、ドレスの肩の結びをはずした。
するりとだいだい色の布が足下に落ちると、下になにも着けていなかった。張った胸、むっちりとした太もも。映画でも見ているように、私が呆然としていると、彼女は風呂場に行った。我に返って、ビールの用意をした。
しばらくすると、彼女は出てきて「ありがとうございました」と裸のまま居間に入ってきた。脱いだドレスをするりとまとうと、ソファーに腰掛け、足を組んだ。
グラスにビールをつぐと、ぐーっと一気に飲んだ。
「おいしいものね」
私も一口久しぶりに飲んだ。おいしい。彼女にまたついだ。
「これ飲んだら、上にいきましょうね」
彼女は私の手を取ると、寝室に行き、昨日と同じように私にパジャマを着せた。
ただ、昨日とは違い、ベッドの上に乗ってきて、私のからだの上にのしかかると、髪の毛をなめた。鼻の頭をなめ、頬をなめ、眉毛をなめるとまた髪の毛をなめた。眠くなってきた。ちらっと胸元から乳首が見えた。そこで、寝てしまった。
いつものように起きると、キッチンには朝食の用意がしてあり、彼女はまだそこにいた。
「もう、行きますけど、何かしましょうか」
本当はもっといてもらいたい、何かお願いしようかと考えていると、わかったようで、「お食事がすむまでおりますわ、でもあまり明るくなるといることができません」
わたしはうなずいて、「ありがとうございます、お風呂はどうですか」
と聞いた。
彼女はえくぼを寄せると、肩の結びを説いて、するっと裸になった。
なかなか風呂場に行かない。
「お食事をなさって」
そういって、彼女は私のそばに寄ってくると、おでこの髪の生え際をじょろっとなめた。
大きな締まったお尻を見せながら、風呂場へ行った。
これじゃ食事などできないと、どきどきしているのに、なぜかトーストにバターを塗って、チーズと一緒に食べていた。紅茶がおいしい。
食べ終わると、彼女が風呂場から出てきてドレスを着て庭に戻っていった。ただにこっとしただけで何も言わない。
その日、書いている童話が、茸の話に変わった。
庭の卵茸は傘が開いていた。きれいな濃い朱色である。
その夜入ってきたのは、妖艶な女性だった。
「ウイスキーいただけるかしら」
「だいぶ飲んだ残りですけいいですか」
「どこのですの」
「スペイサイドのグレンロシスです」
「よかった、私、アイラはだめですの、あの塩の香りは、からだにあいません」
彼女は昨日とはうって変わって、だいだい色のツーピースに身をつつんでいた。それなのに女性の強い香を感じる。服に身を包んでいても、裸身を想像させることのできる女性こそ、妖艶と言う言葉が当てはまるのではないか。
「ロックでしょうか」
「いえ、そのまま」
「お水ももってきましょうね」
「いえ、水はいりません、詩川さんはお飲みになりませんの」
「ロックをちょっとだけ、もう何年もウイスキーは飲んでいませんからね」
「私が作りましょう、お酒はどこにありますの」
「私の部屋の戸棚にしまったままで、こちらです」
私が立ち上がると、彼女もついてきた。髪の毛がぷーんと茸の匂いがした。茸の匂いは古びた本の匂いに似ていると思っていたが、かすかな匂いは、香水になる、誘われる匂いだ。
戸棚を開けると、久しぶりに並んだウイスキーの瓶を見ることになった。なにも考えずに、旨いとだけ思いながら飲んだ頃が懐かしい。
「これにしましょう」彼女は底にほんの少しだけしか入っていない瓶を指さした。
今は作られていないウイスキーだ。グレンユーリーロイヤル。退職記念にもらったウイスキーだ。
彼女はそれを持ってキッチンに行くと、ショットグラスに自分の分を入れ、私用に小型のロックグラスに氷を入れた。最後の数滴が壜の口から落ちた。
彼女は居間のソファーに座ると、ショットグラスを口にもっていった。
私も何十年ぶりに飲んだ。舐める程度である。
「おいしいわ、ありがとう」
彼女は立ち上がると、私の手を取って、寝室に行った。
パジャマに着替えさせてくれると思ったら、下着もすべて撮られ、ベッドに寝かせられた。
彼女は上着を脱ぐと、白いブラウスになり、ベッドの横に腰掛けた。彼女が私におおい被さると、乳房が押しつけられるのが感じられた。両手で私の頭をもつと、顔を近づけ、髪の毛の生え際をなめた。ぷーんと茸の甘い香りがした。そのまま寝てしまった。
明くる朝早く、目が覚めると、パジャマを着て寝ていた。昨日のウイスキーはうまかった。
階下に彼女がいる。私はいそいで起きて下におりた。
キッチンには朝食が用意してあった。
しかし、彼女はもう帰った後だった。
庭を見ると、卵茸が大きく傘を広げていた。
今日はどのような女性が来てくれるのだろう。耄碌したといっても、まだ成り行きの道筋は読める。昨日よりもっと熟れた女性がくるのだろう。
ガラス戸を開けて入ってきたのは、歳で言うと四十ほどか、橙色の浴衣を着ていた。
「日本の着物は涼しくて気持ちがいいですわね、いきなりですけど、湯船に浸からせていただいていいかしら」
女性はちょっと目尻の脇にしわを寄せて、笑窪を寄せた。きれいな女性だと初めて思った。これまで毎日きた女性も若くてとてもきれいな人だったのだろうが、こちらの年老いた気持ちが、まぶしすぎるものにサングラスをかけてしまって、よく見えなかったのだろう。裸眼で見た女性の美しさと言ったらいいか。少し受け入れやすいといったらいいのか。
そんなことを思っていると、居間で浴衣のひもをほどいた。やはりなにも着ていなかった。熟し終わった時の美とでもいうのだろうか。筋肉が目立たない色の白い肌というのだろうか。しっとりとしている。
彼女は風呂場に行った。
出てくると、浴衣をつけ、「お茶をおいれしましょうね」
とキッチンに行った。
「いいお茶があること」
家内が取り寄せている茶である。
急須にお茶を入れてもってきた。
「ちょっと濃いめかもしれないけど」
私の湯飲みに注いでくれた。
香りがいい。茸の香りも混じっている。
「毎晩よらせていただいて、ありがとうございます」
「いや、私の方こそ」
お茶を飲み終えると、彼女は私の手を取って二階にあがった。今日はパジャマに着替えさせられ、彼女がベッドの脇に横座りになった。浴衣の裾が割れ色の白い太股が見える。襟から乳房も丸見えだ。
顔を寄せ、おでこをじょろじょろ舐めた。
そういえば、こうされたとき、一度も声を発したことがない。髪の毛を舐めてどうするのだろう。それに、彼女にいちどたりと手で触れていない。
口を開きかけたときに、突然霧がおおってきた。霧ではない。水っけはない、粉のようだ。目の前が茶色っぽくなり、私は突然眠りに落ちた。
朝、いつもと同じように朝食が用意されていた。
今日は曇りである。雨が降るかもしれない。庭の卵茸の傘は平らに反り返っていた。胞子を出し終わったようだ。昨日の霧は胞子だったのか。
その日はお昼に大学の同級生二人と会うことになっていた。たまたま関西にすんでいる一人が、用事で出てくるので、新宿でお昼を食べないかという。同級生の半数はもう向こうの世界にいっており、めったにあう機会もない。私の家は新宿まで電車で三十五分のところだ。埼玉の一人も同じくらいだろう。もうこの歳になると、たくさん食べないし、ちょっとした寿司屋にいくことにした。
「やー久しぶり」
京都からきた同級生は、我々二人に小さな包みをみやげにくれた。
「なんだい」
「松茸だよ」
「高価なものだよな、わるいね」
「いや、知り合いが採ってきたもらいものだよ」
「元気そうで何より」
「うん、のんびりやってるから」
その男は京都の大学の教授だった。退職してからは非常勤講師などしていたが、もう悠々自適の身分だ。埼玉の男も大きな農家の長男で、すでに子供の代になっており、好きな畑作りをしているようだ。
「詩川も元気そうだ、髪の毛は減ったけどな」
そいつが笑いながら言ったが、そいつは古希の時には毛がなかった。
「東京に何のよう用事だい」
京都の同級生は「うん、品川に孫がいるんだが、曾孫が生まれたんで、お祝いに来たんだ」
「そうかそりゃおめでとう、今日はそこに泊まるんだな」
「いや、狭いマンションだから、夕方帰るよ」
それから、お互いの近況を話しながら寿司を摘まんだ。
「俺は最近変な夢を見るよ」
私が言うと、二人とも、
「俺もよく見るようになった」
「俺も見るな、昔のことが、今と混じっておかしな夢だ」
と言った。それを聞いて何となく安心した。
久しぶりに旧知の人間と話すのは気が晴れるものである。
名残が惜しい気がしたが、京都の同級生の新幹線の時間もあり、機会があったらまた会おうとわかれた。
家に帰ると、宅配ボックスに、夕食の総菜が入っていた。もらった松茸があるが、うまい寿司を食べてきたこともあり、松茸は冷蔵庫の野菜かごに入れた。
いつもより遅く、七時頃、夕飯を食べると居間でテレビをつけた。ガラス戸から見ると卵茸が部屋の光に照らされて赤く見える。少し雨が降っている。
九時を過ぎ、暗くなると、卵茸が大きく膨らみ中から女性がでてきた。浴衣ではなく、橙色の帯を締めた和装の女性である。着物の色も朱色系である。
「こんばんわ」
ガラス戸を開けて入ってきたのは、白髪の混じった短髪のちょっと年をとった女性だ。六十にはなっていないだろう。ふっくらとした白い顔の、ゆったりした雰囲気の女性だ。ふくよかと言ってもいいかもしれない。なかなか色っぽい。
「今日はお顔のつやがいいですこと」
女性が私を見た。
「久しぶりに同級生に会いまして」
「よございましたわね、松茸の匂いがしますが、松茸もお召し上がりになったのですか」
「いえ、京都の友人のみやげで、今冷蔵庫に入っています」
「私には死体の匂いです」
「あ、そりゃすみません、二階にまでは臭わないと思います」
「そうですね、まいりましょう」
女性は私の手を取って、二階の寝室に行った。
「お着替えくださいまし」
女性は私の着ているものを取り、パジャマを着せてくれた。私がベッドに腰掛けると、女性は目の前で帯を解き、襦袢をとると素裸になって、となりにこしかけた。年相応の皮膚だが、しわはあまりなく、胸なども立派なものである。パジャマから接している太ももの暖かさが伝わってくる。女性はふくよかな手で私の頭を抱えると鼻から眉毛、それから髪の生え際をなめはじめた。
私を横たえると、なおもなめ続けた。彼女の大きな胸が私の胸の上に押しつけられ、両足で私の脚を挟み込んだ。
どのくらいなめられていただろう。その間、身動きすらしようと思わず、だんだんと眠くなる。そういえば卵茸の女性が現れるようになって、夢をみない。いやこれが夢なのだろうか。そうしているうちに寝てしまった。
次の日も四時頃目が覚め、一階におりた。食事が用意されている。
トーストとハム、トマトそれに今日は目玉焼きもあった。女性はすでにいなかった。
食べる前に庭を見ると、雨に濡れた卵茸が少ししおれている。
その日は童話の創作が進み、一つの作品ができあがった。ただの趣味で書いているのだが、小説の掲載サイトに載せている。ほとんど反応はないのだが、ときどき、子供に読み聞かせたらとても喜んだ、などのコメントがくることがあり、それがとても幸せな気分にしてくれる。
書き終わったときに居間の電話が鳴った。時計を見ると五時だ。
「今、成田に着いたのよ、リムジンで新宿にでて、そこからタクシーで帰るわ」
家内だった。今日もどる日だったのだ。
「そうか、食事は」
「いらない、機内食食べたばかり」
「わかった、気をつけてな」
友達とハワイに行ってきたのだ。ハワイは一度も行ったことがない。のんびりできていいそうだが、行く気になれない。どちらかというと、ヨーロッパとかオーストラリアなら行ってみたいとも思うが、今は日本のひなびた温泉の方がいい。
部屋に戻って、書き終えた原稿を読み直していると、総菜のデイリーサービスがきた。いつもよりだいぶ遅い。
「遅くなってすみません、雨のせいか市道が混んでましてね、今日はお肉の料理ですよ」
「すみません」
「今日は強い雨じゃないからいいけど、台風が発生したそうですね、気をつけてください、明日から、二人分ですね」
「ええ、家内が帰ってくるので」
「よかったですね」
おばさんは私に総菜の入ったパックを渡すと帰って行った。
牛肉のソテーで食事を終え、居間でテレビを見ていると、玄関が開く音がした。
「帰ったわよ」
家内が大きなキャリーバックをもって居間はいってきた。
「ウクレレ買ったわよ」
「誰が弾くんだ」
「あなたよ」
そういって私を見ると、驚いたように目を大きくした。
「あなたなに、その頭」
「なにって」
「鏡見てないの、前の髪の毛ほとんど抜けちゃってるじゃない」
どういうことだろう。
鏡の前に行ってみた。変わりないように思うが、
「私が行くとき、あなた自分の髪の毛、手でかきあげていたでしょう」
そういえばそんなだったか。
「うつむくと、長くしている前髪が、目に被さるので、手でかきあげるのがあなたの癖でしょ、いっぱしの作家ぶった格好してさ」
そんなつもりはないのだが、確かに手で髪の毛を上に撫でつけるようなことをしていた気がする。ずいぶん若い頃の話だろうに。
「八十になっても、髪の毛はたっぷりあるんだって、いばってたじゃない」
「そうかな」
家内はそんなことをいいながら、旅行鞄をあけた。
ウクレレがでてきた。
「ほら、あげる」
手渡された。
「これは宝貝」
きれいな貝をいくつもだした。男の孫が二人いる。それへの土産だろう。わたしもそのほうがいい。
「これは、ほら、孫にあげるのよ」
貝などでできているレイがでてきた。女の孫たちへの土産だ。自分の子供たちには、免税店でウイスキーやら、チョコレートやらをかいこんでくる。いつものことだ。
そのとき、居間のガラス戸があいた。
家内が見た。
「きゃー」と、大きな声を出すと、その場に倒れた。
中に入ってきたのは、髪の毛は抜け落ち、片目がとろけて、鼻は欠け、唇は紫色に腫れ上がり、頬がそげた顔の女である。着ている着物は雨に濡れ、垂れた乳房が外に飛び出している。
女は濁った片目で私を見た。
「さようなら」
そいう言うと、庭に戻っていった。
家内は倒れたままである。
あわてて、抱き起こして、名前を呼んだが動かない。脈を診ると、かすかにしか感じられない。
あわてて、救急車を呼んだ。その間なにかできないかと焦って、胸を押すべきかどうか迷ったが、心臓が止まっているわけではない。
ともかくソファーの上に寝かせた。
救急車は運良く五分もすると到着した。隊員は素早く注射を打ったり処置をして、救急車に運び入れてくれた。私も戸締まりをして、一緒に乗った。いつも行っている都内の病院を言うと、そこにいってくれることになった。
「ハワイから帰ってきたばかりで、急に倒れました」
「その前になにかされましたか」
「いえ、旅行から家にもどって、居間に荷物を持ってきて、ひろげていました」
卵茸の女が現れたなどとはいえなかった。
「お疲れになっていたからでしょうね、八十一でしたか」
「はい」
「心拍がかなり弱っています、アドレナリンを打ちましが、安心はできません」
私は、二人の子供に携帯電話をかけた。二人とも都内にいる。
病院には二十五分ほどでつき、すぐに救急病棟に入り、処置が始まった。
そうこうしているうちに、二人の息子が駆けつけてくれた。
「かあさんどう」
「まだわからないそうだ」
「どうしたの」
「ハワイから帰ってみやげを広げているときに急に倒れた」
「もう歳だから海外旅行はよしたほうがいいといってたのにさ」
医師がやってきた。
「手を尽くしたのですが、力及びませんでした。お亡くなりになりました」
私はあぜんとした。
息子と一緒に、家内のところにいった。点滴やらをつけられた家内は静かに寝ていた。
「循環器内科にかかっていらしゃいましたね、電子カルテをみると、ちょっと不整脈があったようですね、血圧の薬は飲まれていましたか」
「飲んでいました、旅行中はわかりませんが」
「心臓の動脈に軽い血栓があります、そのようなことで、弱っていらしたようですね、担当医は注意していたと思います。ニトログリセリンも処方されています」
家内は薬のことをあまり言わなかったので、わたしもきにしていなかった。
その夜、家内は病院に置かれ、明日、書類を作ってもらってから、いえに戻すことになった。
「おやじは、一度家に帰りなよ、俺たちがやっとくからさ、朝電話するよ、おやじもたおれられちゃこまるから」
長男の薦めで、タクシーで家に戻った。夜中の二時近い。
息苦しい、重いと言うより、考えることができないような状態だ。部屋に明かりをつけると、土産が床に散らばっていた。
ふと、庭を見ると、つけた明かりに照らされて、食い荒らされてぼろごろの卵茸がだらんとなっていた。ナメクジが一匹、柄の下の方にかじりついていた。
ガラス戸の鍵は開けなかった。
茸道


