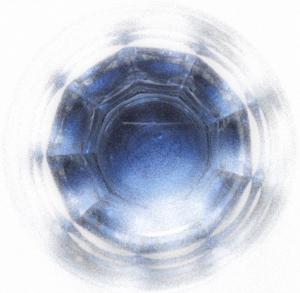母性神話とスティグマ
about 2
子どもが生まれて七か月が経とうとしている。
予定日は十一月だったのだが、二十六日も早く出てきた。帝王切開だった。
鬱の既往歴があってバイジェンダーで、正直子どもを産むのは荷が重く厳しいと感じていた私が自然妊娠して、今日まだ生きていることについて、少し書こうと思う。
結論から言うと、妊娠しても子どもが生まれても私は私で、ほとんどの経過が「ふつう」や「正常」とは違っていたし、この(今のところ)女性固有としか言い難い体験を以てしても、私がふつうの女性に変化することはなかった。
◇
妊娠の実感というのは、時間をかけてじわじわときた。人によって、それはつわりの始まりであったり、エコー画像に写る胎芽や胎児の影であったり、胎動を感じた日であったりするのかもしれない。けれど、初期の間は、いかんせん、自然流産の可能性もあるので、私は妊娠がわかってから一月以上の間、半信半疑であった。最初の健診のエコー下で、こないだまで何もなかったはずの子宮内に、胎嚢が出現しているのを見た瞬間から、それは自分とは異なる存在であること、つまり、ポリープなどとは全く異なる一個の生命であることを強烈に感じたのではあるが。心拍が確認されても、見るたびにヒトの形へと変化していくのを目の当たりにしても、なかなかそれが生まれてくるという実感は持ちがたかった。
「つわり」は一週間ほどで落ち着いてしまった。吐き気やめまいに耐えられず、胎児に害がないとされる漢方薬を使ったら、あっさり引いた。といっても、味覚が変わり妊娠期間を通じて食事はまずく、たくさんは食べられず、あれもこれも食べてはならず、体調はよくて六割程度で、動悸と貧血にもかなり苦しんだし、全然健やかではなかったのだが。
妊娠十週、十二週を過ぎ、胎児の性別分化が始まる頃…というアプリの説明文を目にした頃からだろうか。少しずつ、それ(妊娠)は私の中で現実味を帯びていった。そして一般的にはつわりも落ちつき情緒も安定するといわれる安定期に私は深刻な鬱状態に陥った。
端的に言って、「産む」イメージがし難かった。
それは胎児を大切に思うこと、つまり、一人の人格ある人間とみなし、無事に生み出してやりたいと願うこととは別の地平にある大問題なのだった。
最近流行りの「無痛分娩」については、誰も理解を示さない家族背景である。「水中出産」すらナンセンス、あり得ないという反応だから、自然分娩一択である。なんで産むのは私なのに、その方法を選ぶ権利が私にないのだろうか。
出産によって死ぬだろう。いや、いっそ出産によって死にたい。
なぜ死にたいって、私の存在が子どもの健やかな成長に影を落とすのが怖いからだ。女に生まれたことを肯定したことが一度もない自分。生まれてくるのが女の子であっても、男の子であっても、私の暗さが、抱えている苦悩が、子どもの人格形成を歪めるのが怖い。物心つく前に死んでしまえば、子にとって「母親」とは伝説上の存在になる。その方がいい――そんな観念に囚われ、死に損なった今でも囚われている。
だが結局のところ、私は自然分娩に挑むことにはならなかった。
低置胎盤や前置胎盤というのはふつう妊娠二十週頃から指摘されるものだそうだ。なのになぜだか、私の場合は二十六週にもなって唐突に「胎盤の位置が低い」という話をされた。それまで問題なのは私のメンタルであって妊娠自体は何の問題もなし、という認識だったので、「ふうん、そうなの?」という感じだった。説明も、胎盤の位置は今後上がっていくかもしれないし、もしかすると帝王切開になるかもしれないが、十分に上がれば自然分娩できるから、と楽観的で、はっきりしなかった。そしてそのはっきりしてくれない状況が、出産の前週の三十五週まで続く。
低置胎盤で帝王切開という体験談を、私はたまたま見かけて読んでいた。開腹手術なのに麻酔が効かなくて死ぬほど痛かったとか、結構怖い話が散見される。
ただ正直、切るなら最初から切ってほしい。と思った。
産めるかもしれないからと自然分娩を試みた挙句、緊急帝王切開というのが最悪のシナリオに思えたからだ(実際それが一番ハードモードであると思う)。
さて、私の胎盤は二十六週から少しも上がっていかなかった。お腹側(外側)についていると胎児の成長に伴って上がっていきやすいが、背中側(内臓・背骨側)についていると動かないらしい。で、三十四週にMRIで調べた結果、胎盤は見事に背中側についていた。それでもその日の説明では、三十八週頃に予定帝王切開の可能性が高い、と言われた。
事態が急転したのは、三十五週だった。「偽陣痛」で一晩観察入院する騒動があり、その翌々日の健診で、「辺縁前置胎盤」と診断された。低置胎盤が「治る」どころか、診断名が一段階重くなったのである。そこでようやく「自然分娩はできない。三十七週で予定帝王切開」と告げられた。そして、遅くとも翌週から管理入院すべきと言われた。少量の出血が続いていたからだ。――で、その日の未明に、私は再び少量の出血を起こし、緊急入院することになる。
ふつうは、臨月が近づいたら、お産の体力をつけるために、妊婦は積極的に歩けと指導されるはずだ。そして、安産イコール、正常な陣痛を起こすことである。
けれど私の場合は、陣痛を起こしてはいけないのだった。歩くのはトイレまで、病室を出る時は車椅子で送迎、ベッドから足を下ろして座っているのも駄目、ずっと寝ていろという。入院すると同時に張り止めの点滴に繋がれ、二十四時間点滴だから、シャワーどころか、着替えすら自由にできなくなった。都度助産師に一時的に点滴の管を外してもらわないと袖が抜けないからである。この点滴は変な薬で、手が震え、動悸がして、身体が火照り、何日かすると掌が異様に痒くなった。緊急帝王切開に備えて胎児の肺の成長を促すために、とステロイドは打たれるし、あれよあれよという間に話が大きく、深刻になっていく。
そして私は、そんな点滴を入れて安静にしているにもかかわらず、入院中に二度も偽陣痛を起こした。一日おきに点滴の量が増えてゆき、この点滴はどこまで増やせるのかと尋ねると、「次はもう緊急帝王切開だ」と返ってきた。やっと妊娠三十六週を迎えた朝である。
入院生活に対しても、手術に対しても、私は不思議なほど強気だった。何しろこちらは死ぬつもりでいるから、子どもを無事に出してやるためならなんでも受けてやるという意気込みだった。二週間耐えるつもりで入院したのに、一週間で手術とは、悔しかった。胎盤を剥がした後出血が止まらない場合は全身麻酔だから、と私が一人で説明を受けた。
◇
今は六人に一人が帝王切開だそうで、そのお産のスタイルはもはや全然珍しいことではない。自然分娩した友だちに帝王切開だというと「帝王切開も立派なお産だよね」という謎のフォロー(?)がいただけたし、高齢の親族の大半も「お腹切らなきゃいけないなんて大変ね……」という反応だった(約一名、「帝王切開=陣痛を経験しなかった=無痛分娩」と勘違いした人がいたが)ので、よくあるとされる「ラクできてよかったわね」的なイヤミの被害には(ほぼ)遭わなかったのだが……。
私個人に限っての感想をいうと、帝王切開はあくまでも「手術」だった。(腰椎麻酔の前段階の表面麻酔がなかなか効かず、術後は吐き気と震えで最悪の気分だったので二度とは受けたくないし他人にも勧めないし、麻酔がこんなに合わない体質なら私は無痛分娩だって向いてないだろうと痛感したが……自然分娩させられずに済んでよかったと思っている面はある。)産めないから、手術で取り出してもらった。というのが率直な認識。
ぎりぎり早産児、かつぎりぎり未熟児で誕生した息子は産声こそ上げたが、ほどなく黙ってしまい、呼吸が安定しないとのことで、そのままNICUに連れて行かれてしまった。異常がなければ帝王切開でもできることになっていた「カンガルーケア」は、なかった。
私の身体が、何が起きたのかわからず動揺していた。出産に向けた諸々のラストスパートの四週間がなかったのである。臨月に入ったばかりでこれからという時に、突然お腹を切られ、赤ちゃんは取り出され、側にいない。抱くこともなく、泣き声も聞こえない。
「初乳」が大事だからと時間ごとに助産師が搾乳しに来たが、まるでもって出ない。
――たぶん、私の身体は「死産」の疑いを抱いていたと思う。なんだかわからないが、突然赤ちゃんがいなくなったのだから。
あるいは、まだ妊娠が継続しているような幻想があった。産んだらお腹はぺたんこになるのかと思っていたが、そんなことはなく、ずいぶんと膨らんだままだったし。
赤ちゃんとの再会は手術からおよそ二十八時間も経過してからだった。手術当日は「寝たきり」を命じられ、実際起き上がれたものではなく、翌朝も術後の処置や歩くリハビリなどのスケジュールが先にあったからだ。
母子にとってあまりにも長い時間離れてしまったと感じた。
車椅子でNICUに連れて行ってもらい、対面した息子はお腹の中にいた元気な子どものイメージとはかけ離れていて(お腹の中ではかなり活発で、医師や助産師に呆れられるほど元気な子だった)、これがあなたの子どもと言われてもおよそぴんと来なかった。
それでも不思議なもので、抱いてみて泣かれてみたら、水滴になるほども出なかった初乳が出始めた。お乳は子が外に出たら自動的に出るものではないらしい。その子どもが生きていることを確信して、初めてスイッチが入るらしい。上野のシンシンが最初に出産した時、産声の弱弱しかった仔を抱くのをやがて諦めてしまったのを、薄らと思い出した。
赤ちゃんに関する情報も錯綜していて、そのことも私を混乱させていた。人によって言うことがまるで違うのである。産前、ある人は出産当日から母子同室できるだろうといい、ある人はおそらくNICUに入院と言った。産後、ある人はたぶん明日にもNICUを出られるだろうといい、またある人は赤ちゃんは長期入院になり私が先に退院して毎日母乳を届けに通う生活になり得るとまで言った。術後は貧血のためか朦朧として理解力も落ちていて、小児科の先生の話はポジティブなのかネガティブなのかすらよくわからなかった。――幸い息子は三日で出てきて、残りの入院生活は母子同室でき、一緒に退院できたのだが。
その期間が一番幸福感に包まれていたかもしれない。ベッドサイドまで持ってきてもらえる産後食はおいしかったし(食べても気分が悪くならないこと自体が実に七か月ぶりくらいだった)。子どもを返してもらえたことが何よりも嬉しくて、夕方から何時間も泣きやんでくれなかったりしても特に苦にならなかった。せっかく危険といわれた手術だったのに、死ねなかったなぁ……というがっかり感は薄らあったけれども。
◇
二十代の頃、鬱で何年も通院して薬を飲んでいた。でもそれはもう終わったことで、私は就職面接でわざわざその話をすることもなかったし、社会的には何年も「ふつうの人」で通っていたのだ。
それなのに妊娠した途端、私は再び「精神疾患の既往歴」を保健所にも病院にも開示しなければならず、生む前から「そういうお母さん」として扱われることになってしまった。おまけに性別違和のことがあるから、母乳育児主義の病院からしたら相当厄介な取り扱い注意の患者だったわけである。産前産後の不安定な時期に備えて妊娠中から精神科にかからされたし、そのために古巣のクリニックへ紹介状を書いてもらいにも行った。
産後の生活をイメージしないと。と、各役職の人から言われた。
核家族であるし、夫の職業柄ワンオペになりがちなのは予想されたが、「産後」というものがあるという前提に立ちたくなくて、イメージはしなかった。最後まで。
身内を頼れないなら公的支援を受けないと、一人で育てるなんて絶対に無理ですよ。と皆がいう。保健師さん、助産師さん、病院のソーシャルワーカーさんまでもが。
実際に無理だったが、無理だ、無理だと言われ続けて無理になった感もある。
最初の一か月くらいは、未熟に生まれた子どもが問題なく育つのか心配で必死だったと思う。病院の指示通り、授乳やミルクの補足量、おむつ替え・排便の時間を逐一記録し、自主的に体重も毎日測ってモニターしていた。体重増加は大変なプレッシャーだった。一か月健診で発育が大変良いと言われた時、安堵で疲労が押し寄せたのを覚えている。六週間実家にいた後、自宅に戻った。生後二か月くらいの頃は一番頑張っていて、家事もなんだかこなしていたし、子どもに対しても過剰なくらい一生懸命構って遊んでやっていた。
授乳とミルクと両方やるのは大変なので、いずれミルクを卒業できたらいいと頑張りはしたが、そうはならなかった。生後一か月頃がピークでだんだん出が悪くなり、食欲のある息子は哺乳瓶の方がよくなって母乳を拒否するようになった。子が吸わなくなると途端に乳の出る身体が気色悪くなり、私の方では性別違和が再燃した。それで母乳量維持のための搾乳もやらなかったからか産後二か月半で生理が再開し、息子もいよいよ嫌がって、生後三か月で卒乳してしまった。あっけないものだった。完全もしくはほとんど母乳で育てている人によると、母乳パッドというものはあるがしみ出してしようがなくて、お宮参りに着物なんか着ようものなら着物に染みてしまって大変……などという。私など母乳パッドはついに一度も必要になることはなかった。
妊娠はしたが前置胎盤だし、その子どもは生まれたが帝王切開だし、授乳も一応は試みたがほとんど真似事みたいで、なんだか私らしいな、と思う。
生まれてすぐの緊張感や、赤ちゃんに何かあったら、という恐怖心が薄れていくにつれて、鬱は鬱らしくなっていった。
夫に預けて外出をしてみれば、町で目に映る素敵なものすべてがもはや自分には縁のないものになってしまったように感じられて、余計に虚しく、寂しくなった。
それは決定的でショックな出来事だった。妊娠中の鬱は、なんだかんだ言ってもコロナのせいで、感染警戒のため旅行どころか食事にも行けないし、ワクチンを打つ打たないで悩まなくてはならなかったし、あのデルタ株の第五波で家に籠っていてもいつ感染するかと恐怖していたせいだと思っていた。動物園の動物が檻に囚われているストレスでしばしば子育てにつまずくのと同じ原理である。薬なんかよりも必要なのは自由であって、身軽になって気晴らしに出かければたちどころによくなるに違いないと信じていた。けれど気晴らしが気晴らしにならないなら、それは病気だ。
――死ぬ気になればなんでもできるとはいうが、死ぬ気で頑張った後は死ねないと困る。エネルギーを使い果たしているからだ。気がつけば身体も心も動かなくなっていた。
授乳しないなら抗うつ剤を使うのもありかと考え、年明けから心療内科にかかり、公的な子育て支援を可能な限り受けている。鬱病と診断され、社会的にも再び病人になった。
私の周りには母親の存在に苦悩している人が多い。それは身内であり、大切な友人たちであり、職業柄出会ってきたたくさんの子どもたちであり、自分自身でもある。その語りに耳を傾けてきたから、余計プレッシャーに感じるのだが、プレッシャーに感じたところで、私は自分が思う望ましい「母親」を演じられてはいない。必要最低限の身の回りのお世話ができているだけである。
巷には覚悟がないなら避妊しろとか(女にその選択権は本当にあるだろうか、夫婦や両家の関係があって)、堕ろせばいいとか(そんなに簡単な話ではない)、そんな母親なら死んでしまえというような言葉が溢れている。だから死にたいのだが思うようにいかない。
ただ一日、一日が過ぎていく。
子どもは自分のペースで否応なしに育っていく。今は幸せそうだがいつか、自分の母親が幸せでないことに気づく時が来るだろう。母親が自分を愛していても幸せではないことに。
子どもにはただ、健やかに幸せに生きていってほしい。人としてのモラルと優しさは身につけてほしいと思うが、それ以外のことは何も望んでいない。天才に育てたいだとか、特定の職業に就かせたいとか、世界へ羽ばたかせたいとか、そういった欲望はいっさい抱いていない。どんなことに興味を持ちどう生きようともこの子の人生であって自由だと思うからだ。けれど、子どもが些細な関心を示す度に、将来は野球選手とか宇宙飛行士とか、ナントカ博士かと、無邪気に夢を見るのが自然な親の姿かとも思う。まだ何者でもなく、何者にでもなれそうな我が子を見て、その将来に何の夢も描けない自分もどうなのかと思う。
五年前に喧嘩別れした親友に、私を「毒親」と思うかどうか訊いてみたいものだ。
母性神話とスティグマ