
パニックの町
九州の新聞記者川畑久野は、息子を連れて車で帰省中に事件に遭遇する。温泉で若い女子の死体が上がる。地方の町で起きた殺人事件とその推理。
五月二日(水曜日)

車は『渓山荘』に向かっていた。南町で唯一の温泉宿だ。窓からは見慣れた町並みの風景が広がっている。今回で何度目の帰省になるだろうか。久野(ひさの)はハンドルを握りながら思った。
運転する白のクラウンは、町のはずれに差しかかった。
女がこちらに向かって手を振っている。背は高く眼鏡をかけていた。真っ赤なスーツケースを手にしている。
「なんだろう。車、停めるわよ」
息子につぶやいた。徳広は小さく首を縦に振った。
「すみません。いきなりですが、南陽台まで送っていただけないでしょうか」
若い女は大きな声で窓越しに叫んだ。久野は窓を下げて、
「乗っていきなさい。同じ方角だから」
と安請け合いし、後ろのドアを開ける。女は、先に後ろのトランクに荷物を入れていいか、と訊ねた。久野は、いいわよ、と答え、入れるのを手伝ってやった。女はトランクを閉め、後部座席に尻を載せドアを閉める。女は、ありがとうございます、と首をすくめて遠慮がちに礼を言った。
「ここら辺の人?」
「いいえ。旅行者です。他県のものです」
女は名前をすぐには名乗らなかった。
「稲和(いなわ)県までどうやって来たの?」
「新幹線に乗って。気候もいいし、レンタカーを借りてドライブしようと思ったら免許証を家に置いてきてしまって」
「それはうっかりね。わたし、南町のことならくわしいのよ」
「そうなんですか」
「この町で育ったから」
「よかったです」
「またどこかで会えば町を案内するわ」
「母さん、いいの?」
声変わりした中三の息子が口を挟む。
「まあいいでしょ。旅は道連れっていうやつよ」
「ほんとうに南陽台まででいいので。帰りはバスかタクシーを使うので」
「遠慮しなくてもいいのよ」
「あの、いまは何時ですか。私の腕時計、遅れてしまうので」
「二時半です」
久野の代わりに徳広が携帯を開いて時刻を教えた。
「どうもありがとう」
話すうちに車は中心地を抜け、田園地帯に入った。向こうに山がそびえている。山の中腹からは麓一面に田畑がつづいていた。町全体を上から見下ろすようにしているのは、猪高山の切りたった嶺だ。
隣に座る徳広は、知らない大人の女と車内で一緒になり、どんな会話をしていいものか、ためらっている様子だった。
女は淵井絵美と名乗った。肩の下までありそうな長い髪を後ろで束ねている。
南町を一五分ほど走ったころのことだった。場所は、両側が田圃でその真ん中を突っ切るような平坦な一本道である。田圃を抜けて川を越え、カーブに差しかかったとき、車の様子がおかしくなった。次の瞬間車体が傾き、突然ハンドルを取られた。左のガードレールに当たりそうになった。
「危ない!」
叫ぶと急ブレーキを目いっぱい踏み込む。久野の顔面は蒼白になり、タイヤの軋む音と同時に車体が右に振られた。車は右カーブで車線を塞ぐように斜めに停まった。幸い、対向車は来ていない。助かった。危ういところだった。交通量が少ないとはいえ、ダンプカーでもやってきて衝突したら自分も息子もひとたまりもないだろう。命を落とす危険な場面になっていたかもしれない。
ハザードランプを付ける。数秒運転席から動けなかった。
「母さん、なにが起きたの?」
徳広が久野の顔を覗き込む。語尾が震えていた。若い女は押し黙っている。
「みんな大丈夫ね?」
「おれはへっちゃらだよ」
「私も心配いりません」女の声は少し沈んでいた。
久野は思った。タイヤがおかしい。突然異変が生じたに違いない。
「タイヤがパンクしたみたいね。見てくる」
シートベルトを外してドアを開け、席を降りる。左右の前輪を見た。
案の定、左のタイヤだけが破裂し空気が抜けていた。上着の胸ポケットから携帯を取り出し、番号を調べてJAFに電話した。
「もしもし。あの、いまさっきまで運転していた車のタイヤがおかしいんですが」
「会員番号は何番ですか」
「一〇一〇XXXXXXXXです」
「川畑久野様、ご本人様ですね」
「はい、そうです」
「いま、お車はどういうふうに停まってますか」
「車線を塞ぐようにして斜めに停まってます。ハザードをつけて」
「スペアタイヤはありますか」
「この前使って切らしちゃいました」
「場所はどこですか」
「国道32号線の稲和県猪里(いのさと)市内です。矢能川を越えたところでパンクしたみたいで」
「どんな色で、車名やナンバーはわかりますか」
「白のクラウンで、内海、ま、10―16です」
「わかりました。すぐに係のものがまいります」
厄介なことになった。いままで、ここへ来るのに、こんな目に遭ったのは一度もない。家を出る前は異常などどこにもなかった。途中、ガソリンスタンドに寄ったときもタイヤの空気圧に異常は見られなかった。どこかで細工をされたか、嫌がらせかいたずらの類いに違いない。
ドアを開け、中に入って徳広に説明した。
「タイヤがパンクしたわ。もしかしたらレッカー移動になるかも」
「じゃあ、しばらくこの車に乗れないじゃない」
「そのときはしかたない。諦めましょう」
JAFが来るまで車の中で待機し、徳広の学校での様子などを訊いていた。
四〇分もすると、バンタイプの青い車がやってきた。久野はJAFの係員に、タイヤの状態をくわしく報告した。
「これはタイヤの横になにかが刺さって破裂した様子なので、応急処置ではだめそうですね」
制服姿の係の男はタイヤを見て手で触った上で、渋い顔をした。
「どうするんですか」
「近くの適当な場所までレッカー車で移動します」
「えー、そうなんですか」
「もうしばらくお待ちください」
担当の係の男は、どこかに電話を掛けて状況を報告した。
担当の男がどこかに電話を掛けているあいだに、久野は旅行かばんの中から財布と携帯、化粧道具を取り出し、トートバッグに移し替えた。旅行かばんは車中に置いていくことにした。どうせ着替えと洗面用具ぐらいしか入っていない。
やがて、荷台にレッカーを下げた青いトラックが到着した。最初に来た係員と二人がかりで車の前部をジャッキで持ち上げ、レッカーで前輪の底を浮かし、そのままゆっくり車を運び去った。
「近くのガソリンスタンドまで持っていきますので」
若い係員は訛りのある標準語で教えてくれた。
「そこで修理するわけですか」
久野は試しに訊いてみた。
「ええ、修理はできますよ。時間は少しかかりますけど、どうしますか」
「これから出かける途中だったので、バスに乗って行きます」
「それでは用事が終わったころにこちらに電話をください。いまから一時間ぐらいで修理は完了すると思います。費用については無料ですので」
JAFの男は携帯番号を名刺の裏に書いて久野に手渡した。
不慮の事故に見舞われ、川畑親子はバス停まで歩いた。絵美もついてきた。道路沿いに民家が立ち並び、それも途切れると緑の草の伸びた田畑や草地がずっと奥の方まで広がっていた。
久野は、虫の予感で南町に来るのを拒まれているような錯覚に囚われた。どこかで見られているような気もした。そんな妙な気になるのはここに来て初めてだった。周囲を見回したが、不審者らしき影はない。旅の女はにこにこしながら、ついてないですね、と漏らした。そうかもしれない。思い直した。
事故現場からバス停まで歩き、バスを待った。バスを待つあいだ、トラブルに巻き込まれがっかりした気分を変えようと思った。明るく振る舞い、南町での思い出話を徳広に聞かせてやった。痩せて背の高い女は興味深そうに聞き入っている。
子どもの頃、夏になると滝の下の岩場から川に飛び込んだものよ。思い出深い川だったわ。きっと今も、清らかな水をたたえ、太陽を浴びてきらきらと流れているはず。来る途中で学校がいくつかあったでしょ? 昔のまんまだわ。古びたコンクリート造りの校舎でね。南町の目抜き通りにある公立中学校と公立高校、大通りから少し離れたとこにある工業高校。いまじゃエアコンぐらい入ったのかしら。でも建物はみんな古くなったわ。母さんもだけど。地元の駄菓子屋もあるはずよ。そこには小学校時代から入り浸っていた。
高校時代は、赤い暖簾が目印の中華料理店で友人とよくだべった。町で二、三軒しかないうら寂しげな佇まいの古びた喫茶店もあると思うわ。そこの一つだけは特別な思い出の場所なの。初恋の彼とクリームソーダを飲んだのよ。まるで昨日のようだわ。初恋の話はお婆ちゃんたちには内緒よ。
長話をさえぎるように、バスが来た。バスの側面の塗装は色褪せ、部分的に色落ちしているような市バスだ。南陽台行きである。バスに乗った。空いている席に座った久野は、後部座席の絵美に、
「わたしたち親子は、『渓山荘』という温泉に入りに行くの」
「温泉ですか。いいなあ」
「絵美さんもよければ、一緒に来ない?」
「いいんですか? じゃあお言葉に甘えて」
渓山荘近くでバスを降りた。バス停では他の客も一緒に降りた。
絵美はスーツケースを引きながら、二人についてきた。絵美が話し掛ける。
「主婦の方ですか」
「違うの。夫はこの世を去り、わたしが働いているの」
「いけないことを訊いてしまってすみません」
「いいのよ、別に」
「二人暮らしですか」
「いいえ。義父母と四人暮らし。少しのあいだだけ、実の姉がわたしや夫の代わりをしてくれた。その姉も病気で他界したけどね」
「ごめんなさい。辛いことばかり言わせてしまって。仕事は何をされているのですか」
「N新聞で記者を長いことやってるわ」
「へえ、すごい! 立派ですね。インテリじゃないですか」
「他にできることがないだけよ」
久野は褒められ、少し上機嫌になった。
「名前を訊いてなかったですね」
「ああ、そうだわ。うっかりしてたわ。川畑久野です。よろしくね」
「徳広です」
「こちらこそよろしく」
絵美は、あらためて二人に軽く会釈をした。このとき、その若い女がピンク色のロングスカートを穿いているのにやっと気づいた。
バス停で降り、一〇分ほど歩いた。町の鐘楼が四回鳴るのを聞き、温泉宿に着いた。いつもなら温泉の営業が始まっている時刻である。
が、どういうわけか、建物入口の周囲を大勢の町民が囲んでいる。客というより野次馬に近かった。パトカーに救急車も停まっていて、どう見ても様子がおかしい。なにが事件があったに違いない。適当な人を探して、訊ねてみた。
「いけんしたとです」
「死体が、女の水死体が上がったらしい」
その場に居合わせた男は、興奮気味に語った。物めずらしそうな興味津々の顔つきだった。
「中学生か高校生くらいだって」
別の人が付け加えた。
「ほんとうに?」久野は頓狂な声を上げた。
「物騒やわ」
「ほんとね。こんな田舎町で若者の死体が出るなんて」
「どこの子かしら。可哀相に」
町民の口からは信じられないという声があちこちで聞こえた。それに加えて、平穏な町で起きたミステリー事件に首を突っ込みたい気持ちが滲み出ていた。
事件だ。明らかに奇怪な事件の臭いがする。それは嫌な予感を伴っていた。さっき感じた虫の予感と合わさり、慣れ親しんだ故郷が急に色あせてきた。くたびれたバスの塗装どころの比ではない。生き生きとした青い草花があっという間にしおれたようであり、牙をむいた異国の地に立っているようでもあった。そんな憂鬱な気分に襲われた。と同時に、軽いめまいがした。
「女の水死体。嫌な気分ね。悲劇ならその序章。恐ろしい舞台の始まりかも」
旅の女は赤の丸眼鏡を光らせ、ピンク色のスカートのフリルをしきりに触っている。
久野は絵美という女の言葉を真に受けず、気を取り直した。野次馬をかき分け、入口の前に立つ若い警官の制止を振り切る。中に入り、沓脱で慌てて靴を脱いだ。どかどかと大股で廊下を急ぎ、女湯に入り込む。そこにも制服姿の警官一人がいて、その警官が電話を掛けていた。
「下がって、下がって」
若い方の警官が追いかけてきて規制テープの前で制したが、無視した。トートバッグからデジカメを取り出し、五、六枚撮る。もう一人の警官は本署に連絡しているのか、まだ続きを報告していた。
「裸の少女です。年齢不詳」警官は一息ついて唾を飲み、続けて、「透明な特大のビニール袋に包まれて、被害者はうつ伏せで浮いています。ええ、被害者です。血の気はないです。死んでいる模様。ピクリとも動きません」
そのあいだに、現場写真と死体をさらに一〇枚ほど撮影した。異様な光景だった。淡いピンク色の浴槽の周りに黄色の規制テープが張られ、死体がうつ伏せでぷかぷかと浮いている。短めの黒髪で、腕と足は小麦色に焼けている。あまりの光景に動揺してカメラを持つ手が震えた。愕然として腰を抜かしそうにもなった。
「発見者は渓山荘の番頭。発見時刻は五月二日水曜日の午後四時です。鐘楼が四回鳴ったから間違いないと。ちょうど営業前の時刻に見つけたちゅうて。浴槽の掃除中にはみつからなんだとか。一番風呂に出入りした客はおらんとです」
大きな声で喋っていた、年長にみえる警官は向きを変え、そこで壁に向かって小声で喋った。
「ええ、そうです。確かに、交番に遺体発見の電話がありもした。四時きっかりに」警官は背中を丸めて続け、「それはこちらで確認済みです」
*
「女のだれかさんが、湯船に浮かんでるわ。そこは渓山荘。死んだままで水泳の練習かしら。温泉の入浴は無理ね。鐘が四回鳴ったわ。ちょうど四時ね」
妙な電話である。しわがれた老女の声だった。どこか作ったような、感情のこもっていない、冷酷な訛りのない声だった。電話は一方的にかかってきて、遺体発見の旨を告げるとプツリと切れた。
「もしもし、もしもし」
猪里市の志方交番に最初の電話がかかってきたのは、その日の午後四時過ぎである。ふだんなら交通事故や山や川での行方不明者を捜索するぐらいが仕事の大部分を占めているありふれた田舎の交番である。その交番に詰めていた警官二人はすぐにそこを出て、慌ててパトカーで渓山荘へ向かう。警察へ掛かってきた遺体発見の電話の真偽を確かめに行ったのだ。
まさかほんとうの事件だろうとは思ってなかった。警察への悪質ないたずら程度にしか思ってなかった。退屈な田舎でも、警察をからかう輩などいくらでもいる。
「ほんとうじゃろうか」
電話を取った若い警官は、先輩の警官に訊ねた。
「まさかと思うが、老婆がイタズラ電話なんぞするかのう」
年上の警官はハンドルを握りながら答えた。
「あれは本当に老婆の仕業なのかち思うちょる。老人にしては言うことがはっきりしすぎとる。声色を使っておるかもしれん。それになにかと見間違うたんじゃなかか」
三分もしないうちに二人を乗せたパトカーは渓山荘に到着する。人だかりができていて、只事ではないと若い警官は思った。緊張して中に入ると、女湯で目に飛び込んできた光景に茫然としてしまった。
*
新聞記者としての血が騒ぐのとは別に、なにかねっとりした気味の悪さと得体の知れなさを覚えた。
「ところであんたはだれね? 警察署まで来てもらえるかね」
さきほどの若い警官から呼び止められた。
「わたしはN新聞の社会部の記者です。きょうは久しぶりに帰省して、温泉に浸かりにきた客です」
「記者であろうとなかろうと、念のため事情を訊かせてもらおうか。それが規則だから」
電話を掛け終えた警官がダメを押す。
まもなく稲和県警のパトカー二台が現場に合流した。県警本部の人間らしいスーツ姿の刑事が車から降りてきて死体現場に足を踏み入れた。
年長の警官は若手の警官一人と県警の刑事二人を現場に残し、久野の腕を強引につかむと外に連れ出し、パトカーへ誘導した。周囲にいた見物人が、犯人か、犯人じゃなかかと、騒ぎ出した。手で掻き消すように違うとジェスチャーをして首を振る。警官に、ちょっと待って、と言い、その場にいた息子を呼び止めた。
「徳広。悪いけど、ひとりで内海の自宅に帰れるよね」
「帰れるけど」
「こんなことになってしまって申し訳ないわね。すまないけど小遣いを渡すから、お爺ちゃんのところに戻ってちょうだい」
「いいよ、分かった。しかたないよね」
徳広は明るく答えた。久野が疑われていて、身の潔白を話さねばならないことぐらいわかる年頃だ。もう中三で来年は高校受験。迂闊に事件の衝撃を与えない方がいいに決まっている。
「母さん、仕事するんだろ? 忙しくなりそうだし」
「悪いねえ。どうやら休日を返上して仕事しなきゃならないようだから」
久野は財布から一万円札を出し、徳広に手渡した。
それまでおとなしくしていた絵美がなぜか、思いだしたように言った。
「きょうって何曜日かしら?」
「きょう? 水曜日だよ。そういえば、水曜に水死体?」
徳広はおかしなことを言った。
いや、おかしくない。確かに日付は水曜であっている。そのときは言葉の綾だと深く考えなかった。先に乗り込んでいる番頭と後部座席に並んで座り、パトカーは現場を離れた。
車内は重苦しい雰囲気だった。後ろを振り返った。後方の窓から徳広と絵美の姿が小さくなっていく。いままで走ってきた道をUターンして、猪里警察署までパトカーに揺られた。
なんでわたしが――。そう思ったが、警察署で事情を話さないと自由にしてくれそうになかった。とにかく現場の状況とアリバイを話せばすぐに解放されるはずだ。それより事件記者としての予感が気がかりだった。これで終わればいいのだが。
*
「被疑者の手がかりは?」
猪里署の会議室で、刑事課課長の神取は部下に訊ねた。
「少女を殺したということで、怨恨のセンは薄いかと。強盗もありえませんし」
「嫌な予感がするなあ」
「そうですか。たしかに遺体の現場は異様でしたが」
「初動捜査で指紋も足跡も見つからんと?」
「ええ。いまのところ、関係者の者以外はないらしくて」
「この町に少女ば殺すような大人はおるんか」
「さあ、まずおらんとです。でも、この時期、どんなよそもんが猪里市に来とるか」
「ゴールデンウィークの最中だからか」
「そげんこつです」
「しかし、温泉の湯船で変死か。殺しだとするなら大胆な犯行じゃっど」
「鑑識が調べちょりますが、現場で被害者を見たところ、首に絞められた跡があったとか。死因は絞殺では?」
「別の場所で殺しといて、湯船に晒しものにした、というのか」
「たぶんそげなセンでは、と私も思うちょります」
「少女趣味の不審者を洗うてみるか」
「そのセンもあるかと警戒はしちょります。管内に不審者情報はいまのところありもはんが」
「それから被害者の身元と遺留品はいけんなっちょる?」
「被害者は中学生らしく、明日までに身元を判明させます。身につけていたはずの衣服は日没までにはなんとか見つけられたらと。手荷物も合わせて付近を捜索中ですが、今のところ手がかりが見つかっていないです」
「早う見つけんとな」
「全力をあげて取り組みます」
「ところで、例の遺体発見を告げた電話はいけんした?」
「年老いた女の声のようじゃち、皆は言うちょります。が、話の間と言うかスピードは速く、伝えた内容もはきはきと喋るし、老婆に見せかけ警察を惑わそうとしたち、思われます」
「かけてきたエリアは?」
「auでいうところの浦形局付近です。それも、プリペイド式の携帯電話らしくって」
「あげな携帯は、ショップに持ち込むんじゃろ?」
「はい。携帯端末を持ち込み、携帯ショップで契約するもんです」
「逆探知は?」
「番号が取れちょりまして、携帯会社に情報開示を要求する捜査令状ば現在作成中でして」
「じゃっどん、本人じゃなか人物に携帯端末を転売しよるもんもおるち聞くがな」
「全くそげんとおりです」
「とにかく番号が分かっとる以上、辿れるところまで辿ろう。そっちのセンも大至急追ってくれ」
「わかりもした」
そこで婦警がお盆に茶を二人分持って会議室に入ってきた。机に湯呑み茶碗を置き一礼して出ていった。神取課長は茶に口をつけてのどを湿らせ、
「第一発見者の番頭はなんか言うちょったか」
「普段どおりに仕事しとって、なんも異常はなかったっち」
「収穫なしか。なんも気づかんかったとね?」
「鈍そうな男じゃどん」
「つまり、なんかあっても目が節穴ちゅう」
神取課長は口を手で覆い、欠伸を噛み殺した。
「そげなとこです」
「現場に乗り込んできた記者は?」
「あれはN新聞社会部に勤めちょるベテランの女記者です。やり手で頭もよかと。偶然現場に居合わせ、記事にしようと躍起になるとでしょう」
「たしか、川畑とかいう女じゃっど」
「そうです。よくご存知で」
「若いころ、本署と関わった。参考人として調べるのか」
「ええ、そのつもりですけれど」
「うるさいタイプじゃけん、あんまり刺激せんようにな」
「はい、そのへんは如才なく気を付けちょります」
「それと、単独で勝手に取材するのは気を付けてもらわんと。向こうも仕事だからしかたないじゃろが、犯人を刺激せんようにしてもらわんとな」
「じゃろですたい」
「われわれは市民の安全を守りつつ、一刻も早く犯人の逮捕を急がんとならんち」
「おっしゃるとおりです」
「とにかく、現場付近の訊き込みをつづけろ」
「はい、承知しもした」
*
きょう五月二日はゴールデンウィークの合間だが、久野は有給休暇を取った。消化しないと上がうるさい。二日から六日の日曜日まで五日間連続してカレンダーどおりに休みをもらえた。五連休に帰省しないかと久野から息子に提案した。
大学を卒業してからも、盆と正月は帰省している。自宅から実家まで車で片道二時間程度だ。
ゴールデンウィークだというのに町には観光客が押し寄せるわけもなく、人気の少ない、豊かな自然と農業以外になんのとりえもない片田舎だ。まだ内海市の方がいくぶん都会の色に染まっていた。
久野は、勤務先で自宅のある内海市から一一〇キロ離れた猪里市に車でやってきた。
きれいな海に面した内海市に、高校生の頃から憧れていた。大学時代も、N新聞に就職してすぐに結婚してからも、内海市に住んだ。内海市と違い、猪里市は山に囲まれた鄙びた田舎である。家のすぐそばは杉の木が鬱蒼と茂っていた。周囲も広大な田圃と集落の周りにある畑しかない。その中でも南町は市の中心部で、まだ開けている方だった。
山や田畑に囲まれた自然豊かな町に二、三日身を置くだけで、心と体が自然とほぐれてくる。なんといっても久野の生まれ育った町なのだから。
「久しぶりに、例の温泉にでも寄ってみる?」
「うん」
一緒に久野の実家に帰省する道中、徳広は元気に頷いた。これまでも実家に帰省したとき、徳広を連れてなんどか渓山荘に足を運んだことがある。五月二日は徳広の通う内海市立第一中学校の創立記念日であり、休みに当たっていた。
快適なドライブだった。が、町はずれで女を乗せてから車はパンクした。おまけに、目的地の渓山荘に着くと水死体のお出ましだ。面食らった。休みどころでは済まない気がした。
猪里警察署で三〇分話した。話したと言っても、訊かれたことに答えたまでだ。
「あんたの氏名と住所は?」
「川畑久野。内海市服部町四丁目二三〇番地」
「あんた、当日はどけんしとりやした?」
「内海市を出て、猪里市に車で向かってました」
「ほう。それで?」
「車のタイヤが途中でパンクし、バス停まで歩いて……」ちょっとのどがむせてから、「バスに乗って南町の渓山荘に来ました。息子と旅の女と一緒に」
「息子さんの名は?」
「徳広です」
「住所も同じ?」
「ええ」
「年はそれぞれいくつね」
「わたしが四八、息子が一五」
「わかりもした。で、旅の女というのは?」
「南町のはずれで乗せた旅の人です。名前は――絵美。淵井絵美とか言うちょりました」
「いくつぐらい?」
「たぶん二〇をいくつか過ぎたぐらいかな」
「本件で、川畑さんは現場でなにをしぃちょったの」
「わたしは事件記者です。現場に居合わせたら、たとえ休みでも写真と第一報の原稿を書く使命があります」
「で、女湯でカメラをパチパチ撮ったと」
「はい。なにか問題でも?」
「問題はなか。ただ、警察のやることにはそれ相応の手順がありましてな。事件現場におったのは警官とあなただけ。発見者の渓山荘の番頭も同様の質問を受けておりますから」
「何年も記者をやってます。それぐらいは知っちょります」
久野は頬を膨らませて、ちょっとむくれた。
「とにかく当日の行動をもう少し調べさせてもらうのと、あんたを見た人物の存在がないと帰せませんので」
閉口したが、しょうがない。事故現場に居合わせた経験は少ない。警官の言うとおり、無実を証明してくれる人物からの情報を待った。
やがて本署の警官がなにやら耳打ちして解放してくれた。そのとき鐘が五回鳴った。
取調室を出て、やっと仕事のつづきができると安堵した。警察署内の廊下の壁にもたれて、事件のあらましを慌ててメールに打ち込む。写真をつけてデスク宛てに送信した。
猪里署の建物を出て、敷地の外に出た。
先に自由になった番頭が前を歩いていたので、必死に追いかけた。どうしても話を交わしたかった。
「ちょっと待ってよ、番頭さん」
渓山荘の番頭は、振り返って久野の方を見た。
「なんでごわすか」
久野は息を切らしながら、
「わたし、N新聞の記者で、川畑というものです。警察でも同じようなことを訊かれたかもしれないけれど」と前置きし、「風呂場の掃除をしちょったときには、異常はなかかったとですか」
「はい。ありもはんでした。掃除を終えたんがちょうど三時ごろ。それから私が営業前の風呂場を確認に行ったのが四時」
「つまり、三時から発見時刻の四時までに、犯人が遺体を浮かべたちゅうことでよかですね」
「へえ」
歩きながらトートバッグからノートを取り出し、いま仕入れた情報を平仮名ばかりで殴り書きしてメモを取る。
「その日、四時まで、とくにかわったことはありもはんでしたか」
「さあ、とくになんも」
「問い合わせの電話とか、不審な物音とか、見かけぬ人物とか」
「わかりもはん。なかったと思いますが」
「きょう番頭さん以外に働いていた従業員は何人ですか」
「おい以外には、男三人、女四人です」
「わかりました。あいがとごわした」
番頭とは次の交差点で別れた。国道沿いまで歩きタクシーを拾って、町のガソリンスタンドまで行った。タクシーに乗っているとき、デスクの中平から、
《トップ記事扱いにするから徹底して取材するように》
というメールが届いた。
*
県警の刑事と神取刑事は自らも現場付近の訊き込みをおこない、遺体の発見された渓山荘の校区にあたる学校は、猪里市立第二中学だけだという事実を突き止めた。
夕方の五時過ぎ、第二中の教頭と中学校内で会い、遺体の顔写真を見せ、次のような証言を得た。
「この顔と髪型を念のため担任の先生方に至急確認してもらったところ、三年生の沖本陽菜乃に間違いありませんね」
「そうですか。他に、その沖本という女生徒に関して、当日の行動で分かることはありませんか」
「彼女は卓球部の部活帰りだったと聞いちょりますが」
神取刑事は、その女生徒の部活帰りの足取りはどうだったのか、渓山荘へ行く予定はなかったのか、なにを持っていたのか、自宅の住所、電話番号なども教頭に訊ねた。
*
南町のガソリンスタンドでタクシーから降り、停めてあった自分の白のクラウンを見た。タイヤは新品になっている。修理の内容を記した紙とJAFの担当者の名刺が車のダッシュボードに置いてあった。
クラウンに乗り込み、携帯で実家に電話を掛ける。事情を話そうとして、呼び出し音を耳にしているあいだ、何から話そうかと頭を整理した。父の幸一郎が出た。
「たいへんよ、父さん」
「いけんした、久野? えらい勢いで」
「もひたあ。帰ったばかりの南町で殺人事件に遭遇したと。水死体が溪山荘から上がったと」
「ほんにまあ。そげんこつが起こったと」
「まだ自殺か他殺かはっきりせんが、他殺でまず間違いなか。これから取材せにゃならん。とにかく明日の朝刊に載るのは間違いなかよ。大事件の発生じゃ」
「うちに泊まるんか」
父は冷静だった。
「息子は内海の家に帰した。今晩から実家に泊まるのはわたしだけよ」
電話口の向こうでも、もひたねえ、と言っていた。
「これから猪里署に戻って、くわしゅう取材せにゃあならんど。帰るんは遅うなるで」
車のパンクの件は黙っておいた。
それからクラウンをUターンさせ、猪里署に向かった。着いたら六時をとうに回っていた。この南町では、どこにいても鐘楼の音が町中に響き渡る。鐘楼は、朝の八時から晩の六時まで、長針が真上に来たときに時刻の数だけ鳴るのを思い出した。鐘の鳴ったとき、か。四時に番頭が遺体を発見した。そのときも鐘が四回鳴ったはず――。
さっそく本署での取材が始まった。
サツ回りを担当するのはメディアの新人と相場が決まっている。N新聞の社会部の新人はまだこちらに着いていない。
さきほど中平に電話を掛け、
「取材するのにもう一人、応援を欲しいのですが」
「いま社会部の飯野くんをそちらに向かわせちょる」
「あの新人の飯野くんですか」
「そうだ。Qちゃんは飯野くんが合流するまで、早いうちに情報を得ておいてくれ」
中平にそう指示を受けた。久野の〝久〟を音読みして「きゅう(Q)ちゃん」と呼んでいるのは、社内では土門と中平だけだ。親しい間柄のひともそう呼ぶ。久野は「久」だからとだけ思っていたようだが、周囲は別の意味もあって、アルファベットでQちゃんと呼んでいた。アニメの「お化けのQ太郎」のQではない。なんでも質問し、記事や内容にすぐ疑問を持つ性格から、クエスチョンの「Q」をとってQちゃんなのだ。
昔、新人と組んだときに知り合った警官が猪里署にいた。いまは県警本部の警部に昇進したらしい。警察署内においては、警部の階級は一般の役所の課長クラスのポストだった。長里という中肉中背の男で、彼は久野よりも一回り若かった。
長里警部を捉まえて質問をぶつけてみようと思った。もちろん、警察が個人情報や容疑者の情報をそのまま記者に流すことなどない。
本署のトイレを出たところで、偶然にも長里と顔を合わせた。
「長里さん。ご無沙汰です」
「おや、久野さん。めずらしい。私が刑事部にいたとき以来ですね」
「そうです。きょうは非番だったのですが、事件現場に遭遇して」
「サツ回りの新人が到着するまで、代わりに私に張りつく気ですか」
「しかたないでしょ。それより、容疑者は特定できましたか」
「いきなり核心を突きますね。まだ殺人と決まっていませんよ」
「おっと、そうでした。独断はよくないですね」
「被害者の身元確認だけで大わらわです。急には進みません。ベテランの記者さんならご存知でしょう」
「単なる事故にしては、人がようけ集まっとるようですが」
「そりゃ、田舎町で変死体ですからね」
「事故にせよ、殺人にせよ、大スクープには違いないでしょう」
「とにかく、そんなに簡単に仕事が進んだら我々も苦労しないです」
「ところで、被害者の身元はいつごろ割れそうですか」
「そういう情報も含めて、七時に記者会見を行う予定なので」
「記者会見ときたか。会見を行うというのは、発表できるだけの情報があるわけだ」
「さあねえ。発表するのはうちの部署じゃないから」
「でも殺しなら捜査一課だけでは人手も足りず、とうぜん他の課を含めて動員をかけるでしょ」
「なんべんも言いますが、まだ殺しと決まったわけじゃない。私は生活安全部の警部です。くわしいことは知らんのです」
「情報源として、長里さんの力が必要なんですよ」
「まあ、あなたとの付き合いもあるし、話せる範囲のことはぼかして話しますが」
「お願いします。やがてN新聞の新人も合流するはずなので」
「じゃあ、私は仕事があるので」
長里は振り切るように手を挙げてその場を去った。
地下の喫茶コーナーでロイヤルミルクティーを飲みながら時間を潰していると、ようやく新人が到着した。やせ気味の飯野という男だ。入社一年目の数少ない期待の若手である。
「飯野くん、ご苦労だったわね」
「川畑さんこそお疲れ様です。休みの日に事件取材なんて」
「それより、警察は会見を行うみたいよ」
「ほんとうですか。事件の起きた日に会見とは手回しがよかですね」
「ええ。よほどなにか確証があってのことでしょうね」
「つまり、どういうことですか」
「早く市民に知らしめて、犯人の早期逮捕を狙っているに違いないわ」
「なるほど」
「感心している場合じゃなかよ。飯野くん、きみは会見で質問して顔を覚えてもらいなさい」
「いきなりですか」
「警察とのパイプ作りが事件の情報を得る近道なの。警官との人脈づくりがあとでものをいう世界よ。覚えておきなさい」
「わかりもした」
メディア向けの発表があるから、と捜査本部の刑事は久野や飯野を含めた記者らを部屋の外に締め出した。
「記者会見は夜七時、三階の中会議室でやりますから」
最後にそう言った刑事は、ピシャリと扉を閉めた。
「おい、記者会見じゃち」
「市のニュースでは異例だな」
地元メディアらしき放送局のディレクターの声が耳に入った。大きなビデオカメラを肩に担ぎ、カメラマンと何やら打ち合わせを始めている。地元ローカル局の生中継かもしれない。
「町のスクープなのよ。よく撮りなさい」
飯野にはっぱをかけた。久野も記者会見に臨むつもりでいた。それに備えて、トートバッグの中のスマホの充電パックとICレコーダー、予備の一眼デジカメを確認する。
廊下では、あちこちでざわざわと取材関係者が数人たむろして、何事かを話し込んでいる。
そのあいだに早足で本署から出る。歩いて数分のところにあるコンビニに行き、クリームパンとカフェオレを買いこんだ。本署に戻って外で腹ごしらえをしておいた。久野の姿をまねて、飯野も交替でコンビニに行った。
いろいろな憶測が飛び交う中、時は過ぎて七時が来た。
地元メディアはすでに三階の中会議室の中に陣取り、いまや遅しと記者会見を待ちかねていた。
すでに前方の会議机には県警本部の部長らしき刑事と何人かの部下が資料の紙を持って場が静まるのを待っていた。
「では七時になりました。稲和県警より記者会見をおこないます」
カメラのフラッシュの音があちこちでして、閃光がたかれる。
真ん中の制服の男が立ち上がって、ゆっくりと喋った。
「少女変死事件捜査本部の発表をおこないます。私は稲和県警猪里警察署副署長の今出水と申します。ここにご参集のメディアの方には周知かと思いますが、本日午後四時、猪里市南町三丁目の温泉宿において、女性一名の変死体が発見されました。ただいま遺体を検死解剖中です。他殺体の可能性が高いからです。死因は不明。発見者は事件現場の温泉宿『渓山荘』の番頭五二才男性であります。現在のところ、本市における行方不明者との一致はなく、遺体の年令、氏名等の詳細は調査中です。以上です」
一方的に書類を読み上げた制服姿の副署長は、書類を机に置いた。
最初に口を開いた刑事が、あとを受けて、
「本署からの発表は以上です。質問のある方は、挙手してから所属先と名前を述べたうえで質問してください」
すると、右前方にいた男の記者が手を挙げ、質問した。
「M新聞の畠樹です。女性はどげな状態で死んでいたんでしょうか」
「番頭の証言と目視の確認で、裸体でビニール袋、ゴミを入れる透明な袋に包まれて、湯船に浮いていたということです。うつ伏せで浮いていました。女湯に、です」
また手が挙がった。こんどは斜め後ろの記者が指された。
「はい、そこの男の方」
「南九州放送の若岩と申します。遺体が他殺であると警察が考える理由と証拠をお聞かせください」
「まず、理由は、首元に絞められた跡がある点が一つ目。女性の身体的特徴からして少女ではないかと思われますが、自殺するにしては一人でビニール袋に入りそれを閉じるとは考えにくい。
また、自害する手段や遺書、携帯電話や持ち物などが発見されていない点が二つ目。以上です。
証拠は現在調査中ですが、鑑識によると、ビニール袋内の空気中に高濃度の二酸化炭素が検出されたと聞いています。おそらく何者かが殺意を持って被害者の首を絞めたのち、意図的にドライアイスのようなものを袋に入れて中毒死させたのではないかと捜査一課では見ております」
しばらく会場のあちこちからどよめきの声が上がった。中毒死とは考えなかった。久野に促されて飯野も手を挙げ、指された。
「N新聞の飯野です。いましがた、袋にドライアイスとの発言がありましたが、固体のドライアイス片はビニール袋内に残っていたのでしょうか」
「いいえ。全部溶けた模様です。小さな塊もありませんでした」
会見は以上で打ち切りとなった。
さきほどデスクに送信したメールの倍以上の情報を得た。やはり警察も殺人と見ている。首を絞め、ドライアイスで中毒死とは――。
大急ぎで飯野に会見と質問の内容をまとめさせた。飯野の拙い文章を校正している暇はない。とりあえず飯野を市内の旅館に向かわせ、部屋でノートパソコンを使って原稿を書くように指示した。
猪里警察署を出て飯野と別れ、久野はクラウンに乗り込んだ。すぐにはエンジンをかけず、携帯で速報をデスクに送信する。
《大スクープ。少女殺人事件の様相。首を絞め、ドライアイスをビニール袋に混入の可能性。周到な知能犯》
ベテラン記者らしくざっと短く書いた。
車を出した。走りながら、きょう一日に起きたことを振り返ってみた。知り尽くしたはずの故郷に見知らぬ出入り口があり、裏世界に久野を迷い込ませたような日だった。ホラー映画の一場面を思い出し、怯えた。対向車のヘッドライトに照らされ、慌てて我に返る。
早く実家に戻り、化粧を落としたい。中年記者である前に一人の女としての願望が勝った。
職場では、若い世代の男女比は二対一程度だが、三〇代、四〇代以上では女の数は極端に少なくなっていく。部署にもよるが、久野が現在籍を置く社会部では四〇代以上の社員のほとんどを男が占め、女は片手で数えるほどしかいない。当然、ものの考え方は男っぽく、性格もサバサバしてくるし、整理や校閲の内勤に回されてからノーメイクでも平気になった。
編集局長の土門は、そんな久野をかわいがり、
「Qちゃん。おれが上と掛け合うから、内勤から社会部に戻そうか」
と持ち掛けてくれた。久野もその気になって、七年前から整理・校閲部から社会部に移り、町ネタを取材するようになった。いまでは薄化粧をして外へ出ている。仕事の流れの中で、突撃取材やネタの裏付け、アポをとる取材、ネタがないときの町ネタ探し、と外に出れば一日は目まぐるしく忙しい。
これまでも休日を潰して仕事をすることを経験してきたが、五連休の初日からこうも多忙だと明日からどうなることかとため息が漏れた。
久野は社会部に戻って多忙になった。親子で仲の良い久野は、日曜丸一日休みをもらえるのはたまにしかない。そんなときは、徳広と二人しておいしいものを食べに出掛けたり、車で遠出をしたりした。
内海市内にある水族館に行ったときに仲良しの加瀬親子に会ったのは、つい先月のことだった。
水族館ではイルカショーが定番だが、いなわ水族館ではジンベエザメの泳ぐ姿が見られる。
イルカショーが始まる前に、久野らは大迫力のジンベエザメを見学していたら、偶然にも加瀬親子と対面した。助産師をしている弘子とは、出産以来、懇意にしている。その娘二人がジンベエザメの水槽に張りついているときに徳広も同じ水槽を眺めていた。少し離れて見守っていると加瀬親子に気づき、久野の方から声を掛けた。
「弘子さん、また会ったわね」
久野は加瀬弘子に手を振った。
「よく会いますね。会う約束をしてなくても」
弘子も嬉しそうだった。きょうの弘子は肩まである髪にウエーブをかけ、長袖の白のシャツにピンク色のカーディガンを羽織っている。
「よかったら一緒にイルカショーを見ないけ」
久野の方から誘った。
「はい、喜んで。たしか、イルカショーは一三時三〇分からだから、その時刻にイルカプールで会いましょうか」
「ええ、そうしましょう」
母同士で話がついて、二家族はそれぞれ別れて、他の展示を観て回った。別々の水槽を見て回ったが、結局合流し、久野と弘子は世間話に花を咲かせた。
「暖かくなってきたわね」
「ほんとうですね。花もたくさん咲いて、陽射しも穏やかで」
「春になるとまた一年たったって思うわ」
「新年度の始まりですもんね」
「いまも同じクリニックで働いているの?」
「ええ、すっかり古参になりました」
「産婦人科もたいへんでしょう。忙しくない?」
「忙しいです。いろんな女性が診てもらいに来て、話を合わせるのもたいへんで」
「わたしなんて男ばかりの職場よ。まるっきり正反対ね」
弘子は相槌の代わりに、軽く笑った。
「久野さんの新聞社は忙しいんじゃないですか」
「忙しいち。人手不足でてんてこ舞いよ。先週も稲和大学に出かけて、牛の研究と心理学実験とウイルス感染症の研究を同時に取材して、その足で高齢女性の自動車事故の現場まで行って取材して、すぐに車で支局に戻って原稿の入力でしょ。
そんなときに限って紙面に対する意見の電話がかかってくる。コピーを何部取って、とわたしみたいなベテランも新人と同じ扱いよ。立っているものは親でも使え、って言うぐらいに人使いが荒いの、うちのデスクは」
「でも活気があっていいじゃないですか」
「産婦人科も女同士おしゃべりで賑やかなんじゃないの?」
「ええ、そのとおりです。ママさんたちが妊活の情報交換をしたり、出産のアドバイスを私の代わりにしてくれたり、そうかと思うと、中絶する女子高生が彼氏に付き添われて来ていたりして。産むのか産まないのかの選択の分水嶺ですね」
「なるほど、うまいいい方ね。やることは同じでも、抱えている境遇で、この世に生まれてくる命もあれば生まれてこない命もあるわけね」
「じゃっど。私も同じようなことを患者さんに言いました。尊い命なんだから、よく考えて決めて、産むからには責任と愛情を持ちつづけて育てましょうっち」
「ところで、旦那さん、いい男だけどあっちの方はだいじょうぶなの?」
「あっちってなんね?」
「浮気よ、浮気」
「もてる顔立ちなのかもしれないけれど、家族命ですから、心配してません。娘の面倒もよく見てくれるし」
話が尽きないうちに、お昼の時間を迎え、両家は同じレストランで昼食を摂った。
昼食を終えて、現在の話から出会ったときまで遡り、いろいろな思い出を雑談しているうちに、あっという間に一三時半になった。
子どもらを呼び寄せイルカプールに移動し、二〇分間のイルカショーを見た。イルカ三頭がプール全体をぐるぐると泳ぎ回り、水中でぐんぐん加速して、水面から二メートルあまり上の高さに用意した輪を次々に飛んでくぐり抜ける。タイミングを合わせて一斉に高くジャンプし、四メートルぐらいの高さに吊り下げたボールに頭でタッチする。尾びれを使って水面上で立ち泳ぎをし、観客席に向けて水しぶきをはねあげる。イルカたちの躍動ぶりに、久野も弘子も大きな拍手を送った。
イルカショーが終わり、昼の三時に久野らは加瀬一家と駐車場で別れた。
あれからもう一月がたったのだ。
轍を走りながら、クルマのダッシュボードの光る時計を見つめた。八時一五分とデジタルで表示されている。猪里警察署を出たとき、腕時計を見ると八時前だった。
お腹がすいていた。もうこの先には、いまごろの時刻に開いている店などないはずだった。早く実家に辿り着きたかった。
町を出て、三〇分も走った、一本道から枝分かれした道の先に実家を含む集落がある。その道は舗装されておらず、砂利道だった。
細い山道を上がっていくと、実家の手前で人が倒れていた。夜道で水銀灯が照らしているところに人が地面にうつ伏せになっている。
だれだろう?――髪の毛の長さから女なのか。
車を停めた。降りて確認しようとしたら、人だと思ったのは等身大の粗末な人形だった。服を着せ、かつらをつけてある。なんだ、手の込んだいたずらか。
次の瞬間、かがんだ背中をだれかに強く突き飛ばされた。いや、蹴り飛ばされたのだと思ったときには、山の中腹まで体ごと谷へ転げ落ちていった。切った杉林の斜面を転がるように滑り落ちていく。太い杉の根株にぶつかって止まった。
「あいたたた」
ぶつかった背中が痛かった。背筋が凍りついた。顔見知りの集落でこんな悪さをするガキや大人などいるはずはなかったからだ。そのことを思うと再び戦慄が走った。
車道まで上がるのが恐かった。まだ自分を蹴落とした犯人が潜んでいるかもしれない。山の斜面を慎重に這い上がりながら、なにかあったら体ごとぶつかってやれと身構えた。一歩、また一歩と歩みを進める。上の車道のあたりは何事もなかったかのように不気味なほど静かだった。梟の鳴く声がするだけで物音ひとつしない。
山の斜面を滑り落ち、髪も服も土まみれになった。
社会部にいた駆け出しの当時、首までしかなかった髪を最近になって伸ばし出し、今は肩口までになった。毛先に軽くウエーブがかかっている。仕事をする上ではどちらでもかまわなかった。仕事のときは、どのみち髪を後ろで留めている。人と会う部署に戻され、町中や他社で人と会ったり、こちらから声を掛けたりするときの印象を大事にしようという意欲の表れだった。それで今の髪形に落ち着いた。その分、服装は年相応で落ち着いているから、ちょうどバランスの取れたいい感じだ、と社内では褒める同僚らがちらほらいる。自慢の髪の汚れをざっと手で払い落とした。
「やっと車が見えたわ」
クラウンの影が心の動揺を落ち着かせた。
どうやら周囲にはだれもいないらしい。ドアを開け、運転席に座ると背中にびっしょり汗をかいていた。
こんな経験をしたのは初めてだった。明らかに、自分を標的にしているだれかがいる。学生時代にもこんなひどいいじめやいたずらなどはなかった。男と喧嘩しても、小学生時代ならば勝っていた。
気を取り直し、車を発進させる。
すぐに実家に着いた。
墨で門倉幸一郎と書かれた木の表札を見て、母の笑顔が浮かんできた。
カーポートにクラウンを停める。
「お帰んなさい。どけんしたち? 服が泥まみれじゃがね」
開いた玄関の扉から、母の真由美の甲高い声がする。
「ちょっと裏でこけた」
久野は言い訳をした。耳を澄ますと集落の下を流れる川のせせらぎが聞こえる。さらさらとした音は、まるで合唱のコーラスのようだ。
「母さん、帰ってきたよ。わたしの息子は途中で自宅に戻った。きょうはえらいことがあっての」
「じゃっど。町のあちこちで噂が立っちょっど。ねえ、もひたあ。まあ上がらんね」
玄関で靴を脱ぐ。土の香りがする。自分の靴と隣の長靴に土がついていた。
「やっぱり我が家は落ち着く」
「じゃろだい」
「せっかく骨休めで来たのに、警察に例の事件でしょっ引かれてのう。写真を撮ったど、遺体の」
「たいへんだったね。お疲れさん」
「うん」
短くこたえ、洗面所に行き化粧を落とし、髪留めを外してあらためて櫛で髪を梳いた。顔の汗をタオルで拭い、居間に戻って、
「新聞の取材じゃ。新聞記者として黙っておれん」
「休みで帰ったのに、しんどかことよねえ。まさか地元で大事件が起きるなんて」
「わたしはよか。休みはまた別にもらう」
「これからいけんすんのか」
「また、明日も猪里署に行く。しばらくここに泊まっせ、事件の様子を取材して部下の新人に記事を書かせにゃならんど。写真を撮っせ、部下の文章を書き直しっせ」
「まるで現地の特派員やが」
「そうじゃ。部下は新人でね。新人一人では荷が重すぎる。援護せにゃならん。彼だけでは頼りなかこつよ」
「ええ、そうね。N新聞に変わりはないのよね?」
両親は娘の記事を読むのが嬉しくて、入社以来ずっとN新聞を取りつづけていた。新聞記者になった当時、両親は、インテリの娘じゃ、と自慢し、ぜひN新聞を取ってくれ、と近所に頭を下げて回っていた。その光景を久野は目に焼きつけていた。
「ずっとN新聞ひとすじよ。デスクもな。大きな事件じゃっど、徹底して取材せいちゅうてはっぱをかけちょるが」
「じゃっど」
「あたいも今日は少し参ったち」
「まあ、疲れたでしょ。これでもたもんせ」
真由美は冷蔵庫からミカンを出して、皿に置いた。
「いただきます。車が途中でパンクしてな。それもいま考えるとおかしか、と思うちょる」
「なしてそげな」
「わからん。だれかのいたずらかもしれん。家を出るときはなんも異常はなかったのよ」
ミカンの皮をむきながら、真由美の顔色をうかがう。殺人事件の噂をどの程度知っているのかは分からないが、皮をむき終え、ひと房を摘まんで口に放り込む。
「まあ、わけえ衆はよお。インターネットだの引き籠りだのあるしのう。南町でもあるちて。よう分からんわ。普段はきちんと挨拶できてもな」
「じゃっど。一定の期間が立てばな。日本中のどっかの町で似たような事件が起きるど。それは止められん。教育の質が落ちたんじゃなかか、ち思うちょる」
久野は意見を言った。
「親がよう躾んのよね」
「じゃっど」
しばらくして、車の音が聞こえて家の前で止まった。幸一郎が帰ってきて扉を開けた。父は外出から戻り、会話に加わった。
「久野、久しぶりよな。元気しとったか」
「ああ。元気や」
ちょうどそのとき壁の柱時計がボーンボーンと九回鳴った。腕時計を見たら晩の九時きっかりだった。
テレビを点けた。九時のニュースだ。
「どれ。夕飯を食べとらんでしょ」
真由美が訊ねた。
「わたしはいっでんよか」
「あたしらはもう先に食べた」
「疲れて腹もすいたじゃろ」
幸一郎が言う。
久野は、テレビの画面に食いついた。
「稲和県猪里市南町の温泉で、水死体が発見されました。遺体は女湯の湯船に浮いた状態でした。警察によると、部活動帰りの中学三年生、沖本陽菜乃さんではないかと見られています。他殺の可能性もあるとみて現在も取調べがつづいています」
七時の記者会見の時点では、被害者の名前は伏せられていた。部活帰りの中三女生徒か――。
「女子中学生ちね。沖本さん言うたら、南町の消防士の娘やないけ」
さすがに幸一郎はよく知っている。久野も思い出したように、
「じゃっど。わたしは、沖本さんと一つ違い。猪里高校で一緒やった。彼は中高で柔道部、わたしは中学までの柔道を辞めて茶道部。勉強は向こうがもっとできたど」
「久野の息子も中三じゃなかか」
台所の奥から真由美が口を挟む。
「じゃっち。うちの子は利発じゃけ、こげん事件には巻き込まれん」
「じゃろだい」
「第一、関わらん。まあ被害者は中学のおなごじゃち。大人がその気になればいけな方法でも殺せる」
恐ろしいことを言った手前、少し黙り込んだ。子どもが男でよかったと思った。息子がいる関係で、残業しても夜八時には社を出ている。産休と育休を取ったときは、会社に戻れるのかと何度も上司に確認を取った。そのたびに、ひと回り上で当時副編集長だった土門は、
「Qちゃん、大丈夫だって。ちゃんと君の机は残しておくから」
と休学中の女子高生を宥めるように言い聞かせた。
徳広を身籠りお腹が気になり出してから息子が一歳になるまで、仕事を休んだ。
内海市内の自宅にいた夕方に陣痛が始まり、市内の病院にタクシーで向かった。
病院に着いてから、ちらっとお腹を見られ、すぐベッドに寝かされた。
「ちょっと眠った方がいいわ。その方が進むから」
助産師の態度になぜか腹が立った。久野はちょっとキツイ印象を受けた。
「あなた、まだわけね。二〇代?」
「ええ、そうよ」
「年下なのに生意気ね」
「お産の立ち会いに年の上下なんて関係ない。私の言うとおりにして」
「う、う。く、る、し、い……」
久野はベッドの上で呻いた。
「まだ少し時間がかかるわ」
「とっても痛いの。締め上げるような」
「苦しくても息を止めないでね。息を吐くことを心掛けて」
「息を吐くのね」
「そう。思いっきり深呼吸して」
やがて夜も更け日付が変わったころ、分娩台に載せられ、一時間足らずで男の子を出産した。
陣痛前に助産師と口喧嘩したが、そのあとの処置で彼女とはすっかり仲良くなった。
初産のとき、分娩室で立ち会ったのが、助産師の弘子である。当時、彼女は四つ下で、まだ独身だった。後に、加瀬という医者と結婚した。彼女も子どもを産んで育児を終え、いまは内海市内の産婦人科のクリニックで働いている。
その当時、久野は三三歳。厄年での出産であり、たいへんなお産になりはしないかと不安だったのを、弘子が励ましてくれた。
あれからもう一五年の月日がたっていた。
お産以来、彼女とはいい関係が続いている。あのとき、感情的になっていて逆に怒られたけど、向こうはお産のプロだ。無事に徳広を産め、弘子に感謝する気持ちに変わった。
夫がまだ生きて働いていた頃、職場に復帰した久野は、町で弘子に再会した。顔はよく覚えていた。
「あら、弘子さん、元気?」
「川畑さん? 息子さんもご一緒で」
「奇遇ね。日曜日に同じファミレスで顔を合わせるなんて」
久野は夕食を外で食べに、家族で来ていた。照れて久野の後ろに隠れる徳広に、弘子は語りかけた。
「お母さんに付き添ってきみが生まれたんだよ。いま、いくつ?」
指を四つ突き出して、徳広は笑った。
「四歳か。私のお腹にも子どもがいるの」
「どうも、夫の加瀬と申します」
「結婚して、子どもを授かったんですね」
「ええ、僕は医者で妻が助産師。職場結婚です」
「弘子さんは、小柄だけど美人でエネルギッシュなタイプだもんね。職場のドクターの心を射止めたんだ」
「そういうことになるかしらね」
弘子は上目遣いに旦那を見上げた。
「では、これで」
加瀬が頭を下げ弘子は久野ら一家に手を振って、ファミレスの駐車場で別れた。
それ以来、久野は加瀬弘子とよく連絡を取り合い、子連れ同士で市内の飲食店やショッピングモールで待ち合わせた。食事や買い物を一緒にして、家族ぐるみで仲良くしている。
数年後、夫は過労で倒れ他界した。
夫は家族のため身を粉にして働いてくれた。毎日夜遅くまで残業し、家計を支えてくれた。休日ですら出勤することもしばしばで、家族が揃ったときやっと一家で会話ができた。本音を言うと、久野も夫も朝遅くまでベッドで眠っていたかった。が、遊び盛りの息子を連れ、外出せざるを得なかった。
夫が亡くなる直前、兆候はあった。帰宅して青い顔を浮かべ、息苦しそうにしてソファーにドカッと腰を下ろすと、目を閉じたまま二〇分ぐらい身じろぎひとつしない。
「あなた、だいじょうぶ?」
「う、うん……」
小さな声で答えるのがやっとといったありさまだった。綿のように疲れていそうだった。久野は、このままでは夫が体を悪くするのは時間の問題だろうと思っていた矢先、会社で仕事中に突然倒れ、病院に運ばれたという知らせを携帯で受けた。
慌てて病院まで車を飛ばし、病室に着いたときには、カーテンが閉められていて、中の人間はだれも言葉を発しなかった。
ベッドに横たわった夫の瞳孔は、開きっ放しだった。医者は静かに言った。
「ご主人は先ほどご臨終になられました。急性心不全でした」
「まさか……」
久野は言葉を失った。現実を受け入れるまでに時間がかかった。付き添っていた夫の会社の上司は、
「ここ数か月、川畑さんの残業時間は月一〇〇時間を超えていた。申しわけなか」
と深々と頭を下げた。久野自身も残業の日々であり、なにも言い返せなかった。
葬儀の喪主は久野が務め、涙混じりに弔問客を前に挨拶をした。喪服姿の弘子が駆けつけ、「がんばってね」と彼女もハンカチで目元を押さえ握手し、肩を抱いて励ましてくれた。
義父母と徳広の四人暮らしは変わらなかったが、夫の抜けた穴を埋めるため、遺族年金を受け取りながら仕事に精を出した。
副編集長の土門は、
「一年と少し休んでいたち、仕事に復帰してもなかなか慣れんじゃっど。どうじゃ、しばらく社会部を離れて、整理・校閲部に行かんけ?」
「はい、そうします」
久野は土門を信頼していたから、素直にすすめに従い、育休後から校閲部に移った。
校閲部での仕事は、出来上がった原稿に目を通し、文字の誤りを訂正したり、内容の正しさを確認するためインターネットや特殊な辞典などを使って固有名詞や日付に誤りはないか可能な限り調べ上げたりする作業が主である。
初校を終えるとデスクが再校し、直しを入れて校了にしてから整理部に原稿を送る。整理部の記者は、実際に組んだ紙面でさらに見出しや写真と記事が合っているかを見てチェックするが、版ごとにレイアウトの変更などがあり、初校と組んだ紙面での校閲を繰り返す。限られた時間内に一つひとつ丹念に確かめていく仕事は、内勤とはいえ、プレッシャーのかかる、慌ただしい仕事だった。
「Qちゃん、ここ調べてみて」
「はい、わかりました」
デスクの要請に即答し、パソコン画面上で調べながら、
「デスク。この年にそれは存在していません」
「やっぱりそうか。訂正文を入れといて」
「了解です」
中平デスクと短時間でのやり取りはもちろん、近くにいる先輩も、
「その外国人選手の表記は、こちらが正しいんじゃないの?」
と指摘してくれるのはありがたかった。
ペンを持つ右手の指のあちこちに赤ペンの汚れがつくと、
「ああ、きょうも仕事を頑張った」
と感慨深くなったものだ。
産む前から一年数か月、N新聞を休職していたことになる。小さな徳広を育てるのに精一杯で、残業をこなすのが当たり前の職場では、帰宅して徳広に晩ご飯を食べさせる余裕などなかった。夫も深夜に帰宅する生活だったので、徳広の世話は実姉の知代に頼るしかなかった。幼い徳広は目が離せず、義父母任せにはできなかった。
昼間、徳広は保育所へ行き、夕方から姉に面倒を見てもらった。徳広にとって、いわば知代が母役であり、父役となった。
朝早くに出て、夜遅くに帰宅する生活の久野は、知代の存在がありがたかった。弁当も作らず、授業参観にも行けない。運動会だけは姉妹で応援しに行った。
しばらくは義父母の一軒家で家族六人賑やかに暮らしたが、不幸にも、徳広が八歳のときに夫が過労死、一〇歳のときに姉が乳がんで他界。それ以来、川畑親子は四人家族となった。強くて物事に動じない心を持たせようと思い、徳広に小学三年生から剣道を習わせ、いまも続いている。
四年前から徳広に携帯を持たせた。外で遊んでいるときになにか変なことが起きたら、すぐに久野の携帯に電話するように言い含めてある。
最初こそ久野も心配だったが、携帯の着信音が鳴らないのは、天国の夫と姉が優しく見守ってくれていると思うようにして心を落ち着けていた。
「ほんにのう。犯人は男じゃろか」
幸一郎はテレビを観ながらミカンを摘まむ。
「わからん。ないごて、あげん殺し方をしぃちょったかもわからん」
「さあ、晩御飯ができたよ」
真由美が久野の分のご飯と漬物を食卓に並べだす。
「少しずつたもってね」
真由美が背中を向けると、コンロからいい匂いが漂ってきた。味噌汁の甘い匂いだ。真由美は冷蔵庫から刺身を取り出して小皿に取り分けている。
「ヨコワ。おいしいよ」
真由美は嬉しそうに言った。ヨコワとは、この辺では九州近海で獲れるクロマグロの幼魚のことを指す。稲和県ではブリも養殖しているが、門倉家はみなヨコワの方を好む。
「やはり養殖よりか天然もんやなあ」
久野はヨコワを食べながら呟いた。真由美は、豚肉に大根、人参などの入った味噌汁を温めて、久野の前に置いた。
久野はしばらく味噌汁とヨコワを食べ続け、腹いっぱいになった。
「腹いっぱいたもった。よかでなあ。ごちそうさん」
テレビで明日の天気予報を確かめてから、リモコンで消した。
「風呂が沸いちょるけ、適当に入ってね」
真由美は後片付けを始めた。
「あいがて」
その晩は、夜更けまで事件の様子を幸一郎と語らい合った。母の真由美は先に寝た。
「こげん辺鄙な町で殺人か。ほんにもひたなあ」
幸一郎はまだよそ事のように語った。
「風呂場に死体が浮いちょった。あたいはこの目でしかと見た」
「ほうで。恐ろしかことやのう」
「ほんに恐ろしか」
「早うに犯人が捕まらんと表を歩けん」
幸一郎は眉間にしわを寄せた。
「そうよ。こっちに帰った日に突然出くわせっせ。あげんこつは、わたしの人生にもなかことよ」
久野は口を尖らせた。
「そらそうや。内海でも猪里でも起こらん。南町ではあちこちで、男ん衆もおなごん衆も騒いじょる」
「このまま捕まるやろか」
久野は訊ねた。
「じゃろだい。そげん残酷なこつばする犯人は、がっつ悪か人たい。警察が本気で動けばこん狭い町ですぐに見つかるて。悪い人間はよそ者か変人と相場が決まっちょる」
「じゃっど」
「とにかく、おまえ、疲れたじゃろだい。風呂入って嫌なことは忘れなさい」
「いや、仕事があるでよ。きょうの事件の原稿を書いて、新聞社のデスクに送らにゃならん」
久野は食卓を離れて、隣の部屋に移動した。部屋の灯りをつける。
「チンチンボッボッきばいやんせ(少しずつマイペースでがんばりなさい)」
幸一郎の励ます声が台所から聞こえた。
机の上を整理して、トートバッグの中から大学ノートと筆記用具を取り出す。
原稿を書く前に、トートバッグに入っているデジカメの画像を見直し、使えそうなものを一枚選りすぐっておいた。
やおら大学ノートに原稿を書き出した。書き始めると、会社の雰囲気そのままのモードに突入した。時間のたつのも忘れて書くことに集中し、夢中になって事件を正確に書きとめる。犯人かその協力者と思われる人物からの妨害行為にも腹を立てていた。とにかく、私憤は横に置き、正確な事実だけを書いた。
死体の様子、目に焼き付けた風呂場の状況、発見した当時の時刻、今日の日付と天気。さらには、第一発見者の番頭から聞いた証言、取り巻いていた住民らの様子と感想など、記事には向かない現場の様子も書いた。カットされるだろうが、取材源に最初に居合わせたものとしての現場の空気感は、あとから駆けつけた飯野やテレビ局などより、久野の方がよく把握しているといっても過言ではない。それだけの自負があった。
それらの情報は、あとで特集記事を書いたり、データベース化したりするときに役立つかもしれなかった。
壁掛け時計を見ると、十時を回っている。
五分ほどして、携帯にメールが届いた。飯野からだ。原稿の文字を目で追う。久野は送られてきた飯野の原稿を校閲した。自分の分と合体させて原稿らしく編集し直し、文章を携帯に打ち込み、写真を添付して飯野とデスク宛てに送信した。
壁時計を見やると一一時を回っていた。
久野にはひとつ気がかりなことがあった。現場の警官の小声で話した言葉がそれだった。
交番に遺体発見の電話がありもした。四時きっかりに――。
それがほんとうならば、犯人は三時から四時のあいだ、もしくはそれ以前に少女の殺害を実行し、湯船に浮かべた。いずれ従業員が見つけるはずなのに、四時に交番へ電話を掛けて遺体を見つけたと知らせ、わざわざ警察を呼び寄せたことになる。だれが聞いても、綿密に計画された犯行なのは明白だった。
犯人は冷酷かつ大胆で緻密な知能犯、というイメージが浮かび上がった。
もし、今回の一件だけで終わらずに次々と犠牲者が増えてゆくならば――。
そういうネガティブな展開を考えるのはよそうと思った。その話自体が不謹慎であり、遺族への気持ちを考えると空恐ろしい。逮捕できない場合などと考えてしまうのは、自分が弱気になっている証左だと思った。
外で人の歩く気配がした。縁側の窓を開けているので分かった。
「だれ? だれね?」
その直後、真夜中だというのに、表の郵便受けにぽとりと紙の落ちるような音が聞こえた。ここら辺は静かだ。都会と違う。ダイレクトメールを郵便受けにポスティングするといった習慣はない。
鄙びた町はずれの場所では、車の音以外はほとんど夜に音などしない。音が聞こえるとしたら雨降り前の蛙の鳴き声ぐらいだ。
少々気味が悪かった。音の正体を確かめるのが。いろいろな出来事が一度に久野に降りかかってきた日だ。
それでも意を決し、玄関の引き戸を開けた。人影が見えた。スタスタと音を立て、素早く走り去るのが見えた。軽い足取りに聞こえた。
郵便受けを見ると、折りたたんだ紙一枚があった。
部屋に戻り、灯りの下で紙を広げた。そこにはワープロで書かれた大きな文字で、
記事を書くな。深入りするとおまえが犠牲になるぞ。
と横書きに書かれていた。
ひどく心が痛んだ。犯人は久野が新聞記者と知っている。知った上で、関わるなと警告してきた。仕事に対する妨害であり、同時に久野個人に対する犯人からの挑戦状ともとれる内容である。
「けっしてひるむもんですか」
心の中で叫んだ。握りこぶしを固めた。紙を四つに折り畳み、トートバッグの中にしまった。
疲れていた体が、鉛に溶けていくようにどんよりとして、いっそう疲れた。
久野は風呂が沸いていたのを思い出し、幸一郎を残して入った。
脱衣して背中をよじって鏡を見る。青紫色のあざができていた。
風呂から上がると、内海の自宅に電話を入れた。徳広が無事に帰ったのか、母として心配だった。
「もしもし」
久野は疲れもあって、少し掠れた声になった。相手が黙っているので、もう一度、
「もしもし、徳広?」
「母さんか」
「遅くにごめんね」
「母さん、おれはちゃんと帰れたよ」
「よかったわ。おまえになにか起きたら、母さん飛んでいくからね」
「大げさだよ。それより、仕事、たいへんそうだね。さっき、ニュースみたよ」
「そうなの。稲和県内だけじゃなくて、全国版のトップニュースになるくらいだからね」
「今晩は早く休んで疲れをとってね」
「おまえは優しいね」
「とくに変わったところもないよ」
「次に休みをもらえたら、またどこかへ連れてくからね」
「うん。おれ、温泉でなくても、なにかおいしいものを食べに行くのでもいいよ」
「ありがとうね。とにかく、無事でよかったわ」
「だいじょうぶだってば」
「ついでだけど、そちらで変わったことはなかった?」
「別にないよ。内海市内は平和だよ」
息子の声色で、向こうはいつもと変わりのないのを知った。
「明日の晩も、また電話するよ」
「うん、わかった。じゃあ、夜も遅いから、おやすみ」
「おやすみなさい」
固定電話の受話器をそっと置いた。
息子の声を聞けて、平穏無事を確認でき安心した。
その一方で、明日からのことを考えると、不安で押しつぶされそうになった。布団にくるまり、固く目を閉じた。脳裏に現場の光景が焼き付いたのと、崖から突き落された衝撃、あの脅迫文。それらが一日のあいだに起こり、興奮と恐怖のあまり寝つきが悪かった。
隣の部屋では、祖父の仏壇の前で、なんまんだぶつ、なんまんだぶつ、と念仏を唱える幸一郎の声が小さく聞こえた。
久野は、祖父の魂とは別に犠牲者となった沖本陽菜乃の冥福を祈った。明日、時間があれば、渓山荘の現場に花束の一つでも捧げようと誓った。同じ町で暮らした人間として、一人の大人として。
明日は朝から飯野を連れて警察回りの仕事が待っている。帰省して親孝行の一つでもしたかったけれど、当面、事件の真相をつかむまで、ここは単なる食事付きの定宿でしかない。
五月三日(木曜日)

朝の八時に目が覚めた。いつもより遅い時刻だ。けだるい朝で小雨が降り、空気は湿気を帯びていた。庭から臨む景色は、木々の葉がしっとりと濃くて、向こうの丘あたりは霧が薄く煙っていた。
窓を開け、田舎の空気を吸い込んでみる。不如帰の鳴き声が裏山からこだまする。実にのどかな環境だ。濡れた葉と土の匂いが、むかし嗅いだときの懐かしさと変わらず、気持ちを安らかに保ってくれる。
両親はとっくに朝飯をすませていたようだった。寝ぼけて顔を洗い、寝間着のままで部屋に戻った。昨日投函された紙をもう一度見ようと、トートバッグの中から取り出し、文字を見つめた。
犯人なのか。もしくは事件のいきさつを知る者、犯人を庇うものか。共犯者の可能性だってある。どうやってこれを入れたのか。歩いて投函したのか。それとも車で送ってもらい、近くで降りて歩いてきたのか。
いずれにせよ、久野が昨日現場に居合わせたこと、新聞記者として事件の解明に関わろうとしていることに、敏感に気づいた様子だった。
今日は、憲法記念日で祝日だが、猪里警察署に行かなければならない。念のため、車に細工をされてないか確かめた。どうやら大丈夫だった。
飯野に電話を掛けた。
「飯野くん、おはよう」
「川畑さん。おはようございます」
「さっそくだけど、猪里署、何時に行くね?」
「八時四五分でお願いします」
「わかった。八時四五分ね。遅れないでよ」
「心配なかです」
猪里警察署に集合する時間は九時前と決まった。
それにしても、だれが事件解明の邪魔をしようとしているのか。その人物こそまさに犯人そのものかもしれない。まずは警察に行き、被害者のくわしい死因を突きとめねばならない。
その前に、遅い朝食を一人で食べ、食卓の上に置いてある朝刊に目を通した。新聞記者の性で、どうしても新聞記事が気になる。
N新聞は、やはり一面のトップに少女変死の記事を持ってきていた。昨日の事件をどう報じているかが気になった。大きな見出しが紙面を飾っている。紙面を食い入るように見つめて読んだ。
女生徒の遺体、温泉で 二日午後四時、稲和県猪里市南町の温泉宿、渓山荘で猪里市立第二中三年の沖本陽菜乃さん(一五)と見られる遺体を番頭が発見し、警察が駆けつけて死亡を確認した。番頭の話では、営業直前に女湯に入ったとき、浴槽に大きな透明のビニール袋が浮かんでいた。袋の中に人が衣服をつけずにうつ伏せで入っていた。稲和県警によると、遺体の状況から自殺や事故ではなく他殺とみて調べを進めているという。警察は検視解剖を行っていて死因はまだ不明。
昨日のうちに実家から写真と原稿を送っておいたので、久野と飯野の原稿が新聞に記事として掲載されていた。
携帯の受信フォルダを開けると、
《原稿は届いた。とりあえず記事になって助かった。Qちゃんは飯野くんのサポートをよろしく頼む。警察に張り付かせてやってくれ》
と中平からの返信が届いていた。
朝早く、真由美は庭の隅に植えていた色とりどりの花のうち、咲いていた数本を摘んだらしく、新聞を読みおえた久野に声を掛けた。
「あんたは、陽菜乃ちゃんにこの花を手向けてきなさいよ」
小雨の降る中、花を取ってきてくれた母の心遣いに、
「母さん、あいがと」
と礼を述べた。さっきまで読んでいたN新聞の経済欄を一枚めくって、花を包んだ。
それを机の上に置いて、持ってきた旅行かばんの中から、昨日の服とは違うチェックのワンピースと無地のカーディガンを出し、着替えた。そのまま洗面所へ行き、歯を磨き薄化粧をしてトートバッグを持って車に乗り込んだ。
しばらく走っているうちに雨は止んだ。幾重にも鼠色の雲が重なっては広い空をゆっくり流れている。交差点をいくつか過ぎて、コンビニまでやってきた。
速度を落としてコンビニの駐車場にクラウンを停め、店内に入った。飲み物とM新聞を買った。他紙が事件をどう報じているのか、ライバル紙の記事が気になる。外に出て雨をよけるようにして車に乗り込み、中で新聞を広げた。さっそく新聞の社会面に目を通してみる。大きな縦見出しだった。
温泉で少女の遺体 変死か? 二日午後四時、稲和県猪里市南町の温泉宿、渓山荘で猪里市立第二中三年の沖本陽菜乃さん(一五)の遺体を番頭が発見。女湯の浴槽でビニール袋に入れられ服をつけずに下を向いて浮かんだ状態で見つかった。陽菜乃さんは連休中に卓球部の部活で他校へ試合に出掛け、その帰りだった。家族の話では、当日は朝から出掛け、途中連絡はなかった。「まさかこんな姿になるなんて、まだ信じられない」と両親は号泣した。稲和県警は、異常な状態で見つかったことから、他殺によるものと推定し、調べをつづけている。被害者の所持品も含めて容疑者の情報提供を呼びかけている。事件前、少女の周辺で目立った出来事やトラブル、いじめなどはなかった。
なんてことだ。むごい。改めて思った。犯人は残酷な大人だろう。新聞の情報を頭に入れた。卓球部の帰り道で所持品は見つかっていない。少女の周りでトラブルなし。
赤の他人の無差別殺人かもしれない。また、そう装っただけで知り合いの怨恨殺人の可能性もある。
被害者の家族の談話を聞けなかった分、M紙に頭一つリードされた感が否めなかった。N紙の方は、辛うじて、遺体の発見された現場のカラー写真を掲載できたので、読み手が女湯の見取り図と比較して、実際の現場の大きさを把握しやすいだろうと思った。
コンビニを出て、猪里警察署に車を飛ばした。朝から「サツ回り」だ。
新人時代を思い出す。
「N新聞社会部の門倉久野と申します。よろしくお願いします」
久野は、庁舎から出てきたスーツ姿の刑事を捉まえ、頭を下げて名刺を渡した。
「新入りさんか。おなごに務まるかな」
さっそく相手の刑事から皮肉の先制パンチを見舞われた。相手は涼しい顔をして、こちらに名刺を渡した。猪里警察署刑事課課長 警部 島谷銀次、と書いてあった。
「島谷部長、ここ数日で起きた事件か事故についてお聞かせください」
「おいは部長じゃなかよ。事件の類いもなか」
「そうでしたか。とんだ失礼を」
「三時に出回る日本記者クラブの報道メモを見てくれ」
担当の島谷課長はすげなく言った。
「それだけで済むのなら、新聞記者はわざわざ足を運びません」
久野はむっとした。
「ほう。それで?」
意地悪そうな島谷は、久野を試しているような口ぶりだった。
「この前の豊吉町で起きた強盗事件。あれの続報はなかですか」
「まあ、地域の小さな強盗事件じゃち、なかことはなかよ」
「なら教えてください」
「県警の発表どおりじゃち。犯人の動機はありふれたもんじゃ」
「それだけですか」
「だから、発表したとおりじゃと言うとろうが。副署長から聞いとりゃせんかい?」
それからも最初の一年はサツ回りがつづいたが、第一印象で心よく思われなかったせいか、島谷は苦手な相手になってしまった。もちろん、これまでのN新聞と猪里署とのパイプは保てた。ただ、一年目でもあり、個人的に島谷警部は強面の刑事に映った。
結果的に、サツ回り初体験は、島谷刑事にいいようにあしらわれたのだった。
あの島谷は腕利きの刑事で県警本部に異動になったと聞いたが、はたして彼のような敏腕を連れてくる事態に発展するのだろうか――。
久野は新人以来の島谷との再会を待ち焦がれているような、逆に会いたくないような気持ちになった。
猪里署に着いたら、昨日の水死体の死因や状況などを細かく訊ねてみようと思った。久野の推理では、遺体はビニール袋に入れられていた事実からすると、別の場所で気絶させて運び込み、衣服を脱がしてビニール袋に詰め込んで湯船に放置した。もしくはなんらかの事情があり、脱衣所で少女が服を脱いだときを襲って殺した。そして、服を隠すか持ち去って、遺体をビニール袋に入れて浴槽に浮かべた。
ドライアイスで中毒死するとは知らなかったが、アイスクリームが溶けないように袋などに入れる日常から考えて、もしかすると死亡推定時刻をずらすための巧妙な細工であったのかもしれない。そう推理した。
猪里署に着き、車を停める。
飯野は庁舎の前で待っていた。
飯野が、
「川畑さん。そのカーディガン、表裏が逆です。背中にタグが見えちょります」
彼の指摘に、久野はしまったと思った。急いでいて、薄手のカーディガンの表裏をよく確認しなかった。口を結んだままの笑顔で飯野の肩を手ではたいた。心中で呟く。もう、いやだわ、と。
駐車場の車から降りてカーディガンを着直し、しばらく時間を潰していたら、安全課の長里が出勤するのに出くわし、久野は声を掛けた。
「紹介します。社会部一年目の新人、飯野です」
「飯野と申します。よろしくお願いします」
飯野は名刺を差し出した。相手は一瞥し、あらためてじろじろと眺めまわした。
「記者会見でさっそく質問したんだろ?」
長里の耳にも入っていた。
「ええ、新米でもそれぐらいは」
飯野は少し遠慮気味の様子だった。
「ところで、昨日の事件ですが」と前置きして、飯野は、「昨日の少女の水死体の死因はほんとうにドライアイスによる中毒死なんですか」
「いま捜査中だが、昨日も刑事が言うたように、首を絞めて意識を失わせっせ、ドライアイスの入った袋に詰めっせ、中毒状態で殺害したとみちょる。死因はまだ不明だ。新しかことはなんもないち」
「昨日の記者会見どおりですか。被害者に関することは新聞にも少し出ちょりましたが」
「ドライアイスに関しては、袋を科捜研で鑑定中らしい。何グラムのドライアイスで人体に悪影響を及ぼすのか、稲和県警の科捜研で実験している。まだ死因は特定できとらん。
分かっとるんは、遺体の傷と、氏名と年齢、住所だけだ。捜査本部で知っとることはそれぐらいだ」
「それと卓球部」
飯野は付け足した。
「ああ、そうじゃったか」
「脱衣所に卓球の道具や練習着などの持ち物やかばんは見つからなかったとですか」
「さあな。見つかっておらんと思うが」
「捜査本部が置かれたっちゅうことは、早い段階から殺人のセンで見ちょったっちゅうことですか」
「どうかな。何とも言えんが、ああいう自殺の方法はなかろうが」
「長里さんの安全課からも、五人前後は捜査本部に人をだしちょるでしょう?」
久野が口を挟む。
「まあ、そうだな」
「容疑者の訊き込みはどの程度進んじょりますか」
「まだ二日目の朝が始まったばかりじゃ。そうやすやすとは目撃情報も集まらんじゃろて」
長里は推量めいた、遠回しの言い方をした。久野はさらに食い下がった。
「ほんに大胆な犯行でしょうが。裸にすると指紋はつかんが、被害者を裸にするとき周囲に怪しまれなかったやろか。どうやってドライアイスを入手したんじゃろか。大きなビニール袋に相当量入れないと中毒にはならんじゃち思いますが」
「知らん、知らん。専門的なことは鑑識課か科捜研の人間に訊いてくれ」
長里は顔の前の蝿を払うように手を振って、庁舎の中へ消えてしまった。
久野は飯野に自分の考えを述べた。
「わたしは、犯人は顔見知りかもしれんと思うちょる。中三にもなって、見知らぬ人に首を絞められそうなとき、ふつうは抵抗するか、なにか証拠を残すか、振り切ってすぐにでも携帯で電話すると思うがね」
「あたいはそうともそうでないとも言えません。犯人が市民なのかそうでないものなのかも見当がつきません」
ふと、久野は市民でないものと言われ、昨日拾った旅の女を思い浮かべた。まさかな、と思い直した。連休を利用して旅行する人は大勢いる。疑ってもきりがない。
それに、あの絵美という若い女は、久野らに拾われてからずっと四時まで行動をともにしていた。電話ぐらいはできたとして、首を絞めたり、三時から四時のあいだに気絶した被害者をビニール袋に入れて中毒死させたりするような暇などない。
早い話、絵美には二時半以降のアリバイがあった。徳広の答えた時刻が耳に残っていた。
けれど――ドライアイスという小道具がアリバイに絡んで、二時半以前に気絶させ、徐々に中毒状態で死に至ったとするならばどうだろうか。
あれこれ考えながら、ふと事故現場に寄らねばならないのを思い出した。陽菜乃の中学校に寄る前に、沖本家に寄って情報を得ようかと思ったが、いまごろは葬儀の準備に追われて対応する暇もないだろうと思い、渓山荘へ車を走らせた。飯野も車でついてきた。
渓山荘に着いたのは、午前九時四五分ごろだった。雨の中、傘をさして献花に訪れる近所の人々がいた。
久野は車を路肩に停め、ドアを開けた。
朝、庭で摘んだ、赤や黄色、白色の花々を渓山荘の門柱に添えて首を垂れ、両手を合わせて故人の冥福を祈った。
黒いネクタイとスーツ姿の飯野も、目をキュッと閉じ、数珠を握って拝んでいた。
「飯野くん、これから陽菜乃さんの中学校へ行くわよ」
「話ば訊きに行くとですか」
「当然でしょ?」
二人はそれぞれの車に乗り込み、中学校へ向かった。
被害者の陽菜乃さんのいた猪里市立第二中学校に着いたのが、午前十時だった。鐘楼の鐘が一〇回鳴るのを聞いた。
学校は祝日でがらんとしていたが、事件の対応もあり教頭が出迎えてくれた。教頭は応接室に飯野と久野を通した。応接室で飯野から口を開いた。
「N新聞の飯野です」
「川畑です」
二人そろって名刺を差し出し、頭を下げた。
「教頭の森下です」
「ほんに、この度はお悔やみ申し上げます」
飯野が頭を下げ、久野も一礼する。
「恐れ入ります。被害者の両親もたいへん悲しまれ、言葉にならないと」
「こげなことが起きて恐縮ですが、沖本陽菜乃さんについて少し訊かせてもらいたいのですが」
飯野が切り出した。
「沖本陽菜乃は一五才で本校の中学三年生。成績は中ぐらいでした。卓球部の部活を熱心に取り組んでいたと顧問の先生から聞いちょります」
「それで、当日は顧問の先生と一緒に帰ってきたのですか」
「卓球部の生徒らは、朝から他校へ移動し、公式戦をおこないました。先生は試合後バスで南町まで同伴し、バス停で生徒らと別れました。用事があったので集団で帰れと言ったちゅうて」
「なるほど。卓球部の仲間同士で帰るとき、陽菜乃さんはだれと一緒でしたか」
「警察にも同じことを言ったとですが、ちょっとそこまではまだこちらも把握しとらんで」
久野は質問を変えた。
「陽菜乃さんと仲のよかった生徒か、卓球部員の話を聞けますか」
「きょうは昨日と違い、祝日なので自宅にいとるでしょうな。話を訊くには、生徒の親御さんに学校から連絡を入れて承諾を得ないとならん。じゃっどん、友人が死んじょりますけん、普通の精神状態ではなかでしょう。とても話にならんと。お察しください」
「では、陽菜乃さんの葬儀の後にでも話を聞けますか」
「さあ、わかりもはん」
「わかりました。では失礼しました」
久野はあっさりとその場を切り上げ、行くわよと飯野の袖を引っ張った。
校門を出て近くの駐車場まで歩きながら、飯野が話しかけてきた。
「川畑さん。いつものように食い下がらなくてよかですか」
「だってゴールデンウィーク中で、友人が昨日殺されたのよ。取材できる状況じゃなかよ」
「そげんこつはわかりもす。じゃっどん、なんか死亡に関連した新しか続報を探さにゃ、記事にはならんとでしょう」
「あんた、ベテランに説教する気?」
「いやあ、そんなつもりは」
飯野は気の強い久野にたじろいだ。
「サツ回りよ。被害者の通夜にはわたしが出席して様子を探るから、飯野くんは猪里警察署に張りつくの」
「わかりもした」
新人の飯野は久野の命令に首をたてに振った。
駐車場でお互いの車に別れて乗り込み、飯野は警察署に向かった。
警察の方は飯野に任せ、久野は違う角度から手掛かりを探ろうと考えた。ドライアイスだ。ドライアイスの入手ルートが事件の早期解明の糸口になるかもしれない。
いまのところ、警察も首を絞め意識をうしなわせたのちに、ドライアイスの袋に入れて中毒死させたと見ている。首を絞めただけでは死なないということまで計算済みだったのかどうかわからないが、保険をかけてドライアイスまで用意した。犯人は相当に慎重で完璧を求めるタイプだろうなと踏んだ。
ドライアイスのことを調べようとしても、すぐにはわからない。経験豊富なおばさんのコミュニケーション能力の出番だわと思った。知り合いの肉屋のおじさんがいる。
南町の商店街にある肉屋に向かった。
シャッターの閉まっている商店街の中で、朝から肉の焼ける香ばしいにおいがする。肉屋の前に来た。
「おじさん、お早う」
「Qちゃんか。お早う」
「朝からだけど、コロッケ一つちょうだいな」
「分かった。いま揚げるからね」
ジャーっと揚げ油の撥ねる音がして、パン粉の付いたコロッケがあっという間に狐色に染まった。
「はい、コロッケ一つ。熱いから気を付けて」
「ありがとう。はい、お金」
久野はコロッケを白い包み紙ごと受け取り、代金を大将に渡した。
「ところで、訊きたいことがあるんだけど」
「なんだい、Qちゃん」
「ドライアイスって使うちょりますか」
「ドライアイス? ああ、うちでは使わんけど、食品工場なら使うちょるねえ」
「教えてもらえると助かるのよね」
「えーと、待てよ」大将はいったん奥に下がってから、取引先の業者リストをパソコンで調べ出し、「あった、あった。丸山食品。ここの北S工場が大きいし、たぶんドライアイスも扱っちょるよ。電話は、〇九九四(××)××××」
「ありがとう。恩に着るわ。また、お酒を奢ります」
礼を述べ、久野は北S工場の電話番号をメモした紙を手に、車に戻った。ドアを閉め、エンジンをかける。さっそくカーナビに電話番号を打ち込み、北S工場までの道のりを表示させた。
*
捜査本部の刑事は、ドライアイスを扱う丸山食品の工場に向かう車内で、
「いけんじゃろ。まだ調査中じゃが、首を絞めた跡が薄か」
「そげん思います」
「あたいは、被害者の死因は絞殺によるものじゃなく、高濃度の炭酸ガス、早い話、ドライアイスが風呂の熱で急に溶かされたことによるんではち思うちょる」
「まあ、ドライアイスが危険かどうか、専門の業者に訊ねてみましょうよ」
しばらくして、パトカーは丸山食品の北S工場に到着した。
さっそく刑事は担当者に会い、訊ねた。
「昨日、南町で少女が湯船で変死しました」
「テレビのニュースで知っとります。おどろきもした」
「率直にうかがいますが、ドライアイスが溶けると人体に危険ですか」
「はい。ドライアイスは短時間で溶け切ると、七五〇倍の容積に増えます。場合によっては、密閉された空間などでは中毒死に至るときもあります」
「失礼ですが、少女が入っていたビニール袋から高濃度の炭酸ガスが検出されました」
「それで?」
「おそらくドライアイスをなんグラムか犯人が混入したと思われます」
「つまり……」
「業務用のドライアイスをおたくで管理していると思うのですが、在庫がなくなっていないか知りたいのです」
「うちでは冷凍食品用と水産物用の輸送に使うちょります。いま、係の者を呼んで調べさせますので、しばしお待ちを」
担当者は席を外し、歩いて別の人間を捉まえ、耳打ちをした。
一〇分もたったころ、担当者が戻ってきた。
「この一週間で調べたところ、在庫はいつもどおりの数量を使っただけで、特になんグラムがなくなっていたということはありませんでした」
「そうですか」
「あの、私どもと事件がなにか……」
「特に関係しているとは思っておりませんので。念のための確認です。では」
刑事らはその場を辞去した。
広い構内を歩きながら、刑事は、
「どういうことでしょうか」
「いいか。死因はドライアイスで当たりだ。これから正規ルート以外をあたる」
「と言いますと?」
「ネットだ。ネット通販なら、こんな大きな工場の中に侵入して盗まんでも、やすやすとドライアイスが手に入るち」
「なるほど、そうですね」
「あそこに寄ったのは、人体に危険かどうかを確かめるためだ」
「たしかに」
別の刑事は合点がいったと見え、大きく頷き工場の門へ引き返した。
*
ルートどおりに車を飛ばして、着いたのが一一時前だった。隣の市なので鐘楼はさすがに聞こえてこない。
現場に着いた。門の脇にある守衛室に用件を言い、中に入るための入館証を首から下げた。砂利道を歩いていると、向こうから刑事らしきスーツ姿の男二人が歩み寄ってきた。
「なんだ、どっかの記者か。入れ違いだな」
「どういたしまして。N新聞の川畑です。わたしは記者なりに訊きたいことがあるけん」
「くれぐれも捜査の邪魔だけはせんでくださいよ。こちらは被疑者確保に一刻を争っちょるんですから」
「ベテランなのよ。それぐらい知っちょります!」
フンと顎を横に向け、久野は刑事らの脇をすり抜けて工場の中へ入った。
入り口で渡された帽子とマスクを着け、取材の担当者が来るのを待った。
だだっ広い工場は、床が緑色に、壁と天井は薄いクリーム色にペンキで塗られていた。機械が整然と動き、ベルトコンベヤーの脇に人がまばらに立って作業をしていた。
しばらくして工場内の明るさに目が慣れてきたころ、担当の係長がやって来た。
「初めまして。N新聞の川畑と申します」
「北S工場の大上です」
二人は頭を下げ、名刺を交換した。
「さきほど警察の方々がお見えになりまして」
大上は言った。
「たぶん同じ用件になるでしょう。例の殺人事件のことです。ドライアイスが使われた形跡があるらしくて。それについて話をお伺いしたいのですが」
「刑事さんにも話したことですが、ドライアイスは溶けると七五〇倍の容積になり、中毒死に至る有毒ガスです。業務用のドライアイスはうちの商品の場合、冷凍食品と水産物などの保冷輸送に使うちょります」
「それで在庫が減っていたということはありませんでしたか」
「それはなかとです。昨日も今朝もちゃんと数量は確認しましたし、この一週間での増減は予定どおりです」
「ドライアイスの仕入れに関して、一般人も入手できるものなんでしょうか」
「さあ、そこまでは。ネット通販でも少量ならできると聞きますが、うちでは利用したことがないとです」
「ネット通販か……。分かりました。あいがとごわした」
「昨日の水死を調べちょるんでしょ? 早く犯人が捕まるとよかですね」
「ほんにそのとおりです。犯人は頭が良さそうなので不気味ですよ。では失礼して」
工場を出てクラウンに乗り込んだ。ネット通販という手を使われたら、一般人には特定が難しい。警察のサイバー班以外は、購入者情報を開示できないだろうなと思った。
*
「豊吉町の畑の畦道で見慣れない女が倒れてるわよ。気の毒ね。今は一一時ね」
「もしもし。きさまが殺したのか」
「殺したのかしら。わかんないわ」
プツリと電話は切れた。
電話が猪里警察署にかかってきたのが、午前一一時のことだった。鐘が一一回鳴った直後だった。またしても遺体発見の電話だった。事実上、犯行予告とみなしてもよかった。
「まったく犯人め。大胆なやつじゃち」
「こんども女の声でしたか」
「じゃっど。わけ声じゃった。とにかく、大至急、豊吉町付近で遺体を探せ。事件だ」
昨日のつづきと見て、捜査一課の刑事たちはどやどやと署を出てパトカーに乗り込んだ。
*
飯野の方の動きが気になった。なにかあったか訊こうとして携帯を出したタイミングで、着信を知らせる電話が鳴った。まるで以心伝心のように。
「川畑さん、たいへんです」
「いけんした?」
「次の事件が起きました。いま現場へ向こうちょります」
「どこで起きたの?」
「ああ、すんもはん。豊吉町四一〇番地。大きな一本杉のたもとです」
「わたしもいまから行くから」
北S工場から豊吉町までは方角が正反対だった。してやられたと思った。
三〇分ほどで車は南町に入った。もう昼だと思った矢先に、鐘楼が一二回鳴り響くのが耳に入った。
昨日の警官の会話を思い浮かべた。遺体発見の電話が鐘楼の鳴る時刻に合わせて届くのなら、一一時に電話が警察に――。
そのとき、久野は犯行現場と反対方面の北S工場にいたのだ。振り回されている気がした。こんな大事件は初めてだった。社会部にいた当時の十年間で自殺や他殺は片手で数えるほどしかなかった。
それなのに、昨日と今日とで連続して事件が起きてしまった。大都会か推理小説の世界にいるようで、狐につままれているようだった。
わたしが落ち着かないと。飯野がちゃんと仕事するように支援しなければならない。そう自分に言い聞かせた。
南町を抜け、豊吉町に入り、二〇分ほどでようやく殺害現場に辿り着いた。
付近には民家が数軒点在するだけで、ここも南町の外れ同様、田圃や畑の広がる農村地帯だった。
大木が一本、目の前にあった。そこに捜査員と思われる警官たちが群がっていた。制服を着た警官数人、スーツ姿の刑事らしき人物が三人、カメラを構えたり指紋を採取したりしている制服を着た鑑識課の警官が数人いた。野次馬が遠巻きにして、少しだけいた。
立ちすくんでいた飯野に歩み寄り、訊ねた。
「現場の写真は撮れた?」
「撮りました。見えてるでしょう? あの大木の太か枝に吊るされちょったちゅう話です」
「その話、だれから聞いたの?」
「第一発見者の町民からです。まだ警官に囲まれてくわしい事情ば訊かれちょります」
「大木に吊るされた。死因は何かしら?」
「さあ。首に縄を巻きっせ、吊るされちょったとが、枝が折れ、縄も切れたらしいです。遺体は女。それ以上は分かりもはん。
おいが到着したときには、すでにブルーシートが掛けられ規制テープが張られちょって。許しを得て、枝の折れた木の写真だけは撮らせてもろたどん」
「とにかく、現場の状況と遺体の様子をもちっと詳しく警察に訊かんとね」
「承知しもした」
久野は発見者が刑事らから解放されるのを待って、野良仕事の作業服を着た町民を捉まえた。
「N新聞の川畑と申します。二、三訊ねたいことがありまして。お時間よかですか」
「はい。少しなら」
「現場で遺体を見つけたのは何時ごろですか」
「十時半です。おいが農作業を始めたときで、腕時計で確認しちょりました」
「そのときはお一人で発見されたのですか」
「はい。おいは人が死んでいるのを見かけただけで」戸惑いを隠せない純朴そうな農夫は、「最初は首吊り自殺かと思いました」
「それはなぜですか」
「大木の枝に縄がかけられちょったから」
「遺体は木の枝にぶら下がったままでしたか」
「んにゃ。地面に落ちとりました。枝が折れ、縄が切れて首に巻きついて」
「つまり、体重に耐えられずに枝が折れ、はずみで縄も切れ、遺体が落下したと」
「そげん思います」
「死体だと思ったのは何を見て?」
「なんもかんも息をしちょらんかったとです。口の周りにはすえた臭いがして嘔吐物もあって」
「わかりました。遺体はどんな女でしたか? 服を着けてましたか」
「いまはブルーシートがかけられちょりますが、服は着ちょりました。死体は、首がだらんとして力なく、手足もだらんとして……。ああ、恐ろしか」
「落ち着いてください。大丈夫ですから。犯人はあなたを狙うことなどないですよ」
根拠はない。とりあえず宥めた。
「ほんに恐ろしかです。見たときは失禁しそうになりもした。ほんにもひたあ」
「もひたですね。昨日は南町、今日は豊吉町で死体が見つかるなんて。N新聞始まって以来の難事件ですよ」
「記者さんはほかにはだれを取材するとですか。おいの話も新聞に載るとですか」
「ほんの一行足らずですよ。住所や名前は載りもはん」
「ならよかです」
「遺体の女性に心当たりはありますか」
「さあなあ。派手な服装じゃち、ここらの人間ではなかち思いますが。近くにポーチっちゅうんですか、小さなかばんが落ちてたっちゅうて警官が言うちょりました。パスポートがいけんしたとかこげんしたとか」
「パスポート?」
「んだよ。日本人じゃなかかもしれもはん。アジア系、中国人とか韓国人とか」
「どんな服に見えました? スカート履いちょったとか、赤い服とか」
「ああ、確かに赤い服でした。下はズボン。青いジーパンでした」
「わかりました。ご協力に感謝いたします。またなにか思い出したことがあれば、この名刺の番号までご一報ください」
「へえ」
久野は飯野を捜した。警官の話をメモしている姿が目に入った。彼は携帯画面を見つめて手早くなにか文字を打っている様子で、忙しそうだった。
野次馬のおじさんを捉まえてみた。ちょうど鐘が一回鳴り、午後一時を知らせた。
「死んだ女性についてなにか知っちょるとですか」
「んにゃ。あげん派手な色を着る若いおなごはこのあたりにおらんち。よそもんじゃなかか。昨日の事件とはまた違うでよ」
「やはりそうですか。発見者の方の証言では、パスポートを持っていたち言うんですが」
「アジア系の観光客じゃろだい。この近くに民宿があるでよ。そこの客じゃなかかちゅう話をみんなでしもってたところです」
「民宿の客ね。そげなら外国人でもおかしくはなかですね。その民宿の名前と住所はわかりますか」
「住所は忘れたどん、同じ町内で、『あおば』ちゅう民宿やったげな」
「じゃっど。そこだけが唯一の民宿じゃが」
もう一人のおじさんも口を挟んだ。
「そげんこつなら、わたしは『あおば』に行ってみます。ありがとやした」
一礼して、久野は現場にいる飯野に指で方角を指して合図を送り、車に乗り込んだ。ドアを閉め、エンジンをかけ、カーナビで「豊吉町 民宿あおば」とパネルにタッチする。すぐに一件ヒットした。『あおば』は、ここから四〇〇メートルほどのところにあった。歩いても行ける。クラウンを道に出してすぐに『あおば』という看板を見つけた。
ごく普通の一軒家に映った。宿の主人がいるかと呼び鈴を鳴らすと、エプロン姿の女が出てきた。
「ここの民宿の女主人様ですか」
「ええ、高橋峰子といいます」
「高橋さん。『あおば』に泊っているお客様でトラブルに巻き込まれた人は知りませんか」
「あのぉ、どちらさまで」
「申し遅れました。わたしはN新聞で社会部記者の川畑といいます。この近くでアジア系の人が亡くなりました」
「もひたあ。もしかしてあの中国人の」
「ご存知なんですね?」
「ええ。昨日までうちにお泊まりになられていた中国からの旅行者がいて。李さんと楊さんの女二人連れなんですが」
「それを知りたかったんですよ! 赤い服を着ていたのはなにさんですか」
「ええと。ちょっと気が動転して……。一緒にスマホで写真を撮ったのを見せましょう」
高橋はスマホを取り出し、食卓の後ろで撮った三人の写真を見せた。
「右に写っているぽっちゃりした方が李娜さん。赤い服ですね、たしかに。隣にいる、髪が腰まであるのが楊若溪さんです」
「お二人の年齢は?」
「えーと。二八と二九です。李さんが二八」
それから二、三訊いたあとで、
「まことに申し上げにくいのですが」そこで言葉を切って続けようとしたとき、呼び鈴が鳴った。すみません、と高橋は言い残して玄関を開けた。
刑事が写真入りの警察手帳を見せ、立っていた。
「こちらは猪里警察署のものです。お訊ねしたいことですが……」
「かちあいましたね。わたしもいま訊いているところなんですよ」
「ここから少し行った畑の木で首吊りがありました。パスポートから李娜さんと分かりました。昨日この宿に泊まったとのことですが、そのときの様子をお訊きしてもよろしいでしょうか」
「李さんが自殺?」高橋は訊ねた。
「わかりません。他殺の可能性もあるとみてます」
「香港からいらした二人連れの一人なんです。二泊三日の予定でした。今朝チェックアウトされたばかりです」
「ほう。興味深い。日本語はどの程度喋れましたか」
「ふたりとも片言です。挨拶ぐらい。英語が通じなくて、李さんは少しイライラした様子でした」
「二人の中国人ですが、この一日でなにか変わったことやトラブルに巻き込まれたようなことはなかったですか」
「お互い早口の中国語で会話をなさるので、正直よくわかりません。表情は明るくて、とくに目立ったトラブルもなさそうでした」
「わかりました。あいがとごわした」
刑事は一礼して立ち去っていった。残された久野は、
「日本に観光に訪れて自殺する人なんてまずいないですよ。相棒の楊さんは今どこに?」
「さあ。宿を出るときは、福岡に行くと言っていたので、てっきり稲和空港に向かったと」
「わかりました。楊さんを捜してみます。もし楊さんの足取りがわかったらこの名刺の携帯にご連絡ください」
久野は名刺を渡した。
「困りましたわ。うちの民宿に泊まられた方が亡くなるなんて」
「ご気分は悪かとでしょう。李さんのご冥福をお祈り申し上げます。では失礼して」
久野は辞去し、表に停めたクラウンに乗り込んだ。飯野に電話を入れる。
「飯野くん。遺体発見の電話は今日も警察に届いたか確かめた?」
「確かめもした。一一時きっかりに猪里警察署に掛かってきたそうです」
久野は高橋から聞いた事情を飯野に伝えた。
「これからわたしがそっちに行くわ。合流して、二人で相棒の楊さんという名の中国人旅行者を捜しましょう。事件に関係しているかもしれないわ。ちょっとデスクに電話を入れとくち」
「承知しました」
飯野が言い終わるとすぐ電話を切り、アドレス帳から中平の電話番号を探して、その携帯番号に電話を掛けた。
「デスク、事件です」
「またか」
「はい。今日は、香港から来た女の旅行者が、首に縄を巻かれ大木に吊るされ、地面に落ちちょったらしいです」
「昨日の水死体と関係はあるのか」
「まだわかりもはん。他殺と決まったわけでもなかとです。連れの女の旅行者をこれから捜しに行きます」
「そうか。飯野くんはいけんしちょる?」
「現場にわたしと居ます。デスク」
「なんじゃ、Qちゃん」
「犯人は案外近くにいるのかもしれません」
「ほんとうか? 近くちゅうたらどのへんじゃ?」
中平デスクの声は色めき立っていた。
「わかりません。これは女の勘ですが、犯人は女で、男を従えて殺人を実行しているような気がします」
「なぜそう思う?」
「だって、不自然なんですよ」
「どのあたりがじゃ?」
「もし昨日と同一犯だとしたら、少女や旅行者を相次いで殺すでしょうか」
「二件目は旅行者――。そう言われればそうかもしれん」
「連続殺人に見せかけて、ほんとうに憎んで殺したい人物を最後に持ってくる。もしわたしが犯人だったら、そうするでしょう。それに、被害者の性別も年齢層もばらけた方が容疑者を絞りにくい」
「それで?」
「そもそも凶器が見つからない殺人ばかりで、ナイフなり包丁なりの刺し傷が被害者に見当たらないのが気になるんです。いわゆる小説やテレビに出てくる殺人と大きく異なっている点です」
「とにかく、二件目の事件が起きたのは間違いない。飯野に原稿を送るのを忘れんように言うてたもんせ」
「もちろんです」
そこで電話を切った。久野は自分なりの推理を喋り、車を出してすぐに事件現場に戻った。それぞれの車をそこに置き、周辺で片言の日本語しか喋れない中国人のことを訊ねて回った。
すると、狭い集落のおかげか、目撃したという反応があった。別の農婦から、
「その中国人なら泣きながらエポットとかいうてわたしらに訊ねてきたじゃが、エポットってなんねちゅうて訊ねたどん、首を振るばかりで」
「わかりました。たぶんエアポート、空港へ行きたかったんでしょう。事件の重要参考人じゃっち警察も捜しちょります」
「じゃったら、空港へは行けんとその辺をうろついている可能性が」
飯野が口を挟んだ。
農婦に礼を言い、二人は手分けして楊さんの足取りを追った。楊さんは二九歳で、白いTシャツ姿に赤い口紅をつけている。そう聞いていた。それだけでも豊吉町に昼間ふらふらしている若い女を捜すのはたやすかった。
二〇分後、ティーシャツ姿の若い女が、道端の石に腰掛けて下を向いているのを見つけた。
「飯野くんが英語で喋りなさい。なぜ、李さんは死んだのか。犯人はあなたですかと」
促された飯野は、英語と身振りで伝えた。犯人という単語を翻訳できず、ナイフで刺すジェスチャーになったのが滑稽に映った。
「『相棒と連絡がつかないので捜したら、地面に倒れて死んでいました。犯人は私じゃありません。早く国に帰りたい』と。どうも死体に関わってなさそうな気がします」
「じゃあ、李さんが死んだとき、どこにいて、いつ李さんの遺体を見つけた……」
そこまで言いかけて、邪魔が入った。
「記者さんはそこまでだな。あとは警察が訊ねる」
先程の刑事が追いついた。
「警察署に一緒に行って取材を続けなさい。午後二時までに原稿を書いて、わたしの携帯に送信して」
飯野にそう伝えて、二人は車を置いた現場まで戻った。久野はもう一度現場を見てみようと思った。木の枝が折れたのが気になっていた。ぽっちゃり目の女でも大木の枝が折れるだろうか。やはり他殺。それも男だろうか。相当な力で引っ張り上げないと空中に浮かないはずだ。そう推測した。
現場に戻ると、久野のクラウンと警察のパトカーの二台きりになっていた。鑑識課の警官も刑事もいなかった。まだ若い巡査らしき制服の警官がぽつんと二人でブルーシートを見張っていた。
大木の折れた枝を見上げた。鍛え上げた男の二の腕ぐらいはある。あれが折れたのだ。ぶら下がって折れたのか。規制テープは大木とその向こうに広がる畑まで張られていた。
畑になにがあるのだろう。野次馬になったつもりで畑に行ってみた。
そこに証拠があった。鑑識もきっとカメラに収めたはずだ。馬の蹄鉄の跡が点々とついて、大木の手前の畑から果てしなく向こうまで続いていた。
馬だ。馬が被害者の首の縄を引っ張って木の枝まで吊るし上げ、最後に枝と縄が切れたんじゃ――。
名探偵のような高揚感が頭を駆け巡った。遺体発見の知らせがあったのと結びついて、昨日と同一犯の連続殺人事件じゃろと合点がいった。それがどういう動機かはわからなかった。昨日は女子中学生が、今日は香港からの観光客が狙われた。共通点はどちらも女であることだ。
名探偵――ふと弘子の顔が浮かんだ。
加瀬親子と映画館で出会ったのは、二年前の四月の半ばだった。ちなみに、弘子とは何年も前から二人でよく昼間の取材の空き時間に約束し、時間を決めて会っていた。
その時期に封切られた、何年もつづけて人気を博しているアニメ映画を観に、車で映画館にやってきた。予約していたチケットの代金を機械で払い、ポップコーン一つに飲み物二つを買い込んだ。
いざ入場して席に着いたら、偶然前の席に加瀬一家が座っていた。
館内でべちゃべちゃ喋るわけにもいかず、映画が終わるまで声を掛けるのを遠慮した。映画が終わり、天井の照明が点いてから、
「弘子さん、こんにちは」
と久野が弾んだ声で合図した。
「また会いましたね」
弘子も手を振り返した。二つの家族は退場口から出て、ショッピングモール内で食事をともにした。
「映画おもしろかった?」
弘子は徳広に話しかけてきた。
「うん、とっても。このシリーズ好きだし、残酷なシーンもなくて楽しめるから好き」
「まあ、そうなの。好きなのね」
「わたしは残業や土日の出勤もあって見られないときが多いけれど、だいたい一話か二話完結のテレビアニメだし、見ていて安心感があるのよね」
「そうね。安心感もあるし、毎回趣向を凝らしてますよね」
弘子も『名探偵アガサ』のファンのように答えた。
「息子はアガサの漫画本をたくさん持っていて、ときどき借りて読むの。とっても面白くて、たまってる家事のことを忘れるほどよ」
「わかるわ。大人でも、へえー、と思うような目の付けどころがありますよね」
「あとになると、犯人しか知り得ないような都合のいい状況説明もあるけど、推理の解説を急がないのがいいのよね。言われてみればそう描いてあったって納得する。ちょっと笑える場面も必ず入れてあって」
「飽きさせない工夫が施されています。うまく言えないけど」
「主人公が子どもなのに高校生の脳で推理するギャップも面白いわ」
「映画やテレビアニメ全般にいえるけれど、主人公は成長しないで、観客の方が気づくと年を重ねてますよね。このシリーズもずいぶん長くなったし」
「ほんとねえ。息子もこのあいだ小学校に入ったかと思ったら、もう卒業して中学校に入るでしょ。子どもの成長は早いわよね」
「徳広くんの卒業式には出られました?」
「ええ。その日は仕事をうまく調整して、スーツ姿で息子の晴れ舞台を見に行ったわ。卒業の歌を聞いて泣けてきたわよ。自分のときの卒業式と重ね合わせて思い出して」
「写真、撮りました?」
「もちろん撮ったわ。校門の前に徳広を立たせて一枚と、父兄の知り合いに頼んで、親子で並んだ姿を一枚」
「どんな気持ちでした?」
「それはもう、わたしの胸は一杯で。小四のとき夫が亡くなったでしょ? だからなおさら、子どもが無事に卒業していくのが感動的でね」
「たいへんだったでしょうね」
「そう、たいへん。わたしの人生、山あり、谷ありよ。すでに」
「ところで今日の映画、いけんでした? このアニメシリーズ、大人も楽しめますよね?」
「映画の話から逸れてたわね。『名探偵アガサ』の推理には毎回感心しちゃうわ。今回の謎解きも意外で、犯人の些細なミスに気づいて論理的に追い詰めて自供を促す場面は圧巻だったわ」
久野の感想に、ふんふんと小さく首をたてに振りながら、弘子は、
「アガサちゃんの名探偵ぶりも板についていて、うちのお姉ちゃんも、『ママ。あの無口で真面目そうな男が怪しい。見た目や職業の派手な人たちは目立つし、途中までは犯人かもと思わせておいて、状況がはっきりしてくるとだいたい犯人の候補から外れていくパターンなのよね』なんて、ませた口をきくんです」
「よくアニメシリーズを見つづけている証拠よ。子どもの探偵という設定の目線は、大人に対する偏見や先入観がなくて新鮮なのよね」
そのテレビアニメ談義をひとしきりしてから、久野はいつものようにあとから注文したロイヤルミルクティーを啜った。
「きょう観た映画は、大人びたミステリーの部分といつもの殺人の推理があって、どちらも楽しめたわ」
「ほんとですよね。ふつうなら気付かないようなトリックを見破るんだから、作者はすごい洞察力と観察力をお持ちで、小さなことを突き詰めてミステリーにしちゃう人なんですかね」
「そうなのかもね。わたしなんか、あのヒントってなんだっけって、見終わってから息子に確認しているありさまよ」
「だれが観ても納得いくように作り込んでますよね」
「そうなの。きょうの映画でも感心したけど、シリアスな場面に子どもらしい描写も混ぜながら大人の裏事情を垣間見せているというか。流行も取り入れながら、観る側の疑問点にしっかり答えているところがわたしは好き」
喋った中身は半分以上忘れてしまったが、その日観た映画の筋で、犯人が、計画的に狙った殺人と行きずりの殺人の二つを巧みに使い分けていたのだけはくっきりと頭に刻んだ。まさか、その印象が今回の殺人事件の推理に活かせるとは思ってもみなかった。
弘子と家族ぐるみで付き合ってきたことで、大型連休に起きた殺人事件のヒントを得た。そうだわ。カムフラージュの殺人が起きているに違いない。本命の殺人とは別に。
時間があったので、現場付近の家を訪ねて回った。あるおばさんから重要な証言を聞けた。
「わたしはN新聞の記者をしちょります。この近くで女の外国人旅行者が一人亡くなったのですが、なにか存じ上げませんか」
「あの旅行者け。噂によると、英語が通じなくて困っちょる様子だったでな」
「他になにか覚えていることはありませんか」
「現金しか使えない店が多いちゅうて、不平ば並べていたそうな」
「なるほど」
「あげん人は、寺で騒いで境内にゴミを捨てて帰ったとかいう話も聞いたち」
あくまで聞いた噂としても、重要な話だった。
「あいがとごわした」
久野は頭を下げ、礼を述べてその場を去った。
ノートに訊いたことを素早くメモした。
あとは飯野からの連絡待ちだ。警察から上がった情報と現場の様子を原稿に仕立て上げる。猪里市始まって以来の特大スクープになると思った。なにしろ、二日続きで起きた連続事件だ。警察も舐められたもんじゃと思うと可哀相になった。
しばらくいろいろな情報を頭で整理しているとき、遅れてM新聞の新人記者が到着した。
「これはこれは、N新聞の川畑さん。さすがにいいネタを掴んだような顔をしぃちょりますね」
「いいえ。ネタにするのはわたしでなく、新人の飯野ですから。わたしにはなにもありもはん」
久野はライバル紙にはネタの融通など一切したことがない。
「まあ、昨日の記事はうちの勝ちです。今日の事件も他殺臭いという情報は得ているので」
「猪里警察署も脇が甘いわね。M新聞の新人にばかり情報を漏らして」
「そういう言い方は語弊がありますよ。おいはおいなりに顔見知りの刑事がいるのでうまくやっているだけです」
「うちの飯野くんも見習わんとね。こっちも負けておれんわ」
そのとき腹が鳴り、久野はまだ昼飯を食べていないことに気が付いた。
じゃあ失礼と言ってクラウンに乗り込み、昔の淡い思い出の詰まった喫茶店へ車を走らせた。
喫茶店でサンドイッチを摘まみ、紅茶を飲んでいたら、飯野からの原稿がメールで届いた。
《川畑さん。以下、原稿です。
畑の前に女性遺体 五月三日(木)午前十時半ごろ、猪里市豊吉町の畑前で、大木に中国人女性(二八)が吊るされて枝が折れて落下し、倒れているのを農夫が見つけた。服は身に着けていた。警察が駆けつけて死亡が確認された。死亡女性は香港からの観光客で、稲和県警はもう一人の連れの女性(二九)にも事情を訊ねている。県警によると、首に巻いた縄を何らかの方法で強く引っ張り、自殺と見せかけた他殺の可能性が高いとみて捜査し、死因を調べている。警察は昨日の少女変死事件との関連も含めて、引き続き容疑者の目撃情報を集めている》
「うん。可もなく不可もなくってところかしら」
久野はすぐに感想を返信した。
《まあまあ書けている。あれから現場に戻って新しい発見もあった。記事にするときの地図は本社で用意します。これからわたしもそちらに行くので猪里署で合流しましょう》
久野は紅茶を半分ほど残し、店を出た。車に乗り込み、一路猪里署へ車を走らせた。
昨日に続き、同じ駐車場に車を停め、あとからやってきた飯野と落ち合った。彼はカメラを手に持ち、データを整理していた。久野は言った。
「現場の大木の写真と、李さんのパスポート用写真の二枚。それだけはちゃんとあるわね。虎の子よ。間違っても写真データを削除しないでよ。紙面に顔写真は載せないけど……」
「大丈夫ですよ。それより、もう一人の中国人女性はチェックアウトしてから別行動をとり、見晴らしのよか丘に登っていたみたいです。そのあいだに相棒が何者かに殺されて」そこでいったん言葉を切り、「くわしい話は夜に副署長から発表があるそうです。警察は連続殺人と見て、昨日の殺人との関連や因果関係も視野に入れちょりますよ」と飯野は興奮気味に喋った。
「さぞかし捜査一課もてんてこ舞いね」
夜までのあいだ、他紙やローカル局のテレビなどが大挙してやって来た。久野は、
「ちゃんと名刺交換しときなさい。いざというときに人との繋がりが大事になるから」
と飯野を促した。
あちこちのメディアに名刺を配り、挨拶を終えて戻ってきた飯野は、
「捜査一課の藤宮警部補とパイプができたんですよ」
と声を弾ませた。
「とりあえず、夜の発表まで原稿をデスクに送る以外、手持ち無沙汰ね」
「そうですね」
「夜に発表の意味は分かる?」
「どういう意味がありもはんか」
「だからね。遺体の身元確認や、指紋や毛髪なんかの証拠と犯罪者のデータとの照合作業をしているのよ。もちろん、楊さんの話もくわしく訊いてるはずね」
「藤宮さんは遺留物にも証拠があると言うちょりました」
「その遺留物を県内の科捜研へ送って緊急鑑定してもらっても、半日以上かかる場合もあるわけよ」
「なるほど。勉強になりもす」
「おそらく夜には、遺体の司法解剖も終わって死因が判明するでしょう。それにどんな物的証拠が加わるかよね」
「うちの新聞や他のマスコミも知らない情報が出てくるかも知れもはんし」
「そうよ。その辺に関して、藤宮さんはなんも喋らんと?」
「喋りもはん。捜査一課じゃから口は堅い。ところで今日は何曜日でしたか」
「木曜日よ」
「そうですよね」
「まさか、木曜日に木の事件なんて言うんじゃないじゃろね」
「じゃっど、水曜日に水死体。木曜日に木に吊るされて、ちて考えると分かりやすいかと」
「そんな中学生みたいなこと信じていけんするの。うちの息子並みね。犯人におちょくられちょるのよ」
「息子さんも言うちょりましたか。もし明日も事件が起こるとしたら、金曜じゃから……」
「金にまつわる他殺事件? なにそれ」
「犯人は挑発的じゃ。曜日に因んだ連続殺人」
「そうなのかなあ。とにかく劇場型の犯罪ね。田舎でもこげん大事件が起きるのね。ほんにめずらしか。しかも、楽しいはずのゴールデンウィークに」
感心したような口ぶりに、飯野は、
「卑劣な犯人じゃっど、一刻も早く警察に捕まえてほしか」
と語気を強めた。気を強く持った久野は、昨夜の手紙を思い出した。
記事を書くな。深入りするとおまえが犠牲になるぞ――。
昨日は確かに妨害行為もあった。今日はまだ起きていないと思ったら、鐘が三回鳴り、長里が庁舎を出て、目の前に姿を見せた。
「ちょっとお茶でも飲みましょう」
長里から誘ってくるとは珍しい。飯野を猪里署の駐車場に残し、近くの喫茶店に入った。
用件はマスコミ取材の自粛だった。町の有力者、星永産業の殿田専務から横槍が入り、今回の連続殺人に関して、あまり目立って取り上げるなという。
「川畑さん。申し訳ないが素直に殿田専務の言うとおりにしてください。われわれ公務員は民間企業の利害と関係ないが、市の税収が大幅に減るような事態だけは避けたいのです。
ただでさえ連続殺人の町として風評被害が懸念されるんじゃから、死亡記事はあまり大きく書かんでほしい。農作物が売れんようになったら、猪里市には何億もの被害が出るじゃち」
長里は渋い顔を見せた。
殿田が犯人とつながりがあるからなのか、星永産業に不利益をもたらすからなのかは定かでない。
「わたしは記者として、真実を包み隠さず報道する精神は捨てられないです」
ロイヤルミルクティーを飲みながら、長里に返答した。
ため息をついて、注文したコーヒーを一口啜った長里は、
「それだけの覚悟ならば、警察からの情報提供はあまり期待せんでほしかとね」
と視線をテーブルに落とした。久野は、飯野にその話を喋らなかった。挑発には乗らんし、妨害や暴力、圧力にも屈しない、取材は続ける。胸の中でそう誓った。
二人はしばらく黙ったままで、向かい合った。長里が、ちょっと失礼して、とタバコを取り出しうまそうに吸った。
用件が終わって、久野は身だしなみが気になり出した。髪の毛がパサつく。他の客の髪を見た。人の髪の方が艶と腰がある。美容師に言われたシャンプーに変えようかしら、と思った。他人のものはなんでもよく見えるとわかってはいるが。
それに、着ている服もなんだか合ってない。似合うと思い、社内からも褒められていたチェック柄の服は、もう流行遅れなのかもしれない。斜め前のご婦人は、黒の花柄模様のワンピースを上手に着こなしている。
ないものねだりをして、子どもじみている自分にため息をついた。まだタバコを吸っている長里に、「これ、お願いね」とロイヤルミルクティー代を置いて店を出る。
庁舎前の駐車場に戻ると、コンビニのビニール袋を下げた飯野が鉄柵にもたれていた。
「なにか変わったことはなかった?」
「なにもありもはん。それより長里さんになにか言われたと?」
「いいや、なんも。きょうも夜まで発表はなさそうね」
「わかりもすか」
「なんとなくね。経験よ」
午前中の大木事件についても、昨日の少女変死の死因のことも、警察の公式見解は明らかにされず、ときだけが過ぎていった。長里も藤宮も部屋にこもっているのか気配すら感じない。
久野はしびれを切らし、
「ちょっと中へ入ってくるわ」
庁舎へ入る様子を見て、飯野は、
「いいんですか」
と不安がった。案の定、久野は庁舎の入り口で呼び止められた。
「これこれ、そこのひと。警察官以外は入っちゃならん」
「トイレなんです。我慢できないので。すみません」
制止を振り切り、警官の脇をすり抜ける。問答無用で女子トイレに駆け込んだ。おばさんの図々しさに警官もたじろぎ、許すしかなかった。
実際、手洗いで用を足し、化粧を直すふりをしてしばらく聞き耳を立ててみる。
「おい、例の殺人事件、ちょっと変わっとるな」
「たしかに変わっちょる。裸でドライアイス、次は馬で縄を引っ張って窒息死だからな。ひとおもいにグサッとは違うち」
警官同士の短い会話が耳に入ってきた。意外な場所で重要なヒントを得て、頭にメモした。やはり、馬で縄を引いたんじゃち。
ゆっくり手洗いを出てこそこそっと庁舎を出た。クラウンに乗り込み、トートバッグから取り出したノートに、新たな情報を書き足した。
腕時計が四時半の少し前を指していたとき、飯野が、
「ちょっとコンビニに行ってきます。なにかあったら、携帯に電話してください」
と言い残し、歩いて猪里署を出ていった。
留守を引き受けるはめになり、久野はこれまでのことを頭の中で整理してみた。
昨日は、中三の女生徒が裸で湯船に浮かび、中毒死。今日は、香港からの中国人観光客が縄で大木に吊るされ、恐らく馬で縄を引っ張られて窒息死。凶器はドライアイスと縄と馬。
頭が混乱するばかりで、動機も殺害方法も突飛としか思えなかった。ただ、ナイフや包丁などで刺し殺さない点は、深い恨みを抱いた人物ではない様子だった。
犯人は頭がよく、二人以上が協力し合って、周到な計画的殺人を実行している。しかも、二件とも犯行予告ともとれる電話まで警察にかけているのだ。
はたして、警察の力で捜査が終結するのだろうかと不安になった。そのとき、また島谷警部の顔が浮かんできた。彼が応援に駆けつけてくれるならば、一日と待たぬうちに事件を解決してくれるだろう。それぐらい頼りがいのある人だ。
五時過ぎに飯野はやっと戻ってきた。
「遅いわね。なにかあったの?」
「いいえ、なんもなかです。ちょっとATMが混んでいたのとトイレを借りに」
まんざら嘘でもなさそうな口ぶりに、久野はその言葉を信用した。
夜八時になり、目立った動きがないので久野は実家へ戻った。飯野を猪里署に残して。
「たぶん夜遅くに大木の遺体に関して猪里署から発表があるわ。昼にまとめた原稿にもういちど目を通しておきなさい。発表で分かったことを追加して原稿にまとめて、わたしに送信してたもんせ」
伝言して夜の猪里の町を走った。
八時四〇分ごろに実家に到着した。家の前のアスファルト道路は濡れていた路面がすっかり乾き、坂道を登るタイヤの音がミシミシと力強く聞こえた、
今晩はなにごともなさそうな気配がした。
車をカーポートに停めて、トートバッグを持って降り、玄関の引き戸を開ける。
「ただいま帰りました」
「おう、久野か」
幸一郎の声が奥からした。
「あー、きょうも疲れたど」
玄関から居間の卓袱台にトートバッグを載せ、畳の上にへたり込んだ。
「お疲れさん。飯は食っちょったか」
「まだ、食べとらん」
「腹が減っては仕事にならんち」
「食べに行く暇がなか。次々に目まぐるしく事態が変わるかと思えば、警察署に何時間も貼りついていることになったち。それで収穫はなしで、夜に警察からマスコミ向けに発表が出されるから新人を置いて帰ってきたち」
「新聞記者もたいへんじゃな」
「ほんに。新人時代は体力も気力も漲っていたどん、わたしぐらいの年になると体が追いつかん」
「まあ、残り物でよければあるから、たもんせ」
幸一郎が顎で台所を示したので、
「あいがと」
と礼を言って、冷蔵庫を開けた。中から、ご飯と漬物と煮しめと魚の煮付けを取り出し、ご飯と煮付けをレンジでチンした。
「きょうはいけんじゃった? 噂では聞いちょるが」
「中国人観光客のおなごが犠牲になったど。首に縄を巻かれて引っ張られた。たぶん馬に」
「馬に縄を引っ張らせたんか? 首吊りちゅうた人もおったど」
「うんにゃ。首吊りじゃなか。そう見せかけて、馬を使うてがっつ引っ張ったから、大木の枝に吊るすところが、枝が折れて縄も切れ、地面に落ちたの」
「とにかく、昨日の事件にも勝る残忍さじゃの」
「じゃっち。早う犯人を捕まえてもらわんと、この町の人間は安心して眠れんち」
「まだ仕事は残っじょっど?」
「じゃっど。まだ部下からの原稿が送られてこん。メールで来る時代になったどん、発表する側の警察は昔とさして変わらんち。こちらが情報を待つ身なのはいっしょ」
「まあ、夜は長いけん、ゆっくり食べて、風呂につかりんさい」
「あいがと、父さん」
久野は今晩もニュースを観ようとテレビを点けた。
全国ニュースのトップに猪里市の連続殺人事件が取り上げられた。メインキャスターが固い表情で、
「なぜいま、平穏な田舎で殺人事件が起きているのでしょうか」
と視聴者に問いかける。昨日の事件も含めて、概要と現場の模型を使って説明したあと、現地にいる番組の取材記者を呼んだ。
「南雲さん。そちらの様子はいかがですか」
「はい、こちらは昼間に起きた事件の舞台である稲和県猪里市です。わたくしは、いま猪里署の前にいます。同署内に、猪里市連続殺人事件捜査本部が設置されています。いましがた、捜査本部でメディア向けに会見があり、マスコミ各社は慌ただしい動きに追われています」
「南雲さん。会見というのは、今日起きた殺人と見られる事件のくわしい説明がなされるのでしょうか」
「はい、こちらでは今日の事件に関するくわしい説明がある模様です。現場から中継カメラに切り替えます」
画面は猪里署内の猪里市連続殺人事件捜査本部の中会議室を映していた。昨日と同じ副署長が会議机の後ろに着席し、マイクを握って原稿を読み上げ始めたところだった。
久野は、あとで飯野が何らかの形で会見の模様を送ってくると思いながら、稲和地方訛りの言葉の発表に聞き入った。
お腹がご飯で満たされ、少し眠気が出てきたところで中継と猪里関連のニュースは終わり、政治のニュースに変わった。
壁の時計を見ると夜九時を回り、一五分ほどたっていた。
そのタイミングで、飯野から携帯に着信があった。
「いま、ニュースを観ましたか? 看板は、猪里市連続殺人事件捜査本部と名称を変えました。その部屋で行われた副署長の会見の音声を録音しましたので、念のためお聞かせしますね。
『今日の大木変死事件に関する検視の結果、被害者の李娜さん(二八歳、女性)はペットボトル入りのお茶を飲んだ。お茶に何者かが睡眠剤を混入。不幸にも相棒の楊さんと別行動をとっていた。遺体の司法解剖により、李さんはお茶を飲み二、三〇分して眠った状態のまま縄を首に巻きつけられ、強く縄を引っ張られて窒素死したと判明した。以上』
これだけですが、重要な情報がたくさんありました。いまから原稿を入力します。夜中までには出来上がると思います」
飯野から、ICレコーダーで録音した音声を電話口で聞かされた。飯野の報告を受け、
「馬で引っ張ったのよ。馬は畑の方へ逃げていったはずよ」
と久野は電話口で言った。飯野は、
「畑の方まで行きそびれました。行けば、馬の足跡ば撮れたのに。すんもはん」
と小声で謝った。
「やっせんぼ。それしきのことでしゅんとすんな」
久野は気合いを入れてやった。
「それにしても、現場で馬の足跡ば鑑識に取らせといて、会見ではひと言も触れんかったどん、なぜですか」
「それはまだ因果関係がないからよ。馬が見つかった上で、馬に付いている縄と、李さんの首に付いている縄が同一物だと断定できて始めて、馬が縄を引っ張ったことになる」
「なるほど」
「ただの蹄鉄の跡だけじゃ、そのへんの馬が暴れまわって逃げただけかもしれんじゃろが」
「そういうこつですか。警察も確証が得られるまでは慎重に情報を漏らさんとやりよるわけですね」
「当たり前じゃない。とにかく、早めに原稿書いてね」
久野は半ば呆れて笑いそうになり、こらえた。
電話を切ってから、飯野から追加でメールが届いた。
内容は、久野の推理と警察の見方は一致していた。発表のあと、テレビ局関係者からの質問に対し、眠らされて地面に横たわった被害者を大木の枝に引っ掛け、馬で引っ張って即死させた可能性もあるとの見解で捜査していると認めたらしい。
付近にちぎれた縄があり、馬の蹄鉄の跡が畑に点々と残っていたという事実も、質問のやり取りでわかったことだった。
この辺ではまだ、農耕用として馬を飼うところが一部に残っている。馬が見つかれば恐らく決定的になるだろう。
昨日同様、午後十時に自宅の徳広に電話を入れた。
「もしもし、徳広?」
「ああ、母さん。どうしたの?」
「きょうは、とくに用事はないけど、なにしてた?」
「とくにすることもないから、昼間は友だちと遊びに出掛けた。夜はテレビを観ていたよ」
「そうかい。変わったことはなかったね?」
「ないよ。こっちは相変わらずだよ」
「お爺ちゃん、お婆ちゃんは元気にしちょる?」
「元気、元気。お婆ちゃんが鯵の南蛮漬けを作って、三人で食べたよ」
「そうね。それはよかった」
「ところで、母さん。疲れてない? きょうも猪里市で殺人事件、起きたみたいだね」
「事件が起きると、取材するのが仕事だからしょうがないよ」
「体には気を付けてね。車の運転も」
「あいがと。また、明日電話するわ」
「うん、わかった」
「じゃあ、おやすみ」
「おやすみなさい」
電話を置いて、フーっとため息をついた。自宅にはいつ帰れるのだろうか。まさか、毎日のように殺人事件が起きるかもしれない。とんだゴールデンウィークになったものだ。
午前零時前に飯野から昼間の原稿に加筆したものがメールで送信されてきた。久野は一読し、少し体裁を直してデスクに送った。
その日は疲れて、風呂に入らず寝床で寝入った。
五月四日(金曜日)

朝、雨樋の穴から石畳へ落ちる雨音で目覚めた。もう外は白々としていた。暗い空の下、小雨がサーサーと静かに音を立てて降っていた。近くの田圃から蛙の鳴く声が聞こえた。昔に比べれば、蛙の数もめっきり減った気がする。
布団から起き上がり、丁寧に折り畳んで押し入れに上げた。
父と母の目を通したであろうN新聞の朝刊が、折り畳んで畳の上の卓袱台に置いてあるのが目に留まった。
茶の間に新聞を持っていき、寝間着のままで新聞に目を通した。トップニュースは九州自動車道の玉突き事故だった。
その斜め下に、黒地に白抜き文字で、「二日続きの変死事件」とある。
二日続きの変死事件 三日(木)午前十時半ごろ、猪里市豊吉町の畑の畦道で、中国人女性(二八)が着衣のまま倒れているのを農夫が発見、警察に通報した。猪里署によると女性は死亡、首にちぎれた縄が巻かれてあった。稲和県警は自殺か他殺の疑いで捜査を進めている。県警は、昨日の少女変死事件も踏まえて容疑者の情報を集めている。
記事を目で追うのを終えたとき、携帯電話が鳴り電話に出た。
「もしもし、門倉です」
「門倉さん?」
「あ、いえ、わたしは、今は川畑久野です」
まだ半分寝ぼけていた。電話の相手がだれだかわからなかった。
「川畑さん。『あおば』の高橋です」
「ああ、高橋さん。昨日はお世話になりました」
急に頭がはっきりしてきた。
「実は犯人に心当たりがありもして」
「犯人? ちょっと待ってたもんせ。紙と鉛筆を」
そばにメモ帳とボールペンがあったので、それらを手にしてひったくるように携帯を取る。
「だれです? 高橋さんのおっしゃる犯人とは」
「犯人は……うう、苦しい」
「いけんしました?」
「ちょっと気分が」
「大丈夫ですか? しっかりなさって」
久野は携帯を握りしめ、うろたえた。
「吐き気がする。すみません」
そのひと言を残して、電話は突然切れてしまった。
もう少しで犯人の見当がつくところだったのに。気分が急に悪くなるとはついてなかった。
通り雨が降り、畑で農作業をしていた幸一郎と真由美の安否が気にかかり、傘を持って畑に出ようと玄関に向かった。
玄関に風呂敷包みが置いてあった。開いてみると、弁当を入れるようなタッパーが二つ重ねて置いてある。どこかの家からの差し入れだろうと思い、それを持って台所へ行き棚にしまっておいた。
久野は台所の炊飯器からご飯をよそい、味噌汁と漬物をおかずにして胃袋に流し込んだ。
玄関から両親の声がした。雨合羽姿だ。農作業から帰ってきた様子だった。
「畑に行っちょったの?」
「そうじゃ。そろそろ野菜が穫れる時期じゃで」
幸一郎は答えた。
「濡れて風邪をひくといけんよ。早よ、上がり」
「水曜、木曜と連続して殺人事件が起きたじゃろが。畑で話をしたどん、話題はそのことで持ち切りじゃっち」
幸一郎は眉間に皺を寄せた。
「犯人はいつ捕まるとね」
真由美は久野に訊ねた。
「わたしに訊かれても困るち」
「毎日起きるんが気味の悪かこつたい。水曜は水死体、木曜は木に首吊りちてみんなは言うげな」
幸一郎は近所の人たちの気持ちを代弁した。
「今日は金曜じゃで、金粉にまみれるちてだれかが言うちょった」
真由美は真に受けていた。
「うんにゃ。どっかの金庫から死体があがるじゃろだい」
幸一郎も噂を信じていた。
そのとき、ちょうど時計は朝の九時で、遠くの方で、鐘楼が九回鳴るのが聞こえた。
「いつも鐘楼が鳴るたびに、遺体発見の電話が警察に掛かっちょるちゅう話じゃ」
話はオフレコのはずの秘密にまで及んだ。
「何時にだれが殺されちょるか。推理小説みたいじゃち。考えただけで恐ろしか」
真由美は眉を寄せた。
「だれか知らんけど、玄関にタッパーが置いちゃったど」
話を変え、久野は真由美に言った。
「どこかん人の差し入れじゃっど。今日も遅うなるようなら相棒と一緒に摘まみんさい」
話の途中で、さきほどの高橋のことを思い出し、ちょっと気になることがあるから、と食器をそそくさと流しに持っていき、バタバタと部屋に入って着替えた。トートバッグにタッパー、カメラ、携帯にノートパソコンを詰め、車に乗り込んだ。
今夜、沖本家で通夜があると聞いて、真由美の黒のドレスを拝借した。
朝の道路を飛ばして、猪里署に向かった。
到着すると、飯野はすでに取材を始めている。
「お早う。どう?」
「どうもこうも、金曜日じゃから金融機関は気をつけにゃならんちて、町のみんなは騒いじょります。例の殺人事件で」
飯野はあたりを憚らず、大きな声で話した。
「でもさ。昨日も今日も祝日でしょ?」
「それがいけんしたですか」
「シャッターの降りた金融機関には、ふつう忍び込めんじゃろ」
「そう言われると、そうですね」
「飯野くんは風説を信じとるの?」
「おいは半信半疑です」
「犯人の狙いは別で、ほんとうはだれか一人だけを殺すのが目的で、それをカムフラージュするため無関係な人たちを巻き添えにして殺しちょる気がするわ」
「なるほど。いい推理ですね」
「ところで、『あおば』の高橋さんが犯人に心当たりがあるち、今朝わたしの携帯に電話を掛けてきちょったんよ」
「それは大収穫ですね。で、だれが犯人と?」
飯野の大声に、口を結んで右手の人差し指を立てて、
「それを言う前に、吐き気を催して電話が切れた。そいで、飯野くんを迎えにいき、二人で『あおば』に行こうち思うちょったところよ」
と飯野の耳元で囁いた。
そこへ藤宮警部補が通りがかった。すかさず、飯野は捉まえた。
「藤宮さん。今回の連続殺人で新たに分かったことはありますか」
「報道メモを見てくれ。迂闊なことはこちらから言えん」
二人はすげなくあしらわれた。
その日の午前九時半、報道メモが発表され、次のことが飯野宛のメールに書かれていた。
《所轄署は稲和県警猪里署、容疑は殺人、被疑者不明。被害者は沖本陽菜乃(一五)女、職業中学生。容疑の概要は、五月二日に温泉の女湯で変死した陽菜乃さんの死因が判明。科捜研の検視の結果、中に入れたドライアイスが溶けて炭酸ガスによる中毒死と判明した。致死量は一〇〇グラム。被害者は首を絞められ意識不明のまま、衣服を脱がされて九〇リットルの透明ビニール袋に入れられたと見られる。所持品の卓球用具と着替え、かばん、携帯は、黒のビニール袋に入れられ、裏の駐車場の矢能川に捨ててあった。袋の中にすべてが入っていた。
なお、市の監視カメラには、陽菜乃さんがひとりでコンビニに入るのと出る姿が映っていた。それから先は消息不明》
報道メモに目を通した飯野は久野に訊ねた。
「陽菜乃さんは、渓山荘の湯に入りにきたのではなかですね」
「そりゃ、そうじゃろだい。部活帰りでコンビニに寄っただけよ」
警察はドライアイスの入手ルートをネット販売に絞り込み、購入者情報を開示してもらったのだろうか。
二日たち、やっと一日目の死因が分かった。ネットの情報開示請求を警察がしたならば、ドライアイスの購入元のパソコンのアドレスと所在地も分かるはずだ。
*
「百姓が金庫の中で眠っちょる。十時よ。おやつの時間ね。助けてあげて。隠れん坊ばしちょる」
またしても遺体発見の電話だ。今回も前回と同様、女の声でふざけた言い草である。
「隠れん坊じゃない。きさまが殺したんだ」
「あら、そうなの。証拠は?」
「もうすぐ令状を持って、そちらに行く。せいぜい首を洗って待っちょるがよか!」
刑事課の神取刑事の声は荒々しかった。
電話は無言でプツリと切れた。
そのとき、鐘楼が一〇回鳴った。朝十時を告げる音が南町に響き渡る。それを待っていたかのように、連続殺人事件捜査本部からも制服を着た警官と私服の警官がたくさん出てきて慌ただしくなった。彼らは大急ぎで駐車場へ向かった。
神取刑事は困惑していた。捜査令状を持って携帯会社のauに情報開示を要請して、遺体発見を知らせる奇妙な電話の発信元の番号と名義人、住所などの情報を手に入れた。が、その持ち主の男はインターネットでその携帯を転売していた。
ネットで売った相手は匿名を使い、住所も空き家になっていた。空き家の住所に携帯端末が届いたかどうかはわからないが、大家の話によると、アパートのその部屋は二年以上空室らしく、鍵は掛かっていたが、一階にある郵便受けは開けっ放しだった。身元不明の携帯を使って、犯行予告とも取れる遺体発見の電話を掛けてくる女とは、だれなのか。頭を悩ませていた。
一方で、県警本部刑事部捜査二課の刑事らは、猪里市において市役所の水道局と星永産業の贈収賄事件を追っていた。水道局の元職員からのタレコミがあり、捜査に半年以上かかっていた。
容疑は、水道局の新しい下水道工事の入札に関して、星永産業が受注できるよう便宜を図る見返りに、星永から金を受け取ったというものであった。
ところが、なかなか金の流れが把握できなかった。どうやら、市長が一枚かんでいるのでは、との憶測が課内で飛び始めた。
星永産業から贈った金が市長の懐に入り、市長自らが密かに水道局に星永産業が受注するように便宜を図るよう指示、その際に受け取った金の一部が市長から水道局の職員に流れたらしい、という図式の情報が入ったのだ。
自治体の首長が関与した官製談合である。
税務署からは、市長の払った税金は適正であり、なんの落ち度もないとのお墨付きが出ていた。
星永から市長を経由して水道局の職員に渡った金を洗い出すには、市長本人を取り調べるか、市長個人の口座の金の出入りを調べなくてはならない。おそらく、口利きした市長は、星永産業に、次期市長選挙で何千票かの票集めを依頼したのだろうと推測された。
二課の担当刑事は、市長の口座に不審な金の動きがないことを最近になって確かめ、どうやら自宅のどこかに現金を隠し持っているのでは、と疑り始めていた。
ちょうどそれが四月のゴールデンウィーク前のことである。捜査は大型連休明けに再開されるところだったが、猪里市で連続殺人事件が起き、市長と星永産業の癒着の解明は持ち越しとなった。
その癒着の黒い噂をN新聞の社会部でも一部掴んではいたが、なにぶん、星永産業の殿田専務と関係の深い副社長から直々に、裏が取れていない事実は書かぬよう指示があり、警察発表があるまで社会部は動けなかった。
*
警官が出てきたかと思うと次々にパトカーに乗り込み、サイレンを鳴らしながら、庁舎から続けざまに出ていった。
「また殺人が起きた様子じゃ」
飯野は顔をしかめた。
「飯野くんはパトカーの後を追って。わたしは、一人で『あおば』へ行ってみる」
「わかりもした。気をつけて」
飯野と合流して三〇分もたたないうちに、再び別れた。
豊吉町へ向かっているとき、携帯の着信音が鳴った。車を路肩に停める。現場の飯野からの電話だった。
「やはり金融機関が狙われました。南町三丁目の南陽信金の金庫の中から遺体です」
恐れていたことが起こった。
「飯野くんはそのまま現場を取材して。わたしも遅れて現場に向かうから」
久野は指示を出し、自らはあおばに行ってから南町三丁目へ向かうことにした。
民宿『あおば』に着いた。呼び鈴を鳴らすと夫が出てきた。妻は病院に救急車で運ばれたと言う。
「いけんして吐き気を起こしたか分かりませんか」
「さあ。朝ご飯を食べ終わって、川畑さんに電話を掛けるち言うたとき、吐き気を催して。おいもおどろいてな。救急車を呼んでくれち妻が言うから呼んだ」
「因みに昨日泊まられた客はおりましたか」
「うんにゃ。あげな事件が起きたばかりじゃち、おらんど」
「とにかく、わたしも病院に行ってみます。どこの病院ね?」
「聖愛病院。青野里の」
「ありがとやした」
久野はすぐに車に戻り、また南町に戻ってきた。聖愛病院は猪里市の中でいちばん大きく新しい総合病院だった。
病院に到着したころには一一時を回っていた。途中で聞いた鐘の音がやたらと恨めし気に聞こえた。
病院の駐車場にクラウンを停め、大急ぎで一階の受付に駆け込む。患者名を告げると、「二階にいますよ」と言われた。
二階のナースステーションに行き、高橋峰子という患者が入院しているかと訊ねたら、「二〇五号室にいます」との返事だった。
面会できる時間だったので、四人部屋の二〇五号室を訪ねた。
高橋は廊下側のベッドに仰向けに寝ていた。両目はぱっちりと開けている。
「高橋さん」
年の近い久野はベッドに近づき、高橋の白い手を握った。
「川畑さん、私の見舞いですか」
「あなたのことが心配でやってきたのよ。お体、大丈夫?」
「ええ、なんとか。どうやら食中毒だったみたいです。先生に診断していただいて、一時間ほど前に胃の洗浄と輸液を行ったところです」
「輸液?」
「点滴で、水分や電解質を体にいれることのようです」
「そうなの。たいへんだったのね。いけんしてまた?」
「もしかしたら食べ物でなにかにあたったのかもしれないわ」
「どうぞお大事に。こんな状態で訊くのも気が引けるんですけれど、電話で言おうとしていた犯人の心当たりというのはだれね?」
「私の娘の友人に、市長の娘さんがいまして」
「猪里市長の娘さん?」
「ええ。鹿原志保という大学生です。その子は現在、大学を休学中なんです」
「いけんして、志保さんが犯人かもと?」
「一日目の変死事件を覚えているでしょう? あの沖本陽菜乃さんの家庭教師だったんです。鹿原志保さんが。たしか中二の冬まで」
「なんですって!」
久野は思わず大声を上げ、あわてて口を塞いだ。
「隣町の噂までくわしくはないけれど、娘によると、志保さんは、『教え子の覚えが悪い。丁寧に教えているのに無駄話ばかりに夢中で、腹が立つ』と漏らしてイライラしている様子だったと言います。それだけで犯人と決めつけるのは早計ですけど」
天井を向いた高橋は言った。さらに、彼女はときどき何を考えているのか分からないときがあるから、と娘の由紀も距離を置くようになったというではないか。
久野は頭に入れておくべき、重要な証言だと思った。高橋の勘は当たりかもしれない。
久野は辞去して病室を去り、南町三丁目の南陽信金に向かった。現場について五分後に、鐘が正午の時を知らせた。朝からあちこち回り、お腹が空いたなあ、と思っていると、向こうからやってきた飯野も、
「バタバタして腹が減りもした」
と言った。久野は思いだしたように、トートバッグからタッパーを一つ取り出し、飯野に差し出した。
「これ、近所のひとからの差し入れ。よかったらたもんせ」
「ありがとやんす」
飯野はタッパーを受け取り、さっそく弁当をパクついた。
「こん青いのはヨモギですか」
弁当に添えられていた割り箸で、玉子焼きの緑の〝筋〟を差している。
「かもね。何かは知らんちゃ。もらいもんじゃち」
飯野はおかずだけを食い、握り飯を最後に一気に平らげた。
「それで事件はどうなのよ」
「被害者は百姓の恰好をしちょったそうです。信金の黒い金庫の中の大きか札袋に入れられて死んじょりました」
「今回の連続殺人で初めての男の被害者ね。しかも、密室の殺人か。で、死因は?」
「まだ分かりもはん。司法解剖に回されちょります」
「他に分かっちょることは?」
「遺体発見の電話が午前十時きっかりにあったそうです」
「三人目の犠牲者ね。遺体の発見者と目撃情報はいけんじゃち」
「発見者は南陽信金南町支店の諸村主任です。警察からの電話で慌てて車を飛ばし、支店に入って金庫を解錠して袋を開けたら中に遺体が入っちょって、大騒ぎじゃったと」
飯野の話では、南陽信金は二日の平日に袋の中身を確認して以来、この二日間だれも開けておらず、昨日と今日は休業日。暗証番号も主任以上の役職者しか知らないらしい。外部の人間が札束を入れる袋に触れるのも、金庫を解錠するのも不可能だ。金庫にこじ開けられた形跡もない、とのこと。
いったいどうやって犯人は遺体を金庫の袋に閉じ込めたのか。三日と四日は祝日で店舗は閉まっていた。二日の営業日に殺害して袋に入れたとしか考えられない。
現場を歩き回り、推理を働かせていると、飯野が突然呻きだした。
「いけんした、飯野くん」
その場にうずくまる飯野に駆け寄る。
「吐き気がして……」
「吐き気?」
もしや、と今朝の高橋と結び付けた。
「何か食べ物があたったの?」
「そうかも……。病院へ」
久野はすぐに一一九番へ電話し、救急車を呼んだ。顔の青くなった飯野に付き添いながら、弁当だと心で叫んだ。差し入れの弁当。あの緑の野菜。近所からの差し入れ、とだれかが思わせたとしたら。高橋さん、飯野、久野の三人を狙ったのではないのか。
久野はトートバッグからスマホを取り出し、検索して調べてみた。緑の山菜のうち、五月に穫れて毒のあるものを検索にかけた。トリカブトだの、スズランだの、イヌサフランだの、と毒草がずらずらと出てきた。
救急車の中で中平デスクに連絡を入れ、飯野が吐き気で病院に搬送される旨を告げ、飯野の家族の連絡先、今後の仕事の対処などを訊ねた。救急車はさきほどと同じ聖愛病院に入っていった。
飯野の父が聖愛病院に姿を見せたのは、入院してから一時間と四〇分後だった。久野は、飯野がどうやら弁当にあたったことを詫び、久野の連絡先を父に教えた。
診察した医者に彼の吐き気を催した経緯を説明し、付き添いを飯野の父に任せた。
おまえが犠牲になるぞ――脅迫の言葉が真実味を帯びてきた。もう一つのタッパーを食中毒の証拠品として、警察に届けようと決めた。
ひきつづきデスク宛てに、大至急、ことの経緯をメールする。一連の殺人事件の記事を担当していた飯野が差し入れの弁当を食べて食中毒を起こした様子で、聖愛病院に入院した、と。すぐさま、デスクから返信が来て、飯野の代わりに久野が記事の担当者に指名された。
飯野の携帯を拝借し、その中身の原稿を引き継ぐことにした。
実家に車で戻った。
朝、川畑家に弁当を差し入れた人物はだれなのか。近所の人に訊ねて回った。すると一人の女が浮かんだ。
「背の高かおなごが入っていきよったげな」
隣近所で、早朝に庭の水遣りをしていた顔見知りの主婦が言った。
「ここいらでは見かけん、痩せた女じゃち。水色の帽子に赤い丸眼鏡をかけっせ、わたしに一礼して通り過ぎた。服は目立たんでよう覚えとらん。そうそう、風呂敷包みば持っちょった」
近所の別の主婦がそう明言した。
背の高い、赤い丸眼鏡をかけた痩せ型の若い女――。
服装こそ地味にしていたらしいが、その女はまさしく、ここに来た初日に車で拾った旅の女と特徴が一致している。あのときの女は淵井絵美と名乗り、他県からの旅行者を装ってスーツケースを持って移動していたが、あれは真っ赤な嘘だったのかもしれない。絵美の正体は志保であり、もしかすると弁当を差し入れたのも、高橋の言う大学生、鹿原志保かもしれなかった。
五月二日の陽菜乃さん殺害のアリバイはまだ崩せていないが、犯人グループの一人の可能性は高いと見た。
飯野の携帯を開き、朝の報道メモを再度読み返す。
炭酸ガスの鑑定を鑑識がおこない、ドライアイスによる中毒死と結論付けたという事実から察するに、捜査本部は、当然、被害者の死亡推定時刻を割り出しているはずだ。とすると、警察は志保のアリバイを突き崩すことができると確信しているのかもしれないと思った。
久野は、おぼろげながら、どこかで志保と面識があったと記憶していた。それがいつ頃のことで、なんの取材だったのかはどうしても思い出せなかった。
初日に届いた、取材をつづけるな、という手紙の警告文も、N新聞をはじめとする報道機関各社への狙い撃ちだったのかと思うと身震いした。
一方で、殿田専務が取材の自粛を要請してきたのは、市長の娘が犯行に関わっているからかもと推量した。それなら、圧力云々の筋も通る。
しかし、痩せた女一人で全ての殺人を決行するには、いくつもの問題点があると思った。
例えば、五月三日の事件では、馬の力で被害者を大木に吊るしあげたことや、今日の金庫の札袋に男を封じ込める事件など、女一人で為せる仕業ではない。かなりの腕力が必要だ。共犯者に男の影がちらついた。それは充分にあり得た。男が複数いて、グループで殺人を犯した可能性もあった。
殺人の動機はバラバラで、どれかの殺人を本命にし、他はカムフラージュするために人を殺めていく。猪里市にも恐ろしい殺人鬼が住んでいるものだと思うと、腹は煮えくり返り、怒りと不安で体はぷるぷると震えてくる。
別の見方をすれば、トンネルの出口の明かりが見え、犯人を追い詰められそうだった。そのスリルにぞくぞくしてきた。社会部記者として悪い犯人をあぶりだし、市民を不安と恐怖から救うことができるのはわたしだけだ。ペンの力の大切さと職責の重みが、両肩にずしりとかかる気がした。
車を運転して、ふたたび南町の南陽信金に戻ってきた。途中、鐘が四回鳴るのが聞こえた。
戻るあいだに、蕎麦屋によってかけそばを食べた。
飯野の仇は、絶対にわたしが取ってやるわ――。
気合を込めてウォーキングシューズで現場に入った。黄色の規制テープの近くにいた刑事を捉まえて、訊ねた。
「N新聞の川畑です。病気の飯野に代わり、わたしが事件の記事を担当することになりました。ところで、今回の遺体も連続殺人の三人目の犠牲者と見ていいですか」
「まだくわしい死因が分からんでなあ。しかし、金庫に遺体が入っちょるけん、自殺や事故死ではなかろうよ」
「他殺ですね」
「そりゃそうじゃろ」
「死因はいつごろ分かりもすか」
「報道メモを見てくれ」
「夜には判明しますか」
「なんともいえんな」
「遺体の特徴も教えられんと?」
「うん。教えられん」
「遺体は服を着けちょりましたか」
「それも言えん」
「いくつぐらいの人物ですか」
「それも報道メモに書かれるじゃろうな」
「じゃろうばかりじゃ記事にならんと」
「まあ、そうせかんと。いま、遺体の身元確認をしぃちょるとこじゃが。大体、わしらは公務員ぞ。オフレコ以外で伝えることは法律違反じゃち」
刑事は少し苛立った口調になり、そのまま押し黙ってしまった。刑事から訊きだせることはないとみて、久野は目撃者を探した。
ポロシャツ姿で現場にいた中年の男に訊ねてみた。
「遺体の発見者の諸村さんは知っちょりますか」
「知っちょります。うちの主任です。私も南陽信金で働いちょりますから。私は彼の上司です」
「それはとんだ失礼を。お名前は?」
「三成といいます」
「役職は?」
「係長です」
「三成さんも諸村さんと同じく休日で、警察からの要請があり、金庫を開けたのですね」
「ええ。私の立会いのもと、諸村に開けさせました」
「金庫の鍵はいけんなってましたか」
「うちのはダイヤル式の金庫で、四つの暗証番号を回し、キーで開けるタイプです。番号は私を含めて四人の役職者しか知らんし、キーはふだんから私と諸村以外は、出入りの警備員しか持ち歩いていません」
「きょうはどこにキーがありもしたか」
「私と諸村のそれぞれの自宅に一つずつ」
「刑事の質問のようで申しわけありませんが、最後に金庫を閉めたのはだれで、何日の何時ごろでしたか」
「警察にも言うたんですが、五月二日の午後四時でした。鐘が四回鳴ってからです。閉めたのは諸村です」
「分かりもした。取材にご協力いただきあいがとごわした。もし、なにか思い出したことや伝えたいことがあればこの番号までお願いします」
久野は名刺を手渡し、頭を下げた。
クラウンに乗り込み、今日起きた金庫の変死事件に関して判明した事実をまとめ、デスクに送信した。
《中平デスクへ 以下、原稿です。
金庫の中から遺体 五月四日(金)午前十時過ぎ、猪里市南町三丁目の南陽信用金庫南町支店において、同支店内にある金庫の札袋の中に、身元不明の普段着の恰好の男が入れられているのを、猪里署への匿名の通報により同支店職員が発見。警察の立会いのもと死亡が確認された。支店職員の証言によると、五月二日の四時以降、金庫にはだれも触れていない事実から、県警は他殺と見て死因を調べ、捜査を進めている。猪里市連続殺人事件捜査本部によると、今回の殺人が二日前から猪里市で発生している連続殺人事件と関連があるかどうか、引き続き慎重に容疑者の捜索を行っている。
ここからは私見ですが、密室トリックであり、施錠した金庫をキーで開けられるのは南陽信金南町支店の諸村主任と三成係長、出入りの警備員だけです。わたしは、内部犯行説か、外で殺して袋に入れた内部協力説のどちらかを疑っちょります》
原稿以外に、一連の犯行の続きならば、連続殺人の犯人は複数いるか、協力者のいる可能性があることも付け加えておいた。
猪里署へ向かうあいだ、後ろから「あおり運転」をしてくる黒のスポーツカーがいた。しつこく車間距離を詰め、幅寄せしてくる。ときどき追い抜いて前に入り速度を落とす。
「嫌な車だわ。こんな土地柄でもあおり運転なんてする輩がいるのね」
ひとりごちた。
四時四〇分、猪里署に着いた。藤宮警部補か長里警部が庁舎から出てこないかと期待した。しかし、一〇分たっても二〇分たっても庁舎の出入り口には影すら見えない。
小雨の降る中、雨合羽姿で立ち続けていて、他の用事を思い出した。
「そうだ。タッパーだ。忘れるところだった」
飯野の被害届を出し、同じタッパーの弁当を証拠品として提出すれば、鑑定してもらえると考えた。
「すいません。二人の人間が食中毒の被害に遭いました。これと同じものを食べたんです」
「このタッパーのおにぎりを?」
「いいえ。たぶん玉子焼きの中に混じっている青い葉っぱじゃなかかと」
「青い葉?」
「調べてください。同僚と知人が嘔吐して入院したんです」
そのあと、どういう状況でタッパー入りの弁当を入手したのか、警官に根掘り葉掘り訊かれた。食中毒の被害届は受理された。
一般的に、稲和県に限らず、地方で起きた事故や事件の概要に関して、東京の「日本記者クラブ」に報道メモが配布され、それを東京にいる記者がまとめる。
まとめた中身がメールの形で久野の元に届いたのは、鐘が五回鳴った午後五時のことだった。N新聞は、地元での取材と東京から上がってくる報道メモを突き合わせて原稿を書くことになる。
しばらくして記者クラブから発表された報道メモをまとめたメールの中で、猪里市連続殺人事件に関するメモが一番上に書かれてあった。ゴールデンウィークに起きた事件としては、九州自動車道の玉突き事故よりも価値のある扱いだった。
《所轄署は稲和県警猪里署、容疑は殺人、被疑者不明。被害者名は宇志窪悟(六四)男、職業は農業。容疑の概要は、五月四日(金)午前十時頃、普段着の恰好で猪里市南町の南陽信用金庫南町支店内にある金庫の札袋に入れられた状態で、被害者が死亡していた。他殺の可能性がきわめて高い。死因は不明。現在、司法解剖中》
以上が報道メモの変死体に関する中身だった。農夫が死亡。死因は不明。
久野は、ますます密室トリックだと思った。
これから不審者の目撃情報を集め、現場付近を訪ねて得られる証言などがあればそれも原稿に織り込むことになる。
明日は五月五日だ。官公庁は、今日、明日、明後日までずっと休み。地検に顔を出せるのはゴールデンウィーク明けの七日月曜日になる。今回のような凶悪事件で稲和地検も動いてはいるが、二日の夕方に第一の事件が起きてバタバタしているうちに閉庁時刻をとうに過ぎてしまった。昔の検事なら顔見知りで連絡を取れるが、久野も年を取り、検事もどんどん交替している。現在の検事の連絡先はまだ名刺交換もしておらず、分からなかった。次は七日の午前中まで検事には会えない。
とにかく犯人が逮捕されないかぎり、地検も動きようがないのは確かだ。
他の新聞社、特にライバルM紙との競争もあり、土門編集長も事件の続報が入ればトップ扱いにすると宣言していた。昨日までの話だ。飯野が倒れたいま、社会部の記者として久野しか事件を追う者はいない。
マイナスポイントは、飯野の脱落だけではなかった。紙面に関して変更を迫られた。
五月四日の昼、次のような書簡がN新聞の社会部宛に届いていた。書簡は、事件が未解決で今後も同様の事件が起こるのを見越したように、新聞記事の影響を懸念する内容の意見書だった。
星永産業は、稲和県を代表する会社です。猪里市がこのまま不名誉な新聞記事に晒されるのは、会社にとっても、市民にとっても、けっして好ましくないことです。副社長にも申し入れましたが、要するに、記事の扱いをできる限り小さくしてほしいのです。事実を知る権利は大事です。しかし、事件がせっかくの大型連休の楽しさに水を差し、猪里市を不名誉な場所に変えてしまうようなことはだれも望みません。
会社の総意は全市民の総意と思ってください。この書状を無視して記事を大きく扱うようならば、貴社保有株式の公開買い付けなどなんらかの対抗的措置を取らざるを得なくなるでしょう。くれぐれも、事件については慎重の上にも慎重を期されるよう、筆をすすめていただきたいと願います。
星永産業専務取締役 殿田忠志
殿田専務から直截の注文を付けられ、中平デスクも弱り顔だったらしい。土門編集長も株式公開買い付けだけは避けたい、と頭を抱えたという。
久野は土門編集長からの電話で知り、
「犯人が逮捕されるまで、徹底して記事を一面の目立つところに載せるべきです」
と主張したが、編集長には、
「Qちゃん、すまん。長いものには巻かれんとな。逆らえないんじゃち、おいどん程度の新聞社では」
と通告された。
電話を替わった中平からは、もっと具体的に、
「見出しを小さくする。犯人が逮捕されてから特集を組むように」
と命じられた。
とにかく、事件の燃えさかる火を早く消すためにも、警察の動きを掴んで、犯人を早期に逮捕に導かねばならない――。
その使命感だけで久野は動いていた。
久野は、高橋の口から出た市長の娘、志保のことを知りたくて、志保の家に彼女を訪ねた。女の勘で、志保が犯人に間違いないと思った。連続殺人に女独特のねちっこさがあった。その女と親しくするものが共犯者。ドライアイスを運び、湯船にビニール袋を浮かべたり、馬を用意したり、金庫の袋に遺体を運んだりしたのだろう。最初の犯行も、陽菜乃と顔見知りの志保が車に誘い込み、首を絞めたあとで志保はアリバイ作りを、協力者は犯行のつづきを分担して行ったのだろうと推理した。
そうと分かれば、鹿原市長宅に行ってみなければ、と車を走らせた。
市長の家には人だかりができていた。警察の車も停まっている。ただ、市長は表に姿を見せず、立派な佇まいの雨戸は閉まったままだった。呼び鈴を押してみたがだれも出ず、しばらく待ったが空振りに終わった。
通りががりのおばさんに訊ねてみた。
「これはなんの騒ぎじゃち?」
「市長の娘さんが怪しいち噂じゃ。警察も参考人として娘さんに事情を訊こうとやってきたどん、戸が閉まってだれも出てこんのよ」
「容疑者が娘さんなのはなんでじゃち?」
「志保さんいう娘は、大学を休学中で陽菜乃さんの元家庭教師じゃった」
「そいは知っちょっと」
「彼女は、中国人観光客の泊まった民宿『あおば』の高橋さんとこの由紀さんと友だち。おまけに、今日死んだち噂の宇志窪さんは、二年前の夏祭りで志保さんの尻を触った痴漢じゃち言うが」
「へえ、そうね。犯行の動機は分かりもすか」
「うんにゃ。わからん。でも、被害者すべてに接点があるんは志保さんしかおらんち、みんな言うちょります」
「なるほど。で、肝心の志保さんは自宅に籠っているのかしら」
「さあ、それもわからん。今朝からずっと雨戸は閉まっちょったそうな。おらんかもしれんよ」
「わかりました。ありがとやんした」
おどろくべき口コミだ。報道メモにしか書かれていない被害者の名前がもう住民に知れ渡っている。久野は、これまでの被害者のうち中国人の女をのぞく二人は、たまたま殺されたのではなく、それぞれに志保の恨みを買っていたのではという仮説を立てた。
陽菜乃さんは家庭教師の生徒として覚えが悪く、志保を手こずらせた。宇志窪は痴漢を働いた。二件目の李さんの殺された理由は分からなかった。
とにかく、殺害の動機としてはいずれも薄い。嫌がらせかしっぺ返しをする程度ですまないのには、なにかがある。
もしかすると、これから起こる殺人事件こそがほんとうの狙いで、やはり他はカムフラージュの見せしめの殺人ではないだろうか。
雨上がりの夕焼け空を見上げた。鈍く光る鉛色の雲に、志保の気持ちを投影してみた。明日が最後の殺人かもしれない。警察も志保を追っている。明日は土曜日。土に関係した殺人が起きてしまうのか。
デスクへ送る原稿を書き直してメールで送信したのは、六時を回ったころだった。
《中平デスクへ 連続殺人三日目。以下、原稿です。
農夫の遺体、金庫に 五月四日(金)午前十時過ぎ、猪里市南町三丁目の南陽信用金庫南町支店で、農業を営む宇志窪悟さん(六四)の遺体を同支店職員が発見。警察が駆けつけ死亡を確認した。遺体は施錠された金庫内の札袋に入れられていた。死因は不明。県警は他殺と見て捜査している。猪里市連続殺人事件捜査本部は、今回の事件と過去二件の殺害との関連も含め、犯人の足取りを追いながら、慎重に捜査を進めている》
毎日日替わりで変死事件が起き、市には東京からテレビ局関係者や雑誌記者らが押し寄せて奇妙な盛り上がりを見せていた。平穏だった田舎町はすっかり悪事の舞台として有名になってしまった。
標準語を操るマスコミ連中がぞろぞろと集団で町を闊歩してカメラを回す光景は、かなり奇異に映った。まるで、妖怪の出る秘境を練り歩く探検隊のようであった。それも犯人の狙いだったのかもしれない。
久野は歪んだ心の犯人と向き合い、せめて次の殺人を犯すのだけでも思い留まるよう説得したかった。多少自分が犠牲になってもそうしたかった。真実を報道する以上に、事件を起こさせまいとする良心は、犯行を看過することができなかった。
しかし、市長宅の雨戸は待てど暮らせど、ぴたりと閉じたままでだれも出てくる気配はなかった。
一旦、途中から合流した社会部二年目の記者、品浜を市長宅に残し、峰子の家に引き返して娘の由紀に会い、話を訊いた。夜になりちょうど用事から帰ってきたところで都合がよかった。久野は名刺を渡し、
「最近の志保さんのことを訊かせてくれる?」
と顔を見つめると、怯えた表情で、
「志保とは最近は会ってません。前は普通の礼儀正しい子だったのに、ちょっと周囲と馴染めなくなり出したみたいです」
「それはいつぐらいから?」
「昨年の秋ぐらいから」
「その頃なにかあったのかしら?」
「ちょうど学園祭の季節で彼氏ができたらしくて」
「どんな人?」
「見た目は普通で従順そうに見えました。私が、志保の彼ですか、と訊ねても、照れたように笑って首を縦に振るぐらいで」
「周囲に馴染めなくて具体的にどうなったの?」
「周りは身の丈に合った就活をしていたのに、志保は東京の大企業を狙ってはダメの繰り返しで、みんなと溝ができて一人で抱え込み、悩んじゃったみたいで」
「家庭教師の生徒の話はいつ訊いたの?」
「昨年の夏休みぐらいです。家庭教師がうまくいかないと愚痴ってました。それ以後は知りません」
「わかったわ。貴重な意見、あいがとごわした」
「志保が犯人なんですか」
「それはまだわからないわよ。警察の捜査しだいだわ。マスコミも彼女を犯人と決めつける証拠のない限り、報道できないのよ」
久野は少しでもなだめようと明るい声を掛けた。記者としては耳寄りな話を聞けておおいに参考になった。由紀は高校時代を思い出したのか、遠い目をしていた。
久野は晩も遅くなると迷惑だろうと思い、辞去して沖本陽菜乃の通夜に行くことにした。市長宅には品浜を残しておくことにした。
彼には言って聞かせた。
「品浜くん。市長の家に動きがあれば、すぐにわたしに電話するのよ。どこかから車が迎えに来てもよ。いいわね」
彼に後を託し、沖本家に車で向かった。
暗闇の中、沖本家に到着したのは七時を回っていた。車を向かいの空地に停める。母に借りた黒のドレス姿で、一般参列者として受付で名前と住所、電話番号、勤務先を書いた。
七時から僧侶の読経は始まっていたらしく、用意された広間の座布団のほとんどが参列者で埋まっていた。葬儀社の係員の誘導で空いている座布団に座り、前の人の背中を見た。おもむろに祭壇を仰ぎ見て、生前の沖本陽菜乃さんの明るい笑顔の遺影に、数珠を持った手でそっと合掌した。
座って五分とたたないうちに焼香の順番が回ってきた。座ったまま遺族にまず一礼し、白木の祭壇に向かって一礼して、膝で焼香台まで寄って合掌する。お香をつまみ、目の位置まで持ち上げ、香炉へ落とす。再び遺影に合掌する。膝をつけたまま下がり、遺族に一礼してから立ち上がり、元の座布団に戻った。
通夜は八時に終了し、参列者は互いに挨拶などを交わしながら帰るもの、ご両親を慰めるものに分かれていた。久野は、陽菜乃の知り合いでも、通っていた学校関係者でもなかったので、簡単に喪主の父上に挨拶して、その場を立ち去ろうとしたが思いとどまった。
弔問客の中に、黒の詰襟や濃紺のセーラー服を着た第二中の生徒と思しき数人とすれ違った。友人か部活の仲間だろうか、ヒクヒクと久野の背中越しにすすり泣くのが哀れで、思わず久野ももらい泣きしてしまった。亡くなった現場を目の当たりにしたときの動揺の気持ちと愕然として腰を抜かしそうになった場面が蘇った。
久野は制服を着た女生徒を捉まえ、訊ねた。
「あの、N新聞の川畑と申しますが、一昨日の陽菜乃さんの死ぬ前の行動について訊ねてもよろしいですか」
「はい」
「陽菜乃さんとはどこまで一緒でしたか」
「バス停まで一緒でした」
「そのあとは?」
「陽菜乃は『コンビニで買い物をするから』と言って私たちと別れてひとりでコンビニの方へ歩いて行きました」
「バスの中で、とくに困っていた様子などは話さなかった?」
「いいえ、ふだんと変わらず、明るく元気で。まさか、死ぬなんて……」
同級生らしき女生徒は、ワーッと泣き崩れた。久野は肩に手をやり慰めた。
「陽菜乃さんは悪くない。きっと犯人は捕まるからね」
久野の目にもまた涙がたまり、ハンカチで目を覆って沖本家をあとにした。
道路を歩いて渡り、空地に停めたクラウンを発進させた。品浜の待つ市長の家へ戻るのだ。仕事の合間に通夜の予定を入れざるを得なかったが、はたして失礼ではなかっただろうか。
N新聞の記事を飯野に代わって久野が担当し、事件を報道している。けっして迷惑なことを書いているつもりはないが、残酷な事件を伝えつづけるにつれ、亡くなっていった死者の魂が浮かばれるだろうかと自問してしまう。記事が凄惨な事件をおびき寄せているような錯覚に囚われ、原稿を上手く仕上げれば仕上げるほどやるせない気持ちになり、口の中になんともいえない苦味を感じた。
九時過ぎまで市長の家に張り込んで待ってはみたが、灯りもつかず、食事の匂いもしない。物音すら立たなかった。取り囲んでいた人垣は一人へり二人へりして、いつの間にか警官二人を残すのみとなった。
人の噂を聞いた。
「市長と奥さんは、隣の市の高級ホテルに宿泊し、事態を見守っているとよ」
「あたいが聞いたところでは、市長は病気を理由に聖愛病院に入院し、いちばん料金の高か個室に入って面会謝絶だち」
あちこちでさまざまな憶測が飛び交っていた。
肝心の娘、鹿原志保に関しては、もしかすると男の家か、少し離れたところにあるホテルにでも潜んでいるのではと疑り始めた。
そのまま九時半まで久野は何も口にせず、品浜と一緒にひたすら事態の推移を見守った。
夜一〇時に最後の報道メモがメールで送られてきた。
今日の殺人に関して、死因は農薬の大量摂取による死亡と判明した。農夫が作業をしていたときに持ち歩いていた水筒のお茶から農薬の成分が検出された、とのこと。
久野はすぐ原稿に、《農夫は持ち歩いていたお茶を飲み死亡。お茶に農薬が大量に混入》と死因を反映させ、追加のメールを再送信した。
一〇時過ぎに車を出して猪里署に向かった。品浜をそこで降ろし、扉の閉まった門の外から庁舎の出入りがないかを確かめようとしたときだった。灯りのついた一階の部屋の窓が開き、警官が手招きした。
門の脇の通用口を通り、庁舎の中に入る。警官は廊下の長椅子にかけるよう指示した。
「川畑さんじゃったな。見つかったよ。食中毒を起こした成分が」
「やっぱり玉子焼きからですか」
「これがその鑑定結果じゃ」
蛍光灯の下で、警官は、科捜研の鑑定した結果を書いたワープロの紙を見せた。
「あんたの言うとおりじゃ。玉子焼きの緑は、無毒のヨモギと毒の成分を含むイヌサフランの葉。イヌサフランが体内に入ると食中毒を起こす」
「それで、指紋とかは」
「検出されなかった。差し入れの心当たりは?」
「近所の人が背の高い女を見たと」
「やはり、被疑者と一致してるな」
「鹿原志保ですね?」
「おっと、そげな名前をあげられても困る。そちらの事件は捜査中だ」
「わかりました。遅いのでそろそろ帰ります」
「犯人はなにをしでかすか分からんから、気をつけてな」
「はい、ありがとうございます」
庁舎を出て、車で実家に戻った。実家に着いたのは、一一時前だった。
居間で喪服を脱ぎ洗面所で化粧を落とした。髪留めを外して髪を下ろし、ラフな恰好に着替える。
「そら豆があるよ。たもらんね」
「あいがと。家の庭で穫れたのね」
「じゃっち。穫れたてじゃち」
「箸が進むのよね」
久野は、食卓に出された塩茹でのそら豆から箸をつけ、ある程度食べると、こんどは冷めた天ぷらをレンジで温め、ご飯といっしょに食べた。風呂はシャワーで済ませた。
中平デスクから返信があり、
《疲れているだろうけど、もう少しがんばってくれ》
と慰めの言葉が綴られていた。
部屋の灯りを点け、一人で大学ノートを開く。それまでの経緯を整理してみた。のちに特集記事を組んだときのためでもあった。
連続殺人の裏付けを考えてみた。毎日違う犯人が関わった殺人なら、相当悪質な犯行グループだ。猪里市を危険地帯に陥れて喜ぶような、心ない部外者だろう。初日の温泉変死事件では、証拠品としてドライアイスが使われた可能性が高く、遺留品は陽菜乃さんの卓球道具などが入ったかばんと携帯。それらは矢能川から見つかった。
二日目の大木事件は、証拠品としてちぎれた縄と馬の蹄鉄の跡だった。遺留品は李さんの衣服とパスポート。
三日目の金庫事件は、証拠品として被害者の持ち歩いていたお茶から農薬の成分が見つかった。遺留品は仕事着。
連続殺人と考えるのは、犯行時に目撃者がいない点、殺し方がナイフや銃などでなく、化学品や動物、劇物などの知識を持った者がいて、それらを殺人の道具に利用した点、曜日と殺人に関連がある点、鐘の鳴ったのを合図に犯人が警察に電話で遺体の発見を知らせてくる点が共通していることによる。
犯人はほぼ一〇〇パーセント鹿原志保と彼女に関係した男らに間違いない。警察も、ドライアイスの入手ルートから割り出したパソコンの特定、ビニール袋から検出された炭酸ガスの鑑定、陽菜乃さんの立ち寄ったコンビニなどの監視カメラの解析、被害者周辺と殺害現場付近での訊き込み、民宿のおばさんの証言、信金職員または警備員に対する尋問などから、犯人を追い詰めているはずである。そのときは、まだ、市長の娘のほんとうの犯行動機を知り得なかった。
初日から久野という記者個人への脅しがあり、警察への挑発もあった。稀に見る、周到で執拗かつ大胆な犯行は、一見するとバラバラだ。ところどころに犯人と目される志保の私憤が垣間見えるが、彼女本人の情緒の未熟さとも取れた。市長の娘でありながら、市民全体を晒し者にするような人間は、狭い田舎ではとても普通に暮らしていけないし、馴染めないはずだった。
明日も猪里署に張りついて、犯人の殺人事件に振り回されるのかと思うと、取材や原稿入力の仕事も気が滅入った。
とにかく、個人的な何かが潜んでいる。犯人が、いつ、だれを襲うのかが全く読めず、犠牲者の目星もつかない。
恐らく、捜査本部も何かの証拠は掴んでいるだろうが、いずれも物証と犯人を直接結び付ける決め手を欠いているのだろう。町の噂と状況証拠だけで逮捕、送検し、検察が起訴に持ち込むには時期尚早すぎる。
徳広に電話するのも忘れ、仕事で疲れた体を早く休めたくて、風呂にも入らず、寝間着に着替え、すぐに寝てしまった。
その晩、犯人と対決する夢を見た。志保がピンクのスカート姿で夢に出てきて、
「たとえどんな正義面をしていても、真実を相手に突きつけることほど残酷な所業はないのよ」
と目を剥いて言った。夢からハッと覚めた。
「真実を突きつけるって、記事を書くことかしら」
寝ぼけながら、心がザワザワした。
きっと町民らも、残忍な犯行手口を含めて、事件の真相が日本中に知れ渡る風評を恐れているのだろう。記者としての職責と、元市民としての愛着が睨み合って心は揺れ動き、チクチク痛んだ。
五月五日(土曜日)

朝は夢のせいで二度寝して遅く起きた。幸一郎がランニング姿で寛いでいる。真由美はエプロンをつけ、台所から、
「よく眠れたね?」
と訊ねてきた。
「まあまあ。ちょっと疲れがピークに達しているかも」
久野は言わなくてもいいことを口走ったと後悔した。
「大丈夫け? 疲れちょるときは失敗が起こりがちじゃち」
「うん。気をつける」
母にいらぬ気を遣わせてしまった。でも疲れているのは確かだった。体が重い。
洗面所で顔を洗い、瞼の垂れ下がった素顔を見た。部屋に戻っていつもの服とカーディガンに着替えた。
台所に行き、新聞は読まずにテレビを点けた。東京キー局のワイドショーで、猪里市連続殺人事件の特集が長々と流れている。そのあいだに炊飯器からご飯をよそった。
「視聴者の皆さん。楽しいはずのゴールデンウィークのさなか、稲和県猪里市では、残忍な連続殺人事件が止まりません。なんということでしょうか。住民の方々も毎日不安に怯えている模様です」
テレビカメラはリポーターの男を映し、男は長々と説明した。画面が切り替わり、市民の生の声になった。
「おいどんも水曜、木曜と事件があったので警戒しちょったけど、金曜にまた事件が起きて、ほんとうに残念です」
市民の一人が首から下を映され、答えている。
「猪里もこげなことで注目を浴びてかなわんちよ」
真由美は渋い顔をして横目でテレビを睨んだ。
「じゃっど。だけどよぉ。なんとか警察の力で犯人を捕まえてもらわにゃ」
久野はご飯を口の中に運びながら答えた。
テレビはなおも昨日の事件の様子を報じた。
「昨日午前十時頃、匿名で遺体発見の電話が猪里署に届きました。市内に鐘楼の櫓があるのですが、鐘の鳴るのに合わせるようにして毎回警察に電話があるらしいです。猪里署員が現場に急行し、南陽信用金庫で遺体が見つかりました。職員で主任の方が金庫を解錠すると、おどろくべきことに、札袋の中に男性の遺体が入っていたのです」
そこでいったん南陽信用金庫の建物全体が大きく映し出され、すぐにコマーシャルに入った。久野はテレビをリモコンでオフにした。
待ちかねていたように、携帯の着信音が奥の部屋のトートバッグから鳴り出した。
朝からだれだろうと思った。
「もしもし、徳広だけど」
息子だった。ほっとした。
「なに? 何かあった?」
「あったのはそっちの方でしょ。事件が多くてたいへんじゃないかと思ってさ」
「まあ、徳広まで心配してくれるのね。ありがとう、だいじょうぶよ」
「犯人、早く捕まるといいね」
「そうね。もうすぐ捕まるわ。きっと。それより、内海の家は変わったことはなかったの?」
「全然。友だちと映画に行ったぐらいで退屈しちょるよ」
「ごめんね。せっかく猪里のお爺ちゃんたちと再会できるはずだったのをだめにして」
「いいって、そんなこと。早くこっちに帰ってきてよ。母さんの作るハンバーグが食べたいな」
「まあ、嬉しいことを言ってくれるのね。もうじき帰れるからね」
「仕事、がんばってね」
「はい、分かったわ。じゃあ、また」
久野は息子からの電話を切った。ちょっぴり元気が出て鼻を鳴らした。
いつものように出掛ける準備をして、「行ってきます」と告げた。幸一郎は庭いじりをしていたが、おう、とだけ言って片手を挙げた。
クラウンに乗り込み、窓を開けて走りながら空気を入れ替えた。
途中、コンビニに寄り、クロワッサンを買った。
道なりに走り、ガソリンスタンドで給油するために入った。ガソリンを入れてもらっているあいだを利用して、久野は実家から持ってきた五日付のN新聞に目を通した。
N新聞の朝刊の一面の左下の方に、連続殺人事件の記事が出ていた。扱いは三段抜きの見出しで、ある程度目立っている。殿田専務はまだ怒っているかもしれない。
三日続きの殺人か? 猪里市 四日(金)午前十時過ぎ、猪里市南町三丁目の南陽信用金庫南町支店で、農家の宇志窪悟さん(六四)とみられる遺体を同支店職員が発見。警察が駆けつけて死亡を確認した。遺体は施錠された金庫内の札袋に入れられていた。死因は農薬による劇物死。県警は他殺と見て捜査している。今回の事件と一昨日から続く二件の殺害との関連を含め、猪里市連続殺人事件捜査本部は引き続き犯人の足取りを追っている。
ほとんど、原稿の内容のままであり、死因を加えた点を確認し、久野は新聞をポンと助手席に放った。
猪里署の二つ手前の交差点で鐘が九回鳴った。赤信号のあいだに、携帯のメールフォルダを見たが、新しいメールは来てなかった。
庁舎に入り、駐車場に車を停めた。昔の新米記者時代と違い、庁舎の中に入れないのが歯がゆかった。長里か藤宮を待ったが二人の姿は拝めず、すでに中に入っている様子だった。
事件が発生するまで、こちらはまた受け身の状態で待たされるのかと思っていたら、一台の車が入ってきた。稲和県警と書かれたパトカーがゆっくり停車する。中からグレーのスーツ姿の刑事が車を降りて出てきた。どこかで見かけた顔だ。背は高くないが肩幅が広く、いかにも体育会系のようながっしりした体格で、六〇過ぎの風格を漂わせている。付き添いの制服姿の警官が、
「島谷警部。捜査本部の今日の会議は……」
と説明する声が耳に入った。名前に馴染みがあった。新人時代の思い出が蘇った。髪こそ薄くなっていたが、あの島谷である。サツ回り初日に会った刑事――。サツ回りを終えたあとも、しばしばその活躍ぶりや評判を耳にしていた。優秀かつ敏腕で、難事件をいくつか担当し、解決に導いた功績を持つ刑事。あれから出世の道を歩まず、現場に残りたいと申し出て、警部の職に留まったという噂を聞いていた。
ついに、切り札の投入か。
県警本部の島谷刑事が捜査本部に加わり、士気が上がるのを期待した。久野は事件の解決に胸を膨らませた。今のうちに昼ご飯を確保しておこうと、歩いて庁舎近くのスーパーに行った。お菓子と紅茶のペットボトルを買って、庁舎前の車に戻った。
スーパーでタバコ屋のおばさんを見かけた。向こうから話し掛けられた。昔から知っている、南町に三軒ほどあるタバコ屋の一つだ。
「陽気がいいわね」
「じゃっち。五月になって春物を着ていると、日中に暑くなるでしょ。汗ばんで」
久野は朗らかに笑った。
「じゃっど。上っ張りを脱がにゃならん」
「そうなのよ。わけ人たちと違って着る服に困りますよねぇ」
久野はクラウンに戻るのをあきらめ、しばらく相手と話を合わせた。
「川畑さんは新聞記者を今もやっちょるの」
「ええ。お産と育児で少しのあいだ休職した以外は、かれこれ二五年やっちょります」
「へえ、そうね。ベテラン記者じゃち」
「そうなんですが、今回のような事件は初めてです」
「町も東京からマスコミが押し寄せて、騒がしゅうてなあ」
「ほんとうにねえ」
相槌を打つと鐘の音が十時を知らせた。
「事件の犯人は市長の娘じゃち、みんな陰では言うちょるよ」
「じゃろだい。まだ裏付けは取れちょらんけど、わたしも足取りを追ってるんよ」
「志保さんは猪高山の洞窟でキャンプしとるちて、ある人から聞いたどん」
「猪高山でキャンプを? ほんとうですか」
「噂じゃけど、夜に山道から降りてきて、南町あたりを歩いちょるのを見かけたちゅう人もおるでな」
「分かりもした。猪高山に登ってみます。ありがとやんす」
重要な情報を得た。意外なところに真相は隠れているもんだ。
猪高山といえば、幸一郎が登山好きでよく知っている。幸一郎に訊けば、目ぼしい洞窟が分かるかもしれない。
スーパーから歩いて車に戻ってきた。トートバッグの携帯を開くと、社内からメールが届いていた。同じN新聞の遠山という中堅社員からだ。他のネタの取材を手伝ってくれという主旨だった。
遠山は政治部だ。今、社会部で大事件が起きているのに、なぜ部を越えて協力する必要があるのだろうと首をひねった。そもそも遠山とは話を交わしたことすらなかった。政治部に協力せよなどという話は、デスクからも聞いていない。すぐに断りのメールを入れた。しかし、その後もたびたびネタの取材を手伝ってほしいとしつこくメールが届いた。
仕事の命令は部署のデスクから割り振られ、政治部の遠山の仕事を、畑違いの社会部の久野が引き受ける事態など、本来あり得ない。「援軍」はよほどのことがない限り、しないはずだった。
奇妙なメールにおかしいと勘づいた。久野は遠山をかたる人物が別にいると思った。その人物をおびき寄せようと、午後二時に南町の喫茶店で会いましょう、と約束を取りつけた。だれかが遠山のアドレスを悪用し、なりすまして仕事の妨害をしてくる予感がした。気づかぬふりをして敵の尻尾を掴んでしまおう。ベテラン記者の魂に火が点いた。
猪里署に停めた車で待ちつづけたが、動きがない。今日は土曜日だ。土。どこの土に遺体を埋めるのか。南町や豊吉町など多くの町は、畑と田圃だらけだ。そこいら中に土がある。
一時間たち、鐘が一一回。二時間たち、鐘は一二回鳴っても警察に動きはなかった。記者クラブから回ってくる報道メモのメールも来ない。手持ち無沙汰に思わず欠伸が出る。
五月の照りつける強い陽射しで車内の温度はぐんぐん上がり、暑くて窓を全開にした。
待ち合わせの時刻が迫るのに、犯人はいっこうに動いてくれない。
鐘が一回鳴り、それを合図にクロワッサンを頬張った。
あと一時間で待ち合わせ場所の喫茶店に行かねばならない。
すると、庁舎から警官が二〇人ぐらい出てきた。殺しがあったのかと訊ねたかった。
パトカーはサイレンを鳴らさず、庁舎を次々と出ていく。遺体が発見されたのではないだろうかと思った。情報を求めてパトカーの後を追った。
パトカー数台は、猪高山方面へ向かった。犯人の身柄を確保するためなのかもしれない。先程のタバコ屋のおばさんの話が脳裏をよぎった。待ち合わせ時刻に間に合わなくなるのは分かっていた。犯人逮捕の写真の方が大事だからしかたのないことだった。
警察は麓に到着した。停まったパトカーからぞろぞろと制服姿の警官が出てくる。久野も車を停め、トートバッグを持って後に続く。
しばらく山を登った。やがて、洞窟が目に飛び込んできた。キャンプをした痕跡がくっきりと残っている。そこには、木炭で火をおこし黒く煤けた跡があった。だが人影はない。
「どうやら逃げられたか」
先輩らしき警官の声が向こうから聞こえてきた。こんなことなら、前もって幸一郎に洞窟のくわしい場所を地図に描いてもらうんだったと悔やんだ。
腕時計を見ると、約束の二時を過ぎていた。
*
「どこかでよく目にする人が工事現場の土に埋まってるわ。きっと。いい気味ね。東の原町よ。だって、私が殺したんだもの。鐘が二回鳴ってるわね。二時ね。ふふふ。見つけてあげて」
今回も猪里署の電話が鳴り、初めて殺害を告げて電話は切れた。またもや、女の声だった。警察が犯人を逮捕できないのをあざ笑うように、ふざけた言い草である。これで四回目だ。
「今回は、殺した、と女が言っちょる」
「場所はどこですか」
「東の原町の工事現場じゃち。すぐに応援を頼もう」
捜査一課の刑事は電話に手を伸ばした。
*
警官は、下山する組とキャンプ跡に残る組の二手に分かれた。久野はどうしようかと少し迷い、下山する組を追って車を停めた場所に帰ってきた。
下山組はパトカーに分乗し、サイレンを鳴らして発車した。事件だ。
二時に会う約束をどたキャンして殺人を実行したのか。ここに来たことにほぞを噛んだ。二時に遺体発見の電話をかけたのだろうと思った。
一時間ほど走り、東の原町の工事現場に到着した。腕時計を見ると、ちょうど午後三時半だった。すでに二台のパトカーが停まっている。
現場にはブルーシートが掛けられ、こんもりとした盛り土を囲むように規制テープが張られていた。
「殺人ですか」
久野は近くにいた警官の顔色を見た。
「まだ分からんち。遺体じゃ」
怒ったような声で言い返された。その顔は明らかに動揺している。
現場の写真を撮ろうとすると、
「ブルーシートは写さんようにな」
と分かりきったことを言ってくる。小さな脚立を広げ、上に乗って工事現場と民家をカメラに収めた。
「遺体を見つけたち電話はありもしたか」
「そげなこつは言えん。公務員じゃち、職務に関わる秘密は喋れん」
取り付く島もない言葉に、質問を変えてみた。
「島谷刑事は敏腕と聞いちょりますが、今回で連続殺人も終わりになるんでしょうか」
「なると期待しちょるよ。わざわざ他の事件を外れて駆けつけてくれたからね」
「ご苦労様です。わたしはこれで」
久野は報道メモが出るまで、自分の足で目撃情報を集めて回ろうとした。
近くの民家で話を訊いてみた。
「すんもはん。N新聞の者です。近くの工事現場で見つかった遺体についてお訊ねしたいことがありもして」
久野はトートバッグのICレコーダーのスイッチをそっと押した。
「なんじゃち」
化粧っ気のないおばさんが顔を出した。
「工事しちょるところの遺体のことで」
「ああ。あの男の人かいな」
「ご存知ですか」
「あれは市議の鷺沼さん。哀れな死に方で」
「どげな死に方じゃっち?」
「土の中に埋められちょった。作業員が、土の色がそこだけ違うもんで盛り土を三〇センチばかし掘り起こしたら、下着姿で死んじょった」
久野は重要な証言を得て胸が高鳴った。
「市議の様子になにか変わったところはあっじょっど?」
「ええ、なんぞ体中に赤い、虫刺されの跡があったっち聞いちょるよ」
「虫刺され。そげなこつで死ぬやろか」
「わからん。毒虫かも」
「発見した作業員はいまどこに?」
「警察に呼ばれてパトカーに乗ったで」
「情報、あいがとごわした」
いったんクラウンに戻り、大学ノートに判明した事実を手早く書き込んだ。ICレコーダーはスイッチを切った。万一の道具だ。
南町の猪里署へ車を走らせた。
庁舎に着き、携帯を開いた。報道メモがメールで届いていた。今日の事件に関することだった。
《稲和県警猪里署管内。容疑は殺人、被疑者不明。被害者は鷺沼紘一(六二)男、職業は市議会議員。容疑の概要は次のとおり。五月五日(土)、被害者は下着姿で猪里市東の原町の工事現場の盛り土に埋められ、死亡していた。工事の作業員が発見、県警が駆けつけ死亡が確認された。体中に赤い、虫に刺された跡があった。他殺と、事故死及び死体遺棄で調べを進めている。死因は不明で現在司法解剖中》
民家のおばさんの喋った内容とだいたい一致していた。ただ、虫に刺されたのが死因に関係していそうな気がして、不気味だった。
もう一通のメールを見る。政治部の遠山を語る人物から届いたメールだった。中を開いてみた。
《待ち合わせ場所を指定するから必ず一人で来てほしい。鳴沢ダムの貯水池に午後五時半に来てください》
きっと犯人が遠山の名刺を悪用して、久野と接触を図ってくるに違いない。会う目的は不明だが、犯人と直接話をするチャンスだ、とやる気に火が点いた。自分たちの方から犯行を暴露するわけもなかろうが、都合の良い時間と場所を選んできた。
「慎重に行動しないとね。相手の罠にはまるわ」
久野は心の中で呟き、用心深く応対すべきだと覚悟した。
あとになってみれば、久野が上司の指示を仰がず、警察にも連絡せずに単独行動をとったのは、軽率でベテランらしからぬ行動だった。
しかし、そのときは犯人に自首するよう説得を試みたい気持ちと、相手がもし襲ってきても力でねじ伏せてやるという度胸が勝っていた。
庁舎から出入りするのは制服姿の若い警官ばかりで、午後も長里や藤宮の顔は拝めない。
車の中で長く座っていると体を動かしたくなった。ドアを開けて外に出て、軽く足を曲げ伸ばししてみた。肩も凝っていたのでぐるぐると前後に回してみる。
体を動かしながら、改めて犯人の殺害動機を考えてみた。休学中の志保は市長の娘なのに、なぜ親の顔に泥を塗るような真似をつづけているのか。殺人のほんとうの目的は何なのか。心に闇を抱えているのは間違いない。が、人を殺すだけの激しい憎しみはどこから沸き上がってくるのだろう。
第一の被害者は志保が家庭教師をしていた生徒。首を絞め、全裸状態でビニール袋にドライアイスとともに入れて殺害した。覚えの悪い生徒だというが、若い命を奪うほどではないはずだ。
第二の被害者は香港からの旅行者。志保の友人の民宿に泊まっていた。近隣で訊いた話によると、英語が通じない、現金しか使えない店が多いなどと不平を並べ、寺院で騒いで境内にゴミを捨てて帰ったらしい。外部の者に対して命を取るに値するほど李さんが悪さをしたわけではなかろう。志保との接点もない。
第三の被害者は広大な畑を持つ農夫で、お茶に農薬を混入されて薬殺された。まだ訊き込みが不充分で志保との接点が見えてこない。志保に痴漢を働いたというのは、あくまで噂の段階だ。
そして第四の被害者は市会議員の男。これもまだ訊き込みが足りないけれど、一番市長と関係が深いのではなかろうか。市議と志保の具体的な接点こそまだわかってないが、なにかありそうな気がした。
これらのいずれかの殺人に深い怨恨があり、他はカムフラージュするための偽装殺人――。
会って話をしてみないと腑に落ちないような疑問が、泡のように浮かんでは消えた。猪里署を出て鳴沢ダムへ向かったのは四時半を回っていた。
一時間ほどして鳴沢ダムの貯水池に着き、車を停める。
待ち合わせより五分ほど早く来た。どこを捜しても人影は見当たらない。
柵越しに見える池の水面を見つめた。風が吹いてさざ波が立ち、立った波は静かにじわじわと広がっていく。空を見上げると、雲が山の上にたなびき、太陽をうっすらと隠している。
本来なら、仕事を邪魔するようなメールは見て見ぬふりをして構わなかった。遠山の名刺は、政治絡みの取材で市長がもらったのを、志保がこっそり拝借したのかもしれない。絶対に相手は遠山ではない。犯人もしくは共犯者だと確信していた。
最初に記事を書くなと警告したときから、いつか久野と対決しようと犯人は決めていたのかもしれない。
そのときタクシーがやってきて、静かに停まった。扉が開き、赤い靴がちらりと見える。
ハッと息をのんだ。姿を現したのは、あのときの背の高い旅の女、絵美。今日はデニム姿で、カツカツと靴音を響かせ、こちらへ向かって歩いてくる。
「やっぱりあなただったのね」
「そうよ。私が事件の鍵を握っているの」
絵美は赤い眼鏡を外し、束ねていた後ろ髪をぱらりと解いて、長い髪を山から吹き下ろす風になびかせている。
「あなたは絵美という偽名を使って旅行者に扮した。でも、ほんとうは市長の娘、鹿原志保よね」
「それは認めてあげるわ」
「あなたが犯人なんでしょ? はっきり犯人と認めて自首しなさいよ」
「さあ、どうかしら。証拠でもあるの?」
志保は顔色ひとつ変えず、小馬鹿にしたような言い方をした。
「わたしは許さない。どんな理由があろうと」
「言っておくけど、私は陽菜乃さんの遺体が発見されたとき、あなたたちと一緒に温泉に向かっていたのよ」
「それはあなたの仕組んだアリバイ工作よ。あなたは、共犯者か協力者の車の中にでも陽菜乃さんをおびき寄せ、彼女の首を絞めて気絶させた。そして、何人かで服を脱がせ、透明のビニール袋に致死量に相当するドライアイスと裸の陽菜乃さんを入れた。渓山荘の湯船に共犯者にビニール袋を浮かべさせる役をまかせて、あなたは素知らぬ顔で車を降り、スーツケースを引いて旅行者のふりをしてわたしたちに近づいた」久野はそこで言葉を区切り、ふーっと息を吐いてからつづけて、「おそらく、卓球部の練習着や道具などは赤のスーツケースに入れておいてあとで矢能川に捨てたのね。あなたは旅行者を装い、死亡推定時刻までわたしたちと一緒にいた」
「なかなかの名探偵ぶりね。私はほんとうに旅行中だっただけよ。それに、どうやってドライアイスなんて手に入れたのかしら? そもそも、ドライアイスなんかで人間は中毒死するものなの?」
「それはあとで調べれば、ネットにいくらでも出ていると思うわ。ドライアイスが危険な炭酸ガスに変わるのは、食品工場の人に教わってメモしたわよ。ドライアイスは溶けると七五〇倍の容積になって、たった一時間でも密閉された空間では人体に危険な値を越えることもあるって聞いたわ」
「まあ、そうなの。勉強家ね。よくそこまで調べたこと。褒めてあげる。でも、三日付のN新聞の記事には、二日の被害者の死因がドライアイスだなんて、どこにも書いてなかったわよ」
「それはわざと伏せておいたのよ。わたしたちマスコミ向けに、警察から報道メモというものが発表されるの。その情報を取捨選択して記事にする。報道メモには、ドライアイスによる中毒死とたしかに書いてあったわ。他人が面白がって真似ると危険だから活字にするのを控えたのよ」
「なるほどね。警察の発表を垂れ流しにするだけじゃないのね」
「皮肉はいいの。それより、殺人なんて、けっしてやってはいけないことよ。どんな理由であれ」
「私に突き落とされたくせに、いい度胸ね」
「それだけ元気があるのなら大学に戻りなさい」
「ふん、説教か。父と同じね」
「何なの? ここへ呼び出した目的は」
「私はN新聞が嫌いなの。新聞だけじゃない。猪里全体も嫌い」
「読まなきゃいいでしょ。わたしたちは公正に報道してるわ」
「とにかく目障りなの。あなたのような人間が猪里市をうろちょろしているだけで」
「なによ、それ。どういうこと?」
腹が立ち、食ってかかろうと言葉を選びかけたそのときだ。志保の長い足が一周し、後ろ回し蹴りが久野の顔面に飛んでくる。危ういところで頭を後ろに反らしてよける。
後ろ回し蹴りが通用しないと見るや、相手は間をつめて飛びかかってきた。大柄の体を利用し高く飛び上がると、素早く右膝を曲げての飛び蹴りが久野の体に炸裂する。久野は飛んできた蹴りをよけようとしたが、左腕に命中してしまった。
「痛っ!」
思わず声が出て、右腕で左腕を押さえる。
志保は口を歪めてニヤリと笑うと、長い手を伸ばし、久野の両肩をがっしりと掴んだ。少し腰を引いてから膝蹴りでも見舞おうとしたわずかの隙を突いて、肩を掴まれていた久野は相手の腕を持ち、自分の背中を丸めるようにして地面につける。相手の勢いを利用して右足を腹にあてがい、そのまま跳ね上げる。
カーディガンが汚れ、スカートがめくれようがお構いなしだ。
次の瞬間、志保の体がふわりと宙を舞い、見事に巴投げが決まる。志保は背中からどさりと落ちた。
「くぅ……」
痛いのを我慢するような声を漏らし、手で背中を押えた志保を、久野は上半身だけ起こして体をよじり、睨みつける。
「これでも中三までは柔道を習っていたのよ。負けないからね」
デニム姿の志保は尻を地面につけたままでじりじりと後ずさりしながら、フハハハハと急に大きな口を開けて笑い出した。
「な、なんなのよ。そのふてぶてしい笑い声は」
久野は自分より二回りは若い女にだしぬけに笑われ、顔を真っ赤にして怒鳴った。頭までおかしいのかしら。ゆっくりと立ち上がり、
「なによ。反撃するなら、かかってきなさい」
尻もちをついたまま見上げている志保の目を見つめ、周囲に目をやったそのときだ。
サササッとスニーカーのような忍び寄る微かな足音がしたかと思うと、急に目の前が真っ暗になって、次の瞬間には意識が薄れ気を失った。なにも聞こえず、なにも見えず、時間や空間の概念がどこのなにを基準にしているのか皆目わからない。
どれくらい意識が飛んでいただろう。
遠のく心の沼から這い上がるようにして、ぼんやり浮かぶ橙色の光に気付いたときには、寝床に仰向けに倒れ、呻いていた。
急に目を開け、天井の光のあまりの眩しさに半開きになった。と同時に、後頭部がズキンズキンと痛み出した。そこでやっと、あのとき背後から何者かが素早く忍び寄り、後頭部を思いきり強く殴りつけて気絶させたのだ、と推測できた。志保は、前もって協力者を現場に隠れさせ、久野を後ろから狙わせていた。その瞬間を視界に捉えた。だから、気味の悪い、不敵な笑い声を上げ、勝ち誇ったような顔を浮かべていたのだろう。
「おお。やっと気づいたち」
知らないおじさんが顔を覗き込む。
「ここはどこ?」
「知らんと?」
「知らんち」
「じゃろだい。わしの家じゃち。女の声で電話があってな。貯水池に人が倒れとるち言うて電話が切れもした」
「女って?」
「わしも知らん。聞いたことのない声じゃち。とにかく車を出して助けに行ったんよ」
「白のクラウンはありましたか」
「うんにゃ。車などなんもなかったど」
「そうですか。助けていただき、ありがとやした」
あとでわかったが、そこは住居を兼ねた酒屋だった。
鈍痛を頭に感じながら予測がついた。志保の連れの男が固いもので殴りつけ、志保は携帯の地図機能を使ってダム近くの商店を調べ、そこの酒屋に自ら通報したのだろう。
志保は、N新聞や猪里が嫌い、久野は目障りだ、と心の中を打ち明けたが、心底から久野を嫌っていて憎しみを抱いていたのなら、連れの男にあの場で殺させることだってできただろう。そこまで及ばなかった理由は――。新聞記者に事件を書かせ、町の評判を貶める狙いがあるのかもしれなかった。市長の娘なのに、どういうことだろうか。その辺に屈折した心の闇が隠されていそうだった。
愛車のクラウンはどこへ行ったのか。最初から久野の車を奪い、その車で逃げる計画だったのだ。トートバッグと財布は手元にあったが、車のキーがなくなっていた。
頭を押さえながら、助けてくれたおじさんの家をあとにし、付近を歩いた。道路まで出てみたが、バスもタクシーも一台も走っていない、閑散とした交通量だった。
もう一度さきほどの酒屋に戻った。
〝足〟をなくした久野は、ダムから少し離れた酒屋からタクシーを呼び、南町まで戻った。猪里署の手前でタクシーを降りた。
空を見上げると、夕暮れが西の空を赤く染めていた。車を盗られた被害を届けるのが恥ずかしく、空のように頬を赤らめた。こんな姿は長里や藤宮に見せたくない。
猪里署で被害届を出し、バス停まで歩き、一時間に一本のバスを待った。被害の名称は強盗致傷だった。アラフィフの女に強盗致傷とは。志保の嘲り笑う声が耳に残っていた。N新聞が嫌い、猪里全体も嫌い。久野が目障り。
N新聞が市長を悪く書いたことなどあっただろうかと記憶をたどってみた。ここ十年、そんな記事は政治欄でも見かけたことはない。やはり志保の心の闇が深く、なにかを勘違いしているとしか思えなかった。
何かが引っ掛かっていた。
記憶の片隅で、志保のことを記事にしたような覚えがあった。年のせいか、はっきりと思い出せない。それはほんとうに新聞記事になったのかどうかも、もはやあやふやだった。もう何年も前のことであり、どんな中身だったのか見当もつかなかった。何年も前なら、志保は高校のころかもしれなかった。なんで取り上げたのだろうか。
もしかしたら、その記事の内容が不満で、根に持っているのかもしれないと思った。
一方で、市長の疑惑は記事にこそしてないが、黒い噂は掴んでいた。
あと三分でバスが来るというとき、携帯が鳴った。長里からの着信だった。
「もしもし、川畑です」
「川畑さん。長里です」
「いけんしたとですか? 警察の方から電話だなんて、めずらしい。捜査の動きか情報提供でも?」
「いいえ、まあ、くわしいことは言えんち。明日の晩、マスコミのサツ回りの方を集めたオフレコの懇親会を開くから伝えるように、と今出水副署長が言うちょりました」
「まあ。明日の夜に懇親会を?」
「N新聞は出れんとですか」
「いいえ、喜んで。酒はあまり飲めん方ですが、参加いたしますとお伝えください」
「分かりもした。ではN新聞から一人でよろしいか」
「そうです。捜査もいよいよ大詰めなんですね」
「そげんこつは懇親会で副署長がなんとおっしゃるかしだいです」
「承知しました。では」
電話を切った。おそらく、容疑者として鹿原志保を逮捕する証拠が固まり、段取りがついたのだろう。
頭の痛みも吹き飛んだ。やはり島谷刑事が捜査本部に加わったのは伊達ではなかった。捜査が大きく進展したのだ。
明後日の七日月曜日は新聞休刊日に当たっている。六日に逮捕のお触れが出て七日に逮捕し、七日の夕刊の一面を犯人逮捕の写真が飾るはずだ。
長年の社会部記者としての経験から流れが読めた。
バスがやってきた。ガラガラの車内に席を取り、南町のはずれまでバスに揺られた。夜になり、暗闇の中、ときおりすれ違う対向車のヘッドライトに勇気をもらいながら、ペンは剣よりも強しよ、と心を奮い立たせた。
家に着いたらどっと疲れが出て、腹も減った。まだ頭が腫れて、ヒリヒリ痛む。
「ただいま」
弱々しい声が出る。
「お帰り。疲れたね」
真由美は、久野が頭を殴られてクラウンを盗まれたなんてことは知らない。いつものように陽気に笑って出迎えた。
「ちょっと疲れたち」
「久野が自分から疲れたち言うのは、よほど体にこたえたんでしょ。ご飯はたもった?」
「そういえば食べとらん」
「冷めちょるけどあるよ。たもらんね」
「あいがと。いただきます」
久野は炊飯器に残っていたご飯と冷めた煮しめを食べた。明日のことを思い出し、
「明日は飲んで帰るけん、晩ご飯はいらんち」
と伝えた。
「わかったち。だれと飲むの?」
「仕事相手と」
「あんたは酒が弱い方だから、お酌に回りなさいね」
「分かっちょるよ」
「誘われたのかい」
「召集がかかった。捜査も山場に来たんだろうね」
「へえ、そうね。そげんときは警察もマスコミに近づくんね」
「直接捜査の内容は喋らんのよ。ただ、スクープになるように匂わすの。ねえ、一つ訊いていいかしら」
久野は箸で胡瓜の漬物を摘まみながら真由美の顔を見た。
「なんね」
「今日、鷺沼紘一という猪里市議が殺されたんだけど、その市議と鹿原市長の関係って分かる?」
「鷺沼さんちゅうたら、鹿原さんの後釜を狙っちょる人だがね」
「やっぱりそうか。政敵なんだ。あいがと」
「今晩は原稿をかいて、ゆっくり寝んさい」
「わかったち」
久野は今日起きた事件の原稿を書いてデスクに送信した。
《中平デスクへ 以下、原稿です。
また、連続殺人か? 盛り土の中から遺体 五月五日(土)午後二時過ぎ、東の原町六丁目の工事現場で、市会議員鷺沼紘一さん(六二)の遺体を土木作業員が発見。警察が駆けつけ死亡を確認した。遺体は盛り土の中に埋められていた。死因は不明。遺体には無数の赤い傷があった。稲和県警は事故死と他殺の両面で捜査を進めている。連続殺殺人となればこれで四件目。猪里市連続殺人事件捜査本部は、これまでの三件の犯行と関係していると見て、なお犯人に関する情報提供を呼びかけている》
ついでに、寝る前に長里警部にメールを送り、島谷警部に読んでもらいたいと記した。内容は次のようなことを書いた。
市長の娘の鹿原志保と連れの男が犯人である可能性が高い。第一の被害者から第三の被害者まではカムフラージュするための偽装殺人で、ほんとうの狙いは最初から、第四の被害者である市会議員を殺すことが目的だったと推測している。殺された市議は市長と関係が深く、鹿原市長の後釜を狙うライバルだったと。
夜も更けてきた。明日は、犯人グループも目立った動きを見せない予感がしていた。なんとなく平穏な一日になりそうだわ。そう思うと瞼が自然に閉じて深い眠りについた。
五月六日(日曜日)
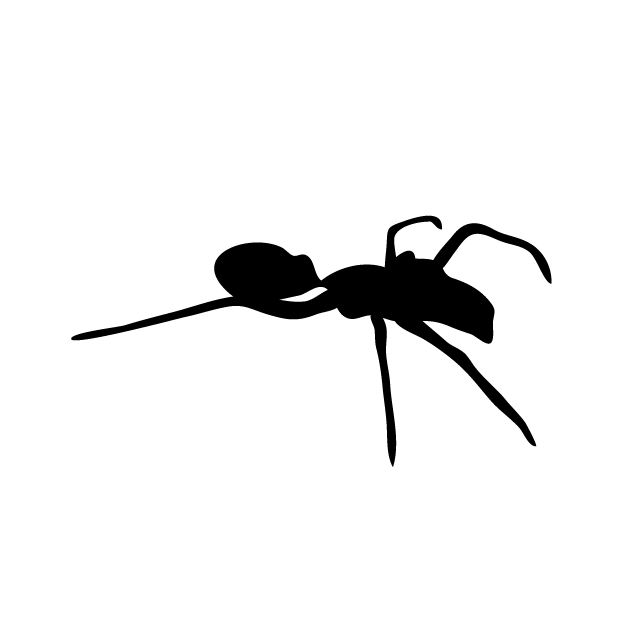
島谷は捜査本部の会議机の上で朝のコーヒーを飲みながら、N新聞を開いていた。
市会議員、土中で不審死 五日(土)午後二時過ぎ、猪里市東の原町六丁目の工事現場で、土木作業員から盛り土の中に遺体があると警察に通報があった。警察が駆けつけ、猪里市会議員の鷺沼紘一さん(六二)の遺体を確認。同市で発生した連続殺人事件としては今回で四件目。稲和県警によると遺体に虫に刺されたような無数の赤い跡があり、事故死と他殺の両面の疑いで調べている。県警は土木作業員からくわしい経緯を聞いている。現場は住宅地として造成され、市中心部から二〇キロの場所。
島谷は、刺された跡が死因と関係しているとは考えてなかった。市議の遺体は司法解剖中だ。
「被害者を刺した虫じゃが、火蟻じゃなかね」
島谷は捜査員のひとりに訊ねた。
「そうじゃと思うちょります。おそらく毒性を持つ虫というと、蜂か火蟻ないしは蛾になる毛虫などじゃなかかと思うちょりますが……」
「なんちゅうたかな。火蟻の症状は?」
「アナフィラキシーショックではなかですか」
若い署員が口添えをした。
「そうじゃ。それそれ。そのアナフィラキシーショックで死ぬこともあるじゃろか」
「まあ、アレルギーのある人は亡くなるかもち、科捜研に聞いたことはありもすが」
「どれぐらいの割合で?」
「アレルギーじたいが少なくて、亡くなる人はほとんどおらんち」
「そうか、やはりな」
「五月五日の土に埋めた遺体の死因は、火蟻でなく別のセンでしょう」
「おいもそう思う。それは置いておいて、水、木、金、土と曜日にちなんだ殺しというセンは犯人の当初からの意図ではなかか」
「じゃと思います。実に単純ですが。ただ、殺害方法がバラバラで手の込んだ殺人じゃち、犯人は複数、もしくは共犯のいる可能性が高いとみております」
被害者に強い恨みを持つ人物はすでに絞られていた。昨夜、N新聞の川畑久野から届いたメールにはすぐに目を通していた。
「昨晩、おいの携帯に転送メールが届いたど。N新聞のベテラン記者さんから。市会議員殺害こそが犯人の真の目的で、犯人は市長の娘とその連れの男じゃち書いてあった」
「町の噂でもそう聞いちょります。証拠を集めて被疑者が罪を犯したのを裏付ける理由が得られたので、いっでん逮捕状を請求できるかと」
「新聞記者も、周辺の訊きこみ情報を相当集めたと見える。その川畑ちゅう女記者が、あちこちで独自に訊き込みをしてがんばっちょったちゅう話ば現場の捜査員から聞いた」
島谷は、新米だったころの久野のあどけない顔を思い浮かべ、いまでは新聞記者がすっかり板についたのと、ベテランのコミュニケーション能力と行動力にすっかり感心した。
ただ、昨日、鳴沢ダムで容疑者と対決して頭にけがを負い、車を盗まれたのには注文をつけたかった。もう少し慎重に行動し、一人で乗り込まず、事前に警察に通報してくれたらよかったのに、と。
県警本部の島谷は、自分が捜査本部に加わることでその士気が上がったと感じていた。数々の事件を解決に導いた島谷は、昨日一日で、猪里市中心部から半径五〇キロ圏内にあるauのサービスショップを、一斉に調べ上げさせた。携帯端末をショップに持ち込んでプリペイド式の契約を行った人物を洗い出すためである。
「結果はいけんじゃった?」
「はい。犯行日から遡って一か月以内にプリペイド式携帯の契約を行った人物は一人しかおりもはん」
「その人物は?」
「鹿原志保でした」
「そうか。やはり睨んだとおりじゃち」
昨日の島谷の指示で、犯行の凶器や道具、アリバイ、犯行動機をつぶさに調べあげ、犯人は大学生の鹿原志保とその恋人の福松光宏に間違いないとの結論に至っていた。もちろん、ドライアイスの入手ルートをネット通販に絞り込み、アドレスの開示要求でパソコンとその所在場所を特定するに至った。
その住所に向かい、着いた先は南町の大きな屋敷だった。鹿原と彫られた御影石の表札は、家全体で威厳を醸していた。市長の家であるのは間違いなかった。
午後から市長宅を訪ねたが、市長も娘も不在だった。島谷は市長宅付近の訊き込みを開始させた。
町民たちは知っていることを次々と口にした。
「市長んとこの志保は一人娘で、高校のころに不登校だったち聞いたげな」
「おいもそげん聞いちょる。大学生になっても三年の終わりごろから休みがちで家にこもり、何をしているのか親ですら把握しぃちょらんと」
「陽菜乃ちゃんは志保の家庭教師の生徒で、宇志窪さんは夏祭りで志保に痴漢を働いたちゅう話じゃ」
「聞いたところでは、李さんち中国の人は、高橋さんの民宿に泊まっていた旅行者じゃっど」
「じゃっち。町内でちょっとした悪評が出たち」
「鷺宮さんは有名じゃっど、市長とライバル関係とも噂されちょる」
あちこちで訊き込みをした結果、最初こそ、住民らはおしなべて喋りにくそうな顔をしていたが、だれかが話し出すと、堰を切ったようにそれぞれ知っていることを語ったそうだ。
それらの証言により、ぼろぼろとメッキがはがれるようにして表面が露わになっていった。父のライバルだからといって、市議に対して憎しみを抱き、殺害に至る強い殺意があったのかどうかは調査中だ。
被疑者として、明日までに志保と光宏の居場所を掴むよう島谷は指示を出した。全国に配備されたNシステムのおかげで、特定の車のナンバーを読みとって手配し、車の位置や時間などがヒットするようにできている。志保は市長の車を使っていないことや久野の車が盗難に遭ったこともすでに確認済みだった。
午後の鐘が三回鳴った頃だった。
「島谷警部。昨日の夜九時ごろ、盗難車が隣の日の出市の交差点を通過していたとの報告が上がりました」
「では緊急配備だ。鹿原志保と福松光宏の写真をできる限り用意して二人の足取りを追え」
多数の警官に写真を持たせ、逃走に使った車を絞り込んだ結果、某所に連泊していることを突き止めた。
島谷は、覆面パトカーを近くに待機させ、盗難車が移動しないか見張りを付けさせた。
夜になった。
白のクラウンはその場所に留まっていた。殺人の動きはその日なかった。
島谷は署員に被疑者二人を見張らせて、自らは懇親会には顔を出さず、夜遅くまで、逮捕状請求の資料と署内へ提出する裏付け資料を作っていた。
*
南町で夜八時に始まった懇親会は、猪里署から署長と副署長が揃って出席した。目的は、事件を取材したマスコミ関係者への慰労もかねていた。
マスコミの警察担当者も続々と会場に集まり、二〇人以上に膨れ上がり宴は賑やかとなった。
会は副署長の挨拶から始まり、マスコミの尽力をねぎらう言葉が並んだ。
挨拶の最後を飾り、署長が立ち上がって、乾杯前にまじめな訓話めいたことを述べた。
「鑑識課長と以前話していたのですが、彼に言わせると、『すべての物質は毒であり、薬でもある。人の側から見て毒になるものは、それを含む動植物にとっては、自身の命を守る〝薬〟なのだから。言うならば、人の使い方しだいでどちらにもなりうる。だから、薬として使う場合、その責任は使ったひとにある』らしいのです。
酒も百薬の長と言われていますが、飲み過ぎは毒です。皆さん、わけ方もいらっしゃるので申し上げますが、くれぐれも悪酔いして他人に迷惑をかけないようにしてください。では乾杯!」
赤ら顔の副署長に、久野はビール瓶を持ってお酌に行った。
「事件解決は、もう時間の問題ですよね」
「長引くようなら島さん(島谷警部)は呼ばない。やるべきことはやっている」
酒の席でも幹部の口は堅かった。
出席しているマスコミの担当者たちは、男も女も、悪酔いしない程度に酒を飲み、四件の連続殺人事件を振り返るものもいれば、明日、明後日にでも犯人逮捕の瞬間を写真や映像で全国に伝えようと、鼻息も荒く各社のカメラマンにメールを入れるもの、署長や副署長にお酌をして容疑者の潜伏先はどのあたりかと訊き出そうとするもの、島谷警部を称賛して、「島谷警部バンザイ! 猪里署バンザイ!」と調子よく叫ぶ輩もいた。
東京から来たというワイドショーのリポーターは、自分たちがこれまで報道で取り上げてきた数々の難事件や怪事件、行方不明事件、時効になった迷宮入りの事件などの遍歴を、言葉巧みに聞かせてくれた。酒の勢いもあり、その手の武勇伝にありがちだが、話に尾ひれがついたり、途中で脱線したりすることもあった。
あっという間に時は過ぎ去り、誰もが楽しい時間を過ごしたその宴の最後になって、副署長の口から、
「明日の午前は開けておけよ」
とマスコミに向けた〝お触れ〟が出た。その「鶴の一声」を聞きたくて皆は集まり、事件解決も秒読みに入った、とマスコミ陣は恵比須顔で店を出た。
いよいよ捜査も大詰めだ。久野をはじめ、マスコミ各社のサツ回り担当ならだれしもそう思ったはずだった。
もちろん、捜査が終結し、マスコミの報道が明日の午前に最高潮に達するのを、出席者全員が始めから承知したうえで、宴席に参加していた。
犯人逮捕
五月七日月曜日、容疑者逮捕の当日を迎えた。久野らはあらかじめ前夜から知り、朝一番に社会部のデスクに電話を入れ、今回の事件解決が今日の夕刊のトップ記事になるはずだと連絡した。
「そうか。Qちゃん、決定的瞬間を逃すなよ」
デスクの声は記事に賭ける熱量が伝わってきそうなほど熱かった。
「ええ、もちろんですとも」
久野も言葉に気合を込めた。本来ならば、飯野にこの大役を任せて自信をつけさせたかったが、まだ若い彼にはいくどとなくチャンスが巡ってくるだろう、といい方向に考えた。彼はまだ入院中だし、早く病気を治して、現場に元気よく復帰するのだけを期待していればよい。
前日に行われたオフレコ懇親会の終わりの挨拶で、今出水副署長がマスコミの記者やテレビ局の人間に、
「明日の午前は開けておけよ」
と明言したのは、もちろん真っ先にデスクの耳に入れ、説明しておいた。久野は朝八時五〇分に猪里署に着き、警察車両がいつ署を出ていくかを待っていた。待っているあいだの車中で、デスクに電話を入れた。警察の車の行き先はてっきり市長の自宅だと思い込んでいた。
ところが、蓋を開けてみると、猪里署を出てサイレンを鳴らしたパトカーは、途中の交差点を右に折れ、別方面へ向かった。久野は仕事用に借りたレンタカーで慌ててハンドルを切り、後を追う。
午前十時を回っていた。
着いた先は、派手な外観の城のような白いホテルだった。犯人は恋人とホテルに泊まっていたのだ。すでに停まって張り込んでいた、複数の覆面パトカーに加え、急行したパトカーが、白亜の建物の駐車場に停まった。
容疑者たちは、迂闊なことに一台の白のクラウンを停めている。見慣れた車体だ。ナンバーは「内海 ま10―16」。間違いなく久野の車だ。一昨日鳴沢ダムで奪われて、こんなホテルの駐車場まで移動していたとは知らなかった。穴があったら入りたかった。
捜査員が中に入り、しばらくして、建物から出てきた志保と光宏の上半身に向けて、フラッシュが一斉にたかれたのは十時十分だった。もちろん久野も、一眼デジカメで写真を撮る集団に混じっていた。二人の顔は一瞬強張ったように見えた。
クラウンはできればテレビに映ってほしくないと願ったが、あとで近所の人に訊いたら、やはり画面の後方に映り込んでいたらしい。
二人は背中を丸めておとなしく警察の指示に従った。何人かの警官が二人の容疑者を取り囲むようにして、警察車両へ誘導する。
フラッシュのたかれるたびに、まるでストップモーションのコマ送りのようにして、二人の影は朝の光から姿を消していく。テレビカメラは警察の車に乗り込む瞬間をしっかりと映していた。田舎を舞台にした殺人事件の終焉だった。
東京のテレビ局がその場面を生中継したのか、それとも編集したのかどうかは知らない。リポーターらしき人物がマイクを手にしてカメラに向かってなにかを喋っている。
久野は逮捕の瞬間を何枚も写した。その中から厳選した一枚の写真が、月曜日のN新聞夕刊のトップを飾ることになった。
写真を撮り終え、取り戻したクラウンで日の出市から猪里署まで向かった。猪里市連続殺人事件に関する報道メモは夜まで出なかった。そのあいだに、白亜のホテルに置いてきたレンタカーを取りにタクシーで向かい、レンタカーに乗って南町の営業所で返却した。
猪里署を出て、車で内海市にあるN新聞九州南支局に戻ってきた。
「ただいま戻りました」
できるだけ溌溂とした声で挨拶し、編集部の自分の席に着いた。机の上のパソコンを早々に起動させた。夕刊の一面に載せる犯人逮捕の原稿を午後二時までに書き終え、デスクに承認をもらった。
《猪里市の連続殺人犯、逮捕 七日(月)午前十時、稲和県警は、稲和大学四年鹿原志保容疑者(二二)と同大学四年福松光宏容疑者(二二)を殺人の疑いで逮捕した。二人は猪里市で起きた連続殺人事件を起こし、日の出市内のホテルに宿泊していたが、身柄を拘束された。警察の調べに対し、二人はおおむね容疑を認め、四件の殺人に関与、それぞれ薬物や毒物、有毒ガスなどを準備し、周到に計画を立て殺人を実行した模様。現在、猪里市連続殺人事件捜査本部は両容疑者の殺害方法や動機の解明などの取り調べを行っている。二人をよく知る人は、「鹿原さんは静かで礼儀正しいけれど、なにをやるかわからない面もあった。人との協調性も欠けていた。福松さんは従順であまり目立たなかった」と話す。捜査本部は、容疑者の逮捕で事件は終息したと見ている。今後、同本部は二人を検察へ起訴する予定》
原稿を書き終え、デスクに原稿データを送信すると、今日に限って無性にコーヒーが飲みたくなった。出入り口の扉を開け、廊下の休憩スペースで自販機のコーヒーを買い、ベンチに座ってホットコーヒーを啜った。
久野は来週の月曜日から代休を取ることにした。
デスクからは、
「連続殺人事件の特集記事は、明日から復帰予定の飯野に任せよう。それより、疲れもあるだろうし、ゆっくり体を休めた方がいい」
と言われていた。
コーヒーを飲み終わり、紙コップを自販機横のゴミ箱に捨てて、両手を突き上げて伸びをした。
廊下の突き当りまで行き、小窓から内海市内のオフィスビルやマンションなどを見下ろした。ここは七階のフロアである。
「徳広は、今ごろ中学校で授業を受けているのね」
あたりまえの日常が、しごくありがたいものに感じられた。事件に遭遇したときから、ベテランの久野ですら、緊張とおどろきを毎日味わうことになった。強心臓で鳴らした記者魂も、ずいぶんすり減った気がした。
小窓から白壁の廊下を歩いて、N編集部のガラスのドアを開けると、中の空気が淀んでいた。
「ちょっと空気が悪くなか? 窓を開けませんか」
「お願いします」
社会部の品浜だけが声を発し、あとの中堅や古参社員は、首を軽く縦に振った。
大きな窓を二つ開けると、五月の薫風が社内のどんよりした空気を打ち消し、爽快感を与えてくれる。
仕事が一段落し、窓際に陣取った、机に向かっているデスクに歩み寄り、声を掛けた。
「これで終わりましたね。一連の事件は」
「事件はな」
「まだなにかあるち?」
「いろいろとうるさい連中がいてな。困っとる」
デスクは口をへの字に曲げた。
「それは星永産業のことですか」
「星永からの圧力もそうだし、市政、県政の動きもある。東京から来たマスコミのお陰で、ゴールデンウィークの後半は、県内のいくつかの旅館やホテルにキャンセルが出た。土産物店や観光バス会社からも新聞への風当たりが強いときている」
「でも、きちんと事実をねじ曲げずに報道しましたよ。痛みはわかりますが、それが記者としての基本姿勢でしょ?」
「まあ正論はな。Qちゃんが、おいどんの喜ぶような明るい町ネタを見つけてきてくれ。それだけが頼みの綱じゃち」
「まあ、ずいぶん都合のよかこと。わかりもした。代休が終わったら。どんな些細なネタでもいいから、読み手がほっこりするような明るいネタを仕入れてきますよ」
最後はデスクに泣きを入れられ、久野も大見得を切るしかなかった。
午後九時に報道メモが出て、久野の携帯にメールで届いた。
《所轄署は稲和県警猪里署、容疑は殺人、被疑者二人。被疑者の鹿原志保は調べに対し、「市議に対して恨みがあった。一方で、父から説教され、困らせてやりたかった」と供述した。県警は殺害方法や動機などの裏付けを慎重に進めている》
以上が報道メモの猪里市連続殺人に関する中身だった。市長である親が立派すぎて、父への嫌がらせだったのかと思った。
帰りに新聞販売店まで行き、いつもより少し分厚いN新聞の夕刊を買った。さっそく事件終焉の記事を読んだ。
連続殺人犯、逮捕 七日(月)午前十時、稲和県警は、稲和大学四年鹿原志保容疑者(二二)と同大学四年福松光宏容疑者(二二)を殺人の疑いで逮捕した。二人は猪里市で起きた連続殺人事件を起こし、日の出市内のホテルで身柄を拘束された。県警は、両容疑者が二日から起きた四件の殺人にいずれも関与し、殺人に及んだと見ている。二人をよく知る人は、「鹿原さんは静かで礼儀正しいが、なにをやるかわからない面があり、人との協調性も欠けていた。福松さんは従順であまり目立たなかった」と話す。猪里市連続殺人事件捜査本部は、動機や殺害方法の取り調べをおこない、容疑者逮捕で事件は終息したとして、今後、二人を検察へ起訴の予定。
久野はクラウンの中で夕刊を読み終え、大きなため息交じりに、
「これで町に平和が戻るわ」
と呟いた。夕陽の沈んだ夜空を仰ぎながら、内海市から実家の猪里市に向けてクラウンを飛ばした。
事件が終結しただけで、猪里市内ののどかな風景がようやく本来のあるべき姿と輝きを取り戻し、日常が戻ってきた。そんな気がした。
夜の田圃の上には星が輝き、半月が山の尾根の上に出ている。滑るようにして国道32号を走る。交差点で信号待ちをしているとき、ヘッドライトが横断歩道を渡る高校生らしき男連れを照らした。にこにこと笑いなにかを喋りながら歩く光景が、猪里市らしさを象徴しているようだった。
安全運転で、これまでの波乱に満ちた毎日を振り切るようにして実家に戻った。実家に荷物を置いたままだった。カーポートに車を停めると、庭の草花が居間の電灯に照らされているのを見て心が和んだ。
「ただいま、帰ったよ」
「お帰んなさい」真由美が玄関まで出迎えた。
「晩ご飯は食べたち?」
「うんにゃ。食べとらん。今晩で実家に泊まるのを最後にするわ」
「内海の方に戻るの?」
真由美は少し心残りのような口ぶりで眉を下げた。
「うん。息子も待ってるから帰るわ」
「ご馳走はないけれど、炊き込みご飯と刺身があるち、台所に座って待っちょってね」
「わかった」
真由美は手を動かしながら、
「仕事はまだあるね?」
「今日の夕刊で、こん事件にかかわるわたしの担当は終わった。あとは新人に特集を書いてもらって終わり」
「そうね。はい、炊き込みご飯」
真由美はお茶碗に炊き込みご飯をよそい、冷蔵庫から取り出した刺身を皿に並べて食卓に出した。
「自宅に戻ったら、徳広にハンバーグを作ってやらにゃならんど」
「子どもはやっぱり母の手料理が食いたいじゃろね」
「そうよね。家事に仕事。また別の意味でたいへんだけど」
刺身を食べながらテレビはつけずに、久しぶりに真由美と話そうと思った。
「ねえ、母さん。あたいは恨まれるようなことしてないよね」
「突然、なんの話ね?」
真由美が訝るのも当然だった。
「N新聞の悪口を言われた。あたいがここにいると目障りじゃ。そげなことも言われた」
「そげんことはだれも思っとりゃせんち。だれが言ったち?」
「鹿原志保。今回の容疑者じゃ」
「志保さんか。あのおなごはちと変わっとる。気にせんこつよ」
「あたい、なにかで彼女のことを取材したような覚えがあるけど、いけな内容だったか思い出せんのよ」
「些細なことでしょ。あんたの悪口なぞ聞いたこつあなかよ。よくできたおなごじゃち評判じゃった」
「気のせいなら、それでよかどん。志保はN新聞を読んでなにか根に持っとったのかも」
「いずれ起訴、裁判になったら、なして悪口を言ったかわかるち。夜も更けてきたし、嫌なことは考えんことよ」
「そうね」
久野は短く相槌を打ち、食事をつづけた。
「ところで、父さんはいけんしたち? 姿が見えんが」
「町の寄り合いで飲みに出掛けた。隣の横内さんが下戸じゃで、帰りにここまで車で送ってもらうち言うちょった」
「そうね。父さんも楽しく飲んじょるのか。いいなあ」
幸一郎の知人らと談笑する姿を思い浮かべるうちに、自宅の一家団欒が頭に蘇った。徳広に電話をしようと思い立ち、腹が膨れ、しばらくしてから、電話を掛けた。
「もしもし、わたし、久野だけど」
「おお、久野さんかい。徳広くんじゃろ? 今、かわるち」
自宅の電話に出たのは川畑の義父だった。
「もしもし、母さん? 徳広だよ」
「元気にしてた?」
「だいじょうぶだって。母さんも元気そうだね」
「明日、そちらに帰れるからね。こっちの事件もほぼ終わったの」
「それはよかった。実は、母さんの作る料理が待ち遠しかったんだ」
「ほんとう? それだけなの?」
「えへへ。実はお小遣いをあてにしちょる。アディダスの靴がほしくてさ。三千円ほどちょうだいよ」
「いいわよ、それぐらいなら。留守番してたからご褒美に」
「やったー。絶対だよ」
息子の喜ぶ声に、母として役に立ったのが素直に嬉しかった。
「ところで徳広。そろそろ修学旅行があるんじゃなかったっけ?」
「ああ、そうだよ」
「どこに行くのか決まったの? 母さん、教えてもらってないけど」
「ごめん、ごめん。東京だよ。言わなかったっけ? スカイツリーやディズニーリゾートに行くんだ」
「まあ。ホテルに泊まるのね。きっと。高いお金を払うんだから、ちゃんと体験してくるのよ」
「体験か。おれ、都会で切符の買い方とか、外国人との会話とかをちゃんと学んでくるから」
「国際交流はいいとして、遊び以外はなにかないの?」
「そういえば、スカイツリーに登る前に国会議事堂に行くよ。見学ツアーで回れるのは、たしか参議院かな」
「ちゃんと案内の人の言うことを頭に入れるのよ」
「わかってるよ。おれも将来、会議場で質問できるような大物政治家になるのを目指すからね」
「ほんとうならたいしたものね。野次を飛ばす方に回らないでよ」
徳広の、どこまでほんとうなのか知れない、夢とも冗談とも取れる話に思わず笑いがこみ上げた。口だけは達者になったわ、と息子の成長ぶりに目を細めた。
「じゃあ夜も遅いし、そろそろ切るよ」
「そうね。じゃあ、修学旅行のくわしい話は家に帰ってからゆっくり聞くとするか。おやすみ」
「おやすみなさい」
息子の朗らかな声を聞けて元気が出た。今夜はとても満足だ。久しぶりの親子の対面を待ち遠しく思った。
風呂場に行き、服を脱いで風呂に入った。風呂に入りながら明日の仕事のことを思い浮かべた。
N新聞九州南支局。職場は変わらないが、連休明けの社会部に舞い込む情報は、もう先週ほど過激なものではなくなるはずだ。事件の続報もあるだろうけれど、もう久野の手を離れた。星永産業の圧力を受けながら、殿田の希望するような市民に喜ばれる紙面を作らねば、と思った。もちろん、飯野や品浜を育てていきながら、だが。
翌日の八日火曜日、朝から飯野が職場に元気な顔を見せた。病気が治り、仕事に復帰した彼は、事件の詳細をあらためて時系列でパソコン上に列挙し、原稿や久野のまとめた資料を基にした三面記事を書いた。
しかし、久野の本音は記事を書かせたくなかった。猪里市という田舎の平凡な町で四件もの連続殺人事件が起きたなんて、まだ信じられなかった。
「あげんのんびりした、平穏で自然だけが取り柄の町が、こんな悪事で有名な場所になってほしくないわ」
心の中の呟きに、忸怩たる思いがあった。それは、なかなか消そうにも消えなかった。そうした思いは、新聞記者だろうと、温泉宿の女将だろうと、すべての市民に共通する心情に違いないと思った。
このあと、どうなるのだろう。市長の娘が容疑者として実刑判決を受けたのちには、市長は責任を取って職を辞するのかもしれない。
町はどうなるのか。風評被害で、市内で穫れる農産物が売れなくなり、よそから猪里市を訪れる観光客の数も激減しそうだ。ニュースや新聞記事を目にした市外、県外の人々にどんなふうに受け取られるか。
編集長が、むかし、朝礼の時間にみんなを前にして語った言葉を思い出した。
「われわれは、事実を報道するのが仕事だ。真実は一つでも、真実ほどひとを傷つけるものはない。ニュースを記事にするだけで終わらず、書かれて困惑する側の人たちの心も考えよう」
その言葉がずしりと胸に響いた。N新聞やライバルのM新聞の記事が猪里市を奈落の底に突き落とすとしたら、どうにもやり切れなかった。いいことだけを記事にするなら楽だ。市民感情としては、伝えてほしくない町の醜聞を記事にしたけれど、ひどく頭が痛かった。殿田の怒る顔が浮かんだ。
N新聞の九州南支局内という小さな組織内でも社内派閥は存在した。 編集局長寄りの社会部デスクの中平を筆頭とする派閥と、政治・経済部長の安西を筆頭とする派閥であった。安西部長は、専務も兼ねる編集局長の土門と対立する北尾副社長の腰巾着だった。新聞社のデスクは各部に存在し、役職的に言えば課長に相当する。専務、部長、課長の順番でいえば、土門、安西、中平の順で力を持つ。だが、土門と通じている中平の傘下に入る同志は多かった。
とくだん、安西派が中平派に対して露骨に嫌がらせをするわけではないが、なにかにつけてふたつの派閥は競い合い、助け合うのも派閥同士内で助け合うのが常だった。
ところが、ここ最近になって、数で劣る安西派に動きがあった。中身の大幅改革とわかりやすい紙面を唱えたのだ。具体的には、N新聞の専属イラストレーターに、新進気鋭で九州出身の雪平成美を起用した。記事の概要を一枚のイラストで表現する視覚に訴えた紙面作りに変え、実売部数を増やした。
久野は中平派に属している。入社以来ずっと中平派だった。飯野も社会部にいることもあり、中平派である。
しかし、飯野は今回の事件を担当し、紙面や記事の扱いに関して不満を漏らしたらしかった。中平からちくちく説教され、異動の脅しまでかけられているとの噂が立った。飯野は安西を頼って、社会部のサツ回りが終われば、政治部へ異動を希望しちょる。そんな声も聞こえてきた。
実売部数の増加を実現し、中平派の不満分子の受け皿として、安西派は中平派の切り崩しを図ってきた。裏に北尾副社長の後ろ盾があったのは間違いない。
両派閥の対立関係に巻き込まれ、困ったことがひとつ起きた。それは今回の連続殺人事件にも深く関わっていた。例の星永産業の殿田専務が懇意にしていた北尾副社長と会食し、副社長を通してまた社会部に圧力をかけてきたらしいのだ。北尾副社長と対等に渡り合えるのは専務である土門編集局長だけだ。その土門や中平デスクを通り越しての圧力であり、社会部の記者らにとっては憤懣やるかたなかった。
「なんで、なんども外から圧力がかかるんだ?」
「社会部を舐めてもらっては困ると」
「安西部長も、追い風を受けちょるのは今のうちだけたい」
「われわれ社会部記者の取材があってこそ、地元の読者に支持される紙面になるのを忘れてほしくなか」
「数年先、中平デスクが退社したら、安西派に吸収されるのでは?」
さまざまな声が中平派内で飛び交った。
派閥の対立は、事件の影響によってよりいっそう社内の風通しを悪くした。原稿を書いた飯野と久野は、猪里市へ取材に出掛ければN新聞への苦情を言われ、風当たりが強かった。
「なんであげな記事を書いたとね」
「猪里市がいけん思われてもいいのか」
批判やお叱りの声をたくさん聞かされた。それはN新聞をよく読まれている方々で、新聞をよく読んでいるからこその叱咤激励でもある、と久野は飯野に言い聞かせた。
今回のようないひどい事件は、どこのメディアが扱っても結果は同じである。犯罪や事故の町としていったん悪名高くなったなら、風評被害が避けられないのは、他の例を挙げるまでもなく、実証済みである。
時がたてば、あの頃こんな田舎でもひどい事件があったね、と振り返れる日が来るのはわかっている。けれど、心に闇を抱えた女子大生とその恋人によって起きた事件の数々は、平和な町に、恐ろしい殺人事件の舞台というレッテルを貼ってしまった。
久野にはそれが分かっていて、心苦しかった。久野が飯野の立場なら逃げ出したくなるような気持ちを感じただろう。
*
逮捕された志保の取り調べが月曜から始まった。志保は、すべての事件に関して殺害は認めたものの、その方法や動機に関しては曖昧な点も多かった。個人的な怨恨で殺害したのは、四件目の鷺沼市議だけだと彼女は主張した。藤宮警部補は、
「お父さんのライバルだから殺した。それもあるだろうけど、他に理由があるんだろ?」
「……」
志保の肩はわなないていた。
「自白した方が罪ば軽くなる。悪いことは言わんち、吐かんね」
優しく言いくるめ、
「辛い経験や嫌なことでもあったんじゃろ」
藤宮は畳み掛けた。自白に信憑性を持たせるため、本心を訊き出そうと試みた。
志保は鷺沼のことを心底憎んでいた。鷺沼紘一は悪い男だった。
あの卑怯な男は、一人娘の志保に目をつけた。父の禊(みそぎ)として性的関係を迫ってきた。
「おまえの親父の談合、ばれたら猪里市全体が酷いことになるぞ」
そう言ってきたのは、四月に入ってからだった。たびたび、父への脅迫メールとは別に、どこで手に入れたのか、志保のメールアドレス宛にのめない要求を突きつけた。
「父の不正をばらされたくなければ、裸の写真を送れ」
「ホテルで三回、性的関係を持ったら、談合の件は見逃してやる」
次から次へと、しつこく志保にまとわりついてきた。
ゴールデンウィークの二週間前、自宅の近くで待ち伏せされ、車に乗せられ、離れた町はずれの廃屋に連れていかれた。
春の陽光が射す中、鷺沼が片手で暗い廃屋の扉を開ける。もう片方の手で志保の体を強く引っ張り、建物の中に突き飛ばした。
志保はほこりをかぶった地面に手と足をついた。仁王立ちの相手を見上げる。
にやけた鷺沼がこれからどんなことをしようと企んでいるのかすぐにわかった。背筋に寒気が走る。言葉を発しようとしたが、恐怖で口が震えて言葉にならない。首を左右にふり、拒絶する。
「おい。志保。おまえの承諾ひとつで、談合は見逃してやるよ」
「ほ、ほんとうですか」
絞りだすようにして、辛うじて小さな声が出る。
「ああ」
「なにを承諾すれば」
そう言い終わらないうちに、その男は志保の体を覆うようにして彼女の服に手を掛ける。
「いやっ。なにするんですか」
「談合、ばらされたくないんだろ? おとなしくしろ! このあま」
ひぃと叫んだときには、大人の男の強い力で洋服がまくられ、ボタンが飛び散った。服がはだけて、下着が見えたと思ったら、荒々しい手が伸びてきてナイフの刃が光った。
「もう一度言う。おとなしくしろ。ナイフが肌に触れたら血が噴くぜ」
ナイフの影が暗闇で見え、志保の体から力が抜ける。それを感じ取ったのか、鷺沼はナイフで服を切り裂き、下着の紐も切った。志保の意思とは裏腹に体は無抵抗で、気付くと相手の思うまま裸にされていた。
「へ。かわいそうに。父親が談合を指示したために、オレに犯されるとはな」
「やめてください」
目から涙をこぼし、志保は嘆願する。
「やめねえな。たっぷり可愛がってやる」
「なによ……」
「どうした? 警察に言うのか? 逮捕されるのは親父の方だぞ」
「あんたみたいな人間のクズはいずれこの世からいなくなるから」
「威勢だけはいいな。減らず口を叩けるのもいまのうちだけだ」
相手はナイフを放り出し、上着を脱いで裸になる。手が志保の下半身に伸びる。
「やめてよ。なにするの。やめてってば」
「うるさい。こうしてやる」
志保の茂みに手が届き、彼女は唇をかんだ。
涙を流しながら、志保は鷺沼に抱かれた。この男だけは、父や私が有罪になっても地獄へ送ってやりたい。激しい感情が迸る。その気持ちを踏みにじるように、男の一物が自分の中に侵入してくる。
痛さしか感じない時間が過ぎていく。こんなうす汚れた人間が父を強請っている。そして、私を犯している。それだけで、殺意を抱くのには充分だった。そのときにはっきりとした殺意が芽生えた。
どれくらいの時間がたっただろう。
しーんと静まり返り、体に寒気を感じた。男の気配がない。
起き上がったとき、背中にヒンヤリした感覚を覚え、土を払い落とす。破けた服を着て体を起こす。
よろよろと歩き、扉を開けると、もう暗くなっていた。そこに車はない。志保はバス停まで歩き、手持ちの金でどうにか家に辿り着いた。
あのおぞましい強姦の一日が頭に蘇り、志保はいたたまれなくなった。
もうあの男はこの世にいない。そう、いないのよ。
しばらくじっと我慢して沈黙を貫いていた志保は、覚悟を決めたのか、重い口を開いた。心の中にため込んでいたであろう殺人の動機や、抱えていた事情をぽつりぽつりと喋りだした。
「個人的に、鷺沼という男が嫌いだった。あの市議には恨みがあった。それとは別に、父から説教され、困らせてやりたかった」
「恨みがあったのと、父上のライバルとはどんな関係があるのか」
「よくわかりません」
「お父さんを困らせてやるとは具体的にいけなわけじゃ?」
「こんな田舎で就職しても未来に希望がない。町が有名になれば面白いだろうし、休学しているのをなじった父を困らせることにもなる」
「なるほど。よっぽど父上が嫌いだったんじゃ」
「そういうわけでもなか」
「話がもうひとつ見えんな。うわべだけの理由では殺人に結びつかん」
藤宮が頭髪に手をやり、撫でていると、志保はまた黙ってしまった。
「じゃあ、話を戻そう。鷺沼にどんな恨みがあった?」
「子どものころ、私が水やりして大切に育てていたチューリップの花壇があった。鷺沼はサッカーの試合を校庭でやり、ボールを取りに入って、負けている試合の腹いせにチューリップの花を踏みにじった」
「たったそれだけのことか」
「職員室に遊びにいったとき、PTAの会長をしとった鷺沼が、『花壇を壊して、そこにプールの更衣室ば建てましょう』と教頭先生に話を持ちかけていたのを立ち聞きした。無性に腹が立った。悔しさのあまり、腹の虫がおさまらず、その晩は眠れなかった」そこでいったん言葉を区切り、横の白い壁に視線を移して、「大人になり、市議になった鷺沼は市長の座を狙う父のライバルになっていた。復讐するには今しかなかったのよ」
志保は滔々と語った。表情は冷淡なままだった。話し終えると、そっぽを向いた。
「なるほどな。鷺沼の殺しだけは怨恨か」
「やつだけはいけんしても殺しておきたかった」
「他の殺人は?」
島谷刑事は咳をひとつして、
「一件目の殺人は意図したもんか」
と訊ねた。
「あの子は家庭教師の教え子。覚えが悪かった」
「それだけね?」
「正直なところ、てこずっていた。恨みはなかったけど」
「なかったけど?」
「いくら教えても勉強ができない時点で、今回のゲームの罰の対象者になった」
志保は少し口元を歪めた。
「ゲーム?」
「殺人のことです」
「ゲーム感覚で殺したち意味ね?」
「そげなことです。鷺沼を殺してゲームオーバー」
「質問を変える。ドライアイスはいけんして手に入れよった?」
「インターネットで注文した」
「それをいけなふうに運びよった?」
「品物は発泡スチロールに入って届いた」
「それで?」
「その容器ごとドライアイスを光宏の車に積み込んだ」
「陽菜乃の殺害方法は?」
「部活帰りにいつも通る道すがら声をかけた。車の中で私が首を絞めました」
「それだけじゃなか。ドライアイスを使うちょるだろ? それも意図したことか」
「はい。前もってネットで調べたら、ドライアイスが溶けて高濃度になると死ぬこともあると」
「あるよ。以前、新聞に載った事件では、洞窟に溜まった炭酸ガスで大人が何人も死んどる」
「そげんことは知らんかったけど、気絶した陽菜乃をビニール袋に入れて殺せると思った」
「思ったじゃなく、前もって計画したんだろ。光宏とあんたの役割分担は?」
「車の中で二人で陽菜乃の衣服を脱がせ、私は車を降りて光宏が開店前の温泉の脱衣所に運び込んだ」
「それから?」
「あとは、彼がドライアイスとビニール袋の準備をし、陽菜乃を袋に入れて湯船に浮かべる計画だった。実際うまくいった」
「気を失った陽菜乃をビニール袋に入れるよう指示したのはどちらじゃち?」
「私です」
「被害者の衣服と持ち物はどこへやった?」
「私が川に捨てました」
「二件目の中国人旅行者。李さんだっけ。あれはいけんして殺した?」
「二人の観光客は町で評判が悪く、神社を荒らしよるで、見せしめに殺してやった」
「ようするによそ者だし、だれでもよかったと」
「まあ、そうですね」
「殺害の方法は?」
「二人は単独で行動したのでやりやすかった。李さんの方を尾行し、彼女が自販機で買った飲みかけのお茶を、隙を見て睡眠剤を入れた同じメーカーのお茶にすり替えた」
「なるほど。それで?」
「眠った李さんを現場まで車で運んだ。現場で車から下ろし、地面に寝かせて首に縄を巻き付けた。光宏が見張っちょるあいだに、私が近くで飼われていた馬を連れてきて、縄の端を大木の枝の上に放り投げ、二人で馬の胴体にくくりつけた」
「あとは馬を走らせたと」
「じゃっち。馬の尻を叩いて畑に走らせた。首に縄が食い込んで死ぬと思っちょったが、衝撃のあまり、枝が折れてあの中国人は落下した。口からどろんとした液体が出て、死んだのを確認した」
「恐ろしかおなごじゃな。三件目。あの宇志窪はいけんして?」
「あの男は、夏祭りで私の尻を触った。汚らわしかった。ただ、それだけ」
「殺害方法は? いけんして金庫の袋に閉じ込めたち?」
「私は知らんち。ただ入りたかったんじゃろ」
「こら! 警察を舐めんな」
刑事は怒った。彼女は疲れてきたのか、投げやりになって罪の自白をいい加減にし出した様子だった。
とにかく、鷺沼以外の殺人は軽い動機で殺した。最後の殺人をカムフラージュするためのゲーム感覚の殺人だ。志保はぺらぺらと喋った。
「ゲーム感覚と言いながら、綿密に下調べまでして行った計画殺人じゃち、罪は重いち」
「分かってます」
分かっている割には平然としている。島谷は思った。普通の田舎の女子大生にしてはやることが大胆過ぎる。しかし、起きた事件は事実であり、自白もほぼ間違いない。
調書をまとめるとき、動機がまだ弱いと思った。子ども時代からの積年の恨みが積もり積もって、私憤から目障りな人物を殺害する計画を立てて実行に及んだ。人殺しをゲームに見立て、人命を粗末に扱った。そういう筋立てで書けばよいのだが、志保の本心を吐露させていない気がしていた。
なにか大きな力、殺人を起こす力というか切迫した事情。それを志保はまだ隠している。ほんとうは、父を助けたかったのではないかとも考えた。
「睡眠剤はいけんして手に入れよった?」
「私が通う心療内科からもらいました」
「農薬もおまえが入れたんだな?」
「はい。私が劇物の混入や睡眠導入剤を入れる役割でした」
「殺人の実行に腕力がいるときは、光宏に手伝わせた。そうじゃな?」
念を押すように藤宮は同意を求めた。
「そういうことです」
志保は藤宮と目を合わさずに頷いた。
「他に罪を犯した覚えはないのか」
「さあ……特にないと思います」
「嘘をつくと罪が重うなるぞ。五日の土曜日、N新聞の川畑記者を呼び出したな」
「え? なんのことですか」
「しらばくれてもやっせんど。調べはついちょる。どこに呼び出したち?」
「知っちょるんでしょ? 鳴沢ダムです」
「そこでなにをした?」
「取っ組み合って、最後は光宏が久野さんを殴打しました」
「それから先は?」
「久野さんが乗ってきた車を奪って、暗くなってから日の出市のホテルへ行きました」
「つまり、傷を負わせ、強盗を犯したことになる」
「それがいけんじゃと言うの?」
「いけんしたって? 立派な犯罪じゃち。強盗致傷ち言うんじゃ」
刑事は苦虫を噛み潰したような表情を作った。
「もう罪はないけ? よう思い出してみ」
「私にはありません」
「ということは光宏にあるのか」
「さあどうだか。本人が署にいるんだから、彼に訊いてください」
「まだ事件の全容が掴めんと。子どものころに心が傷ついて、大人になってから復讐した。それでは時間が飛び過ぎちょる」
「そうでしょうか」
「市長のライバルだったから殺したちゅうのもおかしか。だいたい、そげん簡単に人ば殺すもんかのう」
「疲れたのでしばらく話したくありません。細かい点については黙秘します」
志保はきっぱりと言い切った。
別室では光宏の取調べも同時に進行していた。
「水曜日の件は、きさまが車を運転して、志保と共謀して気絶した陽菜乃さんの服を脱がせ、湯船に運んだんだな」
「はい。間違いありません」
「袋に入っちょったドライアイス、いけんして手に入れたち?」
「おいは知りもはん」
「なんじゃと」
刑事は机を激しく叩いて、語気を強めた。
「志保がネットで買うたちゅうて、ドライアイス入りの発泡スチロールを持ってきたち」
「木曜の大木に被害者を吊るした件。あれは馬で引っ張ったっち調べがついちょるが、その馬はいけんして手に入れた?」
「それも志保が付近で飼われている馬をこっそり引いてきて、二人で縄につないだ。おいは車からだれか気づかんか見張っちょっただけたい」
「では、次。金曜の金庫殺人。あれは?」
「金庫に遺体を入れたのは、警備員です。志保は宇志窪のお茶に農薬を入れて殺害した。おいと彼女はその遺体を袋に入れ、車の後部座席においちょった」そこで光宏はいったん話を区切り、つづけて、「志保はあらかじめ警備会社の警備員を買収し、金庫の金を彼らと折半する約束ば交わしちょったと。
二日の水曜は平日じゃった。警備員らは、集配業務で南陽信金に立ち寄った際、回収した現金袋とは別に、金融事務センターから回ってくる、連休明けのときに使う現金袋と、車の中の遺体の入った袋をすり替えた。信金の関係者は、いつものことだからと高をくくり、そのとき立ち会わなかった」
「つまり、信金の人間は、まさか出入りの警備員が犯行に加担していたとは気づかなかった、というわけか」
「そげなこつです」
「最後に土曜の、市議を土に埋めた事件じゃが、火蟻はどこで集めた?」
「それもネットで志保が集めたとしか聞いちょらんです。おいは知らんと。志保は自宅の押し入れに火蟻を瓶に詰めて何十匹も持っちょったとです」
「いけんして鷺沼を殺した?」
「土曜日、鷺沼の自宅に志保が電話を掛けて喫茶店におびき出した。世間話をしたあと、店を出て裏の畑に連れていき、背後からトートバッグを被せて、おいが煉瓦で頭を殴り、気絶させた」
「それで?」
「そのまま車まで運び込み、服を脱がせて下着姿にした、用意した縄で縛ってから、園芸用の手袋をはめて火蟻を瓶から取り出し鷺沼の皮膚を刺させたち」
「服をめくって火蟻に刺させたのは二人でやったち? それとも志保単独か」
「二人でやりもした」
「それで鷺沼は火蟻に刺されてけしんじゃったか」
「うんにゃ。けしんでおらん」
「いけんしたと?」
「心臓が動いていたので、おいが遠くの工事現場まで車を運転しっせ、工事用の盛り土ば少し掘って、二人で土の中に鷺沼を埋めてから土を元どおりに被せたどん」
「そういうことか。司法解剖の結果でも、死因はアナフィラキシーショック死ではなく、生き埋めによる窒息死となっちょる」
「窒息なんですね?」
「最後に訊くが、犯行に使ったおまえの車はいけんしたと?」
「南町のパチンコ店で乗り捨てました。ナンバープレートも外しました」
「そうか」
「いけんじゃった、光宏の方は?」
藤宮刑事は訊ねた
「わりと素直に吐きもした」
光宏担当の刑事は、うまくいったと言わんばかりの顔をした。
「被疑者の犯行に使った車は?」
「光宏名義の車で、日産の黒のフェアレディZ。南町で乗り捨てたち言うちょりました」
のちに、乗り捨てたフェアレディZは、光宏の供述どおり、南町のパチンコ店の駐車場で見つかった。
「さて、残るは殺害動機の解明だ。いましがた、志保から訊いただけではどうにも解せん。調書にそのまま書いても動機が弱い。最後の鷺沼市議の殺害動機だけははっきりさせにゃならんち」
「女の怨恨ですか。根が深そうですね」
「細かい点については黙秘するそうじゃ。殺害の動機については、弁護士にくわしく話すかもしれんち」
島谷は渋い顔をして喫煙室に向かった。
火曜の午後、物的証拠を押収するために、二人の自供に基づいてそれぞれの家宅捜索がさっそく行われた。
「まずは二階の志保の部屋だ。置いてあるパソコンを押収しろ。それから、睡眠剤や処方箋などの類い、九〇リットルのビニール袋、注文したドライアイスを入れていた発泡スチロールは……ないか」
神取刑事の声が飛ぶ。
「他にはありますか」
「毒関係の本や書類。警備員と交わした契約書もあれば」
「はい」
「それに縄だ。縄もあれば持ち帰れ」
「神取課長。赤いスーツケースもありますが」
「おう。それも大事な証拠品だ。陽菜乃さんの遺留品を入れていたはずだからな。中から被害者の毛髪や指紋が取れたら、自供と一致する」
「火蟻はいけんしますか」
「おお、忘れるところだった。直接の死因とは関係なかが、遺体の傷跡と照合させるため、押入れを探せ。あれば押収する」
「了解です」
「園芸用の手袋にトートバッグと煉瓦もな。おいどんも手袋ばはめて、刺されんように気をつけろよ」
「あとですね。ゲームとかゲーム感覚とか言うちょりました。志保のスマホは署内で押収したどん、ゲーム関係のグッズやDVDも、ですか」
「あれば残らず押収するんだ」
「他は?」
「殺人方法や残忍なイラストの描いてある小説類や絵、DVDなどは全て押収だ。あと、あれもだ」
「あれと言いますと?」
「ほれ。N新聞の川畑記者。彼女の署名入りのN新聞や、そのスクラップ、彼女のことを書き記したメモ類があれば持ち帰ろうか」
「わかりもした」
刑事らは、起訴に向けて、押収した資料を基に、夜遅くまで調書を作成した。
容疑者の事情
志保は弁護士をつけてくれと要求し、
「くわしい動機などについては弁護士に話します。父の知合いの弁護士と面会させてください」
と刑事に訴えた。
しばらくたって、警官に連れられ接見室に通された。
テレビで観たことのある、真ん中に穴のいくつも開いた透明な窓で仕切られている部屋だった。
接見室に男の弁護士が現れた。
「鹿原志保さんですね? 弁護士の岡崎です」
席に着いた岡崎弁護士は、窓越しに挨拶した。
「鹿原志保です。市長の娘です」
「弁護士は、裁判で被疑者の立場に立って、あなたがたを弁護するためにいるのです」
岡崎は弁護士の立場を説明した。
「私、有罪になるのは覚悟しています」
「少しでも刑が軽くなるよう、弁護人として努力するのは惜しみません。まず、事件の背景や動機など、喋りやすいところから喋ってください」
岡崎は優しく言葉をかけた。背広姿のよく似合う、人の良さそうな丸顔の弁護士だった。
志保はこくりと頷いた。警察とちがって高圧的でも冷たくもない雰囲気が、志保を能弁にさせたのかもしれない。
志保は子どものころを振り返り、ゆっくり記憶をたぐり寄せるようにして語り始めた。
小学三年生のとき、自然愛好部のクラス委員に選ばれた。毎日、決められた場所の花壇に水やりをするのを主な仕事として割り当てられた。草花は見るのも育てるのも好きだったので、少しも苦にせず、きちんと水やりをしていた。毎日、せっせと欠かさずに園芸に精を出した。
緑の植物が葉をつけて、少しずつ成長していく様子を見ると元気が出た。とくにチューリップの花に関しては大好きで、春になれば赤や黄色や白の花をつけるのは知っていた。秋に花壇に植えたチューリップの球根が、次の年の春に花をつけるのが愉しみだった。
花が咲いたら友だちを花壇に連れてきて、「私が育てたのよ」と自慢できる。志保にとってはそれもまた愉しみで、冬の寒い時期に芽の出た球根にせっせと水や肥料を与えた。
その児童の夢を奪ったのが、あの男、鷺沼だった。ある日、見知らぬ中年の男たちが集団で学校に姿を見せた。ちょうどゴールデンウィークの始まった四月下旬ごろの土曜日だったと記憶している。
その日、学校は休みに入っていたが、志保は責任感の強さから、休みの日もチューリップの花の水やりをしたい、と申し出て学校に入る許しを得て登校した。
教室には行かず、ランドセルに水筒と菓子パンを入れ、花壇に着くと校舎の壁にランドセルを立て掛け、さっそくチューリップの花に水をやり始めたところだった。
大人の男たちの集団が、校門横の駐車場に車を停めて、校庭の中にぞろぞろと入ってきた。その日、彼らは小学校の校庭を借り切って、サッカーの練習試合を行った。中年同士の対戦であり、ボールを蹴ったり追いかけたりする動きはとても鈍かった。
そのうちだれかが大きく蹴り出したボールが校庭の端の花壇まで転がって中に入った。無神経な鷺沼は、白のティーシャツ姿でサッカーボールを取りに来て、花壇の中に入った。ずけずけと土を踏んでボールを手に取ると、
「ちきしょう。こげんボールが悪かとね」
ボールを見つめて文句を言い、きれいに咲いている花壇のチューリップの花を片っ端からサッカーシューズで踏みつけて去っていった。きれいな花をつけていたチューリップは、無残にも花びらを散らし、ぺちゃんこに押し潰された。
校舎のかげからその大人の顔を、ふたつの瞳が恨めしげにじっと見つめていた。志保だった。志保は唇を噛んで目に涙をため、男の去っていく後ろ姿を見つめた。それよりほかにできることはなかった。その男が悪い大人であり、やっつけたい気持ちはあったが、子どもの自分が喧嘩を挑んで勝てる相手ではない。
あの細長い顔にチリチリパーマの眼鏡をかけた男め。きれいに咲いたチューリップの花にはなんの罪もないのに。いつか、痛い目にあわせてやるから――。
その日、帰宅して、チューリップの花を踏みつけられた、と父に泣いて事情を話した。男はだれなのかと訊ねたが、父は知らないと無愛想に応じて、子どもの話に耳を貸さなかった。
小六のとき、職員室でチリチリパーマ男を見かけたので、話を盗み聞きした。会話から、その男はPTAの会長だとわかった。あの花壇を取り壊しましょう、プール専用の更衣室にしましょう、と教頭に持ちかけていたのもその男だった。
中学に上がっても、高校生になっても、よほど「チューリップのトラウマ」が心に残ったのか、あのときの光景は頭に焼き付き、憎悪は忘れなかった。忘れるどころか募るばかりだった。
時は流れ、志保も大きくなった。
偶然、町中で細長い顔にチリチリパーマの眼鏡をかけた男、小学校時代の元PTA会長を目にした。市議会議員の選挙ポスターの写真で、男はこちらに向かって笑いかけていた。
【さぎ沼こういち】
そう書かれてあった。選挙権が与えられる年令でもあったので、大学一年の志保はその名前をはっきりと覚えた。市議会議員選挙の当日、自宅から近い集会所に行った。そこが投票所であった。受付で投票用紙を受け取ると、何気なく他の候補者の名前を紙に書き、素早く目を走らせた。さぎ沼が「鷺沼」という漢字であるのも頭に刻み込んだ。犯行の三年ほど前のことだった。
鷺沼、鷺沼。
めらめらと復讐の炎が燃え上がり、彼を殺すシナリオを意識して頭に描き出したのもそのころだった。時期は、チューリップ事件のあったゴールデンウィークがいい。浮かれた季節にこの世から消えてくれたらこれほど嬉しいことはない。屈折した心で、殺人計画をひたすら練ることに快感と愉しみを覚えた。
忌まわしい人間、しゃくにさわる人間は、さっさと目の前から消えてほしかった。ゲームのモンスターならデータを削除できる。その感覚で人を殺傷したかった。命の尊さなどというご立派な説教には呆れて耳を貸さなかった。
選挙の結果、鷺沼紘一は何番目かで再選を果たしたのをN新聞の朝刊で知った。すでに市長を務めていた父の座を狙っているとの噂も周囲から耳に入ってきた。とんでもないやつだ、とはらわたが煮えくり返った。
あのときの志保の悔しさを知らないチリチリパーマ男は、なにかにつけて父に胡麻をすり、盆踊りやなにかの地域イベントに駆けつけて顔を出しては、父の立っている場所と反対側にえびす顔でふんぞり返っていた。その姿をインターネットのSNS上でなんども見かけた。
ただ市長の椅子をほしいがために、父の機嫌を取る胡麻すり男。父のライバル。いずれは市長選に立候補するらしい。それだけでも厭だったのに、小三のときの夢を壊した、あのチューリップ踏みつけ事件で憎悪の気持ちは増大し、はち切れんばかりだった。
憎むべき男は他にもいる。志保は平然とした顔をして、こんどは別の人物のことを岡崎に喋りだした。百姓の宇志窪悟についての話だ。
宇志窪から被害にあったのは、つい一年前のことだった。当時、稲和大学に通っていた志保は、夏休みに入っていた。八月のある晩に、高校時代の友人の由紀に誘われ、小学校で行われる地元の盆踊りに出かけた。浴衣姿に着替えて女同士で行き、由紀らと三人で踊りの輪に加わって踊っていたとき、後ろからぬっと手が伸びてきて志保の尻を触った。浴衣の上からぺたりと触られた。大きな手でギュッと包み込むようにして片方の尻を数秒掴まれた。キャッと小さな声を出し、すぐに後ろを振り向くと、赤ら顔の男がこっちを見てにやりとしながら、雑踏にすーっと消えていった。
「ち、痴漢にあった」
隣にいた由紀の浴衣の袖を引っ張った。
「志保、ほんとうなの?」
「嘘じゃない。男にお尻を触られた」
「いけんする? 警察に届けるけ」
「いけんしよう。ねえ、どうすればよか」
「私ならまず相手を捜し出して警察に突き出すよ」
「そら相手の顔は見たどん、逃げられたのよ」
「いけな人相の男やった?」
「酒に酔うた赤ら顔で、えーと」
「もっと他に特徴は?」
「そういえば、頭は角刈りで、最近どっかで見かけた……」
「どこで見たと?」
「あ、思い出した。あのオヤジだ!」
「だれのこと?」
「ほら、隣町の百姓しちょる宇志窪。広い畑さ持っちょって、いばりくさっとる。農業しちょるときは親切じゃっどん、酒飲むとタチが悪か男」
「ああ、あのオヤジね。たしかに志保の言うとおりよ」
もう一人の友だちが二人の会話に口を挟んだ。
「じゃっどん、いけんしたらよかね? 逃げてしもたよ。痴漢て、現行犯じゃなかち逮捕できんと?」
「そうかもしれんね。顔見ちょったど? 容疑者を追わんとならん」
「じゃっどん、人が多くて」
「そいが相手の狙いたい。人ごみに紛れて触ってきて、その中に隠れとる」
「宇志窪を探さにゃならんち」
三人は盆踊りの櫓に付けたスピーカーからやかましく流れる音楽を尻目に、手分けしてずんぐりした体形の宇志窪を捜し回った。
けれども、あいにくその男は盆踊りの輪の中にも、外の露店にもいなかった。まんまと犯人に逃げられた形になった。
けっきょく被害届を出さないまま、志保は由紀ら二人と別れ、失意で家に帰り着いた。警察にどこをどんなふうに触られたかなんて訊かれるのが厭だった。それで泣き寝入りする羽目になってしまった。
宇志窪悟。あのセクハラじじいめ――。
以後、一年にわたり、志保は痴漢行為を受けたことを根に持ちつづけた。
志保はおとなしくみられがちだったが、執念深い女だと自分でも思っていた。
過去に芽生えた怨恨や業腹を帳消しにするには、相手を殺してしまうのがいちばんスカッとする。光宏という恋人もいるし、力が必要なら彼に任せればいい。殺人の手立てなら、いくらでもスマホで調べられる。この町のことは昔からよく知っている。知り過ぎているから、心に溜まった鬱憤は殺人でしか晴らせなかった。
志保は岡崎に憎い相手を殺した理由を長々と語り、自分の行為を正当化した。
「それから、五月三日、N新聞の飯野という記者に電話をしたね?」
岡崎は、飯野と関わったことも知っている様子だった。
「それは、N新聞の記事作りを混乱させようとして、わざと餌をまいたのです」
志保は狡猾な一面を見せた。志保は飯野への電話から食中毒までの一連のことを振り返った。
でたらめの情報を新聞記者に流すと、新聞はどんな記事になるのか。正直、ワクワクした。
公衆電話を使って、自らN新聞社に電話をかけた。五月三日の正午のことだ。係の者が出て、猪里市に出向いている飯野の携帯番号を教えてくれた。
新聞記者にガセネタを掴ませ混乱させようという狙いと、川畑久野というN新聞の女記者を困らせてやろうという目的からだった。
それに対して岡崎弁護士は疑問を呈した。
「いけんしてN新聞の川畑記者を困らせてやろうとしたんだ? 検察はそこを突いてくる」
「それは――」
そのとき、志保はこの弁護士が一番、事件の深層部まで見抜いているのではと思い、怖くなった。警察にも話していない飯野の件や、久野に恨みを抱いている件の一部までを知っていそうな口ぶりに、この中年の、飄々とした風采の男が、実に不気味だった。けれど逆に、彼を味方につければ、私の刑が軽くなるかもと期待を寄せ――ほんとうは始めから極刑など下るわけがないと軽く見ていたのだが――、話せることはこの際話してしまおうという気になった。
「聞いた話だと、最初から川畑親子が渓山荘に行くのを知っていた。それで車にパンクするような細工を施し、JAFを呼ぶ時間稼ぎまでして川畑親子とともに行動し、バスを使うことで渓山荘へ到着するのを遅らせた。赤い眼鏡をかけて旅行者になりすましたのは、一件目の犯行のアリバイのために仕組んだ罠だった、と」
「それは部分的に違います。渓山荘へ早く着いても、温泉は営業してなか。外からは、開店前に光宏が陽菜乃を湯船に運んでいる様子は見えん。アリバイ作りに選んだ相手が、たまたま川畑久野だった」
志保は事実を弁護士に言い当てられても、俯いて否定した。
「ほんとうにそうなのか? 川畑記者になにか個人的な恨みがあったのではと思うちょるが」
志保は言いにくそうに黙り込んでいたが、沈黙の長さに耐えかねるようにして、ほんとうの事情を話し出した。
「あの女の記者と会ったのは、高二のときだった。向こうから私に接近した。名前を伏せ私の飲酒を記事にしようとして、取材を申し込んできた。彼女の名刺をもらった。当時付き合っていた大学生の飲み会に同席して、少しアルコールを飲んだ。ただそれだけなのに、未成年ということで記事にされかけた。父に頼んで手を回し記事になるのは揉み消してもらったが、そのとき恨みを抱いた」そこでいったん区切って息を吐き、軽く息を吸って、「しかし、もっと厭なことが起きた。どこからか情報が漏れて、ネット上の掲示板で私の名前が出回り、高校でいじめの対象になった。それからしばらくして不登校になった。川畑久野。その名前をN新聞に見つけるたびに、反吐が出るほど憎悪した。私にとって、不登校という消せない過去を作ったきっかけはN新聞であり、川畑久野であり、高校の同級生だった。その頃から、この土地のなにもかもが厭になった」
「飯野記者とはいけんした?」
岡崎弁護士は手を素早く動かしながら、汚い字でメモを取っている。
飯野という記者の携帯に電話を掛けて、
「木に吊るされた女に関して、知っていることがあります」
と情報提供の旨を伝えた。その情報の見返りに金を要求した。半端な額ではない。一〇万円だ。大人なら払えないことはない。そう読んだ。あるていどの金になるほどの貴重な情報と記者に思わせる意味合いもあった。
飯野と名乗った記者は、なかなか信用しなかったが、面倒くさそうに、
「わかった。金は払うよ」
としぶしぶ応じた。
「もちろん、ほんとうの話なんですよ」
志保は念を押しながら、真剣な口ぶりで演技した。
「情報が多そうだから、会うときに確実に会えるように、きみのメルアドを教えてくれないか」
向こうの方から頼まれた。電話口で志保はプリペイド式携帯のかりそめのメルアドを教えた。さっそく、メールで待ち合わせを指定した。
《待ち合わせ場所は郵便局の裏の公園で。午後四時半でお願いします》
《了解です》
飯野からの返信は事務的で簡潔だった。
指定した郵便局の裏に、新聞記者が姿を見せたのが、午後四時半きっかりだった。スーツ姿で、やや痩せている印象を受けた。
「N新聞の飯野です。よろしく」
最初こそ名刺を出して丁寧にお辞儀をしたが、相手が若い女一人と分かると、飯野は露骨に見下した態度をとった。その上、「そういう場合の金は、だいたい三万が相場だ」と値切り、さらに、
「きみさえよければ一緒にホテルに行こう」
と体の関係まで要求してきた。若い男のくせに妙にガツガツしている、と志保は不快に思った。
むろん志保は拒否した。
「そういうことを言うなら、情報を提供するのをやめにします」
強く出てみた。体狙いの発言がほんとうか冗談か、見極めたかった。
「いまのはほんの冗談だよ。情報をくれないか」
志保は、すがる飯野に対して、この男は信用できないと女の勘で思った。頭の悪そうな飯野という記者は、目の前の若い女が犯人だとは全く気づいていない様子だった。
志保は、早くその場を立ち去りたくて、
「ちょっと急ぎの用事を思い出したので」
と怒ったような口調で飯野に背中を向け、その場をあとにした。
それで終わりかと思ったら、飯野は、《情報をくれ。体を触らせてくれたら五万はやるから》としつこくメールを送りつけ取引してきた。大人というものは薄汚い。志保は心から侮蔑した。
金だけ先に受け取り、でたらめを伝え光宏に頼んで始末してもらおうかと考えてみた。金と女に汚い飯野という記者が許せなかった。汚らわしかった。そのへんの畑の地面の中にいる虫けら以下の存在だと思った。
冷静になって考えてみると、飯野をダシにして久野をおびき寄せられる可能性があり、リスクも大きいので、殺人は思いとどまった。
しかし、飯野という記者にも反感を抱き、その気持ちは膨らんだ。
あらかじめ、家でイヌサフランの花を飾りたいと父の知り合いの人に頼み込んであった。五月三日の昼過ぎ、毒草のイヌサフランの葉っぱを光宏と二人して摘んでおいた。もしものためにと計画していた。
久野と高橋峰子に毒を盛るつもりが、飯野も入れて一人分増えた。四日の朝早く起きて、イヌサフランの葉をヨモギに混ぜて細かく刻み、玉子焼きに入れ、握り飯を添えた弁当を三個作った。
一つは高橋峰子の経営する民宿の自宅に、残り二つは久野の自宅の玄関に隙を見て置いてきた。どこの家もそうだが、田舎では玄関が開けっ放しのところも多い。それは、よそ者の来ないあいだは、近所に対して心を開いている証拠でもあるような感じだった。
久野が食べなかったのは計算外だったが、由紀の母と飯野にはひとまず報復できて満足していた。由紀の母、高橋峰子は志保が家庭教師の教え子に手を焼いているのを由紀から聞いていたのでいつか人にチクるだろう。そう踏んでいた。田舎の噂の広まるのは早く、だれそれが食中毒で入院したというのは、町の噂ですぐ志保の耳にも入った。
岡崎弁護士は、
「志保さん。四件の殺害方法についてくわしく訊きたいのですが」
と静かな口調で訊ねた。
志保は横を向いていた顔を戻し、岡崎の顔をちらりと見て、口を紙コップの水で湿らせてから、喋りだした。
もっとも憎むべき鷺沼を殺し、その前に宇志窪を殺しておく殺人計画を立てた。時期は、あのチューリップが踏み潰されたゴールデンウィークに決行しよう。ただ、一日に一人ずつ殺していくだけでは面白くない。曜日に因んだ殺害法を考え、刑事らを攪乱してやろう。そのように考えた。
殺害に関しては、火曜日から始めてもよかったが、火をつけて殺すさい、万一こちらに燃え移るのが恐くなった。その危険性から安全な水曜を選び、水曜日から連続殺人を始めることにした。水曜から土曜までのあいだに四人殺そうとすると、残り二人を適当にみつくろってきて殺さねばならない。最初の二人は適当な人間を選び、動機を不明なものにすれば、きっと捜査は混乱して難航する。
いろいろと殺人に関して決め事を作り上げていくうちに、だんだん人の命を奪うのを考えるのが楽しくなってきた。
犯行は、力がいる場合には、恋人の光宏に手伝ってもらうことにした。彼とはなんどか寝たこともある間柄であり、体を求めてくる見返りに、共犯者として殺人を手助けさせようと考えた。
光宏を家に上げて、居間で殺人計画を話したら、最初はたいそうおどろかれた。
が、これまでの憎しみや辛さを訴えると哀れに思ったのか、こちらの言うことに対して、本気で相談にのってくれた。
「光宏。水曜日に殺すとしたら、やっぱり水死させるよね」
「そうじゃろな。じゃっどん、池や川じゃと外から見られはせんけ」
「屋内ならば?」
「屋内とね。水のある屋内ち、どこね?」
「銭湯や温泉よ。プールはまだ早かろ? 温泉がよかよ。開業時間前に忍び込んで、死体を浮かべるの。わっぜえ殺人ショーの幕開けじゃろだい」
話に乗ってきた志保に対して、光宏は冷静に、
「従業員に見つからんち?」
「だいじょうぶじゃち。車中で気絶させて、裸にして湯船に浮かべるの。そうね、ドライアイスでも入れたら死ぬんじゃなかち? あとで調べてみるわ」
「だれを殺すち?」
「家庭教師の生徒。沖本っていう女子中学生よ。その子ね、覚えがほんと悪くてとろいの」
「ガキを殺すのか。なんだか後ろめたくてあまり気乗りせんが」
「だいじょうぶ。私は市長の娘よ。絶対に逮捕なんてされないわ。それに、光宏は私とこれから先も関係をつづけたいんでしょ?」
「それはそうじゃどん」
「だったら、私に協力しなさい」
「木曜日はだれを殺すと?」
「さあ。まだはっきりとは決めとらん。行きずりの殺人なんていけんね? 〝木〟だから、ターゲットを木に吊るして馬で縄を引っ張らせっせ、窒息させるとか」
「残忍な殺害法じゃのう」
「そうかしら」
「じゃっどん、どこの木で、どこから馬を調達するか、早うから下調べしぃちょらんといけんが」
「そいは任してよ。よかとこがあるの。もう目をつけちょるがね」
志保は目を輝かせた。
「金と土は?」
「それこそがメインディッシュよ。〝金〟は金庫に入れておく。〝土〟は土の中に埋める」
「殺害法は?」
「金曜は宇志窪を殺す。じゃから、やつが毎日使うちょるお茶の容器に農薬を入れっせ、二日の午前中に毒殺しておく。遺体は信用金庫の袋に入れて金庫の中に鍵をかけて閉じ込める。信金の専用警備員をすでに買収しちょるで、二日の水曜に空になっちょる袋に遺体を入れっせ、鍵を持った警備員に宇志窪の遺体入りの袋を金庫に入れさせる。あとは二日後の四日金曜に遺体発見の電話を警察に入れりゃよか」そこで二つ咳をした志保は、さらにつづけて、「そうじゃ。鐘が鳴るのに合わせて遺体発見の電話を警察署に掛けようか。それがよか。面白か。ショップでプリペイド式携帯を契約して掛けるち。土曜はそもそも恨みさ抱いた張本人の鷺宮紘一市議。あの男は、気絶させて腕や足を火蟻に刺させて殺してしまおう」
「おいは農学部じゃっどん、火蟻によるアレルギー死は、必ず起きるとは限らんち聞いたどん」
「そげんことは知らんち。体ば縛っておいてから刺させるのよ。どうせ、あとで土の中に埋めるんじゃから」
「そもそも、火蟻みたいな危なか毒虫を、いけんして集めるとね」
「便利なツールがあるじゃろが」
「と言うと?」
「ネットじゃ、ネット。インターネットの掲示板で、『火蟻求む』と書き込むんじゃ。悪かやつらがおるち、すぐに、一〇匹いくら、一〇〇匹いくら、ちて言うてきよるがね」
「恐ろしか世の中じゃな」
「そげんこつは私のせいじゃなか。善も悪も、情報がつぶさに書かれちょるのがインターネットじゃち」
「犯行には、おいのフェアレディば使うか」
「そうしてくれると助かるわ」
「よし、わかった」
「やっと本気になったようね」
「志保がそこまでやるんじゃったら、九州男児として黙って見てはおれんが」
だいたいそんな感じで殺害法を決めた。
志保は上目遣いに岡崎を見て、話し終えた。
「志保さん、大学生活はいけんでしたか」
岡崎は訊ねた。急に志保の身の回りのことに話の矛先を向けてきた。志保はつまらなそうな口調で話した。
大学は三年生までは問題なく通学し、大学生活を過ごしていた。しかし、年があけて三年の冬あたりから週三回ぐらい登校してはいたが、二月から不登校になった。ゴールデンウィークに入る二週間前ぐらいは、他の学生たちがどんどん企業の内定を決めていく中で、自分だけ取り残されて就職先が決まらず、ただ落ち込む日々を家で送っていた。その頃には、父には内緒で休学届を大学に出していた。あとで父に休学しているのがばれ、ひどく叱られた。
そこで、岡崎弁護士は眼鏡の奥を光らせ、訊ねた。
「殺害の小道具はどうやって集めましたか」
火蟻に関しては、インターネットの掲示板で、火蟻五〇匹求む、と書いたら、いくつか問い合わせがあり、売買が成立した。簡単に火蟻は手に入った。それを金曜日まで家で保管しておいた。土曜に鷺沼を呼び出し、喫茶店で話をしたあと、店を出たところを殴って気絶させ、車の中で縄を使って縛り、服を脱がせて下着姿の状態で火蟻に体を刺させた。アナフィラキシーショックで死ぬと思っていたのに死亡しなかったのは残念だった。光宏と相談して、工事現場まで車で連れていき、盛られた工事中の土の中に埋めて、土を元に戻してそのまま放置した。たぶん、生き埋めで死ぬだろうと思った。一番憎かった相手が予定外の死に方になったのは、実につまらなかった。
イヌサフランを集めたのは、三日の一時過ぎだった。農学部に籍を置く光宏が毒草にくわしいので彼の手引きで行った。父の知り合いに、「家に花を飾りたいので」とあらかじめ申し出て、イヌサフランを植えている家にお邪魔し、花壇に植わっていた花を少しと葉っぱを両手いっぱいに摘み、ビニール袋満杯に詰め込んだ。葉っぱを持ち帰って、翌日の朝、調理した。切り刻んで、別に摘んできたヨモギの葉と混ぜ、玉子焼きに加えた。その玉子焼きを握り飯と一緒に三人分作り、タッパーに入れて、高橋峰子のところと川畑久野の自宅の玄関に置いてきた。
農薬を宇志窪のお茶に混入した件に関しては、どこの農家も納屋などに農薬を保管しているので、光宏に頼んで害虫駆除に使う、との理由で借りてきてもらった。外で空のペットボトルに移し替え、殺すときに宇志窪の目を盗んでお茶の容器にペットボトルの農薬を入れた。だれもその場面を変には思わなかったと思う。
同様の手口で、中国人観光客の李さんの場合も、睡眠剤を混入したお茶と李さんの持っていたお茶をすり替えた。睡眠剤は、志保が使い余っていたのを流用した。同じメーカーのお茶にして、飲んだ分だけ減らしておいたら、彼女は全く気づかずに飲み、しばらくして眠った。
志保は興奮したのか、殺害法にまで言及した。
白髪混じりの岡崎は、メモを丹念にとり、頭髪を撫でて黙り込んでしまった。周到な計画を持って行った殺人は刑が重い。それから、怨恨の殺人も含め、被疑者が裁判所で充分に反省の色を見せないと、心証が悪くなる。
人口の少ない、噂がすぐに伝わるような地方都市で、彼女が更生できるかどうか、自信はなかった。とにかく、弁護人としてやれるだけのことをやるまでだ、と自分に言い聞かせた。
水曜日、二人は送検され、検察官が警察を指揮して、実況見分が行われた。まず事件の順番からして、南町の渓山荘から始まり、次に南町の中心部にある南陽信金南町支店、隣の豊吉町の畑、最後に少し離れたところにある東の原町六丁目の工事現場と車で回っていった。
それぞれの場所で、手錠をかけられた志保と光宏がぼそぼそと喋り、なんどか頷いて、おおむね自供を裏付ける説明や再現が行われた。
ただ、二件目の大木殺人について、馬を使うことで、李さんを引っ張って大木の枝が折れるのかどうかに関しては疑問点があった。
豊吉町で飼われている馬は特定できたが、その馬の尻を叩いただけで猛烈に走り出したとは考えにくいという捜査官の見方が大半を占めた。
「いけんして馬を急発進させたんじゃ?」
検察官は志保に訊ねた。
「馬は臆病で耳がいいから、馬の耳元でブリキのバケツを思いきり叩いておどろかせたんです」
志保は馬の突然走り出した秘密を明かした。実際使われた馬に同様の仕打ちをして確かめることはしなかったが、飼い主に訊くと、
「そりゃおめぇ、突発的に逃げるち」
との証言が得られた。
水曜日は、実況見分だけで日が暮れた。
夜になって重要な証言が得られた。検察官が、
「ほんとうの動機はなんですか? もしかしたら、市長が絡んでいるんじゃなかか」
志保は父のことに話を振られ、我慢の針が振りきれてしまったように喋りだした。
「父が星永産業の殿田さんに、『五、六千票頼みますよ、次の市長選挙で』と自宅で電話を掛けているのを偶然立ち聞きしてしまったんです」
「それは知らなかった。それで?」
「その場で殿田さんは了承したらしかった。父は、居間で携帯から市の幹部に電話して、『水道局の下水道工事の入札で星永産業に便宜を図るように』と指示していました」
「なるほど。鹿原市長と殿田氏の癒着ぶりが見えてきた」
「私は聞かないふりをしていました。でも、ある日、あの男が」
「あの男とは?」
「鷺沼です。鷺沼は、工事入札の証拠を握ったらしく、父の携帯にメールを送りつけてきました。私は、父の留守のあいだに、父の携帯を盗み見たんです」
「いけな内容じゃったち?」
「《水道局の下水道工事入札の件で、市長自らが星永産業に便宜を図るよう指示したそうですね。市の担当職員から情報を得ましたよ。いずれ市議会で追及します。きっと、地元の新聞に口利きとして取り上げられることでしょう。来年の市長選挙に影響が及ぶのも必至じゃないですか》そんな内容でした」
「脅しですね。鷺沼は脅しをかけて、市長の座から鹿原氏を引きずり下ろそうとした」
「ええ、私もそう思いました。父も困ってました。だから、父を助けるために、との思いで鷺沼に死んでもらうのが最善の策と思って」
「それで殺した。個人の恨み云々の話より、市長の不正告発を阻止するのが、今回の殺人事件の一番の目的。そうじゃなかか」
志保は唇を噛み、大きく頷いた。
彼女は隠していた動機をついに検察官に白状した。彼女の心には、不登校という父への負い目と、父を救いたくて殺人を実行した狂気が同居しているように思われた。二つの思いがせめぎ合っていたのかもしれない。
検察官が、主犯容疑者の本当の動機を裁判で明らかにすべきだと考えたのも無理のないことだった。
失望と希望
逮捕から三日後、五月一〇日の木曜日、志保と光宏の勾留が決定した。その翌日の金曜日、久野は留置場へ鹿原志保に会いに行った。容疑者の友人と称して面会した。
接見室に通された。すぐに警察官が志保を連れてきて席を外した。志保は長い髪をバッサリ切ってショートにしていた。心境の変化か環境が変わったからかと思ったが、あとで振り返るとそのときすでに覚悟ができていたのだろう。
一五分の制限時間内で一つ訊きたいことがあった。
久野の顔をギロリと睨みつけ、志保は無言で俯いた。
「いけんしてあなたは町をパニックに陥れたの?」
観念したように項垂れていた志保は俯いたまま、ふふ、と無表情で口元だけを動かし、
「人が嫌い、町が嫌い、世の中が嫌いなのよ。ただそれだけよ」
そう言うと横を向いた次の瞬間、舌を出して思い切り噛みきった。悲鳴が上がり、さきほどの警官が慌てて入ってきて、救命措置を施そうとした。
あまりの痛さのせいか、志保は椅子ごと仰向けに倒れて失神した。
久野はびっくりして立ち上がった。
「志保さん、死んだらだめよ。あなたは自分が犯した罪を償わなきゃならないのよ」
久野は透明な仕切りを必死に叩いて、大声で呼び掛けた。けれど、久野の願いも虚しく、一時間後、志保はそのまま息を引き取ったらしかった。
残された恋人の光宏のことを顧みない死に様だった。最初から最後まで、独りよがりな女だった。久野は哀れに思った。彼女にだれも手を差し伸べられないのを寂しく思った。心の闇は深すぎた。
光宏に関しては、殺人罪、強盗致傷罪、共謀罪、犯人隠匿罪などでそれ相応の重い懲役刑になるだろうと思った。
主犯容疑者のあっけない死亡を目の当たりにして、やるせない思いで胸が締め付けられた。もっと早くに志保を捜し出し、凶行を思いとどまらせていたら。
一連の事件で猪里市の評判はガタ落ちになり、市長は責任を取って辞職せざるを得なくなるに違いない。久野も気づいていた。町の未来を考えると、真実を曲げずに報道するのは、一方では職責があり、他方では躊躇と動揺があった。志保とはちがった意味で、久野の心の中にも一種のせめぎ合いのようなものがドロドロしていた。
それでも、編集長の言葉どおり、真実は一つでも書かれて困惑する人たちの心を癒してゆかねばならない、と思った。
それは横に置き、猪里市の未来に泥を塗ることになっても、今後の教訓として、復帰している飯野に事件の特集記事の原稿を書かせた。もちろん、それは捜査関係者に対する取材に基づくものだった。
特集 猪里市連続殺人事件 二人の容疑者のうち、鹿原容疑者は、辺鄙な町だから未来に希望が持てず、就職も決まらないまま大学を休学中で、退屈な毎日を持て余していた。四件の殺人のうち、三件はカムフラージュの殺人であり、軽微なきっかけからゲーム感覚で罰を与えたと供述。本来の目的は、四件目の被害者が父の後釜を狙う政敵であり、小学校のとき大切に育てた花壇を踏み荒らしたのを根に持って大人になり、殺す計画を恋人の福松容疑者と立てた。
市長である父に大学を休学しているのを厳しく叱られ、テレビが来れば市が脚光を浴びる、父も市長の仕事をつづけられなくなるとの安易な考えを持った。ある種の歪んだ心を持ち、愉快さを求めていた。
高校のとき飲酒事件をメディアに取り上げられそうになったのがきっかけでインターネットに実名が出回り、周囲からいじめを受け一時不登校になった。大学に入るも周囲になじめないこともあり、三年の終わりから休学中で、一部の大人に対する不信感を抱いていた。
たとえ物的証拠が挙がっても、市長の娘だから絶対に逮捕されないという勝手な決めつけと、市民の生活を顧みない自己中心的な性格が犯行をエスカレートさせた。
残忍な犯行を実行した鹿原容疑者と福松容疑者は全面的に犯行を認めたが、刑が確定する前に鹿原容疑者が留置場で自殺を図り、そのまま息を引き取った。
町をパニックに陥れた残酷な主犯容疑者は罪を償うことも、被害者やその家族への謝罪の言葉もなくこの町から消えた。
その後、検察は鹿原容疑者を被疑者死亡のまま殺人容疑で不起訴にした。これから、福松容疑者を起訴し裁判も開かれる予定である。はたして事件の真相は解明されるのか。
新聞記者として事件に関わり、二度とこのような事件を起こさせないよう、猪里市が暮らしやすく明るい町に戻るのを期待する。(飯野悟)
飯野の書いた原稿に目を落とし、久野はやるせない気持ちでいっぱいだった。最後まで残念な結果となった。
翌週から五日間の代休を取り、二一日の月曜日から久野は出勤した。社会部の記者として、次に原稿を書くときは、猪里市の明るい、望みの持てるネタを仕入れたい。そう願い、気持ちをリセットした。平穏な日常に戻ろうと、久野は今日も、稲和県内の道路をクラウンで走っていた。
ちょうどそのとき車のFM放送が一一時を知らせた。それに合わせるかのように、携帯が着信音を鳴らし、電話口で中平デスクの明るい声が響いた。
「Qちゃん、いい町ネタが入った。すぐに猪里市へ飛んでくれ」
「はい、これから向かいます」
久野の声も弾んでいた。心なしか空の雲が減り、青い空が午後にかけて広がっていくようだった。
〈了〉
パニックの町


