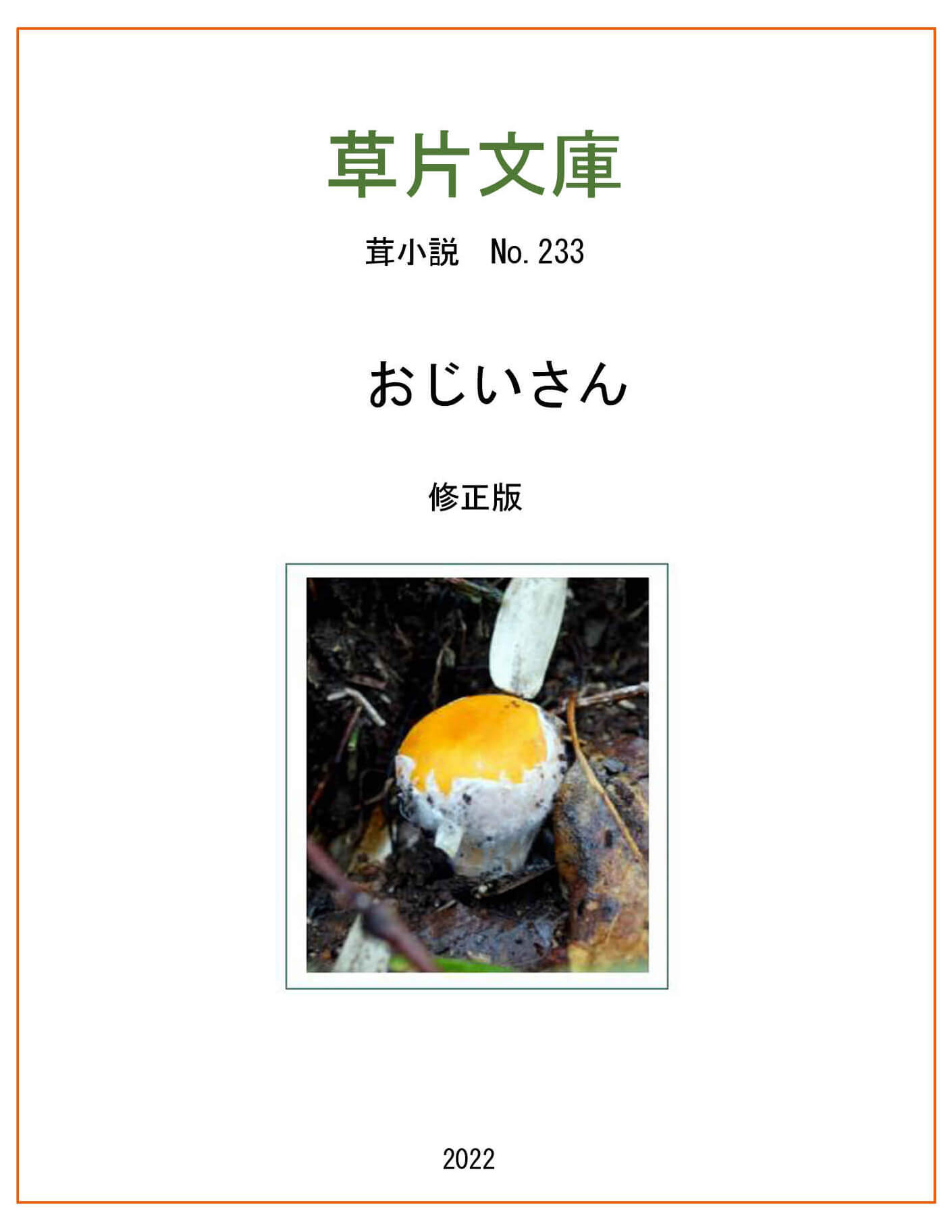
おじいさん
茸おじいさんの話 縦書きでお読みください。
これは僕の一生を、簡単にまとめたものだ。
小学生の頃だった。家族で茸狩りに出かけたときだ。林にはいると、いろいろな茸が生えていたけど、父親が、茸は毒があるものがたくさんある、勝手に採ってはいけないよ、と言って、僕がとろうとしてもだめと言われ、やっととったのは茶色のおもしろくない茸だった。
だが、父親は「これはイグチの仲間で、大きくなるともっとおいしくなるよ」と言って、僕のかごの中に入れた。
真っ赤なきれいな茸があって、採りたいなと思ったのだけど、それは毒よ、と母親にしかられた。
きれいな茸なのに、つまんない、と僕は林の中の小さなせせらぎの脇を上流の方に歩いていった。みんなは夢中になって茸を探している。
流れの上の方で、髭を伸ばしたおじいちゃんが、お鍋でお湯を沸かしているのに出会った。石を並べて、その上に鍋があった。枝をくべて、火の勢いを調節している。
僕はそのおじいちゃんと目があった。しわくちゃの小さな顔をしていて、目尻が下がっている。にこっと笑った。
「ぼおや、きのこ採ったかい」
おじいちゃんはそう聞いたのだが、僕は首を横に振った。
「みんな毒だって」
「こっちにおいで」
おじいちゃんは僕の持っているかごをみた。
「イグチのこどもじゃな、これもうまいよ」
「真っ赤な茸がほしいんだ」
みると、おじいちゃんの腰掛けている石の脇にたくさんの真っ赤な茸がならんでいた。
僕がほしかった奴だ。
「これは紅天狗茸と言うんじゃ、みておいで」
おじいちゃんは、その赤い茸を、ぐつぐつ煮立っているお湯の中に入れた。
すると、赤い茸から赤い色が落ちて、茶色っぽくなったともうと、ぷっくりふくらんで、大きなかわいらしい茸になった。
おじいちゃんは、その茸を取り出すと、僕のかごの中に入れた。
「もう一本、つくるかな」
そういって、赤い茸を鍋の中に入れると、また大きなかわいい茸ができあがった。
「ほらこれもあげよう、もうお帰り、みんながさがしているよ」
ぼくはわけもわからず、小さ流れに沿って、みなのいるところにもどった。
「どこにいってたの、山はあぶないから、一人で勝手にいってはだめよ」
お母さんがおこっている。
お父さんが、僕のかごの中をみた。
「おい、こりゃすごい、ポルチーニの立派なやつじゃないか、みんなみてごらん」
二人のお兄ちゃんもきて、僕のかごの中から手より大きい茸をとりだした。
「これ、食べられるの」
お兄ちゃんが言うと、おとうさんは「これは、イタリアでは、もっともおいしいキノコといわれているんだ」
「すごいね」
「日本では山鳥茸もどきっていうんだよ、よくみつけたな、どこでみつけたんだい」
僕は水の流れる上の方を指さした。
「行ってみいよう、まだあるかもしれない」
お父さんが先に行ったのだが、もうおじいちゃんはいなかった。
次は小学三年の時だ。またそのおじいさんと山であった。学校の秋の遠足で、一年生から三年生は、それぞれのクラスで違うところにいく。僕のクラスは村見山にいくことになった。頂上には町全体が見渡せるいい展望台があった。昔は村だったので、村見山だ。クラスは三クラスあって、山の麓を流れる村見川の上流にある村見滝にいくクラス、村見牧場にいくクラスがある。そこは一年と二年の時にいった。四年になるとクラス替えになり、まとまって遠足にいく。
クラスのみんなで、リュックをしょって、バスで村見山登り口まで行くと、林にはいって、下草を踏みしめて登り始めた。木の枝をリスが走っていくのが見えたり、鳥が林の中でがさがさ歩いていたりする。コジュケイという歩く鳥だと先生が言っていた。
展望台にあがると、先生が村の歴史を話してくれて、昔の建物のある方向を指さしてくれたりした。それが終わると、お弁当の時間だ。みな仲間同士で集まって、もってきたお弁当をひろげ、話をしながら食べた。その後は自由時間である。
あまり遠くにいかないように先生から注意があって、僕は林の中を二人の仲間と歩いた。明るい林で、迷子になるようなことはない。草の芽ぶきや、木の若葉がきれいだ。ここでポケモンゴーをしたらどうなるか、三人ともゲームをもってきていた。
僕たちはゲーム機を持って、好きなところにいった。小さな怪獣が出てきて、捕まえたりしていると、おじいさんが切り株に腰掛けて、お湯を沸かしているのに出会った。
「やあ、また会ったな、ゲームよりこれのほうがおもしろいよ」
おじいさんが沸いている湯の中を指さした。
ぶくぶくいっている鍋の中に紫色の茸がゆだっていた。
「みていてごらん」
おじいさんがそう言ったとたん、紫色の茸がふにゃっとなって、アメーバーのようにとろけだした。みていると、アメーバーは細長く延びて、真っ赤な茸になった。おじいさんは、それを箸でつまみ上げると、
「熱そうだな」
と言いながら、指で摘まんでかじった。
「うん、甘い茸になった」
僕はおじいさんにきいた。
「今、茸は生えないでしょう」
「そんなことはないよ、春にも茸は生えるんだよ」
ほら、おじいさんが指さしたところには、紫色の茸が生えていた。
「これを、煮ると、甘い茸になるんだよ、採ってごらん」
そう言われたので、紫色の茸を採って、湯の中にいれた。やっぱり、グニャグニャになって、赤い茸にかわった。
「食べてごらん」
僕はおじいさんが取り出した赤い茸を食べた。甘くて、まるで、マシュマロを食べているようだった。
「おいしかった」
「よかったな」
そこで、先生の笛の音が聞こえた。集まれの合図だ。
林から道にでると、友達も出てきた。
「何匹捕まえた」
「俺二匹」
僕は一匹だった。こんな林にも怪獣がいるんだ。だけど、おじいさんに会ったことは言わなかった。
中学二年のとき、九州に修学旅行に行った。新幹線で博多に行って、そこから、熊本、長崎、鹿児島の名所を見て回るのだ。なんと言っても、友達と一緒に宿屋に泊まって、くっちゃべるのが楽しい。家から離れる機会はなかなかないもんだ。あの、勉強しなさいって言う母親の声が聞こえないのがいい。小学生の時はそういうものだと思っていたけど、中学になってもいっこうに変わらない。中学生になって、自分では周りが少しはわかるようになったと思うことがあるが、母親の言うことは全く進歩がない。父親だってそうだ、小学生のときは先生の言うことをよく聞きなさいとよく言われた、それはよくわかった。だけど中学に入っても、同じ調子だ。先生の言うことは今でもよく聞いている、そのおかげで、先生も、時には間違っていることを言っていることがわかってきてしまった。
鹿児島の桜島を見てから、土産物屋に行ったら、椎茸をたくさん売っていた。ドンコといって、そのあたりのかくべつな椎茸らしい。友達もみやげに買っている。僕は一人で別の店にいった。店先に白い茸が並んでいたからだ。そいつは生の茸だった。椎茸ではない。じいさんが出てきて「ぼく、大きくなったな、ドンコもいいがな、この生の茸は今までにないすばらしいもんだ、生で食えるよ」と言った。
それで、その白い茸をみやげにかった。母親に渡すと、ドンコ買わなかったのと言われた。この茸はなんというのときかれたので、わからない、生で食べれる、と言うと、どこで売ってたのときくから、桜島と答えた。いくらだったと聞くから200円というと、ドンコならよかったのにといわれた。
香りがないわねといいながら、母親はサラダにした。食べたらそれはそれは、おじいさんの言うとおり、格別においしかった。
高校生になって、理科部に入った。中学のときから、星に興味を持っていて、中学でも理科部と卓球部にはいっていた。高校では物理部の天文班と言った。夏休みに、夜の校庭に集まって、天体望遠鏡で、星を見るのは楽しかった。クラブの先生も来ていたし、電車で通っているのは、親の車で送ってもらっていた。
高校が市の高台にあったので、星がよく見えた。先生に星座を教わり、いわれなどを聞いた。そういった後、みんなちりじりになり、自分の天体望遠鏡を持っているものは、それぞれのところに陣取って星をみた。僕も小さいけれど、自分の望遠鏡を持ってた。もっていない子もいて、友達の望遠鏡でみせてもらっていた。
僕は茂みの脇で望遠鏡を構えた。一年下の女の子で、見せてほしいというので、一緒に空をみた。たまに見かけたので顔は知っていたが、今まで話しをしたことがない。そういえば名前も知らない。
そこへ、人が歩いてきた。おじいさんのようだ。
「やあ、また会ったな」
おじいさんは言った。一緒に空を見ていた娘は、僕の知り合いだと思ったらしい。
「これが生えていた、生で食べるとうまいよ」と二本の白い茸をくれた。
「時間も止まるから、時間を好きに使うといい」
おじいさんはそう言うと、歩いていってしまった。
「たべようか」
僕は一本をその女の子にあげた。
「このまま食べるの」
「あのおじいさんの言うことは正しいんだよ」
「時間が自由に使えるってなんのこと」
その娘は聞いたが、僕にはわからなかった。ともかく僕たちは茸を食べた。そして空を見上げたとき、急にその子の肩を抱きたくなった。そうしたらその子は僕の方に首を乗せたて僕を見たので、唇を吸った。僕は手をその子のブラウスの中の奥の胸に触った。スカートの中に手を入れた。ズボンをおろすと、その子と一緒になった。時間はどのくらいたったかわからなかった。終わった後、その子とまた唇をあわせた。そのとき、そろそろ時間だよという先生の声が聞こえた。
僕は望遠鏡をたたむから、先に行ってとその子に言った。うんと、女の子は先生の方に歩いていった。僕も後を追った。みんなはなぜかざわついていた。
「あの火球すごかったな」と一人が話しかけてきた。後から新聞で知ったのだが、西の空に大きな火の球がおちていったという。みんなそれに見とれ、集まっていたらしい。僕たちはそのころ違う時間にいた。
女の子のお父さんがむかえにきていた。僕は一人で家まで歩いて帰った。とうとう名前も聞かなかった。
あのとき、おじいさんが言っていたように、時間を自由に使えたんだ。そう思った。本当にあったことなんだろうかとも思った。その子とはそれ以来、そういうことはしなかったどころか、ほとんど顔を合わす機会がなかった。同じサークルにいたにもかかわらず、名前もしらないままであった。その子はその後、サークルからやめたようだ。もう大学受験の勉強をしているようだと誰かが言っていた。
三年になったとき、親はある大学に行きなさいと、家庭教師を呼んだ。その大学の三年生で物理をやっている、優秀な男の学生さんだった。教え方はとても上手だった。僕もめきめきと成績をあげた。数学も英語も得意科目になった。それに伴って、ほかの科目の成績も上がった、四年になったときには、高校でいつも五番以内だった。だけど僕は誰が何番でどうだなんて気をつけてみていなかった。ただ物理や数学の問題を解くのが得意だった。天文班には三年のときにはたまに顔を出していたけど、四年になってからはほとんど行かなかった。しょっちゅう模擬試験があったし、予備校でやっている模擬試験もよく受けていた。志望校への合格率はいつも七十五パーセント以上とでた。
センター試験を受けた結果も自己採点すると、やはりそうだった。こうして希望をしていた国立大学に受かった。
大学は家から電車で一時間半ほどかかった。親は大学の近くの小さなマンションを借りてくれた。一人っ子だったせいもあるが、ちょっとぜいたくをさせてくれた。理学部の物理にはいったが、天文学と純粋物理の二本立てで、学ぶ方向の教科を選んだ。サークルはロケットマニアという、昔のロケットのことを調べたり、ロケット映画をみたり、実際にペンシルロケットをとばしたりした。それに野草を食べる旅行の会にも入った。テントを持って山に登り、生えている植物を食べ、露天湯にはいるのである。草の旅という名のサークルだった。
三年になるとき、どの研究室に行くかなかなか決心が付かなかった。天文学か、純粋物理か、ロケット工学か。
夏休み明けには決めなければならない。草の旅の夏休み合宿は長野だった。八ヶ岳のキャンプ場に皆で行って自炊をした。食べられる植物はたくさんある。僕は茸を探して林の中を歩いた。本当に食べられる茸を探すのは難しい。毒茸を採っていったら大変である。よく知っているのは数種類である。
イグチをいくつか採った。卵茸もとれた。そうやって探していると、「久しぶりだねぼうや」という声がした。まだ坊やだ。
顔を上げると、あのおじいさんだった。
「ほら、これも食べられるよ」
おじいさんは黄色い茸を一本差し出した。
「食べてごらん」
とおじいさんは僕に促した。
「すみません」と言って茸を受け取るとかじった。
甘い茸である。
「おいしい茸ですね」
「そうじゃろ、頭の中をすっきりさせるからのう」
おじいさんは、「ナメコがあの木の裏にあるよ」と指さした。
行ってみると、天然ナメコがたくさん生えていた。
喜んで採ると、おじいさんに「ありがとうございます」といったところ、もうそこにはいなかった。
そのとき、突然、茸の傘の働きが頭に浮かんだ。茸は菌糸の集まったもので、傘の裏の襞に胞子を作る。熟した胞子は風にのって遠くに飛び、土の中で菌糸を作り出す。傘の下では風がまくれて飛びやすい、その計算式が頭に浮かんだ。何事も原理を知っていれば応用が利く。
ともかく、ナメコを持って帰ると、サークルのみんなが、さすが先輩ともちあげてくれて、頭の中では、純粋な物理、物性物理を追求しようとはっきりした答えがでて、気持ちが高揚した。
夏休みが終わると、星を意識した物性理論学の研究ができる先生に師事することにした。
僕はノーベル賞をもらった何人もの物理学者の論文を読んだ。膨大な機械と、大勢の優秀な人に囲まれていないと、理論を証明することができない大変な世界であることが改めてわかった。やはり宇宙の成り立ちに関わる現象を突き詰めてみたい。宇宙を一つの生き物と考えると、地球上の生命は宇宙の中にいながら、宇宙とは異なった原理で動いているのではないか。脱皮するように、人は生まれて、新たな生命を作り自分は死んでいく、宇宙はどうだろう、ただ広がっている、どんどん広がり、どこかから新たな物質が生まれる。どこから。それがわからない。ただ生まれる。死がない。宇宙は脱皮して新たな宇宙を産むことがない。いや、異次元に新たな物を作り出しているかも知れない。宇宙の死は無か。
無の物理。素粒子の解剖を新たな側面から行わなければならない。そんな漠然としたことまでは考えたのだが、どこからはいったらいいのかみえない。無の物理学と教授の前で口に出したとき、教授は決して笑わなかった。
「物理学者で超自然現象にはまってしまった人が何人もいるよ、しかもかなり優秀な物理学者がだよ。無という物は我々の学問では解析できないのだね、君の無の物理学は一つの理想かも知れないが、それを知るために、物性物理学をきわめてごらん、有を生む無という物質があるとすれば、その性質の物理学ということになるが、それはおいておいて、我々の宇宙を作る物の物理学的性質をまずつきつめるのだね」
教授はまじめに話を聞いてくれた。
「素粒子で日本は輝かしい成果を上げている、どうだい、もっとださく、小惑星の石、宇宙のちり、そういった物から、宇宙の成り立ち、起源にせまってみたら」
とても納得いく説得だった。今宇宙開発は米露中により競争と協力で進められている。民間の宇宙船計画が中学生の頃始まり、今、いくつかの宇宙ステーションが地球の周りに浮かんでおり、月での住居の設置計画がある。月をステーションとして、宇宙に飛び出そうという計画である。
隕石の密度の形成を、宇中空間にあるときと、地球上に落ちてからの違いを、鉄の分子レヴェルでの変化を予測、実測するという世界にはいった。
卒業論文が学界でも認められ、修士課程から博士課程に進んだ。修士課程では軽い鉄の可能性を論文にまとめたこともあり、それを実践するイノベーションを友人五人と立ち上げた。皆工学の連中で、ロケットクラブで一緒にいた奴らだ。僕は理論を担当していた。
博士二年の秋のことだった。大きな火球が日本全国で観察され、千葉県の林の空で割れたことがわかった。
早速、調査隊のメンバーとして、大きな森の中に隕石の採取に行った。四キロ四方に隕石が散らばったようで、森の周辺の住宅地にも落ちた可能性がある。
僕を含め四名は森の中を担当することになった。森は一キロ四方ほどの広さであり、地図上に線を引き、十メートル四方ごとにそれぞれ違う方向に歩き丁寧に調べた。
二十分ほど調べながら進んでいくと、一本の木の枝がおれて垂れさがっているのが見えた。下草はまだ緑の葉を茂らせており、かき分けながら丁寧に見ていかなければならない。
特にそのあたりは目をこらした。するとあった、草が土にめり込んでいて、石が半分顔を出している。かなり大きな隕石だ。写真を撮ると同時に、手袋をして隕石を拾い、密閉箱に入れた。地図のだいたいのところに番号を振り、標本箱にも番号を入れた。
そのとき、がさがさと下草をかき分ける音が聞こえた。調査仲間かと思い顔をあげると、そこにはあのおじいさんがいた。
「やあ、ぼおや、収穫だったな、でもほら、そこを見てごらん、もう一つあるよ」と節くれだった指を地面に向けた。隕石を拾った脇に、黄色いかなり大きな茸が生えていた。隕石ばかり気にしていて気がつかなかった。
「それはね、そのまま食べると、病気一つしなくなるんだよ、月の茸っていうんだ」
おじいさんは、子供の頃あったときと、全く違わないしわの寄った顔に笑みをたたえた。
僕はその茸をとってその場で食べた。目がはっきりしてきて、力がわいてくるようだった。
おじいさんに礼を言おうと前を見たら、戻っていく後ろ姿しか見えなかった。その日、僕の役割のところで、十一個の大小の隕石を拾った。
採取された隕石は、調査隊長の大学にすべて運び込まれ、調査の分担が決められた。
僕は鉄の分子の調査をすることになった。
後で写真を見たら、おじいさんが月の茸と言った黄色い茸も写っていた。
その隕石の解析に精を出しているときに、隕石の専門誌に宇宙飛行士のことが載っていた。四段階の選考があり、それにパスするとアメリカで特訓を受けることになる。
最初は書類審査で、その後英語面接、地学、生物学などの試験がある。専門を持っていなければいけないのと、コミュニケーション能力に長けていなければならない。それに何よりも健康である。そのころ僕は病気一つしなくなっていた、あとになり、あの月の茸を食べたためだと知る。
ともかく、受けてみようかという気になった、英語で話すのは国際学会で何度か英語で発表もしているし、英語の検定試験は受けたことがないが、なんとかなるであろう。
博士課程三年になり、いろいろな隕石の鉄分子の比較と、月の石や、小惑星から日本の探査船ハヤブサが持ち帰った石との比較結果から論文をまとめると同時に、宇宙飛行士候補生選考試験に挑んだ。
結論から言うと、博士論文の予備調査にパスし、宇宙飛行士候補生の最終面接までいった。
はれて次の三月には博士「物理」の取得と宇宙飛行士候補生にパスした。宇宙飛行士候補生になるのにはなにかしら三年以上の実務経験が必要である。それは博士課程に入ったとき、大学のイノベーション立ち上げ補助費を使って、友人と立ち上げていた、軽い鉄の会社が軌道にのり、大手の鉄鋼会社の資本の元に新たな展開をしていて、その経営と技術者として働いていたので、認められた。
両親は大喜びであった。僕はアメリカに渡り、それから三年ナサで様々な訓練を経て、いつでもステーションに行くことができるようになった。
まもなく宇宙ステーション1号に一年滞在することになった。そのときは五つの宇宙ステーションが地球の周りを回り、それぞれの役割を持っていた。
1号ステーションは月のプロジェクトである。月は南極のように、地球のどの国にも属さない、共同の土地とされていた。そこに都市を造ろうという、百年計画がスタートして1年が経ったときのことである。まだ月に地球の基地は計画されたばかりである。0号宇宙ステーションを動かして、月に着陸させ、それを元に基地を広げていこうという計画である。月の表面はクレーターだらけである。酸素がなく、そのため太陽の光があるときは百度いじょうになり、なくなるとマイナスの百六十度にもなる。0号ステーションはそれに耐えられる構造を持ち、酸素を供給できる仕組みをもっている。さらに、人が住むための、培養による食料の生産設備など、すべてをそなえていた。
今0号宇宙ステーションは、1号宇宙ステーションとドッキングした形である。行き来が自由だ。僕が行ったのは、0号ステーションをみんなで完成させるためである。完成すれば、1号から切り離し、40万キロ離れた月に向かって航行することになる。音速程度であるから二十五分ほどで月にいき、月の周りを回り、タイミングの良いとき月に着陸させる。
1号宇宙ステーションではやることがたくさんあった。0号のメンテナンスと、出発させる準備である。一年後、1号から五人、ロシアの宇宙ステーション、これは5号ステーションと呼ばれているが、そこから五人、ステーション連絡船で0号にやってきて、十人の月基地造営チームを構成して月に向かう。1号にしろ5号にしろ、宇宙飛行士の出身国は皆違う。1号はアメリカが中心になって作られたステーションでも、乗っているのは、アメリカ、カナダ、日本、メキシコ、韓国、オーストラリアなどからきた人間で、5号はロシア、インド、イラン、エジプト、それに日本人もいる。技術、経費などの負担が関係するが、日本は4号以外すべてのステーションに人を送っている。4号は中国が中心である。2号、3号ステーションは0号と同じように月に着陸できるような仕組みを持っている。
ともかく、やることが多くて、毎日が新しい経験ばかりであった。それでも、ラウンジから見る星空は、疲れなど吹き飛ばしてくれる。1号ステーションのラウンジは透明なドームに囲まれ、星空を360度見渡せるのだ。透明なガラス様物質は日本の開発したものだ。昔から大きな水族館のガラスは日本のお家芸である。
一年はあっという間にすぎ、月へいく飛行士の名前が地球の司令室から届いた。ステーションの隊長から皆に伝達されたのだが、なんと僕の名前もあった。これには自分自身が驚いた。ステーションには二十人近くいるが皆ベテランばかりである。まだきて一年の僕がなぜ選ばれたのか不思議だったが、若い者も経験させようということと、基地作りに月の鉱物を利用できるような物性物理の専門知識のある人間がいると思ったからのようだ。五人のうち二人は女性で、植物学者と化学者だった。二人の男は操縦者と総合指令のキャプテンである。医者がいないのはどうしてだろうと不思議に思ったら、5号ステーションから二名の医師が乗り込むということだった。内科も外科もこなす男性医師と、精神科と婦人科をこなす女性だった。後は工学系の人と、副操縦士、それに副キャプテンになる人である。
出発の一月前に0号に乗り込むことになっている。我々も同じである、うまくコミュニケーションをとれるようにしておかなければならない。
0号には三十人収容でき、個室も備わっている。半年後、地球から直接飛び立った月着陸船が、直接人や資材を運び、月での活動をサポートすることになっている。
我々月の基地を作っている間に、2号と3号ステーションが月の上空に移動し、月を回るステーションになり、月の全体を観測する基点と、地球と月の中継所の役割を持つことになる。しばらくしたら、その二つも月の地上に降りてきて、1号と連結される。そういうかたちで、順次新しいステーションが建造され、地球を回っったあと、なれた宇宙飛行士をのせて、月の基地として送られてくる。
さらに、何十年後かには、月と地球が特殊な金属ロープでつながれ、人や物質の移送の手段となることだろう。
我々は一年の任務を果たしたら、直接、帰りの月着陸船にのり地球に戻り、百年の計画の詳細を作るグループにはいることになった。
0号ステーションのエンジン点火一月前に、5号ステーションから、ステーション間の宇宙艇で五人の飛行士が乗り込んだ。我々五人と初めての対面である。皆笑顔がいい人ばかりだ。もっとも、そうでなくては宇宙飛行士になれない。
驚いたのは、精神科で産婦人科の女医さんは日本人だった。小柄だがきびきびと動き、笑窪のかわいらしい女性だった。さらに驚いたのは僕より一つ若いということだった。
一月の間に、皆気心の知れた仲となり、発進の予行訓練も息のあったものになった。専門が違っても、船を動かすときは、操縦士、副操縦士のもとに、何らかの役割を担う。キャプテンとサブキャプテンの二人だけが、操縦フロアーの前の窓と、後ろのドア付近で全体を見渡しているだけである。
月への出発の日が来た。皆緊張というより、期待感であふれていた。僕ももちろん同じ気持ちである。初めて月での生活をする地球人である。
一号ステーションとはすでに切り離されている。キャプテンのゴーのさいんで、操縦士が発射のぼたんを押した。あまりスピードを出さない。音速以上の機能はもっているが、乗っている人間の精神を落ちつかせるための時間をとろいうということである。
三日ほどかけて月の周りへ到着した。着陸するクレーターは決まっている。
飛行は順調で、移動ステーションの機能は完璧だった。月の周りの軌道にのり、予定のクレーターにむかって、徐々に下降していった。
着陸のときが緊張の一瞬ではあるが、何重にも安全機能が付加されているコンピューター制御に心配はいらない。
一応シートベルトで座席に固定されてはいるが、着陸した瞬間はほとんど感じないくらいの衝撃だった。外を見ると、土の埃が舞い上がっているのが見えるが、それもしばらくすると落ち着いた。
それからは地球の上空を回っているときと同じ様な生活が続く。まずは0号ステーションを月に安定させなければならない。
ステーションの四つある一番高い塔は、高さは15メートルほどである。五階立てのビルほどである。そこの最上階にそれぞれ展望室があるが、目的は全く違うところにある。中に大きな脚がしまわれており、月の表面に徐々に下降していき、月の表面、地下10メートルまで脚が入る仕組みになっている。それで月に固定される。いきなりぐっとねじ込まれるのではなく、一月かけて下がっていく。
それまで、我々は外にでない。固定されたら宇宙服を来て外の作業になる。その間は無人車、ロボットによる、外部の情報の収集である。固定の脚の様子もそれでわかる。
僕はロボットがとってきた石のサンプルなどの解析をしていた。鉄を取り出すのは難しくはない。今地球では鉄ではなく軽くて丈夫ないろいろな金属類が作り出されている。しかし我々の技術は鉄をごく薄い金属にできる。しかも他の金属より丈夫でしなやかにである。いずれ月に生産工場を造ることになるだろう。
一月がたち、外にでる許可がでて、月面車で周りの探索にでた。宇宙服も昔のものと比べてずいぶん軽くなり、動くのに苦にならない。
隣のクレーターに、採石によい場所がありそうである。
僕が外にでるのになれたときに、精神科の女医さんが、月の外での人間の精神状態を調べているので、同乗させてほしいといってきた。日本人の女医さんである。このステーションのすべての飛行士たちの、精神状態を出発前からチェックしている。月の地上で働いているときの精神状態も調査もしたいということで、彼女は僕だけではなく、他の人たちとも一緒に出かけていた。
一緒に月面車に乗りこんだ。彼女とは同じ日本人なのに、規則ですべて英語で話をしている。
だが二人で月面車に乗っていると、自然と日本語がでてしまった。宇宙服を来ているので、電波による通信である。二人だけの会話もできる。
「どこの出身ですの」
彼女が聞いた。僕は生まれた県の名前を言った。
「同じですね」
彼女の顔は宇宙ヘルメットの中でにっこりした。
「私高校出てから、医学部に行って、精神科医になったんですけど、宇宙にあこがれてたんですけど、ロシア語もやっていたので、ロシアにいったんです、宇宙飛行士になろうと思って」
「そうなんですか」
そういっているうちに、隣のクレーターの僕の作業場所についた。
車を降りて、岩の重なっている間を通り、鉄を含む石の山のところまで、彼女と歩いた。
大きな岩を迂回したときである。いきなり、我々の前に何かが現れた。
「あ」と僕が声をだすと、彼女は僕の方を向いた。
そこにいたのは、あのおじいさんだった。
「ぼおや、この月の茸をお食べ」
おじいさんは赤い茸をもっていた。
彼女もおじいさんをみて、「もしかして」といった。
僕は高校の名前をいった。
「あのときの」と、彼女は言った。
ぼくも、「あのときの」と目を大きくした。
僕はヘルメットをとって赤い茸を食べた。
おじいさんは彼女にも茸を渡した。彼女もヘルメットをとって赤い茸を食べた。
「時間は止まるから、好きなように使うがいい」
僕は宇宙服をぬいだ。彼女もぬいだ。
僕は彼女の肌に触れた。
僕は彼女の乳首をつまんだ。くちびるをすった。着ているものをすべてぬいだ。
あのときのように、彼女と交わった。
今は名前を覚えた。
彼女は妊娠した。
周りの者は気付かなかった。後半年で地球に帰る。
我々は無事任務を果たし、地球に帰った。英雄になっていた。二人の若い日本人が月の基地づくりに貢献して帰ってきた。
僕たちは結婚した。
子供が産まれる日になった。彼女は自分一人で取り上げると言った。ただ見ていてくれとも言った。
彼女はすべてを用意し、痛みに耐えて、子供を産んだ。男の子だった。僕が用意していた産湯に、彼女自身で産んだばかりの赤子を沈めた。
赤子が僕の方を向いた。
そして片目を開けて「ぼおや、ありがとよ、地球に生まれた」と言った。ドキッとした、耳にはおぎゃあと、産声が響いていた。
その子どもには「月人」と名づけた。一年経つと、もう歩くほど成長が早かった。しかもよくしゃべる。茸の図鑑が好きで、いつも眺めていた。小学校に入ったとき、住んでいた近くの丘で茸をさがしていた。白髪が生えてきた。勉強はよくできた。顔にしわがよってきた。医者の家内は若年老化現象と心配した。
八つのとき、月人の顔は「おじいさん」だった。そして、いなくなった。
我々は、また宇宙飛行士にもどった。
あのおじいさん、月にすんでいたのだ、地球に生まれたかったのだ。
そう思った。
今、月の都市で、一番の年寄りが私である。月の市長をやっている。家内は月の病院長である。
あのおじいさんは、地球のどこかで、茸に囲まれ、月にいる私たちを見ていることだろう。
おじいさん


