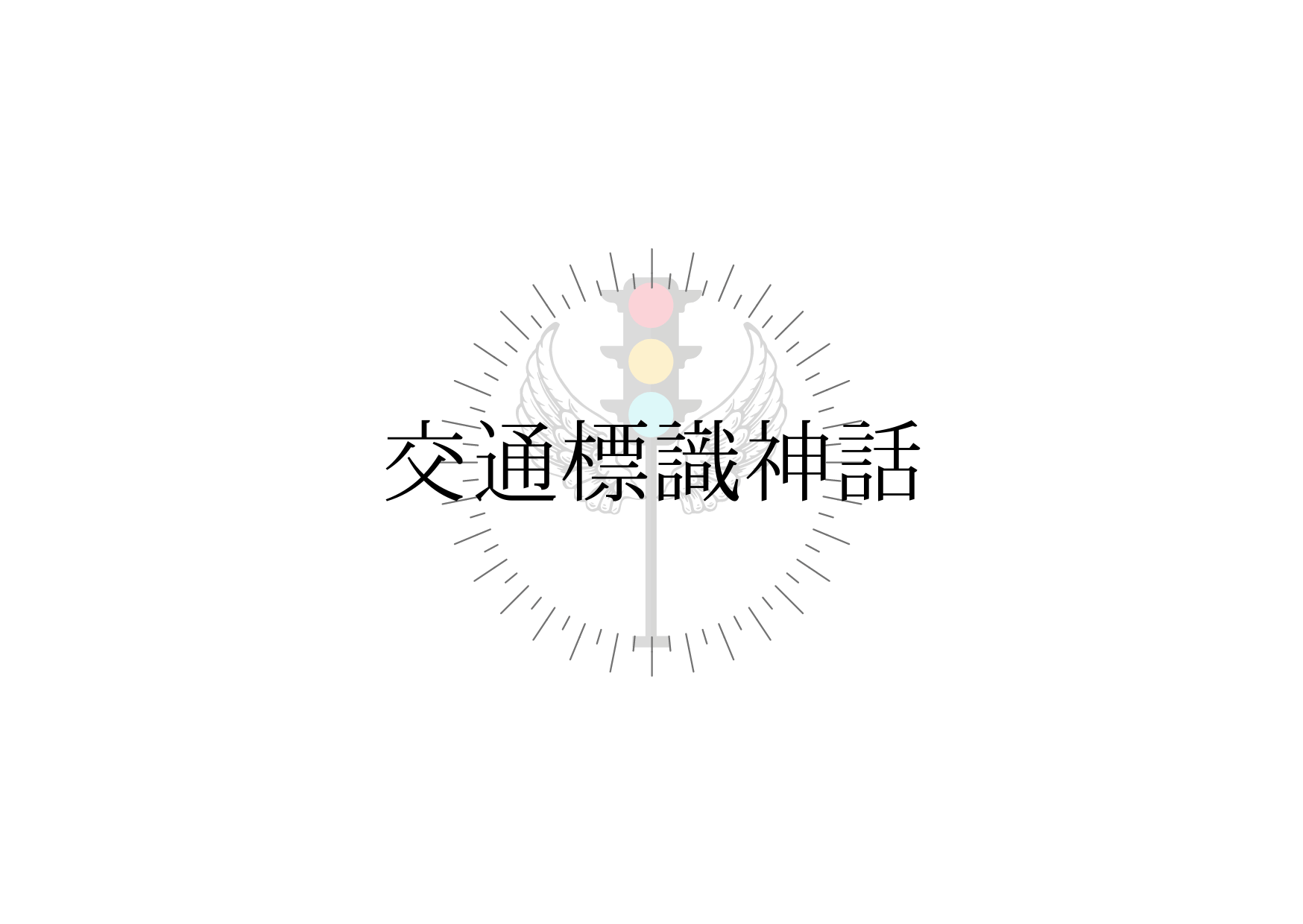
交通標識神話
時として世界が向ける冷たい瞳に、抵抗もできず溺れてしまうことがある。
どうしてふとした瞬間に、虚無に襲われるのだろう。
死にたくなってしまうのだろう。
そんなとりとめのないことを考えながら、ぼくは人皮の道路を歩いている。文字通り「人間の皮膚」を使った皮肉満点の道路だ。十七歳乙女通り。数年前自殺した女子高生の繊細な肌で作られたこの道路は、数多の人間が土足で歩くと忽ち消えない傷で雪白が埋め尽くされた。
僅か数メートルの短い道だが、今でも数本の花束と共に未完全犯罪は絶えない。道路になった「彼女」の上で夜な夜な自慰行為をする者、背徳的な性行為を楽しむカップル、それらを付け狙う通り魔たちの影。そのためか、長年設置されていたらしい公衆電話は匿名の祈りを聞き届ける郵便屋の役割を奪われ水族館になった。ボックスの中では天使の羽のような魚たちが悠々と泳ぎ回っている。現実世界のことなど少しも気にせず、こちらが死にたくなってしまうほど悠々と。まるでそれが彼女と世界への贖罪であるかのように。
「号外、号外、号外──」
頭上にアンドロイドのホログラムが現れた。毎朝七時のニュースピーク。子供の頃なら興味津々に聞き入っていたものだが、流石に毎日毎日「号外」と題されては興味も失せるというものだ。
ちなみに今日のものもいつも通り中身がなく、「祝!忘れられた時代の総理大臣遺骨発見!」というものだった。呆れるくらい無駄なもので溢れている……頭がおかしくなるほどに。
「だ、誰か、助けてください!」
成人男性のような叫び声が聞こえたのは斜め前方からだ。どうやら標識の罠に引っかかったらしい。見てみると「デジタル禁止」とかいうふざけたマークの棒の下から触手のように伸びた食肉植物が男性の足に噛みついていた。彼の手にはスマートフォン。身体は横転しているのにそれだけは大事そうに握っている。なるほど、デジタル禁止、そういうことか。悪趣味なものを作る人間もいるものだ。自分自身気をつけているのでそれらに引っかかったことはないけれど、たまにこういう人が居たりする。
ぼくは慎重に彼に歩み寄って手を貸した。うねる植物を力一杯足で踏んづけると、彼はびっくりしたような表情をして控えめに「ありがとうございます」と呟いた。
すぐさま聞こえたのは、下品な年増のねばねばした笑い声。
「あの子、変わってるわね」
何となく予想はしていた。
「ね。信じられないわ、わざわざあんな面倒なことをするなんて」
聞こえないふりをしようとしても嫌でも耳に入ってしまう。ぼくは口から出そうになった汚い言葉を何とか押し止め、青年に向き直った。
「そんなもの見ながらここ歩くなんてバカじゃないですか?」
被ったパーカーのフードが外れ、無造作に下ろした髪の毛が風に揺られた。
「あ、あの……えっと……」
見るからに年下相手に威圧されて萎縮しているのだろう、青年はしどろもどろになりながら携帯電話を真っ黒な鞄にそっと仕舞い込んだ。
「もしかしてこの道路通るの、初めてとかですか」
少しぶっきらぼうになってしまったことは反省している。
「……お恥ずかしながら、はい」
実は俺少し前まで引きこもりで、と青年は自らの身の上話を語り始めた。もう飽きたのかオバサン達のひそひそ話は聞こえないし、好奇の視線もそれほど感じない。民衆は驚くほど熱しやすく冷めやすいのだ。
涙ながらに語る彼の話をもっと聞いてあげたかったが、生憎ぼくには行かなければいけない所がある。ちょっと薄情だけどぼくは「それじゃあお気をつけて」とだけ伝えて踵を返した。引きこもり病に罹患してしまうのも無理はない、こんな世界なら。
去り際口をぽっかり開けていたのでやはり気になって振り返ると、名前も知らない男はぺこりとお辞儀をしてそそくさと立ち去った。若さに満ちた挙動不審。こんな表現が浮かんでしまうぼくもきっと病気なんだろう。きっとみんな何か病気を持っていると思う。そう考えれば人類悪など存在しないような、そんな純白な思いになった。
この通りにはカタルシスを求めて人々が乱立させた道路交通標識がある。止まれ、一方通行、この先地獄。原色だけに留まらない無秩序なアート作品と化したそれらは、一本一本にかつて市民戦争で使われた機関銃の核の素材が組み込まれている。過去の写真集で見た美しい国はどこへやら、ここはカオスに満ち溢れた呪われた場所だ。
それから、道路の汚れた部分はもうすぐ舗装されるらしい。当然のようにまた自殺した同年代の子が使われるのだろうけれど。心が痛くないと言えば嘘になる。ぼくだってちゃんと女の子で、一応高校生だから。
「やあ、今日も来てくれたんだね」
ぼんやり青空を見上げて歩いていれば目的地に辿り着いた。純黒のペストマスク越しに胡散臭い笑顔を浮かべているのが感じられる。暇だったから、とぼくはそれだけ呟いて、早く中に入れてよと怪人を急かす。
「暇って……学校に行っていないだけだろう。もう、折角外で待っててあげたのに」
呆れ口調になりながらも小さなベルのついた扉を開けてくれる。ここは街角にひっそりと佇む映画館、いや雑貨店、いや喫茶店?質屋?人形屋?――とにかく、何でも揃っている宝物館だ。建物の外観は深海の色をしていて、外に面したウィンドウケースには「人魚姫」という、縹色の袴を着た少女人形がある。閉じられた瞼の上を飾る長い睫毛が妖艶さを放つ。いつもは二体設置されているのだが、今日は一体しか居ないようだ。
中に入ると既に準備は整えられていた。年季の入った自動映写機の光がスクリーンを照らしている。いつも通り、座席は一つ。
お客さんがいないというのももちろんあるけれど、父親のように優しい怪人──店長の好意だ。
「今日は何を見せてくれるの?」
ぼくはそう言って精密にペイントされた星空の瓦礫に腰掛けた。ぼくが生まれるずっと前に起こった大地震のとき、彼が被災地から持ち帰ったものだという。今日の装飾は全体的に廃墟のようだ。
「今日は悲……おっと、ちょっと待ってくれ。薬屋だ」
ゆったりとした足取りで店長は再び扉を開けた。ぼくは後ろを振り返って、今日はどんな人物がやって来たのか見た。毎日毎日違う人が来るから、宅配員観察はもはやぼくの一種の娯楽と化している。
「本日は贖宥状一枚をお支払いクダサイ」
薬屋は液晶画面頭の砂漠系民族衣装だった。ロボットみたいな声をしているが、どうやらちゃんと人間らしいことは何とか察せた。チャンネルで表情を変えているらしく、自分の手で画面横にあるボタンを操作しているのが面白い。詩から飛び出してきたような倒錯だ。ぼくはちょっと苦笑いを浮かべた。
「……君たちというのはまた、奇特な格好をしているものだね。昨日の宅配人の頭はブラウン管、一昨日は活版印刷機だったよ。一体それはどんなファッションなんだい?」
奇特という言葉などこの時代には似合わないというのに、店長はおかしなことを言うものだ。ぼくから見ても端から見ても、彼の方があの薬屋よりも変人に見える。
「そんなソンナ、大層なモノでは。歴史の変遷を考えれば、当然のことデスヨ」
チャンネルが切り替えられ、素朴に笑っている画面が映し出される。レモン色の背景、ニコちゃんマーク。歴史の変遷、というところに疑問を感じたが、店長は「ああ……」と小さく頷いただけだった。
「……ま、いいよ。はい、贖宥状一枚ね。随分と格安じゃないか今日は」
店長は溜息を吐きながら薬屋から小さな鞄を受け取り、中身を覗く。
「品物もちゃんと入っているし」
「アア、それはデスね、今日は『彼女』の赤ん坊が解禁されるノデ、ワタクシ共皆気分が良いカラ、なんデス」
何と気まぐれなんだろう。宅配人の顔がピエロの仮面のような表情に変わった。彼の上司に怒られたりはしないんだろうか。
「彼女の赤ん坊……ああ、そういうことか。わざわざ生々しい言語表現を使うのは辞めてくれないか。気分が悪くなるよ」
「アア、ああ、スミマセン。ワタクシの会社の人間、皆そう言っておりマスので……とにかく、そういうコトです。今日、その『道路』に」
「……それで贖宥状、ということか。全く低俗だね君たちは」
「ハハ、それほどデモ」
今度は目がハートになった惚れ顔。
「褒めたつもりは無かったんだが……じゃ、ご苦労様。交通標識に気をつけてね」
少し不機嫌になった店長がそそくさと会計を済ませ、扉をパタリと閉めた。それを閉じてしまえば、もう薬屋の姿は見えない。フラミンゴのように去って行く姿を想像した。数多の道路標識に目眩を起こしていないことを密かに祈る。
「ごめんね、待たせてしまった」
申し訳なさそうな声色。別にいいよとぼくはスクリーンの方に向き直って、両足をぷらぷらと揺らした。暗くてよく見えないが、どうやら床も星空に霞がかった柄になっている。
店長は奥に入って鞄から薬瓶を取り出し、棚に並べた。今日は何の薬だろう。透明色とレモン色の液体は、おとぎ話の毒薬のような色のものばかりが陳列されている中では異色だ。
「……今はもう無くなってしまったけれど、東京タワーがこの近くにあったことは覚えているかい」
煌めく液体状の幸福を慰めながら店長が言った。まるで何かを思い出したような口ぶりだった。
「え……うん。観光地だったんでしょ」
教科書で習ったことがあるのと、ぼくが小さい頃母親に連れていってもらったという記憶があるからその存在は知らない訳もない。
それに、無くなってしまったのはほんの数年前のことだ。
「そう。それは過去には東京のシンボルのようなものだったんだ。けれど、その最大の電波塔の素材に何が含まれていたか知っているかな」
「知らない」
ぼくが即答すると、店長はペストマスクの位置を直しながらぼくの隣に腰掛けた。
「米軍の戦車だよ」
「……戦車」
彼が纏っている漆黒のコートが更に闇色に澱んで見えた。米軍の、戦車。今はどんな国になっているか分からないけれど、勉強嫌いのぼくにだって彼が言わんとしている意味は言われなくとも分かった、米軍という言葉の示す隠された意味も分かった。
「……何で今、そんな話をするの?」
理解はできるけれど、彼の真意は謎だった。けれどまあいつものように与太話に過ぎないのだろう、軽い気持ちでぼくは聞いた。
「君はあの外に溢れた交通標識というものが沈黙の暴力であることも、私達のほとんどがそれに気づいていないことも、それが植えられた道路の秘密も知っているだろう?……なに、ちょっと豆知識を言っただけだよ。そんな目で見ないでくれ」
籠もった笑い声が響いた。自分が神妙な顔になっていたことに気づいて、ぼくは思わず顔にぺたぺたと触れる。意思とは関係なしに動いてしまうこの筋肉、本当に厄介だ。
「もう。何か危ないことがあるのかと思った」
返答に困ったぼくは瓦礫のとなりにちょこんと置いてあるアンティーク調のテーブルに手を伸ばし、ティーカップをおもむろに取った。来る直前から用意してくれていたのだろう、まだ幾分か温かい。ぼくが熱すぎる紅茶は好きではないことを知っての ことだ。
沈黙が訪れる。店長は紅茶を飲むぼくをしばらく見つめた後、「じゃあ、映画を見ようか」と立ち上がった。良かった、彼がこんな風に隣に座って語りかけてくることはそれほど多くないから。カラスのような仮面の奥でどんな顔をしているのか、そして同様にぼくはそんな彼に対してどんな表情をしていいのか全く見当もつかない。
「月が失声症に罹患しているうちに、太陽の肉声を暴こう」
カラカラカラ。店長が映写機のスイッチを入れると、記憶の糸車が回転し始めた。
「うん、楽しみ」
店長の謎めいた言葉遣いも好きだ。
「もうほとんど作られていないからね」
「勿体ないよね。店長も何か作ってよ」
「いや……私にはそういった才能が無いからねえ。無理な相談だなあ」
残念そうな声だった。本当にそれを悔やんでいるのかと思うほど。
「じゃあ、再生するよ」
「うん」
最初に流れ出したのは、無秩序に編まれた写真たち。
これは、何年前の映画だろうか。いつも見ているものとは大分古いような気がする。色彩こそついているものの、スクリーンに映し出された若い男女の映像には随分粗が見えた。彼らは何をしているのだろう、身の丈分の墓石をリュックサックのように背負いながら荒野を歩いている。二人の身体にスポットが当てられ、右に進み続けている光景しか今のところ映らないために周囲の風景は分からない。
「……古い映画だね」
ぼくは腕を組みながらそう言った。二人とも十七歳前後だろうか、学生服を身に纏って顔にキョンシーのように黄色と紫色の混じった張り紙をつけている。頭には明らかにCGを施した天使の輪。ぽっくり下駄を履いた足が痛々しく青痣を飼っていた。
「なに、ほんの十数年前の青春群像さ」
「ふうん……」
「無名の映画監督の遺作だよ。といっても、彼はまだ存命人物だけれどね」
「そうなの?何て名前の人?」
キャラクターたちは最低限の言葉しか交わさず、雨音のようなピアノの旋律のみが世界を奏でていた。
「……何だったかな。ごめん、後で調べておくよ」
彼はパラパラと薄い冊子をめくっている。映画のストーリーだろうか。ぼくも見たい。軽く身を乗り出して覗いてみたが、どうやら知らない言語で書かれているらしく何て書いてあるかは全く読めない。カタカナを変形させたような文字の形なのに、なぜか読めない未知の言語だった。
「……何かわざとらしい……」
上映時間中にそれ以上喋り続けることは野暮だ。ぼくは店長の言葉に了解したフリをして、彼らの行く末を見守った。
けれどもどれだけ時間が進んでも、二人の若者は歩行だけを続けていた。背景だけが荒野から宇宙へ、宇宙から都会へ、都会から海辺へ、海辺から廃墟へ、廃墟から真っ白で巨大な実験施設へと進むだけだった。だんだんと映像に退屈してお腹さえ鳴り出すぼくとは裏腹に、店長は懐かしいものを見るような目で映像を眺め続けている。
今日のはつまらないな、と心の中で嘆息しながらも、かといってここから出て行く訳にもいかないので、スクリーンの方を見ているふりをしつつ僅かに右へ目をやって、窓の外の風景を観察することにした。一応防犯のためにマジックミラーになっているから、外からこちらの様子が見えることはない。
人類進化の過程の絵、猿人からホモサピエンスまでを表した図が真実だとしたら、ぼくたちの次には何が描かれるのだろうか。それはきっと、見たこともないような偶然的なものではなく、今世界にありふれたようなものがパッチワークみたいに結合して完成するのだと思う。
太陽が出ているのに外はいつの間にか雨が降り始めていた。狐の嫁入りだ。しとしと、しとしと。平日の昼間だから人通りはそれほど多くない。十七歳乙女通りをスーツで闊歩するサラリーマンもいれば、向かいの賭博場のレンガ造りの壁に寄りかかるヘッドフォンの少年もいる。みすぼらしい格好をした浮浪者だって、人の波の中に溶け込んでいる。そこに標識の罠にかかる人間がいるのも日常風景だ。
いつもよりも緩い顔をした人間が多いのは、やはり彼女の第二号が近くに生まれるからだろうか。『十五歳ばけもの通り』。魔女裁判みたいだな、とツッコミを入れたくなる。
通っていく人々は一瞬しか見えない。ぼくはこの先の人生において一度も彼らに会うことはないだろう。命を確認した刹那、まるで幻であったかのように過ぎ去る影。そう思うと何だかぼくが生きている意味も薄れていくような気がした。いや、元々そんなものは無いとは思っているけれど。
ぼやぼや考え事をしていたら、どうやら眠りに落ちたようだった。
慌てて目を覚ますとまだ映画は終わっていなかった。やっちまった、とおそるおそる限界まで左に眼球を動かして店長を見上げる。
「……」
ぼくは控えめに身体を寄せた。何となく起きてるってことが伝わればいいかなという単純な思いだ。これくらいで怒るって訳でもないだろうけれど、店長には失礼なことはしたくないのだ。
酷使した眼球が疲れ、自然と目をギュッと瞑る。その瞬間机にミネラルウォーターが置かれるのが見えた。……どうやら悟られてはいないらしい。ぼくはそっと胸を撫で下ろした。
こうなってしまった以上何か見ているフリをしなくては、と再び視線を戻した。すると突如飛び込んできたのは男女がお互いの心臓部を刺し合っている場面だった。重そうに背負っていた墓石は彼らの背景に置かれ、まるでここが死に場所だと決心しているかのように見えた。寂寥の周波数が二人の左腕についている心電図の流線型で語られる。
寂寥──簡単に言うけれど、それは一瞬画面を見ただけでも分かった。二人が死を決めた場所、それは。
「深海だね」
吐息を込めた声で、彼が口を開いた。美しい瑠璃色に闇色を刺した絶望。バイオリンとピアノを使った悲しい音色だけが人物の感情をここまで表現できるのは、純粋に物凄く尊いことだと思った。今こんな繊細な感性を持っている人間は、一体どれくらい居るんだろう。
ああ、うん、そうだね。と相槌を打とうとして、「あ、う」なんて喃語みたいになってしまう。眠気の抜けない頭だ。
「め、メタファーじゃないの?」
「……どちらの意味で取っても正解だよ」
「そ、そっか」何とか話を合わせようと無理矢理言葉を絞り出した。自分の良心が少しだけ痛む。
「台詞の少ない映画というのは当時には珍しかったんだよ、人間は言葉を喋るのが当然であり、それが人間を人間たらしめている一要素だからだ。だけどこの二人はほとんど喋らない。どこか遠い場所に歩き続けるのが正しいことだと思っている。言葉を交わすことがないから、それが正しいことなのか間違っていることなのか分からない。彼らには表情も無いことだしね、お互いが正反対のことを思っていたとしても、それを表現する術を持たない。こんなに報われない沈黙のフィクションも私達のような変わり者には愛されるけれど、やはり今でも評価は芳しくないようだ、寂しいことにね」
彼がペラペラと感想を語る間、ぼくは耳を遮蔽させてただ大きな身体に寄りかかっていた。「私たちのような変わり者」となぜかぼくまで変人のカテゴリーに入れられてしまったのはちょっと心外だけど、黙っておくことにした。彼らの死に際を見ていたらまた眠くなってきてしまったのだ。知らぬ間に追体験、感情移入をしていたのかもしれない。
「よく眠れたかい?」
最初ぼくはこの言葉を疑問には思わなかった。
「うーん……まだ……」
うーんうーん、まあ、だいぶ眠れたよ。聞き心地の良い低温の声に意識を預けて夢うつつ。
透明のベールを通した淡い太陽光に包まれているような微睡みの中で、店長が何と言ったのかを飲み込めないままでいた。
「随分意識を手放していたようだけど」
そこでやっと我に返った。
「えっ」
やっぱりバレてたか!ぼくはどきりと跳ね上がる心臓を押さえ、平静を保つために笑顔を作ってみせた。
ヘラッ……という擬音が付きそうな下手さだ。
「上映中に眠ってしまうなんて珍しいね。今までどんな作品にも心を傾けて見ていたのに」
「ご、ごめんなさい……気づいたら、うとうとしてて……」
「はは、構わないよ。嫌いなものの一つや二つ、どうってことはない」
「き、嫌いではなかったんだけど!」
「分かるよ。意味が分からないってところかな」
「……うん。ぼく、頭悪いから……」
「そこまで真剣に見てくれていることに感謝だね」
エンドロールが流れていく。シンプルな黒地に明朝体で刻まれた白色の名前たち。普段見るものよりも大分少ない数だ。おそらく低予算だったのだろうと思う。だけど感触は決して悪いという訳ではなかった。描写は独特で刺激されるし、夜だったらもっと集中して見れたと思う。まあ、寝落ちした人間が言っていい言葉じゃないんだけど……。
「彼らはね、自分自身の秘密に気づいてしまったんだよ。自分が実は作り物だったという事実に」
「作り物?」
それは序盤に見ていた冊子に載っていた説明だろうか。
「彼らは自身のルーツを知らなかった。だから自分たちが奇跡の存在だと信じていたんだ。世界創造神話のように、自分は温かな親の胎内から産み落とされたものだと」
「……本当は違ったの?」
「それは、そうさ」
初めて見た、と思う。店長がこんな風に饒舌な姿は。今日はいつもと何かが違う。
やはり、新しい道路のことに関係しているのだろうか。いやでも、彼はそんな世俗的なことを気にする性格だっただろうか。
ぼくと彼の間に沈黙が流れる。涼風の通る隙間なんてないはずなのに、今だけこの空間は温かく、同時に冷たくも感じた。
「……ごめんね。今日はいつもより無駄な事ばかり喋ってしまうね。よし、昼ごはんにしようか」
「……うん」
釈然としないままぼくは返事をした。すると彼は今までのことが幻だったかのように笑顔を浮かべ、何が食べたい?と立ち上がった。それ以上踏み込んではいけないような予感がしたので、ぼくも笑顔を作って「この前見た映画に出てきたあの温かそうなやつがいい!」と答えた。
「映画で見た温かそうなやつ……って、もしかして和食のこと?」
「そうそう、それ。ぼく、食べたことないし生で見たこともないんだ」
普段食べるものは缶詰とか乾燥したものばかりだ。大人たちはよく飽きないものだと思う、決して美味しくない訳ではないけれど、何十年も食べ続けていたら飽きて気が狂ってしまう。
「え、うーん……それは、残念だけど君もご存知の通り無理かな……」
この目の前のおじさん、見た目は異界の怪人そのものなのに、魔法は何一つ使えない。
「だって……そもそもそんなもの作れるはずがないからなぁ……他のものにしてくれるかい?」
もう食べることができないものくらい、作り出してくれたっていいのに。一抹の不満を旨にぼくは分かったと素直に頷いた。冷蔵庫に向かう彼の後を追って立ち上がる。
その瞬間、窓の外を見ると交通標識が一本増えていることに気がついた。
マークはよく見えないが、どうやら人が人の首を何かで切っているように見える。
「ねえ店長、あれ……」
次に視界に飛び込んできたものを説明しようとしたとき、彼は何かに気づいたようにぼくに駆け寄って背後から両手で視界を覆った。
「……見てはいけない」
ヒュッと呼吸の尻尾が氷柱のように壊れていくのを感じた。
別にいい、どうせあんなもの見慣れているのだから──。
いや、そう言うことができたら、どんなに良かっただろう。
「……今」
「……っ」
これが現実だとは、どうか言わないでほしい。
外から咆哮と、悲鳴が聞こえていた。
魔法など存在しない。
あるのはただ、残酷な残酷な。
『世界は何でできていると思う?』
つい先日、店長に紹介してもらった本の一節に、そんな台詞があったのを思い出した。
――花が咲く。
空全体を覆うような、巨大な新生物の花が咲く。
「な、に」
そんな風に、見えた。
「……目を開けるな。大丈夫、何も知らないままでいい」
そう言われ咄嗟に目を瞑る。言えるはずもなかった。いや、口に出すのさえも怖かった。
――まるで子供がいたずらに紙を破くように、外の風景が剥がれ落とされ始めていたことなんて。
交通標識神話

