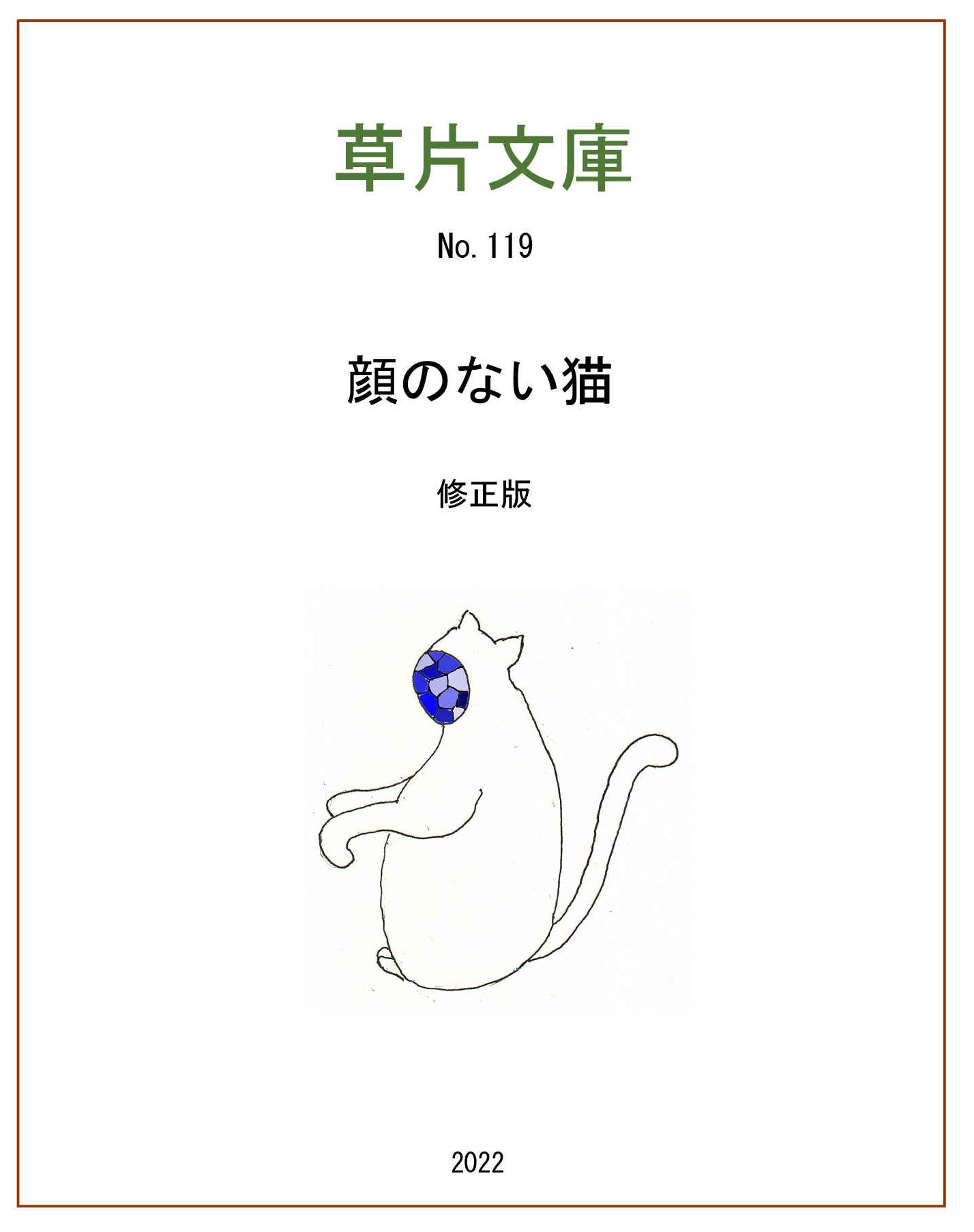
顔のない猫
奇妙な街の物語。縦書きでお読みください。
この町に越してきて一週間ほどになる。ともかく、マンションの林立するコンクリートの町にほとほと愛想を尽かして、逃げてきたようなものだ。なぜって、猫を飼ってはいけない、外に出しちゃいけない、そういったマンションの規則が、あまりにも生き物に冷たく感じられたからだ。規則を作った人たちは、猫が嫌いな人ばかりじゃない。好きなのだが、外に出すと車に轢かれてはかわいそうだという気持ちが強いからでもある。それはわかる、生き物は死ぬ、自動車に轢かれたら痛いだろう、そう思うのも仕方がない。だけど考えてもごらん、自分の目に入れても痛くない子供をマンションの一室に一生涯閉じこめておくのかい。子供はそのように育てられれば、一生涯そうだって、不便さを感じないで、幸せすら感じるかもしれない。比較するものがなければその中で幸せを感じることができるのが人間だ。でもそれでいいのかい。
猫だってそうだ。猫と人間は違うなんていうのは思い上がりもはなはだしい。自分の好きなように生きて死んでいくならば、それは自然である。それでいい。だが、生れ落ちることは自由ではない。生れ落ちた環境は人と同じように、みなちがう。生まれた兄弟は名に不自由もない家に引き取られ、自分と同じようにぬくぬく自由にせいかつするのか、兄弟ごと河原にすてられるか。末っ子だからといって、自分だけ捨てられるか。野良猫だった親から生まれ、生れ落ちたそのときから、将来は餓えにおびえて暮らす運命か。
まあ、考えてみれば、人間だって同じようなものかもしれない。ペットとして生きるようになった猫は、おのずから人間の制約を受けることを覚悟しているのだろうが、飼われた人間の感じ方一つで、違うかたちの猫世をおくることになる。
うちの猫はマンションのゴミ出し場で、カラスたちと一緒に、ゴミ袋に顔を突っ込んでいた。ベージュ、いや灰色の子猫である。生まれてまだ三ヶ月もたたなかっただろう。今時、野良猫とは珍しい。子供なのに自分で生きるためのことは何でもしてきたような強い猫なわけだ。
ところが、僕が、というか、人間が見ると、丸っこい顔に、黒くて大きな目、髭がぴょことはえて、耳がちょっととがっているが、柔らかい毛が生えていて、鼻がピンクで、口を開けるとまだ小さいが、牙さえあるのに、みゃ、と鳴くと、かわいいなと、抱き上げたくなる、そういった猫だった。猫はみなそうだよ、といわれると、その通りだが。
それで、そうっと、自分のマンションの一室に招待したってわけだ。ミルクがあったので、提供すると、もうそれは大喜びで、ぴちゃぴちゃ飲み干した。そして大きなあくびをすると、台所の隅っこで、丸くなってしまった。
長い尾で鼻をかくし、たまに位置をかえて、月があがる頃になって、やっと目を覚ました。
もう、僕の顔を見ると、食べ物をくれる友人だということにしたらしく、みゅみゅとなくので、寝ている間に買ってきた、子猫のための缶づめというのを開けてやると、うまうまうま、とそんな鳴き声をあげて、あっという間に食べてしまった。
もっとくれという。空腹の人間にいきなり、たくさんのものを食べさせては体に悪いということを知っていたので、ミルクをちょっとやって、終わりにした。
もうくれないんか、という顔が、いきなり、緊張して、どこだどこだという顔になった。あ、そうだ、トイレの用意をしていないと思った僕は、ここで今日はがまんをしてくれよな、と、空き箱があったので、底に新聞紙を敷いてやった。
ほら、というと、ぴょんと飛び上がって、中に入って、しょーっとおしっこをした。人間と同じだね、気持ちいい、って、顔してたよ。
その夜はそれで終わったんだが、次の朝、ご飯の用意をして、もう一度箱の中に新しい新聞紙を敷いて仕事にでかけたんだ。もちろん、水とさらに猫缶を開けておいておいた。
今日猫トイレを買って帰るからな、と思って、仕事場に出かけた。漫画家の描いたものを仕上げる仕事だ。何人もの仲間が一生懸命、黒く塗ったり、線を書き直したり、背景を書いたりしている。そいつら誰もが将来自分のマンガの本を出すことを夢見ているんだ。僕とは違う。僕は絵を描きたかった。だがイラストレーターになった、そっちのほうが、めんどうじゃないと思ったからだが、とんでもない、一本の線を引くのに、見てもらえるようになるのに三年もかかった。イラストをかけるようになる前にドロップアウトをして、マンガ工房に派遣会社から派遣される身になった。それでも、家賃と食べるものを払う収入にはめぐまれていたんだ。
ともかく、時間が来ると、さっと引き上げるのは僕一人だ。それでも文句は言われない。やることは人並み以上の出来でやっている。イラストをしっかり勉強したことからそうなのだ。
それで、猫のトイレを買って、中に入れる水に流せる紙でできた砂のようなものを買って、さらに、子猫の好きそうな缶づめをいくつか買うと、なんだかうきうきして、マンションに帰った。同居人が居るということは、やっぱり気持ちに平和をもたらす。だからなんだな、喧嘩してるくせに夫婦のままのがたくさんいる。
ままよ、ドアを開けて部屋の中にはいると、まだ名前を付けていない、子猫ちゃんに、声をかけた。にゃーいるか、とこっちが猫なきをしちまったら、「ああー」と人の声で返事をしやがった。おとなびたやろうだ。
おとなしくしていたらしい、キッチンの、空の皿のところでおちゃんこしている。
「腹減っただろう」と、こっちが日本語でいったら、「にゃー」と猫の声で返事をした。
ともかく、トイレを設置する前に、猫缶を皿に入れてやって、水を新しくしてやった。
ベージュ色の子猫は、うまうまうまと餌を食べた。そのあと、買ってきたプラスチックのタライのようなトイレ場にはいると、座ってショート音を立てておしっこをした。
おや、こいつは雄か、雌か、玉がついているが、小さいというより、半かけだ。半分だけの玉がついている。
まあ、まだ未熟な生まれる前の赤ん坊は、睾丸というのは体の中にあって、生まれて少したつと下に降りてくる。たまには半分しか降りない奴も居るんだろう。
まだおしっこをしている。なんて名前にしてやろう。拾ったときゴミを漁っていたから、ルンペンか、ちょっとかわいそうか、玉が半分しか降りていないから、はんたま、はんぎょく、ちょっといかんな、まあ、しばらく、猫でいいか。
トイレが終わると、顔を洗っている。なんだ、顔を手でこすると、ベージュ色がうすくなるじゃないか。顔がまだらになってきた。
まてよ、と思い、風呂場につれていって、洗面器に風呂の湯をくむと、すこしは暖かい水に、猫をざぶんとつけて、石鹸をつけてこすった。あわだらけになって、猫はいやにゃことするなと手に噛み付いたりしていたが、ともかく洗っちまった。
なんと、乾くと薄汚れたベージュの猫が、まっ白になりやがった。白だったんだ。
それじゃ、名前を白とするか。
いや、ありきたりだ。ルンペンの白だからルンペンブラン。どうだ。なんだかフランス人のような、有名な山のような響きがある。
ルンペンブランと呼んでみた。振り向きもしない。ちょっと長いな。やっぱり、ルンペンか、その方が呼びやすい。ルンペンとはペンペン草の生えている草地で、ルンルン気分で星を見上げて寝る人のことか。まあいいや、おいルンペン、にゃんだ、という共同生活が始まった。
あっという間に白いルンペンはいっぱしの雄猫になった。真っ白な猫っていうのは、雄であっても、どちらかというとほっそり系で、ちょっと狐に似たような顔になるものだ。ところが、ルンペンの奴、どこかのおっさんのようにでっぷりと太って、細い尾っぽをアンバランスに揺らしながら、飯くれとやってくる。ただ、玉は片方おりてこなかったようで、左だけしか膨らんでない。身体が少しばかり左にかしいでいる。そんなに重いわけはないが。
実は、このでぶった猫は、僕に幸運をもたらしたのだ。まだこんなデブになる前、きっと六ヶ月までのあいだだから、三ヶ月頃に描いた、僕のルンペンの絵が、有名になっちゃったんだ。こいつは片足をあげる、あの雄猫がするおしっこのポーズもするし、おとなしげな雌猫がするお尻を下にくっつけそうにしてしゃーっともするし、公園に連れて行けば、おしりを持ち上げて、木にとまっていたカミキリムシに向かっておしっこをひっかけたり、おちゃんこ座りをして、前に向かって放尿をしたり、マンションの木の上から、通りかかった自転車で道を通ったお兄ちゃんにおしっこをひっかけた。お兄ちゃんは蝉にかけられたのだと思ったようだ。そのままいっちまった。よかた。
そういった、ルンペンの放尿スタイルを絵に描いて、ブログに乗せたのだ。そうしたら、出版社から、それに色をつけて、大人用の絵本にしないかと声がかかった。
サールって言う人を知っているかい。フランスの画家で、サールの猫という絵本がある。子供だって面白がるが、大人たちがほしくなるいい絵本だ。そんな本にしたいと、編集者がいってきた。
それで、もちろん、僕は大喜びだよ、ルンペンにたくさんおしっこをさせて、猫のルンペン、おしっこですっきりっていう絵本をつくったわけだ。「ルンペンの楽しみ」といいう題の絵本だ。そうしたら、大売れに売れて、数カ国語に訳されて出版された。たったその一冊の絵で、東京から離れれば、一戸建ての家が帰るほどのお金をもらったんだ。
ルンペンが来てまだ一年にならない。もうマンション組合では猫を飼うことにクレームを付ける人が現れた。このマンションは猫や小さな犬を飼うことは禁止していない。しかし、うるさい人も多いので、そうっとみな飼っている。このルンペンはとてもひとなつっこい、というか、人が大好きで、たまにベランダから抜け出し、マンションの周りで、住人の足にこすりついたりする。好きな人は大喜び、一方で、誰、この汚いデブ猫飼っているの、と金切り声をあげる人もいる。ということで、その女性が管理組合の役員をやっていたことから、外にだすなと言ってきた。
すみませんと謝るだけだが、ルンペンがある日、引っ越そうといったのだ。言ったというのは、床の上に寝っ転がると、ふーとため息をついて、にょこかにいきたい、と言いおった。僕ももっと、自由のある家がほしいと思っていたことから、んだんだ、と相づちを打った。
それで、ネットで家探しをやったわけだ、電車で仕事場まで、一時間判くらいかかってもいい。もし、もっと絵本を描くことができれば、仕事ともやめてもいい。などと考えながら見ていくと、あった、地方まで行かない、近郊というほど近くないところに、四十年前は新しい住宅地だった、以外と整った、住居が売りにだされていた。中にコンビニもあれば、郵便局もある。駅から歩いて十分だ。
木造、二階建て、4DK、持ち主は夫婦そろって、介護マンションにいったとある。五十坪の土地だから庭だってある。生け垣の塀だ。さっそく見に行くと、駅前の不動産屋のおっさんが、いいところだよここは、とのんびりと、部屋の鉢の植木に水をやっていた。
それで買いますというと、見てからにしなよ、実ははいっても一年くらいで出る人が多いんだ。周りの人はとてもいいし、環境もいいのにね、よくわからないんだ。ともかく案内するから、よく見てからにしなよ、とまた言った。
おやじはかばんをもった。店の奥に「お客さん案内するからたのむぞ」と声をかけると、外から猫がとびこんできて、家の中にはいっていった。長い尾っぽをゆらして、大きな袋をつり下げている。雄だ。
おっさんは歩きながら、道沿いの、電気屋、八百屋、酒屋、床屋、クリーニング屋のことを教えてくれた、というより、噂話をずーっとしていた。団地には入る角に、家の案内図があった。反対側のはずれに小さな公園がある。その近くに僕の家はあった。田中とかいてある。元の持ち主だ。
家は昔の木でできた文化住宅である。中もきれいに使ってあって、庭に面して縁側まである。両隣は、僕より一回り年上の夫婦と子供が住んでいて、後ろも同じような家族構成である。
「猫の嫌いな人が居ますか」
と聞いてみた。
「そんなのいるわきゃないよ、あんた、この団地の名前見なかったのかい、あの看板にかいてあったろ」
迂闊にも、買う家に気をとられていて、団地の名前を見落とした。というよりすっかり忘れていた。
「寝子団地、っていうんだよ」と不動産屋はいった。「ネコの団地ですか」「いや寝る子だけどね、猫と同じだろ」
確かに名前はそうだが。と考えていると、おっさんは「ほんとは、猫団地にしたかったんだそうだ、開発した会社の社長が猫好きで、猫が好きな奴にしか売らないと、がんばったようだが、社員は売らなきゃいけない、犬の好きな人もいる、名前が猫ではまずいと、進言したんだよ、そんでね、猫は寝てばっかだし、子供も寝ているのはかわいいし、そんじゃ、寝子ならいいいと、まあ、妥協の産物だよな」
さらに、
「そんなことでさ、やっぱり、猫好きが集まっちまってな、というか、社長が猫好きにしか家を売らなくてな、嫌いな奴はいないさ、ただ犬もいるよ、動物好きは、犬猫関係なくみな好きなものさ、それで困ったことにな、ライオンを飼いたいというのがいてな、あいつらも猫科だからいいじゃないかという人もかなりいたけどな、やっぱり逃げたら怖いというのも多くてな」
「その人はライオンは飼えなかったわけですか」
「ばかいっちゃいけない、みんな人間より他の動物の方が好きだって輩ばかりだよ、その人いるよ、ただ、ちょっとはずれの方にな、自分の家を庭ごと大きな檻で囲っちまってな、ライオンが外に出られないようにしたんだ。たまにライオンが庭で寝そべっているよ、飼い主も一緒にな。いつか見にいくがいいよ、団地の南の方だよ」
こりゃ、いい団地を見つけたものだと、すぐに手を打って買っちまったよ。二千万だ。都内じゃそんな値段じゃ手には入らない。
それで、ルンペンと数えることのできるほどの自分の持ち物をもって、引っ越してきたってわけだ。ルンペンのやつ、おおはしゃぎだ。
今、ルンペンは一日の大半を寝子団地をうろつくことで費やしている。僕なんかよりずーっと団地の中のことをよく知っているに違いない。友達がたくさんできているのだろう。
仕事は遠くなったので、ちょっと大変だが、漫画家の補助の仕事は今月で終わりにして、ネットでできる仕事を回してもらうように、派遣会社に頼んである。所属している派遣会社は、若いイラストレーターや漫画家が登録しており、派遣先の紹介だけではなく、ちょっとしたイラストや、宣伝の絵などの注文も回してもらえる。
一冊売れる本を出したことから、その会社の派遣社員というより、所属のイラストレーターという立場にしてくれるということだ。
まだ越してから一回目の日曜日の朝のことだった。ルンペンの奴、朝食もそこそこに飛び出していった。ガラス戸から庭を見ると、左隣の家との塀に、茶虎の猫がオケツをこっちに向けてすわっている。右隣の塀から飛び降りて、道を走っていった白黒の猫を見た。猫が自由に歩き回っている団地、寝子団地いいじゃないか。
こりゃ、散歩に行ってみなければと、食事をしてから、散歩にでた。この家に住むようになり、初めての団地の中の散歩だ。仕事が、通いでなくなれば、毎日するようになるだろう。天気はよい、まずはすぐ近くの小さな公園に行った。
小さいけれど、公園の真ん中には池があり、蓮が植わっている。その周りにベンチもおいてある。雑木林もあって、中に道が通っている。そちらにいってみると、程々に木が植わっていて、歩いていると気持ちがいい。古くなった木を切ったものか、ところどころに切り株があり、そこに腰掛けて一休みもできる。草の生えている足下に古いドングリが落ちている。植わっている木は椎や樫の木のようだ。。
雑木林の中のちょっと広いところにでた。その先に小高くなったところがある。そこに、煉瓦でふさがれた穴がある。防空壕でもあったのだろうか。周りの木は切られて、切り株がいくつもある。
穴の近くの切り株の上に、猫が乗っている。しかも二匹だ。さすが猫団地、猫のために切り株を作ったように見える。
近づいていくと、姿がはっきりした。なんだ、ルンペンが茶色の猫と一緒にいるじゃないか。こんなところまで遊びに来てやがる。
「ルンペン」と呼ぶと、こっちを振り返って、にゃんだきたんか、という顔をしている。隣の茶虎の猫は振り向こうとしない。茶色の耳がピント立って後ろを向いている。
あれ、おかしいな、前足はこっちにある、尾っぽがないじゃないか。
近づいてみると、茶虎の猫はぴょんと切り株から飛び降りると、林の中にはいっていく。ルンペンも追いかけた。
まあ、猫の遊びのじゃまをしちゃあいけないと思って、自分は今来たところを引き返し、池のほとりのベンチにこしかけた。
石垣で作られた池の縁には、草が伸び伸びと生え、水の中を覗くと、浅い水底に名前の知らないちっこい虫が、しょろしょろ這っていた。
もう少し時間がたつと、団地の人たちがやってくるにちがいない。時計をつけてこなかったから時間がわからないいが、まだ九時ちょっと過ぎくらいだろうか。
もうすぐ五月の連休だ。この公園も老人たちが、訪ねてきた孫と一緒に散歩する風景がみられることだろう。そういえば、不動産屋のおやじが、この団地であんたさんが一番若いことになるな、と言ってたな。
池の上を糸トンボが飛んでいる。団地で育ったので、本物を見たのは初めてだろう。イラストレーターになるために動物植物の図鑑はずいぶん見た。それを絵にして練習をした。画家の人たちは石膏像だとか、偉い人の絵の模写だとかするのだが、自分はそういうことをしたことがない。だけど、図鑑やネットの2チャンネルで無料の動画は目が悪くなるほど見た。そういえば、子供の頃から動物は家にいなかった。ルンペンを自分の家に引き連れてきたのがはじめてだったのだが、なんだか、生まれたときから、ルンペンと一緒に育ったような気持ちになっている。
なあ、ルンペン、と何気なく手を隣にあげると、本当にルンペンが、大きなあくびをして隣に座っていた。
「なんだ、友達はどうした」
「十時だにゃ」
そうか、そろそろもどるか、公園から道にでると、ルンペンもついてきた。ルンペンは朝早くカリカリを食べるので、お十時が必要なのだ。
家に戻って、自分もコーヒーを入れ、ルンペンにはパックの猫餌をあたえた。
ビスケットを食べながら、ルンペンを見ていると、なんと、うまそうに食べるものか。動物はおいしいときはおいしい顔をする。人間ももっと素直においしいものを食べたときに顔にだしてもいいだろうに、テレビを見ていると、タレントは食べた後に言うことを競って、まういーとかしか言えなくなった。口に出さなくたって、自然と表情にでるはずなのに、無理においしそうな顔をする。どれが人間の自然の顔かわからなくなっているのが、電波の時代だろう。
そんなことを思いながら、コーヒーを一口飲んだところに、玄関の呼び鈴がなった。
だれだろう、知り合いらしき人はまだいない、両隣、後ろに、引っ越しの挨拶に行っただけだ。不動産屋のおやじだろうか、と思って、でると、まだ会ったことのないおばさんだった。赤渕眼鏡をかけた人の良さそうな丸顔だ。
「こんにちは、はじめまして、八組の組長をしている八坂です、お引っ越しされた方に、自治会のことを説明にまいりました」
寝子団地には寝子自治会があり、十八の組にわかれていることは不動産屋から聞いた。ゴミの出し方やら、諸々のことも不動産屋が教えてくれたので、もし自治会に誘われたらはいろうくらいにしか考えていなかった。
「あ、ご挨拶に行かずすみません」
おばさんを玄関に招き入れた。おばさんは、「お入りになるならないはご自由ですが、いかがなさいますか、市からの通知は直接きますから、組合の役割は、一斉の清掃や、小学校のもようし、警察からの通知、バザーや、あとは趣味の会の案内程度です、組合費は月百円で、年間千二百円です」
八坂さんは、ゆっくりと説明してくれた。
「はい、はいります、今年の分、千二百円ですね、今もってきます」
「あ、四月おわりにいらっしたので、五月分から、七百円です」
キッチンにおいておいた財布を持ってきて、七百円払うと、玄関にルンペンがでてきた。
「あ、猫ちゃん、顔がある、かわいいわね」
八坂のおばさんがおかしな言い方で、ルンペンの顔をなでた。ルンペンがおばさんの手をくっと、頭で押し上げたので、おばさんは感激して、
「あら、お髭が立派、お名前は」
ときいたから、ルンペン、というと、「あーら、すてきなお名前、いいこちゃんね、有名なお名前よ」とルンペンの喉をさすった。ルンペンの奴、鼻の頭を上に、喉を伸ばして、ごろごろいった。
いい名前だとよ、まさか、しかも有名な名前だ。「ルパン」と間違えたのじゃなかろうか。
「猫は飼っていらっしゃらないのですか」
「いいえ、三匹もいるんだけど、顔がなくて」
え、今、なんて言ったんだろう、よく聞こえなかったが聞き直すのもなんなので、やめた、そのかわり、たくさんあるルンペンの写真の絵葉書を一枚もってきてあげた。
「あら、かわいい、おしっこしている猫ちゃん、あ、あれ、これ絵本で見たことのあるポーズだわね、あの有名な、猫の絵本、あ、あれはルンペンのたのしみだったわね、もしかしたら」
「ええ、僕が描きました。マンガを描いたりしています」
「あの絵本持ってますよ、今度サインしてくださる」
「もちろんです」
「またああいう本だしてくださいな、有名な方が来てくださって楽しみだわ、それじゃ、おじゃましました、ルンペンちゃん内にも遊びにきてね」
八坂のおばさんは帰っていった。
こんなところでも、あの絵本を買ってくれた人がいるとは感激である。だけど変なこと言ってたな、ルンペンに顔があるって。
八坂さんが帰ると、隣の茶猫が玄関の前を通った。ルンペンがそれを見つけると、すっ飛んで玄関から外にでた。そのまま遊びにいっちまった。
自分は仕事部屋に戻ると、アイスクリームのような形をした、猫のおやつの、包装紙のデザインを考えることにした。今日は日曜日だが、気が向いたら、仕事をすることにしている。依頼されたもので、採用してくれれば数ヶ月は収入がなくてもやっていける。締め切りはまだだいぶある。
猫に細いチューブからなめさせるおやつで大当たりした猫餌の会社がある。とある会社が、それじゃ、アイスクリームのようになめさせようと、スティックについたアイスクリーム状の鰹節味の猫のお菓子を開発した。しかも、なめ終わった後に、当たりがでれば、もう一袋もらえるというものだ。これはまだ秘密のことだ。そのカバーの絵はなににしたらいいだろう。ネズミだとみないやがるだろう。猫だって、絵のネズミではみとめてくれない。左甚五郎ほどの腕はない。といっても買うのは人間だ。人間が猫がほしいだろうと思いこんでいるもので、人間から見てもおいしそうじゃなければだめだ。
PCに向かっていろいろな絵を描いてみた。
ふと窓の外を見ると、猫が跳ねている。仕事部屋から庭が見える。隣の茶虎とうちのルンペンが遊んでいる。
ルンペンがガラス戸から僕を認めて、あがってこようとした。窓を開けてやると、飛び込んできて、隣の家の猫もはいってきた。
おいおい、おまえさんがた、仕事中だよ、といいながらも、猫というとさわりたくなる。隣の猫もよくなれているようだ。僕の足下に来て、僕を見上げた。
「ひゃーー」
あまりの驚きに、僕はそれしか言えなかった。
虎猫ちゃんよ、おまえ、顔どうした。耳はある、髭はある、顔の輪郭はある、喉の部分もある、だが目鼻口がない、よく見ると耳も形だけの輪郭だ。
コンピューター画面の見過ぎで、目が疲れている。
頭をなでた。にゃーとないた。だけど口がない。
「のっぺらぼうじゃなくて、なんていったらいい」
鼻の先のあたりにふれると、ある、耳の輪郭の中を触るとある。気持ちよさそうだ。猫は耳の穴をティッシュで拭いててもらうのが好きだ。やってみた。ティッシュに耳のゴミがついてきた。それは透明ではない。
顔の表面が透明だ。頭の後ろの部分はちゃんと毛が生えている。
二匹の猫は、また窓から飛び出して遊びに行ってしまった。
なにが起きたのだい。
ちょっと寝室に行ってごろっと横になった。目に痛みがあるわけではないのだが、眼精疲労だろうか。
しばらく休んで駅にいった。駅に隣接したビルの一階にマーケットがある。二階はこれも小さな家電や家庭用品を打っている店がはいっている。この市にはいくつかの団地が開発されていて、どれも駅からバスで二十分ほどのところにある。だから、駅の周りにはそれなりに店が充実している。寝子団地は歩けるだけとても便利だ。
駅に行く道の途中に昔ながらの、小さな自転車屋があった。自転車は必要だろうと思い買うつもりである。店の中でおじさんが椅子に腰掛けて新聞を読んでいる。脇に白黒の猫がいる。鼻の周りが真っ黒で、左耳が黒、尾っぽはまだらで、背中にいくつかの黒いスポットがある。
僕が入っていくと、ニャアとないた。ちゃんとした猫だ。おじさんが気づいて、らっしゃいと元気な声をかけた。
「自転車を買おうと思うんですけど」
「なんにつかうかね」
「買い物ぐらいですね」
「住まいどこ」
「寝子団地」
「近いね、ほら、あっちに見える山に散歩になどはいかないかね」
市の西側には低い山がつらなっている。
「春は山桜、夏は森林浴、秋はキノコ、冬はそうだな、雪はあまり降らないから行くことはないが、ともかく楽しめるよ」
なにがいいたいのだろう。だが、家で仕事をするようになると、そういう気晴らしは必要になることは確かだ。
「行きたいですね」
「そんじゃ、電動買っと気なよ、楽しいよ」
それが言いたかったんだ、だけど、電動だと七、八万する。
白黒猫が足下にこすりついてきた。頭をなでてやる。猫が電動買えといっている。飼い主想いの猫だ。買うにしても、どれでもいいというわけではない。安い方がいいが、乗っていて気持ちのいい色がいい。モスグリーンの落ち着いたのがあった。それを見ていると、
「そりゃ、いい自転車だ、売りたくないくらいだ。いい色だよな」
想っていることとぴったり同じことを言われると嬉しいものだ。
「いくらです」
「うーん、十万の自転車なんだけど、何せ、最新のモーターで電気食わないんだよね、色もいいし、だけど同じ型のを通販なんかで八万で売っててるんだよね、だから無理して八万でいいよ、通販より、送料分安いよ」
間違っていない。
「もらおうかな、後ろにバックつけて」
「ありがとうございます、いい買いもんだよ、まだ充電していないけど、寝子団地なら電動スイッチ押さなくていいものな」
直接充電できるタイプのようだ。家の外にもコンセントがあるからちょうどいい。
市への登録料、それに保険にもはいって、カードで払うと、そのまま乗って、駅のマーケットに行った。
食料など買い込んで、家に荷物をおくと、団地の中をゆっくりと走って、様子をみた。まだ団地の全貌を知らない。自転車ならすぐ廻れる。
団地の家はみんな同じくらいの大きさで、生け垣のところもあれば、ブロック塀のところもある。猫がのんびり歩いている。塀の上に座っている猫がいた。さび猫だ。ありゃ、また顔がない。顔の輪郭は見えるのだが、顔の中がない。自転車を止めて、手をさしのべてみたが、逃げない。それで触ってみたら、口がある。
自分の目になにが起きているのだろう。いや、ある大学の教授が、目でものを見ているんじゃなくて、脳でみているんですよ、目は感覚器で知覚器ではないんです、目に入った光の信号を網膜でとらえられ、整理され、それが脳に入ると、そこでやっと、絵が脳に知覚され、意味が理解されるのです。言葉にも置き換えられます。と言っていたのを思い出した。ということは、脳がおかしくなっているのだろうか。
そういえば、顔を認識するのは、脳の特別の場所で行っていると言っていた。いや、待てよ、それは他の人の顔で、猫の顔ではなかったな。ともかく、脳なのだ。
そんなことを考えていると、さび猫は塀の上を歩いていってしまった。顔がないとなんと想っているかわからない。面白くにゃ位人間だと思ったのだろう。
ともかく買った自転車で、団地を一周した。ライオンを飼っている家の前も通った。家が大きな檻になっている。残念ながら、ライオンは家の中のようだった。
結構広い団地だから、自転車でもそれなりに時間がかかった。自転車を玄関の脇におくと、説明書をよみながら、外壁のコンセントにプラグを差し込んだ。そのままにしておけば、五時間ほどでいっぱいになる。
そこへ、茶虎のいる家と反対隣の主人がやってきた。本を持っている。野間さんといった。
「隣ののもんです、自治会班長の八坂さんの奥さんにコンビニでおうたら、この本の著者さんだって言うので、サインをもらいに来たんですが、もらえんでしょうか」
僕の絵本、ルンペンのしあわせ、をもってきている。
「あ、どうぞどうぞ、あがってください、サインしますから」
間野さんは、すんませんな、といいながら居間に入ってきた。僕は本に、自分の名前を書きいれた。
「いや、若い猫の好きな人がきたって言うんで、八坂の奥さん大喜びでな、きっとなん人かひきつれてサインをもらいにきますぞ」
「どうぞどうぞ、来月からは家でしごとをしていますので、いつでも」
そこにルンペンがかえってきて、居間をのぞいた。
「お、お宅のルンペンちゃんですな、顔がある」
また、間野さんもおかしなことをいった。
ルンペンがはいってきて、間野さんの隣におちゃんこした。
「顔があるのはいいですな」
おかしい、団地であった猫の顔が見えなかったが、やっぱり顔がないのであろうか。
そこにのっそりと、大きな真っ黒な猫がはいっていきた。この家には猫の入り口があり、自由に出入りできる。
「ありゃ、こら、くろっぺ、よその家に入ってきてはいかんよ、すいませんな、うちの猫で」
「いやいいですよ。ルンペンは反対のお隣の猫とももうなかよしです、きっと、くろちゃんとも仲が良くなって、つれてきたんですよ」と、くろっぺの顔を見ると、顔がない。
思い切って聞いた。
「顔がないように見えるのですが」
「寝子団地の猫はみなそうです。三十年前から顔がなくなったんですよ、まず鼻が消え、口が消え、そのころは、目だけありましたな。はじめはみな怖がったんですが、でも触ると顔はある、どうしてそうなったかわからん、そのうちしょうがない、寝子団地だから、と訳の分からん納得の仕方で、みな落ち着いたわけです」
「うちの猫の顔もなくなるのでしょうか」
「さー おたくさんは数年ぶりの新入居の方だでな」
ルンペンが腹が減ったという顔をしている。となりのくろっぺも同じ顔をしているのかもしれない。
「ミルクをもってきてあげるよ」
僕は皿を二枚と牛乳のパックをもってきた。
さらにミルクを注ぐと、ルンペンはすぐにペチャペチャ飲み出した。くろっぺも飲んでいるようで、白い滴が飛んで音がしている。すると、くろっぺの顔に白い鼻の先があらわれた。ミルクにぬれたようだ。ということは、白く塗れば顔が現れる。
僕は筆と薄力粉を持ってきて、ミルクに混ぜると、くろっぺの顔にぬってみた。目は空洞だが、後は白い猫の顔になった。
「あ、くろっぺ、白いけど顔が現れた、こりゃいい、五年ぶりにくろっぺの顔を見ることができました、家で色が落ちたら、同じことをくろっぺにしてやります、家内が喜ぶ、ありがたいことで」
「一時でよければ、イカ炭を塗ってごらんなさい、黒い猫の顔になりますよ」
「あ、そりゃいい考えですな、ありがとさんで」
間野さんは白い顔のくろっぺをだっこすると、家に帰っていった。
僕は自転車に乗って、八組の組長である八坂さんの家にむかった。八坂さんの持っている本にサインをしてあげようと思ったからだ、途中出会った、黒キジの猫も顔がなかった。庭の中にいるのを見かけた三毛猫にも顔がなかった。きっと八坂さんの家の猫にも顔がないに違いない。八坂さんが寝子団地の猫の顔が消えた理由をしっているかもしれない。
八坂さんの家の呼び鈴を押した。
八坂さんが顔をだした。
「おや、サインしてくださるためにいらしたの」
玄関に出てくると、白黒の猫が一緒に出てきた。やっぱり顔が透明である。
「はい、お隣の間野さんの猫ちゃん、くろっぺに会いまして、顔がなかったので、もしかしたら、八坂さんの猫ちゃんもそうかと思って、どうしてそうなったかご存じだったら教えていただこうと思ってまいりました」
「あーら、そうでしたの、お宅の猫ちゃんに顔があるのをみて、つくづくうらやましいと思いました、本をもってきますね、サインお願い」
八坂さんの差し出す本に、猫の顔を描き、サインをいれた。
「あの、顔は見えないだけで、あるので、猫ちゃんたちに害にならない粉などを、塗ると、毛について、一時ですけど顔がでてきます、間野さんの、くろっぺにそうしてあげました」
「あ、そうね、顔が見たいわね、顔のある頃の写真はあるのよ、写真のように色をつけてくれる人がいるといいわね、草野さん絵描きさんだわね、猫の顔にお化粧をしてくれないかしら、写真をもっていくから」
できないことはないとは思うが、食べられる色絵具をそろえなければならない。
「今材料がいまありませんから、もし本当にお望みなら、材料費をいただければやりますよ」
「それは嬉しいわ」
「そのう、猫に顔がなくなった理由を知る人を知りませんか、お隣の間野さんもよく知らないようですし」
「この団地ができて四十年です、そんなに古くないんですけど、元は田圃や畑だったそうですよ、数件の家があったそうですけど、その中の一軒のお宅が、この団地に引き続きすんでいらっしゃるわ、一組のはずれにある、駅に近い方ね、工藤さん、そこの息子さん二人とお父さんが、それぞれ家を買ってすんでいらっしゃるわ、お母さんはなくなっているので、お父さんは、もう八十五になりますけど、まだお元気でいらっしゃる。その方が何か知っているかもしれないわね、お話するのが好きな方だから、突然行っても大丈夫よ」
「そうですか、それじゃ、時間のあるとき行ってみます、それと、猫のお化粧、やってみます、材料がそろったら、電話します、猫ちゃんを連れてきてください」
「お願いしますね」
八坂さんはにこにこしている。
次の日曜日に工藤さんのおじいさんの家を訪ねた。絵本を持参したら、たいそう喜んでくれて、猫の顔がなくなった話をしてくれた。
「昔、このあたりは、畑や田圃でしてな、古い土地で、縄文のあたりから人が住んでいたと言われています、わしらは、昔からの百姓で、しかも小作人で土地などがなかったんですが、戦後の農地解放で、地主がわしらに割ふっていた田圃をくれましてな、農業をやっていたのですが、子供は東京の方に勤めるようになり、電車の便がよくなり、この辺も通勤圏になったとき、団地の開発が始まりましてな、二軒は自分にもらえるということで、土地を手放しまして、住むようになりました。団地が完成したとき、息子の一人がここから東京に通うようになったわけです。
寝子団地の西のあたり、八組の近くに公園があるのを知ってますかな」
散歩に行ったところだ。ルンペンもすでに遊びに言っている。
僕がうなずくと、工藤さんは話を続けた。
「あそこの雑木林の中に、ちょっと小高いところがありますでしょう、あれは小さな古墳じゃないかという話でね、そこに穴がありましてね」
煉瓦でふたがしてあったとこだ。
「その穴に、異国の人がすんでいたんですわ、それがなんだかぴかぴかする洋服を着ていまして、とてもルンペンのようではなかったですな、終戦直後の話です。しかし、いつのまにかいなくなっていましたな。それで、あそこに誰も近寄ろうとしませんでした。誰にも悪さしなかったんですけどね、だけどなにを食べていたのんでしょうな、水だってどこで飲んでいたのかわからんでした。その穴には外人の飼っていた猫が何匹かいましてな、その当時、内で飼っていた猫も、その猫たちと仲が良く遊んでいましたな、わしがまだ子供の頃ですな」
「戦後、負けた日本に外人さんが一人で、ルンペンのように生活していたというのは不思議ですね」
「うーん、わからんでな、いつから現れたのかも知る人がおらんでな」
「どのような顔をしていた人なのですか」
「いや、それがわからないんです、いつもしおれた古い山高帽子のようなのを、深くかぶっていまして、鼻だけ目立って突き出ていましたな、顔を覚えている人がおらんじゃったな、うちの親父も知らんし、だれにもわからんかった」
「猫もいっしょにいなくなったのですか」
「そうだな、異国の人がいなくなるととき、穴がふさいでありましたな」
「この団地ができるころの話ですか」
「いんや、もっともっと前じゃ、もう六十年もまえじゃろう、わしが二十歳の頃かな」
「寝子団地の猫の顔がなくなったのと、その異国人が関係があるのですか」
「それがな、団地を作るときに、古墳だと思われていたところを公園にしようと、建設課の人や建設会社が雑木林の中をしらべましてな、その穴の入り口もあけてみたわけですわ、中はちょっとした住居になっておった。古ぼけたゴザなんかが敷いてありましてな、猫の毛がたくさんついていたそうですな、それで、いつかその穴を利用しようと、また煉瓦でふたをしたそうです。
話のつづきがありますんじゃ、ここの団地を作った社長の話はきいておられるでしょう。会田権贈という男ですけどな、異常な猫好きということも知っとりますでしょうが、そいつが、穴がみつかったとき、中に入りましてな、写真機をみつけたんですわ、ただ、どこの国のかわからんかったんですが、日本のフィルムが使えたんですな、権贈さん喜びましてな、何せ猫の写真を撮るのが大好きで、まえまえからドイツの写真機で、野良猫を撮っておったんです。
「それじゃあ、権増さんのところにはたくさん猫がいたんでしょうね」
「いや、奥さんが、ひどい猫アレルギーでな、飼えなかったんですわ、それで野良猫の写真を撮っておったんです、この団地を完成させたのは二代目で、やはり猫好きでしてね、息子さん、といってももう六十になりますかな、権贈産は団地の中の一軒に居をかまえておらっしゃったが、息子さんはほかに住んでいますよ」
「それで、猫の顔がなくなった理由は何でしたか」
「まず権贈さんの話にもどりますが、この団地ができたときには、まだ元気で、自分も一軒家をもっていたんですわ、暗室まで作って、自分で写真を撮って、自分で現像して、コンテストに出したりしていたんです。
それで、異国人の暮らしていた穴で見つけた、写真機をきれいにしましてな、写真を撮るようになったんじゃが、野良猫だけじゃなく、飼い猫の写真も撮り始めましてな。それで、うちの猫を撮らせてほしいと言ってきたんです、そうして、みんなの家の猫の写真を撮って、写真集をだしたんですわ、猫は猫好きがわかるんですな、権造さんがカメラをかまえると、そっちに向かって歩いていく、それで、写真集には、団地に住んでいる猫の顔は全て写ってましたな。内のもです、かわいいものです。いろいろな顔がありますが、なかなかいい写真集で、わし等も一冊もらいましたよ」
「いまもありますか」
「もちろん、ちょっととってきましょうかな」
工藤のおじいさんは奥から、B5判のハードカバーの本を持ってきた。タイトルは、猫の楽園だった。
「今でもよく見とるよ」
そこに工藤さんの猫が外からもどってきた。
茶色の大きな猫でやっぱり顔がない。それでも工藤さんの足にこすりついているのがわかる。
「ほら、これだ、このページの左端のがこの猫だ」
本を見せてもらった。三十年前に出した本だ。カラー写真だ。当然、今の猫は孫か曾孫かだろう、そのことを聞いてみた。ところが、
「この猫そのものなんでね、もう三十歳にもなる」
「猫は十歳で人の六十だと言われてますよ」
「んんん、そうだな、だけんど、本当にそうなんだ、この団地の猫は長生きしとる」
そんなバカな話はない。
虎猫、三毛猫、キジ虎、さび、みんなが写っていた。
「ここに写っている猫の顔がみんな、なくなってしまった。しかも、長寿になってな。
理由?、そんなもんわかりゃせん、だけんど、権贈さんが拾った写真機で写された猫だけ顔が消えとる。権贈さんだって、そんな風になるとは思っていなかった。みんなに申し訳ないと、謝罪の金一封と、もうそのカメラは使わないと約束しましてな、寝子団地のみんなも、しょうがないとあきらめたんですわ、それでも、猫たちは顔がなくても猫として楽しんでおりましてな、顔のない猫が生まれとる」
「ギネスに登録できますね」
「そいだら、あんた、顔が見えないことが知られちまう」
「この話は、新聞にのったら、大騒ぎですよ」
「それが困るんじゃ、しゃべったりしたら、たたりがありそうでな、だいたい、新聞記者などが来てみなさいや、わんさか人が押し寄せてきて、猫どもが楽しく暮らせんじゃろうに、猫好きはそんなこといやなんだ」
「ぼくにも猫がいます、もう周りの猫と仲良くなっています、子供ができるかもしれない」
「そりゃいい、もしか顔のある猫が生まれたら、お赤飯んものじゃ、自分のとこの猫の顔みたいと本当はみんなが思うとるよ、それで、当然団地の猫同士で、子供産むので、もう何代目かがいるが、みんな顔がないんじゃ、うちにもこいつ以外に二匹もいるで」
「今度、僕が、みなさんの猫の顔を絵の具でもとにもどそうと思うんです」
「うれしいね、猫のきょろきょろ目が見たいもんよ」
「あ、すみません、目には色が塗れません」
「そうか、それは残念じゃな、それでも目と鼻と耳が顔が表れるるならいいわな、うちの猫も顔描いてくれや、孫猫の顔はどんな顔かわからん、そうじゃ、この本をかすでよ、猫の顔もとに戻してくれよ」
「死なないとなると、みんな生きているわけですか」
「伝染病気にかかったり、事故にあったりすると死んじまう。だから、健康なら長生ききするってことだな」
そういうことで、本をかしてもらった。
僕は自宅で仕事をするようになり、色の材料の勉強をして、無毒の絵の具をそろえた。
仕事は順調で、所属している派遣会社が、コマーシャル作成部門を立ち上げ、商品のパッケージや、マークなどの依頼を受け、僕にも仕事がずいぶん回ってくる。
団地では、八坂さんが周りの人たちに言い広めてくれたので、猫の顔描きの仕事が増えた。連れてきた猫に、工藤さんから借りた本をもとに、顔を復元した。その子孫は写真がない。それで、身体の模様から判断して、顔を描いてやった。材料代だけ払ってもらうつもりだったが、八坂さんが、それだとかえって、頼む方がお礼になにするとか、考えなければならないので、きちんと代金を取った方がいい。と助言してくれた。それで、今時給千五百円ほどだろうから、それを基本料金にして、材料費こみ二千円で引き受けた。
猫に顔を描く作業は夜のみと決め手、一回一匹に限った。自分の仕事もあるし、自分の自由な時間もほしい。それで猫を夕方預かって、一晩うちにおいた。おかげで、うちのルンペンは団地の猫みんなと仲良くなった。しかも、半玉なのに、どうも子供を産ませているらしい。産まれた子供に顔があると、わざわざ言ってきてくれる団地の人がいた。
ふつうのところにいたら、半玉のルンペンなどもてるわけはないのだろうが、寝子団地にきたお陰で、大将気取りである。
そんなこんなで、一年がたち、この団地を造成した建設会社の今の社長が僕のところにやってきた。会田権贈さんの子供だ。といっても70近くなるに違いない。
「いや、おじゃまします、工藤さんから聞きましてな、猫に顔を描いてくださっているということで、感謝しております」
権造さんの息子はお菓子をもってきた。
「今、私どもはこの団地にはすんでいませんが、父親が一軒持っていて、そこで猫と暮らしていました。もうだいぶ前に死にまして、ともかく、変な写真機でみなさんの猫の顔をなくしてしまって、申し訳なかったと、死ぬまで悔やんでおりました。全く奇妙な話で、その写真機はおやじは隠してしまい、どこに行ったかわからなかったのですが、ほっぽらかしていた父親の住んでいた家を、もう40年も経っているし、取り壊そうかと片づけにかかったら、袋戸棚の奥からでてきました。これです」
権造さんの息子が箱に入れられ、風呂敷に包まれた写真機を僕に差し出しだした。
「開けてみてください、ただ、使うことは止めた方がいいと思います。おやじは呪われた写真機だと言っておりました。工藤のおじいさんから聞かれたと思いますが、古墳跡の穴からみつけたもので、その昔、異人さんが暮らしていただろうと言うところです」
それは聞いていた。
「画家で、イラストレーター、本もお作りになっているということを伺って、こちらでもらっていただくのが一番いいのかと、思いまして」
なぜなのだろう、あまり関係ないとは思うが。それを察したのであろう、権造さんの息子は
「いや、本当のことを申しますと、この写真機の処分に困りはてておりました、新しくこられた方でもあり、猫の顔がないことにも動じない方であることをうかがい、きっと、このカメラの処分方法を考えてくださるものと思って、まいりました。是非、よろしくお願いします」
「どのようにしてもいいのですね」
「はい、何事も起きなければ」
なんだか、意味深な言葉だが、ちょっとカメラに興味があることもあって、引き受けますと請合ってしまった。
「どうぞよろしくお願いします」
権造さんの息子は、頭を下げた。
さて、写真機を取り出してみよう、本当は興味津々だったのだ。
風呂敷をほどき、桐箱をあけると、さらにフェルトに包まれた写真機があった。開いてみると、あまり驚くようなものではなかった。むかしあったゼンザブロニカのような形だ。
このタイプのフィルムは、今は好事家が買うくらいで、とても高い、六六版ではなかっただろうか。
カメラそのもの本体にメーカーの名前がなかった。
「僕がいただいても、どうするってこともないのですが、形がいいので、かざっておくくらいですが」
「ええ、それでけっこうですので、どうぞ、お好きなようになさってください、これがあることが気になっていたんで、手放せるだけでも助かります」
「それでは、おあずかりします」
こうして、思いもかけずに、猫の顔をなくしてしまうカメラをあずかることになった。本棚の空いているところにおいておこう、ちょっといい飾りである。
団地の家の猫ちゃんたちの顔描きはずいぶん進んだ。
もう夏も終わりになる。天気予報では台風が明後日あたり接近するかもしれない。この団地に来て、台風は何度か接近したが、そんなに影響はなかった。今度も大したことはないだろう。ルンペンは相変わらず、元気に外を歩き回っている。半玉ルンペンは団地の中で知らない者はいないというほど、歩きまわって、愛想を振りまいている。顔のある猫が生まれました。と何度も団地の人が言いに来た。彼らはとても喜んでいる。
台風は関東に明日上陸するという。家の周りに風で飛ばされるものがないかちぇっくして、午前中の仕事にとりかかったときである。玄関の呼び鈴が鳴った。
返事をして、戸を開けると、入り口に背の高い男性が立っていた。今時珍しい、古ぼけた帽子をかぶり、マントのようなものをはおっている。まだ暑い日が続いているというのにである。
「なにか、ご用でしょうか」
そこへ、僕の後ろからルンペンがでてきた。
「顔がありますな」
その男はルンペンに手をだした。ルンペンがその手にこすりついた。猫好きのようだ。猫が近寄るようなら悪い奴じゃないだろう。飼い猫の顔のことで来たのかもしれない。
雨はあまり降っていないが、曇り空で少し風がある。台風の予兆だ。
「どうぞ、玄関の中へ」
そういうと、「おじゃまします」と入ってきた。ずいぶん背が高い。180、いや190もあるか。
「なにか」
「はい、こちらに、タイムカメラがあるとききましたので、お願いがあって参りました」
「なんのことでしょうか」
「あの、会田さんがもっていたタイムカメラがこちらにあるとうかがいまして」
「え、あのカメラのことを誰にお聞きになりましたか」
「実は、会田権造さんが持っていったことを最近知りまして、その家に行く会田さんは亡くなっていらっしゃり、家は取り壊されているところでした。息子さんがいることを聞いて、訪ねていくと、あなた差し上げたとのことでした」
「確かにその通りですが、会田さんがもっていたということをどこで知ったのです」
「今、私はあの公園にすんでいます、ベンチでこの団地の人が、そういう話をしていました」
寝子団地を作った会田のことはみなよく知っている。
「あなたはどなたでしょうか」
「すみません、名前ないのです」
どういうことだろう。
「正直に言います。私はこの星の生き物ではない、旅をしていて、この星を通りかかったら、運悪く、戦争をしているときで、高射砲で打ち落とされてしまったのです。そんなことは普通ありません、だけど、百万分の一秒、私の乗っている船が姿を見せたときに、砲弾がとんできて、落ちました。ご存じでしょう、古墳だと思われている丘の中には私の乗っていた船が入っています。時空に入り込めなければ戻れません。
それであのカメラを作りました。この星で手に入れたカメラを改造しました。あのカメラで生き物を撮ると、私の星のトラベル管理局に送られます。それで自分を撮って送り返そうとしたのです、ところが表面だけ送り返すことができただけで、私自身は帰れなかった」
そう言うと、彼は帽子を取って、顔を見せた。透明だった。マントをとり、着ているものを上だけ脱いだ。ズボンしかなくなった。透明人間である。
びっくりしたなんてもんじゃない。
工藤さんのおじいさんが話をしていた、穴にすんでいた男というのはこの人なのかもしれない。
「あがってください」
彼は「ありがとう」と言ってあがってきた。ルンペンもついてきた。よほど猫に好かれる異星人だ。
居間に通すと、「何か飲みますか」ときいてみたら、「空気があれば大丈夫です」という返答があった。
仕事場からカメラをもってきた。
「どうぞ見てください。このカメラで、会田さんが猫を撮ったら顔だけなくなってしまったんですよ」
「はい、すみません、このタイムカメラまだ未完成だったようで、自分も色素だけ自分の星に送られたのです。それで、私も猫を撮ってみたのです、そうしたら、猫は顔の色素だけ、私の星におくられました」
「なぜ、送られたということがわかったのですか」
「先ほど言いましたように、古墳の跡とい岡野われている丘の地下に私の船がぺしゃんこになってあります。私は今もあの穴に住んでいます。透明なので、だれにもわかりません、つぶれた船の連絡装置は使えるので、今でも自分の星と連絡をしています」
「顔をなくした猫は、寿命が延びています、どうしてでしょう」
「私も透明になって年をとりません、自分の星の友達の多くはもう死んでしまっています。理由はわかりませんが、私のすべての色は星の管理局に保管されています。もし私に色が戻ったら、あっという間に浦島太郎です。猫たちも顔の色が戻ったら、死んでしまうかもしれない」
「それで、このカメラどうするのですか」
「改良すれば、私は星に帰ることができるかもしれないことがわかったのです、地球の科学が進み、利用できるものができました」
「手にはいるのですか」
「はい、スマホに使われているICをうまくそのカメラに組み込めば、そのカメラはタイムトラベルカメラになります」
「それで、自撮りして、星に戻るわけですか」
「はい、直してあなたに写真を撮ってもらってもいいのですが」
「シャッターを押すのですね」
「はい」
「猫に向けてシャッターを押すと、あなたの星に行ってしまうのですか」
「はい、猫だけではありません、生き物ならば皆私の星にいけます」
「でも帰れませんよね」
「うーん、帰れないことはないのですが、地球の生き物が私の星に行ったとき、どのような形でいきつくかわかりません、一部がなくなって、たとえば骨がなくなって、アメーバーのようになってしまうかもしれません」
「それは怖いですね」
「はい、私は大丈夫です、このカメラ持って帰っていいですか」
会田の息子には自由にしていいと言われている。
「いいですよ」
「ありがとう、カメラを改良したら、持ってきますから、このカメラで私を撮ってくれますか」
「それはいいのですが」
「ありがとう」またそう言うと、「一週間くらいで改良できます」とカメラを持って玄関に向かった。
「必ず、直してきます、よろしくお願いします」
異星人は上着を着て、マントを羽織り、帽子を深くかぶって、出ていった。ルンペンが見送っている。ほんとのルンペンだと言っている顔だ。
それから三日後である。
あの男、異星人がやってきた。
「できました、写真撮ってくれますか」
「それはいいのですが、撮ると、あなたは星に帰ってしまうわけですね、そのあとどうなるでしょう」
「カメラですか、使えますが、私の星と連絡してからでないと、送られた生き物は時空の切れ目の中で漂うことになります」
「それはどういう状態でしょう」
「ただ浮いているのです、時間の中で、永遠に」
「もし、僕がそうなったら、意識はあるのでしょうか」
「ありません、形だけです、どこかの星で、時空の切れ目に漂う、時がとまって浮いている生き物を、その星の時空に引き込んでくれなければ、生き物として生をまっとうしません」
わかったような、わからないことだが、ともかく、永遠の形だけになるかもしれないわけだ。
「わかりました、では、あなたを撮りましょう」
「はい、お願いします、何十年ぶりに、故郷の星に戻れます、感謝します」
「何か飲みますか」
「いえ、空気があれば」
「地球の空気はおいしいですか」
「はい、おいしい方だと思います」
「地球でやり残したことはありませんか」
「もう一度、猫をだっこしたい」
「うちのルンペンじゃだめですか」
「いいえ、いいえ、喜んで」
ルンペンをかかえてわたすと、大きなルンペンがその異星人にだっこされた。よっぽど好きなのだろう。髭を引っ張ったりしている。ルンペンもこすりついている。
「もし猫と一緒に写真を撮ったら、猫も一緒にあなたの星に行くのですか」
「はい」
「猫は生きていれますか」
「はい」
「でも、異星の生き物を移入すると、ウイルスや細菌も一緒に持ち込むことになるので、怖いでしょう」
「いいえ、私の星にはウイルス、細菌類はいません、動物の細胞を利用して増えるようなものはいませんでした。生きていれません、植物もありません、地球でいう、人間とは虫類、それに鳥類しかいないのです。だから毛のある猫はかわいい」
「あなたの星で増えるでしょうか」
「空気も大丈夫、食べ物は大丈夫です、地球上と同じように増えるでしょう」
僕は八坂さんに団地の中の家で、子猫が八匹も生まれて、もらい手を探していることをきいていた。聞いてから三週間だから、まだいるとすると、一人でご飯を食べられほどに育っているだろう。ちょっと聞いてみるか。
「ちょっと待っててくださいね」
僕は八坂さんに電話をかけた。欲しい人がいることを話すと、そのうちでは六匹まだ残っていて、雌も雄もいるそうだ。それでこの団地の人は驚かないと思って、いきさつを話した。
「あら、その異星人、足は何本あるの」
と八坂さんは興味津々である。
「いえ、透明人間になっています」
「あら、見えないの、残念、でも猫ちゃんを大事にしてくれるのなら、いいわよ、もらってきて届けてあげる、すぐにね」
八坂のおばさんは電話をきった。
「ちょっと待っててください、子猫が二匹きます」
「エー、ほんとですか、嬉しい、私は星に帰るともう地球でいう七十歳、平均年齢が百ですので、向こうで子供が生まれれば、猫に囲まれて幸せです」
顔は見えないが声の調子でとても喜んでいることがわかる。
まもなく、八坂のおばさんは三毛猫とキジ虎の子供を抱えて自転車でやってきた。
あがってもらって、異星人に紹介した。
「八坂さん、ありがとうございます、かわいいかわいい」
猫の子供を受け取った異星人は大喜びのようだ。顔のない猫をそだてていただけあって、八坂さんは驚いていない。
「それでは、カメラのボタンを押してくれますか」
八坂さんには証人になってもらおう。
異星人が子猫を二匹抱えて、客間のソファーの脇にたった。カメラを向け、全身が入るように後ろに下がり、教わったとおりに、ボタンをおした。赤い光が、猫を抱えた異星人に当たった。
ぱっと消えるのかと思ったらそうではなかった。だんだんと、子猫を持った透明だった異星人の姿が現れ、それが次第に白くにごってくると、すーっと消えていった。
「やっぱり、蛸だった」
八坂さんがため息をついて帰っていった。
異星人は蛸のように八本の足をもっていた、あとは人と同じようにお腹と胸と頭があった。
それから八ヶ月後、僕の机の上に紙が置いてあった。
「子猫が大人になりました。かわいい子供が産まれて、幸せです、本当にお世話になりました。あなたの机の上に、白い紙をおいて、字を書けば、私が読めます。こうやって交信ができます、写真でも大丈夫」とあり、持って行った猫の子供たちの写真が印刷されていた。
今度、日本のSF作家の本の表紙絵を描くことになっている。それで、「そちらの風景がみたい」と書いて、ルンペンの写真と一緒に机の上に置いた。
今、返信を待っている。
その星はどんな景色なのか、とても楽しみだ。
顔のない猫


