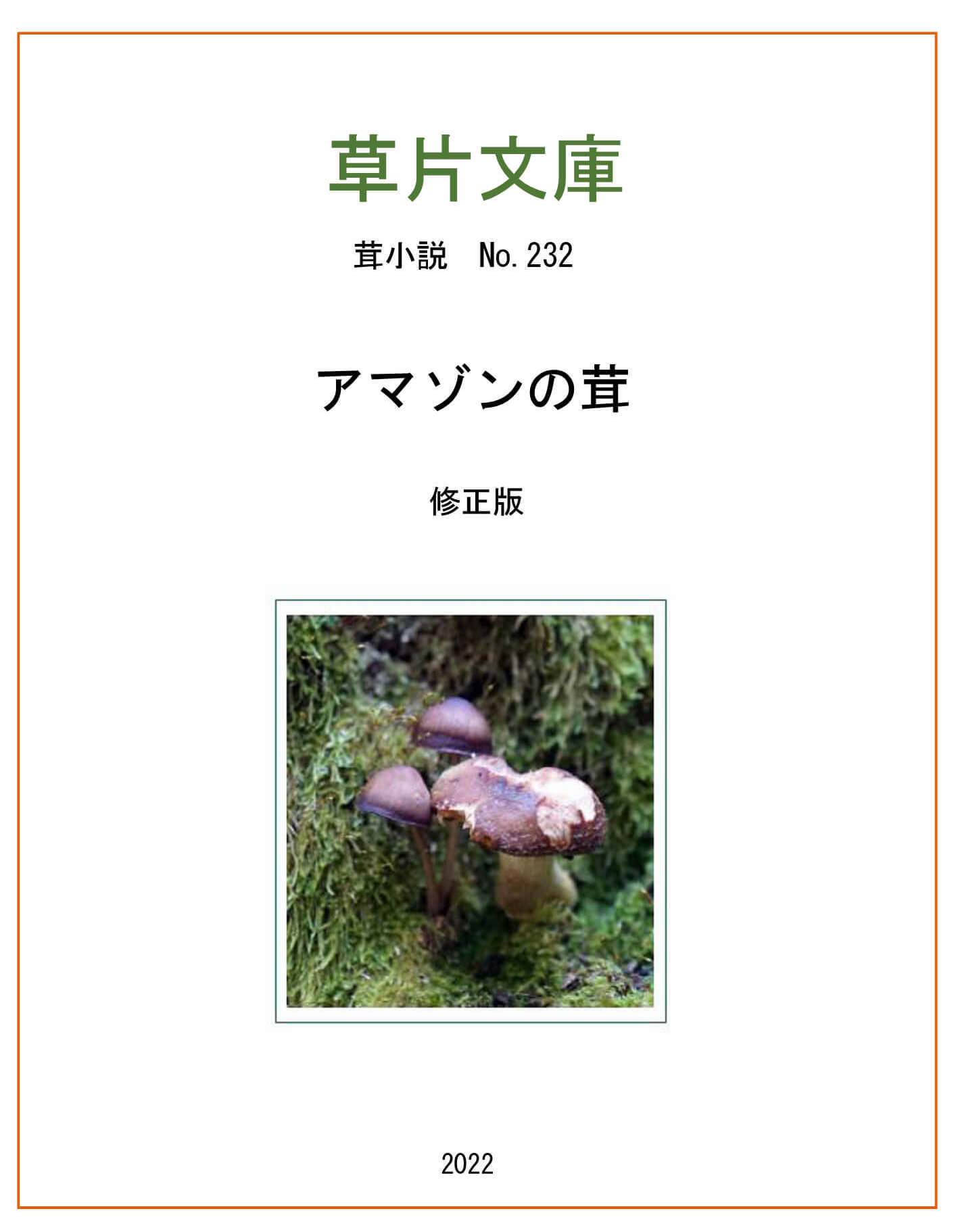
アマゾンの茸
茸冒険ミステリー小説です。縦書きでお読みください。
大学二年が終わったとき、同級生の空間史郎(くうましろう)は留学をした。みなイギリス、フランス、ドイツ、アメリカを留学先に選ぶものだったが、彼が行ったのはアマゾンだった。アマゾンはいくつかの国を通るが、上流にあるペルーのイキトスという、飛行機か船でしか行けない町にいったのである。
彼は一年後アマゾンから帰ってきた。大学に出てきたとき、真っ黒に日焼けして、髭を某々に生やしていた。
学生食堂に入ってきた彼は、僕に日焼けした顔を向け、「がんばってるんだろう、青っちろいな、そのうちゆっくりな」と言い終えると、食券売場に行ってしまった。ふっと彼の焼けた首筋を見たら、てらたらに光ったケロイドのような後があった。アマゾンでなにをしてきたのか、そのうち是非聞いてみたいと思った。
僕は四年で、一年遅れた彼は三年生ということになる。僕は卒業論文作成と、国家試験を受けるべく準備していた。食堂で会った以来、彼とはなかなか会う機会がなかったが、学部事務所に隣接する学生ラウンジでたまたま一緒になった。
「やあ、忙しいと思って連絡しなかったが、確か外務省に入りたかったんだよな、入ったら、こういうものももっていた方がいいよ」
そのとき、彼は髪と髭をきれいに整えて、舶来品のような紺色のブレザーを着ていた。
彼が差し出したのはシェーファーの古い万年筆だった。
「これはね、ペルーのリマの市場でたまたま見つけたんだよ、帰るとき、そこからアメリカ経由で帰ってきた。何でこんなものがあそこにあったんだろうな、古いけどいいものだ」
「嬉しいけど、万年筆は使ったことがないよ」
「君はきっと外交官になる、僕は未来が見えるようになった。この万年筆はサインをするときに使うことになるさ、シェーファーはサインのときよく使われたものなのだよ」
小豆色のキャップに白い丸い印が埋め込まれている万年筆だった。彼はテーブルの上に万年筆をおいた。
僕の上着の内ポケットには、数本の宣伝入りボールペンやシャーペンがはいっている。こういった上等な万年筆など持ったことはなかった。
「アマゾンでの暮らしはどうだったんだい、いつか聞かせてほしいな」
「いつでもいいよ、君が卒論を書くのに飽きたときに連絡くれよ、話して聞かせるよ、電話番号を教えてくれ」
そういって、スマホを出した。僕はまだガラ系の携帯を使っていて、たまに両親に電話をかけるだけで、ネットはほとんど利用していない。彼は僕の言った電話番号にすぐにかけた。僕の携帯がなった。
「来たよ、番号は登録しておくよ」と僕が言うと「スマホじゃなんだ」と不思議そうな顔をした。
「うん、ネットは無料ワイファイでのみつかっている」
ああそうかという顔をして、
「それじゃ、いつでもいいよ、電話くれよ」
と、彼は出ていった。
それからしばらくして、卒論のだいたいの枠が決まった。後は、集めた資料などから、自分の考えをまとめていくだけである。政経学部は卒業研究というものは書きたいものが出すという仕組みになっていた。卒業論文をだすかわりに、いくつかの科目を加えて受講することでも卒業可能だった。しかし、それではものをまとめる力を養えないと思い、卒業研究を選んだ。タイトルは日本の原始的政治形態について、というものにした。古くは倭国の時代、小国に分かれていたときのそれぞれの国の、民をまとめる仕組みと、それが大きな国屁とまとまっていく課程での政治の仕組みである。言うなれば、民衆の心をつかむ方法とでも言うことだろう。安心して生活をさせる、そのために、政治を司るものは、自分を信じさせなければならない。基本的には卑弥呼の鬼道、すなわち呪術、シャーマニズムからはじまる。民衆の安心と、糧を得る方法を考え出したものが政治の中心になり、領土を拡張するために、戦の強いものが頭になる。
そこで、ふとアマゾンの民族の生活はどのような形で治められているか、という興味がわいた。彼の話を聞いてみるのもおもしろいだろう。そう思って電話をかけた。
彼は喜んだ声で、土曜日に自分の家に来るように言ってくれた。彼がアマゾンに行く前、一度彼のマンションに行ったことがある。月島の高層マンションだった。親が東京に出てきたときに使うため、買ったものだという。3DKの広くて、東京湾が望める立派な部屋だ。そのときに、彼は僕の大学の近くの、月三万、一部屋の風呂なし下宿の方が趣があっていい。親のものじゃなきゃ取り替えてもらうのにと言っていた。
彼のマンションには、地下鉄半蔵門線で、西新宿から一本でいける。彼の部屋は三十階のマンションの二十八階だ。エントランスで来たことをつげ、エレベーターに乗った。始めてきたときは、最新の高層マンションに驚いて、すごいものだと、感激すらしたが、今は、自分の住むたった四畳半の一部屋が暖かく思える。あのとき彼の言っていたことに納得している。
288号室に行くと、ドアが半開きになっていてノックをして開けると、やーよく来てくれた、と笑顔で迎えてくれた。
リビングルームの部屋は様変わりしていて、しゃれた西欧の家具があったのが取り払われ、木でできた床の上にはゴザが敷かれ、丸太でできたテーブルの前には、座布団がおかれている。壁には祭壇のようなものが作られていて、しなびたものが三角に積まれていた。
「ずいぶん変えたんだな」
「ああ、アマゾンの生活はこんなものじゃなかったが、ともかく、少しは木の臭いがほしくてね、本当なら引っ越したいのだが、それは卒業して、独立してからだな」
彼の家は九州の唐津にある、旧家で、焼き物の窯元である。
彼はそう言って、日本茶をいれてくれた。前はサイフォンコーヒーだった。
「アマゾンはどうだった」
「よかった、自分の思っていることが間違っていなかったことが明らかになったんだ、ただ、よかったのは、僕が半年生活をともにした部落の人たちかな、ペルーは古くからの国だが、今は、どこも同じかも知れない」
「イキトスがよかったわけ」
「いや、あそこは行くのは大変だが、やっぱりそれなりの都市だよ、そこに一月いて、情報を得てから、外船モーターの小さな船を買って、そこからアマゾンを下っていく途中で、その部落に偶然いきついたんだ」
「それじゃ、あの筏下りと同じじゃないか、怖かなかったかい」
1997年だと思ったが、ある大学の探検部の2名が筏で川下り中、イキトスで兵士に殺害された事件がある。これは結局、金ほしさの犯罪であった。貧困故のことではあるが、様々な議論が巻き起こったという。
「あれは運が悪かったんだな、なにもペルーだからではないよ、日本だって今でもおこっていることだから」
確かにそうである。
「僕は船にテントや諸々のものを積み込むと、陸地沿いに進んだんだ、木々の中で、猿や鳥の声を聞きながらね、あの船の中から見た、星のまたたきは日本では見られないよ。
二日ほど言ったところで、支流というか流れ込んできている川の一つにそって奥にはいっていったんだ、ちょっといくと、森の脇に舟を上げることのできる少し広がった草地があったので、その日は船から下りた。林の中を歩いてみたいと思ってね。船を草地に持ち上げてしーとをかぶせた。テントを担いで、磁石を頼りに東に向かってともかく歩いた。
蔓の絡んだ木々の間を行くのはちょっと怖かったな、猛獣がいたら危ないから、銃をもっていた、キトリスで手に入れたんだ。
食べられる木の実などを、教えてもらっていたから、見つけたら、食べるか、リュックに入れた。テントを張るところがあるようなら、そこで一夜を明かし、船をおいておいたところに戻るつもりだった。
かなり歩いた。日本の森をイメージすると、全く違う。ともかく湿っている。所々に湿地があって、足を取られないように気をつけた。三時間も歩いただろうか、なかなかテントを張るのに適したと思われるようなところがない。船を引き上げたところに戻った方がいいだろうと、思ったときだった。ぴちゃぴちゃと言う、獣の歩く音がした。どんな猛獣が出てくるかわかったものじゃない。銃を手に持ち替えたとき、俺の周りは、すでに取り囲まれていた。
周りにいたのは、獣ではなく、身長が百五十センチほどの原住民だった。荒い繊維で織った布でできた半ズボンをはき、上半身は裸だった。だれもが茶褐色の筋肉が盛り上がった、力のありそうな体をしていた。顔は丸く、鼻が低く、広がっていて、目の大きな、アフリカの人に近い顔をしているが、髪は黒く縮れておらず、長くのばし、唇もあまり厚くはなかった。
彼らは俺をみて、なにやら言ったが、とても柔らかな声で、ゆっくりした話しぶりだった。
全くわからなかったが、俺は日本語で、こんにちわと、お辞儀をした。
そのあと、スペイン語でこんにちはと言ったのだが、彼らは、同じようにお辞儀をして、なにやら言った。全くわからない言葉だった。
彼らの中の一人が、森の奥をさして一言言ったので、俺はうなずいた。危害を加えるような連中には見えなかったんだ。奥にいきたいかと言ったと俺は感じたので、うなずいたのだが、うまく当たったようで、リーダーらしき男の手招きで、奥の方に進んだ。森の中の様子は全く変わることがなく、磁石で確認すると、少し南の方向に歩いたようだ。一時間ほど歩くと、小高い丘が見えてきて、煙がいく筋かあがっていた。この人たちの村のようだ。
近づくにつれ、草でふいた三角のテントのような家がたくさんたっているのが見えてきた。
やがて、木が切り倒され、広場が作られており、そこで、男たちがはいているズボンと同じ生地のスカートをはいた女性たちが竈の前でたむろしている。料理でもしているようだ。
リーダーが、こっちにこいと手を挙げたので、行ってみると、水が入った瓶がいくつも用意されており、彼は一つの瓶に両手を入れると、手を洗った。ほかの男たちもそれぞれの壷で手を洗った。俺はどうしたらいいのか迷っていると、リーダーが、まだ使ってない壷を指さし、手を洗うまねをした。俺にそれで洗えと言っているようだ。
俺が手を洗い終えると、丘に点在する家の一つに連れられていった。
出てきたのは、白髪の混じった髭を生やした男だった。老人と言うにはまだ早い感じだ。つれてきてくれた男が何か言うと、柔和な顔をして、手を伸ばしてきた。握手の習慣があるようだ。求められるまま、英語で、こんにちわ、自分は空間史朗といいます、と言ったんだ。彼は、よくいらっしゃった、私はウビエル、サンドライと英語で返答した。英語が話せるようだ。
後々わかるのだが、そこは、パシキア人と呼ばれる民族の部落で、独自の言語を持ち、自給自足で生活をしている人々だった。ウピエルは英語が話せた。おもしろい習慣があり、探検隊が来たりすると、家を提供し、探検隊の国の言葉を誰かが必ず教わることになっているという。アメリカ人が来たとき、ウビエルが英語を覚えたそうである。
今度は彼が私を尊重の家に連れていき、会わせてくれた。酋長は長い髭を生やした老人で、アリサイといった。彼は私に、空いている家を一つ提供してくれて、いつまで使ってもいいと言ってくれた。ただ、あんたの言葉を一人に教え、話せるまでにするように求めてきた。
俺は、十ヶ月後には日本に帰らなければならない、この村には半年ほどいて、イキトスに戻りたいと、アリサイにウピエルから伝えてもらった。アマゾンの支流の草地にボートを置いたことを言ったら、帰るまで安全なところに置いてくれると言うことだった。
その日、俺の歓迎の宴開いてくれた。広場に何十人ものパキシア人が集まり、肉を焼き、なにから作ったのかわからない酒を飲んで、陽気だが秩序正しく、話を楽しんでいた。
まず驚いたのは、肉を焼いたり、芋を蒸かしたり、特にたくさんの茸類を焼いていた。不思議だったのは、食べ物や酒の係りというものがいなかったことだ。誰かが自然にやっていることだ。指揮するものがいない。
俺はウピエルとアリサイに挟まれて、アリサイの言うことに俺が答え、俺の言ったことを、ウピエルがみんなに言うと、みんなが「おー」といったり、ある男がした質問を俺が答えると、その男が握手を求めてきたりして、その間に俺の器の肉がなくなると、誰かがもってきてくれる、一度ならず、長老のアリサイがいつのまにか自ら、俺に鮭をとってきてくれた。焼いた茸は醤油のような味の汁につけて食った。後で知ったのだが、魚から作った醤油だ。日本にもある魚醤(ぎょうしょう)っていうやつだ。魚醤油とも塩魚汁(しょっつる)ともいうな。
僕も秋田のしょっつる鍋というのは知っている。タイのナンプラーだ。
それで、竈の上の焼いている肉がなくなると、倉庫のような建物から肉を運びだし、竈の火の上に載せるのだが、一緒に飲んでいた誰かがやっていた。
もうひとつ。最初から驚いたのは、料理をするのは女だけではなく、飲んでいた男もいつの間にか立って、なにかをしている。もちろん、女も一緒になって飲んでいる。お互いに区別なく話しているようだ。皆、物腰が柔らかく、俺としてはずいぶん安心したものだったよ。
まあ、だけど用心には越したことがないと、与えられた家で、その晩はちょっと気にしながらシュラフに入ったよ。だけどそんなことは取り越し苦労で、朝になったら、パンが焼けているからと、さそいにきてくれた。昨日の宴会場の竈の上には、ちょっとナンに似たものが焼けていた。それになんとも柔らかいチーズが用意してあった。
ウピエルが来ていて、「チーズの作り方はヨーロッパの人が来て教えてくれました。イタリアの冒険家だったと思います。ここには、山の方に行くと山羊がいるので、そちらの部落の者が、山羊のミルクをもってきて、ここでとれた茸と交換するのです」
「昨日食べた茸ですか」
「そう、食べる茸もあるけど、薬になったり、楽になったりする茸があるので、彼らはそれを喜びます」
パキシア人の部落は俺のいたところだけではなく、いろいろ散らばっているようだ。
その日は、男たちとボートを止めたところまでもどって、水が増えたときの用心に森の中のちょっと小高くなったところに引き上げた。
帰りに、ウピエルが、生えていた一本の紫色の茸を指さして、ウットウットと言った。何だと聞くと、「これは、男に必要な茸で、我々の部族には大事な茸だ」と言った。
バイアグラのような作用があるに違いないと思った。
ウピエルはそれを採ると、肩に掛けていた袋にいれた。ほかの男たちも、茸を探しながら部落にもどった。昨日俺に会ったのは、茸を探しに着て、なかなか見つからなかったので、いつもより遠出し、珍しく川の近くまできたからだそうだ。
彼らは、いろいろな茸をとり、部落にもどると、倉庫のような建物の中で、仕分けをして、乾燥する棚に広げた。
アリシアが、日本語を学びたいという女がいるので、おまえのところにやると言っておいた、と伝えてきた。
俺は部落の中を歩いた。個人個人の家があり、女が子供をあやしていたり、男が家の修理をしていたり、だが、必ず俺が通ると、にこやかにお辞儀をした。俺が最初お辞儀をしたものだから、そうしてくれたようだ。
パキシア人は三食きちんと食べるようだが、昼はスープと果物だけであった。これもどこかの国の人間がきて、それを取り入れた習慣かも知れない。パキシア人は自分たちの生活に、新しいことを取り入れるのが得意なようだ。あのお辞儀を見ても、まさに俺がやったのを見ておもしろいと思ったに違いない。新しいものをすぐ生活に取り入れることができるのは、頭が柔軟の証拠だろう。
夕方食事の前に、ウピエルが女を一人連れてきた。麻のような荒い繊維で織った布のスカートをはいて同じ生地のランニングシャツのようなものを着ている。はちきれんばかりの乳房がシャツの脇からはみ出している。若そうだ。
パキシア人は皆丸い顔をしているが、彼女はその中でも横に楕円のような顔かたちだ。目は大きく、鼻と口は大きくはないが整っている。髪は黒く縮れている。
微笑みながら、ペルー語でこんにちはと言った。ウピエルは、この女の子をマノンカと、紹介して帰って行った。家の中に入った彼女は床の上に横座りになって、もってきたなめした皮を広げると、マノンカとパキシア語で書いて、自分を指さした。彼女が俺に炭を渡してくれたので、パキシア語で書かれた彼女の名前に「まのんか」と書いて、読んだ。彼女はうなずいて、俺を指さしたので、しろう、と書いてそういった。彼女がパキシア語であきらと書いた。これで、それぞれひらがなに相当するパキシア文字が推測できた。
まず、物の名前から教えた。キノコはパキシア語で、ポコリだ。彼女の年がわかった、十六歳だ。俺は二十一だと言った。長老のアリシアは六十五だそうだ。
彼女は毎日、朝食後すぐやってきて、俺のやることを手伝いながら、日本語をおぼえようとした。おはようとか、今晩はとか、挨拶はすぐに覚えた。動物たちの名前も覚えた。一週間たつと、動詞もかなりわかるようになった。主語、目的語、動詞といった、日本の言葉の並び方もわかるようになったのには驚いたが、パキシア語も同じようなので、覚えやすいらしい。さすがに、漢字はむずかしいようなので、書くのはひらがなを中心におこなった。半年いれば、漢字なども少しは教えられるだろう。
二週間ほど経ったときである。マノンカ俺を見てが、いく、という。スペイン語も少ししゃべるのだが、どうもよくわからない。彼女は英語のできるウピエルをつれてきた。彼は、マノンカは隣の部落の人間で、この部落に勉強に来ているところなのだが、父親の具合が悪いので、ちょっとケアーするために、家に帰る。二週間ほどしたら戻るということだった。
なぜマノンカが部落をでてこの部落に来ているのかとウピエルにきくと、十五をすぎた子供たちは二十になるまで、違う部落で生活をすることになっているという。一つには、違う環境に適応する力を養うためと、いい相手を見つけること、だそうで、希望によっては毎年、違うぶらくにいくこともできるそうである。
俺はノートを一枚切りとり、鶴を折った。マノンカも、ウピエルも驚いて見ていた。鶴を病気がこれで回復し、平和になるお守りだと、ちょっと脚色して、ウピエルに通訳してもらって、マノンカに持たせた。
彼女はずいぶん喜んで、自分の家に帰っていった。
ウピエルも教えてほしいと言ったが、紙があればできる、というとうなずいて、ほかの男と女数人を連れてやってきた。
英語でクレーンを教えてくれてと言って、彼はアメリカの週刊誌を俺に渡した。おっと、驚いたね、ここにきたアメリカ人がもってきた雑誌らしいが、ウピエルに言わせると、興味がないものだからこの紙を使いたいとうことだ。紙は貴重だが、この紙は役に立たないと言う。中をみると、ひゃっと、目をおおいたくなったが、ここの人たちは男も女も、顔色一つ変えず、興味を示さない。アメリカのアダルト写真の雑誌である。これで鶴を折って平和になるだろうか。いや、平和なのかもしれない。
破っていいのかと聞くと、もちろんいい、何でこんな写真を撮るんだろうと、言っていた。
みんなに破って一ページを渡し、正方形に切る方法を教え、それからいっしょに鶴を折った。
彼らは覚えるのが早かった。ただ紙を作る技術を持たない。出来上がった鶴を、皆大事そうに家に持って帰った。家のお守りにするという。
数日後、ウピエルがポコリの日だという。茸の日ということだ。三十日に一度、竈のある広場で、茸の薬をのみ、茸の料理を食べ、パキシアの神であるポコリコルシュファに感謝するという。その日には、ほかの部落からも人が集まり、ここのポコリコルシュファに挨拶をすると言う。それぞれの部落で同じ祭りが違う日に行われ、ここの部落の者も、仕事がなければ行くという。
その日は部落総出で、食べ物を作り、倉庫から茸を出してきて、煮たり焼いたりした。数人の男たちは夕方までかかかって、新たにたくさんの茸をとってきて、大きな切り株の上に積み上げた。
その前に篝火を焚き、だれ彼ともなく、手の空いている者から、積み上げた茸に、手をあわせた。
ウピエルにきのこの山に対して、皆はなにをしているのかきくと、ポコリコルシュファに、健康で楽しく日々が暮らせるようにお願いしているということだった。茸を積み上げたものが、神、ご神体というわけだ。
長老のアリシアが、集まった者に声をかけた。何人かの人たちが順番に並び、大きな木の葉の上に並べられた、乾燥した茸を一つ選んだ。その人たちは草原に腰をおろした。アリシアのあいずで選んだ茸を食べ始めた。赤い大きな茸がなくなると、誰かが倉庫にとりに行って木の葉の上においた。
俺はどうしたらいいかわからなかったので、列に加わらず見ていた。かなりの人たちは並ばないで見ている。ウピテルが赤と黄色い茸をとってきて、「おまえはどこか悪くないか」と言った。体の調子はとてもよかったので、「ない」と答えると、彼は「俺は腹がちょっと悪いのと、目が疲れるので、これを食うんだ」と赤い茸と黄色い茸を食べ始めた。
どうも祭りは、薬になる茸を食べることから始めるようだ。それが終わると、アリシアが酒を飲み、みんなももらって飲み始めた。後は自由である。
そこに他の部落から数人の人たちが来た。その人たちはこの部落の人に、挨拶を始めた。俺は挨拶の仕方にとても驚いた。他の部落からきた家族が、ここの一つの家族と挨拶をしたときのことを話そう。
赤子を抱いた母親と父親が、知り合いのこの部落の、やはり赤子を抱いた母親と父親のところに行くと、父親同士は後ろをむいて、尻をつきあわせて、こすり会わせた。赤子を抱いた母親は、相手の母親と前向きで、前のところをこすり会わせた。実に奇妙だった」
そこまで、話して、彼は僕に「ボノボ」っていう猿を知ってるか聞いた。僕は知っているよとうなずいた。ボノボは高等霊長類で、ピグミーチンパンジーと呼ばれる、アフリカの猿だ。雄同士がマウンティングをして、お互いを認識する、雌同士は前をこすり会わせる、ほかほかと呼ばれる行動をする。本来は性的な行動が相手をなだめ、挨拶として、変化してきたといわれている。
「ボノボの行為とよく似てるんだな、それでどうしてそんな挨拶をするんだ、とパキシア人に聞いたら、絶滅した猿も同じようなことをしていた、と答えたんだ。彼らは猿の動きをまねたのだ、彼らの祖先はその猿だったのかもしれんな」と、彼は言った。彼の話はそこで終わりではなかった。
「それで、ほかの部落の父親は赤子を抱いた、ここの部落の母親に挨拶をした。男は半ズボンの前から、自分の陽物をだすと、母親のスカートの中にいれ、腰を振ったんだ。母親は片足を持ち上げ、相手の男の手が足を支えていた。明らかに性交をしていた。逆も同じことをやっていた。それが男と女の親愛の挨拶なんだ。ほかのところでもやっていた。
それから、酒を飲み、料理を食べた。キノコ料理を食べると、皆ゆっくりとしたテンポで踊り出した。俺も茸を食べたら、なんだかほんわかとしてきたんだ。茸の影響だろうな。部落の仲間同士でも、男同士は尻をこすり会わせ、女はスカートの前を会わせてこすり会わせた。女が片足をあげ、男が陽物をスカートの中に入れた。激しく腰を振っているのだが、その男女ともただにこにこしているだけだった。射精している様子もない。挨拶が終わると、男は大きくなったままの物をズボンにしまっていた。
そのとき、マノンカが自分の部落から帰って来たようで、俺のところに来て、片足をあげたんだ。驚いたね、どうしたらいいんだかわからずにいたら、マノンカが俺のあそこを指さしたんだ。縮こまってたよ。するとマノンカの手が俺のズボンに差し入れられたもんだから、急に膨らんじまった、すると、マノンカは笑顔で、俺のをひっぱりだすと、スカーとに入れたんだ。それで下履きをつけていないことがわかった。おれっは。あっという間に果てちまった。マノンカが「きゃー」と大声を出した。まずいことしたと思ったら、ウピエルがよってきた。マノンカに何か言った。マノンカは笑って俺を見ていた。俺はどうしようと、ウピエルを見ると「やあ、おめでとう、すごいもんだ、これで、マノンカはあんたの嫁だ」
といった。責任をとれと言うことかと思ったが、男たちがよってきて、俺の尻に尻をこすりつけて何かを言うんだ。ウピエルに聞くと「大した男だ、日本人はすごい、と言っているということだった。
訳が分からなかった。
それから、マノンカは俺と一緒に住むようになった。おかげで、俺の生活は楽になったし楽しくなった。彼女はめきめきと、日本語が上手になった。おれはあと三ヶ月で部落を離れなければならないことを言ったが、マノンカはうなずいて笑顔で、わかってる、と答えた。
残りが二ヶ月ほどになったとき、長老とウピエルがやってきた。長老の言うことを、ウピテルが通訳してくれた。マノンカも聞いていた。
俺にある夫婦のところに行って、子供を授けてほしいと言うんだ。なんでも、パキシア人はなかなか子供が授からないそうだ。結婚するのは自由だが、なかなか授からず、一人に戻るカップルが多いのだそうだ。
それで、俺がその夫婦のところに行ってどうするんだときいたら、子供を作ってほしいという。
不妊の夫婦に精子を提供するような物なのだろうかと、想像したが、よくわからない。
マリンかは「ぜひいってください」と笑顔で言うし、行くことにした。
ウピエルと一緒にその家に行くと、夫婦が喜んで迎えてくれた。
夫は俺と尻を会わせた。奥さんとはとはどうしたらいいか、ちょっと迷ったが、男と女の挨拶をしたよ。ともかく俺は射精しそうなのを、かなり我慢してたったまま奥さんと交わった。それが挨拶なのだ。
ウピエルが通訳してくれたところによると、結婚して三年になるが子供はできない、夫はウットウットをたくさん食べてもだめだという。ウットウットは紫色の茸でウピエルが大事な茸だと教えてくれてものだ。そこの家にも、ウットウットがおいてあった。
夫は俺の見ている前でウットウットを生のまま一本かじった。すぐにズボンの前をあけると堅く大きくなった物を取り出すと、たったまま奥さんの中に入れた。賢明に腰を動かしていたが、おそらく三十分もそうしていただろう、夫婦ともつかれたようで、離れると、夫は堅くなった物をズボンにしまった。何か言った。ウピテルが、夫はこの茸は効かない、と言っている、しろうなら大丈夫だろう、助けてやってくれ」と言った。
どうしたらいいのだろうかと思っていると、奥さんが、おれのズボンに手を入れて引っ張りだすと、自分のスカートにいれた。そのまま交わって、奥さんが腰を動かしたら、マノンカのときと同じように、あっという間にはてちまった。奥さんは嬉しそうに、微笑んだ。夫がありがとうと、パキシア語でいった。とても喜んでいる様子だった。そのころ、俺も少しはパキシア語がわかった。
ウピエルも喜んだ「おまえはすごい」といった。俺は不思議に思ったことを聞いた。ウットウットはどんな作用があるのか知りたかったのだ。彼の話では、パキシア人の男は一時間交わっていても射精ができず、この茸を食べると、三十分ほどで射精ができるようになるという。だが、茸が効かない者も多いそうだ。ともかく、こどもを絶やさないようにすることが、大事だと彼は言った。
俺は自慰をしないのかと言ったら、いくら試みても射精しないそうだ。
俺が想像するに、挨拶にしかもちいられなくなったことから、脊髄にある射精の反射の仕組みが退化しつつあるのだろう。
それで、その夫婦のところには毎日かよって、夫の前で交わって射精をして、感謝されたんだ。子供ができたら大事に育てたいと言っていて、俺が部落から離れる頃、子供ができたようだと喜んでいた。
ところでな、ウットウットという紫色のポコリは、俺みたいにこらえることができない男が食べたらどうなるか知りたくてな、ウピエルに言って、もらって食べてみた。すると、いきなりあそこが膨らんで、頭の中が快楽に満たされて、何度も射精が繰り返されたんだ。おどろいた効果だよ。夢精を引き起こすんだ。
ともかく、性に関して全く我々とは違う思いを持っていることがわかった。部落を離れるとき、マノンカも妊娠していたが、七から八人の奥さんが俺の子を宿していたんじゃないかな。どうなったかわからないが」
そう彼は話した。そして、祭壇のところにあった干した茸を一つくれた。
「これがウットウットというポコリだよ、乾いたものだと一本必要ないんだ、ちょっと削って、お茶にでもいれて飲んでみろよ」
「すごい経験したんだな、それで、卒業した後どうするんだ」
「唐津のおやじの会社を継ぐことになると思うよ」
その日は、そういう話をして、彼のマンションをあとにした。彼の話は事実なのだろうか。それにしても、そのような部族がいることを聞いたことがない。アメリカやヨーロッパの探検者も訪れているというのだから、そのような珍しい習慣のある部族なら、雑誌やメディアが取り上げていても不思議はないのだが。
そう、それと、彼の首の傷のことを聞くのを忘れた。かなり目立っていたから、大きな怪我のはずだ。彼はその話をしなかった。
信じられない気持ちで、四畳半の下宿に帰り、夕方いつものように食事をした後、公務員試験の受験のための勉強を終え、彼のくれた、干したアマゾンの茸を少し削って、お茶に入れて飲んでみた。
それは驚いた反応だった。頭の中に快楽が走り、下の物が膨らみ、あっという間に下着の中に放精してしまい、また快感が頭の中を満たし、気がついたときはお茶を飲んで一時間たっていた。私はのろのろと、風呂につかり、布団にはいった。
そのことがあって、彼の話したことへの疑いは霧が晴れるように、なくなっていた。
次の日、彼に茸の効き目はすごかったと話した。彼は、そうだろう、使いすぎると頭がつかれるぜ、と言っていた。
五月の連休があけ、大学にでると、級友が私を呼び止めた。その男は「空間と仲良かっただろう、空間が大学どうして辞めたか知ってるだろう」と言った。
しばらく空間とは連絡をとっていなかった。
私は「いや、初めて聞いた、電話してみよう」と携帯で彼を呼びだした。しかし、この番号は今使われていないというアナウンスがながれるだけだった。
「でないな、俺は聞いてないよ、おやじのあとを継ぐと言っていたから、唐津にもどったかもしれないが、それにしても、電話も変えているのはどうしてかな」
「そうなのか、おまえもしらないのか」と級友は言った。
それ以降、空間と話すことはなかった。私は無事、公務員総合職試験にうかり、念願の外交官の道が開け、外務省にはいることができた。二年外務省内で、諸々の仕事をさせられ、二十半ばのときに、ノールウェーの日本大使館に、三等書記官で赴任した。大学時代、外交官をめざしていたこともあり、大学で、他学部だが、文学部の北欧の言葉と、東欧の言葉を任意科目で受講してた。ノールウェーとハンガリーのことばである。そういったこともあり、まず、そこで語学や歴史、風習、それにもっとも大事な人間を学ぶつもりだった。
ノールウェーは漁業国で、日本と似たところがある。ハンザ同盟の発祥の国で、長い貿易の歴史がある。ノールウェーという国はいればいただけ好きになった。年に何度も他の国の大使館の人たちとも集まりがある。赴任して七年がすぎ、二等書記官になっていた。そのまま、ノールウェーにいてもいいくらいに思っていた。
毎年、ノールウェー外務省の招待で、大使館の大使たちのパーティーがあり、私も大使とともに、いつも参加していた。海の珍味とワインの立食パーティーで、会場はもりあがっていた。そういったパーティーではいろいろな国の人たちと話ができて、楽しい。基本的には英語で話すことが多い。
小皿に入ったキャビアをとって、テーブルに戻ろうとしたとき、大使が私を呼んだ。そばにちょっと日本人にも似ている背広姿の男性がたっている。大使は私をその人に紹介した。その上で、彼が、ペルーの領事で、隣にいる小柄な女性が奥さんだと、私に教え得てくれた。領事と握手し、奥さんは、「こんにち」はとぎごちない日本語で挨拶された。見ると小柄な、丸顔の目の大きな女性だった。焦げ茶色の肌をしていて、健康そうな、はちきれそうな体をしている。
「奥さんは、リマの大学で日本語を学んだそうだ、領事もいずれ、日本のペルー大使館に行きたいと考えている、奥さんが日本語をしゃべりたいそうだから、お相手してあげてください」と大使が言った。ペルーの領事も日本語で「よろしく」と頭を下げた。
奥さんはシャンペンを飲みながら、
「マノンナです、よろしく」と自己紹介された。
私も名前を言って、挨拶をして、「日本語がお上手ですね、どこで習いました」と聞くと、「リマの大学です」と答えた。
「あなたはどこの大学ですか」ときいたので、卒業した大学を言った。
「私、その大学の一人の日本の男性知っています、かわいそうに、私たちの生活の習慣を間違えて、もう少しで死ぬところだったのですが、助かって日本に帰りました」
「どうしたのですか」
「その人は、一人でアマゾンをくだって、我々の部族のところにきました。それで、われわれの部族の習慣として、訪ねてきた人の国の言葉を教わるのです、その人は親切に日本語を教えてくれました。おもしろい言葉なので、何人か習いました、私は十六歳でしたが教わりました」
ちょっとびっくりして、空間を思い出した。
「もしかしたら、奥さんはパキシアのひとですか」
「よくご存じですね」
彼の名前はださなかった。
「私たちパキシア人は、変わった挨拶をします。男性同士、お尻をすりあわせ、女性同士、前の方をすりあわせるのです。すりあわせるといっても、必ずしも本当にこすらずに、離れてちょっとお尻をふったり、前を振ったりするだけです。男性と女性も挨拶をします。男はズボンの前に手をかざし、女性もスカートの前で手をかざします。見た目には、性的に見えるのですが、男と女がふれるのはタブーです」
空間が言っていたのとはだいぶ違う。
「そのような風習は、今では、飲んだときや、よほど仲のいい仲間だけの間でみられるだけで、あまりおこないません、日本の彼が来たとき、彼に見せる為に、皆がやって見せたようです。
我々の村は、いろいろな神を祀っていましたが、それぞれの神に、茸を供えました。いろいろな茸があって、薬としても使っていたのです。もっとも珍しくて、不妊の夫婦に利く茸があります。部族の長老が、その日本人にもその茸をちょっと食べさせました。すると、彼は急におかしくなり、部族の女性を追いかけ回し、男たちに取り押さえられました。女性を触ったということで、男の人たちは、森の中の木に縛り付けろと息巻きました。森にはいろいろな生き物がいます。ほとんど生きていることができないでしょう、一晩生きていれば、そのまま放免になります、ところが長老は、わしが食べさせた茸が、日本人にはおかしくさせる物だったのだ、わしにも責任がある、森でなくともよいだろうとおっしゃったので、広場に縛られて転がされたのです。蛭やダニがたかったりするでしょうけど、気持ちが悪くても死ぬことはありません、ところが、彼は運悪く、蛇に首を深くかまれました。肉が腐る毒をもった蛇でした。
ただ運が良かったのは、朝のことだったので、見つかったときは、かまれて時間がたっておらず、見つけた男がかまれたところをナイフでえぐり取りました。首の動脈を切ったらしんでしまいます。だけど男たちはうまいもので、必要なところだけくりぬきました。それでも毒が残り長い間彼は苦しみましたが、助かり、放免されたのです」
「その茸はあなた方にはどのような薬になったのですか」
「不妊症の女性は排卵周期が安定し、無精子症の男性には精子を作るようにさせます」
「すごい薬ですね」
「あまり生えることはありません、めったにありませんが、たくさん採れることがあります、すでに国が調べました、ホルモンと同じように働く物質が入っているそうです、同じ物質ではありませんが、すでにそういった薬はいろいろ開発されているそうです」
彼は部落から船のところに帰る道で茸に出くわしたのかも知れない。それにしても日本の男にはすごい効きかたをした。その成分は何だろう。
「私は、日本に行ったら、その人を捜すつもりです」
「どうするのです」
「とてもいい人でした、私は彼に日本語を教わったので、リマの大学に行く気になったのです、恩人です、お礼をいいます」
「そのときはお手伝いしますよ」
それから彼女は日本のことを知りたがった。
パーテイのあとも、たびたびペルー大使館によばれ、大使と奥さんにごちそうになり、日本の話をした。
奥さんは、私がシェーファーの万年筆を持っているのに気がついて、「それ、部落にきた日本人がもっていたのと同じです」と言った。私はそうですか、と笑った。心中では、空間は自分の万年筆を、リマで買ったと言っていた。本当は自分の使っていた物をくれたのだ。
彼は話を作る癖があったようだ。決してうそを言うつもりなのではないのだろう、芸術家に近い。唐津で陶器の修行をしていたのなら、きっと個性的な作品を作り出していることだろう。
それから二年後、ノールウェーのペルーの大使は、日本の大使館の大使として赴任した。奥さんから時々メイルがはいってくる。
日本では夏休みの季節である。北欧は稼ぎ時、観光客がどっと押し寄せる。日本からの観光客も多く、トラブルや病人が増え、大使館は忙しくなる。
そんなとき、マノンナからメイルが入った。日本語を教えてくれた男性がわかったということだった。空間という人で、九州で陶芸家になっていたということだった。九州に行って、会うことができたという。彼も覚えていてくれて、喜んでくれたという。
彼の作品と、彼の写真が貼付されていた。髭を顔中生やして、熊のような顔になっていた。作品は彼らしい、想像力に富んだデザインだった。紫色の茸が一面に飛び跳ねていた。
この茸がウットウットという、不妊に利く茸です、とマノンナの説明があった。
アマゾンの茸


