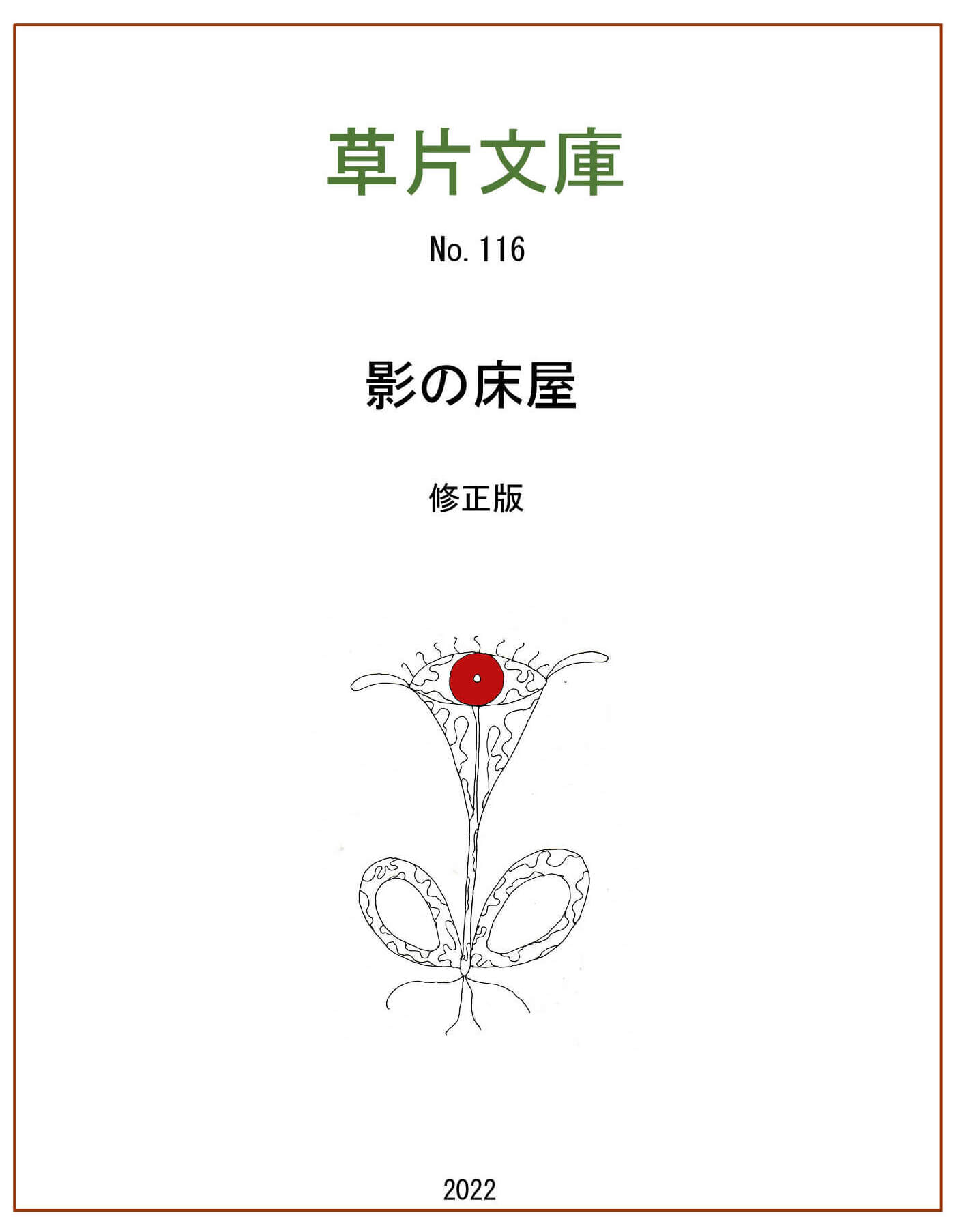
影の床屋
そろそろ床屋に行かなくては、そう思い立ち、いつもの床屋へいく道を歩いていると、どこかで見たことのある老人が近寄ってきた。つるっぱげの頭を光らせ、ロイド眼鏡をかけている。
「おにいちゃん、そろそろ散髪だねえ」
声を聞いて思い出した。田舎の実家の近くの床屋の主人だ。小学校から高校まで、その床屋に通っていた。
「おじさん、なんでこんなところに」と聞いたところ、近くで床屋を始めたという。自分が小学生の頃には、すでにつるっぱげであった。まだ五十代だったのではないだろうか。それにしても今はいくつになるのか。自分が七十五だから、百はゆうにすぎていることになる。よく似た人なのかと思い、どこにあるのときくと、目の前に、赤と青の筋がくるくる回っている、石造りの床屋あった。昔のままじゃないか。
とうぜんはいるものと、床屋の主人はかがんで、戸を開けると、笑顔になった。
中も昔と変わらない。体が自然に動いて、少し裂け目のある擦れた革張りの椅子に腰掛けた。
椅子の前には木枠でできた大きな鏡がおいてあるはずである。
小学生の頃、自分の顔を鏡で見るなんてことはめったにない。鼻の頭におできができたり、ほっぺたを虫に刺されたときぐらいなものである。
床屋の鏡で自分の顔を見ると、なんと小さな目をしているのだとか、どうも鼻が大きいとか、友達の整った顔をおもいだして、ちょっとしょげたものだ。中学、高校になると、そんなことより、髪の出来上がりの方が気になってきた。顔の造作は親譲りで、しょうがな物だと理解し始めていたのだろう。頭の方もそうなのに、髪型を意識しはじめていた。まあ、年頃で、誰もがそんなものなのだろう。。
ともかく、床屋の椅子の前には大きな鏡がなくては始まらない。
ところが、その床屋の椅子の前に鏡はなかった。しかも、椅子の座るところは皮でできているところまでは昔と同じだが、社長が座るようなどっしりした椅子ではなく、回るようにもできておらず、横に寝るように動かすこともできない普通の椅子だった。床屋の椅子じゃない。
昔の床屋を思い出して、中が同じと思い込んでいたようだ。
そう思っても、とりあえず椅子に座っていた。
目の前には白い漆喰の壁があった。
「ぼおや、大きくなったね」
床屋の親父さんはハサミを持って、わきに立った。なにやら壁のスイッチを押すと、腰掛けている椅子の後ろから、太陽の色の光が当たり、椅子に腰掛けている自分の姿の形が、漆喰の白壁に映った。
「どんな頭にしようか」
小学生の頃はおかっぱで、中学になると、前髪をおかっぱではなく分け目をつけて七三にした。
「もう薄くなっちまったけど、一応、七三に」
「中学と高校のときと同じだね」
そういいながら、床屋の主人は、ほとんどない髪の毛の周りにハサミを動かした。
できたよ」
自分ではわからないが、壁に映った自分の頭の影はそのようでもある。
「もしよかったら、下の方も学生服を着た形にしようか」主人は言った。
意味かわからずにいたのだが、自分の悪い癖で、相手の言っていることがわかっていないのに相槌をうってしまう。自分はうなずいていた。
「それじゃ立ち上がって」
自分はいいなりに立ち上がると、主人は椅子をわきに引いた。
立っている自分が壁にかげとして映っている。
はさみを自分の体に沿って、チョキチョキ言わせてうごかすと、「どお」といった。
前を見ると、七三に髪を分けた、詰め襟の学生服を着た自分の陰が立っていた。
「ありがとう、おいくら」
「三百円」
あのころの値段なのだろうか。
「毎日くれば、毎日違う形にできるよ」
僕はうんとうなずいていた。
外にでると、もう夕日が沈むときで、中学生の頃の自分の影は細長く、歩道の先まで伸びていた。
若々しい影で、せめても影だけでも若いと気分は悪くない。
家の前までは影が見えたが、玄関にはいると、消えてしまった。
薄暗くなったので、壁のスイッチを押すと、自分の影が、床に丸っぽくできった。やはりお日様の陽でできた影じゃなければだめなのかと思って、明日が楽しみになってきた。
朝早く、幸いに天気が良かったので、散歩にでた。朝日が後ろからさしてきて、自分の前に中学生の影ができたのだ。若いなと思ったが、なぜか薄かった。散歩からもどり、門に入る前に、後ろを振り向くと、伸びているのは、今の自分の禿っぽい頭で腰が少し曲がった自分の影だった。
たった一日しかもたないのかと、ちょっとがっかりして、まだ開いていない床屋に行って、入り口をたたいた。寝ぼけ眼のおやじさんが、開けた窓から顔をだし、八時からだよと、ぴしゃりと窓を閉めてしまった。
そりゃそうだと、自分の勝手さを反省して、八時を過ぎてから、床屋に行った。
「影は一日で消えるさ、一週間持つ影は千円だよ、よく頼まれるのは、三百円の一日もつやつだ、毎日影を刈にきて、気に入った形になったら、千円で一週間用にかえるさ、ハサミが違うんだ。もしずーとそうしたければ、一万円だ」
一万円は安くはないが、ずーっト若いままだと、いつか疲れるかもしれない。
「影はどんな形にでもできるのですか」
「おーさ、アメリカの大統領でも、マリリンモンローでもいいよ、ただほかの人間にするのは五百円」
「それじゃ、死んだかみさんの影にしてみてください」
そう頼んで見た。
「ぼおやも大きくなったものだね」
そう言って、おやじさんは椅子に案内してくれた。
チョキチョキと、ハサミを忙しそうに動かし、あっという間に影を刈ると、影は三年前の死んだ家内になった。
五百円払って、外にでると、お日様を背にするように歩いた。自分の影はかみさんの形になった。なんだか昔一緒に歩いたときのような気分になった。影を作りながら歩いていたら、知らないところに来てしまった。
辺りをきょろきょろ見回すと、どこかのお寺のお墓だった。よく見ると自分のお寺だった。ついでだから、家内の墓に手を合わせて帰ろうと思ったのだが、自分の寺は確か電車を乗り継いで、三時間ほど離れた町にあるはずだった。
どうしようと考えていると、家内の形をした自分の影が、すーっと墓の中に消えていった。影はまた自分の形に戻っていた。
すると、自分は家の玄関に立っていた。
そうか、影の行きたいところに行けるのかもしれない、と思って、次の日、八時よりちょっとから床屋の前で開くのを待っていた。
「ぼおや、またきたのかい」
「うん」
椅子に座っていった。
「ガリレオ」
と千円札を出した。
おーそうかい、ガリレオガリレイか、それはいい、それはいい、と言いながら、床屋のおやじは僕の影をチョキチョキ切って、ガリレオにしてしまった。
そのまま、朝日を背にあびて、どんどんどんどん歩いていったら、何日かかったかわからないのだが、イタリアのフィレンツェについて、フランシスコ教会にはいっていった。あった、ガリレオの墓が、向かい側にはミケランジェロの墓がある。
子供の頃望遠鏡がほしかった。クリスマスの朝、靴下こそなかったが、小さな天体望遠鏡が枕元にあった。その日は一日中、なにも食べなくてもいいくらい嬉かった。それで月を見た。ガリレオが作ってくれた望遠鏡だと両親は言った。
ガリレオは木星の惑星や、太陽の黒点を発見した。墓の前に来ると、自分の影のガリレオが立ち上がって、ガリレオ自身が作った望遠鏡を貸してくれた。僕は夜になるのを待って、木星の惑星を見た。朝になった、ぼんやりとだが見えた。太陽に望遠鏡を向け、紙に映した。黒点が見えた。嬉しさのあまり、ガリレオの墓を見た。僕の影のガリレオが伸びて、墓に入っていった。僕の影は僕になった。
自分の家に戻っていた。
自分の半生を振り返ると、ガリレオのおかげで、天文学の道にはいり、何万光年も向こうの新しい星を観察し、新たな法則も見つけることができた。
明日は自分の影を最後の形にしてもらうことにしよう。
いい天気だった。秋晴れのさわやかな風の中で、床屋に向かった。ちょっと立ち止まって、背中から朝日を浴びた。自分の影がすーとのびた。もう自分の形の影をみることはない。
「おはようございます」
「おはよう、きょうはどんなかたちにするかい」
床屋のおやじが聞いた。
「最後のお願いします」
一万円札をポケットから出した。
「そうかい、それじゃ、死ぬまでその影にしてあげよう、簡単でね」
床屋の椅子の前に自分の影が映し出された。
床屋のおやじは、ちょきちょきを四回繰り返すと、できたよ」
と言って、僕を立たせた。
床屋の壁には僕の影が長四角に映し出された。
「いい形にできた」
「ありがとう」
床屋のおやじの笑顔がだんだん消えていった。
床屋を出ると、家とは反対の方にあるいた。家は東の方にある。これから、ずーっと、太陽の日を背に浴びて歩いていく。影は長四角のまま自分の前をすすんでいく。棺桶の形をしているのだ。
寿命がつきたとき、僕は自分の前にあるカンオケの影の中に入っていき、消滅することになる。誰にも知られることもなく。
今は太陽を背にして歩くだけである。
影の床屋


