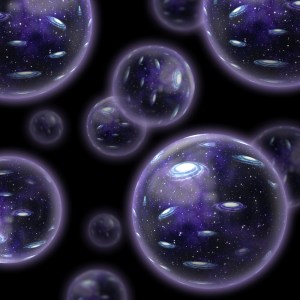第14話
『刑事の物語』
1
連日続く雨で、ビシャル・オル刑事のトレンチコートは濡れていた。署内の床にしずくを垂らしながら、自分のデスクに向かっていた。
鼻の下にたくわえた卑下も濡れていていた。
「例の鑑定結果、デスクに上がってますよ」
若い、白人の刑事がガムをかじりながら、別の事件の資料を見る片手間で伝えてきた。
ビシャルはゴツい指を上げて頷くと、デスクに到着するなり椅子を引き、無造作にトレンチコートを背もたれにかけ、検死の結果に眼を通す。
「鋭利な刃物で腹部を切り裂かれ、内臓は見事に取られてる。顔には大きく逆さ十字のマーク」
「一連の事件と同一犯だよ」
目の前に座る相棒、40代の黒人アルト・コバックがボールペンをデスクにカタカタと落とし、遊びながら言った。
事件は年が明けてすぐに発生した。被害者に今のところ関連性はなく、共通しているのはその残忍な殺し方だけだった。鋭利な刃物で身体を引裂き、内臓を、肺までも全部抜き取り、顔に逆さ十字の傷跡を残す。
3月までに犠牲者は5人であった。
近年まれに見る事件の残虐性に、マスコミも飛びつき、警察の無能さ、憶測、デマが流れていた。
アンチキリスト。
この見出しが堂々とネットやマスコミに拡散され、事件はさらに拍車をかけて注目の的になっていた。
遺体の資料を見ながらビジャルは、
「言わせたいやつにはいわせとけ。興味本位に捜査を撹乱してるだけだ」
と、相棒の言葉を一蹴した。
そこへアラームがなる。デスクへ備え付けの固定電話からであった。
アルトが新聞を無造作に置き、受話器をとる。
「すぐに現場に向かう」
受話器を素早く、あらっぽく置くと、アルトは立ち上がりながら、口早に行った。
「朝から神様は仕事しろとさ。また同じ手口の死体だ」
検死報告書をデスクに置き、ビジャルも濡れたコートに再び腕を通すと、馴れ馴れしいと言いたげに、重い足取りで、署をあとにした。
第14話−2へ続く
2
事件現場は家畜小屋だった。
署から20キロも離れた場所に位置する農場の、今は使われていない家畜小屋。
古い藁が無造作に置かれ、コンクリートの壁は日々が入り、トタン屋根は剥がれて、雨が吹き込んでくる。
傘もささずにやってきた2人組の刑事は、現場を見るなり、一連の事件と同一犯の犯行だとすぐに、遺体を見て理解した。
鑑識たちは淡々と現場の証拠を集めていたが、若い現場保存のために近くにレインコートを着て立っている警察官は、今にも朝食を吐き出しそうな白い顔色をしていた。
一瞥してビシャルは現場に入った。
相変わらず見るに耐えない遺体の状況に、ため息を漏らす。
「なにか犯人の遺留品でも出ればな」
なんの手がかりもない、血まみれの事件現場を見て、黒人刑事はゆっくりと目を閉じた。
神を信じるアルトは、心中で神への祈りを捧げていたのである。
その横で遺体を見ていたビシャルは、あることに気づいた。
「口の中の液体は採取したか」
鑑識の1人の胸ぐらを掴み、強引な聞く。
アジア系の鑑識は、頷き採取したことを言葉で伝えることができなかった。それだけビシャルの迫力がすごかった。
鑑識の服をあらっぽく離すと、遺体に藁を踏みしだきながら近づき、白目を剥き、絶叫に口を開けた、土色の女性の口の中を覗き込んだ。
そこにはタール状の黒い液体が満ちていた。
初老の刑事は濡れたトレンチコートを開き、さらにその下のグレーのスーツの内ポケットに、太い指を入れたが目的の物がないことに気付き、急ぎ相棒に手の平を差し出した。
「ペン持ってないか」
黒人の相棒は、しかたないな、と言いたげに眉をひそめ内ポケットから安いボールペンを抜き出し、ちゃんと返してくれよと言いたげな顔で渡した。
それを奪うようにビシャルは受け取ると、女性の口の中にボールペンをゆっくりと差し込み、口を満たしている黒いタール状の液体をボールペンに巻き付け、ゆっくりと引き上げた。
液体は糸を引き雨の湿気を帯びた冷たい風になびいた。
「原油か?」
相棒が冗談めいていうが、ビシャルはそんな冗談を流し、それがなんであるのかを見極めるべく、じっと見つめた。
すると一瞬だがタールの液体が波打つように、不自然に動いたように見えた。
「今の見たか」
「今乗って?」
相棒は見逃したらしい。しかしビシャルも今のが見間違え、風のせいだったのかもしれない、と思いペンについた液体をコートの裾で荒っぽく拭き、相棒にペンを返した。
嫌そうにそれを受け取った黒人は、もういらない、といった風にボールペンを納屋の、濡れた藁の上に投げ捨てた。
腰を上げたビシャルは周囲を見回し何か事件解決の手がかりがないかを、鋭い眼つきで探した。だがこれと言ってめぼしいものは見つからなかった。
「発見者の証言は取れてるか」
顔が青ざめている警察官に聞くと、今にも嘔吐しそうな顔と声で答えた。
「はい。第一発見者は納屋を修理するため、ここ数日、納屋に通っていたそうです。前日の午後九時まで納屋にいたと証言しております。その時はなにもなく、周辺で人の気配もなかったとのことでした」
これまでの事件の発生条件と同じだった。
これまで5人の犠牲者が出ているが、その場所は必ず人が出入りする場所であり、前日まではなにもなく、翌朝に死体が発見される。共通していた。
目撃者も、決め手となる証拠もない。狂った事件だけがそこにあるだけで、2人の刑事はまるで、何かに踊らされているような感覚に陥っていた。
*
署に戻った刑事たちは、コーヒーを飲む暇もなく、検死官に呼び出されていた。
署から数キロ離れた大学病院まで向かった2人は、地下の検死室に入った。
蛍光灯が目に眩しいほど明るく、ステンレスの検死台がいくつも並んでいた。
その1つにさっきの女性の遺体が乗せられ、検死官が2人を待っていた。
ガランとした消毒液の臭いがする室内にただ1つ、異形の死体があるだけの光景は、死体発見現場さながらの不気味さと異様さがあった。
検死官は身体を包む白衣と、ゴム手袋、ゴーグル、マスク、布の帽子をかぶった、いつもの作業着、といった様子で遺体のそばに立ち、2人を待っていた。
60過ぎの黒人検死官である。この事件は常に彼が検死していた。
「いつものご遺体と変わらんよ。内臓は綺麗にぬかれてる。見事なもんだ。研修医にも見習ってほしいものだよ」
相変わらず口が良くない。
「他に外傷は顔の傷以外にはない。性的暴行を受けた痕跡もないし、爪の隙間まで綺麗なもんだ」
検死官の言葉に、いつも思っていた疑問がアルト・コバックの中で再浮上してきた。
「被害者は抵抗せずに犯行を容認していたと?」
すると検死官は検死に使う道具が綺麗に並べられた台の上に置かれた、資料を一瞥した。
「薬物反応は出ていない。抵抗したあともない。俺の立場からはそれしか言えない。あとの捜査は、お前たちの仕事だろ」
くせ毛の頭を叩き、困った様子のアルト刑事。
ビシャル刑事はこのとき、遺体をただジッと見つめていた。何かに見落としがないか、事件解決につながる発見はないか。隅々まで遺体を観察していた。
「あの黒い液体は」
彼女の口の中に詰まっていた液体。それがこの事件の新しい手がかりになる。ビシャルは静かに、検死官に聞く。
「ラボに提出済みだ。2、3日中には結果がでるだろうよ」
そういうと検死官は手袋を脱ぎ、出入り口の自動ドアの横にあるゴミ箱に捨て、
「遺体は全部を語ってる。それなのに手がかりがないってことは、犯人は人じゃないかもな」
などと冗談を言い置き、部屋をあとにした。
アルトもこれ以上、ここにとどまっても収穫はないとお考えたのだろう、
「先に戻ってるぜ」
と、ビシャルに伝え部屋を去っていった。
1人残ったビシャルは、遺体の女性の顔、今は口も閉ざされている穏やかな顔を見つめた。
大きな逆さ十字の傷がなければ、美しい女性の顔である。
と、その時だ。刑事の視界の端に人影が見えた。顔を開げ周囲を見回すが、誰もいるはずもない。蛍光灯の白い光に照らされた、ステンレスの台が並ぶだけ。
気のせいか。そう思った彼の方を、誰かが掴んだ感覚がした。更に耳元で何語なのかわからい言葉で囁かれた。
ショルダーホルスターからシルバーのS&Wのリボルバーを抜き、周囲に照準を合わせて室内を見回した。
彼のワイシャツは冷たい汗ですでに濡れていた。
やはり誰もいない。
第14話−3へ続く
3
たばこの煙が部屋に充満していた。
ビシャルはヘビースモーカーであり、今の時代には窮屈な思いをしていながらも、たばこをやめることはできず、部屋でロックの安いバーボンを飲みながら一服するのが、いつもの疲れの取り方だった。
外はまだ雨が降っており、安アパートの薄い窓をたたいて、雫が滴っていた。
刑事になる幾度も不思議な経験をしてきた。ベテランと呼ばれる今までに数多くの死体を見て、凄惨な殺人現場を知ってきた。だからこそいえる。眼には見えない何かが必ず現場にはあるし、居る。しかしそれは確実に見える何かではなく、ただ水の中から空を見上げるようにぼやけている感じだった。
それが今日、あの検死台の前で起こった出来事、あそこまではっきりと何かの気配を感じたことはなかく、たばこの本数が考えれば考えるほど、増える一方だった。
すると上の階の住人が帰宅したようだった。
顔を合わせる程度の知り合いだが、ラテン系の女性でミュージシャンをしているらしいことくらいは知っていた。
ヒールを履いている靴音は良く響き、天井の中心まで音は続いた。ところがそこでピタリと音が止まったのだ。いつもならば、生活音が多少なりとも漏れ聞こえてくるはずなのに、今日に限って物音一つしない。
たばこの灰だけが増えていき、ビシャルは耳をそばだてた。
「わたしが気になるの」
黒板をひっかいたような雑音が耳をつんざき、視線を降ろすと目の前に上の階にいるはずの、髪の毛が波打った褐色の雨に濡れた肌の女性が立っていた。眼は白目を剥き、唇は震えている。明らかに正常ではない様子だ。
すると震えた唇が開くと、彼女の喉の奥から黒い液体がおびただしい量、噴射され、ビシャルは頭からそれを浴びせられた。
タール状の粘々とした液体を見下ろした彼。すると液体は生き物のように波打ち、ぷつぷつと泡立ち始めると、それが一斉に目玉へと変化した。それが彼を見上げ視線が合ったのだった。
悲鳴を上げたビシャルはそこで眼が覚めた。
いつのまにか寝入ってしまっていたらしく、指に挟んだたばこは灰に変わりフィルターだけが残っており、グラスの中の氷はすっかりなくなっていた。
上の階ではいつも通り生活音が響き、何一つ普段と変わらない日常になっていた。
だがビシャルのガタイのいい身体には、水を浴びたようにどっぷりと脂汗がにじんでいた。
第14話‐4へ続く
4
あの検死室で起こった奇妙な出来事。その晩に見た悪夢。それが頭から離れないまま、ビシャルは数日を過ごした。
相棒のアルトも長年、一緒に事件を追いかけてきたが、こんなにも疲弊したベテラン刑事の姿を見るのは初めてのことで、正直、どういう風に声をかければよいものか、数日間、迷っていた。
「ラボから例の液体に関する報告書が届いたぜ」
若いアジア系の刑事がアルトに報告書を手渡す。すまないな、と手を挙げて礼を示す黒人刑事。
するとそれを受け取った直後に、デスクから跳ねるように立ち上がったビシャルは、報告書を奪うように自分のものにすると、穴が空くほど報告書を眼をむいて凝視しながら読んだ。
しかし落胆がベテラン刑事の顔を覆い尽くし、報告書はアルトへ放り投げられるように返された。
デスクの上に放り投げられた報告書を読んだアルトも、その内容に眉をひそめた。
「鑑定不能? あの液体は水でも油でもないってのか」
ラボの最新機器を使っても、あの液体が何なのか判明しないということだった。
ただ有機体が含まれていることだけは、記載されていた。つまり何らかの体液である可能性があるということである。
だがそれも刑事たちの推測にしかならない。ラボはあくまでもデータを提示するだけ。
「結局、進展はなしか」
アルトが落胆の顔で両手を後頭部に回す。
その時、電話が鳴った。それが狂気の叫びに2人には聴こえた。
受話器を取ったアルトは、ビシャルを見やり頷いた。ししかしその顔は一瞬にして曇った。
受話器を置くとアルトは口を重く開いた。
「3番街の教会の扉に死体が貼り付けられてるらしい」
その教会ならビシャルはよく知っていた。幼馴染が神父をしている教会である。幼い頃からよく行っていた教会だからこそ、ビシャルの表情は日頃よりも鉛のように、重くなっていた。
*
雨は降っていないが空気は湿り気をおび、空は落ちてくるような雲が黒く垂れ込めていた。
現場は凄惨たる有様だった。凄惨、その言葉しか形容のしようがなかった。
教会の入口、木製の観音開きの扉に、両手両足を太い金属の杭で貫かれて打ち付けられた死体は、全裸の若い女性だった。
身体は胸から下腹部まで切り開かれ、内臓は抜き出されていた。股間からは血が今も滴っている生々しさである。女性はまだ20代のようだが、その顔は悲鳴を上げたまま硬直し、見開かれた眼は白目である。
ところがこれまでになかった特徴もあった。周囲が血まみれなのは言うまでもないが、その空っぽの腹の中に、血液に混じって、例の液体が溜まっていた。それは教会の扉に書かれた神を呪うヘブライ語にも使用され、真っ黒い液体がヘブライ語から垂れていた。
教会の入り口は小さい扉がもう1つ、教会の側面に設置されており、警察官はたちはそこから、教会内部と外を往復していた。
死体の検証はアルトに任せ、ビシャルはもう1つの出入り口、木戸から中に入って行った。そこは幼い頃、よく遊んでいた教会の思い出の場所でもあった。
第14話−5へ続く
5
教会内部は広く多くの木製の長椅子が並べられ、正面の幅のあるコンクリートの通路から入ってくれば、正面に聖書の様々な場面が描かれたステンドグラスが、来るものを出迎え、その手前に設置されたキリスト像を、浮かび上がらせていた。
キリスト像の前には多くのロウソクが捧げられ、その手前に、跪き胸にかけた十字架を握りしめ、聖書の言葉を唱える、白髪の神父の姿があった。
ビシャルは神父のすぐ後ろの長椅子に座り、軽く胸の前で十字を指できざみ、神父が祈りを終えるのを待った。
数分してジョージ・カンゲル神父が祈りを終え、立ち上がると真ん中の通路を挟んだ隣の長椅子に腰を下ろし、胸に下げている十字架の前でさらに指で十字をむすび、静かにうなだれていた。下を見る視線の先では手をかみ合わせ、祈りを捧げ続けている。
「ここに来るのも数年ぶりか」
ビシャルが重たい口を開いた。
「こんな形で再会することになるとは、神の試練だろうか」
神父もまた重たい口を開き、それでも久しぶりに会った幼馴染に気遣いして、軽く笑みを口の端にくっつけていた。
「これも仕事だから聞くんだが、あの女性と面識は」
昔の懐かしい話などをすることもできず、重苦しい教会の中にビシャルの刑事の声が響いた。
神父は喉が詰まったようになり、少しつばを呑み込んでから、答えた。
「ミサに何度か顔を出しているのは覚えているが、それ以外のことはわかない。なんということだ。あー主よ」
更に胸の十字架を握りしめる幼馴染を見て、刑事は静かにため息を漏らしたあと、職業柄ながら、嫌な質問をしなければならないことに、後ろめたさを感じた。
それでも口を開かなければ、質問をしなければならない。
「第一発見者は通行人らしいが、その人物との面識は」
神父は首を横に振る。
「じゃあ昨晩はどこに居てなにをしていた」
刑事の口調は、少しづつだが、強くなっていた。
「主の存在をここまで身近に感じたことはない」
少し間を開けて神父は重々しく、静かにつぶやいた。
「今、外で起こっている事件のことじゃない。いや関係ないとも言えないのかもしれない。わたしは主に使えることを選んだときから、主を身近に感じていた。主が本当にいるのか、疑ったころもあった。だが今ならばはっきり言える。主は我々を見守って下さり、試練をお与えになる」
神父がなにを言いたいのか掴めなかった刑事。だが神父は立ち上がると刑事の顔を直視した。その眼には憂いが垂れ込める。
「もしかすると事件と関係あるかもしれない。君の探している答えは、わたしの行く先にある」
はっと眼を剥き、刑事は立ち上がった。
第14話−6へ続く
6
ビシャルは現場をアルトに任せ、神父を助手席に乗せ、車を走らせた。
垂れ込めていた雲からはとうとう雨が降り出し、どんどん強くなっていった。
神父の案内で車を止めたのは、正面に十字架を掲げた、精神科病院だった。しかも三番街から一番近くにあり、評判があまりよくない精神科病院であった。
キリスト教系の病院であるのは明らかであり、ビシャルも噂程度にしか聞いたことがないが、一度、入院すると出てこられない、という噂が常時流れていた。
雨の中、車を降りて急いで入り口まで走った男たちを、自動ドアの奥にある無数の待合室の患者たちが迎えた。
一般病棟の患者たちは、無言であるもの、落ち着きがなく歩き回るもの、認知症の老人なのか、手をたたき、壁に掛けられたテレビから流れるニュースに興味を持つ老人。その老人に付き添っている40代らしき、疲れた顔をした女性。
そういった人々が長椅子に腰かけ、呼ばれるのを待っていた。
雨に濡れたレインコートで、茫然とするビシャル。彼は精神科という異空間に少し面食らっていた。
「こっちだ」
神父は慣れた様子で刑事を連れ、待合室から廊下を少し行ったところのエレベーターに案内した。古い色褪せた扉のエレベーターに乗り込むと、神父は地下4階のボタンを押す。
この病院に地下が4階まであることに、そもそもビシャルは驚いた。
そうしている刑事にいうわけでもなく、自分に言い聞かせるように、白髪の神父は教会からつぐんでいた口を開いた。
「わたしは聖職者としては、主を信じていない方だったかもしれない。毎日、主に祈りながらも、心のどこかで主の存在を、救いを疑っていたのかもしれない」
胸の前で指をうごかし、十字を刻んだ。
「あの日、あの子に出会った時、わたしは心の底から願った。主よ、この卑しいわたしを救いたまえ、と」
あまりに自分を責めている感じがした神父をいぶかしく思いつつ、刑事は地下、4階に到着したエレベーターの扉が開いたので、出ようとした。
すると神父が刑事の胸に手を当て、静止させると、
「ここからは邪悪なるものの領域に入る。心に常に主があることを忘れるな」
そういって、手を離した。
無神論者というわけでもないが、教会に通うほど神というものを信じてはいないビシャルは、気づくと汗をにじませている神父の顔を一瞥してから、エレベーターを降りた。
そこは地下ということもあるのか、空気が一般病棟とは明らかに違って、冷たさと湿り気、かび臭さを帯びていた。
廊下は白く塗られ、LEDランプで明るくは保たれているものの、清潔感がある分、余計に不気味に感じられた。
エレベーターからは廊下が一本しかなく、その先に複数人の人物が椅子に座っているのが、目視でも確認できた。
濡れた革靴を鳴らしながらコンクリートの床を前へ進むにつれ、その人々が年齢層がバラバラの神父たちの一団なのが分かった。だが神父たちの顔に血の気がない。何か疲れた様子で頬がこけ、ビシャルが横を通っても反応がなかった。
一団の横を通り抜けた先、通路の行き止まりにあるのは、一枚の扉だった。しかしその扉には巨大な金属の十字架が埋め込まれていた。扉も金属製という、精神病院には似つかない頑強なイメージを与える扉である。
「今から見るものはすべて現実だ。嘘、偽りのないこの世の真実だ。心をしっかりと持ちなさい。そうでなければ向こう側に引きずり込まれる」
後ろからついてきていた神父がそういうと、扉の上部にある小窓。そこを目隠ししている小さい扉をゆっくりと開いた。
第14話‐7へ続く
7
刑事は自分の眼が信じらっれなかった。
室内の壁はクッション素材に覆われ、精神患者が暴れてもいい構造になっていた。正方形の部屋の真ん中にはベッドが1つ置かれ、壁際にはトイレらしき小さい部屋がある。それ以外は何もない。
ただ部屋の壁中にはあらゆることば、世界中の言葉、あるいは読めない言葉、今では解読できない古い言葉で、神を呪う言葉が書き殴られており、しかもその書いた文字は真っ黒で、タール状だった。
ビシャルは事件現場を思い出しながら、ベッドを見やる。すると1人の少女らしき髪の長い人影が座っていた。
「あの子は?」
ビシャルが神父に説明を求める。
神父は汗ばんだ顔で、胸の十字架を握りしめて言った。
「エリス・バーンズ、12歳。1年ほど前に深刻な精神疾患が見られるとして、この病院に運ばれてきた。その時には自ら身体や顔を掻きむしったらしく、傷だらけだった。異変はすぐに起こった。彼女の身体は浮遊現象とポルターガイスト現象を起こし、彼女が入院した病棟の患者が怪我する、錯乱するようになり、これがただの精神疾患ではと、ここへ運ばれてきた。わたしに連絡があったのもその頃だよ」
「悪霊つきって、まさかな」
冗談だろう、と言いたげなビシャル。だがその目の前でいすに座っていた少女は座った体勢のまま浮遊を始めた。と、ビシャルの顔をみやった。
その瞳は黄色くにごり、歯は牙のように尖っていた。それをむき出し笑っていた。しかも口を開かないのに、声をが室内に響いた。
なにを言っているのかはわからない。だが少女が発するとはとうてい思えない声色で、流石のビシャルも背筋に氷を入れられた思いだった。
少女は浮遊したまま、腹に響くような野太い声で高笑いするのだった。
慌てて小窓を閉めた神父。
2人の男はしばしの沈黙で、現実を受け入れられないビシャルの、心の整理をまった。
「あの子がこの部屋から出ることは?」
ようやくビシャルは刑事としたの頭が回り始めた。
「この部屋は悪霊祓い、世にいうエクソシズムを行う場所として清められた部屋だ。だから我々神父が勝手に外へ出さない限り、自分の足では出られない」
「さっきの神父たちのアリバイは」
神父の何者かが少女を外に出したのではないかと疑った。
「彼らはバチカンから派遣された神父たちだ。悪霊を外に出すことは、自らの命を失おうともありえない」
間違いない。目の前にいる何かにとり憑かれた、認められない現実を認めざるおえない少女が一連の犯人だとしか思えなかった。
証拠もなければ少女が部屋から出たという事実もない。
これは刑事としてのビシャルの勘でしかなかった。だがその勘が目の前の何かを犯人だと訴えている。
「あの子はずっと部屋に閉じこもったまま、あんな感じなのか」
焦るように刑事の口調は早くなる。
「1日に一度、悪霊払いの儀式を執り行っている。食事は一応、食べてはくれるので、三食運んできてはいるが、ほんとうに接触はそれだけだ」
刑事は鼻の下の髭をなで、少し考えこんでから、
「あの子が犯人だと」
と、刑事でも事件関係者でもない一般人の神父にビシャルは質問した。
しかし驚く様子もなく神父は即答した。
「事件のことを知ってからずっと考えていたことがある。彼女がなんらかの方法で犯行をおこなっているのではないかと。今日、それは確信に変わったよ。教会の扉のご遺体を見た時、あの黒い液体は彼女の中にいる悪霊が放つもの。それと神を呪う言葉」
刑事が考え込むように、眉間にシワを刻んだ。その時だった。音楽が聴こえてきたのだ。
最初、刑事はなにが聴こえているのか分からず、耳をすませていた。音がどこから聴こえてくるのかもわからなったが、次第に部屋の中から聴こえていることに気づいた。
小窓を覆う引戸を開け、中を覗くと、少女の姿はそこになかった。
慌てる刑事。
しかし神父は冷静に十字架を握りしめ、姿勢を少しかがめた。
刑事も真似してかがみ、天井を見上げる。と、刑事の眼が驚きでむき出しになった。少女は天井を歩行していたのだ。傷だらけの顔に満面の笑みを浮かべて。
信じられない光景を再び見せつけられた刑事は、ふと音楽のことに頭が戻り、部屋の中を見にくい小窓から見渡すと、音楽を再生する小型のデバイスが部屋のすみ、床に直に置かれていた。
繋がれたスピーカーからは「野ばら」がイタリア語で流れていた。
「彼女のお気に入りの曲だよ」
神父は慌てる様子もなく、答えた。
音楽が流れる部屋の中、天井を嬉しそうに笑いながら逆さまで歩く姿は、長年刑事をしているビシャルにとって、現実が崩れたような気持ちになった。
それから刑事はどうやって家に帰ったのか覚えていない。ただ雨の夜、いつもの一人がけのソファに座り、安いスコッチをロックで飲みながら、安いタバコを指の間にはさみ、壁にかかった古い十字架を見つめていた。
それは亡くなった両親の遺品の1つだった。
第14話−8へ続く
8
マスコミ、インターネットの憶測が加速度的に、事件へと注目していった。
異端者の儀式。
エド・ゲインの再来。
神父の犯行か!
まったくの根拠のないことが垂れ流され、警察署の電話は鳴り止まなかった。
担当の2人も課長に呼ばれ、すぐに解決するように、禿頭を真っ赤にして、怒鳴られる始末。
しかし教会の事件から10日程は何もなかった。この間、ビシャルは事件を洗いなおしていた。何か見落としはないか、あの黒い液体に類似するものはないか。
アルトは聞き込みに回っていた。事件現場近くの住人に怪しい人物を見ていないか、犯行時間と思われる時間、近くの店の防犯カメラや通りかかる車に何か異変はなかったか。
だが10日過ぎても何の情報も得られはしなかった。
しかも事件は再び発生した。今度は町の東側の繁華街、バーと商店の間の路地で3つの死体が発見された。地面は鮮血と例の黒い液体であふれ、死体の腹は綺麗に切り裂かれ内臓は全部取り出されていた。全員男だったがその顔には逆さ十字の傷跡がまた刻まれていた。
曇り空の中、ビシャルとアルトが現場に到着すると、非常線の外にはマスコミと野次馬が溢れていた。もはや世界中が知っている事件に、注目しないはずがない。
「今度は3人かよ」
頭をかくしかないアルト。
ビシャルは必死に事件現場に何かないか。見落としはないか、眼を忙しく動かしていた。すると町の喧騒の中に聞き覚えのある音楽が流れた。それは町に設置された音楽を流すスピーカーからの物で「野ばら」が流れていた。
ビシャルの忙しい視線は遺体で立ち止まり、耳が立ち、背筋がしびれるようにゾクゾクとする感覚がした。あの光景が、精神病院で見たあの少女の傷だらけの笑顔が脳裏を横切った。
胸が苦しくなった彼は、現場から離れ非常線のテープをくぐり、マスコミと野次馬の間を抜け、繁華街の真ん中を通る大通りに出た。
そこで息を大きく吸い、落ち着こうとする。しかし耳からはあの音楽が入ってくる。
と、視線を上げた彼の前に女の人が立っていた。ラテン系の胸の大きな、褐色の色をした、露出度の高い衣服を着ている。商売女なのは明白だ。
すると女は目の前で突然、痙攣を始めた。身体をブルブルさせて、泡をふき、眼は血走っていた。
病気の発作かとも思った。だがその女性だけならばそれも考えられたかもしれない。しかし痙攣を始めたのは彼女だけではなかった。
野次馬、マスコミ、道を駆け回る子供たちまでも、全員が痙攣を起こしていた。しかも痙攣しながらも、口からは野ばらの歌詞が溢れ出ていたのである。
狂った。自分がおかしくなったのかと思ったビシャルは、車へ駆け込んだ。震える手で鍵を回し、古い型番のセダンを発車させた。
どこを走ったのか、信号で停止したかもわからないまま、気づけば教会の前に車を停め、未だ消えない、消そうとしても消えない謎の黒い液体で教会の正面の扉に書かれた、神を呪う言葉を見つめていた。
第14話−9へ続く
9
メディアや撮影する野次馬で、未だ教会の正面入り口は、死体が運ばれたとはいえ、呪いう言葉が書かれていることにより、人の好奇心を引く場所となっていた。
それを避けて別の木戸から中に入ったビシャル刑事は、ステンドグラスを背にする神の像に頭を垂れた。
それは以前来たときよりも深々としたものだった。精神科病棟での怪異、自分の身の回りで起こっている不思議な出来事。これらを経験したことで、刑事という論理的でなければならない職業にありながら、彼の心の中で自然と救いを求めていた。
聖堂内に神父の姿はなかった。
教会に隣接する母屋にいるのではないか、と刑事は教会の奥、マリア像の横にある木戸を開け、母屋に通じる木製の廊下を進んでいった。
母屋は質素なもので、アパートの小さい部屋ほどくらいしかなかった。
部屋に入ると、未だにブラウン管のテレビがおかれており、そこからは録画したのであろう、あの少女を悪魔祓いしている光景が映し出されていた。
傷だらけの顔に十字架を当てると、まるで肉を熱した鉄板の上にあげたような、焼ける音がして十字架の下から煙が出た。
数人の神父の聖書を読む声が聞こえる中、さらに聖水を振りかけると、彼女は苦しんでいた。
まるで映画だな、と刑事は喉を鳴らし、神父の姿を探すが、居間に彼の姿はなかった。
やはり子供の頃から几帳面だっただけのことはあり、部屋は一人暮らしの男の部屋にしては、綺麗に整頓され、掃除も行き届いていた。
一人がけの椅子の横を通り、綺麗にされている台所を通り、寝室への扉を開いた。
そこでビシャルは絶句した。寝室の壁中に悪霊にとりつかれた少女の写真が貼られ、記録と言うにはあまりに個人的な物が多かった。悪霊祓いの写真もあれば、少女の裸体の写真もある。
もはやこれは神父の領域を超えた、犯罪者の部屋に刑事には見えた。
「ビシャル」
トイレから出てきた神父は、親友の訪問を歓迎するように微笑んでいた。
「これはどういうことだ」
明らかに刑事の顔で神父をみやったビシャル。
神父は何が幼馴染を刑事の顔にさせたのか、理解できないといった顔をして、ベッドの上に腰掛けた。
「ここに写っているのは、悪霊だ。だが誰も信じはしないだろう。だから証明する方法を、わたしは思案してるんだよ」
「思案? 悪霊の証明をするってのか」
刑事は強い口調で神父に迫る。なにか自分の知ってる神父が遠くに行っている気がした。
「ビシャル、君は何もわかっていない。わたしは主に仕えている。わたしが証明したいのは、主なのだよ」
刑事には、目の前の幼馴染がなにを言っているのか、理解できないでいた。神に仕える神父が神を証明したいと言っている。
「神を信じているからこそ、神父を続けているんじゃないのか」
刑事は友として神父の揺らぐ心に訴えかけた。
「信じている。しかし世間は、人類はどうかね? 主を軽々しく口にし、小説、映画、コミックにする。だが信じるものがその中に何人いると思う。オカルトではない、あの子に起こっていることは真実だ」
そういうと居間に早足で神父は向かう。
刑事も後を追う。
神父はブラウン管テレビの前に立ち、今どき時代遅れのビデオテープで再生されている、少女の悪霊祓いの映像を、指し示した。
「現実に悪霊は存在している。この子の中に奴らは大勢でいる。それを祓うことで主の存在を証明したいのだよ、わたしは。だからあの子のことを調べている。どこで育ち、何を好み、主を信じていたのか」
ビシャルには、とても神父の言動とは思えなかった。
「明日だよ、ビシャル。明日、バチカンから司祭様が来られる。悪霊を祓い、無垢なる魂を浄化し、主の力を世界にお見せになるのだ」
ビシャルは何故、神父がビデオを撮影しているのか、何故、今まで司祭を呼ばなかったのか。刑事の推察は鋭くそれらをつなぎ合わせた。
「映像を拡散するつもりなのか。それで神の証明ができると本気で思っているのか」
「主は誰もお見捨てにはならない。無垢なる魂はきっと救われ、人類は主を目撃するだろう」
胸の前で十字を刻み、神父は微笑を浮かべのだった。
「刑事として俺も立ち会う。連続殺人犯の可能性がある容疑者があの子ならば、法律に基づいて、処理しなければならない」
口では刑事らしいことを行って入るが、ビシャルはあの子が心配でもあり、自分に起こった異変が本当に悪霊と呼ばれる超常なるものの行為なのか、確かめたくもあった。
「主は拒みはしない。ただ危険なことだけは覚悟してくら」
存外にも神父は悪霊祓いの儀式への立ち会いを、拒みはしないしなかった。
明日はちょうど3月25日、受胎告知の日であった。
第14話−10へ続く
10
朝日がすでに摩天楼の隙間から登っていた。
アルト・コバックは昨日、東の繁華街、事件現場から姿を消した相棒に何度も電話をかけながら、事件の手がかりがないか、ホワイトボードに張り出した死体の凄惨な写真を見つめ、手元にあるラップトップで、被害者の情報を流し見していた。
するとあることに気づき、眼を見開いた。
被害者全員の誕生日が3月25日だったのだ。しかもそんな基本の情報に今更気づいたのである。
と、アルトのデスクにおいてあったスマートフォンが震えた。画面にはビシャルの番号が表示されていた。
*
精神病院の地下4階。真っ直ぐな廊下の突き当りの十字が刻まれた部屋の扉が開かれていた。
中ではベッドに拘束具のベルトで縛られた少女の姿があり、周囲には複数人の神父と、バチカンからのやってきた司祭が、準備をしていた。
ビシャルは特別な許可を得て、部屋の隅で見学している。
それにしても部屋の中の有様に、改めて刑事は唖然とさせられていた。まず入れられた者が怪我をしないように、クッションになっている壁や天井を、絨毯を敷いた床には、殴り書きした神を呪う言葉が溢れかえり、あらゆる国の文字が今にも襲いかかってきそうだった。
それと臭いである。刑事は入室した瞬間から、部屋の中が糞尿と汗が混じったような悪臭に満たされていることに鼻が気付き、思わず鼻を抑えた程だった。
そうした劣悪な環境下で、少女は笑っていた。拘束具も言われる通りにつけ、ベッドに横たわっていた。
これからなにか大人たちと遊ぶような、楽しげな笑みを浮かべていた。
少女の両親は別室で待機している。この悪霊祓いの儀式が幾度続いたかわからないが、ビシャルが刑事として話を聞く限り、この状況に抵抗心を持ってはおらず、神を信じて、病院にある小さな祭壇のある部屋で、毎日、祈りを捧げていた。
この病院も悪霊祓いを専門とするらしく、使われている地下4階は、悪霊祓い専門の階層になっていた。
ビシャルとしては、それだけ当たり前に悪霊祓いが行われていることに、驚きもあった。
今回はバチカンから司祭を招くほどの特別な悪霊祓いらしく、神父たちの準備も念入りだった。
部屋の四方には三脚を立てカメラを設置し、神父はすでに録画を開始していた。
儀式は唐突に始まった。
司祭が聖水の入った小さい入れ物を振ると、水滴が小窓から入ってくる光に輝き、少女の身体に零れ落ちた。するとすぐに水蒸気になってしまい、それと同時に幼女の笑顔が苦悶に歪み、拘束具を今にも引きちぎらんとするほどの勢いで身体をよぎるのだった。
司祭が聖書の言葉を読み上げ始めると、少女のむき出しの牙の生えた口が裂けんばかり開かれ、この世の物とは思えない叫びが部屋中を駆け巡り、誰もいない地下の廊下で反響した。
続けて司祭の言葉に合わせ、牧師たちも聖書を開き、声を合わせ悪霊の首を絞めるかのように無表情で聖書を読み上げ始めた。
それにますます少女の身体はよじれ、床に打ち付けてあるベッド事、空中に浮かびそうな勢いで、少女の身体は空中に浮かび始めた。
司祭は聖水をかけ、さらに語気を強めて聖書を読む。すると部屋の温度が急激に下がり始め、司祭や神父たちの口から、白い息が発せられた。
部屋の隅で見ていたビシャルも、口から白い息を吐き、寒さで身体が縮こまった。
「無理だ、無理だ。もう終わりなんだよ」
口の脇から黒い液体を垂らしながら、少女の喉の奥から3重になった、人の声ではない何かの声が、司祭たちにそう言った。
黒人の司祭が黄金の十字架を少女の中にいる悪霊に近づける。だがいつもなら苦しむ少女は、平然としていた。
「刑事さん、何も気づかなかったか? 我々が行った儀式の共通点を」
ビシャルは急に話しかけられ、面食らった。それでも頭の中でこれまでの遺体を思い浮かべ、被害者の情報を脳裏から引き出す。
するとなぜだか今まで思い浮かばなかった、共通点がふと頭に浮かび上がってきた。被害者は全員、3月25日生まれ。
「クククク。そうだ、アンチキリストの、反復活祭の儀式だ」
悪霊は刑事に面白がって笑いながら言った。と、高速ベルトが勝手に外れ、少女の身体は自由になった。
「声に耳を貸してはならない」
神父が激しい口調で刑事へ叫ぶ。
その時だ。悪霊の瞳が一瞬で黒いまん丸の瞳に戻り、少女が顔を出した。
「神父様、どうしてなの。どうしてわたしをすぐに救ってくれないの? こんなに苦しいのに。こんなに神父様に救いを求めたのに」
刑事は神父を見た。その脳裏には神父の家にあった複数の写真がよぎる。
「何度も助けてって叫んだのに。神父様は、主の証明のためだって。あの黒いものがどんどん入ってきてたのに」
神父の目的は主の証明。だから彼は悪霊にどんどん蝕まれる少女を放っておいて、深刻化させていたのだ。
これには司祭や他の神父たちも狼狽してしまい、聖書の言葉が途切れてしまった。
その刹那だった。司祭、神父たちの頭が180度回転し、鈍い骨が砕ける音がした。それと同時に、バチカンからの使者たちは、膝から崩れ落ちた。
ビシャルはホルスターから拳銃を抜き、両手で握って構えた。
「ビシャル、やめるんだ、銃を下ろしなさい。無垢な魂を傷つけてはならない。主に逆らう行為と同じになってしまう」
唯一、殺されずに生き残ったジョージ神父。
「あれだけ無垢な魂を実験に使いながら、護るとは、豚の糞のような男だ」
また声色が変わり、悪霊が少女を隠してしまった。再び3重になった声は、ニヤリとしたその、傷だらけの顔を、神父に向ける。
すると部屋中に書かれていた黒い、髪を呪う時間壁から浮き出始めた。それはまるで血管のように脈打ち、生命体のように動き出す。さらに黒い液体が泡立ち始めたと思った瞬間、口が大量に出現した。
それは悪霊の口に泡さて動く。
「神の証明なんて実権は、楽しかったか、ジョージ」
壁の口たちがバラバラに不協和音の如く、次々にジョージの口ずさんだ。
神父は脂汗を見る見る浮き出させ、両耳を塞ぎ、最後にはかがみ込んでしまった。
少女の肉体は、白い患者がまとうローブを着ていたが、その股の部分が真っ赤になった。股間から血を漏らしたのである。
悪霊はそれを感じてさらに悪い笑みを浮かべ、股間に少女の手を伸ばし、ローブをかき分け股間を触り始めた。
その時、一発の銃声が鳴り響いた。
第14話−11へ続く
11
ビシャル刑事は銃声の鳴った方に顔を向けた。そこにはアルト刑事がグロック社製自動拳銃を両手で握り、寒さからくる震えなのか、少女を撃った事実への震えなのか、この異常な状況にたいする震えなのかわからないが、黒人刑事の顔色は、血色が悪くなっていた。
「冗談も大概にしてくれよ。猟奇殺人の次は化け物退治か」
引きつった笑いを浮かべるあるアルト。
「お前がどうしてここに」
ビシャルは当然の疑問を口にした。病院のことも、神父のことも、ましてや少女のことなど、言えるはずもなく、相棒には何も伝えてなかった。
それなのに相棒はここにいる。
「今朝、電話してくれたじゃないか。下手な映画でも作ってるのか」
必死のアルトならでわの冗談で、自分の中で今の状況を消化しようとしているのだろう。しかしその顔に、引きつった笑み以外、余裕などなかった。
ビシャルは電話をした覚えなどなく、空中に浮かぶ少女に視線を返す。
白いガウンに新たな血の染みが増え、アルトの拳銃から発射された弾丸が左肩を赤くしていた。
「これは世界の終わり。ここから始まる終わり」
悪霊の声がそう言うと、小型音楽デバイスが起動し、野ばらが流れ始めた。
アルトはまた少女の姿をした悪霊に拳銃を向けた。目の前の化け物を射殺する。当然の本能であった。
「痛い、痛いよ」
声色が急に少女に変わる。それに合わせ、壁の複数の唇もそれぞれに少女の声を真似し、痛みを訴えた。
この世のものとは思えない光景に、アルトは恐怖から拳銃を何度も発砲し、壁の口を撃ち抜いた。
口はへしゃげて潰れ、肉片を飛び散らせ、鮮血を黒い液体の中に流した。
すると今度は少女の唇が切れて、血が流れ出した。
「止めろ、発砲をやめろ」
喉から枯れた声で叫ぶビシャル。
その声が通じた訳でもないのだが、弾倉の弾が切れたのだろう、引き金が乾いた音を鳴らしていた。
と、アルトは拳銃を床に落とし、突然、力が抜けたような表情になった。
「主よ、彼をお救いください」
ジョージ神父がそういった時、アルトの白いワイシャツの胸から腹部にかけて、真っ赤な染みが広がった。
ワナワナと震える手でアルトはゆっくりとワイシャツを両手で掴み、一気に引きちぎった。その瞬間、今までなかった医療用メスが空中に現れ、血をしたらせていた。
ワイシャツが開かれた時、アルトの腹部はすでに切り開かれ、内臓が床にこぼれ落ちた。何者かの手がかり、見えない手があるかのように、空中のメスと手がアルトの身体の中身を綺麗に取っていく。
生きたままの拷問に、口と鼻から血を流しながら、しかしアルトは身動きできなかった。いっそ殺してくれ、と思いながらも、生かされて、己の内蔵を見つめるのだった。
ビシャルは助けに行こうとした。だが身体が鎖にでも縛られたかのように動かず、無残な光景を見せられるのだった。
神父は神にひたすら祈りを捧げ、胸の十字架を握りしめていた。
「神に祈っても無駄。無垢な魂は闇に落ちた」
壁の口が口々に、落ちた、落ちた、と繰り返し悪霊の言葉こだまさせる。
そうしている間に、内蔵を抜き取られたアルトはすでに絶命しており、空中を飛ぶメスは最後に、死者の顔に逆さ十字を彫り込んだ。
「我らが主への儀式の始まりだ」
3重の悪霊の声がそう叫んだ。
悪霊の主とは何なのか。何が起ころうとしているのか。
無残な形で殺された相棒から視線を少女の形をした、悪霊と呼ばれる物に鋭い視線を向け、銃口も一緒に悪霊へ向けた。
その時、壁の黒い液体が壁から剥がれ始めた。
第14話−12へ続く
12
唇がいくつもついていた黒い粘液は、文字の形を崩し、液体らしく戻っていき、空中に浮遊した。無数にある唇が開き、そこから目玉が浮き出てきた。目玉は焦点が合わず、ギョロギョロとうごめいていた。
ビシャルはそれを何個か撃つも、弾丸は黒い液体に飲み込まれるだけだった。
神父は相変わらず十字架を握りしめているばかりで、身動きができないでいた。
「受胎告知、始まりの日、全てが終わる」
神への祈りの中で、神父はそうボソリと呟いた。
「そのとーり。今日を儀式の日としたのは、忌まわしき始まりの日であるからだ」
悪霊は興奮気味で、すでに少女のいない肉体で喋り始めた。
「3月25日、忌まわしき祝福の日に産まれた者共の魂を喰らい、躯を汚すことで儀式は完成した」
と、言った時だった。部屋の床が消えてしまい、そこの見えない巨大な竪穴が広がった。
しかし部屋にいる人々、物は自然落下しない。空中に浮いているような状態になった。
穴の壁面には、ネバネバとしたあの黒い液体が垂れ、それが生物へと変化していた。鋭い牙のくちばしや、半分溶けた奇妙な生き物。内臓がはみ出た化け物など、到底、形容できない生物たちだった。
穴からは激しい死臭が上がってきて、ビシャルは鼻を腕で覆った。
すると穴の暗がりから急速に上がってきたものがあった。人の生々しい血を滴らせた内臓だった。
そこにさっき殺害されたアルトの内臓も加わり、少女を中心にうずまき始めた。
ビシャルはシリンダー内の弾丸がなくなるまで、拳銃を撃ち続けたが、弾丸は内臓の渦に届く前に、空中で溶けて蒸発してしまった。
そうしていると、神父に異変が起きた。突然、咳込み始め身体が尋常でなく震えだしたのだ。
ビシャルが神父に駆寄ろうとした時、神父の身体は引き裂かれ、中から昆虫とも死骸とも形容できる化け物が現れた。
「我々はデヴィルズチルドレン。時空を汚すものなり」
少女の革を被った何者かが3重の声で叫んだ瞬間、竪穴から黒い大量の液体が溢れ出た。
ビシャルは隠れる場所もなく、黒い液体の中から現れた、腐ったワニのような口に上半身が食いちぎられた。
液体は様々な不気味な生物を生み出しながら部屋を満たし、廊下を一気に進み、病院にいる人々を呑み込むと、病院の壁を突き破り爆発した。
これは始まりに過ぎなかった。
世界中の海、火山、谷、都市から黒い液体が溢れ、数時間のうちに、地球はデヴィルズチルドレンに喰われたのであった。
第15話へ続く
第14話